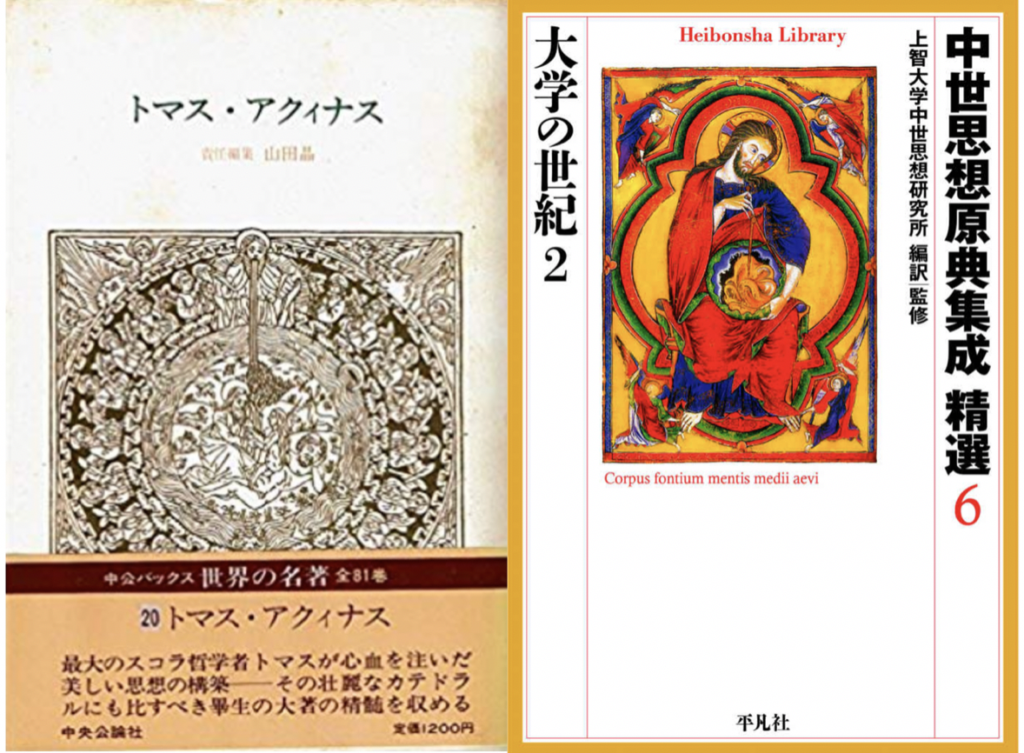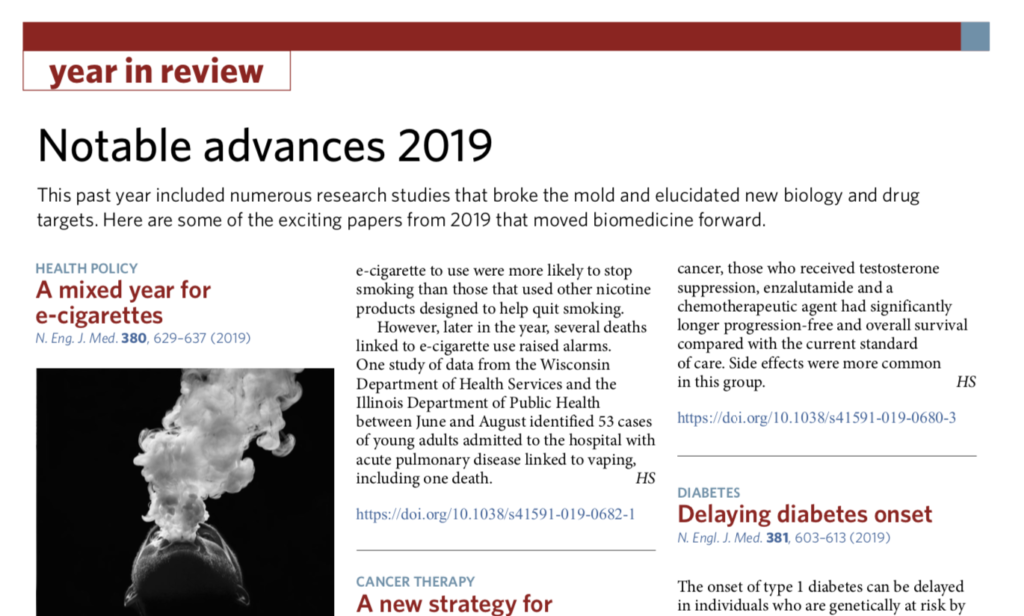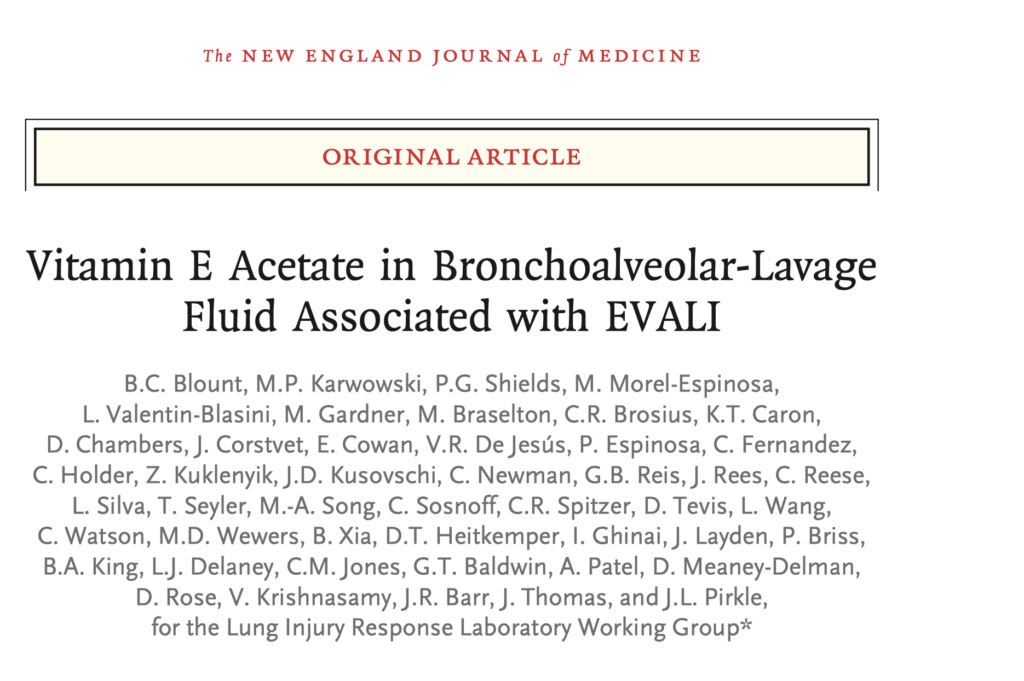2020年1月8日
T細胞の抗原認識の基本は、組織適合抗原(MHC)と結合したペプチドをT細胞の抗原受容体(TcR)が認識することだが、ペプチド以外の金属や、化粧品などスキンケア製品に含まれる脂質が抗原になることがある。実際、アレルギー性の皮膚炎の原因の多くは、ペプチドでない場合が多い。例えば以前紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/1783 )、慢性ベリリウム症を引き起こすBeSO4はHLA-DPのポケットにBeが結合すると、MHCの構造が変化してそれに対するT細胞が誘導される。ただ、多くはMHCと何らかの形で作用しあって抗原性を発揮するので、特定のMHCを持つ一部の人だけが病気になる。
今日紹介するハーバード大学からの論文はこれに対して、多型性のないCD1aに化粧品に含まれる様々な脂質が反応してアレルギーを起こす機構を探った研究で1月3日号のScience Immunologyに掲載された。タイトルは「Human T cell response to CD1a and contact dermatitis allergens in botanical extracts and commercial skin care products (植物エキスやスキンケア製品に含まれる接触性皮膚炎のアレルゲンとCD1aに対するT細胞反応)」だ。
CD1も構造上はMHC抗原と同じだが、ペプチドではなく脂質と結合してT細胞反応を起こすことが知られており、通常細胞内から由来する内因性の資質と結合している。例えば我が国の谷口克先生が明らかにされたNKT細胞もCD1と糖脂質が結合した構造に反応する。
この研究では化粧品などに含まれるアレルゲンがCD1の一つCD1aと作用しあって起こるのではないかと最初から仮説を立て、CD1aと内因性の資質に反応することが知られているT細胞株の反応を指標にスクリーニングしたところ、最終的にアロマオイルに含まれるバルサムペルーを特定する。
最終的にこの中に含まれるbenzyl
benzoateとbenzyl cinnamateがCD1aと相互作用することでT細胞の反応が誘導されることが確認された。
重要なのはこれら2種類の化合物は、これまでCD1と結合する抗原として知られていた極性基を持つ構造とは全く異なる点で、この構造的基盤を調べるため、まず29種類のよく似た化合物を同じようにスクリーニングし、芳香剤として用いられるファルネソールなど15種類の化合物が同じT細胞株の反応を誘導できることを示して、不飽和で、環状構造あるいは側鎖構造を持つ脂質がCD1aと反応するアレルゲンとしての共通の性質であることを示している。
最後にファルネソールとCD1aの相互作用の構造解析を行い、ファルネソールが内因性の脂質をCD1aから追い出すこと、ポケットの底に埋まってTcRとは直接反応しないことなどを明らかにしている。
以上の結果から、化粧品などに使われている芳香剤に対するアレルゲンは、直接TcRと結合するのではなく、内因性の脂質と置き換わってCD1aを安定化させることで、アレルゲンとして働いていることを示している。
おそらくスキンケア製品によるアレルギーは重要な問題なので、抗原の構造的側面が明らかになったことは大きな前進だと思う。しかし、もしCD1aがTcR反応に関わるとすると、なぜ一部の人だけにアレルギーが発症するのか、まだまだ分からないことが多い。いずれにせよ、CD1は様々なアレルギーの媒体として急速に注目が集まってきたようだ。
2020年1月7日
カテーテルによるステントの挿入治療により血液の循環を早期に再開することが可能になり、心筋梗塞の予後は劇的に改善した。しかし、血流が止まっていた間に起こる心臓へのダメージはそのまま残るため、かなりの患者さんでは心不全への進行を止めることは難しく、また不整脈などによる突然死のリスクも抑えることは難しかった。
今日紹介するオーストラリア・シドニー大学からの論文は、再灌流後の損傷治癒に働きかけて心臓機能の低下を防ぐ目的でPDGF-ABが利用できること示した研究で1月1日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Platelet-derived growth factor-AB improves scar mechanics and vascularity after myocardial infarction(PDGF-ABは心筋梗塞巣の瘢痕の力学的性質と血管密度を改善する)」だ。
発生や修復に関わる増殖因子PDGFは、PDGF-AとPDGF-B分子が、それぞれS-S結合で会合して形成され、組み合わせによりAA、AB、BBの3種類が存在する。それぞれ結合する受容体のレパートリーは異なるが、PDGF-ABは受容体αα、及びαβに結合することが知られている。このタイプの他の増殖因子と比べると極めて複雑だが、ともかくPDGF受容体αを発現する細胞を刺激すると考えておけばいいだろう。
このグループはこれまで小動物の心筋梗塞モデルでPDGF-ABが心臓機能を保持するために重要であることを示していた。この研究では、その延長で大型動物豚を用いて心筋梗塞を誘導し、再灌流を始めた時からPDGF-ABを投与した時予後を改善できるか調べている。
結果は期待通りで、この方法で心筋梗塞を起こすと、4割の豚が不整脈などで早期に死亡するが、心筋梗塞後の不整脈、特に心室性の不整脈とそれによる死亡を完全に防ぐことができる。
また、生存した個体の心機能を調べると、心筋梗塞の大きさは変わらないが、心臓の収縮力が維持され、収縮あたりの血液拍出量の低下が抑えられることがわかった。すなわち、梗塞自体は元に戻らないが、PDGF-AB注射は心機能の低下を抑えることができることがわかった。
この原因を組織学的に調べると、梗塞領域に特に小動脈の新生がおこり、血管の密度が高まっている。しかし、心筋梗塞の大きさや瘢痕形成にはPDGF-AB はほとんど効果がない。しかし、修復された時に形成されるコラーゲン繊維の走行が本来あった心筋の走行に一致する方向に綺麗に整えられ、強い力に耐えられるように修復が進んでいることがわかった。この結果、他の部分の心筋の力が伝わって、拍出量が維持される。
また、一般的に梗塞巣では瘢痕の中に心筋の塊が残るまだら模様の組織ができ、これが心室性の不整脈の原因になると考えられるが、PDGF-ABを注射すると、心筋は心筋、瘢痕は瘢痕と綺麗に分離しており、これが梗塞後不整脈による死亡を抑えていると考えられる。
結果は以上で、あとは臨床で確かめるだけの、素晴らしい結果だと思う。もちろん完全に治療するという薬剤ではないが、修復過程に直接働く薬剤がついに心筋梗塞治療にも登場したのではと大きな期待を抱いている。
2020年1月6日
これまで考古学とされてきた学問分野は、精緻な年代測定、DNA配列決定、質量分析など、最新の科学的手法が導入されることで、人間についての科学にすっかり様変わりした。昨年はデニソーワ人を中心に大きな研究の進展ががあったが、今年も面白い話を聞くことができると思う。特に、人類の揺りかごアフリカと様々な古代人の進化系がみられるかもしれないアジアが注目地域だと思う。
今日紹介する南アフリカWitwatersrand大学からの論文は、中石器時代の人類が食べていたでんぷん質のソースを探った研究で1月3日号のScienceに掲載された。タイトルは「Cooked starchy rhizomes in Africa 170 thousand years ago (17万年前のアフリカで調理された地下茎のデンプン)」だ。
この研究の舞台は中石器時代以降のアフリカホモ・サピエンスの研究では有名なBorder洞窟で、数を数えるのに使われた切れ目のある猿の腓骨が出土したことで有名だ。15万年前後から3万年ぐらいまでずっと人類が使っていたという点では極めて重要な遺跡と言える。
この研究では、この洞窟内の地層に火を燃やし続けたことによる灰が主成分の白い地層があり、この中から炭化したいくつもの丸い地下茎の塊が発見されることをまず報告している。また、この地層の年代測定から、だいたい17万年前に始まり、10万年前に使用が終わったことを特定する。
地下茎とされている植物の写真を見ると、小さなぬかごのようなものと考えてもらうといい。ジャガイモも地下茎であることを考えると、我々のイメージでは小さなイモと言っていいだろう。
この研究では電子顕微鏡的形態観察から、現在も薬草として使われているヒポキシスに近いことを特定している。この植物には小さな白い地下茎があり、またほとんどのアフリカ地域で生息していることから、この遺跡から出土した炭化した地下茎はヒポキシスと結論している。
以上が結果で、中石器時代の狩猟採取民も、野生の地下茎を火で炙ってカロリー摂取していた可能性が高いことが明らかになった。
結果は以上で、今後もっと古いアフリカのホモ・サピエンスの遺跡も、動物の骨や石器だけでなく、植物性デンプンの摂取についても調べることで、当時の人たちの生活をより深く理解できると期待される。さらに、他の人類と、ホモ・サピエンスとの交流の手がかりにすらなるかもしれない。
2020年1月5日
「中世哲学なんてしんどいな」と気乗りがしない気持ちを奮い立たせて、アルベルトゥス・マグヌスおよびトマス・アクィナスの著作を読んでみた(図1: 読んだのは、「中公バックス トマス・アクィナス(実際には抜粋版神学大全)」、および平凡社・中世思想原典集成6に収載されていたマグヌスの「ディオニュシウス神秘神学注解」とアクィナスの「知性の単一性について」)。
マグヌス、アクィナスとも、一旦全ての文化的活動がキリスト教に集約した西欧では完全に忘れ去られていたアリストテレスが、イスラム文化との交流により再輸入されたのを機会に、彼の哲学をキリスト教に積極的に取り入れたことで知られている。今回重い腰を上げてスコラ哲学を読もうと思った私の興味も、一見水と油に見えるアリストテレスを、なぜキリスト教の神学者が、積極的に受け入れたのかという問いに行き着く。実際に彼らの著作を読んでみて、たしかにアリストテレスは最も高い権威の「The Philosopher」として敬意が払われていることが理解できた。
例えばアクィナスの「知性の単一性」は、まさにアリストテレスの思想を、できるだけ正確に理解しようとする努力の本だ。この本では、当時アリストテレスの紹介者として広く読まれていたアヴェロエスのアリストテレス解釈についての批判という形式で書かれている。すなわち相手は異教徒(イスラム)なので、アクィナスも隠すことなく自分の意見を展開している。扱われているアリストテレスの著作の中心は「霊魂論」で、私もここで紹介した(https://aasj.jp/news/philosophy/10672 )。プシュケーを霊魂と訳している翻訳でこの著作を読んだため誤解している点もあると思うが、
「以上の通りわれわれは、アリストテレスが人間の知性について述べたほとんどすべての言葉を綿密に考察した。これによってアリストテレスは、人間の魂は身体の現実態であり、可能知性は人間の魂の部分ないし能力であるという考えの持ち主であったことが明らかである。 」中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2 Kindle 版.
と述べているように、霊魂=プシュケー、アニマを、物質と生命を分ける形相として正しく(私から見て)理解し、このプシュケーと知性の関係を追求している。重要なことは、この議論にほとんどキリスト教が登場しないことで、アクィナスがキリスト教という先入観を排して手に入るアリストテレスの著作をできるだけ正確に読もうと努力し、身体、生命、知性などを考える基準を形成しようとしているのがよくわかる。このように、スコラ哲学はアリストテレスという触媒と反応してできてきた哲学であることことは明らかだ。
しかしこれほどオープンな議論が行われている「知性の単一性」も、最終章の第5章の終わりにはアベロエス派をキリスト教信仰に敬意を欠く人たちだと断罪したあと、
「さて上述の誤りを打破するためにわれわれが書いたことは、信仰の教えによるものではなく、哲学者たち自身の論拠と言葉を用いたものである 」中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2 Kindle 版.
などと、これまでの哲学議論は決して信仰の問題にまでは及ばないと締めくくっている。すなわち、アリストテレスも、キリスト教のドグマに反するような解釈の仕方はまかりならぬという主張で終わっている。
苦労しながら読んできて、「なるほどアクィナスもアリストテレスを読み込んでいるな」などと感心した途端、「しかし大事なのは信仰で、哲学議論とは別だ」などと言われると、権威としてのアリストテレスへの強い敬意の念はなんだったのかと戸惑うことになる。いくら読んでも、アリストテレスを本当にキリスト教神学に導入したいのか、それとも権威として信仰とは関係ないところでだけ利用しているのか、本音が見えない。
実際アクィナスやマグヌスの本音が見えないという点が、これらの著作を読むのが苦行になった最大の理由と言える。例えば写真に示した中公バックスの帯には、アクィナスの神学大全を「美しい思想の構築」と宣伝しているが、私自身は読んでそんな気持ちには全くなれなかった。今回読んだ著作にあるのは、アリストテレスへの理解と、それとは無関係の信仰告白で、結局新しい思想を感じることはなかった。
あばたもえくぼというが、よほど最初からアクィナスは素晴らしいと思い込まない限り、ここに書かれた思想が「美しい思想」とか「壮大なカテドラルにも比すべき大著」などとは思えないのではないだろうか。これが中世思想の難しい点だ。このバリアーを超えられないと、その思想そのものに共感することはできないと主張する人もいるが、このバリアーをわざわざ越える必要もないというのが私の結論だ。
では「中世哲学を読んでも収穫がないのか?」と問われると、ヨーロッパの理解という点では苦労してでも読む価値が十分あると思った。すなわち、キリスト教神学にわざわざアリストテレスを導入することで、ヨーロッパの二元論の源流が生まれたことが理解できた。
神を信じるかどうかにかかわらず、我々は理解できることと、理解できないことを常に抱えて生きている。ただ神を信じることで、理解できることもできないことも、究極的に神の領域に押し込むと2元論を表面上解消することができる。この場合、身体は魂に、そして魂は神に従属する(私にはこの関係が、三位一体という概念が生まれるルーツとすら思える)。しかしどんなに信心深い人でも本当に身体から解脱することは難しいのではないだろうか(凡人の勝手な想像だが)。このことを率直に述べたのがデカルトで、身体の領域は神の領域から切り離すしかないとcartesian問題を提出した。ただ、神の領域に全てを委ねて、自分の体の正直な感覚と信仰の矛盾を解消しようとすることの困難は、当時の神学者にも認識されていたはずで、スコラ哲学の議論はこれを反映したものだという印象を今回強く持った。すなわち、大澤真幸さんの「神の実在への疑い」がスコラ哲学の背景にあるという指摘に首肯する。
アクィナスも、マグヌスも、三位一体とキリストの受肉、その死と復活による人間の救済と復活の保証、さらには天使の存在など当時のカソリックの基本的教義に関しては微塵の疑いも抱いていないという建前は明確だ。もちろん本音か建前か知るすべもないが、アリストテレスを議論している時も、これらの概念は常に真性を主張する判断の際の基準として登場する。一方、今回読んだディオニシュウス注解や神学大全(抜粋)では、このオーソドックスな立場からは決して生まれない身体に関わる問いが見え隠れする。すなわち、「神といかにして出会うのか?」さらには、「神の存在は証明できるか?」だ。
例えば「ディオニシュウス神秘神学注解」では、「神にどう近づけるのか?」について考えたディオニシュウスの著作を、マグヌスなりに注解する中で、キリスト教ではタブーと言える人間の側から神に迫るという課題に、マグヌスも取り組んでいる。Stanford Encyclopedia of Philosophyによると、ディオニシュウスは新プラトン主義をキリスト教の教義に取り入れた神学者とされている。原著を読んでいないので個人的考えとして読み飛ばして欲しいが、宗教とも相性のいい哲学者プラトンを参照することで、信仰の立場だけからは問うことができない問いに取り組むことが許されたのだろう。
それが伺えるのが「注解」の第1章でマグヌスが引用している以下のディオニシュウスの文章だ。
「超実体的な三位一体よ、キリスト者たちの神的知恵の超神性的・超善性的な内観者よ、私たちを神秘的な言葉の、超不可知的にして超光輝的な最高の頂へと導いて下さい。そこでは、単純かつ独立かつ改変不可能な神学のもろもろの奥義が、〔その奥義の〕教授者たる沈黙の超光輝的な闇によって秘めやかに覆われています。その闇は、まったき漆黒の中で、最も明るいものをも超えるほどに明るいものを超光輝させており、また、まったくの不可触と不可視の中で、目をもっていない精神を超美的な明るさでもって超充満させています。願わくは、これらのことが私にほんとうに祈りによって実現しますように。」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2 Kindle 版.
「超光輝的」といったプラトン的イメージが前面に出た大変分かりにくい文章だが、私には結局神を直接見たり感じたりできないことの焦りが伝わってくる。そして、自分は神が実際に存在することを確信しているのだから、この信仰に免じて実際に感じてみたいと切に願っているように読める。
Stanford Encyclopedia of Philosophyによると、ディオニシュウスはマグヌスの時代、重要な思想として広く読まれていたようだ。しかし、文章は回りくどいが、自分が神を直接的に感じられない焦りを率直に述べているように思う。当時のカソリックから異論が出てもいいのではとすら思うが、不思議と中世キリスト教では問題にされていないようだ。だからこそ、マグヌスが注解を書くことになった。しかし、Stanford Encyclopedia of Philosophyによると、宗教改革者のルターは「悪性の思想」と言明していたようで、こちらの方が私には納得できる。
ディオニシュウスが中世で広く受け入れられていたのなら、この文章を読んでマグヌスをはじめ当時の人は、私と同じく、神と直接コミュニケーションをはかろうと努力するディオニシュウスの焦りを感じていたのだろうか?この点をマグヌスの注解から推し量るのは難しいが、とりあえず彼の逐語注釈のスタイルを知るため、どんな風に解説するのか引用してみよう。
「おお、超実体的な三位一体よ」と。すなわち、万物を存在せしめた者よ、と。「超神性的」というのは、現に存在しているものを配慮するからである。「超善性的」というのは、それらのものを目的に向けて導くからである。さらに、「キリスト者たちの」──すなわちキリスト者たちによって所有される──「神的知恵の」──すなわち神についての知恵の──「内観者よ」と続くが、それは神のみが神自身の完全なる観想者だからである。だからこそディオニュシウスは神のことを、内を究める観察者であるがごとくに、「内観者」と言うのである。」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2
といった具合に一語一語自分の考えを述べていく(あまり内容は気にしなくていい)。
さてこの神秘神学に隠されたテーマが、「神とのコミュニケーションはどう可能か?」であることがわかってもらえたと思うが、ではマグヌスはこの議論にアリストテレスをどう登場させるのか?
旧約聖書を読むと、例えば出エジプト記には人間モーゼと神の対話がなんども登場する。当然人間と神とのコミュニケーションを議論するとき、出エジプト記は重要な題材になる。実際、神秘神学でもモーゼが取り上げられており、マグヌスも以下のデイオニシュウスの文章を題材として引用している。
「神のごときモーセは、まずもって自己を浄化するようにと命じられ、次いでそうなっていない人々からは遠ざかるように命じられ、こうしてとどこおりなく浄化されてしまった後には、さまざまな音色で喇叭が鳴るのを聞き、たくさんの輝ける光が清らかな溢れるほどに豊かなもろもろの光芒を放射するのを見たのです。そのあと彼は多くの人々から遠ざかりましたが、さらに選ばれた祭司たちとともに神的な登攀の頂上にまで辿り着いたのです」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2
出エジプト記の他の箇所ではモーゼと神との間でもっと直接的な会話があるのに、わざわざ間接的なコミュニケーションが扱われた章が選ばれているのは、神との直接対話のシーンには触れないようにしている意図を感じる。すなわち、直接的なコミュニケーションの様子が描かれている章を取り上げてしまうと、人間モーゼにはできたことが、なぜ自分にはできないか答えることが難しい問題に行き当たってしまう。
いずれにせよ、「感じる」「対話する」と言うことは身体(今風に言えば脳)の問題で、この分野になるとアリストテレスの哲学は誰の目にも最も優れていることは明らかだったと思う。ここに「神と対話できないことに悩む」神学者が、アリストテレスを持ち出す最大の理由があるように思う。このディオニシュウスの文章に対し、マグヌスはここぞとばかり神学的テーゼを認めつつ、巧妙に人間の感覚や認識についてのアリストテレス的側面を加えて注釈している。このときマグヌスが問うたのが、「1」神の観想は脱自であるか、2)私たちの精神は最も優れた仕方で全く知られないものと一つになりうるのか、3)モーセは神自身を見たのであるか?」だ。
そのままマグヌスの答えを引用するとおそらく何が何だかわからないと思うので、かなり脚色してまとめると次のようになる。
まず
「すべてのこのような観想にあっては、脱自が存在するのだと思われる。すなわち、私たちが〔魂の〕上位の能力だけに現実にとどまり続けて下位の諸能力から引き離されている場合にはいつも脱自が存在するのである*」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2
と、神を観想するとき、自分の身体を完全に超越(脱自)する必要があることは認めたうえで、ザクっというと、身体を超えた光に満たされる時に、このことを示す「印」が身体感覚できる形で神から与えられるれると答えている。
さらに、身体的感覚では全く知られない神と一体化できるかという第二問に対して、
「哲学において規定されているような認識のある種の自然的な方法による限りでは、私たちは神について「かくかくのものである」と知ってはいない。というのは、アリストテレスの規定によれば「かくかくのものである」という知識は、遠い原因によって生じるか、原因と置き換えのできる結果ないし原因に比例した結果によって生じるのだからである。私たちはこのどちらの仕方でも神について何かを知ることはできない。・・・・しかし、ある種の超自然的な認識によってならば、不分明さを免れないとは言え、私たちは髪を認識しうるのである」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2
と、たしかに理性では神は認識できないのないのだが、超自然的認識が得られれば必ず神は認識できるという希望を述べている。
最後の、人間モーゼは神を見たかという問題に対しては、「聖書に書いてあるのだから、モーゼは神を見た」と認めた上で、
「顔を見るというのにも2通りの仕方がある・・・覆いなくという仕方では、神の顔は天国で見られるだろう。・・・この意味でモーセは見なかったのである。しかし、モーセは、神の結果のある種の印において神を見たのである」 中世思想原典集成 精選6 大学の世紀2
と、神の世界と現実の世界を私たちは同時に経験できるのだと結論している。
簡単に言ってしまうと、神の世界については聖書の言葉を疑うわけにはいかない。しかし、その揺るぎない神の世界を直接実感できなくても心配はない。そして「神の印」というウルトラCさえ想定すれば、神の世界を現実の世界として感じられると語っている。一見論理的な議論だが、結局「神の印」にこだわったカソリックの伝統から全く逸脱することのない結論で終われる。
同じ神の実在を感じられるかという問題も、トマスアクィナスの神学大全では「感覚」のような身体性ではなく、「理性」の問題、すなわち「神の実在を証明できるか」として提示される。例えば中央公論社版「神学大全」117ページから始まる「第二問 神について、神は存在するか」はその典型だろう。アクィナスはこの問題を、1)神ありということは自明であるか、2)それは論証されうることであるか、3)神は実在するか 、の3項目に分解して、彼の考えを述べている。
もちろんアクィナスの結論は「神の存在は知性的に論証できる」だが、
まず、私たちの理性が神を考られることは、すでに概念が外から植え付けられていることを意味しており、考えられること自体が神の自明性の証拠だというアンセルムスの考え(我思うゆえに神ありとでも言える)を、自明と簡単に片付けるのは間違っていると否定する。その理由としてアリストテレスの「自明なことはその反対を考えられないこと 」という言葉を登場させ、実際に「神は存在しない」と考えられること自体は聖書にも書かれている 」ことから、神の存在は自明ではなく、まだ論証が必要だと自分の立場を明確にしている(なんと回りくどい言葉遊びか。あるいはここまでしてアリストテレスを登場させたがっているというべきか)。
では神の実在の論証は可能か?これについて、まずアリストテレスに従って、
論証には、結果の原因を明らかにして論証する「原因による論証 」と、結果という事実から原因(この場合神)があるとする「事実による論証 」の二つの方法あるとした上で、「神の結果(=印と言える)」を認めることで、事実による論証の一つとして神の実在を論証できると結論している。
そして最後の問い「神は存在するか」について、アリストテレスの目的論をうまく援用して、
「自然がある定められた目的のために働くのは、何か上位の作用者の指示によるものであるから、自然から生ずる事柄は、やはり第一原因としての神に必然的に帰着する」 山田晶編集 中央公論社版「神学大全」
と述べて、神は論証でき、存在すると結論している。はっきり言ってアリストテレスを権威として借りた屁理屈としか言いようがないが、「世界の存在」の実感=神の証明とする論理は、なじみのある17世紀のヨーロッパの汎神論と重なる。
以上のように、アクィナスがアリストテレスを借りて議論したかった中心課題は、理性による神の証明で、最初にあげたマグヌスの「身体的に神を感知できるか」という問いより議論は楽だったと思う。すなわち、理性という複雑で定義が難しいフィルターを通せばなんとでも議論が可能になる一方、「感じるか」と問われると、これに正直に答えるのは難しい。結局はどちらも「神の印」で手を打タざるを得ないが、神の問題を直接身体感覚の問題として立向かうのは勇気がいったはずだ。
実はアクィナスも、「神の本質は肉眼によって見られるか」という短い章を設けて議論している(同本326ページから)。もちろん答えは、「生きているときに肉眼で神を見ることはない」だが、さすがアクィナスで、聖書でも肉眼で見たという記述と、肉眼では見られないという記述の両方があることを指摘した後で、結局これらの記述は感覚と知性の相互作用のなせる技で、「知性の透徹した認識力 」と「物体に神の明るさが反映したもの 」(これも「印」と言えるだろう)が神を見たという感覚の原因だと結論している。
この論理の展開にもアリストテレスの大きな影響が見られるのだが、これ以上追求するのはやめる。読めば読むほど、結論ありきの論理構成で、例えば昨今、安倍首相を守るという結論のために、優秀な役人が知恵を絞って白を黒と答弁を繰り返しているのを見るのと同じ印象を持つ。
結局読んだ感想として、
アクィナスはアリストテレスを読み込んで大きな影響を受けたことは間違いない。 しかし、これはあくまでも「お勉強」の世界で終わり、本音か建前かは別として、信仰の世界は全くアリストテレスとは別という立場を取っていた。 まさにここにヨーロッパ二元論のルーツがみられる。アリストテレスの世界(知性)を導入することで、神の世界(信仰)との相容れない2つの世界を認めたのだ。その意味で、現実の世界も全て神の世界に押し込んでいたそれ以前の思想から考えると、アリストテレスの導入(神への疑い)により新たな思想的駆動力がスコラ哲学によりもたらされたのは間違いない。
今回3冊の本を読んでみて、私のように神の世界が欠落した人間にとっては、「信じること」の意味がわかりにくいことを実感したので、そのままオッカムなど唯名論議論へ進む前に、キリスト教神学者が「創世記」をどう信じていたのか探ってみることにした。
2020年1月5日
Nature Medicineが昨年の医学トピックスとして真っ先に挙げたのが、電子タバコによる肺の損傷が英国や米国で報告されたことだ(図下)。
米国ではなんと2400人の患者さんが病院に緊急入院し、そのうち半数が集中治療室での治療が必要で、すでに52人が死亡し、大変な問題になった。
この原因が電子タバコによることは聞き取り調査などからわかっていたが、最終的な原因物質については特定に至っていなかった。
これに対し米国CDCが全力をあげて調査した結果が1月3日号のThe New
England Journal of Medicineに発表された。
研究では患者さんの肺の洗浄液を集め、電子タバコに含まれており、しかも肺損傷を起こした患者さんだけに存在している化合物を探索し、51例中48人でビタミンEアセテートが含まれていることが明らかになった。
聞き取り調査などから、このビタミンEアセテートはテトラヒドロカンナビノールと呼ばれる大麻成分を溶かすために使われており、8割の人がこの大麻成分を蒸気化して吸っていたことを告白している(Wikipediaに典型的製品が公表されている )。
以上のことから今回の肺損傷の原因は、電子タバコというより、大麻成分を溶かしていたビタミンEアセテートが限りなく黒に近く、ビタミンEアセテートが含まれない電子タバコは他の害はともかく、肺障害については問題ないと結論されたと思う。いずれにせよ、ビタミンEアセテートが含まれているかどうか、各社早急に声明を出したほうがいいと思う。
ビタミンEアセテートはもちろんサプリメントとしても使用され、皮膚のクリームにも使われている。なのにどうして肺でこのような激烈な症状が出るのか不思議だ。現在のところ、長い脂肪鎖を持っており、これが肺を膨らませるのに必要なサーファクタントに潜り込んで機能を障害するのではと考えられている。
他にも、蒸気化するための高温に晒されて、肺障害性の化学物質に変化する可能性も示唆される。
いずれにせよ、ここまでくればあとは動物実験ではっきりと真偽が確かめられるだろう。論文が発表され次第報告する。
2020年1月5日
30億塩基対の巨大なゲノムを持つ我々の細胞一個一個が、これを正確に複製できているということは驚くべきことだ。それぞれの染色体は繋がっていても、大腸菌のように一個のマシナリーで複製することは不可能だ。代わりに私たちのゲノム状には何万もの複製開始点が前もって設けられており、そこから双方向に複製が決まったタイミングで一度だけ起こるよう設計されている。この場所極めはゲノム上の配列と、クロマチンの構造で決まっていることがわかっているが、意外と詳細がわかっていなかった。
今日紹介する北京科学アカデミー研究所からの論文はヒストンH2AFZに注目して、この分子の機能からクロマチンによる複製開始の機構に迫った研究で12月25日号Natureに掲載された。タイトルは「H2A.Z facilitates licensing and activation of early replication origins (H2A.Zは初期の複製開始点のライセンシングと活性化に関わる)」だ。
ここでライセンシングというのは、細胞が一回分裂するとき一回だけ複製が起こるようにする機構を意味する。すなわち、一定の条件が複製開始点に集まった時だけ複製が活性化する機構をさす。このグループは、開始点のクロマチンに集まったH2AFZがライセンシングと複製過程の引き金になると考え、HeLa細胞からH2AFZをノックアウトすると、S期の直前で細胞周期が止まるという観察からスタートし、
H2AFZがライセンシングに関わるH4K20me2やORC1と複合体を形成し、複製開始点に集まっていること、 この過程は、まずH4K20のメチル化に関わる酵素SUV420H1がH2AFZと結合し、これにより活性化された後H4K20のメチル化とH2AFZが結合している複製部位への集積が起こり、その結果ORC1、そして複製マシナリーがここに集積すること、 H2AFZの結合している場所で実際複製が起こっていること、 H2AFZはライセンシング因子として、実際に複製のタイミングも決めていること。 などを明らかにしている。
特に新しいテクノロジーがあるわけではないが、段階的に可能性を追求するスタイルのおかげで、自分の頭の中の複製開始やライセンシングについての知識を整理することができた。この論文は一般の人には難しいと思うので、一般用にはもう一編論文を紹介するが、学生さんたちには是非読んでほしい力作だ。
2020年1月4日
アルツハイマー病(AD)はアミロイドAβの蓄積で引き金が引かれることは広く認められ、多くの薬剤開発がこの蓄積を抑えることに向けられてきた。しかし昨年11月Aβの著しい蓄積があるのに全く認知症状が出ないApoE3変異を持つ70歳の女性の症例報告を紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/11677 )、症状や予後と比例するのは細胞内でのTauの蓄積とする考えが一般的になってきた(西川伸一のジャーナルクラブで紹介している:https://www.youtube.com/watch?v=SGUDm0h184c )。幸い我が国をはじめ様々な機関でTauをイメージ化するためのPETに使う化合物が開発され、リリー社のFTPは2018年第3相の治験が終わり、実際の臨床利用が始まった
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、この新しいFTPを使ってADの予後を予想できるか調べた研究で1月1日号のScience Translational Medicineに掲載されている。タイトルは「Prospective longitudinal atrophy in Alzheimer’s disease correlates with the intensity and topography of baseline tau-PET (アルツハイマー病の萎縮経過をTau-PET の場所と程度から予想できる)」だ。
この研究ではADの初期症状が現れた患者さん32人について、MRIで脳の解剖、Aβ-PETでアミロイドの沈着を、そしてFTPを用いたTau-PETでTauの蓄積を測定し、その後15ヶ月後にMRIで脳の萎縮の進行、症状の進行を調べている。15ヶ月というのは短い様に思うが、FTPを用いるTau-PETが2018年に利用できるようになったことを考えると、最速で研究を進めていると言える。
結果は予想通りで、Aβ-PETと脳の萎縮、さらにはその後の萎縮進行は弱い相関しか見られない。一方、Tau-PETで測定されるTauの蓄積はMRIでの脳の萎縮と強い相関を示し、15ヶ月後の進行の程度とも相関する。
さらに、Tau-PETで蓄積が最も強い場所が、萎縮も最も強いことが明らかになり、Tau蓄積が細胞の変性を反映していることを明らかにしている。また、この検査でTau蓄積が同じ程度に認められる場合、年齢が若い人ほど萎縮が強く、また進行も早いことが明らかになった。
結果は以上で、結論自体はこれまでの解剖例の検討や、脳脊髄液のTsu検査、あるいは実験的なTau-PETのデータから予測されてきたことの確認と言える。また、研究スタート時からTau-PETとMRIによる萎縮検査が一致しているので、わざわざ高価なTau-PETが必要かこの研究からは明らかでない。
結局Tau-PETを使えるようになったのが1年前なので、現時点ではこれで精一杯だろう。しかし、今後特に研究目的での利用が広がることで、症状が出る前にTauを検出して、Aβ蓄積との関係を調べたり、蓄積と萎縮の伝搬の経過を調べたり、実際の患者さんを使った研究が進むと期待される。また、難航している薬剤の開発も、より臨床予後と相関する評価系が生まれることで、新しい展開が見られるように思う。その意味で、新年号にふさわしい論文と言えるだろう。
2020年1月3日
今年最初のNature読んで、この雑誌が社会問題を科学的手法で解決する研究を後押しする強い意志を感じた。持続可能な社会をもう一度目指そうという社説だけでなく、実際この号に掲載された論文の中には、地球温暖化、中国の国土開発、結核の予防など、社会問題の科学論文が3編もあった。以前Scienceが格差問題を特集した時も同じ印象を強く持ったが、このような変化を目にすると、科学を応用と基礎などと分けて考えること自体、古い思想のような気がする。
さて今日はこの3編の中から、米国衛生研究所のグループが発表した、BCGを静脈注射すると高い結核予防効果が見られるという驚きの研究を紹介する。タイトルは「Prevention of tuberculosis in macaques after intravenous BCG immunization (BCG 静脈注射によるアカゲザルの結核予防)」で、1月2日号Natureに掲載されている。
私たち団塊世代が子供の頃は、ツベルクリン反応が陰性だと必ずBCG接種で、結核予防の重要な手段だった。現在どの程度の接種率があるかはわからないが、先進国で結核が減ったのと、予防効果が5割ぐらいという統計が出て、接種率は落ちていると思う。それでも、我が国は接種率が高い方だと思う。
実際のBCG接種は牛の生きた結核菌(BCG)を皮膚に塗布した後、針を刺して皮下に浸透させる方法がまだ使われていると思うが、もっと有効な免疫方法がないのか、例えば気管へエアロゾルにして投与する方法などが試みられてきた。その後、サルを用いた研究で静脈注射で結核感染予防率が高まることが報告され、この可能性をさらに深めたのが今日紹介する研究だ。
研究は単純かつ総合的で、サルに、従来の方法、高濃度皮下注射、エアロゾル噴霧、そして静脈注射でBCG を接種し、感染実験による予防効果の検証を含む、様々なパラメーターを徹底的に調べた論文だ。多くの実験が行われているが、詳細を割愛して結論だけをまとめると次のようになるだろう。
まず、感染予防という面では、静脈注射はほぼ完璧に近く、10匹中9匹で全く感染が起こらなかった。一方、他の方法では予想通り、一定の効果はあっても、結果はまちまちで、完全防御までには至らない。
この背景を調べると、静脈注射した1千万CFUのBCGはほぼ全身に回り、肺やリンパ節、脾臓などで長期間維持される(もともと取り込まれたBCGは何十年もリンパ節で生存することが知られている)。一方、皮下注射では、所属リンパ節だけで、肺までには到達しない。
この抗原が長期間肺や肺門リンパ節に存在するおかげで、一つはアジュバント効果による炎症で、多くの免疫細胞が肺に浸潤する。同時に、感染予防に関わる抗結核作用のあるT細胞などが局所に浸潤するため、完全な予防が可能になる。
だいぶ割愛したが、メッセージとしては十分で、ホストの中で生き続けるBCG を考えると納得の結果だと思う。しかし、炎症誘導性と言った意味ではBCGのおそろしさも物語っており、今後この結果を人間にトランスレーションするとなると、毒性など長期にわたる研究が必要だと思う。
しかし、このBCGの「ホストでしぶとく生き残る」という性質をうまく使えば、結核だけでなく、肺炎やウイルスなど様々な病原体に対する持続的免疫を誘導するワクチンが開発できるかもしれない。
感染症は、南北格差を最も反映する社会問題だが、正月早々格差解消に向けて期待される研究だと思う。
2020年1月2日
年初ということで、自らを奮い立たせる意味で、最も苦手な電気生理学分野の論文を選ぶことにした。はっきり言って、よくわかっていないところもあるが、しかし自分が習った神経生理学が何十年も経って大きく変わっている予感がする論文だった。
オランダロイヤルアカデミー、神経学研究所からの論文で、ミエリンで被覆された神経伝導についての新しいモデルを検証する研究で1月23日号 Cell に掲載予定だ。タイトルは「Saltatory Conduction along Myelinated Axons Involves a Periaxonal Nanocircuit (ミエリン化軸索で見られる跳躍伝導には軸索周囲のナノ回路が関わっている)」だ。
「ミエリン化された軸索では、ミエリンで被覆されていない場所(ノード)だけで脱分極が見られ、ここで生まれる大きなイオンの変化はミエリン化された軸索を普通のイオンの流れとして伝搬し、次のノードに集中している電位依存性イオンチャンネルを開いて脱分極させ、これが例えば1mの神経なら飛び飛びに続くので跳躍伝導という」ことについては、50年前私たちが習った教科書も、今の教科書もあまり変わらないのではないだろうか。実際この概念は、1934年慶應大学の田崎、加藤らにより示されており、当然私たちの習った生理学の教科書でも重要な事実として記載されていた。
この概念のカギは、絶縁体ミエリンによって完全に絶縁されることで、ノード間の軸索は一本の電線としてモデル化できる点だった。
ただ電子顕微鏡による観察や、神経の詳細な活動測定などにより、実際には軸索とミエリン鞘の間に存在する細胞外液も考慮したモデリングが必要ではないかと考えられるようになってきていたようだ。また、ミエリン鞘も生きた細胞である以上完全絶縁などあり得ない。この研究では、軸索の電流、神経細胞膜の電位依存性のアクションポテンシャル回路(医学生にはおなじみの抵抗とコンデンサがセットになった回路)、軸索とミエリン鞘の間の電流、そしてミエリン膜のアクションポテンシャル回路を全て加えたモデルを構築している。モデル自体は生理学を習っておれば理解できるが、この新しい回路を加えることで実際のシミュレーション計算はスーパーコンピュータが必要な大変な作業になるようだ。
いずれにせよ、それぞれの回路の抵抗、コンデンサのキャパシタンスを変化させてシミュレーションすると、やはり軸索街の経路を考慮した方が実際の観察に適合することを確認した後、このモデルから計算される抵抗などの数値が、実際の形態観察に一致することを示している。また、このモデルではアクションポテンシャルこそおこらないが、ミエリン被覆の領域でも電圧の変化が見られることが予想されるが、実際にそれが観察できることも、長い神経を分離して培養し、軸索の電圧を可視化する方法で確認している。
自分が理解できるところだけつなぎ合わせて紹介すると以上が結果で、新しいモデルの方が実際に跳躍伝導が減衰せず早く伝わることを説明できる。軸索とミエリン鞘の間が広いほど抵抗が低くなることから、跳躍伝導の速さはこの広さを反映すると予想できるが、その好例として、最も早い神経伝達が可能なウシエビの神経では軸索ミエリン鞘の間が100ミクロンもあることを示している。
今後はさらにミエリン鞘が切れる場所の特殊性も考慮した回路を加えてさらに精緻な跳躍伝導モデル形成することの重要性を強調して論文は終わっている。
言われてみれば当然の結果で、回路図だけをみるとなんとか理解できた気分にはなったが、実際にはこの上に様々なチャンネルの局在、樹状突起のなどが加わってくるはずだ。それを考えると、新しい技術のおかげで脳全体での活動がよくわかったような気になっても、その背景の一本の神経軸索の複雑さを考えると、理解するとはなんなのか、ゴールは何なのか、立ちすくんでしまう気分になる。
今年もそんな生命科学をめげずに紹介していきたい。
2020年1月1日
読者の皆様明けましておめでとうございます。今年も毎日新しい論文を紹介していきたいと思いますのでよろしく。
さて、1月2日号のNature では今年注目すべきサイエンスイベントをまとめて伝えている。論文ウォッチでは、この「The Science Events to Watch for in 2020 (今年注目のサイエンスイベント)」を紹介して今年の幕をあける。
火星探検
Mars Roverが送ってきた赤茶けた火星の大地の写真をは、火星探検での米国の圧倒的リードを示しているが、今年もNASAは火星の岩のサンプルを採取して地球に帰還したり、ドローンを飛ばす火星探査機を送る。ただ、今年は火星がさらに賑やかになりそうで、中国が独自の探査車の着陸、ロシアのロケットによりヨーロッパの探査車が火星に到着する予定になっている。火星以外では、日本のはハヤブサが竜宮から、NASAのOSIRIS-EXが小惑星のサンプルを地球に持ち帰る。
天文学
昨年のトップニュースはブラックホールのイメージを捉えたことだが、今年も天の川の中心にあるブラックホールをイメージ化する予定になっている。また、ヨーロッパの宇宙局は今年後半に天の川の3次元マップをアップデートする予定。重力波の観察分野では昨年観察された宇宙衝突からの波を観察できるのではと期待されている。
巨大加速器の夢
素粒子科学では、ヨーロッパで計画されている100kmに及ぶ巨大加速器プロジェクトを進めるかどうか決める会議が5月に行われる。210億ユーロという巨大プロジェクトなので、世界が注目している。一方、米国ではミューオンの磁場中での挙動の精密な測定結果が明らかになる予定で、この観測で少しでも予想外の挙動が示されれば新しい素粒子の発見につながると期待されている。
地球温暖化問題に対するアクション
国連の環境プログラムから気候変動へのアクションプログラムが示される予定だが、この中には大気中の炭酸ガスを吸収するプログラムも含まれる。一方、国際海底機構は海底での採鉱を推進するための規制案を提出する予定になっている。しかし、把握が難しい海底での採鉱が取り返しのつかない環境破壊につながるのではと懸念されている。またCOP26がグラスゴーで開催され、各国が炭酸ガス削減目標を示す予定だが、米国の脱退も含めて期待は急速にしぼんでいる。
米国の大統領選挙
大統領選挙の翌日が、パリ協定からの正式離脱の日になる。トランプが当選すればそのまま離脱。しかし、民主党が大統領選挙に勝利するとこの流れを阻止できる。
マウスと人間のキメラ
昨年日本で許可された中内さんたちの、マウスや豚の胚にヒト多能性幹細胞を導入するキメラ動物作成に倫理的注目が集まっている。個人的な感想だが、キメラに対するアレルギーは欧米の方が強い気がする。
常温超電導
昨年常温での超電導が達成できたが、ただ何百万気圧という途轍もない環境が必要だった。この時使われたランタン・スーパーヒドリドの代わりに、イットリウム・スーパヒドリドの合成に期待が集まっている。
Mozzieの逆襲
ボルバッキアを感染させた蚊を環境に放出して(メカニズムは以前紹介したブログ参照:https://aasj.jp/news/watch/10603 )デング熱を媒介する蚊を撲滅するインドネシアでの実験結果が発表される予定。 また、赤道ギニアの島で行われているマラリアワクチンの結果にも期待が集まっている。
固体エネルギー
ペロブスカイトを用いた太陽光発電システムが市場に登場すると考えられている。これによりシリコンより安く効率の良い発電を可能にすると期待されている。また、現行のリチウムイオン電池より安全、高効率、軽量の電池として期待される全固体リチウムイオン電池を装着した最初の自動車が、トヨタ自動車により東京オリンピックでお披露目されると期待されている。
合成酵母
4大陸15研究室が共同して行なっている出芽酵母の遺伝子を、合成遺伝子で置き換えるプロジェクトが今年完成すると期待されている。個人的には、このプロジェクトにより真核生物のゲノムをどれほどコンパクトにできるのか興味が尽きない。
生命科学領域とは違う話が多いので、ここにリストされた話題をどこまでこのブログで紹介できるかわからないが、論文が発表されればできるだけ取り上げていきたいと思うので乞うご期待。