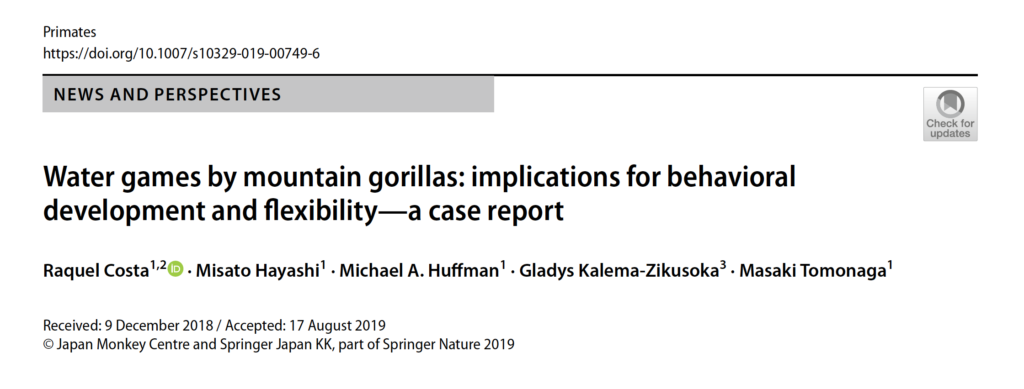2019年9月22日
これまでなんども紹介しているように、デニソーワ人ゲノムは解析されているが、残っている骨格はほとんどなく、どんな姿だったのかがわからない。例えばゲノムレベルでデニソーワ人とネアンデルタール人は我々より近縁と言えるが、9月4日Science Advanceに(eaaw3950)パリ大学のグループは指の骨の形は私たちに近いことを発表している。ただ、中国内陸部から出土したこれまで由来がよくわからないとされてきた骨がひょっとしたらデニソーワ人かもしれないという可能性が生まれたため、急速に骨格がわかるのではという期待がある。
そんな時今日紹介するイスラエル・ヘブライ大学から、解読されたゲノムからデニソーワ人の骨格の形態を推察しようというチャレンジングな論文が発表された。手法自体はbelieve or notで、その正当性を評価はできないが、志はわかるといった論文だ。タイトルは「Reconstructing Denisovan Anatomy Using DNA Methylation Maps (デニソーワ人の形態をDNAメチル化マップから再構成する)」だ。
私たちの形態は遺伝子のオン・オフで決まっていくが、これを決めるのがエピジェネティックだ。ホモ・サピエンスと他の古代人のゲノムは概ね同じと言えるが、このオンとオフの違いをなんとか決めれば、形を想像できるのではないかというのが著者らの期待だ。
このon/offの機構はエピジェネティックと呼ばれ、多様なメカニズムが使われているが、そのうちのシトシンのメチル化は、メチル化によるDNAの経年変化の違いから計算でき、古代人のDNAのメチル化マップを作ることができるというのがこれまでの著者らの研究だ。本当ならこの論文を見落とすはずはないと思って引用を調べると、確かにあまり読まれない雑誌に発表されており、広く認められていないようだ。そこで一発起死回生を求め、今回の研究になったと思う。
研究ではDenisova3と呼ばれる体のゲノムと、2体のネアンデルタールゲノム、そして45000-7000前のホモ・サピエンスゲノムのメチル化DNAマップを作成し、現代の人間やチンパンジーのマップと比較している。
ただ、一般的なメチル化マップだけで形態を予想するほど私たちの知識は進んでいない。またメチル化自体all or noneではない。そこで、遺伝子のプロモーター部分で、強くメチル化されている部分のみを選んで比較し、他の人類と比べて遺伝子発現に差がありそうな遺伝子をリストしている。
そしてこの変化があると思われる遺伝子が、私たちの骨格にどのような影響があるのかを、形質とゲノムの関係をリストしたHPOデータベースから拾い出し、メチル化により変化した遺伝子発現をリストし、それを元に現代人の骨格に変化をつけて、最終的に形態を推察するという方法を取っている。
はっきりいって本当にこれでわかるのかが問題だが、骨格がわかっているネアンデルタール人についてこの方法を用い、例えば顔が長い、顎が広い、等々14以上の顔の形態変化を予測できるとしている。
結論の詳細を省いて、結果をNatureも紹介しているポートレート(https://www.nature.com/articles/d41586-019-02820-0 )で代えるが、まだまだbelieve or notのレベルだと思う。
とはいえ、論文自体は、はっきりと未来の方向性を見据えたいい挑戦だと気に入った。
2019年9月21日
米国ガン治療学会や世界肺癌学会で報告されたアムジェン社のK-ras G12C変異を標的とするAMG510の成績が話題を呼んで、アムジェンの株を押し上げているという報告が相次いでいる。非小細胞性肺癌10例のうち5例でガンが縮小し、残りのうち4例でガンの進行を止めることができたという結果だ。その後のさらに数を増やした結果では、例えば大腸ガンなどは肺癌ほど効かないかもしれないことがわかったが、それでもFDAは迅速審査を行うことを表明している。
なぜこれほどの騒ぎになるかというと、これまで開発がことごとく失敗してきたrasに対する分子標的薬に、臨床的光が見えたからだ。もちろん、長期効果を含めさらなる結果が出ないと、最終判断は難しい。しかし、俄然この分野が賑やかになったきたことは確かだ。今日紹介する英国クリック研究所からの論文も、動物実験だがK-ras G12C変異に対する分子標的薬をコンゴどのように使っていけるか示した研究で、9月18日のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Development of combination therapies to maximize the impact of KRAS-G12C inhibitors in lung cancer(K-ras G12C阻害剤の効果を最大にする併用療法の開発)」だ。
この研究の標的細胞はK-ras
G12C変異をもつガン細胞だが、最初はK-ras阻害剤の代わりに、下流のMEK阻害剤と、IGF1R阻害剤の組み合わせを用いてガン増殖を抑制する際、この組み合わせの効果をさらに高める標的分子をshRNA法を用いてスクリーニングするところから始めている。
この結果、mTOR経路の阻害によって、IGF1R経路阻害によるPI3K/AKT 活性抑制をさらに強く抑制することが可能になることがわかった。これは、K-ras変異によりガン細胞がIGFを分泌することで、IGF1Rに依存性を高め、さらにこの経路の活性がmTOR阻害により促進されるため、IGF1R経路の阻害効果が高まるためであることを明らかにしている。
以上、MEK, IGF1R, mTORに対する阻害剤を組み合わせることで、強いガン抑制効果があることがわかったが、この効果はK-ras変異のあるガンに特異的であることもわかった。
このように、下流のシグナル阻害実験から、標的の全てはK-ras変異と関わっていることがわかるが、これを知った上でK-rasG12C阻害剤をどう使えばいいのか?
実際、K-ras阻害剤だけでこれらのガンを抑制しようとすると、ほとんど効果がないか、あるいは3週間ほどで効果が効かなくなる。K-ras変異を代償するN-rasをノックアウトした細胞株をわざわざ用意して検討した結果、結局MEK 阻害剤だけK-ras阻害剤と代える組み合わせが最も効果があることが明らかになった。
以上が結果で、これだけならわざわざK-ras阻害剤を使うこともないように思えるが、臨床の現場ではMEK阻害剤はガン以外にも様々な影響が考えられるので、K-rasG12Cに特異的な阻害剤は、はるかに使いやすい可能性が高い。
この結論がどれほど受けいられれているのかわからないが、最近相次いで開発されているK-rasG12C阻害剤も、単剤での臨床試験ではなく、最初から現在のras下流治療に変える形での治験の方が高い効果が得られる可能性がある。実際、アムジェンの治験でも、効果がある場合もPartial Responseとされているので、是非根治を目剤したカクテルを考えて、治験を進めてほしいと思う。
2019年9月20日
実は先週、ウガンダに旅行し野生のゴリラやチンパンジーを求めて、KibaleやBiwindi国立公園の山中をトレッキングしてきた。特にゴリラは違ったファミリーとの出会いを求めて、2日連続で山歩きを敢行し、70を越した我が身の老化を思い知った。それでも、予想外に静かなゴリラ・ファミリーとの出会いは疲れを忘れさせた。そして、まだ歩けるうちに思い切ってウガンダ旅行を決断して良かったと、忙しい日本に帰って旅行を振り返っている。
そんな時、Primateという雑誌のオンライン版に京都大学の霊長類研究所と、ポルトガル、ウガンダの研究機関の研究者たちが、まさに私たちが歩いていた領域のゴリラファミリーを観察し続けた論文を発表しているのをみて興奮し、紹介することにした。タイトルは「Water games by mountain gorillas: implications for behavioral development and flexibility—a case report (マウンテンゴリラの水遊び:行動の発達と可塑性―一例報告)」だ。
京大霊長類研究所はコンゴで研究を行なっているとばかり思っていたが、野生とはいえ毎日1時間、入れ替わり立ち替わり8人ぐらいの観光客の訪問を受けるマウンテンゴリラも観察対象にしていることを知り驚いた。
おそらく私たちが見た2つの家族とは違う家族だと思うが、この研究グループはこの地区に生息する一つのファミリーの行動を、特に水遊びに焦点を当てて観察を続けていた。と言うのも、チンパンジーでは記録がある様だが、ゴリラが水遊びをすると言う記録はないらしく、水場の観察がしやすい場所で2018年1月から2月にかけて観察を続けている。
そして幸運なのか、あるいはかなり準備をしていた結果か、2ヶ月に満たない観察期間の内に3回ゴリラが水遊びをするのを観察するのに成功している。
1回目はKanywaniと名付けられている若いオスゴリラが、水飲みに出かけた時、水を飲むだけでなく、手を水中にいれて渦ができるのを見る行動を繰り返した。近くにいたメスのKamaraも同じ様な動作を繰り返していたが、Kanywaniがドラミングで誘っても反応せず、それぞれ勝手に遊んでいた。
2回目は全メンバーが水場に降りてきた際、Kamaraが水の上にしゃがみ込んで水しぶきをあげる行動を繰り返した。そこにKanyndo,
Kabunga, Kanywaniが近づいて、一緒にではなくそれぞれ独自に水しぶきをあげる遊びを繰り返した。
3回目は2回目に登場した7歳のオスKabungaが、ほんの短い瞬間水しぶきを上げて遊んだが、シルバーバックが近くにいたためか、すぐに遊びをやめた。
以上が結果で、たった3回の水遊びの観察かなどと思われるかもしれないが、実際に観察してみると、2時間にわたって眺めていて、ただただ草を食べているのしかわからなかった私と違い、さすがプロだと思う。
この様な小さな発見の積み重ねが、人間とサルの違いを教えてくれるのだろう。
などとわかった様なことは言わないでおく。今日の記事は、京大の後輩(おそらく)が、同じ場所に観察に来ていたと言う興奮と、撮影したシルバーバックの写真を見せたくて書いた。
2019年9月20日
ガンの根治の話になると、今は免疫療法が真っ先に挙がってくるが、ガンの増殖に必要な分子標的薬の開発も活発に続けられている。最近騒がしくなったrasに対する分子標的薬については、明日紹介したいと思うが、今日紹介するコールドスプリングハーバー研究所からの論文は、は分子標的薬として開発された多くの薬剤が、実際にはその標的ではなく、他の標的に対する薬剤である恐ろしい可能性を示した研究で、9月11日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Off-target toxicity is a common mechanism of action of cancer drugs undergoing clinical trials (標的外の毒性は現在治験中の薬剤にしばしば見られる作用機序)」だ。
この研究では現在治験が行われている薬剤の標的として報告されている分子を6種類(CASP3,HDAC6,MAPK14, Pak4, PBK, PIM1)取り上げ、本当にその薬剤がこれらの分子を標的にしているのか、そしてそもそもガンの増殖がこれら標的を必要としているのかを、クリスパーを用いて遺伝子を完全にノックアウトする手法を用いて調べている。
方法の詳細は省くが、薬剤スクリーニングに用いられたガン細胞株から各遺伝子を完全にノックアウトした細胞を作ってみると、驚くことにこの6種類の分子はガン細胞の増殖に必要ないことがわかった。なぜこんなことになるのか、例えばよく似た分子の発現が高まったりした可能性など、いくつかの可能性を調べたが、結局これらの分子は調べたガン細胞の増殖には必要ないことを確認している。
ではなぜ薬剤開発で標的分子を間違ってしまったのか?通常標的分子の必要性の確認はRNAiなどノックダウン法を用いて行われているので、ここに間違いがあるのではと考え、ノックダウンの標的分子をノックアウトされた細胞でRNAiテストを行うと、標的分子がないにも関わらず、ノックダウンの効果が見られることがわかった。すなわち、RNAiは特異性とは異なる毒性を持つことがわかった。
そこで治験中の薬剤の効果を同じように分子標的をノックアウトした細胞でテストしてみると、分子標的がノックアウトされていても薬剤はコントロールのガン細胞と同じように効果を示すことがわかった。すなわち、分子標的薬として治験中のこれらの薬剤は、ガンに対する効果があるが、他の標的を介して効果を発揮していることがわかった。
そこで最後にPBKに対する分子標的薬という名目でオンコセラピー社が現在開発中のOTS964の標的を、OTS964抵抗性の細胞株を樹立して調べると、なんとCDK11で、キナーゼではあってもPBKとはあまり類似性のない分子であることを示している。
驚くべき論文だ。もちろんここで取り上げられた多くの薬剤は、ガンに対する効果を示すため、効果があればそれでいいとも言える。しかし、それぞれの薬剤が標榜する分子標的とは全く関係ない場合は、やはり使用中に様々な不都合が出てくることは明らかで、注意が必要だ。
この研究では、どのプロセスで標的を間違うのかについてもいろいろヒントを題している。最もテストに使われるRNAiが実は人食い的効果があることを知って驚いた。結局、最初のスクリーニングで分子標的が頭にあると、それを中心に全てが進んでしまってこんなことになるのはよく理解できる。少なくとも治験中の薬剤については、完全ノックアウト細胞株でのテストを義務付けることから始めてみればいいように思う。
2019年9月19日
16SリボゾームRNAの配列を指標にして、その場所に存在する細菌の種類と割合を解析する細菌叢のメタゲノム解析のおかげで、私たちの体の中にある細菌叢が果たしている様々な役割について理解が深まった。ただ、この手法の問題は、サンプルとして用いた便や唾液など、データ再現のために保存しておけるが、しかし研究のほとんどは相関を調べることで終わってしまい、その細菌叢の機能的側面をもう一度調べ直すことはできなかった。
これに対し今日紹介するマサチューセッツ工科大学からの論文は解析した細菌叢を培養して、そこに含まれる細菌の機能を何度でも調べることが可能な培養ライブラリーを作成するための研究でNature Medicineオンライン版に掲載された。タイトルは「A library
of human gut bacterial isolates paired with longitudinal multiomics data
enables mechanistic microbiome research(人の腸内細菌の培養細菌ライブラリーと継時的な多元オミックスデータを組み合わすことで細菌叢のメカニスティックな研究が可能になる)」だ。
このグループは、人間の大便中の細菌叢を、あとで何度でも機能実験に使えるよう、含まれる細菌叢をできるだけそのまま培養ライブラリーとして残そうと考えた。ただ、細菌叢に含まれるあらゆる細菌をそのまま培養することはほぼ不可能といえる。そこで、12種類の異なる培地を用いて細菌叢を培養し、それぞれの培地で増殖してきた細菌ライブラリーを11人から形成している。
この研究では、主に一般培地と著者らが呼ぶ選択性をできるだけ排除した培地で増殖してくる細菌について主に述べている。この培地はかなり多くの細菌の増殖を支えることができ、11人から7758種類の細菌を培養で分離することができた。こうして分離された細菌はこれまで細菌叢のデータベースに登録されている何種類かの属のほとんどを含んでおり、細菌叢の一つの代表としてバイオバンクとして維持することができることを示している。
もちろん培養することで失われる属も多く存在するが、逆に16S解析では発見できなかった細菌属が培養では見つかることもある。実際、両方の方法で共通に見つかる細菌でも、その割合はほとんど相関していなことから、培養はフレッシュな便の16S解析を反映しているとは言えず、別物と考えたほうがいい。さらに培養により増殖してくるそれぞれの細菌種は、個人・個人で大きく異なっており、選択培地を用いて培養して増殖する細菌種を絞っても多様性は残る。このように、従来の16Sメタゲノムと異なる点も多いが、様々な利点が存在する。
まず培養されたライブラリーを用いるとかなり精度の高い、全ゲノム解析が可能で、ほとんどの細菌のゲノムをほぼ完全に解読することが可能になる。その結果、遺伝子変異に基づいて解析する系統樹に加えて、同じ遺伝子の存在を比べることで解析するgene content 解析が可能になる。この結果、同じ細菌でも集団内で遺伝子が欠損したり、獲得されたり急速に進化することがわかる。
さらに、細菌叢自体毎日変化する。このため、一点だけの結果では実態を反映できないことが多いが、異なる時点を何点かとってそれを平均すると、各個人に特徴的なプロファイルを特定することが可能になる。細菌叢が培養されたライブラリーでは、異なる5日間ぐらいのサンプルをプールすることで、個人個人の平均化したライブラリーを作ることができる。
さらに、増殖しているライブラリーの中に存在する薬剤や、殺菌剤に対する抵抗性の細菌を培養で特定することもできる。
他にも継時的な細菌種の進化の様子や、メタボロームのバリエーションなど様々な実験をしているが、割愛していいだろう。今回細菌叢を培養ライブラリーとして残すことで、これまで現象論で終始していた細菌叢解析に、何度も繰り返し実験可能な材料(宝の山)が提供されるようになった。
個人的にはメタゲノムに終始している細菌叢研究については食傷気味だったが、これで新しい展開が見られるのではと期待している。
2019年9月18日
亡くなった笹井さんがES細胞などの多能性幹細胞から神経細胞の誘導に取り組んだのは、京都大学の再生研究所が出来た時、暫定人事委員会で最初に選んだ三人のうちの一人(最年少)として教授になってからで、この開発を担ったのが現在金沢大の河崎さんだ。その後、京大の職を完全に辞してCDBに来てからは、あれよあれよというまに、各神経細胞系統だけでなく、脳の構築まで試験管で作れることを示して、大きな話題を呼んだ。実際、当時彼の研究室で開発された技術の上に、日本最初のiPS臨床応用としての網膜色素細胞移植や、ドーパミン神経移植が結実しており、文字通り日本の再生医学を導いたと言える。当時の彼のプロダクティビティーは恐ろしい勢いで、おそらく彼も自信を持ちすぎ、その結果さまざまな妬みを買ったのが、彼の死の原因になったように思う。
ただ、臨床応用は同級生の両高橋先生に任せ、彼自身はオルガノイドに結構執心だった。私自身は、ES細胞を神任せで培養する方法は、科学とは言えないなどと批判側に回っていた。しかし、脳のオルガノイドは私の想像を超えて発展しつつあるように思う。今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文はうまくオルガノイドを形成させると、胎児の脳に見られる自発的神経活動が観察できることを示した研究で10月3日号のCell Stem Cellに掲載された。タイトルは「Complex Oscillatory Waves Emerging from Cortical Organoids Model Early Human Brain Network Development (脳皮質のオルガノイドを用いた初期脳神経ネットワーク発生系で発生する複雑な神経振動波)」だ。
改めて読んでみるとヒトの脳皮質のオルガノイド形成実験は時間のかかる研究で、このグループは人間の妊娠期間と同じ10ヶ月を要してようやく成熟型で安定したオルガノイドが形成されることを様々な方法で示している。中でも、単一細胞遺伝子発現を調べる方法を用いた解析から、GABA 作動性の抑制神経ができるのは6ヶ月を越してからであることを示している。
こうして一見実際の皮質に近い細胞種と構築を持ったオルガノイドができるが、この研究ではこのオルガノイドが神経活動という機能性でも、正常の皮質に匹敵するか調べるため、クラスター電極を用いて活動を継時的に拾っている。
すると、オルガノイドが成熟するにつて、4ヶ月頃から1-4Hzの脳の振動波が観察されるようになり、6ヶ月目では完成する。そしてGABA作動神経系が分化してくると、今度は100Hz近い早い脳波が形成される。そして、この振動波がグルタメートと、GABA作動性のシナプス活動の反映として得られることを示している。
そして、こうして生まれるオルガノイドの神経活動が、35週目の脳波と極めてよく似ていること、そして脳波のパターンを学習させたAIを用いて、オルガノイドの活動の胎生時期を予測させると、実際の培養期間とAIによる推定年齢がほぼ一致することを示し、このモデルがかなり正常の皮質形成プロセスを反映していることを示している。
おそらくここまで精密なオルガノイドを安定して形成するには、かなりノウハウが必要だと思うが、これが可能になると自閉症などグルタミン酸作動性とGABA作動性のバランスが変化する多くの状態の再現も可能になると期待できる。面白くなってきた。
2019年9月17日
カドヘリンは言わずと知れた、CDBの設立と発展のため京大を離れて共に苦労していただいた竹市先生が発見された分子で、中でもE-cadherinはクラシカルカドヘリンと呼ばれる一丁目一番地だ。当時、医学系の私に、E-カドヘリンが消化器ガンの転移の際に低下することを話してもらった覚えがあるが、転移はまず元のガンから離れる必要があり、当然のことかなと思った。
しかしガンによっては様々で、原発から離れる場合も、一時的にカドヘリンの発現が抑制される上皮間葉転換が起これば、必ずしもずっとEカドヘリンの発現が抑えられる必要はない。今日紹介するジョンス・ホプキンス大学からの論文は乳がんの転移にはE カドヘリンが必要であることを示した研究でNatureオンライン版に掲載された。タイトルはズバリ「E-cadherin is required for metastasis in multiple models of breast cancer (E カドヘリンは様々な乳がんモデルの転移に必要)」だ。
このグループは転移乳がんでは、転移先の組織で管腔形成が起こり、Eカドヘリンも発現していることから、本当にEカドヘリンが必要か、必要に応じてEカドヘリン遺伝子をノックアウトできるようにした乳ガン細胞株を用意し、ガン転移に関わる様々な活性を調べた。
まず原発巣から外れて組織へ浸潤する試験管のモデルで調べると、確かにEカドヘリン遺伝子を欠損させると、浸潤性が高まり、試験官内で形成されるオルガノイドから播種が起こりやすい。またガンを移植し周囲を調べると、周りに浸潤しているガン細胞はEカドヘリンを発現しておらず、Eカドヘリンがない方が確かに転移には有利になるように思えた。
しかし次にガンを移植して転移を調べるとEカドヘリン欠損ガン細胞はほとんど転移が見られない。また静脈に直接ガン細胞を注射する転移アッセイでも、Eカドヘリン欠損乳ガンは全く転移が見られない。すなわち、浸潤にはEカドヘリンを抑える方がいいが、転移は全く逆でEカドヘリンが必要になる。
そこでこのメカニズムを調べるために様々な実験を行なっている。ひとつ面白い現象は、乳ガンの特徴である末梢血にガン細胞が流れ出る循環腫瘍細胞についてEカドヘリン有り無しで比べると、Eカドヘリン欠損株を移植したマウスでは循環腫瘍細胞の数が強く抑えられている。すなわち、細胞は浸潤しても循環には流れにくいことがわかる。
最後にEカドヘリン有無での遺伝子発現の比較から、Eカドヘリンが欠損すると、Eカドヘリンが欠損すると活性酸素が高まりアポプトーシスが亢進すること、そしてこれがTGFβシグナル依存性に起こることを示している。すなわちTGFβシグナルを抑制する、あるいは活性酸素を抑えると、Eカドヘリン欠損株でもオルガノイドを形成できる。
以上の結果から、Eカドヘリンが転移には必要だと結論している。ただ、このシナリオが他のガンにも当てはまるのかはまだまだよくわからない。最後はちょっと強引な気がしたが、今後臨床で検証できれば、転移を抑える治療標的を考える意味では面白いと思う。
2019年9月16日
胎児の発生は妊娠中のさまざまなストレスにより大きく影響される。これは放射線のように遺伝子の変化によるものより、遺伝子発現を調節するエピジェネティックな変化が誘導される場合の方が多い。最も有名なのは第二次大戦時に強い飢餓状態にさらされた妊婦さんから生まれた子供に認められた変化で、例えば中年を越してからインシュリン分泌が低下する形の糖尿病が多発したことが知られている。もちろん妊娠中の飲酒も胎児のエピジェネティックスに影響して本来抑えられていた内因性ウイルスが活性化されることが知られている。しかし、まだまだ研究が必要で、特にメカニズムについては動物モデルでの研究が重要だ。
今日紹介するトロント大学からの論文はビタミンC不足の胎児発生、特に生殖細胞発生について調べた研究でNatureオンライン版に掲載された。タイトルは「Maternal vitamin C regulates reprogramming of DNA methylation and
germline development (母親のビタミンCはDNAメチル化をプログラムし直し生殖細胞発生に影響する)」だ。
エピジェネティックスの変化を誘導する要因の一つがDNAメチル基をハイドロオキシ化するTET酵素だが、このレベルがビタミンCにより変化することがすでに知られていた。この研究では妊娠前3日から胎生13日まで、マウスのビタミンC摂取を制限したい時発生への影響を見ている。
驚くことに、ビタミンCを制限しても胎児発生自体は正常に進むが、唯一生殖細胞数だけが、減数分裂の進行が抑えられるために強く抑制されることを発見する。さらに、ビタミンC欠損下で発生したマウスの生殖細胞を調べると、卵子の形成が低下しており、さらに妊娠しても着床が低下し、また流産が多いことを確認している。すなわち、ビタミンCの摂取不足は胎児発生自体は見た目正常でも、特に卵子の発生が抑制され、卵子の機能も異常であることが明らかになった。また、この異常は13日以降ビタミンC摂取を元に戻しても元に戻らない、胎児期のエピジェネティックな変化によることも確認している。
次にメカニズムを調べる目的で胎児DNAのメチル化状態を調べ、Tet1ノックアウトマウスと同じようなメチル化異常が誘導されていることを明らかにし、またビタミンC不足により組織のハイドロオキシメチルDNAが低下することから、ビタミンC不足による以上の一因がTET1の発現低下によることを示唆している。
実際メチル化の異常により変化する遺伝子の多くは、卵子分化過程でメチル化が外れることが知られる遺伝子で、この結果減数分裂時に必要な遺伝子の発現が抑えられ卵子発生の異常が誘導されると結論している。
結果は以上で、ビタミンC不足といった非特異的な変化でも、DNAメチル化の大きな再構成が進む生殖細胞がエピジェネティックなストレスにさらされやすいことを示した、臨床的には重要な研究で、今後他の要因についても、子供世代の生殖能力についての研究が必要であることを示唆する臨床的には重要な研究だと思う。
2019年9月15日
1990年ぐらいから様々な血管形成に関わる因子が明らかにされ、またノックアウトマウス技術も広く普及したため、血管生成の研究は急速に進んだ。そのとき多くの研究者が焦点を当てた分子がTie1とTie2と呼ばれる受容体と、そのリガンドで、もちろんどちらをノックアウトしてもマウスは胎生致死になった。ただ、リガンドが特定されているTie2と比べると、Tie1は現在もなお明確なリガンドが特定されておらず、血管新生への関与はTie2と膜上で結合してダイマーを形成することが主ではないかと考えられてきた。
今日紹介する中国広州南医科大学からの論文は肝臓繊維化の研究から繊維化促進因子として発見されたLECT2がTie1と結合して肝臓の血管形成に大きく影響することを示して、長年の謎を明らかにした研究で9月5日号のCellに掲載された。タイトルは「LECT2, a Ligand for Tie1,
Plays a Crucial Role in Liver Fibrogenesis (Tie1のリガンドLECT2は肝臓の繊維形成に決定的な役割を演じている)」だ。
おそらくこのグループはTie1を念頭に置かず、人間の肝硬変の程度と強く相関する分子マーカーとして、LECT2を特定し、この分子の機能を調べ始めたと思う。
まず4塩化炭素を用いて肝硬変を誘導すると。LECT2レベルは上昇する。またこのモデル系でLECT2遺伝子をウイルスベクターで過剰発現させると、肝硬変は悪化するし、逆にノックアウトしておくと肝硬変は軽減される。すなわち実験的にLECT2が肝硬変を促進する分子であることを確認する。
そしてこの肝硬変の背景に肝臓の類洞の毛細血管増生が起こる一方で。門脈系の血管低形成が存在し、この結果肝臓への血流が低下し、繊維化が起こること考えている。この、類洞の構築が壊れて毛細血管化するという現象はTie2の関与を疑わせる。
そして、LECT2とTie1がリガンドと受容体として直接相互作用すること、またノックアウトやノックダウンでLECT2の作用はTie1が必要であることを明らかにする。ついにTie1と結合する分子が同定され、これが血管形成に関わることが確認された。
次はLECT2のシグナル伝達機構に取り組み、LECT2がTie1/Tie2の結合を阻害してTie2/Tie2の結合を安定化させることで、Tie2へのシグナルを促進し、血管内皮の移動や管腔形成を抑え、同時に門脈形成を抑制すると結論している。肝臓には、一般の血液系と門脈系が存在するが、それぞれがLECT2に対して異なる反応を示すのは面白いが、メカニズムについてはさらに研究が必要だ。
最後に、様々な肝硬変モデルをLECT2のshRNAを肝臓に導入することで肝硬変を抑制できることを示し、この経路を肝硬変の治療標的として使えることを示している。
まだまだメカニズムについては明らかにする点が多いと思うが、Tie1に直接結合するリガンドとしてLECT2を特定し、しかも肝硬変に血管新生異常が強く関わっているというこの結果は、血管形成の研究でもまだまだ新しい分子の道程が必要なことを物語るように思えた。
2019年9月14日
ホモ・サピエンスは、ほぼ10万年かけて先住民のネアンデルタール人やデニソーワ人と交雑を繰り返しながら、地球全体に広がり、各地で独自の民族を形成した。各地に分かれていたとしても、他の類人猿と同じで、その土地にあった狩猟採取民として独立して生活していた。各民族間での交流・交雑があったことはゲノム的にも、考古学的にも明らかになっているが、大きな民族構成の変化はなかったと言っていい。
しかし、その後農業の発生に端を発する文明の変化によって、文明の再構成が起こったことがわかっている。わかりやすく言えば、植民地化されたアフリカやアメリカが文化的(例えば言語や宗教)に統合された状況を考えればいい。この文化的統合の際、中南米では交雑が進み、白人のゲノムの流入が強く見られたが、アフリカではそれほどでもないように思える(これは検証なしの私の印象)。このように、文明の拡大には民族のゲノムの置き換えを伴う場合と、置き換えがほとんどない場合の2種類あり、この理由がわかれば歴史的に面白い。
今日紹介するゲノム解析による先史時代の解析の大御所、ハーバード大学Reich研究室からの論文は、中央アジアからインドにかけて、文明が勃興した時代を、中央ヨーロッパ、イランからインダスにまたがる遺跡から回収した500人を超すDNAについて全ゲノムを解析した膨大な研究で、9月6日号のScienceに掲載された。タイトルは「The formation of human
populations in South and Central Asia (南および中央アジアの民族形成)」だ。
人ゲノム解析の成功が公表された2004年にはまだ、こんな日が来るとは想像だにできなかったが、この研究ではなんと約1万年前から紀元前1000年まで中央アジアからインドを中心にユーラシア全体にわたる遺跡から出土した骨のDNAを解析して、すべての全ゲノム解析と、アイソトープによる年代測定を行なって、それぞれの場所に形成された民族の交流を明らかにしようとしている。
基本的には、ゲノムデータを用いて民族間の系統性および交雑を調べ、それと出土した年代を組み合わせて、文明の伝搬を明らかにしようとしている。524人の全ゲノム解析というだけあって、データは膨大で、実際にはこの論文だけで簡単に終わらせられるはずもなく、一種の中間報告と考えたほうがいいように思えた。今後他の地域の古代ゲノムの解析が進むと、さらに大きな歴史が描かれるような予感がする仕事だ。
全部を紹介できるとは到底思はないので、個人的に興味を持った点だけを箇条書きにしてまとめた。
インドヨーロッパ語と言われるように、カスピ海と黒海に挟まれた領域に発生したYamnaya民族の言語を共通に有している民族がヨーロッパからインドまで広い範囲に広がっている。これまでの研究では、西ヨーロッパへの伝搬は、Yamnaya民族のゲノムが先住民のゲノムを置き換える形で進み、ヨーロッパ民族のYamnaya民族ゲノムの割合は50%近くに登る。この研究では、同じYamnaya由来言語を話すインドについても詳しい解析が行われ、確かにYamnayaゲノムは流入しているが、極めて少なく、西ヨーロッパのようにYamnaya人のゲノムでゲノムが置き換わるということはなかった。 中央アジアの民族は2000年BCEまではイランから移ってきた農耕民が中心だったが、2000年BCE以降Yamnaya民族のゲノムに急速に置き換わってきてカザフスタンを中心とするトゥーラン民族を形成する。 このYamnayaゲノムを多く受け継いだ中央アジアの民族が南インド民族と交流して、2000-1000BCEにインダス民族を形成する。すなわち、現在のインド民族は、イランからの農民、Yamnaya、そして南インドの先住民のゲノムを中心に構成されていることになる。 最後に最も興奮したのは、現在のインドのカーストが、Yamnayaゲノムの割合と強く相関しているという発見で、カーストのトップを占める言語を管理する役目を担ってきた僧侶階級にYamnayaゲノムの割合が高いことは、言語を通した古代の支配関係が、そのまま民族内のカーストとして維持されている現実を見ることができ、民族の形成とは、階級の形成でもあることがよくわかった。 他にも多くの発見が述べられている論文だが、私の好みの結果だけを紹介した。いずれにせよ、新しい歴史学の時代が来たことを実感される力作だ。