これまで12回、ギリシャ、ローマ、中世と哲学書を読んできた。大学時代から今まで、古典的な哲学書も比較的読んできた方だと思うが、系統だって読むことはなかった。時代を追って哲学書を読むという体験は今回が初めてだ。哲学を教えているわけでもないのに、ちょっと馬鹿げているとは思ったが、「この機会を逃せばもう気力は失せるだろう」と読み始めて、そろそろ一年になろうとしている。こんなことでもなければローマ時代や中世哲学書など手に取ることはまずなかったと思う。「しんどいか?」と問われれば、確かに「しんどい」し、何より他のことを犠牲にして本を読む必要がある。すなわち、論文を読むときと同じで読書が義務になる。しかし、しんどいだけではない。中世の著作でさえ、現代の哲学にまで続くルーツを発見することができるし、何よりもアリストテレス、オッカムなど、実際に読んでみないとその価値はわからない著作にも出会うことができた。とはいえ、ようやく中世を抜け出せるかと思うと、正直ホッとする。
近代哲学に突入できれば、一度は読んだことのある哲学書が多い。また紹介しながら、現代の科学や、生命科学の課題へ話題を広げて議論も可能だし、自分の考え(と言っても多くの人の考えに触れる中で形成することができた考え)を積極的に紹介することもできる。などと考えて、パスカルやロジャー・ベーコンを読み始めた時、ドイツの若手哲学者マルクス・ガブリエルが話題になっているのを知って、講談社メチエとして出版された「なぜ世界は存在しないのか」と「私は脳ではない」の2冊を読んで感心した。
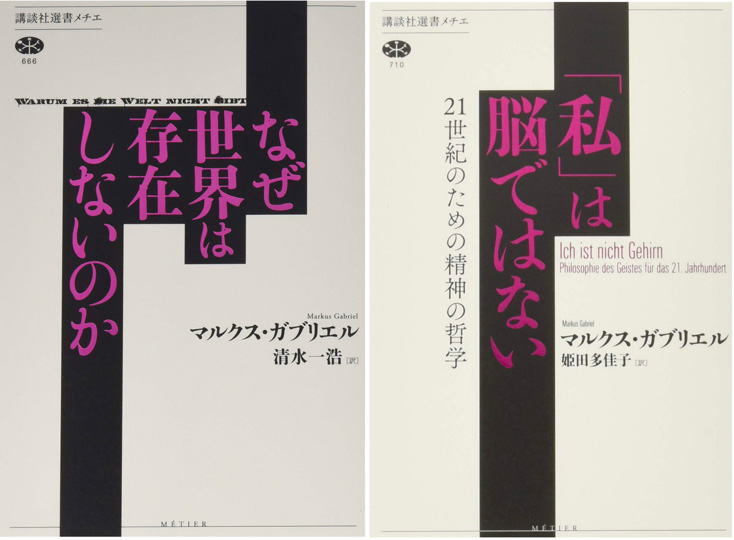
図1 講談社メチエで出版された2冊のマルクス・ガブリエルの著書
「生命科学の目」のバイアスを持つ私の好みの問題だが、現代の哲学者に限ると、ラカンやガタリといった大陸の哲学者より、米国の哲学者の方が、同じ課題を共有でき、身近に感じて来た。実際、米国の多くの哲学者は現代科学(特に脳科学)についての造詣が深いし、つねに科学者との対話を保っているのが感じられる。といっても科学哲学に取り組んでいるというわけではない。形而上学や精神といった哲学本来の問題に挑戦している。例を挙げれば、サール、ネーゲル、デネット、そして哲学者ではないが脳科学者のディーコンなどで、いつかここでも取り上げてみようと思っている。しかしマルクス・ガブリエルを読んで、これまで感じていた大陸の哲学・米国の哲学などという区別は解消した。あまり長くない2冊の本だが、内容は重厚で、まさに現代を代表する重要な哲学者の一人だと思う。これから近代哲学の著作を紹介するときも、参考になる点は多い。そこでちょっと寄り道して今回はマルクス・ガブリエルを取り上げることにした。
これらの著書でマルクス・ガブリエルは、「世界」や「精神」といった哲学本来の課題が、20世紀以降は科学の専権課題になっているが、本当にそれでいいのか?と問う。そして科学にとらわれず多様な角度からのアプローチが必要で、哲学でしか取り組めない問題も多く存在すると主張する。難しい哲学用語を使わない素晴らしい翻訳なので(といっても原文は読んでいないが)、詳しい内容については、是非みなさんが自分で読んで確かめて欲しいと思う。新型コロナ感染による自粛で時間ができた人たちには間違いなくオススメの本だ。特に私たち科学者は、彼が新たに提起した哲学の課題についてどう考えるのか自問した上で、自分が属している科学という領域を再確認する必要があると思う。もちろん私にとっても、生命科学の課題を再考する機会になった。しかし、科学の手法や課題についての彼の理解、そして科学では扱えないと彼が考える課題の位置付けについては意見の相違を感じる点も多かった。そこで今回は本の紹介というより、科学者として彼の投げかけた問題にどう答えるか考えてみたい。
まず彼の著作の簡単な紹介として、マルクス・ガブリエルを褒めるところから始めることにする。
読んでまず驚くのは、彼の分野を超えた膨大な知識だ。しかも、普通哲学書を読んでいるとき感じるアカデミックな匂いがない。驚くべき「物知り」と言ってもいいかもしれない。その知識は、哲学は言うに及ばず、自然科学、芸術など、人間のあらゆる文化をカバーしている。彼が天才と呼ばれるのはこの点だろう。驚くのは、これらの知識が全て、彼の独自の視点を展開するために総動員できるよう整理されており、さらに誰もが身近に感じられる文章で語られる点だ。すなわち、哲学が知識として蓄積され、それらが彼の言葉として語られる。
彼のもう一つの特徴は、多くの人にわかってもらおうと、たとえ話や具体例を多用する点だ。「なぜ世界は存在しないのか」で彼は「世界とは何か」という形而上学問題について、
「わたし自身の答えは、最終的には次のような主張に行き着くことになるでしょう。たったひとつの世界なるものなど存在せず、むしろ無限に数多くのもろもろの世界だけが存在している。そして、それらもろもろの世界は、いかなる観点でも部分的には互いに独立しているし、また部分的には重なりあうこともある、・・。」マルクス・ガブリエル. なぜ世界は存在しないのか (Japanese Edition) (Kindle の位置No.1335-1338). Kindle 版.
と独自の多元的認識論を提案する。すなわち、皆が共有できる一つの世界が存在すると考えるのは幻想で、独立しつつ重なり合う無限に多くの世界が現れるとする新しい多元論だ。その上で、我々の認識にとって存在とは、意味の場に現れたものを認識することだと語っている。
私が驚くのはこの議論自体ではなく、彼がこの概念を一般の人にわかりやすく説明する仕方だ。なんと、ジャクソン ポロックのアクションペインティング(私には意味を拒否した感性の塊としか見えないのだが、例としてウェッブ上の写真を見て欲しい:https://www.flickr.com/photos/piljun/6301137213)を例に概念を説明している点だ。そして、作品全体を眺めるだけでなく、一つの色に集中して筆の動きを読んでみるよう読者を促し、こうすることで一筆一筆がカンヴァス上の「意味の場」に提示されていることが理解され、私たちの頭の中に様々な「意味」の集まる「世界」が再構成されると語る。読んだ後ポロックの絵をもう一度見てもこの「意味の世界」は私のような凡人には見えてこないが、説明はとても新鮮だ。これだけで、十分ベストセラーになること請け合いだ。
美術の他にも、より大衆的な様々な映画も頻回に取り上げている。例えば、宗教、フェティシズム、商品と議論を進めた上で(なぜこのような連環が生まれるのかは本を読んで欲しい)、これを食肉消費(フェティシズム)、肉片から作られたソーセージ(商品)と連想して、最後にドイツの芸術家シュリンゲンジーフの「ドイツチェーンソー大量虐殺」の映画を例として解説している箇所は圧巻だ(彼についてはAASJでもYouTubeで取り上げている:https://www.youtube.com/watch?v=hbeG2z0lLJs&t=5976s)、。
「そのようなヴルスト業界の真実は、一度見たらトラウマになりかねません。そのような事態が、クリストフ・シュリンゲンジーフの映画作品『ドイツ・チェーンソー大量虐殺』では、美学的に見て爆発的とさえ言える表現にまで先鋭化されています」
と、私にとっては見るにたえなかった超グロテスク映画の新しい側面を教えてもらって、なるほどと膝を打った。
もちろん古代から現代まで、哲学者の引用も多い。大事なのは、大陸or米国、過去or現代、という区別なく、各哲学者の著作に現れた「意味の場」が、マルクス・ガブリエルの中に蓄積され、メタ概念として彼の言葉で語られる点だ。多くの哲学者の思想が自由自在に集められ、形而上学や、精神といった哲学本来の課題についてのまとまった概念として、一般の人にもわかりやすく示されていく。しかしわかりやすいからといって、決して哲学の解説書といった類ではい。古代以来、人間が知ろうと努力してきた課題に真正面から取り組んでいる。わかりやすく語ることができるのは、知識が本当に身についているからなのだ。
さらに感心するのは、彼が哲学と科学を決して区別していないことだ。というより科学に対する厳しい批判を行ってはいても、科学を同じ問題を共有するパートナーと考えている。現代科学についてもよく理解しているからこそ自信を持って語れる。科学と哲学がパートナーとして同じ課題に取り組まなければならない点については私も全く同感なのだが、現代の脳科学やダーウィン主義を、哲学の可能性を認めない還元主義として批判する点については (後述)、生命科学者として一言述べたいので、以下「私は脳ではない」を題材に、彼の課題と、科学批判について見て行こう。
この本で彼が目指したのは、「精神哲学:精神を持つ生物としての私たちについて理解すること」、と明快だ。言い換えると、なぜ宇宙の中に生命が誕生し、その中から精神が誕生したのかという問題だ。このように問題設定されると、「え?これが哲学の問題?」と、確かに驚いてしまう。例えば、米国のディーコンのように「宇宙になぜ精神が存在するのか?」を総合的に扱おうとしている科学者/哲学者(彼は認知科学の教授で、哲学者と表現するのは間違っているかも知れない)も存在するが、これほど包括的に問題提起する現代の哲学者はまずお目にかかれない。
科学の問題にも自由に踏み込む米国の哲学者ですら(例えばダニエル・デネット)、「意識:解明される意識」、さらに生物について「進化:ダーウィンの危険な思想」といった具合に、全体の中から一部を取り出し、哲学として議論するのがせいぜいだ。マルクス・ガブリエルのように精神を宇宙の中に位置づけて、その理解を目指すと明言する現代哲学者は、少なくとも私は読んだことがない。そして、精神や意識の問題は、包括的な理解を目指すべきだという考えには私も科学者として完全に同意する。
これまで紹介してきたように、ギリシャ哲学や、あるいはスコラ哲学では、宇宙の中の精神は哲学が取り組むべき当たり前の課題だった。ただ、近代が始まった時点から、このような包括的な課題は科学に任せれば良いという風潮が徐々にたかまり、現代に至っている。この結果、彼が指摘するように「宇宙の中の精神」のような包括的問題については、科学的自然主義か、それと対立する宗教的神秘主義だけが取り組む課題になり、哲学はもはや土俵を下りた感がある。
この状況に対し、マルクス・ガブリエルは「宇宙の中の精神を理解する」と言った包括的な問題は今もなお最も重要な哲学の課題であると主張する。ではこの問に対する彼の答えはなんだろうか?
がっかりさせて悪いが、イオニアの哲学者のように「万物は水からできている、とか原子からできている」などといった解答が示されるなどと期待しても、結局答えは示されない。しかしこれは当然だ。もしこの問題に彼が納得できる説明を示していたら、それこそ大騒ぎになる。事実、哲学どころか科学だって、誰一人として宇宙の中の人間の精神の存在を説明できる人などいるわけが無い。
代わりに「私は脳ではない」では、「意識」、「自己意識」「実のところ私とは誰、あるいは何なのか?」「自由」とセクションを設けて、それぞれの問題に関して、科学、哲学、宗教がこの問題にどうアプローチしたか説明していく。大事な点は、ここで登場する哲学者の引用が「xxxが意識についてこう語った」と言った紹介ではなく、各課題に対するこれらの哲学者の考えが一度彼の頭の中で咀嚼された後、彼の意見として語られる点だ。すなわち、それぞれの哲学者の引用は、すべて彼の頭の中にある思想の核とつながっている。科学では様々な知識が蓄積し、一つの問題に対してその蓄積を持って説明するのが普通だが、彼は哲学、宗教を問わず、あらゆる分野の思想を蓄積して、それを自分の言葉で語るスタイルが可能であることを示している。もちろんこんな離れわざは誰でもできるわけでは無いが。
一方、同じ問題に対する科学領域からの知識は、もちろん彼の頭の中で咀嚼されてはいても、基本的には批判の対象として、手厳しく扱われている。少し長くなるが、一つの例を見てみよう。
「私はミラーニューロンがあることを否定するつもりはありませんし、それがなければ自己意識にも、他者の意識に対する意識にも到達できなかったかもしれないということを否定するつもりもありません。まったく同様に、人間の精神の状態にとって重要な生物学的土台が、偶然の──つまり、それを目的にして計画的になされたのではない──遺伝子組み換えによって生まれ、その後、環境の圧力によって淘汰・選択されたことも否定するつもりはありません。この惑星に意識をもった生物がいること、もしかしたら他の惑星にも意識をもった生物がいるかもしれないことは、宇宙という観点から見れば、偶然の産物です。つまり、特別な理由があって、そうなったわけではありません。あるものはある、それだけのことです」マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.2576-2582).
と、精神の存在が、宇宙誕生以来の必然であるように語る科学(ほぼ物理学とオーバーラップする)に対して反論している。そして、特に最近になって科学は、宇宙から精神までいつか解明できるという思い上がった考えを持つ傾向があることを次のように批判している。
「宇宙の真理についての無知ゆえに、人間には精神をもつ生物としての己の立場を誤って判断する傾向がありますから、神経生物学のフィールドで我々の認識が進歩すれば、それは当然、自己認識の進歩に役立ちます。なぜなら、太陽は私たちが物を見るために輝いているとか、私たちに意識と自己意識があることは、「地上で」繰り広げられる見世物をはるか彼方から文字どおり見物する神の栄光のために催される一種の精神的シンフォニーであると信じるなら、まさに相当な勘違いですから。とはいえ、我々は神経生物学の知識のおかげで、自己意識について、エンヘドゥアンナ、ホメロス、ソポクレス、龍樹〔ナーガールジュナ〕、ジェーン・オースティン、アウグスティヌス、ビンゲンのヒルデガルト、ジョルジュ・サンド、ヘーゲル、ベッティーナ・フォン・アルニム、あるいはマルクスが有していた以上の理解を手にしていると考えるなら、それは誤解です。」マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.2595-2603).
ここでは、「神の栄光を信じる」宗教と比べると、科学は宇宙の真理対してよりまともなアプローチしているとは言え、古今の多くの哲学者の思想を凌駕できていると考えるのはまだまだ早いと述べています。
おそらく彼も、多くの科学者が、科学は全てを説明できるなどと思い上がることなく、黙々と目の前の問題に取り組んでいることを知っているはずだ。しかし、今も昔も、科学は宇宙から精神まで説明したいと考えようとしてきたのも確かだ。そして、この時こそ科学が思い上がる時だと彼は語る。例えばこの本では、利己的遺伝子のドーキンスや、神経学者エリックカンデルを名指しでこの思い上がりの例として批判している。しかしドーキンスもカンデルも、私たち科学者側では、哲学の素養があり、大きなパースペクティブで生命や精神を語れる科学者だと評価し尊敬されている。
彼が言いたいのは、科学者が科学を盾に「宇宙の中の精神」という「一つの世界」を普遍的に語ろうとするときに、落とし穴に落ちるという点だ。確かに私も含めて科学者も、大きな問題に大上段で構える時、哲学をしばしば引用する。これはすでに科学者が科学者であることをやめている証拠だと彼は思っている。だからこそ、私たち科学側のヒーローに対して「カンデルはカントを読んでいないか、読んでいてもわかっていない」と喧嘩を売って、「科学的」であることを裏付けようと、勝手に哲学者まで引っ張り出すなと叱責する。この叱責はさらにつづく。
「神経構築主義は、繰り返し好んで、しかも不当にカントの説に寄りかかっていますが、カントのほうがよほど首尾一貫しています。それは、カントが、神経構築主義が絶えず巻き込まれる矛盾を見破っていたからです。主著『純粋理性批判』でカントがテーマの一つにしているのは、思考という事象の担い手を(非物質的な魂であろうが、脳であろうが)何らかのものとして同定するのは誤った推論であるのを実証することです。こういう誤った推論は自己認識という領域で私たちにつきまとっていて、カントはその誤りを暴こうとしたのです。カントはこういう推論に「誤謬推論」という呼び名をあてましたが、要は誤った推論のことです。誤謬推論が登場するのは、カントによれば、特に、思考能力の担い手はこの世のどこかで見つかるものでなければならない、と信じられているときです。思考能力の担い手は、非物質的で探し出すのが困難な魂や気〔Seelenkraft〕でも構いませんし、脳全体──いくつかの脳部位でも構いません──の中での、はっきりとは場所が特定できないながらも認められている特質や活動でも構いません。」マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.1282-1292). Kindle 版.
このような批判を読んだあとで、ドーキンスやカンデルの著書を思い返してみると、彼の言うのも一理あると思う。要するに、宇宙の中の精神という大きな「世界(マルクス・ガブリエルにとって世界は存在しないのですが)」に立ち向かおうとする時、科学の間違いが始まると批判する。
さらに具体的に指摘が続く。
「神経中心主義が哲学を寄せつけないためにとる典型的な戦術は、まず「私」を「自然化」することです。つまり、「私」を自然科学的に説明したり理解したりできる対象の領域に編入するのです。そうして、「私」は言うなれば神秘的であるという特性を失います。現象の自然化とは、一見すると自然科学的に研究できそうもない現象を、その見かけに逆らって、自然科学で表現できるもの、探究可能なものとして扱うことです。したがって、ここで言う「自然な」とは、「自然科学で探究可能な」というような意味です。そして、このことはすでに多くの疑問を投げかけています。というのも、自然科学で探究可能であるとはどういうことなのかが、まったくはっきりしないからです。」マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.3144-3151). Kindle 版.
すなわち、世界の理解に最も重要な主観的「私」を隠してわかった気になるのが科学の戦略で、この戦略だけで本当に世界を理解できるのかと問う。
そして最後の一撃だ。
「ですから、精神をもつ生物〔知的生物〕としての私たちの状況に新たな視線を投げかけるのは、今世紀に課された重要な課題です。私たちは唯物論〔物質主義〕を克服しなければなりません。唯物論は(物質エネルギーにも基づき、匿名の固い原因で成り立つ現実という意味での)宇宙に見出せるものしか存在しないと私たちに吹き込み、それゆえ意識からニューロンの嵐にまで還元することができる精神というコンセプトを必死で求めているのです。私たちは、多くの世界にある住民です。私たちは目的の王国で行動しており、そこでは自由のための一連の条件が提供されています。」マルクス・ガブリエル. 「私」は脳ではない (Kindle の位置No.5041-5046).
手厳しい科学批判だ。特に、「(一つではない)多くの世界に住み、目的論の王国で行動し、自由な私が存在する」と強調することで、「目的ではなく法則に支配されている一つの世界」を認める科学思想をわざわざ裏返して、NOを突きつけている。
私も少しムキになって紹介してしまったかもしれないが、「私は脳でない」は、現代の科学批判の本だというのが私の感想だ。では、この批判に科学者としてどう答えていけば良いのか。これについてはこれから多くの哲学書を読む中で答えて行こうと思っているが、とりあえず手短に私の考えを述べてみよう。
まず、「私たちは唯物論(物質主義)を克服しなければなりません」という点では私も完全に同感だ。しかしマルクス・ガブリエルがこう語るとき、科学=唯物論と言っているように思えてならない。もしそうなら、それは間違っている。唯物論は科学とは全く無関係だ。私が考える唯物論は、目に見える(物質による)因果性で現象を説明しようとする事で、誤解を恐れずわかりやすく言ってしまえば、物理学がそれに当たる。化学反応は複雑だが、それでも同じように目に見える因果性の連鎖で扱える分野だと思う。もちろん私たち生物も、目に見える物質からできており、物理や化学の法則に従って生き、死んでいくという点では、唯物論的だ。しかし、生物を物理学的因果性だけで説明することは不可能だと私は確信している。
例えば生物には物理世界(生命誕生前の地球に存在していたが因果性)に、生命と同時に誕生した「情報(もちろんその媒体DNAは物質ですが情報は物質ではありません)」が組み込まれている。しかも情報は核酸だけではない。エピゲノム、神経ネットワークなど、様々な媒体を使った情報が組み込まれている。例えば自然界で今、自然にDNAが生成することはまずない(もちろん不可能ではなく、少なことも一度はできてしまったのだが)。一方、どんな小さな生物の中でも、核酸の合成は普通に起こっている。これは、物理法則と、情報が統合されているからできることだ。さらに脳という神経ネットワーク媒体を介する情報のおかげで、人間は地球上にはけっして生じることのない物質を生み出してきた。今私が向かっているパソコンが生物なしに物理法則だけでできるには何年待てばいいのか?
では、科学が唯物論的自然主義ではないとすると、科学とは何か?ガリレオ・ガリレイを読むときに詳しく論じたいと思うが、科学とは事象の理解について、第三者とコンセンサスを得るためのプロトコルを認め合う集団(科学者)が形成するギルド活動だと思っている。このコンセンサス形成のためのプロトコルとしてギルドに認められている方法は、現在のところ数理や実験だ。数理は多くの人と一度にコンセンサスを取ることができるプロトコルだが、もちろん数理的に処理できるからといって正しいわけではない。また、実験は自分の体験を、他の人と共有する手段だが、コンセンサスを得るためには時間とコストがかかることが多く(重力波測定を考えてください)、しかも常に個別の事象だけを対象にせざるをえない。本当の意味で普遍的なコンセンサスを得る事は物理学以外は科学にとって苦手な作業だ。
しかし問題はあっても、実験や数理という手続きを踏めば、少なくとも他の科学者に認めてもらえることはできる。逆に、ギルド内では理論科学の概念が証明されるまで棚上げにされるのも、科学というギルドの規則から考えるとうなづける。このおかげで、私たちの直感とは全く外れるアインシュタインの相対性理論ですら、まず数理的に、そして重力波実験によりコンセンサスとして共有できるようになった。しかしコンセンサスを得るための独自のプロトコルを持つというだけなら、宗教も同じかもしれない。誰かの言葉を信じると決めておけば、信者内で概念を共有できる。
幸い、科学はこの問題を、概念の技術化を通して解決し、宗教や政治などとは異なる質のコンセンサスを形成できている。すなわち、科学ギルドで生まれた概念の多くは、技術化を通して、宗教信条から科学を批判する人とすら共有できる。イスラム教、仏教、キリスト教を問わず、スマートフォンを通して、皆さんは電磁気学の成果を共有しているはずだ。逆に、ギルドメンバーであっても、プロトコルを無視する(捏造する)と、その概念が正しかったとしても、もはや科学者というギルドを去らなければならない。
ただ、このような厳しいギルドのルールをどこまで守れるか、難しい問題だった。そのため17世紀近代科学が誕生した時、科学は物質的因果性に基づく物理学しか対象にできなかった。その結果、科学の対象から物質的因果性では到底説明できなかった生物や精神などが外れ、多くは宗教の領域に預けられることにななる。
しかし、ダーウィンの進化論、そして何よりも20世紀のシャノンやチューリングによる情報科学の成立により、非物理的因果性を科学として(すなわちギルドの認めるプロトコルに従って概念を検証する)扱うことができるようになって来た。今回読んだマルクス・ガブリエルの2冊の本では、情報や情報科学についてはほとんど言及がないのが残念だ。しかし、ダーウィンの進化論というアルゴリズムに情報科学(繰り返しますが、非物理的因果性と言っていいでしょう)が加わって、科学の範囲は大きく広がろうとしている。何よりも、一つの結果を科学というギルドの中で一般化することが可能になって来た(これについてはいつかもっと詳しく論じる)。
以前、柄谷行人さんが、カントのアプリオリは「他人」とおなじだと言っているのに感心したと書いたが、科学に他人とのコンセンサスを得るための揺らぎないプロトコルがあることで、主観的な概念を、他人と共有、すなわちアプリオリへと転換することが科学にはできる。一方、哲学には第三者と概念を共有するための確固たるプロトコルは存在しない。もちろん、マルクス・ガブリエルのように様々な思想を自分の頭の中でもう一度統合するという離れ業は可能なだが、どれほど多くの考えを統合できたとしても、それがコンセンサスになるという保証はない。
「私は脳でない」という彼の考えに私も納得できるのは、「・・・でない」という否定形だからだ。しかし今後哲学で「私はXX」とテーゼが示された時、このテーゼを共有するためのプロトコルは有るのだろうか。これは哲学書を読むときいつも感じる問題だ。おそらく、科学というギルド以外、このプロトコルを確立できたギルドはないと思う。
しかし、私は彼の科学批判を全面的に受け入れたい。まず科学者は、このギルドの中だけで科学者でありうるという点は重要だ。この不自由な牢獄から抜け出して、ちょっと広い世界で話をしてみたいという気になるのはよくわかるが、その時はギルドメンバーではなくなっていることを認識する必要がある。ギルドから離れて脳科学の概念に基づいて説明しても、その説明が科学的だと錯覚してはならない。ここでは、誰もが哲学者と同じ立場に立っている。
とはいえ、「宇宙の中の精神」について科学者も考える事は自由だ。しかし繰り返すが、このように包括的な課題を普遍的に考えてみる作業が哲学の本領と言え、この時は科学者も哲学者と同じ土俵にいる。もちろん自分のよく知っている21世紀に入って急速に進む脳科学の成果を「科学ギルドからの強固な概念」として取り込む事は、哲学的に考える時も重要だ。その意味で、科学者も常に普遍的に考えてみる事は大事で、幸い脳科学にはそんな科学者が多く存在する。
ギルドから一歩出たら哲学者と同じ土俵で対等に渡り合い、できれば協力し合う必要がることを忘れてはならない。ただ、このような対等の協力関係の成立は難しかった。今回彼の本を読んで、マルクス・ガブリエルは、同じ土俵で渡り合い、協力できる哲学者だと確信した。今後彼の新鮮な批判精神が、「宇宙の中の精神」についてわかりやすく説明してくれることを期待して待とうと思っている。我が国の哲学者だけでなく、若い科学者も彼と討論してみると面白い。


