1年間カントの著作を読んできたが、そろそろカントについて書く気になってきた。といっても彼の哲学の解説をする気はないし、私がカントの解説をしても意味がない。「生命科学の目で見る哲学書」の目的は、それぞれの哲学者を生命科学者の視点で読み返し、現在の生命科学の中に位置づけることにある。特に哲学者の中の哲学者カントについては、この生命科学者の視点を貫徹して考えようと思っている。
人類が世界や自然について思いを巡らせ始めた頃、方法に科学 vs 哲学という区別はなかった。というより、科学は存在しなかった。もちろんギリシャ哲学やスコラ哲学でも、世界、自然、人間の理解について様々なアイデアが示されるが、結局Just a theoryあるいはjust an ideaでしかなかった。もちろん、Just an idea であっても権威があれば人間に大きな影響を持つ。たとえば、アリストテレスの生物に関する後生説のドグマは、18世紀になっても発生学の重要な問題として議論された。アリストテレスのドグマが現在にまで影響を保っているケースすらある。現在ユダヤ教やイスラム教は人間の始まりを受精後40日と定めているが、これも人間は最初子宮の中で生命とは言えない物質の塊(Vegetative state)を経た後、40日目に初めて人間になるというアリストテレスの考えを踏襲した可能性がある。一方キリスト教は、受精という概念が科学から提出されたとき、このドグマを捨て、人間の始まりは受精の瞬間からとする。この結果キリスト教ではヒト受精卵を用いてES細胞を樹立するのは禁止されるが、ユダヤ教では40日目までは胎児はモノでしかなく、受精卵を自由に使ってES細胞を樹立することが許される。このように一般社会では古いドグマの影響は維持され、科学の作用は限られている。しかも古いドグマが、ES細胞研究という科学を助けているのも皮肉だ。
しかし17世紀、ガリレオが確立した「科学」は、他の人と合意を得るための明確な手続きが示された革命的方法論だった。結果、この新しい方法は、どこまで行ってもJust an ideaから抜けられない哲学に大きなインパクトを与えた。もちろん哲学者が急に科学者に宗旨替えというわけには行かないが、哲学者も科学的課題により深い興味を示す様になる。例えばデカルトが解剖学に傾倒し、動物から人間まで、多くの解剖を自ら行って得た知識をもとに、自からの思想を形成したことは既に紹介した。他にも、ライプニッツは顕微鏡下にうごめく微生物に強く惹かれただけでなく、数学者としてニュートンに匹敵する業績を上げている。このように、ガリレオ以降の合理主義哲学では科学と哲学の積極的な交流が行われた。結果、逆に哲学が科学に対して大きな影響を持つケースも増えた。例えば深い解剖学の知識に裏付けられたデカルトの二元論は、人間の身体を機械と割り切ったことにより、身体の研究を加速させ近代医学の発展に寄与した。事実、「人間を機械としてしか見ない」という批判は、いまでも医学に対する常套句になっており、二元論の影響の深さを示している。
面白いことに17世紀に科学誕生後、哲学に科学の及ばない対象を求める傾向が現れる。例えば世界を考える時、自然の理解については物理学や天文学、すなわち科学に任せようとする意識が優勢になっていく。その結果、哲学の対象は人間の知識や理性へと向かい、これがイギリス経験論を産む。当時を考えると、おそらく科学者でさえ人間の知性や理性を科学の及ぶ対象とは考えていなかった。そこにロックが登場するが、彼について書いた時、「経験論は神経科学の始まりかも知れない」と紹介したように、経験論の課題は現在の脳科学者の課題とオーバーラップしている。ただ人間の知性は科学の及ばない課題として、自分の頭でじっくり考える中で理解すべき哲学の対象として位置づけられた。すなわち、デカルトでは自分とは何か、人間とは何かという問いでとどまっていた課題が、「人間の知性(Understanding)や理性(Reason)はどのように形成されているのか?」というより具体的な問題として扱われた。そして、皮肉なことに近代哲学者の中では、最も科学との接点の少ない(これは私の印象でしかないが)ヒュームによって、経験論は徹底され、私たちの知性や理性は全て経験の塊で、特別な自己すら存在しないとまで言ってのけた過激な、しかし魅力的な思想が誕生する。
我々の知性が経験で決まるというヒュームの哲学は、現代の生命科学の視点から見ても正しいと言える一方、それを支える脳については対象から除外してしまっている。このヒュームの経験論最大問題を解決すべく、人間の知性や理性、さらにこれを拡大して道徳や判断がどのように形成されるのかを、哲学の立場で考えたのがカントだ。言い換えると、ヒュームが一旦捨ててしまった自己、すなわち経験を受け取る自分の脳の役割を経験論に回復させることがカントの課題だった。そして、この困難な問題をカントはJust an ideaではなく、他の人も客観的に理解できる説明(科学的と言っていい)として提示できないか真剣に模索した。すなわち、知性や理性も生物の究極の形式として捉え、出来るだけ科学的に扱おうとした。この中で、アプリオリや、アンチノミーと言った概念が生まれるのだが、それは次回に回す。
以上がカントが取り組んだ課題についての私の個人的まとめだが、知性、理性、道徳までを生物の究極の形式として捉ようとしたカントについて教えてくれたのがシカゴ大学のジェニファー・メンシュによる研究書「Kant’s Organicism」だった、この本では18世紀の自然史と科学がカントの思想形成に大きく関わった可能性を調べている。そこでカントを直接扱う前に、この本について簡単に紹介し、批判シリーズ執筆前の、カントについて見ておくことにした。
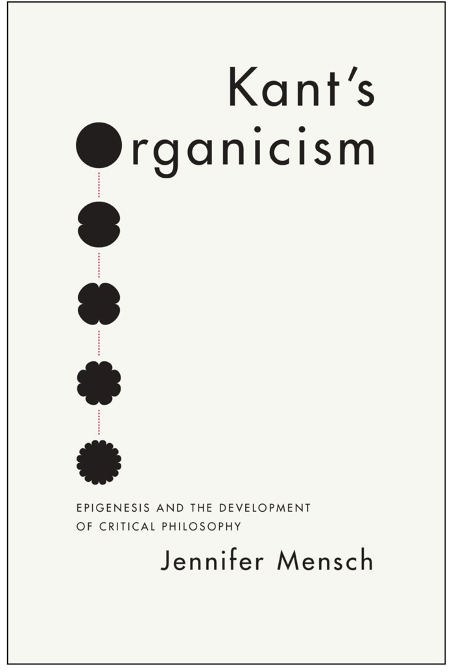
この本の実際の出版は10年以上前で、JT生命誌研究館で中村先生を手伝っていたとき、Kindleでなんとなく購入し読み始め、難しい本なのに面白く一気に読んだ。メンシュさんは、カントが主要な著作を発表する前に書いた論文、手紙や、さらにはカントの講義を聴いた学生のノートまで丹念に読み込んで、彼がプロレゴメナや純粋理性批判を書く前に、当時自然史として知られる大きなトレンドをフォローし、生命の論理をヒントに彼の思想を形成した過程を検証している。おそらく、この時期のカントを調べた研究が本として出版されることは多くないと思う。しかし私にとっては、それまでのカント観を変えるインパクトがあった。すなわち、この本のおかげで、カントの哲学の基本が、タイトルにある「Organicism;有機体論」、すなわち生命の論理をヒントにし、形而上学と人間知性との統合を模索していたことに気づかされた。実際カントは批判シリーズの最後、「判断力批判」で新たに生命の問題をとりあげ、自然目的のもとにOrganizeされた有機体論を展開するが、メンシュさんの本は、判断力批判で述べられた思想が、実際には純粋理性批判を書くまでの長い準備期間に用意されていたことを示している。
この本はカントについての一般向けの解説書ではなく、専門家のための研究論文と言える。実際、カントについてかなりの予備知識がないと何が何だかわからないことが多い。カントの著作を読んだことがある私も最初はほとんど理解できなかったので、ざっと読み通すかわりに、自分の理解を確かめるために、翻訳しながら読んでみた。それでも理解できたとは言いがたいが、その時のつたない翻訳は残っているので、希望される方にはPDFファイルをお送りするので連絡して欲しい。用語の統一性や哲学用語との調整などは全く無視しているので、翻訳内容については保証できないことを断っておく。
まずこの本の概要を紹介する。本の前半は、カントの哲学が準備される期間に自然史形成に関わった人々のことが紹介されおり、またカントが自然史思想とどのように接したかが描かれており、生命科学としてはその思想史を知るだけでも面白い。そして、新しい生命観、すなわち自然目的によりOrganizeされた有機体という、カントを知るための独自の視点は、その後のダーウィン進化論にもつながり、紹介する価値は高い。
この本は8章からなっており、まず各章ごとに簡単に要約する。各章のタイトルは実際のタイトルの訳。
- 序論
18世紀自然史の最も重要なテーマは生物の発生で、デカルト機械論の前成説(最初から身体が出来ている)から、後成説(後から形が出来る)を中心とした有機体論への移行が進んだ。とはいっても、自然史は純粋な科学と言うより、科学と哲学の混じり合った領域で、科学から哲学まで、多くの人を巻き込んで進展した。その意味でこの時代に形成されたカントの思想を後成説・有機体論、そして自然史という3つのキーワードで考えることは重要になる。実際、彼の最初の大学での講義シリーズは自然史についての講義で、人気を博している。そして、自然史から得た有機体の概念を、人間の知性や理性の理解へと拡大する。このように、自然史や当時の生命科学抜きにカントの思想形成を語ることは出来ない。
2,生命の発生と分類
自然史に関わった科学者や哲学者の多くは、発生の後成説を粒子説(我々は小さな粒子から出来ている)と組みあわせて考えた。この粒子説と後成説の考え方に当時の哲学者がどう関わったのか、ロックとライプニッツを中心に紹介している。この中で、それまでの分類中心の生物学が、「生命を持つ対象」を扱う方向へと進んだことについてもまとめている。
3,ビュフォンの自然史と有機体論の始まり
この章では、あの膨大な「自然史」を著したビュフォンと、彼と交流が深かったHales、Maupertuisを通して、彼らが自然史思想をどう形成させたか述べられている。ビュフォンは有名でも、彼の思想や業績が紹介されることは少ない。Menschさんは、当時の様々な文献を読み込んで、自然史がリンネの分類学批判に端を発し、進化、発生、代謝、遺伝と言った問題を扱う生命科学を目指していたことを、うまく紹介してくれている。また、当時の客観的科学はニュートン力学だったため、彼らが力学の力を生命理解に当てはめようとして様々なアイデアを提案していたことも紹介している。有名でも紹介する本の少ないビュフォンを知る意味でもこの章の意義は大きい。
4,カントと生命起源の問題
カントが有名な批判シリーズを発表するのは1781年からだが、これより前の30年間に自然科学の進歩を熱心にフォローしたことで、彼の哲学の基盤が準備されたと考えられる。この章では、物理学から生物学までカントがどのように理解していたのかについてまとめている。物理学や天文学分野では、カントはライプニッツから始め、ニュートン力学をマスターし、天体や物理について著作を残し、また講義も行っている。
そのカントも生命に関しては、物理学や数学とは全く異なる対象であることを認識しており、ビュフォンやMaupertuisのようなニュートン力学に基づく説明を否定し、まず理解することは不可能と考えていた。とはいえ、例えば「個体の発生についての機械論的説明が全て失敗に終わったとしても、超自然的解決を避ける方法」で理解しようとした。特にカントの理性が現象の原理からスタートして全体を認識する能力としていることを考えると、生命の起源の問題はカントにとって最も重要な問題だった。このなかで生命を目的により組織化される有機体としての彼の考えが形成される。
5,形而上学の再生
カントが正式にケーニヒスベルグ大学論理学・形而上学教授の職を得たのは1770年46歳の時だが、それまでの準備期間に様々な自然科学の最新の動向に習熟するとともに、ヒュームの経験論にも精通する。この過程でヒュームの経験論が科学に近い思想であることを認めた上で、形而上学の否定であると位置づける。そして、ヒューム経験論は新しい形而上学と統合されるべきだと考え、それを実現する新しい形而上学を模索し、それをやり遂げる自信も形成していった。この自信が彼の教授就任演説に結実することになるが、この章では「形而上学は、ある課題を自分が知りうることとの関連で決定できるかどうかを知ることと、私たち全ての判断が常に基盤としている経験的概念と問題がどのような関係を持つのかを知ることからなっている。この意味で、形而上学は人間の理性の限界の科学と言える」と、カント独自の形而上学の定義を引用し、彼の新しい形而上学について解説している。内容は難解な章だが、わかりやすく言うと世界の理解について、経験を基盤にする科学に、それを認識する脳科学を合体させるといった感じになる。重要なのは、彼の形而上学は「困ったときの神頼みと言える超越論的観念論を極力除外しようと試みている点だ。カントの目指した独自の形而上学とは何かが、彼の思想形成とともによくわかる様に書かれた章で、新しい方向からカントを理解することが出来た。
6,理性の統一から人種の統一へ
不思議なことに教授就任以降批判シリーズを発表する間の10年は沈黙の10年と言われるぐらい、ほとんどカントは外部への発信を行っていない。この章では、この沈黙の10年にカントが書き残したノートや様々な文章を読み込んで、この間、彼が何を準備していたのかを読み解こうとしている。自然史を含む科学領域から一定の距離を置いた上で、それでも人種といった遺伝と発達が組み合わさった問題と向き合うことで、動物とは明確に異なる人間精神の起源を自分なりに理解しようと試み、生命の起源もカバーできる包括的形而上学のあり方を考えた。この中で、後の判断力批判で扱われることになる、自然目的を因果性に合体さた自然史理解が生まれる。これにより、彼の批判哲学の準備は完成する。
8,Tetensとカントに見られる経験心理学
この章では教授就任後、純粋理性批判を発表するまでのカントの講義ノートなどを読み込んで彼が経験的科学を補う形而上学を構想する過程を検証している。この時カント自身の思想形成を助けたのが、タイトルにあるヨハネス・ニコラウス・テテンスだった。テテンスはドイツ語圏にヒュームを紹介したことで有名で、その思想は、経験主義的で我々自然科学者に近く、彼の「哲学探究」の一節からそれがよくわかる。
「魂の形成と発生、一連の観念の発生、そして思考の全内部体系の成長、即ち完全性の起源などなどは、もし肉体としての脳に基盤をおいているなら、有機的身体の形態形成や、発生、そして成長も同じように考えてはいけないのだろうか?」
このように、世界を外界と精神の統合として理解するという点ではカントと同じ方向を目指しながらも、完全に経験主義に立脚していたテテンスの考えは、反面教師としてなぜ経験の上に超越的理性が必要なのかについてのカントの思想形成に大いに参考になった。
最終章:カントの建築体系、純粋理性批判での体系と有機体
カントの理性は英語ではreasonだが、経験や知性を超えて、世界の原理を求める認識力のことを指している。だからこそ序論で、彼は経験できない神や霊魂の不死を純粋理性にとって避けることが出来ない課題だと、誤解を恐れず述べている。この章では、カントが経験や知性を超えた人間の理性を独自に位置づけることが出来たと確信したうえで純粋理性批判を発表し、また内容を常にアップデートし続けた彼の思想の展開を追いかけている。重要なのは、ともすると誤解される理性について、独断や神秘主義を排して説明できているかが問い直されていく点で、目的と結果が一体化した我々有機体の原理こそが、生命を可能にするとともに、人間理性を基礎であることをカントに確信させたと結論している。
以上とりあえず要約してみたが、研究書レベルの内容は、なかなかまとめるのが難しい。時間のある人は、拙訳Pdfをお送りするので読んで欲しい。
最後に、メンシュさんの本を読んで、私がカントを考える時参考にした点について箇条書きにして終わる。
- カントが純粋理性批判を出版するのは1781年、カント57歳の時で、彼が哲学者を目指してから30年という長い準備期間を経てカントの主要著作が発表されている。
- この準備期間は、ビュフォンを代表とする自然史思想の発展とオーバーラップしている。
- 自然史思想では、生物の発生や進化を取り上げることで、生物学を分類学から切り離して、生命生成の科学が目指された。最初自然史家の多くは、物理法則を生成に利用できると考えたが、最終的に生命生成を説明する基本的概念の確立は出来なかった。ただ、生命発生を、目的により組織化された有機体形成と考える点で一致する。
- カントは、物理学や天文学とともに、当時大きな影響力を持っていた自然史思想の展開をフォローし、自らも自然史についての講義を行った。
- この過程でカントは、後に判断力批判に示される考え方、すなわち生命は物理法則に従うだけでなく、目的により組織化され、目的と結果が一体化した物理法則では説明できない有機体という性質を持っており、人間の知性も理性もこの有機体原理に従っているという考え方に到達する。
生命科学も脳科学もまだ生まれていない時代、生命とは何か?生命進化の究極にある知性や理性とは何か?について理解するための模索が彼の著作の数々で、だからこそ生命科学や脳科学の視点から彼の試みを見直すことが重要であることがわかる。次回は、独断と偏見をおそれず、生命科学や脳科学へと発展する有機体論の萌芽として彼の思想をたどってみたい。
最後に:メンシュさんの翻訳については、一度某社から出版するという話があり、拙訳のままでは問題と思い、愛知教育大学の社会学者、哲学者の宮村悠介先生に添削をお願いし、丁寧な添削をいただいています。宮村さんの添削を参考に書き直そうとした矢先、出版しないという通告を受けました。その結果、宮村さんの添削を反映する作業を行わないまま現在に至っています。そのため、拙訳をお送りするときには、許可はいただいていないのですが宮村先生の添削もお送りします。わかりにくいところは是非宮村先生のコメントを参考にしてください。
またせっかく丁寧なコメントをいただきながら、出版できず宮村先生のご厚意を無にしてしまったこと、この場を借りてお詫びします。本当にありがとうございました。



生命は物理法則に従うだけでなく、目的により組織化され、目的と結果が一体化した物理法則では説明できない有機体という性質を持っており、人間の知性も理性もこの有機体原理に従っているという考え方に到達する。
Imp:
カントの有機体原理
●目的により組織化される⇒Stuart Kauffman氏の自己組織化思想を連想します。
(1076夜 『自己組織化と進化の論理』 スチュアート・カウフマン − 松岡正剛の千夜千冊 (isis.ne.jp)
●目的と結果が一体化した物理法則では説明できない有機体の法則⇒
物理法則は、因果律(原因から結果が従い、時間が順行する)に従う法則を指し、
目的と結果が一体化した有機体の法則とは、逆因果律(結果から原因が従い、時間が巻き戻される)も許容する法則を指しているのでしょうか?
量子力学(物質に関する理論ではなく、情報に関する理論だと思っています)では、逆因果律もありうるとか?
つまるところ、ヒューム氏の主張するように、この世に因果律なんて存在しない!ことになるのだとか??
(逆因果律 – Wikipedia)
(未来が過去に影響を与える我々の常識に反する現象を支持する研究者が増えている | TEXAL
単なる憶測ですが、情報が大きな働きをする対象(生命・脳・量子・コンピューター)を考える時には、西洋科学でタブー視されている、目的論・逆因果律・因果律崩壊etc、
言い換えると、自己組織化等の性質が露になるのではないでしょうか?
カントの有機体原理、時代に先駆けた、超現代的な生命観と考えることもできると思います。
『Kant’s Organicism』の訳、頂けるとありがたいです。
生命科学の重要性が増す現代、日本語訳の出版が必要だと思うのですが。。。
本記事、興味深く読ませていただきました。
現在19世紀生理学とニーチェ哲学との関係を博士論文で探索しており、カントの有機体論についてニーチェが当時の生理学を背景として読み解いた文章も取り扱っています。
翻訳pdf、ぜひ読ませていただきたいです。よろしくお願いいたします。