例によって気になった臨床研究をいくつか紹介するが、今日最も紹介したい論文は変異RASペプチドを抗原として膵臓ガンや大腸ガンの患者さんの抗ガン免疫を誘導する第一相治験のフォローアップ論文で、Nature Medicine にオンライン掲載された。
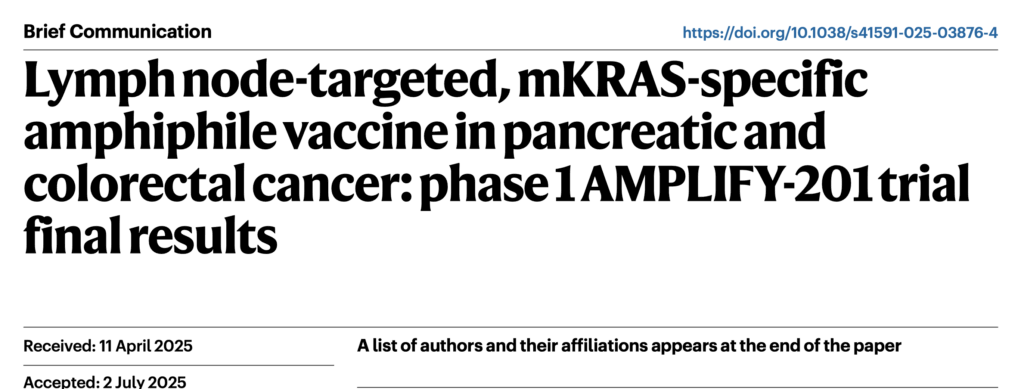
このワクチンについてはかなり期待できるとして昨年1月に紹介している(https://aasj.jp/news/watch/23781)。よく考えられたワクチンで、抗原としては変異RASペプチドを用いており、RASをドライバーとするガンはほとんどが標的になる。このペプチドを脂肪酸を介してアルブミンと結合させ、皮下注射するとすぐにリンパ節に行くように設計している。さらに同じアルブミンにアジュバントとして Tol9 を刺激する一本鎖DNAをつないで免疫を高めている。25例中21例でガンの増殖を抑えられたという結果だったが、今回の論文は同じ患者さんをさらに平均19.7ヶ月まで追跡した結果を報告している。
最初はワクチンだけの治療だったが、その後ガンマーカーが上昇する場合他の治療を組み合わせており、その中には PD-1 に対する抗体もあるが、このような治療上の違いは全くカウントせず、再発、生存期間でフォローしている。コントロールはないが、膵臓ガンで半数が2年以上生存していることから効果は大きい。特に、免疫後のT細胞反応が10倍近く上昇したグループを抜き出してみると2年で生存率が75%で、最初の論文の予想が確認された。他のガン抗原に対する免疫も誘導される spreading も認められており、今後チェックポイント治療や、あるいは粒子線治療などの組み合わせを工夫すれば大きな成果を上げられるように思う。特に、手術前にネオアジュバント治療として採用する治験も是非進めてほしい。すでにコントロールを置いた次にフェーズに入っているということで、かなり期待している。
次の上海交通大学からの論文は漢方薬で下痢止めや肥満防止に使われている黄柏由来のアルカロイドベルベリンが大腸ポリープ切除後の再発を抑えるという治験研究だ。
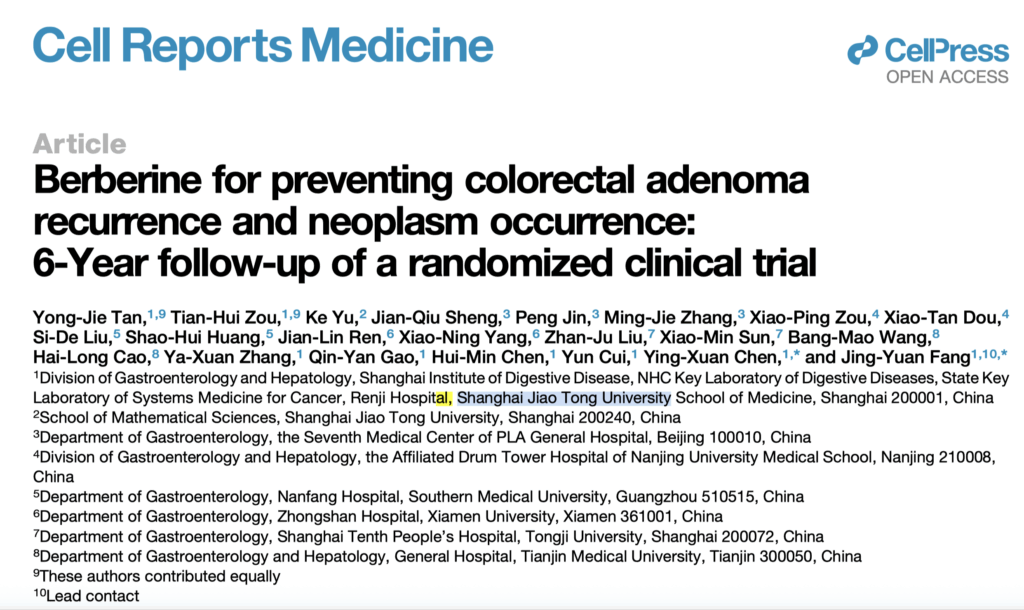
前臨床研究でベルベリンが大腸のポリープの再発を抑えることがわかったので、無作為化して450人づつの規模でベルベリン接種有り無しに分け、まず2年追跡して再発を抑えることを確認したあと、さらに6年までフォローアップを伸ばして調べたのがこの研究だ。6年追跡すると、ポリープの再発だけでなく、ガンの発生についてもある程度追跡できる。
結論としては、ポリープの再発は強く抑制でき hazard ratio で0.58と大きく低下する。ガンの発生についても、ポリープほどではないが一定の効果が見られると結論している。
ベルベリンはサプリとして利用されおり、アスピリンなどと同じく直腸ポリープ、即ちアデノーマを予防的に抑える薬として使えそうだ。最後に、上海交通大学の研究はこれまでも紹介しているが、いつも漢方への気配りが感じられる研究で面白い。
3番目の論文は新しい乳ガンの経口薬に関する治験で、乳ガンは新しい薬とそれに対する耐性のいたちごっこにはなっているが、着々と理論に基づいて新しい薬剤が開発され、再発後の長い戦いを支えていることがよくわかる論文で、8月7日号の The New England Journal of Medicine に掲載された。
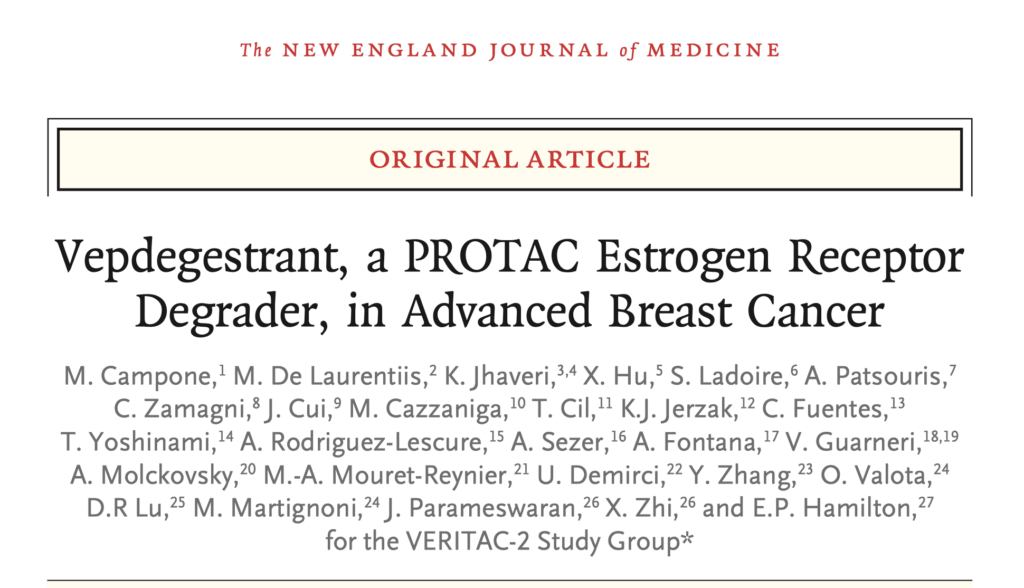
乳ガンの7割を占めるエストロゲン受容体 (ESR) 陽性、HER2 陰性の患者さんの再発例は、ESR 阻害、あるいはエストロゲンの枯渇を誘導するアロマターゼ阻害剤と、CDK4/6 阻害剤の組み合わせが用いられ、このブログで何回も紹介した。ただ、この治療を続けると半分ぐらいの患者さんで ESR の変異が起こり、エストロゲン治療が効かなくなる。
これに対し ESR にタンパク分解システムをリクルートして ESR を分解してしまうプロタック型、あるいは分子糊型の薬剤が開発され、現在はアストラゼネカの Fulvestrant が使われている。ただ、溶解性が悪く筋肉注射が必要で、経口薬が待たれていた。この目的でアストラゼネカは同じ分子糊型 Camizestrant を開発し、同じ号の The New England Journal of Medicine にアロマターゼ阻害剤の代わりに使えることを示している。
これに対し今日紹介する論文は、Arvinas/Pfizer が提供するプロタック型経口薬 Vepdegestrant の第三相治験で、同じように ESR を分解するアストラゼネカの Fulvestrant 筋肉注射と比較している点が面白い。
筋肉注射が必要という問題はあっても ESR 分解なので同じ程度に効果があるのかと思いきや、ESR 変異を持つ患者さんで見たとき、Fulvestrant より明らかに効果が高く、18ヶ月で全くガンが進行しないケースが3割近く存在する。すなわち、同じメカニズムでも、薬により効果は大きく違うことがわかった。
今後アストラゼネカの分子糊型経口剤 Camizestrant との比較が行われるのではと思うが、患者さんの治療可能性が広がる過程は、創薬企業の熾烈な競争過程であることがよくわかる治験だ。いずれにせよ、ESR の変異が発生したときの次の手の効果が高まることは喜ばしい。
ガラッと趣を変えて、次の論文は認知症の発生に対する教育程度の効果を調べた研究で、7月28日 Nature Medicine にオンライン掲載されている。
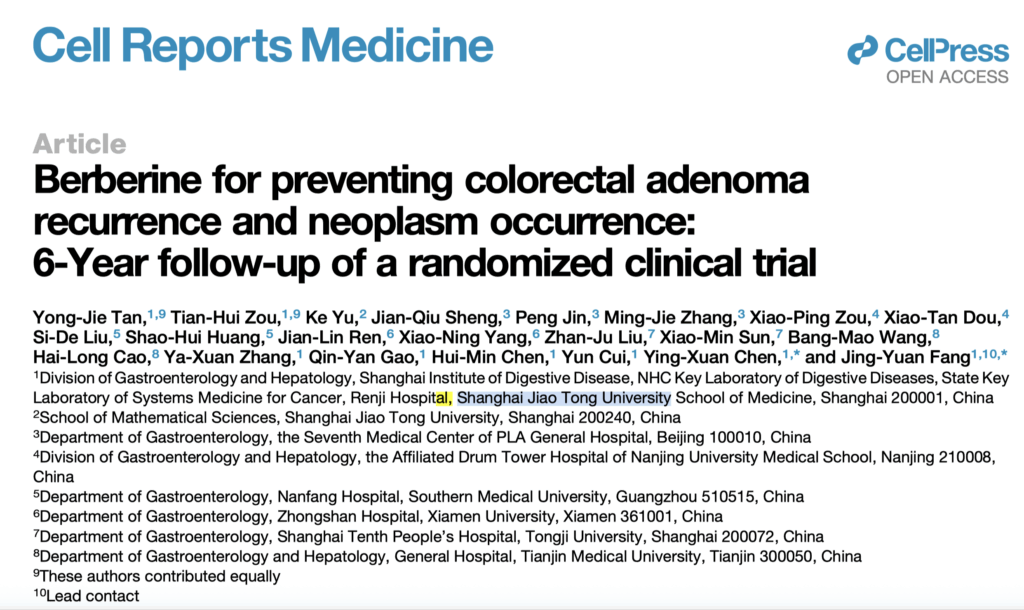
これまで、高い教育を受けているほど認知障害の発生が抑えられることを示す研究は多く存在する。この研究では、ヨーロッパとアメリカの17万人のデータ、その中の1万5千人の MRI データを分析し、これまでのドグマを再検討している。
結果だが、確かに記憶力を測ると教育程度が高いほど高いスコアが出るが、年齢とともに記憶力が低下する速度は全く同じで、結局は脳の老化や認知症の発生を教育では根本的に予防できないという結論になる。
この結果は MRI による脳の萎縮程度でも確認され、教育によって脳機能に下駄を履かせることはできるが、年齢による機能低下速度を変えることはできないようだ。いずれにせよ、若いときに脳を鍛えてスタートラインをずらせておけば、劣化が始まっても余力を残すことができるので、やはり教育は大事だ。



膵臓ガンで半数が2年以上生存していることから効果は大きい。特に、免疫後のT細胞反応が10倍近く上昇したグループを抜き出してみると2年で生存率が75%で、最初の論文の予想が確認された!
Imp:
P2試験の無病生存率データ-発表は2025年第4半期に予定されているようです。
注目のペプチドガンワクチンです。
CAR-T療法を固形腫瘍へ展開するのに肝になりそうな予感がします。
エピトープ・スプレッティング。
(2023年7月11日 | AASJホームページ)
老人誰しも、いつの時代でも、若いものにはまだまだ負けん、といいます。知能指数は一生を通じて変化しないとよく耳にしますが、加齢で衰える認知機能とはどういう種類のものでしょうか。
少々失礼なコメントをご容赦下さい。
もっとも著明なのはやはり記憶です。