数万人規模で自閉症スペクトラム(ASD)とその家族のエクソーム(翻訳されて機能的タンパク質をコードする遺伝子部分)を比べた研究により、家族には存在せずASDの人だけに発見され、おそらくASD発症を強く後押ししていると推察される遺伝子変異が102種類発見されたことを、前回紹介した(https://aasj.jp/news/autism-science/15576)。
1)家族には見られず、ASDの人にだけ発見されること、2)そのほとんどが脳組織で発現していることから、 ASD発症に関わる可能性はかなり高いと言えるが、残念ながら状況証拠を超えない。刑事ドラマに例えると、一つ一つの分子について、しっかりと「裏を取って証拠固めをしないと、起訴には持ち込めない」段階だ。では、どのように証拠固めをすればいいのか。今日から、2回に分けて、そんな証拠固めのしかたについて紹介していくことにする。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、まさに前回紹介した研究に啓発され、見つかった遺伝子の機能を特定しようとした研究で、現時点で可能な証拠固め実験の典型とも言える論文だ。
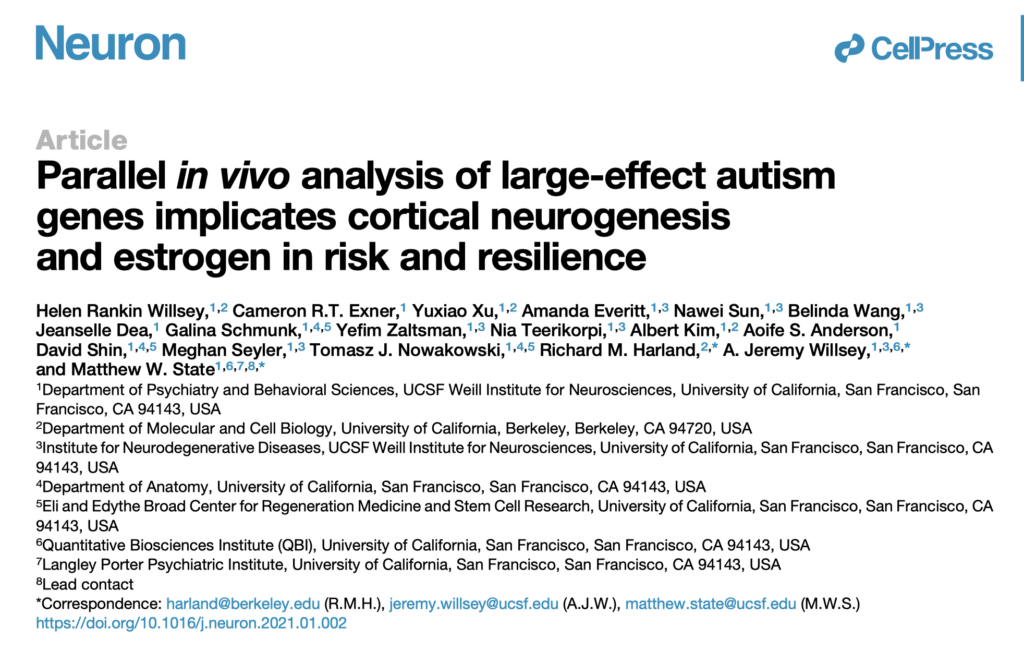
説明の前に、ある遺伝子がASD発症に関わることを示すためにはどうすればいいのか考えてみよう。
ゲノム研究から、同じ遺伝子の変異が、1)複数のASD患者さんで発見され、2)患者さん以外には発見されないとすると(すなわち前回紹介した論文)、この遺伝子がASD発症に関わると決めるための強い証拠と言っていい。ただこれだけでは、どのような過程を経てその変異がASD発症につながるのかを理解したことにはならない。このためには、それぞれの分子の機能を細胞レベル、組織レベルで調べる必要がある。
すなわち遺伝子変異からASD発症までには、遺伝子情報から変異タンパク質への翻訳、変異分子により生じる細胞変化、細胞レベルの変異による脳のネットワークの変化、そして最終的に行動変容と続く複雑な過程があり、この理解が必要になる。
幸い現在では、ASD患者さんで発見されたのと同じ遺伝子変異を導入した実験動物を作成することは可能で、モデル動物レベルではあるが、この過程を詳しく調べる方法は確立している。時間はかかっても、発見された102種類の遺伝子変異を、細胞レベル、脳組織レベル、そして行動レベルと調べていけば、時間はかかるが102通り(おそらく同じ経路に異なる分子が関わっているので、実際にはもっと少ない)のASD発症への道を理解し、うまくいけば治療法の開発まで進める可能性はある。
しかし、せっかちはどこにでもいるものだ。特に研究者には多い。一つずつ総当たりなどと悠長なことを言わず、102種類の中から優先順位をつけて研究スピードを上げられないか調べたのが今日紹介する研究者たちだ。
まず彼らの基準で選んだASDとの相関確率の高い遺伝子トップ10種類選んで(前回紹介した論文のリストには、このうち7種類がトップ10に入っている)、スピード重視でこれら遺伝子の機能を同時並行的に調べる可能性を探っている。
そこで登場したのがアフリカツメガエルだ。最近この動物を用いた発生研究は下火になっているが、一時は発生学=カエルの研究と言っていいほど重要なモデル動物だった。なぜカエルを持ち出してきたかと言うと、複雑だったアフリカツメガエルのゲノム解読が終わり、さらに昨年ノーベル賞に輝いたクリスパー技術を使うことで、この動物でも遺伝子操作が可能になったことが大きい。
実際には、受精卵が一回分割したところで、片方だけの遺伝子をノックアウトしている。カエルの場合、最初の分割でできた細胞は、左右の体に別れて発生するので、同じ個体で、遺伝子を変異させた側と、正常側を比べて、脳発生での遺伝子の機能を知ることができる。
クリスパー技術のおかげで、ガイドと呼ばれる標的遺伝子に対応するRNAを必要数用意しておけば、一度に10種類の遺伝子ノックアウトの効果を流れ作業で調べることができる。しかも、アフリカツメガエルの脳が発生するまでの時間は5日もあれば十分だ。
結果は驚くべきものだった。10種類の遺伝子全てで、機能欠損させた方の脳の大きさが変化する。遺伝子により大きくなる場合もあるし、逆に小さくなるケースもある。すなわち、遺伝子ごとに作用は異なるが、いずれも脳の初期発生に関わっていることがわかる。もう少し細胞レベルで詳しく調べると、全ての遺伝子で、未分化な増殖細胞の比率が、成熟した神経細胞と比べて上昇していることがわかった。すなわち、未熟細胞の増殖が続いて、神経細胞の成熟が遅れていることがわかる。
調べた10種類の遺伝子でほぼ同じ結果が得られたとは、大変わかりやすい結果だ。しかしカエルで脳発生の異常を誘導できたからと言って、同じことがそのままヒトでも言えるとは限らない。
ここで登場するのが、山中さんたちが開発したiPSだ。カエルと比べるとちょっと時間はかかるが、ヒトiPSで遺伝子機能を欠損させた後、神経細胞まで試験管内で分化させ、様々なことを調べることができる。
10種類の遺伝子全ては調べるのは大変なので、とりあえず5種類の遺伝子の機能を欠損させたiPSから神経細胞を誘導してみると、カエルと同じで増殖する未分化細胞が増え、成熟した細胞が減っていることがわかった。
以上のことから、人間でもASD患者さんだけに見られるde novoの変異があると、未分化細胞の増殖が高まり、成熟細胞が減っているのではと推察できる。
実を言うと、この結果はある程度予想されていた。例えば以前紹介したように、一部のASD患者さんでは脳体積の増加が見られることが知られている(https://aasj.jp/news/watch/6509)。さらに、遺伝子変異は特定できていないASD患者さんのiPSから神経細胞を誘導すると、たしかに未分化細胞の増殖が長く続いて、神経細胞成熟が遅れることも報告されている(https://aasj.jp/news/watch/3774)。
詳しくは述べないが、今回明らかにした10種類の遺伝子の脳での発現や機能を基盤にして、前回紹介した102種類の遺伝子の相互関係をコンピュータで調べると、なんと98種類の分子を一つのネットワークにまとめることができること、そしてその多くが未分化な神経細胞が存在するsub-ventricular zoneでネットワークを作っていることも明らかにしている。
以上、完全に理解していただけたか少し不安だが、ゲノム研究で発見されたASDに強く関わる遺伝子が、神経発生時期に、細胞の増殖と分化に関わっており、この遺伝子の変異で、少し未分化細胞が増えすぎて、成熟が抑えられると結論できる。もちろん、同じような解析を続ければ、ASDで変化が起こる他の過程もわかるだろう。
以上の結果で十分面白いと思うが、この論文の著者らはさらにせっかちで意欲的だ。解析した中からDYRK1A遺伝子を選び、この遺伝子が欠損したカエルの脳発生異常を治療できる薬剤をスクリーニングしている。その結果、なんと女性ホルモン(エストロジェン)が、神経細胞の増殖に必要なシグナル分子shhを抑えて、脳の異常を正常化することまで示し、胎児期のエストロジェンで発生異常の一部を直せるかもしれないと結論している。カエルでもうまく使うと、ASD治療のヒントが得られると言うわけだ。
ゲノム研究での発見をできるだけ早く治療開発にまで結びつけたいと言う気持ちが伝わる力作だが、読者の皆さんにとっても、研究の流れを理解する格好の例になったのではと期待する。
次回は、ASD患者さんだけで発生するde novoの変異を、人間でどう研究すしたらいいのかについての論文を紹介する。



西川先生、いつも論文紹介を大変面白く拝読させていただいており、とても良い勉強になっておりありがとうございます。もしよろしければ下記の点につきご教示いただければ幸いでございます。先生もご存じかと思いますが、近年ASDは有病率が大きく増えております(例:サイモン・バロン・コーエン著『自閉症スペクトラム入門』、中央法規(2011))。ASD有病率の増加の理由として診断基準の変化や世間の認知の上昇による受診率の増加が挙げられていますが、de novo変異等の生物学的な変化が増えている可能性というのはあるのでしょうか? どうぞよろしくお願い申し上げます。
増加していることは広く認められています。ただ、de novo変異頻度が何倍も増加するということは考えられません。これまでの研究で、ASDの増加と最も相関しているのが、結婚年齢の上昇、特に父親の高齢化だとされています。精子の場合、高齢になる程変異も増えます。さらに、今最も疑われているのは、エピジェネティックで、クロマチンの構造が年齢とともに変化するので、これが発症を高めていると考えられています。論文については、ゲノムの次に、エピジェネティックとして紹介することにします。
西川先生、回答をどうもありがとうございました。父親の加齢との相関はヒトでも動物実験でも報告があるのは知っていましたが、クロマチンの構造の年齢変化については初耳でした。エピジェネティックについてご紹介いただけるとのこと、楽しみにしております。