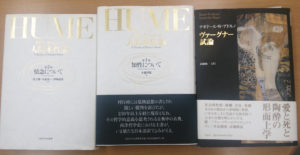2020年1月18日
AASJのホームページは、お陰様で毎日多くの方々が訪問されるサイトになってきました。そこで、訪問される皆様に迷惑がかからない様、私たちのサイトをSSL暗号化をすることに決めました。この作業のため、今月21日朝9時半から25日夜12時まで、こちらで新しい記事をアップロードできなくなります。またひょっとしたら、皆さんからの書き込みが制限されるかもしれません。ただホームページの閲覧自体は問題ありませんので、この期間もこれまで通り訪問していただければ幸いです。
ただ、新しい記事がアップロードできないと、せっかく1日も欠かさず続けてきた論文ウォッチが途切れてしまいます。そこで、今日18日から21日朝9時まで、実際の時間は無視して、25日までの記事をアップロードすることにしました。このため、例えば今日は1月18日と、1月119日の2日分の記事がアップロードします。「え!今日は18日なのに19日になっている」と思われるかもしれませんが、サイトの安全性のための苦肉の策だとご理解ください。
2020年1月1日
昨年はCDB退職以来お世話になったJT生命誌研究館の顧問を辞め、また相次いで二人の母を見送ることとなり、私にとっては節目の一年だったと思っています。幸い、この白髪頭でもアドバイザーとして頼りにしていただけるいくつかの会社のおかげで、AASJでのNPO活動を続けることができています。厚く御礼申し上げます。
このご支援に応えるべく、今年も患者さん、生命科学に興味のある方々、若い研究者、学生さんを対象に、ブログ、動画、講義などあらゆるチャンネルで情報発信を続けていきたいと思います。
特に昨年から「自閉症の科学」「気になる治験研究」そして「生命科学の目で読む哲学書」をライフワークとしてはじめています。そして動画では患者さんとの読書会を中心とした「AASJチャンネル」に加えて、重要な論文やトピックスを動画で解説する「西川伸一のジャーナルクラブ」も始めています。動画は皆様のリクエストにお応じますので、「この病気」、「このトピックス」などぜひご希望をお寄せください。
これまでの専門にこだわらず多くの論文を読む生活を七年近く続けてきましたが、現役時代には感じることができなかった、生命科学の大きな変革のうねりを感じ、毎日興奮の連続です。そしてこの変革が、今我々が直面している重苦しい社会状況の変革にも必ず繋がると確信しています。楽観的と言われるかもしれませんが、なぜ科学が社会を変えることができるのか、今年も講義を通して伝えることができればと思っています。
ではみなさん良いお年を。
(写真は新しいAASJのロゴ、フンボルトペンギンのアイコン、および東京芸大での講義風景です)

2019年5月27日
以下に2018年度AASJ決算報告書を公開します。以下をクリックしてください。
2019年1月1日
みなさまあけましておめでとうございます。
70歳を過ぎたのを機に浮き世のしがらみを捨てようと、今年から年賀状を送るのをやめました。それでも、多くの人とつながることができるのは、SNSのおかげです。今年もよろしくお付き合い願います。
根は飲んべーの隠居ですが、本年も「論文ウォッチ」を毎日欠かさず私たちのNPOからお届けしたいと思っています。その一部は、Yahooニュース個人にも紹介する予定です(
https://news.yahoo.co.jp/byline/nishikawashinichi/)。特に自閉症研究紹介には力を入れます。論文ウォッチは一種の「生命科学の今」の紹介ですが、自分自身がボケないためのノルマでもあります。
このほかに、顧問をしているJT生命誌研究館のホームページ「進化研究を覗く」では、情報科学の視点から生命科学を学び直し、それを一種のノートとして掲載してきました。「無生物から生物」、「言語の誕生」、そして昨年は「文字・Writing」と進んで、現役引退時に計画した目標はなんとか達成できそうです(
http://www.brh.co.jp/communication/shinka/2018/)。
そこで本年からはちょっと趣を変えて、生命科学思想の成立について調べるつもりです。「生命科学者の読む西洋哲学」といったイメージですが、アリストテレスから、カント、パースまで、これまで読み飛ばしてきた本の数々を、今度は生命科学の視点からじっくり読もうと思っています。こちらの方も是非よろしく。
では良いお年を。
2018年12月25日
開催日時:平成30年12月16日(日)14:00~17:00
場所:起業プラザひょうごセミナールーム(サンパル6階)
主催:日本ニーマン・ピック病の会
後援:兵庫県&神戸市難病連、難病の子供支援全国ネットワーク
・特別基調講演 「NPDの最新の治療研究と世界の動向」慈恵医大名誉教授 衛藤義勝先生
ライソゾーム病臨床治療の最高権威者で、1910年のNP病発見、1930年代の各型分類など創世記からの歴史と診断法(遺伝子診断・バイオマーカー共に未完)の現状、症状発現の原理(LDL、コレステロールの転送異常、蓄積により神経細胞を阻害、マクロファージの異常出現によるサイトカインの異常発生)、遺伝子治療開発の現状と可能性)などNPCを中心に病の現状を幅広く且つ判り易く話された。
・基調講演(1) 「NPC治療におけるCDの適正使用に向けて」熊本大学薬学部教授 入江徹美先生
消臭剤「ファブリース」や一部の医薬品の添加剤(可溶化剤)として使われているが未医薬品のHPβCDについて、NPCにどのように効くのか(ライソゾーム中でのコレステロールの運搬役と洗い流し役)、海外での開発動向(各地の研究では体重や体内濃度など基礎データすら不明のまま。Vtesse社はNIHでPhIIb/IIIおよび二重盲検終了。適切な投与設計はまだ不十分)、オーファン薬の早期承認取得には、深い現場認識の下に産官学民の協働が必須など、分り易く話された。しかし、新臨床研究法が施行されると、大学での臨床研究が進行中を含め、実質的にSTOPすると危機感を表され、厚労省への強い働きかけが是非とも必要と訴えられた。
・基調講演(2) 「NPC病の特性について」大阪大学医学部付属病院教授(小児科) 酒井則夫先生
NP病の病態(A~D型共にゴーシェ病とは異なる)、臨床症状、診断(皮膚生検のFilipin染色と遺伝子検査によるNPC遺伝子の確認で確定)、ケア(神経症状は進行し、肝・脾腫大が見られるが、心・腎機能と脳血管の障害は心配しなくてよい)等をを平易に説明され、本病は頻度少ないが患者は増えており、治療推進には、医療者、製薬会社、患者会の協力は必須で、どのような状況においても、患者さんとその家族の幸せを目指す、と結ばれた。
・全講演者をパネリストに迎えてのディスカッションが持たれ、率直で親密な意見交換がなされた。特に、新臨床研究法の施行により、医師主導の治験は難しくなることを念頭に、治療法がない稀少難病患者救済のため、特区設定による医師主導の治験機会確保を提案された。難病連の米田さんから、稀少難病患者や家族への難病連の行動の現状を話され(無力を感ずる)、医療者の対応の現状を質問された。 (田中邦大)
2018年5月25日
以下に、2017年度AASJ決算報告書を公開します。クリックして閲覧ください。
決算報告書
2018年3月12日
1月11日、このHPでレーザーポインターを組み込んだ靴が、パーキンソン病患者さんの立ちすくみを取り除くというNeurologyの論文を紹介した。ただ、この靴は我が国ではまだ手に入らない。ところが、この記事にヒントを得たパーキンソン病患者さんの一人、神戸の中井さんが、色々実験を繰り返して、簡単なレーザーポインターで同じ効果があることを、身をもって実験されました。その効果をビデオに撮り、Youtubeにアップしたので、ぜひご覧ください。サイトは
https://www.youtube.com/watch?v=WbG0vW1d1g0 ご覧になれます。
2016年9月23日
日本フンボルト協会は、フンボルト財団奨学生としてドイツで過ごしたことのある様々な分野の方々の集まりです。会の性格から、おのずと会員のつながりがドイツの科学や文化についてのシンクタンクになっています。これまで会員から集まった情報は、専門家向けには発信されていましたが、一般市民とのつながりは皆無でした。
我が国とドイツは、前大戦での国家主義的体制を奉じて戦い、また戦後めざましい経済発展を遂げるなど多くの共通点を持ってきました。しかし EU発足とドイツの再統一を契機に、経済政策、原発政策、憲法問題、同盟政策などで両国は際立った違いを見せはじめています。このため、今ドイツから学ぶことは多いのではないでしょうか。
この機会に、フンボルト協会に集まる様々な分野の先生に、「ドイツの今」を、ジャーナリズムとは違った新しい視点で語っていただき、ニコ動やYouTubeで発信するという企画を始めることにしました。
10月2日、14時からAASJチャンネルで放送する第一回は、
「ドイツ統一から始まる新しいテロリズム時代」と題して、同志社大学で美学を専門にされている岡林洋教授に、ドイツを代表する前衛芸術家、シュリンゲンジーフの暴力を題材にした映画を題材に、彼のの暴力表現の背景に隠れた東西統一の後遺症について語っていただきたいと思っています。(
http://live.nicovideo.jp/watch/lv276824722)
シュリンゲンジーフはドイツ再統一直後に発表した「ドイツチェーンソー大量虐殺」で注目を集めたドイツの前衛映画監督、演出家です。音楽ファンには、2004年ブーレーズと組んでバイロイト音楽祭で上演された「パルシファル」の「悪夢」と呼ばれる演出で有名で、バイロイト音楽祭で最もブーイングが多かった演奏として記憶されています。
メルケル政権は、欧州の中で最も寛容な移民政策を進めていますが、このリベラルな思想的背景にもドイツ再統一問題が見え隠れしています。これに対する反動として、従来の政治的枠組みを大きく変える新しい右派政党ドイツのための選択肢が、反EU、反移民を掲げて大躍進を遂げていることは同根です。シュリンゲンジーフも「外国人よ出て行け」と題するドキュメンタリー映画を製作した時、おそらくこの問題を感じていたのでしょう。岡林先生の話を通して、現代ドイツの政治状況を理解する新しい視点が得られるのではと期待しています。
2016年6月17日
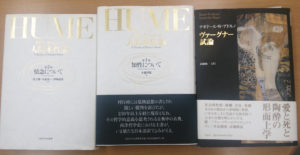
DSC_0011
ちょっとした相談にのったお礼としてTさんから図書券をいただきました。
早速、高額な図書の購入に充てました。どうもありがとうございます。
2015年11月9日

DSC_0009
理事の西川伸一、西川里美が昨日、岸田さんのがんノートに参加しました。参加者の皆さんと歓談でき、今後も交流を続けようというお話をいただきました。がんノートともさらに連携を深めますのでぜひ見守ってください。