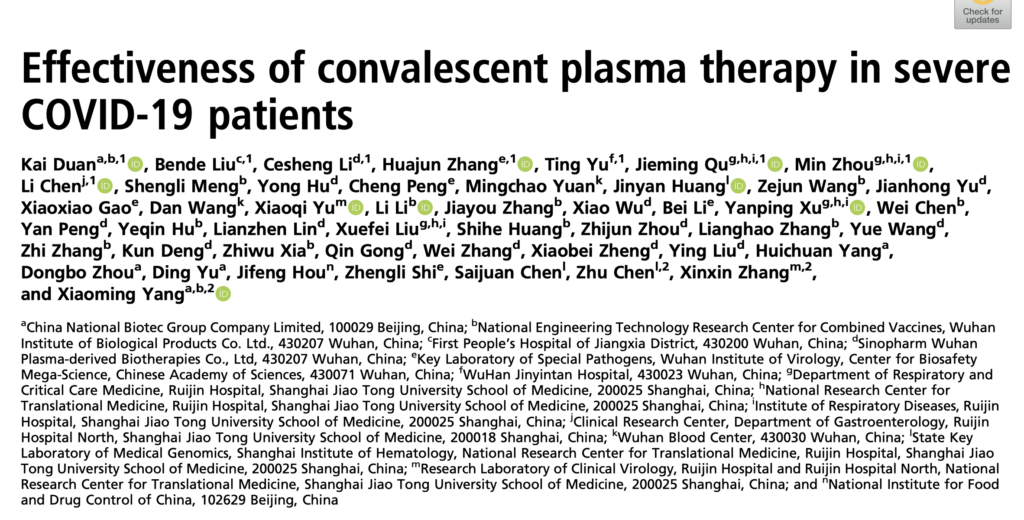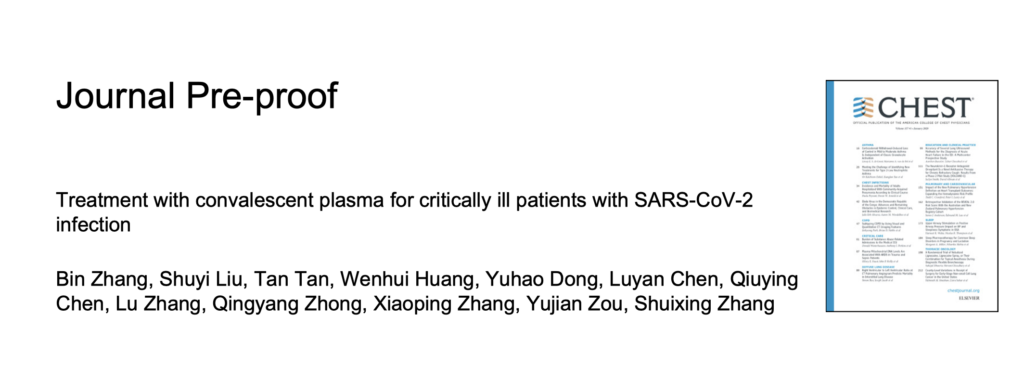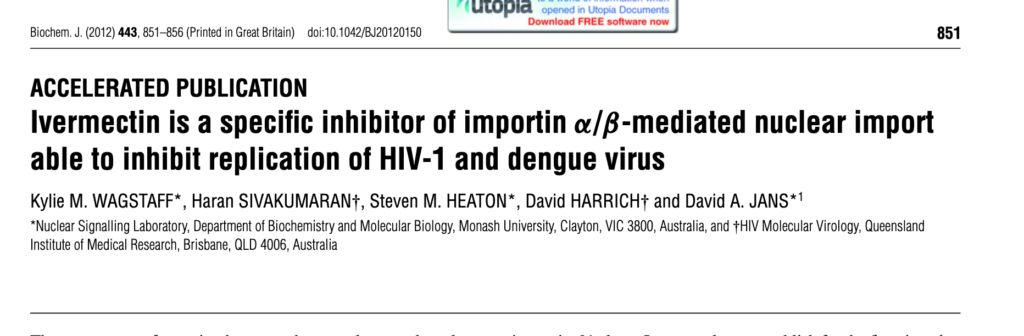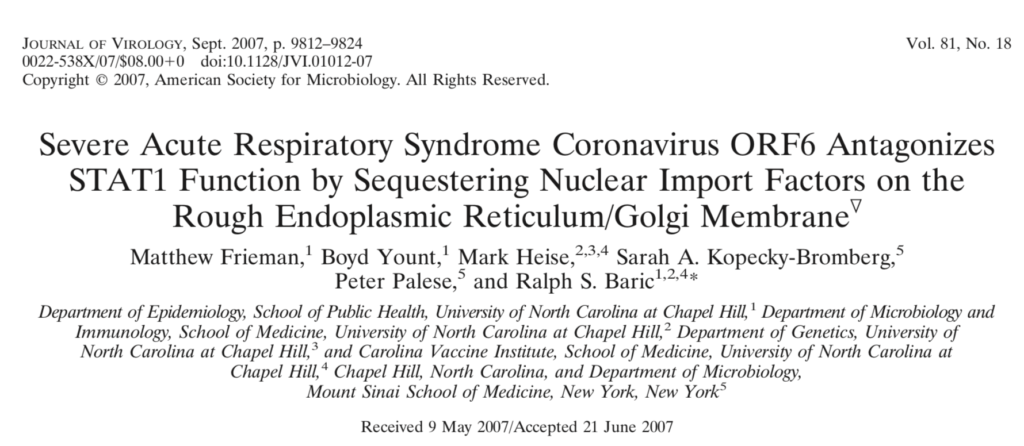2020年4月16日
阪神の藤浪投手についての報道以降、新型コロナウイルスの可能性を調べる一つの症状として嗅覚障害が認められ、メデイアでも盛んに報じられている。最近 International Forum of Allergy & Rhinologyにカリフォルニア大学サンディエゴ校から発表された論文では、インフルエンザ症状を示した中で新型コロナと確定された患者さんの68%が嗅覚障害を示した一方、通常のインフルエンザでは16%で、嗅覚障害は100%ではないが、新型コロナと強く相関することを示していた。
今我が国では一般の感染がどの程度広がっているのか、クラスター対策が限界を迎えてしまったため、わからないという状況になっている。各地域でこれを調べる一つのアイデアがやはり同じ雑誌に紹介されていた。Google Trendを使って嗅覚障害に関わる様々な言葉が何回検索されているのかを調べると、その地域でのコロナウイルス感染者数とgoogle 検索数が高い相関を示す という研究だ。PCR検査を徹底的に行なっているドイツでも相関が見られることから、信頼できる方法ではないだろうか。メディアも、国の調査不十分を非難する前に、自前で様々な検索を行えばいい。 前に紹介したように下水のPCR検査(https://aasj.jp/news/lifescience-easily/12703 )と合わせれば、原発事故モニター並みの推定ができるかもしれない。
個人的には匂いに関わる単語検索数はかなり使えると思う。というのも、十年以上前私も感冒にかかり、すっかり匂いを失った。幸い徐々に回復したが、面白いことに花の匂い、香水の匂い、ワインの匂いなど良い匂いは回復し、今や前以上にワインテースターになった一方、臭いと言われる匂いは排泄物も含めて全く戻ってこない。介護向きの人間になったのも巡り合わせかと親の介護を待ち構えていたが、この能力を使う間も無く全員亡くなってしまった。
少し余談になったが、匂いを失うと回復するかどうかが不安になる。その結果間違いなく、検索は増える。一般の人にとっては藤浪選手の報道が一つのピークになると思うが、現在の検索数を調べてみるのは絶対おすすめだ。
と前置きが長くなったが、今日紹介したいコロンビア大学からの論文は個々の嗅細胞が様々な臭い物質に反応を示し、細胞の興奮を入り口で調節している可能性を示した論文で4月10日号のScienceに掲載された。タイトルは「Widespread receptor-driven modulation in peripheral olfactory coding (抹消の嗅覚コードの受容体依存性の調節は普通に起こっている)」だ。
この研究では匂いに反応する1万個近くの嗅覚細胞の興奮を、様々な匂い物質にさらして同時観察している。仕掛けは大掛かりだが、目的は単純で、1つの細胞が様々な匂い物質に反応する可能性を確かめようとしている。
これまでのコンセンサスは、それぞれの嗅細胞は原則1つの分子に反応して興奮し、ワインのような複雑な匂いは全て高次の統合で行われるとされていた。ところが、1万個単位の細胞を同時にモニターすると、1個1個の物質に対しては確かに反応細胞は分離しているように見えても、同時に2種類、あるいは3種類の分子に晒すと、1つの分子にしか反応しないと思われていた細胞の興奮がポジティブ、ネガティブな様々な影響を受けることがわかった。
詳細は全て省いて結論だけ紹介するが、匂い受容体は実際には様々な分子と反応することが可能で、興奮の閾値を超えるという点で調べると匂い物質との一対一で対応しているように見えるが、単独では刺激の閾値を越せない分子も受容体の反応をポジティブ、ネガティブに変化させられるということだ。要するに、一つの受容体で、何種類もの刺激に違う反応を示すということで、これは入り口から大変複雑だということを示している。なぜワインの匂いが区別できるのか、到底わかりそうもない。
コロナに戻るが、匂いが戻るまで、嗅覚障害に陥った人はgoogleやYahoo検索を続けるだろう。嗅覚細胞は新陳代謝する細胞なので、必ず回復すると言えるが、自分の経験では完全に元どおりにならなかった。おそらく、この回復過程で素晴らしい匂いを脳に焼き付けることで、ぜひ素晴らしい自分の匂い世界を形成してほしい。この論文が示すように、匂いの受容は入り口から複雑だ。
2020年4月15日
昨日紹介した論文からもわかるように(https://aasj.jp/news/watch/12797 )、ガン特異的抗原さえ発現しておれば、私たちに備わった免疫機構は極めてパワフルで、それだけでガンを抑えてくれる。このことがわかると、ネオアジュバント治療のように、まずチェックポイント治療を行なったあと外科治療を併用するという戦略が出てくるのは当然だ。
もう一つ期待されているのが、ガンを放射線や抗がん剤でまず傷害して自然免疫を高めておいたあと、副作用のある治療はやめて、チェックポイント治療に切り替える戦略で、昨年トリプルネガティブ乳がんについて調べた論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/10264 )。ただ、この論文を読んで驚いたのが、シスプラチンのようなプラチナ抗がん剤はチェックポイント治療の前処置として強い効果があるのに、放射線照射は全く効果がない点だ。個人的には、切断されたDNAにより炎症が強く誘導できると考えていた。
今日紹介するテキサス・サウスウェスタン医療センターからの論文は私が抱いていたこの謎の答えを与えてくれた論文で3月30日号のNature Immunologyに掲載された。タイトルは「Tumor cells suppress radiation-induced immunity by hijacking caspase9 signaling (腫瘍細胞はcaspase9シグナルを取り込んで放射線による免疫反応を抑える)」だ。
放射線照射で免疫反が起こりにくい理由の一つは、なぜか腫瘍細胞の1型インターフェロンの分泌が抑えらるからだと知られていたようだ。このグループは放射線照射後の腫瘍細胞にインターフェロンを誘導できる薬剤をスクリーニングして、カスパーゼ阻害剤のemricasanがインターフェロンα、βともに分泌されるようになることを発見する。 すなわち、ガンが細胞死を調節するカスパーゼシステムをうまく利用してインターフェロンの分泌を抑えていることになる。
そこで、CRISPRを使って様々なカスパーゼ遺伝子ノックアウトを行い、casp9をノックアウトするとインターフェロン産生が戻ること、そしてその結果、放射線照射を受けたガン細胞に対する免疫反応が誘導され、ガンを消滅させられることを明らかにしている。
以上がこの研究のハイライトで、あとは
放射線によりミトコンドリアDNAが上昇し、これを感知して自然免疫系が活性化されるが、この経路をcasp9は抑制している。 インターフェロンは、ガンのPD-L1発現誘導に必要で、これが阻害される放射線治療ではチェックポイント治療が効かなくなる。 Casp9を抑制して放射線照射したガンは、チェックポイント治療に高い感受性を示す。 Emricasanを放射線照射とチェックポイント治療に併用すると、ガン抑制効果が上がる。 などが示されている。
状況に応じて細胞の死に方を調節するカスパーゼシステムを逆手に取った、ガンの巧妙な戦略といっていいが、放射線がなぜチェックポイント治療と相性が悪かったのかよくわかった。もしこのシナリオが正しければ、放射線照射したガン局所に、インターフェロンを投与できれば、チェックポイント治療の有効性を高められると思うのだが、それが示されなかったのは残念だ。ぜひ検討してほしい。
2020年4月14日
現在乳ガンなど多くのガンでネオアジュバント治療が行われている。これは、手術前に放射線や抗がん剤を投与して、ガンをあらかじめ叩いておいた後、手術で切除する方法だ。この方法の有効性は様々なガンで確かめられており、放射線や化学療法というと、手術不能の場合の治療としていた従来の考えが大きく変わっていることを意味する。
もしステージが進んだ後でも効果のある治療法を前に持ってくることが高い効果を示すなら、オプジーボのような免疫チェックポイント治療も同じように手術前に持ってきてもいいはずで、まだ試験段階とはいえいくつかのガンでは効果が確かめられている。この方法のもう一つの利点は、必ず組織を切除するため、ガンに対する免疫反応の状態を組織上で確認できることだ。
今日紹介するオランダ ガン研究所からの論文はステージ3までの大腸ガンでCTLA4とPD1に対する抗体を組み合わせたチェックポイント治療の高い有効性を示す研究で4月6日Nature Medicineオンライン版に掲載された。タイトルは「Neoadjuvant immunotherapy leads to pathological responses in MMR-proficient and MMR-deficient early-stage colon cancers(ネオアジュバンタ免疫治療はMMRの発現を問わず初期段階の大腸ガンに対する免疫を誘導する)」だ。
タイトルで MMRと書かれているのはミスマッチ修復機構のことで、複製時のエラーを修復する機構が正常なガン(pMMR)と、低下しているガン(dMMR)を区別して治療効果を比べている。これまでの研究で、MMRが低下すると、ガンの突然変異の数が増え、結果ガン抗原の数が増えて免疫反応が起こりやすいことが示されてきた。
実際にはプロトコルにCox阻害剤まで入っているので、わかりにくいプロトコルだが原則はCTLA4に対する抗体とオプジーボを1回、2週間後にオプジーボだけ1回投与し、あとは手術だけで治療している。従って、未治療の患者さんで抗体治療がどの程度効果があるか、その時の組織反応はどうかが明らかになる。
結果は驚くべきもので、MMRが低下して突然変異が多い(実際に調べている)ガンではほとんどで腫瘍が8割以上縮小し、切除後の組織でガンの縮小をはっきりと確認できる。一方免疫療法が効きにくいとされている修復正常のガンでが完全寛解は2人しかないが、多くで一定の縮小は認められ、さらに進行はしていない。
それぞれのグループの切除組織の免疫状態を調べると、CD8T細胞の数の上昇はdMMR群で強く、効果と相関していることがわかる。他にも、これまでガン抑制活性と相関するとされている分子マーカーも詳しく調べているが、大腸ガンの場合CD8陽性 PD-L1陽性の細胞が最も臨床効果と関連することを示している。
しかし全般に低いとはいえ、pMMRグループでもCD8T細胞は上昇しており、一定程度の免疫反応が起こっていることは想像される。これをさらに確認するため、試験管内で形成させたガンのガン細胞組織に対する自己T細胞免疫反応まで調べ、臨床的には反応が見られなかったケースですら、一定のガンに対する免疫反応が起こっていることを明らかにしている。
以上が結果で、まずMMRが低下している場合、ネオアジュバント治療は今後の標準になる可能性を示唆する。末期に使用するのと異なり、2回注射だけで高い効果があり、経済的にお安上がりだろう。また、問題となる副作用もこの投与法ではまずでない。
問題はMMR正常群だが、それでもガンに対する免疫は成立しているようなので、今後プロトコルを変えて(例えばTGFβもブロックする)ネオアジュバント治療を行うことも考えられると思う。 今後長期予後が示されるまで結論は保留だが、それでも将来標準になる新しいプロトコルが生まれた実感がある。
2020年4月13日
発生過程は最もDNA複製が活発な時期だが、活発であるということはDNA複製時のストレスによるDNA損傷が頻発する時期でもある。この時DNA損傷は修復されるが、それと同時に修復しきれない細胞は細胞死により除去される。問題はこの時どのように細胞が死ぬかで、これまでなんども紹介したように細胞の死に方は、組織や個体の混乱を引き起こさないよう行われる必要があるが、だからと言ってアポトーシスのように、常にひっそりと死ぬのがいいわけではない。当然死骸の処理も必要で、周りの細胞に警告を出す必要のある場合もある。
今日紹介するバージニア大学からの論文は神経発生時のDNA障害を起こした細胞はどのように死んでいくのか調べた研究で4月8日号のNatureに掲載された。タイトルは「AIM2 inflammasome surveillance of DNA damage shapes neurodevelopment (AIM インフラマソームによるDNA障害のサーベイランスは神経発生に必要)」だ。
この研究では最初からアポトーシスではなく、ピロトーシスを誘導するカスパーゼ1を活性化する時に形成されるインフラマソームと呼ばれる刺激分子複合体が、複製ストレスで生じたDNA障害で誘導されるかに焦点を当てて調べている。期待通り、DNA傷害が最も多く蓄積する生後5日目にASC分子を含むインフラマソームが形成された細胞が散見されることを確認する。
次にこのインフラマソーム形成に関わる遺伝子をノックアウトすると、インフラマソームは形成されない。そして驚くことに、生まれたマウスは強い不安神経症を示すようになる。しかし、記憶や認識などの他の神経機能は正常のまま残る。すなわち、インフラマソームの形成は、マウスの正常神経回路発達に必須であることが示された。
次に脳内のインフラマソーム形成過程に関わる分子を調べ、AIM2がDNA切断部位を認識しインフラマソームを形成することでカスパーゼ1を活性化することを明らかにしている。とするとピロトーシスが起こるわけで、サイトカインが分泌され周りに迷惑がかかりそうだが、確かにIL1やIL8が分泌されるが、これらの遺伝子をノックアウトしても、マウスの行動異常は発生しないことから、神経発生の現場ではなんの作用もないと結論している。
そして、カスパーゼはガスダーミンDに働き、細胞死を誘導することで、傷害の強い細胞を除去することで、最終的に神経回路形成を円滑に進めていることを示している。
結果は以上で、発生時にピロトーシスも動員されているが、サイトカインは発生時ほとんど役割を持たず、ピロトーシスも、アポトーシスと同じようにひっそりと細胞は死ぬという結論になる。ただ、気になったのは、どうして神経細胞全体でピロトーシスをブロックして、不安神経症だけが現れるかという点だ?うまく研究すると、不安神経症を示す発達障害を理解できるのではと期待している。
2020年4月12日
本庶先生がTVで、「コロナ研究のために100億円研究予算を緊急に使えるようにすれば、(マスクより:これは私の意見)、政府ができる最も有効なコロナ対策になる」と言ったという話を、SNSで見た。
私も全く同感だ。審査などに時間がかけられないので。どの研究に、どのようにお金を流すか、お金を提供する側の発想力が問われるが、そのためには役所(今こそ縦割りを排すべき)のチームが、常に自らの新しい知識をアップデートし、即座に判断する力をつけておく必要がある。
要するにあらゆる分野の専門家にこの病気と立ち向かってもらう必要がある。例えば、以前紹介した新型ウイルス感染経路の研究から、ウイルスは最初ACE2に結合した後、TMPRSS2(あるいはカテプシンも)により切断されることで細胞に融合することが確認されている(https://aasj.jp/news/lifescience-easily/12537 )。さらに最近、Cov-2のスパイクにCov-1にはないFurin切断サイトがあり、これがACE2により強く結合して感染が広がる原因ではないかという研究も中国のプレプリント雑誌に出ている(http://www.chinaxiv.org/abs/202002.00062 )。
とすると、ウイルスが感染する標的細胞はこれら3種類の条件が揃った細胞であると想像される。早速、英国サンガーセンターのグループを中心に、すでにデータが集められている肺の細胞に関するsingle cell transcriptomeデータを、新型コロナの視点から見直し、全ての気道の細胞が感染する訳ではなく、ゴブレット細胞と呼ばれる分泌型の細胞がACE2とTMPRSS2の発現が高いことを、やはりプレプリント雑誌に掲載している(https://arxiv.org/abs/2003.06122 )。この研究で驚くのは、このような感染しやすい細胞は自然免疫に関わる遺伝子の発現も高く、これが空咳、サイトカインストームなどと関わっている可能性を示唆している。いずれにせよ、Cell Atlasなどこれまで蓄積してきた全てのデータベースの重要性と、single cell trascriptome解析の力を示してくれた。
もちろん、このデータを新しく確認することも重要だ。今日紹介するベルリン・シャルティエ病院からの論文は、毎日出る肺ガン患者さんの切除組織のガンが存在しない場所からsingle cell suspensionを調整し、single cell transcriptome解析を行い、ACE2,TMPRSS2,そしてFurinの発現を調べた研究でThe EMBO Jにオンライン出版された。タイトルは「SARS-CoV-2 receptor ACE2 and TMPRSS2 are primarily expressed in bronchial transient secretory cells (SARS-CoV-2の受容体ACE2とTMPRSS2は気管の分泌移行細胞に発現している)」だ。
実際には解析細胞数もそう多くなく、データもきれいでないなという印象を受けるが、問題は理解した上で大至急データを出すことを重視していることがよく理解できる。結果は、1)低いレベルでほとんどの細胞がACE2は発現している、2)2型肺胞細胞と分泌型移行細胞でACE2とTMPRSS2が強く発現している、3)Furinを同時に発現している細胞も一定の割合で存在する、4)Furinは線維芽細胞で発現が最も高い、などが結果だ。
Sanger Centerの研究と大きな違いはないように思う。今後鼻粘膜も含め、ウイルスが増殖中の細胞解析も出てくると思うが、その研究のための重要な基礎データとなっている。
以上のように、「今自分にできることはあるのか?」、を考えることが感染症専門家に限らず全ての科学者に問われているように思う。
隠居の私には知識を集めることしかできないが、いつでも協力したいと思っている。
2020年4月11日
ヒストン修飾はクロマチン構造変化を調節する重要なメカニズムで、エピジェネティックな変化を理解するときのキーになっている。この修飾の中心はメチル化とアセチル化で、他にもリン酸化やユビキチン化も重要だ。
今日紹介するマウントサイナイ大学からの論文はなんとドーパミン神経ではヒストン3をドーパミン化することでクロマチンの調節が、なぜかコカイン特異的に行われていることを示し、コカインとは何かを考えさせる不思議な研究だ。タイトルは「Dopaminylation of histone H3 in ventral tegmental area regulates cocaine seeking(腹側被蓋野のH3ドーパミン化はコカイン中毒を調節する)」だ。
このグループはすでにヒストンがセロトニンと結合することを、セロトニン神経で明らかにしていた。今回の研究はセロトニンがヒストンと結合するなら、同じモノアミンのドーパミンもヒストン修飾に用いられてる可能性を探索していたと思われる。まず生化学的にヒストン3(H3)の5番目のグルタミン、トランスグルタミナーゼによりドーパミンと共有結合すること、そして典型的なドーパミン依存性褒賞反応の一つコカイン中毒者の腹側被蓋野を集めて調べると、ドーパミン化のレベルが低下していることを発見した。
この発見が研究のハイライトで、あとは動物を用いてドーパミンH3の変化と、コカイン中毒について順番に検討している。
まず自分でコカインを摂取するようになった中毒ラットを作って、コカインからの離脱過程を調べると、最初は強く低下していたドーパミン化H3が、離脱後30日目には回復してくる一方、他のヒストン修飾はほとんど変化がないことを発見する。
次にドーパミン化が起こらないH3の変異体をドーパミン神経に導入して、一旦下がったドーパミン化H3が回復できないようにすると、離脱期間中にコカインにより起こる遺伝子変化の正常化が抑えられること、その結果ドーパミン神経の興奮が低下し、コカイン中毒からの離脱ができないことを示し、ドーパミン化がエピジェネティック調節に関わっていると結論している。
以上が結果で、現象論的には極めて面白いと思う。実際、他の褒賞反応を調べても同じことは見られず、腹側被蓋野のドーパミン神経に限れば今のところコカインでだけ見られる反応だ。コカインがドーパミンのトランスポーターをブロックする作用で精神作用を誘導していると考えると、単純にドーパミン依存性の褒賞反応が起こるだけではこの変化は起こらないと考えたほうがいいいのかもしれない。
ある意味で、コカインがあらゆるプロセスをすっ飛ばして褒賞反応を誘導できることを納得した。
2020年4月10日
医療を行う際の科学的根拠には、メカニズムははっきりしないが経験的に効果があると思う段階、メカニズムが理解できているという段階、そして統計学的に医療効果が確認されている段階まで様々な段階があり、それぞれは必ずしも一致しない。
このことがわかって新型コロナウイルスに対する議論を聞いていると、最終的科学性にこだわった杓子定規な議論が強すぎるように感じる。例えば、アビガンの効果については、理屈としては正しいといえる。なら、ともかく使ってみようかと使って、効果が見られた時、今度は観察研究だから役に立たないと議論が始まる。これは私個人の意見だが、この事態を乗り切るためには、少なくとも理屈があり手に入るならなんでもやってみることも大事ではないかと思う。
今は政府も国民も、この病気に対してレスピレーターとECMOだけが信頼できる科学だと思っているように見える。今こそ現場の裁量で様々な可能性を試し、それを正確に記録した結果が、フィードバックできるシステムが大事ではないだろうか。
理屈があり手に入るという点から新型コロナウイルスに絶対おすすめなのは、回復した患者さんの血清を使ってウイルスを中和するという治療法だろう。この可能性については論文がちらほら出始めていたが、観察研究の集大成ともいえる論文が中国から米国アカデミー紀要に発表された。タイトルは「Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients (重症Covid-19患者に対する回復者由来血清療法の効果)」だ。
この研究も観察研究で、すでに急性呼吸逼迫症候群(ARDS)を発症した10人の新型コロナウイルス感染患者さん(このうち3人は人工呼吸器装着)に対して、ウイルスに対する中和活性の高い回復患者さんの血清を、発症後11−19日目に200ml、一回だけ投与して様子を見ている。
この研究では血清を調整するため、軽症患者さんで発症から3週目の血液(退院後4日目)を40人のドナーから集めている。新型コロナに対しては抗体がすぐに消えるということが言われているが、細胞にウイルスを感染させる古典的な方法で、ウイルス活性を中和する抗体価を調べると、39人で160倍以上の力価があり、それ以下だったのは1例だけだった。すなわち、時期を選べば多くの軽症者の回復血清を明日からでも集められる。
データの詳細は省くが、感染症に対する免疫の力を示す赫赫たる成果で、3日以内に血清からウイルスが消え、レントゲン所見の回復には時間がかかるが、呼吸不全の症状を含め、検査データも1週間以内に改善する。何よりも、3人は退院、残りも回復して退院を待つのみという結果だ。同じ病院でのそれまでの結果では、ARDSを発症した人の3割が亡くなっている。
この論文以外にも、3月27日号の米国医師会雑誌(JAMA)では、人工呼吸器装着の5例全例が回復したこと、また、Chestには人工呼吸器装着の4例全例が回復(3例は退院)したことが示されている。
確かに全て観察研究だが、もし私が現場で働いていたら、この治療を採用したいと思うだろう。3誌で紹介された全ての患者さんは、様々な抗ウイルス剤が用いられており、重傷者に抗ウイルス剤の効果が限定的であることを示している。観察研究といっても、北里柴三郎以来血清療法の科学性ははっきりしており、しかも北里の時代と異なり中和活性も測れる。
考えてみれば、血清療法を最初に開発したのは我が国の北里柴三郎と、ドイツのベーリングだ。その意味では我が国でも当然推進すべき治療法だと思うが、北里の国、我が国では実現に壁があるかもしれない。
最も重要な壁は、ウイルスの中和抗体の力価を測る感染実験施設の協力だ。検査は簡単で、安全な感染実験ができる場所があればいい。国立感染研や、国立大学など、研究者の貢献が必要になる。緊急措置が出た地域の大学では、全ての研究がストップしており、資源は回せるはずだ。
次に重要なのは、米国アカデミー紀要の論文に示されたように、決まった時期に血液を採取することが必要になる。そのために、軽症者の自宅やホテル隔離の場合でも、決まった時点(発症後3週間?)で採血して、力価を調べる体制が必要だ。
しかしこれらは壁といっても、すぐに解決できる。今日の東京都の統計を見ると、幸い中軽症者が1400人、重傷者は30人に過ぎない。人工呼吸器の数を心配することも大事だが、ぜひこの治療を迅速に導入する体制をとってほしいと思う。
現在多くの製薬会社では、中和モノクローナル抗体の開発が加速している。おそらくこれはワクチンより早い切り札になることは、エボラの経験でもわかっている。ただ、この開発が進められているということは、北里以来の血清療法が可能であることを示している。現場の医師と、政府と科学者の一体となった協力体制に期待したい。
繰り返すが、人工呼吸器だけが治療ではない。現場の裁量で行われる様々な内科的治療の中から、可能性の高いものを迅速にスタンダードとして採用できる体制も重要だと思う。
2020年4月9日
喘息は抗原により誘導されるアレルギー反応だが、病理的には極めて複雑な炎症反応で、蕁麻疹のような単純なものではない。この複雑化に関わるのが抗原反応性はない自然免疫に関わるinnate lymphoid cells(ILC)で、特に喘息の場合ILC2が慢性的に活性化されることが様々な病理反応の背景にあると考えられている。
今日紹介するドイツ・ボン大学からの論文は喘息モデルマウスでこのILC2細胞を増殖させる条件を探る中で、代謝を通してこの細胞を調節し喘息を治療する可能性を示した研究で4月14日号のImmunityに掲載された。タイトルは「Lipid-Droplet Formation Drives Pathogenic Group 2 Innate Lymphoid Cells in Airway Inflammation (気管の炎症時のLC2細胞の脂肪滴形成が病気を促進する)」だ。
この研究では、喘息の炎症が慢性化するプロセスを探るため、パパインを抗原にした喘息モデルで、抗原に暴露した後増殖して炎症を慢性化させるILC2を追跡し、ILC2が慢性的に刺激されると細胞内に脂肪滴が形成されることに気がつき、この脂肪代謝の変化とILC2の活性化との関係を調べ始め、ILC2の脂肪代謝について以下の結果を得ている。
試験管内に取り出したILC2の増殖はIL7とIL33の組み合わせで最も強く、この時ILC2細胞内での脂肪滴形成がIL33により誘導される。 この脂肪滴形成は、細胞外から遊離脂肪酸を急速に取り込み利用する過程で、細胞内に溜まった遊離脂肪酸の毒性を抑えて脂肪代謝を高める役割がある。 脂肪滴形成はDgat1分子より調節されており、この分子を欠損させる、あるいは阻害剤で脂肪滴形成は抑えられるが、それと同時に脂肪毒性により細胞の活性が低下する。 ILC2の脂肪滴形成は、脂肪細胞と同じでPPAR γ分子により調節されており、この分子の阻害剤で脂肪滴形成を抑え、ILC2の増殖やサイトカイン形成を抑えることができる。 細胞外の遊離脂肪酸はILC2の増殖や活性を高めるために必須だが、この時グルコースが同時に存在しないと脂肪代謝サイクルがうまく回らない。 グルコースはmTor経路を介してPPARγやDgat1脂肪代謝システムを誘導する。 以上のことから、ILC2がIL7+IL33刺激で活性化される時、エネルギー供給ソースとしてブドウ糖を必要とするが、この経路の促進により代謝のプログラムの変化がおこり、mTor経路を介して、PPARγやDgat1などの脂肪代謝経路が活性化し、外部から活発に遊離脂肪酸を取り込むことで増殖する、と結論している。
この結果から、様々な阻害剤が喘息にも効くなと私のような凡人は考えてしまうのだが、このグループはILC2がサイトカインで活性化された後の代謝経路を変える最初のトリガーになるブドウ糖を摂取を、ケトンダイエットで減らすことでILC2の増殖を抑えられないかと着想し、見事に脂肪滴形成を含むILC2の機能を抑えて、炎症を鎮められることを示している。
喘息にケトンダイエットが行われているのがよくわからないが、慢性化を防ぐ一つの方法と考える価値はあるなと感じた。
2020年4月8日
オーストラリア・モナーシュ大学から発表された我が国の大村さんが開発した抗寄生虫薬イベルメクチンが、試験管内の実験系ではあるが新型コロナウイルスの細胞内での増殖を止めるという論文がメディアを騒がせている。イベルメクチンは寄生虫のクロライドチャンネル阻害剤として働いて、寄生虫を麻痺させると思っていたので、この意外な組み合わせに驚いた。
なぜイベルメクチンで新型コロナウイルスが抑制できるのか知りたくて早速この論文を読んで、そのメカニズムの可能性を学ぶとともに、面白い引用文献も見つけたので今日はこれを紹介する。タイトルは「The FDA-approved Drug Ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. (FDA が認可した薬剤イベルメクチンはSARS-CoV-2の複製を阻害する)」で、Antiviral Researchにオンライン出版された。
もともとイベルメクチンは構造的には極めて複雑で、クロライドチャンネル阻害以外の作用を持っていても良さそうにおもえる。この論文を読むまでは全く知らなかったのだが、このグループはイベルメクチンが細胞質のタンパク質を核内へ運ぶ分子インポーチンと結合して、核内移行を抑制すること、そしてこの結果様々なウイルスタンパク質の核内移行が阻害され、エイズウイルスや、デングウイルスの増殖が低下することを示していた(以下の論文)。
また、この結果を受けてタイではすでにイベルメクチンをデングウイルス治療に使う360人規模の治験が進んでおり、抗ウイルス薬としてのイベルメクチンはすでに臨床段階にある(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02045069 )。
このような背景のもとに、この研究では新型コロナウイルスの細胞内での増殖をイベルメクチンが抑制できるか調べており、サルの腎臓由来Vero培養細胞に新型コロナウイルスを感染させ、48時間後にイベルメクチンを添加、その後のウイルスの増殖を調べている。
結果は報道の通りで、ウイルスの増殖が24時間で1000分の1に低下する。また、服用可能な濃度でこの効果が得られることを示している。
問題があるとしたら、人間の肺細胞での感染実験でないことだが、この点はすぐ実験的に分かることだろう。
この研究ではどのウイルスタンパクの作用が阻害されているのかについても明らかではない。仮説として、ウイルスの増殖に直接関わるタンパク質ではなく、ウイルスに対する自然免疫作用が核内でインターフェロンなどを誘導するのを抑えるタンパク質のインポーチンとの結合が阻害され、その結果抗ウイルス反応抑制が外れて、二次的にウイルス増殖抑制が復活すると考えている。
これだけでは分かりにくいと思うので、もう少し説明しよう。この仮説を調べていて驚いたのだが、SARSウイルスはエボラウイルスとほぼ同じメカニズムを用いて(https://aasj.jp/news/watch/2023 )インターフェロン誘導に必要なSTAT1の核内移行を抑制することが2007年に報告されている(実際にはSARSの論文の方が先)。
すなわち、インポーチン(KPNAが分子記号)はウイルス感染により活性化されたSTAT1を核内に移行させるのに必須だが、SARSウイルスのORF6はインポーチンと競合的に結合してこれを阻害するため、インターフェロンなどの自然免疫が働かずに、ウイルスが増える。イベルメクチンが存在すると、このORF6(おそらく新型コロナウイルスでも同じ?)のインポーチンへの結合が阻害され、この結果STAT1の機能が復活し、ウイルスに対する自然免疫が回復するというシナリオだ。
引用されている文献から見ても、著者らの提案の可能性は高いと感じた。ただ、本当にインターフェロンの産生がイベルメクチンで回復するのかはすぐわかるので是非調べてみたらいい。
最後に、STAT1の作用がSARSのORFで抑えられることは初めて知ったが、とするとエボラと同じメカニズムが存在するため、新型コロナウイルスはサイトカインストームが急速に進むタチの悪いウイルスであることも理解できる。新型コロナウイルスではまだこの点の検討は行われていないが、どちらかについてすぐわかるだろう。もしSARSと同じようにORF6がこの役割を担っているなら、イベルメクチンだけでなく、ORFとインポーチンの結合をより特異的に阻害する化合物も開発できるかもしれない。インポーチンを研究しているグループならかなり早く化合物までたどり着けるような気がする。ORF6がサイトカインストームの引き金に関わるなら、サイトカインストームが荒れ狂うタイプのウイルスについての理解と治療方法がわかるかもしれない。勉強になる論文だった。
注 読者から2μMの濃度に到達するためには現在の100倍程度必要ではないかという指摘がありました。この論文でも高濃度が必要であることはわかっているようで、議論しています。一方、現在進行中のタイのデングウイルスに対する治験では200-400μg/Kgを投与しているので、通常の濃度です。可能性としては、ネブライザーで肺に直接到達させることも可能かもしれません。
2020年4月7日
記憶が神経細胞分化と言ったのはエリック・カンデルだが、マウスを用いて長期に続く記憶痕跡(エングラム)が代謝非依存性の変化として刻み込まれた神経細胞をエングラム細胞と呼んだのは利根川さんだった(と思う)。こんな離れ業が可能になるのは、生きた動物の中で興奮する細胞を条件を替えてしかも継続的に記録できるようになったおかげだが、様々なタイプの神経の中でエングラム細胞というのがどれに当たるのか、詳しく調べた研究はなかったようだ。実際、私の頭の中ではエングラム細胞というと興奮神経を思い描いていた。
今日紹介するMITからの論文は記憶痕跡が、興奮神経だけでなく様々なタイプの細胞により形成されることを示す研究で4月16日号の Cell に掲載された。タイトルは「Functionally Distinct Neuronal Ensembles within the Memory Engram (記憶痕跡は機能的に異なる神経の協調により維持される)」だ。
エングラムが存在するかどうかは、記憶成立時に興奮した細胞が、記憶の再起時にもう一度興奮する現象から推察できるが、この時神経興奮によって誘導される転写因子の発現をマーカーにして追跡される。このような immediate early gene(IEG) として Fos とか Arc などが使えるが、ほとんどの研究は一つの IEG をエングラム特定に使い、いくつかを組み合わせることはなかったらしい。
この研究のハイライトは Fos と Npas4 の2種類の IMG の発現をモニターできるレポーターを用いて、一つの記憶成立と呼び起こし過程をモニターしてみようと着想したことで、そのためにレポーター自体の活性を薬剤で高めたり落としたりできる凝った実験系を構築して、実験中に痕跡が成立する細胞だけが追跡できるようにしている。
複雑な実験が行われているが、結果は比較的単純で、次のようにまとめることができる。
一つの記憶痕跡が成立する時、Fos, Npas4 など、異なる IEG が誘導される。 少なくとも Fos と Npas4 については、異なる細胞で働いており、記憶痕跡が異なるタイプの神経細胞が協調して成立していることを示唆する。 この実験の場合、Fos でラベルされる細胞は興奮神経で、Npas4 でラベルされる細胞は抑制性神経を代表している。すなわち、異なるタイプの神経細胞が、異なるタイプの IEG を使って、異なるプログラムの書き換えを行なっている可能性が高い。 また、Fos が誘導される興奮細胞は記憶の一般化(似た状況での記憶の呼び起こし)に、Npas4 が誘導される抑制性神経は記憶の正確な区別に関わる。 それぞれの神経は、異なる上流の神経と回路を形成している。 他にもあると思うが、以上が主な結果で、記憶のエングラムも複数の異なる機能を持つ細胞タイプとそれにつながる上流下流の神経サーキットの協調により成立し、それぞれの細胞が異なる IEG を用いてプログラムを書き換えることで、記憶成立時の状況と、新しい状況の類似性や違いを判断して、行動を選んでい、とまとめることができるだろう。
かなり生理学にも強いグループだと思うが、記憶エングラムについての概念をまとめ直すには優れた研究だと思う。