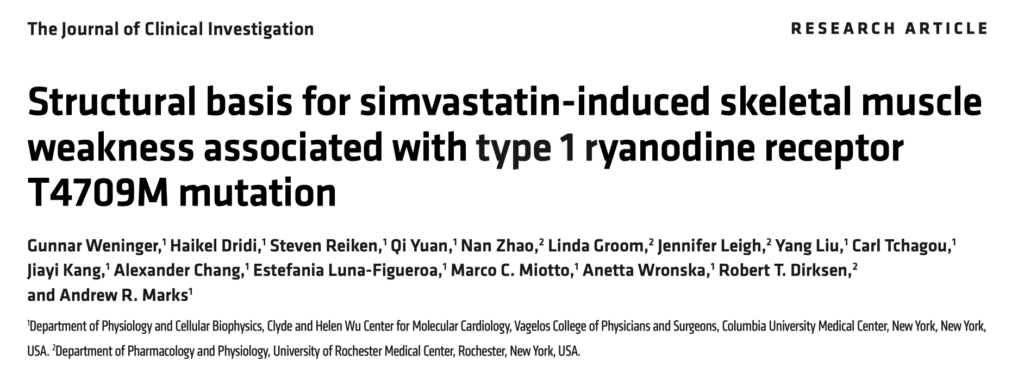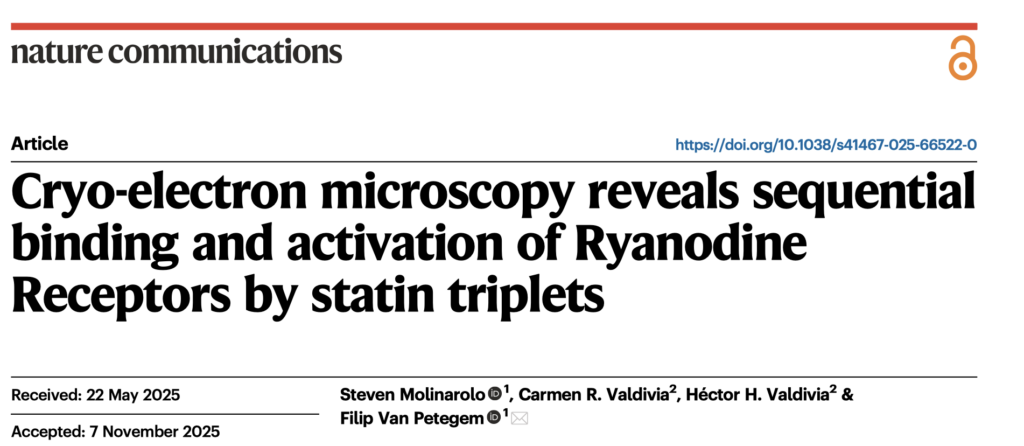2026年2月25日
一般に生成AIが使える様になった後、患者さんの団体に利用を勧めた。あれから二年、おそらくうまく付き合っておられるのだろう、病気についての問い合わせは激減した。事実、最近日本で認可されることが発表されたFOP治療薬の最新状況について聞くと詳しい答えが返ってくる(https://chatgpt.com/share/699e28dc-6b50-8008-814e-840f955b4a35 )。 2月19日のソホノスの認可からリジェレロンの薬剤への期待まで、私から見てもほぼ完璧な答えが示されている。生成AIにより8割のコンサルタント業が消失するといわれているのは肯ける。
今日紹介するオーストラリア Complexity Science Hub 研究所からの論文は、生成AIにより既に影響が出ているプログラム作業への生成AIの浸透を調べた研究で、2月19日号 Science に掲載された。タイトルは「Who is using AI to code? Global diffusion and impact of generative AI(だれがAIをプログラムに使っているか?生成AIの世界的浸透とインパクト)」だ。
現在半分以上のプログラマーに利用されているのがPythonだが、この研究では生成AIが使われたプログラムをAIに学習させることで、プログラム中のAIが使われた箇所を特定するシステムを開発している。多くのジャーナルで生成AIを使った文章をチェックするのと同じような物と考えればいい。このAIを利用して、GitHub に登録しているユーザーからランダムに2000人/year(トータルで6000人)のプログラム開発者を選び、GitHub にデポジットしたプログラムが生成AIをどのように使っているのかを分析、プログラマーのプロフィルとともにそのデータを解析している。
これまで生成AIの浸透についての調査はほとんどアンケートなどのサーべーで行われているのに対し、この方法だとプログラム分野に限られるが実態を詳しく解析できる。ChatGPTが利用される時期からプログラムへの生成AIの利用は上昇し、現在では28%のプログラムは何らかの形で生成AIを使っている。
次に、このAIの浸透の広がりを米国、ドイツ、フランス、中国、ロシア、インドについて調べている。このような調査に日本が選ばれなくなっているのにがっかりするが、ChatGPTが利用されるようになってすぐには大きなリードを保っていた米国は、ドイツやフランスに急速に追い上げられている。次がインドで、驚くことに中国がかなり遅れている。ただ、これは中国のプログラマーがChatGPT等を自由に使えず、またオープンなGitHubへのデポジットをためらうからかもしれない。今はDeepSeekが使えることから、ほとんど差はないのではないだろうか。逆に我が国での現状も是非分析してみる価値はある。
次に、プログラマーの経験年数と生成AIの利用状況を見ると、経験の浅いプログラマーほど生成AIを使う傾向がある。とは言え、経験を積んだプログラマーと経験の浅いプログラマーが利用した生成AIのプログラムへの寄与を調べると、全ての分野で経験を積んだプログラマーのプログラムへの貢献度が高いことがわかる。即ち、経験の高いプログラマーほどうまく生成AIを使いこなすことがわかる。生成AIを使う前と後で、経験者のプログラムを調べると、それまであまり使っていなかったPythonライブラリーも比較的自由に使ったプログラムを書くようになっていることがわかる。
結果は以上で、生成AIについて様々なことを教えてくれる優れた論文だと思う。すなわち、生成AIを使うための専門知識が必要で、その上に生成AIは新たな専門を積み重ねてくれるということがよくわかる。おそらく医学についても同じで、患者さんの団体もある程度の専門知識があることから、急速に生成AIを使える様になっていったのだと推察する。同じことは子供の教育にも言える。生成AIのおかげで、記憶を強要する必要はなくなったが、知識を得るための土台をどう作るのか、真剣に考えるところに来ていると思う。
2026年2月24日
当時の三共製薬(現在は第一三共)の遠藤さんにより開発された HMG-CoA reductase 阻害剤スタチンは、おそらく何千万人もの人に利用され、動脈硬化に起因する心臓死を防いできた。特に生活習慣病の薬剤として長期にわたって安全に服用し、病気を防ぐという意味では画期的な薬剤で、私たち夫婦もその恩恵にあずかっている。使用に当たって最も重要なのが副作用で、例えばリポバス(シンバスタチン)の説明書には、横紋筋融解などの筋肉症状に加えて、肝炎、肝機能障害、黄疸、末梢神経障害、間質性肺炎が可能な副作用として書かれており、血中の酵素で調べるいわゆる肝機能検査が異常値だと使用を躊躇することになる。実際スタチンの副作用が20%の人に見られるという論文が発表された後1年間に、英国だけで20万人の患者さんがスタチンをやめ、その結果2000-6000例の心臓発作を予防できなかったと推定されている。
今日紹介する Cholesterol Treatment Trialists (CTT) と名付けられたオックスフォード大学を中心にした国際グループからの論文は、スタチンの大規模治験のメタアナリシスだが、参加者の個人データを再検討して副作用について調べ直した研究で、2月14日号の Lancet に掲載された。タイトルは「Assessment of adverse effects attributed to statin therapy in product labels: a meta-analysis of double-blind randomised controlled trials(説明書に書かれているスタチン副作用の検討:無作為化二重盲検治験のメタアナリシス)」だ。
この研究では、個人データを再検討できる19の治験について、特に False Discovery Rate を制御した上で、副作用を解析し直している。その結果、確かに高用量で血清のトランスアミラーゼは高まることは観察されるが、アルカリフォスファターゼや γGT の上昇は観察されず、閉塞性肝疾患、黄疸、肝不全が起こることはないと結論している。
他にも、尿タンパクの上昇は見られることがあるが、沈渣で血球が見られる異常は起こらず、また浮腫が起こるという報告は全くない。他にも、認知機能、ウツ症状、睡眠障害、末梢神経炎もスタチンの副作用として認定できない。
以上の結果から、説明書はもっと現実的な指示に変えるべきであると結論している。即ちこれまでの副作用リストを省くのが難しい場合、実際の可能性についてもう少し詳しく書き直すべきだと推奨している。
ただ、この研究で調べ直していないのがスタチン服用による筋肉症状で、これについては昨年12月に米国コロンビア大学から The Journal of Clinical Investigation に、11月20日にカナダ British Clumbia 大学から Nature Communications に、副作用発症メカニズムについての研究が発表されているので、短く紹介する。
両方の論文とも、スタチンと筋肉に発現しているカルシウムチャンネル放出チャンネル・リアノジン受容体とスタチンの結合をクライオ電顕で構造的に解析し、スタチンの結合によりチャンネルの孔が大きくなりカルシウムが過剰放出されるのが筋肉症状の原因である事を突き止めている。
最初の論文ではシンバスタチン、次の論文ではアトルバスタチンとそれぞれ type 1、 type2 の異なるスタチンが用いられているが、結論はほぼ同じで、複数のスタチンがリアノジン受容体に結合して、構造を変化させる。即ち、スタチンが本来の標的以外の分子に結合することで副作用が生じる。
後はシンバスタチンだけについて説明すると、通常の薬のように分子のポケットに入るのではなく、チャンネルが孔を形成している領域の比較的オープンな構造にシンバスタチンが結合し、これによる構造変化でアクセスできるようになった部分にもう一つのシンバスタチンが結合して、穴が大きくなることが構造的に示されている。
以上の結果から、リアノジン受容体への結合はどのスタチンでも見られることから、スタチン服用で筋肉からのカルシウム放出が誘導される可能性があることは間違いない。しかし、結合自体が分子のオープンな構造を標的にした弱い反応である事、複数のスタチンが結合しないと最終効果が得られないことなどから、正常の人では、その後の適応によりほとんど問題にならないと結論している。
一つ明確になった重要な問題は、リアノジン受容体の変異を持つ患者さんでは、スタチンの効果が高まってしまうため、重症な筋肉障害につながる可能性があることが示された点だ。スタチンによるカルシウム放出亢進は、症状の全くない片方の染色体にだけ変異がある人でも見られることから、遺伝子検査を行ってリスクを防ぐことが副作用軽減の最も重要なポイントになる。
ただ、スタチンが結合する時に働く疎水性の領域は、HM-CoA reductaze の結合には必要無いので、今後筋肉症状を誘導しないスタチンを設計することは可能だ。さらに、カルシウムチャンネルを修復するRycalを併用することで、症状を防ぐことも出来るので、絶対必要な場合スタチンを諦める必要はないというのが結論になる。
今や脂肪を下げると宣伝している飲料などよりずっと値段も安く、さらに効果ははっきりしているので当分は服用を続けよう。
2026年2月23日
様々な疫学調査で、人間や動物が高地に順応すると糖尿病の頻度が低下することが指摘されている。人間だけでなく、チベットのブタではインシュリン感受性が高まっていることが知られており、高地、即ち低酸素環境がこの状態に関わることが示唆されている。
今日紹介する米国 Arc研究所からの論文は、高地で血糖が低下するメカニズムを明らかにした研究で、2月19日 Cell Metabolism にオンライン掲載された。タイトルは「Red blood cells serve as a primary glucose sink to improve glucose tolerance at altitude(赤血球は主要なグルコースのシンクとして働き、高地でのグルコース耐性を高める)」だ。
まず、高地で糖代謝を調べた様々な論文がリストされ、この現象が生活習慣の違いではなく高地に対する動物の生理学的反応である事が示される。この中で面白いのは、シェルパと一般人を比べ、高地によるグルコース低下がシェルパでは見られないことが示された点だ。一方、ペルーのアンデスに住む住民では血中グルコースが低い。シェルパの高地適応は心血管系の遺伝子多型で、血中の赤血球は高地順応で増えない。一方、アンデス人は赤血球が高いことから、高地でグルコースが低下するのは赤血球が増えることが原因である事が示唆される。
この研究ではマウスを低酸素状態(通常21%を8%で飼育)に置くと、ブドウ糖を摂取したときのブドウ糖の低下、即ち耐糖能が上試乗する。ただ、これはインシュリンに対する感受性が上がったからではない。また、FDG-PETを用いてブドウ糖取り込み臓器を調べると、特定の臓器で取り込みが上がって代謝されているわけでないことがわかる。
そこで、赤血球の数と血中グルコースの関係を調べるため、瀉血野輸血で血中赤血球数を変化させると、低酸素にしなくても血中グルコースの低下が見られる。すなわち、肝臓や筋肉と同じようにグルコースは赤血球にも取り込まれており、赤血球数が上昇するとこのシンク機能が発揮され、血中グルコースが低下すると考えられる。
ただ、グルコースを取り込むためにはトランスポーターが必要になる。そこで、低酸素状態で飼育したマウスの赤血球を調べると、Glut1、Glut4トランスポーターの発現量が上昇している。赤血球は新しいタンパク質は合成できないため、低酸素状態で合成された赤血球でトランスポーターの発現が上昇して、シンク機能を高めていることがわかる。
さらに、赤血球内でのグルコース代謝が低酸素で変化する可能性も調べ、グルコースから2,3-DPGを作るLRシャントと呼ばれる代謝経路が高まっており、低酸素で赤血球内に2,3-DPGが急速に増加することを明らかにしている。この経路は、ヘモブロビンの構造を安定化させ、ヘモグロビンから酸素の遊離を高める。この低酸素に対する生理反応により、グルコースが赤血球内で消費できるようになっている。
しかし、これに関わる酵素を新しく合成することは赤血球では不可能なので、グルコース代謝が上昇する原因を調べ、赤血球では通常Band-3膜タンパク質に結合して膜に局在することで機能が抑えられている解糖系酵素が、低酸素により細胞質に移行する事で解糖が起こることを突き止める。そして、この膜から細胞質への移行が、低酸素により形成されたデオキシヘモグロビンがBand-3と結合し、代わりに解糖系酵素が細胞質へと移行する事を明らかにしている。
以上、基本的には赤血球が増加して、新しくできた赤血球でのグルコース取り込みと代謝が上昇する事で、高地で血中グルコース上昇が抑えられるメカニズムである事を明らかにしている。とすると、高地順応によりグルコース代謝が改善するはずで、糖尿病を誘導したマウスの血中グルコースが低酸素で低下すること、更にはヘモグロビンに結合して低酸素状態と同じに変化させる薬剤でも耐糖能が改善することを示している。
以上、間違いなく高地で生活すれば糖代謝は改善するので、高地へと移住できる可能性にある人は考えてみてもいい治療になる。
2026年2月22日
昨日は育メン行動を押さえるのが Agouti という予想外の面白い話だった。Agouti 自体は毛色を決める分子だが、Agouti 関連タンパク質は食欲を調節する重要な柱だ。他にもレプチンやオレキシン、そして GLP-1 と食欲を調節するペプチドホルモンは研究が進んでおり、どの組み合わせになるかはともかく、近いうちにこの領域からノーベル賞が出てもおかしくない。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、相手の痛みを見て、自分の痛みとして感じる共感行動に、今度は我が国の柳沢さんが発見した食欲調節ペプチド、オレキシンが関わっているというオレキシン作用の多様性を物語る面白い話で、2月19日号の Science に掲載された。タイトルは「Empathy and prosocial behavior powered by orexin-driven theta oscillations(共感と社会的行動はオレキシンによって誘導されるテータ波により駆動される)」だ。
この研究が対象にしている行動を説明すると次のようになる。 同じケージで飼育しているマウスが電気ショックで苦しんでいるのを見ると、マウスでもすくんでしまう。これが代理凍結 (Vicarious freezing)と呼ばれる行動だ。この後同じケージに戻すと、共感を感じた場合、相手を思いやり毛繕いを行うことが観察される。これらの行動は、観察者の方が実験より前に自分も電気ショックを経験しているかどうかで、変化することが知られている。
まず代理凍結の強さだが、自分で痛みを経験している方が強い。しかし、経験しないマウスでもある程度相手の痛みが理解できてフリーズする。ただ最も大きな違いが見られるのは、ショックの後同じケージに戻ったとき、自分が痛みを経験している場合、毛繕いなど共感行動が強く見られるが、経験がないとレベルが低い。
この行動はよく研究されており、対応する脳領域も前帯状皮質である事がわかっている。この部位の興奮をカルシウム流入で調べると、5−7Hzの領域で、まず代理凍結時に興奮が見られる。興奮レベルは圧倒的に痛みを経験していると高まるが、痛みを理解していない場合もある程度興奮する。しかし、自分が経験していない場合、一緒のケージに戻っても全く興奮は見られないが、経験している場合、同じ5−7Hzに強い興奮が見られる。即ち、自分も痛みを知っている場合、代理凍結から共感行動まで、同じ前帯状皮質の神経細胞興奮により行動がドライブされている。
前帯状皮質にはオレキシンを分泌する神経が視床下部から投射されているが、代理凍結とその後の共感行動時にオレキシン分泌を調べると、オレキシンの分泌がそれぞれの行動時に上昇する事が確認される。オレキシンは、食欲や眠りだけでなく、情動や意欲にも関わることがわかっているので、視床下部のオレキシン分泌細胞を抑制すると、痛みを経験したマウスだけで代理凍結から共感行動時の帯状皮質の興奮が抑えられ、特に共感行動が低下する。
さらにタイミングを AI でコントロールしてオレキシン分泌神経を操作する実験を行い、代理凍結時に前帯状皮質の興奮を刺激しているのが視床下部オレキシン神経である事、そして以前に自分が経験した痛みの記憶が、このオレキシン神経興奮としてリコールされ、共感行動を誘導することが明らかになった。
以上が結果で、前帯状回と共感行動については明らかにされていたが、この研究で視床下部のオレキシン神経が前帯状回の神経の5-7Hz神経興奮を誘導して、行動を制御することが明らかになった。昨日の Agouti もそうだが、食欲ペプチドとして最初同定されたオレキシンも研究が進むと、眠りや今回の共感行動に至るまで、多くの行動に関わることが明らかになっている。今はやりのGLP-1受容体刺激ペプチドも、ひょっとしたら私たちの知らない行動変容を誘導している可能性もある。臨床例の慎重な観察が必要だと思う。
2026年2月21日
ヨザルなど一部の哺乳動物を除くと、ほとんどの哺乳動物の子育てはメスの役目になっている。それどころか、例えばライオンなどではメスの発情を促すため、メスが育てている子供を殺すことも観察される。
今日紹介するプリンストン大学からの論文は、“育メン” 行動で知られるアフリカ縞マウスを用いてこれに関わる脳領域と育メンを押さえる分子として Agouti を特定した面白い研究で、2月18日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Agouti integrates environmental cues to regulate paternal behaviour(Agouti は外界からのシグナルを育メン行動へと統合する)」だ。
子育てをするオスマウスに育メンとはおかしい使い方とは思うが簡単なのでこれで通す。さて、タイトルにある Agouti は元々マウスの毛色を示す言葉に由来しており、色素細胞がメラニン刺激ホルモンでメラニンを発現するのを抑制することで、毛色が茶色にする分子として知られている。一方で、脳内で発現するアグーチ関連タンパク質は食欲を刺激するペプチドとして働いている。
さて、この研究は縞マウスが実験室でも育メンする条件を検討し、離乳した後単独で生活すると、他のオスと一緒に生活する場合より育メン行動が刺激され、逆に子供を殺すことはほとんどなくなることを発見する。
次に単独で生活して育メン行動が刺激されたマウスと他の個体と一緒に生活して育メン行動を示さないマウスの脳で、興奮状態に差が見られる場所をFosの発現で調べ、まさにメスの子育てに関わる領域、内側視索前野 (MPOA) が、育メンオスでも興奮することを発見する。
通常なら、光遺伝学を駆使してこの領域を操作する実験が続くのだが、野生マウスではそうはいかない。まずこの反応が幼児と出会う事で誘導され、育メン行動の場合神経興奮によりFosだけでなくEgr1が誘導される。一方、集団で生活し、幼児に会って殺す行動をとる場合は、FosとともにArcが発現することを確認する。
このことから、MPOAではそれ以前の生活スタイルで神経刺激ペプチドの微妙なバランスが変化しているとにらんで、育メンと子殺しの脳の遺伝子発現を比べる過程で Agouti が育メンで最も強く押さえられるペプチドである事を発見する。即ち、Agouti が高まると育メンをやめ子殺し行動をとる。
この結論が正しいかどうか、アデノ随伴ウイルスを用いてAgouti遺伝子をMPOAで過剰発現させる実験を行っている。まず、育メン行動、あるいはまだ行動が定まっていないマウスMPOAに Agouti を過剰発現させる事件を行うと、行動が定まっていないマウスでは全て子殺し行動をとる。ただ、育メンマウスに発現させても子殺しには移行しない。
後は Agouti が持っている他の機能を介して2次的に育メン行動が誘導されているわけではないことを、食欲をコントロールする実験などを通して確認している。
以上が結果で、Agouti 以外のペプチドについては実験が出来ていないので、育メンを誘導するメカニズムについては完全に明らかになった訳ではないが、今後は例えばオキシトシンなどメスの母性行動を誘導する仕組みを参考に詰めていく必要があるだろう。
いずれにせよ、野生マウスの行動を一定レベルの神経科学へと発展させた面白い研究だ。
2026年2月20日
乳酸菌と並んでビフィズス菌はプロバイオの2本柱だが、実際にはゲノムがわかっているだけでも100種類以上存在する。また遺伝子の一部を使うゲノム検出方法では、InfantisとLongum が一つに扱われ、ビフィズス菌と我々の身体の相互作用を調べるにはあまりにもデータが乏しい。
今日紹介する英国サンガー研究所からの論文は、世界6大陸48カ国からビフィズス菌を集め、これまで明らかになっているゲノムと会わせて、4098種類のゲノムを解読し、それぞれのビフィズス菌系統の分布やホストとの関係を調べた研究で、2月19日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Genomic atlas of Bifidobacterium infantis and B. longum informs infant probiotic design(Bifidobacterium infantisとlongumのゲノムアトラスは新しいプロバイオのデザインを教えてくれる)」だ。
ビフィズス菌の4098種類のゲノムを再構成したことがまず素晴らしい。ビフィズス菌は我々の生活と直結している細菌なので、集められた情報の価値は計り知れない。論文ではこの素晴らしい価値についてわかるようデータが示されていく。特に、南アジアやアフリカのビフィズス菌はこの研究で解読されるまで全くゲノムがわかっていなかった。
菌自体としてはまず infantis が生まれ、そこから longum が派生し、それぞれ独自に種分化を進めている。この過程で longum は特に多様化を進め、現在3種類の亜種に分化している。それぞれをinfantis(BI)、longum の亜種を longum longum(BL)、longum suis(BS)、longum X(BX) と分けて調べている。
生息域で見ると、BIとBS、BXはほとんどが幼児の腸に棲息する一方、BLは幼児の腸にも存在するがほとんどは大人の腸に見られる。生息域から見るとBIからBS、BXと徐々に大人の腸にも移行するように出来ている。特にBSは人間以外の環境や動物から分離されたビフィズス菌を含んでいる。
面白いのは、BIは最も古いビフィズス菌だが、アフリカやアジアの子供に多い。一方、BLとBXは圧倒的に高所得国で見られる。面白いのは高所得国の中でも英国だけが比較的多様性を保っていることで、生活スタイルの多様性が維持されているのか面白いところだ。いずれにせよ、ビフィズス菌に関してはどれかの亜種に収束していくことで、ジンバブエやバングラデシュのような例外を除くと、異なる亜種が共存することは難しい。
この年齢及び地域での生息の違いの原因を遺伝子発現から探ると、例えばBIはいくつかのビタミンBや尿酸を利用する代謝経路が発達している一方、大人に多いBLは粘液やグリカンを利用する代謝系を持っている。即ち、BIは母乳が含む栄養分と密接に関わる一方、BLは植物成分を利用するための代謝経路と密接に関わる。そして、この中に地域で食されている植物に会わせて進化してきた菌株が存在する。
ビフィズス菌はプロバイオとしての歴史が古いが、現在利用されているビフィズス菌を他のビフィズス菌と比較すると、確かに様々な代謝経路を備えているが、生存という点では比較的ヨーロッパやアメリカのビフィズス菌に近い。即ち、アフリカや南アジアの細菌叢とフィットしているとは言いがたい。
最後にこれらの複雑性を比較的簡単に調べるためのPCRプライマーも作成し、今後ビフィズス菌を世界規模で調べ直すことこそ新しいプロバイオを開くと結論している。大体わかっていることだが、ここまで精密に調べることが重要だと思う。
2026年2月19日
GLP-1受容体アゴニスト (RA) や、GLP-1/GIPRA は糖尿病だけでなく、肥満からアルツハイマー病まで様々な病気への適用が試され、2025年の売上高が630億ドル、即ち9兆7千億円になっている驚くべきブロックバスターだ。個人的にも興味津々で論文に目を通しているが、最近目にした GLP-1RA のネガティブな側面を調べた研究を紹介することにした。
まず最初はオーストラリア アデレード大学から2月16日 The Journal of Clinical Investigation にオンライン掲載された論文で、GLP-1RA の副作用についてこれまでの研究をまとめた総説だ。タイトルは「The science of safety: adverse effects of GLP-1 receptor agonists as glucose-lowering and obesity medications(安全の科学:血中グルコースを低下させ肥満を軽減する薬剤GLP-1受容体アゴニストの副作用)」だ。
これまで一例報告も含めて GLP-1RA の副作用が数多く報告されているが、その一つ一つについてメカニズムも含め著者らが感じる結論を明確に示している総説で役に立つ。
まず、この薬剤の最も多い副作用は吐き気、嘔吐、下痢で、偽薬と比べ吐き気(19.3vs6.5%)、嘔吐(7.6vs2%)、で下痢も含めると実に半数近い頻度で起こり、治療中止の最も多い理由になる。現在のところ、ゆっくり量を上げる以外に抑える方法はない。と言うのも、この副作用が GLP-1RA の持つ食欲中枢への直接作用なので、もちろん効果の重要な要素にもなっている。
これ以外の消化器症状として、胃内容物の十二指腸への移行が遅れるという報告があるが、これについては実際に内視鏡で調べた結果では問題がない。
最も重大な副作用の可能性として、胆管炎が指摘されているが、これまで報告されたような胆嚢炎や膵炎のリスクはほとんど上がらない。問題は、ほとんどの患者さんで血中アミラーゼやリパーゼが上昇する事で、これが膵炎などの診断につながっている。
甲状腺ガンのリスクについてもレポートがあるが、正常の甲状腺細胞には GLP-1R は発現されていない。しかし、遺伝性の内分泌腫瘍など前ガン状態に入ると GLP-1R が発現するので、この場合は甲状腺ガンへの進展を後押しする。実際北欧でのコホート研究ではリスク比は0.93と逆に低い。
網膜炎も GLP-1RA の副作用として報告されているが、このほとんどは基礎にある糖尿病による物で、GLP-1RA の直接作用で起こるわけではない。他にも、non-artertic anterior ischemic optic neuropathyと呼ばれる希な病気のリスクも報告されているが、頻度が少ないのであまり問題にならない。
うつ病を誘導するという報告もあるが、大規模コホートでは逆に頻度が下がるということがわかってきた。
あと最も問題になる高齢者のサルコペニアだが、これも本当に筋肉量が低下するかどうかは結論できないとしている。機能的には大規模コホートで筋力が上昇したという報告もあるので、高齢者に使っていいかはさらに検討が必要という結果だ。
以上、全体の雰囲気はほとんど問題がないという結論になっており、消化器症状さえ問題にならなければ長期に使えるという結論だ。
もう一つ紹介したいのは昨年暮れに Journal of Marketing Research にコーネル大学から発表された論文で、GLP-1RA を使い始めた過程での消費動向を調べた面白い研究だ。タイトルは「The No-Hunger Games: How GLP-1 Medication Adoption is Changing Consumer Food Demand∗(おなかが空かないことの影響:GLP-1薬剤は消費者の食を変化させるか)」だ。
この研究では GLP-1RA を使い始めた患者のいる家庭の消費動向を1年にわたって詳しく調べている。まず驚くのは、米国では家庭に GLP-1RA を使っている家族がいる率が2023年で16%を超えていることで、人口比率で見ると8.3%にも達する。肥満が40%の国と考えると当然だが、医療費も考えると大変なことだ。コクラン調査によると、米国では1月のコストが1400ドル近くになる。
これらの家庭では、食料品の購買額が驚くなかれ、8%近く低下する。特に高所得者ほどその傾向が強い。ただ、食品の内容を調べると、GLP-1RA を使い始めることで、食は健康指向が強まり、ケーキやチップスの消費はどんと低下し、逆にヨーグルト、果物の消費は高まっている。
結果は以上で、この雑誌は Marketing の雑誌なので、食品業界に深刻な影響を及ぼす可能性があることを強調している。
以上、おそらく高齢者も使える治療法として定着しそうで、個人的にはその結果食生活が改善されるのなら言うことはない。
2026年2月18日
このブログでも紹介してきたように、膵臓ガンは細胞内の不要物を再利用するオートファジーを活性化させて増殖していると考えられている。しかし、オートファジー阻害剤の効果は期待されたほどではない。
今日紹介するニューヨーク大学からの論文は、膵臓ガンのオートファジーレベルは極めて多様で、増殖には確かにオートファジーは効果があるが、抗ガン剤の感受性にとってはオートファジーは逆の効果があることを示した研究で、2月16日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Extracellular matrix sensing regulates intratumoral heterogeneity of autophagic flux(細胞外マトリックスのシグナルは腫瘍内のオートファジーの多様性を調節している)」だ。
この研究では、膵臓ガンを2次元培養するとオートファジーが低い均質の細胞として増殖するが、マトリックスを含むマトリゲル3次元培養にするとオートファジーレベルが極めて多様になることに気づき、膵臓ガンが単純にオートファジーが高いというより、マトリックスに応じてオートファジーレベルを調節していることを明らかにする。
後は、膵臓ガンでオートファジーに必要な分子の転写因子をポジティブに調節しているのが神経線維腫症の原因遺伝子NF2で、逆にネガティブに調節しているのがYAP分子である事を、クリスパースクリーニングにより突き止める。
NF2とLAT2は通常細胞内の栄養状態を感知してオートファジーを活性化するが、YAPは相方のTEADと協力してレプレッサーとしてオートファジー関連遺伝子を転写レベルで抑制していることになる。またマトリゲル内での3D培養の結果から、YAPを活性化するのはマトリゲルに含まれる様々なマトリックスの可能性が高い。
そこで、YAPを活性化するマトリックスを探索し、最終的にラミニンとそれを感知するインテグリンα3がYAP活性化に関わることを明らかにする。
膵臓ガンは周囲に線維芽細胞が密集し、線維化が進んでいることが特徴とされ、これが膵臓ガンが悪性である重要な要因として考えられてきた。ところがこの研究では、ラミニン・インテグリン・YAPはオートファジーを抑制する方向に働くことから、ガンの増殖にとってはネガティブな作用を持つことになる。とすると、膵臓ガンのマトリックスも単純にガンの悪性化を助けていると言えなくなる。
この問題に対して、膵臓ガン細胞株や膵臓ガン患者さんから採取した膵臓ガン細胞のオルガノイド培養を行い、インテグリンをノックアウトしても細胞の増殖に全く影響がないが、オートファジーを抑制するクロロキンで処理した時に、インテグリンの膵臓ガン抑制効果が見られるようになることを示している。即ち、インテグリン/YAPを抑制してオートファジーを高めることでよりクロロキンへの感受性が高まることになる。ただ、オートファジーだけを膵臓ガン治療の標的にすることはないので、より臨床に近い、クロロキンとゲムシタビンによる治療実験系でインテグリンノックアウトの効果を調べると、ゲムシタビンの抗腫瘍効果をインテグリン/YAPによるオートファジー抑制が促進することを発見している。
この実験はデータもそれほど明確ではなく、そのまま真に受けられるかはよくわからないがオートファジーは増殖を助ける一方、ゲムシタビンなどの感受性を下げる効果があり、これが膵臓ガンの治療を難しくしていることになる。
結果は以上で、膵臓ガンを単純な細胞集団として捕らえるのではなく、周りの環境に応じて多様化して、異なるストレスに集団として対応しているやっかいな集団とみることの重要性を示した研究と言える。ただ、その分実験はわかりにくい。
2026年2月17日
毎日目を通す論文のほとんどは、名の知れた雑誌が中心で、専門誌に目を配ることはコンサルテーションで必要なとき以外ほとんどない。論文紹介のために専門誌を読むのは、紹介する論文を選んだ後、その仕事の背景を調べるときに限られる。このように名の知れた雑誌しか目を通していないにもかかわらず、よく論文が採択されたなと思える変わった論文に出会うことがある。すなわち、ほとんどの人が選ぶとは思えない課題に、真面目に徹底的に取り組んでいる研究で、その真面目さが微笑ましい。
今日紹介するドイツ シュトゥットガルトのマックスプランク情報システム研究所からの論文もそんな一例で、象の鼻ヒゲを、感覚毛であるという仮説の下に、ただ真面目に調べた研究だが、なんと2月12日 Science に掲載された。タイトルは「Functional gradients facilitate tactile sensing in elephant whiskers(ゾウの鼻ヒゲに見られる機能的購買が触覚を高める)」だ。
触覚というタイトルを見て、当然、神経科学の研究かと思ってしまう。実際マウスでは、一本一本のヒゲ由来に対応する、解剖学的に特有な神経配置をとるバレル構造が存在し、生後にヒゲを抜いたりするとばれる構造は消失する。ゾウではどんなバレル構造が見られるのかと読み進むと、この研究では全く神経や毛根の話は出てこず、もっぱらゾウの鼻に分布するヒゲの構造解析に終始している。しかし面白い。
まず鼻ヒゲと言ってもゾウの鼻は長く、定義は難しい。鼻に生えている毛と定義すると、ゾウには1000本の鼻ヒゲがあるらしい。
構造の最大の特徴は、毛が平べったいことで、このおかげで曲がる方向が薄い側に決められる。この構造は生まれてすぐには存在せず、成長とともにわざわざ平べったくなることから、ゾウを特徴付ける重要な構造と考えられる。毛根で作られたばかりの根の部分は他の動物と同じで丸いが、中程になるほど平べったくなる。また、同じ鼻でも物をつかんだりする鼻先ほど平べったい構造がはっきりしていることから、感覚を支える重要な特徴としている。しかし、平べったい毛を形成するメカニズムを知りたいものだ。
次は構造で、他の動物では毛の中心に孔が通っているのが見られるが、ゾウの場合中心の孔はない代わりに、毛全体に数多くの小さな穴が分布している。また、外側にうろこ状の構造がないのも特徴になる。この構造は毛というより、角やひずめに似た構造で、物理学的特性をシミュレーションすると、固有振動数が上昇した結果、外部の振動に強く共振できることが想像される。
このように成分や構造からゾウの鼻ヒゲは基部が固く先に行くほど柔らかい構造を持っているが、ヒゲの感度が高いとされる猫も同じような構造を持つらしい。その結果、フレキシビリティーが増大し、壊れにくが感受性の高い感覚毛が出来ている。さらに、感覚のダイナミックレンジも広い。
以上が結果で、構造の解析と、様々な物理学的テスト、そしてシミュレーションから、鼻先で食べ物をつかんで口に入れるという複雑な行動がゾウで可能になっている秘密のほとんどは、この鼻ヒゲの構造にあると結論している。とは言え、生理学的には少し言い過ぎの気がする。解剖額や発生学的には、元々丸く固かった毛がと中で大きく変化するメカニズムが知りたい。
2026年2月16日
腫瘍細胞にウイルスを感染させて殺してしまう治療法補開発は、20世紀後半からずっと進んできた。腫瘍細胞ではよく増殖し、正常細胞では増殖しにくいように細工したウイルスが使われ、多様なOncolyticウイルスが開発されている。ただ、いくら腫瘍特異的と言っても、全てのガン細胞に感染し全て殺してしまうことは至難の業と言える。そのため、一時開発は停滞したが、その後ガン免疫のパワーが再認識されると、ガン免疫を誘導するきっかけとしてOncolyticウイルスを用いる可能性が生まれ、結果現在では400種類以上の臨床治験が行われる大ブームになっている。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、まさにこのトレンドを科学的にバックアップするための研究で、ヘルペスウイルスを用いたグリオブラストーマ治療により腫瘍局所で起こる免疫反応を、CODEX及び Xenium として知られる最先端の組織学テクノロジーを使って調べ、Oncolyticウイルスがガンに対する免疫を強く誘導していることを明らかにしている。タイトルは「Persistent T cell activation and cytotoxicity against glioblastoma following single oncolytic virus treatment in a clinical trial(一回oncolyticウイルス感染を感染させるグリオブラストーマの臨床治験から持続的な腫瘍に対するT細胞活性化と細胞障害性が明らかになった)」だ。
研究では16人の再発性のグリオブラストーマの主要部位に直接ガン特異的に増殖する単純ヘルペスウイルスを感染させる治験を行っている。この時治療前のバイオプシーと治療後の腫瘍切除標本を集め、これをこのブログでも以前紹介した(https://aasj.jp/news/watch/8803)CODEXと呼ばれる同時に何種類もの抗体を用いる分子発現検査と、Xeniumと呼ばれる拡散プローブを用いた多重分子発現検査を組み合わせて、腫瘍と様々なリンパ球との関係を調べ上げている。組織をバラバラにして調べる single cell テクノロジーと異なり、空間的情報が全て保持されているため高いレベルの情報が得られる。
まず、ほとんどの症例で腫瘍内へのCD8及びCD4T細胞の浸潤は10倍近く上昇し、しかも9ヶ月以上維持されている。それぞれのリンパ球の遺伝子発現から、キラー活性に関わるグランザイムが腫瘍近くのT細胞で発現していることも確認でき、間違いなく腫瘍に対するキラー反応が発生している。
腫瘍とT細胞の空間的関係を調べると、キラー活性を発揮するエフェクターは腫瘍内に潜り込んで反応している。また腫瘍内で新たなキラーT細胞を呼び込むケモカインを発現しており、新たなT細胞をリクルートする構造ができあがっている。面白いのは、新しいT細胞を供給するリザーブとも言える集団は、腫瘍から離れたところに存在して、そこからT細胞を腫瘍に供給している点だ。腫瘍内にはマクロファージの浸潤があるので、これが移動してリザーブを刺激していると考えられる。
ウイルス遺伝子を調べると、腫瘍が壊死に陥った部分にウイルスが存在するが、T細胞からは離れていることから、これまで議論されていたようなウイルスに対する免疫反応が腫瘍を傷害しているとは考えにくい。実際、T細胞のレパートリーを調べると、ウイルスに対する反応はほとんどないと考えられる。即ち、最初からガンに対するT細胞がウイルスにより細胞障害が始まることで急速な増殖を行い、残っているガンを傷害していることがわかる。
だとすると、全ての患者さんが免疫のおかげで治ることになる。実際、腫瘍内でT細胞が増殖しているほど予後は良さそうだが、しかしグリオブラストーマに対しては免疫も完全ではない。T細胞が存在しない腫瘍ゾーンを調べると、特に線維芽細胞様の形態をとり、低酸素により誘導される遺伝子が発現している領域からT細胞が完全に排除されている。この結果、免疫から逃れるガンが発生する結果、免疫治療が限定されることになる。
以上が結果で、実際には様々な情報が得られた研究だが、免疫の可能性とともに新しいガンのしたたかさが明らかになった。このガンのしたたかさを狙った治療を開発することが次の段階になるが、グリオブラストーマも徐々にではあっても治療が可能なガンになりつつある。