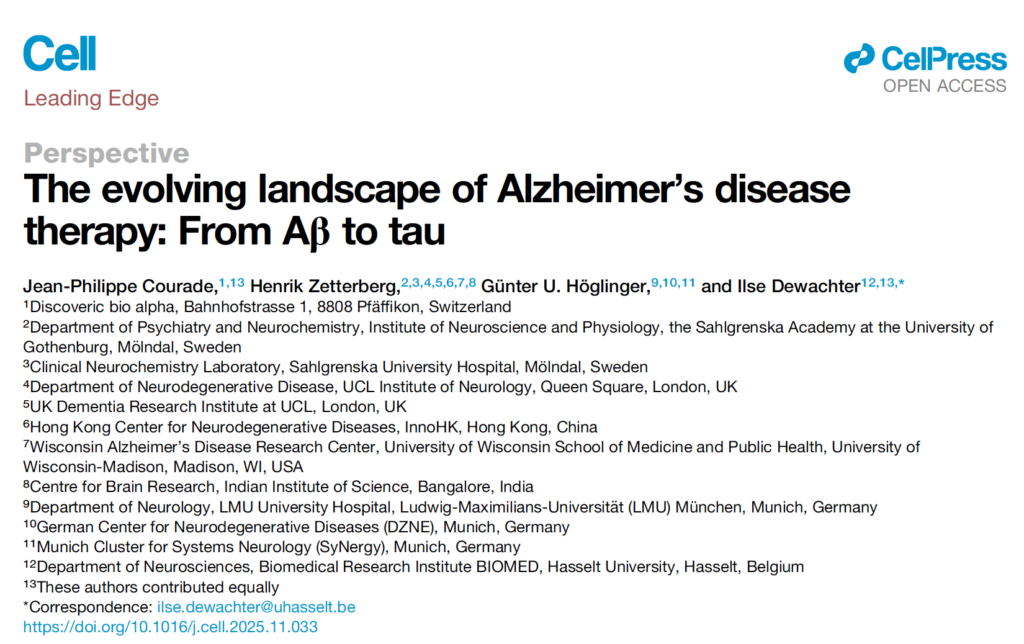2026年2月14日
今年に入って卵子の活性化とメカニカルストレスについての論文を2報続けて目にしたのでまとめて紹介することにした。
まず前置きとして、卵子の活性化についてざっと見ておこう。卵子の活性化の不思議は、一部の卵子だけが活性化され、残りは休止期を維持することで、このメカニズムの鍵を握るのがFoxo3転写因子だ。この分子が欠損すると、全ての卵子が活性化される早発性閉経に陥る。休止期の卵子ではFoxo3が核内に局在し、活性化を防いでいる。一方活性化のためには、Kit受容体からPI3K/AKTを介するシグナルがFoxo3をリン酸化することで核移行を防ぐ必要がある。これでわかったような気になるが、これだけでは休止期と活性化を分かつシグナルについては理解できず、まだまだ知るべきメカニズムがある。
この難しさを割り切って、卵子の活性化異常の患者さんで、卵子を取り巻く顆粒細胞でKitを刺激するSCFの発現を挙げてやれば異常を治療できるのではと仮説を立て、卵巣細胞を用いてSCFを上昇させる化合物を、なんとPCRでスクリーニングし、臨床で利用されているフィネレノンが卵子活性化誘導活性があることを示したのが、香港大学からの論文で、2月5日号の Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Antifibrotic drug finerenone restores fertility in premature ovarian insufficiency(抗繊維化薬剤フィネレノンは早発卵巣不全の不妊を治療する)」だ。
正直に言ってしまうと「乱暴な仮説のもとで、ともかく実験したら、臨床に使えそうな薬剤が見つかった」とまとめられる。と言うのも、もし全ての顆粒細胞のSCFが強く発現してしまうと早発性閉経と同じような状況になるはずだ。それでも、SCFが少し上昇するフィネレノンを投与すると、老化した卵巣の活性化が可能になるが、受精能や発生といった卵子そのものの機能は保全されることから、早発卵巣不全の治療に使えると結論している。
ただ、活性化のメカニズムを single cell RNA sequencing で探ると、最終的にフィネレノンが細胞外マトリックスの形成を抑えることで、卵子を刺激するという最初の仮説とは異なる結果に行きついている。事実、フィネレノンだけではなく線維化を抑えることが知られている薬剤は、卵子の活性化を誘導する。
この前臨床研究を元にすぐにフィネレノンの早発卵巣不全の治験に進んでおり、観察研究だが排卵が超音波診断で観察でき、その中から12個の卵子を採取して受精実験を行い、試験管内で卵割を確認している。この結果がなければ論文は採択されなかったと思う。
結果は以上で、最初の仮説とは異なる結果だが、マトリックス形成が抑えられると卵子が活性化しやすくなることを示している。臨床実験も計画性を感じさせない、結果オーライの研究で、メカニズムに至ってはFoxo3の染色もほとんどされず、全くわからない。
ところが、この結果を新しい観点で説明できる論文が1月16日、九大の永松、浜田、木村、及び阪大の林さんたちから米国アカデミー紀要に発表されている。タイトルは「The intrinsic impact of mechanical stress on the maintenance of oocyte dormancy(休止期卵子に対するメカニカルストレスのインパクト)」だ。
永松さんは私がプログラムディレクターをしていたさきがけメンバーで、林さんは卵子分化の世界をリードする研究者で、この研究はプロの研究と言っていい。最初から、Foxo3の局在に注目して、Foxo3が核局在する卵胞を試験管内で維持するために、外部からメカニカルストレスを加える必要があることを発見する。そして、顆粒細胞に守られない試験管内分化した卵子でも、KitシグナルでFoxo3を細胞質に留められること、しかしこれにメカニカルストレスをかけると、核局在を誘導できることを明らかにする。
長い話を短くしてメカニズムを説明すると、メカニカルストレスはダイネインの活性化を誘導し、細胞膜上のc-Kitを細胞質内に取り込むことで、Kitシグナルを弱める。その結果、Foxo3のリン酸化シグナルた低下し、Foxo3が核内に移行、休止期を維持するというシナリオが、多くの実験を行って納得できる形で示されている。
この研究ではメカニカルストレスが何かについては明確に示されていない。しかし、香港大学の仕事では、コラーゲンなどのマトリックスがこのシグナルに関わり、Kitシグナルが存在してもFoxo3の核内局在を誘導し休止期を維持していることになる。
おそらくインテグリンのシグナルを調べることで、今後もっと面白い可能性が生まれてくる気がする。実際休止期の卵巣は扁平顆粒細胞でぎゅっと締め付けられたような構造をしている。これが何らかのきっかけで、しかも確率論的に緩んで休止期から解放されるのでは等、想像が巡る。ともかく、さきがけのメンバーが面白い研究を続けていることはうれしい。
2026年2月13日
例えば乳ガンで腫瘍切除とともにリンパ節の郭清を行うと、切除側のリンパ管が機能しなくなりリンパ浮腫が起こる。リンパ管の再生も起こるはずなのに、リンパ浮腫の治療は難しく患者さんたちを苦しめる。下肢に起こる重症のリンパ浮腫では、ゾウの足のようになってしまい、単純に体液の循環が悪いという以上に、局所の組織の不可逆的なリプログラミングが起こる。
今日紹介する国立シンガポール大学からの論文は、リンパ浮腫をコレステロール蓄積という観点で見直し、コレステロール除去により症状を改善させることが可能であることを示した重要な研究で、2月11日Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Targeting excessive cholesterol deposition alleviates secondary lymphoedema(過剰なコレステロール蓄積を標的にすることでリンパ浮腫を改善できる)」だ。
病院で働いていたときリンパ浮腫の患者さんの受け持ちになったこともあるが、今回リンパ浮腫の患者さんの組織像を見て、単純に体液が溜まると言った話でないことがよくわかった。ステージが進むと皮下脂肪細胞の肥大が進み、上皮下の強い線維化と肥厚が起こっている。そして、自然炎症が高まるというより、脂肪細胞分化に関わる遺伝子の発現がほとんど消失して、要するに脂肪細胞のリプログラミングが起こっている。炎症の観点から見ると、線維芽細胞の刺激とTh2反応が誘導されている。
この研究では、リンパ浮腫の患者さんで組織にコレステロールが沈着していることに着目し、まず外科的処置でリンパ浮腫が改善した患者さんを調べ、コレステロールの沈着が軽減していることを発見、リンパ浮腫の主要原因がコレステロールがリンパ管に沈着し、組織液のリンパへの灌流を妨げるからではないかと考えた。
そこで高コレステロール症が発症するApoEノックアウトマウスの皮下組織を調べると、コレステロールがリンパ管に沈着し、特に皮下脂肪組織の肥大と線維化が進んでいること、すなわちリンパ浮腫と同じ組織像を示すことが明らかになった。
このマウスにコレステロールを下げる目的でHDLやApoA-Iを注射すると、コレステロールが下がることでリンパ浮腫が軽減する。ただこの治療法はリコンビナントタンパク質合成などコスト面での問題があるので、この代わりにコレステロールに巻き付いて排出する効果を持つシクロデキストリン (CD) の皮下投与でリンパ浮腫を改善できないか、ApoEノックアウトマウス、外科的に誘導した下肢リンパ浮腫、他様々なリンパ浮腫モデルを用いて試している。
結果は期待通りで、完全に元に戻るわけではないが、コレステロールの組織への沈着が押さえられ、浮腫を抑えることができることがわかった。さらに、長期的に経過を追うと、CD投与を受けることでリンパ管新生も促進され、組織に開いたリンパ管端末の数が2倍に増加することがわかった。すなわち時間がたてば、さらに浮腫は軽減していく可能性が大きい。結果は以上で、CDが食品に広く使われ、さらにリソゾーム病の治療に髄腔内投与が行われていることを考えると、人間への臨床応用もそう遠くないと思う。
この研究は、リンパ浮腫を新しい観点―即ち過剰コレステロールがリンパ管の入り口に沈着することが主要原因であるという観点―から見直し、これを証明するとともに、安価な治療法まで提案した重要な貢献で、臨床研究のお手本になると思う。この考えに立つと、外科的にリンパ管を除去してしまった場合でも、時間がたてば浮腫からの回復を期待できる希望が生まれたと思う。
2026年2月12日
ほとんどの読者にとって表皮突起は聞き慣れない言葉だと思うが、毛の少ない哺乳動物にとって上皮を身体にしっかりと貼り付けて皮膚の強度を守るための重要な構造物で、上皮が真皮に向かって突起の様に伸びた構造をとり、イルカやクジラ、ブタ、人間で発達している。進化の系統樹より、体毛の多さに関係して出来ており、人間に近いサルでも表皮突起はほとんど存在しない。また、体毛の多い動物でも、指先のような毛の少ない領域には表皮突起が見られる。
体毛の少ない動物がどうして生まれたのかは今も謎だが、体毛の量と反比例する表皮突起の形成は、長年の問題を解く鍵になるのではと、表皮突起の発生メカニズムを研究したのが、今日紹介するワシントン大学からの論文で、2月4日号 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Rete ridges form via evolutionarily distinct mechanisms in mammalian skin(哺乳動物の表皮突起は進化的に独自のメカニズムで発生する)」だ。
皮膚の研究というとどうしてもマウスになるので、ほとんど表皮突起の研究は行われていないように思う。この研究では、まず人間とブタの表皮の発生を調べ、どちらも毛根や汗腺などの付属組織の発生が終わった段階で生後に発生し、一生涯維持されることを確認している。基本的にはブタも人間も同じ発生過程をたどるので、分子生物学的検討は主にブタで行っても問題ないことを確認している。
論文の圧巻は、イルカ、hairlessブタ、domesticブタ、毛の多いMangalitsaブタ、人間、グリズリー、アカゲザル、ハダカデバネズミ、マーモセット、マウスの皮膚を比べた組織図で、大まかには毛の密度が減ると、表皮突起が発達し、最も発達したのがイルカである事、サルはほとんど表皮突起が見られないので進化とは関係ないことがわかる。面白いところでは、ハダカデバネズミのような毛のない齧歯類だから表皮突起が出来るわけではなく、退化で毛がなくなっても表皮突起は出来ないこともよくわかる。
後は発生のメカニズムだが、皮膚の付属組織に関わるLEF-1-Wnt及びEDA-EDARはノックアウトして付属組織が消失しても表皮突起は形成される。即ち、毛の密度と反比例するように進化するが、一旦出来た発生の仕組みは、毛がなくなってもそのまま維持される。これは人間の頭皮にも表皮突起があるのと同じメカニズムと考えられる。
主にブタ皮膚発生過程で Single cell RNA sequencing 、組織学的細胞動態の観察などを組み合わせて表皮突起形成に必要なシグナルを探ると、重要なシグナルとしてBMPとNOTCHが特定されてきた。もちろん他にも PDGFC など真皮側の細胞に関わるシグナル分子も特定できる。そして、細胞の増殖を調べると、表皮突起形成は細胞増殖層の異なる分布により、増殖して深く真皮に入り込む山の部分と谷の部分が形成されていることを示している。
ただ、これらのシグナルの関与を全て機能的に検討するのは実験的にも難しい。代わりに、BMPシグナルに関しては、マウスの指の皮膚に表皮突起が見られるのを利用して、皮膚でBMPシグナルを抑制する実験を行い、表皮突起の形成が阻害されることを示している。
結果は以上で、表皮突起も一種の独立した皮膚付属物として考える必要があること、また毛根や汗腺と言った他の付属物の発生原基の形成が終わった後で、BMPなど様々なシグナルを動員して、表皮突起と同時に、表皮突起のないポケットへの血管新生などを協調して進めるのが表皮突起形成であることを示している。出来れば、毛根などの付属組織のないイルカでの進化や発生がわかると、我々人間が体毛を減らした原因もわかるかもしれない。
2026年2月11日
毎年4月、できるだけ入学式に近い日を選んで京大医学部の新入生に early exposure としての講義を行っている。3年前からは「生命誕生からChatGPT38億年」というタイトルで、生成AIがDNAと自然言語の世界を統合しつつある今を伝え、新しい未来に彼らがコミットするよう励ましている。いつもある程度の反応は感じているが、昨年講義直後に質問に来た学生さんから「チョムスキーの生成文法は間違っているのでしょうか?」と質問され、講義をして良かったと心底感じた。というのも、生成文法が統語規制として最初から必要だという考えは、我々の脳がAIと同じように教師なしの学習で確率的共起を可能にする言語空間を形成できるとすると間違っていることになる。この点を短い講義の間に感じた入学したばかりの若者がいることは、新しい人間の教育こそが我が国の生きる道である事を確信させる。
大規模言語モデルと同じように我々が言語を処理しているとすると考えると、何故人間だけが言語を話すのかについて答えるのが難しくなる。即ち、脳に統語力が生まれたから言語が出来たと考えるとわかったような気になるが、ニューラルネットを学習させれば確率共起的言語空間を形成できるなら、サルでも成長期に言語を学習することで言語を獲得できていいはずだ。
この考えをサポートするのがある程度の文を理解し300以上のシンボルを獲得したボノボ Kanzi で、他の言語を教えられたチンパンジーやボノボとの最も大きな違いは、言葉を学習していた母親の訓練の場にいることで、幼児期から言語インプットがあったことが挙げられる。
この Kanzi に、実在しない物があたかも存在するように振る舞って遊ぶ、即ち反実仮想能力あるかどうかを調べた論文が英国スコットランドのセントアンドリュース大学から2月5日号の Science に発表された。タイトルは「Evidence for representation of pretend objects by Kanzi, a language-trained bonobo(実在しないが、あたかも実在するように想像する物を表象することが、言語を学習したボノボ Kanji には出来る)」だ。
この研究は言語に長けた Kanzi でないと出来ない。課題は簡単で、二つの透明なコップを机に置き、それにやはり空のピッチャーから水を注ぐふりをする。この時、Kanzi Look と言葉で指令を行う。その後、もう一度コップからピッチャーに水を戻すジェスチャーを見せた後、Kanzi どちらを選ぶ?と聞いて、実際には水がなくても、ピッチャーに戻すふりをしなかったコップに水があるように振る舞うかを調べた。結果は100%ではないが、チャンス以上の確率で、実在しない物をあたかも実在するように振る舞うゲームを遊べることを証明した。
同じような実験を、かごにブルーベリーを入れるという反実仮想実験を行い、同じようにこの能力を証明している。他にも、実験結果が本当に実在しない物を実在するように表象できているのか確かめる実験を行い、少なくとも Kanzi にはこの能力があると結論している。
結果は以上で、褒美を与えたり条件付けを行わなくても、ある程度言葉でコミュニケーションできる Kanzi でないと出来ない実験だが、この結果は様々なことを考えさせる。
言語誕生の最も大きなインパクトは、実在しないことを語れるようになったことだ。その結果、実在しない未来を語り、見たこともない世界を語る宗教もうまれた。科学も同じで、今実在しない物を求める作業といえる。ただ、これが言葉の誕生によるのか、逆に実在しないものを表象する能力が先に発生して言葉が可能になったのか、決めるのは難しい。Kanzi を用いた実験でも、Kanzi だけが言葉を獲得したサルだと考えると、この実験だけでは言語が先か、反実仮想能力が先かは決められない。いずれにせよ、深層ニューラルネットで確率共起的言語空間形成が可能なので、これが出来ない学習条件を考えていくことで、この問題に答えが出るかもしれない。
しかし Kanzi も今や44歳だ。新しい Kanzi は育っているのだろうか?
追伸、Kanzi は昨年3月に死亡しているようです。これが最後の論文でしょうか。
2026年2月10日
パーキンソン病 (PD) の運動障害は運動の調節に関わる基底核回路の異常がドパミン欠乏により起こると考えられており、ドパミン補充療法に加え、症状に応じて視床下核や淡蒼球内節等に電極を挿入し、深部刺激を行うことでこの回路を抑制する治療が行われている。
今日紹介する北京大学を中心とするチームからの論文は、深部刺激治療の様々な困難を解決する目的で、これまで基底核回路を特定するために行われてきた拡散テンソルイメージングの代わりに、安静時の機能的MRIによる結合性検査を用いてPD回路を検討し直し、身体と認知を統合する皮質-皮質下SCAN回路の結合亢進がPD運動異常の原因である新しい可能性を提案し、深部刺激や経頭蓋磁場刺激の標的を定義し直した研究で、2月4日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Parkinson’s disease as a somato-cognitive action network disorder(パーキンソン病は身体と認知機能をつなぐネットワークの異常)」だ。
AASJのメンバーでPD患者でもある中井さんが動画投稿しているように(https://www.youtube.com/watch?v=WbG0vW1d1g0 ) PD運動異常は運動から気をそらすことで改善する。このよく知られた事実から、PDを身体と認知機能をつないでいる皮質-皮質下回路(SCAN回路)の異常と考えたらどうかと着想し、安静時の機能的MRIで脳領域間の結合性を推定する方法でPD患者さんを調べ、SCANの結合性が過剰に上昇しているのがPDで広く認められることを発見している。
ではこれまでの深部刺激の結果をどう位置づければいいのか。そこで深部刺激が効果を示した患者さんで電極が挿入された視床下核が運動野ではなくSCANと結合しており、これを電極刺激で抑えていることがわかった。事実、深部刺激をオンにするとSCANとの結合性が低下することも確認している。また、ドパミン治療でもSCANの過剰結合性を抑えることも明らかにし、PDでの症状改善はSCANを変化させることだと結論している。
さらに、震えの治療としてマイクロウェーブで経頭蓋的に視床中間複素区画を焼く治療を受けた患者さんを調べ治し、焼却場所がSCANのホットスポットに近いほど効果があったことを明らかにしている。
以上の結果から、PDの機能的な最も重要な指標はSCANの過剰結合性であると結論し、この場所を経頭蓋的磁場照射で抑制できないか36人の患者さんを用いて調べ、SCANを標的にした群でだけ1-2週間、症状の持続的改善が見られることを明らかにしている。
結果は以上で、これまでの通説を覆すというより、新しい観点から捉え直し、皮質-皮質下の身体・認知行動ネットワークを治療標的として登場させたことは、今後のPD治療に撮って重要な進歩だと思う。特に浅い領域を標的にしても回路を抑制できるとすると、機能的治療の適用が拡大すると思う。3月のジャーナルクラブは中国の創薬や臨床研究を取り上げようと思っているが、この論文も中国臨床医学の力を示すいい例だと思う。
2026年2月9日
生命科学の進歩を見ていると、ここまで生きてこられて良かったとつくづく思うが、世界を見渡すと、学生時代に理想とした各民族の尊厳を守り平和で平等な世界を作る方向とは真逆の大国が、小国を理由もなく支配する帝国主義に戻りつつあるのを目の当たりにして、暗澹たる気持ちになる。そんな中でも昨年コスタリカを旅行したとき、全く軍隊を持たない永世中立国を政変の絶えない中米で50年以上維持していると聞いて、その奇跡に驚いた。
今日紹介する米国カリフォルニア工科大学からの論文は、アリに寄生するしか生きられない進化の袋小路に迷い込んだハネカクシの話で、2月5日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Symbiotic entrenchment through ecological Catch-22(生態学的Catch-22状態に落ち込んだ共生進化の袋小路)」だ。
タイトルにある Catch-22 とは、知らなかったので調べると、小説のタイトルから来ている様で、にっちもさっちもいかない状況を表す言葉らしい。米国は別としてほとんど知られていない言葉だと想像するが、知らないということでキャッチされてしまう、これも一つのジレンマに思える。
研究の対象はハネカクシとそれが共生しているベルベットツリーアリで、共生すると言ってもハネカクシはアリの半分の大きさがあり、コバンザメのように身体に乗ってしまって、巣の中まで入って餌にありつくという不思議な共生関係だ。数あるハネカクシの種の中で、3種類がこの共生関係を成立させており、それぞれ独立に進化してきたことがゲノムからわかる。
このような共生関係が成立する一つの理由は、アリが他の種を区別するクチクラに存在する一種の脂質フェロモンが、この3種のハネカクシとホストのアリでよく似ており、結果アリの攻撃を受けなくなることによると、それぞれの種の脂質フェロモン (CHC) の分析から明らかになった。
ハネカクシとアリのクチクラに存在するCHCの分析から、Sceptobius と言う種だけは、アリのCHCを使っていることがわかった。即ちCHCを自分で合成しないで、アリに乗っかって身体をこすりつけてCHCを獲得している。とは言え、Sceptobius にもCHCを合成する細胞が存在し、特有のCHCを合成する遺伝子システムを全て備えている。また、CHCはフェロモンとしてだけでなく、クチクラを乾燥から守るために必須で、ふ化後アリとは独立して生存している幼虫、さなぎ、そして羽化したあとは間は独自のCHCを合成して乾燥から身体を守っている。その後アリと共生したときは、ほとんどがアリ由来のCHCに変化する。
即ち、ふ化後一定期間後にアリと共生が始まる時、Sceptobius は自分でCHCを合成するのをやめ、完全にアリに依存するようになっている。実際遺伝子発現を調べると、CHC合成に必要な多くの遺伝子の発現が抑制されていることが明らかになった。
この結果、フェロモンレベルで完全にアリと同化が可能になったが、自分でCHC合成が出来ないため、アリから離れると Sceptobius は乾燥で死ぬこともわかった。
以上、フェロモンとして働くCHCがクチクラの乾燥を防ぐ機能を保つため、ホストに完全同化するために獲得した「自分の臭いを消す」ステルス戦略のを獲得した結果、独立して生きる可能性を完全に失った袋小路に迷い込んだという話だ。確かに面白い話だが、現在の世界の状況を考えると、面白いでは終わらない、寂しい話に思える。
2026年2月8日
我々人間の抗体分子は、H鎖だけでも50種類のV遺伝子、30種類のD遺伝子、6種類のJ遺伝子が存在し、それだけでも1万種類の異なるレパートリーが出来るが、VDJが集まるときに必ず起こる変異や更には増殖時の点突然変異の蓄積により、H鎖だけでも膨大な多様化が起こっている。実際、同じ抗原に対する抗体も、反応する人が異なると全く異なっているのが普通で、これにより我々は外界のほぼ無数とも言える抗原に対応できている。
ところが単一細胞レベルのDNA配列決定が簡単になり、ほとんどのSLEの患者さんの自己抗体が発生初期に特に頻度の高いVH4-34と呼ばれるVH遺伝子を使っていること明らかになった。その後、難治性のBリンパ球性の腫瘍でもVH4-34を使っている頻度が高いことがわかってきた。これらの結果から、VH4-34を認識する抗体がSLEの診断に使われるだけでなく、自己反応性抗体除去治療に使う試みも進んでいる。
今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、VH4-34に対する抗体をCAR-Tに使って、この遺伝子を発現するBリンパ性腫瘍やSLEを治療するための前臨床研究で、2月4日号の Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Chimeric antigen receptor T cells against the IGHV4-34 B cell receptor specifically eliminate neoplastic and autoimmune B cells(IGHV4-34B細胞受容体に対するCAR-Tは腫瘍性及び自己免疫性B細胞を特異的に除去できる)」だ。
現在B細胞性腫瘍やSLE治療に使われるCAR-TはB細胞が共通に発現するCD19を標的にすることが多い。ただ、CD19を標的にしたときは正常のB細胞も除去されるため、治療を受けた患者さんの10%が感染症で亡くなる。さらに、CD19はB細胞の生存にとって必要性が低いため、かなりの割合でCD19を発現しなくなった腫瘍が現れ、再発につながってしまう。
この研究では、CD19の代わりに多くのBリンパ性腫瘍で発現しているVH4-34を標的にすることで、より腫瘍特異的なCAR-T治療を開発できるのではと考えた。即ち、VH4-34は正常のB細胞にはほとんど発現がなく、しかも細胞表面上の免疫グロブリンは正常、異常B細胞を問わず、その生存に必須であることがわかっている。従って、CD19を標的にするCAR-T治療のほとんどの問題を解決できると考えた。
まず、多くのBリンパ性腫瘍の患者さんの腫瘍発現VHを調べると半分以上がVH4-34で、全ての患者さんに対応できなくても、十分意味があることを確認している。一方で、正常B細胞では頻度が5%程度だ。
次に、VH4-34を認識する9G4モノクローナル抗体のVHとVLを組み合わせたCAR-T作成を試みている。例えばVHとVLを結合させるヒンジをIgG4から転用すると、それ自身でT細胞を刺激することや、細胞外ドメインが膜から離れているとキラー活性が出にくいなど、様々な検討を重ねた後、CD19に対するCAR-Tに匹敵する強さを持つVH4-34に対するCAR-T開発に成功している。
このCAR-TをCD-19のCAR-Tと比べると、Bリンパ性腫瘍を強く抑制するだけでなく、CD-19を標的にするときの再発問題が解決すること、またほとんどの正常B細胞はそのまま機能できることを明らかにする。もちろんCV4-34でも変異を重ねればキラーから逃れる心配はあるが、そのような変異が起こりにくいことも確認している。
さらに、SLEの患者さんのB細胞からVH4-34を選択的に除去できること、またCAR-Tの作用を邪魔するVH4-34を持つ血中抗体をフォレーシスで除くことで、自己抗体を分泌するB細胞を除去する効率が高まることを試験管内の実験系で行っている。
結果は以上で、まだ臨床段階ではないが、SLEの治療と、多くのB細胞性腫瘍の治療を前進させる大きな一歩だと思う。個人的には、免疫グロブリンのレパートリー形成を研究していた留学時代を思い出した。
2026年2月7日
多くのガンで、K-ras遺伝子に発ガン性の変異が認められることは、今や一般にも周知されている。発ガンに関わる最も多い変異は12番目のアミノ酸(グリシン)が他のアミノ酸に変化する変異で、システィン(G12C変異)、アスパラギン酸(G12D変異)は中でも頻度が高い。ただこの論文を読むまで、両者の生物活性に大きな違いがあるとは考えたことがなかった。
今日紹介するテキサス・サウスウェスタン医科大学からの論文は、G12CとG12Dを同じマウス肺ガン誘導実験システムで比べ、両者に大きな違いがあることを示すとともに、K-ras阻害剤の使用は免疫チェックポイント治療と組み合わせる必要があることを強く推薦した研究で、2月4日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Kras G12C– and G12D–driven lung cancers differ in oncogenic potency, immunogenicity, and relapse after Kras inhibition in mouse models(K-ras G12CとG12Dは、マウスモデルを用いた肺ガン誘導能力、免疫誘導能力、そして阻害剤使用後の再発に大きな違いがある)」だ。
肺上皮でそれぞれの変異を誘導するシステムで両者を比べると、p53変異の有無に関わらずK12D変異による肺ガンは増殖力が高く悪性度が高い。データを目の当たりにすると、これほど違うのかと驚く。しかし組織学的には両者は同じタイプで、増殖力だけが異なる。これを確かめるために、線維芽細胞に導入して増殖を比べるとG12Dの方が1.5倍ほど増殖が速く、K-rasのアクティビティーも高い。これまで多くの実験は、G12Dで行われているが、実験する側も自然にK-ras活性の高い方を選んでいたのかもしれない。
人間でも同じことが言えるのか、肺ガンの発生時期や経過をG12CとG12Dで比べると、G12Dの方が発症年齢が早いことから、おそらく人間でも同じと言える。
面白いのは、生化学的活性とそれによる増殖力だけではない。ガンに対する免疫反応の惹起力も違いがありそうで、実際のガン患者さんの組織に浸潤するキラー細胞やPD-L1の発現などから見ると、G12Cの方が免疫誘導能が高い。このことはマウスモデルでも確認でき、様々な免疫指標遺伝子発現がG12Cガンの組織で高い。
それぞれの変異に対しては、薬剤が開発されている。この研究ではG12Cに対してはMRTX849、G12Dに対してはMRTX1133が使われ、それぞれのガンの増殖を抑制できることを示している。一言加えておくと、MRTX849は既にFDA認可され使われているが、MRTX1133は治験途中で開発が中止されている。ひょっとしたら、G12Dの活性が高すぎて、治験がうまくいかなかったのかもしれない。 実際、マウスモデルで投与実験を行うと、どちらも再発が見られるが、K12DをMRTX1133で治療したときの方が再発が早い。
そこで、MRTX1133をガンに対する免疫の視点を加えて再検討しようと考え、腫瘍を誘導した後薬剤を投与したときに、薬剤を投与しない群より高い免疫が誘導されるか調べている。結果は期待通りで、様々な条件で調べて、MRTX1133はガン細胞の抑制だけでなく、ガン免疫も誘導する。
そこで、チェックポイント治療とMRTX1133投与を同時に行う治療を、それぞれ単独治療と比べ、両方同時に行うことでガンを長期に抑制できることを示している。この時、ガンが多様なほど免疫のレパートリーも高まり、ガン抑制効果が長続きする。
結果は以上で、なんと言ってもG12CとG12Dでこれほど大きなK-ras活性及び発ガン能力に差が見られたことには驚いた。そして、K-ras変異の標的治療が同時にガン免疫を増強する効果があるので、これを利用することで、標的薬単独治療の泣き所だった再発問題を大きく改善できる可能性も示された。そして、治験を行うとき、G12CとG12Dに対する薬剤は、違った視点で評価する必要があることもわかった。ひょっとしたらMTRX1133も薬剤として復活できるかもしれない。
2026年2月6日
今日の午後7時から「最新のアルツハイマー病治療開発論文紹介」と題して、ジャーナルクラブを開催する。このテーマを選んだのは、以下に示すベルギーHasselt大学からの総説論文を紹介したいと思ったからだ。
この総説では臨床段階に入ったAβ及びTauに対する抗体治療の現状がよくわかるように書かれており、これを元にTauとアルツハイマー病 (AD) との関係を解説した上で新しい治療標的についても紹介しようと考えている。
このように修飾を受け凝集したTauによる神経変性 (=Taunopathy) は、次のAD治療の標的になっているが、ADだけでなく、進行性核上性麻痺 (PSP) 、大脳皮質基底核変性症 (CBD) 、慢性外傷性脳症 (CTE) 、そしてピック病などでも異常Tauの蓄積が認められることから、Taunopathyと位置づけられている。いずれもADと比べると進行が早く、中脳、基底核、運動野を早くから巻き込むため、認知症にとどまらず、運動障害、嚥下障害など生命機能に関わる症状を示す。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、以上のTaunopathyに家族性ADを加えた6疾患の患者さんの脳からTauを分離し、タンパク質の修飾状態を詳しく調べ、それぞれの疾患でTauの修飾状態が異なっていることを示した研究で、2月5日号の Cell に掲載されている。タイトルは「Molecular features of human pathological tau distinguish tauopathy-associated dementias(ヒトの異常Tauの分子様態はtaunopathy関連痴呆を区別する)」だ。
Tau分子は、まずスプライシングの違いでエクソン10の有無、次にタンパク質の切断される場所でさらにリン酸化、メチル化、アセチル化、シトルリン化の有無で詳しく分類することができる。この研究では145カ所の切断部位、195カ所の修飾部位を特定し、この分布を各疾患で比べている。
例えば202番目のセリンのように全ての疾患でリン酸化されている修飾もあるが、それぞれの疾患で修飾状態が全く異なるというのがこの研究の結論で、修飾部位と疾患を学習させたモデルを用いると、ほぼ全ての疾患をTau分子の就職状態から分類することができる。
まだ個々の修飾と病気との関係を理解で来ていないため、この研究も現象論で終わらざるを得ない。しかし、症状や病変部位の異なるそれぞれの疾患を決めているのがもしこれら修飾の違いだとしたら、Taunopathy研究領域は大きく変貌すると思う。時間がかかっても、それぞれの修飾と病気の相関がわかると、病気だけでなく、影響を受ける神経細胞自体についても理解が進む。その意味で、極めて重要な研究だと思う。今日の勉強会でも紹介する予定だ。
2026年2月5日
腸内細菌叢の最近の研究動向を見ていると、細菌叢操作開発研究が大きなトレンドになっている気がする。これまでの操作というと、いわゆるプロバイオとよばれる自然から分離したビフィズス菌や乳酸菌などを摂取する経験的方法が中心だった。従って、細菌性下痢の治療にヨーグルトが処方されることはない。これに対して現在進んでいる細菌叢操作は、遺伝子改変した細菌を摂取させる、あるいは腸内の特定の細菌を狙って腸内で遺伝子操作する方法の開発で、導入する遺伝子により目的と効果を調整する、いわゆる合成生物学領域になる。
今日紹介するカナダ British Columbia大学からの論文は、腸内細菌叢の中でも数の多い Bacteroides を遺伝子操作して、浸透圧を感知する遺伝子発現系を開発した研究で、1月28日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「A Bacteroides synthetic biology toolkit to build an in vivo malabsorption biosensor(腸での吸収不全のバイオセンサー目的のための Bacteroides 合成生物学ツールキット)」だ。
遺伝子発現回路を組み上げて思い通りの性能を持たせるためには、その生物での遺伝子発現についての深い知識とともに可能な回路を設計して試すことをいとわないオタク的性格が必要だと思う。この研究のほとんどは凝った回路設計に費やされている。
目的はタイトルにあるように吸収不全を早期に診断するバクテリアの開発だ。これまで遺伝子操作するバクテリアとしては、研究の進んだ大腸菌などが使われてきたが、接種後腸内に居つく確率が低いのが問題だった。そこで、最近操作に必要な様々なツールが揃ってきた Bacteroides をこの研究では操作対象にしている。実験を見ていると遺伝子導入から改変までかなり操作環境が整っていると言え、利用が拡大すると予想できる。
次に、吸収不全を診断するために、これによって起こる浸透圧変化を特異的に検出できる遺伝子発現回路を開発している。まずプロモーターがオンになると、標識遺伝子発現を抑制する回路がオンになるという二重回路を用いて、多くの合成プロモーターをスクリーニングし、安定で強いプロモータライブラリーを作成している。この研究ではその中の一つを用いているが、今後はツールとして利用できるライブラリーになる。
次はプロモータアッセー系を用いて、Bacteroides の持つストレス反応性のプロモータの中から、浸透圧に反応するプロモーターを試験管内培養を用いて選び出している。そしてこの中から、無菌マウスに摂取させる、その後PEGを摂取させて水を枯渇させ浸透圧変化を起こすマウス実験系で、腸内での浸透圧変化に反応するプロモーターを選んでいる。
ここからが凝り性の面目躍如といえる実験が続き、まずこの回路を Bacteroides のどの部分に入れると安定に性能を発揮するかを、相同組み換えで様々なゲノム領域に導入して調べている。バクテリアでは哺乳動物のような領域特異性はあまりないと思っていたが、実際には結構変化があり、この検討の重要性がわかる。
最後に、浸透圧への感度を上げるために、プロモーターが活性化されて抑制因子が発現したとき、この作用を競合する部位を同じ回路に組み込むことで、最終的に浸透圧の変化に正確で高いダイナミックレンジで可逆的に反応する遺伝子発現回路を完成させている。
最後にこの回路で蛍光タンパク質が発現する Bacteroides を、既に細菌叢が存在するマウスに摂取させ、急な浸透圧変化が腸内で起こったとき、それを検出できるか調べ、550mOsm / kgから650mOsm / kgへの変化により蛍光強度が50倍近く上昇するセンサーが完成したことを示している。また、腸内に摂取させるPEGの量を1%−7%へと変化させるときも、発現が濃度に比例して上昇する感度の高いセンサーであることを示している。
以上が結果で、現在のところGFP発現しか見ていないが、今後この回路をより治療的な遺伝子発現に用いることで、腸内環境に応じて様々な分子が分泌して細菌叢操作が可能になるのではと期待する。