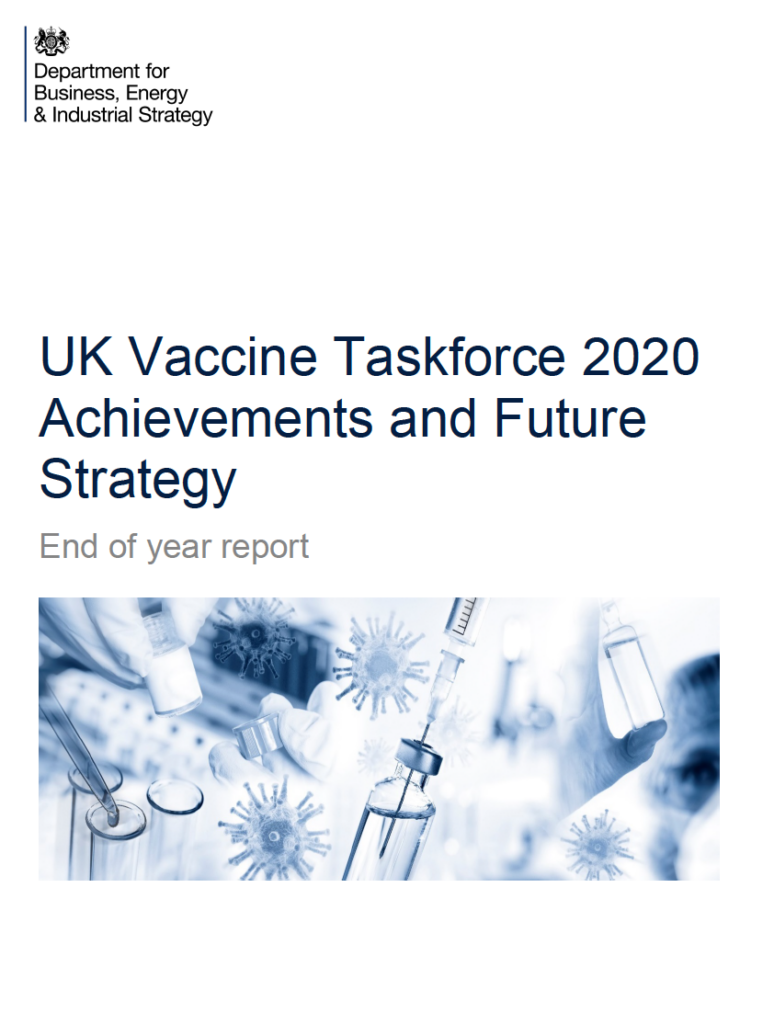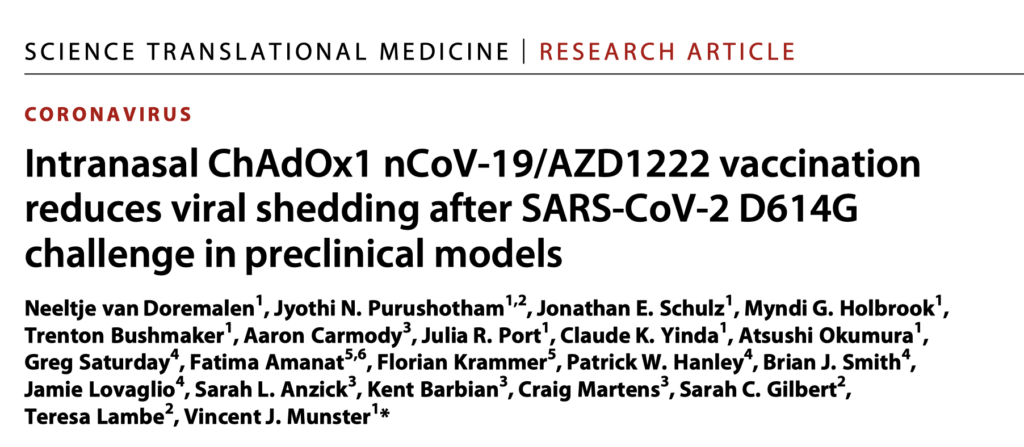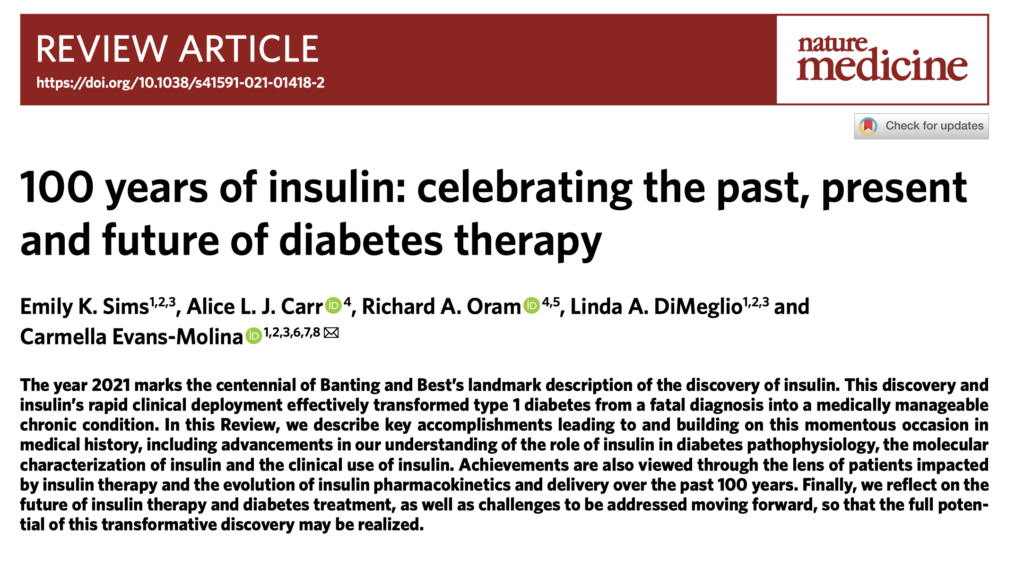2021年8月20日
AASJの事務所は自宅から数分の距離だが、三宮駅の近くに位置している。行き帰り、いそがしい町の人通りを毎日目にするが、いつも通りの平和な風景だ。ところが帰宅した後、テレビで報道される自宅療養(というより自宅放置)の悲劇の切迫感を聞くと、町の風景とのギャップは大きい。どちらが現実かと戸惑うが、自宅放置感染者が東京で3万人を超えているとすると、大災害に見舞われているという方が現実なのだろう。同じような非日常的な切迫感が我が国全体を覆った3.11を思い返すと、今は難局への協力を訴える政府自体の切迫感も欠けているように思う。せめて、大臣皆が作業着を着て陣頭指揮するぐらいの演出がないと、人の気持ちは変わらない。
このような演出の欠落を見ると、要するに政府に適切にアドバイスする人材がいないのか、適材適所ができていないことを実感する。現在の課題は、法定伝染病としての医療体制が崩壊した現状で、自宅放置者に適切な医療を届けることだ。政府の手持ちはワクチンと、リジェネロンの抗体カクテルだが、もう一つ大事なのは、国民に届けられる有効な新しい介入手段を洗いだし、いち早く調達してくるタスクフォースだろう。
多くの方はすでに読まれたのではと思うが、上のレポートは、英国のワクチンタスクフォースの活動を評価した英国のレポートだ。驚くのは、これを一種の経産省が行っている点で、根拠なしの感覚だが、これも適材適所が根付いている証拠のように思える。
そして何よりも、評価の対象になったワクチンタスクフォースの議長に、バイオ企業のことを知り尽くし、密接な交流を持つ英国のベンチャーキャピタリストKate Bingham(https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Bingham )が選ばれ、その任期の6ヶ月で、英国での数種類のワクチン調達を実現し、最後にその活動を評価まで行って使命を終えている点だ。いずれにせよ、ただ科学知識があるというのではなく、世界中の業界に顔の利く人材を選んだ適材適所は素晴らしい。
ともかく災害に対応するにはその場しのぎだけでなく、近い未来も想定した必要な課題をリストして、それを半年単位で解決する冷静なタスクフォースが重要になる。今からでも遅くない。素晴らしいタスクフォースができることを期待したい。世界には調達したい多くの技術が存在する。
例えば現在リジェネロンの抗体カクテルに期待が集まっているが、回復患者血清を用いた治療から考えると、抗体による変異株誘導の危険性は常に考える必要がある。その意味で、変異株はもとより、ほとんどのコロナウイルスに効果があるモノクローナル抗体の開発が進んでおり、変異出現の選択圧になる危険は少ない(https://aasj.jp/news/watch/17067 )。そのうちの一つGSKのsotrovimabは、δ株にも有効で欧州ではすでに認可されている(https://jp.gsk.com/jp/media/press-releases/2021/20210604_gsk-and-vir-biotechnology-announce-sotrovimab/ )。この抗体は、元々新型コロナウイルスではなく、SARSウイルスに対する抗体から分離され、Covid-19にも有効性が確認されており、最初からsarbecovirus全般に効果が期待される。新しい変異株出現も予想して、我が国のタスクフォースがこのような抗体を調達できることを期待する。
うれしいことに、我が国も第3相国際治験に参加している飲み薬の一つにメルクのMolnupiravirがある。感染が確認されたらすぐに服用できる飲み薬で、系列としてはレムデシビルと同じで、ウイルスのRNA合成で取り込まれて、突然変異を多発させ、ウイルス増殖を抑える効果がある。おそらくこれは現状に最もマッチした薬剤で、我が国で治験が行われていることは期待できる。
Molnupiravirが、レムデシビルやアビガンと比べたとき、より期待できることを示す生物学については、8月11日にNature Structural and Molecular Biologyオンライン掲載された、ドイツゲッティンゲンのマックスプランク研究所から発表された論文を読むとよくわかる。
まず経口投与可能で、日本メルクも発表しているように、感染がわかった時点で自宅で5日服用すればよい。服用すると、ウイルスのRNA合成酵素により認識され、CTPやUTPの代わりにウイルスRNAに取り込まれる。そして、MTPを取り込んだ鋳型は今度は、GやAともペアリングしてしまうため、どんどん突然変異の数が増え、翻訳レベル、および複製レベルでウイルスの活動を抑え込むというメカニズムだ。
MTPの優れている点は、取り込まれたとき、RNA合成酵素システムを止めないことで、Mを取り込んだRNAが完成して、指数的に異常RNAを増やしていく。この点で、RNA合成酵素が止まってしまうレムデシビルやアビガンと決定的に異なり、耐性もできにくいと想像できる。治験結果が待ち遠しいし、規制当局も今から情報を集めて、迅速な認可が可能になるよう準備してほしいものだ。
これに少し遅れて、メインプロテアーゼ阻害剤がファイザー、塩野義により開発され、治験が進んでいる。おそらく中国からも出てくる(https://aasj.jp/news/watch/15255 )。国産にこだわらず、可能性はすべて我が国でも治験を進める必要がある。実際、自宅放置者が増加している今こそ、我が国は治験の中心地になれるのではないだろうか。
最後に、ワクチン3回目接種の話が出ているが、これを考えるとき面白い論文がオックスフォード大学から8月18日号のScience Translational Medicineに掲載された。
これはすべて動物実験の話だが、しかし時間スケールとしてはこれから半年を視野に入れるタスクフォースの課題にもなり得る。
研究は、今使われているアストラゼネカのワクチンを鼻から注入することで、筋肉注射より強い肺炎予防効果が得られることを示している。ともかく一回投与で、今拡大中の肺炎を抑えることは可能かもしれない。特に、アストラゼネカワクチンは、我が国で行き場を探している。公衆衛生学的に重要なのは、鼻から免役することで、気道からのウイルス分泌を強く抑えることができる点で、新しい変異株への効果は不明だが、考慮に値する。同じことがmRNA ワクチンでできるかどうかわからないが、個人的感触だがあらゆる細胞に感染できるアデノウイルスの方が優れているように思う。
ほかにもこの一週間だけで、新型コロナの明るいニュースは数多く発表されている。是非そのような中から国民にいち早く提供できる技術を調達するタスクフォースが我が国にもできるのを期待したい。
最後に、ワクチン3回目に一言。現在のmRNAワクチンはスパイクpre-fusion form に蓋をする抗体を誘導するので、比較的変異体にも対応はできる。また、T 細胞の反応は将来の変異体もカバーできる。ただ、変異体の出現が起こる以上、同じ配列で対応するのではなく、ワクチン認可の際、臨機応変に変異体の配列に変えた核酸ワクチンを迅速に認可する仕組みを用意しておくのも、重要な課題だと思う。
2021年8月19日
21世紀に入って、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤は様々なガン治療に使われ始めている。個人的には、多くの分子がHDACの対象になること、および多数のHDACが存在するため、完全に機能を押さえることが難しいことから、効果に疑問を持ってはいるが、ガンによっては高い効果を示すケースも示されてきた。例えば皮膚に浸潤するT細胞リンパ腫(CTCL)では3割の患者さんが一度は完全寛解を達成する。
最初これらのHDAC阻害剤はガンの増殖進展に関わる分子のエピジェネティックな調節機構を介して効果を示すと考えられてきたが、免疫チェックポイント治療が普及し、HDAC阻害剤がその効果を高めることが知られるようになり、ガンだけでなく、ガン周囲組織や免疫系のエピジェネティックスに作用することもわかってきた。この結果、現在HDAC 阻害剤と抗PD−1抗体などを組み合わせた臨床治験が進んでおり、チェックポイント治療のパートナーとして定着する予感がする。
今日紹介するノースカロライナ大学からの論文はマウス膀胱ガンをモデルに、HDAC3 阻害剤がガンネオ抗原の発現を高め、ガン免疫を高める可能性を示した研究で、現在進むチェックポイント治療とHDAC 阻害剤の治験を側面から援護する研究だ。タイトルは「Entinostat induces antitumor immune responses through immune editing of tumor neoantigens(Entinostatは腫瘍ネオ抗原を編集することでガン免疫反応を誘導する)」で、8月16日号のThe Journal of Clinical Investigationに掲載された。
まずマウスモデルで、HDAC3阻害剤entinostatが、免疫系が存在する場合のみガン抑制効果を持つこと、またentinostat投与マウスガン組織ではCD8キラー細胞が上昇していることを確認した後、この腫瘍が発現している922種類のガンネオ抗原がentinostat投与でどう変化するか調べている。
試験管内でentinostatを処理すると、期待通りガンのネオ抗原の発現は高まる。一方、腫瘍を移植した後entinostatを処理した腫瘍では、逆にガンのネオ抗原の発現が強く抑制されている。すなわち、ネオ抗原を発現したガン細胞がキラーT細胞により除去されていることが示唆されている。これを裏付けるように、試験管内でentinostat処理したガン細胞は、よりキラーT細胞に感受性を示す。またにガンに浸潤するT細胞でいくつかのネオ抗原特異的T細胞の数を調べ、確かにネオ抗原特異的免疫反応が高まっていることを確認している。
以上の結果に基づき、最後にentinostatとPD-1抗体を組み合わせたガン治療実験を行い、チェックポイント治療を組み合わせることで完全にガン細胞を除去する確率が大幅に高まることを示している。
以上が結果で、膀胱ガンでもHDAC阻害剤とチェックポイント治療の組み合わせの治験が急速に進む予感がする。長く期待されてきたガンのHDAC阻害剤治療も新しい衣を着て大きく進展すると期待している。
2021年8月18日
21世紀は栄養学の世紀になると予想している。というのも、人間の栄養学を変える様々なテクノロジーが開発され、また栄養学的データベースも急速に整備が進み始めている。これは、ゲノムやエピゲノムと言った生物学的指標だけではない。例えば、スマフォやウエアラブルツールを使った大規模データ取得、さらには、安全なアイソトープを用いた代謝の測定法など、多面的な技術革新が進んだ結果だ。
今日紹介するデューク大学を始め、我が国の栄養研や筑波大学も参加した国際コンソーシアムからの論文は、6421人という大規模な数の人間のエネルギー消費量を測ったデータベース構築の研究で8月13日号のScienceに掲載された。タイトルはズバリ「Daily energy expenditure through the human life course(人間の一生にわたる毎日のエネルギー消費量)」だ。
この研究の目的はただただエネルギー代謝を新生児から高齢者まで計測して、人間の一生での変化を集めたデータベースを構築するというものだ。このために、International Doubly Labelled Water Databaseが設立され、2020年、初期の目標にしていた6700人近くのデータを集めることに成功し、これをまとめたのが今回の論文だ。
エネルギー消費というと、完全に閉鎖系で活動して酸素や炭酸ガスの出入りを調べるヒューマンカロリメトリーを思い出すが、doubly labeled water というのは全く初耳で、興味を惹かれ、なるほどと感心して紹介することにした。
できないことはないが、6000人以上の様々な世代のエネルギー代謝をヒューマンカロリメトリー室につれてきて測定するのは簡単ではない。それを解決するのがこのdoubly labeled water法で、まずこれから説明しよう。
この方法は、被験者に一定量の重水素からできた水と、酸素18同位元素からできた水を投与し、この水素同位元素と、酸素同位元素の体内での濃度を調べることで、代謝量を測定する方法だ。最初、同位元素は体内のウォータープール(WP)に溶け込んでいくので、体液のアイソトープの濃度が上昇していく。このときの上昇速度からWPの量を測定することができるが、さらに水の分布から体脂肪とそれ以外のボディーマスを計算することができる。
さて、平衡状態に達した後、同位元素は体外へ排出されていくが、このとき水素同位元素は水とともに排出されるが、酸素同位元素は代謝による二酸化炭素産生によっても排出される。この排出のされ方の違いから、エネルギー代謝を計算できるという原理だ。昨日のマンモスの行動範囲測定や、今日の代謝測定は、すべて正確に同位元素の濃度を測定できるようになった結果だが、そのおかげで6000人を超える規模のエネルギー代謝データベースが完成した。
結論としては、
エネルギー代謝は脂肪を除いたボディーマスと相関する。 新生時期、脳を含め急速にボディーマスが成長する段階では、エネルギー代謝が上昇し、大体5歳ぐらいでピークを迎え、20歳代まで急速に低下する。 20歳代から60歳代までは、エネルギー代謝は一定に維持されている。 65歳を過ぎると、緩やかにではあるがエネルギー代謝は低下を始める。これは、脂肪を除いたボディーマスの低下に一致する。 妊娠中は大きなボディーマスの変化が起こるはずだが、エネルギー代謝は一定に保たれる。 要するに、高齢になると様々な器官が萎縮し、エネルギー代謝が落ちるという結果だが、例えばこれを無理に変更させた方がいいのか、それとも歳相応に生活した方がいいのかなど、今後の問題になるだろう。筋肉だけ増やせばいいという話ではないはずだ。
今後も栄養学についての論文は積極的に紹介するつもりだ。
人規模のデータから解析する(8月13日号Science掲載論文)
2021年8月17日
9月に入ると、ケニアのセレンゲティ国立公園では、ヌーやシマウマの川渡りが見られる季節に入る。私たちも4年前、この川渡りを見に出かけた。写真やビデオで紹介される川渡りは、まさに渡っている時の映像が示されているので、渡りのサイトに行けば、そのまま川渡りが見られるのかと思っていた。ところが、実際は全く想像したのとは異なり、ヌーやシマウマの大群が岸までやってきているのに、なかなか渡り始めず、あたかも決断できない政治家といった感じで、渡るかと思うと後ずさりして、川を見つめる繰り返しを、なんと4時間近く見る羽目になった。それでも必ず渡りますというガイドの言葉を信じてじっと待っていると、バカなのか、あるいは自己犠牲をいとわない高貴な性質を持っているのか、一匹のヌーが川に飛び込んだ。案の定このヌーは渡る途中でワニの犠牲になるのだが、このヌーに導かれて岸で待っていたすべての動物が川に飛び込むスペクタクルを見ることができた。要するに渡るときに、ワニの危険が待っていることを知っているのだ。それでも、最終的に新しい場所に移動するのは、食物を求めてのことなのだろう。
現存の草食動物から考えて、もっと大きなマンモスは食物を求めて当然広い範囲を移動すると想像されるが、化石になった動物の分布を調べることはできても、個々の動物の移動について調べるのは難しい。これに対し、今日紹介するアラスカ大学からの論文は、マンモスの牙から得られる窒素、酸素、炭素、およびストロンチウムの同位元素からマンモスの生涯とその移動範囲を調べようとした研究で、8月13日号のScienceに掲載された。タイトルは「北極圏のマンモスの生涯と移動範囲」」だ。
ゾウの牙は年齢とともに少しづつ伸びていくので、根元から先まで、そのゾウが生きていた環境が記録されている。タンパク質としてはコラージェンはDNAより安定で、そのときの新陳代謝を反映できる。さらに、骨にはストロンチウムが取り込まれるが、ストロンチウム87とストロンチウム86の比は、生息していた土壌を反映することもわかっている。すなわち、ストロンチウムの同位元素と、アラスカ各地のストロンチウム同位元素の分布を重ね合わせることで、あるときマンモスがどこに生息したかがわかる。
実はこの方法は、歴史学的にも用いられており、例えば英国のリチャード三世の生涯についての解析に用いられているのを紹介したことがある(https://aasj.jp/news/watch/2055 )ので、是非参照してほしい。
さて結論を急ぐと、今回対象になったアラスカ生息のマンモスは、遺伝子解析から雄であることがわかっている。炭素や窒素同位元素の量の変化から、28歳の冬、飢えで死亡したと考えられる。
移動範囲から、大体3ステージに分けることができ、新生児期には親と一緒に大体250kmぐらいの範囲の縄張りを、冬は南、夏は北と移動する。ただ、成人になると、おそらく生殖機会を求めて、これまでとは全く異なる範囲の移動を行い、その後は同じように大体250−300kmの範囲で生活をすることがわかった。基本的には現在の象とあまり変わることはないようだが、冬の飢えは繰り返されている。
一匹の個体について、これだけのことがわかるというのが研究のポイントだが、冬に飢えて死んでいたなら、温暖化でどうして生き残れなかったのかという疑問がわく。これに対し、温暖化の結果、草原ではなく森林が優位になることで、結局マンモスが食べる植物も消失したのではと考えているようだが、古生物学が動物の化石だけではなく、その地域の植物も含めた生態学知識が必要なことがよくわかった。
2021年8月16日
現在のところ、避妊目的でコンドームを避けたいなら、エストロジェンとプロゲストロンが配合された経口避妊薬が利用可能だが、乳ガンのリスクを高めたり、うつ病を誘導したりする可能性を知ると、服用を躊躇する人も多い。
今日紹介するノースカロライナ大学からの論文は、精子を凝集させてしまう抗体避妊薬が副作用のない避妊を実現する可能性を示す研究で8月11日号Science Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Engineering sperm-binding IgG antibodies for the development of an effective nonhormonal female contraception(精子結合性IgG抗体を分子操作してホルモンに依存しない有効な避妊薬を開発する)」だ。
タイトルを読んで、なるほど抗体で精子の機能を抑制するのかと考えて読み始めたが、実際にはそんな簡単な話ではなかった。将来はわからないが、現在のところ、例えば、結合して即座に精子の運動を止めるといった抗体は見つかっていない。一方、精子に対する抗体が原因の不妊症についての研究などから、抗体によって精子が凝集して、その結果粘膜を通る運動ができなくなることが、抗精子抗体の作用であることがわかっていた。
この研究では、精子が発現するCD52に対するIgG抗体の精子凝集能力を高めるために、抗原結合領域(Fab)の数を順番に増やし、IgM並の10個の抗原結合活性を持つ抗体を作成している。これらを元のIgGと比較すると、精子凝集能が10-16倍増加し、また30秒以内に鞭毛運動は見られるものの、凝集の結果、精子が運動できなくなることを示している。このように、IgG抗体でも、操作を加えて抗原結合部位の数を何倍も増やして使えることを示したのがこの研究のハイライトだ。
capacitationと呼ばれる精子ヘッドを覆う分子を外して受精能力を獲得させた精子でも同様に凝集し粘膜で中でトラップされてしまうことを示し、すべての精子に対応できることが確認されている。
最後に人間の精子を、抗体で前処置した羊の子宮に注入したときに、抗体により凝集できるかを、前臨床実験として行い、期待通り98%近くの精子を凝集し粘膜内にトラップできることを示している。
結果は以上で、今後卵巣摘出した女性のボランティアなどの参加を得て、研究が進められるようだ。このようにデザインされた抗体の精子運動抑制効果が高いことを示すのが今回の研究の趣旨だが、元になったIgGについては先行して、ヒトを用いたテストが進んでいるようで、避妊に抗体という選択は実現が近いようだ。
2021年8月15日
SLEは全身の炎症を特徴とするが、以前からこの炎症の主役は、1型インターフェロン(IFN1)の過剰発現であることが示唆されてきた。事実、IFN1を誘導する細胞内DNAの分解や、自然免疫系遺伝子の多型が強くSLEと相関することも知られている。そこで次の課題は、IFN1の過剰発現を誘導するDNAの起源を調べることになるが、中でもミトコンドリア由来のDNAは最も疑わしい刺激ではないかと考えられてきた。
今日紹介するコーネル大学からの論文は、赤血球内に処理できずに残存しているミトコンドリアがマクロファージに取り込まれてIFN1を誘導して、SLEの炎症の強さを左右していることを示した研究で、8月19日号のCellに掲載された。タイトルは「Erythroid mitochondrial retention triggers myeloid-dependent type I interferon in human SLE(SLE患者さんに見られる赤血球内のミトコンドリア残存が白血球を介してIFN1の引き金になる)」。
我々の赤血球からミトコンドリアは完全に除去されている。この研究は最初から、この過程がSLEで障害されていると決めて研究を行い、SLEでは患者さんによっては30%を超える赤血球にミトコンドリアが残存していることを発見する。そして、SLEの重症度とミトコンドリア残存赤血球(MtRBC)の数が完全に相関することを発見した。実際には以前にも報告されていたようだが、その後ほとんど研究が進まなかったというのに逆に驚いてしまうほどの発見だと思う。
この結果は、赤血球に残ったミトコンドリアがマクロファージに取り込まれることでIFN1炎症が高まることがSLEの病態を説明する可能性を示唆している。そこで、SLEでなぜミトコンドリアが赤血球内に残存してしまうのかという問題と、MtRBCがIFN1を誘導するのか、の2つの問題に取り組んでいる。
残念ながらなぜSLEの赤血球でミトコンドリア処理異常が誘導されるのかについては不明のままだが、正常赤血球の成熟過程とSLE赤血球を丹念に調べ。SLE赤血球のミトコンドリア残存を誘導するメカニズムを探索している。赤血球成熟過程では、酸素濃度の上昇に伴いHIF-1αが分解され、その結果HIF1α支配分子の発現が低下、代謝が酸化リン酸化へシフトするが、このとき同時に上昇するミトコンドリアタンパク質のユビキチンによる分解過程が、SLE赤血球分化過程では傷害されていることを明らかにしている。すなわち、何らかの過程でHIF1αの分解が阻害された結果、ユビキチン経路によるミトコンドリア分子の分解が遅れ、ミトコンドリアが赤血球に残存すると結論した。
最後に、MtRBCがIFN1誘導シグナルになるかどうか、MtRBCを抗赤血球抗体と結合させた後、マクロファージに貪食させる実験を行い、MtRBCだけでIFN1が誘導されることを示している。そして、実際の病気との関わりを調べる目的で、患者さんをMtRBC陰性、MtRBC陽性・抗赤血球抗体陰性、そして両方陽性群に分け、IFN反応性遺伝子発現を調べると、MtRBC陽性群はIFN1スコアが高く、また両方陽性群ではさらに上昇していることを示している。
以上が結果で、SLEの病態、特にIFN1による炎症に、赤血球の分化異常と、その結果としてのMtRBC生成が関わるという新しいシナリオを示した、専門家向きだが面白い研究だと思う。
2021年8月14日
プロリン異性化酵素Pin1は リン酸化されたセリン/スレオニンに隣接するプロリンに結合してタンパク質の構造を安定化(時には不安定化)させ、リン酸化タンパク質の様々な機能を調節する役割を持つ分子で、多くのガン細胞で強い発現が見られ、ガンの発生から進展まで、大きな役割を演じていることが知られている。もちろん様々な分子特異的阻害剤が開発されているが、作用が多様なためか、ガン治療にPin1阻害剤を使った研究はまだお目にかかったことはなかった。
今日紹介するハーバード大学からの論文はPin1阻害剤とgemcitabinおよびPD1抗体を組み合わせた治療が、膵臓ガン治療のゲームチェンジャーになる可能性を示した論文で、9月2日号のCellに掲載される。タイトルは「Targeting Pin1 renders pancreatic cancer eradicable by synergizing with immunochemotherapy(Pin1を標的にすると免疫化学療法と相乗して膵臓ガンを完治させる)」と、かなり自信に満ちたタイトルだ。筆頭著者はKoikawaさんで、所属が九大医学部にもなっているので、より期待できるのではと思っている。
おそらくこのグループはPin1の研究を続けているのだと思う。この研究ではマウスモデルではあるが、最も治療困難な膵臓ガン治療を目標に定め、Pin1阻害剤を使える可能性を探っている。そして、比較的低い用量のgemcitabinと、PD-1抗体によるチェックポイント治療にPin1阻害剤を加えたとき、なんと9割近いマウスで膵臓ガンが消失し、その状態が1年以上続くことを発見する。
この効果の元を探っていくと、Pin1阻害剤で膵臓ガン自体の増殖が抑えられることもあるが、なんといっても膵臓ガンの周りの強い線維化を伴う間質が消失し、さらにキラーT細胞の浸潤も強く増強していることがわかった。
すなわちPin1はガンだけでなく、ガンの周囲環境も整える。事実、膵臓ガン組織でPin1はガン細胞および周囲組織で高い発現が見られる。さらに、人間のガンデータベースを調べると、ガンと間質でPin1の発現が高いケースほど予後が悪いことも明らかになった。
後はこの効果の背景にあるメカニズムを丹念に探っている。ガンの間質については、ガンと間質でのサイトカインや炎症物質の分泌を正常化させることが重要なポイントになっている。これに加えて、ガン自体の治療感受性に関わる最も重要な要因として、gemcitabinの取り込みに関わるENT1分子とチェックポイント反応を誘導するPD-L1の発現が、Pin1により抑制されており、阻害剤によりこれらの発現が高まることを発見している。PD-L1の発現が高まること自体は逆に免疫抑制効果があるので、完璧に理解できないが、ENT1の上昇は、低い濃度のgemcitabin治療を可能にしている。
メカニズムの解析は、さらにこれらの分子のリソゾームでの処理過程にまで及んでいるが、割愛する。ただ、これまで膵臓ガンの薬剤感受性を高める因子としてクロロキンが着目されていたのも、オートファジー抑制ではなく、このリソゾーム処理過程に関わる可能性が示されたのは面白い。
最後に、ras/p53変異を導入したマウスで膵臓ガンが発生するのを待って、同じ方法で治療実験を行い、1ヶ月間、3者の組み合わせで治療するだけで、7割のマウスでガンが消失し、その効果が半年続いたことを示している。
ついこの前紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/17240) ,多くの膵臓ガン浸潤T細胞がPD-1ではなくTIGITチェックポイント分子を発現しているという結果を考慮すると、TIGITを加えることで、反応を100%にすることも可能かもしれない。いずれにせよ、早く臨床治験を進めてほしいと切に願う結果だ。
2021年8月13日
昨日に続いて、ちょっと風変わりな糖代謝の論文を取り上げようと思っている。というのも、私は全く気づかなかったが、今年はインシュリン発見100周年ということで、Nature Medicineが特集レビューを掲載していた。このレビューは、インシュリンの発見から、Eli Lilly社の助けによる薬剤としての確立、そしてこの発見が世界中の多くの人の命を助けると知ったトロントのインシュリン発見者たちが、なんと彼らの特許を1ドルで売ったというドラマから、インシュリン薬の進化、さらに1型糖尿病についての治療法の進化などが紹介されている。医学生の一読を勧める。
さて、今日紹介するニューヨーク大学からの論文は最初に仮説ありきの典型研究で、脳の海馬の興奮と血中グルコースの関係を調べている。タイトルは「A metabolic function of the hippocampal sharp wave-ripple (海馬の鋭波リップルの代謝調節機能)」だ。
この研究では、予測される活動に前もって代謝調節機能を備えておくためには、脳を通して調節するしかなく、そのためには海馬のように多くの領域からインプットとアウトプットを受ける領域の関与が必須であると仮説を立てて研究を始めている。
活動のための代謝調節といえば、まず最初に来るのが当然インシュリンとグルコース代謝になるので、海馬のCA1領域の興奮と血中のグルコースを連続モニターし、両者に関係がないかどうか調べている。
海馬では1ヘルツ程度の大きな脳波に重なって、80−100ヘルツの短い波が重なったsharp wave rippleと呼ばれる興奮パターンが見られる。これは、ノンレム睡眠時に多く見られ、記憶の呼び起こし(https://aasj.jp/news/watch/11119 )に関わる可能性を示唆した論文を以前紹介した。この研究のハイライトは、著者の期待通り、このsharp wave ripple(SWR)の出現頻度と、血中グルコースレベルが、逆相関することの発見だ。すなわちSWRの頻度が高まった後は、グルコースのレベルが低下することになる。
これを確認する意味で、今度は光遺伝学を用いて海馬に人工的にSWRを発生させる実験を行い、グルコースレベルが低下することを観察する。
最後に、海馬CA1からの回路を探索し(これも仮説に基づいて調べている)、海馬と下垂体をつなぐ外側中隔核を、やはり遺伝子工学的に発現させた神経抑制システムを用いて抑制すると、SWRとグルコースのレベルの結合が低下することを示している。
結果は以上で、考えてみれば血中グルコースを調節するインシュリン、グルカゴンもホルモンで、自律神経により調節されると考えると納得できる話だ。
いずれにせよSWRが深いノンレム睡眠で多発することを考えると、本当は寝ているときのリラックスに役立っているのかもしれない。
2021年8月12日
脂肪組織写真を見ると、細胞質が脂肪で周りに押しつけられた大きな脂肪細胞が集まった均一な組織に見える(例えば:https://www.researchgate.net/figure/Histology-of-the-epididymal-white-adipose-tissue-WAT-of-mice-in-the-a-low-fat-LF_fig2_236925039 )。ところが今日紹介するスウェーデン・カロリンスカ研究所からの論文は、この均一に見える組織に、20種類の異なる細胞が組織化され、インシュリンに対する反応もこの組織化された構造の中で行われていることを示す研究で、今後の脂肪代謝の研究に重要な示唆を与えている。タイトルは「Spatial mapping reveals human adipocyte subpopulations with distinct sensitivities to insulin(脂肪組織の空間的マッピングによりヒト脂肪細胞サブセットの異なるインシュリン感受性が明らかになった)」で、9月7日号のCell Metabolismに掲載されル予定だ。
この研究は以前紹介した(https://aasj.jp/news/watch/5490 )、カロリンスカ研究所で開発された、組織構造を壊さずにそれぞれの細胞の遺伝子ライブラリーを作成し遺伝子発現と組織の空間情報を合体させる方法を用いて、均質に見える脂肪組織上で遺伝子発現マップを作成している。
後はこの解析だが、組織上での遺伝子発現マップのおかげで、均質に見える脂肪組織に少なくとも20種類の異なる細胞が存在し、それもただランダムに存在するのではなく、特定の細胞同士が集まっている。例えば、脂肪細胞は3種類のプレアディポサイトと3種類の白色脂肪細胞(WAT)に分けられるが、プレアディポサイトのうちの一つは、M2マクロファージと隣接しており、一種のニッチが形成されている。
もちろん解析の焦点は、全く均質に見える白色脂肪細胞で、それぞれレプチンを発現したWATlep, ペリリピンを発現したWATpln、そして血清アミロイドを発現したWATsaaの3種類にきれいに分けることができる。実際、組織からWATの細胞浮遊液を作成して抗体で染めると、発現が完全に分離している3種類の細胞が特定できる。
つぎに、それぞれの細胞の機能的違いを調べる目的で、大きさや、肥満などとの関係を調べている。それぞれのサブセットに大きさの違いはあるが、差はわずかで、細胞の大きさでサブセットが決まっているわけではないことがわかる。
一方、肥満との関係を見るとBMIの高いヒトほどWATlepが上昇し、WATplinが低下している。そして驚くことに、WATplinだけがインシュリンに対して誘導される脂肪合成遺伝子の発現と高い相関を示していた。
もちろんすべてのWATは脂肪を蓄えており、脂肪代謝と蓄積のメカニズムを持っているのだが、この結果はインシュリンにすぐに反応する細胞はWATplinだけであることを示唆している。
この結果をはっきりさせるために、インシュリンクランプを行ったボランティアの脂肪組織を採取し、インシュリンに対する2時間目の反応を遺伝子発現で調べると、WATplinのみで様々な脂肪合成遺伝子が誘導される一方、ほかの2種類の細胞でインシュリン反応性に誘導される遺伝子はほとんど存在しないことが明らかになった。
結果は以上で、それぞれのWATの分化がどのように調節されているのかなどさらに詳しく調べる必要があるが、なんといっても一部のWATしかインシュリンに反応せず、またそれがレプチンを分泌するWATと異なるという結果は驚きだ。
また、時間はかかってもこの技術が着実に成果を上げていることも実感した。
2021年8月11日
障害されると顔の認識ができなくなる相貌失認症が起こる脳の「顔領域」は、記憶したイメージからのトップダウンの神経活動と、視覚刺激からのボトムアップの活動を統合する領域で、私たちの社会生活には欠かせない。
今日紹介するロックフェラー大学からの論文は、アカゲザルの顔認識をさらに細かくカテゴリー化して、親しい顔にだけ反応できる神経細胞を特定し、その性質を調べた論文で、7月30日号のScienceに掲載された。タイトルは「A fast link between face perception and memory in the temporal pole (脳側頭極での顔の感知と記憶の早い結合)」だ。
研究は、アカゲザルに様々なカテゴリーの人間やサルの顔写真を見せ、特定のカテゴリーに反応する神経細胞を、一個づつ電極を刺して調べる、今では古典的ともいえる方法で行われており、私のようなロートルには懐かしい。
ただ、無闇に電極を刺すわけではなく、最初に機能的MRIを用いて、あらかじめ反応する領域を大まかに決めておいて、次に電極で神経活動を記録すると言う順序で行っている。実際には、これまで顔領域として知られている、側頭極の下側(anterior-medial area :AM)と、最近馴染みの顔に反応する領域ではないかと示唆されている側頭極上部(temporal pole area:TP)に焦点を絞って記録を行なっている。
あらかじめ用意した270種類の写真を猿に見せながら、それに対する個別の神経反応を記録すると言う、いわゆるムスケルアルバイトで、ほとんどコンピュータによる処理が行われていない点も、ロートル向きだ。
結果は極めて満足できるもので、これまで知られていたようにAMは、人間であれサルであれ、見ているのが顔であれば反応する神経が存在しており、一方TPには馴染みのあるサルの顔だけに反応する神経が存在することを発見している。すなわち、TPは馴染みがあると言う記憶を、網膜から得た形の感知と繋げている。
一旦細胞が特定できると、様々な実験が可能になる。例えば、写真のコントラストを落として細部がわからなくして、徐々にコントラストを上げていくと、TPの馴染み細胞はコントラストがないと細部がわからず反応できないが、コントラストが上がると徐々に反応が高まる。一方、AM細胞は、コントラストがなくても顔とは認識できるので、コントラストにかかわらず一定の反応を示す。
今度は、写真全体にマスクをかけて、霧で見えないような状態から順々に霧をはらしていくと、TPもAMも霧が晴れ始めた時点で反応が始まる。
さらに面白いのは、馴染みかどうかの判断だが、輪郭、目、口、鼻など部分で記憶しているわけではないが、顔の輪郭を外しても全ての部分が残って居れば馴染みとして反応する。一方、顔のカテゴリーに反応するAM神経は、輪郭、目、鼻などの部分にも反応できる。ただ、なぜか口には反応しない。
最後に、顔認識の後馴染みの認識がくるのか、階層性について様々な実験を行って調べ、それぞれのリンクは独立して感知されたインプットに即座に反応するのに役立っていることを示している。
結果はこれだけで、馴染み細胞を見つけただけで、どうつながっているのか全く不明のままだと言う人もいるかもしれないが、馴染みとは何かを考えさせる意味でも面白い論文だった。おそらく馴染みと、顔の特定とはかなりリンクしていると思うので、知り合いかどうかわからないといった症状を示す人を集めてくると、新しい相貌認識異常の定義も可能かもしれない。