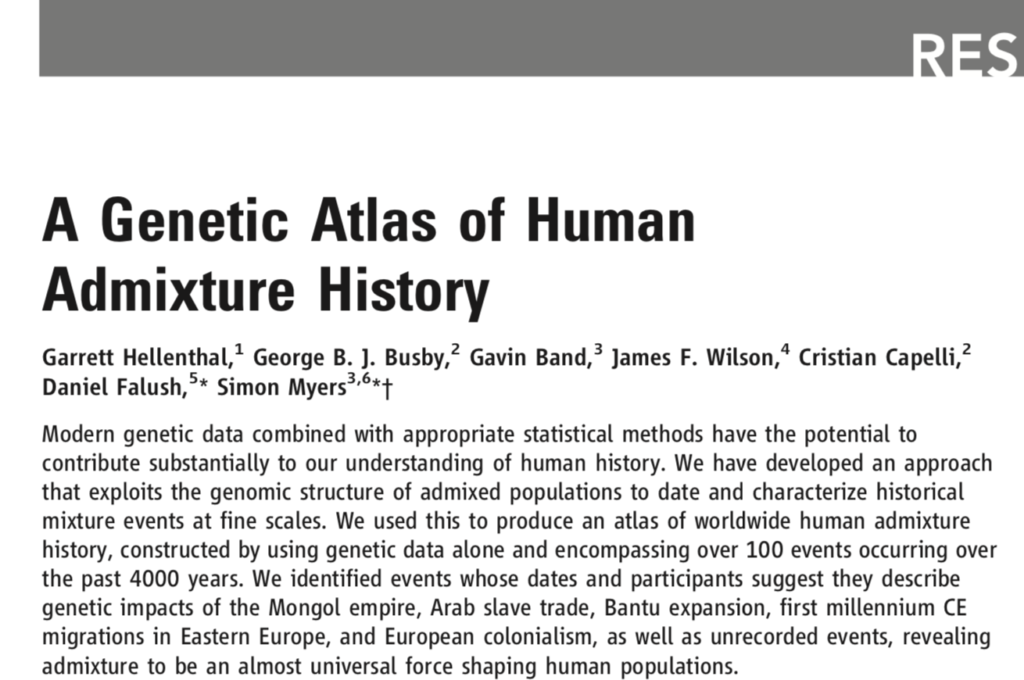2020年6月23日
ゲノムから種を特定することが可能になり、腸内細菌叢の量や多様性をゲノム解析から測定することが可能になり、免疫や栄養状態と腸内細菌叢の状態との相関についての理解が急速に進んだ。ただこの方法で得られる相関を、生物学的因果性へと転換することは難しい。AIもあるのでそれでいいという考えもあるが、生物学者としては、最後は細菌叢を培養して、因果性を目指す研究を行いたいと思う研究者が出てくるのは当然のことだ。
今日紹介するプリンストン大学からの論文はできるだけそのままの形で腸内細菌叢を培養して、様々な機能解析と、その因果性解析に用いることができるか調べた論文で6月25日号のCellに掲載された。タイトルは「Personalized Mapping of Drug Metabolism by the Human Gut Microbiome (人腸内細菌叢による薬物代謝の個人別のマッピング)」だ。
目的は極めて単純で、「腸内細菌叢をそのまま培養できるか?」だ。ただ、何千種もの細菌が存在し、実際にはバイオフィルムも含めて構造化されている細菌叢を培養することは本当は難しい。従って、この研究ではゲノム解析での多様性を維持できるかどうかに絞って、培養法を開発するところから始めている。
もともと細菌培養とは多数の菌の中から特定の菌を分離培養することを指すが、この研究ではその逆をいっている。一人のボランティアの便を14種類の培地で4日間培養し、質量ともに元の大便に最も近い培地を探している。この結果、我が国で開発された岐阜嫌気性培地が再現率7割と優れていることがわかった。
次はこの方法を用いると、試験管内で因果性についての研究が可能かをテストしている。そのために、細菌叢により経口薬が分解されるという現在問題になっている点について、575種類の薬剤をそれぞれ細菌叢培養に加え、加えた薬剤とそれ由来の代謝物を検出している。結果の詳細は省くが、これまで予想されていた薬剤の変化だけでなく、培養を用いるとこれまで知られなかった分解や代謝が起こることがわかった。すなわち、この様な培養を用いて、投与する薬剤が細菌叢により分解されないかあらかじめ調べることができる。
次に、20人の異なる個体にこの解析を広げられるか調べている。ただ、岐阜培地でうまく行ったからと言って、他の人にも同じ培地が通用するかどうかわからない。そこで、10種類の異なる培地を用いて、比較的平均値に近い培地を探索し、最終的にBryant and Burkey培地70、岐阜培地30を混ぜた培地が最も適していると結論している。実際には、あらゆる可能性が試されない以上、この程度で妥協する必要があるのだろう。
その上で、様々な薬剤の分解について20人の細菌叢を調べている。例えばヒストンアセチル化阻害剤ボリノスタットの分解能は個人ごとに多様だが、強心剤ジゴキシンはほとんどの人が分解できるのに2例の例外があると入った具合で、予想通り、薬剤への細菌叢の影響が大きいことがわかる。
次に、薬剤の分解や代謝に関わる細菌種と分子の特定が問題になるが、これを現在知られているゲノム解析の結果から割り出すのは簡単ではなさそうで、どうしても関連する遺伝子が決まっている薬剤に限られてくる。
この問題を克服するために、この研究ではなんと100万個のバクテリアから発現遺伝子ライブラリーを作り、それを大腸菌に導入してできた機能分子ライブラリーに薬剤を加え、その分解や代謝に関わる分子を特定する可能性について、ステロイドホルモンの分解をモデルに示している。
要するに、できるだけそのまま腸内細菌叢を培養することで、生物学的因果性に関わる研究が可能であることを示そうとした論文だ。もちろん色々問題はあるが、この意気込みと、遺伝子発現スクリーニングまでやった徹底性に脱帽。
2020年6月22日
一旦存在が明らかになると、今度はあらゆるものが同じ様に見えてくる好例が相分離現象だろう。今や私たちの細胞の中は相分離した様々な液滴で満ち満ちている様だ。すなわちタンパク質がそれぞれの液滴に分離しているなら、分子量のずっと小さい薬剤の分布はどうなのか?
今日紹介するハーバード大学からの論文はこの問題にチャレンジした研究で、おそらく効果の高い抗がん剤を考える意味では極めて重要な貢献だと思う。タイトルは「Partitioning of cancer therapeutics in nuclear condensates (核内で相分離した液滴への癌治療薬剤の隔離)」で、6月9日号のScienceに掲載された。
この研究は転写やエピジェネティックスの大御所Richard Youngの研究室からの論文だが、Youngはスーパーエンハンサーの研究から、エンハンサー場での転写因子複合体の形成が相分離によると見抜き、この分野をリードしている。
まずスーパーエンハンサー(SE)を形成する転写因子をガン組織より調整した細胞で調べ、期待通り相分離が見られ、SEでの相分離が一般的な現象で
よく知られた5種類の転写因子とメディエーターMED1が相分離していることを確認している。
その上で、それぞれの転写因子が試験管内でも相分離すること、しかしこれらの系に蛍光分子などの小分子を共存させても、分離した駅的に濃縮されることはないことを確認している。
次に、MED1を含む5種類の転写因子の相分離実験系に、プラチナ化剤のシスプラチン、DNAのintercalatorミトキサントロン、エストロジェン受容体阻害剤タモキシフェン、CDK7阻害剤、そしてSEのBRD4を阻害するJQ1を加え、がんの治療薬なら相分離した液滴に濃縮されるか調べている。すると、全ての薬剤はMED1が相分離した液滴に分離すること、そして例えばJQ1、メトキサントロンはそれぞれBRD4 およびFIB1, NPM1にも濃縮されることを発見している。すなわち、普通の低分子と異なり、抗ガン剤の一部はMED1に濃縮され、SEにリクルートされることを示している。
この相分離液滴への濃縮は、非特異的なものでMED1に存在するアミノ酸の芳香環と薬剤側の芳香環の作用により起こる現象で、例えばシスプラチンによるDNAのプラチナ化を指標に調べると、MED1液滴に濃縮されることが活性に重要であることがわかった。そして、シスプラチンによりDNAがプラチナ化されるにつれて、SEが解消されることも明らかになった。
次に、乳ガンのエストロジェン受容体阻害剤について相分離の観点から、詳しい検討を行い、エストロジェン受容体はエストロジェンと結合することでMED1を含むSEに濃縮され、タモキシフェンはMED1液滴内で、このプロセスをブロックすることでエストロジェン受容体のSEへの濃縮を阻害している。その意味でタモキシフェンが濃縮され有効濃度が高まることに相分離は貢献しているが、MED1が強発現することで相分離の液滴が大きくなると、相対的に有効濃度が低下するため、MED1の発現が上昇した乳ガンではタモキシフェンの効果が低下することなど、これまで説明が難しかったことを見事に説明している。
結果は以上で、転写に効果がある薬剤をSEなど相分離液滴に濃縮させることで、より高い薬効が得られる可能性は、今後単純な薬剤動態だけでなく、相分離液滴への濃縮まで考えた薬剤開発が重要であることが理解される優れた研究だと思う。
もしかしたらコロナウイルスの分子も相分離という観点で見直したら面白いことがわかるかもしれない。おそらく、この可能性をテストしている研究者はいると思う。
2020年6月21日
今、我が国では、新型コロナについておかしな逆転現象が起きている。前にも批判したが、外出自粛や新しい生活様式といった本来なら政治家や経済学者が研究者のアドバイスをもとに語る内容を、医師や科学者が語り、ワクチンや治療薬についての見通しを首相や知事といった政治家が語っている。
一方ワクチンについては科学者内でも、期待できるとかできないとか議論がSNSで白熱している様だが、科学者として丁寧な説明にはあまりお目にかかったことがない。丁寧な説明ができるかは、開発したワクチンの免疫学的特性をどこまで正確に検証できるかにかかっている。逆に丁寧な説明がないと、とりあえず抗体ができるから、感染機会の多い医療従事者に使って効果を確かめればいいといった乱暴な議論が横行してしまう。
では丁寧な説明は可能か?今日紹介するオックスフォード大学からの肝炎ワクチンに関する論文を例に、これが可能であること、そして我が国のワクチン開発者も、自らの口で効果について丁寧な説明ができる様、十分な検証実験をする様促したい。論文のタイトルは「MHC class II invariant chain–adjuvanted viral vectored vaccines enhances T cell responses in humans (クラスII-MHCのインバリアント鎖を用いたウイルスベクターワクチンはヒトのT細胞反応を促進する)」で、6月17日号のScience Translational Medicineに掲載された。
抗体誘導を目的に開発された様々なワクチンの失敗から、ウイルス感染細胞を除去するT細胞を誘導するワクチンの開発が現在加速している。以前紹介した様に、うまくキラー型のT細胞(CD8T)が誘導できると、一種類のインフルエンザワクチンでほとんどの異なる系統のインフルエンザへの抵抗力ができる(https://aasj.jp/news/watch/12433 )。
このT細胞免疫は抗体反応に必要だが、抗体反応とは独立に誘導される。例えばBCG摂取を受けたあと、結核菌に免疫ができているかどうかは決して抗体で検証しない。我が国ではほとんどの人が受けことのある、ツベルクリン反応(結核の抗原PPDに対するT細胞の反応を皮膚反応としてみる)で検証している。
このグループは、ウイルスに対するT細胞の反応を誘導する方法の開発を進めてきた様で、長い研究に基づき、人間にはほとんど自然抗体が見られない猿のアデノウイルスベクターを用い、抗原遺伝子に、細胞内で抗原の処理を高めMHCとの相互作用を高める、インバリアント鎖遺伝子を融合させた抗原をデザインし、T細胞の反応を高めるワクチンをにたどり着いた。
この研究では、このワクチンが期待通りウイルスに対するT細胞反応を誘導できるか、ヒトに接種して調べている。結論的には、ワクチン接種で様々な副反応が起こるが、全て軽度で終わること、抗体はほとんど誘導されないこと、長期にわたる強いCD4TおよびCD8T反応が誘導でき、またワクチン接種後のペプチドに対する2次反応も誘導でき、極めて有望であることを示している。ただ、ワクチンの有効性については有望という一言で済ませて詳細は割愛したい。
その代わりに是非紹介したいのは、ワクチンがT細胞反応を誘導できるかどうか、ヒトで確かめる方法が存在するという点だ。
この研究ではインバリアント鎖を融合させたワクチンと融合させていないワクチンを摂取した時、
末梢血にインターフェロンγ陽性細胞が現れ、長期間持続すること、 抗原に用いたタンパク質をカバーするペプチドを準備し、プールしたペプチドに対するCD4T、CD8T細胞の反応を調べると、インバリアント鎖を持つワクチンではるかに高いT細胞免疫が誘導されること、 一部のボランティアについては、MHCとペプチドの複合体を準備し、これと結合するT細胞の数までカウントし、34週間にわたって末梢血中の抗原特異的T細胞の数を数えることができる(なんとCD8Tでは20%が抗原と結合するレベルまで上昇する)こと、 を示している。すなわち、ワクチンに対するT細胞の反応をヒトで正確に検出できる方法が整っているということだ。
それでも、このワクチンがC型肝炎予防に有効かどうかは実際の臨床実験が必要であることはいうまでもない。
この研究から、我が国のワクチン計画を担う研究者へ以下の様に要望したい。
インバリアント鎖の効果からわかる様に、免疫誘導を助けるアジュバントの仕組みがワクチンのキモになるが、これについてそれぞれの方法を正確に説明すること、 動物実験のみならず、ヒトの接種実験でも、ペプチドプールも含めて上に述べた検出方法を用いて、T細胞免疫誘導性について説明すること。 これは研究者自らが語るべきことで、いくら一般の人に知識がないからといって、政治家やメディアレベルの知識でお茶を濁して臨床応用へ突き進むことは許されない。
2020年6月20日
タイトルを見ただけで、実験やメッセージ、そしてその重要性が頭に浮かんでくる論文はまちがいなく面白い。今日紹介するスローンケッタリング癌研究所からの論文はまさにそんな例だと思う。
アンチエージングは今最も注目されている分野だが、実際の臨床で最も効果があるのがsenolysis(老化細胞を溶かす)と呼ばれる方法で、死にかけの細胞を積極的に除去して、新陳代謝を高めることで、組織を若々しく保つ方法だ。この方法は、一般の人が考える老化だけでなく、老化メカニズムが関与する様々な病気、例えば肺線維症や腎硬化症の進行を抑えるため、臨床的価値は大きい。
ただsenolysisを誘導する方法は限られており、遺伝子操作か、あるいは癌治療に使われる特異性の低いリン酸化阻害剤で死にかけの細胞を殺す方法しかなかった。実際、リン酸化阻害剤は腎硬化症や肺線維症に用いられ成果を挙げているので、全身性の老化にも効果があると期待できるが、やはり抗ガン剤を続けて服用するということになると、二の足を踏む人が多いのではないだろうか。
研究は6月17日号のNatureに掲載され、タイトル「Senolytic CAR T cells reverse senescence-associated pathologies (senolysisを誘導するCAR-T細胞は老化に関わる病理を正常化する)」だ。
タイトルからわかるようにsenolysisをCAR-Tにやらせようという話だが、CAR-Tについて少し説明しておこう。CAR-Tはキメラ抗原受容体T細胞の訳で、簡単にいうとキラーT細胞の抗原認識システムを遺伝子操作して、相手の抗原を認識する抗体に置き換えた細胞のことを意味している。白血病治療には、我が国でもすでに認可されており、白血病細胞表面上の抗原に対するCAR-Tを用いて、白血病細胞をほぼ完全に除去することが可能になっている。
この研究ではガンのではなく、老化細胞に特異的な細胞表面抗原に反応して老化細胞だけ殺してくれるCAR-Tを開発すれば、抗ガン剤を服用するより安全な抗老化治療ができるのではと着想した。この着想が研究の全てで、全く新しいCAR-Tの未来が開けたのではないかとすら感じる。
着想できれば、あとは細胞種類を問わず老化した細胞だけで細胞表面に発現が見られる抗原を探索し、この研究ではuPAR(ウロキナーゼ型プラスミノーゲン活性因子受容体)を特定している。
次に、uPARに対する抗体を作成、この抗原結合部分を持ったT細胞抗原受容体キメラ遺伝子作成、T細胞に導入し、uPARを発現した細胞を殺すキラーT細胞株を開発している。
あとは試験管内、生体内で正常細胞は殺さず、uPARを発現する細胞だけ殺すことを確認して、老化ガン細胞、肝臓障害後の線維化、非アルコール性肝炎による繊維化などを標的に前臨床研究を行い、繊維化を抑え病気の進行を止めることを明らかにしている。
以上が結果で、まだマウスモデルの段階だが大きな可能性を感じる。癌の周りの繊維化を抑えれば、膵臓癌の治療に使えるし、肝臓だけでなく、肺線維症、腎硬化症、さらには老化により発病が促進する骨髄異形成症候群など、応用範囲は広い。このシステムでは軽度ではあるがサイトカインストームが誘導されている。全身の細胞が老化し始めた高齢者に投与するときは、最初はかなり注意が必要だろう。
いまや新型コロナですらCAR-Tで感染細胞を根こそぎにしようという時代だ。チェックポイント治療と並んでガン免疫治療のシンボルになってきたCAR-Tは、さらにその可能性を広げようとしている。
2020年6月19日
古事記で日本を造ったとされるイザナギ、イザナミが兄弟姉妹の関係だったのかどうかは諸説あるが、人類誕生初期から近親相姦はタブーになってきたにも関わらず、神話ではこのタブーが破られるのは世界共通のようだ。ギリシャ神話のゼウスは二人の姉を妻にしているし、オペラファンなら馴染深いワーグナーのオペラに登場するジーグフリードは、神ヴォータンと人間の女性との間に生まれたなんと双子の兄妹ジーグムンドとジーグリンデの子供で、近親相姦の究極とも言える関係がわざわざ示唆されている。
ただ、ここまで極端でなくとも、神性を持つ王の一族では、我が国も含めて血統を守ることが重視され、近親婚も許されてきた証拠が多く存在する。このようなタブーからの例外がいつから認められるようになったのか、階層的社会の形成を理解するためには重要な課題だ。
今日紹介するアイルランド ダブリン トリニティーカレッジからの論文は、新石器時代の太陽光に沿った長い廊下を持つNewgrangeの巨大古墳(https://www.knowth.com/newgrange.htm )から出土した男性の骨のゲノム解析から、当時兄弟姉妹婚が行われていたことを示唆する研究で6月17日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「A dynastic elite in monumental Neolithic society(新石器古墳時代(私の勝手な訳)の王族のエリート)」だ。
この研究の目的は近親婚の証拠ではなく、アイルランドという大陸から分離された島国での民族形成、特に新石器時代に農業が導入される時期の民族形成過程を明らかにすることだ。そのためにアイルランド各地から中石器時代2人、新石器時代42人の骨から分離したDNAの全ゲノム解析や年代測定、さらには成分分析を行い、民族内外の系統関係、当時の食事などを調べている。
従来の研究で、新石器時代の農耕は海を渡ってスペインから伝播したと考えられているが、アイルランドの新石器人は英国のそれとオーバーラップしており、海を渡って新しい人達が入ってきて、農耕が導入されることを示している。
他にも、農耕前の狩猟採取民のゲノムでは、アイルランドと英国や大陸との交流はほとんどなかったこと、一方当時陸続きであった大陸と英国では交雑が認められることから、農耕前には海が障壁として交流を阻んでいたこと、あるいは世界最古の21番トリソミーを持つゲノムの発見など、面白い発見が示されている。
しかしこの研究のハイライトは、何と言ってもNewgrangeの羨道墳で発見された男性の骨から、この男性が兄弟姉妹婚により生まれたことがわかったことだ。今回調べられた他の骨の解析から、身分の高いと思われる個体でも、近親婚の痕跡はなく、さらにはこの個体と親戚関係にあると推定される他の王族でも近親婚の痕跡は認められず、近親婚がタブーとして避けられていたことを示している。すなわち、この男性だけが完全な例外になっている。
もちろん1例だけなので、たまたまという話もできるが、この骨が有名なNewgrange 羨道墳から出土したこと、羨道墳では太陽の軌跡が古墳内を長く続く廊下に反映していることなどから、単純な例外ではなく、古墳に埋葬される王族は血縁関係を持つが、その中から神聖な儀式を司るメンバーが選ばれ、このメンバーでは純血を守るために兄弟姉妹婚が行われていたのではと推察している。
これを裏付ける一つの証拠として、英国中世では王が太陽の軌跡を司る能力を身につけるために妹と結婚するという伝説、あるいはDowthにある同じような羨道墳が「罪の丘」「近親婚の丘」と呼ばれていることも持ち出し、アイルランドで早くから極めて複雑な宗教と権力が一体となった社会が形成されていることを示している。
ゲノム解析が歴史解明にいかに有効化を示す新たな論文が付け加わった。
2020年6月18日
山中さんのiPSの登場で議論がほとんど中断したが、ヒトES細胞樹立に向けた倫理的問題を文科省で議論し始めた頃、ヒト胚の尊厳が3胚葉が形成される原腸陥入期に発生するとする考えが欧州にはあることを聞いたのを覚えている。この概念の起源についてはよくわからないが、個体の構造を細胞浮遊液へと解体してから、再構成する時、原腸陥入以降ではほとんど再構成できないので、細胞が個体に属するようになるという意味でこの概念が出たのかと考えていた。
今日紹介するケンブリッジ大学からの論文をは、ES細胞を用いたヒト胚培養で原腸陥入期を超えて体節形成期まで発生を誘導できるという研究だが、胚培養を原腸陥入期を超えて進めてはいけないというルールはヨーロッパでも消失していることがわかった。タイトルは「An in vitro model of early anteroposterior organization during human development(ヒト発生時の前後軸形成の試験管内モデル)」で、6月11日号のNatureに掲載された。
もともとES細胞からembryo body(EB)と呼ばれる凝集塊を形成させ、自発的に発生させる方法はポピュラーで、オルガノイド培養のルーツとして広く行われている。ただ実際のヒト胚と比べると、どうしても細胞分化のバランスが壊れてしまい、三胚葉は形成されても、実際の胚とは程遠い。
この研究ではES細胞をまずWnt刺激化合物Chironで1日処理し、その後細胞を凝集させ、Chironと笹井さんたちが開発したRock阻害剤で24時間培養するという方法を開発し、この方法ではEBがオタマジャクシのような形に伸び、この構造が一種のボディープランを持っていることを発見した。
この発見がこの研究のすべてで、実際マウスでも同じようなボディープランを持ったオルガノイドを形成することは難しい。これは培養に使う分化増殖因子がどうしても発生を捻じ曲げてしまっていたからと考えられるが、それをChironという化合物で置き換えることで、偶然とはいえ乗り越えた。実際、Chironの代わりにWnitを用いてもうまくいかない。もちろんよく使われるBMP4などでもボディープランの発生は観察できない。なぜかChironが持つ様々なシグナル系への副作用が、胚発生の絶妙のバランスを生みだしたことになる。
実際、この発生過程にWnt、BMP、nodalなど、初期発生に必須の分子に対する阻害剤を加えると、発生はうまく進まない。
このEBが伸びて造られる新しい構造では、3胚葉が形成されるだけでなく、細胞の集団の動きが原腸陥入をミミックし、最終的に前後軸を様々な分子マーカーで確認できる構造が形成される。そしてこの構造を前から後ろまで順番に切片として切り出し、それぞれの切片での遺伝子発現を見ると、分子マーカーが前後軸に沿って発現し、ボディープランとともに発現パターンが生まれるHox遺伝子の発現でもこのプランを確認できる。そして、この前後軸の形成を支持するオーガナイザーについても特定できる。
以上詳細を省いて、イメージだけを紹介したが、ES細胞から体の構造を作る試験管内実験系ができたことは重要だと思う。見たところ、前後軸はできても、背腹軸についてはうまくできていないので、次は両方同時に誘導する方法の開発が進められると思う。その結果、どこまで実際に近いヒト胚が形成できるのか、楽しみだ。
2020年6月17日
細菌叢の研究が進んでから、善玉菌と悪玉菌という概念が定着し、善玉菌を摂取して悪玉菌を駆逐するという理屈で、多くのプロバイオ製品が売られている。中でも発酵に関わる乳酸菌はプロバイオの王様といえる。科学が進む以前からの伝統もあり、病気と一定の相関を示すこともある程度わかってきた。ただ、善玉菌の条件を示すことは簡単ではない。おそらくプロバイオ研究は、今コマーシャルで行われているような話ではなく、食と健康を考える21世紀の大テーマだと思う。
今日紹介するベルギー・アントワープ大学からの論文はちょっと変わった観点から乳酸菌の中のLactobacillusを調べた研究で、5月25日号のCell Reportsに掲載された)。タイトルは「Lactobacilli Have a Niche in the Human Nose (Lactobacillusは人間の鼻腔にニッチを持っている)」だ。
この研究の目的は鼻腔の細菌叢を変化させて慢性鼻炎を軽減するためのプロバイオは可能か調べることだ。ただこの研究では伝統的に善玉菌として扱われてきたLactobacillusに焦点をあて、正常人と鼻炎患者でLactobacillusの存在容態が異なるかを調べている。
まずLactobacillusは少数ながら鼻腔にも存在することがわかる。そして期待通り、鼻炎患者さんではLactobacillusの存在頻度や量が低下していることがわかった。そこで、正常人鼻腔からのLactobacillusを分離培養を試み、大きく4亜種、100菌株の培養に成功している。実際には他の増殖の早い細菌が存在するため、この作業は簡単ではなかったようだ。
これらすべてのゲノムを調べ、それぞれの関係を調べたところ、驚くことに分離された菌株のほとんどは、多様性に乏しく、おそらく食品、特にヨーグルトなどを通して摂取した乳酸菌が鼻腔にも居着いたと考えられる。
しかし鼻から分離されたL caseiとL sakeiは、これまで知られている細菌から大きく変異していることも同時に明らかになった。この理由は、鼻腔という新しい環境に適応したと考えられる。
この研究ではその適応として、鼻腔のように酸素分圧の高い場所で生存するために強化された、カタラーゼなどの活性酸素の毒性を低下させるメカニズムとともに、洗い流されずに鼻腔に粘着する性質についても調べ、鼻腔に適応した菌株では線毛と呼ばれる細菌が細胞に接着するときに必要な構造に関わる遺伝子を発現していることを明らかにしている。
こうして鼻腔に適応したLactobacillusとして培養されたのは、馴染みの深いL caseiになったが、これが典型的な悪玉菌とされている、緑膿菌、ヘモフィリス菌などの増殖を抑制することを確認している。また、病原菌による炎症性サイトカインの分泌をLactobacillusが抑制できることも示している。
最後に、L caseiには抗生物質耐性が存在しないことを確認した上で、実際の鼻腔に投与する人体実験を行っている。鼻に噴霧後、5分、10―16時間、そして2週間目に鼻腔に噴霧したL caseiが存在するか調べると、10時間ぐらいまでは存在すること、また噴霧直後では他の細菌の量が低下することも確認している。
もちろん治療実験までには至っていないが、乳酸菌を鼻に噴霧しても重大な副作用はない。ただ、鼻水、鼻づまりは投与を受けた多くの人に見られたので、今後の課題になる。
以上が結果で、Lactobacillusに最初から決めてはいるが、鼻腔から段階的に善玉菌を取り出し、その臨床応用を目指すという点では、なかなか好感が持てる研究だった。
2020年6月16日
ゲノム研究が歴史研究であることを私にはっきりと認識させたのは、2014年ロンドン大学の研究グループによって、今生きている人のゲノムを解読するだけでヨーロッパとアジアの交流史が明らかになることを示した論文だ。この中では、なんとジンギスカンの遠征によるモンゴル族のゲノム流入の時期が、ゲノムから正確に推定できることが示されていた。
この衝撃は大きく、今もゲノムについて講義する時この論文を使っているが、6年以上経った今でもインパクトは色褪せない。
これらの研究は、ゲノム研究から明らかになった一塩基多型SNPを用いて、ゲノムの交流を調べているが、形質の変化という点では、欠損、挿入、重複といった大きな構造変異の方がインパクトがある。ただ、これらの変異は、病気を起こすようなまれな変異を除くと、特定するのが難しい。
今日紹介するウェルカムサンガー研究所からの論文は世界様々な地域から得た911人の全ゲノム配列解析を、GRCh38と呼ばれる1000人ゲノムなどを参考に決定されたレファレンスと比較して大きな変異を集め、その分布を調べた研究で7月3日号Cellに掲載予定だ。タイトルは「Population Structure, Stratification, and Introgression of Human Structural Variation (ヒトの構造遺伝変異の人類構成、階層性、そして流入)」だ。
この研究で明らかになった構造変異の7割以上がこれまで発見されていないということで、大きな集団の解析に、このような構造変異を使うことの難しさを示している。何れにせよこの研究では13万近い構造変異を特定することができ、この13万の変異の各人種ごとの分布を調べると、人種ごとに明確な違いがわかる。さらに、欠損変異でを取り出して見ると、例えばアフリカの人種の中でもさらに細かい人種の違いと対応することが明らかになった。
このように人種の分離をゲノム構造変異で行える最大の理由は、このような変異のなかには、レアバリアントではなく、人種によっては多くの構成員に見られるコモンバリアントである点だ。その例として、この研究ではデニソーワ人の遺伝子流入率の多いオセアニアの人種について詳しく調べているが、8割以上の人に見られるような変異も発見されている。
いくつかについては進化との関わりを推察している。面白い例をいくつか紹介すると、例えばヘモグロビンの転写に関わるHBA2遺伝子の欠損は、高地に住むパプア人では全く見つからないが、ほとんど同じパプア人でも低地に住む人たちには8割以上に見られる。おそらくこれはマラリア抵抗性として選択されてきた。
あるいはNGAMと呼ばれるデンプン消化に関わる遺伝子上流の欠損はブラジルのカリチア人の4割に見られ、その食生活に関わる。
最後に、レトロウイルスなどに対する抵抗性を抑える方向で働くSIGLEC5遺伝子が54%の中央アフリカのムブティ族で欠損していることは、免疫が高まる危険をおかしてもウイルス免疫を高める方が良かったことを示唆している。
もちろんこのような変異のなかに、ネアンデルタール人やデニソーワ人由来の変異があることも確かめている。例えばデニソーワ人に認められる16番染色体上の重複変異は、ほとんど全てのオセアニア人に維持されている。またアメリカ現順民の26%に見られるMS4A1のエクソン欠損はネアンデルタール人由来で、なんとB 細胞の重要遺伝子CD20 をコードしている。
他にも種族特異的な遺伝子コピー数の増加など詳しくは説明できないほど、面白い発見に満ちていると言える。すなわち構造変異は形質へのインパクトが高く、それだけ面白い。
以上、民族形成を考える意味で大きな進歩だと思う。さらにこの研究から、レファレンスゲノムもさらに進化する必要が示唆された。これにより、さらに構造変異の発見が容易になり、ゲノムの人類史も面白くなる。
2020年6月15日
当分旅行は難しくなったが、アフリカ旅行の醍醐味の一つは、毎日毎日、毎時間、毎時間見たこともない鳥に出会えることだ。この多彩、多様な模様や羽色が形成されるメカニズムを理解しようとしても、どこから手をつけていいか途方にくれるだけだと思うが、こんな課題に果敢にチャレンジしている人たちがいる。
今日紹介するポルトガルポルト大学を中心とする研究グループからの論文は、羽色が大きく変化させるメカニズムの一端を明らかにしたオススメの論文で6月12日号のScienceに掲載された。タイトルは「A genetic mechanism for sexual dichromatism in birds (鳥のオスメスの羽色のパターンを形成する遺伝的メカニズム)」だ。
研究ではオスメス共に同じ黄色の羽を持つカナリアと、オスだけが真っ赤な羽色をもつショウジョウヒワを掛け合わせたF1に、カナリアのバッククロスを繰り返すことで作成された、赤い色彩の分布がオスメスで大きく違う形質を安定して示す交雑種を用いて、この違いを生み出す遺伝的変異を特定しようとしている。
基本的にはバッククロスにより、ショウジョウヒワの一部の遺伝子がカナリアに流入することで、この形質ができたと考えられるので、カナリアとショウジョウヒワ、そして新しい交雑種の全遺伝子配列を解析し、新しい形質に関わる遺伝子の特定を試みている。
その結果、赤や黄色の色彩の元になっているカロテノイドを分解するBOC2と呼ばれる酵素遺伝子をコードする領域がヒワからカナリアに移っていることが確認された。さらにこの遺伝子の発現をオスメスで比べると、赤い色の分布の少ないメスで発現が上昇していること、そしてオスメス共に、色素のない羽に強く発現していることが明らかになった。すなわち、赤い色を壊す酵素の発現パターンが、羽色の分布を決め、またオスメスの違いを決めていることを示している。
以上のことから、羽色の分布という極めて複雑な形質も、BOC2遺伝子の発現調節を調べることでかなり理解できるのではという期待が持てる。
最後に、野生の鳥の羽色の分布を決める遺伝子を特定するために、オスメスの羽色の分布が大きく違うヨーロッパセリンやハウスフィンチの羽に発現している遺伝子を比較し、いくつかの候補遺伝子がリストできることを示すと共に、ヨーロッパセリンではヒワと同じようにBOC2を、オスメスの差を生み出す遺伝子として使っていることも明らかにしている。
残念ながら、複雑な模様ができるための遺伝子調節にまでは至っていないが、しかし一つのメージャーな遺伝子の調節領域の解析で、模様の形成という複雑なメカニズムに大きく近づけるという期待は湧いてくる。
2020年6月14日
私たちの細胞は概日リズムを刻んでおり、その結果活動期と休息期を繰り返していることから、薬剤による治療もこれに合わせて行うべきという話をよく聞く。しかし、細胞レベルでこの効果をはっきりと示した論文はあまり見たこともない。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、単純な実験だが薬剤の効果を確かめるためにはやはり細胞の活動性を考慮して効果を調べる必要があることを示した研究で6月3日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Potential circadian effects on translational failure for neuroprotection (神経保護剤のトランスレーショナル研究がうまくいかないのは概日リズムが関わっている可能性がある)」だ。
この研究の目的は脳梗塞に対する神経保護薬を開発することだ。広く知られるようになったが、拘束後できるだけ早く血栓除去をtPAなどを用いて行うことで、梗塞による神経障害を抑えることができる。ただ、これは血流再開の時間を短縮する治療法で、低酸素による神経細胞氏を守るものではない。
これまでの研究で、高酸素治療を始めとして、ラジカル除去剤、グルタメート受容体阻害剤などがマウスやラットを用いた研究で神経保護作用があることが示されており、実際に臨床で試されたものもあるが、残念ながらトランスレーション研究段階で全て効果が認められないという残念な結果で終わっていた。
著者らは、マウスの実験もヒトの治験も全て昼間に行われているが、人間とマウスでは活動性が昼と夜で逆なので、細胞はそれぞれ活動期と休息期にあるはずで、この差が保護剤の効果の違いの原因ではないかと着想した。
そこで、夜活動期のマウスやラットを用いて、血流遮断、再灌流実験を行うと、昼間では効果があった神経保護剤の効果がほとんど消失することがわかった。すなわち、保護剤は概日リズム上、休息期にある場合のみ効果がある。この結果から、人間でも夜間休息期に卒中が起こる場合は別だが、昼間に起こる卒中に神経保護剤が効かないことはうなづける。さらに、卒中の90%以上は昼間に起こるので、ヒトでは保護剤が聞かないことになる。
この概日リズムに従う差が細胞レベルで起こっているかどうかを、マウスの皮質ニューロン培養で確かめている。概日リズム遺伝子Per1,per2をデキサメサゾンで誘導し、高い時を活動期、低い時を休息期として、酸素とグルコース遮断を行い、この時の保護剤の効果を調べると、大きな差ではないが休息期のみで効果がみられる。さらにこの効果が、細胞死のカスケードを抑えることで起こっていることも明らかにしている。
以上が結果で、細胞の実験は差が小さいため、他にも要因があるかもしれないが、私たちの細胞がいかに概日リズムを取り込んで生きているかがよくわかった。簡単な実験だが、着眼点は面白い。