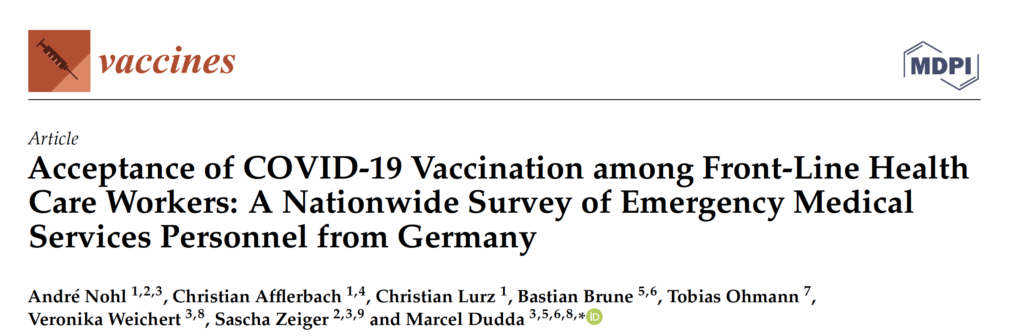2021年7月28日
ガン組織をsingle cell RNA seqで解析した論文は数多くあるが、最大の問題は遺伝子の解析だけでは、検出しているT細胞がガン特異的に反応しているのかどうかわからない点だ。ガン抗原の数が限られている場合は、MHCとペプチドのテトラマーを用いて、特異性を同じ組織で確認することも可能だが、実際のガンでは様々な抗原に反応しているはずで、組織に存在したキラー細胞がガンに反応しているのかどうかは、解析したT細胞の抗原受容体(TcR)を特定し、再構成して、ガンに反応するか調べるという大変な仕事が待っている。
今日紹介するハーバード大学からの論文はまさにこの大変な仕事をやり切った力作で、これからのガン免疫療法に多くの示唆を与えてくれる研究だと思う。タイトルは「Phenotype, specificity and avidity of antitumour CD8 + T cells in melanoma(メラノーマの抗腫瘍CD8T細胞の形質、抗原特異性、そして抗原結合性)」で、7月21日Natureにオンライン掲載された。。
この研究は、5人のステージ3/4のメラノーマ患者さんからバイオプシーで採取したガン組織の細胞と、末梢血をガン細胞で刺激したT細胞についてsingle cell RNA sequencing (sRNAseq)を行い、形質とともにT細胞についてはTcR配列を決定している。このような研究は数多く存在し、少なくともメラノーマでは、組織内に高い頻度で特定のTcRが現れている。すなわちガン抗原特異的T細胞のクローン増殖が起こっていると想定される。
この想定を、出現頻度が高まったガン組織でクローン増殖が起こったと考えられるキラーT細胞のTcR遺伝子を再構成し、正常のT細胞に遺伝子導入し、TcRが反応している抗原を特定したのがこの研究の凄い点だ。そして、ここまでやらないとわからないことは多かった。詳細を省いて、結論を箇条書きにすると、
出現頻度の高いTcRは期待通り、ガン組織に反応しているキラー細胞だった。ただし、ガン抗原(ネオ抗原orメラノーマ特異抗原)に反応するTcRを持つT 細胞のほとんどは、いわゆる抗原刺激後疲弊したTex細胞だった。 組織キラーT細胞でガン抗原以外に反応するTcRの多くはウイルス抗原に反応しており、そのほとんどはメモリー型の細胞だった。 メラノーマ特異抗原に反応するキラー細胞TcRの抗原結合性は低いが、ネオ抗原を特定できたTcRとネオ抗原との結合性は高い。また、この結合性の解析から、突然変異によりMHC分子との結合性が高まる場合に、TcRの結合性が上昇した。 疲弊型Texは末梢血にはほとんど流れてこないが、末梢血でガン組織と同じTcRを持ったTexが多く検出されると、患者さんの予後が悪い。逆に、メモリー型の細胞が多い患者さんでは、予後が良い。 結果は以上だが、この徹底的な研究により、以下のことがはっきり理解できた。
ガン抗原特異的T細胞は組織中に存在し、増殖している。 ただ、疲弊型なのでほとんどは組織内で消滅する。逆に、PD-1抗体でこの疲弊を止めることの重要性がわかる。 これまでガン組織からガン抗原特異的T細胞を分離する試みが行われているが、すぐに疲弊型のT細胞へ分化してしまうことを考えると、TIL採取前から様々なチェックポイントを抑制し、組織内でのメモリー型を増やす必要がある。、また、培養でも疲弊を避ける方法が必要。 組織内に高い頻度で現れるTcRの解析は、プレシジョンメディシンにとって重要な情報になる。 疲弊型のT細胞をさらに前駆細胞型と、分化型に分けることができるが、前駆細胞型の多い患者さんの方がPD-1抗体治療に反応する。 この結果が他のガンにも適用できるのかどうかはわからないが、チェックポイント治療の方法や、組織内の自己キラー細胞を活用する治療に向けた大きな一歩が記されたと思う。
2021年7月27日
以前、ペーボさんたちが発表した、ネアンデルタール人由来のcovid-19重症化に関わる遺伝子多型(https://aasj.jp/news/lifescience-easily/13992 )、および抵抗力に関わる遺伝子多型(https://aasj.jp/news/watch/15012 )について紹介した。これらの論文は、我々の遺伝子が強い感染圧力の元で進化してきたことを示唆している。しかし、これら遺伝子多型がネアンデルタール人で起こったコロナウイルス流行の爪痕である可能性は低いと思う。
では、かって人類が遭遇したコロナウイルス流行の爪痕を知るための方法はないのだろうか。今日紹介するオーストラリア・アデレード大学からの論文は、ウイルスタンパク質と直接相互作用を行うホスト側の遺伝子に絞って、世界各地域をカバーする1000人ゲノムデータを比較し、多くの遺伝子領域で25000年以上前のコロナウイルスによる選択の爪痕が見られることを示した研究で、8月23日号Current Biologyに掲載予定だ。タイトルは「An ancient viral epidemic involving host coronavirus interacting genes more than 20,000 years ago in East Asia(東アジアで20000年以上前におこった、コロナウイルスと相互作用する遺伝子が関与するウイルス流行)」。
これまでコロナウイルスタンパク質と相互作用を示すホストタンパク質は400種類ぐらい特定できているが、この研究では、これら遺伝子領域に頻度高く保存されている領域がないか調べ、なんと日本人を含む東アジア人だけで、約50種類の遺伝子にselective sweepと呼ばれる保存されたストレッチが、高い頻度で維持されていることがわかった。
すなわち、東アジアだけで、コロナウイルスと関わる約50種類のタンパク質をコードする遺伝子の多様性を、強く低下させる出来事が、起こったことを示している。もちろん、他のウイルス感染により同じことが起こる可能性はあるが、これまで知られている他のウイルスタンパク質と関わる分子をコードする遺伝子で同じ検索を行っても、ほとんど引っかかってこないことから、コロナウイルスの流行が起こった確率が最も高い。
この領域の保存された長さから、いつ選択されたかなどが推定できるが、これらの遺伝子の頻度は770−970世代前に集中していることがわかる。今回リストできた全ての遺伝子で、この選択はほぼ同じ時期(世代数から25000年以上前と計算できる)に起こり(すなわち頻度が上昇し)、その後は大きな変化はない。
それぞれの遺伝子の発現と多型との関係を調べると、基本的には発現調節領域に関する多型で、遺伝子そのものの機能を変化させる変異はほとんど観察できない。
面白いことに、この遺伝子多型のほとんどは、肺を中心に、Covid-19の病態に関わる組織や臓器に発現しているが、重症化や感受性に相関するゲノムを調べたときに必ず登場する免疫機能との相関は低い。現在のcovid-19への抵抗力や感受性を調べると、当然免疫系の細胞と強く相関する遺伝子多型がリストされるが、最初からウイルスタンパク質との相互作用でホストの遺伝子を選ぶと、免疫系の遺伝子は完全に除外されるのだろう。
以上、読者には本当かどうか確かめがたい結果だが、東アジア人の先祖が25000年前に受けたレッスンが、もし、東アジア人の抵抗力につながっているなら、デルタ型も何とかしのげるかもしれない。
2021年7月26日
善玉コレステロール、悪玉コレステロールという用語は、それぞれHDL、LDLに対応する言葉として一般の方に広く認知されている。それぞれが、なぜ身体に良かったり悪かったりするのかについては、理解が進んできているが、炎症という切り口は、両者の機能を考える上で重要だ。
というのも、動脈硬化にせよ、糖尿病にせよ、同じ内因性炎症メカニズムが核になっていることが明らかになり、LDLやfreeコレステロールが炎症を誘導する細胞内のインフラマゾーム形成を活性化することがわかっている。
一方、HDLの作用は血中のコレステロールを回収する働きで善玉コレステロールと呼ばれているのだが、実際にはLPSを中和することで炎症に直接関わることも知られている。
今日紹介するワシントン大学からの論文は、小腸で作られるHDL3が門脈を通って直接肝臓に入り、クッパー細胞のLPSによる活性化を阻害して炎症を抑える働きがあることを示した研究で7月23日号Scienceに掲載された。タイトルは「Enterically derived high-density lipoprotein restrains liver injury through the portal vein(腸由来のHDLが門脈を介して肝臓障害を抑える)」だ。
まずタイトルを読むと、「HDLは肝臓で作られているのに、腸で合成されたHDLがなぜ必要になるの?」と違和感を感じる。実際、HDL合成に関わるコレステロールトランスポーターABCA1は小腸でも強く発現しており、小腸でのHDL合成の必要性はよくわかっていなかった。
この研究では、まず小腸で合成されるHDLは、肝臓で合成されるHDLより小さなサイズのHDL3と呼ばれるタイプで、門脈中のHDLのほとんどを占めることを明らかにしている。
そして、この小型のHDL3こそがLPS結合性タンパク質と結合して、LPSと自然免疫に関わるTLR4との結合を阻害し、これにより肝臓のクッパー細胞の自然炎症誘導を抑えていることを明らかにしている。実際、肝臓で合成されるHDL2ではこの活性は低い。
この結果から、肝臓で合成できるLDLではなく、門脈へと移行できる小型LDL3をわざわざ小腸で合成することで、肝臓を炎症から守っていることが想像される。そこで、小腸の2/3を切除することで、腸内細菌叢のLPSの門脈への流入を高める方法を用いて誘導する肝臓の炎症モデルを用い、このとき残った小腸でのHDLの合成をノックアウトする実験を行い、期待通り炎症が増強することを確認している。
HDL合成に関わるABCA1遺伝子発現誘導にLXR核内因子が関わることが知られている。そこで、小腸切除による肝臓炎症誘導モデルマウスに、経口的に定量のLXR刺激化合物GW3965を投与すると、この薬剤は残っている腸管内だけで働き、腸内でのHDL合成を高め、肝臓での炎症や線維化遺伝子の発言を抑え、肝臓の炎症を抑えることを明らかにしている。
詳細なデータは全て割愛して結果を紹介したが、なぜHDLをわざわざ小腸で合成する必要があるのか、その理由がしっかり理解できた。
著者らは、この作用がLPSだけに限らないと考えているようで、もしそうなら経口的に少量のGW3965を服用することで、肝臓の炎症一般をかなり抑える可能性すら存在する。期待したい。
2021年7月25日
C型ニーマンピック病はリソゾームに局在するNPC1およびNPC2遺伝子の変異により、リソゾームからコレステロールの排出が障害された結果、リソゾームに脂肪や糖脂質の蓄積が起こり、神経変性が起こる。ただ、このリソゾームの変化から神経変性への過程については理解が進んでおらず、結果リソゾーム内での蓄積を阻害する間接的な治療を除いて、根本的な治療法は現在のところ存在しない。
今日紹介するテキサス大学からの論文は、細胞内の異常DNAを感知するcGASの下流でインターフェロン誘導に関わる分子STINGのリソゾームへの移行機構を研究する中で、ニーマンピック分子NPC1がSTING活性化と抑制に深く関わり、ニーマンピック病の背景にSTING活性化とそれによる炎症が存在することを示した。この発見は、ニーマンピック病病態理解を大きく進展させたこの分野では画期的な研究で、7月21日のNatureに掲載された。タイトルは「Tonic prime-boost of STING signalling mediates Niemann–Pick disease type C(STINGの活性化と強化がC型ニーマンピック病に関わる)」だ。
cGAS-STINGシグナルが細胞内DNAセンサーとして働いて、IRF3を介するインターフェロンシグナルカスケードを活性化することは広く知られているが、このシグナル経路の理解を難しくしているのが、この過程でSTINGが小胞体からゴルジ、そして最後にリソゾームへと移行する過程と、シグナルとの関係だ。この過程をヒントに、GAS-STING経路がオートファジー制御因子として進化したことを示唆する論文については2年前に紹介した(https://aasj.jp/news/watch/9877 )。
この研究ではSTINGのオルガネラ間の輸送に関わる分子を特定する方法を用いて、261種類の分子を特定し、その中からリソゾームへ移行したときにSTINGと結合する分子としてNCP1を発見した。すなわち、リソゾームストーレージ病の最も有名な分子と自然免疫の核となる分子が出会った。
そこで、まずNPC1遺伝子ノックアウトマウスを用いて、STINGの状態を調べると、STINGの小胞体からGolgiへの移行が促進され、さらにリソゾーム移行による分解が抑制され、最終的にSTINGの高い活性が維持され、インターフェロン誘導が持続することを発見する。すなわち、NCP1が存在しないと炎症が長期に続くことが明らかになった。
この結果は、ニーマンピック病を自然免疫の観点から捉え直すことの重要性を示しており、この方向で研究が行われている。様々なノックアウトマウスを用いた膨大なデータなので、詳細を省いて要点をまとめると次の様になる。
NPC1ノックアウト細胞ではリソゾームからコレステロールが出てこないため、小胞体でのコレステロール量が減り、小胞体からゴルジへの小胞体輸送が活性化される。もともとSTINGは、DNAと結合したcGMPにより生成されるセカンドメッセンジャーにより活性化されるが、小胞体輸送が活性化されると上流のシグナルとは無関係に、STINGがSERBP2に結合し、ゴルジ輸送経路へと乗せる過程自体がSTINGの活性化を誘導する。 リソゾームでNCP1はSTINGのアダプターとして働き、STINGのリソゾーム移行による分解を促進する。すなわち、NCP1ノックアウトではSTINGの分解が進まず、結果活性化されたSTINGシグナルが抑制されず残る。 NCP1ノックアウトマウスの神経病態は、STINGノックアウトで著名に改善する。すなわち、ニーマンピック病はストーレージ病だけでなく、神経の自然炎症が増強した結果発症する病気として捉えられる。 ニーマンピック病の症状は、STING下流のシグナルをノックアウトすることで改善するが、cGASの様な上流シグナルをノックアウトしても改善しない。すなわち、細胞内DNAセンサーとは無関係に、STINGが活性化される。 NCP1ノックアウトによるSTINGシグナル活性化は、ミクログリアだけでなく、神経細胞自体の細胞死を誘導する。 以上、ニーマンピック病の原因分子、NCP1欠損、そしておそらくNCP2欠損でも、コレステロール動態が狂い、小胞体からゴルジ輸送を高める結果、上流のシグナルとは無関係にSTINGがゴルジ輸送システムに結合し、その活性化が誘導され、炎症シグナルがオンになる。さらにNCP1がはSTINGのリソゾーム移行による分解も抑制するため、スウィッチが入った炎症シグナルを止めることができず、炎症が持続する。その結果、神経細胞が直接、あるいはミクログリアを介する炎症により変性することで、ニーマンピック病の神経症状が誘導されるという結果だ。
これまでストーレージ病として納得してきたのとは全く異なるメカニズムが示された。この結果が重要なのは、STINGによる自然炎症シグナルを抑制する様々な薬剤がニーマンピック病にも利用できる可能性が出てきたことで、個人的には大きく期待したいと思っている。
2021年7月24日
昨日は、既存の分子標的薬を論理的に組み合わせるガン治療を紹介したが、今日紹介するイリノイ大学からの論文は、ガンが増殖のために獲得してきたERストレスに対応するメカニズムを逆手にとって殺してしまう、新しいメカニズムを用いた抗ガン剤の開発研究で、7月21日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「A small-molecule activator of the unfolded protein response eradicates human breast tumors in mice (小胞体ストレス応答を活性化してマウス内でヒトの乳ガンを根絶する)」だ。
この研究を理解するには、Anticipatory Unfolded Protein Response活性化を理解してもらう必要がある。unfolded protein response(=小胞体ストレス反応:UPR)は、京大の森さんが発見した機構で、タンパク質が折り畳まれる前に小胞体に停留するストレスを感知するシステムで、シャペロンの合成を促し、翻訳を抑えてストレスを除去する。正常細胞より高い増殖を必要とするガン細胞では、増殖シグナルの下流で、予めUPRを適度に活性化して、通常より多くのタンパク質を急に合成して高い細胞活動を維持する仕組みを持っている。
このグループは、ガンがエストロジェン受容体(ER)を介して急速な転写を行うために、ER依存的にUPRを活性化する経路を、化合物を用いてさらに高めることで、小胞体ストレスをさらに上の細胞死を誘導する段階に誘導して、ガン細胞を殺す方法の開発を目指して研究してきた。これまでの研究でBHP1と呼ぶER結合性の化合物を開発し、ERを発現する細胞を完全に殺せることを示していたが、臨床に用いるには様々な問題があった。
メディシナル・ケミストリーを用いて、BHP1を至適化したErSOと呼ぶ化合物を開発し、この効果を確かめるための実験を行ったのがこの研究で、ErSOがER発現細胞特異的に、UPRを活性化し、細胞死を誘導して乳ガンの治療に使えるか確かめている。
ER陽性の乳ガンには、すでに治療のためにER阻害剤が用いられているが、これはER機能を抑制することで効果が発揮されるが、細胞を直接殺す作用はない。一方、ErSOがERと結合するとPLCγを強く活性化しUPRを活性化することで、直接細胞死を誘導できる。
結果をまとめると、
ERを発現する乳ガン細胞株は全てErSOにより迅速に細胞死に陥る。 マウスに乳ガンを移植する実験型で、ErSOは完全にガン細胞を根絶し、少なくとも半年は再発がない。 静脈にガン細胞を注入する転移ガンモデルで、ErSOは完全にすべての転移ガン細胞を根絶できる。 エストロジェン非依存性の乳ガンもERを発現していれば、ErSOで根絶できる。 低用量でわざと再発を誘導して、耐性が獲得されているか調べると、全く耐性は獲得されておらず、通常用量で根絶できる。 この効果は、おそらくSrcなどの活性化が見られるガン細胞のみ誘導され、正常のER発現細胞にはErSOの影響は少ない。 これまでの生化学的研究から想定される様に、ErSOはSrcを介してPLCγを活性化し、強いUPRを誘導することで、ER陽性細胞を殺す。 以上が結果で、ERが一定レベル発現されて居れば、ER自体の機能とは無関係に、UPR反応をん防御的に高めているガン細胞のみを、殺せるという、あまりにも良くできた結果だと思う。もし臨床応用まで進めばER発現しているガンに限るが、画期的な治療法になると思う。また、ER自体の機能とは無関係に、UPRを活性化できるので、治療の難しい卵巣ガンにも効果が期待できる。なんとか、臨床まで持ってきて欲しいし、同じメカニズムの化合物を他のシグナル経路でも開発して欲しいと思う。
2021年7月23日
今日、明日と、最近気になった分子標的治療について紹介したい。まず今日紹介する上海ガン研究所とオランダ・ガン研究所からの論文は、甲状腺ガンや肝臓ガンなど様々なガンに用いられているレンバチニブの肝臓ガンへの効果がEGFR 受容体と組み合わせることで大きく高まることを示した研究で、7月21日号Natureに掲載された。タイトルは「EGFR activation limits the response of liver cancer to lenvatinib(EGFR活性化が肝臓ガンのレンバチニブに対する反応を制限する)」で、7月21日号のNatureに掲載された。
分子標的薬は一般に一つの分子を特異的に抑制することを目標にするが、一部のキナーゼ阻害剤は、複数のキナーゼをまとめて阻害する力を期待して利用されている。我が国のエーザイが開発したレンバチニブはその代表で、VEGFR、FGFR、PDGFR、c-Kit、RETなどのシグナルを同時に抑えることが知られ、特に手術ができない肝臓ガン、甲状腺ガンに世界中で利用されている。
ただ、肝臓ガンの中でレンバチニブに反応するのは2割程度で、効果を上げるための研究が進んでいた。この研究では、まず、レンバチニブに反応しなくなったガン細胞のリン酸化に関わる酵素をCRISPR/Cas9でシラミ潰しにノックアウトし、レンバチニブの作用を再活性化する分子を探索し、EGFRシグナル経路をノックアウトすると、肝臓ガンがレンバチニブに反応する様になることを発見する。この発見が、研究のハイライトで、あとはEGFRを阻害する薬剤との組み合わせで同じ効果が得られるか、細胞株を用いて調べ、以下の結論に達している。
EGFR発現の高い肝臓ガンでゲフィニティブなどのEGFR阻害薬が、レンバチニブと強調して高いガン抑制活性を発揮する。 複数のキナーゼを阻害するからと言って、レンバチニブと同じ効果があるわけでははなく、ソラフェニブはEGFR阻害剤と組み合わせても効果がない。これは、レンバチニブがソラフェニブにはないFGFRを阻害活性を持つからで、EGFRを高発現する肝臓ガン細胞の場合、FGFRとEGFRの両方を阻害して、下流のMEK-ERK経路とともに、PAK―ERK経路を抑制することで、FGFR-MEK-ERK経路を完全に遮断でき、ガン増殖を抑えられる。 レンバチニブの場合、FGFR阻害効果だけではなく、VEGFR阻害による血管新生を抑制するとともに、NK細胞の活性を高めることも、ガンの制御に貢献している。 以上の結果に基づいて臨床利用についての研究を行い、
ガン組織検査でEGFRの発現が高い患者さんは、レンバチニブの効果が低く、言い換えるとレンバチニブで増殖が抑制されると、EGFR経路を用いてFGFシグナルをバイパスして、レンバチニブ効果を制限している。 治療に反応しなくなった12例の肝臓ガン患者さんを対象に、レンバチニブとEGFR阻害剤ゲフィニティブを併用すると、4例でpartial response、4例でガンの進行抑制が見られた。 結果は以上で、現在利用されている薬剤の組み合わせで効果が得られていることから、有望な治療法になると期待できる。ただこれほど論理的な治療の場合、万策尽きて利用するのではなく、乳ガンと同じ様に、ファーストラインの治療として、アジュバント治療、さらにはネオアジュバント治療としても使っていける可能性がある。これが成功すると、肝臓ガンの治療成績は飛躍的に高まるではと期待している。
2021年7月22日
私にとって色素細胞は、血液細胞と並んで最も馴染み深い細胞だが、メラニンが形成される複雑な過程は、今なお把握し切れていない。実際、メラニンは「黒」か「白」かという単純なものではなく、メラニン自体EumelaninとPheomelaninに分かれ、皮膚の色の違いをもたらす。さらには、メラニンはメラノゾームと呼ばれる細胞内小器官で合成されたあと、細胞間移行によりケラチノサイトに受け渡され、この細胞過程でも色素の濃さが変化する。そして、これら全ての過程を調節するのがMSHそその受容体MCRシグナルで誘導されるマスター遺伝子MITFで、これら全ての過程の総合として、私たちの皮膚や毛の色が決まっている。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、ミトコンドリア膜のNNT(nicotinamide nucleotide transhydrogenase)を介する還元反応が、メラニン合成経路の酵素活性を変化させて、皮膚のメラニン量を変化させる可能性を示した研究で、少しマニアックだとは思うが、皮膚の色素量を変化させる新しい介入ポイントとして可能性のある標的になるように思う。タイトルは「NNT mediates redox-dependent pigmentation via a UVB- and MITF-independent mechanism(NNTは酸化還元反応依存性の色素形成をUVやMITF非依存的に行う)」だ。
タイトルを見て、メラニンや色素細胞形成のマスター分子MITFに依存しないで色素形成を変化させられるのか、と驚いて読んだのだが、実際には勘違いで、この経路は転写とは関係なかった。おそらく活性酸素とメラニン形成の関係を研究するためだったのではと想像するが、メラニン形成メラノーマ細胞のNNT(プロトン勾配を用いてNADH―NAD反応を調節、活性酸素を調節している)をノックダウンする実験をまず行い、NNT が欠損するとメラニン合成が高まることを発見する。
この効果が、メラノゾームとメラニン形成の核過程が増強される結果だが、MITFによる転写経路を介さないことを確認したあと、この効果がメラニン合成の鍵分子、チロシナーゼが安定する結果であることを発見する。すなわち、チロシナーゼはNNTによる酸化還元反応が関わる何らかの経路を通して、チロシナーゼの分解に関わっていること、そしてNNTノックアウトによりチロシナーゼが安定化する結果、メラニン合成、メラノゾーム形成が増強されること、を明らかにした。
あとは、ゲノムデータベースを用いて、NNT遺伝子の多型を調べ、その中の11種類の多型が、皮膚のメラニン形成と相関していること、またこの多型のいくつかはNNT遺伝子発現量と逆相関することを明らかにしている。
最後に、NNT阻害剤を皮膚に塗布することで、メラニンの合成を増やして、紫外線から皮膚を守れることも明らかにしている。
残念ながらNNTによるミトコンドリア内のNAD;NADPH合成から、チロシナーゼ分解までの経路が明確になっていないので研究が必要だが、NNTをうまく増強することで、活性酸素を抑えながらかつ美白につながる方法も開発できるかもしれない。
以上が結果で、色素細胞に興味のある医療や美容の研究者には面白いヒントがあるかもしれない。
2021年7月21日
すでに6割の高齢者がワクチン接種を終えた。私たち夫婦も、昨年の秋mRNAワクチン治験論文を読んで期待したように、接種が終わった6月以降は海外旅行以外、かなりノーマルな生活に戻って楽しんでいる。ただ抗体ができているかどうかは直接確認できておらず、ワクチン効果は論文と自分自身の様々な感染症に対する経験から推察するしかないので、変異株が猛威をふるう今、気持ちが100%ノーマルになることはないだろう。
血中の抗体の上がり下がりのほとんどは、リンパ組織での免疫に関わる数種類の細胞の相互作用の様式の変化を反映したもので、この細胞相互作用が行われる場が、免疫後にリンパ節などで新たに形成される胚中心という構造だ。すなわち抗体が上昇するフェーズで胚中心が形成成長し、抗体が下降するフェーズでは胚中心が縮小、最終的に消滅する。このおかげで、迅速に抗体反応が起こり、また一定期間後反応が低下し、免疫の暴走が止まるようにできている。
今日紹介するロックフェラー大学からの論文は、免疫反応が暴走せず胚中心が退縮する過程を、生きたマウスのリンパ節の長期観察を含む様々なテクノロジーを動員して解析し、ヘルパー細胞から抑制性T細胞への転換が胚中心退縮の引き金になることを示した力作で、動物モデルではあっても免疫反応がこのレベルまで解析できるようになっているのかと、強い感銘を受けた。タイトルは「Expression of Foxp3 by T follicular helper cells in end-stage germinal centers(濾胞ヘルパーT細胞のFoxp3発現が胚中心の終期に起こる)」だ。
胚中心は、抗原を取り込んだ樹状細胞の周りに、B細胞とTヘルパー細胞が集まって、反応が進むリンパ組織内で起こる一種の炎症反応と見ることができる。この反応は極めて複雑だが、とりあえず上昇期はB細胞と濾胞Tヘルパー細胞(Tfh)の動態を抑えておけば、反応をモニターできる。一方、退縮期に入ると、免疫を抑える濾胞Treg(Tfr)が加わって、B細胞がTfhの支援を阻害すると考えられる。
この研究では、NP-OVAを抗原として、NPに反応するB細胞、OVAに反応しているTfh, Tfr、それぞれの動態を経時的に観察するモデル動物を用いて、抗原注射後支配リンパ節で見られる反応をモニターしている。詳しくは紹介しないが、脳研究の光遺伝学レベルのシステムが免疫でも揃っていて、胚中心の消長を細胞レベルで観察できるようになっている。結果をまとめると、以下のようになる。
Tfr機能マーカーFoxp3陽性細胞数は、胚中心の退縮が始まる前に急速に増加する。 Foxp3陽性細胞の振る舞いを、例えばB細胞との接触時間などを指標に観察すると、上昇期と退縮期では質的変化が見られる。さらに、上昇期、退縮期前でTfhとTfrが発現するTcRを調べると、上昇期では全く一致しなかった両者が、退縮期にはいると同じTcRを発現している頻度が高まる。 以上のことから、Tfrは胚中心外から移動してくるのではなく、TfhがFoxp3を発現して、Tfr型へ転換すると考えられる。実際、single cell RNAseqでそれぞれの遺伝子発現を調べると、退縮期のTfrは、TfhとTfrの両方の性質を持った細胞になっている。 最後に、タモキシフェンでFoxp3発現を強制誘導できるようにしたTh細胞を移植して胚中心を形成させた後、まだ上昇期の間にFoxp3をThで強制発現させると、胚中心が退縮を始める。 すなわち、胚中心の形成に関わったTfhが、一定の条件(TcRシグナル変化やTGFβシグナルなどが想像されるが、決定はされていない)下でFoxp3を発現し、T細胞とB細胞の反応を止めて、胚中心の退縮にも関わることが明らかになった。
今後、この仕組みが、長期記憶にも関わっているのかなど、面白い研究が続くように思う。抗体反応研究の総合力をまざまざと見せつける力作だと感銘を受けた。
余談になるが、ここで使われているシステムは、1980年代、私が留学していたRajewskyの研究室で開発していたシステムで、B細胞のイディオタイプをB1-8と記載されているのを見ると、40年前を懐かしく思い出した。
2021年7月20日
大学レベルのワクチン接種が始まったようだが、かなりの割合の大学生がワクチン接種を躊躇しているようだ。メディアでは、馬鹿げたSNSに惑わされている大学生のイメージを強調し、また河野大臣まで、SNS上のデマに惑わされないように、呼びかけている。
ところが、なぜワクチン接種を躊躇するのかインタービューしているTVのニュースを見て、少し驚いた。一人の女学生は、「mRNAワクチンはこれまで使われていないワクチンで、感染予防効果はわかるが、もっと長期に様子を見た後、決断したい」と答えていた。
すなわち、ワクチンの報道が始まった我が国で、新聞・TVなどの大手メディアや専門家が強調したまさに同じことを理由に、高い教育を受けた層もワクチン接種をためらっているように思えた。振り返ってみると、昨年の秋でも、「ワクチンの効果や安全性の確定には何年もかかる」のが普通だという一般論に基づく情報が多く流されていた。とすると、その専門 情報に納得して今もワクチン接種をためらう層は、決してSNSのデマに踊らされている層ではない。
現在では専門家、メディア、政府全員一致で、ワクチン接種一色の報道を続けているが、半年もたたないうちに言を翻されても、信用できないという気持ちもよくわかる。高い教育を受けた層の多くが、一般論でワクチンの問題を印象付けた報道や発言の結果ワクチン接種を今もためらっているなら、私たち専門家は反省すべきではないだろうか。
実際、このような刻々内容が変わっていく複雑な知識について、断片だけを専門家の意見として上から目線で提供することがいかに危険かをこの例は物語っている。事実、マスクからワクチンの安全性まで、その時々で専門家の意見も割れる。その時々の断片的知識だけで一般の方々が判断できるだろうか?
このような複雑な専門知識をそのまま伝えることは難しいが、しかしこの知識のインプットのあり方がワクチンへの態度として現れているのではと思いついて、医療従事者や医学生のワクチン接種の態度を調査した以下の論文に目を通してみた。
最後の論文を除くと、基本的には米国やドイツの病院で働く医師や看護師のワクチンに対する受容性を調べた結果だが、ほぼ一致した結果で、医師に比べて、看護師の受容性は低い。また、医療教育のレベルでも高いほど受容性が高く、低いレベルの教育だと受容性が低いという結果だ。他にも、男性の方が受容性が高く、また高齢者ほど高いというのも全ての論文で一致している。
極め付けは最後の論文で、米国の医科大学と歯科大学でワクチンに対する受容性を調べると、なんとワクチン接種を躊躇する歯科大学生は5割を超え、医学生と比べたとき、2.7倍の差があるという結果だ。
いずれも統計的に完全なデータとは言い難いアンケートに基づく論文だが、それでもワクチンの効果は、時間とともにわかってくる複雑な医学現象であるため、正しい知識を積み重ねることの重要性を物語っている。
では、このレベルの知識の提供をメディアで出来るかといえば難しいだろう。とすると、一番大事なのは不用意に一般論を振りかざさないことだ。すなわち、今回のように知識が刻々変化するとき、知識の提供がいかに難しいかをよく理解し、現在の一般論が、将来多くの人の判断を誤らせることがあることを反省すべきだと思う。
間違っても、ワクチン拒否の理由をSNSのデマのせいにして納得してはならない。梅北2期の参加型ヘルスケアプロジェクトではぜひ知識の提供のあり方についても議論を深めてみたい。
2021年7月20日
発酵食品の威力というタイトルで、Cellに掲載された論文を紹介しているのを、アレっと持った人も多いと思う。21世期に入って、Cell Metabolismを皮切りに、Nature Metabolism, Nature Foodなど発刊がが続いてきたが、これは編集者たちが、食、栄養、代謝などが21世紀の重要な分野であることを認識し、その促進をジャーナルの側でも支援しようと考えているからだろう。
この背景には、感染性(communicable)、非感染性(non-communicable)疾患を問わず、様々な病気の理解に栄養、代謝についての解析が必須であるという確信とともに、例えば特異的因果性を追求する分子標的薬とは違い、栄養や代謝の身体への作用を調べるためには、これまでと全く異なる総合的で革新的な方法論が必要と考えているからだろう。
その結果、今日紹介するスタンフォード大学からの論文のように、毎日の食事の効果を総合的に調べるだけといった論文がCellに掲載される時代が来た。タイトルは「Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status(腸内細菌叢を標的にした食事は免疫状態を変化させる)」で、8月5日号Cellに掲載された。
研究ではまず、BMIが平均25の、既往歴がない健康成人(平均52歳)を39人選び、高繊維食グループと、発酵食グループに分ける。被験者は、あらかじめ決めておいた繊維の多い食品、発酵食品の中から、自分の好きな食品を選んで、4週間かけてそれぞれの食品の量を増やし、それを6週間維持する。その後は自分の好みで、それぞれの食品を選べるようにして、さらに4週間すごす。その間に、腸内細菌叢、便の代謝物検査、血液の炎症性サイトカイン、様々な細胞シグナル等々、総合的解析を合わせて、それぞれの食品の身体への効果を見ている。
重要なのは、数多くの食品の中から選ばせるという形で、生活に合わせた長期コホート研究がしやすくしていることで、従来のXXヨーグルトだけを飲ませるといったコホート研究とは全く異なる。すなわち生活スタイルそのものを問題にしている。結論的にいうと、実際に身体に起こった様々な変化から、どのタイプの食事を取ったのかを、かなり予測できる。この時、最も予測に貢献するのが血液のプロテオミックスで、それに続いて細菌叢、そして細菌叢のプロテオミックスになっている。すなわち、食品は私たちの体を確実に変化させる。
多くの結果が示されており、まとめにくいのだが、面白いと思った結果だけ箇条書きで紹介する。
高繊維食グループでは、期待通り便が柔らかくなる。一方、発酵食を多くとると、お腹が張る。 これまで高繊維食と細菌叢の多様性の相関が示唆されていたが、17週間では大きな変化は見られない。一方、細菌の絶対数は増加しており、便の細菌由来代謝物は増加する。おそらく、摂取した植物繊維の量が、細菌叢のキャパシティーを超えていると考えられる。一方、発酵食品を多くとると、急速に細菌叢の多様性が増加する。ただ絶対数はそれほど増えない。 高繊維食で増加すると言われるブチル酸の上昇は強くない。しかし、側鎖脂肪酸代謝については大きな変化が見られる。これは、細菌叢全体の代謝酵素の変化からも裏付けられる。 高繊維食を摂取した場合の炎症に関する変化は、摂取前の状態に左右される。すなわち炎症の低い状態の人は、繊維食によりますます炎症が抑えられるが、炎症が高い人は、逆に炎症が増強する。これらの変化は、Tfhの変化に相関する確率が高い。 酒好きには嬉しい結果だが、自己申告されたアルコール摂取は、食品による体の変化にあまり影響がない。 発酵食品を多くとると、最初の状態にかかわらず炎症を低下させる。これは血中のサイトカインレベル、および血液細胞中の免疫系細胞の数として表現される。 他にもあると思うが、気になった結果を箇条書きにした。炎症を下げるという観点では、発酵食品が良さそうな結果で、カッテージチーズ、ケフィア、バターミルク、コンブチャ(紅茶などを発酵させた飲料)、発酵野菜、発酵野菜飲料、ヨーグルトなどを選ばせており、参考になる。
基本的にはAIで食べている食品を推察できるぐらいの、人間の代謝状態の総合的把握が可能になってきたことが大きいが、生活に即した科学が基礎科学のトップジャーナルに掲載される時代が来たことは感慨が深い。