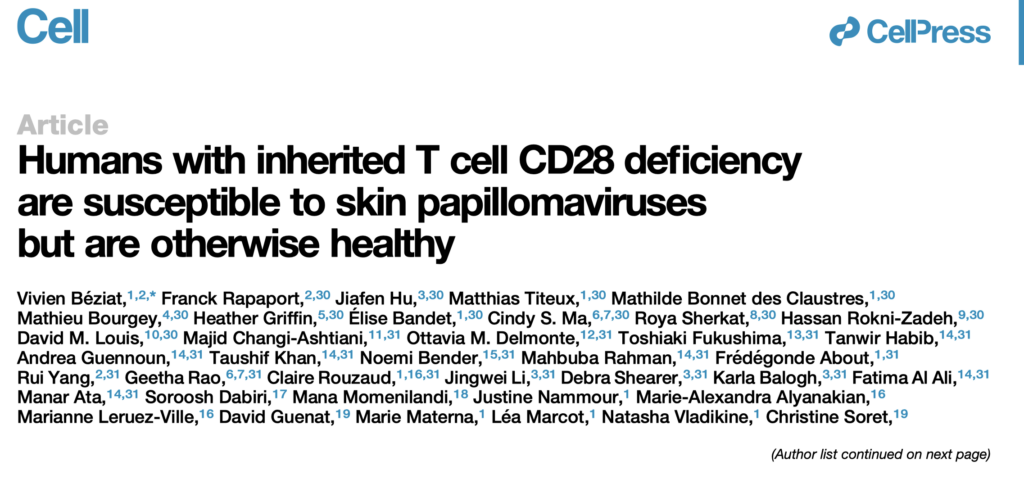2021年7月19日
重いうつ病に、様々な幻覚剤を用いる治療が急速に拡大している。臨床現場に最初に導入されたのは、麻酔剤ケタミンで、これまで何回も紹介してきた。麻酔剤ケタミンを幻覚剤と呼んでいいかどうか難しいところだが、ケタミンも解離体験を誘導することが知られている。
最近になって、幻覚を誘導するドラッグとして用いられていたキノコ、シビレタケに含まれているシロシビンが、セロトニン2A受容体の刺激を介して働き、抗うつ剤として働くことがわかって、FDAもFast Trackで2019年に認可している。最近発表されたThe New England Journal of Medicine(384,1402, 2021)では、抗うつ効果はセロトニン再吸収阻害剤と同等で、しかも副作用が少ない抗うつ剤として使えることが示された。
今日紹介するイエール大学からの論文はこのシロシビンの抗うつ効果の背景にある神経メカニズムを解明しようとした研究で8月18日号Neuronに掲載予定だ。タイトルは「Psilocybin induces rapid and persistent growth of dendritic spines in frontal cortex in vivo(シロシビンは前頭皮質の樹状突起スパインの迅速で長期間続く成長を誘導する)」だ。
研究は単純で、まずシロシビンがマウスにも幻覚を誘導する(頭を左右に振る動作を指標にしている)用量を決定した後、シロシビン投与後の内側前頭前皮質の樹状突起を長期間観察し、樹状突起スパインの成長を7日目と、34日目で記録している。
以前紹介したようにスパインの動態を長期間観察する方法(https://aasj.jp/news/watch/3680 )が開発されたおかげといえる研究だが、投与直後にスパインの数がコントロールに比べて増加し、退縮自体は両群で変化がないため、結果シロシビンにより前頭葉のスパインの数が増えることがわかった。
脳全体で見てみると、前頭前皮質だけでなく、レベルは低いが辺縁系や運動野でも見られる。ヒスタミン2A受容体の阻害剤でこの効果が消えることから、ヒスタミン作動性の神経では同じ効果が得られるのではと結論している。また、効果はメスでより強く見られる。
シロシビン投与直後の神経活動をみると、興奮数と興奮の振幅が高まっており、神経興奮を介するシナプス増強が起こっていることを示している。
重要なことは、こうして誘導されたスパインの変化は、1ヶ月間も維持できることで、ケタミンと同じく一度の投与で迅速かつ長期間続く効果が得られることになる。
結果は以上で、樹状突起スパインの増加などはケタミンの場合と似ているが、作用標的がヒスタミン2A受容体と、うつ病に最も関わりのある神経伝達系なので、基礎的にその効果のメカニズムが明らかになることは、この治療を後押しするように思う。
2021年7月18日
IL-3は一時、最も未熟な血液幹細胞の増殖因子ではないかと考えられたことがあった。事実、私も含めて造血コロニーアッセイを行う時、多能性の幹細胞コロニー形成を誘導する因子として、GM-CSFとともに、もっともよく利用した。また我が国では、2018年に急逝された東大医科研の新井さんと宮島さんがIL-3受容体の遺伝子クローニングに成功し、血液細胞の研究者にとっては、最もポピュラーなサイトカインだったと思う。
その後、c-Kit/SCFなど、骨髄多能性幹細胞の増殖に関わるストローマ細胞由来因子が明らかになり、またIL-3ノックアウトマウスが正常の造血機能を有していたことがわかり、T細胞由来因子であるIL-3はより炎症の調節に関わると考えられる様になった。特に臨床応用という面では、エリスロポイエチンやG-CSFなど他のサイトカインと比べて、大きく遅れをとった、というよりほとんど利用されていないのではないだろうか。
今日紹介するMITからの論文は、血液学者には懐かしいIL-3が、なんとアルツハイマー病を抑制する効果があることを示す研究で、7月16日Nature オンライン版に掲載された。タイトルは「Astrocytic interleukin-3 programs microglia and limits Alzheimer’s disease(アストロサイト由来IL-3がミクログリアをプログラムしてアルツハイマー病(AD)進行を制限する)」だ。
ADといえば、エーザイとBiogenがFDA認可にまでこぎつけたアデュカマブの薬剤としての有効性がメディアでも問題になっている。有効性については今後の臨床利用が明らかにすると思うが、アデュカマブの問題について、よく「Aβは神経変性に直接関わらないから」利用は意味がないなどという発言を聞く。ただ、この発言は間違っている。直接の神経変性がリン酸化Tauで起こるにしても、この過程を誘導する一つの要因がAβであることは何も変わらない。実際、Aβを異常発現させるトランスジェニックマウスは、ADの定番モデルとして利用されているし、またAPOEのADへの役割を考える時、Aβ蓄積の病因としての重要性は言を待たない。膨大な研究のおかげで、AD発症プロセスは、勉強さえすれば私の様な素人にもよく理解できるレベルに整理されている。勉強もしないで、メディア的な知識の断片だけで一般人へ発信することの問題を、アデュカマブ報道を見ていて感じる。すなわち、ADの引き金を引くAβ蓄積を抑制したり、あるいは除去することは今も重要な介入手段と言える。
今日紹介する研究の目的も、ADの引き金になるAβを除去してADの進行をとめる新しい方法の開発だ。しかし、このためにIL-3を着想したのには驚く。というのも、ADに対してIL-3が炎症性サイトカインとしてネガティブな影響があることが知られていた。
おそらく最初はこのネガティブな影響を調べるためだろう、IL-3ノックアウト(KO)マウスとAβ蓄積を起こりやすくした突然変異を導入した5xFADモデルマウスを掛け合わせて正常と比べると、驚いたことに、ノックアウトマウスの方がAβの蓄積が促進し、認知異常が高いことを発見する。この意外な発見がこの研究の全てで、あとは様々な実験を重以下の結果を得ている。
脳では、IL-3はアストロサイトにより定常的に分泌される、一方、その受容体はミクログリアが発現しているが、その発現レベルはミクログリア活性化に関わるTrem2シグナルにより誘導される。 人間のADの脳を調べると、IL-3量は正常脳と比べて特に変化はないが、IL-3受容体の発現量がADで高く、またIL-3受容体発現量とAβの蓄積量、および有病期間の間に強い相関が見られる。 面白いことに、ADの促進因子として知られるAPOE4遺伝型の人では特にIL-3Rの発現が高い。 IL-3はTrem2シグナルで活性化されたミクログリアがAβ蓄積部位に集積する過程に関わる。この集積を、iPS由来のミクログリアとAβ蓄積が強く起こる様にした神経+アストロサイト培養系で再現することができる。 ADモデルマウスにIL-3を持続注入すると、ミクログリアの集積がおこり、Aβの蓄積が抑制され、認知機能が高まる。 以上が結果で、Aβ蓄積がTau異常を誘導する前に、IL-3を脳内に注入することで、ADの進行を止められるということだ。思いもかけない病気ではあるが、IL-3の臨床利用がこんなところで復活したら面白い。また、アデュカマブの認可以降、同じ様な抗体薬の治験や承認申請が活性化されている様だが、IL-3の併用なども面白いかもしれない。
2021年7月17日
昨日発行されたサイエンスでは、表紙がハイエナの親子になっている。新型コロナウイルスのおかげで毎年楽しみにしているアフリカツアーが足止めされているだけに、当然強い興味がひかれ読んでみた。タイトルは「Rank-dependent social inheritance determines social network structure in spotted hyenas(階級依存的な社会的継承がハイエナの社会構造を決める)」で、7月16日号Scienceに掲載された。
内容は、全ての動物社会は遺伝的に支配された実力社会だと思っていた私の考えを改めるもので、ハイエナ社会は、どの家族に生まれたかが将来を決める階級社会であることを知った。
確かに読んでみると、動物社会も階級社会であることが納得でき、またそれが自然であると理解できるのだが、なぜ動物社会は実力社会と思い込んでいたのだろう。
もちろん家族は遺伝的に近いため、体格等々、遺伝=家族という話は出てくるのだが、サファリに参加しても、あるいはドキュメントを見ても、結局は極めて短い時間で観察できるスナップショットをみているだけで、強そうな個体が、闘争の結果ランクを上げるという話で終わる。
一方、今日紹介する研究は、ケニアのハイエナ集団をなんと27年間も観察し続け、その間の各個体の行動を克明に記録した膨大なデータに基づいている。その結果、ハイエナの母親と子供が同じ巣で暮らす1年は当然だが、その後巣を離れても、オスでは5年程度、雌では10年近くも母親と密接な関係を保って集団生活を送ることを示している。
この母親との強い絆のおかげで、もともと高い階級のお母さんとともに行動すると、餌の順番や、オスを選ぶ順番など、自然に得をすることが多くなる。その結果、母親の社会階級が子供に引き継がれることが予想されるが、観察された個々の個体のランクは、全く予想通りで、高いランクの母親の子供は、高いランクを占めるようになる。
ハイエナでは、ランクと寿命が相関するが、この結果高いランクの家族は長生きし、低いランクの家族は寿命が短い。おそらくこれも、ハイエナ社会で階級が固定するのを助けているのだろう。
なんとなく寂しい話だが、社会的階級が継承される動物は、サルや象など、結構いるようだ。いずれにせよ、30年近くアフリカでくる日もくる日もハイエナ家族を追いかけた努力のたまもので、頭が下がる。
長期間観察された動物社会というと、すぐ高崎山のサルを思い出す。ここでは、どの個体がボスザルになるのかがメディアでも話題になるが、高崎山のボスザルは全て貴族の生まれなのだろうか?
2021年7月16日
これまで数多くの相分離に関する論文を紹介し、何回もジャーナルクラブで論文を詳しく解説したので、他の分子と均一に混在していた特定の有機分子同士の相互作用が高まると、急に他の分子から分離し、濃縮した一種の液滴を形成する過程が、細胞内の分子局在と機能を支えていることは理解していただいていると思う。
考えてみると、特定の単位同士の相互作用が強まることで、他の単位の動きとは独立の同調した動きが現れる現象は、物理現象から生物の集団行動まで、様々なレベルで見られる。ただ、このような相転換をいかにして誘導するかが問題になる。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、熟練した運動の開始時に、小脳のプルキンエ細胞でこのような相分離現象を誘導することに成功し、神経ネットワークでも、物理学と同じ法則に従って相分離が起こることを示した研究で、7月8日号のCellに掲載されている。タイトルは「A neural circuit state change underlying skilled movements(神経回路の状態変化が熟練動作を支えている)」だ。
このような研究で最も難しいのは、一定の領域の神経細胞全体が、あたかも相分離が起こったように、急に同調して興奮するという状況が誘導できるタスクを設計することだ。著者らは、少し力を加えると、最初に押した方向へ一直線に動くレバーを設計し、マウスがこのレバーを右前肢で決めた目的に向けて倒せるように訓練し、この動作時に、右前肢に対応する小脳領域に存在する約500個のプルキンエ細胞を、Caイメージングで観察している。
理解しにくいとは思うが、よくできた課題だ。すなわち、最初にどう力をかけるかに成否がかかっており、したがって文字通りこの動作開始時点に「神経」を集中する必要がある。実際、最初の1ー2日ではちょっと触ってしまうとレバーが勝手に動いてしまい、目的に到達できる確率は低い。しかしマウスといえども、1週間もするとうまく神経を集中することができるようになり、成功率は9割を越すようになる。このタスクの設計が、この研究の全てだと思う。
期待通りというべきだろう、右前肢の運動神経が投射する領域の小脳の動きを観察すると、開始時点に多くの神経細胞が同調して興奮するのが見られる。すなわち、一種の相分離が観察される。さらに、同調した神経は興奮後の休止期間でも同調する。ただ、この同調は、それぞれの神経と結合している介在神経が同調して興奮することによって起こっていることも示している。
そして、この同調変化は、外界からの刺激により影響されるのではなく、動作開始時に神経を集中するとする内部からの同調シグナルにより起こっている。すなわち、熟練してくると、このように一定の領域の神経を同調させた運動調節ユニットを形成することで、正確な運動が可能になっている。実際、この同調した活動は、動きが始まった後で外界からこの動きを人為的に邪魔しても、変化が起こらない。
最後に、このような神経細胞の同調も、他の物理化学現象のどう調整と同じルールに従うことを、モデリングを用いて示している。このとき使われているのが、レーザーの同調を説明するための数学モデル、すなわち倉本オシレーション法則で、下部オリーブ核の神経同士の結合性が高まると同調して、この同調性がプルキンエ細胞へと伝達するモデルで、実際の相分離が完全に説明できることを示している。
この論文にも光遺伝学の開発者のDesserothの名前が入っているが、スタンフォード大学からの脳研究は、いつも一味違った深い思索が感じられ、難しくても本当に面白い論文が多い。相分離と言われて、「神経を集中する」意味がよくわかった。
2021年7月15日
6月26日、 MECP2が、従来考えられていたようにメチル化CpGに結合するのではなく、メチル化、あるいはハイドロオキシメチル化されたCAリピートと結合して、ヌクレオソーム形成を調節していることを示したストラスブール大学からの研論文で、この分野の研究方向を大きく変える可能性を持つ研究を紹介したところなのに(https://aasj.jp/news/watch/16028 )、今度はこれまで全くわかっていなかった、CpG island型プロモーターの転写を決定する分子BANPがスイス・バーゼルのミーシャ〜研究所から発表された。今、DNAメチル化についての研究が急速に進展しているのが感じられ、ワクワクする感じが湧いてくる。タイトルは「BANP opens chromatin and activates CpG-island-regulated genes(BANPはクロマチンを開いてCpG island により調節される遺伝子を活性化する)」で、7月7日Natureにオンライン掲載された。
house keeping geneと呼ばれる、細胞の維持に必須の遺伝子は、TATAボックスと呼ばれるプロモーターを使わず、CGくり返しが多く集まったCpG island(CGI)の中に存在するCGCGモチーフを転写開始点として使っていることが知られている。これまで、CGCGサイトがメチル化されるとRNAポリメラーゼ(PolII)のリクルートが阻害されていることはわかっていたが、標的がCGCGであまりに特異性がない領域のため、このモチーフに結合してPolIIをCGIプロモーターにリクルートする分子の発見は難航していた。
このグループは、ヌクレオソームとの結合性が低い、すなわちタンパク質との結合がほとんど起こらない人工的なCGCGエレメントをマウスES細胞の染色体に導入し、細胞内でこの人工的CGCGが間違いなく特異的なタンパク質と結合していることを、タンパク質の結合していない場所をメチル化して、結合部位だけを浮き上がらせる、single molecule footprintingという手法で確認している。
これがわかると、このモチーフに結合するタンパク質を特定できるという確信が得られ、最終的にCGCGに結合するタンパク質BANPを特定している。
ES細胞でBANPが結合している部位を調べると、期待通りhousekeeping 遺伝子のCGIプロモーター部位が1200個ほど特定できる。また、メチル化されたCGプロモーターには結合していない。逆に、3種類のDNAメチル化酵素が全て欠損したES細胞では、結合サイトが増える。次にこれまで知られているCGIプロモーターの転写に関わる分子存在下でBANPの機能を調べると、遺伝子発現を3000倍にも高めることができる。以上のことから、BANPがこれまで謎に包まれていたCGIプロモーターの転写を決定する因子であると結論している。
最後に、クロマチンやヌクレオソームとBANPの関係を調べると、BANPはヌクレオソームの結合を阻害し、クロマチンをオープンにしていることが推察される。これを証明するため、薬剤を用いて分解できるようにしたBANPを用いて、BANPを細胞から除去すると、1時間でクロマチンが閉じはじめ、またヌクレオソームが結合しはじめていることを示している。
以上まとめると、house keeping遺伝子のCGI型プロモーターは、メチル化されるとBANPは結合できないため転写できない。一方、メチル化されないとBANPが強く結合して、ヌクレオソームとの結合阻害を介して、クロマチンをオープンに保つことで、高い転写活性を維持する。
発生学的には、他のCGIとの関係や、そもそもメチル化によるプロモーターの不活化機構も合わせて理解することが重要だが、ガンや老化のように、メチル化自体が変化する場合、BANPの役割が高まってくる。いずれにせよ、クロマチンをオープンにする、ヒストン修飾とは異なる機構が続々明らかにされつつあるが、そのスピードは速い。
2021年7月14日
今回の新型コロナウイルスに対するワクチン開発を眺めていると、ワクチン開発が免疫学だけで無く、病原体についての深い知識に裏付けられたときに成功することがわかる。例えば、mRNAワクチンなどのワクチンが導入したスパイクタンパク質のpre-fusion型が、安定に合成するための分子生物学的工夫などは、まさにコロナウイルス生物学があって初めて可能になる。
ただ、このような工夫の上でも、現在ワクチンによって獲得した免疫がどの程度維持されるのかが問題になっている。この問題は、例えば持続的感染が維持される弱毒化ワクチン開発で実現する可能性はあるが、もともとウイルスゲノム構造が複雑なコロナウイルスでは、弱毒化の戦略が複雑で見えない。さらに、mRNAワクチンと感染から回復した人の抗体を比べた研究から、コロナウイルスの場合、弱毒化戦略が可能かは明確で無い。
そこで考えられるのが、成功しているワクチンの一部をスパイク抗原で置き換えるという戦略で、弱毒化ワクチンの典型であるハシカワクチンにスパイク遺伝子を導入したワクチンが研究されている。
今日紹介する英国サザンプトン大学からの論文は、我々に感染できる病原体に抗原を組み換える発想を、さらに先に進めるワクチン開発研究の話で、正直うまくいっているように思えないものの、着想は面白いので紹介することにした。タイトルは「A recombinant commensal bacteria elicits heterologous antigen-specific immune responses during pharyngeal carriage(遺伝子組換え常在菌を鼻咽頭に定着させて免疫反応を誘導する)」だ。
要するにヨーグルトを使ったワクチンが可能かという課題にチャレンジしている。ただ、腸内での免疫になるとあまりに複雑なので、もう少し入り口、すなわち鼻咽頭に常在するバクテリアをワクチンとして使えるかだ。
実際には、もともと髄膜炎を起こすナイセリア菌と競合関係にある病原性にない鼻腔常在のナイセリアラクタミカ細菌に、髄膜炎ワクチンの抗原としても使用されているNadAという分子が定常的的に発現するよう遺伝子組み換えを行い、これによりNadAに対する抗体と、髄膜炎菌に対する殺菌性抗体ができるのかを調べている。
もともと髄膜炎菌自体も鼻腔の常在細菌だが、常在細菌として振る舞う間はNadAの発現がうまく抑えられるような仕組みを持っており、免疫からも逃れている。この研究では定常的にNadAを発現させたラクタミカ菌を作成(NL)、さらに抗生物質で2日以内殺菌できること、また他の毒性が組み換えにより獲得されていないことなどを確認して、ボランティアの鼻腔に投与、90日まで常在させて抗体やメモリー細胞ができるか調べている。
鼻咽頭に注入すると、期待通り長期間維持される。しかし、どの時点でも呼気に細菌が含まれることはなく、またベッドをともにしているパートナーに組換えNLが感染することはない。
結果だが、常在菌をベクターに用いても、NadAに対するIgGやIgA抗体が形成され、さらにはメモリーB細胞が誘導できる。さらに、低いレベルではあるが病原菌に対して殺菌性を示す抗体もできる。ただ、現在使われているGSK社の髄膜炎ワクチンBexseroと比較すると、抗体価はかなり低いので、現段階では到底治験に進むという段階ではない。
もちろん鼻腔から吸入するワクチンの開発は数多く存在するが、常在菌をワクチンにするという発想を見たのは今回が初めてだ。というのも、もともと免疫反応を起こさないから常在できるので、このハードルを乗り越えることができるということは、私たちの細菌についての知識が高いレベルに達した証左になる。その意味で常識にチャレンジする試みにはエールを送りたいし、ともかく少しは抗体ができたことは、常在菌とは何かを考える意味でも重要だと思う。
余談になるが、この研究で用いられたBexeroワクチンは、組換えタンパク質を用いたワクチンで、髄膜炎に対していわゆる不活化ワクチンしか国産できていない我が国の現状も気になった。
2021年7月13日
これまで、実に多くの免疫システムに関わる多くの遺伝子欠損患者さんが発見されており、免疫システムが極めて複雑な細胞と分子のバランスの上に存在していることがわかっている。そしてついに、本庶先生がノーベル賞を受賞した分子PD-1が欠損した患者さんを、ロックフェラー大学を中心とする国際チームが6月28日Nature Medicineにオンライン発表した。タイトルは「Inherited PD-1 deficiency underlies tuberculosis and autoimmunity in a child(遺伝的なPD-1欠損症により結核と自己免疫が児童期に併発する)」だ。
Introductionを読むと、このグループは結核感染と免疫系遺伝子変異についての豊富な研究経験があるようだ。実際結核は感染防御だけで無く、病気の進行にも免疫システムが関わる複雑な感染症なので、人間で免疫システムを解析するには格好の材料と言える。
このような研究の中で、1型糖尿病、甲状腺機能低下、関節炎と、多臓器自己免疫病を3歳の時から罹患し、結核性の腹膜膿瘍で入院し、最終的に呼吸不全で亡くなった子供を経験する。そして、その兄弟がやはり感染症で亡くなったことを聞き、遺伝性の疾患を疑い、最終的に読み枠がシフトして、短いタンパク質ができてしまう、同じPD-1遺伝子の突然変異が両方の染色体で揃ったことを発見する。この突然変異の結果、PD-1は細胞表面に全く発現されないことも確認している。これまでPD-1自体の変異は発見されているが、機能が完全欠損した患者さんは世界初の症例らしい。
もともと機能阻害抗体を用いたチェックポイント治療が世界中で行われており、今更遺伝子欠損患者さんから得られる情報は少ないのではと思う人もいると思う。実際、この患者さんでは、激烈な結核とともに、多臓器の自己免疫病を発症し、様々な自己抗体が検出され、それとともにいわゆるサイトカインストーム状態が発生していることが示されているが、全てPD-1チェックポイント治療の副作用として広く知られている。
しかし患者さんをじっくり調べ、
結核感染は、PD-1欠損により結核菌に反応したリンパ球からのインターフェロンγやTNFといったサイトカイン誘導が低下していることが原因であることがわかった。 PD-1抗体投与の場合、最初に結核に対する免疫反応が高まり、その後低下することが知られているので、PD-1が欠損すると、最初免疫は増強されても、長いスパンでは特異的免疫も疲弊するのかもしれない。 ほとんどのリンパ球サブセットからのインターフェロンγ合成が低下しているが、同時にγδT細胞、MAITと呼ばれるinvariantTcRを発現した細胞、そしてNK細胞の数が低下していることが、結核への抵抗力がなくなる大きな要因になっている。 STAT3が遺伝的に活性化した患者さんに極めて類似した、double negativeT細胞の増殖とRORγT細胞の増加を伴う自己免疫反応が起こっている。これは、PD-1が欠損することで、IL-6やIL-23が過剰に分泌されるサイトカインストームの結果を反映している。面白いことに、同じチェックポイント治療に使われるCTLA4欠損患者さんでは、逆にdouble negative T細胞とRORγT細胞は低下している。 他にもあるかもしれないが、以上が結果の要点になる。
ある程度予想されているとはいえ、PD-1が欠損している場合でも、特異的な免疫反応が最終的に疲弊することがあること、さらに自己免疫病の基盤としてRORγT細胞が存在することから、RORγを抑制することでPD-1抗体の副作用を治療できることなど、重要なメッセージを示した研究だと思う。
PD-1と並んでCTLA4のチェックポイント機能がノーベル賞を受賞したが、このCTLA4と競合するCD80刺激分子がCD28で、なんとこの遺伝子変異による機能低下を示す症例が、同じロックフェラー大学から7月8日号のCellに発表されている。
詳しくは述べないが、この患者さんは、なんとヒトパピローマウイルス(HPV)2、およびHPV4に感染し、Tree Man Syndromeと呼ばれる、手足の上皮の過剰増殖で、木の枝が手足からのびたと思えるほど激烈な症状を示す。しかし、これ以外はほとんどT細胞の免疫異常は認められておらず、共シグナルシステムが互いに補い合う体制ができていることがわかる。このように、ヒトでの症例を重ねることの重要性がわかる論文だった。
2021年7月12日
引退してから、情報という非物理的因果性が如何に地球上に誕生したかに興味を惹かれ、最初の遺伝情報と生物の誕生、および言語の誕生に関する論文を調べてきた。その結果、無生物から生命と遺伝情報が誕生する過程については様々な機会に講義を行うようになったが、言語に関しては、現役時代の幹細胞研究があまりにかけ離れているのか、あまりお呼びがかからない。
しかし言語、特にシンボル化した話し言葉の誕生が、我がホモサピエンスを地球最強の勝者としたことは間違い無く、最も面白いテーマだ。言語発生に関するこれまでの研究をまとめて考えると、話し言葉は、音やリズムに満ち、しかも階層的に物を教えることが必要な精度の高い石器を作る工房で発生したのではないか、と考えるようになった。どちらにしても証明は難しいので、ワーグナーのオペラ、マイスタージンガーの2幕、Sachs親方が歌を歌いながら弟子のDavidに靴作りを教える場面を拝借して、「言語誕生のマイスタージンガーモデル」と名付け楽しんでいる。
いずれにせよ、言語と音楽の関係は、認知科学の中でも重要な領域であることは間違い無いが、今日紹介するフィンランド・トゥルク大学からの論文は、脳梗塞による失語のリハビリに、音楽、特に声楽曲を聞くことが効果があるという現象の脳科学的基盤を調べた研究でeNeuroの7/8月号に掲載された。タイトルは「Vocal Music Listening Enhances Poststroke Language Network Reorganization(声楽曲を聞くことにより梗塞後の言語ネットワークの再構成を促進する)」だ。
このグループは、音楽療法や、音楽がわからなくなるAmusiaと失語について研究を続けているグループで、昨年、梗塞後の失語の回復が、声楽曲を聞くことで促進される、という結果を発表している。
このメタアナリシスによると、例えば物語が語られるオーディオブックと比べたとき、歌のない音楽自体も失語回復により高い効果を持つが、声楽曲を1日1時間程度聴くことで、それ以上の効果が得られることを示すとともに、言語に関わる脳領域のは灰色髄の拡大が見られることを示していた。
今日紹介する研究はその延長で、同じ患者さんのMRI検査を行い、声楽曲を聴くリハビリによって、
脳構造的には、特に流暢な話し言葉に関わる重要な回路として知られる、中心前回と下前頭回をつないでいるFrontal aslant tractの結合が増加する、 機能的には声を聞いた時の上前頭回から中心前回にかけての領域の機能が高まる、 ことを明らかにしている。
なぜそうなのかは明らかでないが、声楽曲を聴くことで、言語力の強化が可能だが、この結果はまさに言語に関わる脳領域の活動性の上昇と、ネットワークの結合性上昇を伴っていることを明らかにした論文だ。
日本語の場合、言語に関わる領域も少し異なるので、同じことが我が国の失語患者さんでも言えるのかはわからないが、失語のリハビリの難しさを考えると、真面目に検討する価値は十分あると思う。
2021年7月11日
我々の体の多くの組織は、発生過程で増殖を繰り返して臓器を形成すると、ピタッと増殖が抑えられる。例えばイモリなどの脊椎動物は、組織が障害されるとこの抑制が外れ、もう一度完全な臓器を作ることができるが、我々哺乳動物になると、残念ながらこのような機能は失われている。このため、心筋梗塞のように、組織細胞が失われても、再生は起こらず、低下した心機能に体の活動を合わすしかない。
再生能力が欠如した臓器を再生するには、試験管内で準備した細胞を治療に用いる再生医療か、あるいは再生能力を再活性させる方法が存在する。幸い、最近の研究で、私たちの再生能力の一部は、抑制を外してやると再活性化することがわかってきた。
特に最近Hippo/Yap経路と呼ばれるシグナルで、多くの組織の再生能力が抑えられており、再生がないとされてきた神経細胞でも、この経路を遺伝子操作することで、再生が可能であることが明らかになってきた。また、今日取り上げる心筋梗塞後の心筋再生も、Hippo経路の遺伝子操作で再生を誘導できることが、マウスで示されてきた。
今日紹介するテキサス・ベイラー医科大学からの論文は、小動物の実験から可能性が示唆されたHippo/Yap経路の遺伝子操作による心臓再生誘導治療の可能性を、ブタを使って確認し、人間での知見に一歩近づけた研究で、6月30日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Gene therapy knockdown of Hippo signaling induces cardiomyocyte renewal in pigs after myocardial infarction(Hippoシグナルをノックダウンする遺伝子治療はブタの心筋梗塞後の心筋新生を誘導する)」だ。
心臓のHippo経路では、Mstと呼ばれるキナーゼと、そのアダプターSavが、マトリックスなど外界の刺激により活性化されると、転写因子Yap/Tazがリン酸化・分解されることで、その働きが抑制され、再生に必要なシグナルが誘導できないことが知られている。したがって、Hippoシグナルを抑えると、細胞の増殖が誘導される。
この研究ではアダプターSavをアデノウイルスに組み込んだshRNAでノックダウンすることで、心筋でのHippo経路を抑制し、心筋再生に必要なYap/Tazの機能再活性化を試みている。
すでにマウスでは様々な方法で明らかにされていることなので、この研究ではブタを用い、できるだけ人間の治療に近づけたプロトコルを開発しようとしている。そのため、NOGAと呼ばれる、心筋の活動を直接電極で測るカテーテルを用いて、梗塞部位を特定し、そこにウイルスベクターを注入するという手間のかかる実験を行なっている。
結果は上々で、
この方法で、遺伝子を心筋内に導入し、Yap/Tazを核内に移行させ、下流の遺伝子を誘導し、心筋を脱分化、増殖させることができる。 心筋梗塞モデルで、梗塞部位の拍出力の低下を止めることができる。 心拍出力維持は、Hippo抑制により梗塞部位で続く、残った心筋の脱分化、増殖、そして心筋が梗塞部位に再構成された結果だ。 さらに、再生部位にはおそらく炎症を介した血管新生を伴っており、心筋再生を助けている。 以上が結果で、基本的には治験前の前臨床試験になる。残念なのは、若いブタが使われており、中高年の心筋梗塞ではどうなのか、高齢の動物での結果が欲しいところだが、基礎的研究からここまで進んできたことで、心筋梗塞の遺伝子治療の実現も近い予感がする。
特に今回新型コロナワクチン により、遺伝子ベクターなどへの規制はかなり緩和されたと思うので、実現までの時間は短いと思う。現役時代は細胞移植ベースの再生医学のディレクターをしていたが、このままだと遺伝子治療に軍配が上がりそうな気がする。
2021年7月10日
オキーフさんとモザー夫妻のノーベル賞受賞以来、海馬に形成される外部世界の表象についての研究を紹介してきたが、外界の経験を内部イメージ化する過程は決して場所の記憶に限らない。おそらくほとんどの種類のエピソード記憶は同じ仕組みが使われていると考えられる。
実際、今日紹介しようと思っているロンドン大学からの論文の著者らは、2019年に、バラバラに提示されたイメージのセットから、最終的にそれぞれのセットの元になっている6種類のイメージが並んだ順番を、セットを見ながら推察する課題を学習したあと、同じルールに従う新しいイメージセットから、そのセットの背景にあるイメージの順番を構成し直すという課題が、ネズミの場所記憶での脳活動と同じように振る舞うことを発見した。すなわち、それぞれのイメージに対応する神経細胞の活動を脳磁図計で調べると、新しい経験をした後、ネズミの場所細胞で見られる脳活動と同じように、短い周期のリップル波発生に続いて、、それぞれのイメージに対応する神経ユニットの興奮が、経験した順番に順番に再生(replay)される。さらに、推察結果が正しいとわかると、今度は逆順に神経興奮が再生して、内部記憶を書き直すことがわかった。
単純化して解説すると、内部イメージの表象と、現実の経験とを常に参照しながら新しい内部イメージを作っていく脳過程を人間で調べることができるようになった。これを受けて、今日紹介する論文では同じ課題と脳磁図記録を、統合失調症の患者さんで調べる実験を行って、統合失調症の脳機能に切り込めないかチャレンジした研究で、8月5日号のCellに掲載予定だ。タイトルは「Impaired neural replay of inferred relationships in schizophrenia(関係についての推論を再生する過程が統合失調症では障害されている)」だ。
この研究にはもう一つの伏線がある。すなわち、マウスの遺伝的な統合失調症モデルでは、モザーさんたちが定義した場所細胞の記憶形成が障害されるが、このとき新しく海馬の場所細胞で起こった活動経験を、休んでいる時に再生するという過程が特に障害されていることが報告されていた。
だとすると、実際の統合失調患者さんでイメージの順番を推論する課題と、脳磁図計測を組み合わせれば、人間でも解析が可能になる。それを行なったのがこの研究で、結果をまとめると次のようになる。
バラバラに提示されるイメージセットから、元のイメージの順番を推察する課題の達成率は統合失調症で低下している。最終的には、子供でもできる課題なので、順番を言い当てることはできるのだが、正しい推論に至るまでの時間がかかる。 マウスの場所細胞の興奮で見られたのと同じで、新しいイメージを経験後、それぞれのイメージに対応する細胞が再興奮する再生が、統合失調症患者さんではほとんど特定できない。 ところが、再生の際に海馬で生じる高周期のリップル波の振幅は正常より大きい。明確な過程は解析されていないが、興奮抑制のバランスが壊れているため、再生が起こらない。 新しく経験したイメージは、それまでのイメージと対応した連関地図が脳内で形成される(すなわちAを見るとAとともにA’に対する領域も興奮する)。この連関地図が統合失調症では混乱している。 これらの結果を自分なりに考えてみると、統合失調症の人が経験を積み重ねて内部イメージを不断にアップデートしていくことが難しいことがわかるが、ではなぜそうなのかについては、高周期のリップル波の振幅が大きいだけでは、結局メカニズムはわからない。ひょっとしたら、統合失調症の人ではアップデートを拒否する内部イメージがすでに出来上がっているのかもしれないなどと考えてしまう。
こんな空想が広がるが、いずれにせよこの結果や、マウスとの共通性を勘案すると、統合失調症の患者さんは、方向音痴で場所記憶が苦手という話になるが、実際のところはどうなんだろう。