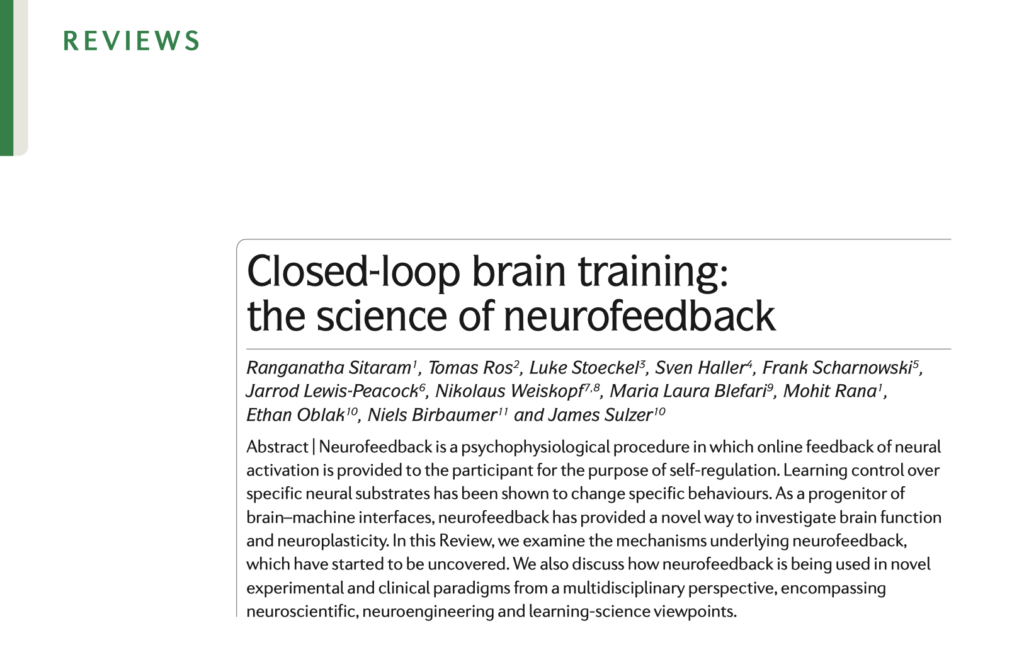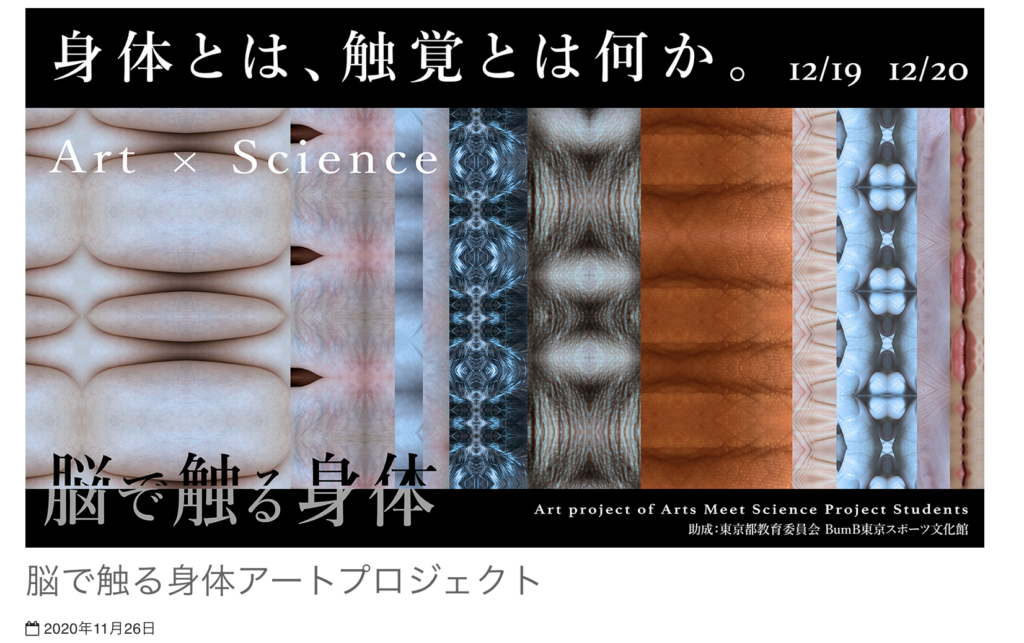2021年1月1日
元旦の論文ウォッチは、Covid-19論文にするか、今日取り上げるNeurofeedbackにするか迷ったが、Covid-19はいずれ収束するので、やはりもっと未来に開かれたNeurofeedbackを取り上げることにした。Neurofeedbackについては昨年9月8日に付随運動を抑制する治療法として紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/11297 )、要するに付随運動の原因となる脳の活動を客観化することで、付随を随意に変えようとする試みだ。
多くの読者の方は「クオリア」という言葉をご存知だと思う。といっても我が国でクオリアというとソニーの高級ブランドを指す。この様な哲学用語にイメージをかぶせて宣伝に使うプロデューサーの教養には脱帽するが、私にとってこの言葉は、主観と客観の壁は絶対打ち破れないという哲学界のマニフェストに思える。
クオリア自体は20世紀初頭から使われているが、一般に普及し始めるきっかけは、米国の分析哲学の流れを汲む、クワイン、ナーゲル、チャルマーズなどが、主観的な認識は決して科学的に客観化できないことを主張した著作だと思う。個人的な意見だが、昨年我が国の哲学ブームのきっかけになったマルクス・ガブリエルの「私は脳でない」も、この認識論の延長にある様に思える。
しかし、これで納得しては科学者が廃る。クオリア論は主観的認識は決して科学の対象にならないということを前提としている。確かに今はそうかもしれないが、その様な壁を克服することこそ科学だと言える。
では何かを感じている私の脳を感じることができるか?もちろん脳自体を感覚するためのシステムを持たない私たちには原理的に不可能だ。しかし、感じている脳を様々な機器で表象化して、それをもう一度客観的に感覚することは可能だ。いずれにしてもすべての感覚は脳内で表象化されている。とすると、脳画像機器による表象と脳内の表象をつなぐことができないか考え始めたテクノロジーがNeurofeedbackではないかと私は思っている。
事実、科学の世界ではNeurofeedbackは医療技術として広がりを見せ始めている。2017年にNature Rev. Neuroscienceに発表された総説では、自分の感覚過程を画像化してコンピュータにより表象化してもう一度脳に戻すテクノロジーが紹介されている(是非お読みください)。
さらには、Neurofeedbackを音で行うデバイスまで販売されている有様で(https://choosemuse.com/how-it-works/ )、否応なしに科学はこの可能性を真面目に追求する必要があるだろう。
今日紹介する英国グラスゴー大学からの論文はNeurofeedbackが外界のシグナルからの反射能力を高める効果があることを示した論文で12月13日号のeNeuroにオンライン掲載された。タイトルは「Up-regulation of Supplementary Motor Area activation with fMRI Neurofeedback during Motor Imagery(運動の構想時の補足運動野の機能的MRIの活動をNeurofeedbackにより高めることが可能)」だ。
補足運動野とは、私たちが自発的に運動を始めるとき、一連の操作を構想し、まとめるために活動する脳領域でMSAと呼ばれており、Neurofeedbackでは、画像機器を用いて感覚の再表象を得るための場所として最も用いられる。
この研究では、信号を見て右人差し指でボタンを押す運動を、動作を起こすかどうか決める比較的簡単な課題を健康人に行ってもらい、500回近くの反応過程でMSAの反応が課題に対する行動と相関することをまず確認する。
Neurofeedback訓練ではMRIを記録しながら同じ課題を行うのだが、課題を行うときのMSAの活動状況を温度計表示して被験者に認識してもらい、フィードバックをかける方法を用いている。すなわち脳MSAの状態を視覚から再インプットされることで、認識するという仕組みだ。この研究では、いわゆる偽薬グループを設定し、同じ過程で、MRIの結果に関係ない温度計表示を被験者に見せている。
結果は期待通りで、Neurofeedbackを受けた患者さんでは課題での右手の反応時間がなんと15msも早くなる。一方偽薬グループでは全く影響はない。さらに、neurofeedbackで訓練が続く間、MSAの反応自体も上昇する。一方、他の感覚野や運動野の活動感受性は誘導できなかった。言い換えると、どの様な感覚かを表現できないにしても(これは温度表示による表象が完全に脳の活動としては認識できていないためだ)、自分の脳の動きを客観的な指標として感じ、この感じをさらに高める方向へMSAをコントロールできたことになる。
以上、neurofeedbackを科学的に検証した論文がまた一つ増えたことになるが、現在のところクオリアをもう一度表象として補足できる場所は、補足運動野の様な、運動を構想する場所にに限られるようだ。
まだまだ脳を感じるという実感までには至らないし、皮肉な見方をすると一つの医療技術で終わるかもしれない。しかし、主観的には決して感覚ができない脳の活動を、なんとか感覚できる様にしようとする方向性には期待しており、初夢として期待できると思っている。
実は年末30日、東京芸大、東大医学部の学生さんを中心に行われているArt Meet Science プロジェクトの定例会に参加したとき、東京芸大の高杉瑠奈さんの企画した「脳で触る身体」プロジェクトの報告を受けた(図は人間の皮膚の写真からPCで作成されたイメージ)。
私の様な頭でっかちな科学知識とは無関係に、脳での感覚を見てみたいという気持ちが伝わるプレゼンで、展覧会に参加できなかったのは残念だと思った。特に話を聞いていて、高杉さんたちのコンピュータデザインが、将来より複雑なデコードされた脳過程をもう一度感覚可能な形で表象するのに使えるのではとフッと考えた。残念ながら今私たちが客観的に知りうるクオリアは単純な量としてしか表象できない。しかし、動物実験からも分かる様に、脳での活動と行動を統計的に相関させてデコードする技術は進んでいる。ただ、複雑な情報をわかりやすくもう一度インプットする方法論がない。デザイン技術がここで生かされ、より複雑な私のクオリアを、分かりやすいデザインとして他の人と楽しむ時代が来ることを夢見ている。
2020年12月31日
高々30Kbのウイルスに全人類の活動が抑制された暗い1年だったと思う。しかし明けない夜はない。「有効で安全なワクチン開発には通常何年もかかる」と無知のマスメディアがお題目を繰り返しているうちに、ウイルス遺伝子配列が報告されてから3日で設計を終え、次の日にはGMP生産が行われ、なんと7月までに前臨床、1/2相を終了して、第3相開始、12月にはワクチンの臨床接種開始という超高速で、有効性の高いワクチンの供給が始まった。ワクチンを接種するかどうかは個人の自由だが、現在の科学の実力を再認識する1年でもあった。
そこで今年の終わりは、もう一つの医学の課題、ガンの制圧に向けた新しい希望になるかもしれないと個人的に期待しているSanford Burnham Prebys Medical Discovery Instituteからの論文を紹介することにした。タイトルは「FOXO44 promotes DNA replication-coupled repetitive element silencing in cancer cells(FOXO44は複製とリンクした反復配列の抑制を癌特異的に促進する)」だ。
最近、様々なエピジェネティック/クロマチン維持に関わる分子を標的にしたガン治療が行われる様になったが、なぜ正常細胞にも必須の機構の抑制がガン特異的に効果を示すメカニズムはわからないことが多い。
この研究では、我々のゲノムの半分以上を占める反復配列の発現を抑えるエピジェネティックなメカニズムが、増殖の早いガン細胞でどの様に維持されているのかに焦点を当てて研究を始めている。というのも、この反復配列の発現抑制はクロマチン構造が一旦解消する分裂時に綻びが出る可能性がある。特に増殖が激しいガン細胞はその危険が高い。そして、反復配列が発現することでウイルス感染と同じ様なRNAやDNAが細胞内に蓄積し、自然免疫を誘導して、最終的には細胞死に至る。したがって、ガン特異的に反復配列の抑制過程を狂わせると、ガンの増殖をおさえ、さらに自然免疫からガン免疫まで誘導する可能性が生まれる。
研究ではまず、反復配列に関わるヒストンコードHeK9me3のレベルを下げる分子の探索を行い、最終的にFBXO44を特定する。あとは、この分子の機能を明らかにし、ガン増殖抑制、そしてガン免疫増強する可能性を、この分子の機能を解析しながら検討している。膨大な実験なので結論だけを述べると以下の様になる。
FBXO44は、反復配列のクロマチンに選択的に結合するが、複製が進む複製フォークと呼ばれる場所でH3K9me3コードを持ったヌクレオソームに結合し、分裂が終わった反復配列に速やかに様々な分子をリクルートして、転写が始まるのを抑えている。エピジェネティックコード形成時に重要なのが、ヒストンリジンメチル化酵素SUV39H1の結合で、FBXO44とSUV39H1の結合が分裂後速やかに反復配列を抑える過程のトリガーになることがわかる。 FBXO44をガン細胞でノックダウンすると、DNAの切断断片が上昇することから、DNA複製時のストレスが高まることがわかる。 これに次いで、細胞質内のDNA断片が上昇し、結果インターフェロン産生に至る自然免疫経路が活性化され、細胞死も誘導する。この効果は、ほぼ全てのガンで見られ、全てを自然免疫と、ストレスで説明できるわけではないが、増殖に関わる様々な分子の発現も抑制される。また、自然免疫経路が活性化することで、ガン抗原の発現も上昇する。 FBXO44をノックダウンしたガンを移植すると、増殖抑制だけでなく転移も抑制されるが、これはガンの増殖が抑制されるだけでなく、キラー細胞の局所への深順から分かる様に、ガンに対する免疫が成立しやすくなったことに起因している。また、FBXO44をノックダウンしたガン細胞では、PD1抗体によるチェックポイント治療によく反応する。 ガンデータベースからFBXO44の発現と予後との相関を調べると、高発現の患者さんほど予後が悪い。 これらの効果はほとんどガン特異的に見られる。また、FBXO44ノックダウンの代わりに、SUV39H1の阻害剤も利用できる。 以上が結果のまとめだが、ほとんどのガンが持つエピジェネティック過程の脆弱性を特定し、全く新しい、しかも増殖抑制から免疫増強まで、すべていいとこ尽くめのエピジェネティック治療が可能になることを示した力作だと思う。新しいガンのエピジェネティック治療元年になることを期待し、本年の論文ウォッチをおわる。
2020年12月30日
確認したわけではないが、原因不明(のちにCovid-19)の肺炎の集団発生についてのレポートが昨年の12月31日に発表されたとされているので、この一年はウイルスに明け、ウイルスに暮れた一年だったと思う。現時点で今年の10大科学ニュースをはっきりと特集しているのはScience誌だけだが、当然このニュースのトップはCovid-19に対するワクチン開発を選んでいる。ここで選ばれたニュースをまず紹介しよう・
Covid-19に対するワクチン開発が、予想を超えるスピードで行われたこと。 様々な分野の科学がCovid-19を知り、コントロールするため、このウイルスに立ち向かう一方、情報の拡散や政治的喧騒とも向き合わなければならなかった。 これまでとは異なるレベルの正確さでタンパク質の折り畳み構造を予想できるAI、AlphaFoldが実現した。 クリスパーを用いた最初の治療がタラセミア、及び鎌状赤血球症の患者さんで成功した。 地球温暖化の予測が正確に行える様になった。 謎の天体Radio Burstの手がかりが得られた。 世界最古の(44000年前)の狩りの壁画がインドネシアで発見された。 HIVウイルスの完全除去の難しさの理由が明らかになった。 常温での超電導が実現した。 鳥類が予想外に賢い理由が理解できた。 個人的印象を述べると、Covid-19のインパクトのために、生命科学から選ばれたニュースは、AlphaFoldを除くと例年よりは小粒に感じる。そのせいか、今回選ばれた論文のほとんどは論文ウォッチから漏れてしまった。
これら論文の解説は、ウェッブ会議元年となった今日夜7時から行うジャーナルクラブで、忘年会をかねてZoomで行う予定にしており(Zoom忘年会に参加したい人はこのHPの連絡先にメールしてください)、またその模様はYouTube配信する(https://www.youtube.com/watch?v=FK0TuO7Bd6A )ので是非ご覧いただきた。
選ばれたほとんどの論文を論文ウォッチで紹介しそびれたとはいえ、論文自体はほぼ読んでいた。ところが、エイズウイルスについての論文は、紹介どころか読んでもいなかったので、大慌てで読んでみたので、今日のジャーナルクラブ+忘年会のために最後に簡単に紹介しておく。
論文はMITとハーバード大学から8月26日号のNatureに発表されたもので、タイトルは「Distinct viral reservoirs in individuals with spontaneous control of HIV-1(HIV-1を自然にコントロールできる様になった人たちに見られる特殊なウイルス供給箇所)」だ。
よくウイルス疾患は薬がないとメディアが語っているのを耳にするが、エイズをはじめ、肝炎ウイルス、ヘルペスウイルスなど、薬剤でコントロールが可能になったウイルス疾患も多い。エイズはその典型で、満屋さんが開発したAZTに始まり、現在ではいくつか作用の異なる薬を組み合わせてウイルス増殖を抑え込むことができる。しかし、治癒できたのかと問われると、答えはNoで、薬を止めると再発してしまう。
これはエイズウイルスが私たちの血液細胞のゲノムに組み込まれているため、抑制が外れると、そこから新しいウイルスを作るからで、身体中からこの供給基地を除いてしまわないと治癒は難しい。
この研究では、大体0.5%ぐらいの確率で存在している、薬をやめても全く再発しない患者さんを選んで、なぜ普通の患者さんとの違いが生まれるのかを調べるため、ウイルスの供給基地になっているウイルスのゲノム上の挿入箇所を詳しく検討している。
と言っても、実際にはウイルスは次から次に新しい細胞に感染し、そのゲノムに組み込まれるので、解析や解釈は難しい。実際、100万個の末梢血中に、ウイルスの供給基地となる完全なプロウイルスは一般患者さんで1個、治癒例で0.1個しかない。要するに多くの細胞を解析し、できるだけ多くの完全なプロウイルスを特定する地道な努力の結果だと言える。その結果、
治癒例では完全なプロウイルスの頻度は低く、また変異を起こした様なウイルスも少ない。すなわち、ウイルスが挿入された後、プロウイルスとしての活動は少ない。 治癒例では、ウイルスがセントロメアや、19番染色体のクロマチン構造が極めて特殊な部位など、基本的に遺伝子発現が強く抑制されたヘテロクロマチン領域に挿入されている。 以上の結果から、たまたまウイルスがエピジェネティックに遺伝子発現が抑制された場所に挿入されると、何かのきっかけで病気が発症はしても、作られるウイルス量が低いため、おそらく免疫系が先に働いて、感染が拡大するのを防いでいる。そのため、病気が一過性で終わることを示している。
事実、調べられた2例では、プロウイルス自体が膨大な数の白血球を調べても検出できないか、ようやく一個見つかるだけという状態で、ある意味で完全治癒が達成できていると言える。
言わずと知れた、エイズは免疫不全を引き起こす病気だ。ただ、初期のウイルス産生量が低いと免疫不全になる前に、ウイルス感染細胞を除去できるチャンスが得られるという可能性を示している。したがって、研究自体は一般患者さんの完全治癒の難しさを物語るが、免疫系さえうまく働かせれば、感染細胞を除去できる可能性も示している。
いずれにせよ、ウイルス感染症の複雑さを物語る研究だと思う。
2020年12月29日
脱髄性疾患でも神経軸索の再ミエリン化が起こることから分かる様に、大人になっても神経のミエリン化はゆっくりではあっても、新しく変化していることはよく知られている。ただ、一本一本の神経について、ミエリン鞘がどの様に変化しているのかをとらえるためには、何週間も一本の神経細胞を見続ける必要がある。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、生きたマウスの皮質神経を一本づつ連続的に観察し、その周りにできたミエリンの変化を調べた研究で、12月18日号のScienceに掲載された。タイトルは「Neuron class–specific responses govern adaptive myelin remodeling in the neocortex(ニューロンのクラス特異的な反応が新皮質でのミエリンのリモデリングをコントロールする)」だ。
生きたマウスの脳内の神経を数週間にわたって観察し続けるという研究は珍しくなくなったが、ミエリンに焦点を当てて観察したというのはそうないと思う。この研究では、視覚野の興奮神経と、介在神経を別々にラベルするとともに、ミエリン化に関わるオリゴデンドロサイトをラベルすることで、神経とその周りのミエリン化を同時に観察できる様にして、同じ神経細胞上のミエリン鞘の変化を追跡している。ただ、ビデオで連続的に観察しているわけではなく、同じ場所を時間を開けて写真を撮り、それを立体画像に再構成し、各神経でのミエリン鞘の変化を調べている。と簡単に言ったが、実際には一本一本の神経で変化を詳しく検討する必要があり、図を見るだけで大変な作業であることがわかる。
まず30日間でどの程度の変化が見られるかを興奮神経と介在神経で調べると、興奮神経では時間とともにミエリン鞘が長くなっていくが、介在神経では成長・退縮両方がバランスよく起こって、全体ではミエリン鞘は一定に保たれていることが明らかになる。さらに、この動態を既に存在するミエリン鞘の変化と、新しいオリゴデンドロサイトによるミエリン鞘形成に分けて調べ、新しいオリゴデンドロサイトによるミエリン化は、既存のミエリンの再構成よりはるかにダイナミックであることを確認している。
この様に、正常の視覚野でのミエリン動態を確認した後、次に片方の瞼を縫合して、見えない様にした時、このミエリン動態がどう変化するか調べている。驚くことに、片方の目を閉じたままにして入力を遮断しても、興奮神経では動態に変化はほとんど見られない。一方介在神経は予想以上にダイナミックに変化することがわかる。 まずリモデリングは両眼視に関わる領域の介在神経で選択的に起こる。これは、片方の目が急に見えなくなる時、両眼視で行なっていた作業をまず変化させる必要があるからと考えられる。しかも、もう少し時間を区切って調べると、視覚入力を遮断し1週目ではミエリン鞘が長くなるが、次の週には今度は退縮が来る。以上の結果から、入力の変化に合わせて、予想外の複雑性でミエリン鞘のリモデリングが行われていると結論している。実際には生理学的実験は行われておらず、この変化の詳細は不明のままだが、脳内で信号に合わせて、一本一本の電線工事が休まず続いていることがよく分かった。これほど複雑だと、今後私の脳でも電線工事の効率の低下は避けられないだろうと覚悟した。
2020年12月28日
ウイルスの増殖にホストの細胞が必須である以上、ウイルスはどこかでホストに順化し、子孫が維持されるための様々な戦略を取る。その一つが、活動を休止する潜在化で、例えば神経節細胞中で潜在化して、疲れたりすると急に水泡症を起こすヘルペスウイルスはよく知られた例だ。同じように潜在化する例がEBウイルスで、ほとんどの日本人はこのウイルスに感染している。このウイルスに感染するとウイルスが持つLMP1 と呼ばれる分子により、B細胞は白血病化することが知られている。ただ、ウイルスが活性化してLMP1が発現した細胞は直ちに、免疫系に検出され除去される。すなわち、EBウイルスはわざわざ感染細胞にガン抗原を強く発現させて、ホストがガンで死んでしまわないよう、ホストの免疫系をコントロールしているとさえ言える巧妙さだ。
今日紹介するハーバード大学からの論文はEBウイルスのLMP1をガン治療に利用する可能性を追求した研究で、12月23日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Mechanism of EBV inducing anti-tumour immunity and its therapeutic use(EBウイルスが抗腫瘍免疫を誘導するメカニズムとその抗腫瘍治療への利用)」だ。
以前はEBウイルス感染で免疫系が標的にするのは、EBウイルスがコードする分子ではないかと考えられていたが、現在ではホスト側の分子が細胞表面に提示された抗原を認識しているのではと考えられるようになっている。この研究ではまず、LMP1を誘導したB細胞は、CD4、CD8陽性細胞両方の強い免疫反応を誘導すること、この時誘導されるT細胞の抗原受容体のレパートリーは多様で、決して導入したLMP1によるものでないこと、さらにLMP1とよく似た共刺激シグナル活性を持つCD40陽性B細胞も、LMP1誘導B細胞に対するT細胞に認識されることを確認し、LMP1は共シグナル分子としてT細胞免疫を高めるとともに、ホスト細胞分子由来の一種のガン抗原の発現を高める活性があり、これによりEB感染細胞に対する強い免疫反応が誘導されることを確認する。
では、ホスト側のどの分子が抗原となって免疫系に検出されるのか、LMP1やCD40を発現したB細胞で選択的に発現する分子の中から、2種類の分子、survivinとEPHA2を選び出し、試験管内のT細胞反応、および抗原ペプチドとMHCが形成する4量体を用いる抗原特異的T細胞を染色する方法を用いて、LMP1が発現するとこれらの分子が一種のガン抗原として働き免疫を誘導することを明らかにする。
重要なのは、この系で活性化される免疫系が検出するのは、クラス1、クラス2―MHCを問わず、細胞内で処理されたペプチドだけで、同じ抗原を細胞外に加えても処理されない。以上のことから、LMP1を発現させるだけで、新しい様々なガン抗原を内在的に調達したB細胞が誘導でき、さらにこのガン抗原の中にはLMP1を発現していない、例えば腫瘍化したB細胞が発現する抗原も含まれる可能性が強く示唆される。
とすると、当然B細胞腫瘍の治療に、LMP1を用いることができる。これを確かめるため、免疫原性の低いBリンパ腫細胞株にLMP1を発現させ、この細胞を用いて試験管内でCD4T細胞を刺激、増幅したあと、このCD4陽性細胞が、LMP1を導入していないリンパ腫細胞を障害できるか調べている。結果は期待通りで、LMP1が導入されていないリンパ腫も完全に除去することができることが明らかになった。また、PD1抗体によるチェックポイント阻害を組み合わせるとさらに高いキラー活性が得られることも示している。
この前臨床研究結果に基づき、実際の慢性リンパ性白血病の患者さんの細胞にLMP1を発現させ試験管内で末梢血からCD4陽性細胞と培養すると、キラー活性を持つ細胞を誘導できること、そして同じキラー細胞はLMP1を導入していない白血病細胞が発現するガン抗原を認識できることを示している。
以上が結果で、まだ前臨床実験と、試験管内でのコンセプトの検証実験が行われたところだが、ディスカッションでは既に臨床治験が進められていることも述べているので、早晩結果を知ることができると思う。慢性リンパ性白血病は、進行するとCAR-T以外なかなか免疫系が治療に動員できない。その意味で、この方法は期待できる。
一方、私たちのほとんどがEBウイルスに感染し共存関係にあるのは不思議といえば不思議で、ひょっとしたら抗体反応で頻回に現れる異常B細胞を検出するために、私たちもEBウイルスを使っているのかもしれない。
2020年12月27日
昨日、エンベロープ型ウイルスの構造タンパク質のうち、私たちの細胞膜に発現するスパイク分子に対する抗体は、まだよくわからないメカニズムで抗体のフコシル化が低下すること、その結果FCγ受容体3a(FCGR3A)に対する抗体の結合性が何十倍も上昇し、ウイルス感染細胞を抗体により除去する確率は高まること、しかしこれは諸刃の刃で、フコシル化されていない抗体が強い炎症を誘導し重症化を誘導することを示した論文を紹介した。
この結果を頭に読むと、今日紹介するハーバード大学からの論文もわかりやすい。論文のタイトルは「Compromised SARS-CoV-2-specific placental antibody transfer(抗体の胎盤通過はSARS-CoV-2で特異的に損なわれている)」で、12月15日Cell に掲載が決まったばかりだ。
Covid-19は子供に感染しにくく、感染してもまず重症化しない。ただ、新生児、乳児についてはこのルールが当てはまらないことが知られている。わが国では少ないようだが、欧米では1歳未満の子供が感染すると、重症化しやすく、川崎病様の全身血管炎に発展することが注目されている。
結論から言ってしまうと、この論文はフコシル化されていない抗体が選択的に胎児に輸送され、これが生後感染したときに重症化しやすい要因になりうることを示している。糖鎖修飾能は高齢化とともに低下し、一方糖鎖修飾を受けていない抗体が胎児に移行しやすいとすると、高齢者と1歳未満で重症化が起こりやすいことも説明がつくと言うわけだ。
ただこの研究ではフコシル化が低下すると重症化するかどうかについては検討していない。新生児が重症化しやすい原因の一つが、母親から胎児に移行する抗体にあると考えて、CoV2に感染した妊婦さんの血中抗体と、臍帯血中の抗体を比べ、その違いを丹念に調べている。
結果をまとめると、
妊娠後期では、スパイクに対する抗体は、Nタンパク質に対する抗体と比べると、胎児に移行しにくい。ワクチンで誘導されたインフルエンザHAや百日咳菌に対する抗体は、正常に胎児に移行する。 移行する抗体の機能を調べると、補体結合能が高く、白血球活性化を誘導する抗体は移行しにくい。 上の結果から、胎児への移行の違いは糖鎖修飾にあると考えられるが、母体と臍帯血の抗体の糖鎖を比べると、胎児にはフコシル化の程度が低い抗体が選択的に移行し、他の糖鎖修飾抗体が移行できていない。 この原因を探ると、CoV2感染により、フコシル化されていない抗体と結合力の高いFCGR3aの発現が胎盤で上昇している。もともと抗体移行は胎盤で発現するFcRnによって媒介されるが、感染母体ではFCGR3aとFcRnが共発現しており、これがFCGR3aへの結合性の高いフコシル化されていない抗体の選択的移行に関わる。 実際には、他のタイプの糖鎖修飾の結果など飛ばして紹介しているが、以上の結果からこのグループは、補体結合能の高い抗体が胎児に移行しない結果、新生児は重症化しやすいと結論している。ただ、昨日紹介したLandsteiner研究所からの論文を合わせると、フコシル化されていない抗体が新生児が重症化しやすい要因になる可能性も考えられる。
毎日論文を読んでいると、Covid-19の医学研究が世界の津々浦々で進んでいることがわかる。この知識財産は圧倒的で、特に実験動物だけでなく人間についてもリアルタイムで研究が進んでいることの結果だろう。おそらく、これをきっかけに21世紀の医学はさらに人間を対象にした科学へと舵を切るだろう。そして、さらに大きな実験、1年にも満たないうちに何億という人に同じワクチンが接種されると言う壮大な試みが進む。ここで得られる情報は、最初の免疫をコントロールしていると言う点で、計り知れない。この試みからどれほど情報を引き出せるのか、わが国の科学が試されている。
2020年12月26日
今週目にしたCovid-19に関する論文の中に、ウイルスに対する抗体の糖鎖修飾とFc受容体の一つ、FGCR3についての論文が2報あったので、連続的に紹介する。以前Ravechのグループによる論文を紹介したが、抗体の活性はFc部分で決まる。特に、Fcγ受容体3aはIgGの糖鎖修飾でフコシル化が行われると結合性が落ちることが知られている。逆に言うと、フコシル化を受けていない抗体に対して強く結合して、抗体による細胞障害を助けることから、抗体からフコースを除去してよりガン細胞を殺しやすい抗体作成技術を謳う多くのベンチャー企業ができている。
今日紹介する抗体の化学研究黎明期のLandsteinerの名前がついたオランダの研究所からの論文は新型コロナウイルス(CoV2)対する抗体のフコシル化の程度と重症度との相関を調べ、重症化している人ではフコシル化されていない抗体の比率が高まっていることを示した研究で、12月23日Scienceにオンライン掲載された。タイトルは「Afucosylated IgG characterizes enveloped viral response and correlates with COVID-19 severity (フコシル化されていないIgGはエンベロープウイルスに対する反応で現れるがCovid-19の重症度と相関している)」だ。
元々アロの赤血球のような膜抗原に対する抗体はフコシル化されにくいことが知られている。この研究ではまず肝炎ウイルス、サイトメガロウイルス、パルボウイルス、おたふく風邪ウイルスなどに対する抗体の糖鎖修飾を調べ、エンベロープウイルス感染ではフコシル化の低い抗体が出やすいことを発見する。これは、エンベロープウイルスの場合、ホストの細胞表面にもウイルス構造タンパク質が発現するため、赤血球に対する抗体反応と同じようなことが起こったと考えられる。
当然エンベロープを持つウイルスCoV2でも同じで、構造蛋白のスパイクに対する抗体ではフコシル化が低下しているケースが存在する。一方、ホストの細胞表面に発現しないNタンパク質に対する抗体では正常にフコシル化されている。
驚くのは、スパイクに対する抗体で見た時、フコシル化が低下している抗体は急性呼吸器逼迫症を発症した重症例で多く、軽症で止まった患者さんでは最初からフコシル化の程度が高い。他の糖鎖修飾でもARDS発症との相関が見られるが、この場合Nタンパク質とスパイクに対する反応ではほとんど差がない。
最後にフコシル化抗体と重症化の指標であるIL-6とCRPレベルを調べると、フコシル化の程度と炎症の指標が逆相関していることを確認している。
結果は以上で、もちろん臨床データなのでyes or noがはっきりしない場合もある。ただ、最後の炎症とフコシル化の程度が逆相関しているデータは、程度の差はあれかなりはっきりしているように思った。
これらの結果から、この論文ではウイルス感染したホストの細胞表面に発現した抗原に免疫系が触れる結果、フコシル化が低下した細胞を殺す能力が高い抗体が誘導される。通常、これはウイルス感染細胞を除去するには良い効果を示すのだが、ある域値を超えると、感染細胞に最初から強い炎症が誘導され、重症化すると言うシナリオを提案している。元々糖鎖修飾は年齢とともに低下することから、高齢者が重症化しやすいことの一つの説明にもなる、説得力のある仮説だと思う。
現在膨大な数の患者さんの血清が集まり、またこれから様々なモダリティーのワクチン接種を受けた人たちの血清が集まるだろう。この検査は基本的に血清さえ存在すればわかるので、今後さらに多くのサンプルで、自然感染と人工免疫の差も含めてフコシル化の違いを見ていくことで、ウイルスやガンに対する新しい抗体治療の糸口が得られるような気がする。
2020年12月25日
ガリレオ以降、個人の思いつきでも、捏造を排して、他人とコンセンサスを得るための方法論を確立した科学は、結局最も信頼できる知識の源として社会を支えてきた。といっても、科学自体はフッサールの言う「生活世界」からは独立した世界だが、技術を通して生まれた様々な製品を通して、生活世界とつながっている。ただ、技術化される前の知識が生活世界と共有されることは少なかった。わかりやすく言えばスマートフォンは科学的知識なしに生まれないが、科学的知識がなくてもそれを所有し、恩恵に預かれる。
しかし、医学知識になると状況が少し異なる。あらゆる医学的技術にはリスクとベネフィットがあり、どちらを選ぶかは、本当は個人の決断にかかっている。ただ知識の質量があまりにかけ離れているため、「私ならこちらがいい」と専門家がオーソライズした意見を参考にせざるを得ない。多くのメディアに専門家が現れて、自分の判断を述べているのはこの現れだ。
しかし今回の新型コロナ感染で分かるように、専門の「意見」は、科学的手続きで決着しない限り一つになり得ない。そんな時、一般の人は何を根拠に決断すればいいのか。この時誰でも参考にでき共有できる「医学的知識とは何か?」。この問題になんらかの答えを出したいと思う心が、現在梅田北再開発に伴う街づくり計画の一つ「参加型ヘルスケア」に私たちAASJが全面的に協力した理由だ。
少し前書きが長くなったが、生活世界と共有できる「医学的知識」の必要性を示す一つの研究が11月16日Nature Biotechnologyにペンシルバニア大学からオンライン出版された。タイトルは「A long-term study of AAV gene therapy in dogs with hemophilia A identifies clonal expansions of transduced liver cells (血友病に対してアデノ随伴ウイルスベクター遺伝子治療を受けた犬の長期経過研究により肝臓細胞の増殖性変化が起こる可能性が明らかになった)」だ。
要するに私の不勉強に過ぎないが、アデノ随伴ウイルスで導入した遺伝子は、ゲノムに組み込まれることはほとんどないと思っていた。ただ、細胞の中で外来DNAがエピゾームの形で長期間存在すれば、組換えが起こると言われても不思議とは思わない。この研究では、血友病の犬の肝臓にアデノ随伴ウイルス(AAV8,AAV9)に組み込んだ第8因子遺伝子を導入し、最長で10年経過を観察した研究で、導入したアデノ随伴ウイルスは長期間間細胞内で働き続け、その結果肝細胞のゲノムにも組み込まれ、組み込まれたウイルスの作用で増殖力が高い肝細胞が発生すると言うものだ。
重要だと思われる結果を要約すると以下のようになる。
遺伝子治療は門脈ルートで一度だけ行っただけなのに、第8因子の血中濃度は正常の1−10%のレベルに保たれ、また血中の第8因子レベルから期待される以上に、血友病による出血などの症状は強く抑えられる。すなわち、組換えタンパク質を投与する治療より、コストも効果も、ベネフィットは大きい。 なんと、9匹中2匹では、4年を過ぎたあと、血中第8因子が上昇している。これは予想外の効果で、ヒトでも同じことが起これば、遺伝子治療の勝利と言ってもいいだろう。しかし、この原因を考えると手放しでは喜べない。すなわち、導入された細胞の一部が選択的に増加していることを示している。様々な方法で検討すると、挿入されたアデノウイルスの効果により細胞の増殖力が高まった可能性が大きい。 アデノウイルス配列をプライマーとして増幅した断片に含まれるホストゲノム配列から、ゲノムに挿入された可能性を探索すると、調べた全ての肝臓で、ランダムに13ー764カ所の独立した挿入を特定できる。 ほとんどの挿入サイトは拡大することはないが、一部は繰り返し検出されることから、挿入された細胞クローンが選択的に増殖している可能性がある。 細胞のクローン性増殖が見られる場合、アデノ随伴ウイルスの一部が細胞増殖に関わる遺伝子に挿入され、その発現が上昇している 10年にわたって肝障害や肝がんの兆候は全くなく、また最後に遺伝子の挿入を調べる目的で安楽死させた犬の肝臓にも異常所見は認められなかった。 効果の持続期間が問題にされているアデノ随伴ウイルスベクターが、低いレベルではあっても10年近く導入遺伝子を作り続けているのは、私の先入観を覆し、この方法の大きなベネフィットとなる。しかし、ゲノムへの挿入がないと思っていたウイルスゲノムの一部が、高い確率で各細胞のゲノムに挿入され、場合によっては細胞の増殖能力を高めることは明らかにリスクといえる。ただ、10年にわたって臨床的には問題なく、治療効果も見られたことは、ゲノムへの挿入があり、細胞の生理に一定の影響があるとは言え、リスクの確率はかなり低いと結論できる。
アデノ随伴ウイルスを用いる治療のベネフィットとリスクは上のようにまとめられるが、この情報は、専門家以外の患者さんが遺伝子治療を受けるための決断には本当に十分だろうか?さらにアデノ随伴ウイルスベクターでゲノム挿入が起こるとすると、チンパンジーアデノウイルスを用いるワクチンでも、同じリスクはある。実際に投与するウイルス量は1万分の1なので、リスクの確率はさらに低くなるが、この論文から考えると決して0にはならない。とすると、今度は患者さんだけでなく、ワクチン接種に際してもリスクとベネフィットを天秤にかける決断が必要になる。
この決断に、専門家がオーソライズされた答えを出すことはできない。このような状況で必要とされる「共有される医学知識」とはなにか、結局患者さんや一般の方と考えていく必要があり、それがうめきた2期街づくり『参加型ヘルスケア』で行っていきたいと考えている。
2020年12月24日
残念ながらまだその姿を見たことはないが、ボノボは類人猿の中で最も平和的で、人間の利他的行動や、道徳的な行動のルーツを探るために研究されている。山を歩いてボノボを探すほどの体力はもう残っていないが、是非コンゴに行ってサンクチュアリーで保護されているボノボを見てみたいと願っている。
今日紹介するスイスNeuchâtel大学からの論文は、ボノボ同士が示す、共同作業の質を調べた研究で12月18日号のScience Advanceに掲載された。タイトルは「Bonobos engage in joint commitment(ボノボは共同のコミットメントを行える)」だ。
タイトルにあるjoint commitmentはなかなか訳しにくい。例えば目的のために協力し合うことは多くの動物で見ることができる。時に、はっきりとした分業体制が見られる場合もある。しかし、ほとんどの場合、行動を支配する自発的脳のアルゴリズムにより、協力が自然に成立するケースが多く、私たちが協力を考える時に想定する、コミュニケーション、責任感、自由な役割設定などは全く存在しない。
タイトルのJoint Commitmentを行動学的に定義すると、1)目的と実現に向けたプランの共有、2)協同中の意図についての把握、3)コミュニケーション能力、そして4)自分の責任についての理解、の全てが備わった協力関係といえる。人間では3歳児ぐらいから明確なjoint commitmentが見られるのだが、他の類人猿に存在するかどうかは議論が分かれている。
この様な協力関係の質についての研究は、トマセロさんたちの研究が有名で、このHPにも言語の発達について述べた時(https://aasj.jp/news/lifescience-current/10954 )、獲物を順番に分け合う能力について調べた「One for you, one for me: human unique turn-taking skills(Melis et al, Psychological Science, 27:987, 2016 : http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177 )という論文を紹介したが、この様な能力をより自然な状態で調べるのは簡単ではない。
この研究ではフランス・ロマーニュにある霊長類の自然動物公園で飼われているボノボ同士の毛繕いを、joint commitmentと仮定し、これが本当にjoint commitmentかどうかを、様々な方法で確かめている。
まず、片方、あるいは両方を食べ物で引き付けてcommitmentから中座させた時、また同じcommitment に戻るか、離れる時、戻る時どの様なコミュニケーションをとるかなどを調べ、
中座しても同じcommitmentに戻る確率は9割近く、それぞれ意図を共有している。 片方だけ中座した場合、特に毛繕いしている側は、自分の責任を理解した様に、様々なコミュニケーションのそぶりを見せる。 Commitment再開後の役割は、中断された時と同じ役割につく。 ランクが離れた間柄ほど、コミュニケーション行動は多く見られるが、同じcommitmentに戻る確率はランクには関係ない。 などなど、基本的には最初に述べた様々な条件を全て備えたCommitmentであると結論している。
論文を読むだけでは本当かなと思うところもあるが、この様な動物行動観察は、観察者にははっきり分かるがなかなか数値として表現できないことも多いと思う。これを思い入れと取るか、あるいは信用するかは読み手の問題だと思うが、私は信用する側に回る。
2020年12月23日
今週はACE2の転写に関する論文が3報も出ていた。Nature Genetics12月号に掲載された2報の論文は、1型インターフェロンにより誘導されるACE2は普通の分子ではなく、大きな欠損がありCovid-19とは結合しない分子であることを示した(NATURE GENETICS | VOL 52 | DECEMBER 2020 | 1283–1293, NATURE GENETiCS | VOL 52 | DECEMBER 2020 | 1294–1302)。最初の頃ウイルス感染により誘導されるインターフェロンでACE2が誘導されることで感染がさらに広がる心配があると懸念されたが、この心配はないことを示した論文だ。
今日詳しく紹介するのはミシガン大学からの論文で、男性ホルモンによるACE2とCovid-19の膜融合時に働くTMPRSS2の発現を調べた論文で12月18日米国アカデミー紀要にオンライン掲載された。タイトルは「Targeting transcriptional regulation of SARS-CoV-2 entry factors ACE2 and TMPRSS2(SARS-CoV-2の侵入に必要な因子ACE2とTMPRSS2の転写調節を標的にする)」だ。
これほど猛烈な勢いでCovid-19の研究や治療開発が進むと、各人の研究も知らないうちに時代遅れになってウカウカしておられない心配がある。その一つが、ウイルスが細胞へ侵入する時に使うACE2やTMPRSS2などの分子に対して作用する薬剤の開発だろう。というのも、ウイルス侵入阻害という点では、モノクローナル抗体治療が最も初期段階で優れている様に思うからだ。ただ、以前免疫が抑制されている白血病の患者さんでも、感染が鼻で止まって無症状のままウイルスを排出し続けた症例を紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/14412 )、感染が重症化へと進展する最初の段階は、肺の細胞への感染で、この段階の抑制は最初の重要な課題だが、この段階は予防と治療の境にある。すなわち、症状が出るか出ないかのうちに治療を始める必要があるだろう。とすると、抗体薬の可能性はもう少し進んだ段階に限られるので、コストの点および気道スプレーの様な使い方が可能な点で、ACE2やTMPRSS2の機能阻害や転写阻害に関わる薬剤もまだまだ捨てたものではなく、是非開発を続けて欲しいと思う。
この研究はACE2とTMPRSS2の発現を同時に阻害する、既に認可されている薬剤を特定することを目的としている。よく読んでみると、特に新しい発想があるわけではないが、この分野をまとめて考えてみるいい機会になった。
男性の高齢者が肺炎へ移行する確率が高いこと、さらには前立腺癌治療でアンドロジェン受容体阻害剤を使っている患者さんでは、感染率が低かったという論文から、アンドロジェンによりACE2やTMPRSS2の転写が調節されている可能性が示唆されている。この論文はこの可能性の再検討と言える。まず、AT2と呼ばれる肺胞細胞でアンドロジェン受容体とともにACE2、TMPRSS2が強く発現していることを確認する。後は、細胞株を用いたり、マウスを用いたり、雑然とした結果が続くので割愛して、人間についての結果だけを紹介すると、in situ hybridizationを用いた検討から、気道の ACE2、TMPRSS2、そしてアンドロジェン受容体の発現が男性で高く、また喫煙者ではアンドロジェン受容体はさらに上昇することを示している。最後に、細胞レベルの研究で、この3者の発現は、既にFDA認可されているアンドロジェン受容体阻害剤、あるいはエンハンサーとプロモーターを繋ぐコファクターBRD阻害剤で抑えられることを示している。
以上が結果で、いくつかの阻害剤を培養系で再検査したという以外、アンドロジェンとACE2の関係などは新しい話ではない。またデータの質は低く、可能性を指摘するために論文を書いたといった印象が強い。
ただ、現在治験が行われているTMPRSS2阻害剤も含めて、この様な薬剤をいつ使えばいいか考えてみるのは、抗体薬が利用できる様になった今、面白い様に思う。既に述べたが、Covid-19の場合、多くの人では鼻かぜで終わるが、進行するケースでの肺への進展の早さが問題になる。したがって、鼻から肺への進展を止めるとなると、予防と治療の境界領域を対象にする治療が必要になる。この段階の治療戦略は、例えば抗インフルエンザ薬を予防に使うといった話とは少し違っており、新しい構想が必要で、その意味で気道へのアプローチ可能な薬剤のリストを増やすことは重要だと思う。