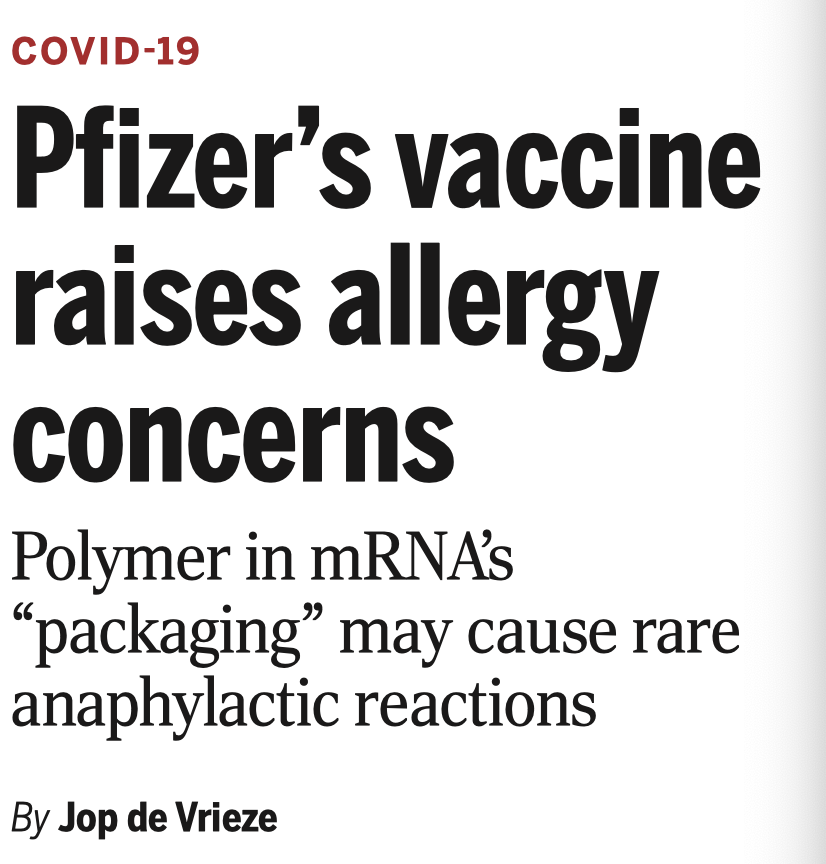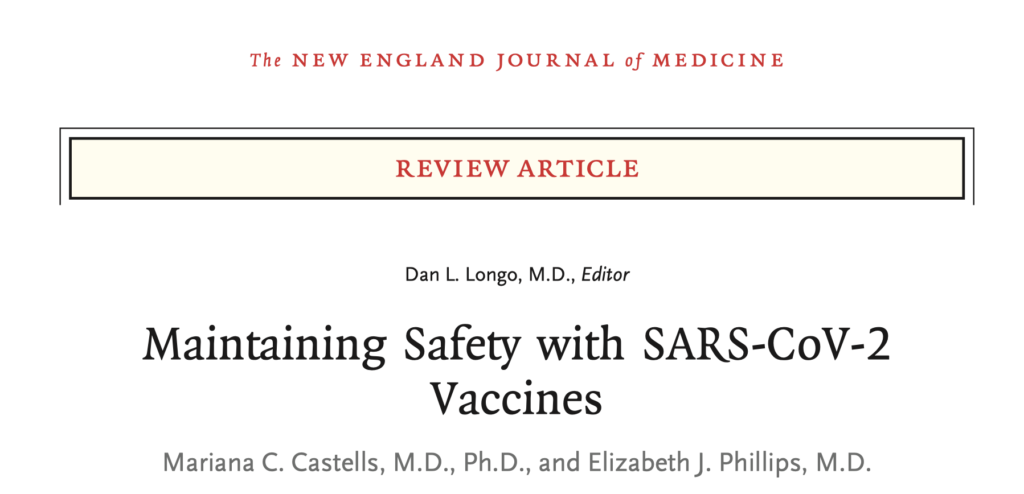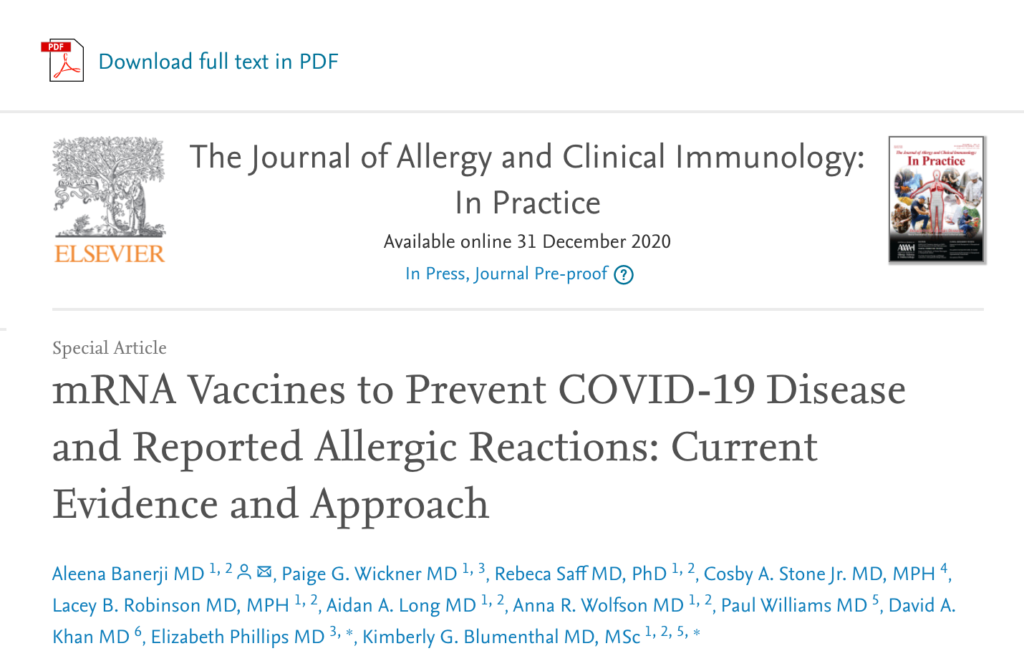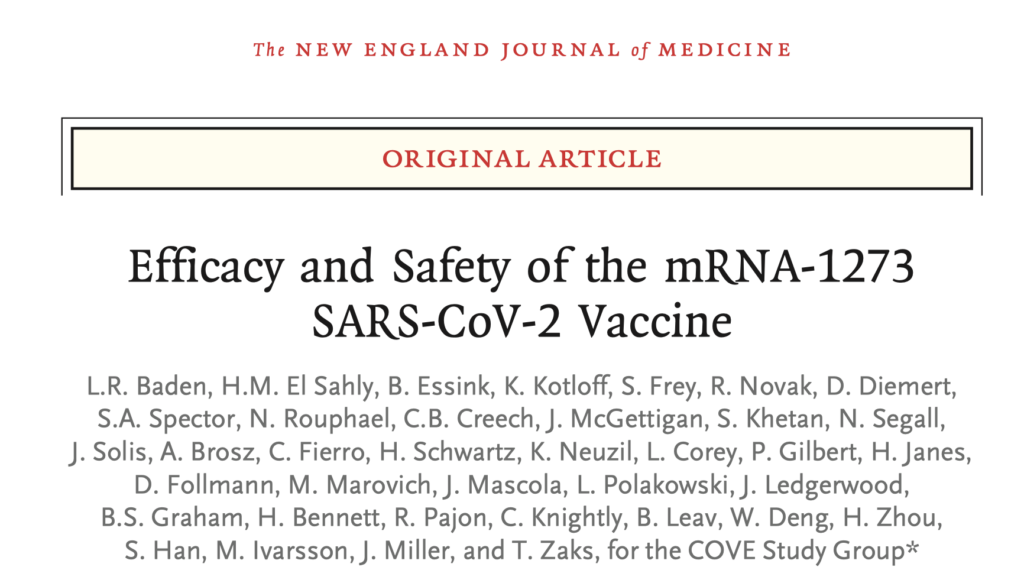2021年1月11日
以前紹介したCovid-19による呼吸不全を肺移植で治療した3例(https://aasj.jp/news/watch/14541 )では、ウイルスは抗体やレムデシビルにより完全にコントロールされているのに呼吸不全は進行してしまっている。すなわち、ウイルス性の急性呼吸逼迫症(ARDS)がどこかの時点で内因性の炎症を誘導して間質肺炎や全身の血管炎が進むことになる。ただ、これをサイトカインストームという一言で語ってしまうと、分かった気にはなっても、本当の理解にはつながらない。というのも、現在知られている炎症の経路はあまりに複雑で、外因性ではじまっても、すぐに自己組織型の内因性の炎症へ移行する。その上、このスイッチはそれぞれの病原体で入り方が異なる。というのも、ウイルス自体、内因性に細胞が持っている炎症システムをいかに抑えるか、多様なメカニズムを持っている。新型コロナウイルスの場合、リボゾームでの翻訳抑制、スプライシングの阻害、タンパク質輸送の阻害で最初のインターフェロンなどの合成阻害、さらに外側からのインターフェロン刺激も、シグナルの抑制を介して徹底的に逃れる仕組みを持っている。すなわち普通考えられない様な自然免疫システムが作られたところに、これで抑制できない炎症シグナルだけが過剰に入ってくることになる。病原体ごとに自律的炎症スイッチの入り方が違っているとすると、この過程をなんとか理解して論理的に重症化を防ぎたいと思うのは当然だ。
そんなことを考えながら、異なる病原体がどの様に自然免疫を抑えようとしているのか調べていたら、比較的最近Science Immunologyにオンライン出版された志賀毒素という懐かしい分子の機能を調べた論文に出会った。タイトルは「Shiga toxin suppresses noncanonical inflammasome responses to cytosolic LPS(細胞質内へ移行したLPSによる非典型的インフラマトゾーム形成を志賀毒素が抑える)」だ。
ウイルスが様々な自然免疫抑制機能を持っていることは、Covid-19が現れる前から理解していたし、このブログでも紹介してきたが、細菌が同じ様な機能を持っていることはあまり考えたことはなかった。
今日紹介する論文は、O-157などの出血性大腸炎の原因菌のトキシンについて研究しているグループの様だ。ご存知の様に、O-157などはファージによる水平遺伝子伝搬を通して、志賀潔博士によって発見された赤痢菌の志賀毒素遺伝子を受け継ぎ、これが激烈な症状の元になっている。志賀毒素(Stx)はグロボトリアオシルセラミドと呼ばれる細胞表面の糖鎖に結合したあと、細胞質内でリボゾームタンパク質の機能を阻害することで、タンパク質合成を阻害することが知られている。メカニズムは違うが、細胞のタンパク合成をまず叩くというのは細菌やウイルスにとっての戦略の様だ。
ただ、これだけだとStxに触れた細胞が死んで出血するという話で終わるのだが、この研究はStxがマクロファージの様な細菌に対する防御機構に対しては、LPSを検出できなくして自らを防御することを明らかにしている。
長くなるので詳細を省いて結論だけをまとめてみよう。
細菌感染に対する重要な自然免疫系はLPSなどの細菌由来エンドトキシンによってスイッチが入る自然免疫系で、この結果NFkb刺激によるTNFやIL-6などのサイトカイン放出、カスパーゼによる細胞死が起こる。
面白いことに、LPSは細胞表面のTLR4に検知されて炎症を起こすだけでなく、細胞質に入って、インフラマゾームと呼ばれる他の炎症経路を介するIL-1βなどのサイトカイン活性化も誘導することが知られているが、Stxはこの経路だけを選択的に抑制する。
そのメカニズムを探ると、インフラマゾームのカスパーゼ11が活性化され、それによりGasdermin Dが分解される経路を阻害することを突き止めている。残念ながら詳細な分子機能は分かっていないが、Gasderminは血液細胞で核酸を分解せずに外に排出するNetosisに関わることを考えると、不思議な炎症の抑え方をしていることがわかる。
研究は現象論だけで、少し物足りないのだが、これほど特異的な炎症の押さえ方をするということは、赤痢菌や大腸菌にとって何か生存に有利な意味があるはずだと思う。
この様にウイルスから細菌までそれぞれが私たちの免疫機能に対応するため進化させてきた抗免疫機能を、ウイルスや細菌の気持ちになって理解できれば、必ず2次的、3次的炎症の特異性を、サイトカインストームという総称ではなく個別に理解できるできる様になるだろう。
しかしこれとは別に、志賀毒素も使い様によっては、炎症制御に使えるかもしれないとも思った。
2021年1月10日
昨年は相分離についての研究が目についた。特にエンハンサーでの転写因子集合から細胞接着、皮膚の果粒層、そして抗ガン剤の効果まで、多くの現象を相分離と関係して説明する研究が多かった。ただ、夏以降は新型コロナ論文に押されて、目にする機会が減った気がしていた。
その意味で今日は久しぶりに転写調節と相分離の論文について紹介する。転写と相分離研究の大御所MITのRichar Youngのグループの研究で1月7日号のCellに掲載されている。タイトルは「RNA-Mediated Feedback Control of Transcriptional Condensates (RNAによる転写凝縮のフィードバック調節)」だ。
この研究が注目したのは、転写時に合成される逆向きの短いノンコーディングRNAの役割だ。これまで、この様なRNAが転写を上げたり下げたりする可能性が示され、クロマチン構造の変化を誘導する可能性などが示唆されていたが本当のところのメカニズムはよく分かっていなかった。この研究では、この短い RNAが濃度依存的にポリメラーゼを含む転写複合体の相分離形成を調節することで、転写調節部位への複合体のロードを促し、その後濃度が上がると相分離が解消し、開始点からの転写複合体が遊離され転写が進むというシナリオの可能性を調べている。
まず、転写開始点とアクチベーターをつないでいるMediator分子に、エンハンサー領域で転写された短いRNAを加えると、濃度依存的にMediatorが相分離を起こすことを確認する。さらに、この相分離がRNAの特異的配列によって調節されているのではなく、RNAの化学的性質に単純に依存して起こっていることを確認する。
この二つの結果は、エンハンサーとプロモーターが集まる部分で合成されている短いRNAがmediatorの相分離を促すことで、ポリメラーゼを含む転写コンプレックスが集められることを示している。
ただ、このままだと転写マシナリーはそのまま相分離された凝縮体の中に捕捉されたままになる。この問題に対し、Youngらはこのとき徐々に短いRNAの量が上昇してくると今度は相分離構造が解消され、これにより転写マシナリーが解放され、転写が進むと考えている。これを証明するために、Medicatorが相分離するとき短いRNAの量を増やすと、相分離が起こらないことを確認している。
あとは、試験管内の転写系を用いて、この様な現象が見られるか確認する実験を行い、試験管内で観察される相分離体の形成が転写効率に関わり、そこに外部から短いRNAを加えると相分離が壊れ転写効率が低下することを示している。
最後に同じシナリオが細胞内でも起こっているかを確かめるため、蛍光標識したmediatorを発現させた細胞で転写開始点での相分離をモニターできる様にし、そこに短いRNAの合成を止めるアクチノマイシンやDRBを加えると、相分離体が安定化してしまうことを示している。
最後に、レポーター分子(ルシフェラーゼ遺伝子)の開始点で短いRNAの合成量を変化させられるコンストラクトを導入した細胞で、実際にRNAが低いところで相分離体が形成され、高くなると相分離体が解消されることを示している。さらにこのとき発現させるRNAの長さを変えて相分離との関わりを調べることで、最初短いRNAが合成されるとMediatorの相分離が促され、時間が経ってRNAの濃度が上昇し、また長いRNA が転写されると相分離体が解消されやすいことを示している。
以上が結果で、いつもながら自分が学んできた転写調節に、新しい視点を与えてくれるさすがと思わせる論文だった。と言っても、この分野のプロから見たら、まだまだ概念先行に見えるのではと思う。しかし、細胞の中でどれほどの数の相分離が進んでいるのか、ちょっと心配になってきた。
2021年1月9日
我が国で最初に接種が始まる新型コロナウイルスに対するワクチンはファイザー/ビオンテックのRNAワクチンになることは専門家でなくても知らない人はいない。しかしほとんどの人が、このワクチンの中核の技術が、ドイツ・マインツ大学発のバイオベンチャー・ビオンテックにより開発されたことを知らないのは残念だ。
今回Covid-19ワクチン開発のトップに躍り出たドイツのビオンテックも、米国のモデルナもほとんど無名のベンチャー企業だが、RNAを用いた地道な研究を続けており、個人的にはガン免疫を誘導する治験に大きな期待を寄せていた。
今日紹介するマインツ大学とビオンテックからの論文は、なんと同じ技術を用いて自己免疫病を抑えるワクチンを作れる可能性を示す研究で1月8日発行のScienceに掲載された。タイトルは「A noninflammatory mRNA vaccine for treatment of experimental autoimmune encephalomyelitis(実験的自己免疫性脳脊髄炎の治療用の炎症を誘導しないmRNAワクチン)」だ。
説明すると長くなるのだが、ビオンテックもモデルナもリポソームに包んでデリバーするmRNAには天然のリボ核酸ではなく、メチル化されたウリジンを取り込ませたmodified mRNAを使っている。これはRNAを細胞内に導入する操作では広く使われている手法で、ワクチンの場合、mRNAの寿命が長くなり多くのタンパク質が合成できることと、細胞内での自然免疫の刺激が少なく、副反応を抑えることが可能だという点が大きい。
この特徴は、自然免疫を刺激して獲得免疫を誘導するという点ではネガティブだが、今回の新型コロナウイルスに対する治験結果を見ていると、ちょうど良い塩梅にこのバランスがとれたと結論できるのかもしれない。いずれにせよ、天然のウリジンとメチル化ウリジンを使い分けることで、自然免疫誘導性の高いものから低いものまで、今後目的に応じてワクチンを使い分ける可能性が生まれる。
今日紹介する論文はまさにこの可能性を追求したもので、T細胞に起因する抗原特異的な炎症による自己免疫病、抑制性T細胞を誘導できるワクチンを用いて抑える可能性を調べている。研究では、実験的自己免疫性脳脊髄炎を誘導するアミノ酸が11個並んだポリペプチドをコードするmRNAを天然のRNA(wRNA)とmodified RNA(mdRNA)を用いて別々に作り、これをリポソームで包んで静脈注射し、脾臓での炎症性サイトカインを調べると、wRNAでは炎症性のサイトカインが強く誘導されているが、mdRNAではほとんど誘導がなく、炎症誘導性で両者は全く異なることを示している。
同じ様な実験はモデルナもすでに発表しているが、このときはワクチンが炎症を強く起こさないことを示す目的で使っている。一方今回のビオンテックの研究では、このとき誘導されるT細胞についても詳しく分析し、mdRNAを用いた場合は強く抑制性T細胞(Treg)が誘導されることを示している。
すなわち、ペプチドの様な短い抗原を用いるとき、炎症誘導性の低いmdRNAはエフェクターの代わりにTregを強く誘導することがわかった。
こうして誘導したTregが自己免疫反応を抑制できるか調べる目的で、同じ抗原を前もって注射して誘導する自己免疫性脳脊髄炎で、症状の出る前にmdRNAによるワクチンを注射すると、発症を抑えることができる。また、発病後にワクチンを注射しても病気の進行を抑えることができる。
さらに、同じミエリン抗原で違う部位のペプチドのmdRNAを用いたワクチンを調整して投与しても、ミエリンに対する自己反応による病気であれば抑えることができる。すなわち、同じ場所で刺激され、IL10などの炎症を抑えるサイトカインを分泌して免疫反応を抑えることがわかった。
このことは、自己免疫に関わるペプチドが同定できなくても、免疫反応を誘導している抗原が特定さえできれば、その一部のペプチド抗原のmdRNAを使うワクチンで治療する可能性を示している。
最後にscRNAseqを用いて、このワクチンを投与された自己免疫性脳脊髄炎マウスでは、抗原特異的T細胞が消失するのではなく、予想通りTregが誘導され、エフェクターT細胞を抑えていること、そしてこの効果はチェックポイントを阻害すると消失することを示している。
結果は以上だが、この論文を読んで私はRNAワクチンの大きな可能性を実感した。もともと、配列がわかればすぐワクチンが作れるという機動性を生かして、ガンワクチンの主流になると予想していた。しかし、今回の新型コロナウイルス感染に対する超迅速なワクチン開発から分かった様に、新しいパンデミックに対する切り札としての役割も実感した。そのうえこの論文から分かる様に、細胞内での自然炎症の強さを調節して、免疫を上げたり下げたりできるワクチン開発まで視野に入ると、可能性は一気に広がる。
マインツ大学の実際の名前はヨハネス・グーテンベルグ大学だが、グーテンベルグによる活版印刷は、ヨーロッパ文化の大改革とともに、文化の大衆化に大きな役割を果たした。その意味で、RNAワクチン手法が、安価な遺伝子操作法、免疫操作法として普及することを期待したい。
2021年1月8日
ボツリヌストキシンは極めて強力な神経毒だが、その神経特異的麻痺作用は臨床に応用されている。さらに最近では、筋弛緩作用を利用するシワ取りなど美容整形でも用いられる様になっている。これほどの神経毒が利用される一つの理由は、トキシンの作用機序が詳しく解析されていることにある。
ボツリヌストキシンは破傷風のテタヌストキシンと同様に神経細胞内に取り込まれてから効果を発揮する毒素で、毒性を発揮するプロテアーゼ(light chain:LC)と、コリン作動性の神経に発現しているシナプトタグミンに結合して神経細胞内に取り込まれるために働くheavy chain(HC)からできている。シナプス端末で神経のエンドゾームに取り込まれた毒素はエンドゾーム内の低いpHでSS結合が離れることでLCが細胞質内に放出され、シナプス形成に働くいくつかのタンパク質を分解してシナプス機能を抑える。しかもLCの細胞内での寿命は長く、長期間神経機能が失われることになる。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、この厄介なボツリヌストキシンを神経細胞内に抗体を移入する道具として使うための開発研究で1月6日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Delivery of single-domain antibodies into neurons using a chimeric toxin–based platform is therapeutic in mouse models of botulism (キメラボツリヌストキシンを使うプラットフォームは単鎖抗体を神経内に導入する治療に使えることがマウスモデルで確かめられた)」だ。
ボツリヌストキシンの神経内への移入効率は高く、以前からこの性質を細胞内へタンパク質を導入するツールとして使えないか研究が進んでいた様だ。このためには、まずLCのプロテアーゼ活性を完全にブロックする必要がある。ただ、プロテアーゼ活性に必要なアミノ酸を置換しても、完全に毒性を除去することはできていなかった様だ。
この研究ではプロテアーゼ活性を除去したLCと、二種類の毒素の部分部分をキメラにしたHCを用いることで、ほとんど毒性がない細胞内への輸送システムの構築に成功している。
この輸送システムの効果を調べるため、正常のボツリヌストキシンが導入されシナプス機能が失われた細胞に、この輸送システムを用いてボツリヌストキシンの活性を抑制するラクダ科の動物で作った抗体分子を導入し、細胞内で毒素を中和できるか確かめている。
これまで何度も紹介した様に、ラクダ科の動物の抗体は一本鎖でできており、化学的に安定で、細胞内分子と特異的に結合できることがわかっている。この研究では、LCに対する一本鎖抗体(nanobody)を輸送システムに結合させることで、細胞内のLCの活性を抑制できるかを確かめることで、この輸送システムの効率を試している。
結果は期待通りで、試験管内だけでなく、マウスにボツリヌス毒素を投与して起こった筋肉麻痺を、輸送システムにより運ばれた抗体がLCを中和して、治療できることを示している。
さらに腹腔内にボツリヌストキシンの致死量を投与したマウスに、この抗体+ボツリヌス輸送システムを投与することで、完全にマウスを生存させることができることも示している。
最後に、この輸送システムはnanobody であれば2本繋いだ大きなタンパク質も輸送できることを示し、将来抗体だけでなく様々な治療分子を神経細胞内へ導入できる可能性を示している。
結果は以上で、細胞質で働く物質に対する抗体を投与できるだけでも、実験や臨床で様々な可能性が開けると思う。残念ながらどのタンパク質を輸送できるかは、タンパク質の性質に強く依存している。これはエンドゾームに取り込まれ、さらにpHが変化することでSS結合が切れ細胞質へ移行するという極めて複雑な経路を必要としているからだろう。当面は抗体のデリバリーに限って実験することで十分な気がする。
ではこの技術が今後大ブレークするかと考えると、簡単ではない様に思う。というのも、nanobodyの場合それ自身を投与しなくても、RNAをモデルナワクチンの様に導入すれば十分で、この様な遺伝子治療と比べた時どの程度のアドバンテージがあるのか、個人的には分が悪い様に思う。
2021年1月7日
小胞体ストレスといえば京大の森さんが明らかにしたストレス感知機構IRE1α分子のリン酸化、その結果起こるXBP1のスプライシングによる活性化、そしてXBP1によりシャペロンなどのERストレス解消に関わる分子グループの転写という経路が中心に来るが、研究が進むにつれこのほかにもPERK経路、ATF6経路が明らかになっている。さらに、それぞれの経路はERストレスを解消する方向の分子を誘導すると同時に、NFkbを介する炎症回路とつながり、最終的には細胞死に至る経路を活性化することもあり、小胞体ストレスの全体像はますます複雑になっている。
今日紹介するMITからの論文はこの複雑性をさらに増大させる分子QRICH1が、小胞体ストレスが細胞死へつながるターミナル過程に関わることを示す論文で1月1日号のScienceに掲載された。タイトルは「QRICH1 dictates the outcome of ER stress through transcriptional control of proteostasis(QRICH1は小胞体ストレスの結果をタンパク質恒常性を転写レベルでコントロールして調節する)」だ。
この研究では細胞株ではなく、マウスの正常腸管上皮細胞を培養し、これをトニカマイシンで処理することでタンパク質の分泌を抑えてストレスをかけ細胞レベルの効果を調べている。面白いのは、この上皮の中に分泌性のゴブレット細胞も含まれている点で、これによりもともと小胞体のキャパシティーの高い分泌細胞と、一般上皮の反応を調べることができる。さらにこの様に異なる細胞種が含まれた系でのストレス反応を調べるため、single cell RNAseqを用いている。その結果、一般上皮ではストレスが長期化するとそのまま細胞死へ移行する一方、ゴブレット細胞ではストレスの長期化にも適応できる転写プログラムを持っていることが明らかになる。
小胞体ストレス経路は極めて複雑なので、それに関わる分子探索も複雑を極めるので詳細は省くが、XBP1のスプライシングを指標としてERストレスを検出する系で、細胞死へ至るターミナル経路へのスイッチに関わるマスター分子QRICH1を特定する。
QRICH1はカスパーゼ活性化に関わる分子であり、小胞体ストレスと炎症を繋ぐ分子としても働くと考え、後半はこの分子に焦点を当てて研究を行なっている。
まずこの分子の発現調節について調べ、小胞体ストレス3経路のうちPERKα経路により活性化されるelF2αによる特殊な翻訳開始点の選択の結果、QRICH1タンパク質の発現が翻訳レベルで上昇することことを突き止める。すなわちQRICH1は小胞体ストレスにより誘導される。
次にこの分子の作用機構について調べ、核内で特定の遺伝子上流に結合して遺伝子発現調節に関わること、そしてこうして転写が促進される分子の多くが、タンパク質合成や分泌に関わる分子であることを発見する。そして、ストレスが続いた細胞でさらにタンパク質合成を進めることで、さらなるオーバーロードにより細胞をターミナル経路へと誘導することを明らかにする。
以上が結果で、QRICH1と炎症経路との直接の関係は明確にはしていないが、普通ならストレスを解消する方向で働く小胞体ストレス経路が長く活性化されると、ストレスを上昇させるQRICH1を中心とするメカニズムが働き、最終的にインフラマゾームの形成から細胞死へと導き、厄介な細胞を速やかに殺しているというシナリオだ。
健全な細胞だけで社会を維持しようとする非情な掟を改めて認識した。
2021年1月6日
抗生物質の探索というと、土の中からの抗菌物質探索の様な地道な美談をついつい思い出す。しかし様々な薬剤に対する耐性菌が問題になってからは、なかなかこの作業も追いつかないため、今や多剤耐性菌は治療する術のない重要な医学問題になっている。
今日紹介する米国フィラデルフィア・ウイスター研究所からの論文は、細菌を殺すのと同時に、キラー細胞も誘導して、耐性菌の出現を止めるという、全く新しい発想の抗生物質開発を目指した研究で12月23日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「IspH inhibitors kill Gram-negative bacteria and mobilize immune clearance (IspH阻害剤はグラム陰性菌を殺すと同時に免疫による菌の除去を活性化する)」だ。
この研究の基盤にはグラム陰性菌や結核菌などの細胞が合成するhydroxy-methyl-but-enylpyrophosphate(HMBPP)がVγ9Vδ2T細胞を直接刺激する抗原になるという免疫学的な発見がある。γδT細胞はMHCとペプチドを認識するαβT細胞と異なり、B細胞の様に直接抗原を認識すると考えられているが、それぞれのV遺伝子組み合わせが認識する抗原は特定できていない。その意味で、Vγ9Vδ2Tは例外とも言える。
このとき抗原になるHMBPPはグラム陰性菌がMEP経路で細胞壁成分を合成するときの中間成分で、IspH酵素によりIPPとDMAPPに分解され、細胞壁合成に使われる。とするとIspHを阻害することで、この経路が止まり、細胞壁形成不全が起こることで殺菌効果が得られると同時に、細菌内のHMBPPが上昇し、Vγ9Vδ2Tキラー細胞を誘導することで、細菌を2重のメカニズムで殺す可能性が生まれる。
この研究ではこの可能性が実現できることを示したもので、
IpsHの発現をコントロールできる様にした細菌を用いて、IpsHをオフにすると、菌の増殖が止まるとともに、Vγ9Vδ2Tを刺激する活性が誘導される。 次にHMBPPからIPP+DMAPPへの経路を阻害する化合物を、IpsHの立体構造をもとに設計し、それを起点に化合物を至適化、殺菌活性の強い化合物を数種類得ることに成功している。 この中から3種類の化合物を選び、臨床例から分離された多剤耐性菌への効果を調べると、細胞壁の機能不全に基づく強い殺菌効果を得ることができた。 さらにこの化合物で処理した細菌は人末梢血中のVγ9Vδ2T細胞の増殖を誘導できる。 化合物と細菌だけを培養すると、当然の様に耐性菌が現れてくるが、ここに末梢血を加えると、耐性菌の発生を抑えることができる。 マウスにはVγ9Vδ2T細胞は存在しないので、人の免疫系で再構成したヒト化マウスを用いて感染実験を行うと、耐性菌でも多くのマウスで細菌の増殖を抑えることができた。 などの結果から、細菌を殺すと同時にキラー細胞を誘導できる抗生物質が可能であることを示している。
まだ人間に投与できる化合物かどうかはわからないが、コンセプトが証明できたことは大きい。なんと言っても、結核菌を含む多くの耐性菌の問題を解決できる。そして、さらにγδT細胞が認識する抗原を探ることで、同じ様な抗生物質を設計することも可能かもしれない。さらにγδT細胞をあらかじめ増殖させるワクチンと抗生物質を組み合わせる治療も可能になるかもしれない。
年初の初夢としては大きな夢の実現に向いた研究だと思う。
2021年1月5日
哺乳動物で血液は骨髄で作られるが、作られたあと、必要に応じて血中に流出していくが、このメカニズムはまだまだよくわかっていない。例えば、造血幹細胞移植のためにG-CSFを投与して骨髄から未熟な幹細胞を動員することが行われているが、 分化幹細胞だけでなく、なぜ未分化幹細胞まで移動を始めるのかよくわからない。
今日紹介するアルバート・アインシュタイン医学校からの論文は骨髄からの血液の移動に自律神経系が関わるはずだと狙いをつけて可能性を検討した論文で12月23日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Nociceptive nerves regulate haematopoietic stem cell mobilization (侵害受容神経細胞は血液幹細胞の動員に関わる)」だ。
この研究ではG-CSFで血液幹細胞を動員するシステムをベースに、この動員に自律神経系がどう関わるか調べている。組織学的には骨髄に投射している神経の多くは、痛覚に関わるとして研究されてきた侵害受容神経とアドレナリン作動性の自律神経なので、まずそれぞれの神経系を化学的に除去する実験を行い、
1)G-CSFを投与して誘導する骨髄での造血は、両方の神経を除去することで強く抑制される。すなわち、造血に骨髄内の神経系が関わっている。
2)侵害受容神経の除去だけでは骨髄増血にそれほど大きな変化はないが、造血幹細胞の末梢血への移動は、侵害受容神経を除去するだけで強く抑制できる。
侵害受容神経は神経ペプチドCGRP を分泌することが知られているので、CGPR投与実験、あるいはCGRPR受容体のノックアウト実験を行い、骨髄からの造血幹細胞の動員はCGRPが担っており、さらに血液細胞特異的受容体ノックアウト実験から、CGRPが直接血液幹細胞に働きかけて骨髄から移動させることを明らかにしている。
タイトルを見た時、おそらくストローマ細胞や血管細胞に侵害受容神経が働いて造血幹細胞が移動するという結論を頭に描いていたが、神経ペプチドが直接血液、しかも未熟な血液幹細胞に働きかけて動員するという結論は意外だった。実際、ほぼ同時に発表されたリンパ節の侵害受容体についての研究では、血管内皮、ストローマ細胞が神経に調節されることで、免疫系を外界からの刺激に備える様にすることが示されており(Cell 184, 2021: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.11.028 )、こちらの方が常識的な結果だと思う。いずれにせよ、直接血液幹細胞に働くとすると、造血幹細胞側で何が起こっているかが問題になるが、cAMP経路を介してCGRPシグナルが伝わるという以上に、幹細胞側の変化を特定できていないのは残念だ。
代わりにと言ってはなんだが、最後にイグ・ノーベル賞ものの実験、すなわち侵害受容体を刺激するカプサイシンを多く含む食べ物(例えば唐辛子)を食べたら血液幹細胞の末梢血への動員が高まるか調べている。結果は予想以上で、G-CSFのみを投与するときと比べて、なんと2−3倍の造血幹細胞が末梢血で検出できる様になる。
結果は以上で、動きのメカニズムが特定できていないのは物足りないが、意外な唐辛子の効果を知って思わず笑ってしまった。
2021年1月4日
一般の人が菌状息肉症などと聞いてもなんのことかわからないが、Mycosis Fungoidesの和訳で、キノコの様(Fungoides)な真菌症と訳せばいいと思う。ただ真菌症というのは全くの診断間違いで、現在はT細胞リンパ腫が皮膚に浸潤した状態を指している。
今もこの診断名が使われているのかよくわからないが、この名前を聴くたび、ガンという病名を患者さんに知らせていなかった時代を思い出す。肺ガンの場合は、真菌症という名前を患者さんには告げることが多かった。
少し脱線したが、今日紹介する米国Lee Moffitt Cancer Centerからの論文は、菌状息肉症やセザリー症候群のような皮膚Tリンパ腫のエピジェネティック治療の可能性を示した研究で12月3日Journal of Clinical Investigationにオンライン掲載された。タイトルは「METHYLTRANSFERASE INHIBITORS RESTORE SATB1 PROTECTIVE ACTIVITY AGAINST CUTANEOUS T CELL LYMPHOMA IN MICE(メチル化酵素阻害剤はSTAB1のマウス皮膚T細胞リンパ腫抑制効果を回復させる)」だ。
昨年大晦日は「ガンの万能薬は可能か?」と題して、ガンのエピジェネティック治療の可能性を示した論文で締めくくったが、遺伝子変異による変化ではなく、ガン特異的エピジェネティックな変化を探して治療する方法は、ますます発展する予感がする。この研究では、進行するとほとんど治療法がない皮膚T リンパ腫でエピジェネティックにSTAB1の発現が低下しているという観察に基づき、マウスT白血病モデルでSTAB1をノックアウトした時何が起こるのか調べることから始めている。
Notch過剰発現によりT細胞増殖の上昇は見られるものの腫瘍化は起こらないが、STAB1のノックアウトにより腫瘍化が起こることから、STAB1が一種のガン抑制遺伝子として働いていることがわかる。さらにこうして誘導されたリンパ腫は、皮膚Tリンパ腫と同じ症状を示すことが明らかになった。
そこでもう一度人間の皮膚Tリンパ腫に戻ってSTAB1の発現を調べると、セザリー症候群ではSTAB1の発現が強く抑制されていることが確認された。また、この発現抑制は遺伝子の変異ではなく、STAB1遺伝子がH3K9me3やH3K27me3ヒストンコードにより抑制されているからであることを突き止めている。
すなわちH3K9me3やH3K27me3などのヒストンコードを形成を阻害することで、STAB1の発現を復活させる可能性がある。もともと皮膚Tリンパ腫にはヒストンのアセチル加工その阻害剤romidepsinが使われている。ただ、この研究によりSTAB1抑制にH3K9me3やH3K27me3が関わることが特定されたので、ヒストンメチル化阻害剤の皮膚Tリンパ腫細胞株への直接効果を確かめ、これまで利用されてきたアセチル化阻害剤より高い効果が、ヒストンメチル化阻害剤、特にH3K9メチル化阻害剤で見られることを明らかにしている。
以上が結果で、極めて古典的な匂いのする全臨床研究だが、皮膚T細胞リンパ腫のエピジェネティックな治療の可能性についてはよく理解できた。おそらく我が国特有とも言える成人T細胞白血病でも同じ効果があるのではと推察され、期待したい。
2021年1月3日
正月3番目の話題はCovid-19、それも接種が進むRNAワクチンの副作用についての総説を選んだ。
オバマ、ブッシュ、クリントン前大統領がワクチン接種を受ける報道が流れたり、流石に画面にはでないがエリザベス女王夫妻がワクチンを受けることが発表されたりするのを見ると、ノブレスオブリージュが今も生きていることを感じる。ワクチンには当然副反応がある。しかし、それを知るためには人間への接種を繰り返す以外に方法はない。こんな時安全性を確かめるためにも、率先してリスクを取るのは、身分が高い人の務めであるという文化だと思う。
幸い率先してワクチン接種を受けるところを公開したみなさんには何も起こらなかった様だが、すでに100万近い接種者の中にはアナフィラキシー反応を起こしたケースが報告される様になっている。しかも、例えばインフルエンザワクチン(おおよそ100万人に1人)と比べた時、10倍の頻度で(おおよそ10万人に1人)、早速接種後15分は様子を見ること、ショックと判断した場合はエピネフリンを注射すること、そしてこれまで強いアナフィラキシーを経験している人は、接種を避けることというガイドラインが示された。
1月1日号のScienceによると、米国国立アレルギー感染症研究所では数回の専門家会議を開き最も可能性の高いアレルゲンがポリエチレングリコールであると結論したことが紹介されている。
おそらくこれらの会議で、議論の内容をワクチン接種の現場、医療従事者、そしてこれからワクチンを受ける一般の人たちへ、情報提供することが決まったのだと思う。
その結果、The New England Journal of MedicineとThe Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practiceにハーバード大学を中心に米国の大学のグループが2つの総説を発表し、RNAワクチンにより起こりうるアナフィラキシーの原因と対応を詳しく述べている。
内容は基本的に同じなので、より詳しく対応策を示している後者の総説をまとめておく。
治験でのアレルギー反応 :ファイザーもモデルナも第3相の治験では、アレルギー歴のある人を省いている。ただ、ワクチン注射に過敏性を示した人は0.5-1%存在するが、偽薬群と比べてほとんど差はない。1人、注射1−2日後に唇が腫れた人が出たが、美容整形目的の皮下注射を受けている人で、それ以外はアレルギー反応は見つかっていない。規制当局のガイドライン: それぞれのワクチンにはRNA以外に様々な化学物質が含まれており、これらに対するアレルギー反応を示す人は最初から除外することを勧めている。また、アナフィラキシーは15分以内に発症するので、15分経過観察を義務付けている。(アナフラキシー歴のある医療従事者が接種を受けたことが報道されているが、これは覚悟して接種を受けたことになる)。一般接種開始後の発症者: 総説の書かれた時点で200万回の摂取に対して10例のアレルギー反応が米国で観察されているが、全て15分以内に反応が起こり、治療を受けている。いずれにせよ頻度は高い。原因: 通常ワクチン接種後のアレルギー反応は、ワクチン成分そのものではなく、それをデリバーしたり、溶かしたりする分子に対して起こる。RNAワクチンに使われるmodified RNAは自然免疫誘導能を下げてはいるが、一定の自然免疫は誘導されるので、これで倦怠感や発熱などの一般的な副反応を説明できる。両社のRNAワクチンの場合、アナフィラキシーの原因を洗っていくと、もっとも可能性が高いのがポリエチレングリコール(PEG)に行き着く。これはRNAを包んでいるリポソームを安定化するために加えられており、ワクチンに使われるのは初めてだが、注射薬、化粧品、食品などに広く含まれており、すでにアレルゲンに触れている可能性は高い。事実PEGに対する抗体は広く検出されるし、アナフィラキシーの報告もある。他の会社のワクチン: PEGはファイザー、モデルナに使われているが、よく似た安定剤Polysorbateは認可を待つアストラゼネカ、ヤンセンのワクチンに用いられているので、これらのワクチンについても同じ様なアナフィラキシーは想定できる。IgE以外の経路: PEGの場合、すでに感作されIgEができていなくとも、補体の活性化を通じて直接マスト細胞を活性化する可能性が指摘されている。また補体活性化による、擬似アレルギー反応も起こる可能性がある。これについてはすでにリポソームで包んだ薬剤投与で経験されている。対策: ワクチン接種の現場で詳しい病歴などを聴く余裕はない。また、PEGに対する皮下テストも実施不可能。とすると、まず接種場所に来る前に自分で危険性を評価してもらう必要がある。そのために、
以前注射を受けた時強いアレルギー反応が起こらなかったか? ワクチン接種でアレルギー反応が起こった経験はないか? 食べ物、ハチ刺され、ラテックスに対してアレルギー反応を起こしたことがあるか? PEGやPolysorbateを含む注射に対するアレルギー反応の経験はあるか? の質問をあらかじめして、この答えから、高リスク、中等リスク、低リスクに分けて、ワクチン接種回避を含めた対策を指示しておく。実際には、全てNOの場合はワクチン接種後15分は経過観察、1−3のうち一つでもYesの場合は30分経過観察、2つ以上、あるいは4にYesの場合はアレルギー診断医の判断のもと接種を受けるかどうか決めることを勧めている。
他にも、アレルギーと思われる反応が起こった時など、現場の医師に対する詳細なガイドラインが示されており、是非一読をお勧めする。また、ワクチン接種実施に際して、アレルギー専門医の強いコミットメントも求めており、医学会全体でワクチン接種で犠牲者を出さないという決意が示されている。ただ、長くなるので割愛して、それぞれのガイドラインについては4日昼12時からYoutubeで緊急の配信を行うことにする(https://www.youtube.com/watch?v=GazBE_fhZTs)。
折しもモデルナ社の第3相治験の結果が発表された。報道されている様に95%の有効率だが、それ以外にも重傷者はワクチン接種群で0という結果も重要だと思う。また、2回接種プロトコルだが、1回目から効果はある様だ。
我が国の場合最終的に受けるかどうかは、接種を受ける人が自分で判断することになるが、それでもこれから始まる接種事業は何千億もの国家事業だ。この事業遂行にあたって一般の協力は必須だ。この時、みなさんの判断を専門家の意見で誘導するのではなく、本当に自分で判断してもらうための共有可能な科学知識とは何か、この機会を捉えて考えてほしいと思う。差し迫った知識共有としては、なんと言ってもアナフィラキシーを含む副反応情報が求められるだろう。そのためには、アナフィラキシーのリスクなどがかなり正確に判断できるスマフォのアプリの作成など、できることは徹底的に行えばよい。新しいIT国家にとって素晴らしい課題だと言える。もちろん、今からでも遅くないので、ワクチン接種に向けた臨戦組織をできるだけ早く準備する必要があるだろう。
欧米の結果を見てから判断したら良いと言った意見を報道している我が国のメディアも存在する様だが、他人任せでは決して次のパンデミックに備える体制は確立できない。ぜひ国をあげて、ワクチン接種の我が国独自の方式を編み出してほしい。実際、この2社にとどまらず、これから多くのワクチンが市場に出回る。これらを適切に選んで、個人に合わせたワクチン接種すら可能になるだろう。それがwithout コロナ時代のニューノーマルだと思う。
2021年1月2日
お正月のお年玉になる様な研究はないかと論文のアブストラクトを見ているうち、紹介し忘れていたが、お年玉としてはうってつけの論文を見つけた。すでに臨床で使われている抗TNF抗体が、初期の1型糖尿病患者さんの病気の進行を遅らせるという論文だ。
1型糖尿病の患者さんの団体日本IDDMネットワークとはもう20年近くのお付き合いだが、この間安心して誰でも利用できる治療法の開発は、残念ながらないと言っていい。私はこの様な治療法の開発に直接携われることはないので、世界各地で行われている研究の中から期待できる新しい治療法の報告をいち早く探し当てて紹介したいと思っているが、この論文は発症初期の患者さんに限るがかなり期待できるのではという感触を持った。少し紹介が遅れたが、素晴らしいお年玉であって欲しいという願いを込めて正月第二弾はこの論文に する。
Jacobs School of Medicineの小児科から11月19日号のThe New England Journal of Medicineに掲載された論文で、「Golimumab and Beta-Cell Function in Youth with New-Onset Type 1 Diabetes (新しく発症した1型糖尿病の若者に対するGolimumab治療とべーた細胞機能)」だ。
この研究の対象は6ー21歳の1型糖尿病患者さんで、診断が確定してから100日以内で、食事プログラムに反応してインシュリンの元になるC-ペプチドのレベルが0.2ピコモルはあることを条件としている。1型糖尿病は進行性の自己免疫病と言えるが、まだインシュリンを作る膵臓のβ細胞が残っている患者さんを対象にしている。
次に、Golimumabは日本ではシンポニーという名前でJansenや三菱田辺から発売されている抗TNFα抗体薬で、間接リュウマチや潰瘍性大腸炎の治療に用いられている。その特徴の一つはオートインジェクターで皮下注射が可能で、患者さん自身で薬剤を注射できる様になっており、インシュリン皮下注射を日常行なっている1型糖尿病患者さんには使いやすいと思う。
治験では無作為に選ばれた56人が抗体投与群、その半分の26人が偽薬注射群になっており、少し多めの導入量投与後、2週間に一回の注射を52週間続けるプロトコルが用いられている。
臨床的結果や方法の詳細については割愛して、簡単にまとめると次の様になる。
この研究は、様々な組み合わせの食事を取らせた後でCーペプチドを測定するテストが、ベータ細胞の機能を最も反映するとして、プライマリーアウトカムとして選んでいる。結果は素晴らしく、ほぼ1年経っても機能低下率が平均で12%にとどまっている。一方偽薬群では、54%の低下率で、ベータ細胞の喪失が進行していることがわかる。 β細胞の喪失が防がれていることを反映し、患者さんのインシュリン使用量も治療開始時とほとんど変わらない。また、食事に対するCペプチド反応がほとんど変化しない一種の部分寛解も4割の患者さんでみられる。 A1cHbについてはあまり大きな改善はないが、感染などの副作用はほとんどない。 私も専門家というわけではないが、一定の医学知識があれば、かなり期待できると思える素晴らしい結果だ。特に、既に我が国でも認可された薬剤で、しかも自分で皮下注射できるタイプの薬剤の効果が確かめられたことは大きい。
この方法が定着すれば、患者さんの早期発見が医師にとって最も重要な課題になる。どうこれを実現するか、今後の結果を見ながら、探っていく必要があると思う。
しかし、抗TNF抗体は自己免疫病治療として最も最初に実現した抗体薬だ。今回の結果を見ると、どうしてこの様な治験が今まで行われなかったかの方が不思議だ。一つの理由は、一般的に用いられている1型糖尿病モデルマウスでこの抗体が全く効果がなかったことが挙げられる。とすると、前臨床にこだわることなく、原理的に可能性があり、すでに安全性が確認された薬剤については、患者さんに試してみるという選択肢もあると思う。
いずれにせよ、思いがけないお年玉になりそうな論文だった。