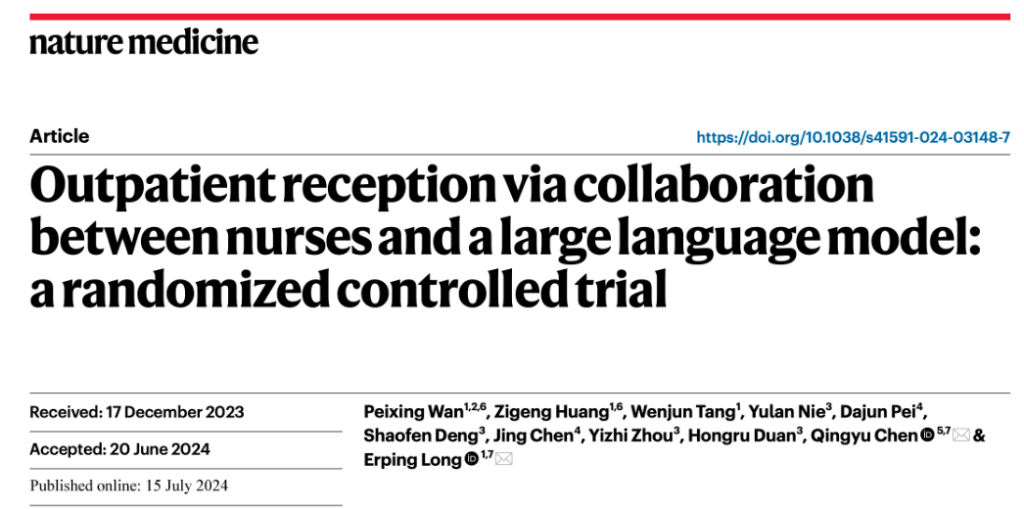2024年7月29日
ミクログリアが凝集したアミロイドβやシヌクレインを掃除してくれることは昔から知られており、この過程をコントロールすることは神経変性疾患の一つの鍵になると研究が進められている。ただミクログリアもマクロファージの一種なので、細胞外に排出された異常タンパク質を貪食して除去すると思っていた。パーキンソン病 (PD) のシヌクレインやアルツハイマー病の Tau の場合、細胞の死んだ後の掃除屋と言ったイメージを持っていた。
ところが今日紹介するルクセンブルグ・システム生物医学研究所からの論文は、ミクログリアが生きた神経細胞から異常シヌクレインを抜き取るだけでなく、元気なミトコンドリアを供給して神経細胞を助けるという驚く結果で、7月25日 Neuron にオンライン掲載された。タイトルは「Microglia rescue neurons from aggregate-induced neuronal dysfunction and death through tunneling nanotubes(ミクログリアは凝集タンパク質による神経異常と細胞死をナノチューブのトンネルを形成して助ける)」だ。
まず実験系だが、脳から取り出した神経細胞に αシヌクレインをプリオンのように取り込ませ、これによりミトコンドリアの酸化的リン酸化システムを中心に遺伝子発現変化が誘導され、最終的に細胞死が起こることを確認している。
次にこの培養系に脳から調整したミクログリアを加えると、神経細胞異常と細胞死を抑制することができるが、この培養を詳しく観察するとミクログリアが神経突起に数多くの微少な腕のような突起を伸ばし、細胞質と細胞質がつながったトンネルを形成していることを発見する。
このトンネルを通して凝集シヌクレインがミクログリアに取り込まれるのではないかと着想し、ラベルしたシヌクレインの輸送を調べると、期待通りトンネルを通ってシヌクレインが神経細胞からミクログリアにアクティブに輸送されているのが確認される。そして、このアクティブな輸送はRACシグナルを介する細胞内のアクチンの再構成により起こっていることを、様々な阻害剤を介する実験から明らかにする。
さらに実際の脳の中に凝集シヌクレインをロードした神経細胞を挿入し、この神経細胞の興奮を調べると、シヌクレインによって低下していた神経の興奮性が周りのミクログリアに助けられて正常化していることを確認している。
以上の結果でも驚くのだが、この研究ではミクログリアと神経細胞を共培養することで、凝集タンパク質により誘導されるミトコンドリア異常に起因する活性酸素の上昇が軽減されるメカニズムを追求し、凝集によるストレスが軽減されるだけでなく、同じトンネルを使ってミクログリアから神経細胞へ正常ミトコンドリアが移送されることを示している。
実際、こうして移送されるミトコンドリアが細胞の活性酸素を正常化していることを示すために、あらかじめミトコンドリア機能を抑制したミクログリアと共培養する実験を行い、細胞の正常化が移送されたミトコンドリアによることを明らかにしている。
最後にパーキンソン病のリスクになる LRRK2 遺伝子変異をもつミクログリアを競売要する実権で、この変異により凝集タンパク質の抜き取りが低下する一方、ミトコンドリアの移送は促進されることを示し、新しい視点からリスク遺伝子の解析を進める必要があることを示している。
結果は以上で、まさにミクログリアが神経細胞のサポートスタッフとして細胞内の新陳代謝に関わることになるが、実際にこの機構が存在するとしたら、神経細胞を保護する初期段階の話だと思う。とはいえ、この機構の意義についてはにわかには信じがたい。
2024年7月28日
免疫系の老化は多岐にわたる。一般的には、新しい抗原に対する反応性は落ちる一方、自己に対する反応が上昇する。Covid-19でこの問題が顕著に表れ、高齢者は感染しやすく、しかも重傷化しやすかったことは記憶に新しい。ではガンに対する免疫はどうか?と考えてみると、論文を読んだ記憶はあまり浮かんでこない。逆に、2021年発表されたチェックポイント治療のメタアナリシスでは、高齢者と若年者で効果や副作用に大きな変化はないことが報告されており、ガン免疫に関してはそれほど大きな差がないのかと思っていた。
ところが、今日紹介するハーバード大学からの論文は、マウスでは間違いなくチェックポイント治療の効果が年齢とともに低下しているが、通常のガン免疫とは異なる経路を活性化して、この問題を克服する可能性があることを示した研究で、7月25日号の Cell に掲載された。タイトルは「Correction of age-associated defects in dendritic cells enables CD4+Tcells to eradicate tumors(樹状細胞の年齢に伴う欠陥を訂正することでCD4T細胞をガン除去に向けることができる)」だ。
研究ではまず老化マウスでメラノーマに対する免疫反応が低下していることを確認したあと、PD-1 抗体や CTLA-4 抗体を用いたチェックポイント治療の効果を比べ、少なくともマウスの系ではチェックポイント治療がほとんど効果を示さないことを明らかにしている。
ところが、老化マウスを TLR 活性化する LPS と、組織障害時に分泌され樹状細胞 (DC) の抗原提示能を活性化することが知られている 1-palmitoyl-2-glutaryl phosphatidylcholine (PGPC) の両方をアジュバントとして用いて刺激すると、驚くなかれガン免疫が復活することを示している。
これはチェックポイント治療にワクチンを組み合わせることの重要性を示しているが、実際起こっているガン免疫反応を調べると、さらに驚くことにガン免疫の主体が CD8T細胞ではなく、キラー活性を持つ CD4T細胞に変化していることを示している。一方、同じように免役しても若いマウスでは、CD8T細胞が主要な役割を占めている。
この現象のメカニズムをさらに調べていくと、LPS+PGPC で活性化されたスーパーDCが、高齢者では CD4T細胞の TH1 反応を強く誘導し、その結果長期に続く免疫メモリー形成だけでなく、CD4T細胞をキラー細胞へと変化させられることを示している。
DC反応の高齢化に伴う変化を調べると、1)高齢化でも変化しない IL-1β 分泌を中心とする自然免疫機構、2)高齢になると機能が喪失し元に戻らない、例えば IL-10 分泌能、そして3)高齢で劣化するが、LPS+PGPC のような強いアジュバント刺激で回復できる CCR7 ケモカイン分泌機機能、の3種類に分けることができ、IL-10 の反応が回復しないまま他の DC 機能を強いアジュバントで活性化することで、普通なら起こらない TH1 に強くバイアスのかかった反応が誘導され、その結果、CD4T細胞をキラー化してガン免疫の低下を補えることを示している。
かなり割愛して紹介したが、以上がマウスを用いた実験の結果で、最後に70歳のボランティアの DC を調整して、高齢者の DC も LPS+PGPC刺激により IL-10 が分泌されないが、TH1サイトカインが誘導される環境を形成し、強い TH1 バイアス反応を誘導できることを示している。
結果は以上で、確かに DC も老化に伴い様々な変化が起こるが、ガン免疫に関する限り、強いアジュバントと抗原刺激をうまく提供できれば、DC を活性化し、新しいキラー活性を誘導できるという結論だ。大変複雑な実験が繰り返されわかりにくいのだが、ガンワクチンを高齢者に使うとき、TLR 刺激だけでなく、スーパーDCを誘導することの重要性を示した結果は、臨床でも調べてみる価値がある。
2024年7月27日
アップルウォッチを使い始めて何年になるだろうか。元々電話も、PCも全てアップルに支配されているためだと思うが、依存度は極めて高い。特に私は補聴器を使っているので、これからも他の時計に移ることはないだろう。
これまで無数のアップルウォッチのようなウエアラブルの身体の活動記録を使った研究が報告されているが、こららの研究が示すのは心拍数や活動記録のような簡単な計測でも、毎日記録されると身体の変調を教えてくれる点で、最も典型的な例が心拍数と体温の変化だけからCovid-19感染を確定診断の3日前に予見できるという2021年 Nature Medicine に紹介された論文だろう(https://aasj.jp/news/watch/18428 )。
今日紹介するバンダービルド大学を中心とする米国の多施設研究は、電子カルテによる病気の情報と、様々な生活や行動記録情報をリンクさせる前向きコホート研究 All of Us に参加し、グーグルウォッチを用いた睡眠記録毎晩調べた6477人のデータを元に、睡眠の質と電子カルテ上の病気との相関を調べた、おそらく睡眠記録としては最も大規模な研究で、7月19日 Nature Medicine にオンライン掲載された。
FitBit と呼ばれるアプリを使うと、心拍数の変化や身体の動きから、睡眠時と覚醒時が区別され、さらにREM睡眠、深い睡眠、浅い睡眠の3種類の睡眠タイプが区別され、しかも毎日の平均が数年にわたって記録され、統計結果が得られる。全員の平均をとると、睡眠のうちREMは20%、浅い睡眠は60%、深い睡眠は15%になり、深い睡眠はかなり短い。
次に、電子カルテと照合して、睡眠の長さや質と、病気との相関を見ると、
睡眠の長さとはっきり関わるのは肥満と睡眠時無呼吸症候群で、あとは意外と相関が強くない。
REM睡眠は心房性不整脈(心房性細動など)と高い相関を示す。
浅い睡眠はやはり心房性不整脈と相関する。
深い睡眠との相関を調べると、様々な病気と低いレベルで相関を示し、なかでもうつ病や不安神経症の相関は強い。
同じように不規則な睡眠パターンは、うつ病や不安神経症とともに、高血圧との相関が見られる。また、弱い相関だが、数多くの病気と相関が認められる。
不規則な睡眠パターンと強い相関を示すうつ病、不安神経症、そして高血圧と、睡眠時間をプロットすると、平均6時間半を底にしてリスクが上昇することから、睡眠は長すぎても短すぎても健康問題を引き起こすというこれまでの結果が確認される。
以上が結果で、内容はこれまで言われてきたことと特に変わりはない。従って、この研究の重要な点は、睡眠の質のような難しい問題をウエアラブルで調べることができ、そのデータから新しい病気を予知する可能性があることを示した点だろうl
ただこの論文の最大の問題は、すでに診断された病気との相関から病気が予知できる可能性が示されているだけで、実際に余地可能性を調べたわけではない。まず、他のポピュレーションでこの検証が必要になるだろう。その際ウェアラブルは充電が必要なので通常は睡眠中は外す。とすると、睡眠用だけのデバイスを安く提供した方が現実的ではないだろうか。ウェアラブルのおかげで毎日の記録が如何に役立つかが実感できるが、睡眠についてどこまで普及するか、是非見守っていきたい。
2024年7月26日
白血病は正常細胞と比べて増殖能力が高く分化能力が低いことが諸悪の根源なのだが、全ての細胞が抗ガン剤に反応するわけではないことがわかっている。すなわち、増殖していない静止期の細胞が存在し、増殖しないため抗ガン剤の作用を乗り越えてしまう。カナダの Bob Jack たちはこれを白血病幹細胞と定義し、ガンを根治するためにはこの集団をたたくことが必要なことを明らかにした。
急性骨髄性白血病の治療にいまだ骨髄移植が必要ということは、白血病幹細胞の概念が定立してすでに四半世紀が経過したのに、この集団をたたく方法の開発ができていないためで、これまでも様々な方法が提案されているが、定着していない。
今日紹介するジュネーブ大学からの論文は、実際の臨床例から白血病幹細胞(LSC)の性質を調べ直し、LSC が鉄の供給能が低いため、鉄を供給するためのオートファジー機構に依存しており、これを標的として LSC 特異的な治療が可能であることを示唆した論文で、7月24日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Targeting ferritinophagy impairs quiescent cancer stem cells in acute myeloid leukemia in vitro and in vivo models(フェリチノファジーを標的にすることで急性骨髄性白血病の静止期幹細胞を試験管内及び生体内で傷害できる)」だ。
この研究は実際の患者さんの AML を免疫不全マウスで継代し、ストックを作ったうえで、LSC の特徴を探っている。ただ、このような研究はこれまでも無数に行われており、定義法はそれぞれ異なるが、最終的に移植後もほとんど増殖せず静止期にある細胞が、次の個体に移植したとき最も増殖能が高いことを示している。そして、LSC のほとんどは静止期にあるため、増殖抑制剤の作用を逃れることを確認している。
その上で、増殖している幹細胞と静止期の LSC の遺伝子発現を、集団、あるいは single cell レベルで解析し、白血病を支える分子の発現とともに、静止期の細胞だけでオートファジーに関わる分子の発現が上昇していることを示している。しかし LSC でオートファジーが高まり、これが LSC 制御の標的になることはこれまでも示されており、新しい発見ではない。
ただ、この研究では LSC の様々な活動にオートファジーは必要だが、特に細胞内鉄イオン維持にオートファジーが必須で、鉄を吸収するためのフェリチン受容体が増殖白血病細胞に発現していても、LSC では低いことを発見する。実際、オートファジー抑制によって、LSC だけでなく、増殖白血病細胞を抑えることができるが、LSC ではこの抑制を鉄を供給することで解消することができる。すなわち、LSC のオートファジーは鉄イオンを維持する目的が大きな部分を占める。
そこで、フェリチンに結合してオートファジーを媒介する NCOA4 分子をノックダウンして AML 細胞の試験管内、及び免疫不全マウスでの増殖を調べると、LSC 特異的に白血病増殖が抑えられることを発見する。この NCOA4 が媒介するオートファジーはフェリチノファジーと呼ばれ、2021年、中国広州 中山大学から NCOA4 とフェリチンの結合を阻害する化合物が報告されている。この化合物を利用して、最後に試験管内、そして免疫不全マウスへの移植実験を行い、この化合物投与で LSC のコロニー形成能や、ホスト内増殖が強く抑制されることを確認している。
結果は以上で、オートファジーというほとんどの細胞で働く機能を、フェリチノファジーという LSC 特異的な機能へうまく転換することで、LSC 特異的に治療する可能性を示したことは重要で、LSC 制御に一歩踏み出せたかもしれない。ただ、データ自体は決して all or none ではないことから、全ての患者さんに使えるのか、根治につながるのかは人間での治験を経て結論できると思う。しかし、期待したい。
2024年7月25日
思い込みによって効果が生まれる偽薬効果は、薬がいらないということなのでうまく使えば逆に医療に使える可能性がある。そのためには、偽薬効果の脳メカニズムを明らかにする必要があるが、動物で偽薬効果の実験を構築するのは簡単ではない。
今日紹介するノースカロライナ大学からの論文は、様々な脳操作法が開発されているマウスを使って、思い込みにより痛みが軽減されるという偽薬効果実験系を構築し、この効果の脳回路を調べた研究で、7月24日 Nature にオンライン掲載された。タイトルはズバリ「Neural circuit basis of placebo pain relief (痛みを軽減する偽薬効果の神経回路)」だ。
なんと言ってもこの研究のハイライトは、再現よく偽薬効果が見られる実験系の構築だろう。少し詳しく説明すると、視覚的に区別可能な2つの部屋をしつらえ、床の温度を30℃、48℃と変えられるようにしておく。どちらの部屋も30℃だと、部屋の境が狭くても行ったり来たりする。次にマウスを最初に入れる部屋の温度を48℃にして、もう片方を30℃に設定すると、マウスは隣の部屋に移動すると痛みがなくなることを学習する。この学習のあとで、両方の部屋を48℃に設定したとき、マウスは同じ温度でももう一つの部屋へと移動し、その部屋での痛みに対する反応が低下する。部屋を薬に見立てて、うまく偽薬効果を再現している。
あとは、マウスが痛みの軽減を期待して隣の部屋への境を越えて痛み軽減を期待する過程の脳活動を様々な方法で調べている。以前思い込みによる副作用が前帯状皮質 (ACC) の興奮によることを示した論文を紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/7527 )、人間の偽薬効果の研究で ACC が最も活動することがわかっており、この研究では ACC からどの領域に投射する神経が最も重要か、TRAP法と呼ばれる活動神経を標識する方法で投射経路を調べ、橋核への投射経路が、偽薬効果を期待してもう一つの部屋に移るときに興奮することを発見する。
この回路がわかると、あとは偽薬効果を期待する時、この回路がどう活動しているかをリアルタイムで調べることができ、まず学習により活動が上昇し、このうち60%の神経が偽薬効果を期待して他の部屋に移るときに興奮することを確認している。
こうして回路が決まると、これを刺激したり、あるいは抑制したりして、この回路が偽薬効果に関わるかを調べることができる。偽薬効果実験でこの回路を抑制すると、偽薬効果がなくなり部屋を移ってすぐ痛みの反応が見られる。一方、回路を刺激すると、部屋を移ってからの痛みの反応が遅れる。
さらに、学習していないマウスで同じ回路を刺激すると、痛み反応を抑えることができるので、学習により脳回路の長期記憶が成立したと考えられ、学習させたマウスの脳スライスを用いるシナプス解析でlong term potentiation (LTP) が成立していることを明らかにしている。
また、ACC から投射を受ける橋核の細胞を single cell RNA sequencing で調べて、まさにドンピシャの細胞、すなわち麻薬に反応できるオピオイド反応性神経細胞が ACC からの投射により活性化することを発見する。すなわち、偽薬回路が麻薬と同じ効果を形成していることを明らかにする。(こんな結果を見ると、痛みですら脳の表象でしかないことを実感する。)
最後に、橋核のオピオイド反応精神系が投射して痛みを抑える領域を、自由に動くマウスの脳の活動を撮影できるミニカメラを装着して調べ、小脳プルキンエ細胞の一部の反応が偽薬効果により抑えられることを発見している。
以上が結果で、偽薬効果の実験系構築から、多くのテクノロジーを組み合わせて結論へと導く、おそらく現在のマウス脳操作実験の典型と思える研究だ。現在難治性疼痛に深部刺激が使われるが、偽薬回路の特性が明らかになることでより効果的な痛みの深部刺激治療が可能になるはずで、期待したい。
2024年7月24日
GPT-4 など一般に利用可能な大規模言語モデル(LLM)も、うまく聞き出すとかなりの医学知識を引き出すことができる。個人的な印象だが、専門的な設問に対しては、正確性が高まる。また、論文を読む気であれば、答えを聞いてから、問題に関する論文リストを要求することで、検証もできる。ただそこまでしなくとも、すでに病気のことを理解している患者さんや家族会が情報源として使う可能性は高く、ある家族会で皆さんと確かめた時は、十分満足できた。
現在医学に特化した LLM も存在するが、それを実際の医療現場でどう利用するのか、というよりどう改良すれば現場に適応するかを考えることは重要だ。これについて Nature Medicine にドイツ・ミュンヘン工科大学と中国北京協和医学院から面白い論文が発表されているので紹介する。
まず最初のミュンヘン大学からの論文は、出来合いの医療ChatBot ( Llama2、OAST、WizardLM など)に腹痛で来院した2400例の医療データを提示したとき、適切な判断ができるかを調べている。
結果は悲劇的で、病院に保存されているデータを全て提供しても、虫垂炎のような一般的な病気以外、胆嚢炎、憩室炎、膵炎などの診断率は遙かに医者の方が優れている。
また症状から入っても、どの検査が必要かを判断する能力に欠けており、さらに検査データを読み取ることも難しい。しかし、質問を症状から順番に提供すると、 Llama2 の診断率は向上していくので、うまくファインチューニングやプロンプト学習を加えれば改善する可能性はある。
かなり割愛して紹介したが、要するにどれほど国家試験のパーフォーマンスが高いとしても、今のままで医学系の ChatBot をそのまま病院に持ち込むことはできないことが示されている。実際、LLM の印象としてどうしても答えを絞りたがる点や、数字に弱い点などを考えると、さもありなんという結果だ。
ただ、例えば患者会の場合のように、限界を知りつつ知識源として使えたとしても、出来合いの ChatBot を現実の病院に持ってきて判断を迫れるようになるのは、まだまだ時間がかかると思う。
これに対して、中国北京協和医学院の論文は、武漢と深圳の病院で、初診の患者さんと看護婦さんとの実際の会話を病院の様々な場所で38737分記録、これをテキストに転換したあと、GPT-3.5のアーキテクチャーをバックボーンとした独自のLLMモデルに学習させ、専門家によるファインチューニングやプロンプト学習を繰り返したあと、初診の患者さんを適切に裁くのに使えるかを調べた研究だ。
ドイツからの論文とは異なり、結果は LLM が正確に患者への対応を改善するという結果になる。おそらく人口の多い中国独特の問題だと思うが、会話の分析から看護婦さんは平均1分間に1人の患者さんに対応しているようで、要するにてんてこ舞いの状態のようだ。従って、患者さんの満足度はどうしても低くなる。
もちろん全て LLM が対応するのは問題があると考え、まず LLM を看護師さんがアシストするシステムを作成し、患者さん2000人を無作為化して、LLM+看護師対応群、看護師対応群に分けて対応し、様々な項目をテストしている。
まず満足度では LLM が関与する方がはるかに良い。そして、繰り返す質問、あるいは感情的問題などが解決されていく。最初の対応もテキストだけではなく、会話で対応できるようにしているので、これならいつからでも使える可能性が高い。
以上が結果で、両方の論文を読んでみて、出来合いの LLM を実際の病院で使うのは簡単ではないが、アーキテクチャーは既存のものを使うとしても、自分のモデルを作っていくことで、問題さえ適切に設定できれば、病院に実装できる LLM の実現はすぐそこに来ていることがわかる。
2024年7月23日
まず次のウェッブサイトをクリックして、掲載されているナショナルジオグラフィックの写真を見てほしい(https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/2317/ )。小さなコウモリの鼻が白く変色しているのがわかると思う。これが北米で猛威を振るう真菌感染症 White nose syndrome で、種によっては95%も個体数が減少して、絶滅が心配されるほど深刻で、しかも現在もなお解決の手がかりがない。
今日紹介するウィスコンシン大学からの論文は、White nose syndrome の原因菌 Pseudogymnoascus destructans(PD)がケラチノサイトに感染し増殖する際の細胞学的、生化学的過程を解析した研究で、少しずつではあってもこの病気の理解が進展しているのがわかる。7月12日 Science に掲載された。タイトルは「Pathogenic strategies of Pseudogymnoascus destructans during torpor and arousal of hibernating bats(コウモリの冬眠中及び覚醒中のPseudogymnoascus destructansの病理的戦略)」だ。
ケラチノサイトに感染して増殖する真菌と言えば水虫を思い出すが、白癬菌は細胞内に侵入せず、角質で増殖する。しかし、PD はコウモリに感染すると、ケラチノサイト内に潜り込むことがわかっている。この研究ではまず、感染初期のコウモリを電子顕微鏡で調べ、菌糸や胞子が細胞内に潜り込めることを確認している。
この研究のハイライトは、冬眠中と覚醒中の PD 感染を再現するために、コウモリのケラチノサイトをパピローマウイルスで不死化した細胞株を作成し、この細胞株が37℃でも、冬眠中の12℃でも培養で維持できるようにしたことで、冬眠を再現できる細胞株ができたことになる。これを用いて PD の細胞内への感染と増殖のメカニズムを研究できるようになった。
この系では胞子も菌糸も細胞内に侵入できる。重要なことは、侵入後も細胞側にほとんど変化がないことで、PD に細胞死を抑えるメカニズムが備わっており、これによって細胞内で発芽や増殖が進むと考えられる。
まず菌糸は12℃で自ら細胞内へ侵入し、これには細胞側の細胞骨格変化などは必要がない。ところが37℃になると、胞子も菌糸も細胞側の飲食作用(エンドサイトーシス)により細胞内に取り込まれる。低温で活動的になる PD のライフサイクルを考えると、高温をじっと耐えている胞子がケラチノサイトに取り込まれ、冬眠が始まり低温になると発芽、そして増殖が始まり、菌糸は自ら伝搬する能力があるので、細胞が寝ている間も、感染細胞を拡大する。さらに低温冬眠中では免疫機能がほとんど作用せず、菌糸増大を止められないという恐ろしい姿が明らかになった。
さらに、37℃で取り込まれた胞子は、DHNメラニンを分泌して、エンドゾームが酸性になり分解酵素が働くのを抑えることで、覚醒中の細胞内でも自らを守れることも明らかになった。
最後に、細胞外の PD と細胞の相互作用に EGFR が関わることを明らかにしている。まず、PD は EGFR と直接結合でき、EGFR に対する抗体で細胞内への侵入を一定程度止めることができる。ただ、EGFR は接着だけに聞いているのではなく、チロシンキナーゼ活性を抑制しても PD の侵入を抑制できることから、PD が EGFR を直接刺激していることが明らかになった。驚くのは、この刺激によるチロシンキナーゼ活性化が冬眠中の温度でも起こることで、これにより細胞側も菌糸の伝搬に手を貸すことになってしまう。
以上が結果で、PD に備わった恐ろしい生存戦略がよくわかる。ただ、ここから野生のコウモリを絶滅から救うためのはっきりした戦略が出なかったのは残念だ。水虫でも治りにくいのに、細胞内に隠れてしまう PD をどう退治するのか、残された時間はあまりないのかもしれない。
2024年7月22日
細胞のゲノムに効率よく遺伝子を導入する方法としては、これまでレトロウイルスを用いる方法、あるいはピギーバックなどのトランスポゾンを用いる方法が使われてきた。ただ問題は、これらの方法ではランダムに遺伝子が挿入されるため、導入場所によっては様々な問題が起こると考えられ、この問題を解決するためにはゲノム配列を調べて、挿入場所が問題ないことを示すしかない。それでも最近の CAR-T でキメラ抗原受容体を導入する目的にレトロウイルスに代わる方法はない。
今日紹介する北京にある中国科学アカデミー研究所からの論文は、28RNA をコードするゲノムサイトに選択的に挿入される R2トランスポゾンシステムをベースにした遺伝子導入法の開発で、7月8日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「All-RNA-mediated targeted gene integration in mammalian cells with rationally engineered R2 retrotransposons(遺伝子操作した R2トランスポゾンの RNA だけで行える挿入場所が決まった遺伝子挿入法の開発)」だ。
この研究では R2トランスポゾンが 5‘端と 3’端にある UTR を用いて R2 が 28rRNAコーディング領域に挿入される特徴を生かすことで、どこに遺伝子が挿入されるかわからないという問題を解決できると考えた。
そこでまず様々な R2トランスポゾンを、5‘、3’端、コードしている遺伝子、そして挿入数などを調べ、最終的に 28rRNA遺伝子部位に挿入されるトランスポゾンを選んで、このシステムを用いて蛍光遺伝子GFP を挿入するベクターを開発する。
一つは R2 のトランスポジションに使われるタンパク質が核内に移行できるようにした遺伝子をコードする遺伝子で、もう一つが R2 の 5‘、3’端の UTR を持つ GFP配列を組み込んだベクターで、両方が細胞内で発現すると、GFPが 28rRNA遺伝子部位に挿入され、そのときだけ GFPタンパク質が合成されるようにデザインしている。
この結果、培養細胞に2%ぐらいの効率で GFP が発現すること、挿入部位が決まっていることを確認する。
このようにシステムが利用可能であることが確認されたので、次に挿入したい遺伝子に付加する5‘、3’ UTR シグナル配列の至適化、さらにトランスポジションに関わる酵素の至適化を行っている。
この詳細は全て割愛するが、最終的に挿入したい遺伝子をコードするベクター、及びトランスポジションに必要な酵素を至適化したベクターを完成させ、なんと20%に達する効率の遺伝子導入法を完成させている。このベクターシステムでは2.5Kbの遺伝子を導入することができるので、多くの目的に利用可能で、標的部位以外に導入される確率は0.6%と低く、さらに導入時の逆転写によって欠失挿入が起こる確率も低い。
さらにこのシステムは、RNAワクチンのように全て RNA に転写させて、それを導入することでも挿入することができる。すなわち、DNAを導入してランダムに挿入が起こる確率をさらに低下させることができる。
以上が結果で、印象的にはまだ始まったばかりで、今後異なる標的部位に導入することも可能になるのではないだろうか。地味な仕事だが、皆が待ち望む遺伝子導入システムになる可能性がある。
2024年7月21日
ヘビ毒に対しては北里・ベーリングの抗血清療法開発以来の抗体薬しか治療方法がないのが現状だが、毒性のメカニズムが明らかになって来ると、抗血清以外の治療薬開発が可能になる。一つの例として2020年5月、ヘビ毒の中のプロテアーゼを金属キレートによって阻害する治療を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/13053 )。
今日紹介するシドニー大学からの論文は、コブラなどの唾液に含まれる毒が局所の細胞壊死を誘導する過程を抑制する分子を探索して、ヘパリンが噛まれたカ所の細胞壊死を防げることをマウスの実験で示した研究で7月17日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Molecular dissection of cobra venom highlights heparinoids as an antidote for spitting cobra envenoming(コブラ毒の分子機構探索によりヘパリン様分子がコブラ唾液の毒性に対抗することが明らかになった)」だ。
コブラ毒は一種類でないことは知っていたが、一般的に恐れられる神経毒や、血栓形成以外に、噛まれた局所の組織壊死とその後遺症がもっと多くの被害者を苦しめている点についてはほとんど知らなかった。この研究では、培養細胞にコブラ毒を加えた時観察される細胞死に関わる分子を特定するため、クリスパーライブラリーで遺伝子ノックアウトを行う方法を用いて、まずスクリーニングを行っている。この結果、Heparan sulfate 合成システムに関わる遺伝子がノックアウトされると、細胞がコブラ毒に対する耐性を獲得することを発見する。この結果は、エジプトコブラでも黒首コブラでも同じで、唾液中の毒による細胞死には heparan sulfate がおそらく一種の受容体として働いていると考えられる。
とすると、ヘパリンやヘパリン様物質を培養中に加えることで、ヘビ毒が細胞に結合するのを抑制できるはずで、これを確かめるためヘパリン、チンザパリン、ダルテパリンをそれぞれ培養に加えると、いずれも期待通り濃度依存的に細胞死を抑制した。このとき、チンザパリンが最も効果が高かったので、これをを中心に研究を進めている。
ヘパリンはコブラ毒のうち cytotoxin3 と cytotoxin4 に結合するが、神経毒の cytotoxin1 や、壊死を誘導する phospholipase2 には結合しない。すなわち、一部の毒にのみ効果がある。
ただ試験管内の実験系だけでなく、マウス皮膚にコブラ毒を注入したときの強い壊死反応をチンザパリンが抑制することから、人間にも利用可能と結論している。
結果は以上で、クリスパースクリーニングから、一般の血栓治療に使われるヘパリンやチザパリンが蛇に噛まれたときに局所に投与することで、ヘビ毒の効果を半減させられるとしたら、抗体やキレート剤と組み合わせて、実践的な、しかも安価なヘビ毒対策を実現できるのではないだろうか。
2024年7月20日
うつ病の治療にケタミンのような麻酔剤やシロシビンのような幻覚剤が効果を示すことがわかってきて、コレラ薬剤の人間の脳に対する作用を調べる研究が進んでいる。2022年4月には、シロシビンの一回注射のあと、うつ病の人では高いレベルを維持している、安静時に活動するネットワーク、default mode network の活動を、シロシビン投与後長期的に低下することを示した論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/19488 )。
今日紹介するワシントン大学からの論文は、シロシビン投与により幻覚体験をしている最中の脳活動、特に神経領域の機能的結合を調べた研究で、7月17日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Psilocybin desynchronizes the human brain(シロシビンは人間の脳の同調性を壊す)」だ。
この研究はうつ病患者さんではなく、25人の正常人にシロシビンとコントロールとしてメチルフェニデート(MTP)を投与し、その効果を機能的 MRI で記録、このデータから領域内や領域間の相関を計算して機能的結合性(FC:functional connectivity)を計算している。
MTP 投与と比べると、シロシビン投与ではともかく脳全体で結合性が大きく変化し、基本的には同じ人の脳領域同士でも、他人の脳と思うぐらい同調性がなくなる。この変化は、default mode network (DMN) で大きい。すなわち、自己に意識を向ける DMN の同調性が失われる。そして、変化はネットワーク内より、離れた他のネットワークとの同調性の喪失の方が大きい。
我々の神経は同調することで統一を保てるが、同調性が失われる結果をエントロピーで表現すると、脳全体の領域でエントロピーが増大する、すなわち規則性が失われているのがわかる。これらの結果は、幻覚剤投与で、神経興奮の変化ではなく、興奮の同調性が失われることが、シロシビンの主な作用であることを示している。
この同調性の喪失による FC の変化が大きいほどシロシビンによる自覚症状が高まる。中でも事故から解放された超越感がこの変化と最も相関するのは納得する。
これが DMN を中心に起こることは、シロシビンで幻覚が現れているときに、被験者に一つの意識的課題を行わせると、同調性が回復することからもはっきりする。
この急性実験のあと、時間をおいて fMRI 検査を行い、脳領域間の機能的結合性を調べている。
3週間たつと、ほとんどの領域間の機能的結合性は回復しているが、海馬前部と DMN の結合は低いまま維持されており、これがシロシビンの抗うつ効果に関わるのではと結論している。
以上が結果で、幻覚剤が脳内の同調性を失わせることで、幻覚につながること、特に幻覚は自分へ意識を向ける DMN 回路の同調性を強く抑制することで自己から自由になることと関連していること、そしてその結果海馬と DMN の機能的結合が長期的に変化するという結論になる。
一回の幻覚剤が長期効果を示すのは怖い話だが、しかし幻覚剤の研究が、デカルト以来哲学的に議論されてきた脳内の自己について知るため重要であることがよくわかる。