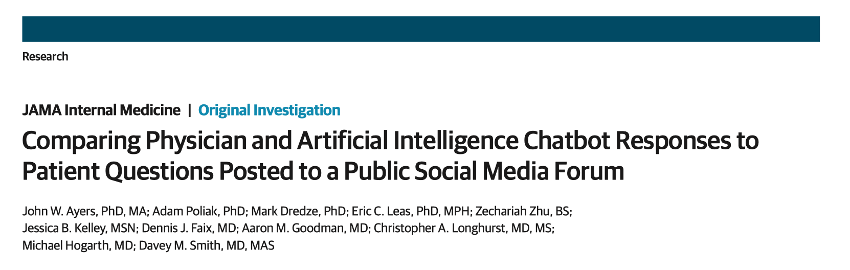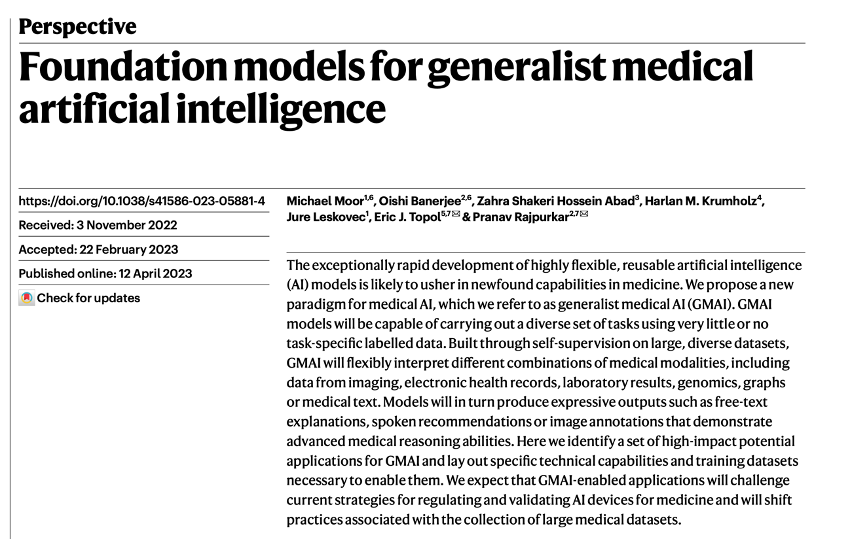2023年5月18日
血管新生というとすぐに血管内皮の増殖を伴うと考えるのが一般的だ。ただ、発達期の場合、体中で細胞増殖が起こると、血管のインテグリティーを維持できるのかいつも心配になる。
今日紹介するイェール大学からの論文は、新生児からの発達期を中心に、ただただ皮膚の血管内皮の動態をモニターし、血管の成長がこれまで考えられてきた内皮増殖を中心に置いていないことを明らかにした研究で、5月10日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Mechanisms of skin vascular maturation and maintenance captured by longitudinal imaging of live mice(マウスを生きたまま長期間観察することで明らかになった皮膚血管の成熟と維持)」だ。
この研究では、タモキシフェンを注射すると血管内皮が蛍光分子を赤から緑にスイッチする遺伝子操作を行ったマウスを用いて、皮膚血管内皮網がどう発達するか調べ、発達期では皮膚血管が増えると言うより、逆に神経の剪定と同じで、密度が減って行くことを観察する。
発達するのに血管が減ると、酸素供給が追いつかなくなるのではと心配になるが、実際には新生児血管網の半分は血管内に血球が存在せず、機能していない。従って、血管機能としては剪定が起こっても同じレベルが維持できる。いずれにせよ、発達期では無駄な血管を減らす剪定が中心になる。
次にタモキシフェンの量を調節して、一部の血管内皮だけが緑に光り、他は全て赤に光るマウスを用意して、剪定時の個々の血管の動態を追いかけると、剪定により失われる血管の内皮は死ぬのではなく、血管内皮網の中に移動し、残った血管で使い回されることが明らかになった。この時、細胞死や細胞増殖はほとんど観察されないが、一個の血管内皮の長さが伸びることも確認している。
すなわち、剪定とはいえ、血管内皮数は変化せず、剪定された内皮は他の場所に移動し、さらにサイズが伸びることで、同じ数の内皮で広い範囲をカバーする新しい血管網が出来ることを示した。
このような血管内皮の移動は大人になると消失し、血管は安定化するが、血管が傷害されると、増殖より先に近くの内皮が移動して伸びるという新生時期の過程が観察できる。従って、血管の再構成はまず血管内皮の移動から始まる。これは血管が広い範囲にわたって傷害される場合も同じで、既存の血管内皮を使い回すことが、毛細血管網のインテグリティー維持の中心になっていることがわかった。
最後に、増殖のない血管内皮の移動や伸長のような細胞過程にも、Flk1とVEGF-Aの血管増殖因子が関わることを明らかにし、このシグナルの多様な機能を示している。
結果は以上で、血管の発達が必ずしも細胞増殖を必要としないこと、また血管内皮細胞は、血管網内で比較的自由に移動することで、構造を保ったままの剪定や再構成が維持されていることが明らかになった。ひたすら観察している研究だが、形態学の重要性が改めて認識される。
2023年5月17日
パーキンソン病にはパーキンなどミトコンドリア機能に関わる分子が重要な働きをしていることが、これらの分子に突然変異を持つ患者さんの研究からわかっている。とすると、ミトコンドリア活性に関わる様々な外的要因もパーキンソン病(PD)のリスク因子として当然考える必要がある。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、トリクロルエチレンにより1975年から1985年、飲み水が汚染された基地に住んでいた退役軍人と汚染のない基地にすんでいた退役軍人を比較した長期的視野の疫学調査で、トリクロルエチレンがPDのリスク因子であることを明らかにした研究で、5月10日 JAMA Network にオンライン掲載された。タイトルは「Risk of Parkinson Disease Among Service Members at Marine Corps Base Camp Lejeune(海兵隊基地キャンプLejeuneの軍人に見られたパーキンソン病リスク)」だ。
私の現役の頃は、長期的なコホート疫学研究というと、国鉄中央病院がメッカだったが、おそらくこれに匹敵するのがアメリカの軍人だろう。完全にフォローアップがなされていることから、例えば多発性硬化症とEBウイルスの関係などは、軍人のフォローアップ研究なしには明らかにならなかった。
さて、海兵隊基地で1975年から10年間、飲み水のトリクロルエチレン量が基準値の70倍まで高まったことが発覚し、その時代に基地で過ごしていた軍人のコホート研究が続いているが、その人達のパーキンソン病リスクを調べたのがこの研究だ。
トリクロルエチレンは金属洗浄剤として現在も使われていると思うが、発ガン性とともに、ミトコンドリアの呼吸チェーンを抑制することが知られており、実験的にもPDを誘導することが知られている。
懸念したとおり、トリクロルエチレンにより汚染された飲み水をとっていた軍人のPD発症率は、コントロールの1.7倍に達しており、ほぼ8万人を対象にしたこの研究で、トリクロルエチレンがPDのリスクファクターであることが確認された。
さらに驚くのは、PDの潜伏期の症状と考えられる、震え、嗅覚障害、勃起障害、不安症状なども、10−20%ほど高いことで、PDと診断されなくても、黒質細胞の異常が始まっていることも明らかになった。
結果は以上で、トリクロルエチレンはPDリスクとして特定できるが、しかしこれを明らかにするのになんと40年もかかることも今回はっきりした。このように長期にわたる研究の結果わかることも多い。結局国民全体の正確な記録をどこまで達成できるかが、重要なことだと思う。おそらくPDなどでは、他にもリスク要因が見つかる気がする。
2023年5月16日
ゲノム解析技術が進んだ結果、腸内細菌叢研究はあっという間に医学の重要分野に躍り出たが、実験動物は別として、人間の細菌叢研究のほぼ100%は便をサンプリングして行われている。ただ、動物実験からは、大便ではなく、もっと上部消化管の細菌叢がホストに大きな影響を持っていることが示唆されており、大便に代わるサンプリング法の検討が待たれていた。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、腸の異なる部位で溶けるように設計されたカプセルを服用させ、計画された場所の消化管腔内の細胞や分子を吸収して、腸各部の細菌叢やメタボロームを可能にする技術の開発研究で、5月10日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Profiling the human intestinal environment under physiological conditions(人間の生理学的条件での腸内環境プロファイルを行う)」だ。
今回使われた4類のカプセルには時間とともにpHなどに反応して、十二指腸、空腸、回腸、そして上行大腸と、それぞれ別のところで剥がれるコーティングが施されており、またコーティングが溶けると、外界からカプセルへ1方向に400µlの液体が流入した後、弁の働きでそれ以上外界から物質が入らないよう設計されている。(オープンアクセスなので、https://www.nature.com/articles/s41586-023-05989-7/figures/1 をクリックして実際のカプセルの写真を見てください。)
実際、内容物のpHを測ると、予想通りの数値を示すことから、カプセルは期待通りの場所でサンプリングを行っていることが確認される。排出・回収までにどうしても時間がかかるが、それでもpHは保たれ、多くのバクテリアは生存していることも確認している。
このように、消化管の異なる部位の非侵襲的サンプリングが可能になったことがこの研究のハイライトで、あとは細菌叢やメタボロームを、便のそれと比べている。
まず、大便と比較すると、各部位の細菌叢は多様性が少なく、また個人差や検出日での変化が大きい。また、存在するバクテリア種もそれぞれの場所ではっきり違っている。逆に言うと、コンディションによる細菌叢の違いをよりはっきりわかる可能性がある。
面白いのは、抗生物質服用の影響を、腸内から直接得られたサンプルでは強く受けている。
他にも様々な実験を行っているが、胆汁の代謝を調べると、カプセルごとに変化が認められ、それぞれの場所の腸内細菌叢により胆汁が代謝され、異なる構造へと変化する時間経過がきれいに示される。また、近い過去に服用した抗生物質の細菌叢や代謝への影響が、腸内サンプリングの方ではっきり見られることから、大便だけで細菌叢研究を行うことの問題が明確に示された。
この研究は腸内のサンプリングが可能であること、腸内でサンプリングした細菌叢や代謝物は、大便内のそれと比べると、多様性が大きいことを示し、腸内でサンプリングを行うことの重要性を示した。今後、様々な病理的条件での腸内各部位の変化についての研究が待たれるが、ひょっとしたらこれまでとは全く異なる結果が生まれるのではと期待している。
2023年5月15日
PD1やCTLA4等に対する抗体を用いた現行の免疫チェックポイント治療が効かないガンや患者さんにも使える免疫活性化戦略として、現在T細胞活性化に関わる様々な共シグナル分子を刺激する抗体や分子の開発が進められている。CD27やOx40はその代表的な分子で、臨床治験結果を待つ段階で、そのうちいくつかは認可される確率が高いと思っている。
この中で少し変わったのがCD137分子で、TNF受容体ファミリー分子で、T細胞だけでなく、B、NK、樹状細胞を刺激できることが知られている。また、他のTNF受容体と同じで、受容体が抗体で3量体を形成すると刺激が入る。他の共シグナルと比べても刺激が強いので、分子活性化抗体の開発が進められたが、抗体のFc部分を介する肝臓毒性が発揮され、毒性を除去した抗体が開発され、2ラウンド目の治験が始まっている。
いくつかの大手製薬企業がCD137に対する薬剤開発を進めているが、今日紹介するスペイン ナバラ大学からの論文は、ロッシュ社の開発した片方が線維芽細胞が発現しているFAPと、もう片方がCD137と結合しFc部分を持たないというかなり凝ったキメラ抗体を用いた治験で、5月10日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「A first-in-human study of the fibroblast activation protein–targeted, 4-1BB agonist RO7122290 in patients with advanced solid tumors(FAPと4-1BB(CD137のこと)に結合するアゴニストキメラ抗体の進行固形ガンへの効果)」だ。
CD137を活性化するためには、膜上で3量体を形成させる必要がある。一方、通常の抗体を用いる場合、活性化出来る濃度の幅が限られる。そこで、片方を線維芽細胞上のFAPに結合させることで、活性化出来る濃度の幅を拡げることが出来る。
一方、懸念材料としてはFAPを発現した細胞が活性化されたT細胞に傷害される心配がある。ただこれまでの前臨床で問題はないと判断し、今回の治験に進んでいる。
研究は末期の患者さんに半分は単独、もう半分はPD-L1に対する抗体との併用で、安全性、血中サイトカイン、腫瘍内T細胞数、などとともに、効果を調べる第1相治験になる。
まず、共シグナルを活性化しているので、ほとんどの患者さんで、この薬剤が原因となるサイトカインストームをはじめとする様々な副作用が出現する。多くは一過性でコントロールできるが、重症の肺炎、肝障害、そしてサイトカインストームがあわせて12%に見られるが、予想の範囲としている。
効果だが、単独投与の場合、効果を示す患者さんは2割にとどまるが、PD-L1抗体によるチェックポイント治療との併用では4割以上の患者さんが反応し、50人の内2人は完全にガンが消失している。
効果を問わず、キメラ抗体投与で末梢血のCD8、CD4T細胞はともに活性化されている。また、バイオプシーで調べたガン組織で、キメラ抗体等予後組織内のCD8T細胞の増加を認めている。
活性化される遺伝子などデータの詳細は省いたが、チェックポイント治療との併用という範囲で、副作用は強いが、期待が持てる結果という結論になる。現在進んでいる共シグナル標的抗体治療の中で、かなり凝った抗体治療だが、今のところ順調と言っていいように感じる。
2023年5月14日
膵臓ガンの多くはrasガン遺伝子の変異とp53ガン抑制遺伝子の機能不全を持つ遺伝的には比較的均一なガンだが、多様性が高いだけでなく、同じようなガン遺伝子セットを持つガンと比べて予後が極めて悪い。この原因は膵臓ガン特有のエピジェネティックな要因にあるとしてこれまでも研究が進んでいる。
今日紹介する米国スローンケッタリング ガン研究所からの論文は、ras変異というgeneticな要因と相互作用するepigeneticな要因を明らかにするため、膵炎後の損傷治癒過程の細胞、マウス膵臓上皮細胞に変異rasを導入した後、発ガンまで様々な段階の細胞など膵臓に発生すると考えられる病理的細胞全てのエピジェネティックスを調べた大変な研究で、5月12日号 Science に掲載された。タイトルは「Epigenetic plasticity cooperates with cell-cell interactions to direct pancreatic tumorigenesis(エピジェネティックな可塑性が細胞相互作用を誘導し膵臓ガン発生を助ける)」だ。
すでに述べたように、膵臓上皮の増殖を誘導するような様々な変化を誘導し、single cell RNA sequencingで解析して、膵臓に現れる可能性のある細胞をまず網羅的にマッピングし、発生したガンは同じガンがないと言えるほど多様であること、損傷や、変異ras による前ガン状態で、すでにガン特有の性質を示し始めることを明らかにしている。
そこで、変異ras自体による変化を捉えるために、変異ras発現後48時間で起こるエピジェネてな変化を、今度はsingle cellレベルのクロマチン構造を調べるATAC-seqを行い調べた。その結果、変異ras発現のみで、損傷治癒増殖時よりさらに強いエピジェネティック変化を上皮細胞が起こし、ガンの方向に近づいていることを明らかにした。
この初期のクロマチン構造変化の病理学的意味を調べると、変異rasにより、一種の幹細胞のような過疎的なクロマチン構造が生まれ、その後様々な方向へ分化する可能性が発生している事がわかる。すなわちrasは分化状態を緩め、膵臓上皮では抑制されている様々な遺伝子も利用可能な状態になり、例えば胃上皮様のメタプラジアも起こっている。
この結果、炎症時と同じで、普通なら反応しない細胞間相互作用に反応する可能性が生まれ、ケモカインを分泌して炎症免疫細胞を誘導したり、逆に免疫細胞に反応して新しい性質が誘導される可能性が生まれる。このような分化の可塑性が生まれた結果可能になる新しい相互作用にかかわる、リガンド、受容体セットをインフォーマティックスを駆使して探索し、前ガン細胞と上皮幹細胞、あるいは前ガン細胞とTreg細胞などとの相互作用に関わる分子が、可塑性を獲得した結果発現し始めることを明らかにする。
そのうち、前ガン細胞で新たに発現してくるIL33に注目し、発現したIL33が上皮でノックダウンされるトランスジェニックマウスを作成すると、変異rasを発現しても発ガンが強く抑制されることを明らかに示し、可塑性誘導の結果新しく発現したサイトカインや受容体が、様々な組み合わせで発ガン過程を修飾して、多様なガンを作り出していることを明らかにしている。
結論としては、ガンはまず発ガン遺伝子がオンになって、それが細胞の増殖だけでなく、場合によっては大きなエピジェネティックな変化を誘導していることになる。また、膵臓ガンの多様性は、この時細胞が可塑性、すなわち多様な分化能を獲得した結果であることになるが、十分納得できる説明だと思う。
2023年5月13日
頭にハンマーが突き出したシュモクザメは、このハンマーを使って深い海底で動きが鈍った獲物をヒットしたり抑えたりしてハンティングする。このため、わざわざ温度が低い海底までコンスタントにダイブする。温かい海域に住む赤シュモクザメでは、このダイビングは時により800mにもおよび、この時の海水温の差は20度にも達する。
今日紹介するハワイ大学からの論文は、赤シュモクザメが潜水時には息(エラ)を止めることで体温ロスを止めることを示した研究で、5月12日号 Science に掲載された。タイトルは「“Breath holding” as a thermoregulation strategy in the deep-diving scalloped hammerhead shark (赤シュモクザメの深海への潜水時息を止めることが温度調節のための戦略)」だ。
研究ではサメの位置、外部温度、潜水深度などを測るテレメーターとともに、運動を記録する装置と、さらに筋肉深くに挿入した深部温度計を装着し、サメの行動をモニターしている。
観察を続けると、赤シュモクザメは夜になると何回も500mをこす深海に繰り返しダイブし、おそらく餌の密度が多い場所では一晩に10回近くダイブしている。
この時の海温差は500mを越す場合、だいたい20度に達し、最低温度は26度から5度まで下がる。ところが、深部体温を見るとダイブ中はほとんど不変で、底で過ごす5分間もほとんど変わらない。しかし、浮き上がり始めて400mまで上がってくると、今度は運動が減り、浮き上がるまで体温は5度ぐらい低下してしまう事がわかった。
変温動物といっても、魚も筋肉を動かすと熱を発生できるので、当然それにより温度を保つ事ができる。事実、ダイビングを始めてから深さが400mを超すと運動が急速に上昇し、体温が生成されている事がわかる。また、浮き上がった時温度が下がるのも、急速運動が止まるのと一致しており、熱の発生が重要である事がわかる。
しかし、体温変化にかかわるパラメーターをモデルングして計算しても、筋肉運動による熱の発生だけでは20度の温度差を超えて、体温が維持されることは考えにくい。
そこで、最終的に出した結論は、サメも息を止める(すなわちエラへの海水流入を抑える)ことで、血管が冷えるのを防いで深部温度を維持しているという結論だ。この研究では、エラへの海流が遮断されることは確認できていないが、これまでのビデオ撮影で、海水の取り込み口が潜水時に閉まる事が確認されているようだ。
結果は以上で、サメもダイビング中は息を堪えているという、ある意味では楽しい結論だ。ただのそれだけ、と言われるかもしれないが、子供に物知り爺さんや、婆さんとして語るためには最高の話題のように思う。
2023年5月12日
ガンの末期になると悪液質と呼ばれる状態に陥り、ただ痩せるというだけではなく、特徴的な容貌や外見を示すようになることは一般の人にもよく知られている。中でも筋肉の萎縮は特徴的で、単純に使わないから萎縮する以上のことが起こっている。
この悪液質にはIL1、IL6などのサイトカインが関わることが知られており、悪液質を止めて生活の質を高めるため、これらのサイトカインに対する抗体を用いた治療治験が行われているが、筋肉萎縮についてはそのメカニズムはわかっていない。
今日紹介するトルコKoc大学(トルコからの論文を紹介するのははじめてだ)からの論文は、ガン末期に筋肉萎縮が進行するメカニズムをマウスモデルと培養細胞で明らかにした研究で、5月10日 Nature オンライン版に掲載された。タイトルは「EDA2R–NIK signalling promotes muscle atrophy linked to cancer cachexia(EDA2R-NIKシグナルがガン悪液質による筋肉萎縮を促進する)」だ。
この研究は極めてオーソドックスだ。まず、マウスモデルで悪液質が誘導されると、筋肉にこれまで機能がはっきりしていないTNFファミリー分子のEdaa2とその受容体Eda2rの発現が上昇することを特定する。
そこで、筋肉培養系でEdaa2を添加すると、筋肉内で蛋白分解システムが高まり、ミオシンなどの分子量が低下するとともに、筋管の形成が強く抑えられる。また、Edaa2遺伝子を筋肉で発現するトランスジェニックマウスでは、悪液質がなくても筋肉移植が起こるし、Edaa2に対する受容体Eda2Rを筋肉でノックアウトすると悪液質を誘導しても筋肉移植は起こらない。
このように、予想外のEdaa2/Eda2rシグナルが悪液質の筋肉萎縮特異的に働いていることを発見したのがこの研究のハイライトになる。
後は、悪液質でEdaar2が上昇する上流のシグナルと、Eda2R下流のシグナルについて、ノックアウトマウスや培養細胞について検討し、
IL6ファミリー分子の一つオンコスタチンMがEda2rの発現を上昇させ、筋肉のEdaa2に対する感受性を上げること、またオンコスタチンM受容体を筋肉からノックアウトすると、悪液質による筋肉萎縮を抑えられること、
Eda2rの下流ではNFκシグナル経路の中のNIKリン酸化を介する経路が働いて、筋肉を萎縮させること、またNIKを筋肉でノックアウトすると悪液質による筋萎縮を防げること、
を明らかにしている。
以上の結果から、ガンの悪液質が誘導されると、IL1. IL6などの炎症因子とともに、オンコスタチンMが誘導され、これにより筋肉でのEda2rの発現が上昇し、Edaa2への刺激感受性が上がることで、NFκB経路のうちNIKを介するシグナルが誘導され、これが筋管形成を抑制、また蛋白分解系を活性化させミオシン量を減らすことで筋肉が萎縮するというシナリオが示された。
おそらく、この経路は抑制できるので、悪液質の筋萎縮を抑えて、生活の質を高める可能性はあると思う。
2023年5月11日
今世界中でChat GPTなど、foundation modelと称される大量のラベルなしデータで学習させ、そのデータの相関を拾って、様々なタスクに対応できるようトランスフォームするAI手法が大きな話題になっている。これは、これまで一つ一つのデータに専門的なタグ付けという膨大な作業が必要だったAI概念を一変させた。
医学領域も例外なくfoundation modelによる変革が起こりつつある。例えばこれまで専門家の正確なタグ付け(例:右下葉に限界がはっきりした陰影があり、大葉性肺炎が疑われるなど、)を必要としたレントゲンフィルムの学習を、極端に言えば異常有り無しだけのタグ付けデータがあれば正確な診断が可能になるというスタンフォード大学からの論文が発表され、レントゲン読影をfoundation modelが自然にこなしていけることが示された。すなわち、私たちが医師に成り立ての頃に学習したのと同じように診断能力をつけていく。
専門家ではない私でも、最近の大きなトレンドを感じることが出来る。そこでいくつかの理由から、foundation modelについて自分の理解を一度まとめようと思ってきた。
まず最も大きな理由は、5年前、患者さんの質問にわかりやすく答えてくれるAIが可能か、何人かの若手情報研究者に聞いてまわったことがある。その時、簡単ではないという答えが圧倒的だったが、Chat GPTは今やそれを実現した。
例えば最近JAMA Internal Medicineに掲載された論文では、専門的ではないが一般の人が聞きそうな問題を、医師とChat GPTに投げかけて、患者さんがどちらの答えに好感を持ったか調べた論文が発表された。言うまでもなく、ChatGPTのほうが丁寧で、しかも患者の気持ちに寄り添っているという結果だった。
おそらく難病患者さんについても十分対応できるようになるだろう。この可能性を聞いて回った若手は限られていたが、現状を見るにつけ、5年前この日が来るのを予測できない若手研究者には少し失望した。
もう一つの理由は、現在行われている議論の多くが、GPTには創造性があるか、倫理性があるかなど、哲学的な話にまで発展していることだが、この議論がカントがヒュームに対して行った反論にとても似ていて、人間の理性とは何かという問題に直結しているからだ。これについては、今、「生命科学の目で読む哲学書」としてまとめている。
いずれにせよ、GPT-4などは、task agnosticと呼ばれ、特定の専門領域へと学習を方向付けることは着手されていない。しかし、私が医学に興味を持ち、医学部で学習し、その後も学習を続けて一定の専門家になるように、foundation modelも医学専門家へと育てる試みが行われるのは、医療や健康に関する消費額を考えると当然のことだ。
今日紹介するスタンフォード大学からの総説は、総合的医学AIを育てるfoundation modelの条件や、それが可能にする世界、さらにその問題についてまで論考した優れた総説で、さすがfoundation modelを最初に提案したスタンフォード大学と感心した。
順を追って紹介して行くと、ガチガチにタグ付けられたデータを必要とするこれまでの医学AIとは全く違う、例えば患者さんの経過とともに検査や画像など異なるモダリティーのデータを学習するとともに、医学を基礎づける文献、知識やグラフなどを、それぞれに表象させたトークンとして学習し、それぞれの関係性の確率をベースに、医師の必要に応じたデータをわかりやすく提示するGMAIと呼ばれるプラットフォームで、おそらく現在建設過程にあるのだと思う。先に述べたようにタグ付けが必要のない自己学習なので、極端に言えば患者さんの様々なレコードを学習するだけで、一般的医師のレベルを十分超える、能力を獲得すると考えられる。しかも、ChatGPTに見られるように、わかりやすい文章で提示したり記録したりしてくれる。
ではGAMIを医療でどう使えるのかについていくつかの例を挙げて説明している。
新しい画像について、レポートできる。例えば「この患者さんの経過で新しい病巣が発生しているか」と聞くと、画像上で新しい病巣を指しながらせつめいしてくれる。またこれに関する医療データも同時にレポートできる。
手術時に、経過のビデオをモニターしながら、言葉で手術の問題について指摘してくれる。また手術中に論文から引き出したアプローチについても教えてくれる。
手術場で役に立つと言うことは、ベッドサイドではもっと助かる。急速な悪化をモニターで検出すると、アラームだけでなく、理由も含めて警告を出し、場合によっては治療法を示唆できる。
今病院で働いている医師にとって何よりもうれしいのは、患者さんとの会話、検査データなどから、わかりやすい記録を書いてくれることだ。この結果、外来で医師がコンピュータにインプットする時間は完全削減される。例えば退院レポートなどは、勿論医師が後でチェックすることは重要だが、同じ形式で病院でレコード出来る。
医師だけでなく、患者さんの質問に対してChatGPTよりさらに詳しい、しかしわかりやすい対話が可能だ。特に、難病や希少疾患の場合はわかりやすく説明してもらえるのは重要だ。
勿論様々な文献にアクセスして引き出してくるので、ガンの遺伝子変異がわかると、蛋白構造まで示され、場合によっては新しい薬剤を使える可能性まで指示できる。
などなど、是非医師の方は自分で読んで未来を確認して欲しい。
ただ問題は、AIをビッグブラザーや神にしないためにも、しっかりと医師コミュニティーでバリデーションを行い、決して鵜呑みにしないことだ。
現在GPT-3だけで、300種類のアプリとリンクしている。おそらく、GMAIはそれぞれの医療現場での利用にあった、もっと多くのアプリとつながっていくだろう。勿論、エネルギーなど様々な問題はあるが、私はポジティブな評価をしている。
折しも、ソフトバンクが、勝ち負けではなくfondation model を日本でも始めることが重要だと述べたことが報道されていた。おそらくこの分野で我が国は大きく後れをとったのだと思う。それでも、始めることが大事だと思う。
2023年5月10日
昨年6月、single cellレベルでCRISPRを利用した遺伝子改変を行い、その効果をsingle cell RNA sequencingを用いて調べるPerturb-seqという技術について述べたカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文を紹介し(https://aasj.jp/news/watch/19994)、またその重要性からYoutubeでの解説も行った(https://www.youtube.com/watch?v=-Yddv5xuPC8 )。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、この技術を血液臨床にどう生かすかを様々な例で示した研究で5月2日Cellにオンライン掲載された。タイトルは「Massively parallel base editing to map variant effects in human hematopoiesis(徹底的なベース編集をもちいてヒトの造血をマップする)」だ。
以前紹介したPerturb-seqはCRISPRガイドRNAを用いて遺伝子をノックアウトし、その結果をsingle cell RNA seq(scRNAseq)で測る方法だったが、今日紹介するハーバード大学からの論文はタイトルにあるようにベース編集法を用いている。
ベース編集というのは遺伝子に切れ目を入れるのではなく、特定の核酸をAからTに変える方法で、現在ではCをGに、AをTに変える技術も進んでおり、ほぼ全てのゲノム領域を一塩基単位で変化させることが出来る。これは、血液発生に関わる多くの変異が一塩基置換であることを考えると、血液臨床に必須の技術になる。また血液は様々な系列に分化するので、scRNAseqにより一つの変異の効果を様々な系列で調べることが大事になる。実際には、突然変異の解析等、これまで個別の症例を詳しく解析する以外に方法がなかった課題が、一網打尽に明らかに出来る。
研究では、ベース編集を行う場所を決めるガイドRNAをレンチウイルスベクターでゲノムにインテグレートさせ、転写されたガイドRNAをscRNAseqで検出して、どのベース編集が起こったのかわかるようにしている。
ベース編集蛋白質は、遺伝子導入により行う代わりに、電気的穿孔による蛋白質の導入で行っている。これにより、編集効率は低下するが。一過性で安全な編集が可能になる。また、scRNAseqを用いることで、編集が行われていない血液が混じっていても、正確に効果が判定できる。
以上の技術を最も効果的に生かす課題として、将来の治療も視野にいくつかの課題を検討している。
CD33発現を低下させる編集法の開発:CD33は白血病の標的抗原だが、正常細胞にも発現している。このため、移植骨髄細胞のCD33遺伝子をノックアウトする方法が試みられている。この目的で、スプライシングに関わる塩基を編集して、正常CD33を効率よくノックアウトするためのガイドRNAのスクリーニングを行い、8割以上の編集成功率が達成できる編集箇所を特定している。
遺伝子編集が期待される病気の一つがサラセミアや鎌状赤血球症のようなヘモグロビン合成のアンバランスの病気だが、発現を抑制する分子のプロモーター領域を網羅的に編集して、この発現を低下させ、幼児型ヘモグロビンの発現を低下させるために最も有効な遺伝子編集部位を特定している。
GATA1は赤血球発生のマスター遺伝子で、これまでも様々な変異が知られている。この研究ではGATA1エクソンを網羅的に編集し、赤血球分化のステージごとにGATA1の機能に影響する一塩基変異を特定している。これらは既に人間の変異として知られている者を含むが、様々な形質を誘導する可能性のある遺伝子変異を網羅的にリストできたことは大きい。
強い赤血球性貧血が起こることで知られる変異を再現し、これが赤血球分化のみ影響する変異であることを正常細胞を用いて確認した。
以上は基本的にはCからTエディターを用いているが、他の塩基編集酵素でも同じ実験が可能。
以上、Perturb-seqでこれまで人間ではほとんど不可能で、マウスでようやく時間をかけて行ってきた実験が、やる気になれば一定の期間で行える時代が来たと、年寄りは目を見張るばかりだ。
2023年5月9日
ヒトの組織には当然様々な細菌が存在しており、解析された古代ゲノムの中には細菌叢由来ゲノムも混在している。これを利用して、たとえば5000年前のペスト菌のゲノムを調べ、中世のペスト菌と毒性を比べる研究をこのHPでも紹介した(https://aasj.jp/news/watch/4277 )。面白いところでは、現在のチューインガムのように噛んでいた白樺の皮に付着していた5700年前の口内細菌を特定し、虫歯菌は存在しないが、歯周病菌は現在と同じように存在することを示した研究も紹介した(https://aasj.jp/news/watch/14280 )。虫歯菌がいないことから、甘いものをほとんど食べなかったことは推察できるが、このように細菌叢の再構成は当時の生活状態を知るための欠かせないデータになる。
今日紹介するドイツ・イエナにあるライプニッツ研究所からの論文は、なんとネアンデルタール人の歯石から細菌ゲノムに存在する分子合成経路を再構成し、当時の細菌の合成していた分子を特定しようとしたチャレンジングな研究で、5月4日 Science にオンライン掲載された。タイトルは「Natural products from reconstructed bacterial genomes of the Middle and Upper Paleolithic(旧石器時代から中石器時代のゲノムから再構成したバテリア自然合成分子」 だ。
おそらくこの研究の本当の目的は、旧石器時代や中石器時代といった10万年以上まえの人間や動物と一緒に存在していた細菌ゲノムをどこまで詳しく特定できるかについて明らかにすることだったと思う。おそらく、口内細菌でも、腸内細菌でもどちらでも良かったのだと思うが、確実に古代の人間と存在している事が確実な点から、dental calculus=歯石を選んでいる。
問題は、この歯石から得られるDNAの中から古代人とともに生息していたバクテリアゲノムをどれだけ再構成出来るかだ。実際は、10万年も経っている顎骨から取り出した歯石のDNAは、変性の仕方から人間と同じ時期のゲノムである事が確実なものを選び出すと、30bp程度にズタズタに切断されており、ここから配列の重なりを見つけ出して、コードしている機能的遺伝子を特定するのは、大変な仕事だ。この時、現存細菌のゲノムをレファレンスに使ってしまうと、間違った方に誘導される心配があるので、レファレンスなしで配列を繋いでいく必要がある。私にはその難しさは想像できるが、使われたアプリケーションなど情報処理方法については全くフォローできていないので、本当の苦労はわからない。
いずれにせよ、大変な作業の末に、1kb以上の配列ストレッチを30-50万種類も再構成し、その中で10KBのストレッチが再構成できたのは8千から2万種類にも達している。また、再構成できたゲノムの7割は、現在の口内細菌のものと相同性があることから、歯石細菌は、死後に歯石に付着したのではないことも確認している。とはいえ、細菌叢研究という観点からは、あまりにも読めたゲノムが少ないので、一般的な口内細菌叢の研究を行うところまでには到底いかない。
そこでこの中からかなり完全なゲノム再構成が可能だった緑色硫黄細菌に絞って、得られたゲノムからその物質代謝経路を特定できるかに課題を切り替えて研究を進めている。緑色硫黄細菌は、現在ではまず口内常在菌ではない。したがって、本当にこの菌が10万年前のネアンデルタール人の口内に存在したかどうか難しい問題だが、すでに述べたように、歯石由来の場合口内細菌である確率が高いことから、10万年前のネアンデルタール人では、この細菌が口内に存在していたと考えられる。
次に。古代の緑色硫黄細菌と現在のところ同じ系統最近との比較を行い、決める事ができた配列から10万年前の緑色硫黄菌と、現在の緑色硫黄細菌は同じ系統に属するが、古代菌として多様性の低い、独自のグループを形成しており、当然これまで全く発見されてはいない細菌種であることを確認している。
次に再構成した古代細菌ゲノムの遺伝子の機能を実験的に確かめられるか、ブチルアセトン合成経路について検討し、現存の菌で見られるのと同じ3種類の核となる分子を挟んで全体で7つの遺伝子セットからなる合成経路の存在が古代菌にも存在することを確認している。これらの遺伝子は、地理的にも全く離れた古代人から分離されていても、遺伝子配列はほぼかんぜんに保存されており、機能的重要性を示している。
最後に、この3つの遺伝子を緑膿菌に導入し、これによりブチルアセトン合成が起こる事を確認している。
以上が結果で、現在の口内細菌の中には存在しないとはいえ、一種類の緑色硫黄細菌のゲノムを50%以上再構成し、またその中の一つの分子合成経路を現代細菌の中で再現できた事が素晴らしい。この研究が行われたイエナはライプチヒからも近く、最近はゲノム考古学によく顔を出すようになってきた。このようにライプチヒだけでなく旧東独地区が新しい科学の中心として進展していることは、ドイツに留学し、東西統合という歴史的事業を目にした私には感慨が深い。