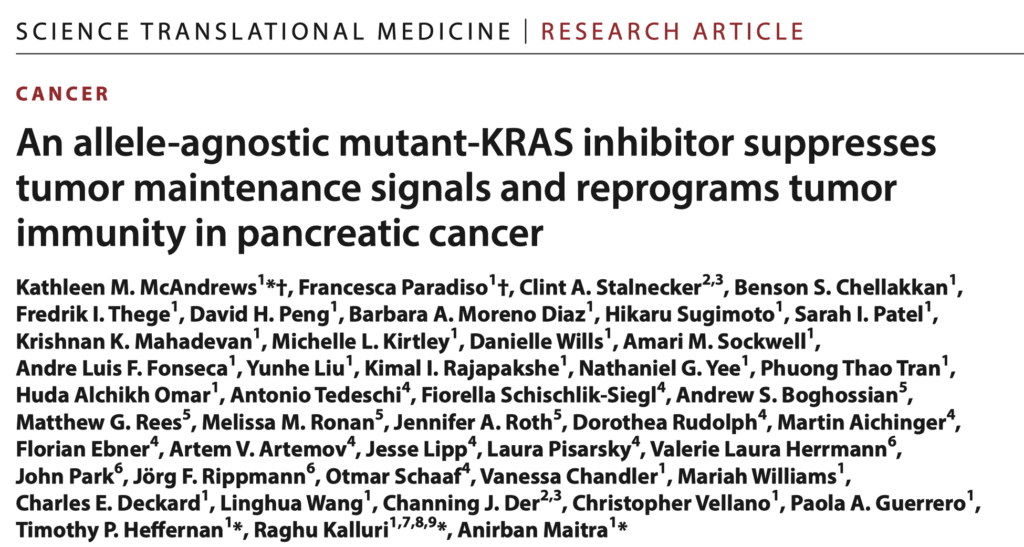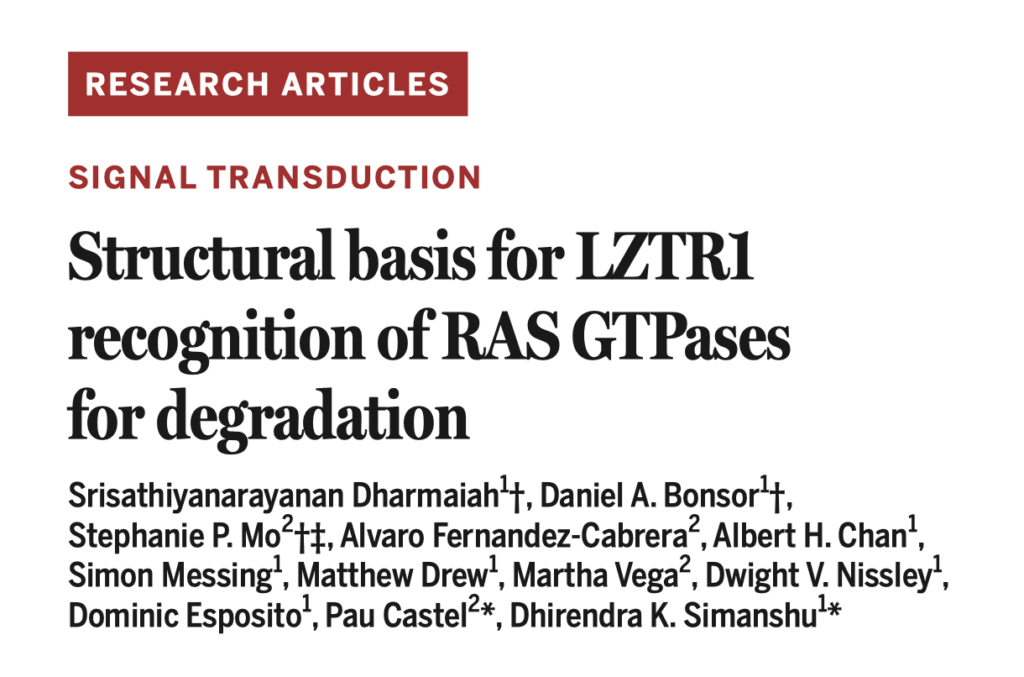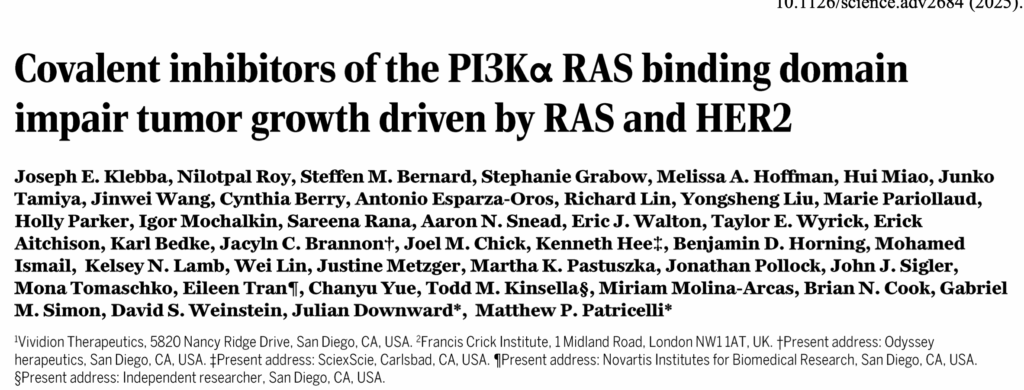2025年10月28日
変異配列を正常配列へと変えるための遺伝子編集の切り札として登場したのがハーバード大学の Lu により開発されたプライムエディターで、遺伝子をカットする Cas9 に逆転写酵素を結合させ、置き換えたい配列を局所で合成させて相同組み換えのテンプレートにする方法だ。ただDNAミスマッチ修復メカニズムが働いて効率を低下させるなどの問題があり、現在はこれらの問題を解決し、コンパクトな遺伝子編集システムを完成させる研究が続いている。
今日紹介するテキサス大学オースティン校からの論文は、元々細菌がファージの増殖を止めるために開発してきたレトロンと呼ばれる逆転写酵素と long-noncoding RNA を CRISPR と組み合わせて、効率の高いプライムエディター開発研究で、10月23日 Nature Biotechnology にオンライン掲載された。タイトルは「Discovery and engineering of retrons for precise genome editing(正確なゲノム編集のためのレトロンの発見と操作)」だ。
レトロンとは、標的RNAの特異性を持つ逆転写酵素とそれに認識されプライマーなしに一本鎖DNA (ssDNA) へと転写される non-coding RNA の組み合わせからできている。このRNAは認識されるための特殊な構造を持っているが、一部は自由に変更できる。これを利用すると、目的の配列を持った一本鎖DNAを合成させることができる。
この逆転写酵素と Cas9 結合させると、Cas9 が切断した領域に合成された ssDNA が濃縮されるため、相同組み換え機構が働くとテンプレートの配列に変異配列を置き換えることができる。ただ、元々細菌の抗ファージシステムとして進化してきたので、哺乳動物で働く効率が低いなど様々な問題があった。
この研究では考えられる問題を一つ一つ解決して、実際に胚操作に使えるまでのリトロンシステムを組み上げるための詳細な条件検討が行われている。まず、哺乳動物でも働くリトロンシステムを探し出すため、データベースから500種類のレトロンを選び、そのうち98種類について実際に正確な編集効率を指標にして、最適なレトロン逆転写酵素探索、最終的に Escherichia fergusonii (Efe1) 由来のレトロン逆転写酵素を選び出している。これを使うと編集効率は20−30%という効率になる。
次にこのレトロン逆転写酵素の認識効率のいい non-coding RNA の条件を絞り込んでいる。この方法でいくつかのゲノム領域の編集を行い、99%以上が目的の配列に置き換えられることを示している。
このシステムは Cas9 と組み合わせるので、Cas9 のガイドとリトロン non-doding RNA の転写条件、あるいは Cas9 とレトロン逆転写酵素をつなぐリンカーの条件など詳細に検討して最適の組み合わせを選んでいる。また、核内移行シグナルについても様々なシグナルの中からトライアンドエラーで選んで、効率を高めている。こうして選んだリンカーなどを使うと、Cas9 だけでなく、Cas12 とも組み合わせられ、Cas9 より高い効率での編集が可能になることも示している。
プライムエディターの最大の敵は、NMHJ による遺伝子修復で、これを防ぐ様々な方法も提案している。最もストレートなのは修復酵素を阻害することで、DNA-PKcs を阻害するだけで効率を何倍も伸ばすことができる。更には細胞周期をS期以降の広範に止めることで、相同組み換えが上昇する事も示している。
以上は培養細胞を標的にした遺伝子編集だが、ゼブラフィッシュの卵にmRNAの形で必要なコンポーネントを注入することで、平均で3%、場合によっては10%近い遺伝子編集効率が得られることを示している。
最近遺伝子編集は臨床応用段階と決め込んで新しい方法をしっかりフォローしていなかったが、開発のエネルギーは落ちていない。100%を目指す遺伝子編集もいつかは可能かもしれない。
2025年10月27日
セロトニンと聞くと、うつ病の治療にセロトニン再吸収阻害剤が使われていることから、脳でのシナプス伝達因子として感情や社会行動などに関わるというイメージが強いと思うが、セロトニンのほとんどは腸内のクロム親和性細胞から作られている。これだけ大量のセロトニンが腸で作られても脳血管関門を超えないので、作用は腸内でとどまり、蠕動などの調節に関わると考えられている。
これほど腸の細胞がセロトニンを合成しているのに、細菌叢研究ではかなり前から細菌叢がセロトニンを作って我々の腸の機能に影響があるのではという可能性が指摘され、論文も発表されてきた。ただ、ヒト細菌叢の中のセロトニン合成細菌を特定するまでには至っていない。
今日紹介するスウェーデンヨテボリ大学からの論文は、ヒト細菌叢からセロトニン合成細菌を特定し、マウスモデルで細菌が合成したセロトニンも腸内神経叢の機能に作用できることを示した研究で、10月20日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Identification of human gut bacteria that produce bioactive serotonin and promote colonic innervation(セロトニンを合成し腸の神経投射を促進するヒト腸内細菌)」だ。
この研究ではこれまで議論されてきた腸内細菌叢がセロトニンを合成しているかという問題を、腸でのセロトニン合成に関わる酵素をノックアウトしたマウスを用いてセロトニンが細菌叢以外から合成できない系で調べている。その結果、血清中のセロトニンは細菌叢の有り無しで全く変化ないが、便中のセロトニンは細菌叢由来部分が全体の半分ぐらいを占めていることを確認する。
次に、ヒト腸内細菌叢を様々な条件で培養し、セロトニン合成細菌の特定を試みている。詳しく書かれていないが、この部分が最も難しかったと思う。最終的にバクテリアの組み合わせの中から、2種類の乳酸菌が共存する場合にセロトニンが試験管内で合成されることを突き止める。それぞれ片方のバクテリアだけでは全く合成されないことから、よく見つかったと感心する。
セロトニン合成代謝物について調べて、これらの細菌は 5-HTP を脱カルボキシレーションすることでセロトニンを合成することを確認している。ただ、これも両方のバクテリアが存在する必要があり、より詳しい解析が必要に感じる。
次に、この2種類のバクテリアを Tph 欠損マウス腸内に移植すると、血清中のセロトニンには変化ないが便中のセロトニンや、腸組織内でのセロトニンが上昇する事を確認し、試験管内だけでなく、腸内でもセロトニン合成が起こることを示している。こうしてセロトニンを腸内で合成できるようになった Tph 欠損マウスの腸組織を調べると、腸内神経叢の発達が促進されていることを発見している。即ち、バクテリアから出会っても腸内でセロトニンが存在することが、腸内神経叢の発達を促し、結果として便通促進に役立つことを明らかにしている。
最後に人間の炎症性腸疾患でこれらの細菌叢に変化があるかどうかを調べている。便中のセロトニンレベルは患者さんと正常人で差がないものの、2種類のうちの細菌の一つ L.mucosae が少し低下していることを確認している。ただ、このデータからバクテリア由来のセロトニンが我々人間でも機能維持に重要かどうか結論することはできない。
以上が結果で、ともかく細菌叢からセロトニンが分泌されることはわかった。ただ、正常のマウスやヒトで、この2種類の細菌により合成されるセロトニンが、腸で合成されているセロトニンに加えて重要かどうかはわからずじまいで終わったと思う。
2025年10月26日
加齢黄斑変性症でも geographical atrophy と呼ばれる進行型になり中心窩が傷害されると視力が急速に低下する。この段階になると新生血管を抑制する治療の効果はなく、再生医療などが残された方法として考えられるが、もう一つの方向は電子センサーにより光を電気パルスに変換して網膜の残った細胞に画像を伝える方法だ。ただ解像度や大きさの問題などから決め手になる方法にはなっていない。
これに対しスタンフォード大学のグループは、光を電気パルスに変えるダイオード ( eye chip) を網膜に埋め込み、これにビデオカメラを通して得られた像を直接投射し、ここで生まれる電気パルスを残っている細胞(主に双極細胞を考えている。)に処理させて画像認識を再構築する方法を考案し、2012年 Nature Photonics に発表していた(Nature Photonics Vol 6, 391, 2012)。
この時から10年、今日紹介するボン大学を中心とする国際治験グループからの論文は、38人の患者さんへ eye chip の移植手術を行い、大きな視力回復が得られたことを報告する研究で、10月20日 The New England Journal of Medicine に掲載された。タイトルは「Subretinal Photovoltaic Implant to Restore Vision in Geographic Atrophy Due to AMD(網膜下の光電インプラントは加齢黄斑変性症の geographic atrophy 患者さんの視力を回復できる)」だ。
この方法は自然光の代わりに光電ダイオードに感知しやすい赤外線に変えてダイオードに投射し、これを画像として感知して貰うようできている。従って、熱が発生しない領域を用いて画像を投射している。
画像はまずめがねに装着したカメラで取り込み、それを赤外線に変換するが、患者さん自身でズームをかけたりピントを合わせられるようになっており、基本的には文字を読むためのめがねといった感じで使われる。人工網膜は 2mm 四方で 30μM の大きさしかないが378画素が搭載されており、文字を読んだりするには十分だ。
評価については、1年後十分残りの神経細胞が eye chip からのシグナルを処理できるようになってから行っており、おそらく予想を超える結果になったのだと思う。まず、カメラ付きめがねをかけない自然視力は全く元のままだが、これは当然のことだ。
しかし、特に文字を読むときには、大きな改善が見られることを示しており、実際 0.1mm の小さなさも検出できている。専門的な logMAR という指標で0.5の改善ということは、ほとんど日常の読み書きには不自由しないというレベルの改善といえる。また、患者さんは1年たつと機械になれ、用途に合わせてzoomしたり、ピントを合わせたりして使いこなすようになる。
もちろん手術なので、様々な副作用もある。一番多いのは眼圧の上昇で、次に網膜の断裂等などが続く。しかし95%は2ヶ月以内に症状は消え、最終的に38人中32人が1年目の検査まで到達している。
以上が結果で、最終的には3年までフォローが行われるのでその結果がまた報告されるだろう。今後再生医療との厳密な比較が行われていくと思うが、おそらくコストで言うと今のところは eychip に軍配が上がるのではないだろうか。
2025年10月25日
朝のウォーキングが唯一の運動だが、10月も終わりに近づくと歩き出しはすっかり暗くなった。とは言え、自分自身の概日周期は時計の時間に支配されており、あまり季節に合わせて変化したようには思えない。しかし、途中で見聞きする鳥の活動は間違いなく季節調整が行われていることがわかる。このような季節によって変化する概日周期にアジャストするメカニズムはまだわかっていないことが多い。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、冬時間、夏時間にアジャストするとき、食事中の不飽和脂肪酸が重要な働きを演じていることを示した面白い研究で、10月23日号の Science に掲載された。タイトルは「Unsaturated fat alters clock phosphorylation to align rhythms to the season in mice(不飽和脂肪酸はマウスの時計分子のリン酸化を変化させて概日周期を季節にアジャストする)」だ。
この研究では昼12/夜12時間の季節から、昼4/夜20時間の冬、あるいは昼20/夜4時間の夏に実験室の光環境を変えたときに、マウスの行動がどう変化するかを調べ、身体の周期の適応を調べている。冬時間にアジャストするのに大体1日0.2時間程度のスピードで40日ぐらいかかって冬時間に適応するが、この時高脂肪食を自由に食べさせるとこの適応が大きく遅れることを発見する。逆にカロリー制限すると、適応のスピードが上がり20日もすると適応がほぼ完成する。一方、昼20/夜4の夏時間への適応を調べると、今度は高脂肪食の方が早く適応し、カロリー制限では適応が遅い。
この適応に時計遺伝子PER2の量とリン酸化が関わることがわかっているので、遺伝的に常にPER2がリン酸化されている変異、あるいはリン酸化されない変異を持つマウスを調べると、活性化型変異では夏時間への適応、不活性型変異では冬時間への適応していることがわかる。そして、高脂肪食では活性化型が上昇しており、これが冬時間への適応を抑制し、夏時間への適応を促進していることがわかる。逆にカロリー制限を行うと活性化型PER2が低下する。即ち、脂肪の摂取が季節への適応を変化させることがわかる。
高脂肪食の内容を精査し、実際に影響するのが不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸の量比であることを突き止め、最終的に不飽和脂肪酸が2つの経路を通して季節時間への身体の周期調節に関わることを明らかにしている。
一つは、不飽和脂肪酸が直接PER2に作用してリン酸化を高め、夏時間への適応を促進する。同時に、不飽和脂肪酸の代謝酵素が概日周期により調整され、活性化型PER2によりオピオイドの一つオキシリピンへと転換され、体温や行動を変化させる一因として働く。
以上が結果で、食によってリン酸化PER2の量を調節することで、夏時間と冬時間の適応が可能になっているという面白い結果だ。昼4/夜20時間というと日本よりより緯度の高い地域だが、季節の変化が激しいことは、食物も大きく変化することを意味している。それぞれの季節で野生の動物が摂取する不飽和脂肪酸がどう変化するのかは把握していないが、おそらく季節によりリン酸化を高めたり抑えたりする鍵になることは十分納得できる。
翻って我々人間を考えてみると、季節とはお構いなしに人工光の中で、勝手に食べたいものを選んでいる。まだ、自然への適応力が残っており、不飽和脂肪酸とPER2がこれを調節するのか是非知りたいところだ。
2025年10月24日
出産と授乳を繰り返した人は乳ガンの発生率が低いことはよく知られている。一方で乳ガンのゲノム研究は、乳腺が生理サイクルや出産授乳というホルモン環境の大きな変化を経過する度に、特にホルモン反応性の遺伝子に変異を蓄積することを示してきた。
今日紹介するメルボルン大学からの論文は、乳腺組織の出産と授乳による変化が長期にわたって乳腺に常在し、乳ガンを抑える組織常在型のキラーT細胞を誘導することを示し、乳腺にまつわる謎を一つ解決した研究で、10月22日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Parity and lactation induce T cell mediated breast cancer protection(出産と授乳はT細胞による乳ガン予防を誘導する)」だ。
ホルモン環境の変化による乳腺の大きなリモデリングが、新しい抗原の誘導やホルモンを介して局所T細胞を刺激する可能性は十分考えられる。著者らはこの可能性を、実際の乳腺組織に存在するリンパ球を調べることでまず確かめようとしている。そこで目を付けたのが、BRACA変異などの乳ガンリスクを持つ人が予防的に受ける乳腺切除で、この組織に存在する免疫細胞を、出産経験のある人とない人で比べている。すると、組織常在型のCD8キラー細胞の数が2倍以上に上昇していることがわかった。しかも、この状態が出産経験後何年も維持されていることも明らかにしている。
即ち、出産と授乳という大きなリモデリングにより、キラーT細胞が局所で誘導され、またそのときのホルモン環境がT細胞にも働いて、組織常在型のT細胞へと変化するという話だ。ただ、これが一般化できるかどうかわからないのは、乳ガンの遺伝リスクがはっきりとした女性の組織を調べている点で、DNA修復異常の結果、新しい抗原が発生する確率が高い状態に限定した結果だということは留意する必要があるだろう。
そこで動物実験に移り、一回目の出産に限り授乳を終えて乳腺が縮小まで進んだ個体、出産はしたが授乳を途中で中断した個体、そして出産を経験しない個体で乳腺組織の免疫細胞を調べると、授乳を終えて乳腺が元に戻る過程を経験した個体だけ組織中の常在型CD8T細胞数が上昇していることが確認された。さらに、免疫刺激に関わる樹状細胞も上昇が見られている。
この状態で乳ガンを移植する実験を行うと、出産授乳を終えた個体では腫瘍の増殖が明確に抑えられる。また、ガンが発現している抗原に対するT細胞の誘導が認められる。免疫不全マウスや移植実験から、ガンに対する免疫はもっぱらCD8T細胞を介しており、常在型T細胞だけでなく、ガン組織への新しいT細胞の供給を必要とする免疫反応であることがわかる。
最後に乳ガンのコホート研究から得られる組織を調べて、出産授乳を経験している乳ガン患者さんで、組織に浸潤しているT細胞が明確に増えていること、さらにホルモンの影響を受けない乳ガンでは出産授乳を経験した女性の方が予後良いことも明らかにしている。
以上、基本的にはホルモンの影響を受けないトリプルネガティブ乳ガンについての話になるが、乳ガン抑制での免疫反応の役割は大きく、マウスでも人間でもこの免疫反応は、生理サイクルではなく、出産と授乳という長期に続くホルモン環境の変化によっておこる乳腺細胞の変化により誘導されるという結論だ。
このように、生理、出産、授乳により何度もリプログラミングを繰り返す乳腺は常に発ガンへのドライブがかかっているが、これを早く察知して異常細胞を抑制するいわゆる免疫サーべーランスが存在することの証明だと思う。
2025年10月23日
長年開発が難しかったRASに対する標的薬も、G12C変異特異的な sotolasib をきっかけに、他の変異もカバーできる panRAS標的薬が治験段階に入るなど、実用が期待される段階に入った。今日は、まだ実験段階の新しいRAS標的薬についての論文をいくつかまとめて紹介する。
まず最初のテキサスMDアンダーソン研究所からの論文は、pan-RAS阻害薬の効き方について調べるとともに、今後の治療戦略の方向性を考えた論文で、9月3日 Science Translational Medicine に掲載された。
研究では様々な膵臓ガンモデルを用いて、pan-RAS阻害剤の一つ BI-2493 の効果を調べている。KRAS のG12D変異に対する効果が最も強いが、他の全てのタイプの変異に対して効果を示すとともに、正常RASに対する効果もある。この部分が、変異タイプ特異的な薬剤と違っており、検討が必要になる。
効果だが、細胞周期の進行を抑えるとともに、間質型から上皮型への転換を誘導し、さらに代謝的にグリコリシス優位から、ミトコンドリアでの酸化的リン酸化優位へと転換する。
様々なマウスモデルを用いて調べると、pan-RAS阻害薬はガンの周りの間質形成を抑えるとともに、キラーT細胞の浸潤を高める。その結果、PD-1抗体によるチェックポイント治療の効果を高める。実際、pan-RAS阻害剤も当然耐性が生まれてくるが、免疫を維持できればこれを乗り越えられる可能性が出てくる。また、耐性を持つガン細胞はYAP経路の活性が上がるので、現在治験中のYAP阻害剤との併用が期待できる。
以上、すぐ始まる臨床応用を念頭に、モデル系で徹底的に調べることがいかに重要かがわかる。
次はフレデリックガン研究所からの論文で、薬剤開発までは至っていないが、新しい薬剤開発の方向性を示す重要な論文で、9月11日 Science に掲載された。
以前、VHLユビキチンリガーゼをRASにリクルートして分解させるプロタック薬剤について紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/25247 )、この研究もこの方向性を狙っている。ただ、RAS本来のタンパク量を調節しているユビキチンリガーゼをRASにリクルートするアダプター分子LZTR1とRASの結合を構造的、更には突然変異導入をとおして解析して、両者が結合する領域をピンポイントで特定し、今後この部位をより強く LZTR1 と結合しやすくするプロタックを開発するための基盤を提供している。
構造研究なので詳しくは述べないが、LZTR1 やそれと結合する RIT1 の変異は、シュワン細胞種が頻発し、ガンになりやすいことから、本来のRASのタンパク量調節因子と知られていたので、より自然の系をプロタックに用いる新しい治療開発へとつながる可能性がある。
最後に紹介する英国クリック研究所からの論文はRASシグナルの重要な柱PI3KとRASの結合を標的にした、共有結合型阻害薬の開発で、これまでのRAS標的薬と併用することでより長期の効果を期待できることを示した研究で、10月9日 Science にオンライン掲載された。
標的のシステイン残基を用いて共有結合できるリガンドは、安定に標的と結合するので高い効果が期待できる。G12Cを標的にした sotolasib もその一つだ。この研究ではPI3KのRAS結合サイトに存在するシステインを狙った薬剤を探索し、最終的にVVD-442という化合物を突き止めている。
試験管内、マウスモデルを用いた研究から、これはRASとPi3Kの結合を特異的に阻害し、RAS依存的なガン細胞の増殖を抑える。特にG12Dに効果が高いが、逆に sotolasib の標的になるG12Cの効果は低い。また、RASとは無関係にEGFRによるPI3Kの阻害効果を持つが、インシュリンリセプターによるPI3Kの活性化は抑制されないため、糖代謝への影響はほとんどない。
マウスへのガン移植モデルで高い効果を示すが、panRAS阻害剤と比べると効果が低い傾向がある。もちろん panRAS阻害剤でも耐性が発生するが、両者を組み合わせると100日間全く耐性なしに腫瘍を抑えられることを示している。
この論文以外にも今年の7月同じシステイン残基を標的にした薬剤開発が報告されており、この戦略もRAS依存性ガンの重要である事がわかる。
以上RASの制御研究が加速しており、特に治療の難しい膵臓ガン治療を大きく変えてくれることを期待する。
2025年10月22日
昨年のノーベル物理学賞は、ニューラルネットを用いた機械学習に対して、ホップフィールドとヒントンの二人に与えられた。これに対し理研の脳研におられた甘利さんは、物理学賞が「物の理」を研究する領域から、「事の理」へと広がったとコメントしていた。この「ものとこと」は、京大医学部教授会で一緒だった木村敏さんの哲学の基本で、「もの」には客観性が存在するのに対し「こと」とは「こと」ば (言葉)でのみ語られる主観と客観の間にある何かと述べられていた。どちらも日本語に即した捉え方だが、西欧的に翻訳し直すと Physics と Metaphysics と言ってもいいのではないかと個人的には思っている。Metaphysics とは哲学の用語に見えるが、これを「物理」を超えると読み換えてみると、理解してもらえるのではないだろうか。そして、自然史研究の18世紀以来、生物学は Metaphysics を科学として取り扱い、ダーウィンの進化アルゴリズム、メンデルの生命情報へと発展した。こう考えると、ニューラルネットを導入したノーベル物理学賞は、まさに物理学がアルゴリズムと情報を世界の説明に用いる metaphysics = 生命科学 の領域へと拡大されたと私には思える。既に Organism を扱うノーベル化学賞は生命科学へと拡大していることを考えると、ノーベル賞の分類そのものが意味をなさない時代が来たように思える。
このように、私は生成AIは元々生命科学の領域に近いと思っているが、今日紹介する中国精華大学からの論文は、Transformer を用いて物理現象から公式を導き出すモデルが作成できることを示した研究で、10月15日 Nature Machine Intelligence に掲載された。タイトルは「A neural symbolic model for space physics(宇宙物理のためのニューラル記号モデル)」だ。
これまで何度も断ってきたが、私は物理と数学が今も苦手で、この論文で行われている数理処理については全く理解できていない。ただ、transformer/attention のようなモデルが物理の公式を導き出すのに使えるということを知って、physics と metaphysics の関係をこれからは分離するのではなく、統合的に見ていくべきだと考え、字面を追ってこの論文がしようとしていることだけを紹介することにした。
イントロで述べられているが、惑星運動のケプラーの法則や、ファラデーの電磁誘導法則は、観測結果を集めて、これをさらに一般化するため導き出された公式と言える。このような公式化を観測データから自動的に行う方法の開発がこれまでも進められており、Genetic Algorithm 法や Monte Carlo Tree Search (MCTC) 等が開発されていたようだ。即ち、物理現象を公式化するアルゴリズムの開発が進んでいた。
このようなアルゴリズムが適用できるのなら、当然 Transformer/attention ベースの言語モデルをこれに使えないかと考え、開発したのが PhyE2E で、Physics と end to end という言葉を使って、近似法ではなく、現象全体を一般化できる公式を導き出すという意図が現れている。
方法だが、現在存在する現象と公式セットだけでは不十分な学習しかできないので、最初 LLM を物理公式でファインチューニングしたあと、27万種類の物理公式を生成させ、これを使って PhyE2E を学習させている。
次にデータだが、まずオラクルニューラルネットを用いて観測データでの変数の相互作用を計算、それを部分式に分解するという前処理を行い、これを学習させた PhyE2E にインプットすると、公式の候補が出てくる。これについてのほとんど評価することはできないのだが、普通の LLM と比べるとかなり複雑だ。しかも出てきた候補を初期値として、さらに既存の genetic algorithm や MCTC を用いて最適の公式が導き出せるようにしている。間違っているかもしれないが、既存のアルゴリズムも含めてあらゆる方法を統合するのがこのモデルと言えるのではないだろうか。
さて結果だが、太陽の黒点数、地球近傍プラズマ圧、太陽の自転角度、局紫外線放射強度、月潮汐による磁気圏電場を説明する公式を導き出している。評価については、より単純な数式で物理単位の整合性があるかどうかを既存のアルゴリズムで導いた公式と比べ、精度が向上していることを示している。
以上が結果で、どのぐらい有用かについては今後物理学での利用を通して評価されていくのだと思うが、個人的には物理学は全く言語モデルから無関係かと思っていたが、人間の全ての活動に LLM が適用できることを知って気持ちを新たにした。
もちろんこの方法で、アインシュタインの一般相対性理論のような抽象的理論構造に基づく方程式が出てくるとは思わないが、physics と metaphysics が異なる方向性から統合するのではないかと期待を持った。
2025年10月21日
血中に流れてくるガン細胞は circulating tumor cell (CTC) と呼ばれ、このブログでも2014年以来何度か紹介してきた。ただ最初の期待とは異なり、10年以上経過しても臨床への展開が進んでいるとは言いがたいように感じる。おそらく早い段階から CTC を見つけるのは難しいことが最大の理由だと思う。
ただ、進行したガンでは CTC がほとんどのケースで検出でき、血中のガン細胞の血栓や大血管への浸潤がその一因である事を示す臨床研究が、テキサスサウスウェスタン大学を中心とする国際チームから10月16日 Nature Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Macrovascular tumor infiltration and circulating tumor cell cluster dynamics in patients with cancer approaching the end of life(大血管への腫瘍細胞浸潤と血中の腫瘍細胞塊の終末期ガン患者さんでの動態)」だ。
この研究が面白いのは、末期のガン患者さんが亡くなる原因は何なんだろうと疑問を持った点だ。そこで、固形ガンで亡くなった108例について、専門家に死因を診断して貰ったところ、意見の一致を見たのが16%だけで、51%のケースでは多くの専門家が最終診断を否定するという結果に終わっている。
なぜこんな話から始まるかというと、著者らは終末期のガン患者さんの死因の多くは腫瘍による血栓や大血管への浸潤による循環障害でないかと考えたからだ。そこで解剖例で組織検査を再検討すると、静脈や動脈での腫瘍塞栓の頻度は極めて高く、10%の患者さんでは大血管に塞栓が見られていた。次にCTスキャンが行われた101例で見ると、60例で大血管への浸潤を認めることができた。
そこで承諾が得られた終末期の患者さん21例について、亡くなるまで血液凝固検査を行うとともに血中の CTC を調べると、67%の患者さんで凝固指数が上昇するとともに亡くなる1日前から血中の CTC 数が急増し、またCTスキャンで大血管への浸潤を検出することができた。即ち、腫瘍細胞塊の急速な循環への流入が終末期の死亡原因の一つとなり得ることを示している。
次いで、CTスキャンで血管への浸潤が認められた患者さんと、そうでない患者さんでの予後を調べると、ガンの種類を問わず血管内浸潤が見られる場合、極端に予後が悪くなることを示している。
元々 CTC の見つかる患者さんでは予後が悪いことは知られており、ガンの血管への浸潤が全身状態を悪くする大きな原因になることを示した、臨床家として高いセンスを示す研究だと思う。ただ、浸潤防止策が明確でない限り、予後を分類するだけではむなしい。是非この原因を探る研究が進むことを期待する。
2025年10月20日
電子顕微鏡 (EM) というと、組織が処理された瞬間のスナップショットに限定され、どうしても時間経過を調べるのは苦手な印象があった。しかし、クライオ電顕が進むのと並行して、サンプルを超低温の液体エタンなどに突っ込むタイミングを変えて、時間的な解析をEMで観察する方法が開発されてきた。
今日紹介する中国科学技術大学からの論文は、神経刺激を受けたシナプスでのシナプス小胞の動態をmsスケールで追跡した研究で、10月16日号の Science に掲載された。タイトルは「“Kiss-shrink-run” unifies mechanisms for synaptic vesicle exocytosis and hyperfast recycling(”キス、縮小、移動“はシナプス小胞の開口放出の極めて早いリサイクリングを統合するメカニズム)」だ。
この論文を読むまでシナプスでの伝達は、シナプス小胞がシナプス膜と融合し、内部の神経伝達因子を吐き出した後、小胞はシナプス膜に同化してしまうと思っていた。即ち、一旦使うと小胞はもう再利用されないと思っていた。
これも間違いではないのだが、もう一つの考え方がタイトルにある ”Kiss-shrink-run” という過程で、シナプス膜と小さな融合を形成した後、ぐっと縮んで伝達因子を吐き出し、あとはシナプス膜から内部に遊離してシナプスを離れ、おそらく再利用されるという考え方だ。この考え方だと、シナプス膜が小胞膜に置き換わってしまってシナプス小胞の結合スペースが無くなるという問題は解決できる。ただ、大体0.1秒程度で起こる現象を経時的に見るのは難しいため、研究が進んでいなかった。
この研究では海馬の興奮神経を取り出して、自然の興奮を全て抑えたあと、光遺伝学的に刺激を加えたときにシナプスで起こる現象を経時的に追跡できる実験システムを構築している。即ちグリッドで培養した神経シナプスに光刺激の後、4,8,30,70msのあとサンプルを液体エタンに漬けるシステムを構築し、100ms程度で起こるシナプス活動を時間を追って観察した。
時間経過を追う前に、シナプスでの小胞を詳細に分類し、膜と接した大きな小胞や融合した小さな小胞など、経過をうかがわせる形態が、シナプス膜の近くのアクティブゾーンに濃縮することを観察し、この分類に基づいて時間経過で起こる現象を解析している。
結果は kiss-shirink-run と一致しており、4msでは、圧倒的に大きな小胞が膜と接して融合を始める像が見られるが、その後穴が空いた大きな小胞、その後穴が空いた小さな小胞、そして70msになると孔が閉じた小さな小胞と、アクティブゾーンに存在する小胞の形態が変化する。即ち、kiss-shrinkの像が見られる。
そのあと、時間がたつとアクティブゾーン外に小さな小胞が見られるようになるので、おそらく小胞はシナプス膜から離れる方向に動くと考えられる。同時に100msを超えるとシナプスでのエンドサイトーシスが起こることから、これによりシナプス膜に残るシナプス小胞の膜を除去しているのではと推論している。これにより、機能的なシナプス膜が保たれる。
以上が結果で、ここまでの時間経過を高解像度で見ることができるのかと驚くとともに、シナプス活動についての考えを改めることができた。見る技術の進歩は休むことがない。
2025年10月19日
動物は自らを様々な感染から守る本能的行動を示すことが知られている。例えば感染した個体を察知して避ける行動などがある。また、感染した個体を巣から取り除くこともある。ただ、今日紹介する英国ブリストル大学からの論文は、アリは集団感染を守るために感染個体の行動が変容するだけでなく、それを察知した健康個体が巣の構造を変化させて感染を防御するダイナミックな行動変化を示すという驚くべき研究で、10月16日 Science に掲載された。タイトルは「Architectural immunity: Ants alter their nest networks to prevent epidemics(建築による免疫:アリは伝染病の広がりを防ぐ為に巣のネットワークを変化させる)」だ。
この研究は、最初から集団の一部が感染したとき、人間のような衛生学的対応が見られるかという問いに向けられている。ガラス容器の中に土を入れて、180匹のアリに巣を作らせる。この時、昆虫の病原性真菌に暴露した20匹の個体を同じ容器の中に入れたとき、感染個体や集団はどのような反応を示すかを詳しく観察している。また、巣の構造についてはCTを用いて解析している。既に述べたように、この実験では感染個体については自分も含めて検知できるということを前提としている。
さて結果だが、まず感染個体は巣の中で過ごすことを避け、なるべく巣の外で過ごそうとしていることがわかる。即ち、自分で感染を察知して自ら自己隔離を行うか、あるいは健康な個体から何らかのシグナルが出て、外で過ごすようになるかだ。これにより、感染を防ぐディスタンシングが可能になる。
ここまでなら驚かないが、その上で感染を感知した健康個体の巣作りが変化する。まず、巣と外界をつなぐ入り口同士の距離が広がり、アリのコンタクトが減る。感染アリは地中で行動しなくなるので巣作りの効率は低下すると予想できるが、全く逆で、健康アリの活動が高まり、より大きな巣ができる。巣全体が大きくなることは感染を防ぐためには寄与すると考えられる。すなわち、健康アリが感染の存在を察知して活動性を上昇させる。
ただ、これにとどまらず巣の構造自体も変化する。まず入り口の距離が離して作られる。そして巣全体が長いトンネルでつながるようになり、部屋と部屋の間が広がる構造をとる。さらに、トンネルや部屋の広さが広くなる。
これらの変化によって本当に感染が防げるかについては実験は行われていない。代わりに、いくつかの条件を決めてシミュレーションを行って感染確率を低下させると結論している。
以上が結果で、できすぎた話に見える。まず感染が察知されることについてはこれまでの研究もあるので、察知して感染個体も非感染個体も行動を変化させることは納得できる。しかし、自然条件では既に巣ができあがっているところに感染が発生すると思うので、感染を察知できても、すぐに全体の構造を新たに変化させることは難しいように感じる。従って巣ができあがった条件では、特に守るべき幼虫を、感染個体から隔離するのが重要に思えるが、ここまでわかるような実験系で是非調べて貰いたいと思う。