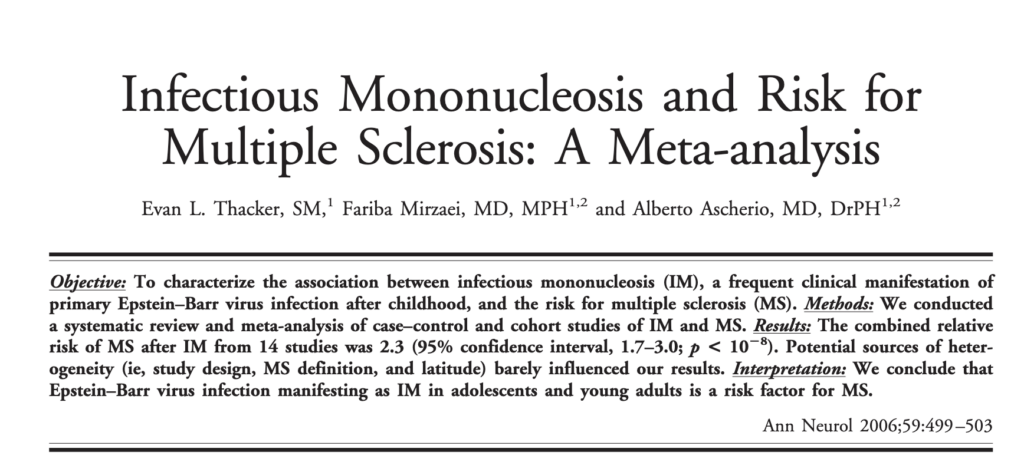2022年1月18日
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は常在菌だが、免疫が低下した方に感染してしまうと、抗生物質が効かないため治療が難しい感染症を引き起こす。抗生物質耐性であることから、抗生物質を投与された家畜で発生した例外的なケースを除いては、病院内で抗生物質が使われることで発生すると考えられていた。もちろん私もそう考えていた。
ところが、今日紹介するデンマーク国立血清研究所を中心とする多施設共同論文は、ハリネズミと人間のMRSAを比較することで、MRSAは抗生物質が誕生するずっと前からおそらくハリネズミの中で発生していたことを示した、まさに「(科学的)事実は小説より奇なり」を地で行く研究で、1月5日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Emergence of methicillin resistance predates the clinical use of antibiotics(メチシリン耐性は抗生物質が臨床で使用されるより前に誕生していた)」だ。
ヨーロッパのハリネズミは200年ほど前にニュージーランドから持ち込まれた外来種で、おそらく定期的な調査対象になっていたのだろう。デンマークとスウェーデンで行われたハリネズム調査は、MRSAが北欧のハリネズミに広く分布しているとする驚きの結果を示した。
MRSAを病院感染由来と思うと、この結果は人間から持ち込まれたMRSAがハリネズムに拡がったと言うことになるが、そこに逆転の発想が持ち込まれ、ひょっとしたらMRSAの発生はハリネズミが先ではないかと考えたのが今回の研究だ。
英国、デンマークを中心に、ヨーロッパの広い地域でハリネズミに耐性遺伝子の一つmecCが存在しているかを調べた結果、様々な国に広く分布しており、英国では7割、デンマークやチェコでは5割近くのハリネズミが耐性遺伝子を保持していることを発見する。
当然次の課題は、これら耐性遺伝子の進化経路をゲノムからたどって、この遺伝子が人間から来たのか、あるいはハリネズミ由来かを調べることになる。詳細を省いてまとめてしまうと、ハリネズミmecCは独立に進化した3種類の系統に分けられ、このうちCC1943系統の3ラインはなんと1800年代に発生していることが分かった。
CC130は最も広く分布しており、多くのラインへと分かれているが、この発生も元をたどると、20世紀初めで、ほとんどのラインは人類が抗生物質を手にする前に発生していることが分かった。また、それぞれの系統で、進化のほとんどはそれぞれの地域で、ハリネズミの内部で起こっていることが示されている。従って、英国と大陸間については、人間や家畜による持ち込み、あるいは鳥を媒介とした感染などが重なる必要はあるが、進化自体は地域のハリネズミ内で進んだことが確認される。
ではなぜハリネズミ内で薬剤耐性遺伝子が発生するのか?これについては、ハリネズミに広く見られる皮膚糸状菌にペニシリン、すなわちβラクタムを合成する能力があり、糸状菌培養上清がブドウ球菌の殺菌効果を有することを示し、ハリネズミ内で、抗生物質合成糸状菌がMRSAを発生させたことを示唆している。
結果は以上で、ウイルスだけでなく多くの感染症が人間と動物の関係に深く根ざしていることを示しており、繰り返すが「科学的事実は小説より奇なり」としか言い様がない。15日から、多発性硬化症の原因としてのEBウイルス、嗅覚受容体発現マクロファージと動脈硬化、甘みを感じる十二指腸のneuropod細胞、そして今日のハリネズミ内でのMRSA発生と、面白い研究を続けて紹介したが、今年も何が出てくるかわくわくする。
2022年1月17日
昨日はマクロファージに発現した嗅覚受容体の話を紹介したが、今日は十二指腸で発現している味覚受容体の話を選んだ。この論文を読むまで、味の感覚は全て舌にある味覚受容体を介して伝達され、好みといった行動は、意識下の味覚認識に依存していると考えていた。しかし、甘みに対する受容体を欠損させたマウスが、なんと砂糖の入った食べ物を好むことが発見され、意識下の味感覚以外にも甘さが感知されていることが明らかになっていた。
今日紹介するデューク大学からの論文は、最近発見されたneuropod細胞が、異なるメカニズムで、蔗糖と人工甘味料を区別し、シナプス結合している迷走神経を刺激することで、蔗糖への好みが形成されることを示した大変な力作で、1月13日Nature Neuroscienceにオンライン掲載された。タイトルは「The preference for sugar over sweetener depends on a gut sensor cell(人工甘味料より砂糖を好む行動は腸の感覚細胞に依存している)」だ。
コレストキニン(CCK)を発現するNeuropod細胞(NC)が、腸管内分泌細胞だけで無く、迷走神経とシナプスを形成することで、感覚神経として働いていることが確立したのはつい最近(2015-2018年)のことだ。この研究では、このNCが、味覚が無くても、砂糖を好む行動を支配しているのではと考え、この可能性を膨大な実験を積み重ねて明らかにしているが、特に脳向けに開発された光遺伝学を腸内へ適応するために開発し直すなど、大変な力作だ。詳細は省いて、結果だけを箇条書きに紹介する。
1)蔗糖や人工甘味料のスクラロースは、十二指腸に注入すると、迷走神経興奮を引き起こす。この興奮は光遺伝学的にNC細胞を過興奮させることで抑制されることから、NCがセンサーになっている。
2)NC細胞にはシナプス形成分子のみならず、甘み受容体を形成できるT1R3やグルコーストランスポーターSGLT1が発現している。
3)蔗糖はグルコースに分解された後、SGLT1を通って細胞内に流入することで、興奮を誘導する。一方、スクラロースはT1R3に直接作用してNCを興奮させる。それぞれの刺激反応の仕組みは、細胞ごとに違っており、これが砂糖とスクラロースを区別する基盤になっている。
4)GLUT1を介する砂糖の刺激はグルタミン酸、T1R3を介する刺激はATPを神経伝達因子として使う。
5)砂糖への好みはグルタミン酸による興奮伝達による条件付けにより成立しており、グルタミンによるシナプス刺激を十二指腸で抑えると、砂糖への好みは消失する。
以上が結果で、まとめてしまうのが申し訳ないぐらいの面白い研究だ。この無意識の感覚がなぜ発生したのか、省略したがなぜ果糖は感じられず、蔗糖なのか、など進化的に面白い話が満載の気がする。
2022年1月16日
つい3日前、嗅覚受容体の一つが乳ガンに発現して、悪性化を誘導するという論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/18764 )。驚いたことに、ガンだけでなく嗅覚受容体が臭い感知以外にも役割があるのではと考えて研究が行われているようで、今日紹介するLa Jolla免疫研究所からの論文は、マクロファージの一部がマウスではOlfr2、ヒトではOR6A2嗅覚受容体を発現し、動物脂肪酸から合成されるオクターナルを感知して、インフラマゾームを活性化し、動脈硬化を悪化させるという驚くべき結果を示している。タイトルは「Olfactory receptor 2 in vascular macrophages drives atherosclerosis by NLRP3-dependent IL-1 production(嗅覚受容体Olf2はマクロファージに発現し、NLRP3依存性のIL-1合成を誘導して動脈硬化を促進する)」だ。
ガンの悪性化を促すことを報告した論文にも驚いたが、この論文の驚きは機能的メカニズムが明らかにされている点で、さらに大きく、当然研究のレベルが高い。
まず、マウスマクロファージがOlf2を発現しており、しかもその発現がApo2欠損動脈硬化モデルマウスに脂肪の多い西洋型食事を与えることで上昇すること、また人間の動脈硬化巣のデータベースを再検討し、Olf2に対応するOR6A2の発現が上昇していることを確認し、マウスやヒトの動脈硬化巣浸潤マクロファージが嗅覚受容体を介して、動脈硬化に関わる可能性を明らかにしている。
次に、Olf2の発現に動脈硬化の上流シグナルTLR4が関わっており、例えばLPS刺激でOlf2発現が上昇すること、またOlf2ノックアウトマウスでは動脈浸潤マクロファージの数が低下すること、すなわちOlf2が確かに動脈硬化に関わることを示している。
重要なのは、Olf2やOR6A2を刺激するリガンドの一つとしてオクターナルが特定されていることで、オクターナル刺激により誘導された活性酸素がインフラマゾームを介してインターフェロンを誘導し、動脈硬化巣の炎症を誘導することがわかった。実際、オクターナル刺激をシトラール(芳香剤として使われる油)で抑制すると、IL-1βの発現も抑えられる。
しかも、オクターナルの合成経路を調べると、動物脂肪に含まれるオレイン酸由来であること、そして西洋型食事を食べると、動脈でのオクターナルんレベルが上昇する。さらに、Apoe欠損マウスでは、この値がさらに上がっており、また動脈内でのオレイン酸からオクターナルへの転換も上昇しており、リガンド、受容体とも動脈硬化とリンクしているという、ちょっと出来すぎた話だ。
後は骨髄移植の系などを用いて、マクロファージのOlf2を働かなくすると、動脈硬化が抑えられること、またシトラールを長期間投与してOlf2を阻害しても、動脈硬化を抑えられることなどを示し、将来ヒトのOR6A2阻害剤が動脈降下薬として使える可能性まで示している。
読みながら、出来すぎた話だと思い続けていたが、裏返せば驚きの連続の論文で、全く新しい動脈硬化治療に発展して欲しい気がする。
しかし、800種類以上嗅覚遺伝子が存在し、多くは脂溶性のリガンドを認識しているなら、当然進化過程で他の目的に使われても不思議はない。マウスとヒトは進化的に近いので、是非他の哺乳動物で調べてみて、この遺伝子がマクロファージで炎症刺激に使われる過程を明らかにすることで、なぜ動脈硬化プロセスが我々に現れたのかのルーツも理解できるかもしれない。
2022年1月15日
多発性硬化症(MS)は、ミエリンに対する自己免疫反応が基盤になっているが、この自己免疫反応の引き金を引くのがウイルス、特にEBウイルスではないかという可能性は長く示唆されてきた(例えば、Ana. Neurology 59, 2006:図)
ただ、EBウイルスの感染は全世界の95%が経験しており、いくらEBウイルス感染後にMSリスクが上昇したからと言っても、確かに因果性があると簡単に結論することは出来ない。
この問題を、米軍兵士1千万人のコホートサンプルを用いて解決し、EBウイルス感染が引き金になっている疑いが極めて濃いことを示したハーバード大学からの論文が1月13日Scienceにオンライン掲載された。タイトルは「Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis(長期追跡研究により多発性硬化症がEBウイルス感染とリンクしていることが明らかになった)」だ。
これまで、EB感染者とそれ以外を分けてMS発症を調べる研究は行われていたが、因果性まで示すとなると、感染と発症との関係をより詳細に追跡する必要がある。この研究では、米軍兵士1千万人の中から955人がMSを発症した集団を対象にした追跡研究を元に、残っている血清からEBウイルスの感染時期やEBに対する免疫反応や神経変性を検査し、因果性を確かめようとしている。
結果は驚くべきものだ。必要な全ての材料が残っていたMS例が801例だが、発症に一番近い時点で採取された血清でEB感染を調べると、陰性だったのは1例だけで、EB感染率を考えても極めて高い。
さらに驚くのは、さらに前の血清を調べ、最初はEBに感染しておらず、その後いつEBウイルスに感染したのか追跡できるケース35例を抜き出してみると、1例を除く全てが、MS発症以前のどこかでEBウイルスに感染し、その後MSを発症していることが明らかになった。すなわち、EBウイルス感染と、MS発症に強い時間的因果性があることが分かった。
同じように、最初は陰性だが、どこかで感染するウイルスとしてサイトメガロウイルスを調べてみると、感染とMS発症とに全く因果性は認められない。
さらに、自己免疫反応による神経変性をある程度反映できる検査マーカーを用いてEB感染、MS発症と、神経変性の始まりをモニターすると、EB感染以後、MS発症前から変性が始まっていることが明らかになった。また、VirScanと呼ばれる網羅的抗ウイルス抗体検出法を用いて、全体的な免疫変化が起こっているのでは無く、EB感染による変化が特異的に起こっていることも確認している。
結果は以上で、極めて大きな集団を対象にすることで、感染実験と同じことが可能になり、結果EB感染によるMS発症リスクは32倍と、驚くべき数値がはじき出されている。
この数値だけで驚くが、もう一度EB感染という視点からこの病気を見直してみると、全く新しい治療が可能になるのではと期待している。
2022年1月14日
アフリカでホモサピエンスが生まれたことに異論を唱える人はいない。ただ、様々なホミニンが存在していたと考えられるアフリカで、最終的にユーラシアに移動したホモサピエンスが形成されたのかはほとんど分かっていない。というのも、ホモサピエンスが生まれたアフリカ内ですら、ユーラシア移動前のホモサピエンスの化石は数えるしかない。
この中で最も古いと言われているのがモロッコIrhoudで発見された約30万年前の化石で、それに続いてやはり30万年前後のケニアEliye Springの化石が存在し、これから30万年前にはホモサピエンスがアフリカ中に広がっていたと結論されている。ただ問題は、発見された骨は完全で無いため、これが本当にホモサピエンスかどうかも議論が続いている。これらに対し、1966年にエチオピアOmo Kibishで発見された化石は、頭蓋の形態から異論が無いという意味で、現在も最も古いホモサピエンスを代表している。
以上、おそらく現代型のホモサピエンスの前に、初期段階の様々な形態が存在し、これらはネアンデルタール、デニソーワ、そしておそらくハイデルベルグ原人などから70万年前ぐらいに分かれたと考えられている。
今日紹介する英国ケンブリッジ大学からの論文は、確実にホモサピエンスと誰もが認める化石が出土したOmoKibishの地層を再検討し、これら初期ホモサピエンスが生きていた時代を20万年前と特定した研究で、1月12日、Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Age of the oldest known Homo sapiens from eastern Africa(知られている最も古い東部アフリカのホモサピエンスの時代検定)」だ。
タイトルから、モロッコやケニア出土の化石はまだホモサピエンスと認めないぞといったニュアンスが感じられるが、いずれにせよ、Omo Kibish出土の化石の時代考証は今も議論が続いているようだ。
エチオピアの化石は800kmほど離れた場所から発見されており、発見された地層の岩石に中性子を照射、新しく生成したアルゴン39と、天然の崩壊で出来るアルゴン40を比較して行う年代測定から、それぞれ19.7万年、16万年と算定されていた。
この化石の年代測定の鍵を握るのが、近くのShala湖カルデラの噴火により各地に降り積もった火山灰を、地質学的に相関させる作業で、この研究では大噴火で形成された、様々な土地の地層と、Kibish化石のすぐ上にある軽石地層との相関を決めることに成功している。そして、この噴火による軽石地層から大きさをそろえたガラスクリスタルを調整し、アルゴン法による年代測定で、Kibish化石の年代は、これまで言われていたより3万年ほど古い、23.3万年前と結論している。
以上の結果から、Omo I、IIとひとくくりで扱ってきたエチオピアの化石は、23.3万年前のKibish化石と、16万年前の新しいHerto化石として扱うべきと結論している。
実際には、完全に地質学の研究で、アフリカホモサピエンス形成過程を調べることが、多くの分野が統合されて初めて可能になる大事業かを認識させる研究だった。
2022年1月13日
3δ株感染では主症状の一つだった嗅覚障害が、オミクロン株ではほとんど発生しないという話を聞いて、嗅覚受容体の発現が結構環境変化に左右されるのだなと感心しているときに、思いがけなくガンの転移と嗅覚受容体の関係を示したハーバード大学からの論文を見つけた。大学の後輩でアラバマで脳外科医として働いている知人、中野伊知郎さんも共著者として参加している。タイトルは「Olfactory receptor 5B21 drives breast cancer metastasis(嗅覚受容体5B21は乳ガン転移を促す)」で、12月17日号のiScienceに掲載された。
私が気づかなかっただけで、ガンの転移や悪化に異所性に発現した嗅覚受容体(OR)が関わっている可能性は、多く発表されているようだ。特に、前立腺ガンや乳ガンでは、転移や悪性度との関連が指摘されていたようだ。考えてみると、嗅覚受容体はG共役性受容体なので、異所性に発現され、刺激物質が存在すれば、細胞の活性を変化させても不思議は無い。
この研究では人乳ガンをマウス血中に注射し、脳、骨髄、肺に転移し増殖できた細胞から細胞株を樹立し、新たに発現してきたORを調べている。人間のORは800種類以上存在するが、転移できた乳ガンでは20種類ぐらいのOR遺伝子の発現が上昇している。
この中から、特に脳転移で上昇しているOR5B21に注目し、研究を進めている。OR5B21は親株と比べ、脳転移では15倍、肺転移では10倍高い発現が見られている。残念ながら、ヒト乳ガンのデータベースサーチでは、乳ガンでOR5B21の発現が上昇していることは述べられているが、脳転移でさらに上昇しているかどうか述べられておらず、実際の臨床例でも同じことが言えるのかは分からないと言わざるを得ない。
とはいえ、実験動物系ではOR5B21は確かに刺激され、STAT3/NFκB/CEBPβ分子経路を介して、乳ガン細胞の上皮間質転換を促進し、またメタロプロテアーゼの発現を上昇させて、結果として転移が上昇することを示している。
またノックダウンすると、転移能力が低下し、マウスの生存期間も延びることが示されている。
結果は以上で、出されたデータが完全とは言えない部分が多いので、結論が一般化できるのかどうかは判断できない。しかし、ORがこれほど様々な場所で発現するとは考えたことが無かった。ORは、抗体やTcRと同じで、一つの細胞には一つの受容体しか発現しないように出来ている。おそらく、エピジェネティック機構の異常で起こるガンの異所性発現では、このルールが守られているのか、それも是非調べてもらいたいと思った。
2022年1月12日
アルツハイマー病(AD)の進行を決めるのが、細胞外へのアミロイドβの沈着と、細胞内でのTau分子の沈着の二要因であることは疑う人はいない。ただ、それぞれの病態への寄与、相互作用などについては分かっていないことが多い。従って、それぞれの要因と、病気の進展速度を相関させる臨床研究が重要になる。
今日紹介する米国クリーブランドのケースウェスタンリザーブ医大からの論文は、通常のADと比べて急速に進行するrapidly progressing AD(rpAD)と、一般的な徐々に進行するAD(spAD)の違いを、Tauタンパクの構造の違いから説明しようとした研究で1月5日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Distinct populations of highly potent TAU seed conformers in rapidly progressing Alzheimer’s disease(急速に進展するアルツハイマー病ではTauを増殖させる高いシード活性を持つ構造を持つ異なるTauが存在している)」だ。
この論文を読んでまず驚いたのが、病理的にも、遺伝的にもまだはっきり違いが認められないのに、病気の進行が6倍も速く、多くが3年で亡くなる一群の患者さん(rpAD)が存在することだ。病気の修飾に関わるApoEタイプのe4が、spADより少ないが、これも半分ぐらいで、全くないわけでは無い。
実際、rpADの進行はプリオン病に近く、またTauが構造変化により、プリオンのように同じ構造のTauを増殖させる可能性が示唆されていることから、おそらくTauが沈殿しやすい特殊構造をとることが、rpADの原因では無いかと着想し、亡くなった患者さんの海馬に沈着するTauの生化学的分析を行っている。
プリオンについて言えば、他のタンパク質をプリオンに変えてしまうシード構造はほぼ1種類しか無い。しかし、この研究の結論は、Tauについては、確かにプリオンと同じシード活性を持つ構造が存在して病気の進行を左右しているが、その活性は一つの構造に収束するのでは無く、少なくとも4種類以上の構造が、シード活性を持ち、病気の進行に関わるという結果だ。
このシード活性を持つ構造を特定するために、この研究では正常Tauでは折りたたまれて隠れている部位を認識する抗体、および構造変化により獲得されたタンパク分解酵素抵抗性を指標にして、rpADで特に上昇している分画を特定している。
これらの分画は、rpADだけで無く、spADでも存在しており、また経過とともに増加してくることから、AD自体が、Taunopathyと呼ばれる、特定の構造を持ったシードTauが、同じ構造のTauを増殖させることが背景になっていることを示している。
最後に、rpADとspADの違いを求めていくと、最終的に蔗糖密度勾配法で分画され、タンパク分解や塩化グアニジウム抵抗性で、4Rと呼ばれているスプライシング型由来のTauの量がこの差を決めていることを明らかにしている。
以上が結果で、ADがTaunopathyが関わること、さらに複数の分子構造がシード活性を持っているため、多様な病態が成立することが理解できる研究だと思う。しかし、AD治療にはまだまだ長い道が横たわっていることを実感した。
2022年1月11日
神経の樹状突起はスパインと呼ばれるとげのように突き出た突起で覆われており、これが興奮性シナプスを形成し、他の神経アクソンからのシグナルを受け取る。これまで紹介したように、一本の樹状突起上のスパインは、刺激に応じて独立した形態変化を起こせることから、それぞれが独立した興奮依存性生化学的ユニットを形成している。すなわち、神経細胞や樹状突起とは独立して、興奮への反応性を変化させる仕組みを持っている。とはいえ、細胞膜はつながった一つの細胞の一部なので、興奮伝達という電気生理学的観点から見たとき、どの程度独立しているのかは明確ではなかった。
今日紹介するコロンビア大学からの論文は、細胞膜での電位を測定するための色素を開発し、これを用いて樹状突起と個々のスパインの膜電位を測定し、スパインの独立性について調べた研究で、1月7日号Scienceに掲載された。タイトルは「Voltage compartmentalization in dendritic spines in vivo(樹状突起スパインの生体内での電位区画化)」だ。
この研究では、スタンフォード大学により開発されていた、膜電位により分子構造を変化させる脱リン酸化酵素を用いた電位センサーを、シナプス局在に関わる分子PSD95と結合するH鎖抗体ナノボディーと結合させたGEV1と呼ぶ遺伝子を開発している。このキメラ分子遺伝子を神経細胞に導入すると、細胞膜上のシナプスと同じ場所に発現し、樹状突起やスパインの局所的膜電位を、生きたマウスの脳内で測定することが出来る。
この方法で膜電位を測定しながら同時にパッチクランプ法で細胞の膜電位を測定すると、神経が刺激されたとき、個々のスパインや樹状突起膜上での膜電位の変化を測定することが出来る。神経が刺激されると、パッチクランプでは大きな活動電位(AP)と、それに続く神経全体に及ばない閾値以下の電位変化が観察される。同じ神経をGEV1センサーで測定すると、APはダイナミックレンジが狭いためか、キャッチできないが、それに続く閾値以下の反応や、APとは無関係の膜電位の変化を捉えることが出来る。
次に、この方法で神経全体の興奮とスパインの興奮の関係を調べると、APが発生するときには同じようにスパインも反応して、細胞全体で一つの反応ユニットであることが分かる。しかし、閾値以下の膜電位変化を記録すると、樹状突起とスパイン全体が連動した膜電位変化とともに、それぞれのスパイン独自の活動が見られることが分かる。
実際に末梢神経を刺激して脳内の興奮を調べると、樹状突起と連合したスパインの興奮回数は上昇するが、スパイン独自で起こる膜電位の変化は全く変わらず、それぞれが異なる機能を持っていることが示唆される。
最後に、光刺激で樹状突起を刺激したとき、個々のスパインを刺激したときの膜電位の変化を調べると、樹状突起を刺激したときには、樹状突起膜もそれにつながるスパイン膜もともに脱分極が見られる一方、スパインだけを刺激したときは、スパインから樹状突起へ興奮が減衰しながら局所的に伝わることを明らかにしている。この結果に基づき、スパインと樹状突起の電気結合モデルが示されているが割愛する。
結果は以上で、神経、樹状突起、スパインの興奮を個別に記録できたという点が重要で、今後このパターンの背景にある分子基盤、また電気ユニットとしてスパインが独立していることの機能的意義が研究されていくことになるだろう。しかし、何でも出来るようになってくるのには驚く。
2022年1月10日
個人の特定に現在利用されるのは、ゲノム、指紋、そして顔認証の3種類が中心だ。今でこそ監視カメラなどの顔認証技術が進んだおかげで、顔認証は法的にも利用されるようになったが、少し前まではゲノムと指紋が主流だった。ゲノムは当然として、なぜ指紋を顔認証に匹敵する個人認証に使えるのか、その成立の仕組みはよく分からなかった。
今日紹介する上海・復旦大学からの論文は、四肢形態形成に関わる遺伝子群が、指紋パターンの形成にも関わることを様々な角度から示した面白い論文で1月6日号のCellに掲載された。タイトルは「Limb development genes underlie variation in human fingerprint patterns(四肢形成遺伝子が人間の指紋パターンの多様性に関わる)」だ。
個人を特定できる指紋といえども、完全にランダムに形成されるわけではない。この分野の研究者によると人間の指紋は大きく6種類にわけられる(例:https://www.researchgate.net/figure/Major-Fingerprint-Types-Whorl-Arc-Tent-Right-loop-Left-loop-and-Double-Loop_fig1_289246081 )。この研究では、それぞれの指紋型を持つ人のゲノム解析を行い、それぞれの型に相関するSNPを探索している。
詳細は省くが、これまで知られていた毛根や汗腺の発生に関わるEDARの様な、皮膚上皮に発現する遺伝子領域だけでなく、四肢の発生に変わる様々な遺伝子領域のSNP(一塩基遺伝子多型)が特定された。これらSNPから想定される遺伝子ネットワークを調べると、SNPと相関している遺伝子の多くは、まさに四肢形成の中心を担う分子として研究されてきた、WntやSHH、さらにはNOTCHシグナルに関わる分子であることがわかった。すなわち、四肢発生過程の延長に指紋形成があり、逆に皮膚発生に関わる過程の分子の関与は少ないことが明らかになった。
このように、SNPリストはできても、指紋形成メカニズムをこのリストからだけで説明するのは難しい。この研究ではまず、両手の中指3本の指紋が良く似ていることに注目し、この共通のパターンと相関するSNPを詳しく解析し、骨髄性白血病の原因遺伝子として知られるEVI1の発現に関わるSNPを特定した後、今度はEVI1自体の指紋形成への関与について、一つのシナリオに到達している。
EVI1は完全欠損すると胎生致死に至る。そこで、Jumbo変異として知られる多肢形成が起こる変異をヘテロに持つマウスの発生を調べると、通常なら連続している指のシワが、断裂することを発見する。また、マウスや人間でEVI1発現を調べると、指紋が形成される前に、指の間質細胞で発現して、細胞の増殖に関わることが明らかになった。すなわち、四肢形成の過程で間質細胞に発現するEVI1の多様性が、間質細胞の分布パターンの多様性を誘導し、このパターンが指紋が維持されるための基盤になることを示している。
指の長さと、指紋のパターンを調べると、渦巻き型と強い相関が見られることから、発生時期の間質細胞の多様性が指紋形成だけでなく、手の形成全体に関わっており、指紋形成もその中の一つの変化として捉えられることを示唆している。
以上が結果で、間質細胞の増殖の仕方のムラによって、指紋の基礎が作られるという話は面白い。ただそれだけでなく、例えばEVI1発現を決めるSNPが指紋と相関することは、指紋から白血病リスクを予測したりする可能性すら示唆しており、さらには手相による占いの根拠にすら発展するかもしれない(?)。
2022年1月9日
自閉症スペクトラム(ASD)の背景には、神経発生過程のちょっとした違いによる神経ネットワークの変化があることが想定されている。中でも、神経興奮を抑制するGABA作動性の神経活動の異常と、それによる感覚異常がASDに関わる可能性が示唆されている。このHPでも、脳内には到達しないGABAシナプス刺激剤を投与すると、感覚異常が改善され、ASD様症状が抑えられることを明らかにした論文(https://aasj.jp/news/autism-science/11245 )や、細菌叢がASDの症状に関わるのもGABA作動性の抑制神経の活動が低下しているためである可能性を示す論文を紹介してきた(https://aasj.jp/news/watch/10310 )。
今日紹介する英国キングズカレッジからの論文は、Spatial Suppressionと呼ばれる感覚抑制で誘導される脳波記録と、プロトンMRSと呼ばれる脳内のGABA濃度を測定とを組み合わせて、ASDの感覚異常がGABA作動性神経の低下に起因する可能性を示した研究で、1月5日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「GABA B receptor modulation of viual sensory processing in adults with and without autism spectrum disorder(ASDおよび正常成人の視覚処理はGABA B受容体により変化させられる)」だ。
これまで、ASDの感覚異常の一つとして、Spatial suppuressionの低下が知られていた。これは、画面に現れる対象物(例えば縞模様)をコントラストを変えて提示し、同時に背景の方も視覚認識を邪魔するような模様を様々なコントラストで提示し、対象物を正確に認識できるかどうかを調べるテストだ。典型人での視覚認識では、対象物のコントラストが鈍っても、周りの邪魔するパターンが強くなっても、認識力は低下する。ところが、ASDの人では、このような低下があまり認められないことが知られていた。
この研究では典型人、ASDを3群に分け、1群は何もしない、2群は少ない量のGABAシナプス刺激剤、そして3群に多い量の刺激剤を服用してもらい、spatial suppressionテストを行ったときの脳波を記録、視覚認識が低下するかどうかを調べている。
結果は、刺激剤を投与していない場合、期待通り典型人ではspatial suppression テストで誘導される脳波の変化が強く表れるが、ASDではこの変化が見られない。すなわち、脳の反応としては周りの背景に邪魔されることが少ない。
ところが、GABAを刺激する薬剤を多く投与したグループでは、これが逆転し、ASDでは認識が邪魔されるのに、典型人では影響が少ない。この結果は、GABA刺激の量が、spatial suppression の程度を調節していることを強く示唆しておりASDでも典型人と同じレベルにGABA刺激を高めてやると、視覚の認識異常が正常化することがわかる。逆に、正常人で同じ量のGABA刺激剤を服用すると、spatial suppressionが見られなくなるのは、刺激が過剰になると回路がうまく働かないことを示している。
このようにGABAの量によりspatial suppressionが調節されていることを確認した後、プロトンMRSと呼ばれる技術を用いて、spatial suppression課題を行っているときの、視覚野でのGABA濃度を測定している。結果は完全に期待通りで、spatial suppressionによる脳波の変化と、GABA濃度の間には強い相関が見られる。そして、ASDでは、GABA濃度の上昇が見られない。
以上の結果から、少なくとも視覚については、GABA抑制性神経の活動の低下が感覚異常を誘導し、それが自閉症様症状にも寄与する可能性が示された。薬剤による症状改善も示されていることから、この過程を標的にした治療法の開発も期待できる、重要な貢献だと思う。