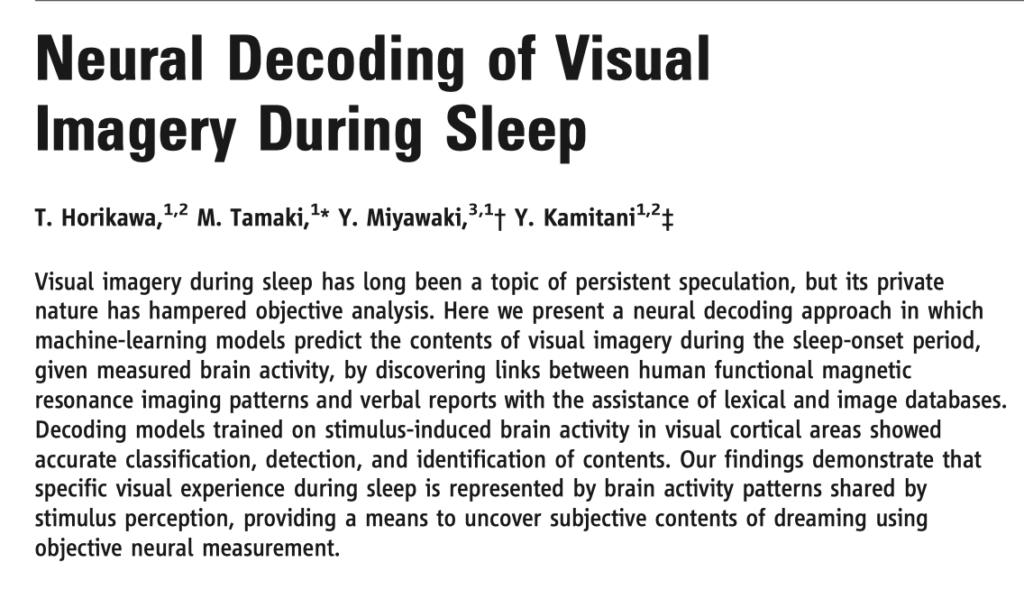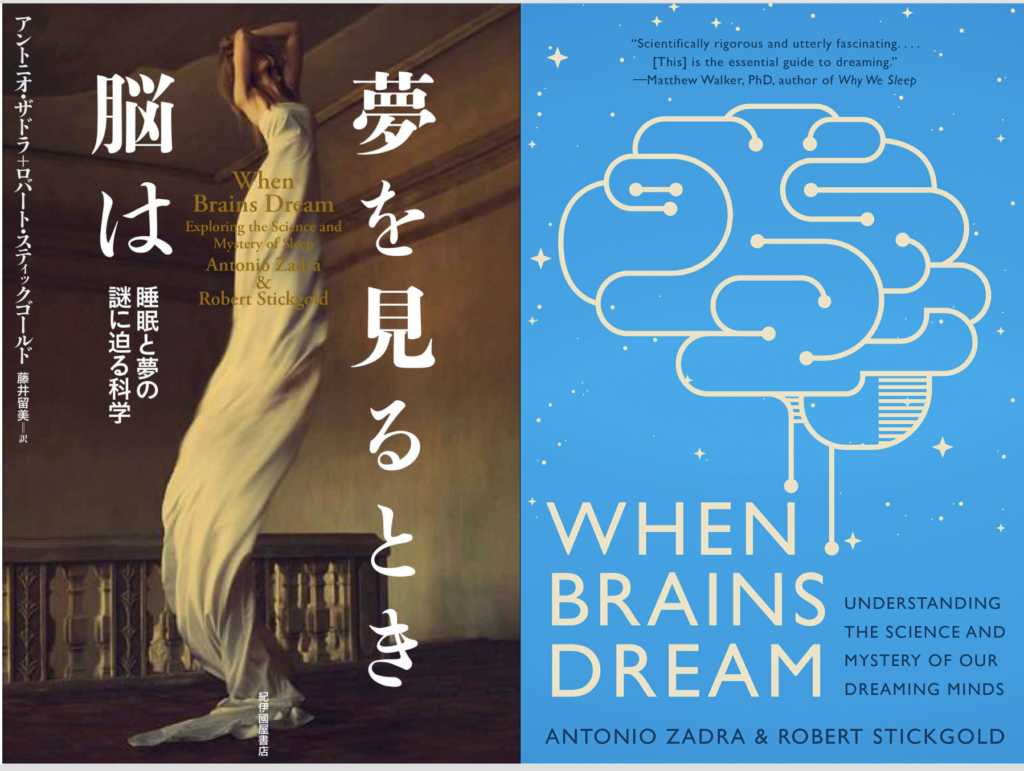2022年10月13日
10月7日に紹介した膵臓ガンは、ガンに対する間質反応によりガンの微小環境が変化させられ、この反応によりガンの周りに集まった線維芽細胞から細胞外マトリックスやサイトカインが提供され、ガンの悪性度が増していくタイプだ。これに対し、最初に組織の線維化が起こり、これが発ガンを促進するタイプの代表例が肝臓ガンだ。勿論、発ガン後も間質との関係は続くが、発ガン前と後では、相互作用のあり方も異なる可能性がある。
今日紹介するコロンビア大学からの論文は、肝臓の線維化の鍵を握る細胞と考えられている Stellate Cell (星細胞、発見者の名前をとって伊東細胞とも呼ばれる)が肝臓ガン発生過程へ関与しいているメカニズムを明らかにした研究で、これまでほとんど知識が不足していた星細胞についてしっかりとしたイメージを形成することが出来た。タイトルは「Opposing roles of hepatic stellate cell subpopulations in hepatocarcinogenesis(肝臓星細胞は肝細胞ガン発生過程の細胞サブポピュレーションに相反する作用を示す)」で、10月5日 Nature にオンライン掲載された。
様々な組織特異的遺伝子改変法を駆使して、星細胞の活性を操作し、様々な方法で誘導する肝臓ガンに対する影響を詳しく調べた膨大な研究だ。
まず、星細胞特異的活性化シグナル、あるいは活性化抑制シグナルを遺伝子導入したマウスで、星細胞の活性化が発ガン過程を促進することを確認し、さらに星細胞自体を除去して、発ガンを促進しているのが星細胞自身であることを明らかにしている。
後は、星細胞が発ガンを促進するメカニズムを探索しており、結果をまとめると次のようになる。
星細胞は肝臓細胞増殖因子HGF を発現するサイトカイン型(cHSC)と、1型コラーゲンを発現する筋繊維型(myHSC)に分けることが出来る。 cHSC は HSC を通して正常肝細胞を守る一方、myHSC はコラーゲンを分泌して、組織の硬度を高め、肝細胞で TAZ の核内移行を促進し、増殖を誘導する。 脂肪肝など様々な変化により、星細胞の cHSC/myHCSバランスが変化することで、発ガン前の肝細胞の増殖が促進され、これを繰り返して発ガンする。 肝臓ガンの場合、発ガン後、myHSCはガン細胞の中に浸潤することは少ない。逆に、胆管ガンなどでは myHSC がガンの中に浸潤する。10月7日に紹介した、切断されたコラーゲンによるガンの増殖機構と同じ機構が肝臓ガンでも働いており、メタロプロテアーゼの発現が高いガンの予後は悪い。しかし、切断されたコラーゲンとその受容体DDR1 は、成立後のガン細胞に効果があり、発ガン過程にはほとんど関与しない。 以上の結果から、肝臓ガンの発ガン過程は、脂肪肝などにより、cHSC/myHSCバランスが崩れ myHSC 優位の環境が出来ると、コラーゲンが分泌され、これが Hippoシグナル系を介して、TAZの核内移行を促し、増殖にスイッチを入れ、発ガンを促進する。発ガンが完成すると、今度はメタロプロテアーゼによりコラーゲンが分解され、DDR1シグナルを介して、ガン細胞の増殖をさらに促進する。一方、完成したガン細胞では TAZ の核内移行が見られないため、組織の硬化を感知する Hippo経路は動いていない。 以上が結果で、星細胞の機能を、発ガン過程からガン成立後までにわたって、よく理解できる結果だ。さらに、正常状態では HGF が肝臓の増殖より、肝臓を守る働きをしていることも見事に示されており、大変勉強になった。肝臓ガンに興味のある人には一読を勧める。
2022年10月12日
8月28日論文ウォッチで紹介した、眼の動きから動物の夢をのぞき見る可能性を調べた論文を、ジャーナルクラブで取り上げ解説します。Youtube で配信しますので、時間が来たら以下の画面をクリックして参加してください。また、直接参加したい方には zoom の URL をメールで送ります。
VIDEO
当日は、この論文の他に、少し古くなったですが2013年、京阪奈にある ATR から Science に発表された、夢解読についての論文も取り上げます。
今回は夢の科学という、ほとんどの人には馴染みのない問題なので、一冊だけ本も推薦しておきます。夢の科学がどのように行われているか、よく書かれた面白い本です。Kindleで英語版でも和訳版でも手に入りますので、読んでみてください。
2022年10月12日
アルツハイマー病 (AD) の発症率は女性の方が約1.7倍高い。最近の Tau 分子の蓄積を調べる PET 検査では、臨床症状のない女性でも、Tau の蓄積が男性より強いことがわかっており、女性の方が Tau が蓄積しやすいことがわかっているが、このメカニズムについては明らかでない。
今日紹介するクリーブランドの Case Western Reserve 大学からの論文は、Tau 分解の印としてつけられたユビキチンを除去する脱ユビキチン化酵素活性が高いと、Tau が蓄積しやすくなり、AD のリスクを高めること、そしてこの分子こそが女性で AD が発症しやすい原因であることを示した研究で、10月4日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「X-linked ubiquitin-specific peptidase 11 increases tauopathy vulnerability in women(X染色体上のユビキチン特異的ペプチターゼ11は女性のTau蓄積症発症リスクを高める)」だ。
細胞内での蛋白質分解にはまず分解する蛋白質にユビキチンの印がつけられるが、同時にこの印を外す酵素も存在し、細胞内での蛋白質分解過程のバランスが保たれている。AD に関わる Tau も、リン酸化されて重合が始まると、ユビキチン化され、プロテアゾームやオートファジー経路を通って、分解して、蓄積を抑えられている。この時、ユビキチンを外す酵素があると、当然分解が起こらなくなり、AD のリスク要因になる。
この研究では、神経系で発現しユビキチン化された Tau から、ユビキチンを外すペプチターゼをスクリーニングし、X 染色体上に存在する USP11 が、Tau 特異的にほとんどのユビキチンを除去する作用を持つことを突き止める。また、その結果、Tau の凝集も促進されることを示している。
では USP11 がユビキチンを外すだけでなく、何故より安定な Tau 凝集を促進するのかメカニズムを探索し、一度ユビキチン化された281番目のリジンのユビキチンを外す過程で、281番目と274番目のリジンがアセチル化され、その結果ユビキチンによる分解経路から隔離されることが、その原因であることを明らかにしている。
以上のことから、USP11 の発現が高いと、AD リスクが高まることは明らかになったので、次にこれが AD 発症の男女差の要因になるかを調べている。
まず AD では USP11 発現レベルが高い。そして、女性の場合 USP11 と Tau の蓄積はより強く相関しており、AD 発症していない個体の脳を比べると、USP11 が女性で高い。すなわち、人間で女性が AD 発症が高いのは、USP11 の発現が高いためである可能性が高い。
この結論をさらに確かめるため、USP11 遺伝子のノックアウトマウスを作成してみると、蓄積が促進される変異型 Tau マウスの海馬のシナプス可塑性が、USP11 ノックアウトで正常化すること、さらに認知機能も改善することから、USP11 が女性の AD 発症リスクに直結していることを強く示唆している。
最後に、ではなぜ女性で USP11 が高いのかについて検討している。X 染色体上の遺伝子ではあるが、染色体不活化を通して男女で発現差がないはずだが、いくつかの傍証から、X 染色体不活化が USP11 では不完全であること、またエストロジェンにより USP 発現が高まることが、女性で USP11 が上昇している原因であろうと結論している。
以上が結果で、脱ユビキチン化酵素のレベルが女性の AD リスクを決めているという意外な結果で、面白い。それでも、新しい何故は生まれる。特に、脱ユビキチン化酵素は100以上あるのに、どうしてわざわざ X 染色体上の USP11 を Tau 脱ユビキチン化に使うようになったのか? アルツハイマー以上に、面白い問題が隠れているかもしれない。
2022年10月11日
通常T細胞は上皮内には進入できない。というのも上皮は adherence junction 及び tight junction で組織化されており、他の細胞を寄せ付けない。この構造に進入する方策として、上皮以外の細胞は特別のメカニズムを発達させている。例えば色素細胞の場合、上皮と同じ E-cadherin を発現して上皮に進入する。一方、IEL と呼ばれる上皮に存在するT細胞は、E-cadherin 自体ではなく、E-cadherin と結合するインテグリンを発現して侵入を実現している。
では、IEL は何をしているのか。上皮という最前線で免疫防御を担っていると考えていいと思うが、今日紹介するニューヨーク大学からの論文は驚くことに、抗菌分子を産生する Paneth細胞を守る役割を IEL の一部が担っていることを示した論文で、10月5日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「The γδ IEL effector API5 masks genetic susceptibility to Paneth cell death( γδIEL のエフェクター分子 API5 は Paneth細胞の遺伝的死にやすさをマスクする)」だ。
少しややこしい論文で、経緯から説明する必要がある。このグループは、元々オートファジーや小胞体輸送に関わる分子の一つ ATG16L遺伝子変異がクローン病のリスクとして働いていることを研究しており、クローン病による炎症で、αβIEL は増加するにもかかわらず、γδIEL が減少し、これと平行して Paneth細胞が著減少していることに着目して、γδIEL と Paneth細胞の現象との関係を調べ始めている。
ATG16L変異を持つマウス小腸にウイルスが感染した後、オルガノイド培養を用いて調べると、Paneth細胞の減少を再現できるが、この系にγδIELを戻してやると、Paneth 細胞の減少を食い止められることをまず発見する。
次に、同じ実験系を用いて γδIEL 由来の Paneth細胞保護因子を探索し、ついに Apotosis Inhibitor 5(API5) が分泌されることで、Paneth細胞及び腸管上皮の細胞死が防がれることを明らかにしている。
しかし、慶応の佐藤さんが開発した腸管のオルガノイド培養がここまで複雑な実験を再現することにただただ驚く。
Paneth細胞保護作用は、ウイルスや細菌感染時だけでなく、T細胞受容体を欠損させIELを減少させたマウスでは、自然に Paneth細胞が減少するので、少なくともアポトーシスが誘導された細胞を守る働きがIELに存在することがわかる。また、上皮を硫酸デキストランで傷害する系でも、API5 の効果を確認している。
最後に、人のオルガノイド培養を用いて ATG16L の変異がある場合は、γδIEL や分泌される API5 が Paneth細胞保護効果を認められることを示し、人のクローン病の新たな治療の方向性になることを示している。
この論文では ATG16L が変異しない正常人での結果が全くないので、あくまでもこの変異を持つ人の話と考えられる。ただ、この変異は比較的多くの正常人でも認められるそうなので、下痢しやすいといった症状を持つ人は、クローン病でなくても、一度遺伝子を調べると役に立つかもしれない。
2022年10月10日
おそらく何らかの遺伝子解析を受けた人の数は1億人に近づいているのではないだろうか。もちろんほとんどは全ゲノム解析ではなく、遺伝子多型 SNPアレーを用いた解析だが、病気との相関が示されている多型の数は多く、どんな健康人でも何らかの疾患リスクが指摘される。ただ問題は、現在用いられている多型のほとんどが、なぜ疾患リスクとなるのかというメカニズムについてはほとんどわかっておらず、統計学的現象論に止まる点だ。というのも、発現分子の配列に関わる多型は少なく、また多くの多型はそれと関わる遺伝子すら特定されていない。そんなわけで、多型のメカニズムを探る研究にはいつも頭が下がる。
今日紹介するトロント・マウントサイナイ病院からの論文は、多型のメカニズム解析の中でもかなり難しい範疇の多型の機能を特定した力作で、10月7日号の Science に掲載された。タイトルは「A noncoding single-nucleotide polymorphism at 8q24 drives IDH1-mutant glioma formation(8q24 に存在するノンコーディング一塩基多型は EDH1 変異によるグリオーマ形成に関わる)」だ。
この研究は、IDH1 変異がメインドライバーになっている低悪性度グリオーマ(Low grade glioma:LGG)で高い頻度で見られる 8q24 に存在する多型rs55705857がグリオーマ形成を助けるメカニズムを解析している。とは言っても、10月1日に紹介したように、IDH1 の発ガンメカニズムも極めて複雑だ。その上に、近くの遺伝子の発現がほとんど相関が認められない多型の関わりを調べるなど、よほど難問好きなグループに思える。さて、この難問にどう立ち向かったのか。
まず、多型により変化する遺伝子を、A型とG型の LGG で比較している。すると、IDH変異による遺伝子発現の影響は大きいものの、リスク多型が存在しても小さな遺伝子発現の変化しかないことがわかる。すなわち、LGG発ガンの下支えとして機能し、決め手ではないことを意味する。また、近くの遺伝子の発現には全く影響ないので、この多型領域はトランスにガンにかかわる遺伝子発現を下支えすることがわかる。事実、Myc自体の発現には関わらないが、Mycの標的遺伝子の発現が上昇していることを発見する。
そこで、この領域を導入したトランスジェニックマウスを作成し、発生過程でのエンハンサー活性を(これはシスの系で行っている)調べると、脳細胞や色素細胞の発生過程で、エンハンサー活性が高まることが観察される。
そこで、この多型が独立で IDH 誘導グリオーマの発生を高めることを示すため、人間の LGG に近い遺伝子改変マウスを作成すると共に、マウスでヒトの rs55705857 に対応するマウス領域を特定し、この部位をA型と、G型の多型、欠損させたマウスを作成し、それぞれを掛け合わせて、IDH による発ガンに対するこの多型領域の役割を調べている。
結果は明瞭で、この領域がG型、および欠損マウスでは、IDHによる発ガンが強く促進される。すなわち、この部位がA型の場合、IDH発ガンを抑える働きがあることがわかる。
この部位の配列を眺めると、まさに Oct転写因子結合領域と言えるので、Oct2、Oct4などの結合を調べると、A型では結合が見られるのに、G型では結合が見られないことがわかった。さらに、Octが結合することで、Mycの発現を抑える働きがあることがわかった。一方、G型そのものは機能を持たない。
以上のことから、この多型領域は Oct と結合することで、遠くに存在する Myc のプロモーターの活性を抑える負の働きがあるが、G型になるとこの働きが消失することがわかった。
この結果は、発ガンにあたっては、G型の人ではMycの発現が高まることが重要であることを示している。とすると、発ガンした LGG で A型と G型で Myc の差がないのは腑に落ちないが、これは完全に悪性化したガンでは他の要因が重なって、Myc 発現がこの多型に依存していないためと説明している。しかし、Myc が発ガン過程で上昇したのと同じメカニズムで、Mycの標的遺伝子の転写が高まるため、全体としてガンの悪性度が高まるということになる。
以上が結果で、大変な研究だと改めて頭が下がる。しかし、一つ一つこのようにメカニズムを決める地道な努力が、ガン克服の近道であることも確かだ。
2022年10月9日
2型糖尿病は、過食など様々な原因による高血糖に対して、インシュリンが分泌され、この状態が膵臓のβ細胞へのストレスを招くインシュリン抵抗性として知られる糖尿病予備軍を経て、続くストレスによりβ細胞が失われてインシュリン分泌が低下する糖尿病へと発展すると考えられている。この過程には、身体の全ての細胞が関わるが、基本的にはβ細胞、筋肉、脂肪組織、そして肝臓細胞の代謝変化を中心に研究されてきている。実際、この領域の進展は著しく、その結果として、私の現役時代には考えられなかった、様々なメカニズムの糖尿病薬が提供され、今度はどれを選ぶか医師が苦労する時代に突入していると言える。
今日紹介するスウェーデン・ウプサラ大学からの論文は、正常人、糖尿病予備軍、そして2型糖尿病と診断されている人が、急死し、膵島などの移植ドナーとして病院に運ばれてきたとき、膵臓とともに、43カ所の組織を採取、それぞれの組織のタンパク質の発現を網羅的に調べるプロテオーム解析した研究で、10月4日 Cell Reports Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Organ-specific metabolic pathways distinguish prediabetes, type 2 diabetes, and normal tissues(臓器特異的代謝経路が糖尿病予備軍、2型糖尿病を正常人から区別する)」だ。
生前拒否していない場合、死体を公共の目的で利用することが法的に許されているスウェーデンならではの研究で、糖尿病や予備軍のプロテオームをここまで詳しく解析した研究はないと言っていいだろう。膨大だが予想通りの結果で、面白い点をまとめるだけにしておく。
糖尿病、予備軍、正常人を比べると、予備軍ですでに始まっていると言える変化のほとんどが、膵臓β細胞に集中している。そして、変化の中心は炎症や、自然免疫に関わる変化に集中している。これは以外に思われるかもしれないが、予備軍のインシュリン抵抗性状態では、ほとんどの組織の代謝は正常になんとか保たれており、この状態を保つための全ての調整がβ細胞に集中し、その結果のストレスが、炎症や自然免疫を活性化していると理解できる。 予備軍から2型糖尿病に発展すると、β細胞では変化はほとんどないにもかかわらず、他の組織で様々な変化が見られる。すなわち、β細胞のストレスが頂点に達してインシュリン分泌が低下し始めると、各組織の糖代謝の低下に対応する様々な変化が起こると考えられる。 最も顕著な変化は、ミトコンドリアの酸化的リン酸化回路とTCAサイクルが脂肪組織や筋肉で低下するが、予備軍では大きな変化がないことから、インシュリン抵抗性段階よりは、インシュリン分泌低下が始まった後の変化と考えられる。 コレステロール代謝に関わる多くの酵素の上昇も、糖尿病発症の結果としてみられる。しかし、肝臓での変化から、これがすぐに肝臓の脂肪蓄積に発展する心配はなく、他の要因が必要。 糖尿病による糖の利用制限を克服するための、肝臓や腎臓での糖新生が、糖尿病成立後に高まる。 糖尿病予備軍から始まる変化で最も恐ろしいのは、凝固系の亢進で、予備軍から始まることを考えると、インシュリン抵抗性によるストレスが多く寄与していると考えられる。この結果は、covid-19感染で糖尿病とその予備軍が重症化しやすかったこともうまく説明する。 以上が主な結果で、概ね予想通りとは言え、それを人間の組織で徹底的に確かめたデータベースが出来ることは重要だ。私も予備軍の一人だが、もう少しβ細胞をいたわる必要があることがよくわかった。
2022年10月8日
抑制性T細胞(Treg)が、自己免疫病を抑えたり、移植臓器拒絶反応を抑える治療の切り札であることはわかっているが、様々な理由で進展は遅い。ただ、Treg の機能や活性化については研究が進んでいるので、これらの成果を遺伝子のレベルに落とし込んで、使いやすい Treg を遺伝子操作で作ってしまおうという研究が行われている。
今日紹介するシアトルにある Benaroya Research Institute からの論文は、T細胞抗原受容体と Treg転写プログラムの両方を遺伝子操作した EngTreg が、1型糖尿病の治療に使えるか調べた研究で、治療実現だけでなく、人間の Treg の性質を知る意味でも重要な論文だと思う。タイトルは「Pancreatic islet-specific engineered T regs exhibit robust antigen-specific and bystander immune suppression in type 1 diabetes models(膵島特異的エンジニア Treg細胞は、1型糖尿病モデルで、抗原特異的および抗原非特異的バイスタンダー免疫抑制を示す)」で、10月5日号 Science Translational Medicine に掲載された。
坂口さんたちが示したように、Treg の分化と機能は FoxP3 と称されるマスター遺伝子により調節されている。即ち、T細胞が FoxP3 を発現してしまうと Treg へと分化してしまう。そこで、この研究では1型糖尿病の患者さんで膵島特異的反応を示すT細胞からT細胞受容体(TcR)遺伝子を分離、それを末梢血CD4T細胞に導入した、膵島特異的T細胞を数種類作成している。こうして遺伝子操作した T細胞は、そのままでは自己免疫反応を誘導してしまう。そこで、この細胞を、FoxP3の発現が抑えられないように、TALENを用いた方法で遺伝子編集を加え、いくつかの膵島由来自己免疫抗原に対するTcRを発現したTreg細胞を作成している。
このように、ヒトTreg細胞の抗原特異性を完全にフィックスすることで、これまで知られている Treg の特徴を完全に再現することが出来る。
まず Treg および、エフェクターT細胞(Tef)ともに、発現TcR を操作したクローンレベルのモデル系を用いて、EngTreg は抗原ペプチド特異的に増殖し、同じ抗原ペプチドに対する Tef細胞は言うに及ばず、同じ培養中に存在する他の膵島由来ペプチド抗原特異的Tef細胞の反応を抑える、バイスタンダー効果を示すことを示している。この実験系では、FoxP3 の発現が固定されているので、生理学的条件を反映しているとは言えないが、治療目的の Treg細胞の性質を詳細に検討できる。
次に、このバイスタンダー効果が、TcR操作Tefだけでなく、自然に誘導された Tef にも発揮されるかを調べる目的で、数種類の抗原ペプチドに対するポリクローナル Tef を誘導し、この反応も、一種類の抗原だけに反応する EngTreg が抑制できることを示している。この結果は、1型糖尿病発症を止めるために、一つの EngTreg があれば十分なことを示し、臨床的には重要だ。
次に、バイスタンダー効果の一部は、直接 Treg、Tef とのコンタクトがなくとも、Treg が分泌するサイトカインにより樹状細胞が変化することで起こることも示している。
さらに面白いのは、EngTreg の抑制活性が、ペプチドに対する増殖反応と逆比例する点で、治療のためのクローンを選ぶとき、ペプチド反応性は重要だが、増殖能より、抑制機能で治療に使う細胞を選ぶ必要があることがわかる。
これら遺伝子操作したヒト末梢血を用いた試験管内の結果が、実際の臨床に利用できるか調べるための前臨床実験として、NOD1型糖尿病マウスを用いて、臨床で予想されるプロトコルを検証している。マウスCD4T細胞に膵島特異的TcRを導入、今度は CRISPR を用いた遺伝子編集で、FoxP3 を持続的に発現する EngTreg を作成し、NODマウスに移植すると、EngTreg は膵臓に移動し、自己免疫性Tef移植による糖尿病の発症をほぼ完全に抑えられることを示している。
結果は以上で、FoxP3 を持続的に発現させる EngTreg がかなり臨床近づいているという実感が得られた。TcR 導入にはレンチウイルスベクターが用いられているが、これは CART の使用実績があるので、安全性を確保することは容易だろう。また、FoxP3 編集にはアデノウイルスが用いられており、標的部位以外の切断の問題は残るが、発症が完全に抑えられるなら、リスクをとる価値はあると思う。
この方法で EngTreg が利用できる用になれば、応用は1型糖尿病にとどまらない。以前、ALS の症状も、Treg移植で抑えられるという臨床実験を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/8483 )。
是非、ALSのような治療手段が限られた病気にも拡大することを願っている。
2022年10月7日
膵臓ガンの特徴は、ガン周囲の線維芽細胞増殖と、コラーゲン合成を伴う強い間質反応で、他のガンに比べて膵臓ガンの予後が悪いのは、この間質反応が関わると考えられており、膵臓ガンの間質に関わる論文は何度も紹介してきた。しかし論文は数多く発表されていても、何が決め手かという整理は出来ていない気がする。おそらく、間質反応が強いと白血球浸潤は多くても、キラー細胞の浸潤が抑えられることが、ガンの予後に関わるというガン免疫からの説明はかなり確かそうだが、間質とガン自体の相互作用については、なかなか決め手がない。
今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文は、ひょっとしたらガンを促進する間質の重要な役割を明らかに出来たのではと期待できる研究で、10月5日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Collagenolysis-dependent DDR1 signalling dictates pancreatic cancer outcome(コラーゲン分解物による DDR1シグナルが膵臓ガンの予後と相関する)」だ。
これまで指摘されてきたことだが、この研究は膵臓ガンの予後に、膵臓ガンが発現するメタロプロテアーゼが関わり、これにより分解されるコラーゲン(cCol)の腫瘍組織での量が、やはり予後に関わるという現象からスタートしている。
この結果は、もしコラーゲンが分解できなければ、ガンの増殖を促進できないことを示唆しているので、メタロプロテアーゼで分解できないコラーゲンを発現するマウスを作成し、ガンの移植実験を行うと、ガン細胞の増殖が強く抑えられることを発見している。
すなわち、メタロプロテアーゼで分解されたコラーゲンはガンの増殖を促進し、逆に分解されないコラーゲン(iCol)はガンの増殖を抑制する可能性が示唆された。そこで、試験管内で両方のコラーゲンの活性を調べると、cCol はガン細胞のマクロピノサイトーシス(外部の分子を大きな小胞を形成して取り込む)を介して、ガン細胞の代謝を高めることが明らかになった。
次に、cCol が膵臓ガン細胞に作用するメカニズムを探索し、DDR1 と呼ばれるチロシンキナーゼ型受容体から、NFkb、p62。そして NRF2 と、炎症でおなじみのシグナルが活性化され、マクロピノサイトーシスが上昇と、ミトコンドリアの生成が亢進することを突き止めている。また、この経路を様々な方法で阻害すると、期待通りガン増殖促進を抑えられることを明らかにしている。
次に、分解されていないiColがこの経路を抑制するメカニズムについてもしらべ、iCol も DDR1 に結合できるが、結合により DDR1 はユビキチン化され分解されることから、受容体としての機能が抑えられることを明らかにしている。
結果は以上で、コラーゲンが切断されるか否かで、同じ DDR1 に結合しても真逆の結果をもたらすことを示し、これまでの膵臓ガン間質についての結果を統一的に説明する一つのとっかかりになるのではと期待できる。また、多くのガン治療標的も示されたので大きな期待が持てる。
実験の進め方はまさにプロの研究で、この研究を行っているのが M Karine というこのシグナル経路研究の大御所なので、納得する。
2022年10月6日
ペーボさんのノーベル賞に私が感じる意義については既に述べた。ただ、古代人ゲノム解析のために、様々な遺伝子解析技術を集中させていったオーガナイザーとしてのペーボさんの役割もおおきい。その結果、人間だけでなく、動物についてもその歴史をある程度知ることが可能になってきた。そんな例がないかと探していたら、少し古いが今年の6月、アフリカのチンパンジーの歴史をゲノムから調べたスペイン・バルセロナ進化研究所からの論文を見つけた。著者の中にはペーボさんの進化人類学研究所も入っており、多くの研究者が集まって発表した力作だ。タイトルは「Population dynamics and genetic connectivity in recent chimpanzee history(最近のチンパンジーの歴史で起こった人口動態と遺伝的関係性)」だ。
アフリカのチンパンジーの国際的研究となると、当然、京大の霊長類研究所も加わって当然だと思っていたが、残念ながらこのようなゲノム研究には参加できていない。一つのスキャンダルの後始末と称して21世紀に最も重要な研究分野の芽が我が国では摘み取られたのではと心配になる。
この研究では、ガーナやコートジボアールといった西地域と、コンゴからウガンダにかけての東地域の828に上るチンパンジーのゲノムを特定し、それらの由来と地域間の交雑を調べている。
といっても、チンパンジーを捕獲して血液を抜くと行った介入ではなく、ひたすら個体の糞を集め、その中に腸から落ちてきたゲノムを集めて解析している。勿論十分なゲノムを集められる可能性は低いので、小さい染色体である21番染色体ゲノムに絞って解読している。
糞から DNA を採取する方法は既に行われているが、チンパンジーの場合サルを襲って食べるため、その DNA の量が、自分の細胞の量を凌駕する可能性がある。このため、チンパンジー21番染色体ゲノムだけをキャプチャーする方法を用いている(これも古代人ゲノム解析では馴染みの方法だ)。
こうして、それぞれの地域で暮らすチンパンジーのゲノムが解読されると、それぞれの歴史や人口動態などが明らかになってくる。その結果、
人類と同じで、60万年から20万年にかけてアフリカのチンパンジーは大きく東西に分離し、ギニアやガーナ地域の西部地域(W)、カメルーンナイジェリア地域(CN)、コンゴ、ガボンを含む中央地域(CT)、そしてウガンダ、ルアンダ、タンザニアの東地域(E)に分離している。 歴史を探ると、コンゴ地域でボノボと別れた後、西へ移動したグループが W と CN へと分離、ボノボとの交雑はこの時期に起こっている。東の集団は100万年以降、CT が東へ移動して E が形成されている。それぞれの地域での交雑は少なく、特に W 集団は完全に分離している。以上のことから、基本的には地理的な距離によって種の固定が進んでいると言える。 この動態は、それぞれの地域を代表する希な変異を用いても解析できる。この方法を用いると、各国の動物園のチンパンジーの由来も、体毛の DNA から特定できる。 象と比べるとチンパンジーの移動距離は200km以下と少ない。これが人類との大きな違いで、文化の交換に基づく多様性が生まれなかった。その中でも、西地域では地域内での交雑頻度が高く、この地域のチンパンジーの文化の多様性の基礎となっている。 結果は以上だが、ここで語られたチンパンジーの歴史は、まさにネアンデルタール人と現生人類が分かれてからの歴史と重なる。この研究で始まった交流の歴史解析を人類と比べることがいかに我々自身の理解に貢献するかは、語るまでもないだろう。ゲノムの21世紀的意義がよくわかる。
2022年10月5日
Sonic hedgehog(shh) は、発生学に関わる人なら馴染みのシグナルだが、この作用機序はちょっと複雑だ。一般にリガンド(この場合shh)は受容体を介してシグナルを誘導するのだが、shh の結合する Patched は、それ自身でシグナルを出さない。代わりに、smoothened と称される膜分子の活性化を抑えている。この抑制が、shh に patched が結合することで外れる。では smoothened を活性化するメカニズムは何か?私の現役時代はわからなかったが、2016年、ハーバード大学のグループがコレステロールが smoothened を活性化していることを明らかにし、コレステロール自体が発生に関わるのかと大きな反響を呼んだ。
今日紹介するカリフォルニア大学バークレイ校からの論文は、smoothen活性化に似たメカニズムがコレステロールセンサーとして働いて、代謝のマスターシグナル mTOR を活性化することを示した研究で、9月16日号の Science に掲載された。タイトルは「Lysosomal GPCR-like protein LYCHOS signals cholesterol sufficiency to mTORC1(リソゾームの GPCR様蛋白質LYCHOS がコレステロールの量を mTORC1 に伝える)」だ。
スタチンの作用に関わるコレステロール合成経路や、LDL、HDLによるコレステロール循環システムはある程度フォローしているが、コレステロールの細胞内センサーの論文をこれまで読んだことはなかった。しかし、shhシグナルもそうだが、細胞が増殖するためには、十分量のコレステロールが存在しないと、分裂は破綻する。逆さまから見ると、コレステロールが少ないときに、分裂などのシグナルに反応しないようにしておく必要がある。
この細胞内栄養状態の情報をまとめて転写を変化させるのが mTOR分子で、アミノ酸やグルコース量と mTORシグナルとに関係は詳しく研究されている。最も有名どころでは、インシュリンシグナル-AKT-mTORで、医学生なら必ず知っている。
これまでの研究でコレステロールセンサーがあるとすると、リソゾーム膜上で mTORC1 を活性化している分子があるはずだと仮説を立てて分子捜しを始めている。まさに細胞生物学のプロの仕事とは何かが堪能できる。
まずリソゾーム局在分子リストの中から、コレステロールセンサーとして設定した条件を満たすシグナル分子 LYCHOS を特定している。これがコレステロールセンサーとして働くことをノックダウンで確認した後、後はこの分子がコレステロールの量に応じて mTORC1 を活性化する分子カスケードを徹底的に調べている。膨大なデータなので、明らかになった最終的な結果だけをまとめると次のようになる。
コレステロールが LYCHOS の N末端部分に結合すると、mTORC1 のリソゾームの局在を促す過程に、GATOR1、KICKSTART、mTORC をリソゾームに局在させる RAGコンプレックスが役者として関わっている。 GATOR1 は通常 KICKSTART分子と結合しており、mTORC1 のリソゾーム局在に必要な分子コンプレックスの活性を抑える機能を持っている。 LYCHOS にコレステロールが結合すると、C末の LEDドメインと GATOR1 が結合してしまうために、RAGコンプレックスの抑制が取れ、mTORC1 がリソゾーム膜に局在し、活性化される。 結果は以上で、smoothenと同じように、LYCHOS がコレステロールで活性化されることが、センサーとして働いていることを示している。コレステロールは、ステロイドホルモンをはじめ様々なシグナル分子の原料になっているが、コレステロール自体でも間違いなく様々な分子に関わっている。こんな論文を読むと、もう少し LDL を下げておこうと思う。