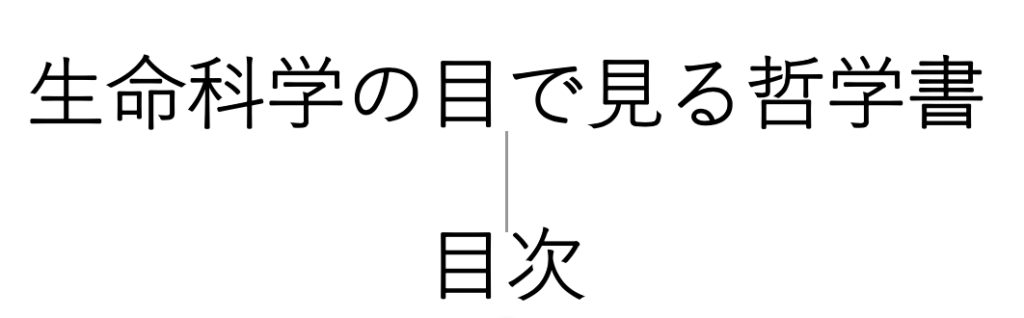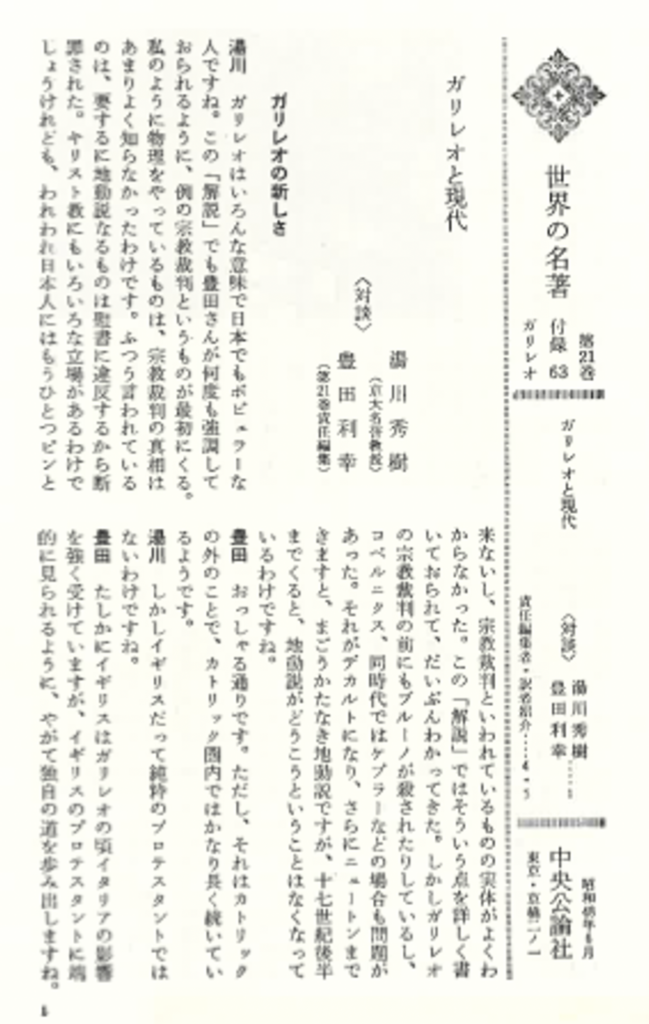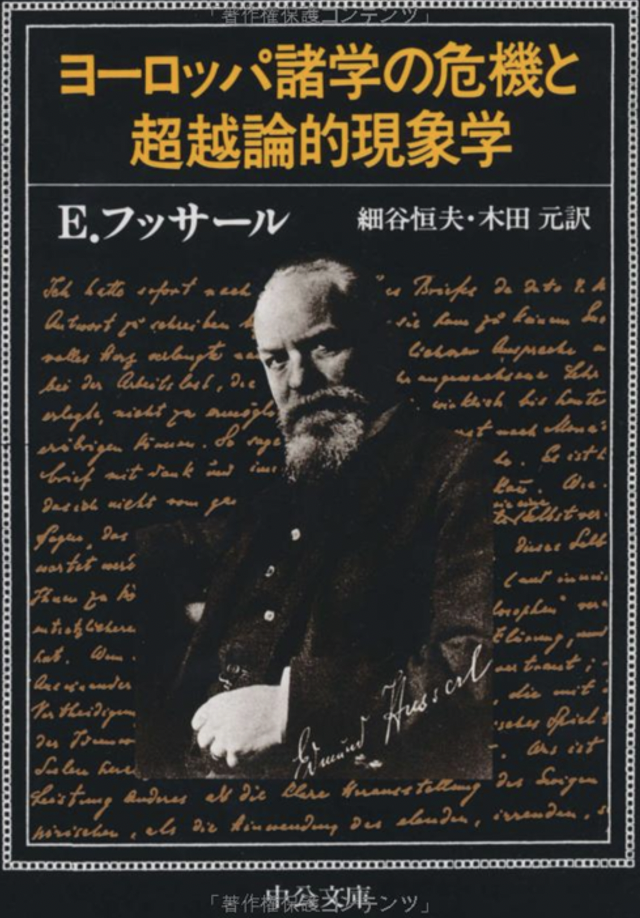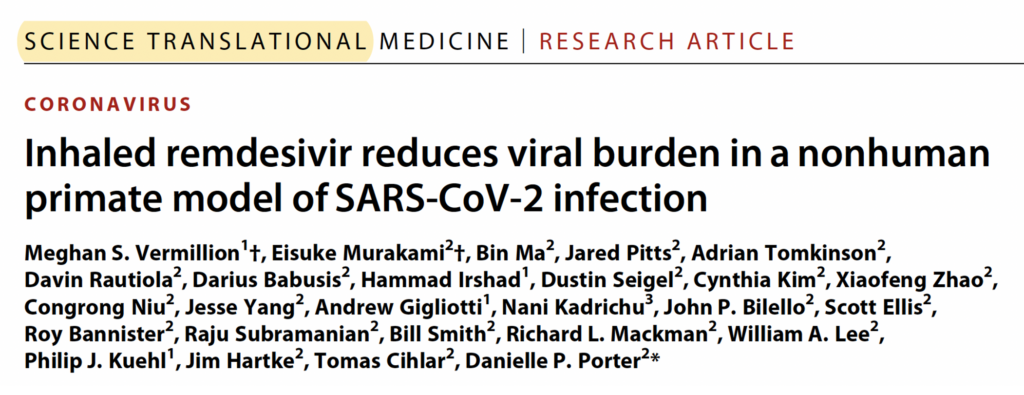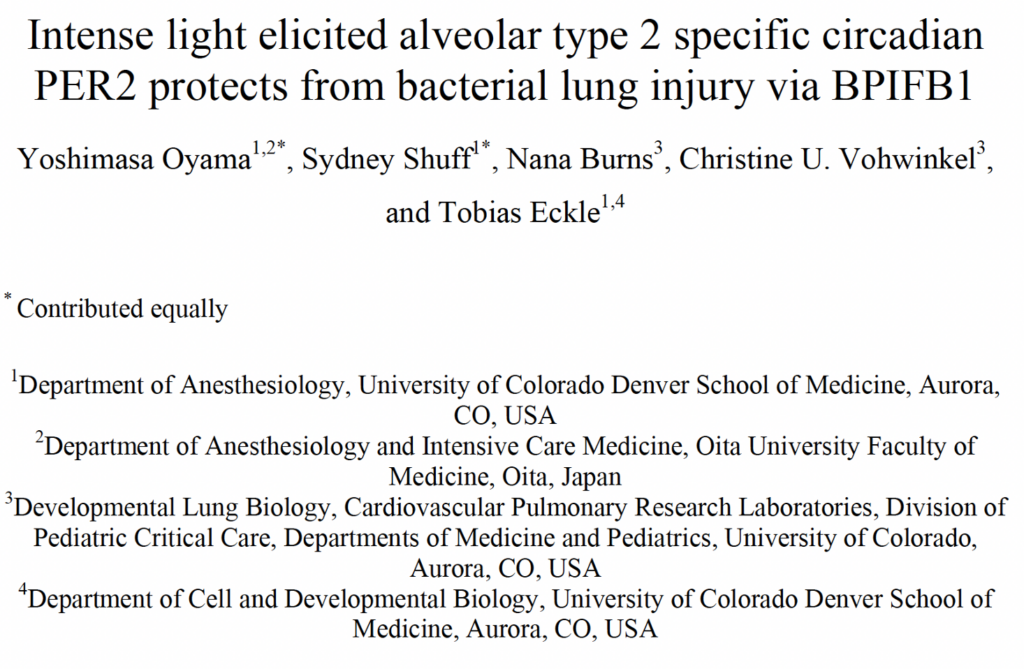2022年4月2日
2022年4月2日
長い研究の歴史を経て、遺伝子治療は現在急速に拡大しており、治療として認可された製品も続々登場している。今回のアデノウイルスワクチンも、あるいはmRNAワクチンだって遺伝子治療と言っていいだろう。すなわち、遺伝子を細胞内に導入して必要な分子を合成させるだけなら、看護師さんに注射してもらうだけでいいぐらい簡単にできるようになっている。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、コラーゲンVIIの欠損により起こるDystrophic epidermolysis bullosaとして知られる、水疱症を、なんと自宅で治療できる様にしようとする研究で、皮膚領域とは言え遺伝子治療がさらに一般治療に近づいていることを感じさせる。タイトルは「In vivo topical gene therapy for recessive dystrophic epidermolysis bullosa: a phase 1 and 2 trial(劣性dystrophic epidermolysis bullosaに対する塗布による遺伝子治療:phase 1及びphase 2 治験)」で、3月28日Nature Medicineにオンライン掲載された。
遺伝性の水疱症は上皮を維持するためのマトリックスの遺伝子欠損により起因し、遺伝子治療や移植治療が試みられてきた。ラミニン遺伝子欠損の患者さんを、遺伝子導入した皮膚移植で治療した研究については2017年に紹介した(https://aasj.jp/news/watch/7648 )。
今日紹介する研究の対象疾患は、コラーゲンVII欠損により起こる劣性dystrophic epidermolysis bullosa(RDEB)で、少しの刺激で皮膚に水疱が生じびらんができる。治療により傷は修復できるが、これが繰り返されるため、痛みと皮膚のびらんが続く。さらに、炎症を繰り返すことで悪性の扁平上皮ガンの発生が高率に起こる。
この治療には遺伝子治療か細胞治療しかない。最初、他人から骨髄移植を受けて線維芽細胞を置き換える試みが行われ、一定の効果が見られているが、元々負荷の高い骨髄移植治療を皮膚に水疱やびらんが有る患者さんに行うメリットがあるかは評価が定まっていない。また、ラミニン遺伝子欠損と同じように、遺伝子導入した皮膚細胞移植も試みられている。
これに対し、このグループは最初からびらんしている皮膚に自宅で遺伝子治療用ベクターを塗布出来る治療を目指している。
このために選んだベクターが、単純ヘルペスウイルス(HSV)ベクターで、感染力が強いだけでなく、大きな遺伝子を導入できること、そして自然免疫を刺激しないという重要な特徴を持っている。
詳細は省くが、細胞内での増殖能を欠損させたHSVベクターに、9kbのコラーゲンVII全長遺伝子を組み込み、このウイルスとMETHOCELと呼ばれるゲルと混ぜた塗布可能な遺伝子治療剤B-VECを開発している。
まず、培養細胞、そして免疫不全マウスに移植した患者さんの皮膚への感染実験で効果を確かめた後、1相、2相の治験を行っている。
重要なのは治療方法で、水疱が出来びらんした局所だけを狙った治療を行っている。ウイルスが入ったゲルを患部にまんべんなく、目薬をさすように一滴一滴垂らした後、一般に使われている非接着性の絆創膏(Tegaderm)をかぶせるだけだ。これを1日おきぐらいに繰り返して安全性や結果を見ている。
この治療により、8割の患者さんでびらんは閉じ、100日以上維持できたが、偽薬投与群ではびらんが完全に閉じることはなかった。また、皮膚バイオプシーで、全層にわたって上皮と真皮の間にコラーゲンVIIの分泌を確認している。
以上が結果だが、値段はともかくとして、自宅でできる遺伝子治療の可能性を期待させる結果だ。同じ病気では角膜損傷も起こることから、今後は目薬なども考えられるだろう。いずれにせよ、値段が一番気になる。
2022年4月1日
17世紀を振り返る最後に、ガリレオ・ガリレイに登場いただこう。生命科学の目で読む哲学書の読者にガリレイについて説明する必要はないはずだ。また、彼の著作は哲学書ではない。しかしこれから述べるように、私は近代哲学の産婆役を果たしたのがガリレオではないかと考えている。すなわち、直感や憶測に基づく独断的知識(=ドクサ)ではない、理性のある人間であれば共通に認め合うことができる客観的な真知(科学的知識=エピステーメー)のあり方(これに匹敵するものは他の分野ではまだ現れていない)を彼が示したことで、哲学の大きな変革を迫り、また哲学と科学、ドクサとエピステーメーの二元論に道を開いたのでないかと考えられている。
これまでデカルト、ライプニッツ、スピノザと17世紀の哲学者を取り上げてきたが、実はデカルトでもガリレオと比べて30歳以上若い。3人の哲学者も当然ガリレオの仕事を読んでいる。そう考えると、哲学とは全く無関係の男が、突然真知のあり方を示したことが、17世紀近代哲学の引き金になったと考えても、時間的には問題はない。
これまで私自身はデカルトの二元論を、心と身体の二元論としてではなく、追求すれば理解できること(=身体)と、追求してもわからないこと(=心)の二元論として勝手に解釈してきた。私の解釈がデカルトの意図と同じだったかどうかはわからないが、このエピステーメーとドクサの二元論にとって、間違いなくガリレオの影響は大きい。このように、哲学とは全く独立していても、科学は哲学に開かれ、哲学に変革を迫る。このインパクトを最初に受けたのがデカルトと言っていい。
ガリレオ以降も、科学から哲学へのインパクトの例を探すことができる。生物学からのインパクトの例は、何と言ってもダーウィンの進化論だろう。しかし、21世紀に入って脳科学が進展することで、さらに多くの同じような哲学へのインパクトが生まれるのではと期待している。他にも重要な最近の例をあげると、論理学とチューリング理論の関係がある。エピステーメーへの方法論を目指してきた論理学は、ギリシャ以来哲学の重要な分野として続いてきたが、20世紀に入ると数学者バートランドラッセルにより数理の枠組を融合して、無矛盾とは何かを求める研究が行われた。20世紀を代表するとされているヴィトゲンシュタインの著作も、この延長にある。これに対し、アラン・チューリングはチューリングマシンを提案し、現実世界(物理世界)の機械的動作に変換できる論理かどうかが無矛盾の基準となりうることを示し、見事に検証できる論理とは何かについての基準の確立に成功する。この結果(私の印象だが)、現代哲学から論理学という領域の重要性が低下したように思う。現実の物理世界や生物世界を説明することは科学だが、このように当然哲学にも大きな影響がある。
ガリレオ以前も、哲学とは独立した科学の萌芽は多く存在した。しかし、哲学や宗教の力は大きく、科学が考える世界は、決して哲学から独立することはできなかった。そこにガリレオが登場し、客観的とは何かを体系化していく。この過程は全く科学者ガリレオの個人的な活動だったが、逆説的にも、それが宗教裁判を経ることで、自然科学は新たに現れた新しい哲学から独立した知識体系として哲学に認識され、対峙することになった。この哲学と科学の二元的関係を確立したのがガリレオと宗教裁判の意義だ。
以上が、今回ガリレオについて私が言いたかった全てだが、まず彼の著作をざっとおさらいして見てみよう。
この稿を書くにあたって、ガリレイの著作三冊、「星界の報告」(講談社、Kindle版)、「偽金鑑識官」中公クラッシック、そして「新科学対話」岩波文庫を新たに読んでみた。
今回はそれぞれの内容について詳しく解説することはやめる。17世紀に書かれたといえども基本的には科学を通した自然の探究方法と理解が議論された本だ。このことは、今回続けてこの三冊を読んではっきり認識できた。読み進むと、ガリレイがまさに現代に生きる科学者と同じで、哲学を特別に意識することなく、純粋に科学から得られる知識を熱心に述べていることがわかる。まさに純粋の科学者がそこにいる。しかも現在の科学者と同じで、人間臭く、野心に満ちている。
たとえば・デビュー作と言える「星界の報告」を見てみよう。これはガリレオ44歳の時に出版され、オランダで開発された望遠鏡を天文学に導入する重要性と、これによる様々な観察、それに基づく考察が淡々と書かれており、天文学の面白さを一般の人(あるいはスポンサー)に伝えようとする意図が伝わる著作だ。現在の科学コミュニケーションの走りと言ってもいい。
そして最大のスポンサーだったコジモ・メディチにあてた謝辞で、彼が初めて発見した木星の惑星の命名について、
「庇護者であられるコジモ殿下、過去のいかなる天文学者にも知られていなかったこれらの星を発見しましたので、全く正当なこととして、それらに殿下の神聖なる仮名を付けようと私は決心したのです。私がそれらの星を最初に見つけたのであるなら、またそれらに名前を与、メディチ星とよぶとしても、誰が私を非難する権利を持つというのでしょうか 」(講談社 星界の報告 伊藤和行訳)
と述べている。大変なごまのすりようだ。
科学者としてこの短い文章を読むと、「科学はすぐに金にならなくとも、名誉や名を後世に残すのに役立つと」熱っぽく語り、今後の研究支援を要求しているように見える。研究のために権力者にこびるのをいとわない。この点でも、現代の科学者も基本的には違うところはない。
その後、彼は教皇にも直接面会するトップサイエンティストとして世界に名を知られるようになる。今で言えばノーベル賞級の学者になる。しかし有名になったが故に、否応なしに地動説をめぐる論争に巻き込まれる。そして1615年には第一次ガリレオ裁判で、地動説を封じられる。この時はある意味で温情に満ちた判決を受けている。一次ガリレオ裁判がこの程度で済んだのは、彼の業績をバチカンも権力者も高く評価していたからだと思う。しかし科学者にとって、宗教的ドグマを理由に自説を自分で否定することは忸怩たるものがあるはずだ。おそらくやりようのない気持ちで毎日を過ごしていたはずだ。そんな1619年に始まったのが、イエズス会・ローマ学院教授グラッシとの彗星を巡る問題についての論争で、表向きは彗星とは何かについての論争だが、その背景にある宇宙観(=科学観)が直接戦わされることになる。この論争の中で書かれたのが「偽金鑑識官」だ。
ガリレオの生涯については、私が大学生の頃出版された中央公論社「世界の名著・ガリレオ」の責任編集者であった、当時、名古屋大学教授の豊田利幸先生が書かれた200ページにわたる解説(この本が一般に手に入らないのは残念だ)が優れている。その中で偽金鑑識官について面白いコメントを述べておられるのでまず紹介したい。(下図は私が医学部を卒業した時に出版された世界の名著に挟まれていた付録。豊田先生と、何と湯川先生の対談が掲載されている。)
「(最終的に書き上がってきた本は)、毒舌の雄で、しかも筆力にかけては当代並ぶものがないとされたガリレオが、いったん決意して筆を取ったのであるから、その文章は、これ以上相手を怒らせるものはない、と思われるくらい、誠に痛烈なものである。この本が、古来、「論争のバイブル」と言われる所以である。 」
私が「偽金鑑識官」を読んで感じたのも、全く豊田先生が書かれているとおりだ。このように、「偽金鑑識官」を読むと、名を遂げた有名な科学者が、彼から見ておおよそ科学者とは思えない小物、偽科学者グラッシの致命的誤りを容赦無く罵倒するアグレッシブな研究者の姿が浮かんでくる。実際このような有名科学者によるアグレッシブな論調は現在でも多く見ることができる。
しかしこの論争の場合、現代と違って問題は科学的論争で止まらない。グラッシは科学者としては小者でも、イエズス会、そしてその背後のカソリック教会の権威を背負って論争に参加している。結局科学的論争は、必然的に教会のドグマ批判へと向いてしまう。
そんな中で、プロレマイオスのような過去の権威をかさに、宇宙を説明しようとするグラッシに対し、この本の最も有名な一節が述べられる。
「サルシ(グラッシが偽名で論争に参加している)さんとやら、そうは問屋がおろしませんぞ。哲学は目の前にたえず開かれているこの最も巨大な書(すなわち宇宙)のなかに、書かれているのです。しかし、まずその言葉を理解し、そこに書かれている文字を解読すること学ばない限り、理解できません。その書は数学の言語で書かれており、その文字は三角形、円その他の幾何学図形であって、これらの手段がなければ、人間の力では、その言葉を理解できないのです。それなしには、暗い迷宮をむなしくさまようだけなのです。それにしても、たといサルシがいうみたいに、私たちの知性は、誰か他の人間の知性の奴隷にならなければならないと仮定し、天体の運動を考察する際には、誰かの説に同意しなければならない・・・・・ 」(中公クラッシックス:山田慶兒、谷 泰訳)
ガリレオの考える真知とは何かが、この一節に集約されている。すなわち、
1) 理性のある人間なら共通の理解に到達できる哲学(自然世界)が存在する。
2) これまでの権威やドグマといった人間の力(人間の憶測や思いつき)にだけ頼っては、自然は本当に理解できない(=ドクサの否定)。
3) 代わりに、数理や実験など他の人と共有できる方法を用いて、世界の共通理解を目指す必要がある。
と主張している。
ここでは自然の言葉として数理や幾何学の話が引かれているが、要するに人間が勝手に想像する世界とは異なる数理や幾何学を適用できる世界が存在すること、そして正しい手続きを踏めばこの世界についての共通の理解が得られること述べている。ただ注意して欲しいのは、ピタゴラスのように世界が数理でできていると主張しているのではない。逆に、数理や幾何学は、世界を理解するための我々が設定する一種の仮説で、数理が当てはまるかどうか検証するための実験が必要になる(ガリレオは多くに実験を行なったことで有名だ)。
現在、科学は様々に定義されているが、突き詰めていくと、理性を持つ人間であれば共通の理解が可能な世界を、他の人と理解を共有するための哲学や宗教とは異なる明確な手続き(数理であったり実験であったり)を設定し、それにもとづいて世界の理解を不断にアップデートしていく過程と言っていい。こうして生まれる知識は、完全に個人の憶測や思いつき(ドクサ)を排除した知識で、決して絶対的ではなく、常に未完ではあるが、発展的だ。このような観念を生み出すためのプロセスが科学だ。重要なことは、この科学知識を得るプロセスは、それまでの哲学や宗教から全く独立している。
しかし、独立しているから宗教や哲学と無関係とはいかない。逆に哲学や宗教から全く独立しようとしたからこそ、ガリレオは最終的な迫害の対象になり、公開の第二次ガリレオ裁判で厳しい判決を受け、引退生活を強いられる。
この隠遁生活の中で書かれたのが「新科学対話」で、引退した老科学者が若い学徒に科学とは何かについて、アリストテレス を信奉する学者を交えて話し合うスタイルで描かれている。そして、この本で彼は、歴史的にも宗教や哲学から切り離すのが難しかった天文学ではなく、彼が多くの実験を重ねて体系化してきた力学に焦点を当てて教えている。
これまで天文学者ガリレオについて主に述べてきたが、ガリレオを科学の父にしたのは「新科学対話」や「機械学(レ・メカニケ)」にまとめられた力学研究かもしれない。事実、ガリレオの実験として最も有名なのは、ピサの斜塔から大小異なる重さの球体を落とした、落下の法則を示すための実験、教会で揺れるランプを見て発見したとされる振り子の等時性の実験のような力学実験だ。この研究により、彼は加速度や、慣性といった、後にニュートンにより体系化される力学を準備した。
このように「新科学対話」はガリレオの到達した地点がまとめられた教科書と言える。かっては野心に満ち、アグレッシブな科学者だったガリレオも、物静かな純粋な科学者として、彼が到達した知識を後進に伝えようとしているのがしみじみわかる。
以上、ガリレオの3冊の著作について、内容の紹介はスキップして、その雰囲気だけを短くまとめてみた。科学者も社会の中で生活し研究しており、ガリレオが世間と積極的に関わっていたことが最初の2冊からはわかる。しかし彼の研究の集大成と言える最後の「新科学対話」では、科学が政治、宗教、そして哲学からも完全に無関係な存在であることが示される。ただ、「新科学対話」に示された新しい方法論は、どれほど世間や哲学から独立していても、ガリレオがバチカンの法廷に引きずり出されたことで、哲学や宗教に新たな問題、すなわち「科学以外にドクサを排したエピステーメーに至る道はあるのか?」と問いをつけることになる。この問いを最初に受けとめたのが、デカルトで、近代哲学はこの突きつけられた問いから始まったと言っても過言でない。
独断的ガリレオの紹介はここまでにして、最後に、非哲学的であったが故に、哲学に対峙する科学という二元的構造の原因を作ったとしてガリレオ批判(=科学批判)を行った20世紀の2人について紹介したい。
「新科学対話」に書かれた、哲学や宗教から独立した新しい知識が、宗教裁判により裁かれたが故に、哲学からの完全分離を自ら求めたことが、人類に新しい問題をもたらしたのではないかと呼びかけたのが、ドイツの劇作家ブレヒトの「ガリレオの生涯」だろう。
この劇では、私が説明してきたように、野心に満ちた世俗的科学者としてのガリレオ、有名になったが故にバチカン法廷に引きずり出されたガリレオ、そして引退して「新科学対話」に取り組む静かなガリレオが描かれるが、劇の最後はガリレオの遺作「新科学対話」が、イタリアの国境を越え世界へと伝えられるシーンで終わっている。
この場面の最初に挿入されたソネットを見てみよう。
さて、この結末をどう考えよう。
知識は国境を越えて亡命し、
知識に飢えた我々は私も彼も取り残された。
いまこそ科学の光を監視して
悪用せずに、活用すること。
でないとそれがいつか火の玉になって
我々みんなを焼き尽くす、
そう、そんなことにならぬよう。
ブレヒト. ガリレオの生涯 (Japanese Edition) (Kindle の位置No.2618-2622). Kindle 版.
お分かりのように、ブレヒトは科学のインパクトを、「我々を焼き尽くす火の玉=原爆」と重ねている。すなわち、哲学から独立したことで、科学が我々を焼き尽くす火を造ってしまうことを予言している。そして「新科学対話」の入った木箱がイタリアの国境を抜けようとするとき、それを見た何もわからない子供達に、その箱を「悪魔の箱」と呼ばせ、その子供達に最後にガリレオの教えを受けた科学者代表アンドレアが次のように科学の可能性を語って終わっている。
アンドレア(振り向きながら)
違うよ、私がやったんだ。ちゃんと目を開けて見ることを学ばなくっちゃ。・・・・・・。そうだ、ジュゼッペ君、君の質問にまだ答えてなかったよね。棒っきれに乗って空を飛ぶことはできない。少なくとも、それには機械が必要だが、そんな機械はまだできていないんだ。もしかしたら永遠にできないかもしれない、人間は重すぎるからねえ。でももちろん、わからないさ。僕らの知識はまだまだ足りないんだよ、ジュゼッペ君。まだほんのとばくちに、立ってるだけだからね。
( (光文社古典新訳文庫 ブレヒト作「ガリレオの生涯」 長谷川道子訳)
すなわち、「科学は、「目を開けてみることを学ぶ」ことから始まる。しかし、どこまで知識が深まり、技術が発展するかを予想することは科学ではない。すなわち、常に未完であることが科学の特徴と言える。そして、未完であることを認識するからこそ、科学は将来も発展し知識をアップデートし、新しい技術を創造し続けるのだ」と述べて終わる。
もちろんこの台詞は、20世紀までの科学の発展と、その戦争利用を実感したブレヒトが書いた、極めて現代的な台詞だが、ガリレオ以降、科学の社会や哲学へのインパクトは指数関数的に高まり、現在に至っている。
ガリレオにより示された新しい世界理解の方法論が、従来(例えばプラトンやアリストテレス )の自然理解と決定的に異なる点は、世界から目的や意味を排除した点だ。これこそが科学と哲学の二元構造が生まれる理由だが、このことをよく示すのが「科学の客観性」と「科学中立論」と表現されてきた概念だ。ブレヒトはガリレオだけでなく、原爆計画に関わったアインシュタインについても戯曲を書こうと計画していたようだ。これは「科学がナチスであろうと連合国であろうと、全ての人間が利用できる客観性と中立性を持つが故に、米国に原爆製造の重要性を説いた」アインシュタインを描くことで、客観性と中立性を掲げて世界から独立してしまった、原爆に象徴される科学の責任を描こうとしたからだと思う。
もう一人ガリレオ批判として紹介したいのが、「本当に科学と哲学の関係はこのままでいいのか?」について、ガリレオにまで遡って考えた20世紀前半を代表する哲学者、エドムンド・フッサールとその著書「ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学」だ。
この本はナチス政権が始まった時期に、ウィーンとプラハで行われた講演をベースにまとめられた著作だ。本の出だしの第4章のタイトルは、「新たな学は初めは成功したが、結局挫折した。その動機は解明されていない 」というセンセーショナルなもので、
「人間が、みずからの理想とする普遍的哲学と新たな方法の有効性に対する生き生きとした信頼を喪失したためであろう。そして実際その通りことは進行した。この方法が確かな成果を上げ得たのは、実証科学においてだけだということが明らかになったのである。形而上学、したがってまた特別な意味で哲学的な諸問題―そこにも一見成功を収めて希望に満ちた端緒がないわけではなかったのだがー諸々の事実事情は違っていた。この哲学的な問題を諸々の事実学に結びつけた普遍哲学は、強烈な印象を与える体系哲学という形をとったが、残念なことにそれは一つの哲学に帰一することなく、相互にバラバラな多くの哲学となった。」
と述べて、デカルト以来のヨーロッパ哲学が、彼が「我々が驚嘆してやまない純粋数学や精密自然科学 」(=事実学)を統合できずに、結局「バラバラな多くの哲学 」に分散してしまった原因を探ろうとしている。
重要なのは、このヨーロッパ哲学史の分析が、ガリレオの実証科学の方法論のインパクトの分析と、これを受け止めたデカルト二元論の失敗から始まっている点だ。すなわち、科学は、「経験によって自明なものとしてあらかじめ与えられている世界を基盤としてその「客観的真理」を問い、世界にとって、つまり全ての理性的存在者にとって無条件に妥当する 」エピステーメーへ到達する方法論を確立したが、その過程で、知識から意味や目的を排除したことを問題視している。
まず、
「ガリレイは幾何学と、感性的な現れ方をし、かつ数学化されうるものから出発して世界へ眼を向けることによって、人格的な生活を営む人格としての主体を、またあらゆる意味での精神的なものを、さらに人間の実践によって事物に生じてくる文化的な諸性質を全て捨象する。 」
と述べて、ガリレオが「事実学」にただただ集中するだけで、主体としてその目的や意味を求めることは全くなかったと明言し、返す刀で自然科学者についても、
「だが、せいぜいのところ方法の最も優れた技術家――彼がひたすら追求する発見もその方法のおかげをこうむるーーでしかない数学者や自然科学者は、このような省察を遂行する能力を全く持っていないのが普通である 」
と、これからも自然科学の側からもう一度普遍的哲学を目指すことは絶対あり得ないと結論している。
このように、ブレヒトやフッサールからみると、科学自体が意味や目的を科学に取り戻すことはないことを強調している。もちろん私自身もこの批判は重く受け止める。要するに科学は科学者を首から上のない機械にしてしまうと批判されている。しかし、私は科学者が哲学を勉強したら、首から上が自然にできてくるとは思わない。逆に、私から見て多くの哲学者は、首から下のない人間になってしまっており、フッサールが嘆くように普遍的哲学の可能性は失せようとしている。
楽天的な私は、おそらく21世紀、脳科学や生命科学がさらに発展することで、もう一度普遍的哲学、あるいは普遍的科学が可能になるように感じている。もちろん、これには科学と哲学の率直な対話は必要だが、世界の各所でこの動きを感じることができる。そして、この動きを伝えることが、生命科学の目で読む哲学書の使命だと思っている。
これで17世紀についての紹介を終わるが、次は大陸からのブレクジット、英国経験論の哲学者を紹介する。
2022年4月1日
Covid-19重症化のリスクファクターとして肥満がリストされ、この指針に従って治療選択も行われているが、そのメカニズムについては明らかになっているわけではない。一般的に、多くの炎症反応が肥満によって悪化することは広く知られているため、Covid-19のケースもその一つかなと納得してしまっている。
今日紹介するソーク研究所とカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、接触性皮膚炎をモデルとして、アレルギー性炎症が肥満で悪化するメカニズムを解明した臨床応用も期待できる研究で、3月30日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Obesity alters pathology and treatment response in inflammatory disease(肥満は炎症性疾患の病理と治療反応性を変化させる)」だ。
研究ではまず、高脂肪食を70日与えて肥満にしたマウスに、化学化合物(MC903)を塗布してアレルギー性皮膚炎を誘導し、正常マウスと比べている。結果は期待通りで、肥満マウスでは炎症の程度が数倍高い。
この炎症はT細胞の抗原反応により誘導されることがわかっているので、次に炎症部位のT細胞をsingle cell RNAseq(scRNAseq)で調べると、同じ炎症と言っても参加するT細胞が質的に異なっていること、すなわち通常のTh2型T細胞が主体の反応から、Th17主体の反応へ変化している。
これを裏付けるように、Th2型反応に対して効果が高いIL4/IL13に対する抗体治療を行うと、正常マウスでは炎症が軽快するのに、肥満マウスの炎症は逆に悪化する(これは現在抗体治療を行っている皮膚科にとっては重要な所見だと思う)。
T細胞の分化にRORγなど核内受容体が関わっていることが知られているので、肥満によるT細胞の質的変化の原因が核内受容体の変化に起因すると仮説を立て、肥満と正常マウスのTh2型細胞を比較した結果、肥満マウスでPPARγの発現が低下していることを発見する。すなわち、Th2型の反応が維持されるためにはPPARγが必要で、これが低下することでTh17型へとシフトする可能性が示された。
この可能性を確かめるため、T細胞でPPARγ遺伝子をノックアウトしたマウスを作成し、接触性皮膚炎を誘導すると、肥満マウスと同じようにTh2型反応がTh17型にシフトし、またIL4/IL13に対する抗体治療により、より炎症が悪化する。すなわち肥満による反応の質的変化を完全に再現できる。
以上の結果から、肥満マウスでもPPARγを活性化させることで、Th2型の炎症に戻セル可能性が示唆される。そこで、糖尿病のインシュリン抵抗性を治療するために用いらているチアゾリジン系のPPARγ活性化剤を投与して、肥満マウス接触性皮膚炎を誘導すると、期待通りTh2型の反応に戻り、炎症の程度は低下、またIL4/13による治療が可能になる。
以上が結果で、モデルマウスに実験は終始しているが、臨床的なヒントが示された面白い研究だと思う。
この研究をトランスレートするとすると、皮膚炎や喘息が通常の治療法では改善しない肥満患者さんには、出来ればTh17型へのシフトが起こっているか調べた上で、チアゾリジン系の薬剤を併用してみるという話になるのだろう。また、Covid-19の炎症についても、PPARγについて調べ直してみることは重要だと思う。
2022年3月31日
エーザイの抗アルツハイマー病薬、アリセプトは、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤で、アセチルコリン(Ach)の分解を抑えることで、Achの量を相対的に上昇させる薬剤だ。
今日紹介するマサチューセッツ総合病院からの論文はマウスにアリセプトを投与したとき、白血球減少が見られるという観察から始め、これがB細胞によるアセチルコリン分泌を介している可能性を示した研究で、3月28日Nature Immunologyにオンライン掲載された。意外性で惹きつけるタイトルは「B lymphocyte-derived acetylcholine limits steady-state and emergency hematopoiesis(B細胞由来のアセチルコリンが定常状態及び緊急事態の造血を制限する)」だ。
タイトルで驚いたが、著者欄を見るとDavid ScaddenやPeter Libbyといった大御所が加わっておりさらに驚く。しかし研究自体はアリセプトの効果の原因を探るといった感じで、オーソドックスな研究で、内容からScaddenやLibbyが加わるのもよくわかる。
アセチルコリンの骨髄への影響を知るため、まずアセチルコリンを合成する酵素を持つ骨髄細胞を探すと、ほぼ全てがB細胞集団であることがわかった。
次は、本当にB細胞のアセチルコリンが造血に関わるのか調べるため、B細胞特異的に合成酵素をノックアウトすると、期待通りノックアウトマウスではB細胞のアセチルコリン分泌量が低下するとともに、骨髄造血、特に白血球造血が上昇している。
次にAch受容体を発現する細胞を探ると、ストローマ細胞集団で発現が見られ、またAch受容体がノックアウトされると、Ach合成酵素ノックアウトと同じ効果がある。すなわち、B細胞のAchがストローマ細胞に作用して増血を調節していることになるが、このメカニズムは完全に明らかにできていない。
例えばAchのB細胞でノックアウトしたマウスでは、骨髄造血に必要なCxcl12が低下していることを示しているが、Cxcl12は未熟幹細胞の維持に必須であると考えると、Achで低下しているとすると、もっと未熟幹細胞が低下してもいいように思うが、そうではない。ただ、この結果か、少し分化した顆粒球系の幹細胞が増加している。とすると、AchはCxcl12発現を上昇させて、未熟幹細胞を維持する役割があるのかもしれない。その場合、老化に伴う造血系の変化をアリセプトが改善する可能性すらある。
そこで、メカニズムを追求するのはやめて、Achにより白血球のリクルートが調整されるという結果を受けて、動脈硬化での炎症がB細胞のAchで影響されるか、ノックアウトマウスを用いて調べている。Libbyたちがこれまで示しているように、Achが抑えられ、白血球が増加していると動脈硬化巣へのマクロファージや顆粒球の浸潤が高まることが確認されている。また、心筋梗塞巣への血球の浸潤を見ても同じで、白血球浸潤が高まる結果マウスの死亡率が高まる。
最後に、これが人間にも当てはまるか、心筋梗塞を起こした時にアリセプトを服用していた患者さん(Achが高い)を集め、服用していなかった群と比較して、血中の白血球数の上昇が少ないことを示し、Achが血中の白血球上昇を抑えるのは人間でも当てはまると結論している。
少し尻切れトンボの感が強い論文だったが、しかしB細胞がアセチルコリンの供給源とはともかく驚く。
2022年3月30日
CRISPRで変異を正常化することが遺伝子治療の究極の目標だと思う。特に、X染色体にある変異の場合、正常遺伝子を導入することは、変異を持つ細胞には良いが、正常な方の細胞では発現が高まり複雑な症状が生まれる心配もある。しかし、今のところ遺伝子ノックアウトの効率は高くとも、正確にコドンを変化させるとなると、まだまだ先の話だ。
この問題を、まだコドン表などができない昔に発見されたamber変異を用いて解決するための条件を探ったのが、今日紹介するMassachusetts Chan Medical Schoolからの論文で3月23日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「AAV-delivered suppressor tRNA overcomes a nonsense mutation in mice(AAVベクターを用いてサプレッサーtRNAを導入するとマウスのナンセンス変異を克服できる)」だ。
サプレッサーtRNAは極めて懐かしい名前で、若い人たちはもはや習っていないのではと思う。かくいう私も、なぜアンバー変異と呼ぶのかは把握していないが、ストップコドンの一つ、アンバーコドン(UAG)を他のアミノ酸に代えることで、premature terminationを防いで正常なタンパク質を合成できるようにする、tRNA側の変異を意味する。
突然変異の多くは、変異により本来のストップコドンより前にストップコドンが現れ、正常なタンパク質ができず、mRNAもすぐに壊れるため、機能分子を作れない。そこで、premature terminationコドンを、UAGを認識してアミノ酸を付加できるAmber suppressor tRNAを導入することで、一つアミノ酸は変化しても、ともかく完全なタンパク質を合成させようという方法が可能かどうか検証することがこの研究の目的だ。
この研究ではpremature terminationコドンを導入した蛍光分子の遺伝子の活性をレスキューする実験で、UAGストップコドンにチロシンを導入できるtRNAが、遺伝子変異を高率にレスキューできることをまず明らかにしている。
あとはこのsuppressor tRNA(変異を抑制できるという意味で付けられる名前)を、培養細胞、そして遺伝子変異を持ったマウスの肝臓に、アデノ随伴ウイルスを用いて導入し、機能分子の合成を復活できるか調べている。
何十年も前にアンバー変異として見つかっているのだから、うまくいくのが当然と思われるかもしれないが、遺伝子治療に使うにはいくつかの問題がある。
1)ストップコドンを認識するtRNAは複数存在するので、うまく導入したsuppressor tRNAが結合して完全なアミノ酸ができる確率はどの程度なのか?
2)そして何よりも、本来のストップコドンが機能しないため、異常タンパク質ができて細胞機能を低下させないか?
結果だが、マウス肝臓ではたらくiduronidaseにpremature terminationが入った変異は、このsuppressor tRNAを導入することで、ほぼ完全に回復させることができている。
一方、異常タンパク質の合成など副作用のほうだが、たしかにストップコドンを超えて作られるタンパク質もはっきり存在するが、細胞にとって十分処理できる程度で止まっている。
以上が結果で、確かにsuppressor tRNAがpremature terminationが起こる変異の場合は、かなり期待できる遺伝子治療になる可能性を示している。Amber変異を発見した人は、おそらく亡くなっていると思うが、富沢、小関先生が訳された「大腸菌の性と遺伝」を読んで知ったAmber変異が現在に蘇った気がした。
2022年3月29日
読んだあと、論文ウォッチで紹介するのはスキップという論文の中で、それでも気になる最近のCovid-19関係の論文をまとめて紹介しておく。
我が国でもオミクロン株の中でも、BA2と呼ばれる新しい株の感染が増えてきているようだが、パリ大学が3月23日Nature Medicineにオンライン発表した論文(上図)は、現在臨床に使われている9種類のモノクローナル抗体薬の、オミクロンBA1、BA2に対する効果を調べたタイムリーな研究だ。
現在我が国でオミクロンに対するスタンダードになっているソトロビマブはBA1には効果があるが、驚くことにBA2には全く効果がない。逆に、オミクロンには効かないとされていたアストラゼネカ社のCilgavimabはデルタ株に対するのと同等の効果を示す。
これまで個人的には、ソトロビマブで決まりかと思っていたが、どっこいそうはいかなかった。今後、いくつかの抗体を用意して、新しい株に対してはその都度効果がある抗体を探すことが必要になる。実際、オミクロンには効果がないとされたリジェネロンのImdevimabは一定程度の効果が期待できる。厚労省はこのような状況に対応できるだろうか。
抗体治療がダメでも幸い、モルヌピラビル、パクスロビドなど、SARS-CoV2(CoV2)の活動を抑える薬剤が開発され、我が国からもシオノギのS217622が承認申請中で、抗体薬以外の治療法が確立してきている。これをうまく使っていくためには、インフルエンザ並みに患者さんが開業医さんに直接受診できるようにする必要があると思う。
当然多くの会社が同じ方向に動いているが、Covid-19の抗ウイルス薬として実績のあるレムデシビルも、中等症の患者だけでなく、家庭でも利用できる方法の開発へ舵を切っている。
一つの方向は、レムデシビルをそのまま吸入する治療法で、薬剤を開発したLovelaceとGilead Scienceはサルを用いた感染実験で、レムデシビル吸入薬の方が、静脈注射より十分の一の濃度で気道や肺のウイルス量を抑える効果があることを示している。(2月23日号Science Translational Research:上図)
レムデシビルを初期治療に使えるようにするもう一つの方向が、経口摂取可能なように分子構造を修飾する方法だ。ノースカロライナ大学とGilead Scienceのグループが、3月22日号Science Translational ResearchにGS-621763という化合物が、マウスの感染実験で有効であることを示している。
結果を一言で表すと、マウスの感染モデルでは、モルヌピラビルより高い効果を示すと言える。ただ、マウス段階なので、臨床応用にはまだ時間がかかるように感じる。しかし、Gilead Science もなんとか初期治療に割って入ろうと力を入れているのがわかる。
レムデシビルもモルヌピラビルも、コロナウイルス以外にも利用できるので、Covid-19に間に合わなくても十分勝算はあるのだろう。
Covid-19感染がパンデミックになり始めた2020年2月に、ドイツ・ゲッティンゲンのドイツ類人猿研究所のグループがCoV2感染時のウイルス膜とホスト細胞の融合にTMPRSS2と呼ばれるセリンプロテアーゼが必要で、我が国で開発されたカモスタットが感染を抑えることをCellに発表した(https://aasj.jp/news/lifescience-easily/12537 )。残念ながらその後の治験で、カモスタットが感染者の治療には有効性なしと結論されたが、TMPRSS2阻害分子の吸入であれば効果が見られるのではと考え、新しいペプチド阻害剤を開発した論文がカナダ・ブリティッシュコロンビア大学などから3月28日Nature にオンライン発表された。
TMPRSS2の機能をナノモルレベルで阻害し、試験管内でカモスタットより効果が高い3つのアミノ酸がつながった分子を開発し、マウスの感染実験系で、感染1日前から鼻腔に投与すると、肺炎の発症を強く抑制できることを示している。しかし、感染後の投与では12時間後の投与で、効果が低下するので、一般臨床で使えるかどうかは疑問がある。ひょっとしたらカモスタットでも、予防的吸入であれば効果があるかもしれない。
最後はCovid-19に関する論文ではないが、ひょっとしたら治療に利用可能かもしれないというコロラド大学が3月10日American Journal of Physiology にオンライン発表した論文だ。
まず全てマウスの実験であることを断っておく。この研究ではマウスを強い光が当たる部屋で1週間飼育すると、肺の2型上皮細胞で時計遺伝子の一つPer2の発現を誘導することができ、この転写因子が緑膿菌感染とそれによる肺炎を抑えることができることを示している。これがウイルス感染症に当てはまるかはわからないが、まずマウスCovid-19感染モデルで確かめてほしい。
2022年3月29日
脳の環境を厳密にコントロールするため、脳血管関門(BBB)が存在するてめ、脳内への薬剤などの移行がブロックされていることは広く知られている。基本的には、血管内皮間のジャンクションを高め、トランスサイトーシスなど細胞自体を通る輸送経路を抑えることでBBBが維持されていると考えられるが、そのためのメカニズムはまだまだわからないことが多い。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、これまであまり注目してこなかった血管周囲細胞が分泌するビトロネクチンがトランスサイトーシスを調節してBBB維持に寄与していると言う論文で3月15日Neuronにオンライン掲載された。タイトルは「Pericyte-to-endothelial cell signaling via vitronectin-integrin regulates blood-CNS barrier(ペリサイトから内皮へのビトロネクチン/インテグリンシグナルが血液中枢神経系のバリアーを調節する)」だ。
この研究では網膜の血管周囲細胞(ペリサイト)にビトロネクチンが強く発現していることに気付き、この意味を調べるためノックアウトマウスを用いて血管の透過性を調べたところから始まっている。
ビトロネクチンというと、身体中を満たしていると思っているので、このような局所の役割があるということ自体が不思議だ。しかし、ビトロネクチンノックアウトされたマウスでは、網膜血管および脳血管で、ペルオキシダーゼのような大きな分子が漏れ出ていることが観察される。すなわち、BBBに重要な働きをしている。
面白いことに、siRNAを用いて肝臓でのビトロネクチン産生をノックアウトしてもBBBはびくともしないことから、脳血管局所でペリサイトと内皮細胞間のビトロネクチンを介する相互作用の破綻が、BBBの破綻につながっていると考えられる。
事実、ビトロネクチンのインテグリン受容体結合部位を突然変異させると、BBBが破綻する。また、試験管内の実験でこの過程にはビトロネクチンの受容体α5インテグリンが関わることも確かめている。
残るは、ビトロネクチンとインテグリンによりBBBが維持されるメカニズムだが、血管内皮同士のジャンクションや、ペリサイトとの接着などはノックアウトマウスでも全く障害されていない。一方、細胞質内に分子を取り込むエンドサイトーシスによって生じる細胞質内の小胞の数が上昇しているのが観察される。また、試験管内の実験で、ビトロネクチンシグナルが抑えられると、エンドサイトーシスが高まることが明らかになった。逆に正常状態を考えると、ペリサイトにより分泌されるビトロネクチンが内皮のインテグリンと結合することで、エンドサイトーシスが抑えられることで、BBBが維持されることになる。
結果は以上で、エンドサイトーシスがビトロネクチンシグナルで抑えられるシグナルメカニズムなど残された課題は多い。内皮細胞をストローマ細胞上で培養していた個人的経験から言うと、ビトロネクチンなどにより細胞膜の運動が安定化する。これはジャンクションの維持に重要と思っていたが、もちろん安定化させてエンドサイトーシスを抑えることもできるのだろう。
使われた網膜血管や血管内皮など、個人的には懐かしい思いで論文を読んだ。
2022年3月28日
筋肉幹細胞についての論文はこれまで何回も紹介してきた。Pax7分子発現が機能的に必須で、分子マーカーとして利用できるため、幹細胞の動態を可視化することができることが、この実験系の特徴になっている。
今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、Pax7を幹細胞分子マーカーとして利用した上で、その形態に基づいて幹細胞集団をさらに階層化した研究で、3月18日号Science Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Piezo1 regulates the regenerative capacity of skeletal muscles via orchestration of stem cell morphological states(Piezo1は幹細胞の形態を統括して骨格筋の再生能力を調節する)」だ。
この研究のハイライトは、筋肉に存在するPax7陽性幹細胞を、生体内で可視化しようとした点だ。筋肉を体外へ切り出して観察するのと異なり、形態的に多様であることに気づいている。特に、筋肉から飛び出す突起の数を数えると、全く突起を出さない丸い細胞から、5本の突起を出し、サイズでも大きな細胞まで、様々なタイプが見つかることが明らかになった。
さらに、切開しなくとも筋肉を観察できる耳の筋肉幹細胞について長期間追跡して、突起があるから移動するというわけではなく、特定の場所に止まっているのに突起を出していることも確認している。
次に、この幹細胞多様性の意義を、幹細胞が活性化され増殖・分化フェーズに入る筋肉障害による再生過程を観察すると、突起を出す細胞から出さない細胞へのシフトが起こり、障害後2−3日をピークに、また元の階層性が1ヶ月で回復することを示している。すなわち、突起のない細胞が障害シグナルに反応する細胞で、このポピュレーションを補うために、必要に応じて突起のある細胞からのリクルートが行われることになる。
もう少し幹細胞生物学的に言うと、突起のある細胞はいわゆる最も未熟で、静止期(quiescent)にある幹細胞で、そこからより活性化しやすい細胞への供給が必要に応じて行われていることになる。
静止期から活性期までの幹細胞の階層性が明らかになると、次は静止期幹細胞を維持する分子メカニズムの問題になるが、筋肉では以前から、昨年ノーベル賞を受賞したメカのセンサーの一つPiezo1の役割が指摘されていた。そこで、まずPiezo1を活性化する薬剤を投与すると、突起のある細胞が減る一方、活性化型の幹細胞が増加する。すなわち、幹細胞を増殖させる側へのシフトが起こっている。
逆に、Piezo1をPax7陽性細胞からノックアウトすると、突起を持つ細胞が増加し、活性化型細胞が減る。すなわち、静止期細胞から活性型へのシフトが抑制される。
以上のことから、Piezo1は静止期細胞で働いて、再生が必要かどうかを感知するときに働いており、再生の必要性が生まれてPiezo1が活性化されると、静止期の細胞から活性化型への分化が起こることになる。
以上の研究に基づいて、最後に筋ジストロフィーモデルマウスを用いてPiezo1の発現、幹細胞の形態を調べ、Piezo1ノックアウトマウスと同じで、Piezo1の発現が低下するとともに、静止期から活性化型へのシフトが抑えられていることを発見している。そして、Piezo1を活性化させる薬剤を投与することで、活性化型の細胞の数が増え、さらに筋肉再生も促進されることを示している。
結果は以上で、完全に形態だけに基づいて幹細胞を見続けている点で、私のような古い人間は好感を持ってしまう。しかし、このおかげで筋肉幹細胞の静止期を決めているメカニズムはさらに解明が進む気がする。さらに、筋ジストロフィーについても、再生をうまく維持して筋肉を守る治療法も確立できるかもしれない。形態侮るなかれ。
2022年3月27日
2日前、リステリア菌がマクロファージを操って脳に侵入するという恐しい能力についての論文を紹介した。この能力には2種類のインターナリン分子InlAとInlBが関わっており、InlBによってマクロファージの細胞死を防ぐことで、ゾンビ化してうまく脳まで運んでもらうと言う話だ。一方、InlAはこれまでの研究でリステリア菌がマクロファージのアクチン系を再構成して、マクロファージの取り付いた細胞へ移行するのに働いている。
今日紹介するアルバートアインシュタイン医科大学からの論文は、マクロファージに入った後、それが接触している細胞に移行すると言う性質を逆手にとって、治療が困難な膵臓ガンの治療に使えないか調べた研究で、3月23日号Science Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Listeria delivers tetanus toxoid protein to pancreatic tumors and induces cancer cell death in mice(リステリア菌による破傷風菌トキソイドタンパク質の膵臓ガンへの導入はマウスでのガン細胞の細胞死を誘導できる)」だ。
これまでも破傷風菌毒素(TT)を利用した細胞障害自体は、特定の細胞を殺して除去する目的で実験では利用されている。したがって、ガン特異的にこの分子が分泌されると細胞を殺すことができる。ただ、リステリア菌にTTを運ばせる場合、他の細胞への影響は無視できない。
代わりにこの研究ではTTの毒性を取り除いた遺伝子を導入し、子供時代に受けたTTワクチンにより誘導されたCD4T細胞をガンの周りにリクルートし、細胞障害性を発揮させるというアイデアだ。
現在ワクチン効果がどこまで続くのか議論されているが、子供時代(我が国では12歳)に受けたTTのワクチンは成人するまで効果を保つことが知られている。また、CD4T細胞メモリーはさらに長く続くことが知られている。
そこで、この研究では膵臓ガン局所に無毒化したTTを分泌するリステリア菌をマクロファージに食べさせて、そこから膵臓ガンへ移行させ、膵臓ガン内でTTを分泌させ、それを抗原として、すでに誘導しているTT特異的なT細胞に殺させると言うアイデアを試している。
子供時代のワクチン 効果を期待する点でユニークな研究だ。もちろん、導入効率(8割の癌細胞に導入できるようだ)だけでなく、安全性やリステリア菌の除去、予想通りCD8ではなくCD4キラーにより腫瘍が殺されるなど、様々な条件を調べているが、詳細は省く。
最後に膵臓ガンが自然発生するトランスジェニックマウスを用いて、ガンが進行してから、この方法の有効性を確かめているが、ジェムシタビンとTT導入リステリア菌を用いると、腫瘍縮小が見られ、ジェムシタビン単独と比べてマウスで2ヶ月生存が延長する。また、腫瘍周りに、リンパ組織様の構造も形成され、おそらくCD4キラー細胞や炎症細胞をリクルートする基地になるという結果だ。
残念ながらこれだけで根治というまではいかないようだ。ただ、この研究ではチェックポイント治療は併用していない。また、人間と比べるとガンのネオ抗原が発現している可能性が低い。したがって、人間の場合、ガンに対する障害性をさらに長続きさせたり、TTを引き金に他の抗原に対する免疫反応を誘導することも可能と思われるので、期待できるのではという感触がある。一方、子供時代のワクチンに完全に依存していいのかという問題はある。まだまだ先は長そうだが、期待したい。