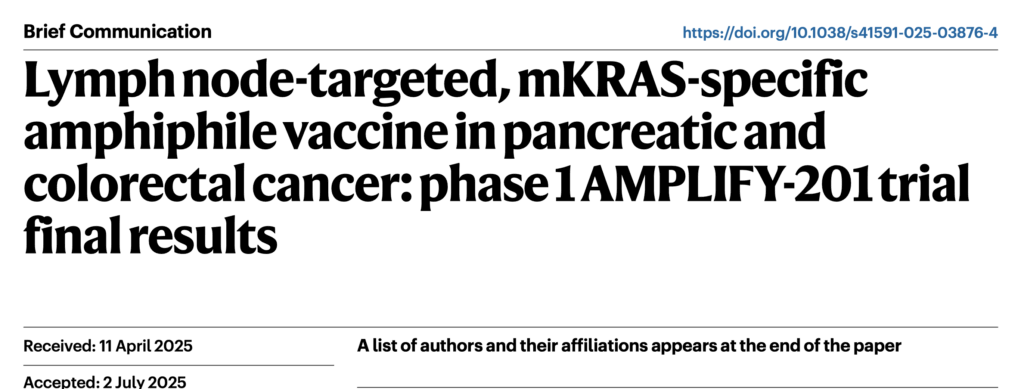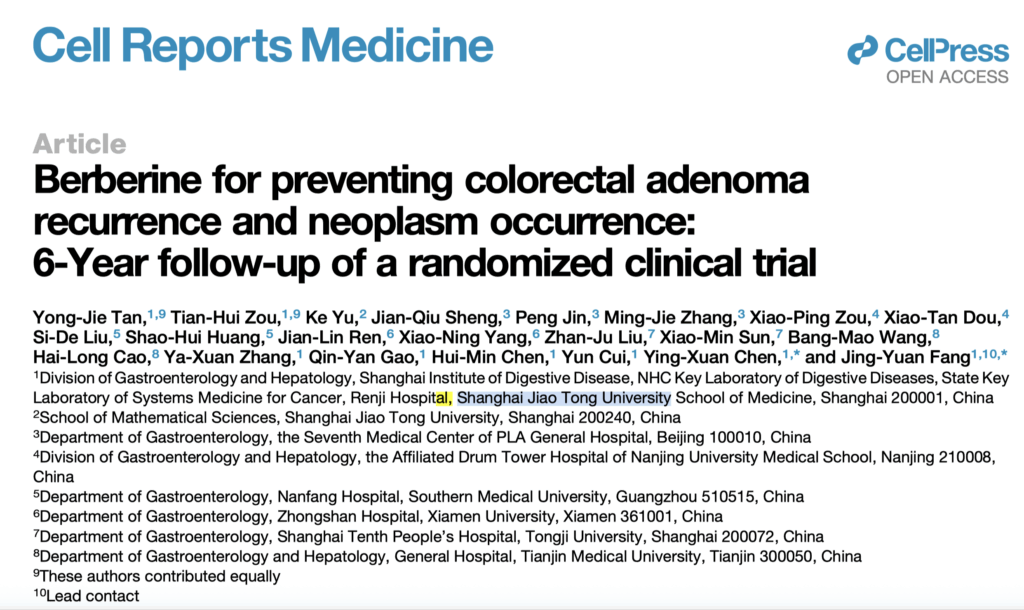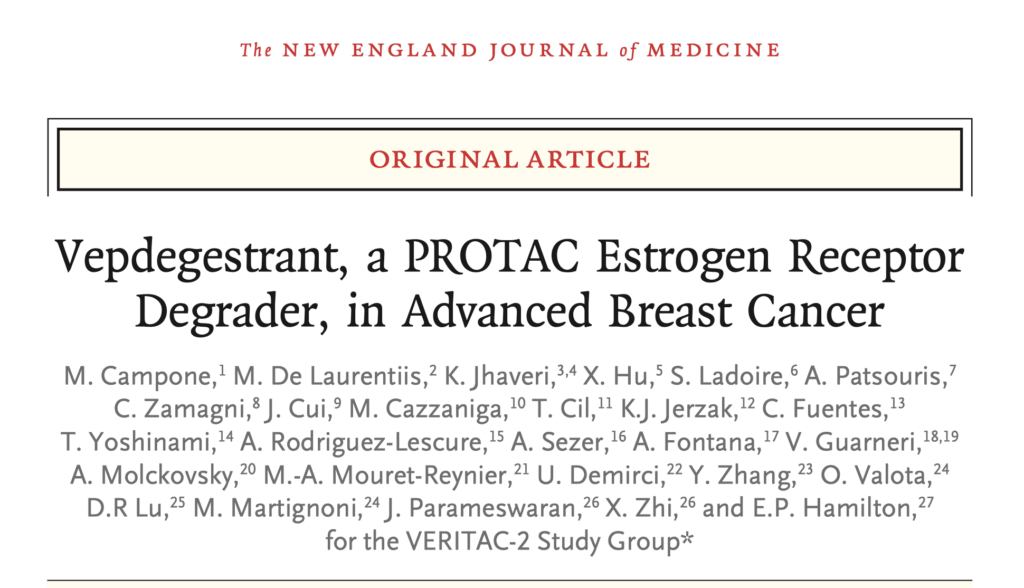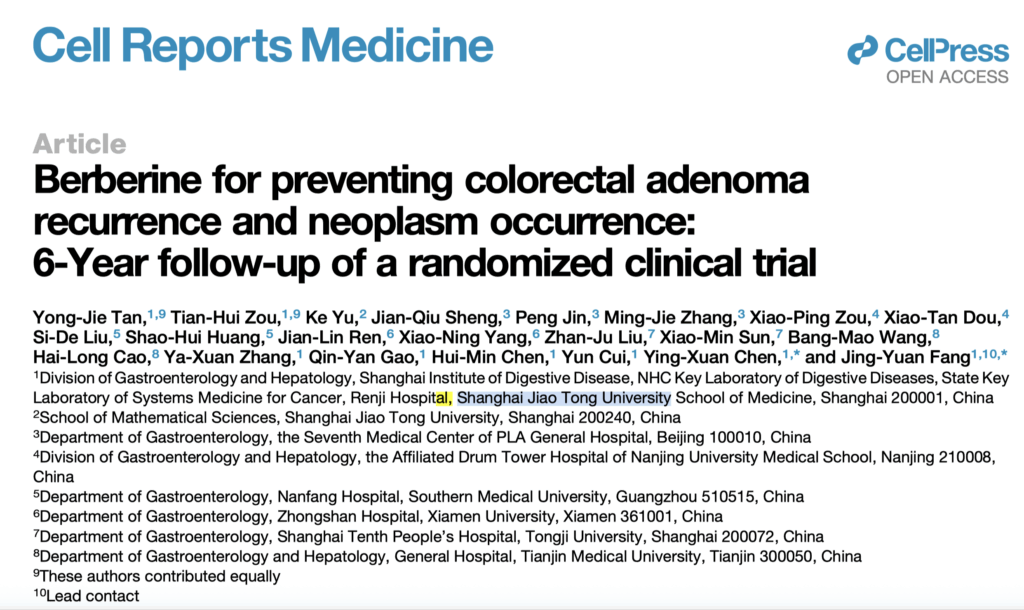2025年8月13日
例によって気になった臨床研究をいくつか紹介するが、今日最も紹介したい論文は変異RASペプチドを抗原として膵臓ガンや大腸ガンの患者さんの抗ガン免疫を誘導する第一相治験のフォローアップ論文で、Nature Medicine にオンライン掲載された。
このワクチンについてはかなり期待できるとして昨年1月に紹介している(https://aasj.jp/news/watch/23781)。よく考えられたワクチンで、抗原としては変異RASペプチドを用いており、RASをドライバーとするガンはほとんどが標的になる。このペプチドを脂肪酸を介してアルブミンと結合させ、皮下注射するとすぐにリンパ節に行くように設計している。さらに同じアルブミンにアジュバントとして Tol9 を刺激する一本鎖DNAをつないで免疫を高めている。25例中21例でガンの増殖を抑えられたという結果だったが、今回の論文は同じ患者さんをさらに平均19.7ヶ月まで追跡した結果を報告している。
最初はワクチンだけの治療だったが、その後ガンマーカーが上昇する場合他の治療を組み合わせており、その中には PD-1 に対する抗体もあるが、このような治療上の違いは全くカウントせず、再発、生存期間でフォローしている。コントロールはないが、膵臓ガンで半数が2年以上生存していることから効果は大きい。特に、免疫後のT細胞反応が10倍近く上昇したグループを抜き出してみると2年で生存率が75%で、最初の論文の予想が確認された。他のガン抗原に対する免疫も誘導される spreading も認められており、今後チェックポイント治療や、あるいは粒子線治療などの組み合わせを工夫すれば大きな成果を上げられるように思う。特に、手術前にネオアジュバント治療として採用する治験も是非進めてほしい。すでにコントロールを置いた次にフェーズに入っているということで、かなり期待している。
次の上海交通大学からの論文は漢方薬で下痢止めや肥満防止に使われている黄柏由来のアルカロイドベルベリンが大腸ポリープ切除後の再発を抑えるという治験研究だ。
前臨床研究でベルベリンが大腸のポリープの再発を抑えることがわかったので、無作為化して450人づつの規模でベルベリン接種有り無しに分け、まず2年追跡して再発を抑えることを確認したあと、さらに6年までフォローアップを伸ばして調べたのがこの研究だ。6年追跡すると、ポリープの再発だけでなく、ガンの発生についてもある程度追跡できる。
結論としては、ポリープの再発は強く抑制でき hazard ratio で0.58と大きく低下する。ガンの発生についても、ポリープほどではないが一定の効果が見られると結論している。
ベルベリンはサプリとして利用されおり、アスピリンなどと同じく直腸ポリープ、即ちアデノーマを予防的に抑える薬として使えそうだ。最後に、上海交通大学の研究はこれまでも紹介しているが、いつも漢方への気配りが感じられる研究で面白い。
3番目の論文は新しい乳ガンの経口薬に関する治験で、乳ガンは新しい薬とそれに対する耐性のいたちごっこにはなっているが、着々と理論に基づいて新しい薬剤が開発され、再発後の長い戦いを支えていることがよくわかる論文で、8月7日号の The New England Journal of Medicine に掲載された。
乳ガンの7割を占めるエストロゲン受容体 (ESR) 陽性、HER2 陰性の患者さんの再発例は、ESR 阻害、あるいはエストロゲンの枯渇を誘導するアロマターゼ阻害剤と、CDK4/6 阻害剤の組み合わせが用いられ、このブログで何回も紹介した。ただ、この治療を続けると半分ぐらいの患者さんで ESR の変異が起こり、エストロゲン治療が効かなくなる。
これに対し ESR にタンパク分解システムをリクルートして ESR を分解してしまうプロタック型、あるいは分子糊型の薬剤が開発され、現在はアストラゼネカの Fulvestrant が使われている。ただ、溶解性が悪く筋肉注射が必要で、経口薬が待たれていた。この目的でアストラゼネカは同じ分子糊型 Camizestrant を開発し、同じ号の The New England Journal of Medicine にアロマターゼ阻害剤の代わりに使えることを示している。
これに対し今日紹介する論文は、Arvinas/Pfizer が提供するプロタック型経口薬 Vepdegestrant の第三相治験で、同じように ESR を分解するアストラゼネカの Fulvestrant 筋肉注射と比較している点が面白い。
筋肉注射が必要という問題はあっても ESR 分解なので同じ程度に効果があるのかと思いきや、ESR 変異を持つ患者さんで見たとき、Fulvestrant より明らかに効果が高く、18ヶ月で全くガンが進行しないケースが3割近く存在する。すなわち、同じメカニズムでも、薬により効果は大きく違うことがわかった。
今後アストラゼネカの分子糊型経口剤 Camizestrant との比較が行われるのではと思うが、患者さんの治療可能性が広がる過程は、創薬企業の熾烈な競争過程であることがよくわかる治験だ。いずれにせよ、ESR の変異が発生したときの次の手の効果が高まることは喜ばしい。
ガラッと趣を変えて、次の論文は認知症の発生に対する教育程度の効果を調べた研究で、7月28日 Nature Medicine にオンライン掲載されている。
これまで、高い教育を受けているほど認知障害の発生が抑えられることを示す研究は多く存在する。この研究では、ヨーロッパとアメリカの17万人のデータ、その中の1万5千人の MRI データを分析し、これまでのドグマを再検討している。
結果だが、確かに記憶力を測ると教育程度が高いほど高いスコアが出るが、年齢とともに記憶力が低下する速度は全く同じで、結局は脳の老化や認知症の発生を教育では根本的に予防できないという結論になる。
この結果は MRI による脳の萎縮程度でも確認され、教育によって脳機能に下駄を履かせることはできるが、年齢による機能低下速度を変えることはできないようだ。いずれにせよ、若いときに脳を鍛えてスタートラインをずらせておけば、劣化が始まっても余力を残すことができるので、やはり教育は大事だ。
2025年8月12日
CRISPR システムを用いた遺伝子編集は、遺伝子切断による変異誘導や一塩基変換に関しては定着してきたが、遺伝子を組み換えたり、一定の領域を置き換える方法はまだまだ研究途上と言っていい。そんな一つが2019年に Liu らが開発したプライム遺伝子編集で、Cas9 に逆転写酵素を融合させ、標的をカットしたあと逆転写酵素で新しいDNA配列を合成させて、希望の配列に置き換える方法を指す。すでにヒト血液幹細胞を用いた遺伝子編集にも使われるなど期待は大きいが、新しく合成した DNA 鎖と元の配列に当然起こるミスマッチ修復メカニズムが働いてしまって、この遺伝子編集効率を大きく低下させるという問題があった。
今日紹介する韓国国立ソウル医科大学からの論文は、昨年ノーベル化学賞を受賞した Baker さんらが開発した RFdiffusion を用いてミスマッチ修復酵素複合体をブロックできるペプチドを設計し、それをプライム編集に組み込んで編集効率を8倍近く高められることを示した研究で、8月5日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「AI-generated MLH1 small binder improves prime editing efficiency(AI により設計した MLH1 結合ペプチドはプライム編集効率を高める)」だ。
プライム編集はこれまでも様々な改良が加えられ、特にミスマッチ修復システムに関わる酵素の機能抑制酵素を組み込んだ方法などが開発されたり、現在までに7バージョンの編集システムが開発されている。この研究では一歩進んで、ミスマッチ修復に必要な MLH1 と PMS2 の結合をブロックする全く新しいペプチドを、RFdiffusion を用いて設計し、プライム編集に組み込んでミスマッチ修復を抑えようと考えた。
Baker さんの方法が本当に多くの研究をインスパイアしているのがわかるが、MLH1 と PMS2 の結合サイトの4つのアミノ酸残基と相互作用できる80残基のペプチドを RFdiffusion を用いて設計し、最初にリストされたペプチドを、独自に開発した AlphaFold3 ベースの拮抗阻害ポテンシャル測定方法を用いてフィルターをかけ、最終的に得られた60種類のペプチドについてはプライム編集時に導入して効率を調べた。効率が3倍以上高まるペプチドが9種類得られており、比較的成功率は高いと言える。
この中から効率が6倍程度上昇した配列の一つをその後の研究に用いている。まずプライム編集システムと別々に細胞に導入してこれまでの方法と比較し、全ての細胞でこの方法が最も高い効率を示すことを確認している。また、この阻害効果が設計通り MLH1 への結合の結果である事も確認している。
その後、プライム編集コンストラクトにこのペプチドを組み込んだコンストラクトを作成、ヒトiPS細胞を含む様々な細胞でその効果を確認したあと、このコンストラクトを直接動物に注射して、肝臓細胞での igf2 遺伝子編集の効率について調べている。プラスミドを直接導入するという効率が高くないと思われる方法をなぜか用いているが、それでも1%近くの細胞で遺伝子の編集に成功している。
結果は以上で、今後デリバリーの方法を改善すれば、プライム編集が目指していた生体内での遺伝子配列の書き換えもぐっと近づいたと思う。また、RFdiffusion などで可能になる全く新しいペプチドデザインを細胞内の分子過程の制御に使うアイデアは、遺伝子編集にとどまらず、ポテンシャルは大きい。RFdiffusion をマスターして新しい利用法を開いたソウル医科大学のグループの今後に期待したい。
2025年8月11日
Aβ アミロイドに対する抗体治療が Tau 異常症が進行していない患者さんの治療に効果があることがわかり、多くの先進国で薬事承認されている。ただ治験段階から、抗体治療の副作用として脳出血が希に起こること、更には患者さんの多くで MRI 画像上で浮腫や微小出血を示す異常像が認められることがわかって、使用に黄色信号がともった。その後の症例検討で、ほとんどは無症状で注意深く経過を見れば良いということで、承認が取り消されることはなかった。
ARIA が生じる原因については諸説あるが、血管に沈着したアミロイドプラークに抗体やマクロファージが集積して血管炎症が起こるのが最も大きな理由と考えられている。今日紹介する米国サンフランシスコにある Denail Therapeutics からの論文は、トランスフェリン受容体に結合力を付与した抗体を用いると、脳血管関門を通りやすくなり、抗体が脳全体に拡散する結果、プラーク除去を低濃度の投与量で達成するだけでなく、ARIA も防げるという重要な研究で、8月7日号の Science に掲載された。タイトルは「Transferrin receptor–targeted anti-amyloid antibody enhances brain delivery and mitigates ARIA(トランスフェリン受容体結合性抗アミロイド抗体は脳内への供給が高まり ARIA を軽減する)」だ。
抗体は脳へ拡散する率が低いため、効果を上げるため様々な方法が試されてきたが、トランスフェリン受容体を介して毛細管血管内皮に組織へくみ上げさせる方法が最も研究されている。このグループは、トランスフェリン受容体結合サイトを Fc 部分に埋め込む独自の技術を開発して脳への移行を高めることに成功していた。脳移行は高まっても、トランスフェリン受容体を多く発現する網状赤血球に結合して Fc 部分を介してマクロファージをリクルートして除去してしまう結果、貧血になる副作用があった。そこで、FC 部分のリジンをアラニンに変化させる突然変異を誘導し、Fcγ 受容体への結合を低下させる抗体を作成し、片方の Fc 部分にトランスフェリン受容体結合部分の埋め込みと、Fc 受容体結合低下変異が共存する抗体が、貧血を誘導せず、通常の抗体より8倍脳内に移行する事を明らかにしている。
様々な試験管内でのテストを経た後、アミロイドを遺伝的に蓄積しやすくしたマウスに投与実験を行い、マウス脳への高い移行性を示すとともに、脳全体に拡散し、アミロイドプラークと結合し、高い効率で除去できることを明らかにしている。
次に同じ治療で ARIA が起こるかマウス脳の MRI 撮影で調べると、通常の抗体投与ではほとんどのマウスに ARIA が生じるが、今回作成した抗体ではほとんど ARIA は起こらない。また組織学的に調べると、通常の抗体では血管の炎症が起こり、漏出がおこるが、これを新しい抗体は防ぐことができる。
以上が結果で、これまで追求されてきたトランスフェリン受容体を用いて脳内拡散を高めるという戦略は、脳へ抗体を届けたいとき重要な方法になることがわかった。さらに、脳内への拡散を高めることで ARIA が防げるという事実は、ARIA がこれまで考えられていたように、血管内のアミロイドに抗体が結合しやすいためで、トランスフェリン受容体と結合させトランスポートさせることで、脳内抗体濃度を上げるだけでなく、血管内でのアミロイドとの結合による副作用を防げることを示した点で大きな進歩だと思う。
これを組み込むことでどれだけ価格が上がるのか知らないが、人間での効果を早急に調べる必要があると思う。
2025年8月10日
先日紹介したリチウムによるアルツハイマー病進行予防の研究からもわかるように、アミロイドプラークや Tau線維の蓄積が起こり、それが細胞死へと繋がるためには、様々な細胞内過程が関与しており、これらを正常化することもアルツハイマー病治療の重要な標的になる。その典型的例が昨年6月に紹介した細胞膜直下のセプシン6を中心とする細胞骨格が壊れると、細胞内のカルシウム濃度が維持できなくなり、神経異常が起こりアルツハイマー病の進行を推進するという論文だ(https://aasj.jp/news/watch/24592 )。 このように神経細胞の細胞骨格は軸索構造の維持からシナプスのリモデリング、そしてシグナル伝達系の維持といった様々活動を支えている。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、神経軸索の膜に結合したアクチンリングを基盤とした周期的細胞骨格のダイナミズムと機能について調べた神経形態学のプロの研究で、8月7日 Science に掲載された。タイトルは「The membrane skeleton is constitutively remodeled in neurons by calcium signaling(神経の細胞膜骨格はカルシウムシグナルによりコンスタントにリモデルされている)」だ。
この研究の対象になった周期的膜骨格は、細胞膜直下に存在するアクチンフィラメントとスペクトリンが規則的な間隔で並んでいる特殊な細胞骨格で、単純な構造的支持だけでなく、軸索の様々な活性に関わると考えられ、当然神経変性性疾患理解にも重要だが、まだまだ研究が必要だ。
そこでこの研究ではこの構造のダイナミックな変化をまず見ることから始めている。周期的膜骨格 (MPS) でアクチンとともに周期的に分布しているスペクトリンを蛍光ラベルして超高解像度顕微鏡で一定間隔で MPS を観察すると、スペクトリンの蛍光はゆっくりと消えたり現れたりを繰り返す。即ち定常状態でも MPS はゆっくりと壊され再構成されている。
MPS の変化を誘導しているシグナルについて、様々な阻害剤を用いて検討し、カルシウムをキレートしたときに変化が完全にストップし、また局所的にカルシウムが流出するケージに入ったカルシウムを用いて局所のカルシウムを高めると、変化が推進することがわかった。即ち、この変化を誘導しているのは細胞質内のカルシウムに依存していることがわかる。
そこで、カルシウム依存的に細胞骨格を調節している分子の阻害剤を用いて、この変化に直接関わる分子を探索すると、1)PKC、カルモデュリン、そしてカルパインの3種類のカルシウム依存性酵素が変化に関わること、2)PKC はアクチンリングに存在してアクチンの長さを安定化させている adducin に働き、スペクトリン・アクチンとの結合性を調節していること、2)カルパインはスペクトリンの分解を調節して MPS の変化に関わることを明らかにしている。実際には詳細な実験が行われているが、カルシウムによって活性が変化する酵素により、MPS の構造と動態が調節されているとまとめておく。
では、このようなダイナミズムを維持することの生物学的意義は何か?この問いについても、見ることに徹して探索を進め、蛍光LDL の取り込みが MPS のダイナミズムがなくなると消失することを発見する。即ち、MPS が壊れたり再構築することが軸索膜でのエンドサイトーシスを促していることを明らかにしている。
結果は以上で、もちろん MPS ダイナミズムは他の細胞機能にも関わると思うが、構造をしっかりと見ることが可能になり、研究は進むと思う。もちろんアルツハイマー病でも何らかの変化が見られる可能性はある。このように、神経細胞内では様々な過程が同時進行し、また相互に絡み合っている。従って、これらをもう一度見直すことで神経変性疾患といえども制御する可能性が生まれると思う。
2025年8月9日
膵臓ガンや肺ガンではある時点でいわゆる激やせが始まる。この症状はガンが栄養分をとってしまうとか、食欲が低下するとか、抗ガン剤の副作用として単純に理解できるものではなく、全身が悪液質として捉えられている状態に移行するためであることがわかっている。実際、悪液質を抑えることができれば、ガンが大きくなっても正常の活動を保つことができ、何よりも延命効果がある。
これまでの研究で、脂肪減少に関わる自然炎症サイトカイン、食欲抑制にかかわる GDF15 、そして筋肉減少に関わるアクチビン経路などが悪液質の分子機構として特定され、主に抗体薬が開発されている。
これに対し、今日紹介するイスラエルワイズマン研究所と米国MDアンダーソンガン研究所からの論文は、右頸部迷走神経をブロックするだけで悪液質を改善できることをマウスモデルで示し、人にトランスレートできれば安全で安上がりな悪液質治療に発展する可能性を秘めた研究で、8月7日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Vagal blockade of the brain-liver axis deters cancer-associated cachexia(脳・肝臓軸を形成する迷走神経のブロックによりガンの悪液質を治療できる)」だ。
このグループは一貫して悪液質の研究をマウスモデルを用いて研究しており、マクロファージ浸潤に関わるケモカインが欠損したマウスではガンを移植しても悪液質が生じないことを報告していた。この研究はその続きで、CCL2 が迷走神経に働いて迷走神経興奮を誘導できることから、悪液質が迷走神経の過興奮により起こっているのではないかという、これまでとは全くことなる着想を得ている。
まず悪液質を誘導するガンを移植すすると横隔膜下迷走神経が持続的に小さな興奮を繰り返すことを発見する。そして以前の研究で明らかにしたように、悪液質発生を CCL2 シグナルブロックにより抑制できることを確認し、CCL2ブロックの効果を迷走神経ブロックで再現できるか調べている。
結果は予想通りで、右頸部迷走神経を切断すると、ガンは大きくなっても体重減少、筋肉減少を抑制し、生存期間を著しく延長することがわかった。さらに、マウスの気分が行動上からも改善していることがわかり、よく動くし、他の個体とも交流を普通に行い食欲も落ちない。即ち、悪液質に伴う脳症状も大きく改善することが明らかになった。そして、抗ガン剤による治療にも耐性が高まり、結果として抗ガン剤治療による生存期間を延長させることができる。
この原因を調べると、悪液質発生による肝臓代謝のマスター転写因子の発現低下を迷走神経ブロックにより正常化することができ、その結果肝臓の代謝が元に戻ることが迷走神経ブロックのメカニズムであることがわかった。
この実験系では迷走神経を完全に切断しても大きな副作用は出ていないが、実際の臨床にトランスレートするためには他のブロック方法が必要になる。そこで痛みを抑えるために用いられる、低周波・交流刺激を一日一回30分行うブロック法をガンを移植したマウスに使うと、迷走神経切除に匹敵する悪液質抑制効果が得られることを明らかにしている。
最後に、さらに臨床応用を容易にするため、皮膚の上から迷走神経の低周波・交流刺激を行い、迷走神経の直接刺激と同じレベルの効果が得られること、その結果、行動も活動的になり化学療法の耐性が上がり生存期間を延ばせることを明らかにしている。
以上メカニズムをまとめると、ガンが誘導する自然炎症の結果 CCL2 ケモカインの濃度が上昇し、脳では迷走神経の興奮状態が誘導される。この興奮は肝臓へ分布する遠位迷走神経からアセチルコリンを介して幹細胞に伝わり、HNF4 の転写を抑制して肝臓の代謝を抑え、悪液質の引き金を引く。同時に脳内での CCL2 によるマクロファージを中心とした炎症が、食欲を抑制して悪液質を悪化させる。この悪性サイクルを迷走神経ブロックは正常化して、悪液質を防止することになる。
以上が結果で、この効果が人間でも確認できれば、悪液質の切り札として、ガン患者さんの治療効果だけでなく、ウェルビーイングにも大きな効果が期待できる。
2025年8月8日
リチウムと聞くと、最近ではもっぱら電池の話題になりがちだが、リチウム電池が普及する以前から、リチウムは双極性障害(躁うつ病)の治療薬として用いられてきた。これは、オーストラリアの精神科医ジョン・ケードが行った動物実験中の偶然の発見に端を発し(Cade JFJ. Med J Aust . 1949;2:349–52)、1970年に FDA の承認を受けて以来、今なお気分安定薬のゴールドスタンダードとして使われている。
本日紹介するハーバード大学からの論文は、このリチウムがアルツハイマー病 (AD) にも有効かもしれないことを示唆した衝撃的な研究であり、8月6日に Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease(リチウム欠乏とアルツハイマー病の発症)」である。
これまでにも、デンマークの疫学研究で飲料水中のリチウム濃度が高い地域ほど認知症の発症率が低いことが報告されていた。また、金属イオンと脳機能に関する研究も多数存在する。そこで本研究では、AD と脳内金属濃度の関連を探索し、MCI(軽度認知障害)および AD脳でリチウム濃度が著しく低下していることを明らかにした。
さらに、アミロイドプラークを組織学的に解析したところ、プラーク内部に周囲の約3倍のリチウムが濃縮されていることが判明。つまり、プラークの形成過程でリチウムが“トラップ”され、細胞内のリチウムが枯渇してしまう可能性が示された。
この仮説を検証するため、アミロイドβ (Aβ) とタウ (Tau) が同時に蓄積する 3xTgマウスにリチウム欠乏食を与えた実験が行われた。その結果、通常食と比較して Aβプラークやタウの沈着が顕著に増加し、行動試験でも認知機能の低下が早期に進行した。
ここで重要なのは、リチウムがプラークやタウの“材料”であるわけではないという点である。むしろ、リチウムの欠乏が神経細胞の恒常性を破綻させ、結果として病的タンパク質の蓄積を促進していると考えられる。
そこで、同じ 3xTgマウスを用いて single nucleus RNA sequencing を行ったところ、ほとんどすべての細胞種で大きな転写変化が確認された。たとえば、神経細胞ではシナプス形成や機能に関わる遺伝子が強く抑制され、オリゴデンドロサイトではミエリン形成遺伝子が低下していた。
さらに、ミクログリアにおいては、自然炎症を促進するサイトカインの発現が上昇する一方で、Aβプラークの貪食能が著しく低下しており、これが病的タンパク質の蓄積に拍車をかけていることが示唆された。
このような細胞機能の破綻の背景として、GSK3β (glycogen synthase kinase-3β) の活性化が関与していた。リチウムは GSK3β を阻害することで Wnt/β-catenin シグナルを活性化し、神経保護に働くとされるが、生理的濃度ではこの作用が不十分に見える。しかしリチウム欠乏マウスでは、βカテニンの核移行が抑制され、GSK3β 活性が上昇していた。また、リチウム欠乏マウス由来のミクログリアに GSK3β 阻害剤を加えると、貪食能が回復した。
以上の結果から、リチウム欠乏により GSK3β が過剰に活性化し、それに伴って細胞機能異常と病理進行が引き起こされるというシナリオが明確に描かれている。
このように、リチウムの補充は有効な治療戦略となり得るが、従来のリチウム塩(炭酸リチウムなど)では AD 治療に失敗してきた。著者らはその原因が、投与されたリチウムがプラークに取り込まれてしまうために脳細胞に届かないことにあると考えた。そこで、プラークに取り込まれにくいリチウム塩をスクリーニングし、リチウムオロテート (lithium orotate) が最も取り込まれにくいことを発見した。
その上で、Aβプラークとタウ線維がすでに蓄積した段階からリチウムオロテートを投与したところ、プラーク数とタウ沈着細胞数の有意な減少、そして認知機能の回復が見られたという。
この研究が示す通り、AD の発症後でもリチウムによって病態を可逆的に改善できる可能性があるというのは、非常に衝撃的である。ただし、使用されたのはサプリメントとして市販されているリチウムオロテートではなく、精密に検討された製剤であるため、今すぐサプリを購入しても意味はない。今後、リチウムオロテートを用いた臨床試験が迅速に開始されることを期待したい。
2025年8月7日
実験の多くは結果を予想して進める。ただ一つの論文が仕上がるまで、だんだん予想が当たる確率は増えてくるのが普通で、予想が裏切られたまま論文としてまとめるのは難しい。
これに対して今日紹介するカナダ・マクマスター大学からの論文は、予想を裏切る結果を粘ってよくまとめたと感じられるという点では面白い論文なので敢えて紹介することにした。タイトルは「ACLY inhibition promotes tumour immunity and suppresses liver cancer(ACLY 阻害はガン免疫を促進し肝臓ガンを抑える)」で、7月30日 Nature にオンライン掲載された。
この研究はクエン酸を Acethyl-CoA に変換する酵素 ACLY が肝臓ガンで上昇しているというこれまでの結果を基に、ACLY のガンの治療標的としての可能性を調べることを目的としている。そのために、ニトロソウレアによる変異誘導に高脂肪食を組み合わせたマウス肝臓ガンモデルを作成し、人の肝臓ガンにかなり近いことを確認したあと、このモデル実験系で ACLY を肝臓特異的にノックアウト、肝がん発生と ACLY の関係を調べている。
結果は予想通りで、完全ではないが ACLYノックアウトしたマウスではガンの増殖が抑制される(もちろんここで予想が外れたら研究は進まない)。
そこで、遺伝的ノックアウトの代わりに ACLY 阻害剤を、脂肪合成を抑制するとして知られる多くの化合物を調べ、SLC27A2 酵素により CoA チオエステルに変換されああと ACLY を競合的に阻害する化合物 EVT0185 を特定する。この転換は肝臓や肝臓ガンだけで起こるので、ACLY のような重要酵素の阻害が他の細胞の副作用なしに可能になる。
しかし、ACLYは TCA サイクルから出てくるクエン酸を Acetyl-CoA とオキザロ酢酸に変換し、TCAサイクルを脂肪合成につなぐ重要な経路で、すぐに他の経路で脂肪合成が始まると予想されるが、このときは幸いにも予想が外れ、肝臓ガンもモデル実験系でこの薬剤を経口投与すると、ガンの増殖を抑えることができた。
EVT0185 の ACLY との結合はタンパク質構造学的解析から ACLY の特異的な阻害剤と予想できるが、効果が本当に ACLY 阻害だけで発生しているのか調べるため、ACLY ノックアウトマウスで ETV0185 投与による肝臓細胞の脂肪合成を調べると、ACLY がノックアウトされて代償経路が発達した肝臓の脂肪合成も抑制できることがわかった。即ち、予想が外れ ETV0185 は他の脂肪合成経路も抑制できることがわかった。ただこれも予想が外れて幸いで、この結果代償性経路が発生しても、肝ガン特異的薬剤として利用できる可能性がある。事実、投与実験では肝臓ガンの増殖が抑えられる。
ではこの効果は予想したとおり、ガン細胞の脂肪合成を締め上げてガンを殺すからなのか?遺伝子発現などから効果メカニズムを探索した結果、予想は大外れで、ガン細胞自体の ACLY を阻害しているにもかかわらず、このガン細胞を免疫不全マウスに移植すると、ETV0185 のガン抑制効果が全く消失する。即ち、ガン増殖自体ではなく、ガンが免疫細胞を呼び込むメカニズムにこの薬剤が効いて、免疫を介してガンを抑制していることになる。
ガン免疫と言うと当然キラー細胞で、キラー細胞が誘導しにくいことが肝臓ガンの免疫治療が難しい原因になる。これまでの結果は、ともかくガンの脂肪代謝を変化させると、ガン免疫を誘導しやすくなることを示唆している。ただここでも予想が外れて、ノックアウトマウスで発生した肝ガン組織を詳しく調べると、ガン組織にはB細胞が主に浸潤している。そこで、CD20抗体でB細胞を除去すると、EVT0185ノガン抑制効果が消失する。
結果は以上で、期待通り脂肪合成経路を阻害して肝臓ガンを抑制する化合物を特定したが、そのメカニズムは全て予想に反した結果で、なぜB細胞浸潤が誘導されるのか、なぜB細胞が肝ガンに効くのかなどはわからずじまいで終わっている不思議な論文だ。このように予想に反する結果を論文にまとめ上げる力も研究者には要求される。ただ、ここまで予想が外れた化合物を、ガンに効くからと言って使うかどうかは難しい問題だ。
2025年8月6日
脳死をヒトの死と認めたとき、では脳死の方を実験目的で使えるかという課題が、生きた人間の身体を用いて異種移植への反応を知りたい医学側の要求として出てくる。儒教の影響の強い日本では問題提起もできないと思うが、実際にこのような実験は行われており、このブログでは、2024年 Nature Medicine に報告されたニューヨーク大学からの遺伝子改変ブタ心臓の脳死体への移植実験を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/24508)。 調べてみるとこの大学ではすでに4例の脳死体への移植実験が行われており、他にも5例ぐらい同じような研究目的の脳死体への移植が行われているようだ。
今日紹介する中国西安にある第4軍医学大学は、中国で脳死体への異種臓器移植研究を推進している施設でこれまでに Nature 論文をいくつか報告しているが、今回は将来異種移植を受けた患者さんモニターのためのヒントを得るべく、移植後定期的に末梢血や肝臓サンプルの検査を行って、起こりうる自然免疫から獲得免疫までの経緯を調べている。タイトルは「Immune cell landscape in a human decedent receiving a pig liver xenograft(ブタ異種移植を受けた脳死体の免疫ランドスケープ)」で、7月30日Nature Medicineに掲載された。
この研究は今年の5月 Nature に中国の遺伝子改変ブタとして報告されており、6種類の遺伝子がヒト化されている。また、おそらく倫理的な取り決めで移植後10日以降は実験を行わないことになっている。脳死体と言え、実際の臨床応用を考え、ステロイドホルモン、抗補体、抗TNF、抗胸腺細胞抗体、抗CD20,そしてマイトマイシンとFK506という徹底的な拒絶反応予防策を移植前から進めている。そしてブタ肝臓を移植後、毎日採取された末梢血、そして2日目と10日目に採取された肝臓サンプルについて、single cell RNA sequencing や組織上での遺伝子発現を調べる方法で、ホストの肝臓への反応を調べている。
これほど様々な抑制処理をしても、好中球、T細胞、単球が移植後の末梢血に現れてくる。遺伝子発現に基づいて、それぞれの細胞集団をさらに細かく分析し、移植により最も活性化される変化を探索している。詳細にわたりわかりにくいが、2つの変化を異種移植による最も重要な変化として指摘している。
一つが初期に単球集団に見られる thrombospondin-1 の発現で、この集団は肝臓にも浸潤し、実際肝臓では Thrombospondin-1 とそれに反応する血小板の CD36 が同じ場所で染色できる。以上のことから。移植初期に見られる血小板凝集は、おそらく thrombospondin-1 陽性単球が組織に浸潤して CD36 を刺激して起こると考えられ、対応が可能になる。
移植初期に様々な自然炎症反応を検出できるが、後期に起こる獲得免疫反応も、T細胞に対する抗体を用いる処置をしているにも関わらず起こってくる。そして、これらT細胞は末梢血や移植肝臓内でも、抗原刺激を受けていた疲弊型タイプであることがわかる。従って、遺伝子改変ブタに対しても、結局強いT細胞免疫反応が起こっていることがわかる。移植後3-5日目には C1QC や VSIG4 といった自然免疫に関わる単球が増える、それらはT細胞のチェックポイント分子 PD-1 を発現しているので、このような単球による異種移植抗原の提示が行われている可能性が高い。
他にもいろいろあると思うが、この2つのポイントに対する処置方法が次のステップへの重要な課題となることがわかる。
いろいろ倫理問題はあるのかもしれないが、異種移植はまだまだ難しい課題が多いことがよくわかる貴重な論文だった。
2025年8月5日
多くの動物ドキュメントでは子育て中の母の行動が最もド感動的なドラマになる。そして我々もそのドラマに、崇高な愛をかぶせてみてしまう。もちろん多くの動物行動学者も同じように崇高なものを感じているのだろうと思うが、脳のレベルにまで落ちてくると、感動の行動も神経領域の活動の有無で終わってしまう。
今日紹介する米国国立衛生学研究所からの論文は、授乳期の母親の子育てへの指向を、それを抑制する食欲中枢から見直した研究で、母の愛情をを拮抗する回路バランスに帰してしまうと言う寂しさはあるが、面白い研究で、7月30日の Nature にオンライン出版された。タイトルは「A hypothalamic circuit that modulates feeding and parenting behaviours(摂食行動と子育て行動を調節する視床下部回路)」だ。
これまでも視床下部に存在する摂食中枢や、あるいは子育て中枢についての研究は読んできたが、この研究の特徴は、食欲からこ子育て行動を見直そうと、まず授乳期に母マウスに見られる食欲増進から調べ始めているのがユニークだ。驚くなかれ、マウスでは授乳中に摂食量が4倍近くに上昇するようだ。確かに、時には10匹を超える子供に授乳させるためには食べることが重要だ。そこで、愛より先に、まず授乳が始まると急速に高まる食欲を調節する細胞について、授乳期と処女マウスを比較する実験で、視床下部弓状核 (ARC) にある最も食欲に関わることが知られている agouti related protein (Agrp) を発現する神経を細胞が食欲増進に関わることを明らかにしている (ARCagrp)
しかし、食べ物がなくなった場合子育てはどうなるのか?食べることと子育てが対立するような実験系を作り、処女マウスと授乳マウスを行動学的に調べている。食べ物の心配が無い場合、どちらも子育てと食べることを両立させる。しかし、食べ物がなくなると、処女マウスはすぐに子育てをやめ、場合によっては子供を傷害する。ところが、授乳期のマウスでは食べ物にありつけない場合もまず子育てを優先し、実際の摂食量が減る。マウスの場合、空腹がより高まると、子育てへの時間は減ってくる。即ち、食欲と子育ては実際には反発し合っている。
この行動の神経背景には、食欲に関わる ARCagrp と子育て神経活動に関わる細胞の関係があるはずで、次に子育てに関わると知られている内側視索前野 (MPOA) へ ARCagrp は神経回路を形成し、ARCagrp 刺激は子育て活動を抑制することを明らかにする。
子育て時に興奮する神経は複雑であることがわかっているので、子育て時に興奮した神経をマークし操作する TRAP と呼ばれる方法を用いて調べ、ARCagrp と回路を形成しているのが bombesin 受容体を発現している神経で (MPOAbr) 、この刺激を抑制すると、食欲への反応性が高まるという関係にあることを明らかにする。即ち、子育てでは MPOAbr が活動し食欲と拮抗することで、子育て優先へと行動を調節しているのがわかる。また、子育て行動を示さない処女マウスの MPOAbr を刺激すると、食べ物がなくなったときに示す子供に対する攻撃行動が抑えられることも示している。
最後に、神経回路の特性について光遺伝学的に詳細に調べ、飢餓状態で子育て行動を抑える ARCagrp から MPOAbr への抑制回路が基本で、まさに母体保護優先回路が基本であることがわかる。そして、両方の領域は授乳期のホルモン環境によりともに高まることが明らかになった。
ただ、子育て回路の方は愛情を感じさせるほど複雑な回路を形成しているため、今後母親の自己犠牲愛にまで進む感動の回路は見つかる可能性は十分ある。脳回路研究は残酷だが、面白い。
2025年8月4日
今日はハーバード大学 George Daley 研究室から8月1日 Cell にオンライン掲載された論文を紹介することにした。というのも、個人的にも付き合いの深かったこの論文の筆頭著者 George Daley が、なんと David Baker さんと組んで LLM を利用した研究を行っているのを知ったからだ。もちろん研究の世界で誰がどう組もうとなんの不思議はない。しかし、大御所と言っていい山中さんと同じ世代の Daley が LLM を使って論文を出しているのを見ると、生命科学分野での LLM の浸透を強く感じる。他にもエピジェネティックスの大御所 Richard Young も、分子の細胞局在を予測する LLM モデルについて論文を発表しており、このブログでも紹介した(https://aasj.jp/news/watch/26318 )。彼らは幹細胞研究を通して個人的交流を持った大御所の話で、他の分野でもおそらく大御所に LLM は浸透し始めているのだろう。
Daley は造血系研究の大御所で、リンパ球も含む血液系細胞操作には Notch 刺激が必須であることを示してきた。Notch はほとんどの組織で何らかの機能を持っているが、血液系でも様々な系列、様々な分化段階で重要な働きをしている。ただこの過程を試験管内に移すときの問題は、Notch 刺激を誘導できる可溶性の分子が開発ができていないことで、Notch を刺激するためには、そのリガンド DLL を細胞に発現させたり、あるいは固相に結合させる必要があった。この問題を最新のタンパクデザイン法を用いて克服し、可溶性の Notch 活性化剤を開発したのがこの研究で、論文のタイトルはズバリ「Design of soluble Notch agonists that drive T cell development and boost immunity(T細胞の発生と誘導し、免疫を増強する可溶性Notchアゴニスト)」だ。
この研究では、最近開発された生理的条件での特異的ペプチド間の共有結合を簡単に実現する SpyCatcher と呼ばれる方法を DLL の重合分子デザインに用いて、Notch の活性化を可能にする分子デザインを探索し、最終的に3つの DLL が結合した構造が、細胞表面上での Notch の重合、そして刺激されたあと Notch の細胞内ドメインの核移行を誘導することを示している。即ち、Notch アゴニスト活性のある完全可溶性の DLL デザイン重合体の開発に成功している。
これだけなら Baker さんの出番はないのだが、Baker さんの成果を取り入れようとする努力が随所に見られ、デザイン重合体の設計に当たっては、3次元構造を AlphaFold などを用いて示している。とはいえ、デザインリガンドと Notch との関係については、機能面以外の構造解析はほとんど行われていない。
一度可溶性アゴニストが開発できれば、あとは Daley のお手の物で、1)これまで細胞上に DLL を発現させて行われてきたプロT細胞からCD4、CD8T細胞への分化を、可溶性アゴニストで完全に再現できること、2)ヒト iPS細胞から造血能のある血管内皮を誘導したあと、デザインアゴニストを用いて CD8、CD4 分化細胞を誘導できること、3)T細胞機能誘導でT細胞の炎症性サイトカイン分泌を誘導できること、更には 4)マウスを免疫するとき同時にデザインアゴニストを投与すると、非投与群より何倍も多い抗原特異的T細胞を誘導できることを示している。
ただこれらの実験過程で、ヒト iPS細胞から CD4 や CD8 T細胞を誘導するとき、他の系では活性が低い2つの DLL が結合したデザインアゴニストの方が高い分化誘導能力を示すことに気づき、Notch シグナル誘導様式が SpyCatcher・DLL 構造で決まるほど単純ではないことを確認し、ここで Baker さんとの密接な関係での研究が進め、以前紹介したペプチドによる様々な形のスキャフォールドに DLL を5個結合させたアゴニストが、ほぼ全ての過程で高い活性を維持するアゴニストとして使えることを明らかにしている。
このように Baker さんの関与は最後の実験になってしまっているが、LLM をタンパクデザインに使うという方法の急速な浸透が感じられた論文だった。
お察しの通りコスタリカ最後の日も長い一日で、ようやく論文紹介もこちらの夜10時を越えた。また証拠写真として、コスタリカで有名なアカメアマガエルの写真を添付しておく。