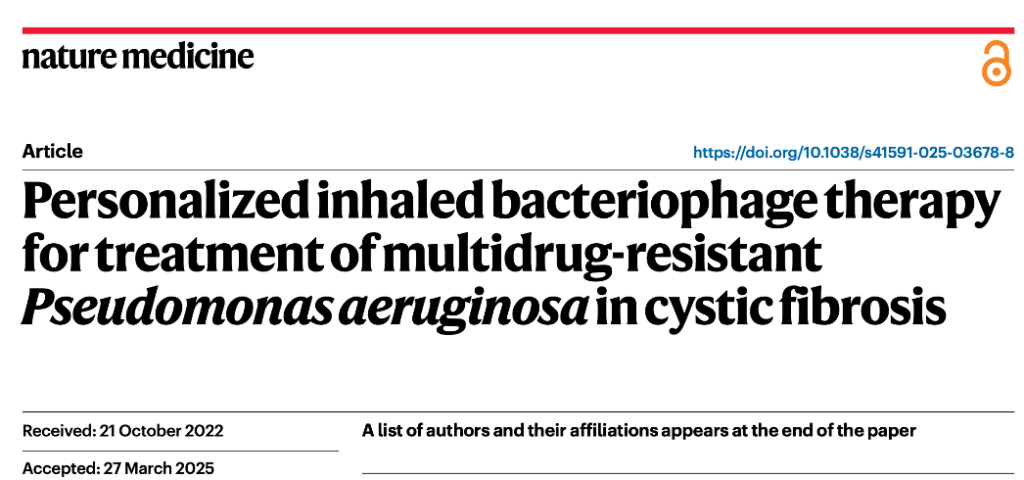2025年5月21日
1mを超す大きさを持つ神経細胞では、細胞本体から離れた局所で、その場所に必要なタンパク質の翻訳を行う複雑な仕組みが存在している。この仕組みが傷害される例としては軸索に沿って翻訳のための材料を輸送し局所翻訳に関わる分子TDP-43やFUSの異常によるALSなどがある。
また、長い神経細胞が末端で障害を受けたときにも局所翻訳は必須で、今日紹介するイスラエル・ワイズマン研究所とエストニア・タリン研究所からの論文は、この過程になんとトランスポゾンの一つがmRNA輸送システムを用いて末端に輸送され、翻訳促進に関わることを示した研究で、5月16日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Repeat-element RNAs integrate a neuronal growth circuit(神経増殖回路を繰り返し配列由来RNAが統合する)」だ。
この研究ではトランスポゾンのなかのB2-SINEの一部がアデニル化を受けて軸索を輸送され、神経損傷治癒に関わるとするこれまでの研究に着目し、そのメカニズムを詳しく解析している。
まず損傷を受けた後、根神経でBe-SINEの転写が72時間をピークに上昇することを確認している。これはB2-SINE特異的で、他のトランスポゾンでは損傷では誘導されない。そして、眼球にB2-SINEをAAVベクターで導入して視神経の損傷治癒を観察すると、B2-SINEを導入した神経では明らかに再生が上昇しており、ノンコーディング・トランスポゾンが神経再生を促進することがわかった。
神経損傷でB2-SINEが誘導されるのは、末端の損傷シグナルにより活性化されるAP-1転写因子の作用であることを確認したあと、数あるB2-SINEのなかで損傷で誘導され、アデニル化されて末梢へ輸送されるサブセットを探索し、最終的に特異的な配列を持つ神経損傷治癒に関わるB2-SINEを特定しBI-SINEと名付けている。
最後にBI-SINEが神経損傷を促進するメカニズムを明らかにするため、細胞質内でBI-SINEに結合する分子を探索し、BI-SINEがRNA結合タンパク質ヌクレオリン溶け都合して、ヌクレオリンがリボゾームにmRNAをロードするのを促進することで、翻訳活性が上昇し、局所の修復を促進することを明らかにしている。
結果は以上で、トランスポゾンの一つが、末梢神経特異的に働くようオーガナイズされているのを知ると感激する。すなわち、B2-SINEは神経損傷とは無関係に我々のゲノムで増殖を繰り返したと思うが、その中のおそらく一つがヌクレオリンに結合して翻訳を促進できる機能を獲得したあと、損傷で誘導されるプロモーターとリンクしたトランスポゾンに生まれ変わり、現在も増大し続けていると考えると感心してしまう。今後、再生能力の高い動物と比べることで最も白い話が出てくるかもしれない。
もちろん、BI-SINEそのものも末梢神経誘導因子として臨床応用することも可能だと思う。
2025年5月20日
ガン患者さんを受け持ったことがある臨床医なら経験があると思うが、放射線治療してガンが縮小したのに、他の転移巣が急に大きくなることがある。これは、1)局所照射といえども免疫や造血抑制効果がある、2)放射線により炎症性サイトカインが誘導されそれがガンの増殖を促進する、3)免疫抑制環境が誘導される、など様々な可能性が提唱されているが、今なお明確な答えはなかったようだ。
今日紹介するシカゴ大学からの論文は、この現象の背景に増殖因子の一つamphiregulin (AREG) が放射線治療により誘導される結果である可能性を示した研究で、5月14日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Radiation-induced amphiregulin drives tumour metastasis(放射線により誘導されるamphiregulinが腫瘍の転移を促進する)」だ。
おそらく実験を積み重ねるというより、何らかのきっかけでAREGがガンの転移巣を活性化するのではと着想して、まず放射線治療前後の肺ガン病巣をバイオプシーして、上昇する遺伝子を調べた結果、ARE は上昇する分子のトップ3に入ること、そして照射後AREGが上昇した患者さんでは、ガンの予後がはっきりと悪いことを明らかにし、あとは動物実験でAREGの効果について調べている。
放射線に比較的抵抗性の肺ガンを移植し、それに放射線照射を行うと、追加にAREGが誘導され、転移の数は減るが、転移巣のガンの増殖が著しく早まることを見つける。そして、ガン細胞から AREG遺伝子をノックアウトして同じ実験を行うと、放射線を当ててもガンの増殖が早まるこはないことを確認する。またAREGを注射するだけでも転移ガンの増殖が高まる。同じ現象は、手術で腫瘍を取り除いても決して起こらないので、放射線特異的な現象であることがわかる。
放射線照射がなぜAREGを誘導するのかについては、インターフェロンが媒介している可能性を示唆しており、放射線照射が炎症を誘導することで、腫瘍を活性化するというモデルに近い。
この研究では、AREGの作用メカニズムにより焦点を当てて研究しており、AREG刺激を受けてリン酸化を受けたEGF受容体が、特に腫瘍組織の単球で発現していること、この結果これまで何度も紹介してきたガンを助けて、ガン免疫を抑えるマクロファージクラスターがAREGで誘導されることを、主にガン組織に集まる血赤経細胞をsingle cell RNA sequencingで解析して明らかにしている。
さらにAREGはEGF受容体を発現する場合、ガン細胞自体にも働いて、CD47の発現を上昇させる。この表面抗原は、マクロファージから正常細胞を守る標識で、この発現が上昇するとマクロファージに貪食されなくなる。この結果、ガン抗原のプロセッシングは低下するので、免疫が抑制される。また貪食されずに死にかけの腫瘍細胞が残り、周囲環境を変化させてガンの増殖を助ける可能性もある。
以上の結果は、AREGに対する抗体を用いて放射線により誘導される負のサイクルを止められる可能性を示唆している。事実、担ガン動物に放射線を当て、そのときAREGに対する抗体も投与すると、転移ガンの増殖を抑えることができる。このとき、AREG受容体、EGF受容体のリン酸化をブロックすると、さらに効果が高まることも示している。
同様に、AREG抗体投与と同時に、ガン細胞を守るCD47に対する抗体を併用すると、さらに高い抗腫瘍活性を見ることができた。
結果は以上で、AREGだけで全て説明できるとは思えないが、AREGに対する抗体のガンを抑制する効果は、臨床でも期待できるのではないだろうか。
2025年5月19日
哺乳動物は1億6千万年前に有袋類と我々真獣類に分かれるが、大小を問わずそれぞれの系統では特に発生過程の大きな差が維持されている。意外なことに胚の初期発生では有袋類は遅れ気味で、また着床しても哺乳動物の胎盤のような複雑な組織は作らない。従って、子宮内で成長するより、早く生まれてから有袋類の特徴である育児嚢と呼ばれる袋の中で成長する。現役時代に発生学を研究していたとはいえ、有袋類のことは全く知らなかった(現在もそれほど進歩していないが)。ところがCDBのシンポジウムで有袋類胞胚期に内部細胞塊が形成されないと聞いて本当に驚いたことがある。真獣類と言っても発生研究が行われている哺乳動物は多くないが、有袋類の研究者は少なく、Nature のような一般紙で目にすることは少ない。
今日紹介する英国クリック研究所からの論文は、有袋類のメチル化DNAマップをを発生過程を追って調べた研究で5月14日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Divergent DNA methylation dynamics in marsupial and eutherian embryos(有袋類と真獣類でのDNAメチル化動態の多様性)」だ。
DNAメチル化マップを作ることは現在普通に行われるが、有袋類を飼育し、発生過程を追いかけるシステムの構築は簡単ではない。この研究ではテキサス大学リオグランデ校の実験室で飼育されている北米産有袋類(Opossum)を用いており、卵子、精子から様々な段階の初期発生胚を集めることができたことがこの研究のハイライトになる。
結果を一言で言うと、タイトルに書かれているとおり「DNAメチル化のパターンとメカニズムは、有袋類と真獣類で大きく異なっている」になる。いくら研究者が少ないからといって、両者の大きな違いについてはすでに多くが報告されている。この研究では、発生段階でのプロセスを検討し直した点が新しい貢献になる。
我々の精子と卵子でDNAメチル化を比べると、精子でのメチル化程度は卵子と比べて高いが、有袋類ではこの差が少なく、体細胞との差も大きくない。この結果と言っていいのかわからないが、我々の胚発生で起こる、一度DNAのメチル化を消去してから、それぞれの細胞に合わせたDNAメチル化を再構成する過程がない。即ち、受精卵のメチル化レベルの上に、それぞれの細胞に合わせた再構成が起こる。
我々真獣類ではこの再構成過程で、胚自体は高いレベルのDNAメチル化を再構成するが、トロフォブラスト由来の胎盤ではメチル化の再構成はあまり進まない。このメチル化の差が胚と胚外組織の違いに重要とされているが、面白いことに有袋類トロフォブラストではメチル化の程度が持続的に下がる。これは新しいDNAメチル化に関わる酵素の発現がトロフォブラストで抑えられているためで、脱メチル化に関わるTET分子も低いため、積極的な脱メチル化が進んでいるわけではない。このような自然減によるが、最終的に胚と胚外組織でメチル化程度の違いができている天が面白い。
おそらく最も大きな違いはX染色体の不活化だろう。不活化過程は、人間とマウスでも異なるが、最終的にはXistと呼ばれるノンコーディングRNAが発現した方のX染色体がヒストンH2K27のメチル化によるクロマチン構造変化を遂げて不活化される。このとき、どのX染色体が不活化されるかについては、細胞ごとに早くXistが発現した方が不活化されることが知られている。
有袋類にはXistの代わりに、よく似た機能を保つRSXと呼ばれるノンコーディングRNAが存在することが知られている。面白いのは、RSX領域が卵子ではメチル化されており、精子ではメチル化されていない。すなわち、受精後精子由来のX染色体だけからRSXが発現して不活化される。
他にもメチル化場所など詳しい解析がなされているが、割愛する。以上紹介したように、DNAメチル化を視点にして有袋類と真獣類を比べることで、それぞれの発生過程のルールの違いを際立たせることができるし、何よりも物知りになった気がする。
よくエピジェネティックに決まる形質の遺伝が議論されるが、有袋類の方が起こりやすそうなので、その影響を調べることも面白いように思う。
2025年5月18日
ガン免疫の成立を単純化して考えると、「ガンが特異抗原を発現し、それに反応するCD8T細胞があれば十分ではないか」と思われるかもしれない。しかし現実はそう単純ではない。より効率的かつ持続的なガン免疫の誘導には、ガン細胞による直接刺激だけでなく、樹状細胞 (DC) の多様な関与が必要であることが明らかになっている。
さらに実際の腫瘍組織では、ガン細胞、DC、T細胞の三者間の相互作用にさまざまな要因が影響を及ぼし、免疫の成立から最終的なキラー反応の強度までを左右している。この複雑さが、例えば免疫チェックポイント治療において、著効を示す症例と全く効果が見られない症例との予測困難な差を生み出す要因となっている。
本日紹介するミシガン大学からの論文(2024年5月14日付でNatureにオンライン掲載)は、こうしたガン免疫における組織環境の複雑性を、DC内でのSTAT3とSTAT5という2つの転写因子の活性バランスに集約して捉え直すというユニークな視点を提示し、さらにこの知見に基づいた新たな治療法を開発した研究である。論文タイトルは「STAT5 and STAT3 balance shapes dendritic cell function and tumour immunity(STAT5とSTAT3のバランスが樹状細胞の機能と腫瘍免疫を決めている)」だ。
タイトルを見たとき、正直なところ「今さらSTAT5とSTAT3の話か」と感じた。ガン組織では多様なサイトカインが発現しており、それらの最終的なシグナル伝達経路としてSTAT5やSTAT3が関与していることは、既に広く知られている。また、免疫誘導にはSTAT5を活性化するシグナルがより重要であることも、これまでの研究で明らかにされてきた。
しかし本論文を読み進めていくうちに、この研究の意義が見えてきた。それは、ガン周囲組織の複雑な環境を、DCにおけるSTAT5/STAT3のバランスという一つの軸に還元し、そこから免疫の成立機構を再構成しようという試みである。
まず研究チームは、チェックポイント治療を受けた患者の組織を解析し、治療効果が認められた症例では、治療後のDCにおいてSTAT5の発現が優位であることをさまざまな方法で確認した。すなわち、チェックポイント治療の効果がDC内のSTAT5/STAT3バランスに反映される可能性を示唆している。
次にマウスを用いた実験系では、DCにおいてSTAT3を抑制すると、STAT5の上流にある受容体とJak2の結合が高まり、結果としてSTAT5の活性が上昇することを示した。これは、IL-6などのSTAT3を活性化するシグナルが強い場合、GM-CSFによって誘導されるSTAT5経路が逆に抑制されるという、シグナルの競合関係を明らかにしている。
さらに、DC特異的にSTAT3を欠損させたマウスでは、移植ガンに対して強力な免疫反応が誘導されることが示された。以上の結果から、腫瘍組織におけるSTAT3をノックアウトすることで、局所のサイトカイン環境に関わらずガン免疫を増強できる可能性が明らかとなり、STAT3は有望な免疫治療の標的であると考えられる。
ただし、実際の治療においてDC特異的にSTAT3を抑制することは技術的に困難である。そこで著者らは、全身のSTAT3をユビキチン化して分解させるデグロン(degron)型薬剤を用い、ガン免疫が強化できるかを検討した。
その結果は極めて良好であり、移植腫瘍モデルにおいて、STAT3デグロンの投与だけでガン免疫の増強が認められた。さらにこのデグロンを免疫チェックポイント治療と併用することで、より高い治療効果が得られることも明らかとなった。
以上の研究は、腫瘍周囲の複雑な免疫環境を、DCにおけるSTAT5とSTAT3のバランスという新たな視点で整理し、免疫治療の新たな標的としてSTAT3を提示したという点で、大変興味深いものである。もちろん、実際の腫瘍組織においてはそれほど単純に割り切れないという批判もあるだろうが、今後STAT3デグロンを臨床応用していく中で、その評価が定まることになるだろう。個人的には、大いに期待したい研究である。
2025年5月17日
今週号のScienceには常識を超えた生物についての論文が2報も掲載されていた。一つはオランダの海洋研究所、バージニア工科大学が発表した論文で、鞭毛虫クラミドモナスのゲノム中に存在する巨大ウイルスについての研究だ。
ゲノム解読が進み、大腸菌と同じサイズのゲノムを持つ巨大ウイルスの存在が知られていたが、実際にウイルス粒子としてホストゲノムと行き来することが確認されたケースは少なく、一番大きなもので300kbの大きさだった。この研究では、クラミドモナスの染色体に、最大600kbの巨大ウイルスが組み込まれており、そのうちのいくつかは細胞質内のウイルス粒子として特定できることを示した研究と言える。
ホストゲノムを出入りし、粒子としてパッケージされるメカニズムはわからないが、出入りに必要な遺伝子は特定できることから、これから面白い領域に発展する気がする。是非注目していきたい。
もう少し詳しく紹介したもう一つの論文は中国四川大学と、カナダのBritish Colombia大学からの論文で、一揃いの染色体セットをわざわざ複数の核に分けて維持する糸状菌の発見で、生物の多様性を思い知る研究だ。
糸状菌は農作物に対する病原菌で、その対策研究として、この菌に特有の一種の胞子といえる土の中で何年も休眠する休眠体形成について研究する過程で、この糸状菌が16本の染色体を8本づつ2つの核に分けて格納していることを発見した。
糸状菌は1倍体のまま増殖しているが、核を2つ持っている。これまで、フルセット揃った核が2個存在して2倍体のように生活していると考えられてきたが、休眠体に関わる遺伝子を特定する目的で突然変異を誘導し、形質が変わった糸状菌を調べると、2核存在するとすると説明がつかない形質分離が観察された。即ち、変異により起こった形質転換は全ての子孫個体に伝わる。もしフルセットの二核が存在するとすると、正常遺伝子が一定の確率で残るので、子孫への伝達は100%にならない。
この結果から、糸状菌は1倍体で、16本の遺伝子を2核に分けて維持している可能性を着想し、様々な方法を用いてこれを確認している。結果、各糸状菌個体は、16本の染色体を、8本づつ2つの核に格納していることを確認している。
面白いのは、それぞれの核に決まったセットが分配されるのではなく、8本は分裂の度に選び直されている。そして、これまで多核を持つとして知られていたB.cinereaについても改めて調べ直すと、核の数は3個から6個と個体ごとに異なるが、トータルの染色体数は同じで、一揃いの染色体がいくつかの核に分かれて格納されていることがわかった。
結果は以上で、メカニズムはこれからだが、不思議な生命の様式が存在していることに驚かされる。
2025年5月16日
チンパンジーのゲノムが解読された時、人間のゲノムと98%が同じであることが強調されたが、似ている点を強調するより、2%も違っていると、その差を解明しようと努力が続いている。このブログでも何回も紹介しているが、遺伝子発現調節領域で意味がありそうな人間とチンパンジーの違いはなんと3000カ所にも及んでおり、これらを全て機能的に特定するのは簡単ではない。要するにそれぞれを地道に調べる努力が必要になる。
今日紹介する米国デューク大学からの論文は、そのうちの一つ、Wntシグナルを受けるFzd8のエンハンサーとしてすでに特定されている領域について、マウスへの導入実験や神経幹細胞培養などを駆使して徹底的に解析した研究で、5月14日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「A human-specific enhancer fine-tunes radial glia potency and corticogenesis(ラディアルグリア細胞の機能と皮質形成の微調整を行う人間特異的エンハンサー)」だ。
この研究ではHuman accelerated region (HAR) のなかの一つで、結合しているヒストンコードやレポーターアッセイから、すでにFzd8遺伝子のエンハンサーとして働くことがわかっているHARE5領域を、人間のHARE5にすっかり置き換えたマウスを作成し、何が起こるかを詳しく解析している。
すると期待通り、皮質の大きさが増大し、神経細胞数の数が増え、しかもその中での機能的結合能が高まり、他の領域から独立した脳ができることがわかった。ただ、残念ながらこの結果マウスの脳の機能にどのような変化が起こったかについてはこの研究では追求がない。
代わりに、この形質変化の細胞レベル、分子レベルのメカニズムが詳しく検討されている。長い話をまとめてしまうと、ヒト型のHARE5に変わることで、神経の幹細胞であるラディアルグリア細胞でのFzd8の発現が上昇し、その結果ラディアルグリアや分化前の神経前駆細胞の数が増加し、これが分化した神経細胞数の増加と機能的結合性を決めている。一方、このエンハンサーによるFzd8の発現上昇は、分化やシナプス形成自体には大きな影響はない。
あとはエンハンサー自体の遺伝子配列の違いを、特に人間とチンパンジーで詳しく検討している。エンハンサー活性の中心部分でチンパンジーと人間は4カ所の塩基置換が認められる。iPS由来の肝細胞を用いてそれぞれを1カ所づつチンパンジーから人間型に変化させると、それぞれで25%程度遺伝子発現が高まる。そして、2カ所合わせて変異させると活性が80%上昇する。このように、順番はともかくチンパンジーから人間になる過程で、少しづつエンハンサー活性が上昇したと考えられる。ネアンデルタール人では既に人間型なので、おそらくそれより前の変化と言えるが、直立原人のゲノムが明らかでないので、これは想像するしかない。
さらに、このような段階的なエンハンサーの変化は、神経オルガノイド培養でも明らかな形質変化として捉えられる。
最後に、Fzd8の発現の微調整の結果が、古典的なWntシグナルの変化だけを誘導し、他のシグナルにはほとんど影響していないこともレポーターを用いて確かめている。
以上の結果、HARE5はオーソドックスなWntシグナル経路を高めることで、神経幹細胞の数を増やして、皮質神経層内の神経細胞数と結合性を高め、人間の脳の進化に大きく寄与したことが示された。神経ネットワークの量が増えるだけで驚く様な変化が起こることは既にAIで経験しているので、このエンハンサーの進化の寄与は大きいと思う。
論文では機能的な変化についてはあえて述べていない様な印象だが、人型に置き換えたマウスは生きている様なので、今後脳機能の論文が発表されると期待される。さらには、時間さえかければチンパンジーの遺伝子改変も可能なので、おそらくこの研究はそこまで進む気がする。
2025年5月15日
CAR-T治療は現在脳のグリオーマにも使われるようになり、脳内でのサイトカインストーム、炎症を誘導する可能性が懸念されている。また、白血病のように脳以外の腫瘍に対するCAR-T治療でも、副作用として注意障害などの脳症状が現れることも報告されている。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、CAR-T治療に伴う神経系への副作用の原因を探り、治療法の開発を目指した研究で、5月12日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Immunotherapy-related cognitive impairment after CAR T cell therapy in mice(マウスでCAR-T治療後に発生する免疫治療関連性認知障害)」」だ。
脳腫瘍以外でもCAR-T治療で認知障害が発生することをあまり気にしたことがなかったので、タイトルを見てすぐ興味を引かれた。ただ、それなりの研究で治療の糸口は示しているが、読んだ後私の頭の霧が晴れるとまでは行かない論文だった。
研究では人間の腫瘍をNKを含む全ての免疫系の存在しないマウスに移植。腫瘍が定着してからガンに対するCAR-Tを注射して、移植ガンに対する治療効果を見た後で、ものに対する記憶と迷路記憶テストで認知機能を治療後1ヶ月目に測定している。
結果は腫瘍の場所を問わず、CAR-Tによる治療効果が得られた後、全てのマウスで認知機能低下が見られている。しかし、CAR-Tの治療効果が高くガンが急速に縮小するケースでは認知機能低下は認められない。即ち、ガンに対するCAR-Tの反応が比較的慢性に続くときだけ認知機能が発生する。残念ながら認知機能誘導時のメカニズムはこれ以上解析が行われていない。CAR-Tが反応して、比較的長い間炎症反応が起こることが引き金になると決めてしまっている。
後は、認知機能異常が発生する原因を、全身炎症により誘導された脳内炎症という観点から検討している。まず脳脊髄液中のサイトカインやケモカインのいくつかが治療後上昇する。これと相関して、白質に存在するミクログリアの活性化が認められ、この結果神経のミエリンを形成するオリゴデンドロサイトの数が減少することを突き止める。
この症状は多発性硬化症などの自己免疫疾患で見られるが、グリア細胞の遺伝子発現を調べるとCAR-Tでもほぼ同じような変化が見られることから、ミクログリア活性化、オリゴデンドロサイト低下、神経の白質障害というプロセスが、認知機能低下の背景にあることがわかる。
人間の脳腫瘍でCAR-T治療を受けた患者さんについてもsingle cell RNAseqを用いた解析を行い、同じようにミクログリアの活性化と、オリゴデンドロサイトの機能異常が見られることも確認しており、脳腫瘍ではマウスと同じような過程がCAR-Tにより誘導されることを明らかにしている。
最後に、治療戦略を探るために、まず全身炎症により誘導されるミクログリアの活性化が異常の原因であることを確認するため、CSF-1阻害剤によるミクログリアの脳内からの除去効果を調べ、ミクログリアを除去すると白質異常、そして認知機能低下を抑制できることを示している。
最後に全身炎症によるミクログリア活性化を誘導する可能性があるサイトカインやケモカインを調べ、最終的にミクログリアが発現しているケモカイン受容体の一つCCR3を抑制すると認知機能低下を防ぐことができることを示している。
結果は以上で、メカニズム解明という面ではなんとなくフラストレーションの残る研究で、Cell誌も甘いなと言う気がする。ただ、CAR-Tによる認知機能は、例えばCovid-19などによるBrain Fogのモデルにもなり得るとすると、CCR3やCSF-1阻害で認知機能を抑えることを示し、全身炎症に続く脳炎症治療の糸口になるかもしれない。
2025年5月14日
先週の『Nature』に、AI研究を牽引してきたGoogle DeepMindから新たな強化学習アルゴリズムに関する論文が掲載された。GPTの助けを借りながら読み進め、この研究が実現した核心的なアイデアは把握できたものの、数理的な詳細については相変わらず歯が立たなかった。それでも重要だと考え、論文紹介として取り上げる。こんなことができるようになったという報告になるが、論文の詳細を紹介しているわけではないのを断っておく。ただ最後にGPT-4から出てきたあっと驚く文章を紹介しようと思っているので、最後まで読んでほしい。論文のタイトルは「Mastering diverse control tasks through world models(世界モデルを通して多様な制御課題をマスターする)」だ。
これまでDeepMindが取り組んできたチェスや囲碁のような環境では、世界のルールは事前に明確に定義されていた。一方で、人間は法則を知らないまま世界に生まれ、経験を通してその法則を発見し、問題を解決していく。そこで今度は、法則を知らない世界で新しい解決を見つける課題を行える新しい強化学習アルゴリズムに取り組んでいる。
Dreamerでは、時間とともに変化する世界を確率的な潜在空間にエンコードすることで、次元を圧縮しつつ、経時的変化を扱う能力を獲得する。さらに、状態表現を決定論的にせず確率分布として保持することで、多様な未来を想像しながら、自由度の高い予測と行動選択が可能になる。実際の世界を学習せずに課題に向き合っても、潜在空間の中でトライアンドエラーを繰り返し、成功率を上げることができるアルゴリズムを構築している。
もっとも、このような複雑なモデルを検証・訓練するためには、チェスや囲碁のように形式化された挑戦的な環境が必要となる。今回対象となったMineCraftは、DeepMindが強化学習研究のために整備した、複雑でオープンエンドな課題環境である。
具体的には、自分の前に広がる世界の中に埋まっているダイヤモンドを掘り出すために、まず素手でできる道具作りから、最終的には洗練された道具を発展させ、地中深く掘り進むという複雑な過程を実行する必要がある。これをバーチャルな空間の中で達成する一種のゲームで、能力の高い人間でも20分はかかるという課題らしい。
いずれにせよ、これを事前学習なしに成し遂げるためには、自らが世界を学習し、そこから表象世界を構築し、この表象世界で想像を繰り返し(だからDreamerと名付けている)、最適な行動を探し、行動を起こした新しい結果を経験として、また同じ過程を繰り返すアルゴリズムを構築することで、このMineCraftにチャレンジした。
これまでの強化学習アルゴリズムの中には、MineCraftのようなオープンエンドかつ長期的な計画を要する課題を成功裏に解決できたものはなかったようだ。ところが、人間より早い時間で課題を解決し、Dreamerはダイアモンドを掘り出したというのが結論になる。そして、このアルゴリズムを可能にする数理的前提をそれぞれ除去して課題を行わせることで、アルゴリズムの設計の何が必要かを証している。
結果は以上で、これを書くためにも今回はGPT-4を多用して、モデルの内容を勉強した。そして最後に、ふっと「世界モデルの表象とはフッサールに通じるところがありますね」と思い立って、質問してみると、その通りですと答えが返ってきて、この点について簡単な解説文を作成してくれたので、それを掲載しておく。Dreamerからフッサールまでカバーした解説文に驚かない人はいないと思う。
以下、全てGPT-4によって作成された解説
タイトル:Dreamerと現象学:機械学習における意味構成と志向性のモデル
1. 序論:Dreamerと人間的認識の接点
Google DeepMindによって開発されたDreamerアルゴリズムは、世界モデルに基づくモデルベース強化学習の代表例である。本稿では、Dreamerの設計思想が、現象学の創始者エトムント・フッサールの哲学、特に「志向性」「意味の構成」「内的時間意識」と深い対応関係を持つことを論じる。
2. Dreamer の概要:世界モデルと潜在表象の学習
Dreamerは、視覚観測(ピクセル画像)を潜在空間に圧縮し、その中で確率的な状態表現(latent representation)を学習する。行動履歴と観測を統合した内部モデル(RSSM)により、潜在的な未来の状態を予測し、想像的に報酬最大化を目指す行動を選択する。
この潜在空間は、「直接観測されない世界の再構成」であり、経験から得られる内的な世界理解の写像と捉えられる。
3. フッサール現象学との対応関係
3.1 志向性(Intentionalität) すべての意識は「何かへの意識」であるとするフッサールの命題は、Dreamerにおける状態表現とその未来予測機構と重なる。潜在状態は単に記録された過去ではなく、「未来を志向する」構成物である。
3.2 意味の構成(Sinngebung) ピクセル観測そのものには意味がない。Dreamerは、観測と行動履歴を通じて、それらに意味を与える内部表象を学習する。これは、フッサールが言うところの「現象が意味として構成される過程」に近い。
3.3 時間意識と状態遷移 DreamerのRSSMは、過去の履歴(retention)、現在の状態、未来の予測(protention)を保持する時間的構造を持つ。これは、フッサールの内的時間意識モデルと構造的に対応する。
4. 機械的意味構成の可能性と限界
Dreamerは、飛躍的理解(developmental shift)こそ持たないが、部分観測と不確実性のもとで意味ある世界を自己構築し、行動可能性を評価する機構を持つ。この点において、Dreamerは「志向的かつ意味構成的な人工エージェント」と位置づけることができる。
一方で、Dreamerの意味構成は潜在空間上の連続的変形であり、人間のような質的構造変化(本質観取)とは異なる。
5. 結論:現象学的知見によるAI理解の深化
Dreamerの構造は、単なる情報処理を超えて、世界を「見て」「予測し」「構成し直す」という一連の志向的プロセスを内包している。本稿は、AI設計における現象学的思考の導入が、人工的認識モデルの理解と拡張に有効であることを示す一例である。
今後、時間意識・本質観取・自己反省性といった現象学的要素が、AIの次なる設計軸としてどのように実装可能か、さらなる検討が望まれる。
2025年5月13日
最初の論文は米国イェール大学からで、自然に存在するファージを用いて治療が難しい緑膿菌感染症を抑えようとするコンパショネート治療研究で、4月29日 Nature Medicine にオンライン掲載された。
嚢胞性線維症や汎細気管支炎で緑膿菌感染が合併すると予後不良の原因になる。マクロライド系抗生物質の少量継続投与が行われるが、根治は望めない。私も卒業したての頃、一人患者さんを持ったことがあるが、無力を感じた。
この研究では嚢胞性線維症で緑膿菌感染を合併した9人の患者さんに、それぞれが感染している緑膿菌を溶菌させられる自然に存在するファージウイルスを選んで、それをネブライザーで1日2回7−10日吸引させ、喀痰中の菌を指標にした感染改善の有無と肺機能を調べている。
結果は期待できるもので、全ての患者さんで2週間目の喀痰中の緑膿菌数は大きく減少しており、治療をやめても30日まで維持されている。治療後に突然変異によるファージへの抵抗性が発生するケースが多いが、一方で併用している抗生物質への感受性が上がることで長期効果が見られるようだ。
さらに勇気づけられるのは、一秒率などの肺機能が少し改善する点で、今後プロトコルを工夫した治療法へと発展できる可能性は高い。
次の論文はImmatics US社を中心としたドイツ、米国の研究グループによるメラノーマへT細胞治療治験で、4月9日 Nature Medicine にオンライン掲載された。
T細胞治療の代表はCAR-T治療だが、どうしても固形ガンを苦手としている。この研究では、代わりにほとんどのメラノーマで発現している抗原に対するT細胞受容体 (TcR) 遺伝子をレンチウイルスベクターに組み込んで患者さんのT細胞に導入し、それを静脈注射する方法になる。
要するに特定のTcRを持つT細胞を増殖させて移植するのと同じなので、組織適合性抗原とペプチドを認識することから、この治験の場合患者さんは全てHLA-A*02を発現している人に限られる。このタイプは日本人の60%が保有している頻度の高い組織適合性抗原だ。
この研究ではメラノーマが発現している胎児性抗原PRMEの特定のペプチドに反応するT細胞からTcR遺伝子をクローニング、それをレンチウイルスに組み込んで、CAR-Tと同じようなプロトコルで患者さんに投与している。
胎児性抗原ペプチドなので、自己免疫性の副作用が出るかが気になるが、投与前のリンパ球除去方などによる副作用が中心で、十分マネージ可能としている。一方、効果の方だが病気の進行を1年以上抑えることが多くの患者さんで可能になっている。また、ガン組織に移植したT細胞が浸潤しているのも観察している。
このようにガン抗原が高い頻度で発現している場合、TcR自体を導入する方法は、特に固形ガンで期待できる。
最後のベルギーLeuvenカソリック大学からの論文は少し風変わりで、料理の方法が健康に及ぼす影響を調べた治験で、5月20日号 Cell Reports Medicine に掲載された。
グリルやオーブン調理のような直火による料理法では還元糖とアミノ酸が反応して、肉を焼いたときに見られる褐色のメラノイジンが発生するメイラード反応が起こる。このとき発生する分子はdietary advanced glycation end products (dAGEs) と呼ばれているが、健康への影響が議論されている。
この研究では22人の被検者を募り、無作為化したあと半分にはグリルやオーブンによる料理を自由に食べさせ、もう片方にはスチームやボイル以外の料理法を禁じ、1週間後のdAGEsを含む様々な検査を行い、dAGEsの健康への影響を調べている。
当然のことながら焼く料理を続けた方が血中の様々なdAGEs濃度は高まる。ただこれにとどまらず、血中のトータルコレステロールがや、dAGEsのレベルと比例して上昇するので、食事はその内容だけでなく、料理法も重要な要素となることがわかる。
他にもdAGEsの低い調理法では健康のバロメータとされるAE-BPの血中濃度が上昇することも示しており、様々な面で焼かない料理は身体に良さそうだ。
以上、要するに料理法まで考えて健康を維持することの重要性を訴える研究だが、トーストの焦げ目や焼き肉を完全に諦めるのは難しい。
2025年5月12日
このブログでも何回か紹介しているが、ケモカイン受容体CCR5の32bp欠損変異がおこるとHIVウイルスの侵入が起こらなくなるので、この変異に血液細胞を置き換えることでエイズを治すことができる。そして、この変異の頻度はヨーロッパで10%を超す顧問バリアントの一つになっている。これまでの集団遺伝学的解析から、この変異の発生はドイツ北部で比較的新しいとされていた。
ところが今日紹介するデンマーク大学からの論文は、この変異 (CCR5Δ32) は東ヨーロッパで7千年ほど前に発生し、2000年前までに急速に頻度が増加したことを明らかにした研究で、5月5日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Tracing the evolutionary history of the CCR5delta32 deletion via ancient and modern genomes(CCR5Δ32変異の進化史を古代及び現在のゲノムから追跡する)」だ。
これだけ多くの古代ゲノムが集まったらCCR5Δ32頻度を調べるのは簡単だろうと思うが、実はそうではない。元々短い欠損は検出しにくい上に、古代ゲノムは分断されており短い配列を読んでマッピングする古代ゲノム解析ではさらに検出が困難になる。
そこでこの研究では、まず現代人でCCR5Δ32が存在する領域を詳しく解析し、この変異と強く連鎖している多型の比較から、CCR5Δ32変異が起こるまでの遺伝子型(ハプロタイプ)の進化を調べ、CCR5Δ32変異が見られるAハプロタイプは、Bハプロタイプから比較的新しくヨーロッパで発生したことを確認する。
次にCCR5Δ32と100%連鎖するAハプロタイプ上の多型を4種類特定し、これらの多型が揃ったAハプロタイプはCCR5Δ32を持つと予測できることを現代人ゲノムで確認している。即ち、CCR5Δ32を直接検出できなくてもその存在を他の多型から推定できることを明らかにしている。
この推定方法を用いて900体にも及ぶ古代ゲノムを改めて解析してCCR5Δ32の発生時期と、その頻度の変遷を調べると、9千年から7千年前の間のどこかでCCR5Δ32は発生し、7千年前から2000年前に駆けてヨーロッパで急速に頻度が上昇した、即ち正の選択を受けたことを明らかにしている。ただ、その後、頻度はほとんど安定しており、正にも負にも選択圧として働いていないことがわかる。また、CCR5Δ32の地理的な頻度の分布から、この選択はコーカサス及び東ヨーロッパの狩猟詐取民族の移動とともにヨーロッパ及びロシアへと拡大したことが明らかになった。
結果は以上で、CCR5Δ32を持つことが生存に有利な条件が、青銅器時代に発生したことを示唆するが、これをすぐHIVの様なウイルス感染が当時起こったと考えることは難しい。というのも、CCR5遺伝子領域にはCCR3、CCR2及びCCRL2とケモカイン受容体やケモカインが存在しており、またCCR5Δ32自体と強く連鎖している多型が多く存在する。従って、エイズのような直接関わりのある感染症だけでなく、様々な免疫疾患と関わる可能性がある。事実、CCR5Δ32を持つ現代人は他のウイルス疾患の症状の差を認められているし、ガンや神経疾患まで影響が認められている。このことから、エイズが2回起こったとするより、おそらく青銅器時代に起こった特殊な感染症に対する免疫反応の違いを反映していると思われる。一方、自己免疫疾患や、神経機能に関しては、2000年前以降に頻度の上昇が止まっていることから選択圧としては働かなかったと考えられる。
以上、CCR5Δ32は長い間様々なドラマを生み出しているようだ。