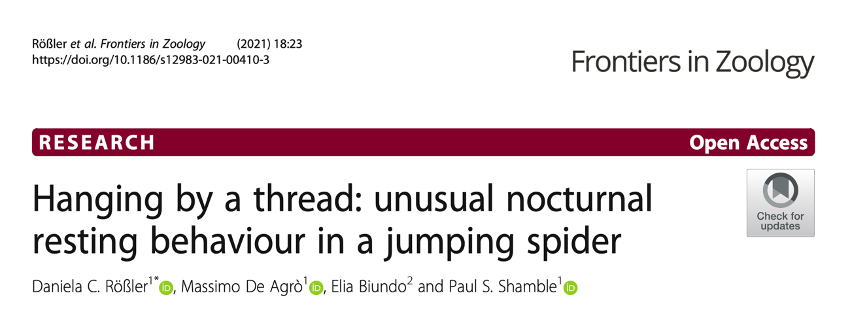2022年9月15日
先日は腸管内に複雑な樹状細胞(DC)系が存在し、その存在が免疫を高めるか抑えるかを決めていることを示す論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/20522 )。そして、慶応の本田さん達により明らかにされたように、DC やT細胞は細菌叢の中の SFB と呼ばれる特殊な細菌群により調節されている。これだけでも複雑なのだが、今日紹介するコロンビア大学からの論文は、この免疫系と栄養との関わりを追求した論文で、読む側の頭をさらに混乱させるが、栄養と免疫を考える上で面白い研究だ。タイトルは「Microbiota imbalance induced by dietary sugar disrupts immune-mediated protection from metabolic syndrome(食事の中の糖により誘導される細菌叢の不均衡がメタボリック症候群を防止する免疫系を消失させる)」で、8月29日 Cell にオンライン掲載された(論文の筆頭著者の Kawano さんは慶応の内分泌内科所属になっている)。
この研究は、最初合成された高脂肪食(HFD)による肥満を抑える免疫系を特定すべく計画されている。マウスに HFD を摂取させると、Th17細胞が低下、逆にTh1細胞が上昇する。これと同時に、Th17誘導に重要とされている細菌種 SFB も消失する。
面白いことに、Th17細胞の誘導を操作したマウスを用いて同じ実験を行うと、Th17 が欠損したマウスでは、HFD によりおこる肥満と代謝異常の程度が強い。また、メタボになりやすいTh17マウスもCD4T細胞を移植することでメタボを防ぐことが出来る。一方、HFD によるTh17 低下は、SFB を直接投与することでも防ぐことが出来る。以上のことから、HFD により起こる肥満は、栄養だけでなく、腸管内で SFB が減少し、Th17 が低下することで、メタボリック症候群防御機構が低下することも要因であることを明らかにする。
では、HFD の何が Th17 低下を招いているのか?追求していくと、驚くことに原因は HFD中の脂肪そのものではなく、なんとそこに加えられた砂糖が原因になっていることがわかった。すなわち、砂糖を投与することで、SFB が減り、Th17 が減る。
以上のことは、砂糖により SFB の増殖が変化することを示すが、SFB のみを移植された無菌マウスでは砂糖の影響が全くないことから、砂糖により他の細菌が増え、結果 SFB が Th17 誘導に関われなくなる可能性を示している。そして、最終的に Erysipelotrichiaceae と呼ばれるバクテリアが増殖して、SFB を粘膜上皮から引き剥がすことで、Th17誘導能がなくなることを示している。
最後に Th17 がメタボリック症候群を抑える仕組みが問題になる。勿論全身の自然炎症を抑える役割がある可能性も捨てられないが、この研究では上皮の脂肪輸送に関わる CD36 の発現を Th17 が抑制することも示し、全身の影響だけでなく、脂肪の体内への移行を抑えることで、Th17 が肥満防止に関わることを示している。
どんどん複雑になり、頭も混乱するが、これらの結果をもとに、メタボのない、バランスの取れた免疫系の維持方法について指針を出して欲しい。
2022年9月14日
チンパンジーゲノムが解読されたとき、我が国では人間とほとんど変わらないことが強調された。サル学でも、人間とサルの共通性を求める方向があるが、この方向性を私は猿の惑星型研究と呼んでいる。一方、徹底的にサルと人間の違いを突き詰める方向性も存在する。例えばネアンデルタール人ゲノム解読の Pääbo さんと同じ研究所の Thomasello さんのサル学がそれに当たる。小さな違いを際立たせることで人間を理解する方向で、私はキリスト教の自然観をとって Scala Natura 型と呼んでいる。
同じように、類人猿、旧人類、そしてホモサピエンスまでのゲノムを比較して、小さな違いを見いだし、その違いを機能的に際立たせる手法で研究を続けているのがライプチヒの Pääbo さんと、ドレスデンの Huttner チームで、おそらく最初は2015年に紹介した ARHGAP11B 遺伝子ではなかったかと思う(https://aasj.jp/news/watch/3151 )。最近では、同じコンビで細胞分裂マシナリーをネアンデルタール人と現代人で比べた論文も紹介した(https://aasj.jp/news/watch/20247 )。この中から浮かび上がるのは、小さな機能変化が積み重なった土台に、新しい脳機能が創発してくるといったシナリオだ。
今日紹介する Pääbo-Huttner コンビの研究もこの流れ上にあるが、これまでと比べるとこれでもかこれでもかと徹底的な実験が行われている。タイトルは「Human TKTL1 implies greater neurogenesis in frontal neocortex of modern humans than Neanderthals(人類のTKTL1遺伝子は、現生人類の前頭新皮質の神経細胞増殖がネアンデルタール人より多いことを示唆している)」で、9月9日号の Science に掲載された。
おそらくネアンデルタール人と現生人類のゲノムで異なっている部位の精細なリストが出来ているのだと思う。その中から、脳に発現している分子の中から、今回はネアンデルタール人と現生人類でアミノ酸一つだけが異なっている、脂肪代謝と糖代謝を結びつける分子 TKTL1 に今回は焦点を当てている。Huttner さんは、神経幹細胞の増殖を研究してきた第一人者なので、この分子が radial glia と呼ばれる幹細胞の中の特に bRG で強く発現していることも、この分子を選んだ理由だと思う。まあ、神経発生のプロが選んだ分子なので、膨大な実験が行われており、結果は箇条書きで紹介する。
現生人型 TKTL1(hTKTL1) と旧人類型 TKTL1(a TKTL1) をマウス前頭葉に導入すると、hTKTL1 を導入した時のみ、radial glia のうち bRG の数が増え、bRG を起点に多くの神経細胞が生産される。 フェレットを用いて同じ実験を行うと、同じように bRG が増殖、その結果、新皮質上層部の神経細胞の数が増え、脳回路の形態変化が起こる。 人間の脳オルガノイドを用いて aTKTL1 に置き換えると、bRG と神経の増殖が低下する。すなわち、hTKTL1 になることで、人間は皮質神経の数を増やすことに成功した。 hTKTL1 による bRG の増殖は、脂肪代謝経路での TKTL1 の働きに依存しており、hTKTL1 は従来型より多くのアセチル CoA を合成する機能を持っている。 実際には代謝について、阻害剤を含めた詳しい検討が行われており、これまでの論文の中でも執念が感じられる。以前紹介した ARHGAP11B も代謝に関わる酵素だったし、今年紹介した KIF の話も分裂に関わる話だった。おそらくまず大事なのは、ともかく脳細胞を増やすことで、制限の中で、すこしづつ効率のいい分子を集めていくことでこれが可能になったのだろう。勿論、この研究の積み重ねがそのまま創発につながるわけではないだろう。しかし、ARHGAP11B をマーモセットに導入する実験を行うHuttner さんだ。今後、ヒト型に変化した様々な動物の脳機能の研究が示されるのだと思う。その時、猿の惑星型か Scala Natura 型かもわかるかもしれない。
2022年9月13日
最近のピーナツアレルギー予防の臨床研究を見ると、腸内でどのタイプのT細胞反応を誘導するかが、アレルギー発症に重要であるかがわかる。すなわち、早くからピーナツ油を摂取させると、抑制性T細胞(Treg)を誘導することが出来、その後のアレルギーを防げる。ただ、Treg が誘導されるメカニズムについてはよくわかっていない。
昨年、Science Immunology に UC サンフランシスコから、腸管には Aire を発現する特殊な樹状細胞(DC)が存在することが発表された。Youtubeでも紹介したように、Aire は胸腺上皮に、自己抗原の動物園を形成し、トレランスを誘導するのに必須の分子だ (https://aasj.jp/news/watch/19920)。そんな分子が腸管の DC に発現しているとすると、ひょっとすると自己抗原に対する Treg の教育が行われているのではと言う可能性が浮上し、わざわざローマ神話の神 Janus という名前がつけられた。
あれから1年、9月7日、Nature に、Janus 細胞及び ILC3 が腸管内で Treg を誘導している指令細胞であることを示す論文が3編オンライン発表された。その中から、最も系がすっきりしたニューヨーク大学 Littman グループの論文を選んで紹介する。タイトルは「A RORγt + cell instructs gut microbiota-specific T reg cell differentiation(RORγt+ 細胞が腸内細菌特異的Treg細胞の分化を指令する)」だ。
実験系をすっきりさせるために、この研究ではヘリコバクターに対するT細胞受容体トランスジェニックマウス由来T細胞を用い、この細胞をヘリコバクターが感染したマウスに移植したとき、Treg、濾胞ヘルパーT細胞(Tfh)、及び炎症性 Th17 細胞が誘導される実験系を用いている。すなわち、T細胞側は完全に一つに絞って研究が出来る。
この実験を、CD11 陽性細胞の MHC II をノックアウトしたマウスで行うと、他のT細胞は正常に誘導されるのに、全く Treg は誘導されない。すなわち、クラスII MHC がないと Treg が誘導できないことがわかる。
異なる分子をノックアウトしたマウスで同じ実験を繰り返し、RORγ 陽性、クラスII MHC 陽性、CCR7ケモカイン陽性、avβ8 インテグリン陽性の DC だけがあれば、Treg が誘導されること、ほかのT細胞にはこの細胞は必要ないことを明らかにする。また、それぞれの分子は Treg 誘導に必須であることを明らかにしている。
後は様々な実験を行い、Aire 陽性の Janus 細胞が必要なのか、ILC3 であればいいのかを検討しているが明確な結論は出ていない。Janus 細胞は Aire 発現で定義されるので、今後この遺伝子を ILC3 でノックアウトする実験が必要になるだろう。従って、結論としては、腸管内での Treg 誘導には、RORγ 陽性の ILC3 が必要十分条件であり、この存在が Treg が出来るかどうかを決めると言えるだろう。
2022年9月12日
現在パーキンソン病(PD)を、手足や頭の震え、筋肉が固くなる、動作が緩慢になる、そして歩行がギクシャクしてバランスが崩れる、といった症状が、黒質のドーパミン産生神経が失われることで現れる病気と伝えている。ただドーパミン分泌低下で、これらの運動症状が現れる生理学的メカニズムは簡単でないが、視床下核(STN)が一つの鍵になっていることがわかっている。例えば PD の患者さんで STN に電極を挿入し、電極周囲の電気活動を拾うと、運動時の特徴的な活動の変化を拾うことが出来、この結果、STN の深部刺激法が開発されている。
ただこの方法は、両足が別々に動くのを制御しなければならない歩行の安定を支持するのはうまくいかない。そこで、歩行時の筋肉活動と、STN に挿入する深部刺激電極での活動記録を相関させ、深部学習させることにより、PD による異常をいち早く検出して歩行を助ける深部刺激開発のためのデータを集めたのがこの研究で、9月7日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Principles of gait encoding in the subthalamic nucleus of people with Parkinson’s disease(パーキンソン病患者さんの視床下核の歩行のエンコードの原理)」だ。
この研究は両側の STN に深部電極を挿入した PD 患者さんが歩行するときの電極周辺のフィールド電気活動を拾って、PD の歩行異常と相関する成分があるかを徹底的に調べている。調べているのは、局所の活動で、細胞の活動ではないので、回路を明らかにすると言うより、ともかく PD 歩行異常を特異的に反映する変化を特定することが目的だ。その結果、以下の過程を STN の活動として拾えることが明らかになった。
PD の障害は行動を起こすときに強く表れる。すなわち、本来無意識的・自動的な運動が、大脳皮質により邪魔されているように見える。この自動性を維持するのが足の筋肉からの固有感覚だが、固有感覚のフィードバックを反映する STN の活動を特定できる。 歩行の開始と終了を反映する STN の活動を特定できる。 両側の筋肉の協調作用を、時間的にも同期して反映する STN の活動を特定できる。 PD の患者さんは小刻みな歩行になるが、大きなステップに必要な筋肉の強い力をうまく協調させるプロセスを反映する STN の活動を特定し、PD での異常を明らかにすることが出来た。 足がすくむ症状に対応する STN の活動が特定できる。 この研究では、実際には β 波と呼ばれる波長の活動を中心に、歩行に必要な STN の活動と、PD での問題を、2本の電極による局所記録と相関させたところで終わっているが、このデータを学習させた AI を用いることで、患者さんの日常生活で、脚のすくみなどの様々な異常が発生するのを60−70%の精度で予測できるようになってきている。
今後、一本の電極で数カ所の検知と刺激が可能になれば、より精度の高い予測が出来るとともに、脳のプログラムに会わせた深部刺激で、異常の発生を抑えることが可能になるのではと期待できる論文だ。
これはローザンヌ大学からの論文だが、同じローザンヌの EPFL では、脊損の患者さんを AI で歩行可能にする方法も開発されている。ローザンヌは神経変性疾患治療のメッカになるかもしれない。
2022年9月11日
自律神経研究紹介の最後の仕上げは、ハーバード大学からの論文、消化管の感覚野マップ作成を目指した研究で、8月31日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「A brainstem map for visceral sensations(内臓感覚の脳幹マップ)」だ。
これまで2日にわたって、内臓感覚が、感染から食事の種類まで、実に様々な刺激を感知していることを見てきた。今日紹介する研究は、内臓感覚についての一種の集大成を目指した研究で、様々な種類や場所からの内臓刺激が延髄孤束核でどう表象されるかについて調べている。
読者の皆さんは、例えば体性感覚野が脳皮質上に、頭から足まで全て備えた、しかし、顔や手の領域が異常に大きなホムンクルスとして描かれているのを見たことがあると思う。この地図作りは、カナダのペンフィールドが転換手術の際に体性感覚野に電気刺激を与えて、どこに刺激を感じたかを丹念に聞き取るという大変な作業に始まっている。その後、体性感覚を刺激した時、どの領域が興奮するかについての研究も進み、このホムンクルス型感覚野は確認されている。
同じような感覚マップを、内臓の迷走神経を介する感覚について描こうとしたのがこの研究で、内臓局所に風船によるメカノ刺激、様々な化学刺激などを加え、その時に反応する延髄孤束核の神経細胞を、カルシウムセンサーの光をモニターする研究を重ねて地図を書いている。
まずストレッチによるメカノ刺激に対するマップを見てみると、ホムンクルスほどはっきりとはしないが、口腔・咽頭部位、胃、十二指腸・空腸がまとまって、上から下へと並んでいる。ただ、口腔と咽頭、あるいは十二指腸と空腸はひとまとまりの塊になっている。
反応する神経は、胃、十二指腸、咽頭の順で多く、迷走神経支配に限ると、口腔刺激に反応する細胞は少ない。これは、顔面神経など他の神経系が発達しているからだろう。
昨日の論文で示されたように、内臓刺激は甘み、うまみ、脂肪の全てに一つの細胞が反応することがある。実際、十二指腸に対応する神経で調べると42%のブドウ糖反応性の神経細胞が、ストレッチによるメカノ刺激にも反応する。すなわち、反応する臓器については比較的明確な階層性が存在しているが、対応する刺激については重なり合っている。
実際、それぞれの臓器から来ている迷走神経の端末と、感覚野の細胞の反応を調べると、感覚野の領域分けが、孤束核に投射してきた迷走神経端末の配置に対応している。
以上、迷走神経は孤束核に地図として表象することが出来、この表象は内臓の位置関係を反映している。一方、刺激については、例えば視覚野、聴覚野といった区別は全くなく、これは一つの神経が様々なインプットに反応することを反映している。
最後に、それぞれの臓器の感覚に対する反応が、狭い領域の孤束核に、臓器の配置に対応する領域を形成できる生理条件について検討し、迷走神経の端末から刺激を受けた抑制性ニューロン、例えば胃領域に存在する抑制性神経が、腸や喉頭領域に投射を伸ばして他の領域の反応を抑えることで、感覚野の局在性を高めていることを示している。
以上が結果で、内臓感覚マップを作るための苦労話も含めて、ゆっくりではあってもこの領域の進歩が感じられる論文だ。しかし、摂食異常など様々な内臓刺激に影響される病気の理解には欠かすことの出来ない過程だ。ただ、残念ながら延髄という場所柄から考えて、人間で正確なマップを描くことは、他の感覚と比べると簡単ではないだろう。それでも、この問題を乗り越えた研究が進むと期待する。
2022年9月10日
自律神経研究紹介2日目は、内臓で味を感じる回路の研究だ。甘みを感じる受容体を消失したマウスが、それでも人工甘味料ではなく砂糖に対する嗜好を示すという有名な研究が発表されて以来、腸で様々な栄養成分を感じるメカニズムの研究が続いている。例えば今1月17日、腸内で砂糖に反応する neuropod 細胞を特定した論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/18825 )。
今日紹介するコロンビア大学からの論文は、脂肪に対する嗜好が、味とは別に生まれる自律神経回路を詳細に解析した論文で、9月7日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Gut-Brain Circuits for Fat Preference(脂肪嗜好性の腸脳回路)」だ。
まずマウスに脂肪液と人工甘味料液を選べるようにして、どちらを選ぶかを調べると、最初は人工甘味料を選ぶことが多いのだが、1日たつと脂肪の方を選ぶようになり、この嗜好性は48時間まで上昇し続ける。
この脂肪を摂取したときに活動する脳を調べると、昨日炎症を感じる領域として紹介した延髄孤束核に強い反応が現れる。昨日紹介した TRAP という方法を用いて、脂肪に反応した神経細胞を除去すると、脂肪への嗜好性は消失する。また、腸と脳をつなぐ自律神経系である迷走神経を切断すると脂肪嗜好性は消える。従って、脂肪に対する腸の感覚は迷走神経を伝って、延髄孤束核に投射することがわかる。
以前にも紹介したように、甘みやアミノ酸も腸で感じることが知られているので、脂肪を感じる経路と同じか違うのかをまず孤束核の細胞の反応で調べると、甘みを感じる経路は、アミノ酸にも、脂肪にも反応する一方、脂肪だけに反応する経路が存在することを突き止める。すなわち、腸では全ての栄養成分に反応する栄養感覚と、脂肪だけに反応する脂肪感覚があり、孤束核の異なる細胞がそれぞれの回路に関わることになる。
あとは、それぞれの経路を使われている受容体や、神経伝達因子について調べ、
これまで知られていたように砂糖の刺激は SGLT1 を受容体として、コレストキニンを神経伝達因子として伝えられ、おそらく同じ細胞が脂肪に反応する GPR40/GPR120 を発現し、脂肪刺激を伝えること。 脂肪だけに反応する経路は、GPR40/GPR120 で脂肪が感知され、TRPA1 陽性迷走神経を介して延髄孤束核に信号が伝えられること。 が明らかになっている。 結果は以上で、脂肪だけに反応して、腸から脳へとシグナルを伝える自律神経系が、私たちが自然に脂肪を求める嗜好を支配しているという話だ。しかし、甘みやうまみに反応する経路は脂肪にも反応するのに、これとは別に脂肪に反応する経路が同じ程度に発達しているのは面白い。私たちの脳は要するに脂肪を求めるように出来ていることか。是非食生活とこの感覚との関係を調べてほしいものだ
2022年9月9日
最近 Nature に自律神経関係の面白い論文が3編相次いで発表されていたので、週末は、自律神経について勉強し直す意味でもこの3編の論文を紹介したい。
最初の論文はロックフェラー大学からで、病気になると誰もが共通に示す行動変化が起こるメカニズムについての研究で、9月7日 Nature にオンライン出版された。タイトルは「Brainstem ADCYAP1 + neurons control multiple aspects of sickness behaviour(脳幹の ADCYAP1 陽性神経細胞が病気にかかったときの様々な行動を支配する)」だ。
私の学生の頃読んだハンスセリエの Stress in Life のイントロダクションは、何十年もたった今も鮮明に覚えている。彼は医学部で病気を症状で分類する鑑別の講義を受けたとき、逆にほとんどの病気が熱や疲れなど共通の症状を持つことに興味を抱き、Just being sick という状態をテーマとして選び、ストレス学説を作り上げる。
このプロセスに副腎皮質ホルモンが深く関わるのだが、どうして just being sick といえる共通の症状が生まれる詳細なメカニズムについてはまだわかっていないことが多い。
今日紹介する論文では感染の代わりに LPS 注射を用い、注射により誘導される食欲減退、活動性の低下、そして深部体温の低下を直接支配する自律神経メカニズムを突き止めることを目的にしている。
LPS を注射して Fos 遺伝子の発現で反応細胞を調べると、200領域に反応が認められる。すなわち、LPS は脳神経細胞に直接強い興奮を誘導する。中でも、延髄にある内臓からの様々な情報を集めている孤束核と延髄最後野が注射後3時間たっても高い反応を維持していること、自律神経の重要な感覚中枢であることなどから、この領域に焦点を絞って研究している。
焦点が決まると、今は特定の神経を操作する方法が確立している。この研究では、それぞれの領域で刺激に反応した細胞(この場合 LPS に反応した)だけを選んで操作する TRAP と呼ばれる方法を用いて、孤束核、最後野の LPS に反応する細胞を刺激すると、LPS 注射と同じ効果を、特に孤束核刺激で見ることが出来る。逆に、この細胞の興奮を抑えてやると、LPS の効果は見られない。
次の実験では、LPS 刺激に反応した孤束核神経細胞を、single cell RNA sequencing で調べ、LPS で刺激を受ける細胞の特異的マーカーを探求し、最終的にアデニルシクラーゼ活性化ペプチド(ADCYAP1)を特異的マーカーとして使える可能性を突き止める。
後は、この遺伝子領域に Cre を導入し、この分子を発現する神経細胞の興奮を調節できるようにして、マウスの行動を調べると、孤束核の ADCYAP1 陽性神経細胞刺激によって食欲と活動性が低下することを確認している。
結果は以上で、just being sick という状態を、脳の活動に伝えるハブを決めた研究と言える。今後は、LPS 刺激がどのように感知されるのか、またこの領域の興奮が、脳全体にどう伝わるかを明らかにすることが必要になるだろう。
この過程にどの程度セリエのストレス経路が関わるかはわからないが、「具合が悪い」状態の理解は、ようやく具体的で面白い領域に発展しそうな気がする。
2022年9月8日
英国経験論の最後として、今、デビッドヒュームを読み直しているが、以前から感じていたように、それまでの哲学の収束点とも言うべき巨人だと思う。なかでも、統計学的現象を物理的因果性とは異なる因果性として理解していた最初の哲学者と言っていいのではないだろうか。
この統計学的因果性は、今や私たちの脳活動の解読研究には盛んに利用されているし、さらに深層学習アルゴリズムとして、人間活動のあらゆる面に進出している。このニューラルネット= AI が不思議な形で理解できるのがガンの診断だ。
現在様々な動物を使って臭いや味からガンを診断する試みが、特にメディアでは取り上げられるが、これはそれぞれの動物のニューラルネットを用いた AI と言っていい。一つの化学物質で話がすめば検査は簡単だが、もう少し複雑な組み合わせだと、検査に AI を用いる必要がある。ただ、化合物の組み合わせをいちいち調べる代わりに、臭いの入り口が複数ある動物のニューラルネットをそのまま用いてる方法は問題はない。ただ、病気を理解するという意味では、この時感知された化合物を知ることが重要だが、臭いの研究の人たちはそこまで行く気はなさそうだ。
今日紹介するオランダ・アムステルダム自由大学からの論文は、血小板に存在する RNA のパターンからガンの存在を診断するという試みで、タイトルが意表を突いていたので紹介することにした。そのタイトルは「Detection and localization of early- and late-stage cancers using platelet RNA(初期から後期のガンの存在と局在について血小板 RNA を用いて診断する)」で、9月1日 Cancer Cell に掲載された。
血小板に RNA が存在し、蛋白質を合成することで機能を維持することは知っていたが、ガン細胞とは何の関係もない血小板の RNA が、ガンの存在により変化させられるので、ガンの診断に使えるという研究だ。ただ、今日紹介する論文は、この前提での大規模研究で、2400人の様々なガン患者さんを用いて PSO (粒子群最適化)という、少し変わったアルゴリズムを用いた AI を訓練し、最終的に AUC で0.91レベルのガンの診断が可能になったという論文だ。
検出にステージごとの違いは大きくない。一方、全く症状がないヒトの方が診断精度が高くなる。というのも、炎症など様々な変化が合併すると、それ自体が検出感度を下げてしまう。その意味では、全く健康と思っている人たちのガンの診断に役立つ可能性がある。
また、少しアルゴリズムを変えると、肺がん、脳腫瘍などは8割近い確率で場所を特定できる。ただ、膵臓ガンになると、ガンがあるかないかについてはわかっても、膵臓ガンとまでは診断できない。
以上が結果で、まだまだ実地診療に使えるというところではないという印象だが、意外なルートでガンの診断が可能という結論になる。
しかし、診断はともかく、何故血小板 RNA でガンの診断が可能かが最も面白い。気になって論文をたぐっていくと、なんと2015年、同じ Cancer CellにTumor educated platelets の RNA という論文を発表している。
これによると、約5000種類の血小板 RNA の中から、約1000種類の RNA を選び出し、ガンと健常人で変化があるい RNA を選び出して、それを診断に使っていることはわかったが、やはり何故このような変化が起こるのかについては tumor education 以上にはわかっていない。すでに7年もたって、この肝心な点がわかっていないとすると、おそらく検査としては普及しないように思う。統計的因果性をそのまま信じられないのが我々自身のニューラルネットの傾向だ。その点で、臭い診断も、化合物の組み合わせがわからないと長続きしないように思う。
2022年9月7日
若い人たちにはにわかに信じられないことだと思うが、以前は、我が国のみならずほとんどの先進国で、公共交通機関でタバコが吸えた。今もたまにへんぴな国で飛行機に乗ると、まだ灰皿付きの座席に出会い懐かしく思う。かくいう私も、飛行機では喫煙席に座っていたし、驚くなかれ外来もタバコを吸いながら患者さんを診ていた。
現在でもタバコが吸えるレストランがあるように、我が国の取り組みはまだまだ腰が引けているが、それでも禁煙に向けた取り組みは進んでおり、その効果もガン統計に表れている。このように、ガンのリスクを明らかにし予防することは、ガンを減らすための1丁目1番地になる。
今日紹介するワシントン大学を中心とする何百もの研究機関が集まって発表した論文は、2019年に行われた、Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factor Study(GBD)と呼ばれる、疾患リスク分析調査の結果で、予防可能なガンのリスクを洗い出すことを目的にした研究で、8月20日 The Lancet に掲載された。タイトルは「The global burden of cancer attributable to risk factors, 2010–19: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019(リスク要因が特定できるガンは2010−2019年の地球規模の問題である:GBD研究の総合的解析)」だ。
地域ごとにデータの質はまちまちと思えるので、国際比較についてはいろいろ問題もあるかもしれないが、このような試みが続けられて、それぞれの国でガンを減らすための科学に裏付けられた政策がプラン出来るのは素晴らしいと実感できる。
結果は膨大なので、一部重要と思った点を箇条書きに書き留めておく。医療に関わるひとは是非自分で読んでみて欲しい。
まず、現在もなお予防可能なガンによる死亡は全体の44%に及ぶ。 DALYと呼ばれる指標で、ガンにより失われた時間を換算する方法を用いることで、より正確にガンの世界的課題を算定できる。これによると、いまだ42% DALY が予防により取り戻せる。 予防可能なガンのリスクファクターのトップ3は、タバコ、アルコール、そして食事で、これは男女変わらない。特に男性ではいまもタバコが大きな位置を占めていることがわかる。 地域別に見ると、この生活習慣によるリスクは東欧、中国が高い。不思議なことに、我が国のリスクは比較的低い方に属している。 肥満など代謝との関わりで見たとき、予想通り米国は最も悪い地域になるが、同じように英国と東欧も最も悪い地域になる。一方、日本はアフリカやインド、そして北朝鮮とともに、代謝リスクが最も低い国になる。 ガンの場合、子宮頸がんのようにセックスにより媒介されるケースがあるので、出生率の高い国と低い国で統計を分けることが出来る。当然、セックスにより媒介される子宮頸がんなどは、多産の国で多い。一方、代謝リスクによるガンは、特に出生率の低い国で今も増加している。 とはいえ、DALY で計算すると、喫煙と飲酒によるガンの失われた時間は低下しており、喫煙では 10年で12%低下している。これに反し、肥満リスクによるガンは上昇している。 以上が私が気になった点だ。いずれにせよ、このような努力のおかげで DALY、ガンによって失われる時間は改善しているが、まだまだ道半ばというところだ。
2022年9月6日
昨日パーキンソン病を睡眠中の呼吸運動から診断するという論文を紹介した後、急に無脊椎動物は寝るのか?ということが気になって調べてみた。結構多くの論文があり、節足動物はもとより、線虫やクラゲでも、それを眠りと呼んでいいのかわからないが、寝て休んでいるような状態があることは広く認められているようだ。とはいえ、さすが夢を見ているかどうか調べた研究はないだろうと思って見てみると、なんと先月ワシントン大学の研究者が、米国アカデミー紀要に発表した、ハエトリグモのREM睡眠についての研究があったので紹介する。タイトルは「Regularly occurring bouts of retinal movements suggest an REM sleep–like state in jumping spiders(定期的に起こる網膜が動く発作はハエトリグモのREM睡眠状態の存在を示唆する)」で、8月8日米国アカデミー紀要に掲載された。
夢の研究をする前に必要なのは、蜘蛛の睡眠だが、2021年このグループは蜘蛛が一本の糸で枝からぶら下がって、足を縮こめて寝るという行動を報告している。
ただ、寝ていると言っても外敵に備えているようで、振動を感じると必ず地上に落下する。一方、起きているとき振動を感じると、糸を伝って登る行動をとる。
この研究では、まだ色素が皮膚を覆っていない、若い蜘蛛を用いて、糸を伸ばして休んでいるときビデオ撮影を行い、4種類の目の中で大きな3種類について網膜の動きを追跡している。
我々と違って蜘蛛には眼球がないため、動眼筋肉で目の方向を決めるのではなく、網膜を動かせて見る方向を決めている。
さて結果だが、休息中は基本的に目は全く動かない。しかし、15−20分に1回、規則的に網膜が動くことが観察される。さらに、網膜が動くときに、足も発作的に動くことが観察された。
結果は以上で、休息中に網膜が規則的に動くことは、我々のREM睡眠と同じで、蜘蛛の休息も、non-REMとREMに分けることが出来ると結論している。
網膜の動きは若い蜘蛛でないと観察できないのだが、成熟個体でも睡眠中規則正しく手足縮める発作が見られることから、これがREM睡眠状態に対応すると結論している。
これが正しいとすると、線虫やショウジョウバエでも休息中にピクッと動くことが観察されているので、REM睡眠は多くの無脊椎動物で観察できるのかもしれない。とすると、蜘蛛の夢とは何かを明らかにするのが、次の課題になる。以前紹介したように、マウスでも動眼運動の追跡から夢を解読できる可能性がある(https://aasj.jp/news/watch/20414 )。おそらく蜘蛛の夢の解読は、もっと簡単ではないだろうか。蜘蛛の夢が解読できれば、イグノーベル賞は間違いない。