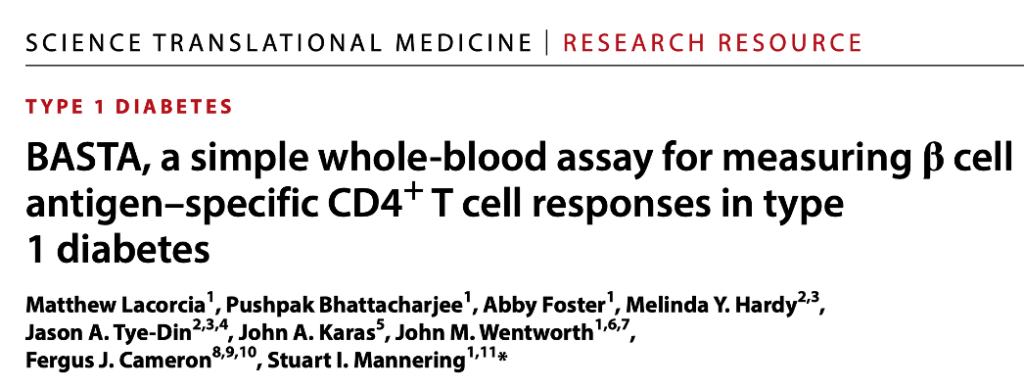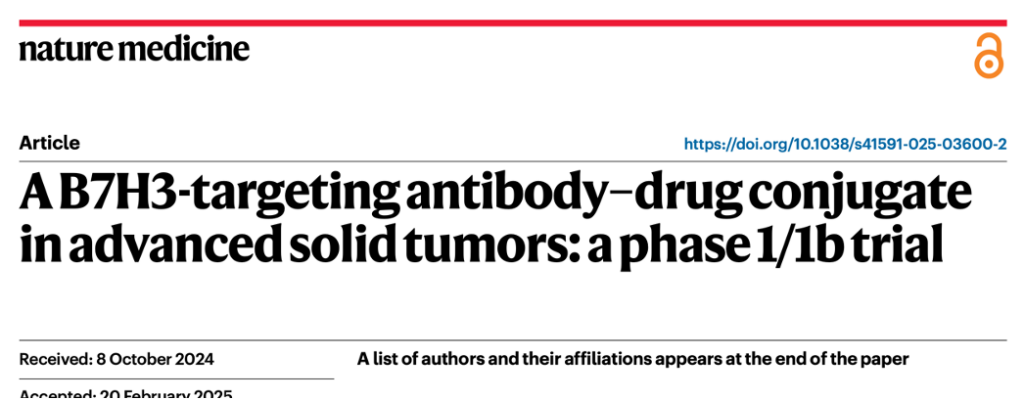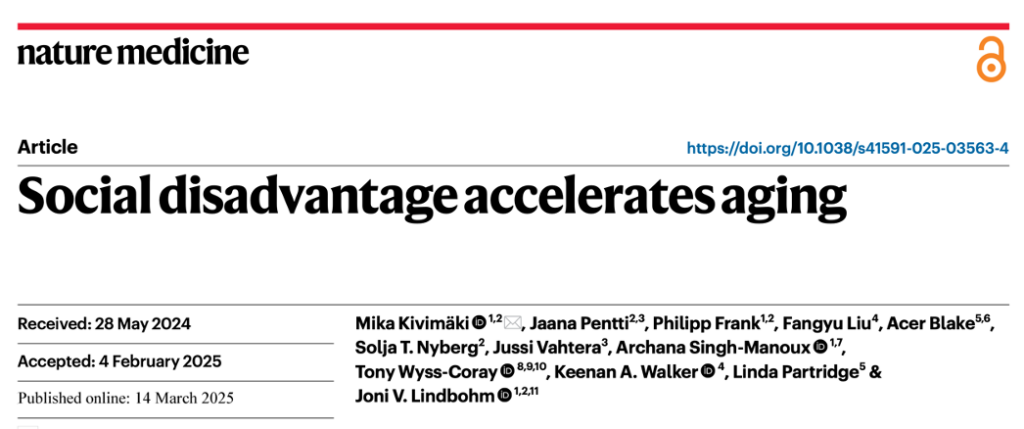2025年3月25日
妊娠に伴い脳を含む様々な組織がリプログラムされ、繁殖という動物にとっての大イベントを無事に終えるための準備が行われる。妊娠中に必要なだけ食べるということは最も重要なことなので、当然腸管もリモデリングされると考えられる。
今日紹介する英国フランシスクリック研究所からの論文は、妊娠中から授乳期の腸管のリモデリングについて調べた研究で、なるほど大きな変化が起こることを納得する論文だが、メカニズムの追求という点では少し不満が残る研究だった。タイトルは「Growth of the maternal intestine during reproduction(生殖に伴う母親の腸管の増殖)」だ。
この研究ではマウスの最初の妊娠前後の腸管の長さをまず比較して、、全長が妊娠前に33cmだったのが、妊娠18日目で40.5cm、そして授乳開始7日目には43cmに達すること、そしてこの変化は子育てが終わっても完全に戻らず39cm程度で落ち着くことを示している。比率で言うと2−3割伸びるのを見ると、ともかく驚く。
これに合わせて、絨毛組織のクリプトや絨毛のはがさも増加する。これは絨毛上皮の増殖が促進され、さらには上皮細胞の移動が早まることで進むことから、リモデリングは幹細胞の増殖の促進および分化した細胞の細胞骨格活性化が誘導する何らかのシグナルが妊娠期に上昇すると考えられる。
このシグナルを探す目的で、妊娠前後の腸管細胞の single cell RNA sequencing を行い、変化する遺伝子を調べると、代謝経路に関わる分子を中心に転写の大きなリプログラムが進んでおり、特に回腸で変化が著しいことが確認された。また、増殖している細胞が最も未熟な Lgr5 陽性細胞ではなく、Fgfbp1 陽性の上皮細胞であることも確認している。
ただ、single cell 解析だけでは変化の核となる分子を特定できないため、さまざまな時期で上皮の変化を調べることで、ナトリウム・グルコーストランスポーターの一つ、SGLT3 が特に妊娠期に上昇してくるのに着目し研究を進めている。
まず SGLT3 が妊娠中の変化に必須かどうかを調べるためノックアウトマウスを調べると、発生、成長、体の維持には全く影響がないものの、妊娠期から授乳期の体重がコントロールと比べると低下していることに気づく。ただ、妊娠中の腸管リプログラムに関しては、SGLT3 では完全に説明できない。というのも、データが示されていないのでなんとも言えないが、おそらく SGLT3 無しでも腸の長さは妊娠中に伸びる。しかし、絨毛の長さの伸びは抑えられ、DNA合成も低下している。
以上のように、妊娠中のホルモンの変化で誘導された SGLT3 は、何らかの形で Fgfgp1 細胞の増殖を誘導し、腸での栄養吸収効率を上げている。ただ、腸のリプログラミングの調節は、ホルモンの直接作用も含めてこの研究では完全に特定できていない。
SGLT3 は、現在腎臓や糖尿病の治療で最も注目を集めている SGLT2 と同じで、ナトリウムとグルコースのトランスポーターの一つで、何故この発現上昇が絨毛上皮の増殖を誘導できるのかについても完全に解明されたわけではない。生理学的な実験から、SGLT3 はグルコースよりナトリウムの取り込みに関わっていることがわかった。したがって、腸管でナトリウムの流入が上昇した上皮細胞で何らかの代謝変化が起こり、Fgfgp1 細胞の増殖を促す分子が提供されるとともに、細胞骨格が活性化されると考えられる。
以上が結論で、これが完全に実験的に示されていないのは残念だ。しかし妊娠中の腸管の変化の大きさには驚いた。物足らない論文だが、この驚きだけでよしとしておこう。
2025年3月24日
ガンが様々な遺伝子変異を重ねるなかで新しい抗原を発現し、それに対するガン免疫が誘導されることを疑う人はいない。とはいえ、免疫によるガン抑制は多くの場合成功せず、これをより高い確率で成功に導くチェックポイント治療が Allison や本庶先生により開発された。それでも、ガン細胞は自分にアタックしてくる免疫から逃れようと不断のチャレンジを繰り返しており、免疫を逃れるためのガンの戦略が続々明らかになり、現在この逃避メカニズムを抑える治療法の開発が続けられている。
ただガンと免疫のバトルは基本的に細胞表面上で繰り広げられると勘違いしてしまうが、今日紹介するテキサス St. Jude 小児病院からの論文は、キラー細胞がガン細胞に働きかけて細胞内の自然炎症メカニズムを誘導することがガンを殺す重要な経路になっていることを思い起こさせてくれた。タイトルは「VDAC2 loss elicits tumour destruction and inflammation for cancer therapy(VDAC2欠失はガンの破壊と炎症を誘導してガンの治療を可能にする)」だ。
遺伝子スクリーニングを通して、ガン細胞が免疫から逃れる過程を抑える分子を探索するという点では、この研究も特に新しいことはない。ただ、この過程でリストされてきた遺伝子の中から、ミトコンドリアに発現している電位依存性の陰イオンチャンネル (VDAC2) に注目したことで、ガンとキラー細胞の相互作用をミトコンドリアの側から眺めてみている点が特徴と言える。
VDAC2 をノックアウトすると CD8 T細胞に対する感受性は格段にしかも持続的に高まる。その結果、チェックポイント治療と組み合わせると、ガンの増殖をほとんど止めることができる。すなわち、ガンが VDAC2 を強く発現することで、キラー細胞のアタックから逃れていることがわかる。
なぜ細胞内の分子がキラー活性を抑えるのか調べていくと、キラー T細胞が分泌するインターフェロンγ に反応してガン細胞内で自然炎症過程と細胞死が起こるのを VDAC2 が抑えることが明らかになった。事実、インターフェロンγ が分泌できない T細胞では、VDAC2 をノックアウトしてもガンのキラー細胞への感受性は上昇しない。すなわち、キラー T細胞はガン細胞の細胞膜に穴を開けるだけでなく、インターフェロンγ を介して炎症性アポトーシスを誘導しており、これを VDAC2 が抑えていることになる。
さらにメカニズムを探ると、インターフェロンγ により誘導されるミトコンドリアの機能異常がおこり、ミトコンドリア DNA が細胞質に遊離する過程を VDAC2 が抑えていることが明らかになった。逆から見ると、VDAC2 が存在しないと、ミトコンドリアから DNA が細胞質へ遊離し、細胞内で外来 DNA を検出する GAS-STING 経路が刺激され、自然炎症を誘導する様々なサイトカインが分泌されると同時に、ガン細胞の細胞死への経路にスイッチが入る。
STING が活性化されると、ガン細胞から CCL5 ケモカインが分泌され、より多くの T細胞がガンの周りにリクルートされるとともに、カスパーゼの活性化から細胞死へと進む。このように、キラー細胞はガンのミトコンドリアに働いて、細胞の中からガン細胞を殺す仕組みを持っている。
この仕組みを VDAC2 は抑制するが、これはインターフェロンγ により活性化される BAK と結合して、BAK が Bax とともにミトコンドリアから細胞死のシグナルを出すのを抑えることを明らかにしている。
結果は以上で、キラー T細胞が細胞内のアポトーシス回路のスイッチを入れるメカニズムの一端が明らかにされた。従って、この回路を抑える VDAC2 を標的にした治療は十分可能だが、同じメカニズムは当然正常細胞にも働いているので、簡単ではないだろう。しかし、細胞の内外から細胞を壊すためのこれだけのメカニズムを見事に回避するガン側のメカニズムを目の当たりにすると、この戦いに勝利することが簡単でないことを実感する。
2025年3月23日
1型糖尿病が自己免疫疾患であることは間違いなく、免疫全体を抑制するCD3抗体や、あるいは制御性T細胞を介して免疫反応を抑える治療法が試されている。とすると、1型糖尿病を理解し、治療法開発が可能な重要な過程が、β細胞で自己抗原が発生する過程になる。このことを最も明確に示しているのが、1型糖尿病リスクとして特定されているインシュリン遺伝子の多型の存在だ。
今日紹介するオランダ・ライデン大学からの論文は、これまで1型糖尿病の発症を送らせるとして知られていた多型がインシュリン自己抗原発生を抑え、さらにβ細胞の活性も高める作用を持つこと、そしてそのメカニズムを明らかにした重要な研究で、3月19日 Cell にオンライン掲載されたタイトルは「Genetic protection from type 1 diabetes resulting from accelerated insulin mRNA decay (1型糖尿病のリスクを下げる遺伝子多型はインシュリンmRNAの減衰を早める)」だ。
これまで1型糖尿病の発症を抑える多型として知られていたのは、プロモーター領域にリピート配列を持つ多型で、胸腺内でインシュリンを転写翻訳することで、インシュリン抗原に対するトレランスを誘導するとされてきた。一方、著者らは同じ多型がインシュリン遺伝子の3‘側の翻訳されない領域 (3’UTR)の多型と強く連関しており、プロモーターの活性ではなく、mRNA の減衰速度の違いで糖尿病の発症を抑える可能性があると着想した。
というのも、β細胞では4割近い転写産物がインシュリン遺伝子からの転写で、当然細胞は強いストレスに晒される。しかも、ストレスによりリボゾームと mRNA とのマッチングが狂い、インシュリン遺伝子から自己には存在しない新しいネオ抗原が発生することも知られている。とすると、もし mRNA が3’UTR の多型で早く分解されるとすると、ストレスが低下し、ネオ抗原の合成も低下すると考える。
この研究では、3’UTR の多型に絞り、糖尿病の発症を遅らせる多型 (P) が RNA 分解を促進しているかどうかを、臓器ドナーから得られた膵臓β細胞を用いて調べている。
この結果ヘアピンループ構造をとる 3’UTR を持つ遺伝子多型は、特に小胞体ストレス存在下では分解速度が速区なることが明らかになった。そしてこの分解を小胞体ストレスで誘導されてくる IRE1α が担っていることを突き止めている。すなわち、インシュリン遺伝子の mRNA が安定だと、小胞体ストレスが上昇し、mRNA を分解するために IRE1α が誘導されるが、1型糖尿病になりやすい多型ではこの作用を受けないために、ストレスが持続することになる。一方、糖尿病を遅らせる多型は、速やかに mRNA が分解され、ストレスの発生を抑えることになる。
さらに、リボゾームと mRNA のマッチングがずれて発生するネオ抗原について調べると、mRNA 分解されやすい多型は小胞体ストレスが軽減されるため、発生が強く抑制されることが確認され、小胞体ストレスとリボゾーム上での翻訳のずれが自己免疫病を誘導するネオ抗原発生の原因であることも確認している。
ただ、mRNA が早く分解される結果はネオ抗原発生抑制だけにとどまらない。小胞体ストレス自体が低下するため、β細胞の活動が上昇し、グルコースに反応しておこるインシュリン分泌も高まることがわかる。
また、グルタミナーゼの発現が低下することも、ネオ抗原が修飾され、組織適合性抗原と強く結合することを抑えて、免疫原性を抑えること可能性も指摘している。
以上のように、インシュリン遺伝子のように大量に転写・翻訳される場合、単純に mRNA の量を増やすのではなく、ちょうどいい量に mRNA を調整することが重要なことがよくわかる。従って、細胞ストレスを抑える遺伝子多型を誘導した後、膵島細胞移植に利用することの重要性がわかる。おそらく、1型だけでなく、2型糖尿病にもこのような多型は関係しているのではないだろうか。
インシュリン分泌を続けるという作業がいかに細胞にとってストレスになるかよくわかる論文だった。
2025年3月22日
乳幼児期の脳は外界からの刺激を受けて急速に発達し学習を重ねているはずなのに、我々は乳幼児期の記憶をほとんど持っていない。これまで不思議に思ったことはなかったが、もし乳幼児期にも海馬の本来の機能があるとすると、確かに不思議だ。
今日紹介するコロンビア大学からの論文は、4ヶ月から24ヶ月までの乳幼児を対象に、エピソード記憶の成立時と呼び起こしについて fMRI を用いて調べ、乳幼児の海馬が記憶をコードすることはできても、記憶が呼び起こせないようになっていることを示した研究だ。タイトルは「Hippocampal encoding of memories in human infants(人間の乳幼児での海馬での記憶のエンコード)」だ。
動物を用いた研究では乳幼児期でも脳では記憶痕跡(記憶のエングラム)を形成することが可能で、記憶がないように行動しても、形成されたエングラムを光遺伝学的に刺激してやると、記憶に基づく行動をとることが示されている。従って、この研究の第一の目的は、記憶課題を課した時に、幼児でも海馬の活性化が起こっていることを示すことで、次の目的がこうして形成された記憶のエングラムを海馬の興奮として呼び起こせるかを調べることになる。
この研究で最も驚いたのは、4ヶ月の乳児の fMRI 検査が行われていることだ。しかも両眼視が可能になってすぐの子供にいくつかの新しいイメージを見せて、それが思い起こせるか2枚の写真を見せて、どちらを見ているかで判断する subsequent memory テストが行われていることだ。方法のセクションを注意深く読んではみたが、この点についての特別な言及はない。もし乳幼児の MRI が可能だとすると、これは人間の脳発達研究に大きく寄与することは間違いないだろう。
さて結果だが、予想通り subsequent memory テストで、1分ほど前に見たイメージに注目するのは12ヶ月を過ぎてからで、要するに乳児では記憶が成立していない。しかし、fMRI でみると新しいイメージに出会ったとき、年齢を問わず海馬の後方が特に強い反応を示していることから、記憶のエンコーディングが行われていることが推察される。
重要なのは記憶を思い起こしているとき、2歳児では海馬の活動が高まるのに、12ヶ月以前の子供では活動が低いままで終わる。すなわち、記憶形成プロセスは動いているのに、それを思い起こすのが抑制されているのか、何らかの理由で海馬に表象することができないことがわかった。
この課題には海馬だけでなく、脳の様々な領域が関わるが、この活動も12ヶ月を過ぎないと検出できない。
以上が結果で、なぜ呼びおこしだけができないのかの脳回路メカニズムについてはわからないままだが、読んでいてフロイトを思い出した。
フロイトは幼児の性体験が呼び起こせないよう無意識下に沈められるが、折に触れて成長後の私たちの行動を陰で支配すると考えた。1歳半までは口唇期の母親への指向性の抑制だが、このようなベクトルが性的体験だけでなく、一般的体験にも存在するとしたら、説明できるかもしれない。
2025年3月21日
今日はこの1ヶ月で気になった臨床研究を紹介する。
まず最初はオーストラリアのセントビンセント医学研究所からの論文で、1型糖尿病患者さんのインシュリンペプチドに対するT細胞の反応を短時間でしかも簡単に測定することができることを示した研究、で3月19日 Science Translational Medicine に掲載された。
この研究で用いられたのは、BASTA と呼ばれる方法で、末梢血にヘパリンを加えて固まらなくした後、抗原ペプチドを加えて炭酸ガス培養器で24時間培養し、その後血清を回収して高感度の方法で IL-2 を検出するという極めて簡便な方法だ。
これまでだと、まず、白血球画分を調整しそれに抗原ペプチドを加えて増殖やサイトカイン産生を見る必要があり、どこでもできるというものではない。しかし、この方法だと病院に炭酸ガス培養器さえあれば、すぐに刺激して、後は血清を検査会社に送ればいい。
さらに驚くのは、従来の方法と比べて感度が良いことで、インシュリンの前駆体配列の中から高い反応を示すペプチドを特定し、これを用いて1型糖尿病の患者さんのみ反応することが示されている。同じ患者さんの血液を異なる時期に検査してもほぼ同じ結果が得られている。ただ、遺伝リスク患者さんの早期発見はまだ難しそうだ。
この簡便法はおそらく1型糖尿病に限らず、感染症やガンにも使える様に思う。細胞を精製する実験から、この検査ではCD4T細胞の反応が検出できていることを示しており、キラー細胞検出は他の方法が必要かもしれない。ただ、すでに免役されたT細胞が血液を流れているかどうかの検査としては大きな前進だと思う。
次は中国・中山大学ガンセンターを中心とする新しい ADC (抗体と薬剤を結合させた治療薬) の大規模第一相研究で、多くの創薬企業のひしめく分野にチャレンジする中国の意気込みが示される研究で、3月13日 Nature Medicine に掲載された。
YL201 という薬剤は costimulatory 分子の一つ CD276 に対する抗体にトポイソメラーゼ阻害剤を結合させた薬剤だ。おそらく抗体は独自のものだと思うが、どのトポイソメラーゼ阻害化合物かなどの詳細が示されていないが、形状は第一三共の DS7300 とほぼ同じと考えられる。
従来の治療の効果が見られなくなった小細胞ガン、鼻咽頭眼、非小細胞肺ガンについて、いくつかの用量で治療を行っている。第一相なので副作用が重要だが、貧血が中心に起こる。ガンだけでなく血液系にも一定程度の発現が見られるからだろう。
効果は上々で、特に他の抗ガン剤が効かなくなった小細胞性肺ガンの多くの患者さんが反応しているのは期待できる。ちょっと驚くのは、ガン細胞の表面 CD276 発現量とは無関係に効果がある点で、なぜこのようなことが起こるのかの検討がないと安心して使えない気がする。
ほぼ同じような治験が我が国の第一三共を始めいくつかの会社から発表されており、ADC の新しい主戦場になっているが、そこに打って出てくる中国の意気込みが感じられた論文だった。
次のロンドン大学からの論文は、教育や収入、生活程度などが把握されているコホートの中から社会的弱者と言われる人たちと老化の速度を調べた研究で、3月14日 Nature Medicine に掲載された。
研究では UK バイオバンクと、フィンランドのコホート研究の参加者が対象で、始まってから10年以上が経過しており、老化に伴う変化を調べられるようになっている。
研究では、老化と関連する83疾患を決め、その発生から老化の程度を測定するとともに、血液のタンパク質から老化の指標の発現しらべ、そこから老化程度を調べている。
結論はどの方法で調べても、社会的弱者の立場に置かれることで老化が進むという結果だ。特に免疫系、腎臓、肺で老化が顕著になっている。老化の指標を調べる研究ではすでに指摘されていたことではあるが、トランプに代表される政治が猛威を振るい始めた社会ではますますこの問題は深刻になるように思う。
2025年3月20日
今日は専門家向けの論文を紹介するが、できるだけ解説部分を多くするとともに、実験の詳細を省いて結論を紹介するようにする。
我々の細胞は細菌などの外来刺激に対して炎症誘導という形で最初に反応するが、これを抗原特異的免疫に対して自然免疫と呼んでいる。例えばバクテリアの LPS には細胞表面の TLR4 が反応して炎症反応を誘導するが、細胞内に入ってきた DNA は GAS-STINGシステムという DNAセンサーが働いている。このシステムは進化的に古く、バクテリアが外来のウイルスやプラスミドを排除する仕組みに由来している。生化学的には、GAS によって DNA から cyclicGMP-AMP が合成され、これが小胞体膜上の STING に結合するとTBK1、IRF3を介して炎症を誘導するとともに、ウイルスに対してインターフェロンを分泌する。
ところが最近、 STING が小胞体からプロトンを汲み出す全く別の機能があることが報告された。今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、重篤な炎症疾患が起こる STING の変異が、従来の IRF3 などインターフェロン下流シグナル経路とは異なる経路で炎症を誘導している分子機構を探るなかで、STINGの新しい機能メカニズムを解明した研究で、3月20日 Cell に掲載された。タイトルは「ArfGAP2 promotes STING proton channel activity, cytokine transit, and autoinflammation(ArfGAP2 は STING のプロトンチャンネル活性を高め、サイトカインの輸送促進を介して自発的炎症を誘導する)」だ。
この研究では GAS を介さずに STING が勝手に活性化している変異を導入したマウスを作成し、クリスパースクリーニングで、ArfGAP2 をノックアウトすると、変異STING の活性化による細胞死を回避できることを発見する。
ArfGAP2 はこのように変異STING活性を強く抑えるが、ノックアウトしても通常のインターフェロン経路には全く影響がない。ただ少しややこしいが、STING・IRF3経路により誘導される様々なサイトカインの分泌は抑えるので、おそらく STING のプロトンチャンネル活性にかかわる機能に関与して、しかもサイトカインの転写ではなく分泌を調節すると考えられる。
この可能性を追求して最終的に次の結論に到達している。
STING は活性化されると、TBK1/IRF3 を介してインターフェロン反応性の様々なサイトカインの転写を誘導する。
これとともに、STING のプロトンチャンネルが開いてゴルジ体の酸性度が低下する。
このアルカリ化シグナルがゴルジから膜への小胞体輸送を促進し、これによりインターフェロン反応性分子も輸送される。
ArfGAP2 がノックアウトされると、STING のプロトンチャンネル活性が低下し、ゴルジでの小胞体輸送が落ちる。
ただ、ArfGAP2 は何らかの過程で、小胞体に乗せるタンパク質をインターフェロン反応性分子が優先されるように調整する役割も持っている。事実、ArfGAP2 非存在下で STING が活性化してしまうと、調整されずにほとんどの分子が輸送されてしまう。
以上が結果で、かなり専門的な論文を簡単にまとめすぎたとは思うが、STING が新たに獲得したプロトンチャンネル活性が、免疫系やマクロファージで、サイトカイン分泌のファインチューニングを可能にしていることを示す重要な論文だと思う。特に持続するウイルス感染などで、過剰炎症を抑える目的でArfGAP2 は重要な標的になると思う。
2025年3月19日
肝臓には間葉系の星状細胞が散在しており、肝臓の繊維化の主役であるとされてきた、しかし、この細胞を除去する実験が可能になって、最近では肝臓細胞の増殖を助ける細胞であることが示され、その評価が大きく変化している。
今日紹介するコロンビア大学からの論文は、星状細胞が肝細胞を助けるメカニズムについて明らかにした研究で、3月12日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Hepatic stellate cells control liver zonation, size and functions via R-spondin 3(肝臓の星状細胞は R-spondin 3 を介して肝臓のゾーン化、大きさ、そして機能を調節している)」だ。
この研究では星状細胞特異的にジフテリアトキシンを発現させ、星状細胞を肝臓から除去する実験から始めている。まず除去するだけで肝臓は小さくなり、肝臓のサイズを決める重要な細胞であることがわかる。そして、肝臓の部分切除や障害により誘導される肝臓の再生実験では、再生力が強く抑制される。
肝臓は中心静脈から胆管の間に肝臓細胞が並んだ構造を持っており、胆管側から zone1、2、3と区別され、代謝機能が異なることがわかっている。このゾーン化には血管内皮が重要な役割を演じているとされていたが、星状細胞を除去するとゾーン化が傷害され、zone1 が肥大し、zone3 が減少することがわかる。すなわち、星状細胞が肝細胞のゾーン化にも関わることがわかる。
試験管内の実験から、肝臓細胞の増殖には星状細胞が分泌する何らかの分子が必須であることが示唆されるので、星状細胞を除去した肝臓を比較することで増殖因子を探索すると、Wnt受容体を補助するLgr4 に結合する R-spondin 3 が HSC 由来の分子であることが明らかになった。
そこで星状細胞特異的に R-spondin 3 が欠損したマウスを作成すると、星状細胞を除去したのとほぼ同じ状態が発生することがわかった。これは、肝臓のサイズが小さくなり、再生時の増殖が抑制され、さらに肝臓の代謝が変化してゾーン化が壊れることである。すなわち、これまで血管内皮が調節していると考えられてきた肝臓のゾーン化を星状細胞も調節していることがはっきりし、おそらく血管内皮由来の R-spondin 3 は zone1 細胞に影響し、ほかの zone は星状細胞が受け持っていることが示された。
さらに、障害による再生だけでなく、星状細胞から R-spondin 3 が分泌されないと、アルコール性肝炎や、高脂肪食による非アルコール性肝炎モデルで肝硬変がより促進されることから、星状細胞は繊維化も防ぐ重要な味方であることがわかった。
事実、星状細胞の R-spondin 3 分泌は TGFβ により調節されており、肝臓の繊維化が進む病気ではその発現が低下し、また R-spondin 3 が高い患者さんほど肝硬変の予後が良いことも確認している。
以上が結果で、最近の研究で少しづつ明らかにされてきた星状細胞の肝臓保護作用を総合的に明らかにした重要な研究だと思う。
2025年3月18日
分野を問わず毎日論文を読んでいると、大概の論文はタイトルを見ておおよその筋を読むことができる。しかし生命科学は多様で、タイトルを見ても「ちんぷんかんぷん」、全く筋が見えない論文も多い。
今日紹介する米国サンディエゴの aTyr Pharma とスクリプス研究所からの論文は、タイトルを見て余計に謎が深まり、論文を読んでこんなことがあるのかと驚いた研究で、3月12日 Science Translational Medicine に掲載された。そのタイトルとは「A human histidyl-tRNA synthetase splice variant therapeutic targets NRP2 to resolve lung inflammation and fibrosis(ヒトのヒスチジンtRNA 合成酵素のスプライスバリアントは NRP2 と結合して肺の炎症と繊維化を改善する)」だ。
さてタイトルだが、生物学を全く知らないと不思議を感じないと思うが、教科書レベルの知識があると、ヒスチジンを tRNA に添加する酵素 (HARS) のスプライスバリアントがニューロピリン2と反応して肺の炎症を抑えるなどと書かれていると、混乱してしまう。 tRNA 合成酵素は、核酸のコードとアミノ酸を結びつける38億年の歴史を持つ生命の基本システムだ。それが、血管増殖因子や神経伸張因子と結合するニューロピリン2 (NRP2) と結合するなどと書かれていると何かの間違いかと思ってしまう。
しかし読み進むと、驚くべき話が広がっていた。すなわち、 HARS に限らず様々な tRNA 合成酵素は、進化の過程で、スプライシングにより他の機能タンパク質に生まれ変わる新しいドメインが獲得されているという話だ。この研究ではヒスチジンを添加する HARS に限っているが、実際には他の tRNA 合成酵素にも新しい機能が付与されているという。私も全く知らなかった世界で、特殊だが是非ジャーナルクラブで取り上げてみたいと思う。
この研究グループが HARS に注目したのは、HARS に対する自己抗体によって肺や筋肉の炎症がおこる anti-Jo-1 症候群の存在による。この症候群が認識している本来の遺伝子がスプライシングで短い部分だけになった HARS-WHEP が、炎症により肺の上皮細胞から分泌され、血中にも流れることを確認し、この分子の機能を調べるために、HARS-WHEP に免疫グロブリン Fc 部分を結合させて安定化した分子を開発している。
まず HARS-WHEP の結合する分子を探索して、NRP2 に特異的に結合することを明らかにしている。NPR2 は炎症が起こるとマクロファージで発現する。このとき HARS-WHEP-Fc で処理すると、マクロファージからの炎症性サイトカインやケモカインの発現が抑制される。
そしてマウスの様々な肺の炎症モデルに投与すると、例えばブレオマイシンによる肺線維症モデルでは、組織病理像を正常化させ、また炎症性サイトカインの分泌も強く抑える。一方、特殊な細菌を用いたサルコイドーシスモデルでは、病理組織は改善しないが、炎症性サイトカインの分泌を抑えることができる。
さらに人間の肺の炎症性症例のバイオプシーで、サルコイドーシスなどの炎症の進展とともに NRP2 発現マクロファージの数が上昇しており、HARS-WHEP-Fc を試験管内で加えることで、マクロファージの炎症性サイトカインの分泌を止められることを示している。
実際には2023年に HARS-WHEP-Fc をサルコイドーシスによる肺線維症の患者さんに投与する第1/2相の治験も行われて期待できる結果が得られているようで、新しい治療法としてもすでに走り出している。従って、この論文はこれまでの研究を基礎的にバックアップするための論文と言える。
以上が結果で、私にとっては臨床時代なじみのあるサルコイドーシスの治療と言うだけでなく、tRNA 合成酵素の変身に驚いた。少しマイナーな話題になると思うが、是非 tRNA の変身について調べてジャーナルクラブとしてまとめてみたい
2025年3月17日
熊本大学に在職していた頃、免疫医学研究施設と遺伝医学研究施設を改組して遺伝発生医学研究施設設立に関わったことがある。当時は各大学の研究施設でこのような改組が文科省の指導で当たり前のように行われていた。当時のはやりは大阪大学にできた細胞工学センターのような新しい風の感じられる名前を考えることだった。しかし、熊本大学では敢えて遺伝発生医学という古い名前にこだわった。折衝の過程で、遺伝学も発生学も医学には必須なのに、系統的な教育や研究ができておらず、両方を強調した研究施設は新しいと説得したのを覚えている。
遺伝学は生物の違いを扱うが、逆に発生学は生物の形成で同じことが再現できることを対象としている。ただ、発生学は遺伝学と統合されることで大きく進歩した。これが、ショウジョウバエや線虫を中心にして進んできた形質の違いを誘導してその遺伝子を探る Forward Genetics で、責任遺伝子が特定できるようになったこと、そして遺伝子改変が可能になり、ともかく遺伝子を変異させて形質を調べる Reverse Genetics の構想が生まれたことだ。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、新生児期の健康に関わり、一般にもよく知られているビフィズス菌のリバースジェネティックス確率を目指した研究で、3月10日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Genome-scale resources in the infant gut symbiont Bifidobacterium breve reveal genetic determinants of colonization and host-microbe interactions(新生児の共生生物ビフィズス菌のゲノムスケールで変異を誘導したリソースは細菌の定着やホストや他の細菌との相互作用の遺伝的要因を明らかにする)」だ。
この研究のハイライトは、最も研究が進むビフィズス菌の一つ Bifidobacterium breve に遺伝的バーコードが着いたトランスポゾンを導入し、ほぼ8割近い領域、1500近い遺伝子の変異を誘導した変異ライブラリーを作成したことだ。それぞれの変異をもった菌株は変異ごとに単離されており、変異が起こった遺伝子の機能を調べることができる。さらに、バーコードがつけてあるので、全体を特定の条件で培養して適応に必要な遺伝子を特定することもできる。要するに、将来ビフィズス菌をより利用価値の高い菌に変化させるためのリソースを作ったという話だ。
もちろん1500近い遺伝子それぞれについて調べるのは時間がかかる。従って、この研究ではこのリソースが様々な目的に利用できることを示すための実験例を示している。面白いと思ったものをいくつか紹介しよう。
同じ機能を保つ酵素が2種類存在しているが、一つの酵素は他の細菌と共同して生存するときに使われ、もう一つの酵素は独立して生存するときに使われることがわかる。すなわち、機能が同じでも実際には環境適合性に大きな差があることがわかる。
ビフィズス菌は母乳に含まれるオリゴ糖を使って定着することが知られているが、大人で他の細菌と競合するとき、ビフィズス菌は一般的な炭水化物を利用できることができないため、ラフィノースなどが必要になる。この酵素学的背景が、このリソースから明らかになっている。
このようなリソースは試験管内での増殖でテストするのは容易で、この研究では150種類の条件で増殖に異常が起こる系統を分離できている。その過程で、ビフィズス菌の由来になった細菌が栄養条件で様々な形をとることの生化学的背景を明らかにしている。また、腸内に定着したとき、ビフィズス菌が名前のようなY型に変化する理由についても明らかにしている。
最後に、ビフィズス菌のもつ免疫機能を変化させる能力にはフェニル乳酸やインドール乳酸のような芳香族基が添加された乳酸が大きく関わることが示されているが、この生成経路の酵素を特定している。
以上が結果だが、要するにリソースができて研究はこれからだという話になる。これまでこのようなリバースジェネティックスが行われなかったのは、細菌の場合変異を丹念に分離した方が早いという考えがあった。そのため、○○菌といった名前をつけたたくさんの菌株を分離するのがメーカーの勝負になってきた。ただ、メカニズムについてはよくわかっていないことが多い。その意味でこのリソースは使い勝手があるのではないだろうか。おそらく大手のメーカーの投資が得られるのは間違いないと思う。
2025年3月16日
我々は様々なものを食べるが、動物性であれ植物性であれ、多くのタンパク質が含まれている。もちろん自己タンパク質ではないので免疫反応の対象になるが、消化管による分解を逃れた抗原も、制御T細胞を誘導することでアレルギー反応へ移行しないようにできている。この過程については、主に遺伝子改変動物を用いた多くの研究から樹状細胞サブセットが重要な働きをしていることがわかっている。
ただ遺伝子改変動物の結果を正常マウスと比較するためには、操作していない動物での樹状細胞 (DC) のサブセットを調べる必要がある。今日紹介するロックフェラー大学からの論文は、細胞同士で相互作用が起こるとき、相互作用した細胞をビオチンでラベルできる LIPSTIC というしゃれた名前の方法を用いて DC と T細胞の相互作用を調べ、制御性T細胞の誘導に関わる DC を特定した研究で、3月14日 Science に掲載された。タイトルは「Identification of antigen-presenting cell–T cell interactions driving immune responses to food(食物に対する免疫反応に関わる抗原提示細胞とT細胞の相互作用を特定する)」だ。
LIPSTIC と呼ばれる方法は以前も紹介したが (https://aasj.jp/news/watch/25129 ) 、この研究では活性化された T細胞に発現してくる CD40L にビオチン添加酵素 (St) を、結合する CD40 に基質 (G5) を融合させ、CD40L と CD40 が結合したときに細胞がビオチン化されるシステムを組み上げている。
全ての CD40 が G5 を発現しているマウスに、CD40L-St を持つ卵白アルブミンに対する T細胞を移植して、卵白アルブミン (OVA) を食べさせると、卵白アルブミン由来ペプチドを提示している DC のうち OVA特異的T細胞と反応する細胞がラベルされることになる。これによって、消化管に繋がるリンパ節でクラス II MHC依存的に T細胞と相互作用している DC を特定することができ、2種類の DC、すなわち DC1、DC2 両方が OVA特異的T細胞とクラス II MHCを介して相互作用していることがわかる。
この方法の利点は、こうして特定した DC を取り出して、試験管内でその機能を調べることができる。すると、ビオチン化された DC1 だけが制御性T細胞の誘導に関わっていることが明らかになった。もちろん同じリンパ節内で DC2 はヘルパーT細胞を誘導している。従って、このバランスが食物アレルギーを抑える方向維持することでアレルギーが防がれている。
これまでの研究で特に新生児期に制御性T細胞の誘導に関わるDCがRORγ陽性のDC1であることが指摘されており、これについてビオチンラベルされたDC1で調べると、食事をとって早い時間に制御性T細胞と反応するのがRORγ陽性DCで、制御性T細胞誘導自体にはRORγDC1が必ずしも必須でないことを明らかにしている。
このDC1,DC2のバランスを調べるため、制御性T細胞の誘導がうまくいかず、食物アレルギーを誘発してしまう寄生虫感染でDC1,DC2がどう変化するかを調べている。
長い話を短くすると、寄生虫感染によってDC1プログラムや移動が変化するわけではなく、寄生虫感染後もDC1細胞はリンパ節内に存在している。しかし、寄生虫感染による自然炎症の結果、DC2の割合が上昇して食品抗原をDC2により奪われた結果、DC1の機能が相対的に低下し、トレランスが維持できないことを示している。
以上が結果だが、印象としては我々の免疫は危なっかしいバランスの上に乗っていることが実感される研究だ。今後もLIPSTICの活躍が期待される。