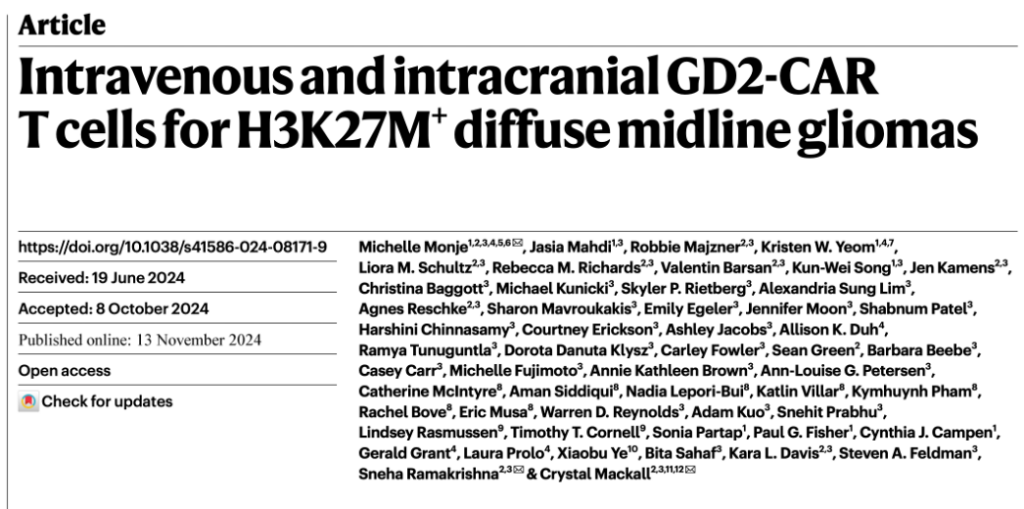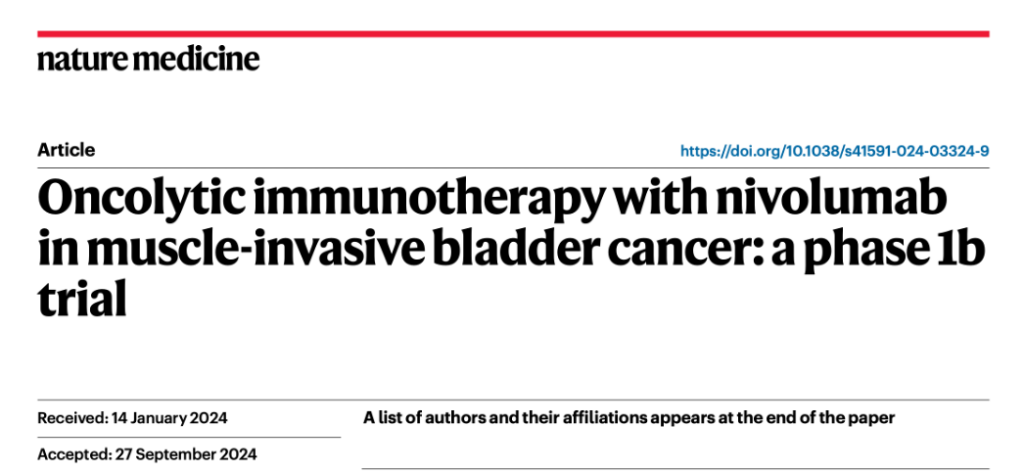2024年12月11日
現在は新型コロナ流行の底に有るようだが、新しい株も発見されている上昇してくるだろう。感染の波は何度も訪れているがパンデミック初期のような多くの死亡者を出すまでには至っていないのは幸いで、教科書通りウイルスとの共存状態が成立しているようだ。ただ、安心は禁物で、常に新しい状態に備える必要がある。その意味で、過去の例をゆっくり調べ直すことは極めて重要だ。
今日紹介する多くの機関が参加している Covid-19 国際研究チームからの論文は、感染後死亡までの鼻咽頭粘膜スワブのデータが揃っている40例の死亡例について詳しく解析した研究で、11月27日 米国アカデミー紀要 にオンライン掲載された。タイトルは、「Lethal COVID-19 associates with RAAS-induced inflammation for multiple organ damage including mediastinal lymph nodes(Covid-19 死亡例はRAAS により誘導された炎症による縦隔リンパ節変化を含み他臓器障害が認められる)」だ。
まず鼻咽頭スワブから死亡例では高いレベルの感染が認められる。また、呼吸器系以外の臓器でも細胞死に至る炎症が認められ全身に病気が広がっていることがわかるが、死亡時の肺以外の臓器では全くウイルスは検出されていない。従って、呼吸器感染からどのように全身病へと発展するかが問題になる。
解析は膨大で、気になった点は動物実験まで行ってデータを集めているので、ここのデータについて紹介するのは避ける。幸い、この論文はオープンアクセスで自由に図を見ることができるので、論文にアクセス後、最後に示されたサマリーの図をみながら読んでいただきたい(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2401968121 )。
タイトルにもあるように、全身に広がる最大の原因として RAAS(レニンアンギオテンシン系)の異常が重要な要因になっていると結論している。事実、患者さんでは遺伝性の血管浮腫の原因遺伝子の発現異常が認められ、レニンアンギオテンシン系が強く活性化され、その結果として血管炎症、さらに血栓が生じ、これが臓器のストレス反応を誘導している。さらに、フィブリン沈着により、補体系の活性化も誘導され、心臓、腎臓などの細胞の炎症反応から細胞死へのプロセスが進む。
これまであまり気づかれなかった病理所見として、やはりタイトルにあるように呼吸器につながる縦隔リンパ節でリンパ球の数が低下する一方、繊維化が進んでいることを報告している。これもおそらく一種のストレスによる炎症の結果で、ウイルスに対する特異的免疫が成立しにくい状態ができている。
この二つの原因が続くことで、各臓器の細胞で様々なストレスがかかり、これがそのままミトコンドリアの酸化的リン酸化の抑制、活性酸素の合成を誘導する。その結果、ミトコンドリアが破壊され、そこから DNA や RNA が放出されることで、ウイルス感染がなくても核酸センサーを介する自然炎症が誘導持続し、最終的に細胞死に陥ると結論している。
結果は以上で、進行例の治療の基本は、レニンアンギオテンシン系の正常化、ミトコンドリアの活性化、そして自然炎症の抑制になるが、抗体や抗ウイルス剤が存在する現在では、まず感染を早期に制御し、悪いサイクルが始まるのを防ぐことが最初の治療ラインになるだろう。弱毒化しているとは言え、直近の80歳以上の死亡率は5%程度で、感染すると100人に5人は亡くなる。その意味で、今こそ剖検例を詳しく検討し、全身に対する治療方法を確立することは重要だと思い、久しぶりに新型コロナの論文を取り上げてみた。
2024年12月10日
女性は卵子が成熟する卵胞期から、排卵期、そして黄体期を経て、月経と続く生理サイクルを繰り返しているが、このとき卵巣から出るエストロジェンは排卵期をピークに、またプロゲステロンは黄体期がピークになり、月経前に急減する。このほかにも下垂体系の卵胞刺激ホルモンや、黄体形成ホルモンが生理サイクルに合わせて上下する。閉経後は基本的にこれらのサイクルは停止する。とすると、当然閉経前のガン細胞もこのサイクルに影響されるはずで、ひょっとしたら治療効果も生理サイクルに影響されるかもしれない。といった素朴な疑問を真面目に調べたのが今日紹介するオランダ癌研究所からの論文で、12月4日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「The oestrous cycle stage affects mammary tumour sensitivity to chemotherapy(発情周期は乳ガンの化学療法に対する感受性に影響する)」だ。
ガンの化学療法により生理周期は乱されるため、生理サイクルとガンの治療開始時期についてあまり真剣に考えてこなかったことは確かだ。しかし乳ガンで手術前のネオアジュバント治療が当たり前になった今、治療開始時期には生理サイクルは維持されており、エストロジェン受容体を発現していることが多い乳ガンでは重要な問題になる。
これをマウスの乳ガンモデルで確かめたのがこの研究のハイライトで、まずガンの状態と生理サイクルを調べると、エストロジェンがピークになる排卵前後(動物の場合はこれをestrous(発情期)と呼び論文でもこの単語が使われているが、ここでは排卵期を用いる)で、ガン細胞の増殖は2倍近くになる。
乳ガンのプレアジュバント治療にはエストロジェン受容体阻害剤を用いることが多いが、この研究では系をシンプルにするため、増殖を抑制する抗ガン剤、doxorubicin あるいは cyclophosphamide に絞って投与時期による効果の差があるかを調べている。
結果は驚くべきもので、排卵期に投与した場合と、黄体ホルモンが高まりエストロゲンが低下する黄体期に投与した場合、ガン細胞の抑制効果は2倍に達する。これは一回投与の実験だが、その後生理サイクルが狂った後も抗ガン剤を1週間ごとに投与するプロトコルで生存期間を調べると、一ヶ月後の生存数が黄体期投与で0に対し排卵期投与で40%と大きな差になっている。
エストロジェン受容体がでているから当然のことかと思ったら、Brca1 陰性のトリプルネガティブ乳ガンでも差は大きくないが、やはり排卵期に化学療法を行った方が効果が高い。
そこでメカニズムを調べるため、ガン側の変化として化学療法に対する耐性を高める上皮間葉転換の可能性を調べると、確かに間葉転換が黄体期に起こっていることがわかった。ただ、これではトリプルネガティブ乳ガンについての実験結果を説明できないので、腫瘍血管を調べると黄体期の血管の内径は排卵期と比べ30%近く低下している。一方腫瘍組織に浸潤しているマクロファージの数を調べると、黄体期の方が遙かに高く、このレベルの差が治療中も維持されている。そこで、腫瘍組織のマクロファージを CSF-1 をブロックして除去すると、黄体期でも化学療法の効果が見られるようになる。このように、ガン細胞だけでなく、腫瘍組織を形成しているホスト側の細胞も生理サイクルにより活性が変わることから、エストロジェン受容体の発現に関わらず、ネオアジュバント治療は排卵期に行うことが良いと結論されている。
最後に、マウスの結果が人間にも当てはまるか、排卵期と黄体期をプロゲステロンの血中濃度で区別して、ネオアジュバント治療の効果を調べなおしてみると、一目瞭然、明らかにプロゲストロンが低いときにネオアジュバント治療を始めたときの方が効果が高い。
以上が結果で、極めて素朴な質問から初めて、臨床的には極めて重要な結論に到達している。今多くのガンでネオアジュバント治療が行われるようになっているので、他のガンでも同じことが言えるのか調べるとともに、エストロジェン受容体陽性の乳ガンに対しては排卵期から始めても良いと思う。私が患者なら、医者にそうお願いする。
2024年12月9日
筋肉を急に伸ばすと筋肉を収縮させて過度のストレッチが防がれるが、筋肉伸張を感知して反射を誘導するのが筋紡錘で、我々が安定した姿勢を保てるのも筋紡錘が大きく寄与している。ただ、筋紡錘のシグナルメカニズムについては研究する人も少なく、わかっていないことが多い。
今日紹介する Imperial College of London からの論文は、筋紡錘を単離して遺伝子発現を調べるところから始めて、筋紡錘は従来考えられていたように求心性の感覚神経と γ 運動の神経による支配を受けるだけでなく、筋紡錘カプセルと求心性感覚神経と密着したマクロファージにより調節されていることを示した研究で、12月4日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Macrophages excite muscle spindles with glutamate to bolster locomotion(マクロファージはグルタミン酸を介して筋紡錘を刺激し運動を支える)」だ。
この研究ではまず筋紡錘を分離し遺伝子発現を調べ、神経系の分子に加えて、免疫系の分子の発現が見られることを発見し、これと反応する血液細胞を探索した結果、CX3CR1 ケモカイン受容体陽性マクロファージが伸張レフレックスに関わる筋紡錘と固有受容感覚神経の接合部に接して存在することを明らかにしている。
続いて、筋紡錘と接するマクロファージの遺伝子発現を調べ、血液系の分子とともに、神経や筋肉に関わる分子を発現しているユニークなポピュレーションで、しかもグルタミン酸を分泌する能力があることを発見する。
そこで、光遺伝学システムを筋紡錘マクロファージ (MSMP) に発現させ刺激すると、筋紡錘の関わる伸張リフレックス回路に直接影響して、筋肉の収縮を誘導することを明らかにする。すなわち、筋紡錘による伸張リフレックスはマクロファージによっても調節されていることを発見する。この発見が研究のハイライトで、あとは調節に関わるメカニズムとしてマクロファージがグルタミンを取り込み、グルタミン酸へと転換して分泌することで、NMDA や AMPA などのグルタミン酸受容体を介して伸張レフレックスを調節していること、そして筋紡錘と相互作用しているマクロファージを欠損させると水泳中の足の動きの協調がうまくいかないことを明らかにして、筋紡錘が神経系だけではなくマクロファージともサーキットを形成して伸張レフレックスに関わることを明らかにしている。
結果は以上で、マクロファージ自体が神経系の持つ能力を獲得して、神経・筋回路に関われるとは驚きだ。しかも、神経自体もグルタミンを介してマクロファージを刺激でき、さらにマクロファージも神経と同じように Fos など神経興奮で誘導される転写因子を発現することを見ると、本当にうまくできていると驚く。
いずれにせよ、マクロファージを参加させることで、回路は神経系だけでなく、神経以外にも開かれることになり、筋肉疾患や筋トレーニングを新しい目で見ることが可能になると思う。
2024年12月8日
抗原に出会うと Notch シグナルが活性化して、同時に導入した遺伝子の発現のスイッチを入れる synNotch システムについては以前紹介した(https://aasj.jp/news/watch/21145 )。この論文では、腫瘍特異的 CAR-T に IL-2 を分泌させる synNotch システムを組み込んで、CAR-T が腫瘍に到達したときキラー標的抗原を synNotch 刺激にも使いキラーが働く局所だけでT細胞を増殖させる方法で、CAR-T が苦手とする固形ガンの増殖を見事に抑制しているのに驚いた。残念ながら ClinicalTrial Gov. で調べても IL-2 の治験は登録されていないが、synNotch でキメラT細胞受容体が発現する And型の CAR-T は現在リクルートが進んでいるようだ。
今日紹介する、同じカリフォルニア大学サンフランシスコ校から12月6日 Science に発表された2編の論文は、同じ synNotch を使うと、免疫を抑制するサプレッサーT細胞を作ったり、あるいは脳でだけ働くキラー細胞やサプレッサーT細胞をつくることが可能で、様々な分野に応用が可能になることを示した研究だ。タイトルは、「Engineering synthetic suppressor T cells that execute locally targeted immunoprotective programs(局所で免疫反応を抑える人工サプレッサーT細胞)」と、「Programming tissue-sensing T cells that deliver therapies to the brain(組織を感知してそこでだけ治療効果を発揮するT細胞をプログラムする)」だ。
基本は synNotch で特定の抗原に反応して転写がオンになるシステムだ。今回は、免疫を抑制するサプレッサーシステムの設計で、局所で免疫抑制サイトカインが分泌されるよう設計している。これまでも抑制性 CAR-T をデザインする試みは行われてきたが、この研究ではい免疫抑制性サイトカインだけでなく、いくつかの遺伝子も加えてデザインし、様々なコンストラクトを調べ、最終的に TGFβ1 と CD25 を同時に発現さる synNotch コンストラクトが、キラー細胞の増殖を抑え、標的細胞を守る効果があることを明らかにする。CD25 は最初組織中に分泌されている IL-2 を取り除いて他の細胞の増殖を抑える目的で発現させるが、その後の実験でサプレッサー細胞に選択的に IL-2 が利用されるのも助けていることがわかった。
タイトルを見て IL-10 を使うのかと思ったが最終的に TGFβ1 担ったのも面白く、実験的に確かめて最も有効なシステムをくみ上げている。最初は移植した腫瘍に対する CAR-T の作用を抑えることを指標としてサプレッサーT細胞機能を詳しく検討したあと、最後は試験管内で形成させた膵臓 β細胞に対するキラーT細胞をサプレッサーT細胞で抑えられるか検討している。
もちろんこの方法を1型糖尿病の発症予防に使うことを目的でシステムを構築しており、人工的抗原を発現させた β細胞を移植し、これに対するキラー活性をがサプレッサーT細胞により抑えられることを示している。
残念ながら NOD マウスの糖尿病発症抑制実験までには行っていないが、すでに特異抗原に対する抗体は開発されているので実験が行われていると思う。これができると1型糖尿病の発症抑制が現実のものとなる。
もう一つの論文は、現在 synNotch を用いる治験の対象になっている、グリオーマ治療の特異性を高めるためのシステム構築になる。グリオーマに対する CAR-T 治療は期待を集めているが、標的に選ぶ抗原の特異性の問題がつきまとう。そこで、脳には発現していない抗原を選んだ上で、これに対するキメラ受容体を、脳組織だけに存在する分子でスイッチが入る xynNotch を用いて誘導し、脳でしか働かない CAR-T の開発にチャレンジしている。
研究のハイライトは、脳特異的な分子の特定で、最終的に BCAN と呼ばれるマトリックス分子に対する抗体を用いた synNotch を構築し、これによりグリオーマに発現する抗原を標的にしたキメラ受容体をただ発現させただけの CAR-T と比べても強い活性を持つキラー活性を誘導できることを示している。同じ腫瘍を脳以外に移植した場合は、全く抑制できないことから脳特異的に働く CAR-T ができた。
最初、synNotch として発現させる抗体によって脳内にトラップされ、腫瘍に到達できないのではと思ったが、全く杞憂で、この形で様々なケモカインも誘導でき、腫瘍にしっかり到達して、高い活性を示してる。
また、この方法を脳に転移した乳ガン特異的キラー細胞として使えることも示しており、かなり大きな期待ができる。
そして最後に同じ synNotch システムで IL-10 を誘導することで、多発性硬化症のような脳内での免疫性炎症を抑えられることまで示している。
結果は以上で、同じシステムの使い回しで、多様な免疫操作が可能になることが示されており、またこのシステムの治験も始まっているようなので期待できる。
2024年12月7日
コーンシロップという形状で多くの飲料や食品に果糖が含まれており、我々の健康を損なっていることがわかっている。小腸上皮で代謝されるが、そのキャパシティーを超えると直接肝臓に果糖が流れ込んで脂肪肝の原因になる。さらに、APC遺伝子欠損マウスのポリープ発生をコーンシロップが上昇させることも知られており(https://aasj.jp/news/watch/9897 )害は代謝にとどまらない。
今日紹介するワシントン大学からの論文は、腫瘍の増殖速度を果糖摂取が上昇させるのは、果糖が直接ガンの栄養補給に寄与するのではなくホストの肝臓で処理された脂質が増殖を助けていることを示した研究で、果糖の効果の複雑さを示す典型研究。12月4日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Dietary fructose enhances tumour growth indirectly via interorgan lipid transfer(食品に含まれる果糖は臓器間の脂質の移動を通して間接的に腫瘍の増殖を高める)」だ。
これまでも腫瘍の増殖を果糖が促進することは報告されており、この研究でもゼブラフィッシュ、マウスの移植ガン実験システムを用いて、果糖摂取がガンの増殖を促進することを確かめている。最初はメラノーマを用いて調べていたが、乳ガンや子宮頸がんでも同じ効果が得られることを確認し、一般的にガンの増殖はフルクトース摂取により促進されると結論している。実際示された図を見ると、効果は著しく、ガンによっては1ヶ月後のサイズが2倍を超える場合も見られ、驚く。これを見るとガンがあるとわかったら、間違ってもコーンシロップ入りの清涼飲料水を飲まないようにしようと思う。
ただ、これは移植ガンの話で、試験管内でのガン増殖系に直接果糖を加えても何の効果もない。これは、ガン細胞では直接果糖から F6P が形成される酵素システムがないためで、ガンが果糖をエネルギーとして利用できる能力は限られている。
とすると、果糖が肝臓で処理されるときに、ガンの増殖を助ける分子が形成されると考えられる。そこで果糖を摂取したとき肝臓で合成されるガン細胞で消費される分子を探ると数種類の lysophosphatidylcholin (LPC) がクローズアップされてきた。果糖の利用に必要なKHK阻害剤を投与すると、LPC の合成が抑えられ、腫瘍の増殖も低下する。また LPC を直接投与すると、ガンの増殖が促進される。そして、腫瘍は取り込んだ LPC をポスファチジルコリンに転換して利用していることを明らかにしている。
結果は以上で、最終的にエネルギーとして果糖が使われているわけではなく、肝臓で副産物として合成される細胞膜の成分フォスファチジルコリンの材料を提供され、分裂に利用していることが示されている。エネルギーだけでなく、様々な材料を使い尽くそうとするガンの姿を見ることができるが、逆から見ると、ガンは兵糧攻めに弱いことになる。繰り返すが、ガンと診断されたら間違ってもコーンシロップを含む飲料や食品は避けた方がいい。
2024年12月6日
自閉症のゲノムについては解析が進み、レアバリアントとコモンバリアントが統合された一つの状態が神経回路形成に影響して起こると考えられている。一方で、自閉症の細胞で見られる頻度の高い変化を捉えようとする試みも行われ、その一つが2019年、このブログで詳しく紹介したスペイン・オチョア分子生物学研究所からの研究(https://aasj.jp/news/autism-science/11072 )で、自閉症神経細胞ではCPEB4 と呼ばれる mRNA の polyA の長さを調節する分子のエクソン4番が飛んでしまっている率が高く、この結果神経機能に関わる様々な分子の翻訳が低下すること、その結果マウスでは自閉症に見られる症状が現れることを示した素晴らしい研究だった。
ただ、ではなぜ小さなエクソンが欠失した分子が少し増えるだけでかなり大きな翻訳の変化につながるのかの詳しいメカニズムは示されていなかった。今日紹介するスペイン生物医学研究所からの論文は、2019年の論文の続報で、CPEB4 の小さなエクソンが相分離やタンパク質の凝集の調節に関わることを示した研究で、12月4日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Mis-splicing of a neuronal microexon promotes CPEB4 aggregation in ASD(神経細胞で CPEB4 のミクロエクソンがスプライス異常を起こすことで CPEB4 の凝集が起こることが ASD に関わる)」だ。
CPEB4 のように特定の標的分子がない場合は、その量の調節が重要になる。これまでの実験で、この量の調節に CPEB4 の相分離が重要な役割を演じていることがわかっていた。余談になるが、以前紹介したように MECP2 も相分離によりクロマチンの構造を決めており(https://aasj.jp/news/watch/13574 )このバランスが崩れることで、多くの遺伝子の発現が上昇したり、抑えられたりして病態を形成しているようで、相分離は今後の研究の重要な鍵になりそうだ。
研究ではまず GFP で CPEB4 を標識し、神経細胞の定常状態で相分離して存在していること、そしてこの相分離が神経の脱分極に伴う pH 変化により誘導され、相分離体は CPEB4 を隔離して機能を抑制する働きがあることを示している。
次に、自閉症で高率見見られる BPEB4 エクソン4欠損(Δ4)の相分離を調べると、Δ4 分子は相分離から溶けでやすいことがわかった。とすると、機能が高まっていいはずなのになぜ翻訳の低下が起こるのかを相分離だけでは説明できない。CPEB4 の分子構造は相分離だけでなく、タンパク質凝集にも関わることを示しているので、次に凝集塊の形成をしらべると、Δ4 では不可逆性の凝集が形成されやすく、しかも少しだけ存在するだけで相分離体の中で正常な CPEB4 も巻き込んだ凝集体を形成し、CPEB4 機能を抑制していることがわかった。
この凝集体形成には CPEB4 のヒスチジンクラスターによることがわかるが、Δ4 に存在するアルギニンクラスタがこれを抑制していると考えられる。とすると、Δ4 ペプチドだけでもヒスチジンクラスターによる凝集を阻害できると考えられ、Δ4 を模したペプチドを Δ4 欠損分子に加えると、凝集形成を抑えることができる。
以上、このペプチドを用いて治療できるかどうかわからないが、なぜ神経症状が中心なのか、なぜ少しの Δ4 欠損分子の存在が翻訳異常を誘導するのかなどがよくわかる研究だと思う。
しかし MECP2 といい CPEB4 といい、神経細胞では相分離、タンパク質凝集という視点から以上を見直すことの重要性がクローズアップされた感がある。
2024年12月5日
最初糖尿病の治療薬として開発された GLP-1 受容体アゴニスト (GLPRA) が今や抗肥満薬として大ブレークし、その結果研究がさらに進んでいることについては何度も紹介してきた。GLPRA は食欲抑制、代謝改善が重要な作用だが、中枢神経系では吐き気など食べることを忌避する作用があり、代謝改善ではインシュリン分泌促進の作用が重要な位置を占める。そのためすでに糖尿病になっている患者さんでの抗肥満効果は低い。このようなことから、現在糖尿病治療の重要な課題は、身体のインシュリン感受性を上昇させ代謝を改善させる薬剤の開発だ。
今日紹介する、デンマーク コペンハーゲン大学のノボノルディスク代謝基礎研究所からの論文はこれまでとは全く異なるメカニズムの抗肥満薬の開発で、デンマークやノボノルディスクがこの分野で圧倒的リードを保っていることを実感させる研究だ。タイトルは「NK2R control of energy expenditure and feeding to treat metabolic diseases( NK2R はエネルギー消費と摂食をコントロールして代謝病を治療できる)」だ。
結論的に言うと、脳に働いて摂食は抑制するが食に対する忌避反応がほとんどなく、身体全体のインシュリン感受性を高め、脂肪を燃やしてエネルギー消費を高めるニューロキニン2 受容体 (NK2R) アゴニストを開発したという研究だ。
おそらくこのグループも最初からここまで素晴らしい結果が得られると予想しなかったのではないかと思う。最初は、GLPRA の大成功の柳の下の泥鰌を探すために HbA1c の値と相関が見られる GPCR 遺伝子をゲノム解析を通して探索し、その近くにヘキソキナーゼ遺伝子があるため、それとの相関として片付けられていた遺伝子多型の一つがニューロキニンなど様々な生理ペプチドと反応する NK2R とリンクしていることを発見する。また、グリーンランドのゲノムコホートから NK2R の発現が高まると、HbA1c が低下し、グルコース代謝が改善していることを発見する。
そこで、NK2R を刺激するニューロキニンをマウスに毎日投与すると摂食が抑制され、2週間で体重が15%低下、さらに筋肉量などはそのままで脂肪だけが減少することがわかった。ただ、ニューロキニンA は分単位で血中から除去されるので、長期血中濃度を維持できる EB1001、そして EB1002 と呼ぶペプチドリガンドを開発している。EB1002 は一回皮下投与するとすぐに酸素消費が高まり、脂肪酸が上がり、体重が数パーセント低下する。また摂食も強く抑制されるが忌避行動は見られない。
重要なのはインシュリン分泌には全く影響なく、hyperinsulinaemic-eugycaemic クランプ実験で、インシュリン感受性が高まることで、グルコース代謝が高まることを示している。まさに、長く望まれていた薬剤に行き当たったことになる。
驚くのはレプチンが欠損した ob/ob マウスの肥満も治せることで、レプチン受容体を介する刺激とは別に、脳に働いて摂食を抑えるとともに脂肪を燃やして肥満を改善する。これまでと全く異なるメカニズムなので、多くの遺伝性肥満にも対処可能かもしれない。
ただ、摂食行動や代謝改善メカニズムに関しては、ともかく様々な細胞に働いて良い効果があるとまとめた方がいいぐらい特定の細胞経路があるわけではない。EB1002を投与すると、確かに視床下部の神経が反応するがそれ以外に脳全体で反応が見られることから、様々なルートで摂食が阻害される。
また、体温計を身体の各所に埋め込んで体温の上昇を調べると、場所ごとに体温上昇の時間に差が見られるなど、これまでの単純な常識ではまだ理解できない。実際、この受容体は体中で発現していることから、その特定は難しいかもしれない。
ただ、臨床応用への期待は大きいので、老化サルを用いた投与実験を行い、GLP-1 などのような吐き気や不安感は認められないこと、糖尿病のサルもコンスタントに体重を低下させられること、インシュリン感受性を高めて血中グルコースを抑えることができること、インシュリン分泌に全く影響ないので低血糖発作はないこと、脂肪代謝を改善し、LDLやトライグリセライドを低下させられることなど、まさにいいことずくめの薬剤であることを示している。
さてこのまま人間を用いた治験に進むか決断の問題だと思うが、うまく行くような気がする。しかし多くの細胞に作用があることから、ガンの増殖を促進したりと言った可能性もあるので慎重に治験は進められるだろうがノボノルディスクの快進撃は止まりそうにもない。
2024年12月4日
重力の小さい宇宙で暮らす宇宙飛行士では骨量の減少が起こることが知られているが、現象の背景に2021年ノーベル賞を受賞したメカノセンサーが関わるのではないかと考えられている。特にそのうちの一つ PIEZO は純粋なメカノセンサーで、体中の細胞に発現している。
今日紹介するフランス・キュリー研究所と、カナダのトロント小児病院からの研究は PIEZO の腸管幹細胞システム維持に関わる役割を調べた研究で、11月29日号の Science に掲載された。タイトルは「PIEZO-dependent mechanosensing is essential for intestinal stem cell fate decision and maintenance( PIEZO によるメカノセンシングは小腸の幹細胞維持と運命決定に必須)」だ。
私がまだ現役時代から様々な幹細胞にストレッチを与えたり、あるいはマトリックスの高度を変化させたりしてその機能変化を調べる研究が行われていた。ただ、なかなか面白い現象を超えて研究が進展することが難しかったが、メカノセンサーを担う PIEZO 分子が発見され研究は急速に進展しており、その典型がこの研究だろう。
腸管では OIEZO1、PIEZO2 の2種類が働いており、片方がなくなるともう片方の発現が上がるので、片方をノックアウトしてもマウスに異常は起こらない。この研究では、タモキシフェンを投与したとき PIEZO1/2 両方がノックアウトされるマウスを作成し、成長してからタモキシフェンを投与、腸管の変化を調べ、幹細胞システムが大きく変化していることを発見する。
まず、絨毛の長さが低下する一方、組織の内側に形成されるクリプトが拡大している。この拡大はクリプト内で増殖する細胞が増えているからだが、最も未熟な幹細胞の数は減少している。さらに幹細胞維持に必要な分泌性のパネット細胞も消失していることがわかった。
この組織像の背景にあるメカニズムを、オルガノイド培養や、single cell RNA sequencing を用いて検討し、腸管幹細胞システムで PIEZO の下流で働いている分子メカニスムを解明しており、以下のようにまとめられる。
PIEZO の活性化によるカルシウムの細胞内への流入は、Wnt の発現を低下させる一方で、NOTCH の発現を上昇させる。
NOTCH の発現が低下すると、パネット細胞への分化が抑制され、幹細胞のニッチが形成できなくなる。一方で、パネット細胞へ分化できないため、Transit Apmlifying 細胞と呼ばれる増殖細胞への分化が進み、増殖が高まる。
パネット細胞の低下と、Wnt 発現の低下により未熟幹細胞の維持ができなくなる。
基本的には、幹細胞分化が変化して、ニッチが形成できないため、幹細胞自身が消失するというシナリオになる。
最後に、腸管幹細胞のメカノセンサーが活性化されるメカニズムを探り、以下のことを明らかにしている。
幹細胞を固いマトリックスの上で培養すると上昇する。
原子間顕微鏡で腸管のマトリックスの堅さを調べると、幹細胞の回りの基底膜は固い。
絨毛形成や蠕動運動で生じる幹細胞のストレッチも PIEZO を活性化する。
以上の結果から、腸管幹細胞は常に環境のストレスをメカノセンサーを介して感知することで、NOTCHシグナルを調節して上皮細胞とパネット細胞への分化を調節し、一方で Wnt 分子発現を通して幹細胞の自己再生を促している。
細胞への力学的力の作用を知って驚いていた時代と比べると、研究が大きく進展したことを実感することができた。
2024年12月3日
今日は最近気になった臨床研究をいくつか紹介する。
まずは、米国・サウスカロライナ大学から11月27日 JAMA に発表された論文で、25歳以下の女性の子宮頸がんの死亡率調べたものだ。米国では子宮頸がんワクチンが2006年に導入され、2022年以降12%づつ25歳以下の子宮頸がんの発生率が低下していることがすでに報告されている。この研究ではさらに死亡率について、ワクチンの効果が見られる以前からの推移を調べた研究になる。死亡率はワクチン接種が始まる前から、コンスタントに低下する傾向にあったが、2013年から急に大きな低下が見られ21年まで続いている。すなわちワクチン効果が10年以内に死亡率として明らかになっている。しかし米国でも Covid-19 パンデミックで接種率が2年間低下し、またその後も接種率の上昇が鈍いことから、この影響が2030年ぐらいから死亡率の上昇としてみられることが懸念される。
次の英国・University College Londonからの論文は、文献調査に基づいてアルツハイマー病 (AD) の Aβ に対する抗体治療を行った際の副作用として考えられる脳萎縮について議論した研究で The Lancet Neurology の10月号に発表された。結論的には、抗体治療で Aβ が除去率が高い薬剤ほど脳萎縮が認められるが、症状レベルでは臨床的に問題が起こっていないことを示している。特に効果が高い薬剤ほど全体が萎縮し、脳室が拡大することがわかる。従って、脳萎縮に関してはアミロイド除去による疑似萎縮と考え、副作用として捉える必要がないと結論している。メカニズムに関しては、蓄積された Aβ が除去される効果、アミロイドに対する炎症反応の低下、アミロイドによる脳の浮腫の軽減などが考えられるが、これについては病理解剖をベースにした詳しい研究が必要だと結論している。いずれにしても、長期にわたる追跡調査が必要だ。
3編目は、米国スタンフォード大学を中心とするグループが11月29日 Nature に発表した論文で、主に小児の脳幹部に起こるびまん性正中グリオーマお対する CAR-T 治療だ。この疾患は平均生存率が11ヶ月と極めて悪性の腫瘍で、ほとんど治療法がない。この中でヒストンH3 の変異が認められるグループは disialoganglioside (GD2) を強く発現しており、これを標的とした抗体を用いてキメラT細胞受容体を構築し、これを患者さんのT細胞に導入する CAR-T 治療を行っている。
リンパ球除去処理のあと、まず静脈注射を行い効果が見られるケースは、脳室内注射を繰り返す治療を行っている。基本的にはコントロールをとらない治験だが、2例は脳室内移植を受けずになくなっているが、残りの患者さんは1-3ヶ月ごとに注射を続けている。13人の患者さんのうち、4例では腫瘍の高度の縮小が見られ、20ヶ月以上の生存が可能になっている。そのうち一人は完全に腫瘍が消失し、あと3例でも縮小が見られている。症状レベルでは9例で改善が見られたことから成功と判断し、今後はリンパ球除去処理なしに最初から脳室内投与を行う新しい治験が進行しているようだ。副作用については、投与後全員に免疫反応による炎症が発生するが、これ自体は予測可能でコントロール可能であると結論している。しかし30ヶ月を超えて生存している2人以外は亡くなっており、この差の理由の検討も今後の課題だと思う。
最後は筋肉に浸潤した膀胱ガンに対する腫瘍溶解性ウイルスと免疫チェックポイント治療の組み合わせの第一相治験で、11月9日 Nature Medicine にオンライン掲載された。
これは Rb1 シグナルの機能異常が見られる腫瘍でのみ増殖できるアデノウイルスに、GM-CSF遺伝子を組み込んで、腫瘍を溶解しながら局所的にガンに対する免疫を高め、さらに抗PD-1抗体で免疫機能を高め、腫瘍溶解によるガン抗原を用いてガン特異的免疫を高める治療だ。これを手術前に行っており、手術後免疫機能を高めることができたか組織学的に調べることができる。
面白いのは治療法で、膀胱内にウイルスを詰めた溶液を注入し、1時間排尿を抑制して膀胱内でウイルスを感染させている。第一相試験なので副作用に重点が置かれているが、21人中17人がプレアジュバント治療を終えている。効果だが、治療を中断した3例に加えて、2例が途中で死亡、最終的に17例が手術まで進んでいる。
組織的には T細胞の浸潤が広く認められ、これが腫瘍縮小と強く相関している。さらに免疫効果の指標となる、ガン組織内に形成されるリンパ節用構造も得られることから、進行したシスプラチンに反応性がない膀胱ガンの治療として可能性が高い。
以上のように、腫瘍溶解だけで腫瘍を制御するのではなく、抗原を湧出させて免疫反応を誘導する方法は今後も期待できる。
最後は筋肉に浸潤した膀胱ガンに対する腫瘍溶解性ウイルスと免疫チェックポイント治療の組み合わせの第一相治験で、11 月9 日Nature Medicine にオンライン掲載された。 これはRb1 シグナルの機能異常が見られる腫瘍でのみ増殖できるアデノウイルスに、GM-CSF 遺伝子を組み込んで、腫瘍を溶解しながら局所的にガンに対する免疫を高め、さらに抗PD-1 抗体で免疫機能を高め、腫瘍溶解によるガン抗原を用いてガン特異的免疫を高める治療だ。これを手術前に行っており、手術後免疫機能を高めることができたか組織学的に調べることができる。 面白いのは治療法で、膀胱内にウイルスを詰めた溶液を注入し、1 時間排尿を抑制して膀胱内でウイルスを感染させている。第一相試験なので副作用に重点が置かれているが、20 人中17 人がプレアジュバント治療を終えている。効果だが、治療を中断した3 例に加えて、2 例が途中で死亡、最終的に17 例が手術まで進んでいる。 組織的にはT 細胞の浸潤が広く認められ、これが腫瘍縮小と強く相関している。さらに免疫効果の指標となる、ガン組織内に形成されるリンパ節用構造も得られることから、進行したシスプラチンに反応性がない膀胱ガンの治療として可能性が高い。 以上のように、腫瘍溶解だけで腫瘍を制御するのではなく、抗原を湧出させて免疫反応を誘導する方法は今後も期待できる。
2024年12月2日
Richard Young はエピジェネティックス、すなわち遺伝子発現の調節研究領域の大御所で、このブログでもすでに8編の論文を紹介している。各論文にはいつも新しい視点や方法が示され、どうしても紹介したくなる。個人的には、2011年3月神戸のCDBシンポジウムを開催したとき、東日本大震災の3日後の開催で多くの講演者のキャンセルが出たにもかかわらず、参加してくれたのを感謝している。
今日紹介するのはこの Young 研究室からの新しい論文だが、なんと遺伝子発現とは全く関係のない分野で、しかも Proteolethargy (タンパク質沈滞)という言葉まで作って、細胞内のタンパク質の運動と慢性病との関係を考えた研究で、おそらく相分離や転写に必要なタンパク質の動態を研究する中で見つけた問題をまとめたのだと思うが、タイトルを見て一瞬 Young の大変身かと錯覚した論文だった。タイトルは「Proteolethargy is a pathogenic mechanism in chronic disease(タンパク質沈滞は慢性病の病因の一つ)」で、11月27日 Cell にオンライン掲載された。
研究では核内の様々な機能に関わる4種類のタンパク質と細胞膜タンパク質に蛍光タグをつけ、こうして発現した細胞内のタンパク質の一分子を高感度顕微鏡を用いて追いかけている。高感度顕微鏡で一分子をキャッチできるのはわかるが、多くの分子の存在する中で追跡する方法の詳細については完全に理解できたわけではない。この方法に蛍光をブリーチした細胞領域に蛍光が回復する時間も細胞内分子運動の指標として用いている。
結果だが、選んだ5種類のタンパク質の全てで、single molecule tracking (SMT) が可能で、この運動が高濃度のインシュリンに細胞が晒されることで20%程度低下することを示している。ここでは、高カロリー食でインシュリン抵抗性が発生した状態を想定し慢性病の一つとして考えているが、次は様々なストレスで起こる活性酸素発生が高まった状況を慢性病の細胞状態として調べ、選んだ全てのタンパク質の細胞内運動が低下していることを発見し、この状態を Proteolethargy と名付けている。
次に Proteolethargy の原因の探索に移っているが、活性酸素上昇で発生することをヒントに、おそらく分子表面に存在するシステインが S-S 結合することでタンパク質同士がつながってしまい、動きが低下するのではと仮説を立て、表面にシステインが存在しないタンパク質の動きを同じように追跡すると動きは低下しないことを発見する。
そこで、システインが5個つながったタンパク質の動きを検出するシステムを作成し、感度を高めた上で高グルコース、高脂肪、炎症、DNA損傷、そして自然免疫刺激など慢性病の一般的原因と考えられている刺激を加えてタンパク質の動きを調べると、全ての条件で Proteolethargy が発生していることを確認している。
これらの条件の多くで活性酸素が発生しており、さらに活性酸素を除去する処理を行うと Proteolethargy が改善するので、Proteolethargy は細胞内活性酸素上昇が主要因であると結論している。
以上が結果で、まとめると様々な慢性病では細胞内活性酸素が上昇し、これがシステインを分子表面に露出しているタンパク質同士の結合を促し、細胞内でのタンパク質の運動を低下させる。この結果、分子間相互作用の頻度が抑えられ、非特異的に細胞全体の様々な活性が低下し、病気になるというシナリオだ。
おそらく、核内での分子同士の集合解離を正確に調べているうちに発想した研究で、Young の大変身ではないだろうが、活性酸素上昇という周知の話に違う視点を与えたさすがのまとめ方と感心した。
余談になるが、イタリアの大作曲家ベルディは生涯悲劇を中心としたオペラを書き続けたあと、最後に喜劇「ファルスタッフ」を作曲するが、この論文を読んでファルスタッフを思い浮かべた。