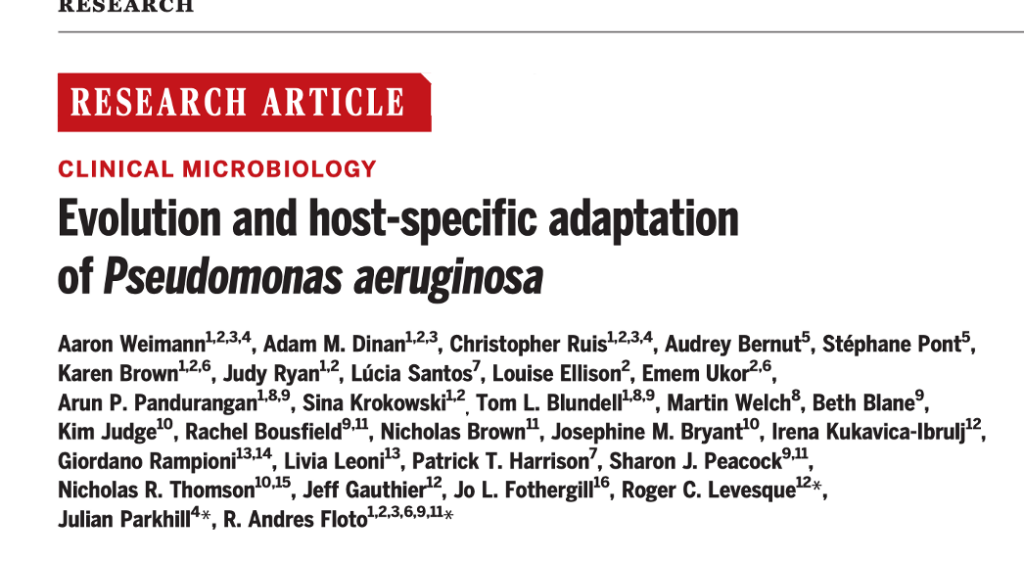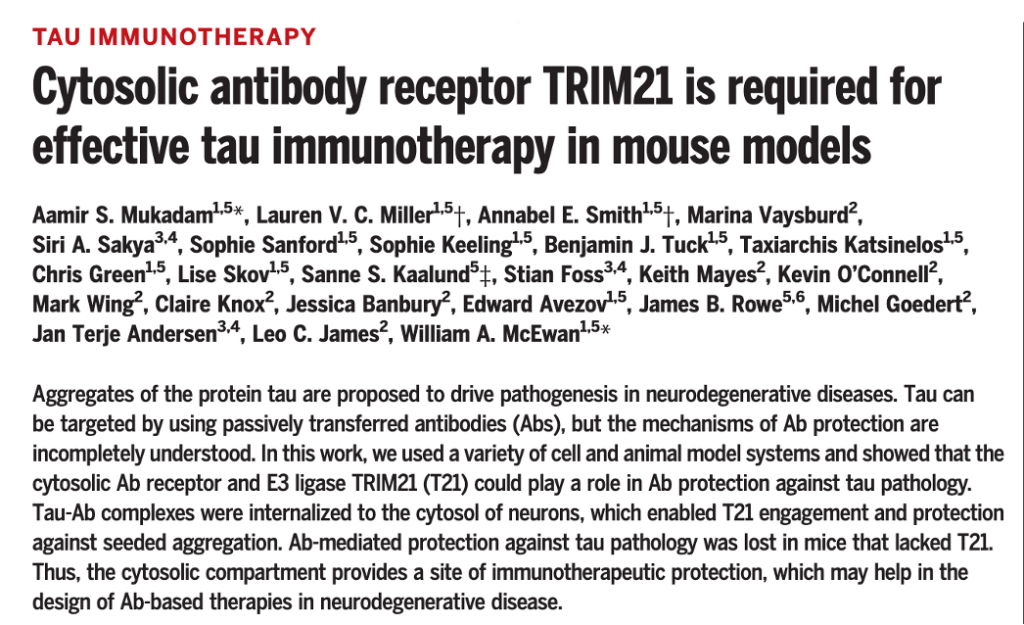2024年7月14日
原生動物と人間の関係というと、マラリアやアメーバ赤痢と言った感染症を思い浮かべるが、病原性がないどころか、人間に益をもたらす原虫も存在するようで、今日紹介するイタリアトレント大学を中心とする国際チームからの論文は、ブラストシスティスと呼ばれる、大量に増殖すると消化管症状を起こすことがある病原性の低い原虫の存在が、健康的な生活スタイルのバロメータとして使えることを示した不思議な研究で、7月8日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Intestinal Blastocystis is linked to healthier diets and more favorable cardiometabolic outcomes in 56,989 individuals from 32 countries(腸管のブラストシスティスは健康的な食事とリンクしており、代謝系や循環器の健康増進と関わる可能性が32カ国56989人の研究から明らかになった)」だ。
元々イタリアのコホート研究でブラストシスティスの腸内での存在がグルコース代謝や脂肪代謝の健康度にリンクしていることが明らかにされており、この研究はそれを確認するための共同研究になる。
便を採取して細菌叢を調べた世界中のコホート研究データから、ブラストシスティスゲノムの存在を探し出し、様々な健康指標と相関させたのがこの研究になる。しかし、世界32カ国でこのレベルのコホートデータが存在し、探す気になれば原虫のデータも集められることは素晴らしい。ただ、はっきり言って、データは多様で、一定の相関が検出できても、原因か結果かを示すところにまでには至っていない。
それでも面白いデータが満載で、まず世界分布を調べると、最も感染が多いのがフィジーで、あとはヨーロッパやアフリカが多い。一方、我が国は中国とともに感染者の低い国になる。面白いのは、ヨーロッパに多い原虫と、アフリカに多い原虫が異なる点で、生活スタイルに強くリンクしていることが示唆される。
調べたコホートでは、新生児の便にはブラストシスティスは全く検出されない。従って、成長する間に感染することになるが、人間で見られるブラストシスティスは動物には全く存在しないので、主に家族内で経口的に伝搬していると考えられる。
一卵性、二卵性双生児での感染様態を比べると、ホストの遺伝的要因には全く影響されず、基本的には生活スタイルを共有することが感染を決めていることがわかる。
この研究のハイライトは、いわゆる健康的食事と言われる食事の摂取とブラストシスティスの相関が、世界中のコホート研究で認められていることで、食の健康度の指標として用いられる指標 hPDI を使うと、ブラストシスティスの感染程度と hPDI に正の相関が見られる。
実際に食が原因である可能性を調べるために、食事を改善するコホート研究のデータを調べ直すと、改善することで新たにブラストシスティス感染した人の数が増えたことを示しているが、メカニズムもよくわからないので、このデータだけでは原因か結果かは結論できないだろう。
次に、病気や健康指標との関係を調べている。便の細菌叢を調べた様々な病気に関するコホートでは、ブラストシスティスはほとんどの場合健康コントロール群で多いことから、健康のバロメータにはなっている。
また、BMI など体脂肪や血圧などの健康指標と相関する。ただ、これも食事と相関するとするとブラストシスティスの直接の影響かどうかわからない。
最後に、細菌叢とブラストシストィストの相関を調べると、一般的に健康的細菌叢と言われているパターンと相関しているが、これも原因か結果かはわからない。
以上が結果で、原虫という意外な健康的食生活のバロメータが見つかったという以外にはなかなかはっきりした結論が出ないが、しかし目の付け所は面白い。おそらく、感染実験まで行く予感がするが、非病原性の原虫を含む飲料まで行ってしまうかもしれない。
2024年7月13日
現在、糖尿病治療薬の市場規模は、抗腫瘍治療薬の半分に達しようとするところまで進展しており、これは患者さんが増えるだけでなく、新しい糖尿病治療薬が使われるようになったことが大きい。中でも GLP-1 阻害薬は、糖尿病患者さんにとどまらず、糖尿病予備軍の抗肥満剤として使われるようになり、大ブレークしている。さらに、安全性が高いことが治験で示された結果、診察なしのオンライン診療による処方が我が国で拡大し、製薬会社も対応に困っているようだ。
GLP-1 の抗肥満作用はもちろん膵臓への作用を介する部分もあるが、もう一つの重要な経路は脳に働いて食欲を抑える作用だ。その結果、副作用として特に治療開始時に吐き気が見られるが、これは GLP-1 が直接脳に作用することを示している。今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、マウスを使って GLP-1 阻害薬に対する脳の反応を調べた研究で、7月10日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Dissociable hindbrain GLP1R circuits for satiety and aversion(後脳の食への満足と忌避の GLP-1 受容体回路)」だ。
驚くことに GLP-1 受容体(G1R)は脳の様々な場所に発現している。この研究ではまず異なる部位の G1R 発現細胞を特異的に除去したときの GLP-1 の体重抑制作用への効果を調べ、後脳の背側迷走神経(DVC) を除去したときのみ体重減少が抑えられることを明らかにする。マウスの結果ではあるが、正常マウスへの影響と比べると、脳への作用が体重減少にかなり寄与していることがよくわかり、まさに GLP-1 作動薬が脳作用薬であることがわかる。
これまでの研究で、GLP-1 は脳で満腹感の誘導とともに、食べ物への拒否感を誘導することで体重抑制に寄与していることが知られている。すなわち、GLP-1 により反応する異なるDVC回路が存在するはずで、それぞれの機能に対応するDVC領域の特定を次に行っている。
DVC には GLP-1 に同じように反応する2つの部位(APとNTS)が存在し、APは吐き気を誘導する薬剤刺激に、NTSは満腹感を誘導する経腸栄養薬刺激に強く反応することがわかった。
そこで、それぞれの領域を個別に遺伝的操作を行い、GLP-1 刺激に対しても、AP領域が吐き気などの食への拒否感、NTSは満足感の誘導に関わることを明らかにする。それぞれの領域は外側結合腕傍核と視床下部室傍核へ投射しているが、異なる神経細胞と結合して、食への拒否感と満腹感を誘導していることを示している。
そして、AP領域の神経活動を抑えて食への拒否感を消失させても、NTS刺激による満腹感の誘導だけで GLP-1 は十分体重減少効果を発揮できることを示している。
以上が結果で、まとめると元々食欲の調節のために独立の回路として存在する、食への拒否感と満腹感は、GLP-1 に同時に反応する。しかし、副作用として捉えられる吐き気といった食への拒否感は、基本的に体重減少には必要なく、GLP-1 は主に膵臓への刺激と満腹感の誘導を通して体重を抑制しているという結論だ。
いずれにせよ、これほど脳への作用があるということを説明した上で、処方することが重要で、私の場合すでに GLP-1 作動薬を使う年齢を遙かに超えているのだが、もし若かったとしたても利用はためらうように思う。
2024年7月12日
タスマニアデビルの感染するガン細胞については何度も紹介してきたが(https://aasj.jp/news/watch/21958 )、孤島に閉じ込められた固有種で、ガン細胞が感染できるぐらいMHCの多様性が低下し、さらに死骸をあさるという食行動を考えると、絶滅の危険は高いといえる。今年、タスマニアを旅行した時、野生のデビルには出会わなかったが、サンクチュアリーでの行動を見ていると、一緒に死骸をあさるというのが正解ではなく、餌の周りでともかく喧嘩をする。当然口腔のガンが感染しやすい性質だと納得した。絶滅を防ぐためには、ゲノムの定期的モニターが必要で、特に個体数が減り近親間交雑が増え、有害遺伝子変異が増加する、遺伝子変異のメルトダウンという現象の兆しをキャッチする必要がある。
絶滅危惧種を科学的に守るためには、絶滅した種についてのゲノム研究は有用だ。その意味で、全ゲノムが解析できるレベルで保存されているマンモスからは絶滅までの軌跡を多く学べる可能性がある。特に、1万年前に起こった水位上昇でユーラシア大陸から孤立したロシア領ウランゲリ島(タスマニアの10分の1の大きさ)に残されたマンモスは、人間が島に上陸するより前に絶滅していたこと、水位上昇で個体数が大きく低下したあと、5000年近く孤立して生存していたことから、絶滅を研究する重要な材料となっている。
今日紹介するスウェーデン自然史博物館からの論文は、ウランゲリ島に孤立する前後のマンモス21頭の全ゲノムを解析し、絶滅までに変異メルトダウン現象が起こっていないか調べた研究で、6月27日 Cellにオンライン掲載された。タイトルは「Temporal dynamics of woolly mammoth genome erosion prior to extinction(絶滅前のマンモスのゲノム崩壊の時間的ダイナミックス)」だ。
この研究では、ウランゲリ島で孤立したあとのゲノムから、特に近親間交雑の程度を知る同じ配列が両方の染色体で続いている Run of homozygocity (ROH) を調べ、ゲノム多様性の減少と、それに基づく個体数を推定している。
まず島に孤立した結果、当然個体数の急激な減少が起こる。この結果、近親間交雑でしか繁殖できなくなり、ROH の数が上昇する。そのときの多様性の変化から島に孤立したマンモスの個体数をシミュレーションすると、なんと多くて8頭。実際にはそれ以下の数から、島全体で2-300頭へと急速に回復したと推定される。すなわち、島に残った一つの群れから20世代ぐらいで一定数に達し、これを維持している。
驚くのは、ROHの上昇と多様性の低下のスピードがその後緩やかになっている点で、当初群れの中での近親間交雑が起こっていても、できるだけ遠い関係の間で交雑するという習性が自然に戻っていることを示している。
しかし免疫に関わるMHCの多様性は40%も低下し、そのまま維持されていることから、感染症などの抵抗性が低下していることは確かだ。
それでも孤立語5000年近く個体数を維持できた原因を調べると、生存に関わる遺伝子変異が集団から自然選択で排除される一方、影響の低い変異はそのまま維持されていることを明らかにしている。
結果は以上で、絶滅までの5000年、ウランゲリ島の環境変化がわからないと、この現象を説明するのは困難だが、個体数が減り、近親間交雑が増加、ROHが増加することで異常遺伝子が蓄積し、メルトダウンを起こすという単純なシナリオは必ずしも正しくなく、特にインパクトの大きな変異を個別に除去し続けることで、5000年という種の維持が可能であることを示している。
一方、2-300頭のマンモスが4000年前にランゲリ島から姿を決した原因がわかると、より面白いシナリオが現れてくると思う。例えば、多様性の減少したポピュレーションに急にストレスがかかって個体数が減ると、その後の回復が強く抑制されるように思うが、そのためには絶滅前の状況を示すゲノムが見つかる必要がある。しかし当分ロシア領での研究は難しいと思う。
2024年7月11日
コレラやペストのように、細菌性感染症がパンデミックとして人類に立ちはだかってきた歴史はよく知っていても、例えば現在最も重要な細菌感染症といえる肺炎球菌感染、嚢胞性線維症や気管支拡張症患者さんの緑膿菌感染などは、人から人へと伝染する伝染病のイメージは少ない。基本的には感染のための条件が多く、感染性が低い結果と考えられるが、間違いなく感染症であることを示す論文が2報 Nature と Science に報告されていた。
Nature に報告されたケンブリッジ大学の論文は、南アフリカで患者さんから分離された肺炎球菌6910ゲノム解析から、感染の広がりを調べた研究で、新しく発生した細菌がゆっくりと広がり、50年ほどかけて南アフリカ全土に広まること、そして肺炎球菌ワクチンが使われるようになり、ワクチンに含まれない肺炎球菌が広がり始め、治療を通して抗生物質耐性を獲得することが示され、肺炎球菌も感染症であることを実感させてくれる論文だ。
今日紹介したい論文はやはりケンブリッジ大学から7月5日号 Science に発表された論文で、世界各地の患者さんから100年近くにわたって分離された9829の緑膿菌ゲノムを解析した研究だ。タイトルは「Evolution and host-specific adaptation of Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌のホストへの適応と進化)」だ。
この研究では、機能的実験も行って緑膿菌の進化を示してくれる。
まず、ゲノム解析から特定の菌が伝搬した経緯をたどることができる。これにより、例えば南米で発生し、北米を通ってヨーロッパへ伝搬し、その後アジア、アフリカへと広がった系統を特定し、緑膿菌も人間の移動で広がることがわかる。また、この進化では水平遺伝子伝搬が進化の強いドライバーとなっている。
緑膿菌感染で最も重要なポイントは、ホストに完全に適応していることで、嚢胞性線維症患者さんに感染する緑膿菌は、嚢胞性患者さんだけに感染し、気管支炎や気管支拡張症患者さんの緑膿菌は同じ病気の患者さんにしか伝搬しない。
これは緑膿菌がマクロファージの中に侵入して増殖するときの環境を反映しており、嚢胞性線維症患者さん由来の緑膿菌は、嚢胞性線維症の患者さんのマクロファージでよく増殖し、これには緑膿菌の Dsk1 発現が関わることを、遺伝子ノックアウトしたバクテリア感染実験で示している。
このような適応を決める遺伝子は、ホストの自然免疫系をすり抜けるための機構に関わる遺伝子などで、ホストの環境に適応するため変化した数多くの遺伝子変異を特定している。
胸部内科医なら誰でも経験すると思うが、慢性閉塞性呼吸器疾患で緑膿菌は最大の敵だ。ホストの環境に合わせた進化の道筋を探ることで、今後緑膿菌のようなやっかいな感染症に新しい治療法が見つかることを期待したい。
2024年7月10日
補体成分の発現異常が統合失調症で存在するという発見以来、補体と神経細胞の関係を研究する論文を見かけるようになったが、補体カスケードの最初を担う C1q に関しても、ミクログリアが分泌してシナプス剪定に関わるという研究を2020年2月に紹介したことがある(https://aasj.jp/news/watch/12355 )。
しかしこれだけでは終わらないようで、今日紹介するハーバード大学からの論文は C1q が細胞内に取り込まれ、しかもタンパク合成を調節しているというのだから驚く。タイトルは「Microglial-derived C1q integrates into neuronal ribonucleoprotein complexes and impacts protein homeostasis in the aging brain(ミクログリアが分泌する C1q は神経細胞のリボゾームタンパク質と統合され老化した脳のホメオスターシスに関わる)」で、6月27日 Cell にオンライン掲載された。
以前紹介したように C1q は老化とともに脳内に蓄積すること、さらに C1q ノックアウトマウスでは認知機能が保持されることが知られており、この研究もその延長で計画されている。まず、C1q と結合しているタンパク質を探索した結果、驚くことに神経細胞内でリボゾームタンパク質と結合しており、老化とともにその量が上昇することを発見する。
C1q の構造に disorderd region と呼ばれる相分離を誘導するドメインが存在することから、ひょっとしてリボゾームとともに相分離が起こっているのではないかと着想し、試験管内で相分離能を調べると、RNA と結合したときだけ相分離すること、そして実際の神経細胞内でも RNA とともに相分離体を形成しており、RNA を分解するとこの相分離体は解消することを示している。
C1q は神経細胞で合成されないため、外部から取り込まれると考えられる。これを確かめるため、脳内にラベルした C1q を注入する実験を行い、神経細胞のエンドゾームに取り込まれたあと、細胞質へと移動して相分離に関わること、そして disorderd region がこの取り込みに関わることを明らかにしている。
最後に神経細胞内での C1q の機能を調べるため、C1q ノックアウトマウスとの比較研究を行い、1年齢を超えたマウスでは、タンパク質合成がノックアウトマウスでは上昇していることから、C1q は一種の翻訳の抑制機構として働いている可能性を示している。ところが、特定のタンパク質について調べると、シナプスの細胞骨格に関わるセプチン、及びミトコンドリアタンパク質だけは、細胞内の濃度が高まっていることを発見している。
機能的には、これまでの研究と同じで、認知機能は C1q ノックアウトマウスで上昇するため、C1q の蓄積は認知機能を阻害する方向に働くといえるが、恐怖消去試験などでは逆にノックアウトマウスの方が異常を示すので、明確な結論は出せない。
以上、機能的意義についてはよくわからないが、しかしミクログリアの分泌する C1q 分子が神経細胞内に取り込まれ、タンパク質合成の現場で相分離を通して翻訳に影響していることは驚く。マウスと異なり、人間の寿命は長いので、今度はヒトでこの現象の意義を研究することが重要になる。
2024年7月9日
Single cell RNA sequencing などの大規模ゲノムデータは、極めてパワフルだがデータが多すぎて、自分の視点がないと、ほとんどの情報を見落として終わる。それでも、今やこの方法なしに論文が書けないほど普及し、おそらくほとんどは一般的に提供される解析方法を用いて論文が書かれていると思う。
今日紹介する横浜理研の統合医学センターからの論文は、10xGenomics が提供する single cell 5’ RNA sequencing データに含まれているにもかかわらずほとんどの研究者が無視しているエンハンサー部位で起こる転写RNA に注目し、これにより CD4T細胞の分化や反応を、これまでの single cell テクノロジーより遙かに詳しく解析できることを示した研究で、どうしても沈滞がちに見えていた我が国の機能ゲノミックス研究も捨てたものではないと実感できる素晴らしい研究で、7月5日号 Science に掲載された。タイトルは「An atlas of transcribed enhancers across helper T cell diversity for decoding human diseases(転写されるエンハンサーを多様なヘルパーT細胞で調べたアトラスは人間の病気の解読に役立つ)」だ。
この論文を見たとき、なんとなく日本の機能ゲノム研究の一種の集大成だと感じた。というのも、村川さんという若いオーガナイザーの下に、私と同世代の林崎さん、山本さん、Carninci (ちょっと若いが)さんが集まって研究を仕上げており、しかも林崎さんや Carninci さんは、CAGE法と呼ばれる 5’端から読む RNAライブラリー作成法を開発し、FANTOM と呼ばれる独自の優れたオープンデータベースを作成し、特にプロモーターやエンハンサーについての研究では重要なリソースになっていた。私のような老兵にこの研究は、この single cell 5’RNA sequencing(s5’seq) を FANTOM とつないでいるという点で、ジンとくるものがある。
これまで数え切れないぐらいの研究で s5’seq が使われているが、この情報の中に CAGEライブラリー研究で明らかになった、転写されたエンハンサー領域(tE)が含まれることは全く無視しされていた。理由の一つは、転写物の量が少ないためだが、この研究では多くの細胞を解析することで、tE を検出し、他の転写データから特定される細胞の亜集団について、tE の発現、特に双方向に転写が見られる部位(btE) に着目して解析している。
どの細胞で研究しても良かったのだが、CD4T細胞を選んだ点もセンスが良く、この研究を成功に導く要因になった。この結果、これまでの方法で14種類の亜集団に分けることができる CD4T細胞のそれぞれの亜集団で検出できる btE を6万カ所特定することに成功している。これらはもちろん ATAC-seq で検出できるオープンクロマチン領域に存在するが、さらに特異的な転写状態を反映できる可能性を示している。この点については、Micro-C と呼ばれるゲノム領域間の相互作用を調べる方法を用いて、btE が実際のエンハンサーとプロモーターの関係性をより強く反映していることを確認し、さらに加えて、BRD4 や H3K27ac で調べられる実際のエンハンサー活性とも btE が相関することも確認している。このように single cell 5’ sequencing データの中から btE 部位を調べることの重要性を念には念を入れて、確認している。
そして、こうして特定した btE や tE と、ゲノム解析により特定された疾患と相関する多型とを比べ、btEで特定できるエンハンサーがより強く疾患の多型とリンクし、例えば多発性硬化症と、慢性腸炎を区別することもできることを明らかにしている。面白いのは、免疫疾患と関係する CD4T細胞で働いていると特定された606の btE の多くが抑制性T細胞に関わる点で、今後 Treg 専門家による深掘りが進むと面白い。
最後に文字通り機能ゲノミックスを進めるため、このグループは CRISPR を用いて btE を活性化する方法も開発しており、こうして特定されたエンハンサー領域の転写が、下流の遺伝子転写の量を決めていることが示されている。
膨大なデータで全部紹介しきれないが、CAGE法開発から始まる研究の一つの重要な節目に到達した気がする。この研究は始まりに過ぎなく、ATAC-seq と RNA転写のみで研究されてきた機能ゲノミックスが大きく変わる可能性を秘めている。発生学から様々な病気、特にガンやガン免疫のメカニズム理解に大きく寄与すると思う。
2024年7月8日
Covid-19感染は現在も続いているようだが、我々の側にも十分抵抗力が形成され、大きな問題にはならなくなってきた。一方で、感染後続く Long Covid と呼ばれる後遺症が問題になり、様々な研究が発表されている。例えば Nature Medicine 6月号には、13万人の感染者について後遺症を追跡した疫学調査が発表され、死亡率や症状は3年経つと消えていくが、それでも1%近い人、特に入院を必要とした重症者で、症状とともに死亡リスクが存在することが示された。
そして、入院した重症者では様々な臓器の症状が3年後も残る一方で、比較的軽度の感染者では、3年後に見られる後遺症は、神経系、呼吸器系、そして消化管に限られていたことが示された。この結果からも、Long Covid では感染が持続している可能性が示唆される。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、持続するコロナウイルスに対するT細胞の反応を人間でモニターできる PETリガンドを使って Long Covid を追跡した研究で、7月3日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Tissue-based T cell activation and viral RNA persist for up to 2 years after SARS-CoV-2 infection( SARS-CoV2感染後組織レベルの T細胞の活性化とウイルスRNA は2年は持続する)」だ。
この研究で用いられたのは、白血病診断用に開発された活性化 T細胞特異的に追跡する PETリガンド18-F-AraG を、Long Covid での持続的T細胞反応追跡に使った研究だ。18-F-AraG は抗がん剤 AraG に18-Fを標識し、これを取り込んだ活性化T細胞の局在を調べる方法で、核酸ENT1トランスポーターを通って AraG が取り込まれると、活性化T細胞で発現が上昇している deoxycytidine kinase によりリン酸化され、サルベージ経路を通って核酸の中に取り込まれるため、この酵素を強く発現する活性化T細胞がある程度特異的に検出できる。最近では、チェックポイント治療での T細胞の反応検出などにも用いられている。
この研究のハイライトは、Long Covid を訴える患者さんで、感染後様々な時期にこの検査を始めて行ってみたということになる。基本的には抗ガン剤を標識に用いてはいるが、特に副作用は観察されず、診断に利用できることがわかった。
さて結果だが、コントロールと比べると、Long Covid を訴える人では、様々な部位で AraG の取り込みが観察される。特に取り込みが顕著な部分は、脳幹、胸部脊髄、尾部脊髄を中心とする神経系に、大動脈弓、肺動脈、心室、そして大腸や直腸で、これらの部位の取り込みが強いほど Long Covid 症状が強い。これらの部位は上に紹介した Nature Medicine 論文での症状部位と一致する。
しかし、患者さんの訴える臓器症状と、AraG の取り込み部位は、肺症状以外は一致が見られず、今後もう少し大規模な調査が必要と思われる。
重要なことは、免疫系の検査と組み合わせてみたとき、抗体反応にかかわらず Long Covid が発生する点で、2年以上たった症例でも、活性化された T細胞が各組織に存在していることは確認された。
AraG 取り込みと直接相関しそうなマーカーを探索した結果、様々な炎症マーカーとの相関が見られたことから、Long Covid では持続するウイルス感染に対して T細胞の反応が維持され、炎症につながっていることが示された。
最後にバイオプシー可能な腸管で、AraG の取り込みが診られた患者さんの全てでウイルスが検出できることを示している。
以上、大体これまで知られていることなので、この検査がどのぐらい有効かは評価しにくいが、しかしT細胞の反応が持続していることは明らかで、今後の問題になる。
2024年7月7日
7月3日 Nature にオンライン掲載された論文の中に、2編考古学論文が含まれていた。
最初はオーストラリアのグリフィス大学からの論文で、インドネシア スラワジにある洞窟画の年代測定の研究で、タイトルは「Narrative cave art in Indonesia by 51,200 years ago(インドネシアの物語が描かれた洞窟画は51200年までに描かれた)」だ。
最も古い絵として知られているのは、スペインのネアンデルタール人が洞窟に残した手形で、これが絵と認めるかどうかは議論がある。一方、ショーベネやアルタミラなどに残る物語を描いた絵画は、ホモサピエンスによるもので、ショーベネのものが3万7千年前になる。
もう一つホモサピエンスの絵画が存在するのが、ホモサピエンスがヨーロッパより早く移動してきたインドネシ アスラワジの洞窟絵画で、鮮明ではないが狩の絵が描かれている。これまで、時代検証で4万5千年前とされてきたが、レーザーを用いた絵の具の採取とウラニウム年代測定から、それより5千年以上前で、おそらく51200年前と結論された。すなわち、ホモサピエンスはさらに早い時期から絵で物語を表現していたことになる
もう一編の論文は中国蘭州大学、デンマークコペンハーゲン大学などを中心に発表された論文で、チベットで続けられているデニソーワ人についての考古学研究の続報で、タイトルは「Middle and Late Pleistocene Denisovan subsistence at Baishiya Karst Cave(中期から後期更新世、デニソーワ人は白石崖溶洞に生きていた)」だ。
デニソーワ人は最初シベリアのデニソワ洞窟で発見された指の骨のDNAで初めて特定された人類だが、次の証拠はチベット白石崖溶洞から発掘された下顎骨がコラーゲン解析からデニソーワ人と判明し、2019年5月に Nature に発表された(https://aasj.jp/news/watch/10139 )。その後骨は発見されていないが、沈殿物からミトコンドリアゲノムを採取する研究で、デニソーワ洞窟及び白石崖溶洞からもデニソーワ人のミトコンドリアDNA が発見され、16万年から4万5千年前まで白石崖溶洞でデニソーワ人が暮らしてきたことがわかっている。
この研究では、この洞窟に残る哺乳動物の骨を徹底的に解析して、チベットに住むヤギ、牛、ヤク、そして馬や鳥を含む様々な骨が出土すること、そしてその骨には明らかに人間の手による様々な細工の痕跡が存在することを明らかにしている。すなわち時代によって使われる動物は変化するが、デニソーワ人は早くから骨を道具として利用していたことが明らかになった。
そしてこの骨の中から、骨が出土したデニソーワ人としては3人目の肋骨が見つかり、DNAは採取できなかったが、これまで通りコラーゲンなどのタンパク質を用いて、デアミネーションを指標とする時代測定、及びアミノ酸配列の解析から、間違いなくデニソーワ人の骨であることを確定している。また、この骨は時代の新しい地層から発見され、デアミネーションによる測定でも4万8千年から3万2千年の間に生存していたデニソーワ人の骨であると推定している。
現在、デニソーワ洞窟、白石崖溶洞、形態学的にデニソーワ人の歯が見つかったとされているラオス・Tam Ngu Hao洞窟などぼちぼちデニソーワ人の生活のあとが追えるようになってきた。次の新しい発見をわくわくしながら待っている。
2024年7月6日
我々の脳の中には、意味やカテゴリーに反応する細胞があることが知られている。例えば、リンゴやハンバーグについて聞いたとき、これらの単語は食べ物として理解されるが、この食べ物というカテゴリーに反応する細胞だ。しかし、これまでの研究では単語の意味については、我々の知識をベースに、研究ごとに自由に決めていた。従って、食べ物というカテゴリーと、乗り物と言ったカテゴリーの違いを客観的に数値化することができなかった。そこに、一つ一つの単語が多次元空間の中のベクターとして表現する言語モデルが現れ、例えば現在使われている ChatGPT では次元数が 12280だが、GPT2 ではぐっと下がって768次元になる。いずれの場合も、しかし単語はその次元空間内のどこかに位置するため、単語同士の距離関係が数値として得られる。
こうして定義できる単語間の距離を用いて意味を定義し、これに対する単一神経細胞レベルの反応を調べた研究が、今日紹介するハーバード大学からの論文で、7月3日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Semantic encoding during language comprehension at single-cell resolution(言語を認識する際の意味がコードされる過程を単一神経細胞で調べる)」だ。
この研究では深部刺激電極設置手術の際に、患者さんの了解を得て言語野に単一神経レベルの記録が可能な電極を挿入し、意味のあるセンテンス(単語が意味なく並べられた場合もある)を中心に被験者に聞いてもらい、そのときの神経反応133個のニューロンで記録、特定の意味に反応する神経細胞集団を特定している。
これまでの研究では食べ物というカテゴリーかどうかと言った分類で調べていたが、この研究では300次元のトークンを持つ150億コーパスを学習させたモデルを用いて、各単語の意味の近さを算出し、それと神経反応を対応させている。ただ、数値ではわかりにくいので、行動、天候といった意味にも分類してくれており、意味に反応する神経があること、そしてそれを言語モデルを用いて同じベクトル座標で研究可能なことを示している。
神経反応をデコーダーで解析することで、各神経の反応から単語の意味をデコードできることを確認したあと、文章として意味のあるセンテンスを聞いたときと、ランダムな単語の並びとして聞いたときで、単語の意味を脳の反応から予測する確率を比べると、単語の意味の理解が文章内のコンテクストにより決められていることがわかる。すなわち、トランスフォーマーのような言語モデルと一致する。
最後に、それぞれの神経の反応と300次元の意味空間と距離とを相関させると、ほぼリニアーな関係が認められ、意味に対する神経反応も、言語モデルと同じように行われているのではないかと推察している。
結果は以上だが、トランスフォーマーモデルの出現で可能になった自然言語の処理方法が確実に言語の脳科学を変えていることが実感できる論文だ。この研究では、脳の反応と言語モデルは別々のモデルとして対応しているが、以前紹介した MRI 画像から脳内に浮かんだ文章を GPT1 を用いて推測する研究のように、両者を統合することも始まっている。GPT を使っていると、自然言語という人間の発明の途方もない壮大さを感じるが、脳から発生した言語を用いて、今度は脳を理解すると言った双方向性が生まれていることがわかる。
次回のジャーナルクラブはアルツハイマー病と考えているが、8月は脳と大規模言語モデルをまとめてみたい。
2024年7月5日
アルツハイマー病治療はようやく βアミロイドに対する抗体薬により現実のものになりつつあるが、さらに進行した患者さんの治療には、神経細胞死を直接誘導する Tauタンパク質の沈殿を抑える治療が必要になる。この目的にも Tauに対する抗体が使えるのではないかと、前臨床、そして臨床実験が行われているが、今のところポジティブな結果は報告されていない。
実際多くの研究者は、細胞内では多楽異常Tau を標的にする場合、細胞内へ移行できない抗体が効果を持つとすると、異常Tau が神経外へ吐き出され、他の神経へと伝搬する過程が唯一のタッチポイントで、それもシナプス間隙で伝搬が起こるとすると効果はあまり期待できないのではと考えている。
そんな時、昨年3月、ケンブリッジ大学から抗体と Tau が結合した複合体が神経に取り込まれ、そこで TRIM21 と細胞内 Fc 受容体によって分解されることを示した論文が発表された。すなわち、Tau に対する抗体は細胞内に取り込まれた場合のみ働くことが示された。
今日紹介するテキサス大学からの論文は、同じメカニズムを利用した Tau に対する抗体治療法の開発だが、抗体をミセルで包んで鼻から投与することで、直接神経細胞内に抗体を到達させようとする研究で、7月3日号の Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Nasal tau immunotherapy clears intracellular tau pathology and improves cognitive functions in aged tauopathy mice(経鼻的 Tau 免疫治療は細胞内の Tau異常症を解消して老化した Tau異常症マウスの認知機能を改善する)」だ。
この研究では Tauタンパク質でも、重合化した毒性の強い形にだけ反応するモノクローナル抗体を作成している。試験管内の実験で、この抗体が異常Tau を細胞に取り込ませる試験で、その毒性を強く抑制することを確認した後、ヒト異常Tau を発現するマウスを用いて投与実験を行なっている。
この時、脳へ効率よく抗体を供給するルートとして、鼻に抗体と投与するルートを選び、脳血管関門を気にせず、嗅球を経由して海馬や視床へと抗体が到達できる。
さらにこの研究では、抗体そのままではなく、ポリエチレン、ポリプロピレンなどを原料とするミセルを作成し、細胞内に取り込まれるようにしている。実際、試験管内で細胞内に取り込まれ異常Tau と結合することを確認したあと、これを経鼻的に Tau異常症マウスに投与し、効果を調べている。
ミセルに詰めた抗体が細胞質内に取り込まれ、異常Tau と結合することを確認し、経過を追いかけると、期待通り TRIM21依存的に異常Tau を細胞内、及びシナプスから除去することを確認している。そして、異常Tau が減少することで、組織学的なシナプス機能も正常化し、最後に認知機能も改善することを示している。
以上が結果で、最初から細胞内の Tau を狙った面白い研究だと思う。人でも同じ方法が可能なら、是非臨床研究へと突き進んでほしい。
この論文を含めて、最近アルツハイマー病の新しい治療法の論文が発表されているので、7月17日夜7時半からアルツハイマー病の新しい治療可能性についてのジャーナルクラブを開催することにする。