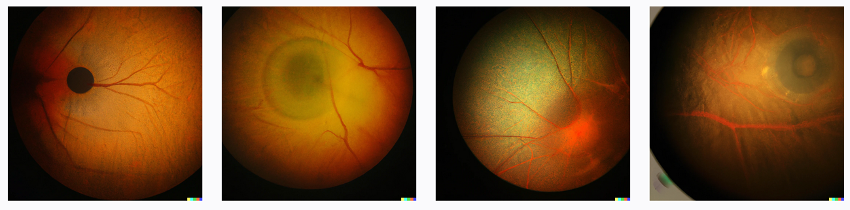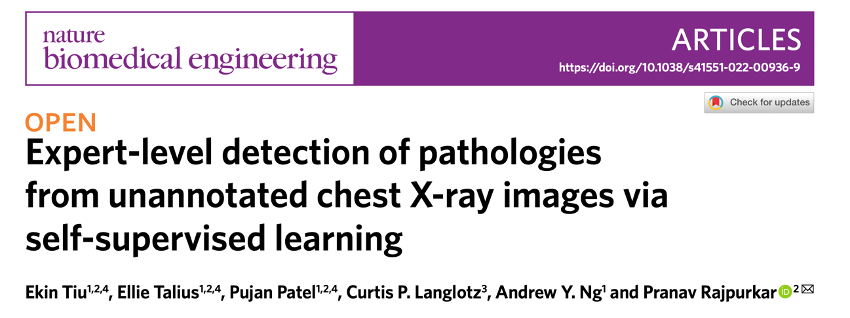2023年9月17日
生成AIを医療に用いる方法開発についての様々な論文がトップジャーナルに掲載されるようになってきたが、ここまで来るとあまり新味を感じない。ただ、多くの人に利用できるように学習を済ませた生成AIモデルの数が増えるのと平行して、医療や医学教育が急速に変わっていくことが予想できる。
さらに今日紹介するロンドン大学からの論文が示すように、既存のAIモデルを利用して、専門分野の画像を学習させ、チューニングすることで、例えば網膜の画像から病気をかなりの精度で予測できるモデルを簡単に作れるとすると、変革の速度は想像以上になると考えられる。論文のタイトルは「A foundation model for generalizable disease detection from retinal images(網膜が像からの病気診断を一般化できる基礎モデル)」で、9月13日 Nature にオンライン掲載された。
研究自体は他の生成AI論文と変わるところはあまりない。既に、7月14日 GoogleのPaLMをベースに医学のquestion&answerを学習させ、最後に専門家がプロットを書いた内容によるIntruction fine tuningを行うことで、米国医師国家試験に85%の回答率で通過し、さらに専門家に匹敵するチャットボットが可能なMed PaLMについて紹介した。(https://aasj.jp/news/watch/22520 )。
この研究は、階層化されて集められた画像の生成AI、ImageNetに、眼科で一般的に行われる網膜画像検査のカラー画像、及びOCT(Optical coherence tomography)検査のイメージを、masked autorencoding(虫食いの画像を見せて完全画像を完成させる一種のクイズ的学習方法)と呼ばれる方法で事前学習させ、後は診断のついた画像でファインチューニングすることで、糖尿病性網膜症、緑内障などはほとんど確実に診断できる生成AIモデルが出来るという話だ。
既存の画像生成AIから専門のモデルを作れるのかといぶかしく感じられるかも知れないが、既存のAIもかなりすごい。例えばユニバーサルな画像生成AI、DALLEに、糖尿病性網膜症の眼底画像とインすると、たちまちこんな画像が出てくる。
ユニバーサルの画像AIもすごいのだ。だから、これを専門的画像だけで学習させ、少ない数の答えのわかった画像でファインチューニングするだけで、実用的な画像診断モデルができあがる。
この可能性は既に、スタンフォード大学から胸部X線写真で示され、この論文が出たときアノテーションなしにレントゲンをともかく読み込ませるtransformer/attemtopmの生成AIの力に驚いた。
以上から考えると、今回の論文は当たり前の話で、わざわざNatureが取り上げるほどかとも思ってしまうが、これまで網膜画像が診断に使われなかった、心臓疾患やパーキンソン病のような他臓器の疾患まで、網膜で診断できる可能性、及び年齢や人種に影響されにくい診断へと発展できることを示した点は重要だと思う。
ここで用いられたmasked autoencodingを用いた学習と、最後の答えを教えるチューニングのコストについて、この研究ではNNIDIAの16GのGPU一つだけ備えたPCで、かなり短期間の努力で、このぐらいの精度のモデルを形成できることを示した点でも重要だと思う。
要するに、あらゆる専門分野が、一般の生成AIとリンクされる時代がそこに来ていることが実感できた。
2023年9月16日
京大医学部の同窓会誌で、卒業後胸部疾患研究所で臨床を始めたときに世話になった泉孝英先生が亡くなったのを知った。私がすぐに基礎医学に行かずに臨床から始めたのも、また臨床研究のイロハを教えてもらったのも全て泉先生のおかげだ。この時臨床研究として取り組んだのが、サルコイドーシス、慢性ベリリウム症、そして汎細気管支炎だった。中でもサルコイドーシスは専門外来に最初から補助役として参加した。
その後1980年に留学して、完全に臨床を離れたので、これらの疾患についての私の知識はここで途切れている。しかし、何10年もたって当時感じた疑問が一つの研究で解明され感動することがある。その例が、このHP で紹介したように金属によりMHC構造が変化し、それに対する免疫反応が基盤にあることを示した研究だ(https://aasj.jp/news/watch/1783 )。
今日紹介する米国・テネシー州立大学からの論文は、サルコイドーシスの重症化に関わるCD8T細胞と細胞活性化メカニズムについて明らかにした研究で、9月13日号の Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「SHP2 promotes sarcoidosis severity by inhibiting SKP2targeted ubiquitination of TBET in CD8 + T cells(SHP2がCD8T細胞内でSKP2によるTBETのユビキチン化を阻害することでサルコイドーシスを重症化させる)」だ。
サルコイドーシスに関する私の知識は1980年からアップデートしていないので、Nature Review Disease Primers のサルコイドーシスを読んでみると、他の肉芽腫性疾患と同じで、何らかの抗原で刺激されたCD4T細胞が、自然免疫系、特にマクロファージを巻き込んで肉芽腫性炎症へ発展することは間違いなさそうだが、まだ抗原や悪性化についてはわかっておらず、治療も私が特殊外来に出ていた頃から特に進歩していないことがわかった。
この研究では、サルコイドーシスの進展にインターフェロンγ(IFNγ) が関わっており、膜型脱リン酸化酵素SHP2を阻害するとFNγが低下、症状が抑えられることに注目し、マウス肉芽腫モデルを用いて、SHP2を発現する細胞の特定から始めている。
結果は、CD4細胞ではなく、CD8T細胞のSHP2が肉芽腫の重症化に関わっていることを突き止める。そして、SHP2阻害剤を用いることで、肉芽腫性病変をつよく抑えることを示している。
あとは、CD8T細胞でのSHP2シグナル下流を生化学的に探索し、
SHP2はT細胞の転写因子TBETを介して、FNγ分泌を促進しするとともに、クラス1MHCの発現を高める。
TBETは、ユビキチンリガーゼSKP2によってユビキチン、分解経路に導かれる。
SHP2は直接SKP2に結合して脱リン酸化を介してその機能を低下させることで、TBETの分解が抑制され、TBETによるインターフェロン合成が誘導される。
サルコイドーシスの患者さんではSHP2の活性が高まっている。
サルコイドーシスの肺組織スライスをSHP2阻害剤で処理すると、FNγの分泌が抑えられるとともに、コラーゲン遺伝子の発現も抑えて肺線維症の進行を止めることが出来る。
以上が結果で、サルコイドーシスの重症化にCD8T細胞が関わること、この細胞が何らかの抗原で刺激されることで、サルコイドーシスの重症化が始まることをを明らかにしている。
治療の面では確かに大きな革新があるとは言えないが、ゆっくりとしてではあってもサルコイドーシスのメカニズムも徐々に解明が進んでいると実感できた。
2023年9月15日
小胞体のような膜構造を持つオルガネラ以外の細胞内凝集体は、大小を問わず今や全て相分離による凝集と考えられるようになっている。しかし振り返ってみると、相分離で細胞内のコンパートメントが形成されることが認識されるようになったのは、大きなコンパートメント、例えば核小体や P-granule と呼ばれる生殖細胞に特有の構造が最初だ。
面白いことに、核小体は rRNA が集まった相分離体だし、P-granuleはmRNA が集まった相分離体で、RNA が関わると大きな構造になるのは、それだけ RNA が大量に存在しているからと言える。
しかし、rRNA であれば種類は限られているので相分離で集まってもいいように考えるが、mRNA となると、化学的には RNA だとしても、その種類は膨大で、それぞれが P-granule に閉じ込められれば、正常な翻訳など出来なくなるのではと心配する。
今日紹介するフランス・コートダジュールの CNRS からの論文は、この素朴な疑問に答えてくれる面白い研究で、9月12日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Self-demixing of mRNA copies buffers mRNA:mRNA and mRNA:regulator stoichiometries(mRNA の自己分離が mRNA同士及び mRNA/調節因子の量変化を緩衝する)」だ。
この研究では線虫の卵子形成で見られる P-granule(PG) を対象にしている。卵子の分裂が止まると現れる大きな粒子でこれまでの研究で様々な mRNA を含んでいることがわかっている。
まず PG を集めて、そこに濃縮されている RNA を調べると、基本的には静止期の卵子で翻訳が抑制されている mRNA が濃縮していることを発見する。すなわち、翻訳を抑制したい mRNA を翻訳機構から隔離している可能性がある。ただ、十把一絡げに隔離すると、当然問題が起こる。
そこで次に個々の mRNA と PG との関係を調べるため、spn-4 あるいは glp-1 をコードする mRNA に焦点を当てて動態を見ると、卵子が静止期に入ると、それぞれの mRNA は一定濃度に達すると速やかに単独で相分離を起こし、小さな相分離体を形成する。その後、単独で相分離した異なる種類の mRNA が集まり始め、大きな PG を形成することがわかった。
この過程をさらに詳しく見ると、卵子の翻訳機構が混乱しないよう、翻訳を抑制する mRNA は抑制因子と結合するが、この複合体が一定濃度に達すると、個別の相分離が起こる。こうして出来た個別の相分離体は、今度は抑制蛋白質など蛋白レベルの結合性を基盤にして大きな PG へと発展するというシナリオだ。
ではなぜこのような相分離が必要なのか?卵子は静止期に入ると、受精まで長期間既に合成した mRNA を大事に保存する必要がある。それを翻訳を抑える分子が行っているが、それだけでは細胞質への mRNA の漏れ出しを完全に抑えられないことから、相分離、そして PG形成を行うことで、細胞質の翻訳機構から完全に隔離することが出来る。
言い換えると、後で必要になる mRNA の利用を抑えてラップに包んだ後、冷凍庫にしまうようなイメージだ。ただ、大事なことは、細胞質での個々の RNA の濃度が低下すると、すぐに冷蔵庫から出し、ラップから出して使えるように出来ている点で、進化の偉大さを感じる。
これまで相分離というと、濃度を高めて機能を局在させると言った使われ方が多かったが、RNAが絡むと、細胞質への供給を適正に保つための保存庫としても機能できるとは本当に面白い。
2023年9月14日
様々な神経疾患の発生頻度には明確な男女差があるし、行動学的にも、解剖学的にも男女の脳は異なっている。この差はそれぞれのニューラルネットの違いなのだが、さらに突き詰めると遺伝子発現の差に回帰できる。ただ、人間の脳は多様性が大きく、何が男女差を決めるのか正確に特定するのは難しい。
今日紹介する米国エモリー大学からの論文は、蛋白レベル、mRNAレベルで脳の男女差に関わる分子/遺伝子を特定し、それと様々な精神状態や脳構造との関わりを調べた研究で、8月31日 Nature Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Sex differences in brain protein expression and disease(蛋白質の発現と病気の性差)」だ。
この研究では、男女の脳の各部分の蛋白質レベル(プロテオーム)と転写レベル(トランスクリプトーム)の分子発現を調べ、まずプロテオームレベルで13%近い蛋白質の発現が男女で異なっていることを特定する。
その上で、それぞれの分子の発現を決める遺伝要因を、全体、あるいは男女別で調べ、蛋白質の発現の差に関わるゲノムの中で、発現差の程度が男女ではっきり異なる、性バイアスが見られる遺伝子多型166箇所特定することに成功している。これまで、同じような比較で男女差を決める遺伝要因が特定された組織は乳腺で、脳はこれに匹敵する要因があることになる。
この遺伝要因の差をもう少しわかりやすく言うと、遺伝子発現に関わる多型のなかでも程度が男女で異なっている多型を特定している。そしてこれらの多型は転写調節領域やノンコーディングRNA、さらにエクソンの多型で、単純に性ホルモンで説明できない複雑な過程が関わると考えられる。
次に、蛋白質の発現とmRNAの発現を比較して、ほぼ8割の違いが両者で一致していることを確認した上で、こうして特定した男女で異なる多型分布を示すそれぞれのゲノム領域と、精神疾患の関わりについて調べ、性差を説明する14種類の多型を特定している。
例えば、その一つカドヘリン13はうつ病の原因遺伝子の一つとして知られている。あるいは統合失調症と相関するPEBP1の多型も男女差があり、この分子は脳発生に関わる。
重要なのは、こうして疾患との相関があり、同じ発現に関わる多型でも男女で程度が異な領域の多くが、炎症や免疫に関わる点で、アルツハイマー病の様な変性性疾患だけでなく、うつ病、アルコール中毒症などが含まれる。
結果は以上で、疾患と相関する多型自体は男女ともに同じように存在するので、その程度の男女差というと少しわかりにくかったかも知れない。しかし、多型の現れ方に男女差があることは、男女差を考える時に重要で、絶対的差と言うより、傾向と言えるような差を扱っている。そして、多くが様々な精神疾患の男女差とも関わっているとすると、この研究の先には、我々が自分の性をどう認識するのか、そして性同一性障害が起こるメカニズムの解明に進む気がする。その意味で、今回特定された遺伝子発現の差の中で環境に影響される可能性があるのが1%に満たない点は重要だ。すなわち、性同一性障害は遺伝的差異として調べることの重要性を示している。
2023年9月13日
お知らせ:今日から画面が変わりました。現在作業中で、検索に問題が生じていますが、作業が終わるまでお待ちください。
アルツハイマー病(AD)の最も重要なリスク因子は脳細胞の老化なので、脳細胞老化自体を抑制し AD進行を抑制できないかは重要な研究方向になっている。そして、老化を抑える一つの方法が老化した細胞を除去して新陳代謝を促進する senolysis で、これまで何回も紹介した。とはいえ、AD患者さんを対象にした senolysis治療が始まっているとは想像しなかった。
上の論文はテキサス大学からの論文だが、5人の AD患者さんを対象に、特異性の低いキナーゼ阻害剤Dasatinib と抗酸化剤quercetin を投与し、安全性と薬剤動態を調べ、次の治療治験へと進むための第一相治験についての報告だ。まだ治療効果を云々する段階ではないが、腎硬化症や肺線維症だけでなく、ADまでこの治療が拡大出来るのか、興味が引かれる。
もう一つ老化を対象にした AD治療の可能性が、筋肉から分泌されるミオカインのひとつ Irisin で、2019年マウスADモデルの記憶が Irisin で回復することを示した論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/9706 )。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、試験管内のADモデルを用いてこの Irisin作用機序を詳しく調べた研究で、9月8日 Neuron にオンライン掲載された。タイトルは「Irisin reduces amyloid-b by inducing the release of neprilysin from astrocytes following downregulation of ERK-STAT3 signaling(Irisinはアストロサイトの ERK-STAT3 経路を阻害して neprilysin 分泌を誘導してアミロイドβ を低下させる)」だ。
結論は、タイトルに全てまとめられている。驚くのは、これを全てヒトAD神経幹細胞を用いた3D培養で行っている点で、Aβの蓄積と続くTau分子のリン酸化という点では5週間培養すると再現できる様だ。
この培養に irisin を加えると、上清に分泌される Aβ量を抑えることが出来る。すなわち、ADの一側面を試験管内で再現できる。この系を用いて、後はなぜ Aβ量が低下するのかメカニズムを調べることになる。詳細を省いて結論だけを箇条書きにすると以下の様になる。
Irisin はアストロサイトに働いて、Aβを分解する neprilysin を分泌させることで、Aβの蓄積を抑える。
Irisin はアストロサイトが発現するインテグリンαV/β5 に働く。
このシグナルは、IL6/ERK-STAT3シグナル経路を阻害し、炎症を抑えることで neprilysin の分泌を促進する。
すなわち、おそらく試験管内培養では、老化と同じで自然炎症が促進しており、アストロサイトが Aβ などを処理する能力が低下している。これに対し、Irisin はアストロサイトの炎症性変化を弱め、neprilysin 分泌を促すことで Aβ を分解し、AD進行を抑制するというシナリオだ。
結局 irisin の作用も自然炎症と細胞老化抑制と言うことになるが、この作用も Aβ蓄積の早期段階で効果が見られることから、運動の効果が irisin分泌だとすると、早くから運動して irisin を増やすことが重要の様だ。
2023年9月12日
アムジェンの開発した Sotorasib を皮切りに、変異 Ras 阻害剤の臨床応用が進んでいるが、使用が進むとともに、少なくとも単独治療では耐性ガンの発生が必須であることがわかってきた。従って、Ras 阻害剤の効果を長続きさせる併用薬剤を見つけることは急務で、研究が進んでいる。
今日紹介するテキサス・ベイラー医科大学とMDアンダーソン ガン研究所からの論文は、Ras の活性化、及びその急速な阻害により起こる蛋白質のクオリティーコントロールの破綻に注目し、これを標的にすることで Ras 阻害剤必発の耐性発生の問題を克服できる可能性を示した重要な研究で、8月9日号 Science に掲載された。タイトルは「Modulation of the proteostasis network promotes tumor resistance to oncogenic KRAS inhibitors(蛋白質恒常性の変化が発ガンK-Ras阻害剤に対する耐性を促進する)」だ。
この研究では、K-Ras 阻害剤に対する耐性を獲得したガン細胞(RASir)の proteostasis と呼ばれる合成蛋白質のクオリティーコントロールを調べ、阻害剤処理により急速に起こる proteostasis 異常と蛋白質の凝集が、耐性発生とともに正常化することを発見する。すなわち、K-Ras 活性化により高いレベルで機能していた proteostasis が、阻害剤の効果で破綻させられ細胞死に陥るが、他の経路で proteostasis は速やかに回復し、耐性が生じることになる。
蛋白質のクオリティーコントロールは細胞生存に必須で様々なメカに住むが存在しているが、RAS 阻害剤で低下し、RASir 細胞で回復する経路を調べると小胞体ストレスセンサー IRE1α を介する経路であることがわかった。
このケースで IRE1α は小胞体ストレスのセンサーとしてではなく、直接 K-Ras 下流の MAPK 分子により活性化されており、この経路が阻害剤で破綻することがわかった。言葉を換えると、K-Ras 活性化で蛋白質恒常性の維持を高める必要があり、これを K-Ras 下流の MAPK 分子が IRE1α を安定化させることで達成している。
阻害剤で一旦 IRE1α が不安定になり、蛋白質の凝集など細胞ストレスが上昇し、細胞が死に始めるが、他の代償経路により IRE1α が正常化すると、K-Ra sなしでもガンは増殖出来る様になる。
この代償経路を突き詰めると、様々なチロシンキナーゼ受容体が働いて、MAPK 分子や、あるいは AKT 分子を介して直接 IRE1α を安定化して、蛋白質のクオリティーコントロールを維持することがわかった。
事実、耐性を獲得したガン細胞を、特異性の低いキナーゼ阻害剤と併用することで、K-Ras 阻害剤の効果が再び回復し、耐性ガンでも増殖を抑えることが出来る。ただ、特異性の低いキナーゼ阻害剤は副作用が強く、実際の治療としては利用が難しい。
代わりに、現在治験が進んでいる IRE1α 阻害剤ORIN1001 を K-Ras 阻害剤と併用すると、少なくともマウスの移植ガン実験では K-Ras 阻害剤治療に伴う耐性ガンの発生と完全に抑制することに成功している。最後の実験は、K-Ras 阻害剤が最も期待される膵臓ガンモデルで行っており、効果が完全でないガンも存在するが、調べた4種類のガンで耐性を抑えるのに成功している。
以上、ORIN1001 は既に臨床応用のための治験が進んでいるので、ここで開発された併用療法が治験へと進む可能性は高いと期待している。
2023年9月11日
腫瘍の周りの環境は4種類に分類される。最も望ましいのは Hot 状態で、ガン抗原特異的なT細胞が活性化され、腫瘍内に浸潤し、それをさらにNK細胞が助けるといった状態だ。この理想的な状態に対して、Cold と呼ばれるのは、T細胞反応が様々な理由で低くなっている状態で、チェックポイント治療やワクチン治療はこの状態を Hot にするために行われる。これら2つの状態以外に、ガン自体が免疫を抑制する suppressed と呼ばれる状態があり、例えばガンが PD-L1 を発現してキラー細胞を抑えるのもこの中に入る。そして最後の状態がキラー細胞の浸潤を防ぐ状態で、Excluded と呼ばれる。
この Excluded と呼ばれる状態は、膵臓ガンのように間質反応により機能的血管密度が抑えられたりするケースもあるが、最も重要な要因として活性化された白血球や樹状細胞が腫瘍局所に浸潤して、リンパ球の浸潤をブロックするケースが最も重要と考えられ、これを標的にして腫瘍内に抗腫瘍免疫活性を回復させる試みが進んでいる。
今日紹介する上海復旦大学からの論文は、CRISPR/Cas により356種類の膜に発現する蛋白質を網羅的にノックアウトした造血幹細胞を作成し、これを放射線照射マウスに移植したあと、腫瘍を移植、その周囲に集まる血液細胞を single cell RNA sequencing により解析し、ノックアウトにより白血球の浸潤が抑えられる分子を探索している。
CRISPR/Cas による網羅的スクリーニングは当たり前の技術になったが、この研究では通常の試験管内スクリーニングではなく、正常骨髄細胞を標的にした後、骨髄再建を行い、さらに腫瘍を移植する in vivo のスクリーニングで、大変な労力をかけている。
その結果、腫瘍組織での発現が低下した細胞膜分子のトップが CD300ld で、期待通り好中球に強く発現し、ノロウイルスの受容体であることがわかっているが、機能がまだよくわかっていない膜分子だった。
この分子をノックアウトしたマウスを作成し、腫瘍移植実験を行うと、腫瘍の増殖が抑えられる。すなわち、この分子は好中球で発現し、腫瘍免疫を抑える働きがある。実際、ノックアウトマウスの腫瘍組織では、腫瘍増殖を助ける CD14陽性好中球の浸潤が選択的に抑えられ、さらにキラー細胞が増加し、逆に抑制性T細胞が低下し、ガンの環境を完全に増殖抑制型にリプログラムできる。
次に、ノックアウトマウスを用いて下流のシグナルを探ると、CD300ld は炎症増強性の環境を形成する S100A8/A9分子の発現を誘導し、腫瘍への好中球の浸潤を促し、腫瘍増殖を助けていることが明らかになった。
残念ながら、CD300ld を刺激する分子が何かは特定されていないが、子の分子を活性化する抗体を用いて刺激実験を行うと、STAT3 が下流で働いていることがわかる。そこで、CD300ld の細胞外部分を抗体Fc部分と合体させたキメラを形成し、CD300ld の機能を阻害すると、ノックアウトと同じ効果が得られ、腫瘍増殖を抑制する。
また、PD-1 に対するチェックポイント治療と組みあわせると、相乗効果が得られることから、ガンの周囲環境を整えることの重要性を示している。
人間の腫瘍組織でも発現が見られ、さらに高い発現を示す患者さんほど予後が悪いことから、人間でも同じように働いており、ガンの治療標的になり得ることを示している。
以上が結果で、本当なら PD-1 チェックポイント治療で Cold 状態を Hot にするとともに、CD300ld を阻害して excluded 状態を元に戻すという治療は十分説得力がある。
2023年9月10日
先日組織学の限界を打ち破る新しいテクノロジーの可能性について解説する YouTubeジャーナルクラブを行った(https://www.youtube.com/watch?v=KtjY4JEEjaA )た。わざわざこの分野をまとめたのは、これまで空間情報は得られるが、個々の細胞の状態については限られた解析しか出来なかったのが、組織構造を犠牲にして単一細胞浮遊液にする必要があった様々なテクノロジーを、組織構造を保ったまま利用できる様になったことのインパクトを感じたからだ。
今日紹介するミラノミケランジェロ財団とケンブリッジ大学が協同で発表した論文は、新しい組織学的方法論の真価を問う試金石となる研究で、新しい組織学を用いて乳ガンの免疫治療の効果を予測できるか調べている。タイトルは「Spatial predictors of immunotherapy response in triple-negative breast cancer(トリプルネガティブ乳ガンの免疫治療の効果を予測する空間的要因)」で、9月6日 Nature にオンライン掲載された。
これまで乳ガンはガンのネオ抗原が少ないこともあり、免疫チェックポイント治療 (ICB) の対象にはなってこなかった。しかし、DNA修復異常を持つケースも多く、現在どのような患者さんを対象として選ぶかの研究が進んでいる。
この研究ではなんと280人の患者さんを無作為に、化学療法+ICBと化学療法のみにわけ、手術前のネオアジュバント治療として治療を行い、ネオアジュバント治療前、治療中、そして終了後手術による摘出標本、をそれぞれサンプリングしている。
使われたテクノロジーは Imaging Mass cytometry (IMC) と呼ばれる方法で、金属ラベルした抗体を用いて43種類の蛋白質を染色した組織に、レーザービームを順番に当てて、そのスポットでの蛋白質の発現量を調べる方法だ。細胞浮遊液については既に CyTOF法として普及している。
ネオアジュバント治療で最初とで途中にバイオプシーも行うというセッティングは完璧だが、組織構造を保存して調べたメリットは残念ながらそれほど感じることは出来なかった。
結論をまとめておくと、
化学療法だけの場合、上皮のサイトケラチンと GATA3 発現のみが夜ごと関わっており、効果予測のバイオマーカーは多くない。
これに対し、化学療法と IBC を組みあわせた場合は、ガンの MHC発現量や、T細胞の転写因子発現や増殖など、効果予測に利用できる要因を多くリストすることが出来る。
組織的には TCF1 を発現した T細胞が MHC発現の強いガンの周りで増殖している場合は効果が高い。また、最初の組織像と、ICB が始まってからの組織像では効果予測に関わる因子が変化し、例えばT細胞では、ガン周囲にパーフォリンやグランザイムといった、細胞傷害性分子を発現する細胞の存在が重要になる。
ガン側では、CD15 のような糖鎖抗原を発現するガンは治療抵抗性の確率が高い。
以上、新しいテクノロジーでないとわからなかったとまでは言えない結論と言える。しかし、このようにパラメーターが増えると、情報処理の方が重要になる。従って、今後より詳しくデータを見直せば面白いことがわかる可能性は十分ある。構造という複雑な過程を情報化するための取り組みは始まったばかりだ。
2023年9月9日
アリクイの様に昆虫を主食にする動物だけでなく、昆虫食は蛋白質源としてサルの脳の進化にも関わるという話がある。中でも面白いのは2014年に紹介した、アルコールデハイドロゲナーゼ4が、オランウータンにはなく、ゴリラ以降我々まで存在しているという話だ(https://aasj.jp/news/watch/2661 )。すなわち、類人猿が地上に降りる機会が増えると、熟した果物を食べる様になり、同時にその中に混在する昆虫が蛋白源となり、脳の進化にも寄与したという仮説だ。
この真偽はともかく、昆虫食、特に豊富に含まれるキチンを食べ続けるとどうなるのかについて調べた面白い論文がワシントン大学から9月8日号 Science に発表された。タイトルは「A type 2 immune circuit in the stomach controls mammalian adaptation to dietary chitin(胃に存在する2型免疫サーキットがキチン食への適応を調節している)」だ。
実は2014年、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のグループにより、キチン食が自然免疫を刺激して好酸球浸潤を伴う消化管の炎症を起こすことを示した論文が発表されている。当然昆虫食に対するよいイメージはない。
これに対し、詳しく調べればキチン食にも良い効果があるのではと詳しく調べたのがこの研究だ。まず昆虫を主食とする動物が食べるキチン量をマウスに投与すると、2014年の論文で示された様に IL-25、IL-33、そして TSLP の3種類のサイトカインを媒介として、自然免疫に関わる ILC2 細胞が活性化し、この細胞により分泌される IL-5 や IL-13 により好酸球浸潤を伴う炎症が起こる。
ただこれだけでなく、キチン食では胃が膨満し、内容物も2倍以上に増加する。さらに調べると、キチン食はまず胃のタフト細胞を刺激し、ここから分泌される様々な因子が、胃を膨満させ、これにより刺激されたメカノセンサー細胞から IL-25 などの ILC2 刺激因子が分泌され、自然炎症が誘導されることが明らかになった。風が吹くと桶屋が儲かる話ぐらいややこしいが、この過程にリンパ球や、腸内細菌叢は全く関わっていない。
では、キチン食を続ければどうなるのか。驚くことに、胃の上皮が発達し、腸の長さも10%異常上昇する。また、好酸球の浸潤を伴う炎症も続く。しかし、キチン食は胃の膨満を誘導するだけでなく、GLP-1 をはじめとするニューロペプチドの分泌も促す。
うまくいけばメタボが改善されるのではと、高脂肪食を摂取させて調べると、インシュリン感受性は昆虫食で改善する。ただ、脂肪が減って体重が低下するまでには至らない。
これは、キチンが速やかに分解されるためではないかと考え、キチン分解酵素の発現を調べると、胃では分泌腺に発現して、キチン刺激により誘導され、特に酸性条件でキチンを速やかに分解することがわかった。従って、キチン刺激は脂肪代謝まで改善するより前に、分解されていることがわかった。
この結果はまた、哺乳動物も昆虫食に適応するため、胃をプログラムし直して、キチンを摂取したときに、キチン分解酵素を分泌する様になったと考えられる。
以上が結果で、昆虫食への適応としてのキチン分解酵素の誘導システム形成の副作用として、IL-5 分泌を伴う2型アレルギーが誘導されるように見えるが、このグループはこれも、消化管への寄生虫感染に対応するための適応ではないかと考えている様だ。
いずれにせよ、昆虫食(エピカニの殻も同じ)は、普通の食事とは異なることがわかった。炎症が起こっても大丈夫かについては、昆虫食を続けている人たちの疫学調査を待つしかない。
2023年9月8日
最近の脳内留置電極を用いた ヒト脳の研究は目を見張る勢いで、例えば脳活動から行動を再現すると言ったデコーディングは実用化のレベルまで達しており、後は安全な長期留置が可能な電極が開発されるかにかかっている。しかし、神経回路となると、あらゆる場所に電極を置くことが出きないため、研究は簡単でない。
今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、甘くて脂肪の多い食べ物の味を覚えてしまうと、同じ食べ物についつい手が伸びて過食になる現象の神経回路を人間で解明しようとした研究で、8月30日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「An orexigenic subnetwork within the human hippocampus(食欲増進のサブネットワークが人間の海馬の中に存在する)」だ。
マウスを用いた研究で、視床下部外側 (LH) の MCHホルモンを分泌する神経から、海馬領域のドーパミン受容体発現神経に投射する神経回路が、美味しい食べ物を覚えて、その食べ物を好む行動に関わることが示されているが、人間では研究が進んでいない。
そこでこの研究では、この回路を人間で研究するとしたら何が可能かを追求している。まず、LHと海馬腹側外側領域(dlHPC)が実際に結合しているか、高解像度の7テスラMRI を用いた確率論的トラクトグラフィーを用いて確かめている。ただ、この方法ではどうしても正確さに欠けるので、両方に電極を留置した希な患者さんを利用して、それぞれの刺激実験を行い、両者が機能的な神経結合を持つことを示している。
ただ、これだけでも飽き足らず、実際の神経投射があるのかについては、死後脳を用いる実験を計画、許可を得て MCHホルモン染色を用いた免疫組織学を行い、解剖学的当社を確認している。
以上、両者の結合を示す証拠を示した上で、次に機能実験を行っている。課題はミルクセーキタスクと呼ばれており、画面で見たミルクセーキに対する神経反応を測定している。面白いことに、水には反応せずミルクセーキに反応して起こる海馬の活動は、θ波と呼ばれる 4−5Hz の成分で、統合された情報が伝えられているときに見られることを考えると、海馬で美味しい記憶が統合されていることが覗われる。
最後に過食の女性でこの回路を MRI で調べると、過食の女性ではこの回路の結合性が有意に低下していることを明らかにしている。個人的には、結合性が上昇するから過食になるのかと思っていたが、統合することは過食を抑制することにも関わるのかも知れない。
以上が結果で、一つの回路を人間で調べるためには何が必要かを教えてくれる面白い論文だ。ここまでの実験を可能にするためには、基礎臨床ががっちりとタッグを組む体制が必要で、是非我が国でもこのような研究を可能にする仕組みが必要だろう。でないと待っているのは、マウスの実験だけで満足する袋小路だけだ。