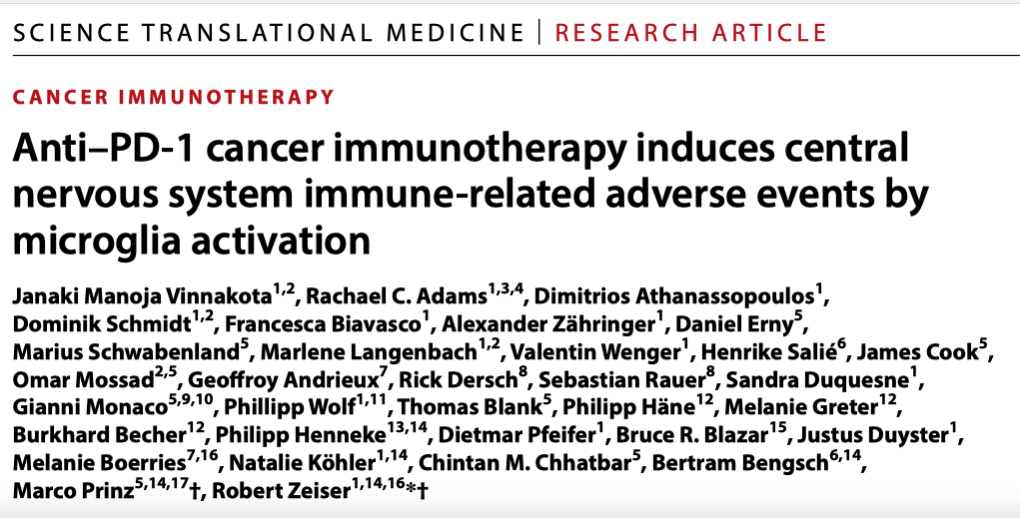2024年6月20日
この記事を読んでいる読者の多くは、現在日本経済新聞に連載中の本庶先生の「私の履歴書」も読んでいることと推察する。私自身は、ドイツから帰って京都で細々と研究を始めた頃に、本庶先生が京大教授に就任されたこともあり、研究室との交流を通して外野から実際に見聞きしていたことなので、当時本庶先生がどう考えていたのかを改めて知ることができ、特に興味深く読んでいる。折しも、昨日、今日と石田さんが PD-1 をクローニングしてからの話なので、それに合わせて PD-1 についての論文を選ぶことにした。
毎日論文を読んでいると PD-1 研究が想像以上に多方面へと拡大しているのがわかる。例えばPD-1抗体が記憶を高めるといった結果はさすがの本庶さんも驚くだろう(https://aasj.jp/news/watch/22566 )。今日紹介する米国・バンダービルド大学からの論文は、肥満パラドックスとして知られる肥満はガンのリスクだが、肥満の人には PD-1 抗体がよく効く現象が、肥満により、マクロファージにより発現する PD-1 で説明できるという論文で、6月12日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Obesity induces PD-1 on macrophages to suppress anti-tumour immunity(肥満によりPD-1がマクロファージに誘導され抗腫瘍免疫を抑制する)」だ。
実を言うとこの論文を読むまで肥満パラドックスのことは知らなかった。肥満がガンのリスクであることは有名な事実だが、PD-1 抗体治療現場では肥満のガン患者さんには PD-1 抗体が効きやすいという現象が知られており、肥満パラドックスと呼ばれていたようだ。この研究では、高脂肪食を投与して肥満にしたマウスでは、正常マウスよりガンの増殖が早い。ところが PD-1 抗体を投与すると、正常マウスと同じぐらいガン増殖を抑制する。すなわちネットで見るとより強い効果があるように見えることを示して、マウスでも肥満パラドックスが再現できることを示している。
次に腫瘍組織を single cell RNA sequencing から、肥満マウスのガン組織ではマクロファージが PD-1 を発現しており、しかも様々なマクロファージの機能が低下していることを発見する。また、マクロファージに PD-1 を誘導する条件を調べると、肥満とともに LPS など炎症シグナルも PD-1 を誘導することを明らかにする。肥満により上昇する遊離脂肪も炎症シグナルと同じように働き、これが PD-1 上昇の原因であることも確認している。
実際腫瘍組織で PD-1 を発現するマクロファージは、ミトコンドリアの活性化を伴う代謝変化とともに、増殖活性が高まっている一方、炎症性サイトカイン経路の低下が見られる。すなわち、炎症シグナルで誘導される PD-1 は、炎症を抑える働きを持つことがわかる。
一方、PD-1 をノックアウトしたマクロファージや、PD-1 抗体処理により、この抑制が外れるおかげで、炎症性サイトカインの発現が上昇し、抗原提示などのマクロファージ活性が高まる結果、キラーT細胞とともに腫瘍を抑制できるという話になる。
この研究では肥満が PD-1 を誘導するということに注目しているが、実際には腫瘍局所の炎症によりマクロファージが PD-1 を発現してチェックポイント機能を発揮するというメカニズムが、たまたま肥満にも当てはまったと考えるべきだろう。PD-1 ストーリーはどこまで拡大していくのだろうか。
2024年6月19日
最近 iPS 細胞由来ドーパミン神経を用いたパーキンソン病治療に関する報道をほとんど聞かなくなったし、論文としても目にする機会がほとんどない。Clinical Trial Government に登録されている治験を検索しても、なんとなく低調な気がする。ES 細胞や iPS 細胞による治療が最も待たれるのがパーキンソン病かと思って見てきたが、大きな壁に当たっているのではと心配している。
おそらく最も重要だと思われるのが、移植した神経細胞が生き残って機能するかだが、これまで経験的に問題が改善したという話はあったが、今日紹介する韓国・大邱慶北科学技術院と米国スローンケッタリングガンセンターからの論文は、実験的に移植ドーパミン神経細胞が失われる原因を特定し、それを解決する方法を示した研究で、6月11日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「TNF-NF-kB-p53 axis restricts in vivo survival of hPSC-derived dopamine neurons(TNF-KF-kB-p53 経路がヒト多能性肝細胞由来ドーパミン神経の生体内での生存を制限する)」だ。
この研究ではまず CRISPR/Cas9 スクリーニングを用いて、移植した iPS 細胞由来ドーパミン神経の維持を妨げている遺伝子を探索し、移植後25日目で生き残っている細胞では p53 分子がノックアウトされていることを明らかにする。この結果に基づいて、p53 をノックアウトしたヒト iPS 細胞由来ドーパミン神経をマウスに移植すると、ばらつきはあるがノックアウトにより生存可能性が促進されることを確認している。
次に移植後の p53 発現を調べると、移植後4時間ぐらいから誘導され、72時間をピークに発現が見られる、すなわち移植というストレスに反応していることがわかる。そこで、p53 を誘導する分子機構を探索し、最終的に TNFα とその下流の NFkB が p53 を誘導していることを突き止める。
ヒト由来、すなわち移植ドーパミン神経が反応性に分泌する TNFα が自らを刺激して NFkB を誘導し、これが p53 誘導に関わることが明らかになった。
そしてこの研究のハイライトになるが、細胞移植とともに TNFα に対する抗体を脳内に投与すると、やはりばらつきはあるが、移植後の生存を高めることができ、さらに6ヶ月後の機能も確認することができる。
最後に、ヒト・マウスではなく、マウス・マウスの組み合わせで同じ実験を行い、このストレスによる TNFα 活性化がヒト細胞をマウスに移植したからではなく、マウスドーパミン神経でも同じ結果が得られることを示している。
結果は以上で、前臨床研究の段階だが、どうして今までこのような研究が行われなかったのかと思うぐらい、重要な研究だと思う。この研究では p53 だけに焦点を当てているが、他にも細胞死を助ける分子も見つかっている。将来は p53 以外の経路も研究されると思うが、TNFα 経路は明日からでも実行可能な点が大きい。もし私が感じているパーキンソン病細胞治療の壁が移植細胞の維持なら、積極的に取り入れて何の問題もない方法だと思う。私の NPO にもパーキンソン病のメンバーがいるが、細胞移植については、10年ほど前に興奮した後何の情報も聞こえてこないため、ほとんど諦めの状態だ。この研究から希望が生まれることを期待する。
2024年6月18日
マラリア、トリパノゾーマ、ライム病など昆虫などにより媒介されて人間に感染する細菌類は、今もなお治療が難しく、人間が克服すべき重要な感染症のグループになっている。今日紹介するイェール大学、バージニア大学、フレッドハッチンソンガンセンターが協力して発表した論文は、このようなベクター媒介細菌と直接反応するホスト側のタンパク質を網羅的に調べた研究で、6月13日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「An atlas of human vector-borne microbe interactions reveals pathogenicity mechanisms(ヒトとベクター媒介細菌との相互作用アトラスは病理メカニズムを明らかにする)」だ。
このグループは細菌と相互作用に関わりそうなヒト細胞外タンパク質3324種類を個別に発現している酵母菌を作成し、この酵母菌とベクター媒介菌(VM)を混ぜた後、VM に結合したタンパク質を特定し、その機能を探る研究を行っている。その結果、713のヒト細胞外タンパク質が82種類の VM と相互作用をすることを見つけている。そして、これらのタンパク質が直接実際の細菌とも相互作用していることを確認している。この方法がこの研究のハイライトで、後は一つ一つの相互作用を調べることになる。この研究でもその一部だけが解析されているが、今日はその中から面白い例をいくつか紹介する。
細胞外で増殖する細菌と、細胞内で増殖する細菌に結合する分子は大きく異なっている。また、一つの細菌あたりに結合するタンパク質は、細胞外細菌に対するタンパク質の方が数が多い。また、以前に調べた常在菌に結合する細胞外タンパク質の数と比べると、病原菌に対してはより多くのタンパク質が相互作用する。
多くの菌の中でも、ダニ感染によるスピロヘータが媒介するライム病やツツガムシ病菌と反応するホストのタンパク質は317種類と多い。このスクリーニングで、CD68 分子がツツガムシ病が感染後マクロファージの中に侵入する分子である可能性が示された。さらに、ツツガムシ病菌はエイズウイルスと同じ CXCR4 と相互作用することがわかったが、なんとツツガムシ病への免疫反応が、エイズ感染を防ぐという観察がある。
マラリアのスポロゾイトは様々なサイトカインに関わる分子と結合するが、マラリア感染が強い一種のサイトカインストームを誘導するのと一致する。特に、IL-15 受容体と強く結合することは、サイトカイン誘導のリード役として機能している可能性がある。
レプトスピラ症では、それまで低い浸透圧に存在していた菌が、人間の中で NaCl に触れて大きな変化を遂げ、その結果バソプレシンと結合するようになることがわかった。レプトスピラはブタで腎障害を起こすことが知られており、この相互作用が原因である可能性がある。
ライム病のスピロヘータの中には神経症状を強く起こすタイプが存在するが、これらの菌は神経系に発現されている分子と特にそうごさようをしめす。
さらにライム病は直接 EGF と反応して遺伝子発現を変えることも発見している。特に、人間の身体に入って体温に晒されたときにこの反応が起こることから、この反応を抑えることが感染拡大を抑える可能性がある。
最後に、細胞内寄生菌の7割以上がディスルフィド基を切断する、イソメラーゼと直接反応すること、またこの酵素を阻害すると細胞内感染が低下することも示している。
以上が面白い例だが、これまで個別に研究されてきたベクター媒介細菌をまとめて調べてみたことで、個別では気づかなかった様々な感染メカニズムが見えてきたという仕事で、派手さはないが重要な研究だと思う。
2024年6月17日
IL-23 は2種類の分子が複合したサイトカインで、そのうち p40 は IL-12 と共通で、p19 が IL-23 特異的という、複雑なサイトカインで、シグナルも IL-12 とオーバーラップするところもあるが、特に腸管の炎症性疾患のメディエーターとして、治療にも利用されている。
今日紹介する米国コーネル大学からの論文は、IL-23 によって腸管で起こる細胞変化を調べることで、自然リンパ球の中の、その一部はパイエルバンなど免疫組織の発生に関わり、我々も現役時代に研究していた ILC3 を刺激し、免疫抑制型に変化させることを明らかにした研究で、6月12日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「CTLA-4-expressing ILC3s restrain interleukin-23-mediated inflammation(CTLA-4 発現 ILC3 が IL-23 に媒介される炎症を抑制する)」だ。
この研究では IL-23 受容体 ( IL-23R ) 陽性細胞を蛍光でラベルしたマウスを用い、IL-23 により様々な細胞で起こる変化をモニターしている。大体6種類の IL-23R 陽性細胞が特定できるが、リンパ組織誘導細胞以外の ILC3 でチェックポイント分子の一つ CTLA4 が発現し、この現象はT細胞のない Rag ノックアウトマウスでも起こることを発見する。
この予想外の発見がこの研究の全てで、single cell RNA sequencing も特定の分子に絞って見直すことで、これまで見落としてきたことが発見できることを示している。当然次の課題は、IL-23 により誘導された CTLA-4 がチェックポイント分子として働くかになる。
これまで IL-23 は腸管への細菌感染で誘導されることが知られているが、この点を確認し、無菌マウスや抗生物質投与マウスでは、IL-23 が誘導されず、その結果 ILC3 の CTLA-4 発現も起こらないことを明らかにしている。すなわち、腸の細菌叢が IL-23 を誘導し、その結果 ILC3 が CTLA4 を発現する。
次に ILC3 が発現する CTLA-4 の機能だが、NKp46 発現 ILC3 で CTLA-4 をノックアウトする実験で、細菌に対する T 細胞反応を抑える抑制性 T 細胞の減少が見られることを発見する。すなわち、ILC3 は抑制性 T 細胞と同じように CTLA-4 を発現し、同時に抑制性 T 細胞を誘導することで炎症の拡大を抑えていることがわかる。
同じ実験を T 細胞のない Rag ノックアウトマウスで行うと、感染による IL-23 により自然炎症は普通に誘導されることから、ILC3 の CTLA-4 発現はもっぱら同時に起こる T 細胞の反応を制限することに向けられていることがわかる。
さらに CTLA-4 と反応する白血球上の CD80、CD86 の量が低下することで、PD-L1 が T 細胞に利用しやすくなり、この結果さらに強い免疫抑制を誘導することがわかる。以上のマウスの結果を、人の炎症性腸炎で調べ、IL-23 上昇により、人の大腸でも ILC3 が CTLA-4 を発現し、同時に白血球で PD-L1 が発現して、炎症を抑えようとしていることを明らかにしている。
以上、ILC3 は lymptoxin 発現により免疫組織の発生の誘導に関わるように、ILC3 の一部のサブセットは細菌性の炎症へのT細胞反応を調節するオーガナイザーとして働いていることがわかった。いずれにせよ、免疫システムの調節の複雑さがまた明らかになった。実際チェックポイント治療で腸炎は重大な副作用だが、自己免疫性の反応だけでなく、炎症抑えるオーガナイザーの役割まで抑えることで症状を重くしていると考えられる。今後の臨床にも重要な発見だと思う。
2024年6月16日
肥満の父親から生まれた子供が肥満になるというエピジェネティックなメカニズムは多くの興味を引きつけてきた。実際、精子のクロマチンは一度完全に解消されるので、ゲノムにエピジェネティックなメモリーが残るとは考えにくい。その後、短い RNA を読む技術が進んだおかげで、受精時に精子から短いノンコーディング RNA が伝わって、それがクロマチン形成を調節するのではと考えられるようになった。
今日紹介するドイツミュンヘンのヘルムホルツセンターからの論文は、マウスの実験と人間のデータベースを組み合わせて、肥満の影響が成熟した精子のミトコンドリア由来 RNA の変化を誘導し、これが分解された短い RNA (sncRNA) として受精卵に伝わり、子供の代謝関連遺伝子をエピジェネティックに変化させることを示した研究で、6月5日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Epigenetic inheritance of diet-induced and sperm-borne mitochondrial RNAs(ダイエットにより誘導されるエピジェネティックな変化は精子中のミトコンドリア RNA で伝えられる)」だ。
PiwiRNA を筆頭に精子形成で多くの sncRNA が形成されるが、これまでの研究で父親の代謝の影響は精子ができてから精巣上体に蓄積される段階で起こるのではと考えられるようになっていた。この研究はまずこの点を確認するため、精子形成後精巣上体に精子が蓄積される2週間を狙って高脂肪食を与え、体重変化とは行かないがインシュリン抵抗性など糖代謝に関わる変化が精子を通して伝えられることを明らかにする。
このとき、高脂肪食で変化する精巣上体 mRNA を調べると、肥満の子供の mRNA 変化とオーバーラップすることから精巣上体での精子の経験が子供の肥満を誘導することを確認している。
次にどの sncRNA が肥満によって最も影響を受けるかを様々な方法で調べ、ミトコンドリア由来の tRNA や rRNA が代謝を関知し、それを子供に伝えていることを決定している。またマウスの結果を、人間の精子で確かめ、特にミトコンドリアの tRNA が肥満と大きく関わっていることを確認している。
そして、この sncRNA が確かに受精卵に伝わっていることを、人工授精後2細胞期に確認している。また、その結果初期胚の転写、特に酸化的リン酸化などミトコンドリアの代謝に関わる遺伝子発現が変化して、これが子供のインシュリン抵抗性を誘導することを確認している。
最後に、ミトコンドリアの遺伝子を変化させた精子を用いる実験で、確かにミトコンドリアの異常が、エピジェネティックに子供に伝わることを確認している。
以上が結果で、もう少しわかりやすく説明し直すと、精子ではほとんどの遺伝子発現はストップするが、ミトコンドリア維持のために RNA が転写されている。精巣上体から受精まで酸素濃度の異なる環境を通過する間に、酸化的リン酸化が高まるため、この mRNA は転写が上昇する。これによって、精巣上皮で経験したミトコンドリア RNAの 変化が増幅され、またこの RNA は分解され sncRNA として受精卵に伝わり、そこでエピジェネティックマーキングを変化させるというシナリオになる。
要は母親だけでなく、なんとか父親の経験も伝えようという涙ぐましい努力がにじんだ話で、面白い。
2024年6月15日
今日は最近読んだ副作用に関する論文3題を紹介する。
まず最初は eClinical Medicine 6月号に掲載されたスウェーデン・ルンド大学からの論文で、2007年から2017年までにスウェーデンで登録された悪性リンパ腫の患者さん11905人について、様々な聞き取り調査を行い、何らかの入れ墨を入れた場合、悪性リンパ腫の発生頻度が1.2倍上昇し、さらに入れ墨後2年以内ではそのリスクが1.8倍になるという調査研究だ。入れ墨はマクロファージを使っていることなので、十分納得できる結果だが、スウェーデンで入れ墨を入れている確率がすでに2割近くになっているということに改めて驚いた。
次の European Heart Journal にオンライン掲載されテイルクリーブランドクリニックからの論文は55歳-72歳の中高年の血清のメタボローム検査を行い、キシリトール代謝物の量とその後3年の心臓血管疾患による死亡率を見ると、代謝物の多い人ほど死亡リスクが高いことを明らかにし、甘味料としてキシリトールを使うことの危険性を警告している。そして、この原因について、キシリトールが試験管内で血小板を活性化すること、さらにキシリトール摂取により血小板の凝集が著名に高まることを示し、これが心臓死が高まる原因であることを示している。かなり食品や飲料に使われている甘味料なので、緊急の検討が必要だと思う。
最後の6月12日号 Science Translational Medicine に掲載されたフライブルグ大学からの論文は PD-1 に対する抗体を用いたチェックポイント治療の副作用の一つが、直接ミクログリアに対する作用によるもので、脳内の神経炎症が上昇する結果、認知機能や運動機能が犯される可能性を示した研究だ。
覚えていただいているかどうか、昨年7月に PD-1 が神経系にも発現しており、抗体により記憶や学習能力が高まるという思いがけない結果を示したデューク大学の論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/22566 )」。今日紹介する論文はこの全く逆で、PD-1 抗体治療による自己免疫性と考えられてきた神経症状の中には、抗体のミクログリア直接作用によるものが存在することを示している。
この論文も詳細を飛ばして簡単に紹介するが、ほとんどはマウスの実験で、正常マウスに PD-1 抗体を投与したとき、抗体は脳に入ってミクログリアの形態変化を誘導し、炎症型ミクログリアへの転換を誘導する。そして、ミクログリアの Syk キナーゼの活性化が炎症型ミクログリア形成に関わっており、Syk キナーゼ阻害剤投与で、PD-1 によって誘導される認知障害は軽減するという結果だ。最後に、PD-1 抗体を投与された人間の脳の解析でも、同じようなミクログリア活性化が存在することを示し、おそらく PD-1抗体投与による神経症状の一部は、ミクログリアへの直接作用であると結論している。
神経に働くと記憶が高まり、ミクログリアに働くと記憶が低下すると相反する論文が出ているので、読む側はどちらもにわかに信じられないと思ってしまうが、結論を得るためには、それぞれの細胞の PD-1 発現から始める地道な研究がまず必要かと思う。
2024年6月14日
考古学での時代計測には科学の粋が集められているように感じる。最も有名なのは有機物の炭素アイソトープの減少を用いた方法で、カバーする範囲から人類の歴史を調べるのに適している。一方考古学で重要になる人間の活動が残った痕跡を調べる方法として、加熱による放射線エネルギーの変化を利用して、最後に加熱された時期を探るルミネッセント法などが知られている。ただ、これらの方法を1万年以上前の旧石器時代に利用しようとしても、区別できる時間解像度が500年単位になってしまい、例えば繰り返し使われた洞窟内での活動の時代測定の制限になっている。
今日紹介するスペインにあるデ・ブルゴス大学からの論文は、高温により残留磁気のパターンが固定されることを利用して、囲炉裏に使われた石の残留磁気を調べて、それが使われた時間を数十年単位で計測した研究で、6月5日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「The time between Palaeolithic hearths(旧石器時代の囲炉裏の使われた時間差を調べる)」だ。
残留磁気を用いて地球磁場の変化を探る研究については知っていたが、この残留磁気が熱によって固定されることを利用して、岩石が熱に晒された時間を推定する方法があることは全く知らなかった。
この研究では、ネアンデルタール人によって繰り返し使われた El Salt 洞窟 UnitX で発見された5カ所の囲炉裏跡が使われた時代関係を、この方法を用いて解析している。といっても、私には測定の具体的イメージほとんどないので、ちょっと調べてみたが、サンプルを調製した後、熱をかけたり、磁場を消去したり、大変な作業を有する測定だ。そして、その地域の地磁気の変化と照合して時代測定を行っている。
実際には使われた絶対的時間を測定するのではなく、残留磁気から5カ所の囲炉裏の間の時間差を調べ、これらは250年程度の時間で順番に作られたもので、それぞれは数十年ー100年程度の時間差で順番に作られたことを明らかにしている。すなわち、人間の寿命レベルの時間的違いで、囲炉裏が新たに作られたことを意味している。
以上が結果の全てで、わかったことはこれ以上でも以下でもない。200年というと鎌倉幕府より長い時間だが、その間にネアンデルタール人で何があったのか、同じ地層の他の遺物を比べないと、この発見の意味を知ることは難しい。ただ、火を使うという人間特有の行動を利用すると、少なくとも鎌倉幕府をさらに5つの時代に分けることができるようになったことから、旧石器時代の歴史がさらに詳しく分析できそうな期待はある
2024年6月13日
他個体からの輸血や骨髄移植は安全に行えるようになっているが、移植する細胞の中に機能的 T 細胞が残っていると、Graft-versus-Host 反応 (GvH) と呼ばれる移植した細胞がホストの臓器をアタックするという、恐ろしい状況が生まれる。いったん起こってしまうと、現在最も有効とされている JAK 阻害剤を組み合わせた方法でも18ヶ月目の生存が38%という状況だ。
この状況を改善する方法として2004年から試みられているのが、間質ストローマ細胞株(MSC)の移植で、明らかに GvH 反応を抑える証拠があるのだが、有効な MSC の安定供給が難しいという最大の問題があった。
今日紹介するオーストラリア Cynata Therapeutics 社からの論文は、一人の個人から調整した iPS 細胞ストックから MSC を誘導し、安定供給を可能にした細胞治療製品 CYP-001 を、ステロイド抵抗性の GvH 治療に用いた観察治験研究で、5月22日 Nature Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Two-year safety outcomes of iPS cell-derived mesenchymal stromal cells in acute steroid-resistant graft-versus-host disease( iPS 細胞由来間質ストローマ細胞を用いたステロイド抵抗性 GvH 病の2年目の成績)」だ。
前もって治験登録を行ったiPS細胞由来細胞を用いた移植治療治験は、我が国も含めて数多く進行していると思うが、2020年同じ Nature Medicine に、論文として結果報告までに至った最初の iPS 細胞利用製品として報告されたのが CYP-001 で(Nature Medicine 26:1720−1725、2020)、今日紹介する論文は同じ患者さんの2年目の経過になる。
2020年の論文では、一人のドナーから100万個の iPS 細胞が入ったバイアルを9万本調整、それぞれの iPS 細胞バイアルからほぼ100人分に当たる MSC 治療用ストックを作成できることが示されている。そして、GvH が発生して標準のステロイド治療に反応しなかった15人について、1週間間隔で2回、100万個/Kgあるいは200万個/Kg CYP-001 を投与して、安全性を確認するとともに、100日目で86%の患者さんが治療に反応したことを報告している。
このとき調整された iPS 細胞及び MSC は計算上ほぼ3000万回の治療に使えるということで、ほぼ世界中の需要を長期間まかなえることになる。
そして今回の報告では、9例の患者さんが2年目も存命だが、そのうち3名は慢性の GvH 症状が続いていることを示している。そして、生存曲線から死亡例は最初の6ヶ月までで4例、12ヶ月で新たに2名発生している。
結果は以上で、GvH 治療として最も期待できるとされる18ヶ月目で38%生存を明らかに凌駕する画期的な成績といえる。今後、急性期を乗り越えた後半年ぐらいで発生する慢性 GvH に CYP-001 を再投与する、あるいはこれまでで最も効果が見られた JAK 阻害剤や、さらに強い T 細胞抑制などを組み合わせることで、GvH を完全に克服できるようになるのではと期待される。
MSCをiPS細胞から作って製品にするとは、現役時代予想しなかったが、iPS細胞段階ではほぼ無限に細胞を増やすことができることを利用して、細胞治療では実現が難しかった全世界で使える一種類の細胞製品を完成させたことが最も重要なポイントだと思う。おそらく FDA の認可も近いと思うので、ついに万国共通に使えるiPS細胞由来細胞製品が生まれたと喜んで良さそうだ。
2024年6月12日
老化を図る生物学的な指標の一つに幹細胞システムのクローン増殖が挙げられる。研究しやすい血液で調べられることが多いが、突然変異の結果増殖能が高まったクローンを高頻度に特定できることがわかっている。そして、このようなクローン増殖は白血病の頻度を高めるだけでなく、機能異常の血液細胞が増えて動脈硬化を助長したりすることが知られている。
今日紹介するペンシルバニア大学歯学部からの論文は、血液クローン性増殖が認められる人に歯周病が多いという観察を、マウスを用いて実験的に確かめた研究で、6月4日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Clonal hematopoiesis driven by mutated DNMT3A promotes inflammatory bone loss(DNMT3A 変異によるクローン性の造血は炎症性の骨喪失を促進する)」だ。
まず4946人の52歳から74歳までの動脈硬化リスクを調べる米国の地域コホート研究参加者の血液を調べると、年齢とともに増加するクローン性造血を3.9%の人で認め、なんとその61.8%が de novo メチル化酵素 DNMT3A の変異を持っており、しかも重症の歯周病が多かったという結果から始まっている。
これを実験的に確かめるため、DNMT のドミナントネガティブ変異をヘテロで持つ骨髄幹細胞を10%、正常骨髄幹細胞を90%の割合で移植したキメラマウスを作り、歯周病と骨の欠損が見られるリューマチ性関節炎で調べている。
まずこの DNMT3A 変異を持つ血液細胞幹細胞は正常細胞より増殖能が高く、3ヶ月も経つと、最初10%だったのが5お%にまで増加する。これとともに、血中 IL-1β、IL-6、TNF が増加し、自然炎症が進行していることがわかる。そして、自然に歯槽骨がむき出しになっているのを認めている。
そこで、実験的歯周炎を誘導すると、DNMT3A 変異を10%持つ個体では、歯周炎の悪化が強く、また歯周での炎症が強く起こっていることを確認する。同じように、骨吸収を伴うリューマチ性関節炎でも、病理的な所見と、症状の悪化が見られる。すなわち、クローン性造血が特に骨吸収を伴うような病気で悪化することを明らかにしている。
あとは歯周組織の single cell RNA sequencing などを用いて、特に歯周病の悪化の原因を探っており、DNMT3A 変異細胞が増えることで、特に白血球の浸潤と炎症性サイトカインの分泌、抑制性 T 細胞の機能不全、そして破骨細胞の分化促進がこの原因であることを突き止める。
DNMT3A の機能を考えると、de novo メチル化が低下することで遺伝子発現異常が起こっていると考えられるので、目血ロームを調べると、全体的に強くDNAメチル化の程度が下がり、多くの遺伝子で発現が高まっていることが認められる。中でも、mTOR を核とする代謝ネットワークに関わる遺伝子の発現が強く認められたので、mTOR 阻害剤ラパマイシンを投与すると、歯周病の悪化を抑えることに成功している。
DNMT3A の機能から考えると、示されたことは、不思議のない納得の話だが、歯学部ということもあり歯周病に焦点を当てた点が面白い。今後高齢者の難治性歯周病は、クローン性造血のサインであるという話になる気がする。
2024年6月11日
相変わらず細菌叢の研究は盛んだが、細菌叢の多様性や種類と身体の状態を相関させる現象論研究から、細菌叢の機能を問うより因果論的な研究へシフトしている。例えば Cell の様な一般紙を1ヶ月振り返ると、胆汁成分から代謝性脂肪肝を防ぐ分子を合成する細菌を特定した研究、そして胆汁ステロイドから妊婦さんに影響のあるプロゲステロンを合成する細菌と酵素についての研究のように細菌の特定・機能のメカニズムの解析が組み合わさった研究と、今日紹介するペンシルバニア大学からの論文のように、膨大な細菌叢データを情報科学的に解析し、やはり有用物質を特定する論文が掲載されており、掲載には現象論を超えたより具体的な結果が求められるようになっている。
今日紹介する論文は、細菌のゲノムビッグデータから機械学習で抗菌ペプチドの特定にチャレンジした研究で、6月5日号の Cell に掲載されている。タイトルは「Discovery of antimicrobial peptides in the global microbiome with machine learning(世界中の細菌叢に存在する抗菌ペプチドを機械学習で発見する)」だ。
研究では、得られる細菌のゲノムデータから、まず遺伝子をコードするオープンリーディングフレーム(ORF)を抜き出し、それをすでに抗菌ペプチド(AMP)を学習した Marcel と呼ぶモデルに読み込ませて、AMP とモデルが判断した、なんと90万近いペプチドを特定している。
といっても90万と言われてしまうと本当にこれが AMP 活性があるのか、やはり実際の実験が必要になる。実際、最初は構造や相同性から、AMP としての機能を確かめようとしているが、α ヘリックスを持つことなどすでに知られている以上に、絶対的な指標は発見されていない。
結局90万の中から100種類のペプチドを選んで合成し、この活性を多剤耐性菌を含む様々な細菌について抗菌実験を行い、79種類に抗菌活性を認めルという結果から、機械学習モデルの予測性が結構高いと結論している。
さらに明確な抗菌活性を示した AMP の殺菌メカニズムを確かめる実験も行い、ペプチド添加により膜電位が破壊され、最終的に細胞壁の破壊を起こす共通のメカニズムを持っていることを示している。そして、これらの AMP を皮膚の感染創に加えることで菌の増殖を抑えられるという生体実験も示している。これらの機能解析結果から、Marcel モデルの信頼性を示した上で、次に AMP がどのように進化してきたのかについて解析を行っている。
この研究で調べられた細菌叢は、土壌細菌叢、海洋細菌叢、人間の腸内細菌叢、口内細菌叢などなど、多岐にわたるが、AMP はそれぞれの細菌叢特異的で、オーバーラップはあまりない。そして、AMP の発現の高い細菌叢は他の細菌を受け入れにくくできており、特定の細菌叢構成を維持する方向で AMP が進化していることがわかる。
次に、このような短いペプチド遺伝子がどのように形成されるのかを調べると、1)長い遺伝子にストップコドンが入る変異で短いペプチド遺伝子が形成される、2)タンパク質をコードする遺伝子が重複後に、ストップコドンが入るケースで、そのほとんどはリボゾームタンパク質由来、3)水平遺伝子伝搬、4)最初から AMP として新たに進化したケース、などが特定できる。
結果は以上で、要するに Marcel モデルを AMP 予測に使えることを示した大変な研究だ。
私たち人間も、インシュリンをはじめとするたくさんのペプチドホルモンを有しており、その多くはプロホルモンを分解して形成されるが、このような合成方法がほとんどないのに驚くが、一方で細菌叢の個性維持に個体間を超えるホルモンのような働きを AMP が持っていることもよくわかる。