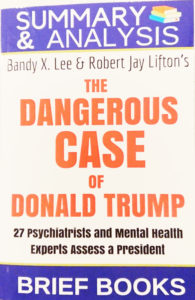2018年1月7日
トレハロースは熱など様々な条件に最も安定な糖だが、精製にコストがかかっていたため、使用は化粧品などに限られていた。その後、デンプンから安価に精製する方法が開発され(最初は1kgが700ドルしたのが、現在では3ドルで精製できる)、多くの食品に添加されるようになって現在に至っている。もともと、多くの自然にある植物に含まれていることから、最も安全な糖として広く使われるようになった。
今日紹介するテキサスベーラー大学からの論文は、確かに食品としてトレハロースが危険というわけではないが、病原性の高いクロストリジウムの病原性を高める役割を果たしていることを示した、ちょっと恐ろしい研究で、Natureオンライン版に掲載された。タイトルは「Doetary trehalose enhances virulence of epidemic clostridium difficile(流行性のクロストリディウム・ディフィシル強毒株の毒性は食事の中のトレハロースにより増強される)」だ。
この研究は、2000年から2003年に流行したクロストリディウム・ディフィシル(CD)RT207株、および1995年から2007年の間に10倍も症例数が増えたRT078の進化が、食品中の炭水化物の変化により誘導されたのではと着想し、様々な炭水化物を調べた結果、2000年以降に広く使われだしたトレハロースが両方の菌株に利用されるが、他の菌は利用できないことを発見する。
次に、トレハロースが利用できるようになるための分子変化を探索し、TreA分子の有無がトレハロースの利用可能性を決めている原因遺伝子であることを突き止める。
この結果をもとに、ではTreAの発現が2000年前後で始まったCDの進化を説明できるか次に検討し、試験管内の実験で、流行性を獲得した株は500倍低い濃度のトレハロースがあればTreAの発現が誘導できること、そしてTreAオペロンを1010種類のCDで調べ、RT028株を含む多くの株では、この違いがTreRリプレッサー遺伝子の1塩基置換により起こっていることを突き止めている。
次に、TreRが正常型の菌株をトレハロースで培養すると、TreBの機能が突然変異によって欠損した細胞株が得られることから、おそらく流行株でのレプレッサー変異が、食品として含まれるトレハロースへの新たな環境適応として選択されたことがわかる。
次に、流行性株をマウス腸内に移植し、トレハロースを含む/含まない2種類の餌を与えて腸炎による死亡率を調べると、トレハロースを摂取することで毒性が強くなることから、トレハロースにより誘導されるtreAが毒性を決めていることを明らかにしている。
以上の結果は、RT027株の話で、同じようにトレハロースが利用出来るようになったRT078株ではtreAは正常のままだ。そこでこの株についても遺伝子の比較を行い、トランスポーターptsT遺伝子が新たに獲得されたこと、これによりトレハロース存在かで細胞の増殖が高まることを確認している。
最後に、私たちの腸内のトレハロース濃度でtreAの誘導が起こることも確認しており、これが決して実験的な条件で起こったことではないことを示している。
まとめると、トレハロースが食品等に使われるようになり独立してトレハロースを利用出来る突然変異が誘導され、これがtreAの発現が高い流行性強毒変異株を誘導し、こうして生まれた強毒株はトレハロース存在下で毒性を最大限発揮するという結果だ。
恐ろしい話だが、2つの重要なポイントがある。一つはCDの強毒株は抗生物質の使いすぎにより発生したという考えは再検討される必要があること、そしてトレハロースを摂取しなければ、流行株でもトレハロース摂取を完全に止めれば毒性が弱いことだ。大至急臨床の現場で確かめるべき重要な論文だと思う。
2018年1月6日
私自身40歳ぐらいから既に30年近く耳鳴りが続いているので、耳鳴りの論文は余計に気になる。2015年にも頭蓋の外から磁場を当てて耳鳴りを治療するJAMA Otholaringology Head Neck Surgeryに掲載された治験研究を紹介したら、読者で耳鳴りに悩む方から、我が国でも治療は行われているが、もちろん保険外で一回5万円かかるという情報を頂いた(
http://aasj.jp/news/watch/3789)。副作用はないが十回は治療が必要なのは、ちょっと抵抗があるだろう。
今日紹介するミシガン大学からの論文は大掛かりな機械が必要のない耳鳴りの治療法開発の研究で1月3日のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Auditory-somatosensory bimodal stimulation desynchronizes brain circuitry to reduce tinnitus in guinea pigs and human(聴覚と体性感覚の二峰性の刺激により脳回路を脱同期させてモルモットと人間の耳鳴りを低下させる)」で、耳鳴りに悩む方々の初夢になればと紹介することにした。
耳鳴りを感じる人ならわかるのだが、何か運動をしたり、痛みを感じたりすると感じなくなることが多い。これは、耳鳴りが純粋に聴覚回路の異常興奮だけで成立しているのではなく、体性感覚など様々な感覚を巻き込んだ回路異常であることを示唆している。神経生理学的に詳しく見ると、聴覚神経の入力を受ける紡錘細胞(FC)は、体性感覚刺激を媒介する顆粒細胞から直接、あるいは車軸細胞を介して回路を形成している。原理的には、耳鳴りはFC細胞を中心とする回路が長期的に増強し(LTP)、同調性が高まっている状態と考えることができる。LTPは長期記憶で、シナプス自体が転写レベル、さらにはエピジェネティックに完全に変化してしまうことで起こるため、耳鳴りは治しにくい。しかし、回路は他の神経にも開いているので、このシナプスを抑制する回路を高めることで治療する可能性が出てくる。
この研究では聴覚への刺激と、首への電気刺激を様々な間隔で与えることで、FC細胞の興奮に影響できるか調べ、音を聞かせた後電気刺激をすると、FCの同期性を抑えられ、逆に電気刺激してから音を聞かせると同期性が高まることを突き止めている。この結果に基づき、音に晒すことで耳鳴りを誘導したモルモットのFC細胞の同期的興奮が、音を聞かせた後電気刺激を与える二峰性刺激で抑えられることを確認している。
この結果を受けて、患者さんの耳鳴りのピッチに合わせて選んだ音をイヤフォンから聞かせた後、首の後ろ、あるいは頬に置いた電極を通して電気刺激する機械を各人に持ち帰らせ、1日30分一ヶ月続けさせている。さらに、一ヶ月休んで、今度は対象と実験群を入れ替え、2峰性刺激で耳鳴りが改善するかを調べている。専門家ではないので、TFI指標がどの程度に相当するかを実感できないが、耳鳴りが長期間続いている人ではこの機器による治療効果が確かにあるという結果だ。基本的に、この機械の副作用はない。
これまでの方法と比べ、生理学的にも納得できるし、また動物実験の裏付けもある。何よりも、音を発生し、一定の間隔で電気刺激を与える機械はそんなに高価なものではないだろう。音の調整など、耳鼻科やあるいは店頭での調整が必要だろうが、私も使ってみたいと思う。
2018年1月5日
私が卒業した1973年には、エイズは存在しなかった。ただ、1980年代になって、ゲイに多い後天的免疫不全病が報告され、ウイルス病として特定されるまでは様々な研究が行われていたのを覚えている。もっとも印象に残っているのは、ドイツに留学している時、マウスの肛門に精子を注入すると免疫不全が誘導されるという論文だ。私自身まだエイズのことを聞いたことがなかった時で、不思議な実験をする人がいるのだと思った。
その後、エイズウイルスが特定されてから、ではどうして急にこのようなウイルスが現れたのかが大問題になった。結局エイズウイルスの起源、サル免疫不全ウイルスに感染していたチンパンジーを食用のために殺した人間が感染し、体内でエイズウイルスができ、そこから広がったことが示された。さらにチンパンジーの感染源が探索され、オナガザル科のスーティーマンガベイなど小型のサルを襲って食べたチンパンジーに感染、その中で2種類のウイルスが組み換えを起こしてサル免疫不全ウイルスが出来上がったことが明らかにされた。
今日紹介する論文はこのエイズ起源についてのシナリオの延長と言える研究でNatureオンライン版に掲載された。タイトルは「Sooty mangabey genome sequence provides insight into AIDS resistance in natural SIV host(スーティーマンガベイのゲノム配列は自然のサル免疫不全ウイルス宿主のエイズ抵抗性にヒントを提供する)」だ。
チンパンジーがスーティマンガベイ(以後マンガベイ)を食べてサル免疫不全ウイルスSIVに感染した理由の一つに、マンガベイではウイルスに感染しても病気が発症しないため、ウイルスが蔓延し、キャリアになっていたことがある。事実、エイズウイルスを感染させてもマンガベイはCD4陽性細胞は正常、低いレベルだがウイルスを作り続けることことが知られている。
この研究は、なぜマンガベイは発病しないのか、ゲノム配列の解析からその解明を試みている。
まずマンガベイのゲノムを解読し、エイズを発症するアカゲザルのゲノムと比較、免疫系に関わる遺伝子を中心に違いを調べて、可能性のある34分子の違いを特定している。しかし、エイズ感染に関わるCD4やCCR5については違いを認めていない。そこで、配列上最も大きな違いが認められた接着分子ICAM-2と、自然免疫に関わるTLR-4に絞ってさらに追求している。
まずICAM-2はマンガベイではリンパ球の表面に出ていないことを突き止め、配列の違いが細胞表面への発現の違いに反映することを明らかにしている(残念ながら、ではこれがウイルス抵抗性にどう関わるかはこの研究では明らかになっていない)。
TLR-4のC末端の配列が感染しないマンガベイでは大きく異なっている。そして、LPS刺激によるNFκBの活性化がマンガベイのTLR-4では強く低下していることを明らかにしている。
そして、この配列はウイルスキャリアとして知られ、またチンパンジーの餌になる4種類のサルで保存されていることも確認している。面白いのは、この違いが全体の進化の系統樹とは別に進んでいることで、何らかの理由で抵抗性のサルが別個に進化してきた可能性が高い。この差を生み出した環境要因が何か、面白い問題が残された。
結果は以上で、なぜマンガベイがキャリアになるのかは明確ではない。しかし、キャリアになるには感染し、ウイルスを作り続ける細胞が必要になる。その意味で、CD4やCCR5が正常であるのも当然だと思う。すなわち発病という点で、この研究はエイズウイルス感染に対するホスト側の多様性を示すとともに、発病の抑制に関する新しいヒントになる可能性がある。
なかなか実験の難しいサルだと思うので、個体レベルの研究は難しいかもししれないが、iPS樹立も含め、今後さらなる追求が進むと思う。
2018年1月4日
Isocitrate dehydrogenaze(イソクエン酸脱水素酵素:IDH)は、低グレードグリオーマの8割以上、急性骨髄性白血病の10−20%に特定の変異が見られることから、私の頭の中では、代謝の変化を介してガンの増殖を助けていると考えてきた。実際、IDHの変異により酵素特異性が変化し、R-2HGが合成され、されにこれがグリオーマの増殖を促進することが示されて、IDH変異=ガンのドライバーという話が出来上がっていた。ところが、グリオーマではIDH変異がある方が予後が良いことがわかり、そう簡単な話ではないことが明らかになってきた。
今日紹介するシンシナティ大学からの論文はオーソドックスな手法でこの疑問を解いてくれた研究で1月11日号のCellに掲載された。タイトルは「R-2HG exhibits anti-tumor activity by targeting FTO/m6A/MYC/CEBPA signaling(R-2HGはFTO/m6A/MYC/CEBPAシグナルを標的に抗腫瘍効果を示す)」だ。
R-2HGはIDH変異体のみにより合成されるため、正常細胞では存在しない代謝物だ。この研究は、変異型IDHによってのみ合成されるR-2HGが本当に細胞の増殖を誘導するのか急性骨髄性白血病AMLの増殖を指標に調べるところから始めている。結果はこれまでの予想に反して、多くのAML株の増殖が抑制され、マウスに移植するモデルでも、R-2HG投与で生存期間を延ばすことができることがわかった。R-2HGによる増殖抑制機構を調べるため、R-2HGの効果が有るガンとないガンの遺伝子発現を比べ、ガン遺伝子MYCが活性化する分子が低下することを発見する。
もともとこのグループはRNAメチル化について研究していたグループで、MYCの活性が低下するのがRNAメチル化酵素FTOを抑制しているからではないかと着想、R-2HGがFTOを抑制することを発見する。他にも、R-2HGはDNAの脱メチル化に関わるTET2も抑制するが、これはR-2HGが効かない細胞株でのみ見られることから、この場合はガンの増殖を上げる方向に働いている。したがって、R-2HGが効果のあるガンに対する作用はFTO抑制がメインの経路で、MYCのRNAメチル化が低下、その結果RNAが不安定化してMYCの活性が落ちることで、細胞の増殖が低下することを示している。他にも、骨髄性白血病の増殖に関わるCEBPAのRNAの安定性も低下させ、これもFTO転写の低下に関わることも示している。
一方、R-2HG抵抗性のガンでは、DNA脱メチル化を介してガンの増殖を抑制するTET2が直接抑制されるため、MYCの不安定化をカバーしていると推察している。
この結果は、グリオーマのドライバーはIDH変異ではなく、逆にIDH変異がグリオーマの急速な増殖を抑えている可能性も示唆する。すでに述べたように、IDH変異は良い予後因子であることがわかってきたが、今回の結果はこれも説明できる。とすると、現在行われているIDH変異分子の活性抑制によりガンを制圧する可能性は低く、逆に悪化させる可能性すらあることを意味しており、注意が必要だ。
一方、R-2HGやFTO阻害因子は、それ自身で根治はできないが、他の抗癌剤と組み合わせて抗癌剤として利用できる可能性がある。他の細胞にももちろん効くため副作用がないとは言えないので、薬剤として利用可能か早急に調べて欲しい。でないと、結局論文のための論文になる。
なんでも疑って見ることが重要であることを示すいい例といえるが、もともとわかりにくいIDHについて学ぶことが多かった。
2018年1月3日
正月3日目、最後の話題は自動運転だ。テレビでも1昨年までは自動ブレーキだったのが、例えばニッサンの最新のリーフのように、TVで自動運転の能力をアピールする車が2017年は増えてきたように思う。これが2018年どう進展するのか、機械学習より一般の注目度は高いはずだ。
実を言うと、私はこれまで運転免許証なるものを持ったことがない。もちろん車を運転する経験はゼロで、常に「乗せられ族」として過ごしてきた。そして世の「乗せられ族」は密かに自動運転車に期待を抱いているはずだと勝手に思っている。免許なしで自動運転車を乗り回す可能性はお金には変えられない。
自動運転車も免許が必要だという話に政府はしたがるかもしれないが、そうは言わせない。というのも、自動運転車を最も期待しているのがタクシーや公共交通業界だ。もし運転手のいないタクシーに乗っていいなら、自動運転車を買って乗り回して何が悪い。
しかし、実際のところどこまで自動運転車は進んでいるのか?免許のない私が車を買うことが可能なのか。そんなことを密かに考えていると、Science誌のレポーターが自動運転車の現状を分析した記事を掲載したので、早速読んでみた。
結論から言うと、メディアやメーカーはそんなに待たなくても私が車を買える日が来るように宣伝しているが、おそらく私の生きているうちにはそんな日が来ないことがよくわかった。このレポートのタイトルは「Not so fast(そんなに早くない)」だ。
まず自動運転と言っても、ドライバーが全てを行うレベル0から、人間が全く何もしなくていいいレベル5まで6段階に分かれており、結局現在買うことができるのは、自動車専用道路でなら車に任せることができるレベル3のようだ。ただ、おそらく消費者はもっと高いレベルを自動運転の宣伝で抱いているはずで、その結果2016年テスラのオートパイロットを信頼しすぎた事故が起こることになる。もちろん現段階でも天気が良くて、整備された一般道なら自分で走るレベル4の車を市場に出すことはできるらしい。しかし、どんな天気でも、行きたいところに連れて行ってくれるレベル5が達成されるのは2075年前後のようだ。とすると、まず免許のない私が生きているうちに車のオーナーになることはないことがわかった。
このレポートは、それでも様々なレベルの自動運転車に備えて、社会や消費者の方も幾つかの項目で準備が必要であること、これまで行われた研究を元にしてうまくまとめている。議論された各項目について見ておこう。
安全性
昨日紹介したように、機械学習ではエラーを許容することが重要になる。また、何か起こってもその理由を特定することは難しい。一方、現在の自動運転の宣伝を見ると、前後左右完全に安全性を確認して運転が行われるとほとんどの人が期待してしまう。その結果、自動運転では決してエラーが起こって、交通事故が起こってはならないと思ってしまう。
それでも、レベル3でも、交通事故による死亡を半減させる可能性を示す研究がある。また、自動運転も機械学習なので、公道を走ることでさらに安全性を高めることができる(ランド研究所の調査)。これらのことから、完全でないことを皆が理解して、早期に導入を図るのが良いと結論している。
運転手付きの車?
自動運転車は運転手付きの車と言える。そこで、一般の家庭に運転手をただで派遣して運転を肩代わりしてもらうと、車の利用パターンがどう変わるかという研究をサンフランシスコで行った研究者がいる。結果はなんと76%も利用率が上がる。特に高齢者では利用率が3倍に上るという結果だ。とすると、国や自治体も交通量の増加に備える必要がある。
車で仕事ができる?
我が国で見かけないが、米国では自動運転で運転中に仕事が可能と宣伝しているようだ。しかしわかってきたことは、自動運転車に乗って本を読もうとすると12%の人が乗り物酔いにかかることだ。今後、そこまで考えた車の設計も重要になる。
個人所有かカーシェアか?
自動運転が普及すると、自分で車を持つ人は減ると予想する研究者が多い。ただ、利用率や目的に合わせた値段の異なるパッケージが提供されるだろう。ただ、このパターンの変化は自治体の政策により大きく左右される。おそらく、都市と地方で政策も異なり、公共交通との連携や補助金行政が問われることは間違いがない。その意味で、交通システムの大改革につながることは間違いない。
メーカーの狙いは?
GMの担当者に聞くと、最初の狙いはタクシーを自動運転に変えることで、これだけでGM本体もタクシー提供者として、一台あたり今の何倍もの利潤を上げることができる、現在より30%利益が上がるようだ。確かに、自動運転車なら運転手を集める必要がなく、車メーカーが直接新業種に参入できる。「運転手をなくす」がメーカーの狙いかもしれない。
政府の対策は?
自動運転車の問題は、メーカーの技術開発以外の研究があまり行われていないことだ。しかし、間違いなく交通システムを変え、運転手という雇用形態を消滅させる技術だとすると、公共機関や大学でももっと研究が進み、それに基づく準備が必要になる。
それにはまず、実験を容易にする規制の緩和、自治体間の連携が必要になる。更には、テロリストが自動運転車を使う可能性すらある。
政府もタクシー会社が消え去る可能性のある大きな転換期であることを理解して、大きなパースペクティブで、エビデンスに基づいてこれに対応する必要があると思う。
このレポートは最後に、「自動運転車は私たちを助けるのか、溺れさせるのか?」と聞かれた政策研究者が答えた一言、「個人的には、簡単に白黒つけられない問題だと思う。というのも、多くの変動要因が多く、多様性があまりにもありすぎる」で締めくくっている。いずれにせよ、私が車の所有者になる初夢は消えた。
2018年1月2日
二日目はいわゆるAIの話だ。
私たちのNPOには将棋のプロに近いメンバーが2人もいて、将棋の話を興奮して話してくれる。このため昨年AASJ内で最も話された話題は、連勝新記録を達成した藤井聡太君のニュースと、棋士対コンピュータの電王戦の話だった。素人から見ても、将棋でAIがプロに勝つとは、AIがこの数年で急速に発達しているのがわかる。
もちろん、医学分野でもAIの進出は目覚ましいものがあり、例えば2月にスタンフォード大学から13万近い皮膚病変の写真と、その病理診断結果をニューラルネットを用いて機械学習させることで、皮膚科の専門家と肩を並べるレベルの皮膚病変の診断が可能になった論文がなんとNatureに掲載されて驚いた(Esteva et al, Nature 542, 115, 2017)。
一方最近のThe LancetのAIと医学について述べたエディトリアル記事では、AIが今後も医学を変化させることは間違いないが、問題も認識され始めたことも書かれていた(The Lancet 390, 2739, 2017)。例えば昨年、IBMがMD Andersonと4年にわたって協力してきた研究が中断され、またGoogleと英国Royal Free London NHS Foundationとの協力で進められていたDeepMindを用いたAI研究からのデータ流失が起こり、AIに対する不安が高まっているようだ。
このように、AIで社会がどう変わるのか、私の苦手分野だが2018年にその輪郭が見えるのではと注目している。
幸い昨年の終わりにScience誌は機械学習の世界の第一人者、E. BrtnjolfssonとTom Mitchellが共同で書いたこの分野の展望についての総説を発表したので、今年のAIの発展を予測する意味でも、この総説を紹介することにした。タイトルは「What can machine learning do? Workforce implication(機械学習は何ができるのか? 労働力に関する示唆)」だ。(Science 358, 1534, 2017)。
この総説の焦点は、AIが人間の現在の労働形態をどう変えるかだ。
さすがこの分野のプロで、まず本当のArtificial intelligenceは到底到達できない先に存在しており、今AIと大騒ぎしているのはmachine learning(ML)のことだと断定している。
その上で、一般的に言われているように、置き換わる仕事、置き換わらない仕事があるにしても、実際にはMLだけでもインパクトは大きく、経済や雇用についての大変革が進んだ結果10年以内に勝者と敗者が決まるほどの破壊的効果があることを予言し、各国政府は今から準備が必要だと忠告している。
いずれにせよ、MLを使いこなすには、まず学習することが何をもたらすのかを見極め、学習させる情報をどう加工するかがカギになり、新しいアルゴリズムやパラメーター設定方法の開発が今も進んでいる。このためにも、どのような仕事がMLに置き換えやすいか8項目挙げている。
1.
はっきり定義できるインプットとアウトプットの間の関係の学習:医学情報がまさにこれにあたる。すなわち、データから病名を診断する過程は、インプットとアウトプットが明確に定義されている。ただ、予測や診断が可能になったからといって、因果関係を理解したことではない。
2.
多くの適切なデータが得られる学習:ニューラルネットによるMLではデータが飽和して能力の限界に到達することはない。どんなデータも利用できるが、人間の手で対象をよく分析し、データをタグ付けし直すことで、ML の能力を高められる。
3. ゴールが明確で、定量的に評価できる学習:MLから考えると自明の話だが、例としては都市の交通量のコントロールなどがこれにあたる。ただこの時、データが期待しているゴールとの関連でラベルされるようにデータを調整するのが望ましい。
4.
常識や多様な知識が必要な段階的に論理を詰めていく過程の必要でない学習:迅速な反応が求められるタスクを選ぶのが重要。常識や多様な知識に基づいて、段階的に論理を進めるのは苦手。しかし囲碁やチェスは、その後の展開を正確にシミュレーションできるため、段階的論理過程に見えても、MLは得意。逆に、現実世界のシミュレーションは難しい。
5.
背景にある理由を説明する必要がない学習:診断にしても、囲碁にしても、MLは正解を出すことができるが、なぜそれを正解として選んだかの理由付けは出来ない(これこそが将来のAIの一つの条件、しかし人間だから理由が説明できるわけではない)。
6.
失敗が許容でき、実証性が必要のない学習:アルゴリズムの基本は統計学、推計学で、必ず間違いがあることは理解する必要がある。
7. 現象やインプット・アウトプットの関係が安定な学習:現在のアルゴリズムは、対象の振る舞いがある程度安定していることが必要で、状況が早く変化する現象には利用しにくい。
8.
熟練、技が必要ない学習:ロボットに使うとき、まだハードの方が、機械学習についていかないことを理解する(明日この問題は自動運転で取り上げる予定)
その上で、クリエーティブな仕事がMLには不可能かも議論している。人間でも創造性が生まれる基本は、脳の回路を毎日書き換える経験の量が重要で、この書き換えによりそれぞれユニークな自己の回路が形成されることで、創造性が生まれていると私は思うが、MLの仕組みから考えれば、経験に応じて創造性が生まれてもおかしくない。著者らも創造性をMLは持たないというのは甘い考えで、学習した内容はそれぞれ異なるため、独自性が生まれ、それに基づいて判断すれば、自ずと創造性が生まれると考えている。
最後に、以上のことを理解した上で、MLを考える時の経済問題6項目あげている。
1、
雇用のMLによる置換:まちがいなく、多くの職はMLで置き換わる。例えば、コンピュータソフトを仕上げる工程は、今やMLの独壇場なようだ。
2、
価格の自由度:ML導入で価格が落ちることで、利用者が増えて、全体の消費額が増えるような領域。
3、
人間と機械の相互性:MLの導入により、それを使う人間のスキルが要求されるといった相互性がある分野。
4、
収入の自由度:ML導入により失われる雇用は多い。従って、労働市場の流動性が高く、新しい需要に対応出来る経済運営が必要。
5、
労働供給の自由度:MLにより新しい仕事が増えても、それに対応する人間の供給が制限されると、給与の差が拡大することになる。
6、
ビジネスの新しいデザイン:経済活動全体がMLで変化することを理解して、長期的なビジネスプランが必要。
などだ。
要するに、産業革命によりもたらされた資本主義では、「労働者が消費者でもある」とマルクスが気づいた時と同じような大きな変化が起こることを意味している。とすると、この総説も表面をなぞっているだけで、それぞれが2018年MLの進展をウォッチし続ける必要があることを物語る。
医学で言えばMLで診断率が上がったと喜ぶだけでなく、「誰もが最適の健康を維持できる」医療システムの構造変化をMLを使って加速するプランを考える人が現れることが重要だと思った。
2018年1月1日
1日から3日間今年議論が続きそうな話題に関する総説やコメンタリーを紹介する。
元旦の今日はトランプに関する話題だ。いうまでもなく、トランプは世界中で一番力を持つ米国大統領で、核戦争開始のボタンを手にする人物だ。また、選挙中からはしかワクチンと自閉症の関係を捏造した有名な論文の著者Wakefield率いるワクチン反対運動と手を結ぶなど、反科学的立場を鮮明にして米国科学界と敵対している。その意味で、米国だけでなく、世界の科学界にとって、今年予定されている中間選挙の結果は、今後の方向を占う意味で重要な問題だ。
このような状況で、もし多くの精神科医や臨床心理士が「トランプは深刻な精神疾患にかかっており、彼は大統領の資格がない」という本を出版したらどうなるのか?実際、ネット上にはそんな意見はごまんと溢れているので、私はあまり影響はないように思うが、専門家の意見となると説得力が上がり、トランプ支持者は黙っていないはずだ。
我が国では、医師が集まって首相の病気について意見を集めた本を出すことなど到底考えられないが、米国ではそんな本が出版されてしまった。タイトルはそのものズバリ「The dangerous case of Donald Trump(ドナルド・トランプの危険な症例)」だ。
計画者の一人Yale大学の精神科医Lee博士が前書きに書いた本の出版までの経緯は次のようなものだ。大統領選挙中からその後のトランプの言動に、深刻な精神的問題を見て取ったLee博士を含む数人が、まずトランプの精神問題について懸念を示すNew York Times宛の手紙を回し、署名集めを行った(現在では5万5千人の署名が集まったようだ)。
次に昨年の4月20日タウンミーティングが行われたが、そこには報復を恐れてか24人の専門家しか集まらなかったが、参加者が100日で原稿を書いて緊急出版したのがこの本になる、
この本が出版されると、専門家は診察してもいない人の病気について意見を述べてはならない」とする米国精神科学会のGoldwaterルール違反であると、厳しい批判が行われる。結果「専門家は政治に影響する発言をしてはならない」と言う意見から、「米国大統領の権力を考えると、自分の意見を述べるのは当然だ」と言う意見まで、現在も米国医学会では白熱した議論が続いているようだ。
私自身がこの議論を知ったのは、12月27日号のThe New England Journal of Medicineにフィラデルフィアの精神科医Claire Pouncy発表した「President Trump’s mental health – Is it morally permissible for psychiatrists to comm.ent?(トランプ大統領の精神状態 — 精神科医がコメントするのは倫理的に許されるか?)」という意見論文を読んだからだ(DOI:10.1056/NEJMp1714828:
オープンアクセスで誰もが読むことができる)。
この意見論文でPouncy博士は、米国精神医学学界元会長のLiebermanがこの本について、「真面目な学術的な本ではなく、安っぽい、勝手で愚かなタブロイド判精神医学」と批判し、さらに精神科学会も「診察せずに政治家の精神疾患に関する意見を述べることを自粛する」Goldwater ruleを盾に、この本の著者らを反倫理的と糾弾する構えを見せていることに対し、専門家が黙ってしまっていいのかと、全面的にこの本の著者らを支持する意見を述べている。
またThe New England Journal of MedicineもおそらくPouncy博士を支持する意味でこの意見を掲載したのだと思う。
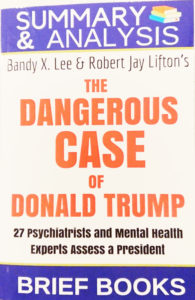
この意見を読んで、私も早速本を購入し、斜め読みしてみた。300ページを超す本で、全部読む時間がないという人のために、それぞれの意見を解説してくれる要約本まで出版する念の入れようだ(写真)。
全員反トランプとはいえ、27人もの専門家の意見が集まった本なので一言でまとめるのは難しいが、ビデオ、ツィートなどに残された文章を手掛かりに彼を分析する限り、トランプは間違いなく「悪性ナルシズム」「反社会的性格障害」「偏執狂的性格障害」「妄想性障害」などの診断名が与えられるべきで、これには十分医学的根拠があることを専門家の視点から分析している。他にも、精神科医として、トランプの言動が多くの市民の精神状態まで変化させている実感についても書かれている。
詳しくは要約本でもいいので読んでほしいと思うが、ベトナム戦争時。兵役逃れを繰り返した張本人でありながら、政権を軍人で固め、しかも「スタッフには最も優秀な人間を雇うが、優秀な人間は決して信用してはならない」などとうそぶいている話が出てくると、この本の指摘も納得でき、トランプに北朝鮮対応を任せている我が国としても心配になってくる。
学会内でも意見が分かれているとはいえ、確かに、精神科医がメディアを通して意見を公にし、こんな本まで出ると、ネットで「トランプはクレージー」とツィートするのとはわけが違う。実際この本の主題も、トランプの精神状態だけではなく、精神科医は政治家の精神状態にコメントしてはならないのか、あるいは、核戦争のボタンまで持っている人物となると、専門家として意見を述べるべきなのか、世の中に問いかけるものだと思う。この本で繰り広げられた主張が、今年一年どう広がり、中間選挙に影響を持ちうるのか、個人的には今年の注目ポイントになる。
個人的には、トランプ支持者は、知識人や専門家の意見にまったく耳を貸すことはないと思うが、専門家が公に向けて意見をどう述べていくのか、米国だけでなく我が国でも議論すべきだろうと思う。特に我が国では、例えば小保方事件でも専門家が集められた番組が組まれたように、専門家の意見をメディアも重要することが多い。しかし、おそらく政治的問題について、この本で示された専門家が公に話し始めるガッツは、我が国の専門家にはないだろう。実際我が国の専門家の意見は、メディアが決めた意見を支持する発言をするのが関の山だ。
その意味で、この本を肯定するのか、否定するのかというテーマに絞って我が国の専門家も議論してみればいいと思う。
実際、Goldwaterルールとは、核戦争も辞さないと大見得を切ったGoldwaterを精神科医が大統領不適格と意見を集めたことが裁判沙汰になり、Goldwaterが勝利した結果、精神科学会が作ったルールだ。しかし、同じことはどんな民主主義国でも起こりうることで、今議論を始めないと手遅れになるだろう。
この本で、私が一番心に残ったのは、トランプに頼まれ、長期間彼と行動を共にして「The Art of Deal」というタイトルの本を書き上げたTony Schwartzが述べた一節だ。彼は「トランプが参加するビジネス会議に数多く参加したが、会議で誰かがトランプに反対するのを見たことがなかった」と書いている。もちろんトランプはそれがリーダーシップで、まさに「The art of deal」だと自慢していると思うが、国家で同じことが起こると、歯止めの効かない最大の危険を抱えることになるのは歴史を見れば自明のことだ。昨年の森友・加計と続く報道を見ていると、同じ危機は我が国にも起こっているように思う。もちろんトランプと違って、精神科の医師が声を上げる問題ではないだろうが、様々な分野で専門家の行動に注目が集まる2018年だと改めて思う。
2017年12月31日
昨日紹介したNature Medicineが選んだ2017年のトピックスにはガン免疫が2つも選ばれ、免疫療法がガン根治の切り札として期待されていることをうかがわせる。そこで今年の最後を締めくくる論文として、ガン抗原の新しい特定方法の開発研究を選ぶことにした。スタンフォード大学からの論文で、タイトルは「Antigen identification for orphan T cell receptor expressed on tumor infiltrating lymphocytes(ガン組織に浸潤するリンパ球のT細胞受容体の反応する抗原を特定する)」で、1月25日号のCellに掲載される。
期待を込めて読んだが、まだまだ完全でない研究だ。しかし、研究は挑戦的だ。何度も紹介しているように、チェックポイント治療が効くかどうかは全て癌に対する免疫反応が成立しているかどうかにかかっている。これを調べるために、昔は癌と患者さんのT細胞を培養して、癌に対するT細胞を増幅することが試みられていた。ただ、この方法で実際にどのペプチドがガン抗原として働いているかは特定できなかった。
そこで、癌のゲノム解析から、癌のみで突然変異が見られるペプチドを特定して、これに反応するT細胞がある場合、これをワクチンとして免疫する方法が成功を収めた。個人的にもこの方法が当分本命かと思うが、一方で癌を切除した時、その組織にあるT細胞は免疫反応を起こしている可能性が高いなら、このT細胞のTcRに結合する抗原を特定できれば、癌特異的キラーT細胞を大量に調整して治療に役立てることができる。しかし、浸潤T細胞の数は多くなく簡単ではない。
この課題にチャレンジしたのが今日紹介する研究で、人間の組織適合抗原(MHC)を表面に発現する酵母を用いて、様々な長さのペプチドがランダムにMHCに結合してTcRに提示されるペプチドライブラリーを用意している。この方法で、すでに反応する抗原ペプチドがわかっているT細胞株を刺激できる抗原を特定できること、またネオ抗原の特異的T細胞がわかっているメラノーマで予備実験を行った後、2人の大腸癌の患者さんの組織に浸潤しているT細胞が反応する抗原を特定できるかの本実験を行っている。
最も大変なのが、ガン組織に浸潤しているTcRの調整で、一人の患者さんあたり数百個のT細胞を単離、一個づつ発現しているTcRを特定している。同じように正常組織に存在するT細胞についても同じ解析を、比較のために行っている。それぞれの単一細胞について、T細胞の形質も同時に調べている。これらのデータに基づいて、ガン組織のみで、二個以上のキラーT細胞で発現していた(すなわち組織で増殖していた)TcRを選ぶと最終的に20種類のTcRが残った。
こうして選んだ個々のTcRで表面にペプチドライブラリーを発現した酵母を染色し、染色できた酵母を増殖させ、また選択するというサイクルを3回繰り返し、残った酵母のDNA配列決定により、各TcRが認識するペプチドを特定している。
手のかかる複雑な実験の結果、この方法で特異的ペプチドの特定にまで至ったのは4種類のTcRだけで、残りのTcRでは抗原が特定できなかった。さらに、ガンのネオ抗原と反応していることが特定できたのは1つのTcRだけで、あとは正常の分子由来のペプチドだった。実際に特定できたペプチドがT細胞を刺激できることも、細胞株に各TcRを導入する実験で確認している。
ただ話はこれだけで、特定したペプチドを用いればガン免疫を誘導できるかどうか、機能についてはわからない。したがって、読んだ後、この方法に大きな期待が持てるという実感はない。しかし、人間でガンに対する免疫反応を解析するために努力していることはよくわかる研究で、この論文で終わらせずに、この解析を多くの患者さんで行い、データを蓄積して欲しいと思った。
2017年12月30日
今日紹介するのは、Nature Medicineの編集者が1年を振り返って、面白いと思った研究論文を分野ごとに紹介している。私も一編を除いて全て読んでいたが、読み落とした論文があったのはショックだ。また、幾つかの論文についてはこのブログでも紹介したので、もう一度リンクさせておく。ただ、Nature, Scienceのニュースと違って、かなり専門的であることは断っておく。
ガンのチェックポイント治療
抗PD-1抗体などを用いたチェックポイント治療が現在抱える最大の課題は、効果のばらつきの原因を明らかにし、治療効果の予測を可能にするとともに、最終的には全ての人で効果が得られるようにする方法の開発だ。その点で今年最も重要な論文と指摘されたのがジョンホプキンス大学からNatureに掲載された論文(Nature 545,60,2017)だ。この研究は、治療前後で患者さんの血液のT細胞を調べ、メラノーマに関する限り全ての患者さんでガンに対するT細胞ができているが、ガン細胞の数が多すぎるとT細胞が枯渇して治療が効かない可能性を示した。この結果はチェックポイント治療の前にできるだけ腫瘍を減らすと効果が高まる可能性を示しており、新しい治療プロトコルにつながる。
もう一つの論文、ミスマッチ修復酵素が変異したガンではチェックポイント治療の効果が高いというやはりジョンホプキンス大学からの論文で、すでにメルクの抗PD-1抗体はこの適用についてFDAの認可を受けている(
7月30日記事参照)
ガンワクチンの可能性
私も7月8日、7月9日に紹介した、実際のガンの持つガン抗原を特定して個人用ワクチンを作成してガンを治す第1相治験論文が、
ハーバード大学から、および
ドイツマインツ大学からそれぞれ発表された。ともに、かなり期待を持たせる結果だ。この進歩は、ガンゲノムのDNA配列からガン抗原として働くペプチド断片を特定する技術が発展したおかげだが、現在のところ特定された抗原が免疫反応を誘導できるかは試験管内での検査が必要で、一般治療となるには時間がかかると思う。
神経細胞死を誘導するミクログリア
今年もミクログリアと神経細胞死の研究論文が数多く発表されているが、紹介されているのは1月スタンフォード大学から発表された論文で(Nature 541,481,2017)、ミクログリアがIL-1α、TNF、C1qを介してアストロサイトを活性化すると、アストロサイトは本来の神経保護作用を失い、神経細胞死を誘導するという恐ろしい発見だ。ただ、この恐ろしいアストロサイトは多くの変性性神経疾患で見られることから、この経路をブロックできると変性性疾患の治療も可能になるかもしれない。
GABA受容体を刺激して糖尿病を治す
1月にオーストリアとフランスからGABA受容体の活性を高めると、膵臓のα細胞がβ細胞へ転換し、糖尿病が治療できる可能性が示された。特にオーストリアからの論文は、この経路をなんとマラリアの治療薬として有名なアルテメールがGABA受容体の活性を高めることを示しており、
この論文を読んだ時は本当に驚き1型糖尿病の治療が可能になるのではと大きな期待を持った。
血液系の老化と心臓病
血液幹細胞を研究していたのにこの論文は完全に見落としていた(言い訳:おそらくアフリカ旅行のせいだと思う)。末梢血液細胞のゲノムが解析され、高齢になると、一個の幹細胞クローン由来の末梢血が増えてくる現象が最近注目されている。全体の幹細胞が減るだけではなく、一部の幹細胞の増殖が強まるせいだと考えられているが、このような血液細胞でこのようなクローン性増殖を示すクローンが多いと、心筋梗塞のリスクが2倍高いことを示す論文が7月New England Journal of Medicine(377,111,2017)に発表された。原因を確かめるため、血液のクローン増殖の最も多い原因になっているTET2欠損血液細胞を移植する実験で、TET2欠損マクロファージが炎症性のサイトカインを発現して動脈硬化を悪化させることで危険性が高まることを明らかにしている。この結果は、昨日紹介した、Ilarisによる心筋梗塞再発防止につながるから驚きだ。
FSHを抑制して肥満を治療する
この論文(Nature 546,107,2017)は発表当時
このブログでも紹介したが、FSHの作用による骨粗鬆症の治療薬の研究中、脂肪が減ることを発見し、そのメカニズムを追求した研究だ。詳細は全て省くが、FSHに対する抗体が白色脂肪細胞を褐色脂肪細胞へと変換させ、脂肪を燃やして、痩せることができることが明らかになり、更年期肥満の治療法が開発されたことになる。確かに、これまで見落とされていた重要な事実で、面白い論文だが、もしこの抗体で更年期肥満が治療できたとしても、個人的にはそれほど大騒ぎするほどではないように思った。
クリスパーによるヒト胚操作。
我が国でもヒト胚の遺伝子編集が大きな話題になり、中国での研究をきっかけに様々な意見がメディアに溢れた。クリスパーがあればヒト胚の遺伝子編集が可能なことはわかりきっている。それを敢えて行うからには、論文の品格が問われる。この状況で、品格が高いヒト胚研究とはどのようなものかを示したのが、この記事が取り上げたオレゴン大学からの論文だ(Nature 548, 413, 2017)。深い考えによる病気の選択(MybPC3変異)、iPSによる予備実験、Cas9によるDNA切断修復と、モザイク卵形成阻害のための条件の検討など、プロとは何かを存分に見せた品格の高い論文だった。我が国の役所でも審議されていると思うが、このぐらいの品格の高い論文を読み合せするぐらいの覚悟で議論してほしい。
細菌叢研究の新しい方向
細菌叢の研究は我が国でも盛んだが、一部の研究者を除くと、細菌の種類をゲノム解析で調べるだけの域から出ていない。すでにトップジャーナルでは、そのような研究は見向きもされない。正確に、因果性を調べることが求められる。その典型が今回選ばれたロックフェラー大学からの論文だろう(Nature 549, 48,2017)。この研究ではバイオインフォマティックスと大腸菌を用いた工学的手法を用いて、細菌叢が合成できる多数のN-アセチルアミド類(NAS)と、ホスト側のGタンパク質共役型受容体(GPCR)の相互作用を丹念に調べ、一部のNASが人間のGPCRに直接作用すること、そしてそのうちの一つがマウスの血統を低下させることを示している。わが国は、免疫でははこのような総合力のある高いレベルの研究ができているが、代謝分野はかなり遅れている印象だ。
以上、かなり妥当な選択だと感心した。
2017年12月29日
Nature, Scienceでは2017年総括はあらゆる分野にまたがるが、医学研究全般を掲載するNature Medicineでは当然医学に関わる2017年のニュースがまとめられ、医学に興味のある人には便利だ。2017年見出しを飾った薬剤、と2017年注目すべき進歩の2つのパートに分けて紹介しており、今日から二回に分けて紹介する。最初は今年見出しを飾った薬剤を紹介する。多くが抗体薬で、何よりも恐ろしく価格が高い。新薬が認められるのはめでたいが、手の届く薬剤をどう開発するのか考える時期が来たことを物語る記事だ。
1、 Dupixent
RgeneronとSanofiが開発した、IL-4受容体に対する抗体で、重症の湿疹への治療効果が認められた。メカニズムから考えると当然の結果だが、1年に400万円近い金額がかかるのが難点。
2、 Ocrevus
多発性硬化症の中の15%程度に当たる、一次進行性多発性硬化症を対象にした抗体薬で、CD20陽性B細胞を標的にしており、ロッシュの子会社ジェネンテックにより開発された。同じ標的に対して、すでにリツキサンが存在するが、Ocrevusは完全にヒト化されている点で異なる。ただ、年700万円近いコストが問題。
3、 Kymriah
すでに私も何度も紹介したガン抗原に対するキメラT細胞受容体遺伝子を用いるCAR-T治療で、ノバルティスにより開発され、急性リンパ急性白血病の根治をもたらすのかもしれないと期待されている。ScienceやNatureのニュースの今年のニュースにも取り上げられているが、一回の細胞移植にかかるコストが5000万円近い。
4、Radicava
我が国から唯一選ばれた薬剤で、田辺三菱製薬により開発され20年ぶりにALSに効果があることがFDAにより認められた神経保護剤だ。治すことはできないが、進行を33%遅らせる効果がある。
5、 Ilaris
ノバルティスにより子供の全身性リュウマチに対する薬剤として利用されていたIL-1βに対する抗体薬だが、2017年、心臓発作の既往のある患者さんの再発を抑える効果があることが発表され注目されている。3ヶ月に一回、皮下投与だが、一回150万円程度の費用がかかる。
6、 Idhifa
Celegeneによって開発された、IDH2遺伝子の変異により増殖していることが確認される急性骨髄性の治療薬。IDH2に対する阻害剤としては最初の薬剤で、経口投与可能。2割近くの患者さんが、この治療で完全寛解する。治療には月300万円程度かかる。
7、 Imfinzi
非小細胞性肺ガンに対する抗体薬で、PD-1に結合するリガンドPD-L1を認識する。アストラゼネカによる開発された。ステージ3以上の患者さんに効くのは予想できるが、PD-1に対する抗体が普及している今、どのように利用されるのか予想できない。
8、 Heplisav-B
Dynavaxにより開発された大人に対してB型肝炎ウイルスの感染を予防するためのワクチン。何度も認可が拒否されたいわくつきのワクチンだ。ワクチンが認可されたのは喜ばしいが、小児への効果は低いらしいので、どのような状況で利用するのか?
以上は完全成功例だが、黄色信号、赤信号が灯った薬剤についても見出しを飾ったとして紹介している。CAR-TをAMLに使おうとCD123をがん抗原として用いたフランスCellctisの第1相治験で死亡事故があり、臨床治験が差し止められた。CAR-Tはパワフルな治療だけに、今後もこのような事故は予測できる。メルクの抗PD-1抗体薬だが、ミスマッチ修復変異を対象にするという今年の10大ニュースになったヒットを飛ばしたものの、頭頸部腫瘍に対する効果は初期効果を上げていない。最後が、AlnylamとSanofiが開発した血友病に対するRNA薬で、異常たんぱく質の産生を抑える目的で開発されたが、第2相治験中に死亡事故で、治験がやり直しになった。
治験がうまくいかなかった薬剤について紹介する気はないが、一つだけ残念なのが、メルクが開発していたアルツハイマー病に対するBACE阻害剤だ。実際、私のブログでもメルクの
Science Translational Medicine論文を紹介したが、実際の治験になると効果がないことがわかていたとすると、論文を書くための論文を書いたということになる。