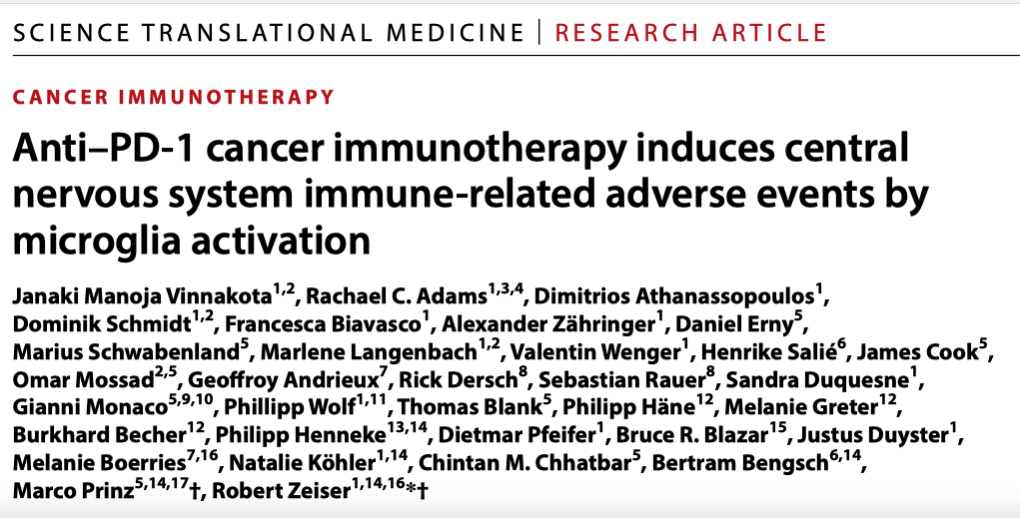2024年6月24日
年齢とともにY染色体を喪失した血液細胞が増加して、この頻度が様々な疾患リスクや余命と相関することが知られている。これは、このブログで何度も紹介したクローン性血液増殖がY染色体を喪失した幹細胞で起こりやすいことを示している。
今日紹介する米国 Broad 研究所、フィンランド分子医学研究所、英国 MRC 、そして米国 NIH を中心に世界のゲノムデータベースが集まって発表した論文は、同じような性染色体の喪失がX染色体でも年齢とともに見られ、同じようにクローン性増殖を反映しているが、メカニズムはY染色体喪失とは異なることを示した研究で、6月12日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Genetic drivers and cellular selection of female mosaic X chromosome loss(女性の X 染色体喪失モザイク発生に関わる遺伝的原因と細胞レベルの選択)」だ。
一本しか存在しない Y 染色体喪失と比べると、2本ある X 染色体の喪失をゲノム解析データだけから特定するのは難しい。しかし、インフォーマティックスを駆使して、2本の染色体を区別して頻度を調べることで、片方の染色体が喪失することで起こる細胞レベルの増殖優位性による変化を特定できる。
この研究では世界中のデータベースから90万人近くの女性のデータを集め、X 染色体喪失が起こった細胞が血液に存在する可能性を調べると、なんと12%の女性で X 染色体喪失が見られ、その頻度は40歳以下では3%、80歳を超えると35%と、年齢とともに増加する。
生活習慣との相関を調べると、肥満との相関はないが、喫煙とは相関を認めている。そして、Y 染色体喪失と同じく、白血病の発生リスクと相関する。
さて、これだけ高い頻度で X 染色体喪失が検出できると、起こりやすいゲノム多型を調べることができる。この研究では実に56種類の相関するゲノム多型を特定している。これらは、1)白血病のリスクに関わる多型、2)分裂時の染色体分離異常に関わる多型、そして 3)免疫異常に関わる多型の3種類に分類できる。1)は血液細胞の増殖を反映し、2)は染色体喪失事態の起こりやすさを反映し、3)は免疫反応に伴うリンパ球の数の変化を反映すると考えられる。
面白いのは、この56種類のうち7種類しか Y 染色体喪失の頻度を上げる多型と相関していない点だ。例えば、HLA は免疫反応を通して細胞増殖の変化を反映すると考えられるが、X 染色体喪失と強く関わるのに、Y 染色体喪失とはほとんど相関しない。他の X 染色体喪失特異的に相関が見られる多型も、免疫反応に関わる遺伝子多型が多く、個人的印象では女性に多い自己免疫疾患発症とメカニズムを共有する可能性がある。
他にも同じ解析から、X 染色体上の多型により片方の染色体へシフトが起こる可能性についても調べ、細胞増殖や、染色体分離といった現象に関わる多型とは全くことなる、セントロメアを中心に分布する多型が強く相関することを発見している。すなわち、分裂糸の形成や染色体への結合に関わる多型が、X 染色体喪失のしやすさの指標となることが明らかになった。
主な結果は以上で、Y 染色体喪失だけでなく、X 染色体喪失も老化の指標として使えることが明らかになるとともに、共通のメカニズムもあるが、X 染色体喪失に関わる特有のメカニズムが存在し、それが女性特有の病気とも関わることが明らかにした、面白い研究だ。
2024年6月23日
我が国は地理的にも災害列島といえるが、この災害を「絆」を合い言葉に皆で寄り添うことで克服してきた。しかし、災害は生きるための資源を極端に減少させるので、少なくなった資源を奪い合う競争が起こる可能性がある。
今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、プエルトリコの小さな離島に住むサルがハリケーンのあと寄り添って暮らすようになったことを10年にわたる観察で示した研究で、6月21日号 Science に掲載された。タイトルは「Ecological disturbance alters the adaptive benefits of social ties(生態系の混乱は社会的絆の適応的価値を変化させる)」だ。
このグループは2013年から Santiago島とよばれる小島で暮らすサルの生態調査を行っていた。そしてその途中2018年、この小島をハリケーン・マリアが襲った。これによりプエルトリコでは人的・経済的な被害が発生するが、Santiago島でも63%の植物が失われることで、直射日光を避ける日陰が極端に減少することになる。その結果、Santiago島は日40度を超す灼熱の島に変わってしまい、熱調節機能が低いサルにとって、日中直射日光を避ける日陰で暮らす以外生き残れないという状況が生まれる。実際ハリケーン前後で温度を測ると、直射日光下で29度が39度と10度も上昇している。一方日陰では、27度が31度と、上昇はしているものの押さえられているのがわかる。この研究ではこの機会を捉えて、サルが日陰を求めてどのような行動変化を示すのかを、ハリケーン前後の行動変化、特に日陰を求めて争いが増えたのか、逆に寄り添うことで日陰を分かち合う社会的寛容性が芽生えたのかについて調べている。
さて結果だが、ハリケーン後社会的なネットワークがより強化され、ハリケーン前より他の個体と一緒に寄り添って過ごす頻度が増えた。これと平行して、個体間の争いが大きく減少し、これがハリケーン後現在まで続いている。
さらに、灼熱の島へと変化したにもかかわらず、サルの死亡率は低下していることも明らかになった。すなわち、争いを避け、絆を深めることが灼熱の島で生存する条件だったことがわかった。
あとは、この絆の深まりは、毛繕いの増加を示すわけではないので、新しい絆行動として発生した行動変化で、日中少ない木陰で寄り添って過ごすという行動から、もっぱら木陰を共有する新しい適応行動が発生したことがわかる。
あとは、行動変化と様々な要因と生存確率との相関を計算し、最終的に影を分け合うためより絆を深めるという行動が、生存可能性と最も相関することを示している。
以上が結果で、こうして深まった絆を道徳と呼ぶことはできないとおもうが、それでも我々人間の道徳の起源に関わることは間違いなく、今度は行動の背景になった脳機能についても研究が進むことを期待する。
この論文を読みながら、今年3月、Bonobo and Atheist (邦題:道徳の起源)の著者 Frans de Waal さんが亡くなったことを思い出した。個人的には存じ上げないが、論文や著作はいつも感心する一人で、この論文のように彼の遺志を継ぐ研究が続いているのには励まされる。
2024年6月22日
PD-1 抗体によるチェックポイント治療の成功は、ガンに対する免疫がかなりの割合で成立しており、この反応が PD-1 により低下するのを防ぐことで、免疫を維持できることを示した。一方で、治療に全く反応を示さない人、さらには反応しても途中で抗体が効かなくなる患者さんがいる。前者は免疫が成立していない可能性があるので、ワクチンなど免疫を成立させる必要がある。一方、一度は反応する患者さんでは、レベルはともかくガン免疫は成立していたのに、PD-1 だけでは免疫を維持できないと考えられる。
今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、PD-1 抗体が効かなくなった人の中には JAK 阻害剤を併用することでガン免疫を再活性させられることを臨床例で示した研究で、6月21日号 Science に掲載された。タイトルは「Combined JAK inhibition and PD-1 immunotherapy for non–small cell lung cancer patients(非小細胞性肺ガンの JAK 阻害と PD-1 抗体の組み合わせ治療)」だ。
2日前に紹介した肥満パラドックスでもわかるように、炎症、特に1型インターフェロン(IFN1)による慢性炎症はガン免疫を低下させることが知られていた。そこで、IFN1 を阻害する、IFN1 に対する抗体、あるいは JAK 阻害剤を PD-1 抗体と併用する実験を行うと、期待通りガン免疫を高めることがわかった。
JAK 阻害剤はすでに認可され臨床で使われているので、そのまま非小細胞性肺ガン患者さん21人の治験に移行している。対照を置く研究ではなく、21例全員、まず6週間、PD-1 抗体のみで治療して、反応を調べ、その後6週間、PD-1 抗体と JAK 阻害剤の併用治療を行い、そのあとは PD-1 抗体単独投与で経過を見ている。
このプロトコルで調べると、PD-1 抗体単独で十分な反応が得られた患者さん、PD-1 抗体単独では反応が悪かったが JAK 阻害剤との併用でガンを抑えることができた患者さん、そしてどちらにも反応できなかった患者さんの3群に分けることができる。
そこで、PD-1 単独に反応した患者さん、反応できなかった患者さんを比べると、反応した患者さん Ki67 陽性の増殖キラー細胞が増加していることがわかった。ただ、7割近くの患者さんではこの増加が観察できず、臨床的にも反応が見られない。ここに JAK 阻害剤が加わると、3割以上の患者さんでガンの抑制が見られる様になるが、JAK 阻害剤に反応した人と、反応しなかった人を比べると、未熟な高い分化能を持った CD8T 細胞の増殖が観察され、この細胞から分化したメモリーやキラー細胞が供給されていることがわかった。さらに、これらのT細胞の発現する抗原受容体遺伝子を調べると、ガン抗原に反応したと思われるクローンが増加していることがわかる。
そして、マウスの実験で示されたように、JAK 阻害剤によってT細胞の IFN1 反応系が抑制されていることが確認され、JAK 阻害剤による未熟 CD8T 細胞の増殖は、IFN1 による炎症抑制が重要な要因であることがわかる。
最後に、併用療法に全く反応しなかった患者さんをさらに詳しく調べると、基本的には JAK 阻害剤で炎症が抑えきれなかったことがわかる。
かなり省略して結果を紹介したが、PD-1 抗体単独療法で反応が悪いと思える患者さんも、JAK 阻害剤を後から加えることで、ガンを抑制できることがわかったのは重要ださらに、患者さんの反応をここまで詳しく知れべられると、今後の治療方針や改善点がはっきりした。特に、慢性炎症の関わりをさらに詳しく調べることは重要だと思う。
この研究では、IFN1 による慢性炎症のT細胞への直接効果が調べられているが、同じ号の Science に掲載された Scrips 研究所からの論文ではホジキン病の患者さんでも PD-1 抗体と JAK 阻害剤の併用療法が効果を示すこと、そして腫瘍組織での白血球の浸潤を押さえリンパ球の浸潤を高めることが示されている。従って、JAK 阻害剤はこれまで腫瘍免疫の効果を抑制してきた様々な要因を解決してくれる可能性があることになり、早く大規模な治験を進めてほしい。もちろん、もっと長期の結果は必要だが、理論的には期待できる。
2024年6月21日
大規模言語モデル(LLM)の登場により、私の頭の中はいっぺんに活性化された。もちろんその便利さも一因だが、私の場合 LLM が生命誕生以降の地球の歴史が一つのピークに達したと感じてしまったからだ。というのも、現役を退いてからは、大学では系統的に教えない「無生物から生物の誕生」、そして「言語の誕生」について、自分なりに納得できる説明をまとめ、講義として提供してきた(これらは HP 上の YouTube 配信としても提供している(https://www.youtube.com/watch?v=3F5w2LRmhHY&t=98s )(https://www.youtube.com/watch?v=Hzt0APHhX24&t=8s )(https://www.youtube.com/watch?v=2WUvk2vCGSA&t=333s )ので是非ご覧いただきたい)。それぞれの講義で教えているのは、物理法則とは別の「アルゴリズムと情報」が生命誕生後の地球を理解する鍵になる点だが、まさに生命誕生以降の過程が様々なコンテクストの蓄積として LLM に実現しているという実感を持っている。これに驚かないはずはない。その結果、今、講義を頼まれると、「生命誕生からChatGPT38億年」というタイトルで話をしている。
この講義の中で特に強調しているのが言語の誕生だ。最初の言語はもちろん音と言う物理法則に媒介されているが、それ以外は物性のない情報が地球上に生まれたことを意味する。この物性がないという性質が、全く物性に縛られない現象を記述することを可能にし、結果物理的には存在しない未来を構想し、神や死後の世界に至るまでを記述する宗教など、人類の歴史を作ってきた。
しかし、物性のない現象の記述、見たこともないことを語ることは、LLM でいうハルシネーションに当たる。今日紹介するオックスフォード大学からの論文は LLM で発生するハルシネーション、中でも作話を検出する方法についての研究で、9月19日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy(大規模言語モデルのハルシネーションを意味論的エントロピーを使って検出する)」だ。
基本的には、様々な検証された question/answer をレファレンスに、LLM から出てきた答えを評価する作業でハルシネーションが起こるかどうかを解析するのだが、手作業でやるわけにはいかないので、答えのセンテンスからハルシネーションを割り出す計算法を開発し、これによりハルシネーションの有無を判断する。すでにこの目的で様々な方法が開発されているが、今回の方法は文章全体を解析するのではなく、文章が示す意味を抽出してその意味が正しいかどうかを調べる、semantic entropy 計算法を開発している。
すなわち、LLM に「エッフェル塔はどこにありますか」と質問すると「パリ」「パリです」「フランスの首都パリです」から「ローマです」まで様々な答えが返ってきて、文章も含めて間違いを計算すると(naïve entropy)と、間違いを正確に確率として計算できなるという問題があり、これをパリ、フランスといった正しい答えだけについての semantic entropy として計算する方法を開発している。
そして、様々な question/answer 集をインプットして分析すると、semantic entropy 法が、これまで開発されたハルシネーション検出法を凌駕したという結果だ。
他にも、GPT4 から21人の記録がある人物の履歴を作成させ、150項目について示された事実が正しいかどうかを調べ直す作業を行って、semantic entropy 法のパーフォーマンスが高いことを示している。
以上が結果で、これにより作話を検出して自動的にフィードバックする仕組みを確立できれば、ハルシネーションを減らすことができるというのが結論になる。
最初に述べたように、文字が生まれるまで言語は物性が希薄な情報で、その場で消えるか、人間のニューラルネットにかろうじて保持できるだけだった。しかし、そのおかげで経験しない現象を語れるようになり、未来、宗教、虚構、ねつ造といった、言語情報特有の世界を開発できてきた。ハルシネーションには、間違ったことを習うことで発生する確信を持った間違いと、学習していないことを答えてしまう間違いに分かれるが、後者が実際には人間を作ってきた気がする。
その意味で、質問を自動的に繰り返すことで、物語や宗教といった壮大なハルシネーションが LLM から発生するかどうかを調べるのも面白い気がする。
2024年6月20日
この記事を読んでいる読者の多くは、現在日本経済新聞に連載中の本庶先生の「私の履歴書」も読んでいることと推察する。私自身は、ドイツから帰って京都で細々と研究を始めた頃に、本庶先生が京大教授に就任されたこともあり、研究室との交流を通して外野から実際に見聞きしていたことなので、当時本庶先生がどう考えていたのかを改めて知ることができ、特に興味深く読んでいる。折しも、昨日、今日と石田さんが PD-1 をクローニングしてからの話なので、それに合わせて PD-1 についての論文を選ぶことにした。
毎日論文を読んでいると PD-1 研究が想像以上に多方面へと拡大しているのがわかる。例えばPD-1抗体が記憶を高めるといった結果はさすがの本庶さんも驚くだろう(https://aasj.jp/news/watch/22566 )。今日紹介する米国・バンダービルド大学からの論文は、肥満パラドックスとして知られる肥満はガンのリスクだが、肥満の人には PD-1 抗体がよく効く現象が、肥満により、マクロファージにより発現する PD-1 で説明できるという論文で、6月12日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Obesity induces PD-1 on macrophages to suppress anti-tumour immunity(肥満によりPD-1がマクロファージに誘導され抗腫瘍免疫を抑制する)」だ。
実を言うとこの論文を読むまで肥満パラドックスのことは知らなかった。肥満がガンのリスクであることは有名な事実だが、PD-1 抗体治療現場では肥満のガン患者さんには PD-1 抗体が効きやすいという現象が知られており、肥満パラドックスと呼ばれていたようだ。この研究では、高脂肪食を投与して肥満にしたマウスでは、正常マウスよりガンの増殖が早い。ところが PD-1 抗体を投与すると、正常マウスと同じぐらいガン増殖を抑制する。すなわちネットで見るとより強い効果があるように見えることを示して、マウスでも肥満パラドックスが再現できることを示している。
次に腫瘍組織を single cell RNA sequencing から、肥満マウスのガン組織ではマクロファージが PD-1 を発現しており、しかも様々なマクロファージの機能が低下していることを発見する。また、マクロファージに PD-1 を誘導する条件を調べると、肥満とともに LPS など炎症シグナルも PD-1 を誘導することを明らかにする。肥満により上昇する遊離脂肪も炎症シグナルと同じように働き、これが PD-1 上昇の原因であることも確認している。
実際腫瘍組織で PD-1 を発現するマクロファージは、ミトコンドリアの活性化を伴う代謝変化とともに、増殖活性が高まっている一方、炎症性サイトカイン経路の低下が見られる。すなわち、炎症シグナルで誘導される PD-1 は、炎症を抑える働きを持つことがわかる。
一方、PD-1 をノックアウトしたマクロファージや、PD-1 抗体処理により、この抑制が外れるおかげで、炎症性サイトカインの発現が上昇し、抗原提示などのマクロファージ活性が高まる結果、キラーT細胞とともに腫瘍を抑制できるという話になる。
この研究では肥満が PD-1 を誘導するということに注目しているが、実際には腫瘍局所の炎症によりマクロファージが PD-1 を発現してチェックポイント機能を発揮するというメカニズムが、たまたま肥満にも当てはまったと考えるべきだろう。PD-1 ストーリーはどこまで拡大していくのだろうか。
2024年6月19日
最近 iPS 細胞由来ドーパミン神経を用いたパーキンソン病治療に関する報道をほとんど聞かなくなったし、論文としても目にする機会がほとんどない。Clinical Trial Government に登録されている治験を検索しても、なんとなく低調な気がする。ES 細胞や iPS 細胞による治療が最も待たれるのがパーキンソン病かと思って見てきたが、大きな壁に当たっているのではと心配している。
おそらく最も重要だと思われるのが、移植した神経細胞が生き残って機能するかだが、これまで経験的に問題が改善したという話はあったが、今日紹介する韓国・大邱慶北科学技術院と米国スローンケッタリングガンセンターからの論文は、実験的に移植ドーパミン神経細胞が失われる原因を特定し、それを解決する方法を示した研究で、6月11日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「TNF-NF-kB-p53 axis restricts in vivo survival of hPSC-derived dopamine neurons(TNF-KF-kB-p53 経路がヒト多能性肝細胞由来ドーパミン神経の生体内での生存を制限する)」だ。
この研究ではまず CRISPR/Cas9 スクリーニングを用いて、移植した iPS 細胞由来ドーパミン神経の維持を妨げている遺伝子を探索し、移植後25日目で生き残っている細胞では p53 分子がノックアウトされていることを明らかにする。この結果に基づいて、p53 をノックアウトしたヒト iPS 細胞由来ドーパミン神経をマウスに移植すると、ばらつきはあるがノックアウトにより生存可能性が促進されることを確認している。
次に移植後の p53 発現を調べると、移植後4時間ぐらいから誘導され、72時間をピークに発現が見られる、すなわち移植というストレスに反応していることがわかる。そこで、p53 を誘導する分子機構を探索し、最終的に TNFα とその下流の NFkB が p53 を誘導していることを突き止める。
ヒト由来、すなわち移植ドーパミン神経が反応性に分泌する TNFα が自らを刺激して NFkB を誘導し、これが p53 誘導に関わることが明らかになった。
そしてこの研究のハイライトになるが、細胞移植とともに TNFα に対する抗体を脳内に投与すると、やはりばらつきはあるが、移植後の生存を高めることができ、さらに6ヶ月後の機能も確認することができる。
最後に、ヒト・マウスではなく、マウス・マウスの組み合わせで同じ実験を行い、このストレスによる TNFα 活性化がヒト細胞をマウスに移植したからではなく、マウスドーパミン神経でも同じ結果が得られることを示している。
結果は以上で、前臨床研究の段階だが、どうして今までこのような研究が行われなかったのかと思うぐらい、重要な研究だと思う。この研究では p53 だけに焦点を当てているが、他にも細胞死を助ける分子も見つかっている。将来は p53 以外の経路も研究されると思うが、TNFα 経路は明日からでも実行可能な点が大きい。もし私が感じているパーキンソン病細胞治療の壁が移植細胞の維持なら、積極的に取り入れて何の問題もない方法だと思う。私の NPO にもパーキンソン病のメンバーがいるが、細胞移植については、10年ほど前に興奮した後何の情報も聞こえてこないため、ほとんど諦めの状態だ。この研究から希望が生まれることを期待する。
2024年6月18日
マラリア、トリパノゾーマ、ライム病など昆虫などにより媒介されて人間に感染する細菌類は、今もなお治療が難しく、人間が克服すべき重要な感染症のグループになっている。今日紹介するイェール大学、バージニア大学、フレッドハッチンソンガンセンターが協力して発表した論文は、このようなベクター媒介細菌と直接反応するホスト側のタンパク質を網羅的に調べた研究で、6月13日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「An atlas of human vector-borne microbe interactions reveals pathogenicity mechanisms(ヒトとベクター媒介細菌との相互作用アトラスは病理メカニズムを明らかにする)」だ。
このグループは細菌と相互作用に関わりそうなヒト細胞外タンパク質3324種類を個別に発現している酵母菌を作成し、この酵母菌とベクター媒介菌(VM)を混ぜた後、VM に結合したタンパク質を特定し、その機能を探る研究を行っている。その結果、713のヒト細胞外タンパク質が82種類の VM と相互作用をすることを見つけている。そして、これらのタンパク質が直接実際の細菌とも相互作用していることを確認している。この方法がこの研究のハイライトで、後は一つ一つの相互作用を調べることになる。この研究でもその一部だけが解析されているが、今日はその中から面白い例をいくつか紹介する。
細胞外で増殖する細菌と、細胞内で増殖する細菌に結合する分子は大きく異なっている。また、一つの細菌あたりに結合するタンパク質は、細胞外細菌に対するタンパク質の方が数が多い。また、以前に調べた常在菌に結合する細胞外タンパク質の数と比べると、病原菌に対してはより多くのタンパク質が相互作用する。
多くの菌の中でも、ダニ感染によるスピロヘータが媒介するライム病やツツガムシ病菌と反応するホストのタンパク質は317種類と多い。このスクリーニングで、CD68 分子がツツガムシ病が感染後マクロファージの中に侵入する分子である可能性が示された。さらに、ツツガムシ病菌はエイズウイルスと同じ CXCR4 と相互作用することがわかったが、なんとツツガムシ病への免疫反応が、エイズ感染を防ぐという観察がある。
マラリアのスポロゾイトは様々なサイトカインに関わる分子と結合するが、マラリア感染が強い一種のサイトカインストームを誘導するのと一致する。特に、IL-15 受容体と強く結合することは、サイトカイン誘導のリード役として機能している可能性がある。
レプトスピラ症では、それまで低い浸透圧に存在していた菌が、人間の中で NaCl に触れて大きな変化を遂げ、その結果バソプレシンと結合するようになることがわかった。レプトスピラはブタで腎障害を起こすことが知られており、この相互作用が原因である可能性がある。
ライム病のスピロヘータの中には神経症状を強く起こすタイプが存在するが、これらの菌は神経系に発現されている分子と特にそうごさようをしめす。
さらにライム病は直接 EGF と反応して遺伝子発現を変えることも発見している。特に、人間の身体に入って体温に晒されたときにこの反応が起こることから、この反応を抑えることが感染拡大を抑える可能性がある。
最後に、細胞内寄生菌の7割以上がディスルフィド基を切断する、イソメラーゼと直接反応すること、またこの酵素を阻害すると細胞内感染が低下することも示している。
以上が面白い例だが、これまで個別に研究されてきたベクター媒介細菌をまとめて調べてみたことで、個別では気づかなかった様々な感染メカニズムが見えてきたという仕事で、派手さはないが重要な研究だと思う。
2024年6月17日
IL-23 は2種類の分子が複合したサイトカインで、そのうち p40 は IL-12 と共通で、p19 が IL-23 特異的という、複雑なサイトカインで、シグナルも IL-12 とオーバーラップするところもあるが、特に腸管の炎症性疾患のメディエーターとして、治療にも利用されている。
今日紹介する米国コーネル大学からの論文は、IL-23 によって腸管で起こる細胞変化を調べることで、自然リンパ球の中の、その一部はパイエルバンなど免疫組織の発生に関わり、我々も現役時代に研究していた ILC3 を刺激し、免疫抑制型に変化させることを明らかにした研究で、6月12日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「CTLA-4-expressing ILC3s restrain interleukin-23-mediated inflammation(CTLA-4 発現 ILC3 が IL-23 に媒介される炎症を抑制する)」だ。
この研究では IL-23 受容体 ( IL-23R ) 陽性細胞を蛍光でラベルしたマウスを用い、IL-23 により様々な細胞で起こる変化をモニターしている。大体6種類の IL-23R 陽性細胞が特定できるが、リンパ組織誘導細胞以外の ILC3 でチェックポイント分子の一つ CTLA4 が発現し、この現象はT細胞のない Rag ノックアウトマウスでも起こることを発見する。
この予想外の発見がこの研究の全てで、single cell RNA sequencing も特定の分子に絞って見直すことで、これまで見落としてきたことが発見できることを示している。当然次の課題は、IL-23 により誘導された CTLA-4 がチェックポイント分子として働くかになる。
これまで IL-23 は腸管への細菌感染で誘導されることが知られているが、この点を確認し、無菌マウスや抗生物質投与マウスでは、IL-23 が誘導されず、その結果 ILC3 の CTLA-4 発現も起こらないことを明らかにしている。すなわち、腸の細菌叢が IL-23 を誘導し、その結果 ILC3 が CTLA4 を発現する。
次に ILC3 が発現する CTLA-4 の機能だが、NKp46 発現 ILC3 で CTLA-4 をノックアウトする実験で、細菌に対する T 細胞反応を抑える抑制性 T 細胞の減少が見られることを発見する。すなわち、ILC3 は抑制性 T 細胞と同じように CTLA-4 を発現し、同時に抑制性 T 細胞を誘導することで炎症の拡大を抑えていることがわかる。
同じ実験を T 細胞のない Rag ノックアウトマウスで行うと、感染による IL-23 により自然炎症は普通に誘導されることから、ILC3 の CTLA-4 発現はもっぱら同時に起こる T 細胞の反応を制限することに向けられていることがわかる。
さらに CTLA-4 と反応する白血球上の CD80、CD86 の量が低下することで、PD-L1 が T 細胞に利用しやすくなり、この結果さらに強い免疫抑制を誘導することがわかる。以上のマウスの結果を、人の炎症性腸炎で調べ、IL-23 上昇により、人の大腸でも ILC3 が CTLA-4 を発現し、同時に白血球で PD-L1 が発現して、炎症を抑えようとしていることを明らかにしている。
以上、ILC3 は lymptoxin 発現により免疫組織の発生の誘導に関わるように、ILC3 の一部のサブセットは細菌性の炎症へのT細胞反応を調節するオーガナイザーとして働いていることがわかった。いずれにせよ、免疫システムの調節の複雑さがまた明らかになった。実際チェックポイント治療で腸炎は重大な副作用だが、自己免疫性の反応だけでなく、炎症抑えるオーガナイザーの役割まで抑えることで症状を重くしていると考えられる。今後の臨床にも重要な発見だと思う。
2024年6月16日
肥満の父親から生まれた子供が肥満になるというエピジェネティックなメカニズムは多くの興味を引きつけてきた。実際、精子のクロマチンは一度完全に解消されるので、ゲノムにエピジェネティックなメモリーが残るとは考えにくい。その後、短い RNA を読む技術が進んだおかげで、受精時に精子から短いノンコーディング RNA が伝わって、それがクロマチン形成を調節するのではと考えられるようになった。
今日紹介するドイツミュンヘンのヘルムホルツセンターからの論文は、マウスの実験と人間のデータベースを組み合わせて、肥満の影響が成熟した精子のミトコンドリア由来 RNA の変化を誘導し、これが分解された短い RNA (sncRNA) として受精卵に伝わり、子供の代謝関連遺伝子をエピジェネティックに変化させることを示した研究で、6月5日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Epigenetic inheritance of diet-induced and sperm-borne mitochondrial RNAs(ダイエットにより誘導されるエピジェネティックな変化は精子中のミトコンドリア RNA で伝えられる)」だ。
PiwiRNA を筆頭に精子形成で多くの sncRNA が形成されるが、これまでの研究で父親の代謝の影響は精子ができてから精巣上体に蓄積される段階で起こるのではと考えられるようになっていた。この研究はまずこの点を確認するため、精子形成後精巣上体に精子が蓄積される2週間を狙って高脂肪食を与え、体重変化とは行かないがインシュリン抵抗性など糖代謝に関わる変化が精子を通して伝えられることを明らかにする。
このとき、高脂肪食で変化する精巣上体 mRNA を調べると、肥満の子供の mRNA 変化とオーバーラップすることから精巣上体での精子の経験が子供の肥満を誘導することを確認している。
次にどの sncRNA が肥満によって最も影響を受けるかを様々な方法で調べ、ミトコンドリア由来の tRNA や rRNA が代謝を関知し、それを子供に伝えていることを決定している。またマウスの結果を、人間の精子で確かめ、特にミトコンドリアの tRNA が肥満と大きく関わっていることを確認している。
そして、この sncRNA が確かに受精卵に伝わっていることを、人工授精後2細胞期に確認している。また、その結果初期胚の転写、特に酸化的リン酸化などミトコンドリアの代謝に関わる遺伝子発現が変化して、これが子供のインシュリン抵抗性を誘導することを確認している。
最後に、ミトコンドリアの遺伝子を変化させた精子を用いる実験で、確かにミトコンドリアの異常が、エピジェネティックに子供に伝わることを確認している。
以上が結果で、もう少しわかりやすく説明し直すと、精子ではほとんどの遺伝子発現はストップするが、ミトコンドリア維持のために RNA が転写されている。精巣上体から受精まで酸素濃度の異なる環境を通過する間に、酸化的リン酸化が高まるため、この mRNA は転写が上昇する。これによって、精巣上皮で経験したミトコンドリア RNAの 変化が増幅され、またこの RNA は分解され sncRNA として受精卵に伝わり、そこでエピジェネティックマーキングを変化させるというシナリオになる。
要は母親だけでなく、なんとか父親の経験も伝えようという涙ぐましい努力がにじんだ話で、面白い。
2024年6月15日
今日は最近読んだ副作用に関する論文3題を紹介する。
まず最初は eClinical Medicine 6月号に掲載されたスウェーデン・ルンド大学からの論文で、2007年から2017年までにスウェーデンで登録された悪性リンパ腫の患者さん11905人について、様々な聞き取り調査を行い、何らかの入れ墨を入れた場合、悪性リンパ腫の発生頻度が1.2倍上昇し、さらに入れ墨後2年以内ではそのリスクが1.8倍になるという調査研究だ。入れ墨はマクロファージを使っていることなので、十分納得できる結果だが、スウェーデンで入れ墨を入れている確率がすでに2割近くになっているということに改めて驚いた。
次の European Heart Journal にオンライン掲載されテイルクリーブランドクリニックからの論文は55歳-72歳の中高年の血清のメタボローム検査を行い、キシリトール代謝物の量とその後3年の心臓血管疾患による死亡率を見ると、代謝物の多い人ほど死亡リスクが高いことを明らかにし、甘味料としてキシリトールを使うことの危険性を警告している。そして、この原因について、キシリトールが試験管内で血小板を活性化すること、さらにキシリトール摂取により血小板の凝集が著名に高まることを示し、これが心臓死が高まる原因であることを示している。かなり食品や飲料に使われている甘味料なので、緊急の検討が必要だと思う。
最後の6月12日号 Science Translational Medicine に掲載されたフライブルグ大学からの論文は PD-1 に対する抗体を用いたチェックポイント治療の副作用の一つが、直接ミクログリアに対する作用によるもので、脳内の神経炎症が上昇する結果、認知機能や運動機能が犯される可能性を示した研究だ。
覚えていただいているかどうか、昨年7月に PD-1 が神経系にも発現しており、抗体により記憶や学習能力が高まるという思いがけない結果を示したデューク大学の論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/22566 )」。今日紹介する論文はこの全く逆で、PD-1 抗体治療による自己免疫性と考えられてきた神経症状の中には、抗体のミクログリア直接作用によるものが存在することを示している。
この論文も詳細を飛ばして簡単に紹介するが、ほとんどはマウスの実験で、正常マウスに PD-1 抗体を投与したとき、抗体は脳に入ってミクログリアの形態変化を誘導し、炎症型ミクログリアへの転換を誘導する。そして、ミクログリアの Syk キナーゼの活性化が炎症型ミクログリア形成に関わっており、Syk キナーゼ阻害剤投与で、PD-1 によって誘導される認知障害は軽減するという結果だ。最後に、PD-1 抗体を投与された人間の脳の解析でも、同じようなミクログリア活性化が存在することを示し、おそらく PD-1抗体投与による神経症状の一部は、ミクログリアへの直接作用であると結論している。
神経に働くと記憶が高まり、ミクログリアに働くと記憶が低下すると相反する論文が出ているので、読む側はどちらもにわかに信じられないと思ってしまうが、結論を得るためには、それぞれの細胞の PD-1 発現から始める地道な研究がまず必要かと思う。