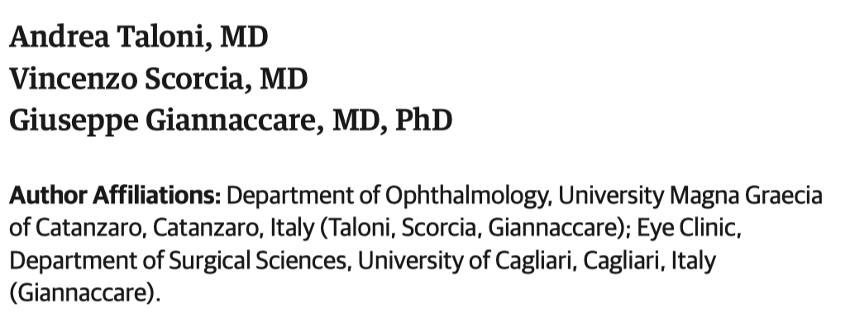2024年1月12日
ちょうど2年前、多発性硬化症(MS)が EVウイルス感染を条件として発生することを示した Science の論文を紹介した。そして、昨年12月 EVウイルス感染から MS発症までの免疫メカニズムを詳しく解析した論文がウイーン医科大学から Cell に発表された。そして、今日紹介するのは MS がなぜヨーロッパ人、特に北欧に多いのかについて1万年にわたるゲノム解析から調べたケンブリッジ大学、オックスフォード大学、ブリストル大学他の共同論文で、1月11日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Elevated genetic risk for multiple sclerosis emerged in steppe pastoralist populations(多発性硬化症の遺伝的リスクの上昇はステップ遊牧民で発生した)」だ。
新しい治療法の開発は急務だが、MS発症のメカニズムに関しては一区切りついた気がするので、今日紹介する論文も含めて次回の Youtubeジャーナルクラブでこれまでの研究のまとめをしたいと思っている。その時はここでは紹介しなかったウイーン医科大学の研究について特に詳しく解説する。
さて、今日紹介するのは病気のリスク遺伝子が集団の中でどのように変化するかをヨーロッパを形成した様々な人種の古代ゲノムを石器時代にまで遡って調べ、現代ヨーロッパ人での MSリスク遺伝子の変遷を調べている。
一般的には、交雑と選択を繰り返して形成される現代ゲノムの中に、病気のリスク遺伝子がなぜ維持され続け、場合によってはリスクが高まる方向に選択されているのかは不思議に見える。ただ、現代の病気と、古代の病気の質を考える時病気の遺伝子リスクを多面的に見ることが必要になる。
MS のリスク多型は実に233種類も特定されているが、そのうち32種類は MHC遺伝子領域内にあり、最も高いリスクが HLA-DRB1*15:o1 と呼ばれるクラスIIMHCだ。この研究ではヨーロッパ人の基盤になる古代ゲノム、すなわちトルコから南欧の農耕ゲノム(FG)、コーカサス遊牧民ゲノム(CHG)、ウクライナからカスピ海までのステップゲノム(SG)、東欧の遊牧民ゲノム(EHG)、そして西部遊牧民ゲノム(WHG)が交雑を繰り返す中で MSリスク遺伝子がどう変遷していくのかを調べている。
すると5000年前まではほとんど存在しなかった例えば HLA-DRB1*15:o1 が、急に SG に現れ、SG がヨーロッパへと拡大する中でヨーロッパ人全体に拡大することが明らかになった。また、リスク遺伝子全体のスコアで見ると、交雑を繰り返す中でリスクが上昇していることも明らかになった。すなわち、5000年前、ちょうどヤムナ文化が発祥する頃から HLA内の MSリスクに関わる多型が急速に現れ、他の民族と交雑する中でも、そのまま自然選択され、さらに他のリスク遺伝子も合わせて、現ヨーロッパの高いMSリスクを持つゲノムができあがっていることを示している。
勿論 MSリスクがポジティブな選択要因になるはずはないので、主なリスク多型について他の病気との相関を調べると、結核、EVウイルス、サイトメガロウイルスなど、感染症に対する抵抗性多型が集まってMSリスク多型を形成していることが明らかになった。
一般的に Th1反応はウイルスなどの細胞内感染、Th2は細菌などの細胞外感染に対するゲノム多型につながるが、MSでは両方の反応に対するリスク多型が集まっており、極めて複雑な感染免疫システム形成の結果として生まれたリスク多型と言っていい。
ただ、その後ヨーロッパは真っ先に衛生などを通して感染症を克服してしまったために、代わりに MSリスク多型として分類されてしまったという話になる。
しかし、このような面白い歴史の書き方が出来るようになった21世紀、人間がより憎み合い殺し合うのを見ると、そんな多型も調べたくなる。
2024年1月11日
CRISPRシステムの面白いのは、細菌が外来のウイルスやプラスミドから自分を守るための様々な戦略を開発している点だ。最も良く使われているのは Cas9 で DNA二重鎖を切断するので、ゲノム編集に用いているが、他にも特定の RNA を分解したり、Cas10 のように活性化されると手当たり次第に一本鎖核酸を分解する種類など実に多様で、これが様々な使用アイデアを産んでいる。ただ、これまで研究されてきたのはその核酸分解酵素活性だった。
ところが今日紹介するロックフェラー大学からの論文は、Cas10 を含む3型クリスパーシステムに存在するもう一つの遺伝子Cam1 が膜に穴を形成して脱分極させるという面白い機能が存在することを示した研究で、1月10日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「The CRISPR effector Cam1 mediates membrane depolarization for phage defence(クリスパー関連分子の一つ Cam1 は膜の脱分極を通してファージウイルス感染に抵抗する)」だ。
これまでの研究で3型クリスパーの Cas10 が一本鎖RNAを切断するとき、Palmドメインで環状のオリゴアデニル酸を合成する。これが cAMP のようなセカンドメッセンジャーとして細胞の増殖を止める働きをすることがわかっていた。
この研究ではオリゴアデニル酸合成と細胞増殖停止に Cam1 が関わるのではと考え、まず Cas10 の存在しない細菌の Cam1 を分離、これをブドウ球菌に導入し、その機能を調べている。
まず、Cam1 とオリゴアデニル酸が結合すること、そしてこの結合により細胞の増殖が停止、一定期間静止期のまま生存できることを明らかにする。
次に、Cam1蛋白質の構造解析から、この分子が通常4量体で細胞質に存在し、Cas10 の働きでオリゴアデニル酸が合成されると、これと結合して細胞膜へと移行して細胞膜に小さなチャンネルを形成することで、細胞膜を脱分極させ、これが細胞の分裂を止めることを明らかにする。
通常この穴は十分小さく、細胞死の測定に使う PI 色素は糖鎖がないため、細胞は PI で染まらず、実際増殖を止めたままオリゴアデニル酸が消失すると、再増殖が可能になる。
最後に、Cas10、Cam1 それぞれ別々、あるいは同時に発現するブドウ球菌を用意して、ファージウイルス感染抵抗性を詳しく調べ、ウイルスが感染すると、Cas10 がまずウイルス核酸とともに、近くの一本鎖核酸をズタズタにすることでウイルスの増殖を防ぐ。この時、環状のオリゴアデニル酸が合成され、これが Cam1 4量体と結合して活性化、膜移行を誘導することで、細胞膜を脱分極させ、細胞分裂を止めることで、ウイルスの拡散を防いでいることがわかった。
我々も、バクテリアを感知する自然免疫系がカスパーゼを活性化、それにより切断されたガスデルミンが細胞膜に穴を形成、それを通して IL1 が分泌されるシステムを持っているが、似ていると言えば似ている。
おそらく、このシステムを哺乳動物細胞へ移して面白い細胞エンジニアリングを可能にする技術が既に用意されているように思う。クリスパーの輪はどんどん拡がりそうだ。
2024年1月10日
高齢者として狙われているのか、FBでは老化を遅らせることをうたったNMNの宣伝がよく来る。NMNは経口可能な NAD前駆体で、体内の細胞で NAD を上昇させ、サーチュイン(SIRT)を活性化して、様々な蛋白質の脱アセチル化を通して老化を遅らせるというワシントン大学の今井さん達が強く推奨している方法だ。
今井さん達はさらに脂肪細胞から血中に放出されるエクソゾームに含まれた NAD合成酵素が脳の視床下部に達して、視床下部活性化を通して脂肪細胞をコントロールするフィードバック回路を提唱している。
今日紹介するワシントン大学の今井さんの論文は、このフィードバックループ、すなわち視床下部の脂肪細胞調節機構に視床下部神経が発現するフォスファターゼ分子 Ppp1r17 が関与していることを調べた研究で、1月8日 Cell Metabolism に掲載されている。タイトルは「DMH Ppp1r17 neurons regulate aging and lifespan in mice through hypothalamic-adipose inter-tissue communication(視床下部背内側核は視床下部―脂肪間のコミュニケーションを通して老化と寿命を調節する)」だ。
読んでみると、この研究は視床下部背内側核(DMH)と脂肪組織との関係に関わる研究として独立している。これまで DMH には老化に関わる遺伝子SIRT1 が発現していることがわかっていたが、この中の一部が SIRT1 で活性化される Nkx2.1 により誘導され、食欲や脂肪代謝の調節に関わることが知られていたPpp1r17 を発現していることを発見している。
Ppp1r17 を発現している神経の投射を調べると、交感神経を通して末梢組織と関わる領域への投射が見られる。そこでアデノウイルスを用いて DMH神経の Ppp1r17遺伝子をノックダウンすると、白色脂肪組織が肥大している。
以前交感神経のオキシトシンが脂肪代謝を高める論文を紹介したが、まさに Ppp1r17神経により調節される交感神経は脂肪分解に関わることを意味している。
次に Ppp1r17 の視床下部での機能を調べる目的で、遺伝子発現を調べると、この分子が神経細胞の代謝とともに、シナプス形成にも関わっていること、さらには試験管内での神経培養を用いて、Ppp1r17 が神経の自発的興奮に関わることを明らかにしている。すなわち、Ppp1r17 がノックダウンされると、神経活動が低下する。実際、Ppp1r17陽性細胞をジフテリアトキシンで傷害しても、同じように肥満が起こることから、DMH細胞中の Ppp1r17陽性神経細胞は交感神経系を介して脂肪細胞の活性化に関わることが明らかになった。
Ppp1r17 はサイクリック GMP依存性プロテインかイネース(PKG)の調節を受けているので、同じ細胞で PKG をノックアウトすると、Ppp1r17 の核外への輸送が低下し、Ppp1r17 の機能が保たれる。この結果、Ppp1r17ノックダウンの反対の結果、すなわち脂肪代謝が高まることが示された。
驚くことに、このマウスでは老化が遅れ、運動機能も保たれる。さらに、今井さん達が提唱してきたNAD合成酵素を含むエクソゾームの血中濃度が高まる。
以上が結果で、老化との関係はまだまだ詰める必要があると思うが、白色脂肪組織の中枢支配メカニズムとしては面白い研究だと思う。
2024年1月9日
多剤耐性菌による院内感染は医学の重要な課題で、そのためにはこれまでとは異なるメカニズムの抗生剤の開発が必要で、多くの企業がしのぎを削っている。
今日紹介するロッシュ研究所からの論文は、LPSを細胞壁へ輸送する過程を阻害するこれまでとは全く異なるメカニズムの環状ペプチドの開発で、1月3日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「A novel antibiotic class targeting the lipopolysaccharide transporter(リポポリサッカライド輸送系を標的とする新しいクラスの抗生物質)」だ。
大晦日に、中外製薬研究所独自の環状ペプチドライブラリーを用いた K-Ras阻害剤開発の話を紹介したが、もともと微生物から分離した薬剤のなかにはサイクロスポリンやバンコマイシンのような環状ペプチドが存在する。このことから、さまざまなサイズの環状ペプチド、あるいはそれにアミノ酸以外のジョイントが結合したテザード環状ペプチドライブラリーを合成して提供するベンチャー企業が存在し、この研究ではこの会社から45000種類のライブラリーを購入し、さまざまな細菌でスクリーニングした結果、多剤耐性菌にも作用する化合物を発見する。
この化合物は3種類のアミノ酸が diphenyl-sulfide で環状になったテザード環状ペプチドで、ここから耐性菌の代表 A. baumannii への効果が高まった化合物をアミノ酸の置換や側鎖の改変により開発している。
この化合物は感染動物の治療に効果があるが、LDL を沈殿させる副作用があり、濃度が高まると致死的になる。そこで、LDL沈殿活性が低下した化合物を、さまざまな情報をもとに改変して、最終的に LDL沈殿作用のない zosurabalpin の開発に成功した。
あとは、zosurabalpin がこれまでの抗生物質とは異なる作用機序であることを示すため、まず zosurabalpin が結合するバクテリア分子の同定を行い、プラズマメンブレン上に存在する LPS を細胞壁へと移行させる分子コンプレックスに結合し、実際この輸送系の機能を阻害することを明らかにしている。すなわち、これまで全く標的になっていなかった過程で、多剤耐性菌についても効果が期待できる。
この研究は薬剤の開発で終わっているが、同じ時に発表されたハーバード大学からの論文は、LPS が結合した輸送タンパク質に結合することで輸送が阻害され、一種の通行止め状態が誘導され、細胞壁の維持形成ができなくなることを示している。
以上が結果で、多剤耐性対策も一息つけるかもしれない。また、なんとなく環状ペプチドへの注目がますます高まっている気がする。
2024年1月8日
世界最古の化石についてご存知だろうか。まだ、生命誌研究館の顧問をしていた時代、「進化研究を覗く」と題して時々のトピックスを紹介していたが、2014年世界最古の化石がどの様に研究されているのかをまとめて紹介したことがある(https://www.brh.co.jp/salon/shinka/2014/post_000005.php )。これによると、35億年前の保存性が高い地層に存在する粘液細菌からなると考えられるストロマライトの中に認められる構造物こそが、細菌の化石とされている。もちろんなかなか証明が難しい分野なので異論も多い。しかし、多細胞生物が地球上に発生する6億年より前の生物は全て単細胞生物なので、この時期の化石研究は、当然単細胞の様な極小の構造を探すことになる。
今日紹介するベルギーリエージュ大学からの論文は、地球で光合成が始まり、酸素環境が形成されるきっかけになったシアノバクテリア、すなわち藍藻の発生時期を化石から調べ、おおよそ17億年以前には進化していたことを示した研究で、1月3日 Nature にオンライン掲載されている。タイトルは「Oldest thylakoids in fossil cells directly evidence oxygenic photosynthesis(化石の中に見られる最も古いティラコイドは酸素発生性光合成の直接的証拠になる)」だ。
光合成は植物に特徴的と思ってしまうが、他にもクロレラなどの藻類、そして藍藻の様な原核生物でも行われる。そして、この藍藻が葉緑体の起源となっており、ゲノムから見ると藍藻の進化は30億年前と推定されている。この結果、地球に初めて酸素が生まれ、その後酸素を利用する生物が進化してくることになるが、実際藍藻に似た細菌が古い地層に残っているのか、研究が続けられている。
しかし、細菌の化石を特定できるとしても、光合成を行っていたことをどう証明するのか。この研究では藍藻や葉緑素に存在する光合成のための膜に結合した小器官ティラコイドに着目した。そこで、オーストラリア、カナダ、そしてコンゴのシェール層から見つかっていた藍藻の仲間と考えられる化石を電子顕微鏡を用いて観察し、オーストラリア、カナダの化石の中に、明確にティラコイドと言える構造を発見する。
これが結果の全てで、あとはこれが化石形成過程のアーチファクトではないことを、例えばこの細菌が化石化された条件(Burial temperature)をラマン顕微鏡で調べると言った方法で確認している。すなわち、化石化が起こる過程の温度は180−200度程度で、十分に細胞内の構造が保存されることを示している。この様に、この分野で最も重要なのは、年代測定と、化石化課程の検証になるようだ。
結論としては、最も古い光合成を示す化石として17億年が示された。さらにコンゴから出土した藍藻類の化石にティラコイドが存在しなかったことは、12億年前には現在に見られるような光合成藍藻と、光合成を行わない藍藻が分離していたことも明らかになった。
これまでほとんど使われてこなかった電子顕微鏡を使える様にしたことが、細菌化石の解析が、最古の光合成細菌を特定に繋がったことになる。同じ方法を使って探せば、さらに古い藍藻化石が見つかることが期待できそうだ。地球規模で考えれば地学と生物学は近い。
2024年1月7日
昨年の科学のトップニュースとして、GLP-1Rアゴニストが痩せ薬として受け入れられ、今や薬が手に入らなくなるほどのブロックバスターになっていることを NatureもScience も共にリストしていたのは意外だった。それほど肥満への関心が高いということだと思うが、本当に服用し続けて問題がないのかはもっと長いスパンで見ていく必要があるだろう。実際、GLP-1Rを刺激する治療と言っても様々な方法があり、肥満も含めたメタボ改善という観点でどの治療が一番安全で効果があるのか、糖尿病から少し離れた観点から効果を調べていくことは重要だ。
今日紹介するバンダービルド大学からの論文は、GLP-1Rアゴニストと、内因性のGLP-1レベルを高めるDPP-4阻害剤を、インシュリン感受性改善という点に絞って調べた治験研究で、1月号の Diabetes に掲載された。タイトルは「Weight Loss–Independent Effect of Liraglutide on Insulin Sensitivity in Individuals With Obesity and Prediabetes(肥満の糖尿病予備軍に対する、体重減少による効果とは別のリラグルタイドのインシュリン感受性改善効果)」だ。
GLP-1アゴニストは、皮下注射、あるいは内服で直接GLP-1受容体(GLP-1R)を刺激する治療で、現在痩せ薬として注目されている薬剤だ。これに対しDPP-4阻害剤は、GLP-1やGIPなどいくつかの消化管ホルモンを分解する酵素DPP-4を阻害することで、GLP-1など消化管ホルモンの局所での濃度を上昇させる働きがある。
薬剤グループは、無作為化偽薬試験として効果を確かめているが、調べた母数が少ないのが問題になる。この問題を認めた上で、結果だが、GLP-1RアゴニストもDPP-4阻害剤もほぼ同じ効果があると思っていた私にとっては驚きだ。
最も重要な目的は、体重低下が始まる前から、GLP-1R刺激によりインシュリン感受性が上昇するのか調べることだ。というのも、GLP-1Rアゴニストが魅力があるのは、体重が低下するだけでなく、インシュリン抵抗性などメタボ指標が大きく改善することだが、これが体重減少の結果なのか、GLP-1Rアゴニストの直接効果なのかはわかっていなかった。
結果は明瞭で、体重減少が始まるより以前、すなわち薬剤投与後2週間から、空腹時血糖、インシュリン濃度、そして HOMAR-IR と呼ばれる指標から、GLP-Rアゴニストではインシュリン感受性が上昇していること、一方ダイエットやDPP-4阻害剤ではこの様な効果が全く見られないことが明らかになった。
さらにこの効果は、GLP-1R阻害剤で完全に消失することから GLP-1R に対する刺激であることは明らかだ。
結果はこれだけだが、同じメカニズムと思っていた薬剤も、効果が全く異なることに驚く。さらに、体重で見るとDPP-4阻害剤は14週目でもほとんど減少がない。この薬剤は、早くから糖尿病薬として使われてきたが、痩せ薬という騒ぎが起こらなかったのもよくわかる。
なぜこの違いが出るのか。内因性のGLP-1の場合、おそらくまず膵臓や肝臓に作用すると思われる。また、DPP-4阻害剤は GLP-1 だけでなく、様々な消化管ホルモンに作用する。実際、DPP-1阻害剤だけで、血中グルカゴンの濃度が高まっている。
今後動物実験を含めて、それぞれの治療法の長期効果と、具体的な作用とを対応させる研究が必要になると思う。しかし、これだけ歴史のある薬剤でも、本当にわからないことが多い。
2024年1月6日
ガンのゲノム解析が始まった頃の驚きの一つは、それまでガンのドライバーとか、抑制遺伝子として馴染みのあった遺伝子のほかに、IDHのような代謝酵素や、SF3Bといったスプライシングに関わる分子の変異が高い割合で発見されたことだ。それから何年も経って、その意味を理解できる様になってきた。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、現在治験が進むSF3Bスプライシング因子阻害剤をさらに有効に活用するための前臨床研究で、1月3日号の Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Splicing modulators impair DNA damage response and induce killing of cohesin-mutant MDS and AML(スプライシング阻害剤はコヒーシン変異を持つMDSやAMLの細胞死を誘導する)」だ。
標的がわかっていると言ってもスプライシングはあらゆる細胞でも働いておりガン特異的ではない。そこで、抗ガン治療の常道と言える異なるメカニズムを標的にしてガン特異性を高めようと考えるのは当然だ。この研究ではその候補として、ガンや白血病で変異頻度が高いコヒーシンに注目した。もともとコヒーシンは分裂時の染色体分離に異常があり、この変異と合わさるとSF3B阻害剤の効果が高まるのではと着想した。
白血病株のコヒーシンをノックアウトしてSF3B阻害剤を加えると、変異のない白血病に対する効果が弱かったSF3B阻害剤の効果が何十倍にも高まることを観察する。ただ、調べていくとこれは変異コヒーシン遺伝子のスプライシングがSF3B阻害剤で変化するわけではなく、コヒーシン変異により誘発されるDNA損傷修復がうまく行かないため、細胞死が誘導されることがわかった。
そこで、阻害剤で誘導されるスプライシング異常分子を調べると、コヒーシン変異に関わらずDNA損傷修復に関わる様々な分子、例えば最も有名なBRCAなどの正常分子がほとんど消失することを明らかにしている。修復機構を機能的に調べると、実際にSF3B阻害剤で修復効率が著しく低下していることがわかる。
もともとBRCA変異のような修復遺伝子の機能異常は、ガンの弱点だとされてきた。SF3B変異でこれを誘導できるなら、コヒーシン変異がなくても抗ガン剤に対する感受性が高まるはずで、この研究でも実際の白血病細胞をコヒーシン変異有無に分けて、SF3B阻害剤と、修復阻害剤や一般の抗ガン剤と組み合わせて効果を見ている。コヒーシン変異のある場合だけ、SF3B阻害剤の治療効果が見られるという結果で、遺伝子検査の上で治療を行うことの重要性を示している。
あとはSF3B 阻害剤投与の第一相治験に参加した患者さん3名の末梢血について RNAsequencing を実施し、白血病細胞株でみられたのとほぼ同じ、DNA損傷修復に関わる分子のスプライシング異常が誘導されていることを確認している
以上の結果から、SF3B阻害剤の効果は主にDNA損傷治癒に関わる遺伝子のスプライシング異常を誘導することで発揮されるが、これに加えてDNA損傷が高まる変異を持つ変異が加わることでその効果はさらに高まることが示された。
この様に、様々な治療薬を組み合わせるガン治療はこれまで以上に重要になるが、このためには患者さんのガンゲノムを調べて治療計画を行うことが必須になる。この点で我が国は圧倒的に後進国だ。今日、友人の一人が食道ガンで亡くなった。相談されたとき、主治医に私費でガンゲノム検査をしたいので切除組織の一部を分与してもらう様アドバイスした。残念ながら大学病院であるにも関わらず、その申し出は意味ないと拒否された様だ。しかし、抗がん剤治療だけでなく、免疫治療に関しても、ゲノム検査はますます重要になる。そして、ガン特異抗原の有無などは、一般的なオンコパネル検査ではわからない。一方、変異の情報処理については、大規模言語モデルの出現でますます一般化されつつある。その意味で、我が国のガンゲノム検査を、根本的に見直す必要がある。そのとき、検査は民間主導にすることが重要だ。
2024年1月5日
メディアには関節の痛みを軽減すると称する様々なサプリが溢れているが、それだけ多くの人が関節症状を訴えていることになる。このほとんどはいわゆる変形性関節炎で、軟骨がすり減ることで起こってくる。そして、現在の医学でも痛みを緩和することは出来ても、軟骨の変性を食い止めることは難しかった。
しかし、今日紹介するニューヨーク大学からの論文は、変形性関節炎の病態メカニズムの一端を解明し、治療への糸口を見つけた点で重要な研究だ。タイトルは「Nav 1.7 as a chondrocyte regulator and therapeutic target for osteoarthritis(Nav1.7は軟骨の調節因子で変形性関節炎の治療標的になる)」だ。
このグループは、元々痛みを緩和するために電位依存性のナトリウムチャンネルを研究する中で、軟骨にもいくつかの電位依存性Naチャンネル(Nav)が発現し、中でも Nav1.7 が変形性関節炎で上昇していることを発見する。
この現象と変形性関節炎の関係を調べるため、マウスの軟骨、あるいは感覚神経から Nav1.7 をノックアウトして、外科的あるいは化学的に軟骨を傷害して変形性関節炎を誘導すると、痛みに関しては感覚神経、軟骨特異的ノックアウト両方で発生が抑制される。一方、関節炎の病理的進行と症状改善について見ると、なんと軟骨特異的に Nav1.7欠損マウスで進行を止めることが出来ることを明らかにしている。
Nav1.7 については、てんかん治療目的などで様々な特異的阻害剤が開発されており、これを全身投与することでノックアウトと同じように症状を改善することが出来る。
次に、Nav1.7チャンネル阻害が変形性関節炎進行抑制のメカニズムを培養軟骨を用いて検討し、チャンネル抑制により発現が上昇する分子の中で、シャペロンである HSP70 と生理活性物質ミッドカインがそれぞれ軟骨細胞のコラーゲン増殖など再生型の代謝、およりマトリックス分解酵素などの炎症型分子の賛成を抑える役割があることを発見する。
最後に、Nav1.7チャンネル抑制によりこれら分子の細胞外への湧出が誘導されるメカニズムも検討し、流入したナトリウムがナトリウムカルシウムトランスポーターによって細胞外へ排出される結果、細胞内のカルシウム濃度が高まり、それによりこれら分子が細胞外へ湧出することを示している。
以上が結果で、なぜ変形性関節炎が Nav1.7 の発現を高めるか、あるいはカルシウムとHSP70、ミッドカインの分泌など、まだまだ詳細については詰める必要があると思うが、これまで全く糸口のなかった変形性関節炎治療開発については大きな進展だと思う。内服できる Nav1.7阻害剤は存在し、効果があることも示されたが、これまで精神疾患に使われていることを考えると、そのまま高齢者に使っていいかは問題になると思うが、局所持続投与が可能なら大きな関節だけでもすぐ治療可能になったほしい。
2024年1月4日
DNAメチレーションが遺伝子発現調節のエピジェネティックファクターとして重要な働きをしていることは誰も疑わない事実だ。ただ、これまでの研究は、例えばビスルファイドシークエンシングと呼ばれる、メチル化されたDNAを化学変換して特定する方法、すなわちメチル化されたシトシンをゲノム上で特定する技術に基づいていた。さらに最近では NOMe-seq のように、クロマチン構造とメチル化DNAの特定を同時に行う方法も開発され、メチル化DNAの機能が明らかになっている。
これに対し今日紹介するリトアニア・ビリニュス大学からの論文は、クロマチンが開いているメチル化されていないシトシンと、脱メチル化過程にある 5hmDNA を同時に特定する方法を開発し、メチル化されていないシトシンから遺伝子発現を見直した研究で、DNAメチレーションも裏から眺める重要性を教えてくれる研究だ。タイトルは「One-pot trimodal mapping of unmethylated, hydroxymethylated, and open chromatin sites unveils distinctive 5hmC roles at dynamic chromatin loci(一つのチューブ内で、クロマチンの開いた場所のメチル化されていない、あるいはハイドロオキシメチル化部位を解析するとダイナミックな染色体上での 5hmC の機能が明らかになる)」だ。
まず方法だが、開いたクロマチンに存在する GC、 CG部位に、それぞれ異なるDNAメチル化酵素を用いて化学修飾を行い、また 5hmC部位にも別の酵素を用いて化学修飾を行う。その後DNAを切断し断片にプライマーを結合させるとともに、修飾した場所に別のプライマーを結合させる。その後、両方のプライマーからDNA増幅を行い、ラベルされたCG、 GC、 5hmCの部位をゲノムの上にマッピングしている。これにより、その時どの領域のクロマチンが開いていたか、そしてそこに存在していたメチル化されていないCを特定できる。また、同じ場所にあってラベル出来なかったCはメチル化されていたと考えられる。
この解析を、ES細胞から神経幹細胞、そして神経細胞への分化過程で行って、転写される遺伝子と照らし合わせて、分化の過程でおこるメチル化、脱メチル化過程を解析している。
これまでメチル化DNAの解析からわかっていたように、分化とともにメチル化部位がダイナミックに変化し、それとともにクロマチンの構造も変化することが、この解析からも確認される。
しかし、メチル化されていない場所を見ることで、全く新しい風景も開けてくる。例えば、プロモーター部位でクロマチンが開いて、メチル化が起こっていなくても、遺伝子発現が起こらないケースが多く認められる。このほとんどは、転写開始点より下流の、遺伝子本体のメチル化が残っているためで、これが脱メチル化過程により 5hmC へと変換されると、転写が始まる。
また、5hmC はイントロンと接するエクソン側に多く存在しており、スプライシングに関わる領域の抑制を完全に取り除いた後、転写にゴーサインが出ていることもわかる。
実際このような遺伝子本体の変化は、分化終了より前から進んでおり、転写が単純にプロモーターとエンハンサーの領域だけで決まるわけでないことがよくわかる。
以上が主な結果で、ゲノムワイドにメチル化部位がわかってきたとき、遺伝子本体のメチル化は何をしているのかなど議論があったが、この論文でよく理解できた。現象は常に表と裏から見ることが重要だ。
関係ない話だがおそらくリトアニアからの論文を紹介するのは初めてだ。今後も応援したい。
2024年1月3日
ウェッブを介するデータサーチなしに私の今の生活はあり得ないが、他の人と比べても私は依存度の高い生活をしている。まず一日の長い時間モニターに向かっている。そして論文は言うに及ばず、一般の本も出来るだけウェッブを介して読んでいる。Kindle で買える場合は、既に持っている紙媒体も買い直している。これは、読みながら思いついたことをすぐにウェッブサーチ出来るからで、デスクに座っているときは Kindle も普通の PC で読んでいる。ただ、依存度が高いからと言って、サーチエンジンを信じているわけではない。すなわち鵜呑みにしない経験が必要になる。そこで今日はウェッブデータを鵜呑みにしないことの重要性を実験的に示した面白い論文を紹介する。
最初の論文は12月20日 Nature にオンライン掲載された論文で、間違った情報をウェッブサーチで調べることで、余計間違った話を信じてしまう危険性を示したセントラルフロリダ大学からの論文だ。
この研究ではウェッブでの呼びかけに応じた千人規模の参加者を無作為化して2群に分けた後、フェイクであることが専門家により確認されたニュースを発生後、様々な時間をおいて伝え、ニュースが正しいかどうか答えてもらう。この時、一群にはウェッブサーチを参考にして真偽を調べるよう指示すると、驚くことにウェッブサーチをかけた群の方が間違ったニュースを正しいと信じる確率が10−20%上がることを発見した。このようなニュースは、時間がたつと専門的ファクトチェッカーにより間違いと示されるようになるが、この傾向はニュースが発生してから時間がたってもあまり変わらない。
実際どんな情報を見て間違いを信じるのかを調べると、あまり当てにならないニュースソースから情報が返ってきたときに、信じ込む傾向が強くなる。
最後に、なぜ信用性の低いサイトからのデータが引っかかってくるのかを調べると、サーチの仕方がそれぞれの政治信条や、ウェッブと付き合うためのリテラシーにより影響され、未熟で思い込みが激しいほど、信頼性の低いサイトから結果が帰ってしまうことを示している。
以上が結果で、これはサーチエンジンの話で、SNSになるともっとひどい結果になる気がする。いちいち思い当たる結果とはいえ、無作為化し、よくデザインされた実験として行ったことが重要だ。
次の論文は新しくなったGPT-4を使って、データねつ造が可能であることを示したイタリア・Maguna Graecia大学から12月号のJAMA Opthalmologyに発表された論文だ。
昨年11月、GPT-4が大幅にアップデートされ、新しいデータベースにアクセスしたり、計算したり、イラストを作るのが一段と楽になったが、パイソンを使う Advanced data analysis(ADA) を介して、データ解析も可能になった。
このグループは角膜手術の異なる術式の成績結果を ADA に読み込ませ、その上で結果についても指示を出すと、元々は差がないというデータセットから、指示通りの結果を捏造できることを明らかにした。
この論文では、指示通りに結果が捏造されることだけが示されているが、なぜそうなったのかを、Nature 誌が調べさせており、その結果男女が適当に入れ替えられていたり、評価に使った指標と個人とのリンクが変えられていたり、参加者の年齢の偏りが強くなっていたりと、捏造能力に長けていることがわかった。
詳しく調べれば必ず明らかになる捏造だが、査読の時に見つけるのは不可能だろう。
ガリレオに始まる科学は、他の人の同意を得るための手続きを示したことで、宗教が押しつけていた捏造を排除したことにある。その意味で、学生さんに講義するとき、捏造するのは自由だが、捏造した時点で科学を拒否したことになると教えている。ウェッブサーチや AI は、決定論的なので、宗教にはなり得ても、科学にはなり得ないことが明らかだ。この点も AI 開発の今後の焦点になる。