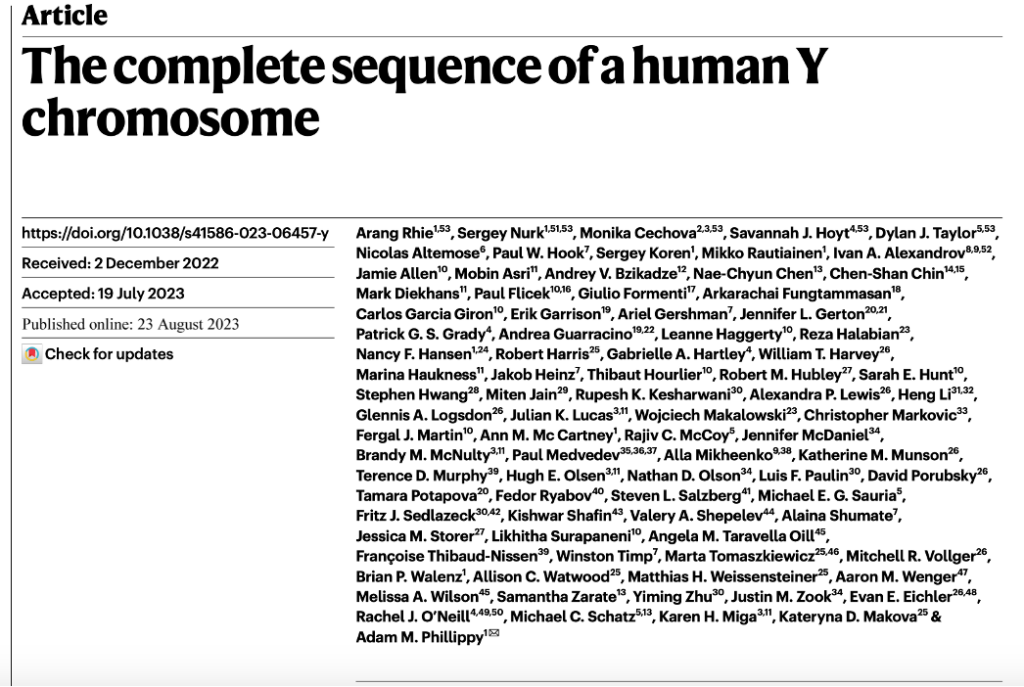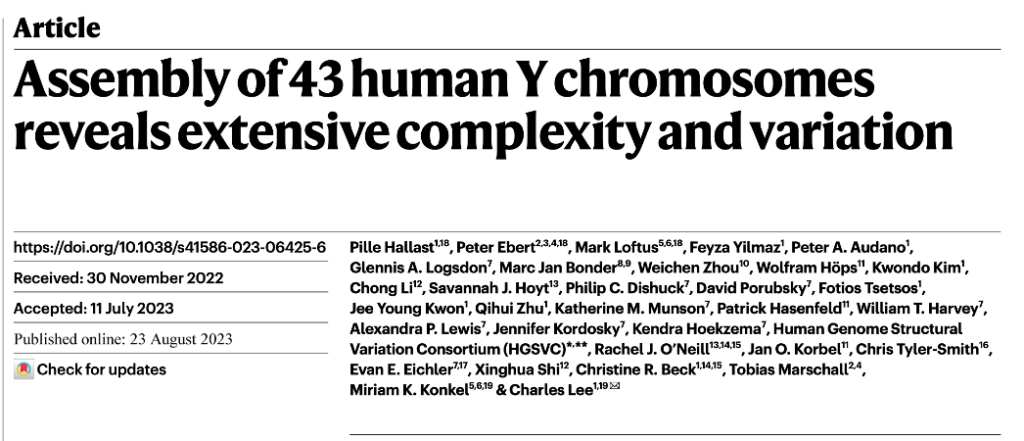2023年9月5日
微生物を分離しその抗菌活性を調べることで多くの抗生物質が開発されてきたことは一般にもよく知られている。このことは、細菌が培養できないと抗生物質は発見できないことを意味し、できるだけ多くの細菌を集めることの重要性が語られてきた。逆にいうと、培養が難しい微生物は研究の対象外になってしまう。
今日紹介するドイツ・ボン大学とオランダ・ユトレヒト大学からの論文は、普通は培養が難しい細菌を分離し、ここからこれまでとは全く異なるメカニズムで黄色ブドウ球菌をはじめ多くの細菌を殺すことのできる抗生物質を開発した研究で、8月22日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「An antibiotic from an uncultured bacterium binds to an immutable target(培養困難微生物から分離した抗生物質は変化が起こらない標的に結合する)」だ。
最初 uncultured を、培養していない細菌と間違ってしまい、細菌叢のゲノム研究から新しい抗生物質を発見する論文かと読みはじめて、普通の培養では他の細菌に押されて培養できない細菌を培養して抗生物質活性を探索する研究であることを理解した。
この研究の培養方法は96ウェルのクラスタープレートに、ほぼ一個づつ細菌が入る程度に培養し、なんと12週もかけてようやく細菌が増えてきたことがわかるほどゆっくりと増殖してくる細菌を黄色ブドウ球菌に作用させ、抗生物質活性のある細菌を分離し、それが Eleftheria 菌であることを遺伝子解析から明らかにしている。
あとは、この細菌の培養上凊を生化学的に分離精製し、最終的に Clovibactin と名付けたアミノ酸が組み合わさった新しい抗菌化合物に辿り着いている。このように、わざわざ培養困難微生物を選び出したことがこの論文のハイライトだが、実際に Clovibactin を分泌していた菌は Eleftheria 一種類だけなので、努力に報いようと運も味方についてくれたのかもしれない。
次に、Eleftheria 菌がこのような複雑な抗生物質を作っているのかを確認するため、ゲノム解析を行い、四種類の酵素からなる合成のためのオペロンを特定し、合成過程を明らかにしている。
肝心の効果だが、バンコマイシンと比べても、黄色ブドウ球菌を急速に溶菌させる活性がある。また、最終殺菌効果も高い。さらに、抗菌スペクトラムも広い。また、動物細胞には全く影響がなく、動物に静脈注射してもはっきりした副作用は見られない。またマウスでのブドウ球菌感染をバンコマイシンと同程度に抑えることができる。
最も重要なのは、これまでの抗生物質と比べて、耐性菌の出る確率が100倍以上低いことで、今後の感染治療に変革をもたらせる可能性がある。そのため、詳しく作用メカニズムを解析している。この過程はまさにこの分野のプロの仕事といった感じで、まず Clovibactin が細胞壁構成に関わる基本分子 Lipid II および C55PP 分子に結合していることを突き止めると、NMR や原子間力顕微鏡を駆使した構造解析から、ほとんどの細菌が依存しており、他の分子経路が存在しない Lipid II に結合し、これを重合させることで、細胞壁のペプチドグリカン合成が阻害される。このユニバーサルに存在する他の経路で代償できない過程を標的にしているため、耐性が起こりにくい原因であることがわかる。
結果は以上で、Clovibactin自体がそのまま夢の抗生物質として利用されるかどうかはわからないが、作用機序がわかったことで耐性のない抗生物質という夢を実現する方法が明らかになったことは大きい。このようなプロがいてくれるおかげで医学も進む。
2023年9月4日
最初に臨床応用が行われたCAR-T治療は、T細胞にCD19に対するキメラ抗体を導入することでCD19を発現するBリンパ性白血病を殺す治療だった。最初の論文を読んでCAR-T治療がいかに効果が強いか認識したのは、白血病細胞だけでなく、なんと正常B細胞まで除去されていた点で、キラー細胞の力を思い知った。
ただこのキラー細胞の強さが、CAR-T治療の普及を妨げている。すなわち正常細胞に全く影響の出ないガン特異的抗原をみつけるのが難しい。実際、大人では発現していないだろうと考えて行った治療で、正常細胞が障害されたケースが報告されている。
今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、このガン特異的抗原を特定することの難しさを逆手にとって、すべての血液細胞に発現しているCD45分子を標的にしたCAR-Tを用いる代わりに、造血系とCAR-T自身のCD45が発現するエピトープを編集して、CAR-Tに殺されないようにする逆転の発想を検証した研究で、8月31日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Epitope base editing CD45 in hematopoietic cells enables universal blood cancer immune therapy(CD45陽性血液幹細胞のエピトープ編集によりすべての血液ガンに対する免疫治療が可能になる)」だ。
同じ週の Nature にも、ハーバード大学から血液幹細胞や血液ガンで発現する FLT3、c-Kit、 IL3-R などをエピトープ編集するCAR-T 開発の論文が発表されており、この方向研究も競争が激しいことを示している。
さて、ペンシルバニア大学からの論文だが、CD45ノックアウトCAR-Tを用いてCD45がCAR-Tの増殖と維持に必須であることを確認している。すなわちCD45に対するCAR-Tを実現するには、まずCAR-Tが発現するCD45の機能を保ったまま、抗体には反応しないようにエピトープ編集を行う必要がある。結局CD45の機能部位とは全く異なる場所を認識する抗体をCAR-Tのキメラ抗体として用い、抗体に認識されるエピトープのアミノ酸を置換する作業をCRISPRを用いて行い、CD45を発現するガンは殺すが自分自身は認識されないCAR-Tを完成させている。編集の効率は高いが、いずれにせよ本来の編集できないCD45を発現しているCAR-Tは培養しているうちに殺し合って消滅する。こうしてできたCAR-Tは移植したマウスの中で長期に維持され、CD45を発現しておればすべての血液ガンを殺してくれる。
このCAR-TをCD45を発現する人間で応用するためには正常血液のCD45もCAR-Tに認識できないようにエピトープ編集する必要がある。そのため、ヒトCD34造血幹細胞を精製し、同じ方法でCRISPRを用いたエピトープ編集を行い、こうしてできたCD45造血幹細胞を免疫不全マウスに移植、増殖維持されることを確認した上で、最後のCD45を標的にしたガン治療が可能かの実験を行なっている。
エピトープ編集を行った血液幹細胞を移植、その後骨髄性白血病を移植、そして最後にやはりエピトープ編集を行ったCAR-Tを移植すると、見事に白血病は除去され、ほぼすべてのマウスが生存している。
結果は以上で、CAR-Tもどんどん複雑になっているが、しかし元々多くの白血病では骨髄移植が行われるし、またCAR-Tのほうも現在治験が進んでいる誰でも利用できるユニバーサル型を編集すれば、割と簡単に実現できるような気がする。期待したい。
2023年9月3日
繰り返し刺激を受けたシナプスの伝達性が持続的に高まる長期増強(long term potentiation:LTP)は、学習の細胞的基盤とも考えられる神経生物学の重要な概念の一つだ。この長期的シナプスの伝達性変化は、カルシウムの流入により活性化されるカルモジュリンキナーゼ (CAMKII) が関わっていることが指摘されていた。すなわち、神経興奮によるカルシウム流入は、CAMKII を活性化を誘導、活性化された CAMKII はシナプスでグルタミン酸受容体(GluR)と結合し、GluR やそれと結合している分子をリン酸化し、これによりシナプス伝達性が高まると説明されていた。事実、CAMKII の ATP 結合部位の変異によるリン酸化活性の消失は LTP 消失につながることも示され、この考えは通説になっていた。
今日紹介するコロラド大学からの論文は、CAMKII は LTP に必須だが、リン酸化活性ではなく、CAMKII の構造変化により GluR と持続的に結合することがシナプス伝達性を高めるという、通説の見直しを迫る研究で、8月30日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「LTP induction by structural rather than enzymatic functions of CaMKII(LTPは CaMKII の酵素活性より構造変化により誘導される)」だ。
通説では LTP には CaMKII のリン酸化活性と、それに続く GluR への結合が重要であると考えられていた。この研究では、シナプス刺激によるカルシウム流入なしに、光で抑制ドメインを解除することで、ATP 結合部位と、GluR への結合部位が同時に開く人工 CaMKII (m CaMKII) を用いることで、CaMKII の酵素活性と、GluR 結合活性をそれぞれ分離して LTP への作用を調べている。
この mCaMKII を発現したシナプスでは、光を当てると刺激なしに LTP を誘導できる。次に、この分子の GluR 結合部位に変異を、ATP 結合ドメインへの変異を別々に導入して LTP への影響を調べると、GluR 結合部位変異では CaMKII リン酸化活性は維持されるのに、LTP 誘導ができなくなる一方、ATP 結合が消失する変異では、リン酸化活性は消失しても、LTP 誘導は正常に行われることを発見する。すなわち、LTP に CaMKII のリン酸化活性が必要だとする通説が否定された。
この発見がこの研究のハイライトで、あとはこの発見をいくつかの方法で再検証している。中でも面白いのが、CaMKII のキナーゼ活性阻害剤 AS283 を用いた研究だ。LTP にリン酸か活性が必要ないことは、AS283 を用いた阻害実験からも確かめられるが、驚くのは ATP 結合部位に変異を導入した CaMKII に AS283 を作用させると、変異で失われていた LTP 誘導能が回復する点だ。すなわち、CaMKII のキナーゼ活性より、ATP 結合により CaMKII 構造が変化し、GluR に結合することが LTP を誘導することが明らかになった。
最後にこの結果を元に、変異型 CaMKII を誘導したマウス海馬を、AS283 を用いて CaMKII の構造変化を誘導することで、LTP を誘導する実験を示して、新しい LT P誘導実験システムが可能であることを示している。
2023年9月2日
善玉コレステロール(=HDL)や悪玉コレステロール(LDL)という言葉は一般の人にもよく知られるようになっている。この言葉を聞くと、コレステロールに異なる善玉、悪玉があるように思うが、実際には HDL と LDL はそれぞれ異なる分子構成を持つ脂肪運搬用構造で、その中にコレステロールが詰まった一種のカーゴで、LDL の場合カーゴへとまとめるのは ApoB として知られるタンパク質だ。このタンパク質の周りに、肝臓でまず Very Low density lipoprotein(VLDL) が形成され、これが血中で加水分解が起こり LDL できる。具体的には、肝臓内で ApoB にトリグリセリド、コレステロール、そしてフォスフォリピッドが付加されてできた構造物が VLDL だ。
今日紹介する米国ミルウォーキーにあるVersiti血液研究所から論文、tPA が低い人は VLDL が高値で動脈硬化リスクが高いという意外な関係についてそのメカニズムを調べた研究で、9月1日号 Science に掲載された。タイトルは「Intracellular tPA–PAI-1 interaction determines VLDL assembly in hepatocytes(細胞内でのtPA-PAI1相互作用により肝臓でのVDLの合成が決められる)」だ。
この研究は一見 VLDL とは何の関係もないように思える tissue plasminogen activator (tPA) が低いと動脈硬化リスクが高まるという現象を理解しようと始まっている。ここでいう tPA とは脳梗塞と診断されたら静脈注射により脳血栓を取り除くために使われる、タンパク分解酵素で、LDL 合成との接点は、この相関以外にほとんど知られていなかった。
そこで、tPA が肝臓での VLDL 合成に影響するかを調べる目的でまず、LDL 受容体をノックアウトして、マウスでも LDL 検出できるようにしたマウスに、tPA のアンチセンスRNAをアデノウイルスベクターで投与し、肝臓でのtPA発現を抑えると、VLDLの合成が増加することがわかった。この効果は、血栓と違って血中に tPA を注入しても得られない。すなわち、肝臓細胞の中で tPA の合成が上がると VLDL 合成が低下、逆に tPA が抑えられると、VLDL が増加する。また、同じ結果は培養ヒト肝細胞でも確認された。
ApoB にコレステロール、トリグリセライド、フォスフォリピッドが集められ VLDL が合成される過程は小胞体内で進み、microsomal triglyceride transfer protein (MTP) がこの過程のドライバーとして働いている。もし tPA が細胞内で VLDL 合成を抑えるなら、ApoB と MTP の相互作用を阻害している可能性が高い。実際生化学的な研究から、tPA は ApoB と直接結合して、MTB が ApoB に作用するのを阻害し、それに続く VLDL 合成を抑えることを明らかにしている。すなわち、tPA は血栓形成を防ぐ線溶系機能だけでなく、細胞内では VLDL 合成阻害剤として VLDL 合成の調節に関わっている可能性が示された。
この tPA の VLDL 合成調節因子としての作用をさらに調べると、これまで tPA の酵素活性阻害剤として考えられてきた PAI-1 が、肝臓内で直接 tPA と結合すると、今度は tPA の VLDL 合成抑制活性が失われ、結果 VDLA の合成が上昇することを示している。
面白いことに肝臓での PAI-1 と tPA の結合は脂肪を摂取することで上昇する。すなわち、脂肪を摂取すると、肝細胞では PAI-1 と tPA の結合が促進され、その結果 tPA による ApoB と MTB 相互作用の抑制が外れるため、VLDL 合成が上昇、その結果 LDL 上昇と動脈硬化へと進むというよくできたメカニズムになっている。人間でも PAI-1 の発現が低い人では LDL が低いようで、おそらく同じ機構が働いていると考えられる。
結果は以上で、脂肪摂取で PAI-1 と tPA の結合がなぜ高まるのかについてはこれからの問題だが、細胞外で働いていると思っていた tPA や PAI-1 が肝臓細胞内で VLDL 合成に関わるという面白い結果で、今後新しい脂質異常治療の標的へとつながる可能性もある。
2023年9月1日
現在も戦争が続いている今、ウクライナ戦争を分析した論文が Nature に発表されるなど、まず誰も想像できないはずだ。しかし、今日紹介するノルウェイのトロムソ大学とウクライナ国立宇宙機構からの論文は、2022年2月24日、ロシアのウクライナ侵攻から撤退までの期間、チェルニヒウからキーウにかけてのウクライナ北部で行われた戦闘の様子を、地震計や爆轟計を用いてモニターできることを示した研究で、8月31日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Identifying attacks in the Russia–Ukraine conflict using seismic array data(ロシアーウクライナ衝突での攻撃を一連の地震計測システムのデータから読み解く)」だ。
1963年8月に成立した部分的核実験停止条約では、地上核実験が禁止されたが、核実験をモニターするため、世界200箇所に地震計と低周波音波動を感じるセンサーが設置され、現在も稼働している。この一つがウクライナ、キーウ近くのマリーンに設置されており、データが公開されている。
この研究のすべては、この公開データが、2月24日ロシア侵攻から4月撤退までの戦争の様子を反映しているはずだと着想した点にある。これまで、精密な衛生写真で戦争を読み解く努力が様々な機関で行われているが、時間解像度、すなわち攻撃間隔や一回の規模については、ほとんど0に等しかった。
一方、地震計や爆轟による低周波計は、位置を測定するため複数が一つのセットとして設置されているおかげで、地震速度と、音速を元に、どこで攻撃による爆発が起こったのかを、地震と区別して、ほぼリアルタイムでモニターすることができる。実際には、地震波と低周波が一致するのは全体の3割ほどしかない。検出頻度が低いのは、音の周波数など検出に選んだ閾値の問題と考えている。
最終的に振動と低周波音から場所が特定できた爆発は、ロシアの北部地域侵入から4月初旬のキーウ領域からの撤退まで、地震に換算してマグニチュード0.1-2まで、全部で1282回検出されており、キーウから虐殺で有名になったブチャ、そして北部のコロステン、そしてかなり離れた北部の都市チェルニヒウまで分布している。
検出される爆発の程度もある程度は計算でき、例えばイスカンダルミサイル(TNT火薬相当で700Kg)は、マグニチュード1.7と計算されている。頻度の高い榴弾砲のレベルの爆発はTNTで7kg程度で完璧に捉えられる。
こうして記録した波を、実際の記録と照合して検証することも行なっている。例えば2月27日、有名なホストーメリ空港へのロシアの攻撃が数ヶ所の観測機でどう捉えられたのか、一つの爆発が、それぞれの計測でどのような時間差で現れるかが示され、イムで地上への攻撃をモニターできることを示している。
結果は以上で、これまでのような報道だけでなく、衛星画像に加えて、地震計や爆轟計は完全ではないが、ほぼリアルタイムで爆発の規模と音から、攻撃手段(例えば榴弾砲)まで特定できることから、今後重要な戦争記録手段として利用されると言える。
このような公開データが積み重なることで、当局による発表以外の事実に一般人も触れることができるのが21世紀の戦争と言える。ただ、このような客観的な記録は、現場にいる人間の恐怖や苦悩がすべて捨象されるので、恐ろしい記録とも言える。
2023年8月31日
この HP で何度も紹介しているように、膵臓ガンの特徴は極めて強い間質反応にあり、線維芽細胞が増加するとともに、コラーゲンを中心にマトリックスの過生産が起こり、組織は「硬い」とよく表現される。そして、この強い間質反応が、膵臓ガンの治療成績が30年間改善せず、極めて悪性のガンとされる理由の一つとなっている。
今日紹介するオーストラリアの創薬ベンチャー Pharmaxis と Garvan 医学研究所を中心とした国際チームからの論文は、間質を標的として細胞画のマトリックスを低下させる薬剤の開発についての論文で、8月28日 Nature Cancer にオンライン掲載された。タイトルは「A first-in-class pan-lysyl oxidase inhibitor impairs stromal remodeling and enhances gemcitabine response and survival in pancreatic cancer(新規の Panlysyl oxidase 阻害剤は膵臓ガンのストローマを再モデル化し、ゲニシタビンの効果を高め、生存期間を延長できる)」だ。
上に述べたように、膵臓ガンを抑制するために間質のマトリックス合成を抑えてみようと考えるのは当然の帰結で、コラーゲンやエラスチンの重合に関わる lysyl oxidase の機能阻害剤を用いる治療の開発が進められてきたが、明確な結論には至っていなかった。
この研究では、これまでの阻害剤が、4種類ある Lysyl oxicase(LOH) のうち一部しか阻害できないのが問題ではないかと考え、すべての LOH に効果がある薬剤 PXS-5505 を開発した。ラットを用いた薬剤動体や、副作用テストの結果は上々で、経口投与でガン組織に速やかに到達し、6ヶ月追跡で問題になる毒性は見られなかった。
LOH はガンが発現しているわけではなく、周りの間質組織が発現する。実際にこの分子がガン治療の標的になるのかを確認する意味で、ガン患者さんのデータベースから、ガン組織での LOH 発現量が高い人と低い人に分けて予後を調べると、高い人は明らかに生存率が低い。すなわち、ガンに直接効くわけではないが、ガン治療を補助する意味で、治療に使える可能性はある。
そこで、マウス膵臓ガンモデルを用いて、PXS-5505 の効果を調べている。このモデルでも、ガン組織の LOX は正常組織の10倍以上で、人間の膵臓ガンに近い。この組織でのコラーゲン沈着を試験管内で PXS-5505 が抑えられることを確認し、治療実験に進んでいる。
繰り返すが、PXS-5505 はガンに直接効くわけではないので、これを投与してもガン増殖に変化はないが、膵臓ガンでよく使われるゲムシタビン(gem)と組み合わせると、gem 単独より生存期間を伸ばすことができる。実際、PXS-5505 投与ではガン周囲の間質反応を抑えることに成功している。
最後に、ヒト膵臓ガンを脾臓に移植して、増殖や転移を調べる実験系を用いて、PXS-5505 は gem と併用することで、肝臓への転移を gem 単独より強く抑制できることを示している。
マウス膵臓ガンモデルで PXS-5505 を投与すると、それだけでガン組織への血流量が増加することも観察しており、これらの結果から、膵臓ガンの間質反応により薬剤のガンへの浸透が妨げられているので、gem の効果を高めていると考えられる。一方、免疫系細胞の浸潤については、残念ながら効果はあまりなく、免疫療法との併用が可能かは今後の課題になる。
結果は以上で、今後人間に使うことになるが、マウス実験から見ても根治につながるものではないが、間質を標的にした治療という意味で、期待したいと思っている。
2023年8月30日
抗原と結合する部位だけでなく、抗体の Fc 部分は様々な機能を持っている。補体を活性化して細胞を溶かすのもこの部分の機能だし、また何よりも抗体が他のタンパク質と比べて血中に存在できる期間が長いのも全て Fc 部分のおかげだ。ただ一方で、Fc 部分を認識する受容体の中にはリンパ球の機能を抑制する FcγRIIB 分子もあり、これがガン免疫を担う細胞で発現すると、抗体によるガン治療を抑制する可能性が指摘されてきた。ただ、ガンを攻撃するキラー細胞が FcγRIIB を発現するかどうかは議論が続いており、また PD-1 治療も問題なく行えているので、臨床的にはあまり問題ないと考えられてきた。
今日紹介する米国・エモリー大学からの論文は、人間の CD8キラー細胞の一部には FcγRIIB が発現しており、ガン免疫効果を低下させていることを示した研究で、8月23日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「FcγRIIB expressed on CD8 + T cells limits responsiveness to PD-1 checkpoint inhibition in cancer(CD8陽性T細胞が発現している FcγRIIB は PD-1 チェックポイント阻害ガン治療を抑制する)」だ。
この研究ではまず、FcγRIIBが割合は少ないが確かに末梢血の CD8 陽性細胞に発現していることを確認した後、ガン局所で様々な炎症性サイトカインを分泌する主要な細胞であることを明らかにしている。キラー活性で見ると、FcγRIIB 陽性も、陰性も同じような能力があるが、そこに強い炎症を誘導できるのは FcγRIIB 陽性細胞であること言う結論だ。もし炎症誘導がガン抑制に重要だとすると、治療抗体の Fc 部分により FcγRIIB が刺激され、ガン抑制効果が低下する可能性がある。
この可能性について、今度はマウスに移植したガンに対するチェックポイント治療実験を行い、FcγRIIB ノックアウトマウスではチェックポイント効果が高いこと、さらに PD-1 抗体を投与するときに、FcγRIIB の機能を阻害する抗体を投与すると、チェックポイント抗体の効果が高まることを明らかにしている。
実際には、ガンの種類を変えたり、FcγRIIB に対する抗体を変えたりして様々な実験を繰り返し、間違いなく FcγRIIB がチェックポイント治療効果にネガティブに働いていると結論している。
最終的には人間でも同じかは明確ではないが、チェックポイント治療を受けた人では FcγRIIB 細胞が減少することから、少なくとも使った抗体が FcγRIIB 陽性 CD8T 細胞の増殖を抑制していることは確かそうだ。
以上の結果から、チェックポイント治療に FcγRIIB 受容体に対する抗体を必ず組み合わせよと言うのは乱暴だろう。FcγRIIB と Fc との結合は交代のサブクラスによって違うので、これが正しいとすれば、今後は FcγRIIB 刺激性の低い Fc にして使用すればいいだろう。
臨床的には解決可能で重大な問題ではないが、いずれにせよ長年の問題には終止符が打たれた。
2023年8月29日
奄美のトゲネズミのようにY染色体がなくてもオス・メスの区別ができ、Y染色体なしで正常に性生殖が可能なので、Y染色体は将来滅亡する運命にあるというお話は、一般メディアによく取り上げられる話題だ。しかし、マウスY染色体の完全配列が決まり、Y染色体で独自に遺伝子増幅が進み、多様化していることがわかると(https://aasj.jp/news/watch/2485 )、消滅説のような単純な考えは完全に否定され、染色体の中でも最も多様性が高い染色体として様々な機能があるように思える。
考えてみると、人間の男らしさは多様で、しかも人種やY染色体のタイプとも相関が強い。要するに人間でもY染色体の完全ゲノムを解読し、その多様性の程度を調べることは、人間のY染色体の運命を知る意味で重要だ。しかし人ゲノムがほぼ完全に解読された今でも、Y染色体をテロメアからテロメアまで完全に解読することができていなかった。
これはY染色体には膨大な数の重複配列が存在するため、リピートを完全に読み切ることが難しいからだ。すなわち、現在一般に用いられる次世代シークエンサーでは読めるストレッチが短いため、リピート配列には歯が立たない。この問題を、single moleculeシークエンサーを組み合わせてようやく解決し、95%以上Y染色体ゲノムを解読した論文が8月23日 Nature にオンライン掲載された。
ただ、今日紹介したいのはこの論文ではなく、同じ時 Nature に Jakson研究所から発表された、43人のY染色体を single moleculeシークエンサーを合わせて、それぞれほぼ完全に解読、比較した以下の論文を紹介したい。この研究のポイントは、21種類のY染色体のタイプ(ハプログループ)を代表する43人を選んでいる点で、このハプログループの関係から、18万年前ホモサピエンスがまだアフリカで暮らしていた時以来の歴史を追いかけることができることだ。
このように、人類史とY染色体を重ね合わせた面白い研究なのだが、研究の真髄を味わおうとするとY染色体の場合、かなり専門的なゲノム知識が必要で、実はこの論文も紹介するのが極めて難しい。そこで、今日は論文に即して紹介するのをやめ、面白いと思ったポイントだけを紹介する。
まず、Y染色体はオープンな染色体構造(ユークロマチン)の中に、閉じたクロマチン(ヘテロクロマチン)が点在する前半部分と、完全にヘテロクロマチンだけの後半部分に分かれ、機能的遺伝子は前半にしか存在せず、後半は繰り返し配列からできている。
男性の多様性という目でこの染色体を見ると(勝手な見方をお許しあれ)、まず全体の長さがまちまちなのに驚くが、長さの違いは特に後半のヘテロクロマチン部分に集中している。
長さに大きな差はないが、前半のユークロマチン部分も多様性では負けていない。構造的変異、挿入欠失、そして単一塩基の違いを比べると、1Mbあたりそれぞれ、1.9個、165個、994個と驚くべき数だ。
この構造変化の中心は逆位で、その部分のゲノムの向きが逆さまになっている。こんなことが起こるのは、Y染色体には対立遺伝子が存在せず、組み替えでもとに戻ることがないためだ。ただ、人間の歴史の過程で固定してほとんどのハプログループに存在する逆位部分がある。詳しい説明は専門的になるので省くが、これは染色体の交換を抑制し、ゲノムを守る役割があると考えられる。
マウスの解析により、Y染色体上の遺伝子の中にはコピー数の大きな多様性がある遺伝子が示されているが、人間でもTSPY遺伝子は23個から39個までコピー数の多様性が見られる。
後半のヘテロクロマチン領域には機能的遺伝子はなく、ザクっと言うと171塩基配列を持つDYZ3と呼ばれる繰り返し配列に、170塩基からなる α繰り返し配列が組み合わさってできている。当然、長さも違うし、組み合わせも異なる大きな多様性が存在する。これは組み換えのないY染色体でも、繰り返し配列が存在すると遺伝子変換が起こりやすく、多様性の原因になる。
以上が私が勝手に選んだこの論文のポイントだが、読めば読むほどY染色体は多様化するようにできている。この多様化を見ると、遺伝子が存在しないから後半のヘテロクロマチン領域は消失する運命などと言えるはずがない。おそらく、この遺伝子のない多様化も、男性の多様性になんらかの役割をしていると言えないだろうか。
大谷選手や、世界陸上を見ていると、Y染色体がないと到達できない頂点があるように思える。おそらく人間が多様性を維持する限り、Y染色体による男性の多様性も維持されていくと思う。
2023年8月28日
昨日に続いて、ノンコーディングRNAが関わる論文を紹介する。フランクフルト大学からの論文で、なんと歳をとると心臓と神経系の連結が低下することを示し、それにマイクロRNAと呼ばれる翻訳制御に関わるRNAが関与することを示した研究だ。タイトルは「Aging impairs the neurovascular interface in the heart(老化は心臓の神経血管接点に大きく影響する)」で、8月27日号 Science に掲載された。
心臓には交感神経、副交感神経、そして感覚神経が投射しおり、痛みを感じたり、胸をときめかせたりしている。確かに歳を重ねると、胸のときめきはなくなっては来るが、心臓に分布する神経数が低下するとは思っても見なかった。しかし、副交感神経、交感神経ともに、活動が低下すると不整脈になることが知られていることから、神経支配の低下はときめかないでは済まない深刻な影響があるらしい。
この研究ではまず、老化マウスでは心臓に分布する神経数が左心室特異的に大きく低下していることを発見している。右心室では若者と比べて差はない。同じ心室でこれほどの差があるとは予想外の発見だ。しかも、三種類すべての神経で数が低下している。
この原因を遺伝子発現と組織学を組み合わせて追求し、老化マウスでは神経との接合を排除する semaphorin3(sema3) の血管内皮での発現が上昇していることを発見する。神経数の減少に sema3 が関わっていることを確認するため、内皮で sema3 を過剰発現させると、神経数は減少するし、逆にノックアウトすると心臓へ分布する神経数が上昇することも確認している。
ではなぜ老化により心室血管の sema3 が上昇するのか?このメカニズムを追求し、sema3 の遺伝子翻訳を低下させるマイクロRNA、miR143/145 の発現が老化により低下し、sema3 のタンパク質量が上昇してしまうこと、そして miR143/145 を低下させているのが、血管内皮の細胞老化であることを発見している。
残念ながらなぜ細胞老化により miR143/145 が低下するのか、また老化はあらゆる血管内皮で起こっていいのに、どうして心室血管特異的なのかといった問題については議論できていない。代わりに、以前紹介したことがある dasanitiv(広いスペクトラムのリン酸化阻害剤)と抗酸化のためのケルセチンを投与して老化した細胞を積極的に除去する処理を18ヶ月齢から始めると、miR143/145 の低下が抑えられ、結果神経分布の減少を抑えられること、そしてその結果、神経密度減少により誘発されると考えられる心臓の交感神経、副交感神経のバランスが正常化して不整脈の危険性が抑えられることを示している。
結果は以上で、なぜ左心室だけでこのメカニズムが働くのかについての説明がなくフラストレーションが残るが、しかし神経密度が半数になるというのは驚きの話だった。
2023年8月27日
無菌マウスは一般的に太らないことが知られており、細菌叢が我々のカロリー摂取を高めてくれていることがわかる。「なに!太らされるとは許せない」と考えられるかもしれないが、太るほど食べられる様になったのは最近のことで、人間が食うや食わずの時代には、細菌のおかげで栄養が摂取できていたと言える。実際、細菌叢は植物繊維を脂肪酸に変えてくれるし、腸上皮での脂肪摂取も高めてくれることが知られている。
今日紹介するテキサス・サウスウェスタン大学と中国・浙江大学からの共同論文は、細菌叢が脂肪代謝を高めるちょっと変わった毛色の存在を示唆する研究で、8月25日号 Science に掲載された。タイトルは「The gut microbiota reprograms intestinal lipid metabolism through long noncoding RNA Snhg9(腸内細菌叢は小腸の脂肪代謝を長鎖ノンコーディングRNAのSnhg9を介してプログラムし直す)」だ。
この研究は無菌マウスと通常のマウスの象徴上皮の遺伝子発現を比べるところから始まり、細菌叢が形成されることで発現が低下する遺伝子の中で Snhg9遺伝子がトップに来ることを発見する。
Snhg9 は、翻訳される遺伝子ではなく、長鎖ノンコーディングRNAと呼ばれる機能的RNAの一群に属している。ノンコーディングRNAはDNAからタンパク質まで様々な分子と反応して多様な機能を発揮することが知られているが、この研究ではタンパク質と結合するRNAではないかと仮説を立て、Snhg9 と結合するタンパク質を探索した結果、これまで細胞分裂や、細胞死に関わることが知られており、またヒストン脱アセチル酵素SIRT1の抑制因子として知られるCCAR2分子が見つかった。
生化学的研究、および Snhag9 を過剰発現する実験から、Snhg9 が CCAR2 と結合することで、CCAR2 と SIRT1 との結合が阻害され、結果 SIRT1 の活性が上昇することを明らかにした。SIRT1 は様々な分子のエピジェネティック制御因子だが、脂肪代謝のマスター分子と言える PPARγ を抑制することが知られており、Snhag9 の発現は、SIRT1 の活性をレスキューすることから、PPARγ の発現を抑えると予想される。結果は予想通りで、Snhag9発現により PPARγ発現が抑えられることを確認している。
さらに Snhag9発現により脂肪代謝の変化が起こるか、小腸の上皮で Snhag9 を過剰発現するトランスジェニックマウスを作成し、脂肪の吸収が抑えられるとともに、高脂肪食を摂取しても体重の増加や代謝異常が起こらないことを確認している。
以上、阻害分子の阻害の阻害といったわかりにくい話だが、無菌動物では Snhag9 の発現が上昇しているために、PPARγ の機能が抑えられ、脂肪代謝が低いレベルで維持されるという話になる。逆に、細菌叢が成立すると、Snhag9発現を抑えて、PPARγ の発現が上昇するため、脂肪代謝が上昇して、太ることになる。
最後に、細菌叢による上皮の Snhg9発現抑制メカニズムを探り、ホストと細菌叢の相互作用に関わる3型自然リンパ球が IL22 や IL23 を分泌して上皮を刺激することで、Snhg9 の発現が抑えられることを示している。
以上が結果で、面白い仕組みだが、実際に人間で存在するのかを、オルガノイド培養などを用いて確認する必要があるそして、なぜ無菌条件で Snhg9 がわざわざ発現して脂肪代謝を抑えている必要があるのか、この進化的理由がわからないと、この現象を完全に理解することはできない。