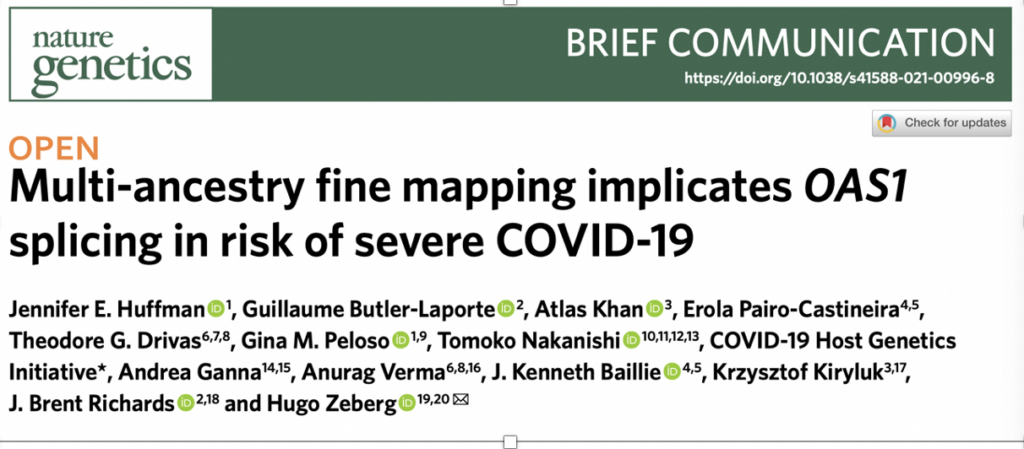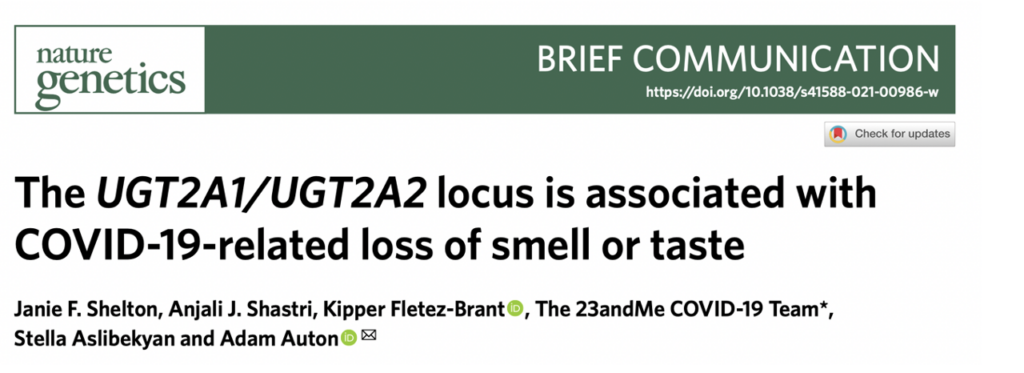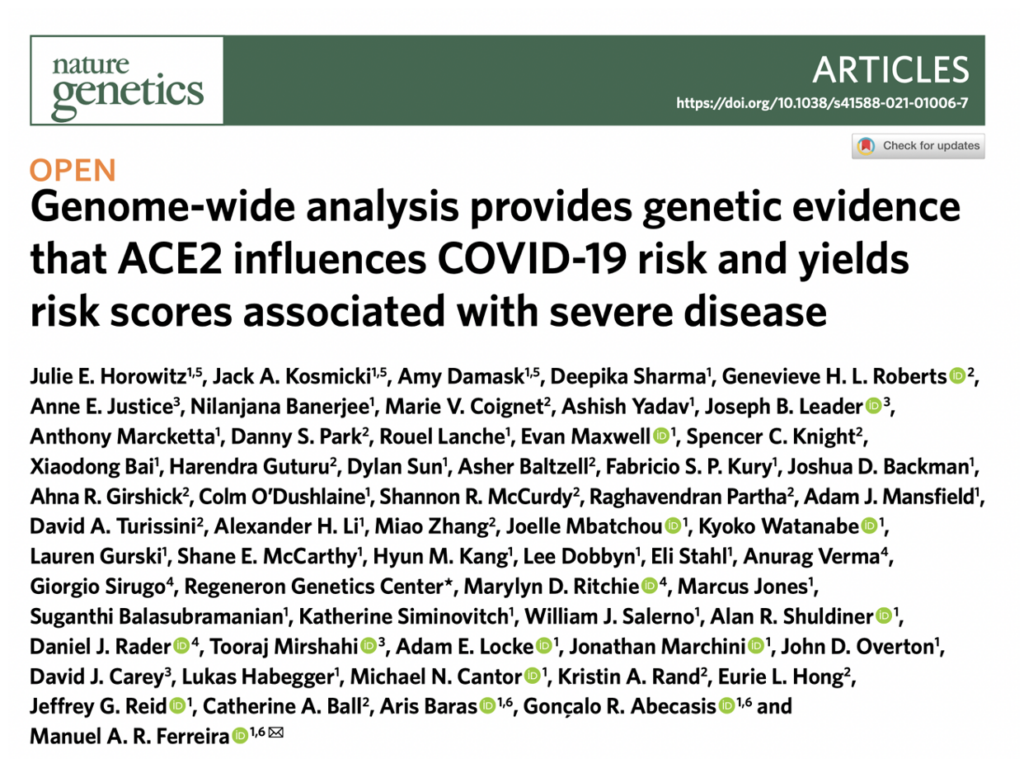2022年3月8日
アンギオテンシン変換酵素(ACE)は、アンギオテンシン(AT)Iを分解してATIIに変換し、血管の緊張性を上げ血圧を維持する機能を持っている。このATIIをさらに変換して、今度は血管をリラックスさせる作用を持つのがACE2で、今回のパンデミックでもっとポピュラーになった生体分子だろう。
このACEと血圧調節については、臨床でも揺るぐことのない事実で、今も多くの人が(私もだが)、ACE阻害剤や、ATIIが結合する受容体の阻害剤を高血圧治療として服用している。既に長期間のデータがあり、効果とともに安全性の高い薬剤と言えるのは、血圧のサーキット以外にACEが働いていないからだと思っていた。
ところが今日紹介するミネソタ大学からの論文は、なんとACE阻害剤が脳内麻薬として知られるエンケファリンを切断して、脳の報償系に作用しており、ACE阻害剤が報償回路に影響する可能性を示した驚くべき結果で、2月24日Scienceにオンライン掲載された。タイトルは「Angiotensin-converting enzyme gates brain circuit–specific plasticity via an endogenous opioid(アンギオテンシン変換酵素は脳内麻薬物質を介して脳の回路特異的可塑性の閾値を決める)」だ。
前脳に存在する側座核は基本的に抑制ニューロンからなるが、ドーパミン受容体を発現しており、ドーパミン報償回路の核となっていることが知られている。この研究では、ACEが側座核神経の中のドーパミン受容体1(D1R)を発現している神経に特異的に発現していることに着目し、この機能を調べる目的で、降圧剤として利用されているカプトプリルを脳スライスに転化すると、D1R発現細胞のみで、神経興奮が長期に抑制できることを観察した。すなわち、ACEが機能している。
この機能がATIからATIIへの変換ではないことを確認した上で、ACEが分解するペプチドを探索すると、脳内麻薬物質として知られるエンケファリンの一つ、MERFを切断する作用を持つことを発見する。さらに、D2Rを発現する側座核神経でこのMERFを強く発現していることも明らかにしている。
機能的実験から、カプトリルで処理するとMERFの切断が抑制されるため、細胞外のMERF濃度が上昇すること、ACEが抑制されるとMERFの刺激閾値が低下し、D1Rを発現する側座核神経の興奮が抑制されることが明らかになった。すなわち、ACE阻害は側座核での脳内麻薬物質を高め、D1R発現抑制ニューロンの興奮を抑えることが明らかになった。
最後に個体内でD1R発現細胞の興奮抑制効果を調べる目的でカプトリルの全身投与の脳機能への効果を調べると、
1)合成麻薬フェンタニルのうつ誘導作用効果が強く抑制される、
2)カプトリル自体は大きな行動変化を誘導することはない、
3)しかし社会性の上昇が見られ、μオピオイド報償回路の刺激が高まっている、
ことなどを明らかにしている。
以上、個体レベルでもACE阻害剤により、一見脳内麻薬が高まっている状態が生まれていることが示された。これを副作用というのか、うれしい効果というのかは人それぞれだろう。実際、うつ病の方がACE阻害剤を服用して、良くなったという報告はあるようだ。おそらく我々高齢者にとっては、良い効果の方が多いかもしれない。今はAT受容体阻害剤を服用しているので、次からACE阻害剤に変えてもいいなと思い出した。
2022年3月7日
完全に引退してしまっていると、論文を読むとき誰の仕事かあまり気にならないので、読んで面白いと思った後で著者の所属を見るようになってしまった。このような読み方をすると、どこの国から論文が出ているのか、不思議と当たることがある。
今日紹介する華東師範大学からの論文もそんな例で、読んでいる途中で中国からの論文だなというのがわかった。わかる理由は、研究の発想が変わっている点と、論文の書き方、そしてわかりにくい実験についての記述だ。論文のタイトルは「Local hyperthermia therapy induces browning of white fat and treats obesity(局所的高温治療により白色脂肪組織が褐色化し肥満が治る)」で、3月17日号のCellに掲載されている。
タイトルにあるように、白色脂肪細胞を部分的に熱にさらすと、白色脂肪組織が熱を発生する褐色脂肪組織に変わり、痩せられるという話だ。もともと、白色脂肪が低温にさらされると褐色化して熱を作るようになるという話は生理学的にも納得の話として広く受け入れられている。これに対して、この研究は逆張りを行って、熱を加えることで同じ効果が得られるかを考えている。
この発想はまさにユニークだが、中国伝統医学といえるお灸を考えると、ここで中国かなと思ってしまった。研究ではまず褐色脂肪細胞を41度で培養すると、発熱に関わる様々な遺伝子が誘導できる。
そこで生体でも同じことが起こるか調べるため、体内に注入でき、光を当てると発熱する分子を鼠蹊部に注入、それを41度に10分維持する実験を行い、本来発熱を起こさない白色脂肪組織が発熱することを確認する。人間の実験も行っている。おそらく皮膚の外から熱を鎖骨上部に20分照射すると、発熱が見られる。
最後に、慢性効果を調べるため、3日に一回、10分だけ41度に脂肪組織をさらす実験を行い、高脂肪食を食べても体重の増加を抑えることが出来、さらには血中グルコースも抑えられることを示している。
後はこの効果のメカニズムを調べ、
1)熱は予想通りheat shock factor、HSF1を誘導して、発熱や代謝を変化させる。
2)HSF1はメチル化RNAに結合するタンパク質Hnrnpa2b1を誘導する。
3)Hnrnpa2b1は、発熱に関わる分子のmRNAを安定化させることで、発熱を高める。
ことを明らかにしている。
以上が結果で、最後のメカニズムに至る研究は、新しい発見だと思う。
読んで誰もが考えるのが、ではサウナはどうかだが、このグループは否定的だ。というのも、身体全体のストレスを誘導することで、ノルアドレナリンなどが誘導され、痩せるのに役立たないと結論している。
では実際に何をすればいいのか。もう少しその点のアイデアを議論したらいいのだが、何の答えも提案していない。本当はこっそりやっているのかもしれないが。結局最初思いついたように、毎日お灸を据えるのが良さそうだ。
2022年3月6日
若い血液に触れると若返ることができるという話は、昔から存在する。おそらくドラキュラ伝説でも同じことだろう。ただ、この可能性は科学的にも追求されている。このHPでも、若い個体と老化した個体の血管をつないで、循環を共有させるパラビオーシスが細胞老化や若返りに及ぼす影響についての研究(https://aasj.jp/news/watch/1549 )、あるいは臍帯血注射により脳が若返る可能性を示した研究(https://aasj.jp/news/watch/6761 )、を紹介した。
これらの論文を読むときいつも思い浮かべるのは、細胞病理学を提唱したウィルヒョウと体液説を提唱したロキタンスキーの有名な論争だ。この時は近代的な細胞病理学が勝利し、ロキタンスキーは多くの人の記憶から消えてしまったが、老化研究を通してまさに復活している感がある。
これら紹介した論文は全てカリフォルニアにある大学から発表されているが、今日紹介する論文もスタンフォード大学からで、パラビオーシスの影響をsingle cell RNAseqを用いて詳しく調べた研究で、3月2日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Molecular hallmarks of heterochronic parabiosis at single-cell resolution(年齢が異なる個体のパラビオーシスの影響の分子指標を単一細胞レベルで調べる)」だ。
研究は単純で、3ヶ月令マウス同士、18ヶ月令マウス同士、そして3ヶ月/18ヶ月令マウスでパラビオーシスを行い、なんと5ヶ月循環を共有させた後、各臓器を取り出し、single cell RNAseq(scRNAseq)を用いて単一細胞レベルの遺伝子発現を調べ、パラビオーシスによる効果を調べている。
繰り返すが、研究自体は特に目新しいものではない。しかし、パラビオーシスの効果をscRNAseqで調べることで、細胞レベルの影響と、転写レベルの影響を分けて調べることで、極めて包括的に環境と老化の関係を明らかにすることが出来る。その意味でこの研究は、これから行うべき実験の方向性を示し、データを集め始めた最初の論文と言っていいだろう。パラビーシスだけで無く、senolysis、抗酸化剤など、様々なアンチエージング手法が研究されているので、将来的にはこれらを同じプラットフォームで比較することで、より大きなデータベースが完成すると思う。おそらくこのグループも、同じことを狙っていると思う。
さて結果は当然極めて膨大で、一言でまとめるのは難しい。主なポイントだけまとめておく。
1)老化血液と触れることで、若い細胞に老化によるのと同じ変化がおこる。また、若い血液に触れることで、老化細胞で一定の若返り効果が、転写レベルで見られる。
2)パラビオーシスに最も強く反応するのが肝臓細胞だが、血管内皮、間葉系幹細胞、血液幹細胞、免疫細胞などは老化、若返りともに影響を強く受ける。
3)遺伝子レベルで見ると、一番目立つのはミトコンドリアの電子伝達系の変化で、細胞レベルの変化に共通してみられ、老化とミトコンドリアの関係の重要性が確認される。ただ、他にも注目すべき遺伝子変化が、パラビオーシスによる老化促進、あるいは若返り現象として特定できるので、今後の重要な課題になる。
4)コラーゲン遺伝子発現の低下は老化に特徴的で、この結果間質により支持される細胞の変化が誘導される。
個人的に気になったのは以上の結果だが、循環する分子に、老化や若返りに関わる因子は必ず存在することを示すという点からは、極めてインパクトが大きい仕事だと思う。
若い血の秘密が、科学的に明らかにされれば、私たち高齢者も恩恵にあずかることが出来るようになるかもしれないが、現在のところ現象だけで、手がかりはまだまだという印象だ。
2022年3月5日
これだけ多くの人がCovid-19に感染すると、感染のしやすさ、重症化、様々な症状などについての遺伝子リスクを調べることで、最終的には病気のメカニズムを理解し、治療開発にまで結びつけることが出来る。このHPでもいくつか研究を紹介したが、最も驚いた論文は、Covid-19重症化や、感染抑制に関わるゲノムの一部がネアンデルタール人由来だったという、ドイツのペーボさん達からの論文だろう。このようなGWASと呼ばれるゲノム研究は、一回で終わるわけでは無く、多型と病気のメカニズムの理解に向けた目標に向かって常にアップデートされる。実際、対象となる人数が増えるにつれ、その精度は上昇していく。
昨日、Nature Geneticsのオンライン掲載論文に目を通していたら、なんとこのようなアップデート論文が3編も掲載されていたので、今日はまとめて紹介することにした。
まず最初のライプチヒ・マックスプランク進化人類学研究所からの論文は、ペーボさん達がコロナウイルス感染から我々を守る、ネアンデルタール人由来遺伝子として特定したrs10774671多型が、本当に感染防御に関わるのかを確かめるために行った、ゲノム研究だ。
以前の解析で見つかったrs10774671は、OAS1と呼ばれるポリアデニレース遺伝子とリンクしており、この分子の血中濃度が高いと、重症化率が低いことも確認されていた。しかし、ネアンデルタール人由来の遺伝子断片は75kbに及び、rs10774671が形質を決めていることを完全に証明するには至っていなかった。
そこでこの研究では、ネアンデルタール人の遺伝子が流入していないアフリカ人について調べ直し、rs10774671のG型変異がCovid-19感染リスクを減らす多型に間違いないことを明らかにしている。
次の論文は、ゲノム解析サービスの大手23&Meが、ゲノム解析が終わっている顧客に、ウェッブ上でアンケート調査を行い、Covid-19感染による味覚、嗅覚異常のリスク遺伝子を探索した研究だ。
この論文は、民間ゲノムサービスのパワーを感じさせる論文だが、100万人も顧客を抱えていると、ウェッブで聞くだけでなんと7万人近い感染者を特定でき、またそのうち68%が味覚嗅覚異常を訴えている。嗅覚異常の方が多いという状況でも、相関する多型を特定することが可能で、rs7688383多型と特定することに成功している。しかもこうして特定された多型がリンクしている遺伝子は臭い受容体に結合した脂溶物質を除去することに関わる、まさにドンピシャの分子UGT2Aだった。
結果は以上だが、この研究は、
1)感染ウイルス自体の作用で起こることが明瞭な嗅覚、味覚障害でも、起こりやすさというゲノムリスクが明確に存在する、
2)嗅覚受容体への持続的刺激が、ウイルスによる嗅覚障害を促進する新しい可能性があることを示し、嗅覚障害理解に重要な貢献をしたと思う。今後、神経後遺症などについても、詳しいゲノム解析を期待したい。
そして最後のリジェネロンからの論文は、これまで集まったゲノム解析を調べ直したまさにアップデートのためのメタアナリシスだ。リジェネロンは、最初の抗体薬を発売した会社だが、ゲノム解析も着々と進めている。
この研究の一つの目的は、これまでの研究を新しい目で見直し、感染や重症化リスクを算定するための指標を開発することで、最終的に相関が確認された多型を総合して多型を計算する方法を開発している。ただ、こうして得られるリスク変化は、重症化率で見て1.6倍(オッズ比)程度で、肥満や年齢などの臨床指標によるリスク上昇と比べると寄与率は低い。
もう一つの目的は、対象者の数の制限からこれまで特定できなかった多型を、多くの解析を集めることで新たに特定することで、この結果0.2%-2%の割合で存在する、発症を予防する多型rs190509934の特定に成功している。しかも、この多型は、ウイルス感染に必須のACE2の発現を決める多型で、これもドンピシャだ。
このように、感染のゲノム解析は、今後もアップデートされ、新しい可能性を開いてくれると思う。
2022年3月4日
アルツハイマー病は、世界的にも女性に多い病気で、おそらく発症数では男性の2倍以上ではないかと思う。この一つの原因として、閉経期に脳下垂体で合成されるゴナドトロピンの一つFSHの急上昇があるのではと疑われてきた。事実、閉経期に認知機能が一次的に低下することが知られている。
今日紹介するマウントサイナイ大学と深圳大学からの論文はこの考えを裏付け、FSHが直接神経細胞に働いて、アミロイドタンパク質や、Tauタンパク質を切断し沈殿させるメカニズムを促進することを示した研究で、新しいアルツハイマー病の治療開発の可能性を開くかもしれない。タイトルは「FSH blockade improves cognition in mice with Alzheimer’s disease(FSHを抑制することでマウスのアルツハイマー病を改善させることが出来る)」で、3月2日Natureにオンライン掲載された。
このグループは最初からFSHがアルツハイマー病(AD)を悪化させると決めて研究を行っている。そのため、血中FSHを中和する抗体を作成し、これを卵巣摘出で閉経期を再現したアミロイドβが沈殿しやすくしたマウスADモデルに投与している。
これまで知られているように、卵巣を摘出すると、FSHが上昇し、それとともに沈殿型アミロイドβやTauが脳内に検出される。ところが、FSH抗体を投与したマウスではアミロイドやTauの沈殿は見られない。
このメカニズムを探ると、FSHが神経細胞のFSD受容体を刺激して、アミロイドやTauを切断して沈殿させるδシクレターゼを誘導することが原因であることを特定している。実際、このペプチダーゼをノックアウトすると、ADの進行は抑えられる。
もちろんFSHは男性でも分泌されているので、オスのADモデルマウスに長期間FSHに対する抗体を投与し続けると、認知機能の低下が防がれ、アミロイドの集積は見られない。
後は様々なノックアウトマウスを用いて、FSH、 FSHR,、C/EBPβ、δsecretase、アミロイドβ、Tau沈殿という経路が実際に働いているかを確認しているが割愛していいだろう。ともかく、FSHは急性的にも慢性的にも、神経に直接働いて、アミロイドβやTauの沈殿を促進している。
これらの結果は全てマウスでの結果で、人間でも同じことが言えるのか、今後の研究が必要だが、FSHが少なくともADを悪化させるのだとすると、これを抑える治療はADの新しい治療法へと発展できるのではと期待できる。
2022年3月3日
現在乳ガンの治療は、手術前の化学療法や放射線療法のようなネオアジュバント治療に加えて、手術後も患者さんに恨まれるぐらいの徹底したアジュバント治療を行う。これによって、術後10年ぐらいして急に転移が見つかるという不幸をかなり減らすことが出来る。
しかし今でもネオアジュバントや徹底的なアジュバント治療が行われる前の、あるいは受けられなかった患者さんの中から、転移が見つかるケースは多い。幸い、乳ガンに関しては分子標的薬が充実しており、遺伝子を調べながらこれを組みあわせる治療で、転移ガンにも対応することが出来るが、完全ではない。
そこで登場するのが免疫治療だが、ガンに対する免疫反応が高くないとしてチェックポイント治療などは標準治療から外れているし、固形ガンなのでCAR-T治療もまだ開発できていない。代わりに、2-3割の乳ガンで発現が見られるHer2に対する抗体治療が行われ、化学療法との併用なので一定の効果が見られているが、決定的とはなり得ていない。
これに対し抗体治療とT細胞治療をまとめてやろうとする、片方はHer2、片方はT細胞を刺激するCD3を認識する抗体を用いて、ガンとT細胞の相互作用を高めてやろうとする治療が開発され、乳ガンだけで無く、数多くの治験が進められている。
今日紹介する大手製薬会社Sanofiのボストンにある研究所からの論文は、このbispecificな抗体を、さらにT細胞の共刺激に関わるCD28も認識するtrispecific抗体に変えて、乳ガン治療に使えないか調べた前臨床実験で2月26日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「A trispecific antibody targeting HER2 and T cells inhibits breast cancer growth via CD4 cells( Her2とT細胞刺激分子を認識するtrispecific抗体は主にCD4T細胞を介して乳ガンの増殖を止める)」だ。
この抗体は、Her2とCD3に対するbispecific抗体のCD3に結合する側に、さらにCD28とも結合できる領域を組みあわせるもので、設計を見ていると、様々な可能性を試して最終的に行き着いたという構造になっている。
まず試験管内でテストすると、bispecific抗体と比べてT細胞の活性化作用はつよく、ガンに対するキラー活性も優れている。
この研究で一番驚いた結果は、免疫系が存在しないマウスに、人の乳ガンとともに、ヒトのT細胞を移植して、抗体のキラー活性を調べる実験で、驚くなからCD8陽性のキラー細胞を移植してもガンの増殖をほとんど抑えられていない一方で、CD4陽性T細胞を移植した場合には、ガン増殖が完全に抑制された。
さらに、ガンの方の反応を見てみると、CD4陽性細胞とtrispecific抗体を投与したマウスでは、ガンの細胞周期がG0/G1で停止していることも明らかになっている。
これが乳ガン特異的な話なのか、trispecific抗体特有の話なのか、一般的な話なのか、今後重要な問題になるが、CD4陽性細胞による免疫性炎症の重要性をつよく示す結果だと思う。
最後はサルを用いた安全性試験の結果で、基本的には100㎍/kg投与でもサイトカインストームなどは起こさず安全に使えることを示している。
以上が結果で、乳ガンにも免疫治療を使えるようにするための開発が着々とするんでいることがわかる。気になるとすると、これほど複雑な抗体になるとどうしても血中半減期が短くなっている点で、これが次の課題になるような気がする。いずれにせよ、T細胞とガンを強制的に相互作用させる抗体治療はCAR-Tまで置き換える勢いで進んでいる。
2022年3月2日
我が国の状況は把握していないが、世界規模で見るとメトフォルミンは現在2型糖尿病に対して最も広く処方されている薬だ。腸上皮細胞のGLP-1を誘導してインシュリン分泌を促し、肥満による炎症を抑えインシュリン抵抗性を防ぎ、肝臓の脂肪合成を抑え、さらには代謝を改善して寿命まで延ばしてしまう。これで500mgの錠剤が20円程度となると、夢の薬と言っていい。
AASJでも、この夢の効果の背景についてYouTubeで解説した(https://www.youtube.com/watch?v=FBBh8JsJguQ )。そして、この作用の多くの部分はAMP-activated protein kinase(AMPK)の持つ多様な作用を介しており、AMPKはミトコンドリアの呼吸複合体の中のcomplex1がメトフォルミンに阻害されることで、AMP濃度が上昇して活性化されると解説した。
ところが今日紹介する中国厦門大学からの論文は、complex1を阻害する経路は高いメトフォルミン濃度により誘導される経路で、実際の服用量で到達するメトフォルミン濃度では、この経路では無くリソゾーム膜上のvATPaseを介する系でAMPKが活性化されることを示した、本当なら、通説を変える重要な貢献だ。タイトルは「Low-dose metformin targets the lysosomal AMPK pathway through PEN2(低容量のメトフォルミンはリソゾーム上のAMPK経路をPEN2を介して調節する)」だ。
元々この研究グループは、細胞内のグルコースが低下したときAMPKが活性化される過程を研究しており、この延長でメトフォルミンがこの経路にも影響がないか調べていたのだと思う。
ただ結果は予想以上で、細胞内のメトフォルミン濃度が40μM程度では、彼らが期待したとおり、リソゾーム上のv-ATPaseを阻害して、リソゾームが酸性になるのを抑えるとともに、AMPKを活性化する。しかも、AMPレベルは変化していないので、ミトコンドリアを介さずに、メトフォルミンがAMPK活性化を誘導することが出来ることが明らかになった。
この新しいメトフォルミン作用経路を探るため、UV照射でタンパク質と共有結合するメトフォルミンを開発し、メトフォルミン結合タンパク質を特定し、その一つ一つをRNAiによりノックダウンしてメトフォルミン作用が変化するかを調べたところ、PEN2分子をノックダウンしたときだけメトフォルミンによるAMPK活性化が起こらないことを発見する。またPEN2が期待通りリソゾームに局在する分子であることを確認している。さらにPEN2のリソゾーム局在を阻害すると、メトフォルミンの作用は失われるので、メトフォルミンの作用はリソゾーム上でvATPaseを阻害することを介することがわかる。
次にPEN2に結合してメトフォルミンの作用をv-ATPase阻害へと媒介する分子を探索した結果、最終的にATP6AP1分子が特定された。PEN2結合タンパク質は全部で123種類同定されているが、その中でv-ATPaseに直接関わるのはこの分子だけで、通常v-ATPaseのコンポーネントとしてAMPK活性化阻害に関わっているが、PEN2と直接結合することで、v-ATPaseの機能が阻害され、結果AMPK活性化に関わることが示された。
最後に、低い濃度でもメトフォルミンの様々な生体作用が得られること、またこれらはPEN2ノックアウトで消失することなどを示して、低濃度のメトフォルミンで、一部のAMPKを活性化することで、メトフォルミンの重要な機能が十分達成できると結論している。
メトフォルミンの作用をもう一度見直す必要性が示された重要な研究だと思う。
2022年3月1日
免疫チェックポイント治療(ICT)は、ガン抗原特異的な治療ではないが、ガン特異的な抗原に対する免疫反応が存在し、ガンを征圧できることを明らかにした。当然、次の一手はガンのネオ抗原を明らかにし、ガンと戦うT細胞を特定することだ。
ガンのネオ抗原については、ゲノムからガン特異的な変異を特定し、これを抗原として患者さんを免役する治療がメインになると思うが、mRNAワクチンを開発するビオンテックやモデルナに今回巨額の資金が環流したことから、今後の大きな伸展が予測できる。
これに対し、ガン抗原特異的なT細胞を特定することは、簡単でない。ガン細胞と患者さんのT細胞を反応させて、増殖してきた細胞のT細胞受容体(TcR)を含めた様々な性質を調べるのが確実な方法だが、実験室はともかく、臨床応用となるとハードルは高い。
もちろんガン抗原が特定された場合は、患者さんのMHCにペプチドをロードする方法でガン特異的T細胞を特定できるが、これも実際の臨床応用を考えると、現時点ではハードルが高い。
今日紹介する、ガン組織に浸潤するT細胞(TIL)を用いた治療に執念を燃やしている米国NIH Rosenberg研究室からの論文は、転移ガン局所のTILを様々な観点から詳しく解析し、ガンに対して反応している細胞の性質を特定し、これからガン特異的T細胞を特定しようとした研究で、2月25日号Scienceに掲載された。タイトルは「Molecular signatures of antitumor neoantigenreactive T cells from metastatic human cancers(ヒト転移ガン組織から得られたネオ抗原特異的T細胞の分子的特性)」だ。
この研究では、TILに焦点を絞ってsingle cell RNAseq(scRNAseq)を実施し、まず11種類のクラスター(C1からC11)に分解している。次に、RNAseq配列からそれぞれのT細胞と対応させ、まず抗原特異的増殖により分裂しクローン増殖の痕跡を持つT細胞を探し、主に3つの分画にのみクローン増殖が見られることを確認する。
もちろんクローン性増殖が見られるTcRだとしても、ガン特異的ではない。そこで、患者さんの末梢血で同じようにクローン性増殖が見られるTcRを特定し、TILと比べることで、1)クローン性増殖が見られ、2)TILのみに存在するTcRをガン特異的ととりあえず考えて、どの分画にこれが存在するかを確かめると、CD8T細胞もCD4T細胞も、分化が進んで機能が低下した分画(実際にはそれぞれ11種類のうちのC6、C1分画に濃縮されていることを発見する。一方、末梢血にも存在するクローン増殖を示すTcRはメモリーなどに対応している。もちろんこの中にも、ガン特異的TcRも含まれているが、感染などに反応するT細胞や、バイスタンダーT細胞と区別することは難しい。
一方、TILだけに存在するTcRクローンは、ガン抗原との持続的な相互作用により、分化が進み疲弊しているため、機能的にはICTで再活性化しない限り抗ガン活性は失われているが、ガン特異的TcRを特定する目的には役に立つ。即ち、ガン組織が得られた場合、C6、C1分画を調べれば、ガン特異的TcRを特定できる可能性が高い。
そこで実際にこの戦略でガン抗原特異的TcRを特定できるか検証するため、新しいガン組織を解析し、ガン特異的と推定したTcRを持つT細胞を再構成し、ガンに対する反応を調べると、CD8T細胞では60%が、CD8T細胞では30%が患者さんのガン細胞に反応することが確認された。
以上が主な結果で、ガン特異的なTcRを特定する信頼できる方法を探そうとするRosenbergの執念が伝わる力作で、TILを用いるガン治療とともに、TILの新しい利用法だと期待している。
2022年2月28日
論文ウォッチを始めて早10年近く、細菌叢についての実に様々な論文を紹介してきた。おそらくこのトピックスは、論文ウォッチで扱われたトピックスの中ではトップ3に入るのではと思う。しかし、肺の細菌叢について紹介したことは一度もなかった。
今日紹介するドイツ・ゲッティンゲン大学からの論文は、肺の細菌叢を、ネオマイシンの気管注入で変化させると、タイプ1インターフェロンを誘導するLPSの量が増え、脳内のミクログリアが変化し自己免疫反応が低下するという、なんとも不思議な現象を示した研究で、2月23日Natureにオンライン掲載されている。タイトルは「The lung microbiome regulates brain autoimmunity(肺細菌叢が脳の自己免疫を調節する)」だ。
この研究は、マウス気管にネオマイシンを注入することから始まっている。まずネオマイシンというのが珍しい。同じアミノグリコシル系を用いるなら他の薬剤もあるのにと思ってしまう。さらに、このような抗生物質で細菌叢処理をする場合、細菌叢を除去することを目的にするのが普通なのだが、この研を究では、dysbiosisと呼ばれる通常とは異なる細菌構成を誘導することが、目的になっている。
このような変わった実験条件で行われているのだが、驚くなかれ、気管にネオマイシンを投与すると、自己免疫性の脳炎が著しく改善するという結果が得られる。まず、なぜ改善が見られるのかを調べていくと、自己抗原に対する免疫反応の誘導や維持が影響されるのではなく、肺の細菌叢が変化することで、脳内のミクログリアが局所の自己免疫反応を維持できないタイプに変化してしまうことで、脳炎が抑えられていることが明らかになった。
脳内の自己免疫性炎症が維持されるためには、ミクログリアが必要であることはこれまでもわかっていた。この研究でも、脳内のミクログリアを除去すると、ネオマイシンの気管注入と同じ効果があることも示している。ただ、肺細菌叢の変化だけでは、ミクログリアの数は変化しない。かわりに、自己免疫性炎症に必要なtype IIインターフェロン刺激による分子発現が消失し、type Iインターフェロンの刺激を受けたタイプに変化してしまっている。即ち、肺の細菌叢の変化により、ミクログリアがtype Iインターフェロン刺激優位になることで、ミクログリアの自己免疫性炎症を支持する機能が失われるという、不思議な現象が起こっている。
この考えを支持するように、肺細菌叢で起こっているdysbiosisを調べてみると、type1インターフェロンを誘導するLPSを発現する細菌の数が2.5倍に増え、血中のLPSも上昇している。結局、dysbiosisと言った間接的要因ではなく、LPSが存在すればよいことになるが、実際LPSを発現する細菌を不活化して気管投与しても、同じようにミクログリアの変化を誘導し、自己免疫性脳炎を抑えることが出来る。
以上が結果で、もう一度まとめると、気管にネオマイシンを注入すると、LPSを発現する細菌種が気管で増え、このLPSは脳内でTLR3を介してtype1インターフェロンを脳内で誘導し、この結果ミクログリアが変化して、自己免疫性炎症の維持が出来ず、脳炎が治まるというシナリオになる。
全部読み通した後で考えてみると、最終的には肺の細菌叢を変化させるという迂遠なことはやめて、脳内に直接LPSや1型インターフェロンを投与すればよいことになる。しかし、炎症を抑えるのに、別のタイプの炎症を誘導するという、毒をもって毒を制する方法が、実際の臨床現場で受け入れられるのは簡単でないように感じる。
2022年2月27日
ニキビは青春の思い出で、そのときは仕方がないものと考えていたが、実際にはれっきとした感染症で、基本はニキビ菌と言っていいのかCutibacterium acnes感染を中心とする細菌叢による感染症で、ニキビ菌に対する私たちの炎症反応が、毛根という場所により修飾された特殊な組織反応を引き起こす。従って、治療の基本は殺菌が中心になるが、最近ではレチノイドを利用して、組織反応を抑える治療も行われるようになっている。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校皮膚科からの論文は、バイオプシー下、ニキビ組織をsingle cell RNAseq(scRNAseq)を用いて詳しく解析し、ニキビ組織の成立メカニズムを明らかにするとともに、それに基づいてマウス皮膚ニキビモデルでメカニズムの検証を行った研究で2月16日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Antimicrobial production by perifollicular dermal preadipocytes is essential to the pathophysiology of acne(毛根周囲の前脂肪細胞による抗菌反応がニキビの病態生理成立に必須の条件)」だ。
この研究ではニキビという特殊な病理像を決めているのは線維芽細胞だと決めて、毛根周囲組織細胞からPDGFRα陽性の線維芽細胞を分離。それについてscRNAseq解析を行っている。線維芽細胞と言っても多様で、正常で5種類の違ったポピュレーションが存在する。そして、ニキビが発症すると、F1とF3集団が上昇していることがわかった。
遺伝子発現を手がかりに他の集団と関係づけて、F1、F3がどのような細胞かを特定すると、レプチン受容体を強く発現した未熟線維芽細胞といえるF0集団が、より分化したF2集団を通って、最終的に成熟した線維芽細胞に落ち着く経路に対し、炎症刺激が強く加わることで、様々な炎症性分子を発現するとともに、レプチンを介した前脂肪細胞分化の様相が合わさったのが、F3からF1への経路であることが特定された。即ち、ニキビでは細菌刺激により、炎症とともに前脂肪細胞への強いドライブがかかった特殊な病態が成立していることがわかった。
重要なのは、このニキビの経路ではcathelicidinなどの抗菌物質の発現が強く見られる点で、すなわち自然の抗菌作用がこの経路で発揮されていることがわかる。しかし、脂肪細胞への分化が誘導される結果、分泌された脂肪自体は菌の増殖を助けるだろう。悩ましいニキビは、この除菌と助菌の微妙なバランスにあるからかもしれない。
さすがニキビといえども、ニキビ菌の感染実験は難しいので、ここからはマウスモデルを用いて実験を進めている。そして、マウスでもニキビ菌感染によって前脂肪細胞分化への強いドライブがかかることを確認している。またscRNAseqで、ニキビ菌感染により人間のニキビ組織と同じように脂肪細胞分化と、炎症反応が合わさった細胞プロファイルが優勢になることを確認している。
あとはニキビ菌に対する反応の誘導経路についてだが、線維芽細胞の培養システムで、TLR2の刺激により炎症反応とともに、前脂肪細胞への分化も誘導される可能性を示している。
最後に、ニキビになぜレチノイドが効果を示すのか、マウスにニキビ菌を感染させるニキビモデルで調べ、転写レベルで抗菌物質の発現を高める一方、脂肪細胞への分化を阻害することがわかった。即ち、除菌と助菌の競合状態を、除菌だけの状態へと戻すことが、レチノイドの効果であることを明らかにした。
驚くという研究ではないが、ニキビも研究すると奥が深い。