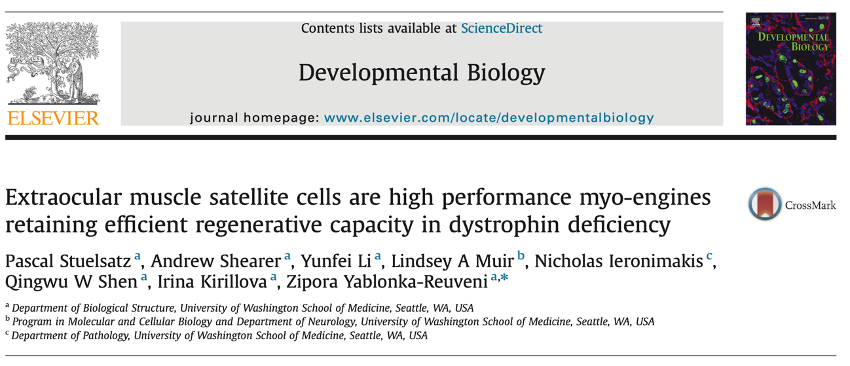2023年3月14日
細胞の増殖に関わる分子の変異が、ガンのドライバーや抑制に働くことは容易に理解できても、例えばTCAサイクルの様な基本的な代謝経路に関わる酵素の変異がガンへと発展するメカニズムは理解が難しい。
最も知られた例がグリオーマとIDHで、TCAサイクルの基本酵素の変異により生成する2HGと呼ばれる分子が様々なメチル化反応を阻害することにより、転写のプログラムが狂い、ガンになること明らかにされている。すなわちTCAサイクルでも、単純なエネルギー産生ではなく、それに関わる様々な分子の合成経路が狂うことで、ガンの発生しやすい状況が生まれることが示される。
今日紹介するケンブリッジ大学からの論文も、TCAサイクルのフマル酸からリンゴ酸へと転換する酵素fumarate hydratase(FH)がなぜ悪性の腎臓ガンの原因になるのか、そのメカニズムを調べた研究で、3月8日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Fumarate induces vesicular release of mtDNA to drive innate immunity(フマル酸がミトコンドリアDNAの小胞体輸送を誘導して自然免疫を駆動する)」だ。
おそらくこのグループはFH変異と腎臓ガンや平滑筋腫発生の関係を長く研究していたのだろう。腎臓でタモキシフェン注射でFHが欠損するマウスを作成し、FH欠損の効果を調べたところ、細胞の増殖や代謝に大きな変化が起こるわけではないが、自然免疫に関わる分子の発現が腎臓細胞で起こることを発見する。
様々なガンで、炎症の役割が示唆されており、この結果はFH欠損による腎臓での炎症がガンを誘発する原因である可能性を示唆している。このシナリオを確認するため、まずFH欠損が自然炎症を誘発するメカニズムを探っている。
この結果、FH欠損により細胞内のフマル酸が上昇するだけで、ミトコンドリアからDNAが漏れ出し、これが細胞内核酸センサーを刺激し、TBK1-IRF3経路が刺激されることがわかった。事実、細胞膜を通過できるフマル酸を添加するだけで腎臓上皮細胞の自然免疫が誘導される。
最後に、フマル酸蓄積がミトコンドリアDNA流出を誘導するメカニズムを探り、ミトコンドリア形態の変化などを考慮しながら、最終的にフマル酸がミトコンドリアからの小胞体形成、遊離を誘導し、この中に含まれるDNAがRIG-1やcGASと言った核酸センサーにキャッチされ、自然免疫を誘導することがわかる。
以上の結果は、FHが腎臓ガンの促進因子になる原因は、慢性の炎症および、おそらく細胞死の促進が組み合わさった結果であると考えられる。当然、他の原因による腎臓ガンでも、この経路が阻害されることでより悪性になることが予想される。
しかし、代謝経路と単純にまとめることの間違いを、IDHやFHの例は教えてくれる。勉強になった。
2023年3月13日
昨年6月クリスパー/Casを用いて網羅的に遺伝子ノックアウトを行った細胞での転写の変化をsingle cell RNA sequencingを用いて調べるPerturb Sequencingについて述べたカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文を紹介し(https://aasj.jp/news/watch/19994 )、さらにクリスパーとsingle cell sequencingが合体したまさに現代を代表するテクノロジーなのでYouTubeでも解説した(https://www.youtube.com/watch?v=-Yddv5xuPC8 )。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、この技術にマイクロ流体コントロール(マイクロフルイディックス)技術を合体させ、single cellテクノロジーと本来的に相性が悪い細胞間相互作用を研究できる様にし、多発性硬化症の炎症を抑える回路を明らかにした研究で、3月10日号 Science に掲載された。タイトルは「Droplet-based forward genetic screening of astrocyte–microglia cross-talk(液滴培養を用いたアストロサイトとミクログリア相互作用の遺伝的スクリーニング)」だ。
細胞相互作用を調べるためには、少なくとも2種類の細胞が同時に存在する実験系が必要になる。この研究では、マイクロフルイディクスを用いて単一のアストロサイトとミクログリアを一つの液滴の中に閉じ込める方法の条件を至適化して、2−3日間細胞培養が出来る様にし、単一細胞同士の相互作用を、そのままtwo cell mRNA sequencingで調べられる様にしている。
次に、アストロサイトにNFkBレポーターを導入、一方ミクログリアに遺伝子ノックアウト・クリスパーライブラリーを導入、それぞれを一つの液滴に閉じ込め、アストロサイトのNFkB誘導に関わる分子を探索し、4種類のミクログリア分泌分子と、それに対応する4種類の受容体が、アストロサイトの炎症反応を抑えることを発見する。
この研究では4種類のシグナルの内、Amphiregulin分子(Areg)と、その受容体EGFRに焦点を絞り、多発性硬化症モデルでAreg発現を抑えるレトロウイルスベクターを脳に注射する実験を行い、Areg発現が脳で抑制されると、炎症が高まることを明らかにしている。
一方で、アストロサイトとミクログリアが閉じ込められた液滴培養の遺伝子解析から、Aregの発現を高めるアストロサイト因子がIL33であることも明らかにしている。
主な結果は以上で、細胞間相互作用の研究をsingle cell同士のレベルで行い、その結果を網羅的に遺伝子発現として把握するこの系は、まだまだ完全でない細胞間相互作用の研究を前進させる様な気がする。しかし、続々実現する新しいテクノロジーが、合体することでより高いテクノロジーへと発展するのを見ると、我が国の科学が元気になるためには、このような新しいイノベーションにチャレンジする若手研究者が出てくることが必要だと思う。
2023年3月12日
昨日はガンのネオ抗原についての研究を紹介したが、なぜネオ抗原研究が重要かというと、ガンの免疫を完全にコントロールするためには、免疫系が反応してガンを殺せる抗原を患者さんごとに把握し、100%の免疫治療を実現するためだ。同じように、いつかは100%のガン免疫治療を実現できると期待できるのが、特定のガンが共通に発現する抗原を認識する抗体をT細胞受容体 (TcR) につないだCAR-Tだ。
CAR-Tが期待される最大の理由は、抗原から反応に至るまで、最終的には完全にコントロール可能な免疫療法を可能にするからだ。ただ、固形ガンに利用できるCAR-Tが開発できていないだけでなく、効果がはっきりするB細胞白血病でも100%のガン免疫治療にはほど遠いのが現状だ。
そのため100%を目指して、抗原受容体に結合させるシグナルを見直す動きが加速しており、その例がずいぶん前に紹介したSynNotchシステム(https://aasj.jp/news/watch/5863 )で、これが固形ガンもカバーできる可能性を持つことも最近紹介した(https://aasj.jp/news/watch/21145 )。
これに対して、今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、ほとんどのCAR-Tシステムに使われている CD3ζ部分を完全に見直すことで、高い効果のみならず高い安全性も実現するCAR-Tが可能であることを示した研究で、3月8日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Co-opting signaling molecules enables logic-gated control of CAR-T cells(シグナル分子を利用することでCAR-Tをコントロールする論理回路が実現する)」だ。
この研究の目的は、ガン特異性を保証するために、2種類の抗原が存在する細胞のみに反応出来るCAR-Tを開発することだ。タイトルの論理回路というのは、コンピュータープログラムでおなじみの、A and B to goといった、AとBが存在すればオンという回路のことで、ガン表面上の二つの抗原を検知したときのみ殺すCAR-Tになる。
このために、CD3ζシグナルと共刺激シグナルを分離する方法や、SynNotchシステムが開発されたが、まだまだ完全ではないと考え、この研究では抗原受容体の下流を完全に見直すことから始めている。
その結果、CD3ζと結合するZap70の下流シグナルのみで、試験管内のみならず、マウスへのガン移植系でも大きな効果があることを示している。圧巻は現在最もよく使われているCD3ζCAR-Tと比べた実験で、試験管内では大きな差を認めないものの、移植ガンのキラー活性でみると大きな差があることがわかった。
ただ、これは一個の抗原でオンになる回路で、2個の抗原で初めてオンになる回路を形成するには、Zap70のさらに下流のシグナルを用いる必要がある。Zap70はLAT分子とSLP76分子を会合させこれによりPLCγシグナルを活性化することがわかっているので、今度はZap70を用いる代わりに、CD19に対する抗体にはLAT分子、もう一つのHER2抗原に対する抗体にはSLP-76分子を結合させ、二つの分子が会合したときだけT細胞活性がオンになるように細胞を設計すると、両方の抗原が存在するときのみ反応するCAR-Tが出来るのだが、一つの抗原にもある程度反応し、副作用の原因になる。
この抗原が揃わなくても一定の刺激がオンになる原因を、両方の分子がGADS分子により橋渡しされるからだと考え、LAT及びSLP-76からGADS結合部分を除いてCAR-Tを設計し、
1)2つの抗原が揃ったときのみ活性化されること、
2)これまで開発されたAND型論理回路のCAR-Tと比べても高いガンキラー活性を示すこと、
をしめし、ついにAND回路で動くCAR-Tが完成したと結論している。
今後固形ガンなどにも効果があるかなどが検討されると思うが、ここまで徹底的にシグナルを見直すグループが存在していることは、CAR-T分野の競争が激烈化していることを覗わせる。
2023年3月11日
昨年11月、「究極のテーラーメイドがん治療」(https://aasj.jp/news/watch/20969 )というタイトルで、ガンのネオ抗原に対するT細胞受容体を遺伝子クローニングし、それを正常細胞にCRISPRで導入して、がん治療に用いる治験研究を紹介した。まだまだ画期的な結果には至っていないが、ついにここまでできるようになったのかと印象深かった。
今日紹介するカリフォルニア大学ロサンジェルス校からの論文は、この論文とほぼ同じ方法を、治療ではなくチェックポイント治療での免疫反応の解析に用い、ガンに対する免疫反応を把握するという点では、労を厭わず徹底的に行われた研究で、3月2日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Neoantigen-targeted CD8 + T cell responses with PD-1 blockade therapy(PD-1阻害治療でのネオ抗原に対するCD8T細胞の反応)」だ。
この研究ではPD-1抗体を中心に、場合によっては他の方法も加えた治療を受けておられる転移性悪性黒色腫11名について、治療効果と、末梢血および腫瘍組織に存在するネオ抗原特異的T細胞の数や動態との関係を調べている。
このような研究はこれまでも行われているが、ネオ抗原特異的T細胞の抗原受容体を再構成し、機能を確かめたクローンを特定して、治療効果と対応させようとしている点が大きく違っている。具体的には各患者さんについて、
ガンのエクソーム検査及び、遺伝子発現検査から、ネオ抗原として働いてそうな変異を特定。
変異を含むペプチド部分が、MHCとβマイクルグロブリンと合体した遺伝子を293細胞株に導入、この細胞が分泌するネオ抗原ペプチド/MHC/βミクログロブリンライブラリーを回収。
これを蛍光とバーコードで標識して患者さんのガン組織リンパ球や末梢血と反応させる。
反応するT細胞を分離、バーコードから反応するネオ抗原を特定するとともに、抗原受容体を遺伝子クローニング。
この抗原受容体を正常細胞の受容体とCRISPRを用いて置き換え、ガンやネオ抗原に対する反応を調べる。
この過程を通して、確かにガンと反応していると考えられるT細胞受容体の、ガン組織や末梢血での出現を調べている。
PD-1治療に反応した3名の患者さんでは、複数のネオ抗原に対する抗原受容体の出現が何度も検出できる。また、一つのネオ抗原に対しても異なる抗原受容体が反応している。
ガン組織で検出できる抗原受容体と、末梢血での抗原受容体とは必ずしも一致しないが、サンプル量が少ないことを考えると、実際には同じと考えてよい。
一方、PD-1治療の効果がなかった患者さんについて調べると、多いとは言えないが、同じようにネオ抗原反応性を確認できる抗原受容体を特定できる。しかし、末梢血や腫瘍組織での出現を調べると、1個か2個の抗原受容体が検出できるだけで、しかも繰り返して検出できない。
以上が結果で、免疫がしっかり成立していないと、チェックポイント治療は期待できないことを改めて示した結果だが、ここまで徹底的な実験で示されると、ガンの免疫をまず成立させ、また成立できたかどうかを確認する方法の重要性が実感できる。しかし、新しい方法の威力は素晴らしい。
2023年3月10日
病原体の種類を問わず、感染すると炎症と共に、Just being sick と表現できる、熱、倦怠感、食欲不振、頭痛、意欲の減少などがおこる。このうち多くの症状が、局所の炎症シグナルが脳へ伝えられ、行動を変化させる結果であること、そしてこの伝達に関わる一つの主役がプロスタグランジンであることもよく分かっており、事実プロスタグランジンの合成を阻害するアスピリンやイブプロフェンがこれらの症状の多くを改善してくれる。
このような全身に共通の症状が発生し、それをアスピリンで治すことができるのは、プロスタグランジンの全身効果かと思っていたが、今日紹介するハーバード大学からの論文は、インフルエンザ感染が脳へ伝わる経路を丹念に解きほぐし、この反応が、舌咽頭に分布する感覚神経を介して脳へと伝達されることを明らかにした研究で、3月10日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「An airway-to-brain sensory pathway mediates influenza-induced sickness(気道から脳への感覚経路がインフルエンザによる体調不良を媒介する)」だ。
これまでの研究で、インフルエンザ感染によりプロスタグランジンE2(PGE2) が合成され、これが神経の PGE2受容体EP3 を刺激、その結果体調不良に至ることが薬理学的研究から分かっていたが、どの神経細胞がインフルエンザ感染を脳に伝えているのかは分かっていなかった。
この研究では、インフルエンザ感染、PGE2、EP3シグナル経路が主役であることを確認した上で、EP3 を発現して、鼻咽頭部から脳に至る神経経路を、文字通り一本づつ解きほぐしている。具体的には、神経細胞 single cell RNA Sequencing データベースから EP3 を発現する神経細胞を特定し、それぞれの神経細胞特異的な遺伝子に導入した遺伝子スイッチを使って、その神経だけから EP3分子をノックアウトし、体調不良が改善されるかを調べるという、大変な実験だ。
この結果、迷走神経下神経のうちで NP9 と分類できる感覚神経の EP3 をノックアウトした時のみ、症状が改善される、すなわちアスピリンを飲んだのと同じ効果が得られることが分かった。また、ジフテリアトキシンを用いてこの感覚神経を除去する実験でも、同じように症状の改善が見られることを示している。また、この感覚神経経路は、特に咽頭から舌にかけて分布しており、ここから最終的に延髄の孤立核へとつながった感覚経路であることも、確認されている。
以上の結果は、少なくとも上気道感染の PGE2 の合成は局所で感知され、特異的な感覚神経経路を通って延髄に伝わり、全身症状を引き起こしており、PGE2 がホルモンのように全身を巡って症状を起こすわけではないことがはっきりした。
専門家には当たり前の話かもしれないが、感染による just being sick がプロスタグランジンの全身効果と思ってきた私には、目から鱗の論文だった。
2023年3月9日
FGF21 については、すでに2−3回このHPで紹介してきた。最も期待されているのは、代謝ホルモンとして脂肪分解を促進し、肥満を防止できる可能性だが、昨年2月に紹介したように、アルコールで誘導され、アルコール消費を抑える効果があるという報告を見て(https://aasj.jp/news/watch/19091 )、その効果の多様性に驚いた。
今日紹介するテキサス大学からの論文は、同じようにアルコールと FGF21 の関係を調べ、FGF がアルコール急性症状による脳機能低下を抑える働きがあることを示した研究で、3月7日 Cell Metabolism に掲載された。タイトルは「FGF21 counteracts alcohol intoxication by activating the noradrenergic nervous system(FGF21はノルアドレナリン神経システムを刺激してアルコール中毒に対抗する)」だ。
この研究は、FGF21ノックアウトマウスにエタノールを投与し、起き上がり反射を指標に一種の酩酊状態からの回復を調べ、FGF21 がないと回復が遅れることを発見している。すなわち、FGF21 が急性アルコール中毒にも何らかの役割がある。
そこで、今度は正常マウスにアルコール急性中毒を誘導し、1時間後に FGF21 を腹腔注射して酩酊状態からの回復を見ると、回復が2倍早くなる。一方、麻酔剤や精神安定剤などで同じ実験を行なっても FGF21 の影響が見られないことから、アルコール特異的に働いている。
FGF21 でアルコールの代謝速度が変化することはないので、以上の効果は全て脳への効果と考えられる。そこで、Fos分子の発現を指標にアルコールの効果を調べると、青班核のノルアドレナリン神経の一部が興奮し、この興奮は FGF21 をノックアウトすると見られないことが分かった。また、FGF21 を注射しても、青班核のノルアドレナリン神経を興奮させる。
さらに FGF21 刺激には Klotho分子が必要で、この遺伝子を神経特異的にノックアウトさせたマウスでは、FGF21 の反応が見られない。
最後に、神経特異的にノルアドレナリンが合成できないマウスを用いて、FGF21 の効果がノルアドレナリンシナプスを介して起こっていることを証明している。
以上が結果をまとめると、アルコールは肝臓での FGF21分泌を誘導し、これによって青班核のノルアドレナリン神経を刺激し、この神経がさまざまな領域で、酩酊から覚醒させるというシナリオになる。アルコール中毒の特効薬として使われるようになるかどうかはわからないが、FGF21 研究には目が離せない。
2023年3月8日
ダーウィン進化論は、世界(生命)の理解に初めてアルゴリズムを導入したと考えているが、偶然による多様化(この時はDNA情報などといった概念は存在しなかった)と、選択(環境の同化といっていいのかも知れない)の組み合わせで、最初の単純な生命からこれほどの多様性が生まれたことを説明したことに驚く。
しかし、この偶然による多様化はDNA情報が生まれてから現在まで同じなのか?勿論、化学的性質としては同じだろうが、DNA情報が置かれている状況により、当然違いが生まれるはずだ。今日紹介するデンマーク・コペンハーゲン大学からの論文は、なんと68種類の脊髄動物について生殖系列の突然変異の頻度を調べた論文で、3月1日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Evolution of the germline mutation rate across vertebrates(生殖系列突然変異頻度の脊髄動物内での進化)」だ。
生殖系列突然変異は、親から子へと遺伝する変異を意味し、従って親の生殖細胞が形成される過程で生まれる。ただ、難しく考えなくても、親子の体細胞をとってきてゲノムを比べれば、ほぼ生殖系列変異をリストできると考えてもらえる。この研究では従って、68種類の脊髄動物の親子のゲノムを採取して、親に存在せず、子供だけに存在する変異の中で、生殖系列由来と考えられる頻度の変異をリストしている。
実験自体は簡単で、今までなぜこのような研究が行われなかったのが不思議な気がするが、しかし親子であることを確かめた68種類の脊髄動物を集めることは簡単ではないと想像する。結果をまとめると以下の様になる。
突然変異の頻度は、種によって大きな多様性があり、はっきりとした傾向を見つけるのは難しいが、一般的に変異が大きい種は、は虫類や鳥類に多く、調べた全脊髄動物中でトップにたったのが、ダーウィンの名を冠した、ダーウィンレアと呼ばれる鳥類だったのは、因縁めいて面白い。
生殖細胞の形成を考えると当然だが、生殖時の親の年齢と突然変異頻度は比例する。基本的には生殖細胞系列の分裂回数と比例すると考えて良い。
同じように、精子と卵子の形成のされ方から、一般的にオスの方が変異頻度が高い。例えば、多くの精子を常に用意しているスズメやペンギンではオスの変異頻度がメスの数倍に達する。一方、卵子の数の多い鳥類やは虫類では、オスメスの差が減る。
変異頻度と、進化による遺伝子の変化の確率はほぼ比例しており、ゲノム情報の多様化が進化の駆動力であることがわかる。
突然変異頻度は、様々な生活スタイルに左右される。例えば成熟までの時間がかかるほど、変異数は高まるし、子供の数が多いほど、変異数が低くなる。
はっきりとした理由はわからないが、家畜化されると一般的に一年間に生殖細胞で起こる変異頻度が高まる。
以上が結果で、ともかくやってみて結果が出ることが重要で、後の理屈づけはこれからの問題だろう。
2023年3月7日
形態以外に分類方法がなかった我々の学生時代、組織や細胞の特徴を表す言葉を覚えることが、病理学の勉強だった。このおかげで、言葉というシンボルだけで、複雑な形態を思い浮かべることが出来る様になった。病気で多くの人にも知られている例は、パーキンソン病のレビー小体だろう。
今でも病理学で教えていると思うが、少しマニアックなのが Tingible body macrophage(TBM)だ。リンパ濾胞の中に存在する大きなマクロファージで、特に細胞内に死細胞断片が取り込まれたことによる特徴的形態をしている。おそらく断片化した核酸が染まるので tingible と呼ぶのだと思うが、B細胞濾胞で免疫反応が始まり胚中心が形成される過程で現れるため、B細胞の増殖と細胞死が起こる胚中心で、細胞を急速に処理し、異常な反応を抑えることがその役目だと考えられている。実際、TBM に細胞が食われなくすると、胚中心が大きくなり、自己抗体を伴う自己免疫が発症する。
今日紹介するオーストラリア・ガーヴァン医学研究所からの論文は、様々な組織学的技術を駆使して TBM の由来と成り立ちを明らかにした研究で、3月2日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Apoptotic cell fragments locally activate tingible body macrophages in the germinal center(アポトーシスによる断片が局所的に胚中心の tingible body macrophage を活性化する)」だ。
まずマクロファージ系列を標識したマウスに免疫して胚中心を作らせ、TBM を他の場所のマクロファージと比較し、同じマクロファージでも、リンパ節辺縁やT細胞領域のマクロファージとは異なる性質を獲得していることを明らかにしている。
次に、生きたままリンパ節組織を観察する方法を用いて、TBM が濾胞内でほとんど動かず、しかし長い突起を伸ばして死細胞の断片を貪食していることを明らかにする。生体を観察する方法で、突起に補足された細胞断片が取り込まれる様子が見れるというのは驚きだ。
次に、発現している蛍光分子をブリーチしてターンオーバーを調べる方法で、通常はあまりターンオーバーのない、いわゆる組織常在マクロファージで、免疫反応前から B細胞濾胞に散在しており、免疫により胚中心が形成されると、細胞断片を取り込みはっきりと目立つ様になることを示している。また CSF1受容体をブロックしてもほとんど数に変化がないことからも常在細胞であることがわかる。
最後に、典型的な TBM 形態をとる様になるスイッチが、死細胞を取り込むことに依るのではと着想し、濾胞内の B細胞を人為的に殺す方法を用いて、免疫による胚中心形成が起こらなくても、B細胞のアポトーシスが起こり始め、その断片を TMB が取り込み始めると、典型的形態を誘導できることを明らかにしている。
以上が結果で、病理で TBM を知ってから50年ぶりに、TBM に目がとまり、一つの形態にも様々なメカニズムが背景にあることがよくわかった。
2023年3月6日
大事な発見もあまり専門的な雑誌に発表されていると、ほとんど目にとまらず、忘れ去られることは珍しいことではない。時によっては、その現象が再発見されても、最初の発見者が忘れ去られたままになることもある。
今日紹介するパリ・クレティユ大学からの論文は、この忘れ去られていた大事な発見に目をとめ、プロの目で、ドゥシャンヌ型筋ジストロフィーの治療可能性を明らかにした論文で、3月1日号の Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Thyroid-stimulating hormone receptor signaling restores skeletal muscle stem cell regeneration in rats with muscular dystrophy(甲状腺刺激ホルモン受容体シグナルによってラット筋ジストロフィーの筋肉幹細胞による再生が可能になる)」だ。
まず忘れ去られていた論文から紹介しよう。2015年ワシントン大学からDevelopmental Biologyに報告された論文で、
外眼筋と呼ばれる動眼のための筋肉は、ジストロフィンが欠損しても幹細胞の自己再生と筋肉の再生が維持されているという発見だ。すなわち、ジストロフィン欠損でも再生を維持できるメカニズムが外眼筋には備わっているという結果だ。このような驚くべき結果が8年間も忘れられていたというのに驚くが、筋肉幹細胞研究のプロの一人 Frederic Relaix の目にとまった様だ。
ラット筋ジストロフィーモデルで、骨格筋、外眼筋について Single cell RNA sequencing を行い、またその結果を組織学的に検証することで、
ジストロフィンが欠損した骨格筋は、p16 や p21 が高発現し、老化が進み、その結果再生能力が失われている。しかし、この老化は外眼筋では見られず、筋肉再生が維持できる。
正常ラットで、骨格筋と外眼筋の転写を比較すると、甲状腺刺激ホルモン受容体の発現が後者でのみ見られる。
ジストロフィン欠損外眼筋筋肉幹細胞は、試験管内で増殖を続けることが出来るが、甲状腺刺激ホルモン受容体の機能を阻害する薬剤で、骨格筋と同じように増殖が低下する。すなわち、甲状腺刺激ホルモン受容体シグナルの有無で、外眼筋と骨格筋の差を説明できる。
阻害剤の効果は、シグナル下流の cAMP を上昇させるフォルスコリンで元に戻せる。
を明らかにした。
以上の結果を、ヒト骨格筋、及び外眼筋で確認した後、最後にジストロフィン欠損マウスにフォルスコリンを週2回注射するプロトコルで、筋肉の喪失を抑えられるか調べ、4ヶ月目で、機能的にも組織的にも、病気の進行をある程度抑えられることを示している。
結果は以上で、フォルスコリンの注射を長期的に続けられるかどうかは難しい問題だが、ジストロフィン喪失の影響を幹細胞の増殖と老化に収束させて、病気の進行を抑えるための標的を明らかにしたことは極めて重要だ。
さらに、幹細胞の一般的な老化についても抑える方法へと発展するかも知れない。さすがプロの目だと感心した。
2023年3月5日
アフリカには1000を超す言語が存在し、ピグミーと呼ばれる rain forest huntergatherer からマサイ族まで、身長だけで見ても多様な人種が存在することはよく知られた事実だ。また、地球上に現存するホモサピエンスは全てアフリカ由来であり、アフリカの民族形成史は人類を理解するためにも重要な課題と言える。ただ、ヨーロッパ人の侵入後を除くと、各民族間の交流を記した記録が乏しく、理解が進んでいない。
今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、現代アフリカ人のゲノムを解析することで、ゲノムに残った民族交流の歴史や、地域への適応について調べることで、アフリカの民族形成を理解しようとした研究で3月2日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Whole-genome sequencing reveals a complex African population demographic history and signatures of local adaptation(全ゲノム解析はアフリカ民族の形成史の複雑性と、各地域への適応した遺伝的特徴を明らかにする)」だ。
この研究では12部族から15人ずつ、全ゲノムを30カバレージで解読して、アフリカ人特有、また各民族特有のゲノムの特徴を調べている。私たちはアフリカ民族というと、マサイ族、ズールー族、ピグミー族などを思い浮かべるが、より専門的な分類(Amhara Fulani Dizi Chabu Hadza Mursi Sandawe Tikari Herero RHG !Xoo Ju|’hoansi)が使われている。Google で調べると、実に多様な民族で、それぞれの言語は大きく4種類の系統に分かれている。
勿論これまでもアフリカ人ゲノムは解析されてきたが、ここまで系統的に調べられたことはなかった様だ。以下に面白いと思った結果を一存でピックアップした。
アフリカ人民族のルーツを29−15万年、すなわちホモサピエンスの出現に近いところまで遡ることが出来る。当然ネアンデルタール人やデニソーワ人のゲノムは流入していないので、ホモサピエンスの多様化と選択をストレートに研究できる。
想像通り、その後のアフリカ民族の形成史は極めて複雑で、単純な系統樹を書くことが難しい。これは、複雑な交雑の歴史と、移動の歴史が重なるためで、この研究ではアフリカを離れた集団に近い Fulani と最も遠い Ju|’hoansi までの系統樹と、各民族で交雑が起こった歴史についての最も可能性の高いモデルが示されている。ちなみに Fulani は西アフリカの最も北に位置しており、納得できる。
驚くことに、これまでの膨大なゲノム研究でも記載されなかった SNP(遺伝子の塩基レベルの多型)が530万種類も発見され、そのうちの78%はアフリカ人特有であることがわかった。また、3万近くははっきりとアミノ酸変異を伴っており、今後の研究が容易な SNP といえる。
これまでのゲノム解析で、頻度は多くない病気に直結する SNP として分類されていたものが150も存在するが、アフリカ民族では頻度が5%以上の SNP が44も存在し、病理的と分類するのは問題であることがわかった(例えば立ちくらみと相関する DBH遺伝子 SNP はアフリカでは普通に見られる)。
10万年間の人口変遷についても計算しており、東アフリカの Hadza や Chabu のように急速に人口が減っている民族の存在から、厳しい競争の歴史および勝ち組、負け組の存在も見ることが出来る。
このように強い人為的圧力と、アフリカ特有の大きな環境の多様性の結果、それぞれの民族特有の SNP の中に、その土地への適応の後がはっきり見られる遺伝子群が特定できる。例えばアフリカ人のメラニンは真っ黒から茶色まで変化があるが、Sandawe族では、明るい皮膚に関わる様々な SNP を持っており、機構に適応したと考えられる。詳しくは述べないが、IL6 の反応性に関わる多くの遺伝子が Fulani では高まっており、これがマラリアへの抵抗性獲得に貢献している。あるいはタンザニアの Mursi や Dizi では、それぞれ異なる腎臓発生に関わる SNP が選択されており、砂漠地帯へ追いやられた結果の適応と考えられる。
以上が私が面白いと思った結果だが、適応についてはピグミーで見られる骨格に関わる多くの SNP は、極めて重要な発見だと思う。今後、アフリカで古代人のゲノムが解析できる様になると、暗黒大陸という言葉は死語になると思う。