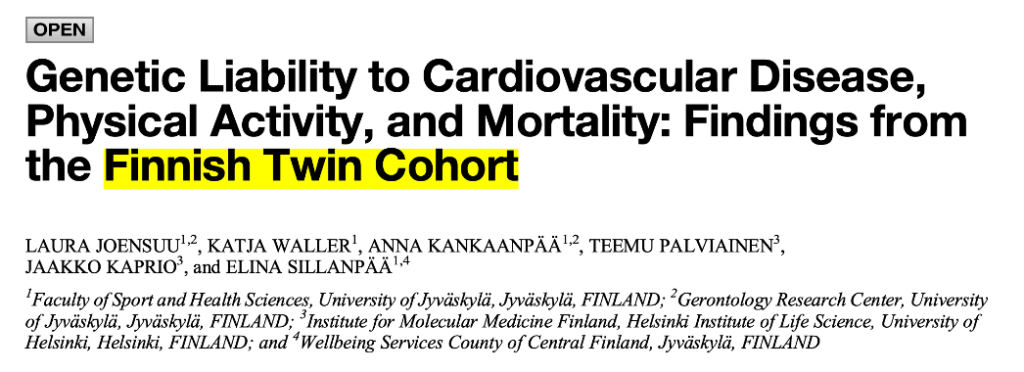2025年4月29日
現在アルツハイマー病 (AD) の発生プロセスに関しては、アミロイドβ (Aβ) の蓄積が最終的にはTauのリン酸化、細胞内蓄積、そして細胞間伝搬を伴うTaunopathyを誘導しないと神経細胞変性は起こらないと考えられている。しかしマウスにADを発症させるモデルのなかには、3種類のヒトの遺伝的Aβ変異を2種類のAβを切り出す酵素プレセニリンの変異と組み合わせた5xFADマウスのようにTaunopathyをそれほど起こすことなくシナプス喪失が起こることがある。おそらくTaunopathyも誘導されると思うが、Aβ蓄積だけでも炎症を誘導してシナプスの変化が起こる可能性を示しておりAD病理の複雑さを示している。
今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文はAβとシナプス喪失を直接繋いでいるメカニズムの一つにPHGDH分子が存在することを示した研究で、4月23日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Transcriptional regulation by PHGDH drives amyloid pathology in Alzheimer’s disease(PHGDHによる転写調節がADに起因するアミロイドプラーク病変を誘導している)」だ。
この研究で着目したのは最近示されたADの海馬や前頭葉ではグルコース代謝でフォスフォグリセリン酸をフォスフォヒドロキシピルビン酸に変換する酵素PHGDHで、この作用はセリン合成に必須であることから、セリン供給が増えてグルタミン酸受容体の過剰活性がADを誘導すると考えられていた。
この研究ではAβとTauの変異を誘導した3xTgマウス脳局所にPHGDHを過剰発現させるとAβプラーク形成とシナプス喪失を高められることから、PHGDHがADの病理に直接関わることを確認したあと、ヒトES細胞から誘導した脳オルガノイドにヒト血清を加えてAD様の病変を発生させる大変なモデル系を用いて、AD誘導とともにPHGDHが上昇すること、そしてこのときPHGDH発現をノックダウンで抑制するとAD病理の発生を抑えられることを明らかにしている。
このようにPHGDHはADのマーカーだけでなく、AD 発症に直接影響する分子であることが明らかになった。そこで、このメカニズムを探索する目的で、まずセリン合成に関わる酵素活性部位を欠損させたPHGDHをオルガノイドに導入する実験を行ている。結果は驚くべきもので、酵素活性がノックアウトされたPHGSDHでもAD病理と促進することができる。すなわち、この分子はセリン供給とは別の経路を介してAD病理を誘導していることになる。
そこでPHGDHの様々な部位を変異させ、AD病理誘導能力を調べると、核移行シグナルとbHLH構造が必須であること、即ち一種の転写因子として働いてAD病理誘導に手を貸していることが明らかになった。
そこで、PHGDHにより変化する遺伝子発現の中から、AD病理発生に最も関わる遺伝子を探索し、PHGDHが発現することで起こる変化の中で、IKKとHMGB1が最も重要であることを突き止める。即ち、PHGDH発現上昇とともにこれらの分子の発現が上昇し、またそれぞれをオルガノイドでノックダウンすると、オルガノイドでのAD病理の発症を抑えることができる。
IKKはNFκBを介して炎症を誘導し、またHMGB1はTLRなどの発現を調節して炎症誘導に関わることがわかっている。また、PHGDH効果によるAD病理ではTaunopathyの関与は少ない。即ち、PHGDHはAβ蓄積と炎症を直接つなぐ分子であることを示している。
幸いこれまで開発されたPHGDH阻害剤の中には分子の立体構造を変化させる阻害剤があり、これを用いるとIKKやHMGB1の遺伝子誘導に関わる転写調節因子としての作用も抑制できることがわかった。この化合物を脳オルガノイドのAD病理誘導系に加えると、Aβ蓄積、シナプス喪失を防ぐことができる。最後に、Taunopathyの影響の少ない5xFADマウスに投与すると、認知機能の改善が見られた。
以上が結果で、Taunopathyだけでなく、場合によっては炎症誘導だけでAD病理が起こることを示した面白い研究だと思う。
2025年4月28日
神経細胞と同じで、脂肪細胞は大人になると新しいリクルートがないと考えられてきた。即ち、脂肪太りはもっぱら脂肪細胞が大きくなる結果で、数は増えていないことになる。これに対し、人間の神経細胞が成長後も増殖をしていることを原爆実験時に取り込んだアイソトープの減衰から調べた同じ方法を用いて、脂肪細胞も増殖していることが証明された。
今日紹介する米国シティーホープ医学センターからの論文は、さらに一歩進んで、発生後一度は新しいリクルートが途絶えた脂肪細胞が、中年になると俄然新しい細胞がリクルートされることが我々の中年太りの背景にあることを示した研究で、4月25日 Science に掲載された。タイトルは「Distinct adipose progenitor cells emerging with age drive active adipogenesis(年齢とともに新しく出現する特別な前駆細胞により年齢に伴う脂肪合成が起こる)だ。
新しい脂肪細胞のリクルートを調べるため、成長期に分化した脂肪細胞の全てを遺伝的に標識する方法を用いることで、新しいリクルートが寄与した場合、標識細胞が薄まって行く現象を使っている。結果は、これまで示されてきたように新しいリクルートがあることが確認されるのだが、驚くことにこのリクルートはマウスが9ヶ月例になるまでにはほとんど見られず、9ヶ月目ぐらいから急速に新しい脂肪細胞が作られて脂肪組織に供給されることがわかった。そして12ヶ月例を超えるとこのリクルートは減少するので、マウスで言えば一種の中年期に新たな脂肪細胞合成が起こって、肥満の原因になっていることになる。
次に異なる時期の脂肪細胞を移植する実験から、若いマウスの脂肪細胞は新しい脂肪細胞を供給する能力は低く、12ヶ月例の白色脂肪組織にリクルーターが存在していることを確認している。
次に脂肪組織の single cell RNA解析から、中年期に数が増えてくるリクルーター集団を特定し、なんとES細胞の維持にも用いられるLIFに対する受容体とPDGF受容体αを同時に発現している細胞としてセルソーターで生成することができることを発見する。
この集団を取り出して試験管内で培養すると、12ヶ月例の脂肪組織では増殖性の高い細胞を分離することができ、この培養に脂肪細胞分化のカクテルを加えると脂肪細胞への分化を観察することができる。また、この細胞を精製して移植する実験を行うと12ヶ月例の幹細胞は組織内で強く増殖して組織の脂肪細胞を増加させることを確認している。
このように脂肪細胞をリクルートするこれまで記載されていない幹細胞をLIF受容体とPDGF受容体αを組み合わせて特定できるようになったわけだが、LIF受容体はたまたま発現しているだけなのか、幹細胞の増殖に必要なのかをノックダウン実験や、阻害剤を用いて検討し、脂肪幹細胞の増殖にLIF受容体が必要であることを明らかにしている。また、若いマウスの脂肪細胞にLIF受容体を過剰発現させる実験も行い、増殖能が2倍に増えることを示している。
LIF受容体阻害自体は正常組織にあまり大きな影響がないので、脂肪幹細胞が働き出す9ヶ月目から10週間長期に阻害する実験も行い、内臓脂肪が選択的に減少することを明らかにしている。
最後に、人間の中年男性から脂肪組織を提供してもらい、PDGR受容体αとLIF受容体を発現している脂肪幹細胞が中年のヒトにも存在することを明らかにしている。 以上が結果で、もちろん代謝で脂肪細胞が肥大することも重要な要因だが、中年になると脂肪細胞自体が、特に内臓脂肪でリクルートしやすくなっているということで大変面白い研究だと思う。ただ、人間でも同じかどうかはこの研究だけでは不十分なので、是非調べていってほしい。
2025年4月27日
現在まさに移動中で飛行機を待っているところなので、時間のかからないということで、ハワイの希少な習性を持つ毛虫のゲノムを決定したというハワイ大学からの論文を紹介する。タイトルは「Hawaiian caterpillar patrols spiderwebs camouflaged in insect prey’s body parts(ハワイの毛虫の一種は蜘蛛の巣をパトロールして餌を探し、餌の死骸を身体に巻き付ける)」だ。
要するに極めて珍しい毛虫をふ化させたあと、許可を得てゲノム配列を決定したという話だ。「で、どんな珍しい毛虫か?」ということになるが、百聞は一見にしかずなのだが、この論文はオープンでないので写真が見られない。そこでググった結果、Scientific Americanにこの論文に掲載されている論文が全て再掲載され、アクセスできることを知った。そこでURLを掲載するのでまずご覧いただきたい(https://www.scientificamerican.com/article/carnivorous-bone-collector-caterpillars-wear-corpses-as-camouflage/ )。
まず毛虫だが、最初の写真にあるように、caterpillerが自分の周りに棘のようなキチン質を巻き付けているのがわかる。この棘の由来を観察していると、蜘蛛の巣に残っている昆虫の死骸から切り出してきて、ちょうどいい長さに剪定して巻き付けていることがわかる。そのため、連続殺人犯についての推理小説のタイトル bone collector という名前がつけられている。
この死骸をどう調達しているかだが、同じウェッブサイトの2枚目の写真は、bone collector が卵を抱えたクモと、同じ蜘蛛の巣に(といっても美しいウェッブというより、シート状の蜘蛛の巣を指す)存在しているのがわかる。
そしこの bone collector が蜘蛛の巣をパトロールして残った死骸や、あるいは引っかかったばかりの昆虫を餌にしている、珍しい肉食のcaterpillerであることがわかる。しかも、同じ巣の上で、同じ種同士が殺し合うことが観察される。この結果、一つの蜘蛛の巣には1匹の bone collector だけが存在する。
この種は極めて出会うのが難しく、オアフ島の15平方Kmの限られた場所でしか見つかっておらず、これまで22年にわたり150回以上の生態調査が行われ、全体で62匹しか見つかっていない。面白いのは、この死骸を身体に巻き付ける結果、bone collector がクモに襲われた例は全く見つかっていない。
このcaterpillarの一匹を孵化させて、標本を作るときに腹部からDNAを取り出し、ゲノム解析を行っている。その結果、太平洋で孤立したハワイ諸島のヒポスモコマ属の一員で900万年前に分岐してそのまま現在まで続いていることがわかった。
以上が結果で、ともかく習性が面白い昆虫を大事に孵化させ、なんとかゲノム解析まで進んだという研究で、ゲノムの意味についてはこれからの話になるが、絶滅危惧種というより絶滅してしまったかもわからない状態の昆虫なので、おそらく研究はネアンデルタール人の研究と同じような考古学的研究になると予想できる。
2025年4月26日
2020年以前の統計しか見ていないが、我が国で大腸直腸ガン (CRC) は増加を続けて、おそらく現在では男性でも胃ガンの発生率を超えていると思う。一方欧米では発生率の低下が認められているようだ。また最近の傾向として、50代以前の若年層のCRCは世界中で増加をしており、その原因についての探索が行われている。例えば欧米と我が国の違いにについては、脂肪分の多い欧米型の食事や肥満による影響とされ、我が国で増加している傾向は同じ枠組みで説明されてきた。しかし、若年層での増加が世界的に見られることから、これを単純に生活習慣の問題として片付けることはできない。
今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校を中心とする我が国の東大医科研や国立ガンセンターを含む国際チームからの論文は、800近くの世界各国から集めたCRCの遺伝子配列解析から、ガンで起こった突然変異の特徴を解析し、突然変異を誘導する要因について調べた研究で、4月23日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Geographic and age variations in mutational processes in colorectal cancer(大腸直腸ガンの突然変異過程の地域と年齢による違い)」だ。
このブログでも何度も紹介しているように、ガンで見られる突然変異の起こり方の特徴から変異の起こる原因を特定することができる。これらはCatalogue of Somatic Mutations in Cancer (COSMIC) としてカタログ化しており、例えばSBS1は加齢とともに起こるタイプで、SBS4はタバコなどの化学発ガンで起こるタイプと分類され、ガンでこれらの特徴を調べることで、ガンの変異の原因をある程度推察することができる。
この研究ではまず1000近いCRCを集めて全ゲノム解析で変異のタイプを調べている。ただ大腸ガンの場合、遺伝子修復機構に変異が起こるタイプが存在して変異の特徴に大きく影響するので、注意深く修復の低下しているCRCを除いた800例について、地域差、年齢差などを調べている。
この研究では、なんと我が国が、集団の年齢差を調整したCRCの年齢調整罹患率で今や世界トップになってしまっていることが述べられており、まず驚いた。
この研究では若年層と高齢層のCRCに分けて比べている。もちろん老化とともに起こってくるような変異は若年層のガンでは低い傾向にあるが、世界中で見られる若年層の増加傾向の原因を明確に示すようなはっきりした変化は認められていない。
次に地域での差を調べると、コロンビアやアルゼンチンで地域特異的な変異が特定された。この地域特異的な変化の原因は特定できていないが、南米で特に目立っていることから、強い環境要因の関与が考えられる。とはいえ、この環境要因を単純な化学化合物の暴露と決めつけることはできない。というのも、腸内細菌叢の違いも地域差の原因になり得るからだ。
その最も顕著な例として、この研究では大腸菌の分泌するコリバクチンにより起こると考えられているSBS88と呼ばれる一塩基変異とID18と呼ばれる挿入/欠損タイプに注目している。このタイプは、若年層でのガンで特に目立つ。驚くのは、このタイプが我が国で多い点で、大腸ガンより直腸ガンでそれが目立っている。即ち、我が国のCRC増加はコリバクチンへの暴露と相関している可能性がある。
ところがCRCの患者さんでコリバクチンを作る大腸菌が見つかるわけではない。従って、コリバクチンの暴露は発生期から幼児期にかけて一過性に起こっている可能性がある。特にID18タイプは早期におこるAPC変異の特徴のかなりの部分を占めていることから、成長期に一時的にコリバクチン産生バクテリアに晒されたことが、発ガンを促進している可能性が明らかになった。
以上が結果で、細菌叢に紛れ込んだ発ガン物質産生のバクテリアがCRC発ガンにとってかなり重要な役割を演じていることがわかる。とすると、極めてユニークな変異のパターンが目立つコロンビアやアルゼンチンなどのCRC発症に関しても、特定の細菌が原因になっている可能性がある。
いずれにせよ我が国でコリバクチンによる変異型が多いことにおどろいたが、もしこれが我が国でのCRC増加の重要な一因だとすると、いつ暴露されたかも含めて詳しく調べると面白いはずだ。うまくいけば子宮頸がんのように幼児期にCRCを予防することも可能かもしれない。
2025年4月25日
KRAS阻害剤の開発が進むことで、少しは膵臓ガンの治療にも光が差してきた気がする。ただ、薬剤抵抗性の出現など一つの標的だけでは根治は難しい。従って、免疫治療を組み合わせるか、あるいは他の標的に対する薬剤を使う併用治療の開発も進められている。そのうちの一つが、このブログでも紹介したオートファジー阻害剤による治療だが、現在のところ切り札にはなり得ていない。
今日紹介するミシガン大学からの論文は、PIKfyve1分子が膵臓ガンの新しい治療標的としてかなり有望であることを明らかにした研究で、4月23日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Targeting PIKfyve-driven lipid metabolism in pancreatic cancer(PIKfyveによる脂肪代謝は膵臓ガンの新しい標的になる)」だ。
すでに述べたが膵臓ガンの新しい標的としてオートファジーを含むリソゾーム活性が注目され、いくつかは治験にまで進んでいる。この研究も細胞内でリソゾームの活性に必要なphosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PtdIns (3,5) P2)やphosphatidylinositol 5-phosphate (PtdIns5P) を合成するPIKfyve1を標的にすると膵臓ガンの増殖を抑えられるのではと仮説を立て研究を進めている。
まず正常膵臓上皮と比べて膵臓ガンではPIKfyve1が強く発現していることを確認した上で、膵臓上皮でPIKfyve1をノックアウト、その後ガン遺伝子を導入して膵臓ガンの発生を見ている。すると期待通り、PIKfyve1がノックアウトされていると膵臓ガンの発生を強く抑えることができる。
PIKfyve1阻害剤はすでに治験で安全性が確認された薬剤が2種類あるので、この薬剤を予防的に投与すると、ノックアウトマウスと同じで膵臓ガンの発生を抑えることができる。
以上PIKfyve1が何らかの形で膵臓ガンの発生に関与していることは間違いない。元々リソゾームでのオートファジーなどの活性を変化させることを念頭にこの分子を選んでいることから、他のリソゾームやオートファジー阻害剤と比較すると、他の薬剤より効果が高く、オートファジー以外の過程もPIKfyve1により起こっていると考えられる。
そこで阻害剤による遺伝子変化などを調べ、最終的にPIKfyve1阻害により脂肪代謝が高まることが明らかになった。すなわちPIKfyve1阻害によりリソゾームの調節異常が起こり、リソゾームからリサイクルされた様々な脂質の供給が止まった結果、これを補うためにに脂肪酸合成経路が上昇して必要なスフィンゴ脂肪酸やコレステロールが作られることがわかった。
この代償的脂肪代謝に関わる経路を探ると、膵臓ガンのドライバーとして働くKRAS-MAPK経路により誘導されたMYCが脂肪代謝に関わる遺伝子セットを誘導していることが明らかになった。即ち、PIKfyve1で誘導された脂質代謝の問題を、KRAS-MAPK経路で補っていることになる。だとすると、PIKfyve1阻害と同時にKRAS阻害を組み合わせると膵臓ガンの増殖をさらに強く抑制できるはずで、人の膵臓ガンを移植したマウスモデルで治療実験を行うと、両方を併用したときに最も強い抑制効果が得られる。さらに、マウスにガン遺伝子を導入して誘導される膵臓ガンでも、両方併用で強い効果が認められた。
以上が結果で、、これまでのオートファジー阻害の枠組みを拡大して、脂肪代謝のバランスという意外な膵臓ガンのアキレス腱を狙ったなかなか面白い標的で、すでに第1相の終わった薬剤が使用できることを考えると、結構期待できそうだ。
2025年4月24日
プリオンタンパク質は、一旦、神経変性につながる異常型に転換すると、正常タンパク質を異常型に変え、治療法のない狂牛病などの神経疾患を誘導する。しかも、異常型のプリオンタンパク質を食べることで異なる個体に伝搬する。このように、病気の原因としてのプリオンタンパク質はよく知られているが、正常型の機能については一般にはほとんど知られていない。ノックアウトマウスが作成され、ほとんど異常が見られないとされたこともあるが、現在ではプリオンタンパク質の様々な機能が明らかになっている。さらに、神経系だけでなく、腎臓など他の組織での発現と機能についても報告されており、欠損すると蛋白尿や薬剤による腎障害の重症化が起こることが知られている。
今日紹介する中国杭州にある南方医科大学からの論文は、正常型プリオンタンパク質が慢性腎疾患で腎臓の繊維化を促進する働きがあることを示した研究で、4月16日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Condensation of cellular prion protein promotes renal fibrosis through the TBK1-IRF3 signaling axis(細胞内でのプリオンタンパク質の相分離はTBK-IRF3シグナルを介して腎臓の繊維化を促す)」だ。
これまでプリオンタンパク質 (PrP) は腎臓を保護する分子として知られていたが、このグループは様々な腎障害のバイオプシー標本を調べ、PrPが腎臓の尿細管上皮で上昇していることを発見する。さらに、PrP発現レベルは腎臓の機能を示す eGFRと逆相関している。また、この上昇が腎臓の繊維化誘導因子として知られるTGFβによって誘導されていることを発見する。
PrPの上昇が腎臓の繊維化に寄与しているかどうかを調べる目的で、尿細管上皮特異的にPrPをノックアウトすると、尿管を閉塞させた時に起こる腎臓の繊維化を軽減することができる。すなわち、PrPの発現は腎臓の繊維化の一因になっていることを示している。
そこで、尿細管特異的にPrPを過剰発現させPrPにより誘導されるシグナルを探ると、TBK1-IRF3を中心とするインターフェロン反応性経路が特定され、この刺激により上皮から線維芽細胞刺激分子 (CXC5) などが分泌され、繊維化が促進することを明らかにする。さらにこの経路の活性化はPrPが細胞内で相分離を起こすことで誘導されることを様々な実験から確認している。
最後に、TBK1経路を阻害する化合物を用いて、腎臓の繊維化を一定程度抑えることができることを示し、この分子経路が慢性腎障害の標的になると結論している。
結果は以上で、正常型のプリオンも病気を悪化させる分子として働くのかという意外性が売りの論文だった。ただ治療標的になるかどうかは使われている腎障害モデルが限られているのでわからない。一つ気になるのは、腎臓の尿細管でも異常型のプリオンが発生しているのかだ。一つでも異常型タンパク質が発生すると正常型を異常型に転換させるが、他の細胞に伝搬させる仕組みがないので、気づかれないのかもしれない。
2025年4月23日
細胞は常に壊されており、そこから様々な分子が末梢血に供給されるため、末梢血から壊れた細胞の一種の考古学を行うことができる。これを利用したのがリキッドバイオプシーと言われる血中に流れるDNA断片からガンをはじめとする病気の診断や経過観察を行う方法だ。もちろんRNAも末梢血に流れているが、DNAよりさらに分解される可能性が高く、エクソゾームのような細胞膜に守られたRNA以外は検出できても病気の診断に利用することなど難しいと考えられてきた。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、意味があるかどうかは問わず、ともかく末梢血に流れるRNAの遺伝子配列から景色を見てみようとした研究で、4月16日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「An ultrasensitive method for detection of cell-free RNA(末梢血のRNAを超高感度で検出する方法)」だ。
まずともかくRNAを末梢血から精製して量や由来を調べている。だいたい血清1ccには細胞20個分のRNAが含まれており、凍結保存しても最初の1ヶ月は分解されていくがそれを超えると安定に維持されることを確認して、RNA生成のための様々なステップを至適化している。
こうして精製したRNAの遺伝子配列をそのまま調べると、圧倒的多数が血小板由来のRNAで、まずこれを除くことが必要になる。強い遠心分離、さらには配列からデータから除去する方法などを組み合わせると、他の組織からのRNAが見え始める。
ただこれだけでは血小板を始め血液細胞血管細胞からのRNAが圧倒的多数を占めるため、DNA考古学でも用いられる特定のRNAの配列をベースに純化する方法を用いることで、例えば肺や肺ガン組織などからのRNAがようやく見えるようになる。こうして見える特異的RNAをコントロールとして使うハウスキーピング遺伝子RNAと比較した指標を作り、特異的RNAを測る方法を確立している。
これが実用可能かどうかについて、肺ガンの診断を行っている。一個の細胞から2本のDNAが湧出されるDNAと異なり、RNAはより多くの分子数が湧出されるためか、ここまで徹底した方法を用いた場合はRNAを使う方が感度が高い結果だ。しかし、実際の臨床でここまで丁寧に特異的RNAを精製してくるのは簡単ではないと思うし、またDNAの場合もキャプチャー法を用いることで感度を上げられるので、この結果はそのまま鵜呑みにできない。
しかし、RNAでないとわからないこともある。例えばガンが形質転換をしたような場合で、実際に非小細胞性未分化ガンが小細胞性未分化ガンへと変化したのを捕まえることができている。同じように、抗ガン剤抵抗性は必ずしもゲノムレベルの変異だけで起こるものではなく、例えばEGFRの代わりに他のチロシンキナーゼの発現が高まるケースも捕まえることができる。
さらに、同じ変異を持っているガンでも原発はどこにあるのかも当然診断することができる。
以上が結果で、確かにRNAでないとわからないことがあるのはよくわかるし、これを可能にする努力は大きき評価できる。しかし、現在の様々な方法を組み合わせた臨床にどのぐらい大きな助けになるのかについては疑問を感じる。
ただ論文の中で一つ感心したのは、コロナワクチンを注射した人からワクチンRNA断片を1週間ぐらいは検出できるという点で、100マイクログラム皮下注だとすると、感度はたいしたものだと思う。
2025年4月22日
表題に記載したPROTACという言葉はほとんどの人になじみはないと思う。これは Proteolysis targeting chimera の略で、タンパク質の機能を抑える通常の薬剤と異なり、標的タンパク質に結合してそこに様々なユビキチンリガーゼをリクルートし、標的タンパク質を壊してしまう薬剤のことを指す。おそらくサリドマイドが骨髄腫発症に関わる転写因子分解に用いられたのが最初だと思うが、現在では新しい創薬モダリティーとして開発が進められている。ただ、通常の化合物と異なり、最低2種類の分子と結合するためサイズが大きい。
このようにサイズは大きいのだが、経口投与可能で細胞内で転写因子を標的にできるということから、細胞膜を拡散で通過できると(少なくとも私は)考えてきた。これに疑いを持ち、実際には細胞表面のCD36に結合してエンドサイトーシスで細胞内に取り込まれることを示したのが、今日紹介するアーカンサス医科学大学を中心とする研究グループの論文で、4月17日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「CD36-mediated endocytosis of proteolysis-targeting chimeras(CD36を介するエンドサイトーシスがタンパク分解を標的にするキメラ分子の取り込みを媒介する)」だ。
この研究では500Daを超える大きな化合物が簡単に膜を拡散で通過できるはずはないと疑うところから始めている。そこで、VHLをリクルートしてBRD4を分解するPROTACにビオチンを結合させ、細胞内でこの分子と反応するタンパク質を調べている。もちろんVHLやBRD4のような標的の結合が検出されるが、それ以外に細胞膜に存在するCD36やそのエンドサイトーシスに関わるいくつかの分子が特定された。すなわち、PROTACがCD36と結合してエンドサイトーシスで細胞内に取り込まれる可能性が示された。
そこで、CD36やエンドサイトーシスに関わる分子をノックダウンする実験を行い、PROTAC特異的に細胞の取り込みと効果にこの過程が必須であることを示している。また、蛍光化合物を結合させた実験でも、これを確認している。
さらに、様々なPROTACや大型の化合物についても検討を行い、500Daを超える多くの化合物がCD36を介して細胞内に取り込まれることを示している。
この経路が多くのPROTACの取り込みに関わる経路だとすると、最初からCD36への結合性も考慮した分子設計により薬剤の効果を高めることが可能になる。この点を検討するために、PROTAC活性はあっても細胞内に取り込まれにくい化合物に様々な化学修飾を行い、その結果CD36との親和性を高める修飾が薬剤の取り込みだけでなく、効果を高めることができることを明らかにしている。
そして最後の仕上げとして乳ガン細胞株を移植した実験系で、CD36への親和性を変化させたPROTACによる治療実験を行い、同じ標的で、同じユビキチンリガーゼをリクルートするPROTACでもCD36の親和性が高まるほど治療効果が格段に上昇することを示している。
結果は以上で、これまで薬剤効果検証時に想定されていない過程が明らかになることで、薬剤の設計や効果の予測などが今後可能になると言える。著者らはこの例としてアンドロジェン受容体を標的にするPROTACが患者さんによって効果が大きく変化するのは、前立腺ガンのCD36発言程度に関わる可能性を示唆している。このようにより高いレベルのプレシジョンメディシンが可能になるだけでなく、エンドゾームや小胞体を標的にしたPROTACの開発など、結構面白い世界が広がると思う。
この研究が行われた大学は米国の小さな大学で、著者は名前から見ても中国系とインド系がほとんどで、一人だけスペイン系の名前だが、今後このような活動が米国で維持できるのか心配になるほど、面白い研究だと思う。
2025年4月21日
気になった臨床研究を3報紹介する。最初の2報はこれまでほとんど疑うことがなかった概念に対するチャレンジで、残りは最近進んでいる新しい糖尿病薬のアルツハイマー病(AD)予防効果に関する論文になる。
まず最初は、オランダ Radboud大学を中心とするグループから3月30日 Nature Medicine にオンライン掲載された論文で、慢性心不全の患者さんは水分制限をすべきかどうかについての観察研究だ。
慢性心不全患者さんの場合、循環血液量が高まると心臓に負担になると単純に考えて水分摂取を制限する。特に利尿剤を処方する場合は薬剤の効果が減じるとされている。ただ、水分制限が腎機能の悪化を招く可能性もあり、本当に水分摂取制限が必要か最近疑問が提出され始めている。
この研究では障害度をそろえた500人の慢性心不全の患者さんをリクルートし、片方は従来通り水摂取を1500ml以下に制限、もう片方は自由に摂取させて3ヶ月後のKCCQ-OSSと呼ばれる生活の質評価を行っている。
結果は、両者に差はなく3ヶ月という短い期間ではあるが、慢性心不全の場合はわざわざ水摂取制限をする必要はないという結論になった。ただ、より高度な心不全の場合は全く別であることは申し添えておく。
次は高齢者の心臓血管障害での死亡率に日々の活動状況はあまり影響ないという論文で、フィンランド ユヴァスキュラ大学のグループが Medicine & Science in Sports and Exercise の4月号に掲載されている。
黄色でマークしたように、この研究はフィンランドで続いている双生児のコホートを使って、遺伝的に一致した条件で、様々な生活環境が様々な死因と関係するかを調べている。17年以上に及ぶ経過をフォローするうち、1195人の参加者が死亡し、そのうち389人の死亡が心臓血管障害による死亡と診断されている。これらの中から、同じ双生児ペアでも、運動など毎日の活動性に差がある人を比べてみると(コホート参加後の調査で、若いときの活動生は含まれない)、高齢になったあとでの身体的活動性はあまり死亡率に影響がなく、遺伝的な要因と、若いときの身体状況でほとんどが決まるという結果だ。高齢になっても適度な運動を私も推薦しているので、気になる結果だ。ただこれはあくまでも死亡率で、筋肉維持や生活の質向上にはやはり適度な運動は重要だと今も思って実践している。
最後は JAMA Neurology に4月7日オンライン発表されたフロリダ大学からの論文で、GLP-1受容体アゴニストやSGLT2阻害剤など、最近糖尿病薬として利用されるようになった薬剤がアルツハイマー病(AD) を予防するという最近の結果を再確認するために行われた研究だ。
この研究では OneFlorida+DataTrust に登録されている1700万人の中から50歳以上の2型糖尿病で治療を受けている人たち51960人を投与薬剤で分別したあと8年間追跡、ADを発症したかどうかを調べている。
結果はこれまでの研究と同じで、GLP-1受容体アゴニスト、SGLIT2阻害剤ともに服用者は、他の薬剤(例えばメトフォルミンなど)の服用者と比べると、ADになるリスクが3−4割低下する。
ただ、さらに服用年齢を65歳以上に絞ってみると、効果は低下し、逆転する場合もある。高齢者の場合ADリスクは痩せていると高まることが知られているので、体重を低下させるこのような治療は高齢者では慎重に行うべしというこれまでの結果を支持している。
いずれにせよ、これらの薬剤がなぜADリスクを減じるのか、正確なメカニズムオ解明が待たれる。
2025年4月20日
昨日に続いて、クローン性増殖から骨髄性白血病までの経路に関する論文を紹介する。今日紹介するオックスフォード大学からの論文は急性骨髄性白血病の分化を誘導して治療する方法の開発だが、昨日紹介したDNMT3a 変異によるクローン性増殖と繋がっている。タイトルは「Perturbing LSD1 and WNT rewires transcription to synergistically induce AML differentiation(LSD1とWnt経路の操作により急性骨髄性白血病の転写をプログラムし直して分化を誘導できる)」で、4月16日 Nature にオンライン掲載された。
白血病は分化能が抑えられた未熟細胞の増殖を特徴とするので、分化を誘導して治療することが試みられた。古くは京都大学ウイルス研教授だった市川先生がその後 CSF-1と呼ばれる分化因子を特定した1967年から始まる。そして最も成功したのがPML-RARα 転座を持つAPLの All trans retinoic acid 治療で、PMLの分解を促進する arsenic trioxide と組み合わせて白血病の治癒を可能にしている。
未熟幹細胞ブラストの増殖が特徴の急性骨髄性白血病 (AML) でも分化誘導治療は試みられてきた。若い人の場合骨髄移植が選ばれるが、高齢者になるとこれは難しいので、分化誘導治療は魅力的だ。現在行われているDNAメチル化阻害剤とBcl2阻害剤の組み合わせもこの中に入るのかもしれない。
この研究ではDNAメチル化阻害ではなく、ヒストンメチル化に関わるLSD1の阻害剤を軸に分化療法の開発を目指した。これまでの研究でもLSD1阻害剤がAMLの分化を誘導することが知られているが、これがAMLを抑えるまでには至っていない。そこで、LSD1阻害剤存在下で、さらにAMLの分化を誘導し増殖を抑える分子を探索し、最終的にWntシグナルに関わるβカテニンの安定化を促進するGSK阻害剤が強い活性を持つことを発見する。
さらに、AML白血病細胞を移植する実験系でLSD1阻害剤とGSK阻害剤を組み合わせると、白血病の増殖を抑え、マウスの生存を延長すること、そして投与により細胞が分化してCd11マクロファージマーカーを発現することを確認する。
次にメカニズムについて Atac-seq を用いたクロマチンレベルの解析を含む遺伝子発現解析を行い、LSD1阻害で発現してきた IRF7が安定化したβカテニンと強調して様々な遺伝子調節に介入することが、細胞の分化誘導に繋がることを発見する。
中でも、インターフェロンシグナルに関わるSTAT1の転写を誘導することが発見旧聞か誘導の大きな要因であることを特定している。ただ、他の分子の転写調節の変化もこの効果を後押ししていると考えられる。
最後に、患者さんから単離したAMLに対する効果を調べている。面白いことに、昨日紹介したDNMT3aの変異を持つ患者さん(調べたAMLのほぼ半数)ではこの治療法は効果を示すが、変異がないが場合はほとんど効かないことがわかった。また、この研究で特定されたインターフェロン、Wntシグナルがこの治療で最も影響を受けることも確認している。
以上が結果で、現在の治療に加えて新しい分化治療法の開発は、高齢者に見られるAML治療に最も大きな進歩だと思う。さらに、その効果がDNMT3a 変異AMLで最も強く見られることは、クローン性増殖とAMLをつなぐ大きなヒントになると期待している。