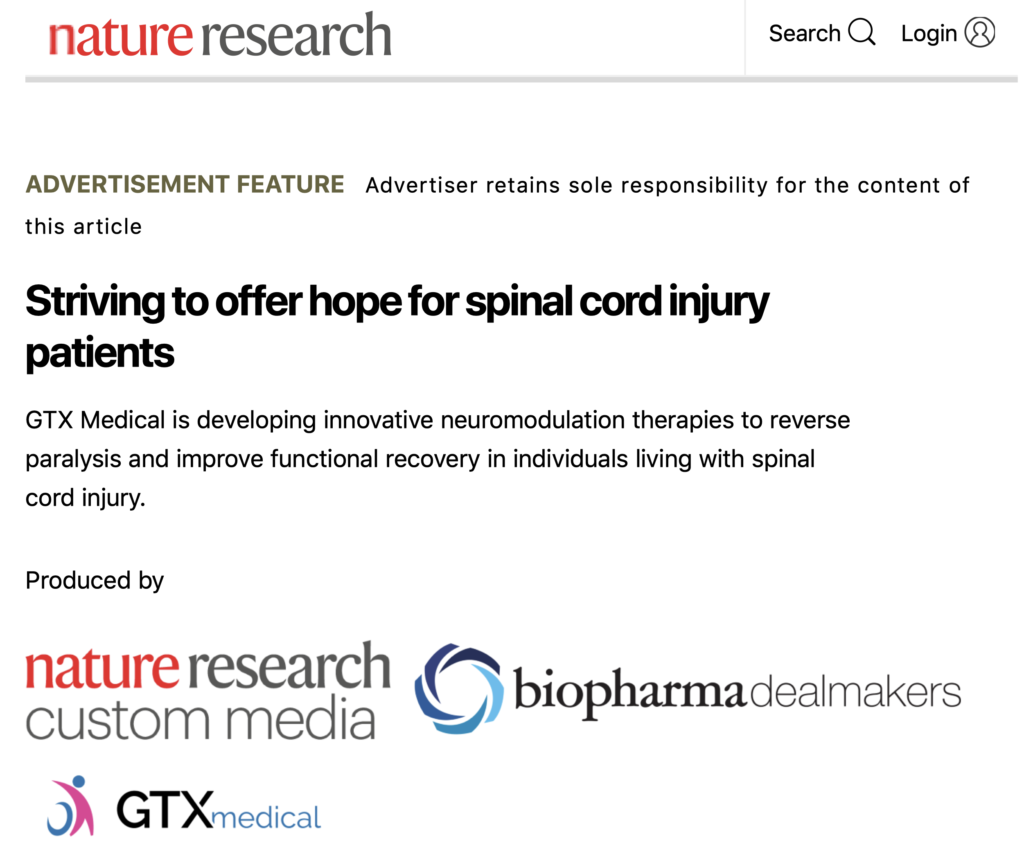2020年10月24日
ドーパミンはパーキンソン病との関わりがあまりに有名で、アセチルコリンによる興奮性シグナルを抑制してバランスをとっている運動機能をすぐ思い浮かべるが、実際にはセロトニンとともに私たちの気分の調節に深く関わっていることがわかっている。おそらくうまくいって満足感を得た時のドーパミン作動性「ご褒美回路」についてはほとんどの人が知っているのではないだろうか。ただご褒美回路という名前からも分かる様に、ほとんどの実験は褒美や罰で条件づけられた動物実験で、ドーパミン作動性、セロトニン作動性の神経を記録するという実験系から生まれた概念で、同じことが生きた人間で働いていることを証明できているわけではない。というのも、ドーパミン神経を選択的に記録する技術がこれまで存在しなかった。
今日紹介するロンドン大学と米国ウェークフォレスト大学からの共同論文は直接的ではないが、、間接的にドーパミンやセロトニンの反応を人間で記録する方法を開発して、動物実験の様に褒美や罰の条件付けが必要のない課題でのそれぞれの反応を調べた研究で12月9日号のNeuronに掲載される予定だ。タイトルは「Sub-second Dopamine and Serotonin Signaling in Human Striatum during Perceptual Decision-Making(感覚に基づく決断を行なっている時の秒以下の単位のドーパミン、セロトニンシグナルを人間の線条体で記録する)」だ。
しかし、生きた人間の脳でドーパミンやセロトニン反応をどの様に記録できるというのか?よく読んでみると、筆頭著者の一人Kishidaさんたちが2011年に発表した方法で、深部刺激治療を目的に線条体に挿入された電極を通して、ドーパミンやセロトニンの酸化を誘導し、この反応から生まれる電流を記録することで、ドーパミンなどの量を秒以下の単位で調べる方法だ。最初はドーパミン、その後セロトニンについても測定が可能になっている。しかし、決して直接測定しているわけではないので、動物実験を繰り返し、それぞれのニューロトランスミッターの変化のパターンを学習し、それに基づいて各トランスミッターの反応を推定している。
対象者は深部刺激電極を設置する手術を受けるパーキンソン病2名、突発性振戦の患者さん3名で、電極設置のタイミングで、設置前に指導した課題を、設置後繰り返させることで、課題を行っている間の、ドーパミン反応とセロトニン反応を見ている。
さて課題だが、多くの独立に動いているドットが、決められた方向に動いているかどうか判断する課題で、それぞれのドットが協調していることが認識できる場合は判断が簡単になるし、また動く方向が指定された方向からのズレが大きいほど判断は優しくなる。すなわち、ドットの動きに関する確信の感覚と、それぞれの動きから統計的に判断する過程を一つの課題の中で、分離して調べることができる。
さて結果だが、はっきりしているのはセロトニンの反応で、多くのドットが揃って動いた時には安心して低くなり、逆にバラバラに動いているため不安に感じる時は上昇する。しかし、ドーパミンの反応は感覚の確実性には全く左右されない。
一方、方向性を最終的に判断するプロセスについてはドーパミンとセロトニンは逆相関しているが、共に関係している。すなわち、すぐに決断できる場合は、ドーパミン反応が高まり、セロトニン反応は下がる。また、判断を間違った場合はどちらもあまり変化しないが、判断が正しかった場合は、ドーパミン反応が高まりセロトニン反応が低下する。
結果は以上で、感覚についての不安がセロトニン反応に反映していることを示せたのは、新しい発見の様だが、大体のシナリオはこれまで動物で行われた研究に近い気がする。いずれにせよ、深部刺激治療が進んだ今、ドーパミンだけでなくセロトニンについても正しく反応を調べて、患者さんの治療につなげる可能性が生まれた様に感じており、研究の進展を期待している。
2020年10月23日
腸内細菌叢が局所の免疫システムに大きな影響を与えることは広く認められ、健康な免疫システム確立のための様々な方法の開発が進められている。また、安倍首相の炎症性腸疾患の再発時に話題になった様に、腸内の炎症を鎮めるために、わざわざ便を移植するのも、免疫システムに細菌叢が大きな影響を持つと考えられているからだ。
今日紹介するカナダ・マクマスター大学からの論文は、腸内細菌が免疫系に作用する一つの経路が Aryl hydrocarbon receptor(AhR )を介している可能性を示した研究で10月21日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Aryl hydrocarbon receptor ligand production by the gut microbiota is decreased in celiac disease leading to intestinal inflammation (芳香族炭化水素受容体のリガンドが腸内細菌叢により合成されることで腸管の炎症に繋がるセリアック病を抑える)」だ。
AhRはダイオキシンの受容体として働いた悪いイメージがあるが、バクテリアなど外界で合成された有機物のセンサーとして働いていると考えられてきた。しかし、免疫システム調節機能や、血液幹細胞の自己再生を高めることがわかって、これらのシステムの操作法の開発に用いるための研究が進んでいる。今回腸炎をAhRで制御しようというタイトルを見て、なるほどとすぐ納得するぐらい重要なシステムだ。
これまでの研究でAhRは腸上皮のバリア機能を高め、炎症性サイトカインを抑えることが知られている。そこでまず、細菌叢のAhRリガンド合成の材料になることがわかっているトリプトファンを3ヶ月食べさせたマウスで、グルテンにより誘導されるセリアック病を抑えられるか調べ、トリプトファン食がT細胞の浸潤を抑え、上皮のバリアー機能を維持し、抗菌物質リポカリン2の分泌が抑えられることを示している。
そして、これがトリプトファンに適応した腸内細菌叢が、通常の細菌叢と比べて多くのAhRリガンドを合成することによることを示している。元々グルテンを投与した腸内では細菌叢の変化が起こるが、トリプトファンに適応した細菌叢はグルテン投与でもAhRリガンド合成能を維持できることもわかった。
一方、トリプトファンが私たちの細胞で代謝されると、AhRの機能を抑えるキヌレニンが合成されるが、腸内細菌叢がトリプトファンに適応することで、私たちの細胞の代謝に回らないため、炎症を高めるキヌレニンの合成は低下するという効果もあることを明らかにしている。
トリプトファンの話はここまでで、あとはトリプトファン合成能を高めたロイテリキンを投与すると、トリプトファンを摂取させるのと同じ効果があること、そして当然ながらAhRのリガンドを投与することでも同じ様に炎症が抑えられることを示している。すなわち、トリプトファン食の効果は、トリプトファンからAhRリガンドを合成できるバクテリアの作用であること、そして炎症が外因性のAhRリガンドで抑制されていることを示している。
最後に、人間のセリアック病の患者さんの便を調べ、AhRリガンドの合成が低下していること、逆にキヌレニンのの量は上昇していること、そしてその結果AhRの活性が低下していることを明らかにしている。
以上単純だが、なるほどと納得できる研究だ。ぜひ、セリアック病だけでなく、腸管の慢性炎症治療の方法開発に至ることを期待する。
2020年10月22日
今回の新型コロナウイルス治療で今最も注目が集まっているのは抗体療法だが、この方法の問題はコストだ。化学合成できる化合物とは異なり、細胞に抗体を作らせ、それを精製する必要がある。当然様々な規制をクリアして、静脈に大量駐車しても安全な抗体を薬剤として届けるには、儲けがないとしてもコストは覚悟する必要がある。
抗体薬のコストを下げるための一つの可能性は、抗体を飲んで摂取することだ。抗体自体は、遺伝子操作をした牛からミルクとして回収することができる。もしミルクの中の抗体を飲んで摂取できれば、コストは今の抗体薬の100分の1にまで下げられるだろう。ただ、問題は飲んだ抗体が体の中に入るのは、乳児期だけで、私たちの腸管上皮にも抗体を取り込む能力は残っているが、胃と十二指腸を通ることで、抗体自体の活性を保つことができないため、この夢は実現できない。
今日紹介するオスロ大学からの論文は、粘膜上皮を通して大きな分子を体内に導入する方法の開発についての研究で、10月14日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「An engineered human albumin enhances half-life and transmucosal delivery when fused to protein-based biologics (遺伝子操作した人間のアルブミンは、他のタンパク質と結合させると血中の半減期と上皮を通したデリバリーを高めることができる)」だ。
読んでみると、驚くほどの話ではないが、上に述べた様に、抗体を食べることができればいいなと考えている私にとっては、学ぶところの多い論文だった。まず、粘膜を通して抗体を摂取する時に必須のFcRn受容体は、ほとんどの粘膜上皮に発現しており、腸管だけではないことを知った。
次に同じFcRnが抗体だけでなく、アルブミンも輸送する能力を有しており、実際にはアルブミンの輸送の方がずっと効率が高いこともよくわかった。
以上を確かめた上で、この研究ではヒトFcRnで置き換えたマウスモデルを用いた、経鼻的に投与したアルブミンを肺から吸収するという実験系を作り、アルブミンを体内に摂取するための条件を探索している。消化管と違い、投与できるタンパク質の量は限られており、それでも絶対量でマウス当たり、20〜50μg、人間にすれば100mgが投与できて、なんとそのうち7〜8割が体内に摂取できるという結果だ。
次にこの効率をさらに上げるために、アルブミン遺伝子に突然変異を導入し、正常のアルブミンと比べて4倍以上粘膜から移行できる、3箇所のアミノ酸が変化したQMPアルブミン開発に成功している。また、取り込みが高いだけでなく、血中での半減期も高まっている。
最後に、QMPアルブミンに、半減期が極端に短い血液凝固の第七因子を融合させ、体内に摂取できるか調べ、体内に移行するだけでなく、半減期も約3日に延長していることを示している。
これにより血友病を治療できるかどうかまでは確かめていないので、評価は難しいが、人間にして100mgぐらいのタンパク質を、血管ではなく粘膜を通して投与できることは、抗体の含まれたミルクを飲んで病気を治すという可能性が現実になることを示したと思う。
2020年10月21日
焦点を絞らず論文を読んでいると、よくこんなことを考えるなと感心する、想像もしなかった着眼点の研究に驚かされることが多い。今日紹介するバルセロナの医学生物学研究所からの論文はそんな例で、細胞内に形成されている脂肪滴が、代謝の調節だけでなく、細菌感染の第一線防御機能として働いていることを示した研究10月16日号のScienceに掲載されている。タイトルは「Mammalian lipid droplets are innate immune hubs integrating cell metabolism and host defense (哺乳動物の脂肪滴は細胞の代謝とホストの防御を統合するハブとして働く)」だ。
一般的に着眼点がユニークな研究は最初から仮説に基づいて進められる。この研究では細菌感染の代わりにマウスにLPSを投与、これにより自然免疫と脂肪代謝変化を誘導した後、肝臓の脂肪滴を取り出し、そこに存在するタンパク質を大腸菌の培養に加えて、細菌毒性をまず調べている。
結果だが、LPS投与により肝臓での脂肪滴の数は上昇するとともに、大腸菌を殺す活性が高まっている。また、脂肪を取り込ませて脂肪滴の数が増えた人のマクロファージと大腸菌を混合培養した場合も、同じ様に大腸菌を殺す活性がある。この時大腸菌を取り込んだマクロファージを見ると、大腸菌の周りに脂肪滴が近づいて接着していることを確認する。以上の様に、自然免疫が活性化されると脂肪滴がまず細菌の防御の第一線として働くという仮説が確かめられたことになる。
次に脂肪滴による細菌毒性の分子機構を探索すべく、定量的質量分析を用いてLPSで活性化した脂肪滴と、正常の脂肪滴を比べると、驚くべき数の分子発現が変化していることを示している。この様に多くの分子が変化する場合、結局個人の好みで焦点を絞る必要があるが、このグループは脂肪代謝と自然免疫が持つ矛盾点、すなわち脂肪はミトコンドリアの酸化的リン酸化を高めるが、自然免疫では嫌気的解糖が進むというこれまで結果に着目し、細菌の感染は脂肪滴とミトコンドリアとの関係を断つことで、この両方の課題を克服しているのではと仮説を立て、LPS投与により起こる代謝変化がこの可能性を支持していることを確認した後、ミトコンドリアと脂肪滴を繋ぐ重要な分子PLIN5に着目して研究を進めている。
結論ありきの論文だが、結果は見事で、LPS刺激によりPLIN5の発現が低下し、その結果ミトコンドリアと脂肪滴との接着が低下する。このLPSによる脂肪滴とミトコンドリアの接着の減少はPLIN5を強制的に発現させると消失する。逆に、PLIN5発現が高いと、バクテリアと脂肪滴とのコンタクトが減る。
この変化に呼応して、PLIN2が脂肪滴に発現することで、以前紹介したViperin(https://aasj.jp/news/watch/13949 )や抗菌ペプチドcathelicidinなど自然免疫誘導時の細菌毒性に関わる様々な分子が脂肪滴表面に集まってきて、ミトコンドリアから離れた脂肪滴が抗菌オルガネラへと変換することを示している。
結果は以上で、ミトコンドリアも細菌の一種と考えると、元々細菌とコンタクトして代謝を助ける役割を持っていた脂肪滴を、感染時に臨機応変にリプログラムして、抗菌オルガネラに帰るという面白い話だ。ただ読んでいて、結論へと導かれる気がするのも事実で、感動したという話にはなりにくい。
しかし、先日紹介した細胞の形態を核が感知するという話も、この論文も面白いと読んでみた研究がスペインからの論文だと知ると、研究にも民族性があることを感じる。
2020年10月20日
腸内細菌叢が直接自律神経系を刺激して、中枢神経系に影響を及ぼすことは、一般的に認められる様になっているが、腸管はこの様な自律神経系の支配とともに、神経堤から移動してくる、粘膜下のマイスナー、筋層のアウエルバッハ、腸管固有神経叢の支配を受けており、これらも当然腸内細菌叢の影響下にあると考えられる。
今日紹介するロックフェラー大学からの論文は腸管各領域の腸管固有神経叢を分子マーカーで詳しく分類し、それぞれの集団と腸内細菌叢との関係を調べた力作で10月16日号のScienceに掲載された。タイトルは「Microbiota-modulated CART + enteric neurons autonomously regulate blood glucose (腸内細菌叢により変化したCART陽性腸管神経は自発的に血糖を調節する)」だ。
この研究では、腸管固有層の神経叢の領域による多様性を手がかりに、この多様性に腸内細菌叢が関わるかどうかの検討から始めている。まず、生体内で新たに転写が始まった遺伝子の転写を神経特異的に調べる方法を用いて、特に神経ペプチドの発現の違いなどで特定できる局所的な多様性が存在し、この多様性のかなりの部分が、局所の細菌叢の量や質の違いによって決まっていることを突き止める。
加えて、細菌叢が存在しないと腸管固有神経自体の数も低下することがわかった。この神経細胞減少は、細菌叢移植により元に戻ることから、細菌からのシグナルが神経細胞の生存に必要で、このシグナルがないと細胞死のエフェクターCasp11依存性に、神経細胞が死ぬことを確認している。そして、この一部は、腸管を出て肝臓や膵臓の自律神経とシナプス結合を有することを発見する。
この様にして、各領域の腸管固有神経特異的な分子マーカーを確立したあと、回腸の固有神経細胞が発現しているCART遺伝子座を操作し、細胞特異的に刺激やが可能なマウスを作成し、腸管固有神経を外的に興奮させる実験を行なっている。驚くことに、CART陽性神経興奮が続くと、血糖が上昇し、インシュリン分泌の低下が見られること、そしてこれは腸管固有神経から腸管外へと伸びたシナプス結合により、肝臓での糖新生が調節されているためでであることを明らかにしている。
逆に、腸管固有神経細胞維持に必要な細菌叢を抗生物質投与で除去すると、腸管神経細胞が減少し、この結果肝臓への刺激伝達が欠損するため、血糖の低下が見られることを確認している。しかし、細胞死に関わるCasp11が欠損したマウスでは神経細胞死が起こらないため、血糖の低下は起こらないことも明らかにしている。
以上が結果で、細菌叢はその腸管固有神経細胞の維持と多様化に大きく関わっており、特に回腸のCART陽性神経細胞は、興奮により肝臓での糖新生を高めることで、血中のグルコースレベルを維持しているとするシナリオを提案している。少し複雑だが、腸内固有神経細胞というニッチを標的にした面白い力作だと思う。
2020年10月19日
トランプ大統領が、リジェネロンのCov2に対するモノクローナル抗体投与を受け急快復したことを宣伝しているが、快復者からの抗体による治療論文などから判断すると、本当に2〜3日で症状がほとんど取れる場合があることは理解できるし、おそらくモノクローナル抗体を用いた治療治験でも同じような結果が出ていることを背景に、投与に踏み切ったのだろう。折しも、FDAがエボラウイルス感染症に対する最初の治療法として、やはりモノクローナル抗体を認可したという報告が出ていた。実際、レムデシビルも参加したエボラウイルス感染症の治験で有効とされたのがモノクローナル抗体だけだったことも記憶に新しい(https://aasj.jp/news/watch/11936 )。
このようにモノクローナル抗体に対する期待は高いが、更に高い効果を持つ抗体治療が可能であることを示す論文がロックフェラー大学Fc受容体研究の大御所Ravechの研究室から10月8日号のNatureに掲載された。タイトルは「Fc-optimized antibodies elicit CD8 immunity to viral respiratory infection (Fc領域を至適化した抗体はウイルスによる呼吸器感染に対するCD8免疫を誘導できる)」だ。
この研究では、致死量のインフルエンザウイルスを感染させたマウスにモノクローナル抗体を投与して、その治療効果を確かめる単純な実験系を持ちいている。この時、インフルエンザに対するモノクローナル抗体を、抗原特異性はそのままに、4種類のFc受容体に対する結合活性が違うようにFc部分を操作した人工抗体を作成して比べることで、抗体治療時のFc受容体の活性の差を調べている。更に、実験には全てヒトFc部分を持つ抗体を用いており、これに対応するマウスの方のFc受容体も、全てのマウスFc受容体を人のFc受容体で置換え、また発現パターンも人に近づけたマウスを用いることで、マウスでの研究結果がすぐに人間に応用できるよう計画されている。
驚くべき結果で、FcγRIIaに対する結合活性が高い抗体を4時間前に前もって投与していたマウスは全例生存したが、同じ中和活性を持つ抗体であるにもかかわらず、FcγRIIaに対する結合活性が低いFcを持つ抗体では半分以上のマウスが死亡し、更にFc受容体と全く反応しないFcの場合は、全く効果が見られないことが明らかになった。また、結合する抗原決定基を変えて同じ実験を行っても、結果は全く同じである事を確認している。
おそらく、試験管内の感染実験で中和活性を調べれば、差はほとんどないと考えられるので、生体内での抗体の抗ウイルス活性は、中和活性だけで単純に決められないことを示唆している。
では、この差が生まれるメカニズムは何か?感染の場である肺について様々な細胞の性質を比べ、FcγRIIaに高い結合活性を持つ抗体を前投与した場合のみ、CD40を発現した成熟した樹状細胞が肺で上昇していること、そしてその結果肺内に多くのCD8陽性細胞が誘導されることを発見した。すなわち、FcγRIIaが感染時に存在することで、まずウイルスと結合した抗体がFcγRIIa を発現するDC1樹状細胞を活性化し、その結果CD8キラー細胞がウイルスに対して誘導できることを示している。
以上の実験は全て感染前に抗体を投与する設定で行っているが、抗体による感染の悪化ADEの可能性を確かめるために、感染後3日目に抗体を投与する実験も行い、やはりFcγRIIaとの結合を高めたFcを持つ抗体だけがマウスを投与量依存的に治すことが出来ること、また基本的にはADEの発生は見られないことなどを明らかにしている。ただ、感染が成立した後の抗体投与量は、予防的に効果がある量の20倍必要であることも示している。
以上、全てインフルエンザウイルス感染モデルでの研究だが、
まず、抗体の治療効果はウイルス感染を中和する活性だけで決まらない事。 Fc受容体の活性化により、初期から感染局所でキラー細胞が誘導され、ウイルス増殖抑制に大きく貢献すること。 予防的抗体が、感染を防ぐだけでなく、抗原による細胞性免疫に誘導して、ホストの免疫を誘導するのに役立つ事。 例えば、低容量の抗体を投与した後に弱毒化ウイルスワクチンを投与するプロトコルも考えられること。 など、抗体による感染症の治療を考える時学ぶ点は多かった。
もちろんいくらヒトの遺伝子に置き換えているからといって、マウスモデルの研究でこの結果をそのまま人間、更にはCovid-19に当てはめることはできないが、免疫系の複雑さを示すとともに、抗体に様々な問題が存在しても、それを改善していくための多くの知識が蓄積していることがわかった。
2020年10月18日
我々の細胞は押し合い圧し合いのラッシュアワー状態で存在しており、その中で自分の位置を全体に合わせてうまく変化させ、スペースを埋める必要がある。この外的な圧力を感知して細胞の形態を変化させるメカニズムについてはほとんどわかっていない。
今日紹介するスペイン・バルセロナの国立光学研究所からの論文は細胞をひしゃげさせたときに核で始まる細胞の活性化を細胞学的に解明した研究で10月16日号のScienceに掲載された。タイトルは「The nucleus measures shape changes for cellular proprioception to control dynamic cell behavior (核が細胞の形態変化を測って細胞運動の動態をコントロールする固有の受容感覚として働く)」だ。
細胞生物学の典型的プロの仕事で、適切なパラメーターを使って細胞を適切に見ること、細胞内の調節機構に熟知して、適切に阻害剤を選んで分子経路を明らかにすること、そして細胞自体を厳密にコントロールする技術を持つこと、と三拍子が揃っている。
もちろん課題も明確で、細胞を圧縮したときミオシンIIの活性化を媒介とする細胞形態の変化が起こるメカニズムの解明だ。
研究ではミオシンIIを可視化した細胞を用いて細胞に圧縮操作を加えたとき、ミオシンIIが活性化され細胞の収縮活性が高まる。この速やかで長く続く変化が、核が引っ張られ、核内膜が展開することと相関することを発見し、この核膜に始まる細胞運動の活動活性化過程を解明している。
分子阻害剤を駆使した経路研究が詳細に行われているので、全てをすっ飛ばして結論をまとめると以下の様になる。
細胞が圧力を受けて核内膜が展開すると、これを感知してphospholipase A2(cPLA2)が核膜と結合して、一種のカルシウム依存性のメカのセンサーを作る。 PLAにより合成されるアラキドン酸によりミオシンIIが活性化される。 この核の形態の変化は、小胞体と核膜が接近してSTIM-Orai分子が濃縮されることによる、細胞内のカルシウム濃度の上昇と強調しており、これにより受動的な形態変化を、他の原因、例えば細胞が膨大するといった変化を区別して、細胞活動とリンクさせる。 まとめてしまうと結論は簡単になったが、実際には知識がないとなかなかついていけない、しかし細胞の形態を考える上で重要な発見だと思う。
2020年10月17日
光遺伝学や、光を使った神経記録により、脳科学は大きく変革した。ただ、このシステムで明らかになるのは、基本的には神経ネットワークの詳細で、このネットワークの活動を維持し調節している分子機構は、別の方法で探す必要がある。従って、神経ネットワークに関わる分子機構の解明には、ある行動に関わる神経を特定し、その遺伝子発現から機能と相関する分子候補を特定し、CRISPRなどを用いたreverse遺伝学で分子と機能の相関を詰めていくのが現代の方法だ。
と思っていたら、ロックフェラー大学のグループが、非近交系のマウスの機能的変化を捉えて分子を調べる古典的なForward遺伝学を近代的脳科学と組み合わせた面白い論文を発表したので紹介する。タイトルは「A Thalamic Orphan Receptor Drives Variability in Short-Term Memory (視床のリガンドが特定されていない受容体が短期記憶の多様性を発生させる)」だ。
この研究では5種類の純系マウスと、野生種を系統化した3系統をそれぞれ掛け合わせて得たF2をランダムに交配して得た非近交系マウス100個体についてT字迷路を用いた短期記憶テストを行うと、期待通り検査成績が大きく変動している。あとは、人間集団で行なうゲノム検査と同じGWAS検査を行い、スコアと相関するSNPを探した結果、5番染色体のSmart1と呼ぶ多型座を特定することに成功する。
次にこの多型が記憶力を反映しているか確認したあと、この多型の本体を明らかにする段階に入るが、人間とは違って脳組織での遺伝子発現をそれぞれの多型で調べることが簡単なので、まずSmart1遺伝子座に存在する遺伝子の、各脳領域での遺伝子発現と記憶力の相関を調べ、最終的にSmart1座に存在し機能的に記憶力と最も相関する遺伝子としてGpr12として知られる、リガンドは特定されていないG共役型の受容体を特定する。
さらに、Smart1座の多型により、Gpr12の視床での発現量が2.5倍の差があり、発現が高いほど記憶力が良いことを確認する。
あとは、迷路行動中のカルシウム流入を様々な領域で調べる回路解析を行い、Gpr12の発現量と相関して、記憶の獲得および維持過程での視床と皮質の興奮の同調性が高まることを明らかにしている。神経生理学的実験から、Gpr12がグルタミン誘導性のカルシウム反応を高めることが示されており、おそらく神経の活動閾値をGpr12が調節し、前頭皮質と視床の回路を同期させているのだろう。
以上が結果で、形質の差を見つけて、その遺伝的背景を特定することで、正常過程の解析からだけではわからない機能を明らかにするforward遺伝学が今も役に立つことを示した面白い研究だと感じた。今後Gpr12の発現や機能を標的にすることで、記憶障害治療にもつながるのではと期待している。
2020年10月16日
以前、 論文紹介で「脊髄損傷治療の大きなステップ」と、ローザンヌ大学からNatureに報告された、硬膜外電気刺激をコントロールして脊髄損傷患者さんの運動機能を取り戻す方法の開発について紹介した (https://aasj.jp/news/watch/9166 )。慢性の脊髄損傷患者さんが、5ヶ月程度の比較的短いリハビリは必要だが、自分で歩行できるようになったという研究で、そこで示されたビデオ映像( https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-018-0649-2/MediaObjects/41586_2018_649_MOESM8_ESM.mp4 )は衝撃的だった。
この記事では、この技術を開発した研究者たちが大学からスピンオフして、GTXmedicalという会社を立ち上げ、2024年の認可を目指して、来年から治験をはじめること、またこの技術がFDAの画期的デバイスとして認められたことを報告している。
いよいよ慢性期の脊髄損傷を対象にした治療法の治験が行われることになり期待したいが、我が国でもはやく治験ができることを期待したい。
2020年10月16日
ダウン症候群は21染色体の数が3本に増えることによる病気で、知能の発達遅延とともに、様々な身体症状を伴う。この様に病気の原因がはっきりしていても、発症メカニズムは複雑でまだまだわからないことは多いが、トリソミーによるタンパク質合成の変化で細胞内にストレスがたまり、変性や炎症が起こることが引き金になっているのではと考える研究者は多い。その結果、直接このストレス反応を標的にした薬剤治療の可能性も示唆されてきた(https://aasj.jp/news/watch/11744 )。
今日紹介するイタリア工業研究所からの論文はマウスモデルではあるが、ダウン症候群の神経症状の一部がミクログリア異常活性化により誘導され、この過活性を是正することで症状を改善させる可能性を示した研究で12月9日号のNeuronに掲載される予定だ。タイトルは「Rescuing Over-activated Microglia Restores Cognitive Performance in Juvenile Animals of the Dp(16) Mouse Model of Down Syndrome (過剰活性化されたミクログリアを是正することでマウスダウン症モデルDp(16)の認知機能を改善できる)」だ。
このマウスで使われたのは人間の21番染色体に相当するマウス16染色体の一部を重複させたモデルマウスで、ダウン症では110〜150遺伝子が重複するのに対して、113種類の遺伝子が重複しているモデルで、炎症やミクログリアに関わる遺伝子はほぼ全て共通して重複している。
この研究では最初からダウン症による脳内のミクログリアの変化に注目して研究を行い、様々な指標で見たときにダウン症モデルマウスの脳内ミクログリアが過剰活性していること、そして1型インターフェロン刺激下流の分子を中心に発現が上昇していることを発見する。
そこでミクログリアの数を減らす目的でCSF-1の機能を阻害する薬剤を投与すると、脳内のミクログリア数が低下するとともに、シナプスのスパイン形成が正常化し、並行して認知機能も改善することを示している。
ただ闇雲にミクログリアを除去するというのは問題が多いので、次にこれまでも示唆されてきた炎症を抑えるCox2阻害剤acetaminophenでミクログリアの活性を抑えられないか調べ、acetaminophen投与でミクログリアの活性化が抑制され、認知機能も改善することを示している。
元々acetaminophenはCox2を抑えて、炎症メディエーターであるプロスタグランディンを抑えるのだが、この研究では炎症だけでなく、ミクログリアのメカのセンサーTrpV1にも働いてミクログリア特異的に活性化を抑える可能性も示している。
そして、acetaminophenの作用メカニズムがインターフェロン刺激によるサイトカインの発現抑制、それによるスパイン形成阻害の解除などを介していることを示しているが、詳細は省いていいだろう。また、この効果は決してDp(16)モデルに限らないことも示している。
以上、ダウン症の認知障害の一部を、ミクログリアの活性化を抑制することでh治療する可能性が示され、薬剤の候補としてCox2阻害剤とともに、TrpV1阻害剤が特定できたことがこの研究のポイントだ。では、実際のダウン症の認知機能低下の治療は可能なのだろうか?
この研究では成人後のダウン症の剖検例を調べ、確かにミクログリアの活性化が起こっていることを確認し、副作用の問題さえ克服できれば、大人になった後でもミクログリアを標的として認知機能低下を治療できる可能性を示唆している。
今後、発達期の介入も含めて、ミクログリアを標的にするダウン症治療の薬剤治療が開発されることを願う。