長年開発が難しかったRASに対する標的薬も、G12C変異特異的な sotolasib をきっかけに、他の変異もカバーできる panRAS標的薬が治験段階に入るなど、実用が期待される段階に入った。今日は、まだ実験段階の新しいRAS標的薬についての論文をいくつかまとめて紹介する。
まず最初のテキサスMDアンダーソン研究所からの論文は、pan-RAS阻害薬の効き方について調べるとともに、今後の治療戦略の方向性を考えた論文で、9月3日 Science Translational Medicine に掲載された。
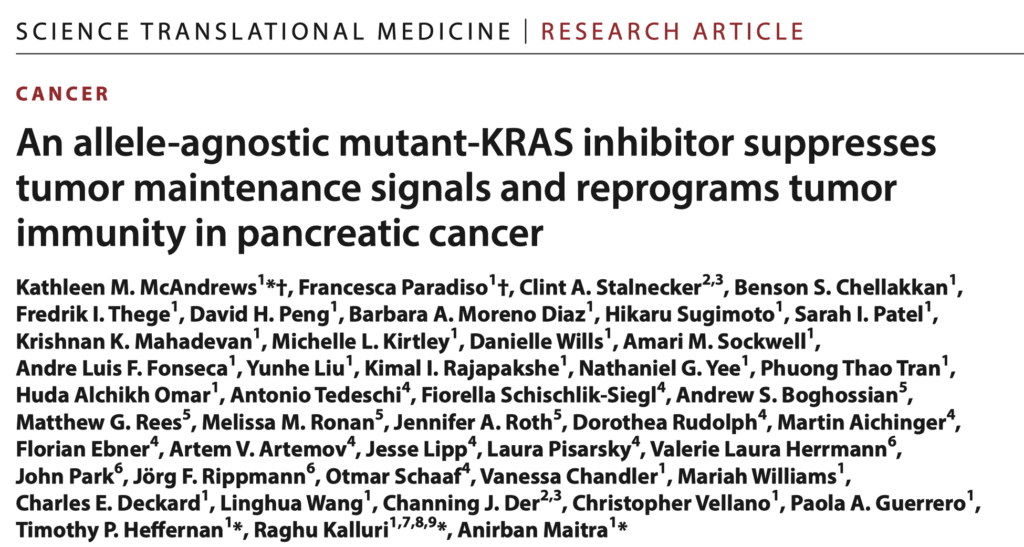
研究では様々な膵臓ガンモデルを用いて、pan-RAS阻害剤の一つ BI-2493 の効果を調べている。KRAS のG12D変異に対する効果が最も強いが、他の全てのタイプの変異に対して効果を示すとともに、正常RASに対する効果もある。この部分が、変異タイプ特異的な薬剤と違っており、検討が必要になる。
効果だが、細胞周期の進行を抑えるとともに、間質型から上皮型への転換を誘導し、さらに代謝的にグリコリシス優位から、ミトコンドリアでの酸化的リン酸化優位へと転換する。
様々なマウスモデルを用いて調べると、pan-RAS阻害薬はガンの周りの間質形成を抑えるとともに、キラーT細胞の浸潤を高める。その結果、PD-1抗体によるチェックポイント治療の効果を高める。実際、pan-RAS阻害剤も当然耐性が生まれてくるが、免疫を維持できればこれを乗り越えられる可能性が出てくる。また、耐性を持つガン細胞はYAP経路の活性が上がるので、現在治験中のYAP阻害剤との併用が期待できる。
以上、すぐ始まる臨床応用を念頭に、モデル系で徹底的に調べることがいかに重要かがわかる。
次はフレデリックガン研究所からの論文で、薬剤開発までは至っていないが、新しい薬剤開発の方向性を示す重要な論文で、9月11日 Science に掲載された。
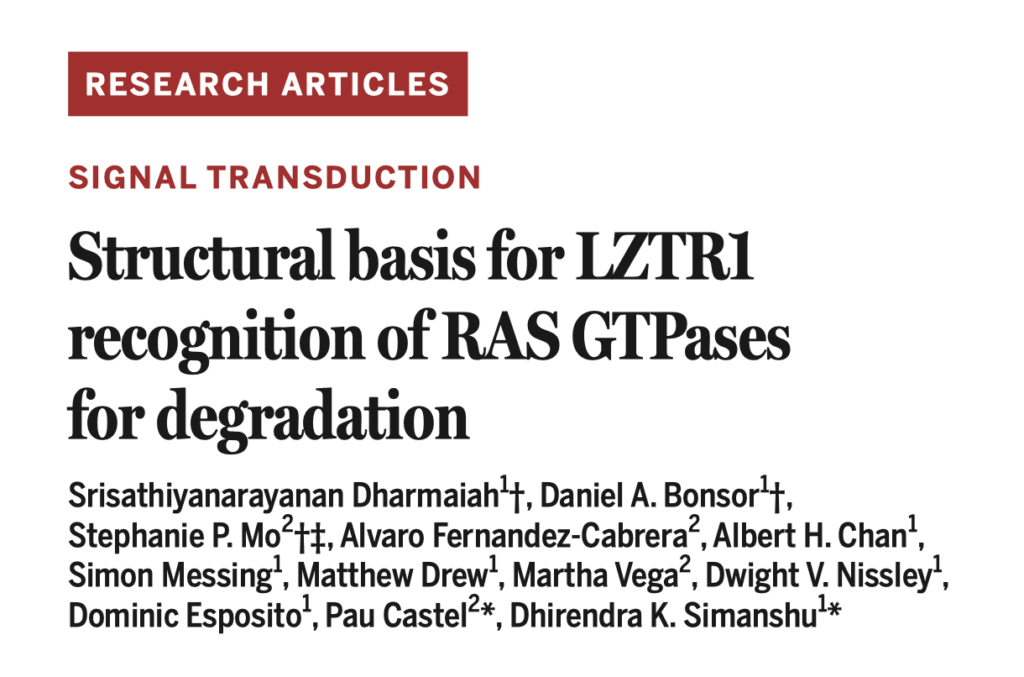
以前、VHLユビキチンリガーゼをRASにリクルートして分解させるプロタック薬剤について紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/25247)、この研究もこの方向性を狙っている。ただ、RAS本来のタンパク量を調節しているユビキチンリガーゼをRASにリクルートするアダプター分子LZTR1とRASの結合を構造的、更には突然変異導入をとおして解析して、両者が結合する領域をピンポイントで特定し、今後この部位をより強く LZTR1 と結合しやすくするプロタックを開発するための基盤を提供している。
構造研究なので詳しくは述べないが、LZTR1 やそれと結合する RIT1 の変異は、シュワン細胞種が頻発し、ガンになりやすいことから、本来のRASのタンパク量調節因子と知られていたので、より自然の系をプロタックに用いる新しい治療開発へとつながる可能性がある。
最後に紹介する英国クリック研究所からの論文はRASシグナルの重要な柱PI3KとRASの結合を標的にした、共有結合型阻害薬の開発で、これまでのRAS標的薬と併用することでより長期の効果を期待できることを示した研究で、10月9日 Science にオンライン掲載された。
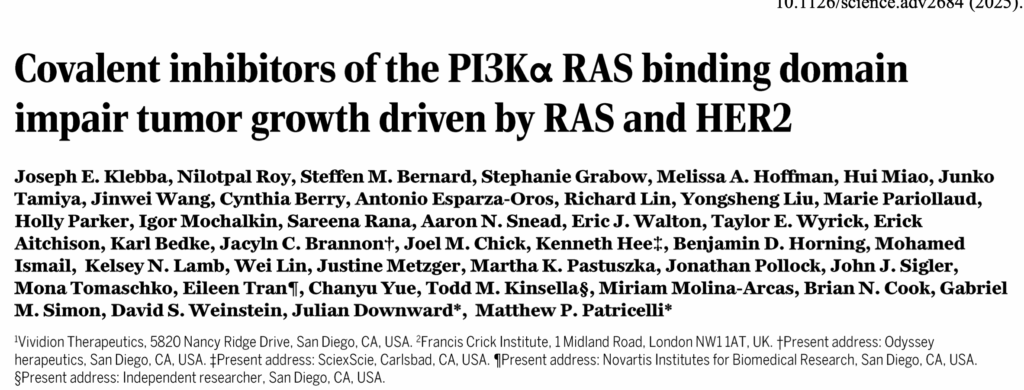
標的のシステイン残基を用いて共有結合できるリガンドは、安定に標的と結合するので高い効果が期待できる。G12Cを標的にした sotolasib もその一つだ。この研究ではPI3KのRAS結合サイトに存在するシステインを狙った薬剤を探索し、最終的にVVD-442という化合物を突き止めている。
試験管内、マウスモデルを用いた研究から、これはRASとPi3Kの結合を特異的に阻害し、RAS依存的なガン細胞の増殖を抑える。特にG12Dに効果が高いが、逆に sotolasib の標的になるG12Cの効果は低い。また、RASとは無関係にEGFRによるPI3Kの阻害効果を持つが、インシュリンリセプターによるPI3Kの活性化は抑制されないため、糖代謝への影響はほとんどない。
マウスへのガン移植モデルで高い効果を示すが、panRAS阻害剤と比べると効果が低い傾向がある。もちろん panRAS阻害剤でも耐性が発生するが、両者を組み合わせると100日間全く耐性なしに腫瘍を抑えられることを示している。
この論文以外にも今年の7月同じシステイン残基を標的にした薬剤開発が報告されており、この戦略もRAS依存性ガンの重要である事がわかる。
以上RASの制御研究が加速しており、特に治療の難しい膵臓ガン治療を大きく変えてくれることを期待する。



