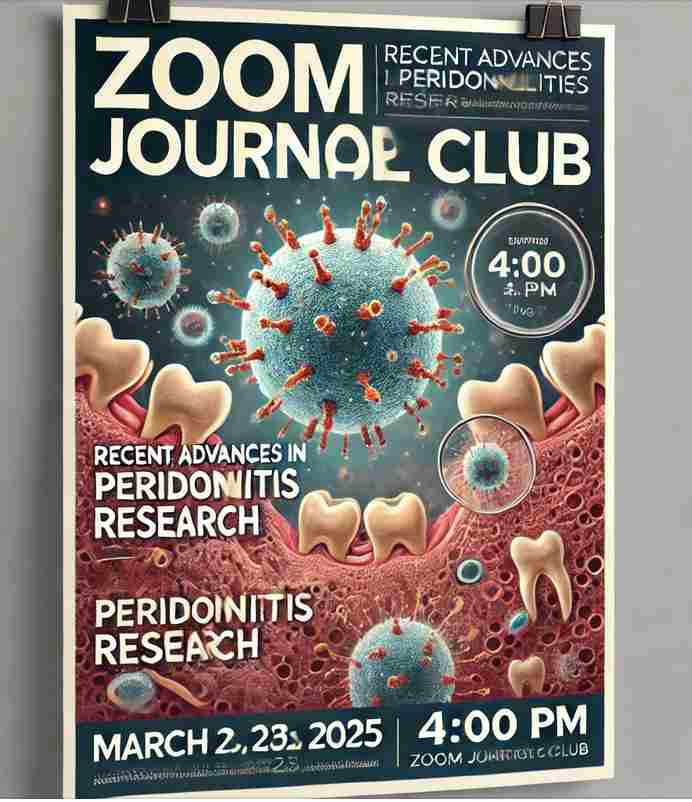2025年3月15日
Covid-19パンデミックが始まった当初、子供がかかっても軽症で終わるとされていたが、唯一例外として感染後1−2ヶ月後に極めて重症の全身の炎症が起こることが報告され、川崎病に似ているので注目を集めた。この原因を巡っては様々な研究が行われ、IL-1 などの炎症性サイトカインのストーム、特定のV遺伝子を持つ T細胞の増加、マクロファージの活性化など、様々な現象が報告されたが、一つのシナリオにはまとまっていない。
今日紹介するドイツ ベルリン シャリテ病院とドイツ リュウマチ研究所を中心とする国際チームからの論文は、小児 Covid-19 関連多系統炎症性症候群 (MIS-C) の患者さんから得られる様々なピースと試験管内実験を合わせて MIS-C の発症機序について説得力のある仮説を提案した研究で、3月12日 Nature にオンライン掲載されている。タイトルは「TGFβ links EBV to multisystem inflammatory syndrome in children(TGFβ が EBウイルスを小児の多系統炎症性症候群と結びつけた)」だ。
この研究では MIS-C の患者さんの血中サイトカインを、軽傷の Covid-19 患者さんと比較し、特に TGFβ の血中濃度が上昇していることを発見する。TGFβ は T細胞のキラー活性を低下させることが知られているので、これを MIS-C を攻める糸口として研究を進めている。
次に血液細胞の変化を見ると、ほとんどの細胞系列で TGFβ 刺激による遺伝子発現が誘導されているのがわかる。しかし、最も大きな影響が見られるのは T細胞で抗原刺激を受けたばかりの T細胞の増殖が誘導されている。しかし、試験管内での反応を調べると、T細胞のキラー活性は予想通り強く抑制されている。この変化は、TGFβ に対する抗体で元に戻る。以上から、Covid-19 感染が重症化する過程でまず TGFβ の分泌が上昇し、これが T細胞を中心に免疫系へ影響を及ぼし、特にウイルスを除去する T細胞反応が低下した状態が形成されることになる。
次はこの状態から全身の炎症が誘導されるメカニズムだが、著者らはこれまで知られている特定の V遺伝子を持った T細胞の増殖に鍵があるのではと考え、この V遺伝子により認識される抗原を探索している。もちろんただ闇雲に探索したのではなく、感染症が重症化するとき、身体の中に潜んでいたウイルスが再活性化され、これが全身性の炎症を誘導していると仮説を立て、EBウイルス、サイトメガロウイルス、はしかウイルス、アデノウイルスに対する V遺伝子を調べべ、最終的に EBウイルスに対する V遺伝子が MIS-C で上昇する V遺伝子と重なること突き止める。
とすると、感染後 TGFβ が上昇する過程で、内因性の EBウイルスが再活性化されると予想される。そこで、MIS-C の患者さんの血清、B細胞、あるいは血清などを詳しく調べ、MIS-C患者さんで、血清中抗EBウイルス抗体とともに、EBウイルスが上昇していること、また大人の重症化した Covid-19 でも同じように EBウイルスが血中に検出できることを明らかにしている。
結果は以上で、EBウイルスが活性化されることで全身の炎症が誘導されるまでの過程は、当然起こることとして処理されている。この点をそのまま認めるとすると、この研究により以下のシナリオが完成したことになる。
Covid-19 が持続すると、TGFFβ が上昇し、特に T細胞のキラー活性が抑えられる。これは Covid-19 をさらに重症化させるとともに、それまで抑えられていた内因性EBウイルスの再活性化を促し、この結果全身性の炎症へと発展し、MIS-C が発症するというシナリオだ。
実際には世界中のコホート研究をまとめて研究が行われており、元は東ベルリンにあったシャリテ病院の研究力が高まっていることを実感する。2000年を迎えようとする時期に、私もフンボルト財団の支援でドイツ リュウマチ研究所に3ヶ月逗留したことがある。実際には新しい建物の開所式をまたいで滞在したので、ちょうど関わっていた神戸理研開設に役立つ体験だった。このときの所長Andreas Radbruchも論文に名を連ねており、世界の研究所を束ねる研究を組織するところまで来たかと感慨深く読んだ。
2025年3月14日
ガンの多様化に様々なガン遺伝子の増幅、特に染色体外に飛びだして複製可能なユニットを形成する環状DNAがガンの多様化と悪性化を後押しして、ガンの治療を困難にしていることは何度も紹介してきた。
今日紹介するイタリアベローナ大学と英国グラスゴー大学からの論文は Myc遺伝子の増幅に焦点を当て、オルガノイドと実際の組織を比べながら、Myc増幅、特に環状DNA型の増幅の意義とダイナミックスを調べた研究で3月12日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「MYC ecDNA promotes intratumour heterogeneity and plasticity in PDAC(染色体外Mycは膵臓ガンの腫瘍内多様性と可塑性を促進する)」だ。
この研究は特に新しいというわけではないが、膵臓ガンの患者さんからガンをオルガノイド培養し、試験管内での機能実験を、保存してある実際の組織と照らし合わせる丹念な実験が行われている。
まず39例の膵臓ガン患者さんから41種類のオルガノイド培養 (POD) を樹立し、全ゲノム解析を行って、遺伝子変異を詳しく解析している。予想通り、ほぼ全ての POD で KRAS遺伝子変異が認められ、また p53変異も7割を超す。ただ、この研究では変異ではなく、遺伝子増幅に着目し、Myc、 CDK6、CCND3は全て遺伝子増幅が主要な変化であることを示している。
Myc増幅のうち染色体外DNA増幅が見られるのが4例で見つかり、この中の増幅程度の異なる2種類を選び出し、POD を詳しく検討している。染色体外DNA は増幅という点から見るとガンの悪性化を後押ししているように見えるが、実際には複製が染色体と一体化していないため、ガン細胞にとっては重荷になる。従ってガンがこのバランスをどうとっているのかが見所になる。
まず染色体外Myc増幅が見られる POD では、Myc遺伝子の数に大きなバリエーションがあることがわかる。すなわち、一方的に数が増えるというものではなく、腫瘍細胞の状況に応じて増幅程度が異なっているのがわかる。
Myc はガン増殖に必須の Wntシグナル下流にあることが知られているので、Wntシグナルの程度と増幅が関係しているのではと考え、Wntシグナルを遮断する実験を行っている。ガンの POD といえども Wintシグナルを遮断すると増殖が止まる。しかし、Wnt が遮断された条件で増殖を再開する細胞を見ると、Myc増幅が大幅に増加していることがわかる。すなわち、Wntシグナルが弱い場所では Myc を増幅させて増殖を維持している。もちろん増幅自体が問題ではなく、Myc が転写され翻訳されることが重要で、Myc をウイルスで導入して過剰発現させると、Wnt を遮断しても増幅は起こらない。
それどころか、環状Myc が減少してしまうことから、環状DNA はガンにとっては重荷であることがわかる。すなわち、Myc の発現と増幅によるコストをうまくバランスをとっていることがわかる。
この研究の面白いのは、POD での発見を組織で再確認している点で、組織上での Wntシグナルと Myc増幅を調べると、実際の組織上でも Wntシグナルが低いガンの中心部で Myc増幅が起こっていることが示されている。
以上が主な結果で、Myc 自体は Wntシグナルの補完をしていると考えていいが、環状DNA により Myc増幅が起こり始めると、増幅程度を上げたり下げたりしやすく、それ自体でガンに対するネガティブな影響はあるが、複雑なガン組織や転移の際の可塑性を高める重要な要因になっていると結論している。
いずれにせよ、Mycは標的として使えるので、ガンのアキレス腱を狙える可能性は高い。
2025年3月13日
歯周病は単なる口腔内疾患ではなく、全身に影響を及ぼす重要な感染症です。近年、Single Cell Technologyの進歩により、歯周病に対するホストの免疫応答が急速に明らかになりつつあります。最近は歯科専門誌に限らず、CellやNatureといった一般誌にも論文が発表され、広い医学分野からの関心も高くなっています。3月23日午後4時から、私の中学の同級生の医師、歯科医師が集まって事務所からジャーナルクラブをお届けします。Zoom参加希望の方は連絡お願いします。
Screenshot
2025年3月13日
若い読者の皆さんは見ていない人も多いと思うが、我々世代が最も鮮烈な印象を受けた映画がスタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅」だった。リヒャルトストラウスの交響詩「ツァラトストラはかく語り」に乗って夜が明けた太古の地球、様々な動物たちが起き出した世界で、サルから道具を使う人類が生まれる歴史が描かれる。そして人類誕生の象徴として描かれるのが、得体の知れない人工物に興奮したサルのなかの一匹が、動物の骨格から大腿骨をつかみ出し、道具として使いはじめ、この骨器を用いて争いに勝利したあと骨を空に投げると、その骨が急に同じ形をした宇宙船に変わり、音楽もヨハンシュトラウスの「美しき青きドナウ」へとスイッチする。
この長いオープニングで、道具の使用が宇宙船まで連続した人類だけの歴史であることが描かれるが、キューブリックが石器ではなく骨器を最初の道具として描いたことは興味深い。というのも、石器は400万年まえのアウストラピテクスから発見されており、またチンパンジーなども簡単な石器を作ることが知られているが、間違いなく道具として使われたことが確認できる骨器は50万年前のエレクトスの遺跡からしかこれまで見つかっていなかった。
今日紹介するスペイン国立歴史学研究所と米国インディアナ大学からの論文は、人類進化研究の重要な地域として注目されているタンザニア オルドバイ峡谷で発見された150万年前の骨器を作っていたと考えられる工房についての研究で、3月5日 Nature にオンライン掲載された)」。
タイトルは「Systematic bone tool production at 1.5 million years ago(150万年前の組織的骨器生産)」だ。
この研究はタンザニア オルドバイ峡谷で発見された150万年前のエレクトスの遺跡から、1万に上るアシューリアン型石器とともにそれに匹敵する骨器と思われる骨の断片を発見したことが全てで、あとはこの骨器が道具として製作されたものであることを証明するための記述に終始している。ただ、これを骨器というのか食べ跡というのかは専門家の議論に任せて、著者の側に立って骨器として紹介を進める。
まず殆どの骨器は2tを超える大型動物の骨を用いており、象やカバ、そしてバッファローの占める割合が多い。そして、多くはフレッシュな骨を割って骨髄を取り出したあと、道具へと加工されたことがわかる。一部は死後時間がたってから道具に使ったと考えられ、映画に出てくるような骨格になった骨を使った可能性は低い。
アシューリアン石器はそれ以前の石器と異なり、何度も叩くことでエッジを歯のように細工していることが特徴で、人間が目的を表象し、それに会わせたプランを作ることができるようになった証拠と考えられているが、骨器も同じような細工が行われて、斧や包丁のような形態が作られていることが写真で示されている。
重要なのは、石器と異なり長くて大きな道具が骨から作られていることで、重い石器の間を埋めていることがわかる。
要するに、今回発見された骨は、まさしく道具で、決して食べるときに割ったり砕いたりしたものではないことを様々な方法で確認し、150万年前に骨器が道具として使われたと結論している。
これが最も古い骨器になるが、もしそれ以前にないとすると、エレクトス誕生によってより人間らしい知能を備えて石器を急速に進歩させたのに重なって骨器ができたと考えられる。しかし、なぜこの時点から50万年前まで、様々な場所でエレクトス遺跡があるのに、骨器が発見されないのかという謎が残る。今後の発掘にかかってい入るが、大型の骨器も、最終的に石器に取って代われ、使われなくなったが、その後矢尻などよりファインな胴部の誕生に会わせて復活したと考えるのがいいのかもしれない。しかしアフリカのエレクトス進化から目が離せない。
2025年3月12日
ついついお菓子に手が出るのは食べた後の快楽回路が存在するからで、この脳回路が我々を肥満に導いていることはあまり疑う人はいない。実際、動物に甘くて脂肪の多いおいしい食べ物を与えると、ドーパミンが分泌され、快楽回路が活性化される。また、人間でも同じような実験が行われて、この考えを支持してきた。
しかし、今日紹介する米国衛生研究所からの論文は、脂肪分が多く甘い食品に対する人間の反応は決して単純なものでないことを示した研究で、3月4日 Cell Metabolism に掲載された。タイトルは「Brain dopamine responses to ultra-processed milkshakes are highly variable and not significantly related to adiposity in humans(高度に加工したミルクシェークに対する人間のドーパミン反応は極めて多様で肥満との関係は見られない)」だ。
脳内のドーパミン分泌を測るために様々な方法が開発されているが、刺激に応じての反応する時間過程を調べたい場合は PET を用いる。この目的に開発されたのが、炭素11でラベルされた raclopride を用いる PET で、受容体に結合した raclopride はドーパミンが分泌されると受容体から解離するので、アイソトープシグナル減少として測定できる。
研究は単純で、一晩の絶食のあと PET検査を行い、絶食後の PET検査、そしてミルクシェーク摂取後30分の PET検査で、受容体に結合した raclopride の量を測定している。おそらく最初は全員で結合raclopride の減少(=ドーパミン分泌)が見られると予測したと思うが、期待に反し、線条体のドーパミン量の測定値は空腹時とミルクシェーク接種後で殆ど変化を認めていない。
しかも、一人一人受容体に結合した raclopride の変化を調べると、ミルクシェークで解離するケースがある一方、逆に結合が上昇するケースも数多き存在し、実際に食したミルクシェークへの反応は人それぞれということがわかる。
事実それぞれの被検者にミルクシェークを評価させると、ドーパミンが分泌されたレスポンダーは、おいしい、もっとほしいと感じるとともに、絶食後の空腹感が高いことがわかる。かといって、この反応と肥満度や血糖などの身体的指標と比べると、殆ど相関はない。従って、最初ミルクシェークを食べたときの反応だけで将来の肥満度などを予測することはできない。
ただ絶食後の空腹感の強さは強くドーパミン分泌と相関が高いので、この空腹感の多様性の原因を探ることが重要になる。そして、ミルクシェークによく反応した人は、ビュッフェ形式の食事で自由に選んで食べられる状況で、甘くて脂肪の多いクッキーを選ぶ傾向が見られた。
以上が結果で、単純にドーパミン分泌が快楽回路だとするのは人間では当てはまらないが、特に空腹感の強さと相関する脳回路の形成は肥満への危険シグナルになることを示している。
米国では肥満に至る行動を変化させるための研究に大きな助成金が出ているが、動物実験ではなく、人間で調べることの重要性がよくわかる結果だと思う。今後人間の欲に関して単純化して話をするのはやめておこう。
2025年3月11日
ヘリコバクターを始め様々な細菌がガンの増殖を誘導することが知られている一方、ガン組織の細菌叢を調べる研究が行われた結果、膵臓ガンをはじめとするいくつかのガンで、特に嫌気性菌叢が成立するとガンに対する免疫が誘導されやすく、ガンの予後が改善していることが示され、このブログでも紹介した(https://aasj.jp/news/watch/10700 )。「ならば」と、嫌気性腫瘍環境でのみ増殖できる細菌を作成してガン免疫を誘導する研究が行われている。うまくいけば安上がりのガン治療になると期待できる。
今日紹介する深圳先端技術研究所を中心とする中国研究グループからの論文は、腫瘍の嫌気条件だけで増殖できるよう遺伝子改変したサルモネラ菌がガンの増殖を抑えるメカニズムを明らかにした研究で、3月3日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Bacterial immunotherapy leveraging IL-10R hysteresis for both phagocytosis evasion and tumor immunity revitalization(バクテリア免疫療法は、 IL-10受容体のヒステリシスを高め、貪食能と腫瘍免疫の再活性化を誘導する)」だ。
このバクテリアは好気条件では増殖が抑えられる回路を導入されている。驚くのは、静脈注射するだけでガンを移植した嫌気条件に潜り込んでそこで増殖することで、1千万個注射するだけで移植したガンの増殖を強く抑制できる。また、大腸ガン自然発生モデルでもガンの発生を予防できる。この効果がガンに対する免疫誘導であることは、同じガンを他の場所に移植するとすぐに拒絶されるが、他のガンは全く拒絶できない。
期待通り腫瘍組織内のCD8キラー細胞が増加するが、外部からガン組織へのリンパ球流入をブロックしても影響がないので、局所のキラー細胞だけを増殖させている。そして最も驚くのは、この機能が IL-10を抑制することで消失する点だ。IL-10 は抗炎症性のサイトカインで、ガン抑制の逆の作用があると考えられていた。しかし最近になって、キラー細胞の再活性化を強く誘導することが知られるようになり、治験も行われ始めている。その意味で、バクテリア免疫療法が IL-10を介しているという発見は重要だ。
腫瘍組織を調べると、キラーT細胞とマクロファージが IL-10受容体を発現している。さらに、IL-10自体はマクロファージや発見球が発現している。試験管内刺激による研究から、低濃度のIL-10でも、IL-10によって IL-10受容体の発現がさらに誘導されるというサイクルが始まって、キラー細胞やマクロファージが活性化されることがわかった。
そして、腫瘍組織内のマクロファージがバクテリアを貪食した結果 IL-10が誘導され、これがタイトルにあるヒステリシスを誘導し、マクロファージもキラー細胞も活性化サイクルに入ると考えられる。一方で、IL-10 は好中球の腫瘍組織内の活性化を抑え、バクテリアの増殖を維持できるようにしている。
以上が結果で、メカニズムも納得できるので、あとは人間で同じようにガンの抑制が可能か調べるだけになった。人間の場合、原理的には局所注射で十分だと思うが、実現すると安上がりのガンの免疫療法が実現するのではないだろうか。
2025年3月10日
乳児期の細菌叢の形成が、ホストの免疫や代謝に大きな影響を及ぼすことは何度も紹介してきた。このとき、細菌叢からの代謝物によりホスト側の細胞がエピジェネティックに変化して、持続的に反応性を変化させることが示されており、持続的な健康を保障するための細菌叢操作をどうすれば良いのか様々な研究が進んでいる。
今日紹介するユタ大学からの論文は、離乳後固形物を食べるようになるまでの時期に真菌の一種の Candida dubliniensis が腸内に発生すると、膵臓のβ細胞の増殖が高まり、将来の糖尿病発生を防ぐという驚くべき研究で、3月7日 Science に掲載された。タイトルは「Neonatal fungi promote lifelong metabolic health through macrophage-dependent b cell development(新生児期の真菌は一生涯続く代謝的健康をマクロファージ依存的β細胞発生を通して保障する)」だ。
この研究のハイライトは、無菌マウスと通常の実験室マウス(SPFマウス)の膵臓のβ細胞量を、大人になってから比べたという一点にある。今まで行われなかったのが不思議だが、無菌マウスではβ細胞量が半分程度に減っている。
細菌叢の効果がいつ発揮されるのかを調べる目的で、殆どの細菌を殺せる抗生物質を様々な時期に投与してβ細胞量を比べると、マウスで10日から21日まで投与した群でだけβ細胞量が低下した。
この時期は離乳期から固形食に変化する時期で、細菌叢も大きな変化が起こる。ただ、この研究ではこの変化とともに真菌に着目し、この時期にマウスでは C.dublinensis が増加し、その後消失する一過性のウェーブが見られることを示している。実際、この真菌を無菌マウスに移植するとβ細胞量が増加する。
このメカニズムを探るため C.dublinensi を投与したマウスの膵臓を調べると、C.dublinensi を投与した群でだけマクロファージの数が上昇していることがわかる。ただ、特に活性化されているわけではなく、C.dublinensi により何らかのメカニズムで膵臓へのリクルートメントが高まると考えられる。
膵臓のマクロファージを一時的に除去する実験を通して、C.dublinensi が効果を発揮するためにはこのマクロファージの上昇が必須で、これにより長く持続するβ細胞の増加が見られることがわかる。そして、その結果投与を受け膵臓内のマクロファージが上昇したマウスは血中インシュリンの濃度が高い。
あとは、マクロファージを誘導する C.dublinensi 側の条件を探り、完全に分子を特定したわけではないが、細胞壁抗生物質の変化が重要で、例えばマンナンの量が低下すると、誘導能力が高まること、あるいは菌糸の形態なども誘導能に関わることを示している。とすると、将来細胞壁成分のみで膵臓の増殖を高める可能性がある。
最後に、こうしてβ細胞の増殖を誘導すると糖尿病の発生を遅らせることができるか、1型糖尿病マウスを用いて調べ、最初の時期にβ細胞を増やしておくと、確かに病気の発症が遅れることを示している。さらに驚くのは、薬剤投与でβ細胞を障害して C.dublinensi を投与すると、回復が早まることも示している。
結果は以上で、離乳後固形食に移る食の変化に応じて起こる細菌相変化とともに、特殊な真菌が増えてマクロファージの膵臓へのリクルートを増やし、β細胞を増やしてくれるという面白い話だ。これが人間にも当てはまるなら、1型、2型を問わず将来の糖尿病発症を抑える方法の開発に繋がる重要な発見だと思う。
2025年3月9日
昨年の暮れに、エピジェネティックスの大御所の一人Richard Youngが細胞内のタンパク質分子の動きを測って、この動きが鈍化することが病気の症状の細胞レベルの原因で、この状態を Proteolethargy と呼ぼうと提案した論文を紹介した (https://aasj.jp/news/watch/26318 ) 。彼は今も多くの論文を発表しているが、研究の焦点がタンパク質の局在、特に相分離と転写調節の関係へと移っているように見えていたので、Proteolethargy の論文を読んで「なるほど」と納得し、新しい領域への飽くなき挑戦をいとわないスピリットを感じていた。
今日紹介する Richard Young と、同じMITの機械学習研究部門からの論文は、相分離やシグナル配列により決定される細胞内局在に特化して作成したタンパク質の言語モデルについての研究で、3月7日 Science に掲載された。タイトルは「Protein codes promote selective subcellular compartmentalization(選択的な細胞内コンパートメント化に関わるタンパク質のコード)」だ。
タンパク質は特定の機能を発揮するために様々要素が集まっている。まず、安定な立体構造をとる必要があり、このタンパク質のコンテクストを予測するのが AlphaFold をはじめとする様々な大規模言語モデルだ。この多次元空間に配置している各タンパク質の記述的な機能を融合させ、例えばリン酸化酵素活性を持つ新しいタンパク質を設計することを試みたのが先日紹介した Evolutionary Scale 研究所のESM3 になる(https://aasj.jp/news/watch/26196 )。
相分離などによりタンパク質が様々な細胞内領域に局在化するコンパートメント化に興味を持った Young らは、タンパク質の配列からまずこれを予測する言語モデルが作成できないかと考えた。そのために、タンパク質に表現されるコンテクストと自然言語による記述を融合させられる ESM を選び、細胞内の13カ所のコンパートメントに関する記述を融合させた ProtGPS と名付けた独自のモデルを作っている。
この過程を見て感心したのは、コンパートメント化がはっきりわかっているたかだか5000種類のタンパク質を、800万パラメータの2層からなる小さなニューラルネットに学習させている点だ。すなわち、GPU は必要だが、自分の目的に合わせたパソコンレベルのモデルの利用が始まっている。GPT-4は1750億パラメータで、ずっと小さくて次元圧縮して内部の解析が可能な GPT-2 は17億パラメータだが、今回使われたネットワークは桁違いに小さい。
しかし、5000タンパク質を学習させた ProGPS は、タンパク質のコンパートメント化について極めて高い確率で予測することができる。
ただ、生成 AI という観点からはまだまだ万能ではない。蛍光タンパク質の局在を決めるための配列を設計させても、全くうまくいかない。これは設計でできたタンパク質の折りたたみを含むタンパク質としての化学的性質が表現できていないためで、これを改善するため配列設計を既存のタンパク質言語モデル EMS2 に存在する配列に限ること、本来のタンパク質の折りたたみを変化させないこと、目的のコンパートメントに存在するタンパク質が持っている配列であることなどの条件を加えて設計すると、ようやく核内局在で 4/10 で成功するようになる。今後学習するタンパク質を増やしたモデルが形成されると、他のコンパートメントも含め、コンパートメント化を指定できる新しい配列も設計できるようになるだろう。
最後に、形質変化が起こることがわかっている突然変異のうち、細胞内局在を変化させる変異を予測する可能性も調べ、ProGPS 多次元ベクトル空間内での距離から、局在の変化が予測できることも示している。
以上が結果で、まだまだ入り口とはいえ言語モデルの新しい可能性を感じさせる論文だ。何よりも計算機からパソコンへの移行が間違いなく起こることを予感させる。そして、この変化を主導するのは生命科学だといえる。
2025年3月8日
医学教育の最初は人体解剖というのが今も定番だと思うが、血管の走行に関しては、決まったパターンをとるものと個人差が大きいパターンがあることに気づく。ただ、個人差の大きいパターンに関しては、殆ど気にせず様々な条件が重なると当然起こってくる個人差だと考えていた。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、個人差だと思っていた走行の多用性も場合によってはそのメカニズムを特定することができることを示した研究で、3月5日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「CXCL12 drives natural variation in coronary artery anatomy across diverse populations(様々な人種で CXCL12 は冠状動脈走行の自然の多様性の原因となる)」だ。
タイトルにある CXCL12 は最初 SDF-1 と呼ばれており、1993年に本庶研の田代、仲野さんにより、続いて1994年に岸本研の長澤さんにより遺伝子クローニングが行われたケモカインだ。当時私たちは独自に樹立したストローマ細胞株 ST2 と東北歯科大学小玉さんの樹立したストローマ細胞株 PA6 を利用して造血を研究していたが、田代、仲野さんは ST2、長澤さんは PA6 から SDF-1 をクローニングしたので特に印象が深い。実際長澤さんらにより、ストローマ細胞造血に関わることが示されたが、その後 Cyster らによって私たちが研究していたリンパ組織の発生にも関わることが示され、常に注目してきたケモカインだ。ただ、現在では血液やリンパ組織だけでなく、血管や心臓の発生維持に関わることが明らかになり、多彩な作用があることが知られている。
この研究は心臓の裏側を支配する冠状動脈回旋枝が、左右どちらの下降枝から分岐するのかの、いわゆる血管走行の多様性を決める遺伝性調べるため、ゲノム解析二よりマッピングを行い、ヨーロッパ系、アフリカ系ともに CXCL12 の近傍の多型と強く相関することを発見する。
これまで知られている CXCL12 の多型は4種類知られており、そのうち近くに存在する3種類のノンコーディング領域の多型が走行多様性を決めると考えられる。ノンコーディング領域なので遺伝子の発現量を調節していると考えられるが、多様性で終わるような軽微な変化を捉えるのは難しい。
この研究では胎児心臓の single cell レベルのクロマチン構造を調べたデータを読み込ませた AIモデルを作成し、特定した多型がそれぞれ細胞特異的クロマチン構造変化と対応することを確認している。
その上で、心臓の胎児発生時期の CXCL12 とその受容体 CXCR4 の発現を調べ、冠状動脈発生時に CXCL12 が冠状動脈起始部の回りに発現し、CXCR4 が冠状動脈上皮に特異的に発現していることを、組織上の遺伝子発現アッセイから明らかにしている。
以上のことから、発生途上で CXCL12 の微妙な量の変化により、左右どの下降枝から動脈が伸びてくるのかが決まると想定される。とすると、CXCL12 遺伝子が半分のマウスを調べると、起始部の選択が変わるのではないかと着想し、マウスCXCL12 ノックアウト・ヘテロマウスの動脈走行を調べると、通常右下降枝から分岐するケースが多いが、CXCL12(+/-) では、両方の下降枝と大動脈から分岐するケースが多いことがわかった。
結果は以上で、致死的でない遺伝子発現の変化が我々の身体の多様性を作っていることを実感させる面白い仕事だと思う。特にノンコーディング領域の多型を調べるための方法などは、学ぶところは大きい。
2025年3月7日
上皮間葉転換 (EMT) は、細胞接着構造で互いに結合していた上皮が細胞同士の結合力の低い間葉系細胞などに転換することを指し、発生過程では胎児上皮からの中胚葉の分化、神経管からの神経堤細胞の分化で見られる極めて重要な過程だ。EMT はその特異的な組織学的特徴からガンでも指摘されており、多くの場合 EMT を起こすと悪性度が高いと考えられてきた。
今日紹介するテキサス MD アンダーソン研究所からの論文は、EMT の役割が強く疑われてきた膵臓ガンに関して EMT 過程をモニターし、また操作できるマウスを用いて、EMT がゲノム不安定性を引き起こしてガンの多様化と悪性化に関わることを示した研究で、3月5日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Evolutionary fingerprints of epithelial-tomesenchymal transition(上皮間葉転換の進化過程の刻印)」だ。
先日タイトルの重要性について述べたが、この論文のタイトルを見て膵臓ガンの研究だとわかった人はほとんどいないのではないだろうか。私もまず進化発生学の論文かと読み始めたぐらいだ。読み始めればすぐに膵臓ガンでの EMT が研究対象であることがすぐわかるが、膵臓ガンに興味のある人は読み始めないのではないかと思う。しかし、ガンの研究者にとっては面白い研究だと思うので、少し残念な気がする。
この研究のハイライトは EMT で発現するビメンチン遺伝子をスイッチとして、EMT を経験した膵臓ガンを追跡したり操作したりできるようにした点で、EMT について議論している膵臓ガン研究論文は多く読んだが、このタイプの試みは初めて見た。難しい方法ではないので、今まで殆ど試みられてこなかったのが不思議なぐらいだ。
ガンの進展途上で EMT が起こったときにスイッチが入って蛍光を発するマウスでは、間葉系形態をとった細胞だけでなく一度間葉系に変化した後、また上皮様に戻る細胞が存在することがわかるが、高い増殖力を示し転移するのは殆どが EMT の後に間葉系形態を保った細胞であることがわかる。また、発ガンの早い時期から EMT が発生しガンの主要成分を占めるようになることがわかる。EMT 細胞の高い増殖性は、ガン細胞のオルガノイド培養や細胞移植でも確認されている。
ここまでならこれまでの研究でも他の方法を用いて示されており、EMT がガンをさらに悪性化させると考える根拠になっているが、この研究では EMT を起こした細胞を薬剤で殺せるようにしたマウスモデルを用い、EMT を殺したときのガンの増殖や転移を調べている。結果は予想通りで、増殖だけでなく、ガンの転移も強く抑制することができ、また生存期間も延びる。おそらくこの実験は、ガンの進展にとって EMT が必須であることを直接示した最初の論文ではないだろうか。
次に、EMT がガンの進展に大きな影響を持つメカニズムについて、染色体の安定性に焦点を絞って調べている。すると、EMTを起こした細胞でだけ大きなゲノム変化が起こりやすくなって、ゲノム不安定状態が起こっているのがわかる。また分裂時に染色体が断裂してしまうクロモスプリシスという状態が EMT 後に起こっていることも明らかにしている。これはマウスモデルだけでなく、人間の膵臓ガンのデータベースを調べると、EMT を起こした刻印を持つ細胞でクロモスプリシスが起こっていることを確認している。
クロモスプリシスは分裂時に紡錘糸が染色体に結合できないために起こるが、このグループが以前開発した single cell レベルで特定の領域のクロマチン構造を調べる方法を用いて紡錘糸の結合するセントロメア付近のクロマチン構造が開いてしまっており、その結果紡錘糸の結合がうまくいかないと結論している。実際、EMT を起こしたガン細胞では、分裂時間が長くかかっている。
結果は以上で、EMT がガンの染色体不安定性と強く相関していること、またクロマチンの変化がさらに大きいクロモスプリシスを誘導する因子になることはわかり、ガンの EMT がガンのゲノム多用性を発生させる大きな要因であることが理解できた。ただ、これが膵臓ガンの難しさの全てかどうかはわからない。とはいえ、single cell レベルの独自の解析技術など、高い力量を示す面白い研究だと思う。