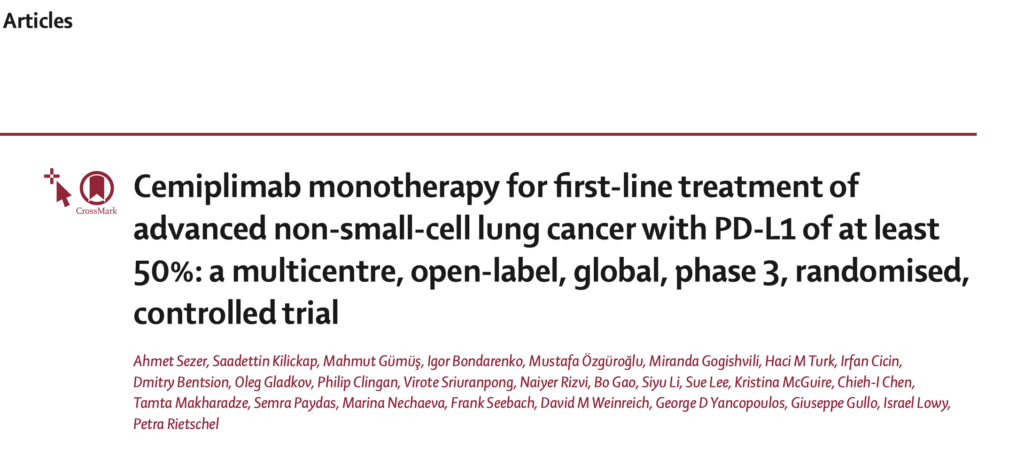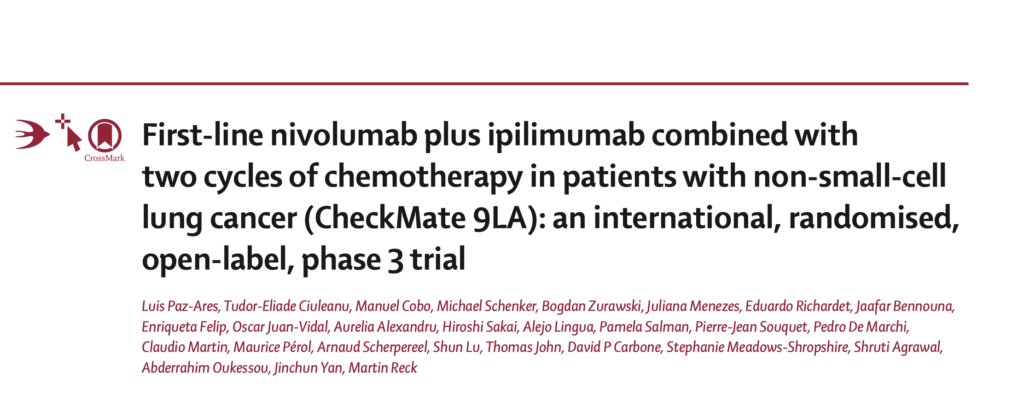2021年2月28日
Covid-19の重症化に深く血栓がかかわり、この原因がSLEの様に白血球の特殊な細胞死NETosisや自己抗体が関わることが示唆されている。その意味で、SLEの病態を理解することは、Covid-19理解にも重要だと思うが、ではSLEの病態がどこまで解明されているのかと考えると、まだまだ不明な点が多い。
今日紹介するケベック大学からの論文は血小板がFcγRIIA受容体を介して、SLEの病態に深く関わる可能性を示し、SLE研究の盲点をついた研究で2月17日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Platelets release mitochondrial antigens in systemic lupus erythematosus (SLEで見られる血小板により分泌されるミトコンドリア抗原)」だ。
この研究は、SLEのシンボルマーク、抗核抗体や抗DNA抗体ができる過程に関わるDNAは本当に核内DNAだろうかと言う素朴な疑問に発している。DNAはミトコンドリアにも存在し、事実NETosisが起こるときにはミトコンドリアDNAも細胞外に吐き出される。さらに、白血球よりはるかに多い数の血小板も4個前後のミトコンドリアを持っている。これらの考察に基づき、この研究では最初からSLEの病態に血小板とそれ由来ミトコンドリアDNA がど関与しているかに絞って研究を行なっている。要するに、血小板は重要であると言う結論だが、そのために少しごちゃごちゃと実験が行われわかりにくいので、結論だけを要約すると以下の様になる。
血小板に自己抗体と自己抗原(DNAなど)が結合した抗原抗体複合体が作用するとFcγRIIAを介してシグナルが入り、ミトコンドリアとともにミトコンドリアDNA(mtDNA)決勝番外に遊離される。 SLEでは病状に関わらず血小板が常に活性化された状態にあり、免疫複合体によりすぐにmtDNAが遊離される。 mtDNAはNETosisにより遊離される核内DNAと異なり、そのままでは拡散分解酵素の作用を受けない。 マウスはFcγRIIAを持たないので、ヒトFcγRIIA遺伝子を導入したトランスジェニックマウスでSLEを誘導すると、FcγRIIAを導入したマウスで腎臓への血小板のトラップが起こり、マウスの寿命も短くなる。すなわち、活性化された血小板が免疫複合体が沈着する局所に集まり、そこでミトコンドリアが遊離することで、mtDNAが供給され、病態を進行させる。 以上が主な結果で、結論としては、いったん自己免疫状態が発症して免疫複合体が形成されると、その作用で血小板からミトコンドリアが遊離され、ミトコンドリア自体、そしてSLEの場合mtDNA を供給することで、局所だけでなく全身の病態を進行させると言う考えだ。
すなわち、自己免疫の最初のトリガーがかかると、血小板は病気を進行させる危険な細胞へと変身することを示した研究だが、この変身はFcγRIIAを阻害することで完全に抑えられることになる。今後、FcγRIIAをSLEの新しい治療標的として利用する過程でこの仮説の妥当性が確かめられると思うが、同じ様なメカニズムが働いていそうな重症化Covid-19にも試してみる価値はある様に思う。
2021年2月27日
現在Covid-19に対する我々の武器は、ワクチンや抗体治療に集約されている感があるが、これまで紹介してきた様に新型コロナウイルス(Cov2)の細胞内での増殖過程とそれに関わるウイルス側、ホスト側の分子が明らかになるに従い、様々な過程を標的とする薬剤の開発が進みつつある。個人的には、ウイルスタンパク質の活性化に必須のプロテアーゼに対する阻害剤、特にコロナウイルス特異t的な阻害剤が開発されることを期待するが、臨床目処がついているのは、まだ他のRNAウイルスのプロテアーゼ阻害薬の使い回しの様だ。
一方、ウイルスタンパクやウイルスRNAと相互作用するホスト側タンパク質も解析が進んでおり、これについては、特効薬というほどではないが、いくつかの既存薬が、その作用メカニズムと共にリストされている。既に臨床に使われていることから、現在の標準治療に加える形で、着々と知見を進めることが重要だ。
今日紹介するマウントサイナイ医大から、2月26日号のScienceに発表された論文も、現在発表が増えつつある抗ウイルス薬研究の一つなのだが、なぜわざわざ今の時点でScienceに掲載されるのかという疑問と共に、ひょっとしたら治療薬として効果が証明されつつあり、エディターが選んだのではないかと期待を抱かせる前臨床研究だ。タイトルは「Plitidepsin has potent preclinical efficacy against SARS-CoV-2 by targeting the host protein eEF1A(ヒトeEF1Aを標的とするPlitidepsinは前臨床試験ではSARS-CoV-2に対して高い効果を示す)」だ。
以前にも紹介したが、このグループはウイルスタンパク質と結合するホストタンパク質を網羅的に解析し、ウイルスが必要とするホスト側の分子を抑制する抗ウイルス剤の開発を試みていた。その中で、ウイルスの複製に関わるNsp9とタンパク質翻訳に関わるエロンゲーションファクターと結合することを発見、元々骨髄腫などの治療目的で開発されていたeEF1A阻害剤に着目し、最終的にPlitidepsinがウイルスの増殖を抑制することを見出していた。
Plitidepsinに関しては既に第I/II相の治験はcompleteとなっているので、Cov2に対する効果も含めてかなり情報が集まっているはずだ。実際、そのことは論文に書かれており、また実験に使う量の安全性についてもこの治験結果をもとに議論している。そんな中で、純粋に培養細胞とマウスを用いた前臨床研究結果がScienceに発表されたということは、第III相に進めるよほどいいデータを持っていて、慌てて基礎データを発表してきたのかと勘ぐってしまう。
示された結果は、
ウイルス感染した細胞でのウイルス増殖を、既に安全が確認されている量のPlitidepsinで抑制することができる。 eEF1Aの変異体を用いた抑制実験から、PlitidepsinはeEF1Aに直接結合しウイルスの増殖を抑制する。 メカニズムとしては、ウイルスがNタンパク質を合成する際、ゲノムの一部を複製して、そこからもう一度短いプラス鎖のRNAを作り、それを翻訳するが、翻訳を抑制することで、このマイナス鎖の短いRNAの合成が抑え荒れることでウイルスの増殖が阻害されることによる。 マウスを用いる感染実験で、現在使われているRemdesivirを遥かに凌駕する治療効果がある。 とまとめられるが、この様な研究は多く発表されているので、これぐらいならScienceにはいくらCovid-19論文でも採択されないと思う。おそらく、治験の結果がかなり有望で、新しい治療薬として、remdesivirと共に利用可能であるという情報が回っている結果、Scienceに採択されたのではないだろうか。特にHost側の遺伝子を抑制する方法は、コロナウイルス一般に有効で、現在問題になっている変異ウイルスについても利用できる。そう勘繰ると、すぐに大々的に報道される様な予感がする。
2021年2月26日
腸内細菌叢について、3人の医師とともに行うzoom勉強会の2回目を3月1日夜7時から予定しており、いつものジャーナルクラブとしてYoutubeでも配信予定で(https://www.youtube.com/watch?v=Ht9FD38lS74 )、最近紹介した細菌叢に関する論文を再度取り上げて読み直しながら、その背景にある科学について議論するつもりだ。もしzoom に直接参加したい方がおられたら、アカウントをお送りする。ただ、内容は少し専門的になる。とはいえ、テレビコマーシャルでお馴染みの「免疫力」「善玉菌・悪玉菌」といった、わかりやすくするために作られた言葉が撒き散らす間違った概念を専門家として正していくことは重要だと思い、勉強会を企画している。
今回は細菌叢の発達について考える予定で、論文は既に用意しているが、新たに加えたいと思う完全ではないにせよチャレンジ精神がよくわかる論文が、ハーバード大学とマンチェスター大学から2月24日、Natureにオンライン出版された。タイトルは「Multi-kingdom ecological drivers of microbiota assembly in preterm infants(早産児の腸内細菌叢の集合を決める複数の界からなる生態系ドライバ)」だ。
腸内細菌叢の複雑性は、もともと何千もの細菌種が存在するというだけでなく、それがホスト側の因子と、毎日変化する環境変化の影響を受けていることで、ある時間を切り取ったとして、よほどのことがない限りその意味を理解できないことだ。
この研究では、従来の細菌叢測定に定量的要素が欠如していること、そして細菌種の比率だけで議論が行われていることの問題を改めるため、彼らがMulti-Kingdom Spike Sequencingと名付けた、サンプルに定量化されたバクテリア、古細菌、カビを加えて細菌叢ゲノムを調べることで、加えたレファレンスの量を指標に、各種細菌の種類だけでなく、量までも同時に定量できる方法を開発し、これまで比率だけを問題にした細菌叢研究の問題点を明らかにしようとしている。
原理的にもなぜこのような定量性のある方法が普及しなかったのか不思議なぐらいだが、結果は明確で、これまで比率だけで判断されていた結果が、絶対数から測定した場合と大きな乖離があり、いかに問題があるかを明らかにしている。
また、生後1ヶ月ぐらいは、カンディダなどの真菌類も細菌叢の成長に重要な要素になることを示している。
この方法で細菌叢の発達に関わる様々な要素を分析すると、一番大きいのは最初にどの菌が優勢であったかで、次に時間、そして食物摂取が来ることがわかる。
細菌叢の発達が遅れるとされている帝王切開で生まれた子供の腸でも、細菌の消長が繰り返され、個人差は大きいが、経膣出産時と比べたとき、決定的な違いが見つかるというわけではないこともよくわかった。
この研究では、それぞれの細菌種(大きな括りなので生物学的には界と呼ばれるレベル)間の相互作用を、得られた結果から推定し、例えばstaphylococcusはKlebsiellaの増殖を高め、逆にKlebusielaはStaphylococcusを抑えるなどの関係も導き出している。そして、それぞれの関係が本当かどうか、マウスにそれぞれの菌を組み合わせて移植して、相関関係を確認している。すなわち、将来最初の組み合わせが絶対数と共に測定できれば、かなり細菌叢の発達や、それを助けるための介入法が予測できるという話になる。
以上が結果で、高々4−5種類の関係で本当に細菌叢を理解できるかについては問題があると思うが、それでも現象論に埋もれてあがいている細菌叢研究を、より科学的にしようとする強い意志が感じられる研究だと思う。次回のジャーナルクラブにはぜひ取り上げる。
2021年2月25日
一般的なアトピー性皮膚炎に関しては、アレルギー性の炎症であることはわかっていても、その原因を完全に特定することが難しいのが普通だ。ただ、患者さんの多くで皮膚に黄色ブドウ球菌の増殖が見られることから、これが炎症を高める重要なファクターになっているのではと考えられている。したがって、緑膿菌を皮膚から除けば症状は改善すると期待されるが、これがまた難しい。
今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校皮膚科からの論文は、黄色ブドウ球菌の増殖と炎症性物質の生産を抑えるために、常在のブドウ球菌を用いる可能性を追求した臨床試験を含む研究で2月22日Nature Medicineにオンライン発表された。タイトルは「Development of a human skin commensal microbe for bacteriotherapy of atopic dermatitis and use in a phase 1 randomized clinical trial(アトピー性皮膚炎の細菌治療に利用できる皮膚常在菌の開発と第1相無作為化臨床治験)」だ。
研究では健康人皮膚常在菌の中に試験管内での黄色ブドウ球菌(SA)の増殖を抑制する細菌がないかスクリーニングし、最終的に同じブドウ球菌、S.hominisの系統(ShA9)にたどり着く。
次にShA9が実際の皮膚でSAによる炎症を抑えるか調べると、ShA9は抗菌物質を分泌してSAを殺すだけでなく、クオラムセンシング機構に働きかけて、SAによる炎症物質の分泌を抑え、皮膚の炎症を抑えることができることを明らかにする。
細菌学的な検討から、ShA9による殺菌効果に抵抗性のSAは存在しても、クオラムセンシングを抑える機能に抵抗性のSAは現在のところ認められないことから、SAによるアトピー皮膚炎の炎症促進効果を断ち切ることは期待できる。
以上の検討に立って、この研究ではSA陽性のアトピー性皮膚炎患者さんをリクルートし、ShA9塗布の安全性を確かめるとともに、ShA9を塗布することでSAを正常の細菌叢に置き換え、皮膚の炎症が治るかを調べている。目的としては第1/2相と言っていいように思える。
もともと皮膚炎が存在するので、コントロールの塗布液でもいろんな症状を訴えるようで、自己申告制の有害事象についてはShA9塗布群より、コントロール群の方が報告率が高い。いずれにせよ、短期間の治験では重大な問題は起こらなかった。
効果だが、まず塗布したShA9の抗菌分子RNAは治療中維持される。不思議なことに、常在細菌のコロニー数が塗布すると上昇している。これと呼応して、SAが分泌する毒素の発現は塗布により強く抑制される。一方皮膚症状については、一定程度の改善が認められているが、短い期間であること、またアトピーを示す病巣の一部だけが対象になっていることから、これはあくまでも参考資料と言っていい。
これを補完するため、マウス実験でSAの毒素を抑制することで炎症が低下し、また常在細菌叢が正常化することが示されているが、これが人間で起こっているかどうかさらに検討が必要になるだろう。
今まで多くの論文を読んできたが、一つの細菌で、黄色ブドウ球菌を抑えて、常在菌を再構築できることを明確に示した研究には出会ったことがなかった。その意味で、この研究は細菌を持って細菌を制するという戦略が可能であることを示す重要な貢献だと思う。また、SAは鼻や皮膚の感染症を起こすこともあることから、ここでも活躍できるかもしれない。
一つだけ気がかりなのはS.hominisは体臭成分の一つだと思うので、気にならないかどうかだが、そんなことはとっくの昔に計算済みだと思う。
2021年2月24日
生きている動物の脳内のシナプス形態変化を1ヶ月という長期間記録し続ける技術については2015年紹介したことがあるが(https://aasj.jp/news/watch/3680 )、スパインと呼ばれる樹状突起のシナプスが、出たり入ったりするとともに、形態も変化するのを見ると、この変化が自分の脳でも起こっているのかと感慨にふける。
今日紹介するコロンビア大学からの論文は、同じ技術を使って、長時間の麻酔を行ったあとのシナプス変化を調べた研究で2月10日米国アカデミー紀要に掲載された。タイトルは「Prolonged anesthesia alters brain synaptic architecture(長時間の麻酔は脳のシナプス構築を変化させる)」だ。
高解像度の蛍光顕微鏡で一本一本の神経突起を8日間観察し続けることは大変な実験だが、あとは一般に行われるisoflurane吸入麻酔をほぼ1日近く続け、その前後で同じシナプスを観察する、実験自体は単純な研究だ。これと並行して、簡単な行動解析も行っている。増井期間中は、呼吸、心肺機能は正常に保ち、病理学的障害が脳に生じないようにしている。
要するに長期間昏睡状態に置かれたとき、脳回路はどう変化するかが問題になっている。まず、麻酔による大きな身体的変化や行動変化も起こらない。ただ、最初経験した物体が新しいもので置き換えられた時に費やす時間差が消失することから、作業記憶が障害されている可能性が示唆される。
さて肝心のシナプス変化だが、この研究では観察しやすい感覚領域を用いて調べている。軸索と結合しているスパインは日々消長を繰り返しているが、面白いことに麻酔中はシナプスが増える方向に変化し、こうして形成されたスパインはその後3日ぐらい安定に維持される。麻酔というと脳の働きを抑えると思うので、スパイン形成が高まるというのは不思議に感じるが、冷静に考えてみると、生まれてからシナプスの選定が刺激依存的に起こると考えると、刺激が停止した状態では十分あり得るかと思う。ただ、麻酔から覚めた後は、今度はスパインが消失する率が高まるので、最終的に元に戻るという話になっている。
結果はこれだけで、タイトルをみて、麻酔には問題があるのかと構えて読んだが、あまり気にしないでいいというのが個人的印象だ。しかし、成熟した脳でも刺激がないと、スパイン形成方向に偏ることは、刺激依存的シナプス剪定は、大人になっても続いていることがよくわかった。
ケタミンについてはそれ自身が持つ代謝リプログラム経路がわかってきたが(https://aasj.jp/news/watch/14546)、isoflurane自体の効果も含めて、生化学的研究結果を知りたい。
2021年2月23日
昨日まで2回にわたって、これまでガン治療の最後の手段だった免疫チェックポイント治療(ICI)を最初に持ってくる方向が間違いなく将来の標準になる可能性について紹介した。この順番が定着すると、最初に問題になるのは、ICIが効かない人が、PD-1+CTLA4の併用療法でも半分以上おられる点だ。しかも、StageIIIになると、この時の結果が予後を左右する点だ。すなわち、治療可能性の宣告が早々に下ってしまう。これを回避する唯一の手段は、腫瘍に対する免疫を高め、ICIの確率を高めることになる。
このためにはICIをスタートさせる前に、ガン特異的ネオ抗原に対して免疫を行い、キラーT細胞のレパートリーを高めることになるが、今日紹介するハーバード大学からの論文は、ネオ抗原だけでなく、それに釣られて起こる自己免疫反応、すなわちepitope spreadingもガン治療に利用できることを示した研究で2月17日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Epitope spreading toward wild-type melanocyte-lineage antigens rescues suboptimal immune checkpoint blockade responses (正常メラノサイトの抗原へepitope spreadingが起こることで免疫チェックポイント反応を至適レベルに高められる)」だ。
ICIの副作用は、免疫反応の閾値を下げるため、普通なら抑制されている自己免疫反応が高まることだ。面白いことに、メラノーマの患者さんにICIを行うと、かなりの数の人に白斑が生じることが知られている。同じ治療を受けても、肺ガン患者さんでは起こらない。このことは、メラノーマに対して免疫反応が始まると、epitope spreadingが起こって正常メラノサイトの発現する抗原まで標的になっていることを示している。
この研究では、実際これがepitope spreading によるかどうか調べる目的で、ICI治療の効果があった患者さんと、効果がなかった患者さんで、色素細胞が正常に発現する分子に対するキラー細胞が誘導されているか調べ、ICIの効果があった患者さんのみ正常抗原に対するT細胞が誘導されていることを確認する。
もしepitope spreadingが起こるなら、免疫の成立していないガン細胞でも、まずネオ抗原を増やしてガン免疫を高めてやれば、自然にepitope spreadingが起こってICI治療が可能になると考えられる。そこでICIに反応性の低いメラノーマをUV照射し、ネオ抗原を高めて免疫する実験を行い、これによりネオ抗原だけでなく、正常抗原に対しても反応が拡大し、UV照射を受けていないガンに対してもキラー細胞が誘導できることを示している。もともとUV照射はランダムに変異を誘導することから、ネオ抗原を持つ細胞の比率はバラバラで、ネオ抗原だけに免疫が成立しても、ネオ抗原を持たない腫瘍が増殖してしまうが、epitope spreadingが起これば、全てのガンを殺す可能性が出てくる。
メラノーマの場合はUV照射は選択肢だが、他のガンの場合に使える方法を開発する目的で、最後にablative fractional photothermolysisと呼ばれる、簡単に言えばレーザーで焼き切る方法で腫瘍の一部を壊して抗原を吐き出させると共に、TLR7を刺激する薬剤で自然免疫を高めることで、腫瘍抗原に対する免疫反応からepitope spreadingが起こって、ガンを治療できるか調べている。
結果は期待通りで、複数のガンが存在するセッティングで、一つの場所でこの処理を行い、ICI を行うと、他の場所に存在するガンも消失する。実際、正常抗原に対するキラー細胞も誘導されており、epitope spreadingが起こったことを示している。
他にもいろいろ実験が行われているが、以上が主要な結果で、epitope spreadingはICIがfirst lineの治療になったとき、効果のある患者さんを増やすために、切り札になる可能性を示している。
少し余談になるが、ワクチンには必ず必要な自然免疫の活性化により、ひょっとしたらepitope spreadingが起こって、後々自己免疫病が発症しないかは、免疫学者の頭をよぎったことは間違いない、もちろんRNAワクチンの場合、そのことは考慮済みで、自然免疫にキャッチされないmψ1という人工核酸をウリジンの代わりに用いて自然免疫を抑える工夫が行われている。
面白いことに、このRNAワクチンで話題のビオンテックは今年7月NatureにICIの効かなくなったメラノーマ患者さんに、4種類の正常色素細胞が発現する抗原のRNAを導入して、ICIの効果を半分の患者さんに誘導できたという論文を発表した。
このとき使われたのは、人工核酸ではなく、ウリジンを持つ自然のRNAで、これが強い自然免疫を誘導することで、ガン免疫を再度復活させることができた。この結果は、ビオンテックがこの分野でノウハウを蓄積した優れた会社であることを示すと共に、epitope spreadingを人工的にRNAワクチンで起こせること、さらに必要に応じて自然免疫を起こすことが強い免疫には必要なことを示している。
効果と副反応は表裏一体で、どちらかだけをみて何かを結論する愚だけはマスメディアも避けてほしいと思うし、RNAテクノロジーの歴史を勉強しないで、このワクチンについて語るのもやめてほしいとつくづく思う。このHPでは2017年からビオンテックを紹介しているが(https://aasj.jp/news/watch/7088)、今や専門家も含めて日本国民がまだかまだかと首を長くして待っている技術の重要性は、とっくの昔にわかっていた。
2021年2月22日
チェックポイント治療はメラノーマや肺ガンのように遺伝子変異が多いガンから認可され、徐々に適応が広がってきた。同じように、ネオアジュバント治療も、メラノーマで始まり、大規模治験は肺ガンへと拡大されてきている。そこで今日は肺ガン、特に非小細胞性肺ガン (NSCLC)治療をまずチェックポイント治療から始める治験について、最近の論文から紹介したい。
まずネオアジュバント治療ではないが、化学療法とチェックポイント治療を比べた治験がスペインとトルコからThe Lancet OncologyとThe Lancetに発表されている。NSCLCの中でガンのドライバー遺伝子が特定できたものは標的薬で治療できるが、それ以外の予後はよくない。これらの論文では、ドライバー遺伝子が見つからなかったNSCLC患者さんを、PD-1+CTLA4を合わせたチェックポイント治療と、従来の化学療法とに振り分けて、それぞれ約三年近く観察し、いずれの論文もチェックポイント治療の方が生存期間が長いことを示している。この結果は、今後我が国でもステージの進んだ肺ガン治療は、チェックポイント治療から始めるようになることは間違いない。
ただ我が国で一般的に行われているように、薬剤としてはPD-1だけでいいのか、あるいはPD-1+CTLA4の併用でいくのかが問題になるが、副作用の問題を除くと、両者併用が優れていることを示唆するのが、チェックポイント治療をネオアジュバント治療に用いたテキサス大学からの論文だ。タイトルは「Neoadjuvant nivolumab or nivolumab plus ipilimumab in operable non-small cell lung cancer: the phase 2 randomized NEOSTAR trial (手術可能な非症細胞性肺ガンのネオアジュバント治療としてのnivolumab単独、あるいはnivolmab+ipilimumabの比較:第2相NEOSTART無作為化治験)。
タイトルにあるように、この研究はStageIからIIIまでのともかく手術可能な症例を集め、手術前にPD-1抗体単独、あるいはPD-1+CTLA4抗体併用を2週間に1回投与、3回投与した後手術を行うというスケジュールで治験を行っている。普通の治療より間隔も短いからかもしれないが、自己免疫性の副作用は避けられず、ネオアジュバント治療中1人は肺の炎症により入院している。最終的に、単独23例、併用21例が治験を終えている。
この研究でstageを広く取っているのは、手術サンプルを調べて、効果を病理的に調べることが主目的になっているからで、生存率で評価した場合、手術可能症例ということもあり、30ヶ月時点では大きな違いはない。
しかし、切除標本の病理所見は、両者で大きく異なり、ガンの縮小率、そして局所へのT細胞の浸潤という点では、PD-1+CTLA4併用療法が明らかに優れていることを示している。 T細胞受容体についても調べており、治療により腫瘍内のT細胞受容体の多様性が上昇すると同時に、クローン性増殖も認められるが、この指標でもやはり併用療法の方が効果が高いことを示している。
以上の結果は、昨日のメラノーマと同じで、ネオアジュバント治療には、副作用は上昇するが、PD-1とCTLA4に対する抗体を併用するのが最も効果的だという結論になる。メラノーマでは、ネオアジュバントで効果があったかどうかが、手術とは無関係に予後を作用することになったが、肺ガンでは、ネオアジュバントの効果が、手術後の成績にも反映されるのか、もう少し待つ必要があるだろう。
このように、ガンになったらまず免疫療法という方向性が定着するような予感がする。
2021年2月21日
私が現役の頃は、ガンに対する最も信頼おける治療法は外科手術で、それがうまくいかない場合に放射線や化学療法を行なっていた。しかし、乳ガンを中心に、転移の存在が想定されるステージでは、外科手術だけでは再発が避けられないことがわかり、これまで外科を助ける目的で行われてきた放射線や化学療法を、外科手術の前に持ってくるというネオアジュバント治療が、長期的効果を得るための定番になってきた。
そして最近になって、これまでの治療法に加えて、PD-1やCTLA4を標的とした免疫チェックポイント治療が新たな治療として登場し、これまでの方法では治療が叶わなかった患者さんの治療に使われ、大成功を収めた。とすると、これだけ効果のあるチェックポイント治療を、外科療法や化学療法の前に使う方がいいのではと考えるのは当然で、特に外科療法の前にチェックポイント治療を持ってくる方法の可能性が調べられ始め、このHPでも2回チェックポイント治療をネオアジュバント治療に使った臨床研究について紹介した(https://aasj.jp/news/watch/12797、https://aasj.jp/news/watch/9787 )。
治療する医師の側からみると、ネオアジュバント・チェックポイント治療には大きなメリットがある。まず、ガン免疫が成立しているかどうかが先にわかる。そして、チェックポイント治療の結果を、切除した標本で確かめることができ、この治療を阻む問題についても解析できる。ただ、それ自体がどれほど効果があるのかについては、これまでより大規模な研究が行われており、間違いなく今後のガン治療が大きく変わるという結果が示されつつある。
実際2021年に入ってからもすでに57の論文が発表されているので、気になる論文を順に紹介することにした。最初はNature Medicine2月号に発表されたシドニー大学を幹事とする国際共同治験結果を紹介する。タイトルは「Pathological response and survival with neoadjuvant therapy in melanoma: a pooled analysis from the International Neoadjuvant Melanoma Consortium (INMC)(メラノーマのネオアジュバント治療に対する病理的臨床的効果:国際コンソーシアム参加施設でプールした成績)」だ。
この研究ではStage III B or Cで最初から転移が予想されるメラノーマ患者さん192例を、PD-1+CTLA4抗体、PD−1抗体のみ、そしてBRAF変異のあるケースは標的薬をネオアジュバントとして用い、その後腫瘍を摘出し、腫瘍で認められる病理的初見と、その後の予後について調べている。効果を病理で確かめ、その後の臨床経過と相関させる、まさに、ネオアジュバント治療のメリットを利用するものだ。
まず切除腫瘍から判断する病理的効果だが、標的治療の方がcomplete responseとしては成績がいいが、near complete responseを入れると、免疫治療の方が良い。面白いことに、標的治療のcomplete response はall or noneでnear completeというのがない。これはガンそのものに標的薬が聞くかどうかが問題で、免疫治療でのガン障害とは様相が大きく異なることがわかる。
重要なことは、ネオアジュバント免疫治療を行う場合、PD-1とCTLA4両方に対して抗体を持ちる方が圧倒的に成績がいい点で、病理的反応性の頻度はPD-1単独25%に対し、なんと63%に及ぶ。
そして期待通り、ネオアジュバント治療に対する反応が、完全に将来を予測できる。すなわち、二年目の生存率で見ると、病理的にcomplete responseが見られた患者さんでは89%が再発がないのに、最初に反応しなかった患者さんでは50%再発する。予後に関していうと、complete responseもnear complete responseも差がない。
さらにcomplete response群、及び反応が悪かった群でも標的薬よりチェックポイント治療の方がはるかに成績がいい。
以上の結果から、メラノーマ進行例で手術可能な場合は、PD-1とCTLA4を組み合わせたチェックポイント治療を行なった後、手術というのが一番良いという結果になっている。
明日は同じNature Medicineに掲載された肺がんの治療について紹介する。
2021年2月20日
何度も繰り返してきたが、個々の細胞ごとに遺伝子発現を調べることができるsingle cell RNAseqの技術は、生命科学一般に大きな影響を与えたが、とりわけ人間を用いる医学研究へのインパクトは大きく、新しい発見を続々もたらしている。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、最も悪性の腫瘍の一つグリオブラストーマに対する免疫反応細胞を、腫瘍に浸潤するリンパ球のsingle cell RNAseq(scRNAseq)を用いて調べ、新しいチェックポイント分子を見つけたという研究で、3月4日発行予定のCellに掲載された。タイトルは「Inhibitory CD161 receptor identified in glioma-infiltrating T cells by single-cell analysis(グリオーマに浸潤しているT細胞のsingle cell解析により抑制性のCD161受容体が発見された)」だ。
この研究ではグリオブラストーマと、IDH変異を持つグリオーマに分けて、手術サンプルから浸潤しているT細胞を分離、得られたT細胞のscRNAseqを行い、ガンに対する免疫状態を調べている。
まずはっきりしたのは、ガンに対する免疫成立を示唆するリンパ球のセットが全て腫瘍組織に存在すること、またグリオブラストーマではより強いストレスが免疫細胞にかかっていること、そしてグリオブラストーマに対してはより強い免疫T細胞が浸潤していることがわかった。
これだけなら、なるほどグリオーマにも免疫が成立しているという結論で終わるのだが、不思議なことに浸潤したT細胞がT細胞受容体とともにNK細胞受容体を発現しており、しかもNK受容体を発現している細胞ほど、キラー活性に関わる遺伝子発現が高いことを発見した。
そこでNK受容体が誘導される条件について調べるため、T細胞受容体からクローン増殖しているT細胞と、増殖していないT細胞に分けてNK受容体の発言を調べると、T細胞受容体依存的に増殖している細胞ほどNK受容体の一つ、KLRB1(CD161)の発現が高いことが明らかになった。
CD161は、CLEC2D分子を認識し、PD-1と同じようなチェックポイント分子として働くことがわかっている。すなわち、CDC161が増殖細胞に強く発現するということは、増殖を抑えるチェックポイント阻害がかかっている可能性を示唆している。
グリーマ組織ではCD161のリガンドCLEC2D分子は、グリオーマ自体と、浸潤している樹状細胞などの骨髄級で発現が見られることから、PD-1とPD-L1とよく似た発現パターンを示している。そこで最後に、CD161がチェックポイント分子としてガン免疫を阻害しているのか調べるために、末梢血のCD161陽性細胞を分離、このT細胞からCD161遺伝子をノックアウトし、そこに腫瘍特異的T細胞受容体遺伝子を導入して、グリオーマに対するキラー活性を調べるという凝った実験を行い、CD161ノックアウトすることでキラー活性が2倍上昇することを示している。また、この効果をヒト化した免疫系を持つマウスグリオブラストーマモデルで生体内でも確かめている。
最後に、他のガンでも同じようにCD161が発現しているかも確かめ、ほぼ同じような遺伝子発現パターンを持つT細胞が複数の種類の腫瘍にも認められることを示している。
以上が結果で、ほぼ全ての実験を人間の細胞を用いて行っていることから、実際の臨床に移しやすい結果だと思う。結果を見る限り、PD-1/PD-L1ほどの効果があるとはいえないが、グリオブラストーマの悪性度を考えると、ぜひ突き詰めていって欲しいと思う。
2021年2月19日
マンモスというと、大きな牙と長い毛を持つ毛長マンモスのイメージが定着しているが、実際にはアフリカで最初発生し、その後いくつかの種に分かれ、寒い環境に適応して毛長マンモスになったと考えられている。さらにアメリカで発見されたコロンビアマンモスは、ユーラシアから移動した毛長マンモスの子孫が、より暖かい環境に再適応して短い毛になったと考えられている。
もちろんマンモスはホモサピエンスともオーバーラップして存在しており、これらマンモスのゲノム研究も進んでいるが、コロンビアマンモスのゲノムの解釈には、さらに古い時代のマンモスゲノムの解読が必要だった。
今日紹介するスウェーデン自然博物館研究所からの論文は、なんとこれまで解読されたゲノムの中では最古、100万年以上前のマンモスゲノムを解読し、コロンビアマンモスの系統を明確にした研究で2月17日号のNatureに掲載された。タイトルは「Million-year-old DNA sheds light on the genomic history of mammoths(100万年前のDNAがマンモスのゲノムの歴史を明らかにした)」、で堂々と世界記録をうたっている。
これまで解読された最も古いゲノムは50万年前後で、だいたいこれが限界かと考えられてきた。方法を読む限り特に大きな方法の変化があったわけではないが、35b以上の断片のみいくつかの改良を合わせて、シベリアから出土した、地質年代で100万年前後のマンモス化石の歯からDNAを調整、ミトコンドリアに関しては完全に、核内DNAに関しては、5千万、9億、36億塩基対の解読に成功している。
シベリアの低温で化学的変化が抑えられていたとはいえ、100万年前のゲノムを解読したというのがこの研究のハイライトで、実際得られたミトコンドリアDNAの配列から計算される年代は、それぞれ165万年、134万年、87万年、核内ゲノムの解読が高いレベルで行えた2匹については、核内ゲノムでの年代測定も行い、128万年、82万年といずれも記録レベルであることを示している。
さらに重要なのは、今回解読された2種類は、これまで特定されていた系統群からかなり離れ、一種は毛長マンモスとは250万年前後に分離していることがわかる。
このように新しい系統群が見つかったことでわかった最も重要な発見は、これまで系統関係がはっきりしなかったコロンビアマンモスが、今回発見された新しい系統群と、毛長マンモス系統群が一度交雑してできた雑種由来であることがわかったことだ。実際それぞれのゲノムがほぼ半々で混ざっている。
さらに、今回発見された系統群では、低温適応に必要な毛長マンモスが進化させたTRPV3遺伝子の4種類のアミノ酸置換のうち、2種類しか有していない点で、おそらくシベリア出土とはいえ、低温適応途上の系統群であったと推察できる。
結果は以上で、マンモス分類学にとって重要な発見というだけでなく、より古いDNAの解析が可能かもしれないことを示した意味は大きい。ミトコンドリアについては解読が行われ出した直立原人までゲノム研究が広がれば、アフリカでの人類誕生の謎に光が当たること間違い無い。期待したい。