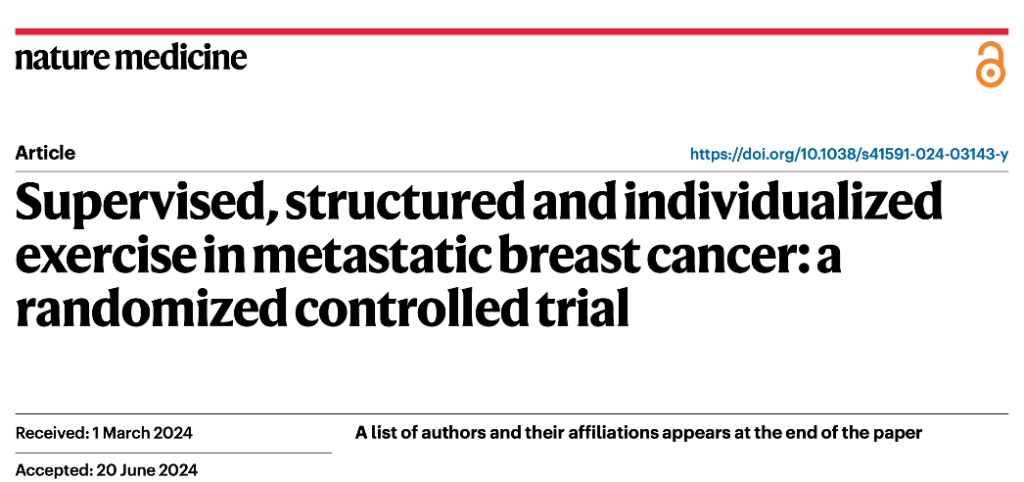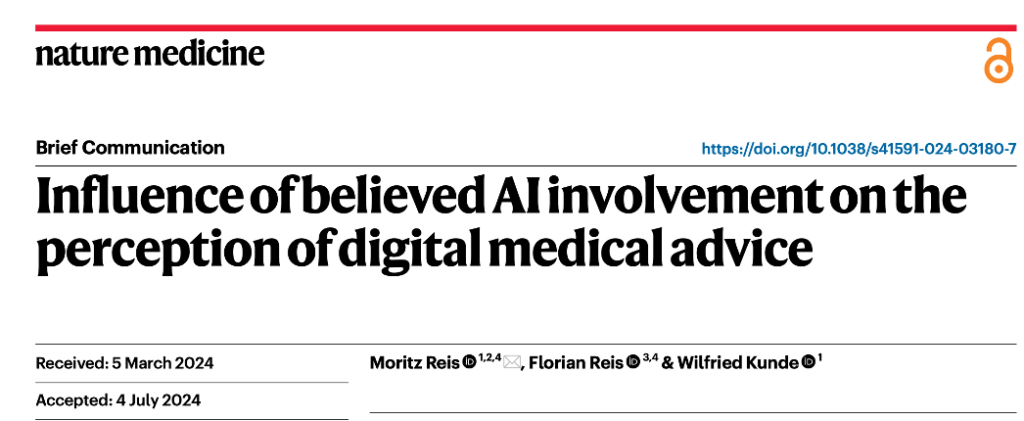2024年8月18日
人工知能と我々の脳を比べたときの大きな違いの一つが、我々の脳は睡眠し、しかもその間に覚醒時の記憶をよみがえらせ、その中から長期間留め置く記憶を形成する点だ。一方人工知能ニューラルネットは、神経回路の重み付けをするという意味では似ていても、常にインプットの嵐に晒される中での重み付けで、膨大なエネルギーを必要とする。
この睡眠時に行われる記憶の選択は、我々の人生そのものといえる脳の個性の基礎となっているが、睡眠中の記憶呼び起こしに海馬で観察される sharp-wave-ripple (SWR) という同期した神経興奮が関わることが知られていた。しかし、覚醒時のどの経験が SWR により組織化されているのかは、そのとき処理されている情報を特定する必要があり、簡単ではない。
今日紹介するコーネル大学からの論文は、まだまだ現象論ではあるが、これまで記憶の定着に関わるとされてきた SWR に加えて、新しいタイプの興奮が存在し、これが SWR による記憶への組織化を妨げていることを明らかにした研究で、8月16日号 Science に掲載された。タイトルは「A hippocampal circuit mechanism to balance memory reactivation during sleep(睡眠時の記憶呼び起こしをバランスさせる海馬の回路)」だ、
記憶の定着が覚醒時の神経興奮を SWR としてポジティブに選択するとしても、覚醒時の経験インプットは膨大で、ポジティブ選択だけで大丈夫かと思う。この研究ではマウス海馬の CA1、CA2、CA3 に複数の神経を同時に記録できる多重電極を設置し、睡眠中の神経興奮を記録し、これまで観察されてきた SWR に加えて、特に海馬 CA2 領域深部に BARR (barrage of action potentials)と名付けた、ゆっくりした周期の、しかも長時間続く集団的興奮が起こっていることを突き止める。
SWR は覚醒時の学習に関わった神経細胞で起こることが知られているので、学習時に活動した神経と、SWR、BARR の関係を調べると、SWR はこれまで知られている様に学習時に活動した神経が興奮するが、BARR は学習に関わった神経を抑える方向に働き、学習時と SWR に強く興奮した神経では、BARR時期には強く抑制されることがわかった。
また、このときの興奮に関わる神経細胞も、光遺伝学的に調べると、SWR では Parvalbumin 陽性介在神経、BARR ではコレシストキニン陽性のバスケット細胞が、錐体細胞と異なる回路を形成し、学習時の神経興奮を、それぞれポジティブ、ネガティブに調節していることがわかった。
最後に、BARR の発生を光遺伝学的に抑制する実験を行い記憶の定着について調べると、BARR を抑えても記憶の定着が抑えられることがわかった。
2024年8月17日
昨日Zoom開催した「大規模言語モデルと人間の脳を比較した研究論文」についてのジャーナルクラブをYouTube配信しているので是非ご覧いただきたいが(https://www.youtube.com/watch?v=lpzWzTTdcjc )、一般には難しい内容をうまく伝えられたか心配だ。ご覧いただいて、是非問題点を指摘してほしい。
ただ、このジャーナルクラブで伝えたかったのは、Transformer 誕生以前も脳活動と単語や意味を相関させるために機械学習を多用していた脳科学が、Transformer ベースの大規模言語モデルによってさらに新しい可能性を切り開いていることだ。大規模言語モデルは、我々の言語世界を、多次元空間に分布している単語などの構成ユニットとして表現している。すなわち、我々の頭の中で繰り返し行われてきたユニットのコンテキストをベクトル空間の位置として表現できる様になった。これを利用することで、同じコンテクストを感知している脳の神経活動を、コンテクストレベルで言語へと再変換できる様になり、これまでの様な脳活動と単語といった単純な相関を遙かに超えた研究可能性が生まれている。
この脳活動と大規模言語モデル (LLM) を比較し、統合する研究の可能性を示せるいい例はないかと論文を調べていたところ、8月15日号の The New England Journal of Medicine に、コーネル大学を中心とした国際チームからCognitive Motor Dissociationについての論文を見つけたので、紹介することにした。タイトルは「Cognitive Motor Dissociation in Disorders of Consciousness(意識異常で見られる認知と運動の乖離)」だ。
Cognitive motor dissociation (CMD) は、周りで起こっていることを認知できているのに、運動機能が完全に傷害されているため、わかっていると伝えられない状況を指す。従って、一般的な検査だけだと、植物状態として十把一絡げにされてしまう危険がある。
これを調べるためには、植物状態であることを診断したあと、脳の活動を見る機能 MRI (fMRI) や脳波系を用いて、患者さんに例えば「手を開いたり閉じたりしてみて」といった認知課題に、それに合わせて運動しようとする脳反応が現れるかを調べる必要がある。この検査は、ただ音が聞こえるとか、光に反応するといった以上の脳の認知機能を必要とする課題で、これによって患者さんが本当は周りの会話を理解していることすら診断できる。
この研究では北米とヨーロッパの様々な施設に入院している植物状態の患者さん241 名について、マニュアルに精通した専門家による認知反応検査と、脳内で行動を思い浮かべる様指示したときに見られる神経反応を fMRI や脳波計で調べる検査を行い、認知反応検査で植物状態と診断された患者さんの何パーセントが指示を頭の中で思い浮かべられるかを調べている。
結果はなんと植物状態と診断された25%の方が CMD 状態で、わかっているのに動けないだけであることが明らかになった。ただ、この研究では患者さんの反応を完全に理解できているわけではない。刺激に対する反応以上であることはわかるが、しかし患者さんの訴えたいことを理解できているわけではない。
しかし、言語をベースにした脳活動の解読が可能になると、おそらく CMD の患者さんの中には、大規模言語モデルを通して、会話が可能になるのではないかと想像する。遠い未来の様に思うが、実際には一定のレベルであれば実現は早い気がする。そんな世界を GPT-4 に書かせてできたイラストも掲載しておく。
2024年8月16日
今日は、ほとんどのメディアが昨日報道していた、オーストラリア・パースにあるカーティン大学から発表されたトーンヘンジの祭壇石がスコットランドから運ばれてきたことを示した論文を、自分なりに紹介することにした。
上の図は2011年、最後の大学院生だった木下夫婦とストーンヘンジを訪れた時に撮影した写真だが、3000年前から建設を始めた理由は何であれ、ホモサピエンスの発明した最大の道具、言語の壮大さを感じる構造物だ。言語は音と言う媒体を持つが、道具の中では最も物性に乏しい。しかも、個人の中にとどまらず社会的に勝手に進化した上で、また個人に寄生する。このおかげで、物理的に存在できない未来を表現できるようになり、それは死後の世界といったフィクションを可能にした。エジプトと異なり、ストーンヘンジが構築された時代、ブリテン島にはまだ文字はなかったと思う。とすると、ストーンヘンジは、見たことのない言語世界に多くの人が動かされ、協力してそれをこの世に実現使用とする驚くべき努力を示している。
その意味で、これらの巨石をどこから切り出し、運んできたのかは人類学にとって重要なテーマで、研究が続けられてきた。まず、ストーンヘンジを代表する外側のサークルはイングランド南部のサーセン石で、大きい石だが近くで調達している。
これ以外にはウェールズ地方から運ばれてきた小さな石が存在し、何回にもわたって建築が進められた際持ち込まれたと考えられる。なぜわざわざウエールズとも思うが、場所的には200kmぐらいで、特に異なる種類の石を配置することを構想したのだろう。
この論文が調べたのは、近くには存在しない石の中でも大きな砂岩で、6 t もある。これまではこの砂岩もウェールズから運ばれてきたとされてきたが、これを疑って調べ直したのがこの研究だ。
紹介した様に、責任著者はオーストラリアの大学に属しており、国宝級の構造物から、30ミクロンのセクションをオーストラリア在住の研究者に託したというのにまず驚く。
この論文を読むと、現代の鉱物学がどのように進められるのかもよくわかる。砂岩は様々な成分が固まっているので、それぞれの成分の形成年代をアイソトープの年代測定を使って調べたあと、岩石自体が形成される過程をベースに、砂岩全体の特徴を決めている。
こうして決められた岩石ができる過程をベースにした特徴を、英国に分布する様々な砂岩と比べると、スコットランドの Laurentia 楯状地をベースに、グランピアン地方のオルドビス紀のマグマ活動由来の珪長質岩と苦鉄質岩が合わさって形成された砂岩とほぼ同一と結論できる。
ヨーロッパの自然博物館に行くと、膨大な鉱物コレクションが展示されているが、現代の鉱物学の手法と重要性を改めて認識させられる研究だ。
そして、これが正しいとすると、スコットランド北東部グランピアン地方から、はるばる750km、言語的に形成された共同幻想に駆られて6tもの石をストーンヘンジまで運んできたことになる。産地が海辺にあり、陸路はほぼ考えられないので、すでにイギリスを一周する海路ができていたと結論しているが、それにしても驚くべき人間の共同エネルギーを駆り立てる言語の力を思い知る論文だった。
2024年8月15日
エイズが問題になり始めた1980年代からエイズ研究を見てきたが、当時、訳のわからない死の病だったエイズも、いくつかの薬剤を組み合わせる抗レトロウイルス療法 (ART) の開発によって、患者さんも免疫不全から解放され、死の病ではなくなった。とはいえ、HIV を体内から除去する方法は達成しておらず、患者さんは一生涯 ART 治療から解放されないため、現在ワクチンや、遺伝子操作をはじめとする、ART から患者さんを解放する方法の研究が進められている。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、毒をもって毒を制するというか、欠陥エイズウイルスを感染させて、エイズウイルスの増殖を邪魔する方法の開発で、8月9日号 Science に掲載された。タイトルは「Engineered deletions of HIV replicate conditionally to reduce disease in nonhuman primates(HIV に欠損を導入して感染させるとサルのエイズ症状を抑えることができる)」だ。
ウイルス感染が続くと、欠陥ウイルスゲノムができて、これがウイルスとして放出することで、病原性ウイルスの伝搬が防がれるという現象は、特に RNAウイルスで観察されてきた。従って、エイズでも欠陥ウイルス感染が持続感染することで、病原ウイルスの増殖を一定程度抑えられるのではと期待される。しかし残念ながら、エイズウイルスではこのような現象はほとんど報告されてこなかった。
そこで、CD4T細胞が持続的に供給される長期培養系で、蛍光ラベルした HIV を感染、維持する実験系を作成し、100日間培養を続けると、HIVウイルスの増殖とT細胞数が逆相関的に上下を繰り返しながら HIV感染を維持できるが、50日目ぐらいから、HIVの数が持続的に低下する状態が生まれる。このときに、欠陥ウイルスが発生したと予想し、このときに発生した HIV を調べると、2回実験を行って2回とも、Pol遺伝子の一部から、vif、vpr修飾遺伝子が欠損したウイルスが発生していることがわかった。
この欠陥ウイルスは HIV と同時に感染させると、試験管内でのウイルス増殖を抑えるが、効果が長続きしない。そこで、自然発生した欠陥ウイルスをさらに操作して、増殖や感染性を高めたウイルスTIP-2 を完成させている。このウイルスでは、最初の欠損により除去された central polypurine tract と呼ばれるプラス鎖合成に必要な部位を再導入し、tat、 rev調節遺伝子から env構造遺伝子まで除去している。この結果、感染すると、病原性を持つ完全な HIVウイルス粒子ができるのを邪魔するとともに、自らもウイルス粒子に取り込まれて CD4T細胞に感染し、感染した細胞で病原性HIVウイルスの増殖を抑えることで、トータルの病原HIVウイルス量を抑えると期待できる。
実際の身体の中でも、理論通りトータルのウイルス量を抑え、免疫不全の発生を抑えられるか調べるため、サル型エイズウイルスモデルで、TIP-2 を前もって投与すると、致死量のサルエイズウイルス感染でのウイルス量を低下させ、ART なしにサルの生存を維持できることを明らかにしている。
この動物で血中ウイルス量を調べると、1例で全く低下が見られず死亡したケースを除くと、大体ウイルス量を 1/1000 に抑えることに成功している。さらに、免疫不全の発生が抑えられることから、HIV粒子に対する抗体の産生もコンスタントに見られる。
あとは人間の CD4T細胞培養を用いたモデル系で、ART を使っている患者さんが治療をやめたときに、HIV産生量を抑えられるか、あるいは T細胞数が保全されるかなどを調べ、最終的に人間でも一回の注射で、HIV をコントロールできる可能性は高いと結論している。
実際には HIVウイルスを除去できるわけでもないし、欠陥ウイルスも感染するので、飛び込んだゲノム部位に応じて様々な問題が起こることは理論的に予想できるが、例えばサハラ以南のアフリカで治療を受けられるのは今も50%程度にとどまっていることを考えると、一回の注射でトータル HIV ウイルス量を落とす治療は魅力的だ。100日間 CD4T細胞を飼い続ける培養で発見した執念の欠陥ウイルスなので、ぜひ治験にまで進んでほしい気がする。
2024年8月14日
ほとんど検査法の開発論文については紹介したことがないと思うが、今日は面白いなと思った検査法開発論文を2編紹介する。
最初のハーバード大学とオックスフォード大学からの共同研究は、血中のタンパク質を使って生物学的老化度を測定しようとする試みで、8月8日 Nature Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Proteomic aging clock predicts mortality and risk of common age-related diseases in diverse populations(タンパク質による老化時計は、様々な集団の死亡率と、老化に関わる病気を予測できる)」だ。
現在、生物老化を測定できると標榜して提供されているのは、Horvath 時計の様なメチル化DNAを調べる方法がポピュラーだが、例えば単純な死亡率との相関が得られないなどの問題があった。これに対して、メチル化にせよ最終的には身体のタンパク質の変化につながることから、様々なタンパク質の量を組み合わせて老化を図る方法が研究されている。この典型が細菌老化研究の大ヒットとして紹介した IL-11 が老化を促進しているという論文で(https://aasj.jp/news/watch/24856 )、一つのタンパク質でも機能がはっきりしていることで、老化との相関が明確に理解できる。
この研究では UKバイオバンクに登録された平均57歳、4万5千人規模のコホート参加者を11年から14年観察した結果を、血清中の2897種類のタンパク質の中から、老化に相関するタンパク質204種類、及びさらに絞り込んだ20種類を総合的に計算したスコアと相関させている。
まず、204種類でも、20種類でも、英国内の集団だけでなく、中国やフィンランドのコホート参加者についても、ほぼ同じように実年齢と強い相関を示す。
ただ、実年齢だけでなく、どちらのスコアでも、たとえばテロメアの長さ、あるいは自覚的老化指標や、歩く速さなどと相関する。さらに、腎臓、肝臓、心臓疾患とも関連することから、同じ実年齢の中での老化度をかなり正確に知ることができる。
この検査の最大の売りは、単純な死亡率や、心臓、肺、肝臓、腎臓など、様々な病気の起こりやすさとも相関することで、例えばスコアの高い場合、早発性のアルツハイマー病のリスクも予測できる。
このように様々な指標で比べたとき、DNAメチル化を指標とする老化時計より優れており、特に死亡率を反映することがこの方法の最大の売りになっていることが示されている。
この指標に用いる20種類のタンパク質は、細胞外マトリックス6種類、炎症4種類、ホルモン産生調節3種類、細胞シグナル3種類、エネルギーバランス2種類、発生分化3種類で、その気になれば安価で提供できると思われる。今後、介入でこの指標を若返らせることができるかなどの研究が行われると思うが、手軽な老化時計の検査にかなり近づいている気がする。
もう一編は、スペイン La Rioja 大学、イタリアベローナ大学を中心とする国際チームからの論文で、膵臓ガンの早期診断を、なんと自己抗体を用いて実現しようとする研究で、Angewandte Chemie にオンライン掲載されている。タイトルは「Detection of Tumor-Associated Autoantibodies in the Sera of Pancreatic Cancer Patients Using Engineered MUC1 Glycopeptide Nanoparticle Probes(ガンに関連する自己抗体を、膵臓ガン患者さんの血清で操作した MUC1 糖ペプチド結合ナノパーティクルで診断する)」だ。
通常ガンの診断は、ガン細胞が分泌する分子をいち早く捉えて診断に用いる方向で行われるが、この研究では膵臓ガンが産生するムチンの一つ MUC1 の20−120回繰り返す20アミノ酸が糖修飾された場合、自己抗体が作られやすいということに着目し、MUC1 ペプチドに反応するモノクローナル抗体との結合を指標に、糖鎖修飾を受けた短いペプチドを14種類設計し、膵臓ガン患者さんの血清で、膵臓ガンとそれ以外を区別できるか調べている。2種類の抗体との結合を指標に設計した中で、5E5 という抗体に結合する4種類のペプチドは、全てコントロールと膵臓ガンを明確に区別することに成功している。
結果は以上で、早期診断可能かどうかはこれからの問題だが、一般に使われるゴールドナノ粒子を用いる、かなり特異的なガン診断が、なんと自己抗体を指標に可能になるとは驚きだ。かなり期待している。
2024年8月13日
以前、腸内細菌移植で自閉症スペクトラム症状が抑えられる原因の一つが、細菌叢の変化に起因する脳内タウリンの上昇で、タウリンを妊娠中から食べさせると自閉症様症状が抑えられるとするカリフォルニア工科大学からの論文を紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/10310 )、この論文を読まれた方が、自閉症スペクトラムにタウリンを飲ませていいかと聞いてこられた。ただ、紹介したのはマウスの実験で、元々タウリンが神経系に影響する詳しいメカニズムがよくわかっていないので、タウリンは飲んで悪いという話は少ないが、それでも消化管症状や糖代謝が変化することも指摘されているので、飲むとしても慎重に様子を見た方がいいと答えた。このような、動物実験と実際の臨床ギャップについては論文紹介でいつも頭を悩ませる点だ。
ただ、今週読んだ8月7日 Nature オンライン論文の中にスタンフォード大学から、これもネズミでの結果だが、タウリン研究としては重要な研究が発表されていたので、紹介することにした。タイトルは「PTER is a N-acetyltaurine hydrolase that regulates feeding and obesity(PTER は摂食と肥満を調節する N-acetyltaurine hydrolase )」だ。
この研究は最初から N-acetyltaurine (NACT) をタウリンとアセテートに分解する酵素特定を目指す、極めて古典的な仕事だ。NACT はその合成経路も明確ではないが、運動や飲酒に伴って上昇する面白いタウリン化合物だ。
腎臓組織ホモジネートを分画し、NACT を分解する酵素 (PTER) の活性を持つ分画を絞っていって、最終的に NACT にかなり特異的な PTER を特定し、遺伝子クローニングに成功する。久しぶりに古典的手法の研究を読んだ気がして、逆に不思議な気分だ。
次に生化学的特異性、そして αフォールドを利用した構造解析を行ったあと、ノックアウト実験に進んでいる。PTER をノックアウトすると、期待通り様々な組織で NACT の濃度が上昇する。もちろん血中濃度も上昇するが、心臓、脾臓、腎臓、筋肉での上昇は大きい。
次に、ノックアウトによる代謝変化を調べると、ノックアウトでは体重上昇が軽度に抑えられ、また食事の摂取量も低下し、インシュリン感受性も上昇する。
次に高脂肪食を与えたときに、代謝改善効果があるか調べると、ノックアウトだけでは大きな変化はないが、タウリンを投与してさらに NACT を上昇させると、摂食量の低下が見られる様になる。
そこで、ノックアウトではなく NACT をそのままマウスに投与する実験を行うと、50mg/kg 投与で、摂食が低下し、体重も減少する。以上の結果から、NACTは直接代謝を変化させる作用は低いが、摂食を抑制することで代謝の改善と体重減少を誘導することが明らかになった。
最後に、この摂食抑制作用のメカニズムを調べ、脳幹の摂食中枢神経のGDNF受容体が刺激される際の閾値を変化させることで、摂食を抑制しているのではないかと結論しているが、メカニズムについてはまだまだ研究が必要だと思う。
最後に、タウリンから NACT が合成される経路を検討し、1)PTER 自体によるタウリンとアセテートから NACT 合成経路、2)酵素非依存的経路、3)そして腸内細菌叢による経路が存在する可能性を示している。
タウリンは健康飲料としてポピュラーな分子だが、実際の代謝経路についてはまだまだ研究が必要なこと、そしてその中から思いもかけない健康への介入方法が生まれる可能性がよくわかる論文だと思う。多くの患者さんたちが注目しているので、研究を加速してほしい。
2024年8月12日
プロバイオやプレバイオで不安を和らげ、自閉症スペクトラムの社会性を回復できることを示した論文について一度まとめて紹介したことがあるが(https://aasj.jp/news/autism-science/11102 )、このような相関関係は腸脳相関と呼ばれて盛んに研究されている。
腸脳相関は細菌叢が脳に働くと言うだけでなく、例えば迷走神経を刺激して細菌叢を変化させ腸のバリアーを高め、炎症性腸疾患の症状を改善できることを示した論文の様に、逆方向の関係を示した論文も多い。
今日紹介するマウントサイナイ医科大学とチュービンゲンマックスプランク研究所からの論文は、迷走神経刺激と細菌叢の相互作用について、特に十二指腸のブルンナー腺に注目して明らかにした研究で、8月8日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Stress-sensitive neural circuits change the gut microbiome via duodenal glands(ストレスに感受性の神経回路が十二指腸腺を介して腸内細菌叢を変化させる)」だ。
ブルンナー腺は十二指腸粘膜下にある粘液腺で、アルカリ性の粘液を分泌して胃酸を中和し、消化酵素の働きを助ける重要な腺で、粘液を作るという点では小腸以降の腺組織と同じでも、ペプシノーゲンの発現、Mucin6 の強い発現、EGF分泌などはブルンナー腺特異的で、独立した粘液組織と考えられる。
以上の特徴は、消化だけでなく、当然細菌叢にも影響があると考え、この研究ではまずコレシストキニンによりブルンナー腺を刺激したときの小腸細菌叢を調べ、特に乳酸菌の増殖が高まることを発見する。
コレシストキニンは消化管ホルモンなので、このブルンナー腺の特徴が腸脳相関にも関わることを示す目的で、ブルンナー腺の神経支配を光遺伝学的方法を用いて探索し、最終的に延髄の dorsal motor nucleus (DMV) 由来の迷走神経がブルンナー腺を支配していることを確認する。
この結果に基づいて、様々な方法で迷走神経を刺激したり、除去したりする実験を繰り返し、迷走神経刺激によりブルンナー腺が活性化され、粘液が分泌されることで乳酸菌の増殖が起こることを明らかにする。ただ、変化は細菌叢にとどまらず、例えば迷走神経刺激が伝わらなくすると、腸上皮バリアーが弱まり、感染が起こりやすくなり、腸内リンパ組織や脾臓の免疫反応低下にまで影響が及ぶことがわかった。その結果、病原菌感染によるマウスの死亡率は上昇する。
重要なことは、ブルンナー腺刺激、あるいは抑制の効果が、全て腸内細菌叢を介して起こっていることで、ブルンナー腺を除去したマウスでも、健康マウスの便移植、あるいは乳酸菌とビフィズス菌を会わせたプロバイオ投与で、バリアー機能や免疫機能を回復させることができる。
まさに文字通り、腸脳相関の系といえるが、研究ではさらに高次脳機能との関わりを調べるため、まず DMV 領域に投射する中枢神経を探索し、不安やストレスに関わる脳領域である扁桃体と DMV との結合を特定する。次に、扁桃体を刺激する実験を行い、扁桃体の興奮は、MDV を介してブルンナー腺を活性化し、乳酸菌の増殖を促す。一方、不安やストレスは、扁桃体神経の興奮を抑制し、その結果ブルンナー腺の活動が低下し、腸管の炎症や免疫異常を誘導することを明らかにする。
一方、マウスにストレスを与えた時に起こる細菌叢や腸内免疫系の変化は、迷走神経系刺激で回復できることを明らかにしている。
以上、脳高次機能、自律神経、消化管ホルモンサーキット、そして細菌叢の複雑な相関が明らかになった。いずれにせよ、ストレスが続いたときは迷走神経を刺激するか、プロバイオは効果がありそうだ。
2024年8月11日
最近読んで気になった臨床研究をいくつか紹介する。
最初のコロンビア大学とウクライナ人口研究所からの論文は、1932年ホロドモールと呼ばれるウクライナ生産穀物をスターリンが略奪した結果起こった、なんと2%のヒトが飢餓でなくなったという悲しい歴史の最中に生まれた子供の2型糖尿病リスクについての研究で、8月9日 Science に掲載された。
これまで、1944年オランダでの飢餓、1959年の中国の飢餓時に誕生した子供が、エピジェネティックな変化により、中年以降になってから2型糖尿病のリスクが高まることが報告されている。この研究も同じラインにあるが、ウクライナの飢餓期間が1933年前半に集中し、地方ごとの飢餓の記録が残っており、しかも国家的糖尿病登録が存在することから、正確にリスク判定ができるメリットがある。
結果だが、2型糖尿病は飢餓以降に生まれたポピュレーションで増加傾向にあるが、飢餓に見舞われた地域とそれ以外の地域であまり差はなく、飢餓とは無関係な傾向であることがわかるが、1933年前半に生まれた集団は、特に母親が妊娠初期に飢餓を経験した場合に、リスクが4倍近くに跳ね上がっている。中国の研究では、子供時代の飢餓も糖尿病リスクを高めることが報告されているが、ウクライナの飢餓では、妊娠中期以降の飢餓経験では、リスクは上昇しないことが示された。
以上が結果で、エピジェネティックスとは何かを教えてくれる悲しいエピソードだが、今もなおこのような悲しいエピソードは地球上で絶えることがない。
次の中国南京大学と米国ミシガン大学からの論文は伝統的な心臓に対する漢方薬Qiliqiangxinの効果を、無作為化二重盲検偽薬治験で調べ直した研究で、8月2日 Nature Medicine にオンライン掲載された。
3119のHYAH心機能分類で、通常の身体活動で症状が出る2度以上の患者さんで、左心室ポンプ機能(HFrEF)が 40% 以下、BNP が 450pg/ml 以上の心不全の患者さんを無作為に分け、偽薬、あるいは Qiliqiangxin を投与して死亡率と様々な心臓発作の頻度をアウトカムとして調べている。
結果は、いずれの評価指標もも Qiliqiangxin 投与群で2−3割改善する一方、ほとんど副作用は見られなかった。これまで漢方薬は長い歴史を持っていても、大規模治験は行われてこなかった。その意味で、この研究の意義は大きい。ただ、SGLT2 阻害剤が組み合わさった新しい標準治療が進展している現在、これを押しのけて使われるチャンスは少ないと思う。一方で、Qiliqiangxin は炎症を抑えたり、PPARγ 活性化機能もあることから、現在の治療法と併用で効果があるかを調べる治験が重要だと思う。
次のユトレヒト大学を中心とするヨーロッパ、オーストラリアの研究施設が共同で発表した論文は、ステージ Ⅳ の転移乳ガンに対するエクササイズの効果を無作為化治験として調べた研究で、7月25日 Nature Medicine にオンライン掲載された。
この研究では転移が発見されて2年、様々な治療を行ってきた357名の患者さんを無作為に分け、片方は転移性乳ガンの治療とともに、専門家によるエクササイズプログラムを9ヶ月続け、もう片方は転移性乳ガンの通常の治療だけを続け、9ヶ月目の自覚的 QOL を調べている。
結果だが、明らかに疲れやすさを中心に QOL は改善する。これが結果の全てで、生存期間などについては最初から評価項目にはしていない。転移した後も、乳ガン治療は長丁場が続く。その意味で、患者さんの QOL をアウトカムにする治験の意義は大きい。
最後のドイツ・ビュルツブルグ大学からの論文は一般の人(ドイツ人)が AI に対して持つ印象の違いを調べた研究で、7月25日 Nature Medicine にオンライン掲載された。
研究では、患者さんの質問に答える様々なシナリオを一般の人に見てもらって、患者に寄り添っている、信頼できる、理解できる、の3点について評価してもらう。このとき、全く同じ答えのソースを、医師による、AI による、あるいは AI と医師によると変えて提示したとき、シナリオに対する印象が変わるか調べている。
結果は明確で、患者に寄り添うか、信頼できるかについての評価は、AI が答えを出すソースに入っていると低下する。重要なのは医師と AI の場合も、医師だけより評価が低いことから、一般の人たちが AI に対してまだ信頼していないことを示している。
以前実際に ChatGPT と医師に同じ問題を答えさせて、その答えを患者さんが評価した論文では、圧倒的に ChatGPT の答えがわかりやすく寄り添っているという結果だったのを考えると、人間が間違いなく AI を敵視し始めていることがわかる。
以上、いろんなことが臨床テストとして調べられている。
2024年8月10日
骨髄幹細胞は骨髄にとどまって様々な血液細胞を作り続けるが、一部は骨髄を離れて血液に流れてくる。これを利用したのが末梢血幹細胞移植で、動員される幹細胞の数を増やすために、G-CSFを前もって投与する。この末梢血幹細胞でも十分造血系再建が可能なため、何故ある幹細胞は骨髄にとどまり、同じ能力のある幹細胞が骨髄から離れるのか、明確な答えはなかった。
今日紹介するアルバートアインシュタイン医科大学からの論文は、マクロファージから骨髄局在のための分子を、膜の断片が移行する Trogocytosis により獲得した幹細胞が骨髄に残りやすくなるという、意外な事実を示した研究で、8月6日 Science に掲載された。
元々このグループは骨髄内のマクロファージが血液幹細胞の骨髄局在を決める重要な要因であることを研究していた。その中で、血液幹細胞をマクロファージのマーカー F4/80 でさらに2群に分けることができることを見いだしていた。各群を移植して幹細胞の機能を調べると、F4/80 陰性群の方が再建能は高いが、分化能ではほ同じといえた。
次にG-CSFを投与したときの動員を調べると、動員されるのはほとんど F4/80 陰性幹細胞で、F4/80 陽性群は骨髄から動員されにくいことがわかる。面白いことに、老化マウスでは F4/80陽性 の細胞が低下する。
表面マーカーを用いて血液幹細胞をさらに分別するのは血液学の王道で、遺伝子発現の違いを調べた普通の仕事になるのだが、この研究では F4/80 だけでなく、いくつかのマクロファージマーカーが同時に発現していることなどから、遺伝子発現の違いではなく、マクロファージの膜成分が膜ごと幹細胞に移行する Trogocytosis により分子が移行するのではと着想し、これを確認するための様々な実験を行っている。
決め手になるのは、ドナーとレシピエントの血液を区別できるようにして、幹細胞移植を CD169 / 蛍光分子を発現しているレシピエントに移植すると、ドナーの血液幹細胞の中に、レシピエント由来の蛍光分子を取り込んでいる細胞が存在することを示した実験で、これによりマクロファージから何らかの機構で様々な分子を取り込んだ幹細胞が、骨髄に局在する能力を付与されている可能性が示唆された。
マクロファージから幹細胞へと分子が移行するするメカニズムとして、一番ポピュラーなのはエクソゾームを介する伝搬だが、エクソゾーム形成を阻害しても、分子移行が起こること、さらに培養実験から、細胞と細胞が接着することが移行に必須であることを示し、エクソゾームではなく、Trogocytosis によりマクロファージ分子が幹細胞に移行すると結論している。
この移行により、骨髄内局在を決めることが知られている CXCR4 が幹細胞に移ってくると、より骨髄への局在化が促進されると結論している。そして、Trogocytosis には c-Kit の発現とシグナルが関わっており、シグナルを薬剤で阻害すると分子移行は低下する。すなわち、幹細胞の中でも c-Kit 発現の高い幹細胞ほど Trogocytosis が高まり、マクロファージ由来分子を獲得しやすくなると結論している。
以上は全てマウスの話なので、最後に人間の骨髄でも同じ現象が見られるのかを調べており、c-Kit の発現が高い集団ほど、マクロファージマーカーを発現していること、また末梢に流れてきた幹細胞にはマクロファージマーカーの発現が低いことを示し、人でも同じことが起こっていると結論している。
結果は以上で、転写の違いでないという点についてはさらに実験が必要だと思うが、Trogocytosis のような意外なメカニズムが骨髄局在を決めているとすると、骨髄幹細胞の動態を一から見直す必要がある。
2024年8月9日
昨日は脳内にできた腫瘍とセロトニン神経との相互作用を研究した論文を紹介したが、これに続いて今日紹介するロックフェラー大学からの論文は、乳ガンに脊髄後根から投射している感覚神経が分布すると悪性度が増して転移することを示した研究で、8月7日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Neuronal substance P drives metastasis through an extracellular RNA–TLR7 axis(神経由来サブスタンス P が細胞外 RNA による TLR7 刺激を誘導し転移を促進する)」だ。
このグループは、神経投射を誘導する SLIT2 分子が乳ガンの発生した血管内皮から分泌され、これが乳ガンへの神経投射を促し、これが乳ガンの転移を促進する可能性を明らかにしていた。この研究では、血管内皮から SLIT2 遺伝子をノックアウトする実験で、SLIT2 がないと脊髄後根からの感覚神経投射が阻害されることを確認し、あとは神経と乳ガンの相互作用について研究を進めている。
まず、転移性が異なる乳ガンをマウスに移植する実験から、転移性が高い悪性の乳ガンほど感覚神経投射の程度が高く、しかも乳ガン自体も神経細胞が発現する分子を発現して神経の様に振る舞うことを発見する。
次に乳ガン細胞のオルガノイド培養実験で、感覚神経と共培養することで転移性が低い乳ガンも転移性の高い乳ガンへと転換することを示し、神経細胞自体がガン細胞の悪性化を誘導していることを明らかにする。
逆に転移性の高いガン細胞を移植する実験で、移植組織の感覚神経を除去していこうと、転移が起こらないことも確認している。
次は、乳ガンと感覚神経の相互作用のメカニズムになるが、
乳ガンと感覚神経が共培養されると、神経細胞の興奮が高まり、その結果様々な神経ペプチドが分泌される。
これらペプチドのうち、サブスタンス P (SP) は培養に加えると、乳ガンに発現している受容体を介して、悪性度を高める。また、SP を分泌できないマウスに移植すると、転移が強く抑制される。
人間の乳ガンでもリンパ節転移が例では、組織内の SP 発現が高い。
を明らかにする。
次は SP による悪性化のメカニズムだが、SP が直接悪性化分子を誘導するのではないため、わかりにくいところだが次の様になる。
まず SP に対する受容体の発現量が高いと、細胞死を誘導する。このため、強い刺激を受けた一部の細胞で細胞死が誘導される。こう聞くと、SP は乳ガンを殺してくれる良いシグナルに見えるが、細胞死した一部の細胞から RNA がリリースされると、これが乳ガンの TLR7 分子を介する自然免疫刺激シグナルを誘導し、その結果 PI3K-AKT という重要なシグナル経路を介してガンを悪性化させる。
細胞死なら神経投射がなくても常に起こっているのではと思われ、無理があるシナリオに見えるが、SP の刺激を抑えることが知られる、吐き気を抑える目的で使われている薬剤アプレピタントを乳ガンを移植したマウスに投与すると、乳ガンの増殖が抑えられることを示して、このシナリオに沿った乳ガンの治療可能性を示しており、乳ガンの場合末梢での神経投射がガンの悪性化に重要であると結論している。
アプレピタントは抗ガン剤による吐き気を抑えるために利用されていると思うので、ネオアジュバント治療時にアプレピタントを使用したかどうかでガンの再発を調べる調査は重要な気がする。