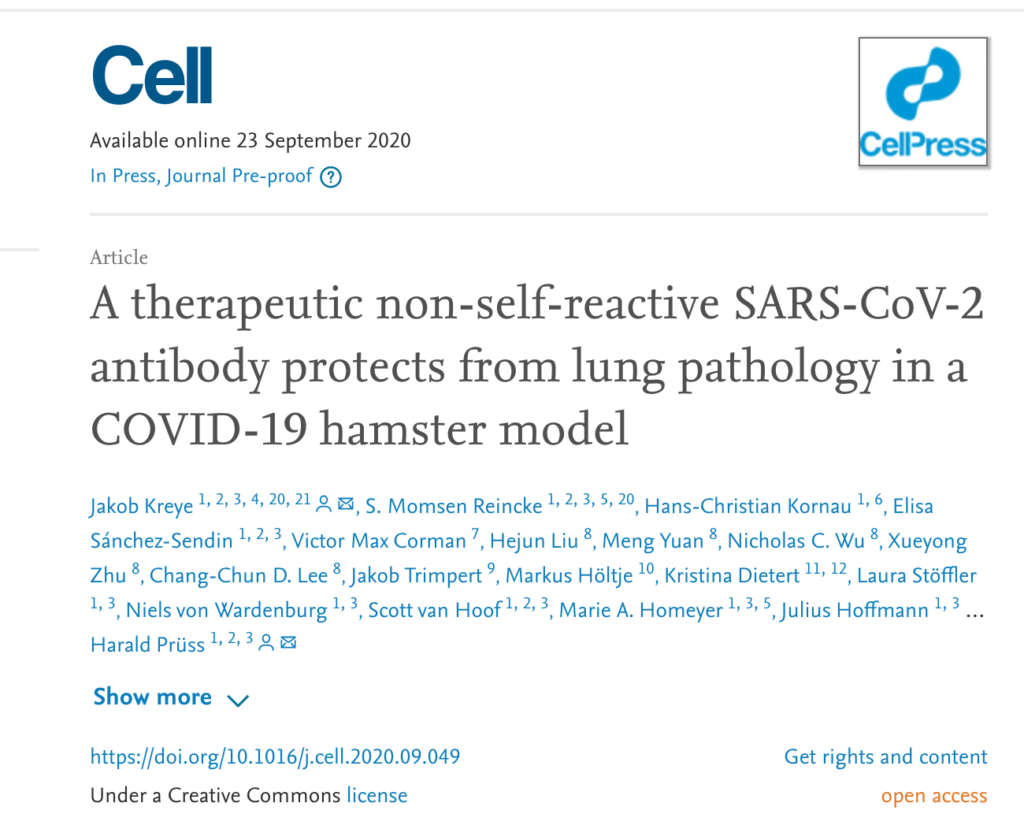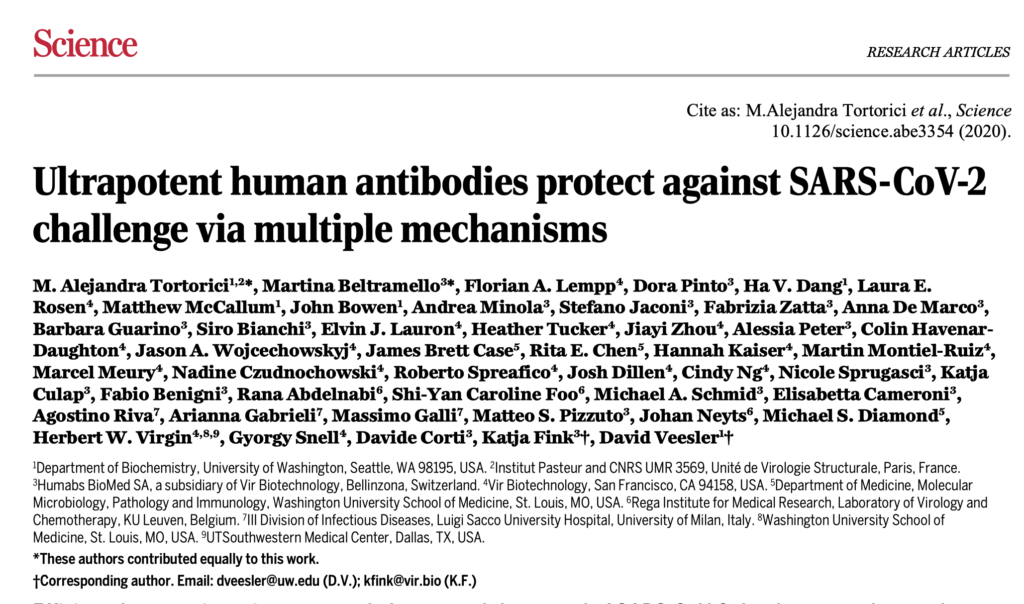2020年9月27日
4月10日最初に指摘して以来(https://aasj.jp/news/watch/12765 )何度も繰り返す様に、新型コロナウイルス(CoV2)特異的な薬剤として最初に登場するのはモノクローナル抗体薬になる。感染者のB細胞のsingle cell解析を行い、抗体遺伝子を取り出して、そのままモノクローナル抗体として使う技術は既に完成しているし、抗体薬を考えるのは当然のことだ。事実既にいくつかの抗体薬の第3相の治験は終わりつつあることは、この技術の完成度を物語る。大量生産については受託生産するファウンダリーも多く存在し、一定の量であれば臨床用の生産はすぐできると思う。FDAも迅速審査を行うだろう。もちろん治療薬開発を支えるCoV2に対する抗体反応についての論文の数は多く、もはや新しい発見があるとは思えないほど飽和している様に見える。
この様な現状をみると、今更CoV2に対するモノクローナル抗体の論文に新規性は全くない様に思うが、今日紹介したい2篇の論文は、CoV2に対する抗体利用についてまだまだ調べることがあり、たとえ現在治験が進んでいる抗体薬が市場に出回っても、まだまだ改良の余地があることを示した研究で、先週CellとScienceに相次いでオンライン掲載された。
それぞれ感染経験者のB細胞から抗体遺伝子を分離、それを発現させた抗体の反応を調べるという点では、これまでの研究と同じで、示されたデータの多くは、これまで発表された論文の再確認なので、新しいと思った点について列挙する。
まずCellに掲載されたベルリン神経変性疾患研究センターからの論文では、10人の患者さんから集めた500近いモノクローナル抗体について解析し、
抗原特異性を問わず、メモリーB細胞のみを純化してCoV2スパイクに反応するクローンの頻度を調べ、平均7%ものクローンがCoV2反応性であることを示している。すなわちかなり高い頻度で抗体反応が細胞レベルで誘導されている。またその多くがウイルス感染に対する中和活性を持つ。 これまで示された結果通り、生まれつき持っている抗体遺伝子を用いている抗体が多く、突然変異の蓄積は少ない。その中で選んだ最も中和活性が高い18種類の抗体のうち、なんと4種類がマウスの組織に反応する。残念ながら、人間の組織で調べていないので不満は残るが、自己組織反応性の抗体がワクチンなどで誘導される確率は高いので、注意が必要。また、治療用のモノクローナル抗体も、自己組織反応性のチェックを厳密にする必要がある。 珍しく33箇所の変異が認められた中和抗体も分離しているが、結合サイトは、他の抗体と異なっている(ただ、これを一般化できるかはまだわからない)。 ハムスターモデルで感染実験を行なっている。鼻粘膜に感染させる前、後で最も中和活性の高い抗体を投与して、ウイルス量を各組織で調べている。いずれの方法でも、症状を抑えることに成功しているが、面白いのは予防的に投与しても、鼻粘膜でのウイルス感染は防げず、鼻粘膜でウイルスは増殖する。しかし、その後起こる肺病変は完全に抑えられる。もし鼻粘膜にも移行できる抗体が使えれば、感染自体を抑えることも可能かもしれない。 肺炎が発症した後での投与実験が行われていないので、抗体治療を行うとすると、早めに1回注射ということが最も合理的プロトコルになる様に思う。 Scienceに発表された、ワシントン大学からのもう一編の論文は、CoV2のスパイクの構造と抗体の関係を考慮して治療抗体のあり方を提案した研究だ。ここでも紹介した様に(https://aasj.jp/news/watch/13833 )コロナウイルススパイクタンパクは、様々な修飾を受けて、最終的にウイルス侵入を助けるため、その構造は七変化とすらいえるほど変化する。この研究では、ACE2に結合する前の構造と、結合するためのRBDがオープンになった構造に対する2種類のそれぞれ中和抗体を調べ、オープン前の構造に対する抗体は、スパイクの構造を閉鎖型で安定化させ、ACE2結合部位が表面に出るのを抑えることで中和することを示している。
この研究では、中和活性だけでなく、感染細胞を殺すためのADCC やADCP活性も調べており、両方を同時に存在させることで、多様な抗ウイルス活性を実現できることを示している。
最後に、これまでスパイク遺伝子に発見された変異を集めて、2種類の抗体を組み合わせた場合の有効性について調べ、2種類を組み合わせることで、ウイルスの変異により抗体薬が効かなくなる確率を下げられることを明らかにしている。
重箱の隅を突くといってしまえばそれでおしまいだが、本当に詳細な研究が進んでおり、少なくとも私にとって新しいことが報告され続けていることがよくわかる2篇の論文だった。しかし、ここまでしなくとも、今の抗体薬で十分だろうが、安心できるに越したことはない。
2020年9月26日
一時と比べると、ネアンデルタール人やデニソーワ人のゲノムについての論文を読む機会はずいぶん減った様に感じる。逆に、我々ホモサピエンスの歴史をゲノムから読み解く研究が増えてきた様に思う。しかし、なぜネアンデルタール人が4万年ぐらい前に絶滅したのか、この絶滅にホモサピエンスはどうか変わったのかなど、知りたい疑問は多い。当然この分野でも、さらに精度をあげたゲノム解析から、古代人間の関係を調べる研究は続いている。
今日紹介するこの分野のメッカライプチッヒにあるマックスプランク進化人類学研究所からの論文は、これまでほとんど詳しい解析が行われてこなかった古代人のY染色体の一部を正確に解読して、関係を調べた研究で9月25日号のScienceに掲載された。タイトルは「The evolutionary history of Neanderthal and Denisovan Y chromosomes (ネアンデルタール人とデニソーワ人Y染色体の進化)」だ。
最初に古代人ゲノム解析が行われたのは当然のことながらミトコンドリアDNAだった。その結果、ネアンデルタール人は現代人と40万年ほど前に別れたことが推定されたが、その後体細胞ゲノムの解読が進んだ結果、ネアンデルタール人とデニソーワ人は、我々人類から60〜70万年前に分離した先祖から分かれた種であると推定された。両者の推定の違いを説明することはなかなか難しいが、デニソーワ人とネアンデルタール人が別れたあと、現代人の交流を通して現代人の母由来のミトコンドリアがネアンデルタール人に流入し、この系統に由来するネアンデルタール人が、デニソーワ人と共通のミトコンドリアを持つ集団を置き換えてしまったと説明されている。
この研究では母系を代表するミトコンドリアの代わりに、男系を代表するY染色体に焦点を絞って古代人ゲノム解析を行っている。ただ、体染色体と異なり、小さなY染色体の精度の高いゲノム解析は進んでいなかった。
この研究では比較的保存状態の良いデニソーワ人2体、ネアンデルタール人3体のDNAサンプルから、6.9Mbに相当するY染色体で組み換えの心配のない幾つかの領域と結合するDNAを濃縮し、これらについて解析を行っている。5万年前のスペイン出土のネアンデルタール人については、ほんの一部の領域の解析ができただけで終わっているが、あとはほぼ狙った領域全体のゲノムの解析ができている。
こうして得られたゲノムの違いから、各個体の持つY染色体の進化を計算するのだが、研究の大部分は用いたデータや方法から正しい計算が可能かについての検証に割かれている。
これを全て認めると、体染色体とは全く異なる進化の道筋が明らかになる。デニソーワ人と現代人のY染色体の分離は体細胞ゲノムから計算される結果とほぼ一致する。しかし、ネアンデルタール人と現代人については、35万年前後と計算された。
すなわち、ミトコンドリアゲノムと同じで、Y染色体で見ると、ネアンデルタール人は現代人に近いことになる。解析できた配列の量は少ないものの、最も古いネアンデルタール人のY染色体は、他の2体よりデニソーワ人に似ていることを考慮すると、ミトコンドリアゲノムと同じで、我々現代人のY染色体がデニソーワ人から分岐した後のネアンデルタール人に交雑を通して流入し、本来のネアンデルタール人のY染色体を置き換えてしまったと考えるのが妥当ではと提案している。
古代人間の競争だけでなく、ミトコンドリアでもY染色体でも、結局ホモサピエンスがネアンデルタール人を既に駆逐する勢いにあった様だ。
2020年9月25日
母親の腸内細菌叢が胎児の発達、特に脳発達に関わるのではという可能性はこれまで何度も指摘されてきたが、ほとんどが神経機能や行動レベルの解析を用いた研究で、胎児発達期の影響か、生後の脳発達過程への影響かについては明確ではなかった。
今日紹介するカリフォルニア大学ロサンゼルス校からの論文は胎児期の脳発達に絞って母親の腸内細菌層の影響を調べた研究で9月23日号のNatureにオンライン出版された。タイトルは「The maternal microbiome modulates fetal neurodevelopment in mice(母親の腸内細菌叢がマウス胎児の脳発達に影響する)」だ。
この研究ではまず、無菌マウスや抗生物質で腸内細菌層を除去したマウスを妊娠させ、14.5日目の胎児脳の遺伝子発現を正常胎児と比べることから始めている。この結果、333遺伝子の発現変化がリストされるが、神経の伸長や反発に関わることが明確なNetrin-G1aに絞ってその後の実験を行なっている。ただ、333種類の遺伝子発現が何らかの変化を示したということは、腸内細菌叢の影響力の強さを物語っており、今後さらに研究が必要だろう。
さて、Netrinに戻ろう。これを指標に胎児脳を調べると、視床と皮質をつなぐNetrin陽性神経細胞が減少し、これに伴い視床のサイズも減少していることが明らかになった。
次に胎児視床組織培養で見られる軸索伸長反応を調べ、線条体や下垂体組織と培養した時に軸索伸長反応が低下することを明らかにしている。その結果、生まれてきた子供では、四肢の感覚が低下していることも確認している。
あとは、こうして見つけた指標を、細菌を母親に移植することで正常化できることを確認した上で、正常化能力のある最近の特定を試み、胞子形成を行うClostridia(Sp)を最も有効な細菌種として特定している。そして、この細菌種を導入した母体の血液や、胎児脳の代謝物を比較し、Spを移植したときに血中で上昇が見られる細菌由来の代謝物、Imidazole propionateとtrimethylamine N-oxideなどを含むカクテルを加えることで、解剖学的異常、軸索伸長異常、さらには感覚神経異常をすべて正常化できることを示している。
人間で腸内細菌叢を完全に除去することはほとんどないので、どこまで参考になるか分からないが、細菌叢がもう一つの器官として様々な分子を生産し、これが胎児発達に影響する可能性はよく理解できたと思う。その上で、では人間でどう調べていけばいいのか、すぐ答えは出てこないのでなんとなくフラストレーションが残る論文だ。
2020年9月24日
アイソトープとレントゲンフィルムを用いてDNA配列を決めていた頃使っていた方法の一つが、サンガーらにより開発されたチェーンターミネーター法で、ポリメラーゼによってdeoxyNTP の代わりに、dideoxy NTPを取り込ませることで、それ以上のDNA伸長を抑える反応を利用している。
実は現在ウイルスのゲノム増殖抑制に使われる多くの薬剤も、ウイルスポリメラーゼによりゲノムに取り込まれてゲノムの伸長を抑えるチェーンターミネーターで、アビガンや、ヘルペスに対するアシクロビル、エイズに対するAZTなどが有名だ。
今日紹介するイスラエルワイズマン研究所からの論文は我々の体の中でこの様なチェーンターミネーター作用を持つ核酸アナログを合成する仕組みの進化についての研究で4月16日号のNatureにオンライン掲載された。タイトルは「Prokaryotic viperins produce diverse antiviral molecules(原核生物のviperinは様々な抗ウイルス分子を合成する)」だ。
この論文を読むまで全くViperinについて知らなかった。インターフェロンは、RNA分解、翻訳阻害、RNA編集、NO産生、キラー誘導など様々な分子を総動員してウイルスの増殖を妨げるが、その中の一つで、CTPをウイルスRNAの伸長阻害するチェーンターミネーターddhCTPに変換する酵素だ。ということは、私たちの体の中にもチェーンターミネーターを合成する仕組みがあることを意味している。
この研究では、人間のViperin遺伝子と相同性を持つ遺伝子が細菌や古細菌など原核生物にも存在することに着目、私たちが持っているViperinは原核生物で最初に生まれた分子をルーツとしていることを明らかにする。
次に、原核生物Viperinの中から、抗ウイルス活性を持つpViperinを選び出し、その機能について調べている。pViperinは他の抗ウイルス防御システムとリンクして原核生物ゲノムに組み込まれており、ファージウイルスなどDNAウイルスの増殖を抑える働きがある。驚くことに、人間のViperinを大腸菌に導入しても、ファージウイルス抑制作用を持っている。
ただ、CTP特異的に働いてddhCTPを合成する人間のViperinと異なり、pViperinの基質は様々で、GTPやUTPに作用してチェーンターミネーターを合成するViperinも存在する。また、RNA依存性RNAポリメラーゼだけではなく、DNA依存性の転写過程でもチェーンターミネーターとして働く子をと明らかにしている。
以上が結果のすべてで、生命誕生以来ウイルスに生物が悩まされ続けている歴史がわかるとともに、個人的にはViperinという内なるチェーンターミネータ合成システムを知ることができ、大変面白い論文だと思った。
ただ、全体のレベルで見たとき、平時ならNatureに掲載される確率は低かったのではとも感じるが、コロナ禍の今、原核生物にこれほど多様なチェーンターミネーターを合成する仕組みがあるのなら、新しい抗ウイルス薬を原核生物の中から探し出せる可能性が示された点を評価されたのだと思う。
2020年9月23日
新型コロナウイルスの感染はスパイクタンパク質がACE2をはじめ、いくつかのホスト側の分子と結合することから始まる。当然感染防御および治療の第一線として、抗体をはじめとするこの過程の阻害剤の開発が進んでおり、このブログでもなんども紹介してきた。しかし、モノクローナル抗体にせよ、可溶性の受容体にせよ、コストの面で利用できる国は限られる。
このため、安価な感染予防方法はないかなといつも論文を探しているが、今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文は、新しい感染予防の方法としては期待できると感じた。タイトルは「SARS-CoV-2 Infection Depends on Cellular Heparan Sulfate and ACE2 (SARS-CoV2感染は細胞の発現するHeparan SulfateとACE2に依存している)」で、9月10日Cellにオンライン掲載された。
この研究は、多くのウイルスが細胞表面上の特異的分子に結合する際、細胞表面に集まるための方策として細胞膜上に多量に存在している多糖類を使っていることに着目し、新型コロナウイルス感染も、ACE2だけでなく多糖類に依存している可能性について、スパイクタンパク質の構造を見直すところから始まっている。
その結果ACE2と結合する部位に接して陽性に荷電した領域が分子表面に存在し、そこに全ての動物細胞に存在するヘパラン硫酸(HS)が結合できる可能性が示された。面白いことに、新型コロナウイルス(CoV2)もSARSウイルス(CoV1)もHS結合部位が保存されており、HS結合の重要性がわかるが、CoV2でさらに陽性荷電の高いアミノ酸が一つ付け加わっていることで、この結果CoV2がより高い感染効率を獲得していると考えられる点だ。
以上は、一種机上で行う理論的検討の結果で、あとはこの結果を実験的研究で示す必要がある。そこでまず、ウイルススパイク分子を合成しHSへの結合を調べると、予想通りCoV2はCoV1より強くHSに結合し、さらにHS結合によりACE2への結合チャンスが高まることも示している。すなわち、スパイクとACE2の結合チャンスをHSが高めることがわかった。また、細胞膜上のHSをヘパリナーゼで分解したり、あるいは合成経路を遺伝子ノックアウトで阻害する実験を行い、細胞膜上にHSが存在しないとスパイクの結合が低下することを明らかにしている。
以上の結果は、細胞がプロテオグリカンとして合成する細胞膜上のHSがスパイクのACE2への結合を助けており、HSをプロテオグリカンから遊離させてしまうと、HSの作用が消失することを示している。とすると、最初から可溶性のHSやヘパリンを加えておけば、スパイクの細胞への結合が阻害される可能性がある。事実、HSやヘパリン存在化でスパイクの細胞結合実験を行うと、期待通り結合は阻害される。
そして最後に、ウイルスの細胞への感染効率を調べる実験系で、ヘパリナーゼ処理やヘパリンがウイルス感染を抑えることを確認している。
以上、新型コロナウイルスは細胞上に形成されたHSを用いることで、最終的にACE2への結合チャンスを高めており、これをヘパリナーゼ処理や、可溶性のHS、あるいは同じ糖鎖構造を持つヘパリンでも抑制できることが示された。
全て試験管内の実験系で、動物を用いた感染実験が必要だが、この結果はヘパリナーゼやヘパリンといった安価な感染予防が可能であることを示している。もちろん阻害効果は100%ではないが、ウイルス感染は確率論の問題なので、少しでも感染ウイルス数を減らすことは、個人にとっても社会にとっても重要だ。ここからは私の勝手な想像だが、外出前にヘパリナーゼやヘパリンを吸入して鼻粘膜を感染から守るといったことも可能かもしれない。
もちろん感染が疑われるとき、さらなる感染を抑える目的でヘパリンなどを服用する可能性もある。じっさい、多くの病院では血栓予防のために低用量ヘパリンを新型コロナ感染に用いており、もしこの処置が血栓予防以外に、ウイルスの際感染を抑えていたら一石二鳥になる。もちろん出血傾向を高めるヘパリンをむやみに服用できないが、この研究では抗凝固作用を取り除いたヘパリン様物質でも感染防御に効果があることを示している。
ウイルス感染を確率論の問題として捉えれば、少しでも感染量を減らすことは重要になる。その意味で、感染効率を下げるための様々な方法に関するインスピレーションが湧いてくる論文だ。
2020年9月22日
慢性腎炎の治療の柱は食事制限だが、これまで忘れられていた腎障害経路が腸内細菌叢だ。確かに言われてみると、アミノ酸代謝経路からインドールのような腎毒性のある分子が腸内で合成され、これが慢性腎炎を悪化させる可能性がある。
今日紹介するハーバード大学からの論文はこの可能性を追求し、腎毒性を調節できる一つの経路を特定した研究で9月18日号Scienceに掲載された。タイトルは「Diet posttranslationally modifies the mouse gut microbial proteome to modulate renal function (食事がマウス腸内細菌叢のタンパク質の翻訳後調節により腎機能を調整する)」だ。
この研究ではマウスにアデニンを投与し、腎毒性のあるDHAに変換して慢性腎炎を誘導するモデルを用いて、この時やはり毒性を持つH2S、 インドールなどの元になる硫黄を含みアミノ酸(具体的にはシステインやメチオニン)を食べさせる実験系で慢性腎炎を悪化させるか調べている。
少なくとも私の予想に反して、硫黄を含むアミノ酸(SAA)投与量が低いほど、血清のクレアチニンが上昇し、組織的に腎炎が悪化する。しかし、これは腸内細菌叢が存在する場合だけで、無菌マウスでは悪化が抑えられる。ただ、完全に元に戻るわけではないので、著者らがいうほどはっきりした結果とは思えないが、いずれにせよ腸内細菌叢はもともと陣毒性物質を産生しており、SAAを多く食べさせることでそれを抑えられることが示唆された。
ただ、腸内細菌叢ではあまりに複雑なので、この研究ではこれを大腸菌に置き換えて、大腸菌が存在するときに低SAA食により、慢性腎炎が悪化するというシステムに転換して、大腸菌側の遺伝子を変化させ、このメカニズムを探っている。
SAAを多く与えた方が、腎障害が防げるという結果は、SAAが大腸菌の代謝を変化させ、その結果腎毒性物質の合成が下がることを示唆している。SAAはタンパク質のスルフィド化に関わることから、著者らはタンパク質がSAA投与でスルフィド化されることで大腸菌側の酵素活性が抑えられ、腎毒性物質合成が下がるのではと考えた。
そこでスルフィド化される大腸菌タンパク質を特定し、その中からトリプトファンをインドールに変換するTnaAを特定する。そして、SAAによりTnaAがスルフィド化されることでインドール合成が抑えられ、大腸菌の腎毒性を抑えることができることを示している。
わかりにくいかもしれないのでもう一度まとめると、腸内細菌叢の中にはインドール合成により腎障害に関わる種が存在するが、SAAを多く与えてこの過程に必要な酵素活性を抑えると、腎臓を守ることができるという話になる。
一つの経路だけの話だが、腸内細菌叢が腎毒性物質を合成する可能性は明確に示され、またそれを食事中のアミノ酸などで抑えることが可能であることは、治療上重要な指摘だと思う。
2020年9月21日
最近トップジャーナルに運動の効果についての研究を多くみるようになった。例えば昨年、エクササイズを続けると筋肉に発現しているFNDC分子が分解されirisinという物質が分泌され、これが海馬に働いて記憶のシグナルが活性化されるという面白い論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/9706 )。このように、運動の主体である筋肉は、自ら運動を測定して様々な分子を分泌し、全身に情報を伝えおり、このようなメカニズムが急速に解明されつつある。そして、これらの結果はすぐに、アスリートも含めて、私たちの運動能力を高める様々なメニューとしてフィードバックされている。
今日紹介するハーバード大学からの論文はアスリートの運動能力を高めるという意味ではかなり重要な研究でないかと思う。タイトルは「pH-Gated Succinate Secretion Regulates Muscle Remodeling in Response to Exercise(pHにより制御されるコハク酸分泌がエクササイズに対する筋肉のリモデリングを調整する)」だ。
運動を繰り返すと、筋肉自体だけでなく、それを支える神経や血管などが再構成され、運動能力向上に寄与することは、誰もが経験することだ。しかし、この運動能力のリモデリングを誘導するメカニズムについてはまだまだ不明な点が多い。
この研究では運動後の筋肉内で分泌される分子が、筋組織の再構成を誘導すると目星をつけメタボローム解析を行った結果、コハク酸が運動に反応して細胞外液に分泌されることを発見する。同じことは人間でも確認された。コハク酸は運動により活性が高まったTCAサイクルで産生されることから、筋肉の活動を伝達する分子としては理にかなっている。
しかし問題は大事なコハク酸は細胞内のレベルが少々上がっても細胞外には出てこない点で、細胞外に出ているということは、筋肉細胞内からチャンネルを通して外に出てきていることを示唆している。この分泌のメカニズムを探った結果、筋肉運動で細胞内のpHが低下することで、コハク酸がカチオン化され、これがコハク酸のトランスポーターMCTにより細胞外へ分泌されることを明らかにする。まとめると、運動により高まった代謝で細胞内のpHが下がり、これによりカチオン化されたコハク酸が、メッセンジャーとして分泌されるという巧妙な仕組みが明らかになった。
次は、このメッセンジャーがどの細胞に作用し、どのように組織再生に関わるかだが、従来からコハク酸受容体として知られているG共役受容体SUCNRに絞って筋組織での発現と機能を調べ、
SUCNR1は筋肉細胞ではなく、血管も含めて周囲の細胞で発現している。 正常マウス運動時に見られるPKAやMAPKシグナル経路が、SUCNR1ノックアウトマウスでは見られない。 SUCNR1が周りの組織で活性化すると、細胞接着や、細胞外マトリックス分泌、神経支配などに関わる分子の発現が変化する。 これらの結果、コハク酸シグナルは、運動後の筋組織強化に関わるが、このシグナルが抑制されると全く運動の効果が見られない。 などを明らかにしている。運動、細胞内pH低下、カチオン化コハク酸分泌、周囲細胞の転写誘導、筋組織強化という美しいシナリオだが、この結果を生かしたトレーニングプログラムもすぐ開発されるように思う。コハク酸の塗り薬もすぐ出るかな?
2020年9月20日
ゲノムの変異によるガンも含めてあらゆる病気はエピジェネティックな違いが関わると言っていいが、2型糖尿病の場合、オランダの飢餓研究という有名なコホート研究がエピジェネティックな要因の存在を示すものとして例に挙げられることが多い。オランダ飢餓研究は、戦争が終わる前の冬、ドイツ軍の経済封鎖の結果市民が飢餓にさらされ、その時に生まれた子供たちを長期的に追跡したコホートだ。母体の飢餓により、生まれた子供に様々な変化が起こることが明らかになったが、中でも子供たちが60歳を超えた頃から、インシュリン分泌が低下した2型糖尿病の頻度が高まることが報告され、発生時に被ったエピジェネティックな変化により何十年も経て現れる体質が形成されるのかと驚いた。
今日紹介するスウェーデン・ルンド大学からの論文は糖尿病になりやすいエピジェネティックな変化を末梢血で診断できるか調べた論文で9月16日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Epigenetic markers associated with metformin response and intolerance in drug-naïve patients with type 2 diabetes (初めて治療を受ける2型糖尿病患者さんのメトフォルミンへの反応性を決めるエピジェネティックな指標)」だ。
この研究の目的は、糖尿病に至るエピジェネティックな変化を血液細胞のメチル化パターンから診断するエピジェネティックマーカーの開発だ。しかし、糖尿病はインシュリン分泌から感受性まで、多くの臓器が関わる複雑な病態なので、糖尿病全体を対象にしてもうまくいくとは思えない。そこでこの研究では、糖尿病治療ではまず最初に用いられるメトフォルミンが効いた人と、効かなかった人を選んで、この差に関わるDNAメチル化マーカーを探索している。
もう一つの問題は、糖尿病の病態には直接関わらない末梢血のメチル化パターンから、多臓器が関わるメトフォルミン感受性が診断できるかだが、先に述べたオランダ飢餓研究でも、病気と対応する末梢血のメチル化パターンの変化が報告されているので、やってみる価値はある。
結果だがメトフォルミン反応性、非反応性の2群のDNAメチル化状態の中から、メトフォルミン反応性の人、非反応性の人特異的なメチル化パターンを見つけることに成功している。
そして、これらの指標を合わせて計算することで、末梢血のDNAメチル化パターンからメトフォルミンに対する反応を、9割以上の確率で予測できることを明らかにしている。
さらに、血液のメチル化パターンが、糖尿病に関わる脂肪組織のメチル化パターンと対応することを確認し、この変化が体全体(例えば栄養)で起こった刺激への反応として起こっていることを確認し、血液が診断に使えることを明らかにした
最後に、この中の2種類の遺伝子を選んで、培養肝臓細胞のメトフォルミンに対する反応とこれらの遺伝子発現とに関わりがあるか調べ、メトフォルミンの作用がこれらの遺伝子の発現変化により直接変化することも確認している。
以上、末梢血に起こったエピジェネティック変化でも、糖尿病の病態を診断するために用いられることを明確に示した力作だと思う。
2020年9月19日
ヨーロッパ文化といえばもちろんキリスト教と切り離すことはできないが、一方で土着の文化も深く根付いているのがわかる。一つの理由は、キリスト教化前のギリシャ文化の影響の強さで、小説から音楽まで、ヨーロッパ文化を味わうにはギリシャ神話や文学の知識が必要になる。そしてもう一つ、いわゆる北欧神話も、キリスト教に改心した後も文化の底流を形成し続けた。ワーグナーのニーベルングの指輪はその典型だが、この文化は北欧のシンボル、バイキングのイメージと重なる。おそらくスカンジナビア各国はバイキングを誇りにしていると思うが、バイキング自体不思議な存在だ。決してバイキングと呼ばれた人たちが同盟国を形成していたわけではなく、おそらくバイキングにより襲われたりした中世ヨーロッパの人たちが、海から災いをもたらす共通の集団として総称していたのでは無いだろうか。(以上は個人的想像で根拠はない)。いずれにせよ、バイキングはどんな人たちなのか?
今日紹介するコペンハーゲン大学を中心とする研究グループからの論文は、この問題をバイキング時代(AD750-1050年)を中心にバイキングに関わる遺跡から出土した骨のDNAを解析して明らかにしようとした研究で9月16日号Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Population genomics of the Viking world (バイキング世界の集団ゲノミックス)」だ。
この研究ではなんと442人のバイキングと考えられる人たちの遺骨を集め、全ゲノム解析を行い、バイキングと総称される人たちと、当時のヨーロッパ人との関係、さらには現代のスカンジナビア人とバイキングの関係を調べている。元々バイキングの歴史をほとんど知らないため、完全に理解できているか心許ないが、大きなストーリーをまとめると次の様になる。
ほぼ全てのバイキングゲノムは青銅器時代のヨーロッパ人とオーバーラップする。 ただ、他の文化との交流の結果少しづつ違いが生まれ、大きくデンマーク型、スウェーデン型、ノルウェー型に別れる。これは、海を渡ってどの地区と交流があったかによる。またバイキング時代、デンマーク型にはスウェーデンやノルウェーバイキングのゲノムはほとんど存在せず、交流は北へと進んで行ったことがわかる。事実デンマーク型はデンマークを超えて広く分布する拡大型。ただ、この違いは時代によって変わっていく。 ゲノムで区別できるそれぞれのグループは異なる方向へ進出し、例えばノルウェーグループはアイスランドやグリーンランド、スウェーデングループは東方、そしてデンマークは英国方面へ進出している。ただ、バイキングが攻撃したと思われる地域では、複数のグループのゲノムが残っていることから、異なるグループのバイキングが協力して進出することもあった。 親戚関係にあるバイキングのゲノムは、同じ場所だけでなく、何百キロも離れた場所から出土しており、バイキング時代の進出範囲の広さを示す。 現代のスカンジナビアゲノムは、バイキング時代をおおむね継承しているが、スウェーデンだけは15−30%のゲノム領域に減少しており、デンマーク型のゲノムを中心に、他の地域が合わさっている。 以上が主な点で、北欧に興味のない人にはどうでもいいことだろう。ただ、私たちが顔や骨格から、中国や韓国朝鮮の人をなんとなく区別できる様に、スカンジナビアの国々もそれぞれ違いがわかると思う。とすると、この研究結果を思い浮かべながら、もう一度顔を見比べるとまた違った趣が出てくる気がする。是非日本、韓国、台湾などこのスケールのゲノム研究から、より詳しい交流史が描かれることを願う
2020年9月18日
何年もにわたって論文を読んでいると、次の論文が待ち遠しい研究グループがいくつかできてくる。中でもスタンフォード大学のKarl Deisserothのグループは、光遺伝学の創始者というだけではなく、毎回思いもかけない脳機能を取り上げ「こんな風に研究ができるのか!!」と感心させてくれる。
そして今日紹介する論文はマウスで研究ができるとは思えなかった解離現象に関する研究で9月19日号のNatureにオンライン出版された。タイトルは「Deep posteromedial cortical rhythm in dissociation(脳後内側深部に見られる皮質リズムが解離に関わる)」だ。
解離体験を一言で説明するのは難しいが、自分が現実の世界やこれまでの記憶などから切り離された気持ちになることで、自分であるという感覚が喪失していると言えるだろうか。もちろん誰でも経験があることだが、特に重症の場合離人症、解離性健忘、解離性同一性障害(多重人格)と病名をつけている。
おわかりのように解離体験は極めて主観的な体験で、これを動物実験で解明しようとはなんと大胆なと、思わず引き込まれる。もちろん、主観的体験をマウスで記録することは難しい。代わりにDeisserothたちが目をつけたのが、解離性麻酔薬と知られるケタミンだ。ケタミンは、皮質上部を抑制し、一方深部を刺激して、実際に現実からの解離感覚を誘導することが知られている。
研究ではまずケタミン投与により、脳梁膨大部皮質(RSP)と呼ばれる後脳深部得意的にゆっくりした1−3Hzの興奮の波が検出されることを発見する。と簡単に書いたが、Deisserothの論文には欠かせない新しい技術が使われている。この研究では脳全体を神経細胞レベルで記録するための方法で、RSPの神経全体が振動するのを見せられると感激する。
次にこのゆっくりした脳の興奮リズムが皮質のどこから発生しているのか、層ごとにカルシウムシグナルが記録できるマウスを用いて調べ、第5層の神経細胞の興奮によりこの興奮リズムが形成されていることを明らかにする。
RSPは元々脳の様々な領域と同調しているが、ケタミン投与後10分ほどでこの同調は完全に切れる。しかし、視床の一部では、逆により強い同調興奮が見られ、さらに連結はしていても、逆相の振動をおこす視床領域も特定している。このように、解離自体生理学的には脳領域間の結合性が新たに作られることに基づくと言える様に思う。
次の問題は、RSPとの結合の新たな再構成を、マウスの行動と対応させられるかだが、スクリーニングの結果感情やモチベーションに関わる反応が低下することに気づき、これを解離体験の代わりに使っている。本当にそれでいいのかという意地の悪い批判もあるかもしれないが、私はこれで納得した。
そして最後の詰めになるが、RSPで遅い脳波が発生することが解離体験の引き金かどうか調べている。得意の光遺伝学で第5層の神経細胞に2Hz周期で刺激を与え、行動変化を調べると、様々な刺激に対する反射は全く損なわれないが、子育などの感情的な行動が著名に低下していることを確認する。逆に、RSPの第5層の神経細胞の興奮を光遺伝学的に抑制すると、ケタミンによる解離現象が抑えられることも確認している。そして、ケタミンによりRSPのリズムが生まれるメカニズムについても明らかにしている(この論文はジャーナルクラブで取り上げるので、その時にこの回路も詳しく説明する)。
ドストエフスキーの小説白痴で何度も登場するのが、てんかん発作まえに感じられる解離体験だが、最後にDeisserothたちも脳内電極により広い範囲をモニターし続けたてんかん患者さんの中で、実際に主観的解離体験を経験した症例の脳興奮記録を詳しくしらべ、RSPに対応するposteromedial 皮質で3Hzのリズムが刻まれることを確認し、ネズミでの結果が人の解離体験にも対応できることを示している。
以上、面白いこと間違い無いのだが、全部説明しきれない。そこで、来週25日午後7時からジャーナルクラブでより詳しく説明するので乞うご期待。
VIDEO