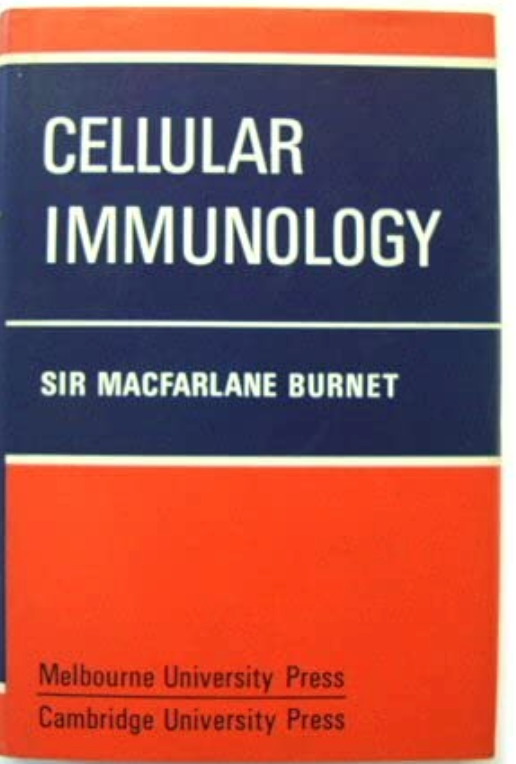2024年2月29日
細胞の中で蛋白質の新陳代謝は重要な問題で、そのためにユビキチン化・プロテアゾームやオートファジーと、ノーベル賞に輝いた重要な機構が不断に働いている。しかし、これらの機構は我々のゴミ処理と同様、膨大なエネルギーが必要で、受精前の未熟卵では低いことが知られている。
今日紹介するバルセロナ科学技術研究所からの論文は、未熟卵から受精、卵割が進む間の蛋白質のゴミの特殊な処理方法を明らかにした研究で、2月20日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Mouse oocytes sequester aggregated proteins in degradative super-organelles(マウス卵子は凝集した蛋白質を、分解するためのスーパー細胞小器官に隔離する)」だ。
「卵子形成過程で蛋白質のゴミは出るはずだが、排卵されるまで長期間ゴミを分解できずに生きていく必要がある卵子は、ゴミ問題をどう処理しているのか?」と問うたことがこの研究の全てと言える。
実際凝集した蛋白質を卵子で染めると、受精前には数十個の大きな塊に集められ卵子内に散在するが、受精後速やかに分解されることを発見する。そしてこの塊内の蛋白質は既にユビキチン化を受け分解前の状態で存在するだけでなく、塊には壊れたエンドゾームや小胞体などの小胞のかけらが多く集まっていることを明らかにする。すなわち、凝集蛋白質がゴミ処理のための細胞内小器官のかけらとともにひとまとまりに集められている。
面白いことに、このゴミの塊は、卵子が成熟とともに、アクチン依存的、すなわちアクティブに細胞膜直下に集められ、その後消滅する。すなわち、ゴミはカーゴとして組織化され、このカーゴがアクチン依存的に膜直下に運ばれる。このELAVと名付けたカーゴを卵から取り出し、その形成の分子基盤を調べると、RUFY-1と呼ばれる細胞内マトリックスがゴミ融合させて塊にする分子であることを明らかにする。すなわち、カーゴ内には様々な小器官のかけらが蛋白質のゴミとともに集まっているが、カーゴ自体は小器官を形成せず、RUFY-1に絡められた塊になっていることを明らかにする。
そして、受精による卵子の活性化でプロテアゾームやオートファジーに必要な分子が膜直下に供給されると、集められた小器官のかけらが再活性化され、集まった蛋白質のゴミは分解される。すなわちこのカーゴは、ゴミ処理器官として再活性化し、蛋白質のゴミを分解する役割も担っていることを明らかにしている。
以上が結果で、ライブイメージングを含む卵子のイメージングを駆使した細胞学で、カーゴの形成、融合、再活性化を可視化したわかりやすい研究だ。蛋白質のゴミの処理には膨大なエネルギーが必要になる。これは排卵まで何年もの長い期間静止して過ごさなければならない卵にとっては大きな負担になる。このために、まずゴミを処理器官ごと集めて静かに寝かせておき、卵の活性化とともにまずゴミを燃やして発生という大事業に備える戦略はよく出来ている。
この卵子の戦略を勉強しながら、結局核のゴミを処理できずに後回しにしている我が国では、次の成長など望めない気がした。
2024年2月28日
私が最初に免疫学に惹かれた最大の理由は、学生時代理学部動物学教室で故村松繁先生が主催されていたBurnetのCellular Immunologyの読書会に出席したからだと思う。
この本の中で、バーネットはガンが突然変異で起こること、そしてその突然変異は免疫系に監視され抑えられているという免疫監視の考えを述べていた。当時革新的だった考えを疑う人は今やいなくなったと思うが、実際の免疫監視が起こっていることを実感できるデータを得ることは簡単ではない。
今日紹介するニューヨークIchan医科大学からの論文は、免疫監視が働いていることを実感させてくれた面白い研究で、2月23日号 Science に掲載された。タイトルは「An immunogenetic basis for lung cancer risk(肺ガンの免疫遺伝学的リスク)」だ。
もし免疫監視が働いているとすると、当然抗原が多様なほど免疫システムにキャッチされやすいはずだ。そこで、この研究では肺ガンを例に抗原提示に必須分子であるMHC遺伝子を調べ、各MHC遺伝子がヘテロ(異なる対立遺伝子を持つ人)とホモの人を選び出し、ガンの発生率を比べている。MHCがヘテロの場合、当然ガン抗原の多様性は倍になるので、ヘテロの方がホモよりガンになりにくいと予想できる。
まず意外だったのは、キラー細胞が認識に使うクラス I MHC(HLA-I)、すなわち HLA-A、B、Cではヘテロもホモも全く差がないことだ。では免疫監視はないのか?とクラス II MHC(HLA-II)、すなわち HLA-D (6種類存在する)を調べると、全ての HLA-II でヘテロの人は肺ガンになりにくい。特に、HLA-DRB と HLA-DQB ではヘテロの人はオッズ比で3割も発ガン率が低下する。
さらに面白いのは、この差が喫煙者だけの差を反映している点だ。すなわち喫煙を続けていた患者さん、あるいは以前喫煙していた患者さんでは HLA-II のヘテロ効果が見られるが、喫煙歴の全くない人では HLA-II のヘテロ、ホモとも全く発ガン率に差がない。すなわち、タバコにより遺伝子突然変異が多発するほど、HLA-II のヘテロ vs ホモの効果がはっきりしている点で、まさに免疫監視が働いていることを実感する。
さらに詳しく、HLA-II 各領域の多型と発ガン率の相関を調べると、抗原ペプチドが結合する部位がヘテロであるほど、発ガン率が抑えられることを明らかにしている。
最後に、なぜタバコで HLA-II に偏った免疫監視効果が見られたのか調べるため、喫煙者の肺の細胞を調べ、肺胞マクロファージや肺上皮で HAL-II が喫煙者で上昇していることを示している。そして、ガン免疫を逃れた肺ガンの多くが HLA-I のみならず HLA-II を欠損させていることも明らかにしている。
以上が結果で、バーネットの時代に考えたほど免疫監視は単純ではないが、間違いなく監視システムが働いていることは実感できる面白い研究だ。
2024年2月27日
IL-10 は多くのサイトカインの中で炎症を鎮める役割を持つ重要なサイトカインとして知られている。シグナル経路についてもよく研究されており、最終的に STAT3 のリン酸化による転写調節が主要な経路だ。こう言ってしまうと、理解できた気になるのが不思議だが、実際にはなぜ IL-10 で炎症が治わるのか、説明になっていない。実際 STAT3 は炎症性サイトカイン IL-6 の下流にも存在する。
この問題を問い直したのが、今日紹介するイエール大学 Flavell 研からの論文で、炎症のメディエーターとして重要な脂質に注目して IL-10 の役割を調べた研究で、2月27日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「IL-10 constrains sphingolipid metabolism to limit inflammation(IL-10 はスフィンゴリピッド代謝を制限して炎症を抑制する)」だ。
もともと脂質代謝は複雑でとっつきにくい。しかし、オメガ脂肪酸からプロスタグランジン、ロイコトリエンなど炎症メディエーターは脂質代謝の理解なしに考えられない。そこで、IL-10 により抑制される TLR2 経路を正常マウス及び IL-10 欠損マウス由来マクロファージで刺激し、脂質代謝物の IL-10 欠損による変化を見ると、IL-10 欠損マクロファージで様々なタイプのセラミド、特に長いアシル鎖を持つ VLC セラミドが上昇していることを発見する。セラミドは炎症誘導に関わることが知られており、脂質代謝を介して IL-10 が炎症抑制に働くという仮説と一致している。
そこで、VLC セラミド合成に関わる Cer2 酵素をノックアウトした骨髄由来マクロファージを調べると、TLR2 刺激に対する炎症反応を抑え、IL-10 欠損による炎症を抑えられることを示している。また、IL10 受容体と CerS2 セラミド合成酵素の両方をノックアウトすると IL-10 ノックアウトによる腸の炎症を抑えることが出来る。
後は、さらに詳しく TLR2 シグナルと、IL-10 シグナルのセラミド合成についてアイソトープを用いた代謝実験を行い、
炎症では脂質代謝に関わる遺伝子の発現が変化し、スフィンゴリピッド合成と VLC セラミドの蓄積が起こる。
VLC セラミド合成は炎症に関わる NFkB 経路の REL に依存している。
IL-10 はセラミド合成過程ではなく、セラミドから mono-unsaturated fatty acid(MUFA) を合成する遺伝子を誘導し、セラミドの蓄積を抑える。
また、MUFA 自体もまだよくわからないメカニズムで炎症を抑える。
などを明らかにしている。脂質代謝は単純に遺伝子発現ネットワークだけで決まらないので、炎症シグナル、IL-10 シグナルの間の脂質代謝経路についてはわからない点も多い。従って、この研究は IL-10 シグナルを脂質代謝の観点から見直す入り口に立った仕事と言っていいだろう。しかし、MUFA が多いオリーブオイルは炎症を抑制することが知られていることから、面白い分野に発展すると思う。
2024年2月26日
胃粘膜が生息するピロリ菌は慢性炎症を誘導して胃炎や胃潰瘍の原因になるだけでなく、東大の畠山さん達により SHIP2 から Erkシグナルを活性化させて細胞増殖を誘導する分子CagA を胃上皮細胞に注入することで胃ガン発生を促進することが示されている。
今日紹介する香港中文大学からの論文は、口腔連鎖球菌も同じように胃ガンのリスクファクターになる可能性を示した研究で、2月15日号 Cell に掲載されている。タイトルは「Streptococcus anginosus promotes gastric inflammation, atrophy, and tumorigenesis in mice(口腔連鎖球菌はマウスの胃炎、萎縮、腫瘍化を促進する)」だ。
人間の胃ガンに存在する細菌叢を調べるとピロリ菌だけではなく、体内の様々な場所に常在している口腔連鎖球菌も存在することが知られているようだ。また口腔連鎖球菌は酸に強いことが知られているので、ピロリ菌のように胃ガンを誘導するのではと着想し、後は完全にマウスでこの可能性を調べる実験を行っている。
まず、通常のマウスに口腔連鎖球菌を3日間連続投与して2週間目で調べると、ピロリ菌ほどではないが炎症が誘導される。さらに長期間投与し続けると、胃上皮内に口腔連鎖球菌が持続し、ピロリ菌に匹敵する慢性胃炎を引き起こすこと、さらに1年目では上皮の萎縮、さらには腸上皮化生が発生することを突き止める。まさにピロリ菌と同じ活性がある。
そこで、無菌動物に口腔連鎖球菌を投与して胃上皮細胞の増殖を調べると、細胞の増殖が上昇し、さらに粘液細胞への化生が進むことがわかり、このことから胃ガン発生を促進することが想像される。
これを調べるため、胃ガン細胞を皮下に移植し、これに口内連鎖球菌を注射すると、ガンの増殖が上昇する。さらに、発ガン剤ニトロソウレアを投与する系で口内連鎖球菌を感染させると、発ガンが促進されることを確認している。
最後に上皮増殖を促進するメカニズムを探ると、口内連鎖球菌は TMPC分子を介して上皮が発現するアネキシンに結合し、上皮にとりつくとともに、アネキシンを介して ERKシグナル経路を活性化することを明らかにしている。
関わる分子は異なっても、炎症誘導、そして上皮の ERKシグナルを介して胃ガンの発生を助ける能力を口腔連鎖球菌が持つことはよくわかった。とはいえ、人間でも疫学や細胞学的研究が必要だと思う。
2024年2月25日
成人T細胞白血病は、一昨年ご逝去された高月清先生のグループが特定したレトロウイルス(HTLV-1)感染後に起こるT細胞白血病だ。感染経路が特定できているので新しい感染者はほとんど防げているので、いつかは消滅する病気だと思うが、これまでに感染したキャリアからコンスタントに発症者が出ており、2021年の論文を見ると770例の発症がある。病気のメカニズムについてはまだわかっていないことも多く、ウイルスのTax分子が細胞の転写を変化させることが指摘されてきた。
最近この分野はほとんどフォローできていなかったが、今日紹介する東大・新領域創生科学研究科からの論文は、HTLV-1 感染後、白血病発症までに積み重なるエピジェネティックな過程を明らかにした力作で、2月21日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Mechanisms of action and resistance in histone methylation-targeted therapy(ヒストンメチル化標的治療の効果と耐性のメカニズム)」だ。
久しぶりに我が国から発表された、基礎から見ても面白い臨床研究だと思う。筆頭著者が責任著者を兼ねているのも好感が持てる。若い研究者が全体を引っ張っているという感じがする。
ATLに決め手となる治療はなかったが、最近第一三共が開発したヒストンメチル化に関わるEZH1、EZH2阻害剤バルメトスタットが効果を示すことが明らかになり、このメカニズムの解明は感染後の ATL発症過程を理解する鍵になると考えられる。この疑問に答えようと、治療を受けた患者さんの ATL細胞のエピジェネティックを調べたのがこの研究だ。
これまで示されていたようにバルメトスタットはほとんどの患者さんの白血病を抑える効果がある。そこで、治療前と治療後でバルメトスタットが標的とするヒストンの H3K27me3 量、結合部位、クロマチンの構造などを総合的に調べると、期待通り H3K27me3 の量が減り、特に転写の始まる部位でのクロマチン構造が緩み、転写が上昇する。ただ、詳しく見ると、患者さんによるバリエーションは大きい。しかし、ほとんどのケースでATL細胞の増殖が低下すると言うことは、ウイルス感染後 EZH2 の活性が高まり、H3K27me3 結合した転写開始点が増えることで、ガンの増殖を抑制する分子の発現が低下し、白血病が進むことがわかる。
だとすると、やはりほとんどの患者さんがバルメトスタット治療2年ほどで再発する原因はエピジェネティックメカニズムの変異が加わって、抑制性の染色体構造が緩んでしまった結果である可能性が高い。
実際、変異を起こした患者さんで調べると、半数が EZH2 の変異が起こり、バルメトスタットが効かなくなってしまった結果であることが確認される。
さらに面白いのは、EZH2 などのエピジェネティック分子複合体の変異が全く認められないケースが半分近く存在する点で、そのケースを探ると、DNAのメチル化を外す TET2遺伝子の欠損、あるいは新しくDNAをメチル化する酵素DNMT3の発現が高まっていることを発見する。
ヒストンのメチル化とDNAメチル化の関係は比較的よくわかっているが H3K27me については、クロマチンが閉じているにもかかわらず、その部位のDNAメチル化がほとんどないため、複雑な遺伝子発現に対応するための特殊な関係と思われてきた。
この研究では見事に、EZH2変異がないケースでは、H3K27me3 でサイレンスされている部分にDNAメチル化が起こっており、これをデシタビンでブロックすると、バルメトスタットの効果が再現することを示している。
他にもエピジェネティックス制御に関わる PRC2分子群の翻訳が高まるケースも示しているが割愛していいだろう。
結果は以上で、発生学でこれまで問題になってきた H3K27me3 と DNAメチル化の2種類のエピジェネティック制御の面白い関係が、見事に患者さんの白血病の中に見られることがわかる、発生学から見ても勉強になる研究だと思う。このような統合的な臨床研究をやり遂げる若手がどんどん出てくることを期待する。
2024年2月24日
Science系の雑誌にヘビについての論文が3編も同じ週に掲載されていたので紹介することにする。ただ、論文が多いので紹介は簡単に済ませる。
最初はニューヨークのStony Brook大学からの論文で、ヘビの進化スピードをトカゲと比べた研究。2月23日号 Science に掲載された。タイトルは「The macroevolutionary singularity of snakes(ヘビのマクロ進化の特異点)」だ。
ヘビは頭の形、長さ、脊椎の数、四肢の欠損といった形態だけでなく、蛇毒や感覚分子などでみると、同族のトカゲと比べて進化速度が早く感じられる。実際、トカゲでも四肢を欠損するケースがあるが、そこからヘビのような多様化が起こることはない。これを調べるため、ヘビで見られる形態を中心にした新しい変化の出現を一つの指標に統一し、ゲノム進化のマップにオーバーラップさせたのがこの研究だ。
結果は、ヘビの多様化はトカゲの何倍も早い。ただ、新しい形質への特異点が独立して起こり、これが重ね合わさって多様化が進んでいる。すなわち、ヘビへの進化のキーはヘビへの進化で起こったこのシフトに負うところが大きい。そして、このシフトを促したのは、おそらくその肉食性と捕食行動を支える形態変化で、これをきっかけにそれぞれの環境に合わせた進化を進行させてきたと結論している。
以上の仕事は自然選択要因から進化を見た研究だが、次のコロンビア大学からの論文は、ヘビでは我々哺乳動物とは異なる減数分裂時の遺伝子組み換えサイトの形成方法が存在することを示した研究で、同じ号の Science に掲載されている。タイトルは「Patterns of recombination in snakes reveal a tug-of-war between PRDM9 and promoter-like features(ヘビの組み換えパターンから、組み換えホットスポットについてのPRDM9とプロモーター様部位の競争が見えてくる)」だ。
PRDM9分子はヒストンのメチル化に関わる分子で、マウスや人では減数分裂時の組み換えが起きやすい場所を決めている。ただ、ノックアウトマウスの解析からこれ以外にも組み換えホットスポットを形成する仕組みの存在が知られており、場所としてはCGリッチなプロモーター様構造がそのサイトになっおり、PRDM9分子が欠損すると、そちらにシフトすることが知られていた。
この研究ではヘビのPRDM9をクローニングし、同時にヘビの組み換えホットスポットパターンを特定している。その結果、マウスや人と異なり、PRDM9結合部位と、プロモーター様部位が両方組み換えホットスポットとして利用されていることを明らかにしている。
以上の結果は、哺乳類と異なり2種類の組み換えホットスポット形成がヘビでは生きていることを示している。すなわち、余分なホットスポットをヘビは使えると言うことで、ひょっとしたらこれがヘビの大きな形態変化に継ながっているのかも知れない。
そして最後のカリフォルニア・スクリップス研究所からの論文は、多くのヘビ毒を中和するモノクローナル抗体を開発したという研究で、2月21日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Synthetic development of a broadly neutralizing antibody against snake venom long-chain α-neurotoxins(調査α神経毒型ヘビ毒を広範に中和する抗体の合成的開発)」だ。
ヘビ毒にはいくつかのサブタイプが存在するが、最も重要で広く分布しているのが 3-フィンガートキシン(3FTx)で、アセチルコリン受容体に結合して呼吸を止める。トキシンの構造は多様だが、標的は同一なので、この部位に対する抗体が出来ると、多くのヘビに対応できる。
このために、ランダムに突然変異を誘導したヒトの Fabライブラリーをスクリーニングし、最終的に95Mat5と名付けた抗体の分離に成功している。そして、試験管内での中和実験とともに、マウスに投与することでほとんどの 3FTx型のヘビ毒を中和できることを明らかにしている。
以上、ヘビ論文3題でした。
2024年2月23日
サリドマイドの作用機序解明以降、標的蛋白質にユビキチンリガーゼをリクルートして分解させる PRORAC と呼ばれる薬剤の開発が続いている。特にスーパーエンハンサーに存在する BRD蛋白質を標的にする PROTAC は臨床応用に近いところにきていると言えるだろう。
このように PROTAC は標的分子とユビキチンリガーゼを結びつける接着剤の役割を担うのだが、今日紹介する英国ダンディー大学とオーストリア科学アカデミー研究所からの論文は、新しい標的分子分解方法の可能性を示した研究で、2月21日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Targeted protein degradation via intramolecular bivalent glues(分子内2価接着による標的蛋白質の分解)」だ。
我が国のエーザイが開発していたスルフォンアミド化合物 E7820 をエンハンサー構造に関わる BRD分子と結合する JQ1 を結合させた分子 IBG1 が三菱田辺製薬により開発され、低濃度で様々なガンの増殖を抑制できることが特許として申請されていた。
この研究ではこの IBG1 が設計通り DCAF15分子を介してユビキチンリガーゼを BRD分子にリクルートするのかを調べた結果、確かに BRD分子は分解するが、DCAF15 非存在化でも分解が起こることから研究が始まっている。
まず BRD4分子に蛍光分子を結合させ、IBG1 による BRD4分子分解に関わるユビキチンリガーゼとその受容体を探索すると、CRL4/DCAF16 依存的に BRD4 が分解されることを突き止める。
では、IGD1 が接着剤として BRD4 と DCAF16分子を結合させるのかを調べていくと、驚くことにDCAFと結合すると考えていたE7820がなんとBRD4分子のブロモドメイン(BD1)と結合することがわかった。すなわち、IGD1はBRD4分子に存在する2つのBD(BD1とBD2)を引き寄せる効果があり、この結果生まれた新しい蛋白質の構造を包むようにDCAF16が働き、BRD4をユビキチン化、分解に導くことがわかった。
結局、本来DCAF15と結合すると考えたE7820がたまたまBD1と結合することでこの現象が発見されたことになり、E7820の代わりにBD1結合分子を使えば同じ効果が得られることになる。この考えに基づき、もともとBDドメインと結合するJQ1をE7820に置き換えた化合物IGD3を合成してBRD4分解活性を比べると、UGD1を越える活性を示すことが明らかになった。
さらに、JQ1をつなぐ構造をもっと短くしてリジッドな化合物を合成してしらべると、今度はDCAF16の代わりにDCAF11/CRL4をBRD4分子と結合させて分解することがわかった。
以上が結果で、化合物の作用を再検討することから新しい作用機序がわかり、新しい創薬標的が明らかになった面白い研究だ。しかも、蛋白質によってはそれ自身の構造変化でユビキチン化される可能性があることも示され、生物学的にも面白い。
この結果、これまでとは異なるメカニズムでBRD4を分解する薬剤が開発できることがわかり、今後スーパーエンハンサー依存性のガンのアキレス腱を突く治療法がより加速することも期待できる。極めて専門的な論文だが、期待したい。
2024年2月22日
ノボノルディスクのセマグルタイドが2月22日から我が国でも販売されるという記事が日経に出ていた。とっくに認可されて使われていたのかと思っていたので驚いたが、GLP-1 作動薬と腎臓でのブドウ糖再吸収を阻害する SGLT2 阻害剤は糖尿病治療を変革している。面白いのは、糖尿病治療として開発されたこれらの薬が、糖代謝を越えて様々な効果を発揮していることで、我々の身体の代謝システムのネットワークの複雑性を物語る。
今日紹介するミュンヘン大学を中心に200を超す研究機関が集まって発表した論文は、2型糖尿病(T2D)のゲノムリスクデータを世界中から集めて、新しく解析し直し、糖尿病発症に至る複雑な経路を明らかにしようとした研究で、2月19日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Genetic drivers of heterogeneity in type 2 diabetes pathophysiology(2型糖尿病の病態生理の多様性の遺伝的要因)」だ。
T2D のゲノム解析はこれまで何度も発表され、我が国でもかなり早くから解析が進んでいた。この過程で、糖尿病タイプの人種差とゲノムの関係(例えば東アジア人はインシュリン合成に関わるゲノムリスクと相関する T2D が多い)ことなどが示されてきた。
この研究では、このような人種差の問題も視野に入れ、これまで集まったゲノムデータを同じ方法で解析するとともに、多型が特定された領域のクロマチン構造を様々な細胞で調べたデータを参照して、ゲノム多型と T2D との関係に細胞過程を反映させようとしている。
多くの結果はこれまで報告された結果と一致しており、また膨大なので、個人的に面白かった結果だけをまとめておく。
まず、T2D と相関する一塩基多型(SNV)は1300に及び、T2D が様々な回路が複雑に絡まった病気であることを示すが、これらの SNV を膵臓のβ細胞関連2種類、血糖、体脂肪、メタボリックシンドローム、肥満、脂肪代謝異常、肝臓脂肪代謝など、それぞれ特別な検査項目で分別できる8つのカテゴリーに分類できる。
糖尿病は様々な理由で起こるインシュリン抵抗性ステージを経て、β細胞が疲弊してインシュリンを作れなくなるステージへと進むが、それぞれの段階で様々な経路が存在することがゲノムからわかる。
勿論、体脂肪と肥満は当然オーバーラップするのだが、8つのカテゴリーに分別した SNV のクロマチン状態を対応させると、同じブドウ糖代謝異常でも小腸の GLP-1 受容体発現が高いクロマフィン細胞で強く発現している遺伝子は、プロインシュリン産生と連関しない β細胞関連 SNV に見られることがわかる。すなわち、GLP-1 経路をより強く反映しているのがこの経路になる。
また脂肪細胞や肝臓細胞で説明できると考えがちな脂肪代謝と相関する SNV の中には、膵島細胞で発現が見られるものがある。これらは、インシュリンとは全く別に、膵臓と脂肪代謝をつなぐ経路があることを意味している。
さらに、代謝異常と相関する SNV には脳皮質の抑制性神経細胞で強く発現しているケースが認められ、神経代謝ネットワークの T2D への関与を示している
世界中からデータが集まっているので、当然 T2D 発症経路の人種による違いを調べることも出来る。これまで、東アジア人は膵臓 β細胞の異常に直接関わる SNV の関与が強く、逆にヨーロッパ人は脂肪代謝異常と関わる SNV との相関が強いとされていた。
この研究でも、同じ結果が認められたが、アジア人を BMI で、痩せの強い人、肥満の強い人に分けると、人種差として見えていた物が、実際には BMI の差であることを示している。
他にも、妊娠時糖尿病、多囊胞性卵巣症候群、糖尿病末期の血管や腎臓異常などとの関係も詳しく見ているが、割愛するが、ゲノムから眺めると、確かに糖尿病の成り立ちの複雑性がよくわかる。すなわち、糖尿病でも個人にあったプレシジョンメディシンが必要であることを示している。
2024年2月21日
マルチモーダル AI により、テキストからイメージが作れるようになってすぐ、例えば医者とインプットすると男性の医師が描かれ、看護師とインプットすると女性で描かれるというジェンダーバイアスが問題になった。しかし、AI は主にパブリックなデータベースから画像を拾っているので、この結果は我々が利用しているパブリックデータベースやソーシャルネットにジェンダーバイアスが存在していることを意味している。
今日紹介するカリフォルニア大学バークレイ校からの論文は、Google のようなパブリックデータベースに蓄積されたジェンダーバイアスを調べ、またそのバイアスが我々にどう影響するのかを、画像とテキストに分けて調べたユニークな研究で、2月14日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Online images amplify gender bias(オンラインのイメージがジェンダーバイアスを増幅させる)」だ。
この研究ではまず、3500近い社会的カテゴリーについて100枚のイメージを Googleサーチで集め、それぞれのイメージの性別を6500人近くの人間に手分けして判断させている。この結果、9割は性別を決めることが出来ている。一方、language model のエンベッディングを利用して、テキストに表現されるジェンダーバイアスについても同時に調べている。
それぞれのジェンダーバイアスを比べると、画像でのバイアスが極めて高い。例えば水道工事となると画像ではほとんど男性になるが、テキストではその半分程度のバイアスしかない。逆も同じで栄養士の画像はほとんど女性だが、テキストではバイアスは半分以下になる。
さらに、職業を問わずイメージ全体で見るとネット上の女性イメージがそもそも少ない。さらに、人口統計で見られる実際のジェンダーバイアスと比べても、画像に蓄積されたバイアスは高い。一方、テキストでは人口統計のバイアスも是正されている。
次に、このバイアスが我々の判断にどう影響するか、先入観が少ない科学や芸術と言った特殊な職業について、Google で調べた後、その職業について心理的なジェンダーバイアスが生まれたかどうかを、自己申告や、心理テストで調べている。
結果は、ウェッブから拾ってきたデータ自身のジェンダーバイアスは、データが画像の場合より増幅されて我々のイメージとして定着することが明らかになった。一方、テキストの心理的効果はランダムだ。
結果は以上で、我々が毎日作り出しているイメージが SNS上で社会化され、それが今度は我々の判断に影響するというサイクルが発生し始めていることを意味する。
ルソーの一般意志を Google のような新しいテクノロジーで拾い上げることが可能になったことを東浩紀さんが「一般意志2」で書いたのは10年以上前で、優れた先見性を持った著作だったが、これを越えてテクノロジーが進んでいることを感じる。
2024年2月20日
皮膚の幹細胞を培養して調整した皮膚や、角膜から調整した幹細胞の移植治療はすでに臨床応用が進んでいる。とすると、現在研究が進む肺胞や気管上皮の幹細胞を移植する治療が考えられてもいいはずだ。しかしながら、細胞を局所に移植する方法や、対象となる領域の広さから、肺機能不全の幹細胞治療は進んでいなかった。
今日紹介する上海同済大学からの論文は、ひょっとしたら慢性閉塞性肺疾患(COPD)の幹細胞治療が可能かも知れないと思わせる臨床治験研究で、2月14日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Autologous transplantation of P63 + lung progenitor cells for chronic obstructive pulmonary disease therapy(慢性閉塞性肺疾患のP63陽性自家肺幹細胞移植)」だ。
慢性気管支炎や肺気腫では肺組織の自己再生が低下していることが知られている。このグループは、自己再生に必要な幹細胞を COPD治療に応用できるのではと研究を進めてきて、前臨床では P63陽性幹細胞移植が効果があることを明らかにしていた。
そして今回20人の COPD患者さんを対象に肺から調整した P63陽性幹細胞移植治験に踏み切っている。
P63陽性細胞の採取だが、肺ガンの診断に使われる気管支鏡下ブラッシングを用いている。私が臨床医の時代からブラッシングは重要な検査だったが、いつも診断に必要なだけの細胞が取れているか心配だった。そのぐらい少量の細胞しか採取できない方法でも、全員で移植が可能な細胞数が培養出来ている点に驚いた。
次に移植だが、20カ所に気管支鏡を挿入、洗浄後細胞を移植している。COPDの患者さんにはかなり負担の大きな治療になると思う。
結果だが、気管支鏡による細胞採取や移植に伴う副作用を除くと、移植後24週まで重大なイベントは起こっておらず、第一相治験の目的はクリアしている。
12週目と24週目で一酸化炭素を用いる肺拡散試験で評価している。実際には一秒率なども測定しているが、このような effort dependent な機能測定法では効果は検出できていない。しかし、肺拡散試験では12週目で7割の患者で改善が認められ、24週でも53%で改善が維持されている。もともと炎症など様々な問題が存在した上での自己再生不全なので、長期の維持が難しいとすると、進行を抑えるには毎年移植が必要になるかも知れない。この改善は、単位時間の歩行距離や、自覚症状としても確認でき、クオリティーオブライフ改善でも期待できる。
とはいえ、細胞移植の効果が全く見られなかった人が1−2割は存在している。この研究で感心したのは、効果が見られなかった細胞と、見られた細胞について遺伝子発現を調べ直している点で、効果が見られなかった細胞では培養中に分化が進んでしまっていることも明らかにしている。この結果は重要で、今後移植前に細胞のクオリティーを確かめることが出来る。
以上が結果で、COPDに細胞治療という、私が臨床で働いていた頃には考えられない可能性が生まれたと驚いている。