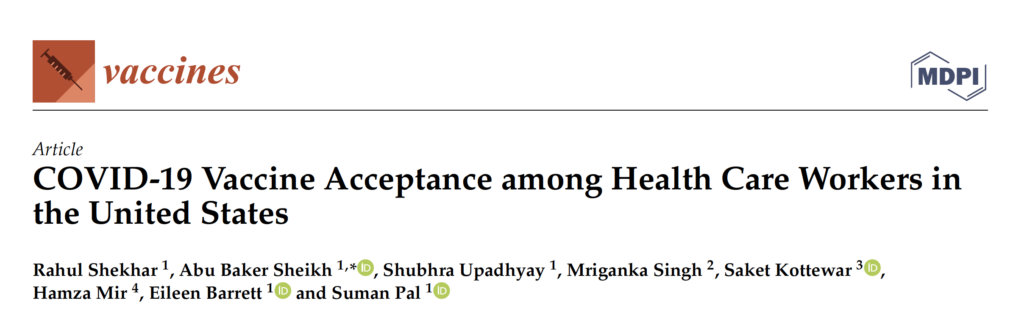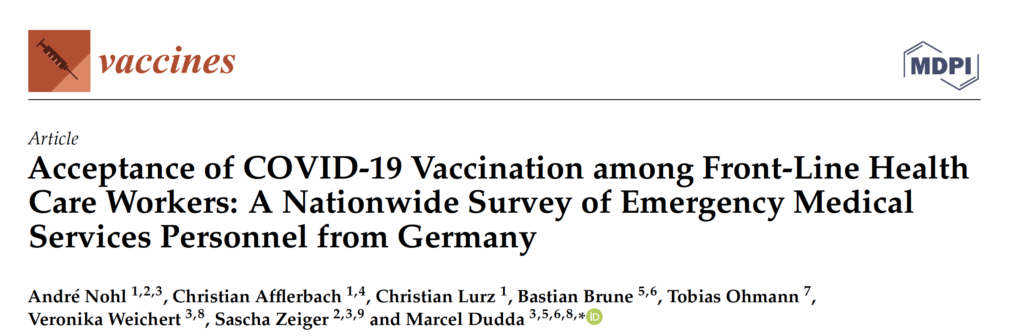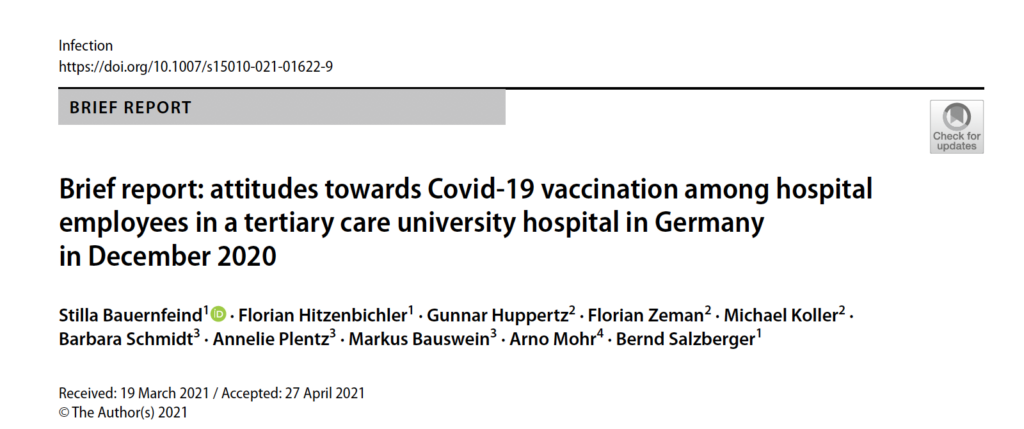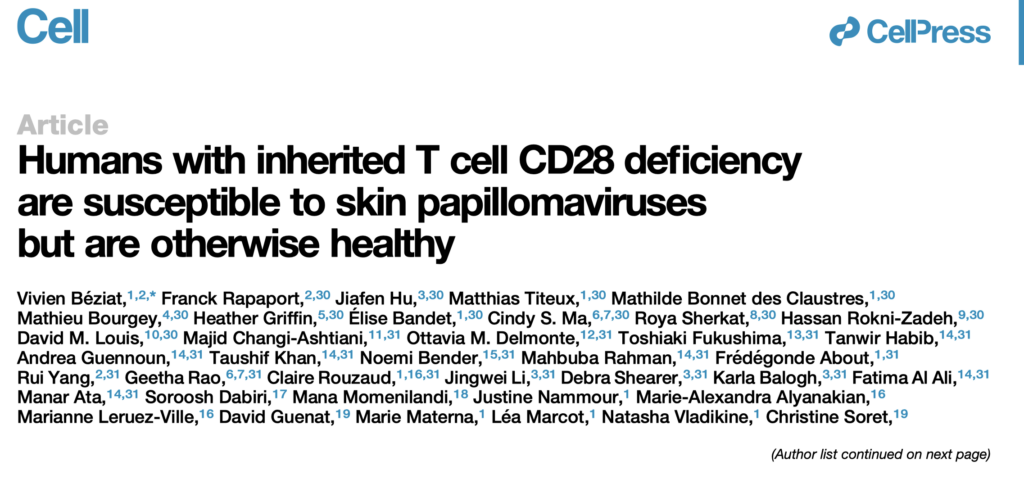2021年7月21日
すでに6割の高齢者がワクチン接種を終えた。私たち夫婦も、昨年の秋mRNAワクチン治験論文を読んで期待したように、接種が終わった6月以降は海外旅行以外、かなりノーマルな生活に戻って楽しんでいる。ただ抗体ができているかどうかは直接確認できておらず、ワクチン効果は論文と自分自身の様々な感染症に対する経験から推察するしかないので、変異株が猛威をふるう今、気持ちが100%ノーマルになることはないだろう。
血中の抗体の上がり下がりのほとんどは、リンパ組織での免疫に関わる数種類の細胞の相互作用の様式の変化を反映したもので、この細胞相互作用が行われる場が、免疫後にリンパ節などで新たに形成される胚中心という構造だ。すなわち抗体が上昇するフェーズで胚中心が形成成長し、抗体が下降するフェーズでは胚中心が縮小、最終的に消滅する。このおかげで、迅速に抗体反応が起こり、また一定期間後反応が低下し、免疫の暴走が止まるようにできている。
今日紹介するロックフェラー大学からの論文は、免疫反応が暴走せず胚中心が退縮する過程を、生きたマウスのリンパ節の長期観察を含む様々なテクノロジーを動員して解析し、ヘルパー細胞から抑制性T細胞への転換が胚中心退縮の引き金になることを示した力作で、動物モデルではあっても免疫反応がこのレベルまで解析できるようになっているのかと、強い感銘を受けた。タイトルは「Expression of Foxp3 by T follicular helper cells in end-stage germinal centers(濾胞ヘルパーT細胞のFoxp3発現が胚中心の終期に起こる)」だ。
胚中心は、抗原を取り込んだ樹状細胞の周りに、B細胞とTヘルパー細胞が集まって、反応が進むリンパ組織内で起こる一種の炎症反応と見ることができる。この反応は極めて複雑だが、とりあえず上昇期はB細胞と濾胞Tヘルパー細胞(Tfh)の動態を抑えておけば、反応をモニターできる。一方、退縮期に入ると、免疫を抑える濾胞Treg(Tfr)が加わって、B細胞がTfhの支援を阻害すると考えられる。
この研究では、NP-OVAを抗原として、NPに反応するB細胞、OVAに反応しているTfh, Tfr、それぞれの動態を経時的に観察するモデル動物を用いて、抗原注射後支配リンパ節で見られる反応をモニターしている。詳しくは紹介しないが、脳研究の光遺伝学レベルのシステムが免疫でも揃っていて、胚中心の消長を細胞レベルで観察できるようになっている。結果をまとめると、以下のようになる。
Tfr機能マーカーFoxp3陽性細胞数は、胚中心の退縮が始まる前に急速に増加する。 Foxp3陽性細胞の振る舞いを、例えばB細胞との接触時間などを指標に観察すると、上昇期と退縮期では質的変化が見られる。さらに、上昇期、退縮期前でTfhとTfrが発現するTcRを調べると、上昇期では全く一致しなかった両者が、退縮期にはいると同じTcRを発現している頻度が高まる。 以上のことから、Tfrは胚中心外から移動してくるのではなく、TfhがFoxp3を発現して、Tfr型へ転換すると考えられる。実際、single cell RNAseqでそれぞれの遺伝子発現を調べると、退縮期のTfrは、TfhとTfrの両方の性質を持った細胞になっている。 最後に、タモキシフェンでFoxp3発現を強制誘導できるようにしたTh細胞を移植して胚中心を形成させた後、まだ上昇期の間にFoxp3をThで強制発現させると、胚中心が退縮を始める。 すなわち、胚中心の形成に関わったTfhが、一定の条件(TcRシグナル変化やTGFβシグナルなどが想像されるが、決定はされていない)下でFoxp3を発現し、T細胞とB細胞の反応を止めて、胚中心の退縮にも関わることが明らかになった。
今後、この仕組みが、長期記憶にも関わっているのかなど、面白い研究が続くように思う。抗体反応研究の総合力をまざまざと見せつける力作だと感銘を受けた。
余談になるが、ここで使われているシステムは、1980年代、私が留学していたRajewskyの研究室で開発していたシステムで、B細胞のイディオタイプをB1-8と記載されているのを見ると、40年前を懐かしく思い出した。
2021年7月20日
大学レベルのワクチン接種が始まったようだが、かなりの割合の大学生がワクチン接種を躊躇しているようだ。メディアでは、馬鹿げたSNSに惑わされている大学生のイメージを強調し、また河野大臣まで、SNS上のデマに惑わされないように、呼びかけている。
ところが、なぜワクチン接種を躊躇するのかインタービューしているTVのニュースを見て、少し驚いた。一人の女学生は、「mRNAワクチンはこれまで使われていないワクチンで、感染予防効果はわかるが、もっと長期に様子を見た後、決断したい」と答えていた。
すなわち、ワクチンの報道が始まった我が国で、新聞・TVなどの大手メディアや専門家が強調したまさに同じことを理由に、高い教育を受けた層もワクチン接種をためらっているように思えた。振り返ってみると、昨年の秋でも、「ワクチンの効果や安全性の確定には何年もかかる」のが普通だという一般論に基づく情報が多く流されていた。とすると、その専門 情報に納得して今もワクチン接種をためらう層は、決してSNSのデマに踊らされている層ではない。
現在では専門家、メディア、政府全員一致で、ワクチン接種一色の報道を続けているが、半年もたたないうちに言を翻されても、信用できないという気持ちもよくわかる。高い教育を受けた層の多くが、一般論でワクチンの問題を印象付けた報道や発言の結果ワクチン接種を今もためらっているなら、私たち専門家は反省すべきではないだろうか。
実際、このような刻々内容が変わっていく複雑な知識について、断片だけを専門家の意見として上から目線で提供することがいかに危険かをこの例は物語っている。事実、マスクからワクチンの安全性まで、その時々で専門家の意見も割れる。その時々の断片的知識だけで一般の方々が判断できるだろうか?
このような複雑な専門知識をそのまま伝えることは難しいが、しかしこの知識のインプットのあり方がワクチンへの態度として現れているのではと思いついて、医療従事者や医学生のワクチン接種の態度を調査した以下の論文に目を通してみた。
最後の論文を除くと、基本的には米国やドイツの病院で働く医師や看護師のワクチンに対する受容性を調べた結果だが、ほぼ一致した結果で、医師に比べて、看護師の受容性は低い。また、医療教育のレベルでも高いほど受容性が高く、低いレベルの教育だと受容性が低いという結果だ。他にも、男性の方が受容性が高く、また高齢者ほど高いというのも全ての論文で一致している。
極め付けは最後の論文で、米国の医科大学と歯科大学でワクチンに対する受容性を調べると、なんとワクチン接種を躊躇する歯科大学生は5割を超え、医学生と比べたとき、2.7倍の差があるという結果だ。
いずれも統計的に完全なデータとは言い難いアンケートに基づく論文だが、それでもワクチンの効果は、時間とともにわかってくる複雑な医学現象であるため、正しい知識を積み重ねることの重要性を物語っている。
では、このレベルの知識の提供をメディアで出来るかといえば難しいだろう。とすると、一番大事なのは不用意に一般論を振りかざさないことだ。すなわち、今回のように知識が刻々変化するとき、知識の提供がいかに難しいかをよく理解し、現在の一般論が、将来多くの人の判断を誤らせることがあることを反省すべきだと思う。
間違っても、ワクチン拒否の理由をSNSのデマのせいにして納得してはならない。梅北2期の参加型ヘルスケアプロジェクトではぜひ知識の提供のあり方についても議論を深めてみたい。
2021年7月20日
発酵食品の威力というタイトルで、Cellに掲載された論文を紹介しているのを、アレっと持った人も多いと思う。21世期に入って、Cell Metabolismを皮切りに、Nature Metabolism, Nature Foodなど発刊がが続いてきたが、これは編集者たちが、食、栄養、代謝などが21世紀の重要な分野であることを認識し、その促進をジャーナルの側でも支援しようと考えているからだろう。
この背景には、感染性(communicable)、非感染性(non-communicable)疾患を問わず、様々な病気の理解に栄養、代謝についての解析が必須であるという確信とともに、例えば特異的因果性を追求する分子標的薬とは違い、栄養や代謝の身体への作用を調べるためには、これまでと全く異なる総合的で革新的な方法論が必要と考えているからだろう。
その結果、今日紹介するスタンフォード大学からの論文のように、毎日の食事の効果を総合的に調べるだけといった論文がCellに掲載される時代が来た。タイトルは「Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status(腸内細菌叢を標的にした食事は免疫状態を変化させる)」で、8月5日号Cellに掲載された。
研究ではまず、BMIが平均25の、既往歴がない健康成人(平均52歳)を39人選び、高繊維食グループと、発酵食グループに分ける。被験者は、あらかじめ決めておいた繊維の多い食品、発酵食品の中から、自分の好きな食品を選んで、4週間かけてそれぞれの食品の量を増やし、それを6週間維持する。その後は自分の好みで、それぞれの食品を選べるようにして、さらに4週間すごす。その間に、腸内細菌叢、便の代謝物検査、血液の炎症性サイトカイン、様々な細胞シグナル等々、総合的解析を合わせて、それぞれの食品の身体への効果を見ている。
重要なのは、数多くの食品の中から選ばせるという形で、生活に合わせた長期コホート研究がしやすくしていることで、従来のXXヨーグルトだけを飲ませるといったコホート研究とは全く異なる。すなわち生活スタイルそのものを問題にしている。結論的にいうと、実際に身体に起こった様々な変化から、どのタイプの食事を取ったのかを、かなり予測できる。この時、最も予測に貢献するのが血液のプロテオミックスで、それに続いて細菌叢、そして細菌叢のプロテオミックスになっている。すなわち、食品は私たちの体を確実に変化させる。
多くの結果が示されており、まとめにくいのだが、面白いと思った結果だけ箇条書きで紹介する。
高繊維食グループでは、期待通り便が柔らかくなる。一方、発酵食を多くとると、お腹が張る。 これまで高繊維食と細菌叢の多様性の相関が示唆されていたが、17週間では大きな変化は見られない。一方、細菌の絶対数は増加しており、便の細菌由来代謝物は増加する。おそらく、摂取した植物繊維の量が、細菌叢のキャパシティーを超えていると考えられる。一方、発酵食品を多くとると、急速に細菌叢の多様性が増加する。ただ絶対数はそれほど増えない。 高繊維食で増加すると言われるブチル酸の上昇は強くない。しかし、側鎖脂肪酸代謝については大きな変化が見られる。これは、細菌叢全体の代謝酵素の変化からも裏付けられる。 高繊維食を摂取した場合の炎症に関する変化は、摂取前の状態に左右される。すなわち炎症の低い状態の人は、繊維食によりますます炎症が抑えられるが、炎症が高い人は、逆に炎症が増強する。これらの変化は、Tfhの変化に相関する確率が高い。 酒好きには嬉しい結果だが、自己申告されたアルコール摂取は、食品による体の変化にあまり影響がない。 発酵食品を多くとると、最初の状態にかかわらず炎症を低下させる。これは血中のサイトカインレベル、および血液細胞中の免疫系細胞の数として表現される。 他にもあると思うが、気になった結果を箇条書きにした。炎症を下げるという観点では、発酵食品が良さそうな結果で、カッテージチーズ、ケフィア、バターミルク、コンブチャ(紅茶などを発酵させた飲料)、発酵野菜、発酵野菜飲料、ヨーグルトなどを選ばせており、参考になる。
基本的にはAIで食べている食品を推察できるぐらいの、人間の代謝状態の総合的把握が可能になってきたことが大きいが、生活に即した科学が基礎科学のトップジャーナルに掲載される時代が来たことは感慨が深い。
2021年7月19日
重いうつ病に、様々な幻覚剤を用いる治療が急速に拡大している。臨床現場に最初に導入されたのは、麻酔剤ケタミンで、これまで何回も紹介してきた。麻酔剤ケタミンを幻覚剤と呼んでいいかどうか難しいところだが、ケタミンも解離体験を誘導することが知られている。
最近になって、幻覚を誘導するドラッグとして用いられていたキノコ、シビレタケに含まれているシロシビンが、セロトニン2A受容体の刺激を介して働き、抗うつ剤として働くことがわかって、FDAもFast Trackで2019年に認可している。最近発表されたThe New England Journal of Medicine(384,1402, 2021)では、抗うつ効果はセロトニン再吸収阻害剤と同等で、しかも副作用が少ない抗うつ剤として使えることが示された。
今日紹介するイエール大学からの論文はこのシロシビンの抗うつ効果の背景にある神経メカニズムを解明しようとした研究で8月18日号Neuronに掲載予定だ。タイトルは「Psilocybin induces rapid and persistent growth of dendritic spines in frontal cortex in vivo(シロシビンは前頭皮質の樹状突起スパインの迅速で長期間続く成長を誘導する)」だ。
研究は単純で、まずシロシビンがマウスにも幻覚を誘導する(頭を左右に振る動作を指標にしている)用量を決定した後、シロシビン投与後の内側前頭前皮質の樹状突起を長期間観察し、樹状突起スパインの成長を7日目と、34日目で記録している。
以前紹介したようにスパインの動態を長期間観察する方法(https://aasj.jp/news/watch/3680 )が開発されたおかげといえる研究だが、投与直後にスパインの数がコントロールに比べて増加し、退縮自体は両群で変化がないため、結果シロシビンにより前頭葉のスパインの数が増えることがわかった。
脳全体で見てみると、前頭前皮質だけでなく、レベルは低いが辺縁系や運動野でも見られる。ヒスタミン2A受容体の阻害剤でこの効果が消えることから、ヒスタミン作動性の神経では同じ効果が得られるのではと結論している。また、効果はメスでより強く見られる。
シロシビン投与直後の神経活動をみると、興奮数と興奮の振幅が高まっており、神経興奮を介するシナプス増強が起こっていることを示している。
重要なことは、こうして誘導されたスパインの変化は、1ヶ月間も維持できることで、ケタミンと同じく一度の投与で迅速かつ長期間続く効果が得られることになる。
結果は以上で、樹状突起スパインの増加などはケタミンの場合と似ているが、作用標的がヒスタミン2A受容体と、うつ病に最も関わりのある神経伝達系なので、基礎的にその効果のメカニズムが明らかになることは、この治療を後押しするように思う。
2021年7月18日
IL-3は一時、最も未熟な血液幹細胞の増殖因子ではないかと考えられたことがあった。事実、私も含めて造血コロニーアッセイを行う時、多能性の幹細胞コロニー形成を誘導する因子として、GM-CSFとともに、もっともよく利用した。また我が国では、2018年に急逝された東大医科研の新井さんと宮島さんがIL-3受容体の遺伝子クローニングに成功し、血液細胞の研究者にとっては、最もポピュラーなサイトカインだったと思う。
その後、c-Kit/SCFなど、骨髄多能性幹細胞の増殖に関わるストローマ細胞由来因子が明らかになり、またIL-3ノックアウトマウスが正常の造血機能を有していたことがわかり、T細胞由来因子であるIL-3はより炎症の調節に関わると考えられる様になった。特に臨床応用という面では、エリスロポイエチンやG-CSFなど他のサイトカインと比べて、大きく遅れをとった、というよりほとんど利用されていないのではないだろうか。
今日紹介するMITからの論文は、血液学者には懐かしいIL-3が、なんとアルツハイマー病を抑制する効果があることを示す研究で、7月16日Nature オンライン版に掲載された。タイトルは「Astrocytic interleukin-3 programs microglia and limits Alzheimer’s disease(アストロサイト由来IL-3がミクログリアをプログラムしてアルツハイマー病(AD)進行を制限する)」だ。
ADといえば、エーザイとBiogenがFDA認可にまでこぎつけたアデュカマブの薬剤としての有効性がメディアでも問題になっている。有効性については今後の臨床利用が明らかにすると思うが、アデュカマブの問題について、よく「Aβは神経変性に直接関わらないから」利用は意味がないなどという発言を聞く。ただ、この発言は間違っている。直接の神経変性がリン酸化Tauで起こるにしても、この過程を誘導する一つの要因がAβであることは何も変わらない。実際、Aβを異常発現させるトランスジェニックマウスは、ADの定番モデルとして利用されているし、またAPOEのADへの役割を考える時、Aβ蓄積の病因としての重要性は言を待たない。膨大な研究のおかげで、AD発症プロセスは、勉強さえすれば私の様な素人にもよく理解できるレベルに整理されている。勉強もしないで、メディア的な知識の断片だけで一般人へ発信することの問題を、アデュカマブ報道を見ていて感じる。すなわち、ADの引き金を引くAβ蓄積を抑制したり、あるいは除去することは今も重要な介入手段と言える。
今日紹介する研究の目的も、ADの引き金になるAβを除去してADの進行をとめる新しい方法の開発だ。しかし、このためにIL-3を着想したのには驚く。というのも、ADに対してIL-3が炎症性サイトカインとしてネガティブな影響があることが知られていた。
おそらく最初はこのネガティブな影響を調べるためだろう、IL-3ノックアウト(KO)マウスとAβ蓄積を起こりやすくした突然変異を導入した5xFADモデルマウスを掛け合わせて正常と比べると、驚いたことに、ノックアウトマウスの方がAβの蓄積が促進し、認知異常が高いことを発見する。この意外な発見がこの研究の全てで、あとは様々な実験を重以下の結果を得ている。
脳では、IL-3はアストロサイトにより定常的に分泌される、一方、その受容体はミクログリアが発現しているが、その発現レベルはミクログリア活性化に関わるTrem2シグナルにより誘導される。 人間のADの脳を調べると、IL-3量は正常脳と比べて特に変化はないが、IL-3受容体の発現量がADで高く、またIL-3受容体発現量とAβの蓄積量、および有病期間の間に強い相関が見られる。 面白いことに、ADの促進因子として知られるAPOE4遺伝型の人では特にIL-3Rの発現が高い。 IL-3はTrem2シグナルで活性化されたミクログリアがAβ蓄積部位に集積する過程に関わる。この集積を、iPS由来のミクログリアとAβ蓄積が強く起こる様にした神経+アストロサイト培養系で再現することができる。 ADモデルマウスにIL-3を持続注入すると、ミクログリアの集積がおこり、Aβの蓄積が抑制され、認知機能が高まる。 以上が結果で、Aβ蓄積がTau異常を誘導する前に、IL-3を脳内に注入することで、ADの進行を止められるということだ。思いもかけない病気ではあるが、IL-3の臨床利用がこんなところで復活したら面白い。また、アデュカマブの認可以降、同じ様な抗体薬の治験や承認申請が活性化されている様だが、IL-3の併用なども面白いかもしれない。
2021年7月17日
昨日発行されたサイエンスでは、表紙がハイエナの親子になっている。新型コロナウイルスのおかげで毎年楽しみにしているアフリカツアーが足止めされているだけに、当然強い興味がひかれ読んでみた。タイトルは「Rank-dependent social inheritance determines social network structure in spotted hyenas(階級依存的な社会的継承がハイエナの社会構造を決める)」で、7月16日号Scienceに掲載された。
内容は、全ての動物社会は遺伝的に支配された実力社会だと思っていた私の考えを改めるもので、ハイエナ社会は、どの家族に生まれたかが将来を決める階級社会であることを知った。
確かに読んでみると、動物社会も階級社会であることが納得でき、またそれが自然であると理解できるのだが、なぜ動物社会は実力社会と思い込んでいたのだろう。
もちろん家族は遺伝的に近いため、体格等々、遺伝=家族という話は出てくるのだが、サファリに参加しても、あるいはドキュメントを見ても、結局は極めて短い時間で観察できるスナップショットをみているだけで、強そうな個体が、闘争の結果ランクを上げるという話で終わる。
一方、今日紹介する研究は、ケニアのハイエナ集団をなんと27年間も観察し続け、その間の各個体の行動を克明に記録した膨大なデータに基づいている。その結果、ハイエナの母親と子供が同じ巣で暮らす1年は当然だが、その後巣を離れても、オスでは5年程度、雌では10年近くも母親と密接な関係を保って集団生活を送ることを示している。
この母親との強い絆のおかげで、もともと高い階級のお母さんとともに行動すると、餌の順番や、オスを選ぶ順番など、自然に得をすることが多くなる。その結果、母親の社会階級が子供に引き継がれることが予想されるが、観察された個々の個体のランクは、全く予想通りで、高いランクの母親の子供は、高いランクを占めるようになる。
ハイエナでは、ランクと寿命が相関するが、この結果高いランクの家族は長生きし、低いランクの家族は寿命が短い。おそらくこれも、ハイエナ社会で階級が固定するのを助けているのだろう。
なんとなく寂しい話だが、社会的階級が継承される動物は、サルや象など、結構いるようだ。いずれにせよ、30年近くアフリカでくる日もくる日もハイエナ家族を追いかけた努力のたまもので、頭が下がる。
長期間観察された動物社会というと、すぐ高崎山のサルを思い出す。ここでは、どの個体がボスザルになるのかがメディアでも話題になるが、高崎山のボスザルは全て貴族の生まれなのだろうか?
2021年7月16日
これまで数多くの相分離に関する論文を紹介し、何回もジャーナルクラブで論文を詳しく解説したので、他の分子と均一に混在していた特定の有機分子同士の相互作用が高まると、急に他の分子から分離し、濃縮した一種の液滴を形成する過程が、細胞内の分子局在と機能を支えていることは理解していただいていると思う。
考えてみると、特定の単位同士の相互作用が強まることで、他の単位の動きとは独立の同調した動きが現れる現象は、物理現象から生物の集団行動まで、様々なレベルで見られる。ただ、このような相転換をいかにして誘導するかが問題になる。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、熟練した運動の開始時に、小脳のプルキンエ細胞でこのような相分離現象を誘導することに成功し、神経ネットワークでも、物理学と同じ法則に従って相分離が起こることを示した研究で、7月8日号のCellに掲載されている。タイトルは「A neural circuit state change underlying skilled movements(神経回路の状態変化が熟練動作を支えている)」だ。
このような研究で最も難しいのは、一定の領域の神経細胞全体が、あたかも相分離が起こったように、急に同調して興奮するという状況が誘導できるタスクを設計することだ。著者らは、少し力を加えると、最初に押した方向へ一直線に動くレバーを設計し、マウスがこのレバーを右前肢で決めた目的に向けて倒せるように訓練し、この動作時に、右前肢に対応する小脳領域に存在する約500個のプルキンエ細胞を、Caイメージングで観察している。
理解しにくいとは思うが、よくできた課題だ。すなわち、最初にどう力をかけるかに成否がかかっており、したがって文字通りこの動作開始時点に「神経」を集中する必要がある。実際、最初の1ー2日ではちょっと触ってしまうとレバーが勝手に動いてしまい、目的に到達できる確率は低い。しかしマウスといえども、1週間もするとうまく神経を集中することができるようになり、成功率は9割を越すようになる。このタスクの設計が、この研究の全てだと思う。
期待通りというべきだろう、右前肢の運動神経が投射する領域の小脳の動きを観察すると、開始時点に多くの神経細胞が同調して興奮するのが見られる。すなわち、一種の相分離が観察される。さらに、同調した神経は興奮後の休止期間でも同調する。ただ、この同調は、それぞれの神経と結合している介在神経が同調して興奮することによって起こっていることも示している。
そして、この同調変化は、外界からの刺激により影響されるのではなく、動作開始時に神経を集中するとする内部からの同調シグナルにより起こっている。すなわち、熟練してくると、このように一定の領域の神経を同調させた運動調節ユニットを形成することで、正確な運動が可能になっている。実際、この同調した活動は、動きが始まった後で外界からこの動きを人為的に邪魔しても、変化が起こらない。
最後に、このような神経細胞の同調も、他の物理化学現象のどう調整と同じルールに従うことを、モデリングを用いて示している。このとき使われているのが、レーザーの同調を説明するための数学モデル、すなわち倉本オシレーション法則で、下部オリーブ核の神経同士の結合性が高まると同調して、この同調性がプルキンエ細胞へと伝達するモデルで、実際の相分離が完全に説明できることを示している。
この論文にも光遺伝学の開発者のDesserothの名前が入っているが、スタンフォード大学からの脳研究は、いつも一味違った深い思索が感じられ、難しくても本当に面白い論文が多い。相分離と言われて、「神経を集中する」意味がよくわかった。
2021年7月15日
6月26日、 MECP2が、従来考えられていたようにメチル化CpGに結合するのではなく、メチル化、あるいはハイドロオキシメチル化されたCAリピートと結合して、ヌクレオソーム形成を調節していることを示したストラスブール大学からの研論文で、この分野の研究方向を大きく変える可能性を持つ研究を紹介したところなのに(https://aasj.jp/news/watch/16028 )、今度はこれまで全くわかっていなかった、CpG island型プロモーターの転写を決定する分子BANPがスイス・バーゼルのミーシャ〜研究所から発表された。今、DNAメチル化についての研究が急速に進展しているのが感じられ、ワクワクする感じが湧いてくる。タイトルは「BANP opens chromatin and activates CpG-island-regulated genes(BANPはクロマチンを開いてCpG island により調節される遺伝子を活性化する)」で、7月7日Natureにオンライン掲載された。
house keeping geneと呼ばれる、細胞の維持に必須の遺伝子は、TATAボックスと呼ばれるプロモーターを使わず、CGくり返しが多く集まったCpG island(CGI)の中に存在するCGCGモチーフを転写開始点として使っていることが知られている。これまで、CGCGサイトがメチル化されるとRNAポリメラーゼ(PolII)のリクルートが阻害されていることはわかっていたが、標的がCGCGであまりに特異性がない領域のため、このモチーフに結合してPolIIをCGIプロモーターにリクルートする分子の発見は難航していた。
このグループは、ヌクレオソームとの結合性が低い、すなわちタンパク質との結合がほとんど起こらない人工的なCGCGエレメントをマウスES細胞の染色体に導入し、細胞内でこの人工的CGCGが間違いなく特異的なタンパク質と結合していることを、タンパク質の結合していない場所をメチル化して、結合部位だけを浮き上がらせる、single molecule footprintingという手法で確認している。
これがわかると、このモチーフに結合するタンパク質を特定できるという確信が得られ、最終的にCGCGに結合するタンパク質BANPを特定している。
ES細胞でBANPが結合している部位を調べると、期待通りhousekeeping 遺伝子のCGIプロモーター部位が1200個ほど特定できる。また、メチル化されたCGプロモーターには結合していない。逆に、3種類のDNAメチル化酵素が全て欠損したES細胞では、結合サイトが増える。次にこれまで知られているCGIプロモーターの転写に関わる分子存在下でBANPの機能を調べると、遺伝子発現を3000倍にも高めることができる。以上のことから、BANPがこれまで謎に包まれていたCGIプロモーターの転写を決定する因子であると結論している。
最後に、クロマチンやヌクレオソームとBANPの関係を調べると、BANPはヌクレオソームの結合を阻害し、クロマチンをオープンにしていることが推察される。これを証明するため、薬剤を用いて分解できるようにしたBANPを用いて、BANPを細胞から除去すると、1時間でクロマチンが閉じはじめ、またヌクレオソームが結合しはじめていることを示している。
以上まとめると、house keeping遺伝子のCGI型プロモーターは、メチル化されるとBANPは結合できないため転写できない。一方、メチル化されないとBANPが強く結合して、ヌクレオソームとの結合阻害を介して、クロマチンをオープンに保つことで、高い転写活性を維持する。
発生学的には、他のCGIとの関係や、そもそもメチル化によるプロモーターの不活化機構も合わせて理解することが重要だが、ガンや老化のように、メチル化自体が変化する場合、BANPの役割が高まってくる。いずれにせよ、クロマチンをオープンにする、ヒストン修飾とは異なる機構が続々明らかにされつつあるが、そのスピードは速い。
2021年7月14日
今回の新型コロナウイルスに対するワクチン開発を眺めていると、ワクチン開発が免疫学だけで無く、病原体についての深い知識に裏付けられたときに成功することがわかる。例えば、mRNAワクチンなどのワクチンが導入したスパイクタンパク質のpre-fusion型が、安定に合成するための分子生物学的工夫などは、まさにコロナウイルス生物学があって初めて可能になる。
ただ、このような工夫の上でも、現在ワクチンによって獲得した免疫がどの程度維持されるのかが問題になっている。この問題は、例えば持続的感染が維持される弱毒化ワクチン開発で実現する可能性はあるが、もともとウイルスゲノム構造が複雑なコロナウイルスでは、弱毒化の戦略が複雑で見えない。さらに、mRNAワクチンと感染から回復した人の抗体を比べた研究から、コロナウイルスの場合、弱毒化戦略が可能かは明確で無い。
そこで考えられるのが、成功しているワクチンの一部をスパイク抗原で置き換えるという戦略で、弱毒化ワクチンの典型であるハシカワクチンにスパイク遺伝子を導入したワクチンが研究されている。
今日紹介する英国サザンプトン大学からの論文は、我々に感染できる病原体に抗原を組み換える発想を、さらに先に進めるワクチン開発研究の話で、正直うまくいっているように思えないものの、着想は面白いので紹介することにした。タイトルは「A recombinant commensal bacteria elicits heterologous antigen-specific immune responses during pharyngeal carriage(遺伝子組換え常在菌を鼻咽頭に定着させて免疫反応を誘導する)」だ。
要するにヨーグルトを使ったワクチンが可能かという課題にチャレンジしている。ただ、腸内での免疫になるとあまりに複雑なので、もう少し入り口、すなわち鼻咽頭に常在するバクテリアをワクチンとして使えるかだ。
実際には、もともと髄膜炎を起こすナイセリア菌と競合関係にある病原性にない鼻腔常在のナイセリアラクタミカ細菌に、髄膜炎ワクチンの抗原としても使用されているNadAという分子が定常的的に発現するよう遺伝子組み換えを行い、これによりNadAに対する抗体と、髄膜炎菌に対する殺菌性抗体ができるのかを調べている。
もともと髄膜炎菌自体も鼻腔の常在細菌だが、常在細菌として振る舞う間はNadAの発現がうまく抑えられるような仕組みを持っており、免疫からも逃れている。この研究では定常的にNadAを発現させたラクタミカ菌を作成(NL)、さらに抗生物質で2日以内殺菌できること、また他の毒性が組み換えにより獲得されていないことなどを確認して、ボランティアの鼻腔に投与、90日まで常在させて抗体やメモリー細胞ができるか調べている。
鼻咽頭に注入すると、期待通り長期間維持される。しかし、どの時点でも呼気に細菌が含まれることはなく、またベッドをともにしているパートナーに組換えNLが感染することはない。
結果だが、常在菌をベクターに用いても、NadAに対するIgGやIgA抗体が形成され、さらにはメモリーB細胞が誘導できる。さらに、低いレベルではあるが病原菌に対して殺菌性を示す抗体もできる。ただ、現在使われているGSK社の髄膜炎ワクチンBexseroと比較すると、抗体価はかなり低いので、現段階では到底治験に進むという段階ではない。
もちろん鼻腔から吸入するワクチンの開発は数多く存在するが、常在菌をワクチンにするという発想を見たのは今回が初めてだ。というのも、もともと免疫反応を起こさないから常在できるので、このハードルを乗り越えることができるということは、私たちの細菌についての知識が高いレベルに達した証左になる。その意味で常識にチャレンジする試みにはエールを送りたいし、ともかく少しは抗体ができたことは、常在菌とは何かを考える意味でも重要だと思う。
余談になるが、この研究で用いられたBexeroワクチンは、組換えタンパク質を用いたワクチンで、髄膜炎に対していわゆる不活化ワクチンしか国産できていない我が国の現状も気になった。
2021年7月13日
これまで、実に多くの免疫システムに関わる多くの遺伝子欠損患者さんが発見されており、免疫システムが極めて複雑な細胞と分子のバランスの上に存在していることがわかっている。そしてついに、本庶先生がノーベル賞を受賞した分子PD-1が欠損した患者さんを、ロックフェラー大学を中心とする国際チームが6月28日Nature Medicineにオンライン発表した。タイトルは「Inherited PD-1 deficiency underlies tuberculosis and autoimmunity in a child(遺伝的なPD-1欠損症により結核と自己免疫が児童期に併発する)」だ。
Introductionを読むと、このグループは結核感染と免疫系遺伝子変異についての豊富な研究経験があるようだ。実際結核は感染防御だけで無く、病気の進行にも免疫システムが関わる複雑な感染症なので、人間で免疫システムを解析するには格好の材料と言える。
このような研究の中で、1型糖尿病、甲状腺機能低下、関節炎と、多臓器自己免疫病を3歳の時から罹患し、結核性の腹膜膿瘍で入院し、最終的に呼吸不全で亡くなった子供を経験する。そして、その兄弟がやはり感染症で亡くなったことを聞き、遺伝性の疾患を疑い、最終的に読み枠がシフトして、短いタンパク質ができてしまう、同じPD-1遺伝子の突然変異が両方の染色体で揃ったことを発見する。この突然変異の結果、PD-1は細胞表面に全く発現されないことも確認している。これまでPD-1自体の変異は発見されているが、機能が完全欠損した患者さんは世界初の症例らしい。
もともと機能阻害抗体を用いたチェックポイント治療が世界中で行われており、今更遺伝子欠損患者さんから得られる情報は少ないのではと思う人もいると思う。実際、この患者さんでは、激烈な結核とともに、多臓器の自己免疫病を発症し、様々な自己抗体が検出され、それとともにいわゆるサイトカインストーム状態が発生していることが示されているが、全てPD-1チェックポイント治療の副作用として広く知られている。
しかし患者さんをじっくり調べ、
結核感染は、PD-1欠損により結核菌に反応したリンパ球からのインターフェロンγやTNFといったサイトカイン誘導が低下していることが原因であることがわかった。 PD-1抗体投与の場合、最初に結核に対する免疫反応が高まり、その後低下することが知られているので、PD-1が欠損すると、最初免疫は増強されても、長いスパンでは特異的免疫も疲弊するのかもしれない。 ほとんどのリンパ球サブセットからのインターフェロンγ合成が低下しているが、同時にγδT細胞、MAITと呼ばれるinvariantTcRを発現した細胞、そしてNK細胞の数が低下していることが、結核への抵抗力がなくなる大きな要因になっている。 STAT3が遺伝的に活性化した患者さんに極めて類似した、double negativeT細胞の増殖とRORγT細胞の増加を伴う自己免疫反応が起こっている。これは、PD-1が欠損することで、IL-6やIL-23が過剰に分泌されるサイトカインストームの結果を反映している。面白いことに、同じチェックポイント治療に使われるCTLA4欠損患者さんでは、逆にdouble negative T細胞とRORγT細胞は低下している。 他にもあるかもしれないが、以上が結果の要点になる。
ある程度予想されているとはいえ、PD-1が欠損している場合でも、特異的な免疫反応が最終的に疲弊することがあること、さらに自己免疫病の基盤としてRORγT細胞が存在することから、RORγを抑制することでPD-1抗体の副作用を治療できることなど、重要なメッセージを示した研究だと思う。
PD-1と並んでCTLA4のチェックポイント機能がノーベル賞を受賞したが、このCTLA4と競合するCD80刺激分子がCD28で、なんとこの遺伝子変異による機能低下を示す症例が、同じロックフェラー大学から7月8日号のCellに発表されている。
詳しくは述べないが、この患者さんは、なんとヒトパピローマウイルス(HPV)2、およびHPV4に感染し、Tree Man Syndromeと呼ばれる、手足の上皮の過剰増殖で、木の枝が手足からのびたと思えるほど激烈な症状を示す。しかし、これ以外はほとんどT細胞の免疫異常は認められておらず、共シグナルシステムが互いに補い合う体制ができていることがわかる。このように、ヒトでの症例を重ねることの重要性がわかる論文だった。