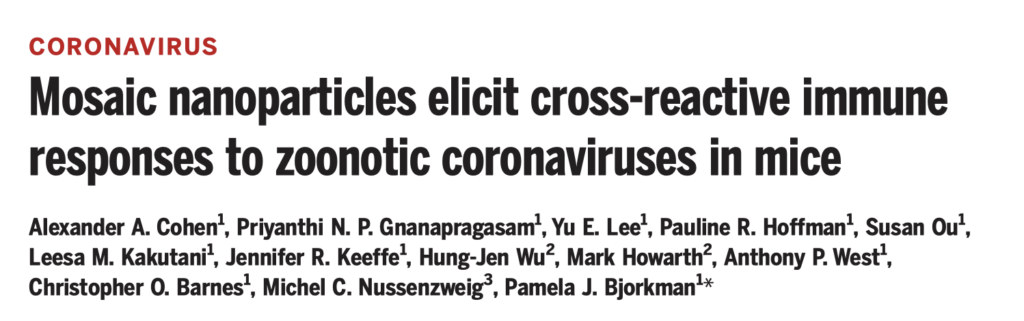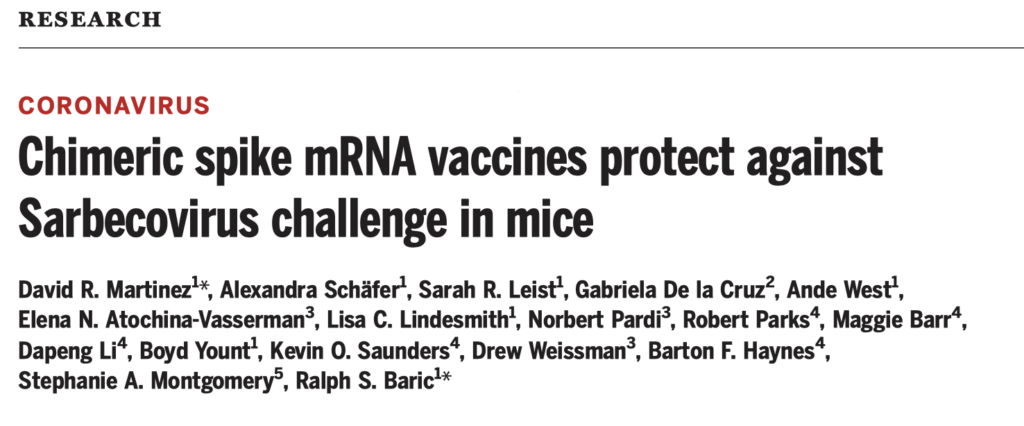2021年9月7日
Non-coding RNAと呼ばれる、ペプチドをコードしているわけではないが、細胞の中で重要な機能を担っているRNA(もちろん最も典型的なのはリボゾームRNAやtRNAだが、このほかに様々なRNAがそれ自身で機能をもって働いている)について知れば知るほど、生命誕生前にRNAワールドが間違いなくあったことを確信する。
そのうちの一つRN7SL1は、シグナルペプチドとリボゾームに結合して翻訳を止めるSRP複合体の中核で、7Sと呼ばれるだけあって300bpの大きなRNAだ。もちろんこんなものが裸で存在したら、そのまま自然免疫を誘導するのだが、実際には6種類のタンパク質と複合体を作っており、問題はない。
今日紹介するペンシルバニア大学からの論文は、このRN7SL1を自然免疫刺激に使って、ガンに対するCAR-Tの機能を高められないか調べた、大変面白い論文で9月7日号Cellに掲載された。タイトルは「The immunostimulatory RNA RN7SL1 enables CAR-T cells to enhance autonomous and endogenous immune function(免疫刺激性RN7SL1はCAR-T細胞自身の活性とともに、ホストの免疫も増強する)」だ。
なぜRN7SL1を使おうとしたのかという点は完全に理解できなかったが、RN7SL1や他のRNAを脂肪粒子に詰めて投与する実験で、普通のRNAは一つのRNAセンサー(RIG1 or MDA5)だけで自然免疫を誘導できるのに対し、おそらく複雑な3次構造のためにRN7SL1は両方のセンサーが働かないと、自然免疫が活性化しない。このため、わかりやすく言うといい塩梅にガン免疫が増強されるようで、移植ガンにRN7SL1を直接注射し、チェックポイント治療と組み合わせると、他のRNAより強い抗ガン免疫を誘導できる。
この方法は、今後ガン免疫を高める方法として利用できるが、この結果をさらに進めて、RN7SL1をCAR-Tで発現させることで、例えば固形ガンでは効果が落ちるCAR-Tを活性化できないか研究を進めている。メゾセリンやCD19に対するキメラ受容体遺伝子とRN7SL1あるいはランダムなRNAを組み込んで、キメラ受容体と同時にRN7SL1が発現するCAR-Tを作成すると、ランダムなRNAと比べて遙かに強い腫瘍抑制効果を示すことがわかった。
面白いことに、CAR-Tは独立して腫瘍を傷害するため、原則他の免疫システムが存在する必要はないはずだが、RN7SL1を発現するCAR-Tの効果は、ホストの免疫細胞が存在する方が遙かに高い。すなわち、RN7SL1を発現するCAR-Tから、何らかの形でRN7SL1が分泌され、周りの免疫システムを巻き込んで免疫を増強している可能性がある。これについて様々な実験を行い、
RN7SL1を発現したCAR-Tは、エクソゾームを介してRN7SL1を周りの細胞へ伝達する。 詳細は省くが、CAR-Tから移行したRN7SL1は、樹状細胞、白血球などほとんどの細胞に受け渡され、不思議なことに抗ガン作用を助ける方向にホスト免疫系を組織化する。特にチェックポイント治療の効果が高まる。 さらに、このような免疫系の再編成を通して、CAR-Tとは別に、腫瘍ネオ抗原に対するキラーT細胞も動員され、ガンを様々な面から傷害する。 ホスト本来のガン免疫機能を高めることで、CAR-Tが結合する抗原がガンから消失しても、ホストの免疫機能が穴埋めをして、ガンの再発を防ぐ。 CAR-Tがエクソゾームを介してRN7SL1を周りの細胞に伝達することを利用し、mRNAワクチンのように、異なるペプチド抗原をCAR-Tに発現させると、このペプチドはガンで発現し免疫を誘導する。 以上、自分でガンを殺すだけでなく、ホストのガン免疫を活性化し、必要に応じて、新しいガン抗原までも提供するスーパーCAR-Tが可能であることを最後に示している。
RN7SL1を用いたアジュバントの開発、RN7SL1とキメラ受容体コンストラクトによる、ホスト免疫を巻き込むCAR-T治療の開発、そしてガン抗原まで提供できるスーパーCAR-Tと盛りだくさんの研究で、さすが最もCAR-T研究の進んだペンシルバニア大学と感心すると同時に、結構高く売れそうな将来の技術になる気がする。
2021年9月6日
サルから人間への脳発生過程では様々なイノベーションが起こったことは間違いないが、これを特定するのは簡単ではない。これまで、サルには存在しない新しい遺伝子の出現や、新しい分子機能の発生などについては紹介したことがあるが、この進化に最も大事だと考えられている転写調節領域の進化については、研究は少ない。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、この課題克服のために想像を絶するほどの努力を払って、サルから人間の過程で新たに起った転写調節領域の変化を網羅的に解析する手段と資源を開発し、哺乳動物の進化過程で変遷し、かつ人間特有の機能が発生した転写調節領域を特定した研究で、10月20日号のNeuronに掲載予定だ。タイトルは「Rewiring of human neurodevelopmental gene regulatory programs by human accelerated regions(ヒトの神経発生遺伝子調節プロブラムを人間の進化で変化している領域を用いてプログラムし直す)」だ。
繰り返すが膨大な仕事だ。まず、人間とサルの発達期の脳を用いてエンハンサー活性をクロマチン沈降法(H3K27など)で調べ、ヒトで大きく変化している原因になると考えられる配列(HARと呼んでいる)を約3万種類集め、この領域を中心にした人工エンハンサーライブラリーを合成している。こうして作成したエンハンサーを、ミニプロモーターとバーコードをつけたルシフェラーゼ遺伝子と結合させたライブラリーにして、エンハンサー活性をバーコードの出現頻度で検出できるライブラリーにして、これを細胞に導入してエンハンサー活性を網羅的に調べている。
ルシフェラーゼ遺伝子をマーカーに使ってしまうと、蛍光活性と一個一個のエンハンサーを対応させる必要が出てしまうので、網羅的解析には適さない。そこで、トランスフェクトした細胞全体を集めて、転写されているRNAの配列を調べ、そこに存在するバーコードの頻度から、エンハンサーの活性を測定するという、まさにバーコードによる「見るから読む」技術で、何万もの異なるエンハンサー活性を一度に測定することが可能になっている。
人間とサルの同じエンハンサー領域ライブラリーの活性を、神経細胞株で調べると、人間で新たに出現したエンハンサー配列(HAR)の半分は、神経細胞内でサルより高いエンハンサー活性を示す。また、発生途上の神経前駆細胞でも同じように高いエンハンサー活性を示す。
また、発生過程の神経細胞を、クロマチン沈降法によるエンハンサー解析や、HiCなどの染色体相互作用測定法で調べた時に特定できる調節領域と、HARを対応させると、40%近くの調節領域にHARを認める。
このように、HARの活性から、そのエンハンサー部分を持つ転写調節領域を特定すると、自動的に転写活性がサルから人間への過程で変化する遺伝子を特定することができる。この研究ではその例として、調節領域に2つのHARがサルから人間への進化過程で挿入された遺伝子PPP1R17を特定する。そして、実際HARがエンハンサーとしてプロモーターと相互作用していることをHiCを用いて確認している。
後は、この遺伝子の発現をマウス、サル、人間と比べると、マウスからヒトまで小脳のプルキンエ細胞では発現が見られる一方、大脳皮質の発現は人間とサルだけで見られること、また皮質での発現もサルでは生後も長期間持続する一方、ヒトでは胎児期だけに発現している。
結果は以上で、実際2種類のHARがヒト特異的なPPP1R17遺伝子発現の生後の低下に関わっているのかについては確認していないし、この遺伝子の発現を早くオフにすることの脳機能に及ぼす効果が何なのかはまだわからない。この遺伝子がG1-S移行を調節することから、細胞の増殖による人間特異性に関わるのではと想像されるが、まだ研究は必要だ。
しかし、エンハンサー活性をバーコードによりバルクで調べられること、それを用いて、脳発生に関わるエンハンサー活性検出ライブラリーを、ヒトを含む様々な動物で完成させていることに、本当に時代が変わっていることを感じた。
2021年9月5日
このHPを始めてからすでに8年が経過したが、考えてみると、心臓の生理学についての論文は紹介したことがなかったように思う。これは、生理学分野の進展が遅いからではなく、単純に私が一般生理学が苦手なだけだ。しかし、今日紹介するデンマーク、コペンハーゲン大学からの論文を読むと、生理学が臨床に直結する学問として、新しいテクノロジーを取り入れながら発展しているのがよく理解できた。タイトルは「Functional cross-talk between phosphorylation and disease-causing mutations in the cardiac sodium channel Nav 1.5(心筋の電位依存性ナトリウムチャンネルNav1.5の疾患関連変異とリン酸化の機能的相互作用)」だ。
まず、電位依存性ナトリウムチャンネルについて少し解説する必要がある。心臓の収縮は電位依存性の、ナトリウム、カリウム、カルシウムチャンネルが動員されることで、規則正しい鼓動を刻んでいる。その中のNav1.5は、心筋の活動電位のトリガーになっている分子だ。驚くことに、500種類もの突然変異が知られており、心室細動の原因になるブルガダ症候群や、QT延長症候群の原因になるが、多くの変異は無症状で経過することが多い。それでも急死などの原因になるのではないかと疑われている。特に難しいのは、この分子が様々なシグナルによりリン酸化され、特性が変化することで、突然変異もNav1.5がリン酸化された条件で調べる必要がある。
この研究では、Nav1.5の1495番目のチロシンをリン酸化チロシンに変化させ、リン酸化された時、遺伝子変異がチャンネル機能にどのような影響があるかを調べている。この研究の最大のハイライトは、Nav1.5を2本のタンパク質に分けて翻訳させ、それをタンデムタンパクスプライシングと呼ばれるメカニズムを用いて一本にまとめるときに、すでにリン酸化したチロシンを挿入するという、私にとっては初耳のテクノロジーを使って、リン酸化Nav1.5を細胞表面に発現させることに成功している。
これにより、Nav1.5の突然変異と、リン酸化が集まるチャンネル機能への影響を正確に評価できる。また、Nav1.5は構造が詳しく解析されているので、これを用いて分子レベルで何が起こっているのかシミュレーションを行っている。
結論をまとめると以下のようになる。
正常分子がリン酸化されると、チャンネルが開く電位は低下することから、リン酸化がチャンネル感受性を上げることがわかる。シミュレーションから、この効果はリン酸化されたDIII-DIVリンカー部分の構造変化を誘導されることがわかる。 Q1476Rと呼ばれる変異は、それだけではチャンネル特性をほとんど変化させないが、リン酸化と組み合わせると、電位依存性が大きく低下し、興奮しやすくなる。これも、DIII-DIV部分の大きな構造変化によることがシミュレーションからわかる。 K1500が欠損した変異では、活性化の電位ではほとんど正常と違いが見られないが、完全に閉じるまでの時間がかかり、late currentと呼ばれる電流が流れることがわかる。 この系を用いると、現在使われている不整脈治療薬の効果を正確に測定できる。また、チロシンキナーゼ阻害剤を治療に使う重要性も確認できる。 以上、何よりもprotein splicingと呼ばれる方法に感心して選んだが、生理学はそのまま臨床に直結しており、重要性を認識できる素晴らしい研究だと思う。
2021年9月4日
現在、世界中で腸内細菌叢とガン免疫との関わりを調べる研究が加速しており、慶応大学医学部の本田さんは、ヒトの膨大な細菌叢の中から、ガンのチェックポイント治療を高める細菌セットを分離することに成功している。このような現象が起こるのは、細菌叢と免疫系をつなぐ自然免疫細胞innate lymphoid cell(ILC)、特にILC3の存在が大きい。
今日紹介するコーネル大学からの論文は、主にマウスモデルを用いて大腸ガンでのILC3の役割を調べた研究で、9月16日号のCellに掲載された。タイトルは「Dysregulation of ILC3s unleashes progression and immunotherapy resistance in colon cancer(ILC3の調節異常によって大腸ガンの増殖と免疫治療抵抗性が高められる)」だ。
ILC3は京大時代に、当時、大学院生だった本田さんや助手の吉田さんたちが特定したパイエル板組織のinducer cell に一番近いILCだが、当然腸組織で多く存在している。この研究では最初からILC3が直腸ガンでどうなっているのかに焦点を当てており、フローサイトメトリーを用いてガン組織を調べている。
結果は明瞭で、ガン組織ではILC3が低下し、逆にILC1が増加している。この原因を探っていくと、ILC3がリプログラムされてILC1へと分化してしまうことが明らかになった。また、これと同時に腫瘍組織のtype1免疫反応細胞が減少していることがわかった。
この結果はILC3細胞が直接type1免疫細胞の維持に関わり、ILC3減少によりTH1が低下した可能性も否定はできないが、本田さんたちが示したようにILC3が持つ細菌叢との相互作用を介して、2次的にtype1免疫反応細胞が減少している可能性が強く示唆される。
そこで、ILC3特異的にクラスIIMHCをノックアウトしたマウスを作成して、腸内細菌叢を比べると、対照に比べて細菌叢が大きく変化している。そしてこのノックアウトマウス由来CD4T細胞を大腸ガンマウスに移植すると、同じようにtype1免疫細胞が局所で減少し、また同じマウスからの便移植でもtype1免疫細胞の減少が見られることがわかった。以上のことから、ガン局所でのtype1免疫反応の低下は、まずガン発生によりILC3が低下し、この結果type3免疫細胞との相互作用起こらなくなり、それが細菌叢の変化を誘導して、最後にtype1免疫反応を低下させるという複雑な過程を反映していることを示している。
事実、ILC3のMHC-IIをノックアウトしたマウスでは、実験大腸ガンマウスモデルで、体重減少が促進し、また良性ポリープ数こそ減少するが、悪性のガンの発生は促進していることがわかり、ガン免疫に腸内ILC3が維持されることの重要性を示している。
これまで、炎症性腸疾患でもILC3細胞が低下する事が知られているが、患者さんからの腸内細菌叢はILC3が低下したマウスの細菌叢と同じ様にチェックポイント治療に対する抵抗性を誘導することも示している。
以上、大腸ガン発生でなぜILC3が低下するのか(仮説としてはガンストローマ細胞のTGF-βやIL-23が働いていると考えられている)、また実際にはどの細菌がチェックポイント治療抵抗性に関わっているのかなど、トランスレーションのためにはまだまだ実験が必要だが、細菌叢とガン免疫をつなぐメカニズムが徐々に明らかになっているのを実感する。
2021年9月3日
先週、ウオレス線の東側で発見された7000年前のホモサピエンスが、人類出アフリカ南ルートで移動した民族を代表していることを示したドイツ・イエナマックスプランク人類歴史科学研究所からの論文を紹介したが、なんと同じマックスプランク研究所から、今度は南ルートの起点となるサウジアラビア人類遺跡発掘調査に関する一種の中間報告が9月1日号のNatureに発表された。ドイツ考古学やゲノム考古学の大躍進を目の当たりにすると、シュリーマンの伝統が生きているのでは思える。タイトルは「Multiple hominin dispersals into Southwest Asia over the past 400,000 years(過去40万年にかけて人類の東南アジアへの移動が何度も起こった)」だ。
何度も繰り返すが、ホモサピエンスがイスラエルからヨーロッパ、アジアに進出したのはようやく5万年前の話だが、インドからインドネシア、そしてオーストラリアへのホモサピエンスの進出はそれより前に起こったと考えられている。すなわち、ネアンデルタールと対峙したあと急速に全世界に広がった北ルートとは異なるホモサピエンスの民族形成が、南ルートの解析によりわかるはずだ。
ホモサピエンス最古の骨はモロッコで出土した30万年前のものだが、エチオピアでは約20万年前、UAEでは12.5万年前の遺跡が発見されている。この研究では、サウジアラビア砂漠地帯の中心にある古代の湖、KAMに注目し、発掘を行ってきた。そして、期待通り、異なる時代を反映する地層から、多くの石器や動物の化石が発見され、それについて報告したのがこの論文だ。
今は完全に砂漠化しているKAMは、地球規模の気候変動に合わせて、緑が生い茂った時期が、40万年前、32万年前、20万年前、12万年前、10万年前、7万年前頃に存在し、化石からカバも生息する十分な深さの湖が存在していた。
この研究では、かつて湖だった様々な場所から出土した石器を解析して、どのような人類が存在したのかについて、石器の種類から推察している
ヨーロッパからの石器については以前Sheaさんの本を元に、解説しているので参考にしてほしいが(https://aasj.jp/news/watch/8185 )、今回地層の年代測定から、40万年前、30万年前の2つの遺跡から出土する石器は、Acheulian文化に属する石器で、骨が出土していないので確実とは言えないが、ホモサピエンスやネアンデルタール人とは異なる人類、あるいはそのルーツに近い人類が、アフリカから移動してきたことを示すと考えられる。おそらくH.Ergasterと考えていいだろう。
一方、20万年前、13万年前、7.5万年前の遺跡から出土する石器は、イスラエルでホモサピエンス、ネアンデルタールが共存していたLevant文化の石器で、ホモサピエンス、場合によったらネアンデルタール人がこの地に移動していたことを示している。
結果は以上で、今後の発掘で人骨が出るのを期待するが、エチオピアで発掘されたホモサピエンスの骨とほぼ同時期に、おそらくホモサピエンスのサウジアラビア進出があり、13万年、75千年と、このルートを使って何波にも分かれてホモサピエンスが東南アジアからオセアニアへ移動したことを示す遺跡が、新たに発見された。すなわちこのあたりが、南ルートでの人類移動の起点になっている可能性が示された。まだまだ先は長いが、さらに大発見が続く予感がする。
2021年9月2日
電極を脳内に留置して、刺激により様々な異常を補正するneurostimulation療法は、心臓のペースメーカー療法並みに普及して、根本治療ではないが、対症療法として定着している。特にパーキンソン病など異常運動や疼痛抑制など、その範囲は広い。ただ、てんかん時の同調した神経興奮を抑えるためにneurostimulationが開発されているのは全く知らなかった。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、現在行われている局所の脳波異常を記録しながら発作を探知し、刺激でそれを抑えるresponsive neurostimulation system (RNS)が効果を発揮するメカニズムを、同じデバイスで記録した興奮を詳しく分析することで明らかにし、より効果的な刺激方法を開発しようとした研究で8月25日号Science Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Long-term brain network reorganization predicts responsive neurostimulation outcomes for focal epilepsy (長期にわたる脳神経ネットワークの再構築が焦点性てんかんのNRS治療効果を予測する)」だ。
NRSは深部電極とは異なり、神経細胞に電極を挿入するのではなく、脳内ではあるが脳の外に刺激と記録をかねたデバイスを設置する。このため、ペースメーカーと同じように長期間の使用が可能だ。すなわち、てんかん発症にいたる脳波を検知して、一定の領域を刺激して、それぞれの神経に独自性を与えて興奮させることで、同調を止めるという原理と考えられてきた。
この研究では、この治療に反応する人と、反応しない人がはっきり分かれてしまう点に着目し、効果がある場合は、てんかんの焦点を形成する細胞と結合する神経ネットワークの結合性が低下しているのではないかと考えた。
これを証明するため、長期間設置したNRSデバイスで記録できる神経興奮を、領域間の同調性、すなわち結合性という視点で分析し直し、RNS治療を繰り返すうちに、てんかん巣内の低波長の神経結合性が低下する一方、外部との体は腸の結合性が上昇すること、逆に治療が成功する人ではてんかん巣内の高い波長の結合性が増強するようプログラムされることを明らかにした。
すなわち、ペースメーカーのように、人工シグナルだけでてんかんを制御するのではなく、時間をかけててんかん巣内で過興奮をとどめるようにネットワークがプログラムされ直すことが、治療効果に作用することを結論している。
そして、このリプログラムされる程度が、異常興奮を察知しておこるNRSでの刺激数に依存しており、今後さらにプログラムし直すことを目的とした刺激法や波長を工夫することで、この治療が効果を示さない人たちにも利用できるようになるのでは議論している。
この論文は、全く知らないことを学んだというだけでなく、直接電極を挿入しなくとも、領域記録と刺激をリンクさせた方法で、神経ネットワークを刺激依存的にプログラムし直せる可能性を示した点で期待できる。この領域のAI依存性はすさまじい勢いで進んでいることも実感した。
2021年9月1日
動脈硬化を慢性炎症という枠組みで捉えたのはPeter Libbyで、ここから生活習慣病や老化を炎症として捉えるトレンドがスタートしたと言える。実際プラーク形成の細胞動態を見ると、炎症以外の何物でもない。その後、ゲノム研究を中心に多くの動脈硬化分子が発見されたが、多くは自然炎症に関わる分子だった。中にはCD40リガンドやAPRILのように免疫系調節に関わるTNFファミリーに属する分子が、血管にも作用して動脈硬化を悪化させることも知られている。すなわち、動脈硬化が様々な炎症分子の作用の上にできていることがよくわかるが、それぞれが原因か結果かは、なかなかわからない。
今日紹介するウィーン医科大学からの論文は、動脈硬化で上昇していることが知られているTNFSF13(=APRIL)の、動脈硬化への関わりを調べた論文で、動脈硬化が一筋縄では理解できない複雑な過程であることがよくわかる研究だった。タイトルは「APRIL limits atherosclerosis by binding to heparan sulfate proteoglycans(APRILはヘパラン硫酸プロテオグリカンに結合して動脈硬化を抑える)」で、8月25日Nature に掲載された。
APRILが人間の動脈硬化で上昇していることはわかっているので、動脈硬化巣でその受容体の発現を特定し、それぞれの遺伝子をノックアウトした動物モデルを組み合わせればメカニズムは特定できると期待して、研究が始まったのではないだろうか。
まずAPRIL遺伝子をノックアウトしたマウスを、悪玉コレステロール(すなわち自然炎症の誘導因子)として知られるLDLが高レベルで維持されるLDL受容体ノックアウトマウスとかけあわせると、LDLで誘導される動脈硬化が悪化する。一方で、元々APRILの機能が知られていたB細胞の方は、APRIL KOではほとんど影響受けないので、この結果はAPRILの血管への直接作用を反映していると考えられる。
そこで、APRIL KOの代わりに、APRIL受容体BCMA KOマウスで同じ実験を行うと、動脈硬化には影響されないので、これまで知られていた受容体シグナルとは全く異なる経路でAPRILが作用していることになる。
この新しいメカニズムを探すため、まず血管内皮細胞が発現するAPRIL結合分子を探索し、最終的にヘパラン硫酸結合プロテオグリカン(HSPG)であることを突き止めている。従来の研究でHSPGはLDLの血管基底膜への滞留を誘導して動脈硬化を悪化させることがわかっている。すなわちAPRILはHSPGと結合してLDLの血管基底膜への滞留を抑える可能性が示唆され、マウス大動脈でのLDLの滞留をAPRILが押さえることを示している。
このように、メカニズムが明らかになると、治療標的になり得るか、またAPRILを臨床診断に用いられるかを調べることが重要になる。
まず治療の方だが、プロテオグリカンとAPRILの結合を高める抗体を開発し、これを投与することでAPOE欠損マウスの動脈硬化を押さえることができることを示している。ただ、抗体以外には現在のところ手段はない。
一方診断の方だが、これは簡単でなかったようだ。すなわち、ヒト血中APRILはB 細胞と反応できるタイプのcanonical APRILと反応できないnoncanonical APRILが存在しており、通常noncanonicalタイプ(ncType)が多いことがわかった。最後にncTypeと動脈硬化の関わりを調べると、症状のないグループでは低いほど心臓病になる確率は高い。すなわち、APRILが動脈硬化を押さえていることがわかるが、いったん動脈硬化症状が出ると逆にncTypeが高い人ほど心筋梗塞が増えるという、複雑な結果になっている。
結果は以上で、メカニズムはよくわかるが、診断や治療にそのまま使える結果かというと、問題が多いと思う。動脈硬化はやはり一筋縄ではいかない病気で、当分はスタチンと食事、運動以外の治療は望めないようだ。
2021年8月31日
現在腎不全に対する治療法は、人工透析と腹膜灌流があるが、腹膜灌流の方は様々なメリットがあるにもかかわらず、普及していない。我が国の腹膜灌流比率1%は例外としても、欧米でも10−20%の普及率にとどまっている。この理由の一つは、自宅での清潔作業が必要であるなど運用上の問題もあるが、現在使われているicodextrin入りの灌流液が、生物学的に全く不活性というわけではなく、どうしても腹膜を刺激して、血管新生、腹膜細胞障害、線維化などを誘導して、灌流効果が低下してしまうことも問題になっている。
今日紹介するウィーン大学からの論文は灌流液による腹膜の変化のメカニズムを探り、この作用を塩化リチウムで抑えることが可能であることを示した研究で、8月25日号のScience Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Lithium preserves peritoneal membrane integrity by suppressing mesothelial cell αB-crystallin (リチウムは中皮細胞のαBクリスタリンを抑制して腹膜の機能を保全する)」だ。
まず、世界中で安全に使われている灌流液に満足せず、さらに完全なものにしようと努力しているこのグループに脱帽したい。このグループは、灌流液に加えることで、灌流液による影響を軽減させる分子を探索する中で、細胞保護作用と抗炎症効果が知られている塩化リチウムに着目し、この研究を始めている。
研究ではヒトの腹腔由来中皮細胞を培養し、灌流液に暴露したときに見られる変化を、細胞学的遺伝子発現解析や発現タンパク質解析で特定するとともに、この変化を塩化リチウムにより抑制できないか調べている。
結果は期待通りで、灌流液にさらすことで中皮細胞の細胞死や形態変化が誘導されるが、これを塩化リチウムが見事に抑制することができる。そして、遺伝子発現やタンパク質発現の網羅的研究から、この変化を誘導するマスター遺伝子として、αBクリスタリンを特定する。
事実、灌流液にさらされた中皮細胞ではαBクリスタリンの発現が上昇し、塩化リチウムはこの上昇を抑える。そして、αBクリスタリンを過剰発現した細胞では、灌流液による細胞死や形態変化の誘導を塩化リチウムが抑制できなくなる。
次に、このメカニズムを解析し、灌流液がαBクリスタリンのリン酸化を介して核内移行を誘導し、TGFβにより活性化されるSMAD4のユビキチン化を抑制することで、TGFβシグナルが増強し、中皮細胞から間質細胞への転換が誘導されること、そして塩化リチウムはこのαBクリスタリンリン酸化を抑え、中皮細胞/間質細胞転換を抑えることを明らかにしている。
最後に、マウスの腹膜灌流モデルで誘導される、腹膜肥厚、線維化、血管新生などを塩化リチウムが抑制できることを確認し、臨床へのトランスレーションが可能であることを示している。
以上が結果で、少なくとも現在の腹膜灌流液は刺激性があり改善の余地があること、またこの問題を灌流液に塩化リチウムを加えることでかなり改善できることを示している。ただ、臨床へのトランスレーションに当たって今後確認が必要な点は、塩化リチウムの副作用の問題だ。塩化リチウムは躁病に対する薬剤としてすでに利用されており、命に関わる有害事象が発生する可能性は少ないが、それでも腎毒性などが指摘されており、灌流液に加えて使う場合も副作用への注意が必要になる。ただ、著者らは灌流液に有効濃度の塩化リチウムを加えても、血中の塩化リチウム上昇が少ないことから、副作用もかなり局所で抑えられると議論しているが、今後の研究が必要だろう。
いずれにせよ、αBクリスタリンを、灌流液の腹膜障害性の鍵として特定できたことは、今後より安全な腹膜灌流液の開発に大きく寄与できると期待する。
2021年8月30日
先週、梅北2期、参加型ヘルスケアプロジェクトの活動として、WHO武漢調査にも参加された国立感染研究所・獣医科学部部長の前田健先生をお招きしzoom講演をしていただいた。熱い議論が続き、1時間を優に超してしまったが、その様子は近々このHPでも公開するので楽しみにしてほしい。今後多くの新しいコロナウイルスが、動物の中で人間に感染する機会を待っていることがよくわかる講演だった。
もしコロナウイルス、特にsarbecovirusにより、新しいパンデミックを覚悟する必要があるとすると、一つは広い範囲のsarbecovirusに効果がある治療薬とワクチンの開発が必要になる。
例えばすでに米国政府が170万回分を12億ドルで調達を決めたメルク社molnupiravirは、以前紹介した、経口投与可能、ウイルスRNA複製を中断しないで遺伝子変異を指数関数的に上昇させるという特徴で、レムデシビルを凌駕する可能性があり、しかも軽症者に投与可能な治療薬だが(https://aasj.jp/news/watch/17631 )おそらく他のSarbecovirusにも効果があるだろう。
他にも現在治験が進むCoV2ウイルスのメインプロテアーゼを標的にしたファイザーや塩野義の阻害剤も、SARS関連コロナウイルス(sarbecovirus)全体に効果を示すのではないだろうか。
またEUが緊急承認したGSK社ウイルス中和モノクローナル抗体sotrovimabは、元々SARS患者さんから分離された抗体で、多くのsarbecovirusに効果を示すことから、新しいsarbecovirusパンデミックの備えになる。
このような広いスペクトラムのsarbecovirusの感染を抑える抗体が存在する事実は、同じような抗体を誘導できるワクチンの開発が可能であることを示している。またこれとは別に、スパイクの一部がup formをとるときに初めて分子表面に現れる領域に対するモノクローナル抗体が、ほとんどのsarbecovirusに効果があることを示した研究は、この領域特異的に抗体を誘導するワクチンを設計できれば、多くのコロナ感染に備えることが可能であることを示している(https://aasj.jp/news/watch/17067 )。
よく効く薬と抗体薬があれば、ワクチンは必要ないのではという考えもあるが、パンデミック制御に必要なコストはワクチンの方が驚くほど少ない。これは国産が可能になっても同じで、広い範囲のsarvecovirusに対して抵抗力をつけるワクチンが設計できればそれに越したことはない。
ただ、お手本になる抗体とそれが認識しているスパイク領域の構造がわかっても、それだけを誘導するワクチンの設計は、簡単ではなく、現在は様々な可能性を試す試行錯誤の段階にある。そのための一つのアイデアは、様々なウイルスのreceptor binding domain(RBD)を同時に免役するワクチンの開発で、例えば今年の2月、ウイルス様粒子上に数種類のRBDを発現させるワクチンが開発され、様々なコロナウイルスに対する免疫が誘導できることを示す論文がカルテックから発表された。ただ、構造が複雑なことを考えると、コストなどの面で実用化は遠い気がした。
これに対し、今日紹介するノースカロライナ大学からの論文は、いくつかのウイルスのスパイク分子を混合して免役するという発想から始まってはいるが、mRNAとより単純なモダリティーを持ちいている点で実現性は高く、これにより多くのsarbecovirus感染を抑えることができることを示した研究で8月27日号Scienceに掲載されている。
この研究では、RBDだけを抗原にしないで、スパイク全体を抗原に用いるが、それぞれの領域を様々なウイルスから持ってきたキメラ遺伝子を合成し、これをmRNAワクチンとして免疫に用いている。大きな分子を用いることで、細胞性免疫ペプチド抗原も十分確保するという点では、スパイク全体を使う方がRBDだけに絞るより実践的だ。様々なキメラ遺伝子を用意する必要はあるが、mRNAワクチンをモダリティーとして利用する場合は、十分実現性はあると思う。
実際には、N末領域(NTD)/RBD/S2領域の組み合わせを、コウモリウイルス/SARS/CoV2、SARS/Cov2/SARS、SARS/Cov2/Cov2、そしてCoV2/カメウイルス/CoV2の4種類キメラ遺伝子を用意している。
目的はノースカロライナ大学と同じで、4種類全部を用いれば、多くのウイルスに対応できると考えた。実際、4種類全部、あるいは最初に2種類、後から他の2種類でブーストと言った方法で免役すると、たしかに様々なウイルスに対応できるワクチンとして利用できることがわかった。また、様々なCoV2変異株にも効果があり、マウスの肺炎を予防する効果も高い。以前紹介したシンガポール在住のSARS感染者にCoV2ワクチンを接種することで、多くのウイルスをカバーする抗体が誘導できた結果(https://aasj.jp/news/watch/17664 )を考えると、ワクチン戦略としても十分あり得るかと納得できる。
この論文の明確な結論としてはここまでで、4種類を同時注射でもワクチンとして十分実現性はある。これとは別に、個人的に最も面白いと思ったのは、数種類を同時注射しなくても、カメ/CoV2/CoV2型ワクチンを単独で用いても、CoV2に対しての抗体誘導能は劣るが、調べた4種類全てのsarbecovirusに抗体が誘導されていた点だ。
これは個人の想像に過ぎないが、ACE2結合のための最も肝心のRBDがカメに置き換わったことで、up/downフォームの頻度が変化したりして、以前紹介した領域(https://aasj.jp/news/watch/17067 )に対する抗体を誘導できた可能性がある。全てポリクローナル抗体であること、そして抗原の構造解析が全くできていない点で、まだまだ研究が必要だが、さらに研究を重ねれば、sarbecovirus全般に対応できる、一種類のワクチンも開発できそうな印象だ。
このように、ワクチン競争はもはや新しいパンデミックを予想して、一つのウイルスだけでなく、その種全体をカバーできるワクチン開発にシフトしていることは確かだ。これはsarbecovirusだけでない。論文を見ていると最近だけでも、インフルエンザ、αウイルス、HIVなどなど、全てで開発競争が熾烈になっている。その意味で、今回のコロナウイルスパンデミックは、ワクチン研究にとって、大きなブースター効果があったと思う。
2021年8月29日
子宮内膜症は、子宮と名前がついているが、実際には子宮以外の卵巣や卵管(他にも様々な場所)に内膜様の組織ができてしまい、それが月経周期に併せて増殖・消退を繰り返す病気で、内膜症の場所を特定するのが難しい場合、診断が遅れる。治療としては、内膜の増殖を止めるためのホルモン治療が中心だが、内膜自体を除去する手術も行われる。
今日紹介するオックスフォード大学からの論文は、症状の重い子宮内膜症患者さんの遺伝学的解析から neuropeptide S(NPS)とその受容体neuropeptide S receptor 1(NPSR1)が内膜症の誘導因子であることを突き止め、治療可能性を示唆した論文で8月25日号Science Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Neuropeptide S receptor 1 is a nonhormonal treatment target in endometriosis (Neuropeptide S receptor 1は子宮内膜症のホルモン以外の標的になる)」だ。
すでにゲノム解析から、頻度は少ないが子宮内膜症と相関する遺伝子座が特定されており、この研究では染色体7番にある遺伝子座の中から、最終的にNPSR1遺伝子のアミノ酸の変化を伴う突然変異が子宮内膜症に関わっていることを特定している。
ただ、これは頻度の低いレアバリアントなので、次にNPSR1遺伝子がより広い範囲の子宮内膜症に関わっている可能性を、SNPデータベース探索により調べ、この領域にあるいくつかのSNPが子宮内膜症に関係すること、またそのうちのいくつかがNPSR1発現に関わっていることを確認している。
これで十分な気もするが、驚くことにこの研究ではアカゲザルの集団の子宮内膜症と遺伝解析を組み合わせた研究も行い、NPSR1の変異が子宮内膜症に関わることを明らかにしている。おそらくオックスフォードでは人間のデータをバックアップするためのサルの集団が維持されていると思われるが、用意周到さに驚く。
後は、NPSR1が子宮内膜症にどう関わるか、メカニズム解析になるが、これは難航したようで、正常と内膜症組織でNPSR1の発現などはほとんど差がない。様々な探索の結果、CyTOFと呼ばれる細胞内分子まで単一細胞レベルで調べられる方法で、ようやく子宮内膜症患者さんの腹腔液の中のマクロファージでNPSR1の発現が上昇していることを発見する。
メカニズムの探索はここまでで、あとはNPSR1阻害分子が存在するので、マウス腹腔に炎症を誘導したとき、この阻害剤が腹腔内の炎症を押さえて、痛みを取るかどうか、マウスモデルで調べている。結果は上々で、マウス子宮内膜症モデルで、痛みを示す行動を強く押さえるとともに、炎症性マクロファージをある程度抑制することを示している。
結果は以上で、NPSR1が脳で機能していることを考えると、脳には到達しないお薬が必要になるが、治療の難しい子宮内膜症症状改善に使えるのではと期待できる。
しかしこの論文で一番驚いたのは、サルの集団でゲノム解析が行われている点で、さすがサル学の進む日本でも、ここまで踏み込んだ研究はないように思う。