最も気になった臨床研究から始める。
熊本大学医学部で免疫学を担当していたとき、講義の最初に抗体を最初に発見したのは誰か知っているか?と訪ねることにしていた。残念ながら答える学生さんはいなかったが、答えはベーリングと北里で、彼らが抗体の発見者と言われる理由は、破傷風の嫌気性培養に成功し、破傷風の血清療法を開発したからで、抗体を用いて治療が行われたのは、彼らの破傷風やジフテリアの治療が最初になる(von Behring E, Kitasato S. Ueber das Zustandekommender Diphtherie-Immunität und der Tetanus-Immunitätbei Thieren. Deutsche Medicininischen ochenschrift1890;49:1113-4.)。特に北里は熊本県小国村出身ということで、一人ぐらい答えてほしいなといつも期待していたので残念だった。
現在は外傷の状態から破傷風のリスクがあると判断すると、ワクチン接種歴のある人はブースターワクチンを接種して様子を見るが、接種歴が不明だと免疫グロブリン注射が行われる。今最初に紹介する中国から論文は、ヒト免疫グロブリンの代わりにジフテリアトキシンに対するヒトモノクローナル抗体の第三相治験に関する報告で、7月8日 Nature Medicine に掲載された。
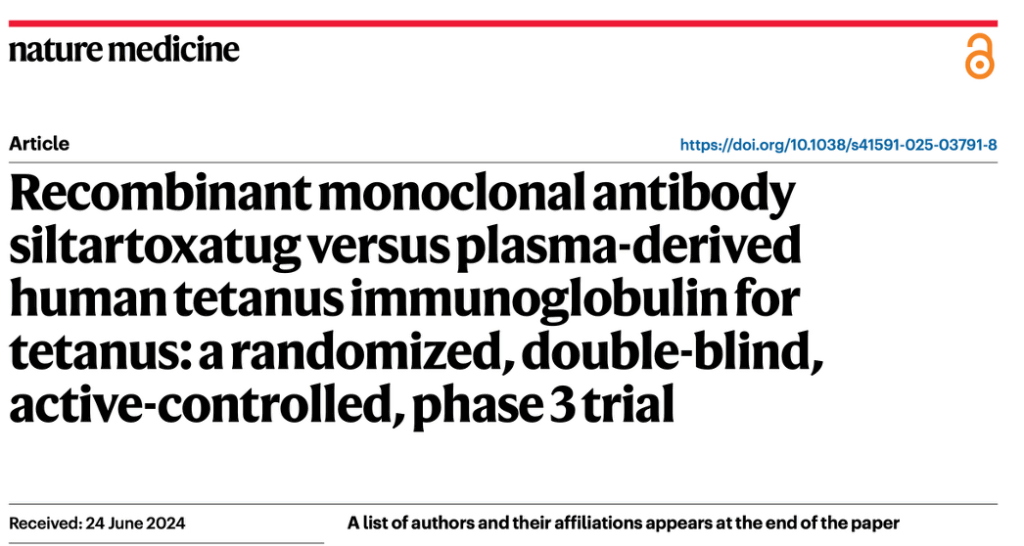
治験は中国全国の救急外来から外傷で破傷風のリスクがある患者さんを388名集め、ヒト免疫グロブリンかモノクローナル抗体を投与して、破傷風の予防効果と安全性を見ている。このうち70名はワクチンも接種している。実際の効果については、全例で破傷風が発症しなかったので比較はできない。代わりに、投与後90日目までの血中の中和抗体価を測定し、モノクローナル抗体の方が長期間有効濃度を維持できることを示している。
結果は以上で、わざわざモノクローナル抗体を開発する必要が無いと製薬会社は取り組んでいないのだと思うが、1890年のベーリング・北里論文から135年。感慨が深い。
2番目のフランス リヨンにあるガン研究会からの論文は、2008年から2017年に生まれた人たちが将来胃ガンになる確率を予測した論文で、7月7日 Nature Medicine にオンライン掲載された。
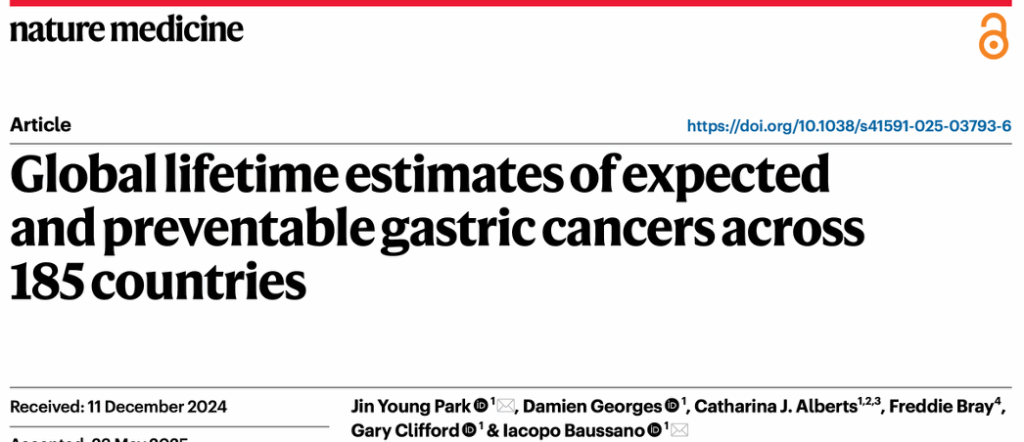
詳細は知らないが、各国での胃ガン発生率を元に、ATLASというモデルを使って将来の胃ガン発生率を計算している。
世界全体で1600万人の胃ガン患者が発生し、そのうち76%はピロリ菌によると予想できることから、ピロリ菌のスクリーニングと駆除が重要という結論だ。各国の統計の中で、我が国は患者さんが減少している先進国の一つだが、ヨーロッパと比べると数は多い。一方、アフリカでは発症率の増加が続き6倍以上になると予想している。要するに予測統計が示されているだけの論文で、図や表を眺めるための論文だが、論文の主張は胃ガンは子宮頸がんと同じで予防可能なガンなので、我々日本も含めてピロリ菌対策を徹底する事が最も安上がりな公衆衛生策ということになる。
3番目のワシントン大学からの論文は、身体に良くない3大フード、加工肉、甘い飲料、そしてトランス脂肪酸の健康リスクを計算した研究で、7月1日 Nature Medicine に掲載された。
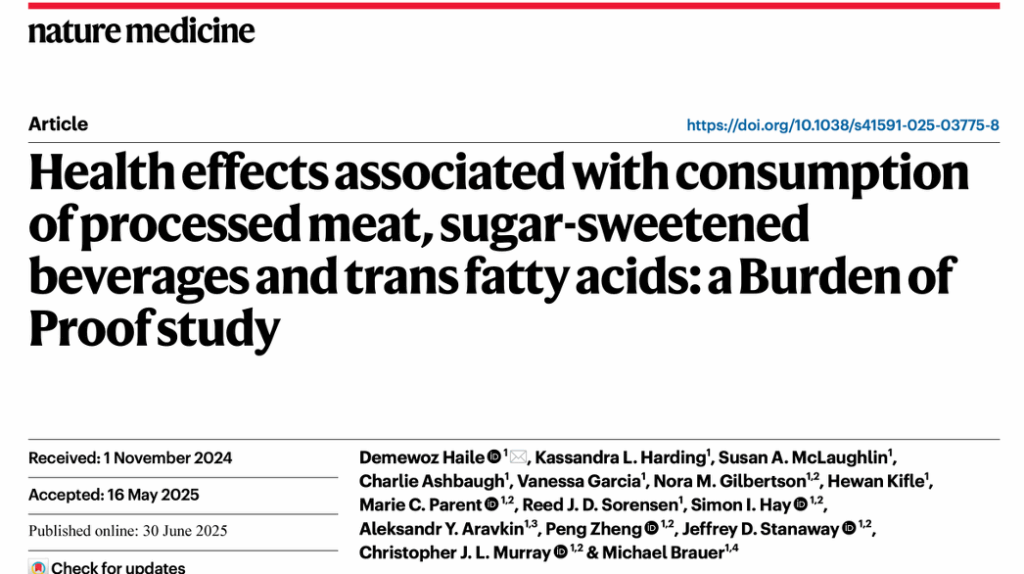
この研究家過去の論文についてのメタアナリシスで、Burden Proof Meta-regression メタ回帰を用いてリスク算定を行っている。結果はこれまで言われているとおりで、加工肉の場合、糖尿病が11%、直腸大腸ガンが7%増加する。砂糖を添加した甘い飲料の場合は8%糖尿病リスクが高まり、虚血性心疾患リスクが2%上昇する。最後にトランス脂肪酸の場合は3%心疾患リスクが高まるという結果だ。2型糖尿病で見ると、加工肉が最も問題のように見えるが、これら3大フードの取り過ぎには警鐘を鳴らし続ける必要がある。
4番目のオレゴン大学からの論文はお風呂、伝統的サウナ、遠赤外サウナの身体への急性効果を調べた研究で、5月7日 American Journal of PhysiologyのRegulatory, Integrative and Comparative Physiology セクションにオンライン掲載された。
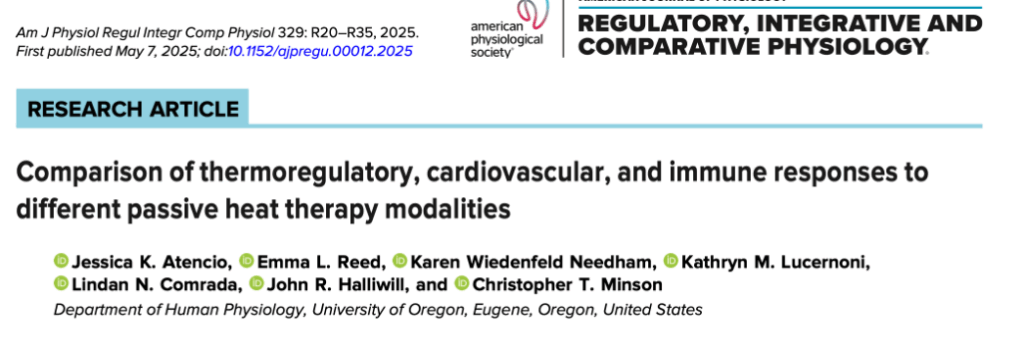
研究では20人の男女に、1週間づつのインターバルで、40.5度のお風呂45分、伝統的サウナ10分3回、そして低温赤外サウナ45分を経験してもらい、入浴中も含めて心拍出量、血圧、体温、満足感などを測定するとともに、入浴1時間後の血液検査で炎症指標を調べている。
結果だが、体温上昇、心拍出量、発汗などでは入浴が最も効果がある。しかしIL-6など炎症性のサイトカインも入浴で上昇する。即ち、40.5度でも、入浴が身体に対するストレスとしては最も強いという結論になる。私も十和田温泉で一度ひっくり返って病院のお世話になったが、温泉好きの日本人には気になる研究だ。



