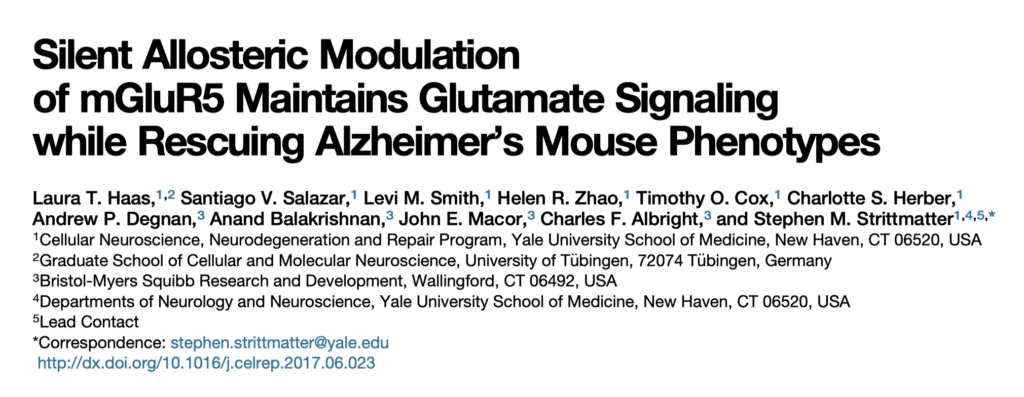2022年6月20日
再生医療のハイウェイプロジェクトを引き受けたとき、選ばれた臨床の先生に、Nature やScienceなどに論文を出版するより、臨床的成果を上げたかどうかを評価したいとお願いしたのは、ほぼ15年前のことだが、最近、NatureやScienceも、臨床研究を採択するようになっている。ただ、臨床や前臨床研究の場合、他の分野の研究と比べると、採択基準は甘いなという印象を受ける。すなわち、あくまでも臨床応用ですぐに期待できるかどうかに基準が置かれ、詳しいメカニズムの解析が採択基準から外されると言うことだ。そんな例の典型を読んだのでこの点も考えながら紹介したい。
テキサス大学からの論文は、メラノーマをBRAF/MEKを標的にして治療を行う時、アンドロゲン受容体が誘導され、しかも標的治療の効果を落としてしまうと言う研究で、6月15日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Androgen receptor blockade promotes response to BRAF/MEK-targeted therapy (アンドロゲン受容体の阻害により、BRAF/MEK標的治療の反応が高まる)」だ。
タイトルだけ見ても、メッセージはすぐわかるし、多くの臨床雑誌で目にするタイトルと同じだ。事実、アンドロゲン受容体阻害剤をBRAF/MEK阻害剤と組みあわせればメラノーマ治療効果が高まるという結果が、この研究の主要メッセージと言っていい。
逆に言えば、何故こんなことが臨床現場でわかっていなかったのかが不思議になる。この研究ではまず、様々なステージのメラノーマに対して行われたBRAF/MEK阻害治療の効果を男女で比較して、ほぼ全ての場合、男性の方が女性より治療効果が低いことを明らかにする。
本当にこれまでこのような結果が示されなかったのか驚く結果だが、後の実験方向は見えている。
まずこの結果は男女でアンドロゲンの血中濃度が異なるという話ではなく、治療を始めるとガンのアンドロゲン受容体の発現が上がってくる結果であること確認している。そして動物実験から、このように誘導されたアンドロゲン受容体が、男性ホルモンの多い男性で刺激が続くため、BRAF/MEK阻害剤の効果が低下することを示している。
そして最後に、より臨床的な状態に似せるため、標的治療を始めると同時に、テストステロンを注射する実験、アンドロゲン受容体阻害剤enzalutamideを注射する実験、また両方を阻害する実験などを行い、確かに治療開始によりアンドロゲン受容体が上昇して、これがテストステロンで刺激されると、BRAF/MEK経路の阻害効果が低下すること、またenzalutamideでのアンドロゲン受容体阻害効果は、完全にテストステロンレベルを抑えた、すなわち去勢状態が必要であることを示している。
結果は以上で、ガン研究としては拍子抜けする。すなわち、何故RAF/MEK阻害でアンドロゲン受容体が上昇するのか、また何故アンドロゲン受容体刺激で、RAF/MEK阻害が抑えられるのか、メカニズムについては全く何も示されていない。しかし、臨床の立場では、こんな簡単なことで治療効果が高まるなら、明日からでも治験に取り組んで欲しいと思える結果だ。特に、BRAF/MEKに限るのか、他のMEK経路にも共通なのかも大事だと思う。
ただ、やはりNatureはもう少しメカニズムを追求した論文だけ掲載して欲しいと個人的には願っている。
2022年6月19日
今日紹介するハーバード大学、Dian Mathisラボからの論文は、免疫学長年の謎を解明したとても重要な論文なので、次々回のジャーナルクラブの題材にすることを約束して、ここでは概要だけを紹介する。幸い共同著者に挙げられている和歌山大学、改正さんを個人的にも知っているので、彼にも参加してもらってこの研究の重要性を伝えたいと思う。タイトルは「Thymic epithelial cells co-opt lineage-defining transcription factors to eliminate autoreactive T cells(胸腺上皮は体細胞の分化を決める転写因子を動員して自己反応性T細胞を除去する)」で、6月16日 Cell にオンライン掲載された。
私たちの免疫細胞は、自己の細胞や分子には反応しない免疫寛容が成立している。T細胞については胸腺内でT細胞が分化する時、自己抗原反応性のT細胞が除去されるからで、この概念は私の学生時代から既にMedawarらの研究により明らかにされていた。しかし、私たちの体細胞は極めて多様で、それぞれに対応する自己抗原をどうして胸腺で用意できるのかについては、古くからの謎だった。
ただ、Aireと呼ばれる、コファクターのような役割を持つ分子が、胸腺内で自己抗原を用意するのに重要な働きをすることがわかっていた。そして、Aireがランダムに末梢組織の分子の転写を誘導することで、胸腺上皮細胞が自己抗原を展覧会のように提示できるのではと考えられてきた。
この問題解決のため、Mathisらは胸腺上皮を分離し、single cellレベルでAtac-seqを用いてクロマチン状態を調べた。そして、オープンなクロマチン部分の特徴を調べると、Aireが存在することで、特にヒストンコードの差が生まれるのではなく、Aire結合サイトが特異的にオープンになっていることを明らかにした。一種パイオニア因子に似ている。いずれにせよこの結果は、Aireがクロマチンをオープンにして転写マシナリーを動かすというこれまでの考えと一致する。
ただ、2次元展開した胸腺上皮の各クラスターで発現している分子を詳しく見ると、ランダムに転写のスイッチが入っているのではなく、それぞれのクラスターが、末梢組織の分化に必要な別々の分子セットを発現していることに気付く。例えば、Aire欠損マウスで発生が見られないクラスターは、FoxAとその下流分子を発現する内胚葉系の臓器に遺伝子発現が似ていることを突き止める。ジャーナルクラブでは詳しくデータを見ていこうと思っているが、胸腺上皮のクラスターを、腸上皮、皮膚、神経、筋肉型と分けられるのを見ると、興奮する。
さらに、胸腺上皮分化に平行するAireの発現に伴って、胸腺上皮内で末梢組織プログラムが、未熟から成熟へと分化することまで、M細胞の分化を例に示している。すなわち、胸腺上皮は自分の分化の過程で、Aireによってスイッチが入った末梢組織の分化を実際に再現して見せて、この時に発現する抗原を、自己反応性T、細胞の除去に使うというわけだ。山中さんの4因子も真っ青の能力を、胸腺上皮とAireが実現していることになる。さらに、さすがこの分野を見続けていたMathisだけあって、1800年代の組織学では、胸腺上皮が様々な形態を示すこと、すなわち末梢組織のプログラムが発現している可能性が既に示唆されていていたことまで言及している。
最後に、末梢組織特異的に蛍光分子が発現するようにした遺伝子改変マウスで、同じ分子が胸腺上皮で発現して、免疫寛容が成立することも示している。この時、T細胞除去だけでなく、Tregの誘導も同じように起こる可能性も示している。
概要は以上で、要するに胸腺内に様々な組織の動物園が形成され、T細胞を教育しているというのだから驚く。さらに、これまで不思議だった多くの問題の解決の糸口が見つかるように思える。例えば坂口さんの胸腺除去実験で、何故内分泌組織の自己免疫が起こりやすいかなどだ。
まだまだ説明したい点が満載の論文だが、詳細はジャーナルクラブで説明するので、それまでしばしお待ちを。
2022年6月18日
久しぶりにCovid-19論文を取り上げる。スタンフォード大学とイェール大学からの論文で、最近問題になっているcovid-19感染後の厄介なbrain fogと呼ばれる現象について、マウスモデルで研究している。タイトルは「Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation(軽度の呼吸器Covid感染は様々な神経系細胞とミエリンの調節不全を起こす)で、6月7日Cellにオンライン掲載されている。
我が国でも感染が収まりつつあり、世界中でも「ワクチンも行き渡り感染しても軽い」と考えられるようになったので、現在ではlong covidや、軽度感染の後に思いがけなく続く様々な神経症状を取り上げて、注意が喚起されている。この意味では、なかなかタイムリーな研究だ。
研究では肺にβ株のcovid-19を感染させ、その後の脳の変化を見ている。この時、軽い肺炎だけが起こって、全身にウイルスが回らないよう、単純にACE2トランスジェニックマウスを使わないで、感染に必要なACE2をコードしたアデノウイルスをコロナウイルスと同時に投与するというトリックを用いて、軽症のcovid-19感染を再現している。
そして、感染は軽症で肺だけに限局されていても、脳では様々なサイトカインが、感染直後だけでなく、7週間後も高いレベルを維持している。特にとりわけこれまであまり注目されていないCCL11は、1週間目より7週間目の方がさらに高いレベルを示している。この結果、脳のミクログリアが活性化され、老化による白質障害で見られるミクログリアによく似た性状を示すようリプログラムされることを示している。
これと呼応して、白質維持に関わるオリゴデンドロサイトの喪失がやはり7週間持続し、さらに海馬の神経真性が抑えられる。以上の結果から、covid-19の場合、軽症でも持続するCCL11が、中心的役割を持つ炎症が脳で持続し、これがbrain fogの原因になると結論されている。
次の問題は、この炎症の分子的主役がCCL11なのか?、なぜcovid-19だけでこれが問題になるのか?、そして、このモデルは人間の症状を説明できるか?だ。
まず、CCL11をマウスに投与する実験を行い、驚くことに海馬白質特異的にミクログリアの活性化を誘導し、海馬の神経再生を抑制することを示している。ただ、これが持続的自立的炎症を誘導するのに十分かについては検討されていない。
次にインフルエンザ感染と比較して、同じようにCCL11を中心にした炎症が続くが、7週目でも上昇しているサイトカインの数や、ミクログリア活性化の程度などで、炎症の程度が低いことを示している。
ただ、なぜcovid-19のみこのような現象が起こるのかについては、答えは出ていないと思う。今後、他のコロナ株も含め、同じ実験系で調べることは重要だろう。特に、肺だけに炎症を限局させて脳を調べる実験の意味することは、ウイルスとは関係なく、脳で自律的な炎症の引き金が引かれることなので、より踏み込んだ実験が必要だと思う。
最後に、人間でもbrain fogを訴えた患者さんの脳ではCCL11が上昇していることを示している。
以上、まだ現象論的研究に終始しているが、局所の炎症が、サイトカインを介して細胞をリプログラムし、自立的持続的炎症を誘導するメカニズムを解明してほしいと思う。
2022年6月17日
ジャレットダイアモンドのベストセラー「銃、病原菌、鉄(Guns, Germs, and Steel)」で取り上げられたように、世界史を形作ってきた最も大きな要因は、戦争と疫病だった。中でも中世の1346年から始まったペスト大流行は、10年でヨーロッパの人口が半減するほどの猛威を振るった。当然多くの記録が残され、それを手がかりに、この大流行がどのように始まったのか、研究が続けられている。
既に論文ウォッチでも2回紹介しているように、最近では疫病の起源と歴史を調べる手段として、ゲノム研究が加わり、大きな成果を挙げている。この結果、人類は5000年前よりペストと付き合っており(https://aasj.jp/news/watch/4277 )、また中世大流行のペスト菌だけでなく、他の系統も地域的流行に関わってきたことなどが示されている(https://aasj.jp/news/watch/4768 )。
今日紹介するライプニッツ マックスプランク人類進化研究所、チュービンゲン大学、そして英国スターリング大学からの論文は、中世のペスト大流行に関わるペスト菌の起源を、キルギスタンのKara-Djigach墓地に埋葬された遺骨から特定した研究で6月15日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「The source of the Black Death in fourteenth-century central Eurasia(14世紀ヨーロッパの黒死病は中央ユーラシア起源)」だ。
この研究では、中央ユーラシアで1338年に墓碑の数が急増しており、疫病についての記述が残されている墓地から、1338年に疫病で亡くなったと思われる人骨を掘り出し、ゲノムを調べている。まず、7体について民族的由来を確認した後、同じゲノムに混在しているペスト菌を再構成している。実際には3体の骨から、最終的には同じペスト菌ゲノムが再構成され、これまで知られている古代から現代まで、様々なペスト菌ゲノムと比較している。
この地区でエンデミックが起こった時期を1338年と特定できることから、これがヨーロッパパンデミックからほぼ8年前なので、その起源に近いため大きな期待が持てる。結果は期待通りで、ヨーロッパパンデミックに関わった系統、Branch1が、他のBranch 2、3、4から分岐する起点に存在することがわかった。
この分岐が起こった時期をゲノムから計算すると、大体ヨーロッパ流行の直前、1317年以降であると計算している。以上の結果から、天山地域を含む中央ユーラシアで発生したペスト菌が、この地域での短いエンデミックを起こした後、ヨーロッパに伝播したと考えられるが、これが戦争によるのか、交易によるのかについては今後の研究が必要になる。
いずれにせよ、それ以前、天山地域では、6世紀以降ヨーロッパ系統以外のいくつかの系統ペスト流行が確認されており、この地域でペスト菌のreservoirが形成され、ここから起源後のほとんどのペスト菌が供給されたと考えられる。とすると、reservoirを特定することが、パンデミック予測の鍵になるので、この分野への研究が進むと思う。細菌学もどうやら地震予知学に似てきた。
2022年6月16日
昨年話題になった幻覚剤によるうつ病治療のように、この10年うつ病に対する様々な新しい治療が開発され、成果を上げている。中でも麻酔に使うケタミンを1回投与することで、長い期間うつ病症状が改善するという発見は一般にも広く知られるようになった、重要な発見だ。しかし、そのメカニズムについては、まだまだよくわかっていないことが多い。論文ウォッチでも、すでに3回もケタミンの作用機序を調べた論文を紹介した。それぞれ、ケタミンが作用する下辺縁皮質とスパイン(https://aasj.jp/news/watch/3687 )、ケタミンによる外側手綱核領域の興奮抑制(https://aasj.jp/news/watch/8066 )、さらにはケタミン作用でのmTORの役割(https://aasj.jp/news/watch/14546 )、など様々だが、全体を見渡すと、結局混乱はあっても解決はないという段階に見える。
今日紹介するイスラエル・ワイズマン研究所からの論文は、臨床的な治験のバックアップもあるようで、その意味では解決の方に道を開いてくれたかなと思える研究で、6月20日号Cellに掲載される。タイトルは「Ketamine exerts its sustained antidepressant effects via cell-type-specific regulation of Kcnq2(ケタミンの抗うつ作用はKcnq2の細胞特異的調節を介している)」だ。
ケタミンの作用機序は、神経学的な研究と、生化学・分子生物学的研究に分かれるが、この研究はまず後者のアプローチで、ケタミンにより特異的に遺伝子発現が変化する細胞と遺伝子を特定しようとしている。
実際、ケタミンの効果は遅れて現れるので、決して神経回路を単純に刺激した結果では無く、刺激によって起こる細胞のプログラムの変化に基づいていると考えられる。その意味で、この研究が用いたsingle cell RNAseqは最適の方法と言える。
研究ではケタミン注射後2日目の海馬背側部を取り出し、single cell RNAseqで解析している。そして、ケタミンが作用するグルタミン神経で発現が変化する遺伝子165種類の中から、電位依存性カリウムチャンネルKcnq2に着目する。Kcnq2は神経の興奮性を調節するチャンネルなので、真っ先に注目するのはうなずける。
脳のスライス培養で調べると、ケタミンによる刺激はKcnqチャンネル電流を上昇させる。また、ストレスでうつを誘導すると、Kcnq2の海馬での発現が低下する。そこで、kcnqがうつ症状やケタミンによる治療効果に関与しているのか、海馬でのkcnq2遺伝子ノックダウンを行い調べると、Kcnq2がノックダウンされると、ケタミンの効果は消えてしまう。すなわち、ケタミンの効果の少なくとも一部はKcnq2分子の発現を介していることが明らかになった。
そこで、ケタミン刺激と、Kcnq2チャンネルとの関係を様々なシグナル阻害剤を用いた方法で探索すると、ケタミンによりカルモジュリン/AKAP5/カルシニューリン/NEFAT経路が活性化され、Kcnq2転写が上昇することを突き止める。
もともとうつ症状は、カルシウム代謝の関わりが示されており、またカルモジュリンを標的にした治療薬も開発されており、これによりケタミンが初めてこれまでのうつ病理解と接点を持ってきたとも言える。
とすると、ケタミン刺激の代わりにKcnq2を活性化しても、うつ症状に変化が見られるはずだ。実際、Kcnq2阻害剤はうつ症状を高め、逆に活性化剤はうつ症状を抑えることが示された。
さらに、両者のシグナルは相互作用するため、ケタミンとKcnq2アゴニストを同時に投与することで、さらに長期間強い抗うつ作用が見られることも示している。
以上が結果だが、このKcnq2アゴニスト、retigabineは既に人間のうつ病への効果が示され治験中の薬剤であるらしく、Kcnq2の即効性の効果と、ケタミンの遅効性の効果を組み合わせた新しい方法の開発へ道が開かれたように思える。
2022年6月15日
今日は論文の内容より、この内容を伝える著者の立ち位置に抱いた違和感について述べてみたい。
コペンハーゲン大学が Human Genetics and Genomics Advances にオンライン発表した論文で、グリーンランドの住人のなんと30%がLDL受容体のアミノ酸変異を伴う変異を有しているという話だ。タイトルは「An LDLR missense variant poses high risk of familial hypercholesterolemia in 30% of Greenlanders and offers potential of early cardiovascular disease intervention(グリーンランド人の30%に家族性の高コレステロール血症につながるLDL受容体(LDLR)のミスセンス変異が存在し、早期の治療で循環器疾患を予防できる可能性がある)だ。
LDL受容体は、脂肪やコレステロールが詰まったリポタンパク質を細胞内に取り込み、代謝するための必須の分子で、血中コレステロールと代謝を決める重要な因子の一つで、家族性高コレステロール血症につながる様々な変異がこれまで特定されてきた。
この研究はその変異の一つで、137番目のグルタミン酸がセリンに置き換わった変異で、LDLRのLDLへの結合活性が60%に低下することが知られている。
この研究ではまず、原住民イヌイットとヨーロッパ人のゲノムが混じり合ったグリーンランド人約2000人を対象に、この変異の頻度を調べ、なんと29.5%のグリーンランド人がこのアレルを有していることを突き止めている。
この結果を見たとき、おそらくほとんどの生物学者はなぜ30%もの人に、機能低下につながるアレルが維持されているのか不思議に思うはずだ。タイトルにわざわざ30%とまで書いてあるので、その議論があるに違いないと思うはずだ。
しかし、期待は見事に裏切られ、論文ではこの変異によりLDL、特に粒子径の小さいLDLが上昇していること、リポタンパク質粒子を形成するApoAも上昇していることを示し、おそらく血中でリポタンパク質粒子のクリアランスが低下する結果、相対的にLDL、ApoAが上昇していることを示している。
そして、動脈硬化による虚血性心疾患の頻度が1.5倍にまで高まっているにもかかわらず、多くの人が未治療で、今後遺伝子診断+早期治療で病気発症を防げると結論している。
医師の目線としては特に問題ない書きようで、多くのゲノム研究論文と同じだろう。とはいえこれで終わっていいのかには異論がある。実際、なぜ極地で暮らしてきたイヌイットがこの変異を維持し続け、ヨーロッパ人と混血が始まった後も、3割の人がこの変異を有しているほうが、生物学者にとってはずっと面白い。
血中のLDL上昇が問題になるのは、最終的にそれが細胞に取り込まれるからで、逆に取り込みにくいということは、LDLRの機能が低下することで体を守っている可能性は高い。動脈硬化の主役マクロファージではLDLRだけでなく、酸化されたLSLを取り込む多くの受容体が働くため、この変異の副作用として動脈硬化はしかたがない。しかし、これを補っても余りあるベネフィットがどこかにあるのではと考えてしまう。
例えば脂の多い食事のため、細胞への取り込みが抑えられたほうが、コレステロールの毒性から守られるのか、あるいはもっと他のベネフィットがあるのか。
実際この論文のタイトルを見たとき、以前紹介したシロクマの進化論文を思い出した(https://aasj.jp/news/watch/1531 )。この研究では、ヒグマとシロクマのゲノムを比較し、ApoBやLDLなど動脈硬化で問題になる遺伝子が多くリストされることが明らかになった。すなわち、動脈硬化メカニズムを積極的に利用して、血液を寒さから守っている可能性すらある。
イヌイットから何が飛び出すか、興味は尽きない。
2022年6月14日
β アミロイドを除去する治療法の失敗を見て、アミロイド仮説は消え去ったと勘違いする人もいるようだが、遺伝変異やダウン症の研究から、多くのアルツハイマー病でも Aβ の蓄積がアルツハイマー病の引き金を引くことは間違いない。
ただこれはかなり病気の初期の話で、一旦引き金がひかれると神経細胞内でのTauの蓄積は自立的に進むので、Aβ を除去しても手遅れになる。従って、Aβ 仮説に基づく治療を進めるためには、引き金が引かれる初期段階を捉えて治療する必要がある。
この初期段階を捉える手掛かりとして注目されるのが、Aβ 蓄積が始まると神経の興奮が上昇すること、そして神経細胞自体は正常でもシナプスの密度が低下する可能性が、動物実験から示唆されている点だ。
今日紹介するイェール大学からの論文は、このグループが発見したメタボトロピックグルタミン酸受容体に対する化合物が、動物モデルのアルツハイマー病進行を止めるという発見の、細胞学的メカニズムを明らかにした論文で、シナプス密度の現象を食い止め、アルツハイマー病(AD)の引き金を止める可能性があると期待できる。タイトルは「Reversal of synapse loss in Alzheimer mouse models by targeting mGluR5 to prevent synaptic tagging by C1Q(アルツハイマー病マウスモデルでmGluR5を標的にすることで、シナプスに C1q が結合を止めることでシナプス喪失を抑制できる)」で、6月1日 Science Translational Medicine に掲載された。
2017年、このグループは mGluR5 に結合するが、アゴニストやアンタゴニストに見られる神経症状を全く起こさない silent modulator、BMS-984923 をブリストルマイヤー社のライブラリーから特定し、これがアルツハイマー病初期に起こるシナプス喪失を止める作用があることを Cell Reports に報告した(下図)
この研究はこの続きで、この化合物の作用機序を探っている。ネズミや猿を用いて、この化合物が経口摂取可能で、神経症状を誘導しない有望な化合物であることを示している(実際に臨床治験が始まっているので当然の結果だ)。
その上で、この薬剤の効果を調べるには脳のシナプス密度を調べることができる小胞体グリコプロテイン(SV2A)を標的と標的にしたトレーサーを用いた PET をバイオマーカーとして用いられること、すなわち AD モデルマウスにこの薬物を1ヶ月服用させると、シナプス密度を回復させられることを明らかにしている。
あとは、薬剤投与による遺伝子発現変化を single cell RNA seq で調べ、AD 進行に関わるとして知られる遺伝子を含む多くの遺伝子の発現を、特に神経細胞で正常化できること、さらにはシナプスを元に戻すことで、Tau のリン酸化を防げることも明らかにしている。
そして最後に、この薬剤がおそらく Aβ と mGluR5 との結合が、シナプスに保体成分 C1q が結合して穴が開き、局所的にシナプスが失われるプロセスを防ぐことを明らかにしている。
以上が結果で、mGluR5 modulator 化合物が AD 進行を抑えるという現象論が、しっかりとメカニズム研究で裏付けられた感じだ。
基本的には Aβ 除去療法と同じ時期を狙っているのだが、Aβ と細胞との相互作用を標的にしている点で、より効果は高いように感じる。しかも経口投与可能ということで、大きなヒットになるチャンスはある。
ただ、治療可能性だけでなく、AD の初期過程を詳しく調べる大きなツールができたことも重要だと思う。
2022年6月13日
大人になってから腸内細菌叢を大きく変化させることは簡単でないが、乳幼児期はもともと細菌叢が発達する時期なので、様々な介入が可能だと考えられ、研究が進められている。この介入可能性は、細菌叢の個人差として現れる。すなわち、細菌叢の個人差が大きいということは、それぞれの子供の置かれた生活環境で大きな変化が生まれることを示唆し、裏返せばそれだけ介入により変化しうることを示している。
その意味で、生活スタイルと子供の腸内細菌叢の発達を調べることはこの分野の重要課題だが、これに正攻法でチャレンジしたのが、今日紹介するスタンフォード大学からの論文で、6月10日号 Science に掲載された。タイトルは「Robust variation in infant gut microbiome assembly across a spectrum of lifestyles(様々な生活様式を超えてみられる子供の腸内細菌層の大きな多様性)」だ。
この研究ではデータベースに集まった1900人の細菌叢16Sメタアナリシスを解析して、個人間の多様性をそれぞれの国や部族ごとに調べると、工業化された米国やスウェーデンではその多様性が極めて大きい一方、アフリカの狩猟採取民では多様性が乏しいことをまず確認している。
面白いのはこの多様性が生まれる時期を調べると、工業化が進んだ国では10ヶ月前後で強く多様化する一方、Haza族のようなアフリカ狩猟採取民では、個人差がようやく30ヶ月かかって現れることを示している。
個人差は少ないが、細菌叢構成成分の多様性は Haza族の子供は高く、面白いのは、Haza族の子供から分離された細菌の実に24%が新しい種類であることを確認している。幼児期の細菌叢の病気や免疫に対する重要性を考えると、Haza族に存在する新しい細菌種の機能を調べる意義は大きい。
また、これまで工業化とともに喪失している細菌叢や、逆に獲得された細菌叢についても調べ、まず喪失している細菌は、動物の細菌叢と共通の細菌が多く含まれており、工業化諸国の子供の細菌叢には全く存在しないこと、また工業化とともに獲得された細菌叢は、大人だけに見られる細菌叢であることを示している。
いずれにせよ、長期間かけて生活スタイルごとの細菌叢が形作られていることがはっきりした。この点をさらに詳しく調べるため、今度は細菌叢の全ゲノム配列を決定し、細菌系統内の違いも詳しくわかるよう調べると、例えば母乳により育てられることと密接に関わるビフィズス菌も、生活スタイルにより維持される系統が全く異なっていることを明らかにしている。
そして、幼児発達初期に生活スタイルの差が現れるほとんどの細菌は、母親から幼児へと伝達されやすい細菌であること示し、各生活スタイルの核になる細菌叢が、母親から子供に伝達され続けていることを示している。とはいえ、Haza族では、母親が異なっても同じ環境で居住している場合、多くの細菌叢を共有しているのに、スウェーデンでは異なる家族間の共通性は低下しており、これが個人の多様性を生んでいることがわかる。
実際にはそれぞれの細菌について、詳しく解析しているのだが全て割愛した。要するに、母から子へ、核となる細菌種が伝達されること、そして幼児期の環境の多様性、離乳後の食べ物の多様性などで、細菌叢が形成されることを示している。結論はすでに指摘されてきた話で、特に新しいことはないが、ze全ゲノム解析を含めた大規模な解析で、おそらくこの細菌種の解析結果が宝の山だとおもう。特に野生と関わる細菌種を今後工業化した社会に導入できないかという意図が見える仕事だ。
2022年6月12日
コロナ 禍のおかげで公共の場で体温を測るのが当たり前になった。幸いどこで測っても、この2年間発熱したことがないが、何もなければ私たちの体温は狭い範囲で維持できていることを実感する。
体温維持のメカニズムは解明が進んでおり、体温の上下を感じた視床下部の神経回路が、皮膚や筋肉、脂肪組織に指令を出し、汗、筋肉収縮、褐色脂肪組織刺激などを通じて、体温を調節している。これにより、外気温の変化に耐え、運動による熱の発散が行われ、体温を一定に保てている。
これに対し、なぜ感染症などの炎症で病的な発熱が起こるのかについてはよくわかっていないことが多かった。バクテリアやウイルスが増殖してそれが熱の発生源になることはほとんど考えられないので、炎症の誘導物質と、発熱調節神経回路の関係を解明する必要があった。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、昨日のGLP-1による食欲抑制の研究と同じで、炎症感知から発熱までの神経回路を丹念に特定した研究で、6月8日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「A preoptic neuronal population controls fever and appetite during sickness(病気の際の発熱と食欲減退を調節する視索前野神経)」だ。
この研究でも、immediate early gene発現を元に興奮神経の特定、神経間結合の特定、光遺伝学的神経刺激、特定の細胞の除去、などの遺伝子改変マウスが駆使されているが、これらを利用する出発点は、炎症刺激を最初に感知して興奮する神経の道程になる。これまでの研究で、この機能を持つ神経が視索前野に存在することがわかっていたので、LPSや人工核酸のような発熱物質を投与したとき、視索前野で興奮する神経を、single cell RNAseqを用いて特定し、これがこれまで内部温度を感受する神経とは異なることを明らかにした。
そして、この神経が炎症の重要なメディエーター、CCL2ケモカイン、プロスタグランディン2(PGE)受容体、そしてIL-1β受容体を発現しており、それぞれの因子に反応して興奮することを突き止める。すなわち、炎症のメディエーターと神経回路がつながった。
あとは、この炎症反応性の細胞を起点に発熱や食欲調節回路を一歩づつ特定する実験が行われ、
炎症反応性の視索前野細胞の興奮が異常な発熱を誘導するのに必要かつ十分。 炎症反応細胞は脳の12領域に投射しており、炎症時の起こる様々な行動変化に関わる。 発熱については、内側視床下部で熱を感知して体温発生を抑制する神経を抑制し、また褐色脂肪を刺激して発熱させる神経を活性化して、異常発熱を促すことを明らかにしている。 これと同時に、食欲低下誘導についても、食欲関連ペプチドAgRP神経回路を抑制、一方メラノコルチン発現神経回路を刺激して食欲を抑制することを示している。 以上が結果で、ハイライトは視索前野の炎症メディエーターと発熱や食欲に関わる神経回路を繋いでいる神経を明らかにしたことだろう。この神経を抑制すると、実際感染でも熱は出なくなる。
今後、異常発熱がコントロールできないときの薬剤の開発につながる可能性もあるが、発熱自体は私たちにとって病気と戦うための重要な手段なので、医療としてはこのバランスをうまく取ることが必要になる。
このような論文を読むと、また一つ勉強できた気になる。感謝
2022年6月11日
昨日に続いて消化管ホルモン GLP-1 についての研究を紹介する。
糖尿病治療での経験と、昨年発表され、また昨日紹介した論文でも確認されたセマグルタイドによる肥満治療の治験研究を元に、投与しやすいリベルサスを用いた肥満治療が、自由診療で行われていることについて言及した。昨日の論文を読むと、GLP-1 作動性細胞刺激を肥満治療に用いても何の問題もないように思えるのだが、一つだけ懸念がある。
それは、治療では GLP-1 が全身に投与される点だ。GLP-1 は消化管ホルモンとして、小腸と胃とのコミュニケーションに関わるインクレチンとしてまず特定された。また、その半減期は時間単位なので、GLP-1 受容体を発現する脳神経細胞に直接作用しているとは考えられない。従って、もし脳細胞が投与された GLP-1 の直接の標的なら、非生理学的な状態を作っていることになり、長期的に見たとき予想もしなかった副作用につながる可能性はある。
今日紹介するマウントサイナイ Icahn 医科大学からの論文は、消化管で分泌される GLP-1 が脳に働く回路を詳しく調べた、大変面白いプロの研究で6月2日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「An inter-organ neural circuit for appetite suppression(臓器間の神経回路が食欲を抑制する)」だ。
結論的に言うと、消化管から分泌される GLP-1 で十分食欲を抑制する効果があることを、GLP-1 分泌細胞からスタートして、神経回路をつないで明らかにした。実験の詳細を読んでいて、爆発による障害で胃壁が皮膚につながった青年を対象に、空いた穴から消化の様子を観察したウイリアム・ボーモントを思い出した。
この研究では消化管の局所神経を操作するためのあらゆる方法が用いられている。まず、GLP-1 に反応して胃が膨満し食欲が低下するのは、全て回腸のL細胞が分泌する GLP-1 の作用であることを確認している。
次に、この GLP-1 シグナルが GLP-1 受容体を発現した、intestinofugal 腸管神経に働き、この興奮が腹腔神経節へシグナルを送り、これが Nos1 を発現する胃の交感神経に働いて、動きを抑制し、胃を膨満させることを突き止める。この回路を通して胃に伝わったシグナルは、次に迷走神経ではなく、胃の痛みを伝える脊髄後根を介する感覚神経を伝って、毛様体で固有感覚として処理され、視床下部、傍視床下核に伝えられ、この神経により胃が膨満し食欲を低下させることを明らかにしている。などと簡単に書いたが、それぞれの神経を光遺伝学的に、あるいはアデノ随伴ウイルスを用いた神経接合追跡法などを用いて、一つ一つ検証し、この回路だけで胃の膨満から、食欲低下までを誘導するのに十分であることを確かめている膨大な実験だ。
おそらくこの研究のハイライトは、回腸のL細胞由来の半減期の短い GLP-1 でこの回路を刺激できること、そして迷走神経ではなく、脊髄神経を通って胃の刺激が脳に伝わり、胃を膨満させて食欲が落ちることを示し、これまで指摘されていた脳の GLP-1 受容体陽性細胞は通常ではほとんどこの反応に参加しないことを明らかにしたことだろう。
以上が結果で、まさにプロの重要な論文だと思う。もしこの研究が正しいとすると、GLP-1 受容体陽性細胞を非生理学的に刺激し続けた時、何が起こるのかよく調べて、GLP-1b作動神経活性化の長期効果や副作用をはっきりさせることが、この薬剤を肥満治療に使うための重要な条件であるように思う。