


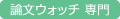 1月28日 アルツハイマー病治療の新しい標的(1月22日 Cell オンライン掲載論文)
少し遅れたが、今年最初のジャーナルクラブは2月6日午後7時から開催する。タイトル...続きを読む
1月28日 アルツハイマー病治療の新しい標的(1月22日 Cell オンライン掲載論文)
少し遅れたが、今年最初のジャーナルクラブは2月6日午後7時から開催する。タイトル...続きを読む 1月27日 梅毒トレポネーマの歴史を探る(1月22日 Science 掲載論文)
昨日に続いて今日も考古学の研究で、スイス ローザンヌ大学からの論文だ。コロンビア...続きを読む
1月27日 梅毒トレポネーマの歴史を探る(1月22日 Science 掲載論文)
昨日に続いて今日も考古学の研究で、スイス ローザンヌ大学からの論文だ。コロンビア...続きを読む 1月26日 インドネシア・スワレシで発見された手形絵の意義(1月21日 Nature オンライン掲載論文)
ホモサピエンスがイスラエル回廊を突破してユーラシアに移動したのは4万5千年前前後...続きを読む
1月26日 インドネシア・スワレシで発見された手形絵の意義(1月21日 Nature オンライン掲載論文)
ホモサピエンスがイスラエル回廊を突破してユーラシアに移動したのは4万5千年前前後...続きを読む 1月25日 血小板による炎症増強の新機構(1月22日号 Science 掲載論文)
コロナパンデミックで脚光を浴びたのが感染の重症化の問題で、サイトカインストームや...続きを読む
1月25日 血小板による炎症増強の新機構(1月22日号 Science 掲載論文)
コロナパンデミックで脚光を浴びたのが感染の重症化の問題で、サイトカインストームや...続きを読む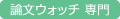 1月24日 生体内で細胞特異的にタンパク質の新陳代謝を調べる方法の確立(1月21日 Nature オンライン掲載論文)
アルツハイマー病などの神経変性疾患の最も大きなリスク因子は老化で、これら疾患に見...続きを読む
1月24日 生体内で細胞特異的にタンパク質の新陳代謝を調べる方法の確立(1月21日 Nature オンライン掲載論文)
アルツハイマー病などの神経変性疾患の最も大きなリスク因子は老化で、これら疾患に見...続きを読む 1月23日 一酸化窒素吸引だけで肺の細菌感染症を抑えることができる(1月21日 Science Translational Medicine 掲載論文)
一般の方にとって窒素酸化物は大気汚染物質のイメージが強いと思うが、その中の一酸化...続きを読む
1月23日 一酸化窒素吸引だけで肺の細菌感染症を抑えることができる(1月21日 Science Translational Medicine 掲載論文)
一般の方にとって窒素酸化物は大気汚染物質のイメージが強いと思うが、その中の一酸化...続きを読む 1月20日 脳内での強化学習過程を海馬の場所細胞から探る(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
私たちのNPOの理事の一人の呼びかけで「AI x 生命科学」と名付けた勉強会を行...続きを読む
1月20日 脳内での強化学習過程を海馬の場所細胞から探る(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
私たちのNPOの理事の一人の呼びかけで「AI x 生命科学」と名付けた勉強会を行...続きを読む 1月19日 頭蓋骨髄中の白血球に脳へ薬剤を運ばせる(1月16日 Cell オンライン掲載論文)
この10年中国の研究力は急速に高まっており、毎日論文を読んでいるとそのことを強く...続きを読む
1月19日 頭蓋骨髄中の白血球に脳へ薬剤を運ばせる(1月16日 Cell オンライン掲載論文)
この10年中国の研究力は急速に高まっており、毎日論文を読んでいるとそのことを強く...続きを読む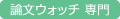 1月28日 アルツハイマー病治療の新しい標的(1月22日 Cell オンライン掲載論文)
少し遅れたが、今年最初のジャーナルクラブは2月6日午後7時から開催する。タイトル...続きを読む
1月28日 アルツハイマー病治療の新しい標的(1月22日 Cell オンライン掲載論文)
少し遅れたが、今年最初のジャーナルクラブは2月6日午後7時から開催する。タイトル...続きを読む 1月27日 梅毒トレポネーマの歴史を探る(1月22日 Science 掲載論文)
昨日に続いて今日も考古学の研究で、スイス ローザンヌ大学からの論文だ。コロンビア...続きを読む
1月27日 梅毒トレポネーマの歴史を探る(1月22日 Science 掲載論文)
昨日に続いて今日も考古学の研究で、スイス ローザンヌ大学からの論文だ。コロンビア...続きを読む 1月26日 インドネシア・スワレシで発見された手形絵の意義(1月21日 Nature オンライン掲載論文)
ホモサピエンスがイスラエル回廊を突破してユーラシアに移動したのは4万5千年前前後...続きを読む
1月26日 インドネシア・スワレシで発見された手形絵の意義(1月21日 Nature オンライン掲載論文)
ホモサピエンスがイスラエル回廊を突破してユーラシアに移動したのは4万5千年前前後...続きを読む 1月25日 血小板による炎症増強の新機構(1月22日号 Science 掲載論文)
コロナパンデミックで脚光を浴びたのが感染の重症化の問題で、サイトカインストームや...続きを読む
1月25日 血小板による炎症増強の新機構(1月22日号 Science 掲載論文)
コロナパンデミックで脚光を浴びたのが感染の重症化の問題で、サイトカインストームや...続きを読む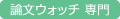 1月24日 生体内で細胞特異的にタンパク質の新陳代謝を調べる方法の確立(1月21日 Nature オンライン掲載論文)
アルツハイマー病などの神経変性疾患の最も大きなリスク因子は老化で、これら疾患に見...続きを読む
1月24日 生体内で細胞特異的にタンパク質の新陳代謝を調べる方法の確立(1月21日 Nature オンライン掲載論文)
アルツハイマー病などの神経変性疾患の最も大きなリスク因子は老化で、これら疾患に見...続きを読む 1月23日 一酸化窒素吸引だけで肺の細菌感染症を抑えることができる(1月21日 Science Translational Medicine 掲載論文)
一般の方にとって窒素酸化物は大気汚染物質のイメージが強いと思うが、その中の一酸化...続きを読む
1月23日 一酸化窒素吸引だけで肺の細菌感染症を抑えることができる(1月21日 Science Translational Medicine 掲載論文)
一般の方にとって窒素酸化物は大気汚染物質のイメージが強いと思うが、その中の一酸化...続きを読む 1月20日 脳内での強化学習過程を海馬の場所細胞から探る(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
私たちのNPOの理事の一人の呼びかけで「AI x 生命科学」と名付けた勉強会を行...続きを読む
1月20日 脳内での強化学習過程を海馬の場所細胞から探る(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
私たちのNPOの理事の一人の呼びかけで「AI x 生命科学」と名付けた勉強会を行...続きを読む 1月19日 頭蓋骨髄中の白血球に脳へ薬剤を運ばせる(1月16日 Cell オンライン掲載論文)
この10年中国の研究力は急速に高まっており、毎日論文を読んでいるとそのことを強く...続きを読む
1月19日 頭蓋骨髄中の白血球に脳へ薬剤を運ばせる(1月16日 Cell オンライン掲載論文)
この10年中国の研究力は急速に高まっており、毎日論文を読んでいるとそのことを強く...続きを読む 生命科学の目で読む哲学書 23 カントの生物観―ジェニファー・メンシュ著「Kant’s Organicism」の紹介。
1年間カントの著作を読んできたが、そろそろカントについて書く気になってきた。とい...続きを読む
生命科学の目で読む哲学書 23 カントの生物観―ジェニファー・メンシュ著「Kant’s Organicism」の紹介。
1年間カントの著作を読んできたが、そろそろカントについて書く気になってきた。とい...続きを読む 生命科学の目で読む哲学書22回:番外編 ChatGPTと実験哲学あるいは合成哲学の可能性
デヴィッド・ヒュームについて書いて以来、ずっとカントの著作と格闘している。これま...続きを読む
生命科学の目で読む哲学書22回:番外編 ChatGPTと実験哲学あるいは合成哲学の可能性
デヴィッド・ヒュームについて書いて以来、ずっとカントの著作と格闘している。これま...続きを読む 生命科学の目で読む哲学書 20回 バークリー:世界を仮想現実と言い切った反科学哲学
イギリス経験論の哲学者として、教科書的には、イングランドのジョン・ロック、アイル...続きを読む
生命科学の目で読む哲学書 20回 バークリー:世界を仮想現実と言い切った反科学哲学
イギリス経験論の哲学者として、教科書的には、イングランドのジョン・ロック、アイル...続きを読む 生命科学の目で読む哲学書 19回 ジョン・ロック:脳科学の始まりと言えるかもしれない
17世紀を代表する大陸合理主義哲学を終え、今回から、ロック、バークリー、そしてヒ...続きを読む
生命科学の目で読む哲学書 19回 ジョン・ロック:脳科学の始まりと言えるかもしれない
17世紀を代表する大陸合理主義哲学を終え、今回から、ロック、バークリー、そしてヒ...続きを読む 17世紀近代哲学誕生はガリレオに負うところが大きい( 生命科学の目で読む哲学書 18回 )
17世紀を振り返る最後に、ガリレオ・ガリレイに登場いただこう。生命科学の目で読む...続きを読む
17世紀近代哲学誕生はガリレオに負うところが大きい( 生命科学の目で読む哲学書 18回 )
17世紀を振り返る最後に、ガリレオ・ガリレイに登場いただこう。生命科学の目で読む...続きを読む なぜスピノザだけが「エチカ=倫理」を書けたか?(生命科学の目で読む哲学書第17回)
なかなか生命科学の目からスピノザを位置づけられたという気になれず、延ばし延ばしに...続きを読む
なぜスピノザだけが「エチカ=倫理」を書けたか?(生命科学の目で読む哲学書第17回)
なかなか生命科学の目からスピノザを位置づけられたという気になれず、延ばし延ばしに...続きを読む 17世紀近代科学誕生に関わった人たち: ライプニッツのモナド論を現代的視点から読み直す (生命科学の目で読む哲学書 16回)
今回は、この歳まで何回かチャレンジして、結局理解できいないまま放置していたライプ...続きを読む
17世紀近代科学誕生に関わった人たち: ライプニッツのモナド論を現代的視点から読み直す (生命科学の目で読む哲学書 16回)
今回は、この歳まで何回かチャレンジして、結局理解できいないまま放置していたライプ...続きを読む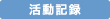 京都大学野生動物センター・熊本サンクチュアリーの寄付活動に応援メッセージを寄せました。まだ募集中なので、是非皆様もご寄付お願いします。
寄せた文章は以下のサイトでご覧になれます。 https://readyfor.j...続きを読む
京都大学野生動物センター・熊本サンクチュアリーの寄付活動に応援メッセージを寄せました。まだ募集中なので、是非皆様もご寄付お願いします。
寄せた文章は以下のサイトでご覧になれます。 https://readyfor.j...続きを読む