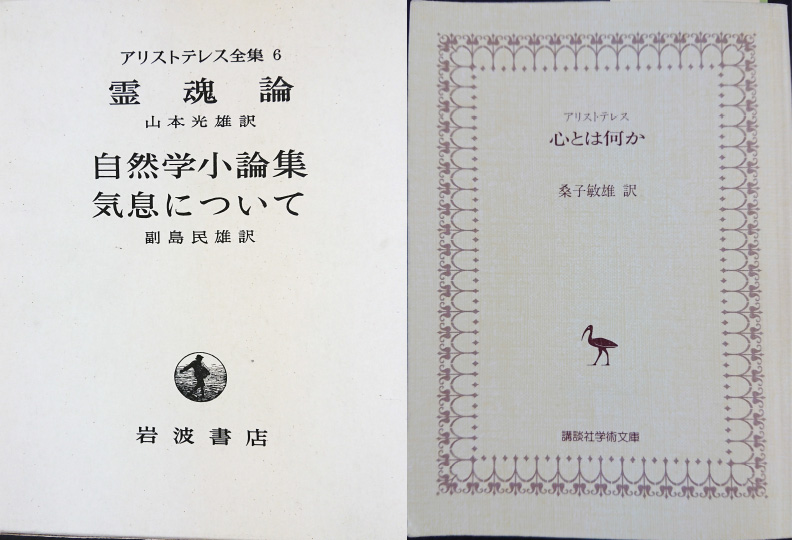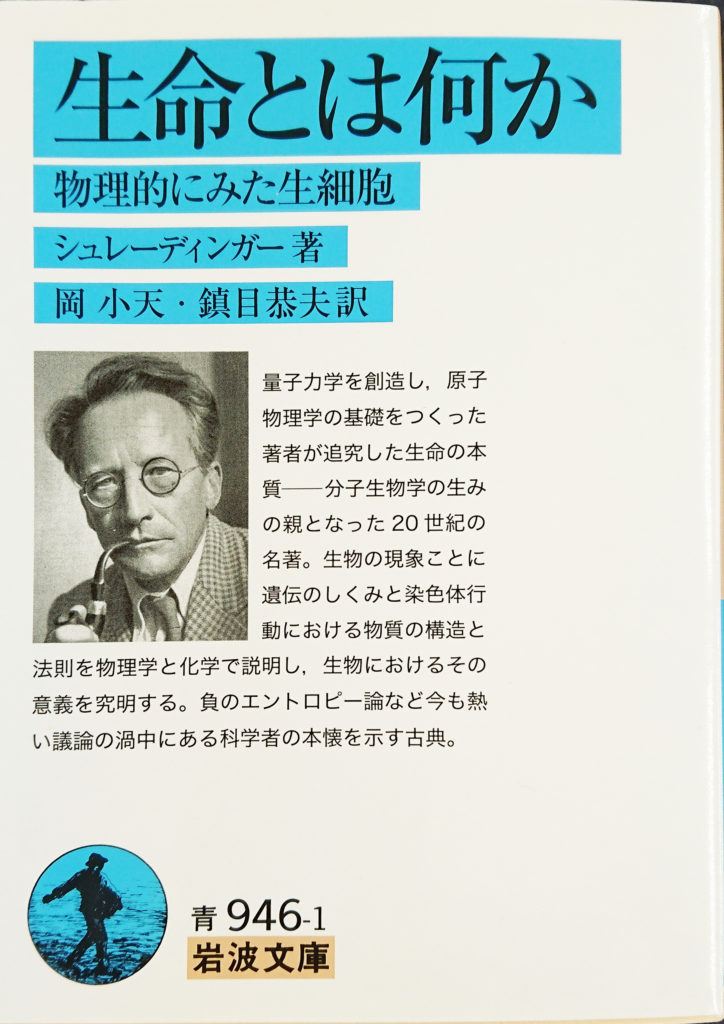2019年8月9日
細胞培養が可能になってから、ガン細胞がホストとは無関係に増殖を続け、自然に進化する過程を観察することができるようになった。例えばHeLa細胞などはほぼ60年近く細胞独自の進化を遂げていると言える。しかし驚くなかれ、同じように6000年近くも、ホストからホストを乗り移って勝手に進化している犬のガンCTVT(犬の感染性性器腫瘍)が存在する。生殖器官の細胞に発生したガンが、ホストの免疫システムを逃れるようになり、性交を通して個体から個体へ感染するようになったガンだ。同じようなガンにタスマニアデビルの顔面にできるガンがあるが、この歴史はたかだか50年程度のものだろう。
今日紹介するケンブリッジ大学を中心とする研究グループの論文は、世界各地から546種類のCTVTを集め、タンパク質に翻訳される遺伝子部分(エクソーム)の配列を調べ、CTVTの進化を調べた研究で8月2日号のScienceに掲載された。タイトルは「Somatic evolution and global expansion of an ancient transmissible
cancer lineage (古代に発生した感染性がん細胞系列の進化と世界規模の伝搬)」だ。
現存の人間のゲノム解析と同じで、現存しているガン細胞の配列からわかるのは、そのガンがいつ発生し、どのように世界中に広がったかという歴史と、進化に関わる選択要因は何だったのかという点だ。
まず歴史だが、おそらく6000年ほど前にシベリア地方で発生し、その地域で維持されてきたCTVTが、2000年ごろインドとヨーロッパに独立に伝播する。おそらく人間の移動とともに、500年前にヨーロッパからアメリカ大陸に移った細胞は、急速に拡大し、またヨーロッパやアジアに再侵入する。その結果、おおくのCTVTは中南米で見られることになる。
現在原因が明らかになって、このガンは収束しつつあるらしいが、壮大な歴史がここに書かれている。しかも、ホストの環境に依存するとはいえ、高等動物の細胞が独立して進化を続けているとは生命の力強さを感じる。
この歴史はゲノム上の変異の蓄積として読み取ることができるが、変異の種類について調べることで、進化に影響した要因を推察することが可能だ。実際には、どのタイプの変異、例えばCからT へといった変異がどの核酸配列(例えばCCCかTCCか)で幾つ見られるかをカウントするのだが、これにより細胞の分裂時のDNA修復ミスか、APOBECによるのか、あるいは紫外線などの一本鎖変異なのかがわかる。
基本的には細胞が増殖する時におこる修復ミスによる変異が中心なのだが、例えば紫外線障害の変異を調べると、性器のガンが皮膚に飛び出て、そこでUVの影響を受けるようになったため新しいタイプの変異を蓄積するようになったガンや、あるいは代謝の変化を反映しているガンなど、様々な要因が特定できる。
しかし、では突然変異は強く選択されているかを調べてみると、変異の蓄積はほとんど中立的に起こっていることがわかる。
他にも色々話はあるが、要するに6000年の歴史を超えてガン細胞が独立に子孫を増やしてきたという驚きが、この研究のハイライトだ。
2019年8月8日
今日紹介したいのは、アリストテレスの「霊魂論」(「心とは何か」)で、前回紹介した動物論諸作に先がけて書かれた著作で、現代の生命科学者でもそれほど抵抗なく読める面白い作品だ。
図1 アリストテレスの「Peri Psyches」は、岩波書店版では「霊魂論」、講談社版は「心とは何か」と訳されている。生命科学者から見るとどちらもタイトルとして適切でないと思うが、訳としては圧倒的に講談社版が読みやすく、生命科学の若い研究者や学生でもスムースに入っていける。
しかしこの本を読み通してまず浮かぶ疑問は、なぜこの本を「霊魂論」と訳したのかという点だ。冒頭の写真には、山本光雄訳の岩波版と、講談社桑子俊雄訳「心とは何か」を示したが、他にも京大出版会 中畑正志訳「魂について」の3冊の翻訳がある。それぞれプシューケースを「霊魂」「心」「魂」と訳しており、私たちがこれらの訳から受ける印象は、「心と体」という時の「心」に等しい。しかし、この本を読めばアリストテレスの「プシューケース」を「霊魂」や「心」として訳すと、少なくとも現代人に対して本の内容について間違ったイメージを与えることがわかる。例えばよほどの宗教・哲学好きでない限り、生命科学に関わる研究者や学生は、この本を手にとることはないだろう。
おそらくこの本の内容から一番適切な訳は「生命について」ではないかと思う。実際扱われているのは、無生物と生物の違いだし、その対象はあらゆる生物に及ぶ。もしこのことがわかるようなタイトルがついておれば、膨大なアリストテレスの著作の中でも、もっともっと生命学者に読まれる本になっていたのではないだろうか。例えば、20世紀分子生物学のきっかけになったと言われるシュレジンジャーの「生命とは何か」と同じタイトルでもよかった。
図2 分子生物学の黎明期に読まれた、物理学者シュレジンガーが生命について考えた「生命とは何か」
気になってWikipediaでこの本のタイトル、プシューケースが各国でどう訳されているかを調べると、日本語と英語が「心、soul」を使っており、ドイツ語、フランス語ではラテン語の「Anima」が使われている。なぜこの差が生まれたのか是非知りたいところだが、私自身の印象でも、animaのほうがしっくりくる。
この本の主題についてアリストテレスは、
「そこで私たちは探求の新しい出発点を取り、「生きているということによって」無生物と生物は区別される」と述べることにしよう。しかし、「生きていること」は多くの意味で語られる。そこで、以下のどれか一つが備わっていれば、私たちはそれを生きていると言う。すなわち、理性、感覚、場所的な運動と静止、さらに栄養に関わる運動、すなわち衰退と成長である。」
と、彼の主題が生物を無生物から区別している全ての特徴であり、その背景にある原理であることを明確に述べている。したがって、プシュケーを「心や霊魂」と訳してしまうと、生命の高次機能に限定してしまうことになる。例えば、
「つまり、心とは今述べたような能力の原理であり。それらの能力、栄養摂取能力、感覚能力、思惟能力、運動能力によって定義される」
からわかるように、この場合「プシューケース」は植物の栄養摂取能力のような生命の基本能力の原理でもあるので「心」と言ってしまうと混乱するだろう。この場合は「生気」とか、「生命の原理」とでもおきかえて読む必要がある。一方、理性、感覚といった生命の性質は、生命原理の延長上にあるとはいえ、「生命の原理」で置き換えてしまうと逆にわかりにくい「心=脳科学問題」だ。要するにアリストテレスのプシュケースの範囲があまりに包括的なため一つの単語で訳すのが難しく、哲学の人たちが自分たちに馴染みのある言葉を選んでしまったというのが実情だろう。
しかしプシューケースとは何かを考える哲学者は今もいるのだろうか?
確かに宗教では心とは何か、生命とは何かが問われるが、おそらくそれに真正面から取り組んでいる哲学者は少ないだろう。一方、現代の生命科学はアリストテレスが「プシュケース」として表現した生命の性質を、今や包括的に研究している。ただこの問題を一つの原理として研究することはまだまだ難しく、「無生物と生物の違い」を探る生命起源に関する研究分野から、「脳の認識、記憶、統合」についての脳科学分野まで、多くの分野に分けて研究している。その上で、情報や進化といった全分野を関連づける原理が存在することも認識しており、現代の生命科学は生命を包括的に扱い始めていると言っていい。ギリシャ時代の自然学を現代の科学と比べることは意味がないが、しかし生命と包括的に向き合おうという気持ちは互いに共通すると言える。
少し前置きが長くなったが、本の内容に移ろう。本は2部構成になっており、最初はイオニア以来、アリストテレスまでのギリシャの哲学者や自然学者が生命をどう考えていたかについて、アリストテレスがまとめた章で、2部はそれを受けて自らの考えを展開している。例によって、この時代の議論の一つ一つに真面目に付き合う必要は全くない。重要なのは、アリストテレスがどんな人だったのかという点だ。
すでに述べたように、プラトンやアリストテレスは、方法は全く異なるが、それ以前のギリシャ哲学の集大成を行うことを自らの義務と考えていた。この本の1部は「生命とは何か」に関するギリシャ哲学の集大成を図ったもので、デモクリトスを中心に、ピタゴラス派、エンペドクレス、プラトン、ディオゲネス、ヘラクレイトス、アルクマイオンなど多くの哲学者が述べていた生命の原理についての説が紹介されている。
例えばアリストテレスはデモクリトスの考えを以下のように紹介している(この文脈では心と訳されている箇所は混乱を招くので、プシューケースという原語を添えておいた)。
「デモクリトスは、心(プシューケース)を一種の火で熱いものであると言っている。彼は、形と原子とは無数にあるが、そのうちの球形のものが火と心(プシューケース)だと述べる(それは空気中のいわゆるちりのようなものであり、これは窓の間を通過してくると光線の中に現れる)。そして、あらゆる種類の種子の混合体を全自然の元素と呼ぶ(これはレウキッポスも同じ)。そのうちで球形のものを心(プシューケース)と呼ぶのだが、その理由はこのような形状はどんなものでもよく通過することができ、自分自身も動きながら他のものを動かすことができるから、というわけである」
慣れないと理解しにくいと思うが、 デモクリトスは無生物に生命を付与しているのも原子の一つで、これが私たちが栄養をとり、動く生命特有の性質の元になっていると考えている。なんと荒唐無稽な作り話と思われただろうが、実はこの文章を読んだとき、ライプニッツのモナド論、ボイルやビュフォンの種子説に近いので、驚いてしまった。すなわち、18世紀、自然史という膨大な著作を著したビュフォンでさえ、デモクリトスと50歩100歩だったのだ。いつか議論したいと思うが、おそらく18世紀の自然史家たちもアリストテレスを通してこのデモクリトスの考えを知り、参考にした可能性は高いと思う。
このように、「生命は数だ」とか、「空気だ」とか、あるいは「火だ」とか、本当にあれこれ考えていたのがよくわかる。とはいえ、単純にナンセンスとは言えないように思う。実際、現在も生命を数理で説明しようとする人たちはいるし、「火=エネルギー」の問題として捉える人もいる。大事なことは、最も宗教的と言われるピタゴラス派ですら、宗教くささを排した説明を心がけていることで、これは現在の科学と同じだ。ギリシャの自然学者にとって、生命はあくまでも自然の問題であり、自分で説明を考えなければならない問題だった。柄谷行人が「哲学の起源」で述べていた、イオニア哲学の本質がここにもはっきりと現れている。
これと比べると、その後のキリスト教はこの生き生きした議論を、すべて宗教的ドグマを持って排除した。だからこそ、17から18世紀この重石が取り除かれた時、ライプニッツやボイルたちがイオニアの哲学を再評価し、有機体論の形成へと進んだのではないだろうか。
このように、アリストテレス以前のプシュケース論をまとめた後、2部ではアリストテレス自身の考えが披露される。強調したいのは、プラトンの神秘主義と異なり、アリストテレスは神秘主義を排し、自然学に徹してこの問題に取り組んでいる点だ。先の引用も含めて彼の言葉を見てみよう。
「そこで私たちは探求の新しい出発点を取り、「生きているということによって」無生物と生物は区別される」と述べることにしよう。しかし、「生きていること」は多くの意味で語られる。そこで、以下のどれか一つが備わっていれば、私たちはそれを生きていると言う。すなわち、理性、感覚、場所的な運動と静止、さらに栄養に関わる運動、すなわち衰退と成長である。」
「つまり心(プシューケース)とは、今述べたような能力の原理であり、それらの能力、すなわち栄養摂取能力、感覚能力、思惟能力、運動能力によって定義される。」
と問題を極めてはっきりと提示している。
しかもあらゆるものを説明してしまうと悪い癖もここでは抑えており、
「理性すなわち理論的考察能力についてはまだ何もはっっきりしていない」
と述べて、取り上げた問題が難しい問題である事を告白している。
だからと言って全て「生命の不思議」などと神秘のベールに閉じ込めることはしない。引用から分かるように、生物と無生物の区別は真面目に観察すれば一目瞭然で、さらに生命の特徴は、一つではなく様々な形で(理性から栄養まで)生物に現れることをはっきり述べている。すなわち、これらの特徴は下等から高等まで、階層的に現れる。例えば栄養による運動は全ての生物に共通に存在し、場所的移動を可能にする運動は様々な動物に、感覚、心的表象はより高等な動物に、そして思惟や理性などは、人間に特有の、しかし全て生物特有の性質であると述べている。
まさに現代生物学が、生命共通のDNA情報や代謝の問題から始め、動物の運動、神経系の進化、脳の進化、さらには人間の精神のような高次機能まで対象にしているのに似ていないだろうか?
このように、「生命とは何か」問題を、階層的に現れる生物の特有の性質として定義した後、全ての生物に共通の「栄養摂取と生殖」「感覚の問題」「知ること、考えること」にわけて考察している。しかし、今の生命科学者にぜひ読んで欲しいと思える考えを彼から学ぼうとしても難しい。結局この本を読んでわかるのは、アリストテレスが18世紀まで続く生命についての自然学の基礎を確立しただけでなく、18世紀に至るまで彼が到達した地点から少しも進歩がなかったことだ。
事実習うことはないにしても、ずっと読み進めると、よくここまで考えていると感心する。いくつか印象に残った文章を順番に引用しよう(全て講談社桑子版)。
「心(生命の原理)は物体ではなく、物体の何かなのであり、だからこそ物体のうちにそなわり、しかも、一定の条件を持つ物体のうちにそなわる」 (筆者コメント:これは38億年前物理世界に新しい生命に伴う原理が生まれたことに通じる)
「栄養摂取能力は植物以外のものにもそなわっていて、心(プシュケース)の能力の第一のものであり、また最も共通のもので、これに基づいて「生きることが全てのものにそなわるからである」 (物質代謝とエネルギー代謝が生命特有の性質であることは誰も疑わない)
「感覚器官の一部が作用を受けた時に、見ることが生じるからである。というのは感覚器官の一部が作用を受けた時に、見ることが生じるからである。見られている色そのものによって作用を受けることは不可能である。すると残るのは、中間媒体によって作用を受けることだから。」 (感覚を媒体からの作用と明確に定義している)
「一般的に、全ての感覚について、感覚は感覚対象の形相を質料抜きで受け入れるものだということを把握しなければならない。それは、ちょうど蠟が指輪の印象の刻印をその材料の鉄や金なしに受け入れるようなものである。」 (全ての感覚は一度神経の活動に表象される)
「心的表象は感覚とも思考とも異なるからである。心的表象は感覚なしには生じないし、心的表象なしに判断を持つことはない。しかし、心的表象が思惟や思うことでないということもまた明らかである。心的表象の方は、望めば私たちの元に生まれる心的情態であるのに対し(ちょうど、記憶の入れ物の中に物を入れ、そしてその像を作る人々のように、眼前に何かを作ることができるから)、」
「心的表象は感覚器官のうちに残留し、感覚に類似のものであり、動物はこれにより多くの行動を行う。」 (現在neural correlatesの研究の全てはこの課題に向かっている)
「「心は形相の場所である」とする人々は上手いことを言っている。ただし、心の全体ではなく、思惟する部分がそうである。」 (アリストテレスの形相概念は全く神秘的ではない)
などなどで、問題の整理という意味では素晴らしい思考能力だと思うし、私のような凡人が到底及ぶところではない。実際、プラトンの神秘性と比べると、形相も、今風で言えば私たちの脳の問題として捉えている。しかし繰り返すが、彼の考えを知ったところで生命の原理問題について何か解決の糸口が見えるものではない。
そして生物を動かすものについて、レベルの高い思索を繰り返した後、彼は目的論者アリストテレスに立ち戻り、最後にこう締めて思考を終える。
「動物が他の感覚を持つのは、すでに述べたように「存在すること」のためではなく、「よく存在すること」のためである。例えば、資格を持つものは、水中や空中にいて、一般的に言えば透明なものの中にいて物を見るためである。また味覚を持つのは快と苦のために、食物の中にあるものを感覚し、それに欲望を持ち、そちらへ動くためであり、聴覚を持つのは動物が信号を受け取るためである。」
イオニアの様々な考え方を集大成してついに到達したのが「目的により組織化するのが生命の原理だ」という結論だ。
これは驚く。すなわちライプニッツから始まるデカルト機械論批判の様々な考え方を、カントが自然目的を持つ存在としてまとめるあの18世紀に酷似している。とすると、ダーウィンの登場まで、私たちはアリストテレスの到達点から一歩も抜け出せなかったことになる。
ではアリストテレスの目的論とはなんだったのか、次回は動物緒論を離れて、彼の「形而上学」を取り上げる。
さて稿を終える前に、生命科学をアリストテレスの到達点から大きく前進させたダーウィンの進化論とアリストテレスの「霊魂論」との意外な関係を指摘して終わりたい(と言っても、私がそう感じているだけだが)。
まずダーウィンの種の起源の最終センテンスを読んでみてほしい。
図3ダーウィンの種の起源下巻と、最後のセンテンス
言うまでもなくダーウィンは、「種の起源」の中で、単純な生命から多様な生物が進化するための理論を述べている。この進化の壮大なプロセスが、決して星の運行を考える物理学では説明できないプロセスであることを、「この惑星が確固たる重力法則に従って回転する間に・・・」進化が起こったことを明示した後、しかしこの進化の法則に従う生命も、最初「生命のもと(あまたの力)が、無生物に吹き込まれ」、物理世界に新しい世界が生まれたことを暗示している。そしてこの吹き込む(breath:息)という表現は、ギリシャ語の「プシューケー:息」と完全に重なる。おそらく、ダーウィンもこのセンテンスを書きながら「霊魂論」を思い出していたのではないだろうか。
しかし彼が読んだアリストテレスは「On the Soul」だったのだろうか。
2019年8月8日
我が国で幹細胞治療を検索すると、トップに美容形成クリニックが来て、結構細胞自体を使う治療がビジネスになっているという印象をうけるが、その詳しい実態となると把握しきれていないのではないだろうか。
今日紹介するアリゾナ州立大学からの論文はカリフォルニアを含む米国の南西6州で幹細胞を使った治療を行なっているビジネスの実態調査でStem Cell Reportsに掲載された。タイトルは「Characterizing
Direct-to-Consumer Stem Cell Businesses in the Southwest United States (米国南西諸州で消費者に直接幹細胞治療を提供するビジネスの実態調査)」だ。
何かストーリーがあるわけではないので、それぞれのセクションで面白いと思った点を箇条書きにしておく。
使われている幹細胞の種類と治療対象
脂肪組織からの幹細胞の使用は実に、60%に達し、その一部は他人からの細胞を用いている。次に多いのが骨髄で40%に達している。驚くのは、羊膜、胎盤を使うクリニックもあることだ。 対象となる疾患の7割は整形外科疾患(半分がスポーツによる異常)で、それに続くのが炎症性(ほとんどが関節炎)疾患になる。意外なことに、美容形成は2割にとどまっている。しかし、自閉症まで実に様々な病気に細胞が使われている。 ビジネスモデル
3つの会社がフランチャイズサービスを提供している。 幹細胞治療だけを行なっているクリニックは25%で、4割は他の治療の一環として幹細胞を提供してもらい使っている。残りは、幹細胞が中心だが他の治療も行なっている。 調査したクリニックは169箇所だが、そのうち51箇所は2つの異なるビジネス(例えば形成外科と再生医療)を同時に運営している。 ほとんどが疾患を絞って幹細胞を提供している。 幹細胞クリニックの運営
幹細胞を唯一の治療手段にしているクリニックに絞ってスタッフを調べると、60%がMDで、残りは理学療法士、カイロプラクティシャン、自然療法士など。 働いている医師のほとんどは整形外科か形成外科医。 使われている幹細胞のほとんどは脂肪組織か、骨髄。 以上まとめると、広がりがあるとはいえ、まだまだ完全に確立した標準療法にはほとんどがなっていないことを示すとともに、多くが規制の網から逃れる形で運営されていることもわかる。
今後特に幹細胞治療をうたったクリニックについては追跡が必要で、脂肪組織を始め使われている細胞が適切に処理されているのか調査が必要になる。しかし、このような実態調査は我が国でも進めてほしいと思う。
2019年8月7日
ずいぶん昔、このブログを書き始めた頃、琥珀の中のDNAは50年持たないという論文を紹介したことがある(http://aasj.jp/news/watch/480 )。この結果自体はそれでいいのだが、問題は琥珀からDNA を分離して古代の昆虫のDNA を解析したという論文が1992年ごろトップジャーナルに相次いだことだ。1992年はマイケル・クライトンの「ジュラシックパーク」が出版されて2年目にあたる。小説にヒントを得たとは思いたくないが、琥珀の中の生物の生々しい姿を見ると、確かにDNAも残っていると思いたくなる。結局あの時発表された論文のほとんどは汚染された現代のDNAを見ていたのだと思う。
このように世間が当たり前と思い込んでしまうことについての研究は論文は通りやすいかもしれないが落とし穴が多い。その一つが細菌叢の研究で、あらゆる身体的異常が細菌叢の問題とされてしまう。その一つが、早産や未熟児と胎盤の細菌叢の関連についての研究だ。我々古い世代は胎盤は無菌的と思っているので、出産前から胎盤に細菌叢が存在するというのはそれだけで驚いてしまう。
今日紹介する英国サンガー研究所からの論文は、妊娠中毒症や早産など様々な出生時の異常を追跡するコホート研究で、主に帝王切開で得られた胎盤を用いて、厳密なコントロールを置いた上で、得られたDNAの配列を決めるメタゲノム解析と、16S リボゾームのアンプリコン解析を比べ細菌叢を正確に特定しようとしている。タイトルは「Human placenta has no microbiome but can contain potential pathogens(人の胎盤には細菌叢はないが、病原性のある菌が感染する場合もある)」で、7月31日号のNatureに掲載された。
おそらく最初からこのような結果になるとは想像していなかったのだと思う。しかし結果は驚くべきもので、メタゲノム解析とアンプリコン解析で共に検出できる細菌はポジティブコントロールとして置いた細菌以外は全く存在しなかった。また同じ結果はアンプリコン解析を複数回繰り返す方法でも確認されている。
もちろん、一致はしないが胎盤サンプルから細菌は検出される。しかし結局検出される細菌は実験室の試薬や器具から汚染されており、それ以外は出産時の母親から汚染されたもので、これについては、今回行われたように同じサンプルを異なる方法や試薬で並行して調べるしかないことを示している。
一つだけ明らかになったポジティブな結果は、多くの胎盤で妊娠中にアガラクチア菌の感染が見られることで、感染ルート、その影響を詳しく調べるという新しい課題が生まれた。しかし、この菌の有無は妊娠中毒症や、早産とはほとんど連関はない。
以上、この例は実験研究が陥りやすい罠の典型で、要するに皆が思い込みに基づいてストーリーができてしまう。細菌叢研究で言えば、これまで無菌的とされてきた組織については今後も細心の注意が必要だろう。
もちろん、便を始めもともと多くの細菌が存在している組織やサンプルではあまり問題にならないと思うが、注意するに越したことはない。
2019年8月6日
抗原によりキラーT 細胞が活性化された後、抗原から離れた細胞はメモリー細胞へと分化し、一方抗原に持続的にさらされるとPD-1を発現するexhausted typeへ分化する。この反応が免疫のブレーキになるが、このブレーキをPD-1に対する抗体で外して、もう一度ガンと戦わせるのがチェックポイント治療で、ガン抗原が常に存在するガン局所では極めて合理的方法だ。
この考え方だと、ガン局所のキラーT 細胞はPD-1抗体によって活性化されても、クローン自体は変化することはないはずだ。ところが、今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、少なくとも皮膚ケラチノサイトのガンSCCでは、PD-1抗体処理により、局所に新しいキラーT細胞が現れガン免疫に関わることを示し、PD-1の複雑な機能を示唆する研究だ。タイトルは「Clonal replacement of tumor-specific T cells following PD-1 blockade
(PD-1阻害の後に見られるガン特異的T細胞の入れ換え)」だ。
この研究ではサンプルの採取しやすいSCCを標的にPD-1抗体治療を通常どおり行い、治療前と、最終投与以後54日までにサンプルを取り、組織中の浸潤T細胞(TIL)について、single cell transcriptomeを行い、ガン局所での細胞の変化を調べている。
期待通り、PD-1投与を行なった組織ではほとんどのタイプのT細胞の数が上昇しているが、期待通り抗原に反応している細胞系統とブレーキがかかりはじめた疲弊型に2分する。
問題はガン局所で増殖しているT細胞が期待通りガン局所で増殖したのかどうかだ。これを確かめるため、それぞれのT細胞の発現する抗原受容体を解析すると、抗体治療の後で増殖しているPD-1陽性のexhausted typeでは、抗原特異的と思われるクローンが選択的に増殖していることがわかる。
ところが驚くことにPD-1抗体治療前のTILと比べたとき、治療前にはなかった全く新しいクローンが増殖していることがわかった。実際、新しくガン組織に現れたexhausted typeのクローンは末梢血にも認めることができるので、おそらく新たに浸潤してきたものだろうと考えている。
以上の結果は、ガン免疫は決して組織内で終始する過程ではなく、またPD-1も疲れ始めたT細胞に鞭打ってガンを攻撃させるのではなく、常に新しいT細胞をリクルートし活性化することがガン免疫成立、そしてPD-1治療効果の鍵になることを示している。とすると、常にガン局所に新しい戦力を導入し、それをより強く活性化する方法の開発が必要だが、現在この分野は賑やかなので、必ずや期待できる治療法が開発されると思う。
2019年8月5日
コラーゲンやヒアルロン酸を飲んだり、塗ったりすることをうたう製品が多い中で、最近では資生堂の様にマイクロニードルに塗りつけて、表皮を突き破ってヒアルロン酸を皮下に注入する方法が開発されている。もしこの様な方法が消費者に支持されるなら、消費者も言葉だけでなく、科学的合理性を選択していることを意味し、他の会社も見習うのではと思う。
ただ、マイクロニードルの問題は液体を注入できない点だ。したがって、針表面に薬剤をコートする必要があり、注入できる量も限られている。これに対し今日紹介する韓国スンシル大学からの論文は、蛇の歯を模倣した針を設計することで、圧力なしに液体を皮下に投与する方法を報告し7月31日号のScience Translational Medicineに掲載されている。タイトルは「Snake fang–inspired stamping patch for transdermal delivery of liquid formulations(蛇の牙にヒントを得て液体を皮膚を通して注射するためのパッチ)」だ。
私も知らなかったが、蛇には長い牙の中から毒を注入するタイプと、溝のついた牙を差し込んで、自然に液体を相手の皮内に注入するタイプがある様だ。このグループは、後者にヒントを得て、溝のついたマイクロニードルの上部に液体のリザバーを設置して、リザバーから流れる液を溝を通して皮内に注入する方法を思いついた。
この着想が全てで、あとはマイクロニードルの長さや形状、レザバーの材質や形を検討している。実際期待通り、圧をかけなくともこの方法で、1cm角のパッチであれば100μℓの液体を皮内に、なんと1秒もかからず注入することができる。その後皮下で拡散するには時間がかかるが、もちろん大きな分子であれば注射局所にとどまることもあるだろう。アルブミンだと、15分も過ぎると局所から速やかに運び出される。
最後に、この方法で免疫を誘導するワクチンが作れるかどうか、インフルエンザワクチンを用いて実験を行い、期待通りマウスをインフルエンザ感染から守ることができることを示している。
2014年クモの足についている圧力センサーに習って感度の高い振動センサーを開発したソウル大学からのNature論文を紹介したことがあるが(http://aasj.jp/news/watch/2574 )、韓国は実際の生物にヒントを得た製品を開発するバイオミメティックス分野に力を入れている様だ。ここではワクチンを前臨床として用いているが、実際には化粧品などのゲームチェンジャーになる可能性が感じられる。
2019年8月4日
おそらく発癌に関わる遺伝子の中でもp53ほど奥が深い分子はないだろう。DNA 損傷を始め様々な細胞へのストレスで活性化され、多様な分子の発現を誘導し、細胞周期、細胞死、DNA修復などに関わるだけでなく、例えば血管新生や代謝調節にも関わり、これら全てはガンの悪性化と関わる。
今日紹介するオランダ・ガン研究所からの論文は、p53とWntの予想外のリンクを発見した研究で、またまたp53の奥の深さを垣間見さえてくれた。タイトルは「Loss of p53
triggers WNT-dependent systemic inflammation to drive breast cancer metastasis (p53が欠損するとWnt依存性の全身性の炎症が誘導され乳がんの転移を誘導する)」だ。
がんの増殖浸潤転移には組織炎症が促進因子として強く働いていることが知られている。7月9日に紹介した膵臓癌転移を抑えるADH-503は、白血球のガン組織への浸潤を抑えることでガン免疫を高めることで効果を発揮していることを紹介した(http://aasj.jp/news/watch/10513 :Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vxZFpDx4rIg )。
今日紹介する研究も、まず炎症を誘導しやすいガンを探すために、マウスの様々な遺伝子改変で誘導される16種類の乳がんが末期になった時期に組織の白血球浸潤を調べ、驚くことにp53遺伝子を両方の染色体で欠損させた9種類のガンでのみ白血球の浸潤が見られることを発見する。すなわち、ドライバー遺伝子などには関わらずp53欠損と白血球浸潤が強く相関することを見つけた。さらに、p53陰性腫瘍の周りの白血球は、幹細胞マーカーであるc-Kitまで発言していることがわかった。
さらにこの関係を確かめるために、同じガン細胞からp53だけをクリスパー/Cas9で欠損させた細胞株を作り、親株と欠損株をマウスに注射する実験を行い、白血球の浸潤がp53と関連していること、また浸潤してきたマクロファージによりIL1βのレベルが高まっており、ガンの進展を促す組織構造が生まれていることを確認する。
では、p53が欠損により直接誘導されるどの分子によりこの様な未熟白血球の浸潤がおこっているのか調べる目的で、ガンの遺伝子発現を比べ、Wnt1,6,7Aがp53欠損株で上昇していることを発見する。すなわち、p53はWntの発現抑制に関わっていることになる。そして、誘導されたWntは白血球幹細胞に働き、全身性の炎症を誘導してその結果乳がんへの浸潤が高まると結論している。
最後にこの考えを確かめるため、Wntを抑制する化合物LGK974をマウスに投与する実験を行い、p53陰性の腫瘍特異的に、ガンの転移を抑制できることを示している。
P53=細胞周期とDNA 修復と考えていた頃から考えると、何と複雑になってきたのかと改めて感心した論文だが、では正常でp53がWntの発現を抑制することの意味は何だろうと疑問は膨らんでいく。おそるべしP53 。
2019年8月3日
今日から神戸で、MECP2重複症患者さんの家族会(http://www.mecp2.jp/ )のファミリーキャンプが開催される。私たちAASJは初期から家族の人たちの奮闘を見ており、この記念すべき第一回キャンプに参加するのをたのしみにしている。嬉しいことに、MECP2に関する研究は着実に進んでおり、遺伝子治療以外にも様々な治療法が開発されつつある。
今日紹介するマサチューセッツ工科大学からの論文はMECP2が欠損する方のレット症候群治療のための研究だが、同じ方法は重複症にも用いられると期待できる。論文は8月1日号のScience Translational Medicineに掲載され、タイトルは「Pharmacological
enhancement of KCC2 gene expression exerts therapeutic effects on human Rett
syndrome neurons and Mecp2 mutant mice(KCC2遺伝子発現を薬理的に促進することでレット症候群の神経やモデルマウスに対する治療効果がある)」だ。
レット症候群もMECP2重複症も原因となる遺伝子変異ははっきりわかっており、遺伝子編集によるゲノム治療が最終的治療法といえる。ただ、MECP2分子の機能研究から、MECP2の異常により機能異常が起こっている分子を見つけ出し、その機能を正常化させるための研究も進んでいる。この研究は、まさにこの方向性の研究だ。
このグループはレット症候群の神経細胞ではクロライドイオンと、カリウムイオンの輸送に関わるKCC2の発現が低下していることを発見していた。この分子は、興奮性神経と抑制性神経のバランスを維持する重要な働きがあり、レット症候群の症状の一部がこの異常を反映していると考えられる。
この研究ではヒトES細胞のKCC2遺伝子を標識してその発現をモニターできるようにし、発現が高まる化合物を探索し、数種類の化合物を発見している。面白いのは、こうして発見された化合物はそれぞれ異なる経路に関わる。
一つは白血病の治療に使われるFLT3阻害剤で、これをマウスの脳スライス培養で調べると抑制性神経の効率を高めることができる。同じように、BIOなどのGSK3β阻害剤、レスベラトールなどのサーチュイン経路、そしてピペリンなどのTRPV1刺激と、4種類のKCC2発現を高める薬剤が特定できた。
最後に、レット症候群モデルマウスの呼吸と運動機能について、Flt3阻害剤やピペリンが症状改善に効果があるか調べ、期待通り大きな効果が得られることを示している。残念ながら、社会行動の正常化などについては調べていないため、今後の研究が待たれる。
結果は以上で、MECP2変異があっても、その下流の遺伝子の発現を正常化させるための方法は何通りもあることを明確に示した点で、希望を与える貢献だと思う。もちろん、抗がん剤をそのまま使っていいのかなど、多くの問題は残されている。また、他にも多くの標的があるだろう。ぜひこの方向の研究も進んで欲しいと願っている。
2019年8月2日
最近のトップジャーナルの編集者は、論文としてのレベルはそれほどでなくても、すぐに人間の健康に役立つ論文なら、以前よりサポートするようになったと思う。その結果、NatureやScienceで症例報告まで掲載されることがある。雑誌の目的が、多くの人の興味を惹くことである以上、仕方ないことだと思う。
今日紹介するデューク大学からの論文はそんな一例で、メチオニン制限食によってガンの治療効果を高めることができることを示した研究で、8月1日のNatureにオンライン出版された。タイトルは「Dietary methionine
influences therapy in mouse cancer models and alters human metabolism (メチオニン制限食はマウスのガンモデルの治療効果を高め人間の代謝も変化させられる)」だ。
メチオニンは人間にとって必須アミノ酸の一つで、したがってメチオニンが関わる葉酸を中心とするone carbon代謝と呼ばれる経路はメチオニンの摂取量により決まる。しかもこの回路は、核酸代謝や、抗酸化反応など、細胞の増殖や寿命に関わる重要な代謝物の合成に必須であることがわかっている。そのため、これまでアンチエージングやガンの治療として、メチオニン制限食の可能性が示唆されていた。
タイトルからわかるようにこの研究もガンの治療の一環としてメチオニン制限食がどのぐらい有効か調べることを目的としているが、この発想自体は新しいわけではない。ただ、実際の治療セッティングに役立つようにしっかりと研究が行われている点で評価されたのだろう。
まず制限食に変えてすぐ(2日後)に様々な代謝物からみた代謝が変化することを示している。これは治療という観点から見ると重要だ。そして、移植された自然発生腫瘍の増殖を、制限食だけでかなり抑えられることを示している。しかし、予想通り決して完治することはない。
次に、制限食だけでは抑制がうまくかからない腫瘍も、同じ代謝経路に関わる核酸阻害剤5FUと併用すると、一定の効果を示し、実際代謝もさらに大きく変化することを示している。同じように、放射線照射との協調性もみられる。
最後に、では同じような食事で人間の代謝もすぐに変化するかボランティアを用いて検討し、マウスと同じような核酸代謝、エネルギー代謝、酸化反応への効果が認められることを示している。しかし、ガンの治療実験は行われていない。
以上が結果のすべてで、正直言って掲載されるレベルとはお世辞にも言えない。しかし、著者らも述べているように菜食主義や地中海食の食事にはこの基準に達するものが存在しており、またFDAの許可が必要というわけではないので、低栄養さえ気をつければ、明日からでもトライすることができるという点で、掲載されたのではないかと思う。おそらく、ほぼ全てのガンに効果があると思うので、その意味で重要な論文だと思う。
2019年8月1日
今後急速に人口が減少すると予想される我が国も積極的に外国人労働者を受け入れる方向に舵を切ったが、今や先進国で移民政策なしに成長はないと言ってもいい。要するに、それぞれの国の必要から移民政策がある。しかしどんなに必要だからと言っても、移民政策は差別と表裏一体で、差別のない多民族社会を維持するためには強い政治的リーダーシップが必要になる。この差別意識のドグマは、ヨーロッパではブレクジットやポピュリズム政党の台頭として顕在化したが、多民族社会を国の精神にしていたはずの米国でも、2016年のトランプ選挙のあと彼の発言に支えられ、アメリカ第一主義のもと移民制限から差別へと拡大しつつあるように見える。
今日紹介するニューヨーク、Stony Broock大学を中心とした共同グループによる論文は、このようなアメリカの変化を医学データから検証しようとする研究でJAMA Network Openに掲載された。タイトルは「Association of Preterm Births Among US Latina Women With the 2016 Presidential Election (米国でのラテン系女性の早産は2016年大統領選挙と相関している)」だ。
社会学的調査で差別の実態を調べることはわが国でもよく行われているが、米国では医学調査で差別を裏付ける試みが行われているようで、トランプが選挙キャンペーンでメキシコ国境の壁から、不法移民の強制送還までキャンペーンした影響を、ラテン系住民の血圧や、精神疾患、あるいは低体重児の出産頻度の増加などとの相関として調べられてきていた。しかし、これまでの研究は統計学的に完全ではなく、トランプにjust an opinionと片付けられそうなので、3000万人に及ぶ国の出生統計をもとに、ラテン系住民(合法、非合法の滞在者を問わない)の出生に対する早産率を調べたのがこの研究だ。
基本的には大統領選挙に入る前と、選挙後の早産率を月ごとに比べたもので、統計的正確さを確保するために、様々な調整を行なって、予断が入らないよう様々な工夫が行われているが、詳細は全て省く。
結果は、全体で見たとき選挙中に妊娠していたラテン系住民の早産率は、それ以前と比べ0.6%近く増加している。もちろん大きな差ではないが、月ごとに見ると、選挙後2017年2月と、7月ではっきりとした増加が認められることから、ラテン系移民を名指した選挙キャンペーンにより、早産率が上がったことは間違いないと結論している。
結果は以上で、相関が見られるという以上の調査ではない。ただ選挙中の発言の影響ということで、一人の政治家の発言が多くの人の健康に影響がある可能性を示す一つの例にはなるだろう。個人的には、身体の医学を社会の問題と結びつけようと常に努力している米国の医学の幅広さに感心した。